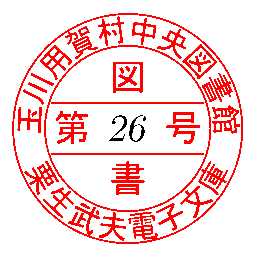
一
法史学とは法の変動の過程を理解することを目的とする学問であるから、この学問の性質を明かにするためには、その対象即ち法の変動の過程の何たるかを明かにしなければならない——
法はいふまでもなく裁判の基準であるから、それは、その有効期間だけを限つてみれば、一定の内容において静止してゐる。凡そ基準自体は動揺してはならないのであるから、法もまた動揺してはならないのである。しかし法の有効期間には、長かれ短かれ、限りがある。或時間の経過の後にはそれは改正を受け、廃止を受けて、また新法の制定となる。これを法の変動といふ。法の変動とは、法的秩序がその内容に新しきを加へ、旧きを棄て、別異の内容へと転化してゆくことをいふのである。
法の変動は或は緩漫な速度を以て行はれ、或は急速な仕方において行はれる。或は無意識の間に行はれ、或は意識的努力を以て行はれる。或は法的秩序の枝葉的な点について行はれ、或は原則的な点について行はれる。しかも法の変動は一回だけでは終止しない。変動は変動を呼び、さらにまた変動を呼び、無限に動揺の波を追うて行く。ゆゑに法の変動は一の事実ではなくて事実の連続であり、一の出来事ではなくて出来事の系列だといはねばならない。これを法の変動の過程といふ。
然らば社会は何の目的のために、かうまでその法を変動させるのかといふと、それは、社会がその時の実定法中に何等かの過誤を発見し、それを是正し克服して、一層正法へ接近せしめんと欲するからだと見るの外はあるまい。即ち法の変動は、社会が実定法と正法との間の矛盾を止揚するがために起す運動だと見るの外はあるまいから、従つてここに、問題は一段と深化して、(一)正法とは何か、(二)正法と実定法との間の矛盾はいかにして生ずるか、(三)その矛盾はいかにして止揚されるか、等の点に触れざるべからざる順序となるのである。
二
まづ正法の何たるかを考へてみるに、一派の人々はいふ——凡そ一社会の人々は、彼等が現にもつ生産諸力即ち人間の知力・体力・技術の力・機械の力・組織の力・自然の力・動物の力等々を生産行程に応用して生産活動をなし、その成果に倚頼して生きてゆくの外はないのであるから、いかにすれば一社会の人々がもつ生産諸力を最も効果的に、最も能率的に活用しうるかは、社会死活の問題だといはねばならない。ゆゑに社会は法を立て法を変へるに当つても、生産力拡充の問題を重点におく。最も効果的に生産を挙げ、最も能率的に人間を動かしうるやうな法律を組立てようとする。最もいい法律とは最も合生産的に人間相互を連絡づける法律である。これを合生産的法律機構といふ。合生産的法律機構が即ち正法である、と。
しかし人間の社会的要求にはさまざまある。効益の増進を欲するの情・伝統の持久を欲するの情・理念の実現を欲するの情。さらにこれを内容的に見れば、経済上の要求・政治上の要求・軍事上の要求・文化上の要求・道徳上の要求等々さまざまあり、さうして出来うべくんばこれら諸要求の全部に調和ある満足を与へんとするのが、社会本然の欲求だと見ねばならない。もちろん外的事情の已むことをえざる制約の下においては、諸要求のうちの一だけをとり、他のいくつかを擲たざるべからざる場合もあるのであつて、この事は、戦時において軍事上の要求を特に重んじ、他の要求をしばらく度外におかざるべからざる一事だけに見ても明瞭だといはねばならない。ゆゑに社会が時あつて経済上の要求に重点をおき、他の諸要求を度外におくといふ場合もまた可能となるわけであり、吾人もこれを否定はせぬが、しかし事情は絶えず転じ、必要も絶えず変る。今日は経済上の要求の上におかれてゐる重点が、明日は軍事上の要求の上に移り、さらにまた文化上の要求の上に移るといふことも充分起りうべきことなのである。ゆゑに論者にしてもし経済上の要求のみを単本位的に固執し、経済上の要求のみが法変動の推進力だとか、常にここに法変動の震源地が存するとか考へるならば、それはいはゆる『膠柱の見』だといはねばなるまい。
三
経済上の要求を偏重する見解に対立するものは、道徳上の要求に偏向する見方である。曰く——正義は永遠の憧憬であり、恒久の価値である。歴史あつて以来、人間は正義を眼ざして向上の一路を辿り、歩一歩これに近づいて来た。よしやその完全なる顕現は未しとはいへ、ここに立法の目標の存することだけは確かである、と。
しかし『法律学は単なる経済学ではない』やうに、また『単なる道徳学でもない』。立法者が正義の要求を無視せぬことは事実であるが、同時にまた経済上の要求を忘れぬことも事実である。時とすると、『正義』といふロマンチツクなものの傍に、『経済』といふリアリスチツクなものの立つてゐることさへあるのである。例へばギリシヤ・ローマの学者は奴隷制を以て正義に反するとは考へなかつたが、これは奴隷制が古代社会の経済的基礎だつたからであつた。又中世の学者は庄園制を以て正義に反するとは考へなかつたが、これもまた庄園制が中世社会の経済的基礎だつたからであつた。よき立法者は決して一面的ではない。彼は正義を尚ぶと共に経済上の要求をも考へ、文化を愛すると共に政治上・軍事上の必要をも忘れぬのである。
畢竟われらは正法を一義的に規定してはならない。合生産的法律機構が正法だとか、合正義的法律機構が正法だとか決めてしまつてはならない。むしろわれらは形式的に、正法とは当該社会の維持及発展に真に役立つ法をいふと定義すべきであらう。さうしてその時々の必要に即応して一々具体的に正法を内容づけて行くべきであらう。もし或時代に『生産力の拡充』が、その社会の維持及発展のために真に必要であるならば、合生産的法律機構がその時代の正法となる。又もし或時代に『国防の充実』が、その社会の維持及発展のために真に必要であるならば、合国防的法律機構がその時代の正法となる。
四
右のごとく正法とは社会の維持及発展の目的に真に役立つ法律機構をいふのであるから、正法は、社会の維持及発達の目的に対して手段たる関係に立つといはねばならない。社会にしてよく正法の発見に成功し、よくその実現に徹底するならば、社会は必然的にその維持及発展の目的を達成しうる順序となると見ねばならない。従つて人々は、正法をその具体的内容において発見せんとするに当つては、当該社会の具体的目的の実現を制約するであらうところの一切の事情を遺漏なく考慮の中に取入れるべきである。なぜかなら、手段が手段としての精確性を具有するためには、目的の実現を制約すべき一切の事情を考慮の中に取入れて一の綜合率を作り、この綜合率の上に、手段自身を確立せしめなければならないからである。一切の事情の考慮の上にガツチリと設計された手段でなければ、以て目的を現実の上に実現させるに足るだけの力がない。さうしてさういふもの、即ち手段としての精確性を欠くものは、正法の名に値せぬのである。
請ふ、海戦で以てこれに諭へんに、彼我の艦船すでに相接し、将に砲火を交へんとするに当つては、わが目的は敵艦の撃滅にあることもちろんであるが、よくこの目的を達成するがためには、手段をして充分なる精確性を具有せしめなければならない。即ち敵艦の速力と方向・我艦の速力と方向・風の速さ・波の動き・その他一切の事情を考慮の中に取入れて一の綜合率を作り、この綜合率の上に砲撃の方向を定めなければならない。正法の発見もまたこれに似てゐるのである。一切の事情の遺漏なき考慮の下においてのみ、真の正法即ち手段としての精確性をもつ法は発見されうるのである。
かやうに正法は社会の維持及発達といふ目的に対して必然手段たる関係に立つてゐるのであるから、正法の発見は、難事であるが不可能事ではない。ちやうど砲撃の命中を制約する一切の事情を考慮の中に取込んで一の綜合率を作ることが、難事ではあるが不可能事ではないのと同じやうに、当該社会の具体的目的の達成を制約する一切の事情を考慮の中に取込んで、手段としての精確性をもつ法即ち正法を、具体的に発見することも不可能事ではないのである。ゆゑに人民は立法者に向つて正法の発見を要望することができる。さうして立法者自身もまた現に正法の発見に向つて不断の努力を注ぎつつあるのであつて、その状は恰も、かの砲術長が砲撃の精確性に向つて不断の努力を注ぎつつあるのと一般である。
五
かやうに正法の発見は不可能ではないのであるから、事実上も正法の顕現を見てゐる場合が少くない。否、実定法の内容の殆ど全部は正法だといつていいのである。国家が正法の名において実定法を適用し、正法の名において実定法の遵守を国民に要求してゐるのも尤もだといはねばならない。
しかし実定法と正法との間に常に一致があるとばかりは限らない。実定法の内容が正法から離れてゐる場合も絶無ではないのである。例へば、それあるによつて却つて社会生活の平和を破つてゐるやうな規定。それあるによつて却つて社会的生産力の発達を害してゐるやうな規定。それあるによつて却つて社会文化の向上を妨げてゐるやうな規定——かういふ社会の維持及発展の目的に対して逆行するやうな規定もないではないのである。これを実定法と正法との矛盾といふ。
六
いかにして実定法と正法との間に矛盾を生じ来るかといふと——立法者が正法の発見を念願してゐることはもちろんの事実であるが、正法なるものはすでに見たごとく、当該社会の具体的目的に対して必然手段たる関係に立つ法なのであるから、正法を具体的内容において発見しようとおもへば、当該社会の具体的目的の達成を制約する一切の事情を厳正周密に認識しなければならない。然らざれば手段としての精確性において欠けることとなるからである。而もこの事たる、決して容易ではないのである。否それは殆ど不可能にも近いのである。社会現象に関する科学的研究の発達なほ甚だ不充分なる今日、何人かよく当該社会の具体的目的の達成を制約する一切の事情を、科学的精確性において、見透すことができるであらうか?
ここにおいて立法者は、その政治家的明察に訴へて正法を発見しようとする。一種の『勘』と『思付』とによつてこれを発見しようとする。而もこの原始的方法を以てしてなほよく正法の発見に成功する場合もあるのは、一見不思議のやうであるが、実はさして異とするにも足りない。なぜかなら『正法』は或表現形態をとつて立法者の前に現に立ち現れてゐるのである。『正義感』とか『公平感』とかいふロマンチツクな形態をとつて現に彼の前に立ち現れてゐるのである。ゆゑに立法者にして真にもし彼の『正義感』『公平感』に忠実であるならば、彼は期せずして正法をリアルに把握することとなるであらう。古来多くの立法者が当該社会の維持及発達に真に貢献的なりし正法を発見することによく成功し来つたわけは、彼等が彼等の『正義感』『公平感』に忠実なりし結果である。彼等は彼等の『科学的視覚』を以てせず、むしろ彼等の『道徳的嗅覚』を以て巧妙にも正法を嗅ぎ当てて来たのである。しかし『勘』は遂に『勘』である。それは科学的精確性をもたない。それによつて明察よく正鵠を射る場合もあるが、奔逸遂に的を外づす場合もある。かくして実定法と正法との矛盾は生じ来る。
次に一国立法の枢機には事実上いろいろの政治的勢力、例へば貴族・官僚・政党・資本家・労働者・ジヤーナリズム・民衆等々が参与する。これを立法参与者といふ。立法参与者の参与ぶりを見てゐると、彼等もまた正法の発見に誠心を傾け尽くしてはゐるが、しかし凡そ人間の判断はその人の立つ社会的立場から拘束を受け易いといふ事実もある。従つて立法参与者の意見にして彼等の立場の表現であり、彼等の利益の反映であるといふ場合も生じないではないのである。現に毎年議会季節に入ると、法の制定によつて新たな利益にありつく望みのある人々の厚顔な立法運動・法の改廃によつてその現有利益を喪失せんとする虞れのある人々の利己的な反対運動・無智な輿論と横暴な勢力の跳梁——さういふものが前後左右から群がり起きて、立法者の立法方向を牽制するのが見られるではないか。かくしてまた実定法は正法から離れ去ることとなる。
仮りに実定法と正法との間に完全なる一致を実現しえたとしても、この一致は永遠持続的なものではない。なぜかなら社会の目的は、或ときは生産力の拡充、或ときは国防の充実といふふうに変化しつつあるのであるから、これに対して手段たる関係に立つ正法もまたその内容を変化せしめざるをえぬからである。或時点において正法的だつた実定法が、他の時点においては、すでにもう正法性を失つてゐる場合も生ずるであらう。
慣習法の場合をとつて見ると、慣習法は民衆がその慣行と確信とを以て自然の間に形成してしまふのであるから、その内容は通常民衆の意思と一致し、社会の必要とも一致してゐるが、しかし慣習法はその性質上保守に陥り易い。社会発達の大目的からいふと、慣習法は往々にして進歩の桎梏でしかないといふ場合があるのである。かくしてここにもまた実定法と正法との間の矛盾は生じ来る。
七
さて実定法と正法との間に矛盾ありと見る場合には、社会はこれをそのままには放置しておかない。なぜかなら正法への意思は社会の最も根元的なる意思である。それは人間が最も円満に最も健全にその生々発達の要求を実現しようとする意思そのものの現れなのだからである。よつて社会はかかる場合には法変動の過程、いひかへれば実定法と正法との間の矛盾を止揚しようとする運動を展開し来る。
然らば法変動の過程即ち矛盾止揚の運動は、いかなる形態において展開されるかといふと、わたくしはそれとして三つを数へる。解釈による場合・立法による場合・革新による場合がそれである。
まづ解釈による場合から見ると、実定法と正法との間の矛盾が甚しからず、大体において実定法が正法的である場合には、解釈は文理解釈の方法をとる。文理解釈は実定法の文言に即して実定法を意味づけるものであるから、その解釈成果は殆ど実定法の原意を越えないが、実定法そのものが正法的である場合には、かかる解釈方法を以て足るのである。
実定法と正法との間の開きがやや大きくなつて来ると、解釈は論理解釈の方法をとる。論理解釈は論理的秩序に即して実定法を意味づけようとし、論理的秩序のためには実定法の文言を或は拡張し、或は縮少し、或は変更することさへも辞しないのであるから、その解釈成果はかなり実定法から離れることになるが、実定法を離れるのはそれだけ正法へ近づくゆゑんでもあるのである。
さらに一層実定法と正法との間のギヤツプが大きくなつて来ると、解釈は沿革解釈・比較解釈等の方法をとる。沿革解釈はいふ——凡そ立法者は一定の沿革を前提として立法してゐるのであるから、解釈に当つても沿革に従ひ、これとの密接なる連絡において現行法を意味づけねばならぬと。比較解釈はいふ——凡そ近似の文化階段に立つ国々はみな近似の法律文化をもつのであるから、解釈に当つても外国の立法傾向や学説傾向やに留意し、これとの平行関係において、自国の法律を意味づけねばならぬと。しかし沿革は現行法の外にあり、外国法は内国法の外にある。ゆゑにこれらとの平行関係において実定法を意味づけるのは、実は大いに実定法を離れ去ることになるのであるが、これもまた実定法を正法化さす目的のためには已むことをえぬ措置なのである。
さらに一層実定法と正法との間の矛盾が甚しくなつて来ると、目的解釈・結果解釈等の方法をとる。目的解釈はいふ——法は何等かの目的を達する手段として立てられたのであるから、解釈に当つても立法政策上の目的に留意し、これに従つて実定法を意味づけてゆかねばならぬと。結果解釈はいふ——法は実際生活に適用されるために立てられたのであるから、解釈に当つてもこの点に注意し、解釈の成果をして実際生活上の要求、殊に正義実現の要求・便宜増進の要求・伝統持久の要求に適合せしめることを怠つてはならないと。この種の解釈は、端的に正法への接近を標榜してゐるだけに、実定法からは最も遠く離隔することになるのであるが、これもまた実定法を正法化さす目的のためには已むことをえぬ措置なのである。
八
次に立法の場合をとつてみると、立法は実定法と正法との間のギヤツプが解釈を以て填めらるべくあまりにも大となつてしまつた場合の手段であり、さうしてこれが実定法正法化のための最も普通の手段とはなつてゐるが、しかし立法にはなほ能力上の限界がある。立法を以てしては立法参与者の立場に触れる改正をなすことがなかなか容易でないといふことがそれである。
立法参与者とは、すでに見たごとく、立法者(君主国の君主・民主国の議会)の立法に事実上参与する人々をいふのであるから、その実質は時にとつて大いに異る。或は貴族が、或は官僚が、或は政党が、立法参与者となる。同じ政党でも、或は保守党が、或は進歩党が、立法参与者となる。資本家が、労働者が、ジヤーナリズムが、民衆が、立法参与者となる場合もある。
さてこれらの立法参与者の参与ぶりを見てゐると、もちろん彼等も全体社会の利益のために立法意見を立ててゐる。いかに彼等が全体社会の利益のために立法意見を立ててゐるかは、彼等が国防の安全・民族の発展・文化の向上・教育の普及・衛生の完備・体位の向上等々純粋に全体利益的なる立法に対して積極的なる熱意を示してゐる一事だけを見ても明かであらう。否、彼等は彼等に対してややもすれば反噬せんとする階層の利益のためにさへ立法意見を立てる。資本主義国家における社会立法や労働立法は、立法参与者たる人々が、立法に参与しえざる階層の利益のために立案してくれた所のものだといつてもいいであらう。しかし人間の判断がとかくその人の立つ社会的立場から拘束を受け易いといふこと・その人のもつ基本的利益の線から離れ難いといふことも事実なのであるから、立法参与者の意見に、時として過誤があり偏向があるといふことも避け難い。主観的個人的にはいかに真摯であり誠実であつても、客観的社会的には、彼等の意見が彼等の立場から離れ切つてゐないといふ場合も生じるのである。即ちここに一定の人々を立法参与者とする立法の運命的限界が横はることとなる。
九
終りに革新を見ると、革新とは立法者自身が立法参与者の実質を交替させることをいふ。例へば君主固の君主が今までは貴族の層を立法参与者となし来つたのに、以後は市民の層を立法参与者となすに至るがごとき、民主国の議会が今までは社会党を立法参与者となし来つたのに、以後は国粋党を立法参与者となすに至るがごとき、これである。
けだしおもふに立法参与者の立法意見は彼等自身の立場に囚はれ易い関係にあるのであるから、或種の人々を立法参与者とする立法は、大体においてその種の人々の立つ立場と平行して流れてゆく。立法の内容そのものはもとより千変萬化するが、立法の根本傾向は一定して動かうともしないのである。諺に『蝦躍れども斗を出でず』といふが、或種の人々を立法参与者とする立法もまた斗を出づることを難しとするのである。そこには量的変化はあつても質的変化はない。よつて立法者——全体利益の代表であり、最高理性の表現であり、社会の矛盾を一層高次の次元に統一することを以てその使命とする立法者——は、その崇高なる使命の完遂のために、立法参与者の交替を敢てする。平氏に代へるに源氏を以てし、ホイグ党に代へるにトリイ党を以てする。これによつて蝦は初めて斗を躍出る。立法は初めてその限界を越える。量的変化は質的変化となる。
しかし人もし革新(Rechtserneuerung)を以て革命と同一視するならば、誤りこれに過ぎたるはないであらう。革命は事実上の行動であり、否、暴力であり、破壊であるから、政治史の研究対象とはなりえても、法律史の研究対象とはなりえない。革新はこれに反して、立法者自身が、実定法を正法化さすために執るところの合法手段なのであるから、それは法律史の研究対象の、而も主要な一つとなるのである。
一〇
要するに実定法と正法との間の矛盾は、解釈により、立法により、革新によつて止揚される。しかし解釈されたもの・立法されたもの・革新されたものは、これまた実定法といふ・一個人為の制作品たるに過ぎない。従つてそこにもまた多少の過誤がつきまとふことになる。たとへ一時は完璧を以て歌はるるにもせよ、久しからずして正法的要求との間に若干のギヤツプを生じ来ることを免れえぬのである。よつて社会は再び実定法正法化の運動、換言すれば法変動の過程を展開し来る。かくして矛盾は次々に生じ、変動も無限に続いてゆく。
法史学とは右のごときものとしての法変動の過程、即ち実定法正法化の過程をリアリスチツクに理解することを以て目的とする学問なのである。
昭和十五年一月