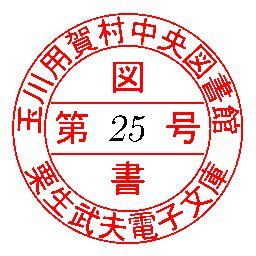
一 法律解釈の特性・神学との共通性
法律解釈の特性、殊に文芸作品の解釈に対するその特性に始めて気付いた人はといへば、それは、十九世紀の神学者Schleiermacher(1768--1834)であつたであらう。彼はその『解釈の観念について』(Ueber den Begriff der Hermeneutik)と題する・秀れた小品論文の中において、文芸作品の解釈と法律の解釈との間には一の見逃すべからざる相異が横はるとなし、次のやうにいつたのである——
『法律の解釈は文学書の解釈と同一ではない。法律の解釈は法律の範囲の確定(Bestimmung des Umfangs der Gesetze)を仕事にする。すなはちそれは或条規のなかに明確には包想されてゐない場合に対して、その条規がどんな関係に立つであらうかを決定せんとつとめるものである(一)』。
一 Schleiermacher, Über den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf T. A. Wolfs Andeutungen und Abts Lehrbuch. Sämtliche Werke, 3. Abt. 3. Bd. S. 347 Anm.
この単句の下にSchleiermacherはどんな意味を思念してゐたかといふと、恐らくそれはかうであつたであらう——法律は文芸作品のやうな鑑賞の対象ではなくて、生きた生活の規範である。生活において群がり起る無辺際の法律問題は、みな法律の前へもち出されて、法律からの解決を俟つ。法律としては予ねてからそれへの答を用意しておいた場合もあるであらうが、さうでない場合もまた少くはないであらう。しかし法律は答の用意を欠いてゐた場合にも、なほ且つ答へざるをえぬのである。一切の法律問題へ何等かの法的解決を下すのが法律の使命であるからである。よつてここに法の内容をその原始的意味以上に豊富化し、精細化する作業が始まることとなる。それが法律の解釈である。法律の解釈は従つて、法律の内部に初めから包蔵されてゐた意味を探がし当てる作業ではなくて、むしろ外部から、より深い意味・より完全な内容を法律の中へ注ぎ込む作業であると。Schleiermacherが、『法律の解釈はある条規のうちに明確には包想されてをらない場合に対して、その条規がどんな関係に立つであらうかを決定せんとつとめるものである』といつたのは、条規の内容を事案に適当に応答しうる程度にまで、豊富化させ精密化させることが法律解釈の使命であり又本質であると見たことを示すものではなからうか(一)。
一 Vgl. Radbruch, Grundzüge der Rechtsphilosophie 1. Aufl. S. 193.
いかにも法律は一切の法律問題の裁断者である。われらの法律生活において湧き上り群がり起る一切の問題はみな法律の前へ持ち出されてそれから裁断を受けるのである。法諺も『裁判所は法律を知る』といつてゐる。裁判所としては自己の前へ持ち出されてくるあらゆる問題へ答へざるをえぬのである。法律の中に予ねてから答を貯へてゐた場合はもちろん、何の用意のなかつた場合にもなほ且つ答へざるをえぬのである。よつてここにどうしても一切の可能的事案を適当に処理するに必要なるべき限度内において、法律の内容を豊富にし完全にし精密にするための仕事が必要とされてくる。解釈はさういふ仕事である。ゆゑに法律の解釈はSchleiermacherの気付いたやうに、外から内へ意味を吹きこみ、注ぎ込まうとする仕事である。文芸作品の解釈のやうに内から外へ意味を汲み出し、すひ出さうとする仕事ではない。一は外から内へ、他は内から外へ。換言すれば法律の解釈は対象(法律)へ意味を賦与する作業であり、文芸の解釈は対象(文芸作品)から意味を抽出する作業である。二者の相異は決して見逃がすことをえないのである。
しかし右のやうな特性は法律解釈のみの特有であるであらうか、他にこれと類似の操作を行ふ解釈学がないであらうか?少くともそこに法律解釈学類似のものとして神学殊に聖書の解釈学がある。聖書の解釈学も法律の解釈学と同様、外から内へ意味を賦与するといふ特性をもつてゐるのである。なぜかなら聖書の宗教生活におけるはなほ法律の法律生活におけるがごとくである。法律生活上のありとあらゆる紛争が洗律の前へもち出されて法的解決を受けるやうに、宗教生活上のありとあらゆる苦悶煩悶も聖書の前へもち出されて宗教的解決を受けるのである。ゆゑに聖書は自己の前へ提出されてくる各種の難問題へ適当に応答しうるために、自己を一層深遠化させ荘厳化させ美麗化させる必要を感じて来る。実に聖書の解釈とは聖書の文字的意味を超え、作者の原始的意味を超えて、聖書の内容を深遠化させる仕事であるのである。それは聖書の中からその原始的意味を引出すといふよりも、聖書の中へ、外部からより新しい意味・より深い意味を注ぎ込み、吹き込む仕事である。仕事の性質において聖書の解釈と法律の解釈とは全く同一轍であるのである。
だから学者は夙に法律の解釈と聖書の解釈との間の同一性に気付いた。例へばEngelsはいふ——
『法学的世界観は神学的世界観の俗界化である。教義や神の法の代りに人間の法が、教会の代りに国家が、登場した。』(Engels, Juristen-Sozialismus. Neue Zeit 1887, 49 fg.)
Radbruchに至つては最も鮮かに法律解釈と聖書解釈との間の類似性をつかんでゐる——
『聖書の内容が、外来の問題に答へる必要上から規定されてしまふやうに、法律の意味内容も外来の問題に答へる必要上から規定されてしまふのである。又、聖書の解釈者がその作者の思念してゐたよりもより多量の意味を聖書の中に発見しなければならぬやうに、法律の解釈者もその作者の思念してゐたよりもより多量の意味を法律中に見出さねばならぬのである』と。(Radbruch, Grundzüge der Rechtsphilosophie 1. Aufl. 183, 193, 207; 3. Aufl. 110 fg.)
要するに法律解釈の特性は『外から内への意味賦与』といふ点に見出されるのである。さうしてこれは法律の解釈ばかりでなく、聖書の解釈も等しくもつ特性なのである。
二 文理解釈
法律解釈の特性は、事案の適当なる解決に必要なるべき限度内において、法律の内容を完全化させ精密化させ豊富化させる点にあること、前段所述の通りであるから、法律解釈の方法は一にこの目的から決定される。即ちもし法律の内容が事案の適当なる解決に堪へうる性能を初めから蔵してゐる場合には、解釈の方法は至つて簡単である。この場合には敢へて技巧を弄して法律の内容をより一層美化させ完全化さす必要を感じないからである。しかし法律の原始的内容が事案の適当なる解決に堪へざるものある場合には解釈家は、いろいろ複雑な解釈技術を使用するに至る。解釈技術の種類態様は一に法律の事案解決堪能力を充分にするの必要から規定されるといひうるであらう。でいまこの見地から私は法律解釈の方法の各種を概観することにすると——
法律の制定が新らしく、その内容もまた事案の適当な解決に堪へる性能をもつてゐる場合には、解釈家は法律の原意を尊重し、その文言に忠実であらうと努める。すなはち多く文理解釈の方法を使用することになる。例を遠いローマの昔に求めると、東ローマの皇帝ユスチニアンは彼の大法典の編纂を了へたときに、自分ながら自分の法典の輝しい出来栄に見とれた。そして学者たちがこの見事な法典へ勝手な『解釈』を加へて法典の原意を曲げたり、損ねたりするだらうことを極端に忌み恐れた。よつて帝は特に法律を発して『解釈』を禁止し、ただ法典の尨大な内容を簡単な要録に縮めることと、法典中の難語に語註を加へることとだけを許したのであつた。『抜萃』と『語註』だけが学者に余された仕事となつた。それ以外の・若くはそれ以上の『解釈』は固くこれを禁止してしまつたのである。
フランス民法の制定者ナポレオン、プロシヤ州法の計画者フリードリッヒ大王も、共に学者たちが彼等の立派な法典へ解釈を加へることを忌み嫌つた。そして古への皇帝ユスチニアンの例に倣つて、これを厳禁しようとさへ企てた。けだし完全なものへは何も加へる必要がない。その法典の完璧性を信じ切つてゐた彼等は、情として勝手な解釈を加へられることを排撃せざるをえなかつたのであらう。
法典の内容が斬新性を喪失して来ると解釈の必要も生じて来る。しかし当初は法律と社会との間のギャップがさほど大きくもないがために、解釈の活動はなは鈍状を免れない。せいぜいのところ法典中の難語難句に解説を加へたり、多少の演衍を施したりする位の所に止るのである。なぜかなら解釈の任務は法律と社会との間のギャップをカバーする点に存する。カバーする必要のない所には、解釈の必要も亦起らないからである。
歴史的にこれを見ると十二世紀の頃北イタリイに栄えたいはゆる註釈学の学者達(Glossatoren)は、ローマ法典に対して『語註』を施すだけに満足した。けだしローマ法典は、彼等にとり完全無欠の一大法典。これに外部から勝手な解釈を加へるがごときは一種の冒涜だとまで見てゐたからである。フランス民法・プロシヤ州法・オーストリヤ民法等の編纂の直後においても、文理解釈を主たる方法とする解釈書の続出を経験したのであつた。
すなはちこれを現代に見るも、何かそこにある特別法の発布があると、すぐそのあとを受けて、主として文理解釈による解釈書の出現するのを見る例ではないか。
三 論理解釈
文理解釈と平行して、若くはこれにやや後れて発達するのが論理解釈である。論理解釈は法典内に含まれてゐる各法条が論理的秩序を構成してゐると見る。すなはちこんなふうに考へる——『各条はそれぞれ独自の支配領域をもち、各々人生の一角づつを支配してゐる。各条互に他を犯さず、他よりも犯されざる関係にあるから、各条相互の間に矛盾や重複はありえない。矛盾重複ありと見るは表面的な観察である。一層鋭く各法条相互間の支配領域を峻別して行くならば、そこに補完と調和の関係こそあれ、矛盾撞着の関係はないことを発見するであらう』と。又こんなふうにも考へる——『人生のあらゆる法律問題は、必ず何れかの法条から規定を受けてゐる。法的規定を受けてゐないやうな問題はない。かかる問題ありとおもふは皮相の見である。法典の規定を周到に観察して行くならば、必ずやいづれかの規定が問題に答へてゐることを発見するであらう』と。すなはち論理解釈は法律の円満・完全・無欠陥性を前提的に信仰するのである。そして矛盾・重複・欠陥・不明等々は法律の単に表見的なる欠点に過ぎないと考へるのである。解釈の本使命は、法律の表面に浮在するこれらの矛盾・欠陥・不明・重複等の諸欠点を清拭して、法律本然の姿たる円満完全の相を発揚させるところに存すと見るのである。この目的のために論理解釈者の先づ使用する方法は、縮小解釈と拡張解釈とである。縮小解釈は二箇の法条が表見上衝突してゐる場合に、法条の一つを強ひて狭く意味づけ、その支配領域をわざわざ縮小させて、以て二法条の間の衝突関係を補完調和の関係に転化させるのである。拡張解釈は法に表見上の欠陥ある場合に、ある法条の意味を強ひて広く意味づけ、問題の場合をもその法条の支配領域内に包摂させて、以て法の欠陥を充填せしめんとするのである。拡張解釈と縮小解釈との適度の併用によつて、法の表見上の欠陥と矛盾とは清除せられ、法の本来の相たる円満具足の姿が発揮されるに至るのである。
これを歴史に顧みると、論理解釈の方法を初めて使用したのは、やはり註釈学者(Glossatoren)であつたであらう。彼等はローマ法典の円満完全性を信仰してゐた。ローマ法典上に発見される矛盾・重複・不明・不当・欠陥等々の諸欠陥は単に表見的な欠点に過ぎないと考へてゐた。よつて彼等はこれらの表面的諸欠点を清拭してローマ法典本来の姿を発揚させるために論理解釈の方法を用ゐ、縮小及拡張の両手段を使用したのである。
爾来いづれの時代の法律学も論理解釈を解釈上の最重要の武器として使用し来つたこと縷説を俟たぬが、しかし論理解釈の最も華々しい発展は、十九世紀のドイツにおいて『一般法学』なる新学問の建設を見た頃からであらう。けだし一般法学は部門法律学の全般に対する総則である。それは部門法律学の全般に、若くは少くともその大部分に、共通してゐるところの基本的法律観念、例へば権利・義務・支配権・請求権・形成権・権利主体・権利客体・権利行使・権利侵害・法律要件・法律効果等々の諸概念を吟味検討する。さうして部門法律学に向つて、一般法学の研究成果に聴従してその部に特有なる概念の構成を試みるやうに要請する。すなはち一般法学は実用なき学理的概念を立てようとするのではない。むしろ部門法律学上の概念構成を制約し、従つてまた部門法規範の意味内容をも制約するところの生きた概念を構成しようと力めるのである。部門法律学上の諸概念は、一般法学上の諸概念に照破されて訂正と改変とを受けねばならぬ。一般法学上の概念はそれ自身実定法からの帰納によつてえられ、逆にまた実定法上の概念として積極的に作用する綜合概念である、と見られてゐるのである。
何故十九世紀の解釈学が一般法学的考察方法を使用するに至つたか、何故法の諸領域に互つて支離滅裂に散在せる諸概念を拾ひ集め、これを統一づけ類型づけて、種々の基礎的法律概念、例へば権利主体・権利客体・適法行為・違法行為・請求権・形成権といふの類を整然と形作るに至つたか——これについては論ずべき多くのものをもつが、ここは今その場所でない。ここではただ一般法学的考察方法の使用が、十九世紀の、実は支離滅裂的なる法律素材へ体系的秩序を与へ、学的荘厳味を加へたといふこと、その結果として当時の法律の意味内容が大いに整備され、完全化され、その事案解決堪能力も大いに高められたといふこと、すはなち一般法学的考察方法は十九世紀法を完全化さすための解釈手段の一種であつたといふことを一言するに止めておく。
四 沿革解釈—比較解釈—目的解釈
法律の制定が古くなりその性能も衰へてくると、解釈の機能は却つて高まり、解釈の方法も複雑となつてくる。けだし法律解釈の本質は、法の内容を事案の適当なる解決に必要なるべき限度にまで豊富化させる点に存するのであるから、法の性能の衰退と共にこれを補強し弥縫するがための手段も俄然その数を繁増させて来ねばならぬ道理であるからである。
これを十九世紀の法律史に見ると、概してその前半期の解釈学者は文理解釈・論理解釈・一般法学的考察方法等々の手段を使用するに止つた。なぜならば十九世紀前半の解釈学者は、その頃編纂されて未だ多くの歳月を経ざる民法典や商法典やを金科玉条視する傾向をもつてゐた。法典の内容は完全であり、学者はただ単に法典の内容を解明し、解明の成果を論理的に整序すれば足ると思惟してゐたからである。しかし時勢の推移は立法の当時予想だもされなかつた新開題を群生させた。裁判官は法律の原意のみに拘泥してゐては到底満足には解決しえざるべき幾多の新問題に遭着することとなつた。よつてここに法の原意を越えて法の内容を豊富化させる必要を生じた。沿革解釈・比較解釈・目的解釈等々、種々の新解釈技術は十九世紀の後半期に入つて活躍し出したのである。
沿革解釈は法の沿革的背景を重んじる。すなはちそれはかう考へる——『法規は歴史的の発達物にして長き沿革の尾を背後に曳いてゐる。或ものはローマ法に、或ものはゲルマン法に、或ものは中世都市法に、或ものは近世国家法に、その源を発してゐる。もとより立法者は沿革との間の連結を切断して新規に立法することも可能であるが、より多くの場合、彼は沿革を前提し、その上に多少の作為を加へるだけに満足するのである。このやうな場合には、沿革は言外の法である。沿革を基礎的前提として立法者は立言してゐるのだからである。従つて沿革を探るは法の意味内容を明かにする一つの道である』と。十九世紀のドイツにおいて、いはゆるロマニステンが法規のローマ法的基礎を探査し、いはゆるゲルマニステンが法規のゲルマン法的基礎を吟味したのは、かくすることによつて法の意味内容を最も根本的に明かにしうると信じたからである。
比較解釈は外国法殊に先進国の立法傾向へ注意を払ふ。いはく——『同一の文化段階に立ち、同一の社会経済事情に立つ国々はほぼ同一の法内容をもつ。立法の権こそ国別であるが、立法の内容は大体共通である。一国の適法とするところは他国も適法とし、一国の違法とするところは他国も違法とする。ゆゑに新たに法を立てるに当つては他国の立法例を参照する必要があり、既存の法を解釈するに当つても、他国の立法傾向や学説傾向へ注意を払ふ必要がある。最近の立法傾向に一致する解釈方針をとるは自国法の発展を嚮導して法の最近の発展動向に追従させるゆゑんである』と。いはゆる比較法学派が外国法の研究によつて自国法の古きを新たにし、欠けたるを補はしめようとする志向を有せしこと、ここに贅説するまでもあるまい。
目的解釈は法の言表よりもむしろその根本精神を、法の外形よりもむしろその内在目的を重視する。必ずしもそれは文字の意味に囚はれず、論理の要求に従はず、むしろ端的に立法の趣旨・制度の精神へ直入して、これに従ひ法を意味づけ内容づけようとするのである。出現の順序からいふと、この解釈方法は文理解釈・論理解釈・沿革解釈等々の常套解釈手段よりも遥かに後れて出現するを常とするのである。常套の解釈手段を以てしてよく解釈の目的を達しうる間は、人は何をわざわざ法の目的・法の精神といふごとき神秘的・形而上学的なものをもち出す必要があらうか。精神をいひ目的をいふは、解釈の対象たる法律が常套の解釈技術を以てしては到底救治しえざる程度にまで古物化し廃朽化してしまつた後でなければならぬのである。十九世紀の法律学史について見ても、目的解釈が自覚的に使用され出したのはJhering以後の事であつたであらう。
五 自由法学及び社会法学
以上吾人は文理解釈・論理解釈・沿革解釈・比較解釈・目的解釈等々につき簡単な省察を試みたが、ふり返つて考へて見ると、これらはみな法律そのものに拘泥してゐる解釈である。文理解釈は法律の文言に、論理解釈は法律の論理に、沿革解釈は法律の沿革に、比較解釈は他国の立法例に、目的解釈は法律の内在的目的に、結局みな法律そのものに論拠をおく。いづれもみな法律に即して法律を内容づけようとするもの、法の内面から法を膨脹させようとするもの、一口にいへばいづれもみな内在的法律解釈であるのである。
ゆゑに解釈の対象たる法律そのものが極端に古物化してしまつてゐる際には、上述の諸手段は総じて不適当のものとならざるをえない。なぜならばすでに古物化してしまつてゐる法律に就いて、その文意を尋ね、論理を跡づけ、目的を探つても、遂に大した収穫は期待できぬからである。しかし法がなほ法である以上は、何とかしてその性能を発揮せしめねばならない。何とかして事案を適切に解決しうる堪能力をもたしておかなければならない。それにはある程度まで法律を離れて別に生ける社会の規範意識をとらへ、これを制定法の規定と接合連結させるの外はない。すなはち外在的法律解釈の方法を用ゐるの外はない。これが実に社会法学や自由法学の立場である。
自由法学や社会法学は右のやうに、法の内在的解釈の方法を以てしてはどうしても解釈の目的を達しえぬ場合に執られるところの非常的解釈手段であるのであるが、歴史上この方法の大いに用ゐられた時代は少くない。凡そ立法の機能の甚だしく鈍り、社会に対する新法律の供給甚だしく不充分なる場合には、社会は大抵古き法律組織に対して自由法学的解釈態度をとるものなのである。古代において、中世において、近世において、吾人は屡々かかる情勢の下における自由法学の活躍を目睹して来たのである。共和政治の末葉におけるローマの法律学のごとき、中世都市の発展期における法律学のごとき、欧洲への進出期におけるマホメット教徒の法律学のごとき、いづれも自由法学の典型的なるものに外ならなかつた。
しかしここに一つ強く注意せられねばならぬことは、自由法学は現行法に対して自由な態度をとるとはいひ条、決して革命的な態度はとらぬといふことである。自由法学が自由であるのは制定法の文言に対してである。制定法の立法原理・根本主義に対してではないのである。制定法の立法原理・根本主義は自由法学のむしろ力めて擁護し、力めて支持せんとするところである。自由法学はいはば制定法の基礎原則を確乎不動のものとして是認し、その舞台の上でいはゆる『自由』に躍つてゐるだけである。それはなるほど生ける社会の規範意識には注意を払ふ。そしてこれと制定法とを握手させようとも試みる。しかし社会の実際を見ると、そこには制定法の主義精神と妥協し提携しうる底の思想、すなはちせいぜい改良主義的なる思想も流れてをり、到底これと妥協し提携することをえぬ思想、すなはち革命的なる思想も流れてゐる。自由法学が社会の規範意識だとして採択するところのものは、前者すなはち改良主義的なる思想であつて、後者ではないのである。革命的なる社会思想に対しては、自由法学は黙殺か、然らざれば排撃の態度をとるのである。
これを現代の自由法学に見ても、それの妥協主義・協調主義・平和主義は明かである。現代の自由法学は『法条及び法概念からの解放』を叫んでゐる。『法の自由なる発見』を主張してゐる。『裁判官の自由なる人格活動』を要請してゐる。しかし現代の自由法学は決して現行法の基礎原則に対して挑戦しようとするものではないのである。現代の私法はいふまでもなく財産私有主義・営利自由主義・個人意思尊重主義等々の上に建設せられ、編成せられてゐるのであるが、現代の自由法学もまたこれらの諸原理を支持し擁護する。そして僅かにこれらの基礎原理の破壊となるに至らざる限度内において、生ける社会の規範意識を採択し、これと制定法とを連結させ提携させてゐるだけである。それはかの社会政策といふものに酷似してゐる。社会政策が一方において資本主義的経済秩序を支持しつつ、他方において資本主義から生ずる社会的悲惨を可能的に救治せんと試みてゐるやうに、自由法学も一方において資本主義的法制を支持しつつ、他方において生ける社会の規範思想を取入れようとしてゐるのである。
六 法律社会学
終りに『法律社会学』及『法の唯物史観』について一言すると、これらはもちろん解釈学ではなくて一種の説明科学である。なぜならば両者は法の意味内容を闡明することを目的とせず、むしろ社会における法の変動の原因や、法が社会生活の展開に対して与へる影響やを究明することを目的としてゐるからである。いひかへれば法を一箇の社会事象と見て、その発生の原因とその惹起する結果とを科学的に論究せんとしてゐるからである。法に対してかかる冷静なる科学的研究心の勃興するのは、もちろん社会事象一般に対する科学的研究心の勃興の影響でもあるが、同時に又法に対する宗教的信仰心の冷却の結果でもある。一定の法律体制の永遠性・完全無欠性を盲目的に信仰する精神の盛なる間は、法を一箇の社会事象と見てその発生変動の原因を考へようとするやうな科学的態度は決して起りえぬのである。それはちやうど、宗教心の盛な時代に宗教を一箇の社会事象と見てその発生変化の原因を論じようとする宗教科学が起りえぬのと同様である。宗教心の冷却と同時に宗教科学が起るやうに、一定の法律体系の権威の失墜と共に法律社会学や法の唯物史観やは現はれるのである。現代において法律社会学や法の唯物史観やが新しい花のごとくに咲き出でんとしつつあるのは戒心すべき現象ではあるまいか?