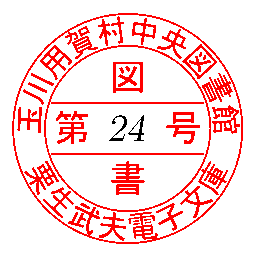
一 ナチ革命の経過
ナチ革命の経過を回顧してみると、一九三三年一月三十日、ヒンデンブルグ大統領はヒットラーを宰相に任じ、翌々二月一日、議会を解散して新政府に対する国民の信任を総選挙の結果に問うた。四日には『国民保護のための命令』を発して、新聞又は集会で発表される政治的意見に対する取締を厳重にした。二十七日には議会の建物が怪火にかかつて焼失したので、大統領はこの事件を国民から自由権を剥奪するためのいい口実に利用することができた。すなはち大統領は事件の翌日・二月二十八日に、『共産党員の危険行為を取締る必要上』と称して、『国家及び国民保護のための命令』を発し、徹底的に国民の自由権を制限してしまつた。ワイマール憲法が保障してゐた国民の自由権は此命令によつて殆ど全く没了されてしまつたのである。
しかし上述の諸処置は、みなワイマール憲法の認めてゐた大統領緊急命令の形式で行はれたのであるから、どこまでも合憲法的だつたのであつた。一体にドイツでは一九三一年頃から緊急命令の頻発を見てゐたのであり、三二年度などは緊急命令の数が正規の法律の数よりも十二倍も多かつた程だつたから、ヒットラー時代に入り沢山の緊急命令が出だしたからとて、何も『革命来』などと慌てるほどの事でもなかつたのである。だからナチ革命の経過を巧妙に論じたショイナー教授の論文は、一月三十日ヒットラー就任の日から三月五日総選挙の日までをナチ革命の準備期だつたと見てゐる。本格的革命作業の開始したのは総選挙の日以後であつた。
三月五日の総選挙はナチ及び其友党の大勝利に終つた。彼等は全く議会において絶対多数を占めてしまつた。よつて彼等は三月二十三日、憲法改正に要する多数を以て、『国民及び国家の危険克服のための法律案』を可決した。そして翌二十四日にこれを公布して即日効力を発生せしめた。これによると、政府は議会の協賛をうることなしに、即ち政府の決定のみを以てして、『法律』を制定することができる。そしてこの『法律』で以てワイマール憲法の規定に牴触する定めをなしても差支ないとあるのである。だからこの法律は議会を否認したのも同然であつた。なぜなら、政府は議会の協賛なしに法律を制定しうることとなつたのだから。いな、この法律はワイマール憲法自体を否定したのも同然であつた。なぜなら、政府はワイマール憲法の条章に牴触する定めをなすことも可能になつたのだから。ゆゑにひとは三月二十四日の法律を『ワイマール憲法を破つた法律』とよび、『暫定憲法』ともよぶ。暫定憲法とよぶわけは、この法律の効力が一九三七年四月一日を以て失はれることに予定されてゐるからである。とにかくこの法律こそナチ革命の基軸をなし、あらゆる革新の基礎となれるものではあつた。
七月に入るとヒットラーの政権はやうやく固く、反対諸勢力は全然影を潜めてしまつた。よつてヒットラーは七月六日、国代理官等を前にして演説を試み、『革命は勝利に終つた。敵党は屏息した。今は我党如ち国家である。今後の政治はもはや革命(Revolution)ではなくて、革命によつて打開された新道程上における進化(Evolution)である』といひ放つた。内相フリックも七月十一日文書を以て、『革命の終了、新国家生活の開始』を全国に告げ知らせた。ゆゑにひとは七月十一日を以てナチ革命終了の日と見るのである。
要するにナチ革命は三十三年一月三十日ヒットラーの新政府組織から三月五日総選挙の日までを準備期となし、三月二十四日の暫定憲法を以て一挙に中核を衝き、七月十一日のフリック布告を以て一応の終了を告げた次第なのである。
二 ナチ政権下の立法及行政
ではナチ革命はドイツの国家秩序にどんな変革をもたらしたかといふと、第一は立法における議会の機能の凋落である。上述のごとく議会はその立法権を政府に移譲し、政府をして『法律』を制定することを可能ならしめてしまつたのであるから、いはば議会はその本来の機能を喪失し、殆ど無用の存在化してしまつたのであつた。元来ナチの思想からすると、政府こそ国民意志の完全なる代表者であるのだから、政府以外に別に国民意志の代表者を置くやうな必要はない。従つて『民意の代表機関としての議会』ならば、これをおくほどの必要もないといふことになるのである。又、ナチの見解を以てすると、国家一切の権力は大総統一人の手に集中せらるべきものなのであるから、『独立政治機関としての議会』なども別にこれをおくほどの必要もない。強ひて議会に存立の余地を与へようとおもへば、『大総統の諮問に応ずる諮問機関』としてだけだといふことになるのである。ヒットラーが前述の通り議会の立法権を剥奪し、全くこれを無力化してしまつたのも、議会を単なる彼の諮問機関たらしめようとの考へからであつたのであらう。
第二は行政における法治主義の後退である。法治主義とは国家の行政活動を能ふかぎり法的制約の下におかうとする主義であるが、ナチ一派にいはせると、元来この主義は国家権力の発動に対する不信任の念の発露である。国家は何をするかも知れない・その権力を濫用するかも知れないと考へたればこそ、国家を堅牢な法律体系の域内におしこめ、法的レールに沿うて行動させようとしたものであつたからである。しかしナチの国家観を以てすると、国家は個人の利益の擁護よりも国家自身の固有目的の追求に向ふ。だから国家がその活動の道程上において多少は個人の利益を犠牲にすることあるべきは自然の数と見ざるをえない。従つて国家が個人の立場を顧慮するのあまり、みづからの行動を法的に拘束することは余りに小心に過ぎたるものだと考へるのである。よつてナチの行政法は行政官庁の行為を法の拘束から解放し、行政官へなるべく広い自由裁量の余地を与へようとする。又、個人の公権を否認し、個人は単に行政の客体であつて、公権の主体でないと見る。従つて又個人から行政訴訟提起の資格をも否定し去らうとする。さらに地方団体の自治権能をも制限し、なるべく地方団体を国家指導の下に立たせようとする。かやうにナチの行政はどこまでも官憲的圧迫的であるからタルンハイデン教授のごときはいふのである——『ナチ国の行政は非法規的であり、非訴訟的である。もし法規に拘束さるるものを行政といひ、拘束せられざるものを政治とよぶならば、ナチ行政官庁の活動は行政でなくて政治である』と。
要するにナチ革命の大なる成果は政治の優越・法律の低落を来たしたことであつた。立法においては議会が殆ど立法権を喪失してしまひ、政府が行政権と立法権とを兼併することになつた。行政においては行政処分の合法性を重んじる思想よりも、その政治的合目的性を重んじる思想の方が遥かに強くなつた。従前は政治が法律に隷属してゐたのだが、今では法律が政治に隷属するやうになつてしまつた。
では司法におけるナチ革命の影響はどうであつたか?ここにも政治の優越・法律の低落を見たであらうか?
三 ナチ政権下の司法
ナチ革命の進行途上、司法権の独立の疑はれたことが一再ならずあつた。議会放火事件の裁判に関し、ユダヤ人の放逐に絡む諸事件の裁判に関し、裁判所の法令審査権の問題に関し、政府側と裁判所側との間に危く意見の対立を見んとした際など、急進ナチ党員の間に、政府はよろしく裁判所の行動に干渉を加へよとの議論の出たのも事実であつた。彼等からすればナチ国は権力国であり、大総統が一切の国家活動を指揮してゐるのであるから、大総統が裁判所の行動までを指揮したつて悪いことはないといふのであつた。しかし司法大臣フランクは極力干渉主義に反対した。彼は裁判所の行動に対する政府の干渉は法的安全に対する国民の期待を裏切り、新政府に対する国民の信頼をも失はせることになると、深くその点を惧れたのである。よつてフランクは三三年九月三十日ライプチッヒに開かれた『ドイツ法曹大会』において、又同十一月十五日ベルリンに開かれた『国民社会主義法曹大会』において、さらに又三四年二月十七日ケルンに開かれた『ドイツ法曹大会』において、重ね重ね裁判所の独立・非党派的裁判の維持を保証する旨の声明を繰返して行つたのである。ドイツの学者にとつてはフランクのこの声明がよつぽど有難かつたものと見え、談偶々この事に及べばどの論文も異口同音、フランクの功績を称美してゐるのを見るのである。
しかし司法権独立の保証はそんなにまで有難いものであつたであらうか?私見によれば裁判所へ独立の地位を認めてやるといふことは、ナチ政府にとり大した譲歩を意味するものではなかつた。なぜなら、政府はすでに法律制定の権利を握りもつてゐる。任意の法律を作つてその適用を裁判所に命じうる地位を占めてゐる。ゆゑに裁判所に独立の地位を認めてやるといふことは、政府の作り与へた法律の解釈適用につき、裁判所へ判断の自由を認めてやるといふまでのことであり、いはゆる犬を鎖でつなぎ、鎖の長さの限度内において跳躍の自由を認めてやるのと一般であつたからである。
元来裁判所の独立が政府にとり恐ろしかつたのは、議会に立法権のあつた間だけである。議会が独立して法を作り、裁判所が独立してそれを適用するとあつては、政府も脅威を感ぜざるをえぬのであるが、政府が一旦立法権を併呑し、任意に法律を作りうることになると、裁判所へ独立を許しておいても別段頭痛にもならぬのである。ナチ政府が裁判所のために独立の地位を承認してやつたのは、裁判所の力の程度を相当に見くびつたからのことであつたであらう。
しかしそれにしても政府以外に独立の国家機関が存在するといふのは気懸りには相違なかつたので、ナチは一方、裁判所の独立を認めつつ、他方、その独立の範囲を縮小して行かうとする策謀を弄したのであつた。策謀とは——
第一は裁判所の法令審査権の否認である。法令審査権は法令の有効無効を裁判所が判断するといふ主義であるが、凡そこれが革命政府にとつては迷惑至極のことなのである。なぜなら、革命政府の発布する新規大胆な無数の法令が一々裁判所からその効力を疑はれ、その適用を拒まれるとあつては、革命事業は到底思ふやうに進捗することをえないからである。現にイタリイではムッソリーニ政府の発布した法令のうち五百箇以上が裁判所から適用を拒まれ、さすがのムッソリーニをして一時途方に暮れしめた例さへあつた後であるから、ナチはかなり腹をきめて断乎たる態度に出た。裁判所から法定審査権を奪取つてしまふのが彼等の目的であつたのである。司法官はこれに対してもちろん不平満々だつたが、意外に脆くその腰は挫けてしまつたし、学界の輿論も翕然として政府に追従して行つたので、ナチは案外容易にその目的の到達に成功することができたのであつた。学界の輿論の有するところは、『およそ大総統を戴く国民にあつては、法令審査権は大総統に属して裁判所に属せず。裁判所は大総統アドルフ・ヒットラーによつて法的効力を有すと認められたる法令を解釈適用してさへゐればこれでその任が尽きる』といふにあつた。
第二は司法における適法主義の凋落である。適法主義とは司法にいささかも政治的考慮を交へず、純粋に法を法として解釈適用しようとする主義であるが、この主義もナチにとつてはあまり都合のいいものではなかつた。なぜなら、この主義は司法をあまりに政治から中性的ならしめ、殆ど不感症たらしめる。それは全く法自身のために法を適用しようとする。法が命じてゐるなら常に命じ、法が許してゐるなら常に許さうとする。或る判決の結果、政府の立場がいかに苦しくならうとも、政府の政策がどんな影響を受けようとも、そんなことには頓着せず、ただ一本調子に法を宣言し執行しようとする。ゆゑにそれは殆どナチの政治理論と正面的に衝突する。ナチは政治価値の優越性を認め、法律を政治に隷属させようとするのに、適法主義は法律価値の優越性を認め、政治を法律に隷属させようとするからである。
よつてナチはドイツの裁判所をして伝統の適法主義を棄てさせ、代りに便宜主義すなはち政治的考慮を法的判断裡に混入せしめる主義を採らしめようと欲したが、この場合にもナチは御用学説の賑々しい支持を受けることに不自由は感じなかつた。カール・シュミットなどは彼の無数の著書論文を一貫して——『従前の法的判断は法と政治・法と道徳・法と社会等々を峻別して来たが、元来法は政治・道徳・社会等々から離れて孤在してゐるのではない。これらのものと結び合ひ、絡み合つて国民意識の中に生動してゐるのである。だから当来の司法は政治・道徳・社会・経済等々の実質的考慮をも加へなければならない。すなはち大いに非法律的《ウンユリスチツシユ》にならなければならない。法は裁判の単に一応の基準に過ぎぬとおもふべきである。真に具体的に妥当な判決を下さうとおもへば、法の外に当事者の地位・資力・性格等の、いはゆる主観的実情を考慮の中に加へなければならず、さらに又客観的情勢、即ち一国施政の根本方針をも考慮の中へ加へておかなければならない。むろん一々の裁判行動につき裁判所が政府の指揮を受けたりしてはならないが、しかし一国政治の基本的なテーゼとは歩調を合せて裁判して行くことを要するのである。すなはちこれを、ナチ国家についていへば、ナチ国家はそもそも何を排斥し、何を克服しようと欲してゐるか、何を新たに造出し産出しようとしてゐるか、それらの点に関するナチ国家の意志を深く洞察した上にて、それらの国家目的の達成に奉仕すべく、法を運用して行かなければならない』と主張してゐる。
現にドイツ最近の判例を見ると、たしかにナチの政治方針を考慮に入れたと見られるものが少くない。例へばナチのユダヤ人排斥方針に迎合するために、強ひて理由を『重大なる人的要素の錯誤』に求めて、以てユダヤ人との間の婚姻を無効ならしめた判決。ナチの為替政策に迎合するために強ひて理由を『良俗違反』に求めて外国人との間の種々の契約を無効ならしめた判決。ナチの農民保護政策に迎合するために、強ひて理由を『給付不能』に求めて土地売買契約における債務者即地主の給付義務を免れしめた判決。ナチの反対党弾圧主義に迎合するために、刑法の正文をみだりに拡張解釈して、実はいはゆる『正文なき刑罰』(Strafe ohne geschriebenes Recht)を実行した判決。数へ来ればシュミット一派の主張する政治的司法はドイツ司法現下の実状なのである。
しかし真に裁判所の適法主義を打破しようとおもへば、学説の力位で圧迫を加へるだけでは足らない、進んで制度そのものへ変革を加へる必要があるのである。すなはち裁判所をして適法主義をふり廻はすことを制度上不可能ならしめてしまふ必要があるのである。現にいまドイツはかうした見地から司法制度の改革、殊に刑事訴訟法の改革をやかましく論議してゐる。以下簡単に刑訴改革論の要点を紹介してみよう。その中にナチの司法政策の真志向がずゐぶん露骨に現はれてゐて、おもしろいとおもふから。
四 ナチ政権下の刑訴
ナチは一九三三年三月十八日叛逆罪に関する特別手続を発したのを手始めとして、証拠法を変へたり、宣誓法を改めたり、刑事裁判の公開を禁じたり、多くの改正を行つて来たが、刑事訴訟法全般の根本的改正は未だ不実行に残してゐる。しかし刑訴は元来国家の刑罰権を実現し、国家の権威を発揮する所以の手続であるので、国家権威を強調するナチにとつては、刑訴の改正は忽緒に附すべからざる問題である。エッキスナー教授などは、『ナチにとつては刑訴の改正は刑法改正以上の問題である』といつてゐるのである。それゆゑに目下ナチは、『国家が変れば刑訴も変る』(anderer Staat anderer Strafprozess)なるモットーの下に、刑事訴訟法の根本改造を企て出したが、その改正眼目は何辺にあるであらうか?
近著の『刑法雑誌』を見るとエッキスナー、ジーゲルト、ヘンケル等の諸大家が轡を並べてこの問題を論議してゐる。その他諸雑誌にもいろんな人々の意見が見えてゐる。いまその間に小異をすてて大同を紹介してみると——
裁判所の構成については合議制を廃して単独制をとらうとしてゐる。けだしナチは国家の政治をさへ独裁者の一手に委ねてしまつた位であるのだから、裁判事務などは単独判事の処理に一任してもいいと考へるのである。合議と選挙とはどこまでも彼等の禁忌である。彼等は何事でも単独人をしてその全責任において独断専行せしむるに如かずと考へてゐるのである。裁判なども、単独判事の裁判の敏速・強力・新鮮なのは、合議裁判の平凡・鈍重・定型的なのに勝ること万々だとしてゐるのである。
審級については控訴審の廃止を主張してゐる。控訴審は事実及法律の両面に亘つて、第一審が一旦判決した事件を、さらに新たに審理判決するものであるから、徒らに時と費用と努力とを浪費させるばかりでなく、多大の時間をその間に経過してしまふ結果、却つて事実の映像を不鮮明にさせる。控訴あるがために事実の真相が蔽はれ、みすみす事件が証拠不十分として無罪にされてしまふ場合が決して少くはないのである。民事についてはともかく、刑事に関する限りは、控訴は無用の存在といふよりも、むしろ有害の存在だとナチは見てゐるのである。
公訴の提起については便宜主義の徹底を主張する。従来の便宜主義は主として犯人の性情・境遇等の主観的諸事情を見て訴の提否を決定してゐたに止つたが、当来のそれは、犯人の主観的事情ばかりでなく、社会の情勢・政治の動向をも見て訴の提否を決定しなければならないと主張する。これが司法を政治に隷属させようとする彼等の志向の現はれであることはいふまでもない。
当事者については彼等は検事の訴訟法上の地位を極力高めようと図つてゐる。彼等にいはせると従来の訴訟法は検事の活動をあまりにも窮屈に制限し過ぎてゐた。これは検事によつて被告人の自由権が侵害されるだらうことを恐れたからであり、やはり国家活動に対する人民の猜疑心の現はれ・不信任の思想の発露に過ぎなかつた。そしてその結果は徒らに検事の訴追力を薄弱化するだけに終つてしまつたのである。だから当来の訴訟法は検事に思切り権力を与へて、彼の訴追力を十分に強くしてやらなければならない。殊に差押・勾留等の強制力を検事が自由に使用しうるやうに改めてやらなければならないと主張するのである。
その結果ナチは予審手続の存続にも反対する。彼等はいふ——予審手続はやはり検事不信任の思想の現はれであつた。検事に強制取調を許すときは、被告人の人権が蹂躙される危険大なりと見て、別に予審判事をおき、これをして強制取調をなさしめたのに外ならなかつた。ゆゑに当来の訴訟法がもし検事不信任の思想を去り、検事に強制取調の権能を与へるならば、予審は自然無用となり、捜査から公判へ直続するやうになるといふのである。
弁護士についてはナチは弁護士の公的性質を高調する。即ち当来の弁護士は単に当事者の代理人として当事者の立場ばかりを擁護してゐてはならない。むしろ判事の協力者として、公正なる国家刑罰権の発動のために、立働かねばならぬ高き公的責任をもつと主張してゐるのである。営業としての弁護は一変して、公務としての弁護にならなければならぬと見てゐるのである。
かくしてナチの刑事訴訟法改革の企図はあくまでも検事の権威を高め、その権限を強くして全く検事本位の訴訟法を築き上げてしまはうとしてゐるのであるが、かくの如きは検事をしてナチの法律理論・刑罰方針を尖鋭的に主張させ実行させんとの意図からである。できることなら検事の力を通じて裁判所の判決をナチ政府が欲するがごとき方向へ引きずつて行かうとの魂胆からである。そこに彼等の法律軽視の思想・政治優越の信念の強く描き出されてゐるのを見るのである。
五 政治の優越・法律の下属
しかし右のやうな思想傾向、すなはち法律の犠牲において政治目的を達成しようとする思想傾向は何もナチの特有ではない。変革期の歴史運動を担任する政治的勢力は、常にかうした思想傾向をもつてゐるのである。イタリイのファッシヨ、ロシヤのボルシェビキイ——むろんその間に、主義精神の同じからざるものはあるが、政治優越の思想はひとしく抱いてゐるのである。
この点につきナチ法律学者の錚々たる一人ケールロイター教授はいつてゐる『法律は「出来上つた秩序」であり、「固まつてしまつた図式」である。それは静止的恒久的な性質をもつてゐる。ゆゑにかかる秩序を用ゐて生活争議を処理解決せんとする司法は、生活が保守的安定的なる時代・人々が同型の生活を反覆して生きてゐる時代の統治方法としては適当である。しかし一旦社会が変革の過程中に投入れられると、古い秩序を標準として生活紛争を解く作用よりも、新しい価値・新しい秩序を創出する作用の方が切要となる。——それが即ち政治である。政治は新価値の創造に向ふ。法律が静的合理的の秩序である間に、政治は改革的・突進的な過程である。安定期には概して法律が政治を統制するが、変革期には常に政治が法律を圧迫するのである』と。即ち現下のドイツで、政治が司法を圧迫してゐるのは、変革期を表徴する一の現象に過ぎないと見なければならない。