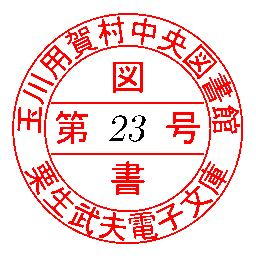
一 ナチ学者の国家観
ドイツの法律学はいま雷雨の中に立つてゐる。法の全域に対して『法律更新』の大計画が立てられ、そしてそれが精力的に敢行されつつある。憲法・行政法・社会法・経済法などはもちろんのこと、刑法・訴訟法・土地法・会社法・親族法・相続法なども、根幹的に揺れてゐる。全然ヒットラーの政治の影響を受けてゐないやうな静謐な法律区域は今は全くないであらう。だからヒトッラーの出現はドイツ政治史の転回であつたばかりでなく、同時に又ドイツ法律史の転回であつたといふべく、見方によつてはさらに又、ドイツ法律学史の転回であつたともいはねばならぬであらう。なぜならヒットラーの法律更新案の根柢には、『ドイツ国民社会主義』の理論がある。ドイツ国民社会主義の理論は初めのほどは単に時局的・宣伝的のものに過ぎなかつたが、漸次修正を受け鍛錬を経て、今では相当に体系的なものとなりつつある。現下のドイツ法理学は国民社会主義を哲学的に深め、理論的に厳密化する仕事に追はれてゐる形ちである。無数の雑誌論文と夥しい小著作とが理論戦線の正面で躍つてゐる。知名の法律学者にして国民社会主義の理論の哲学的深化を試図してゐる人も少くない。ここに紹介しようとする数名の学者の国家観・法律観及び私法観は、かうした党与的・迎合的学説の中の代表的な五つ六つである。
さて彼等国民社会主義の学者たちの国家観はいかがであらうか、いひかへれば彼等はそもそも国家をばどんなものだと想つてゐるのであらうか?近著の『公法雑誌』は、これに関するハンス・ゲルバー(ドイツ公法学一方の雄)の論文を載せてゐる。まづこれから読み始めると、ゲルバーはいふ——『国民社会主義の国家観の特色は、国家を工作物《アンスタルト》とは見ない点にある。工作物とは一定の目的のために立てられ、利用せられ、そしてその利用性の喪失と共に廃棄されてしまふ設備である。それは手段的・利用的なもの、合理的・機械的・技術的・設定的なものである。二十世紀初頭の国家学説の中には、国家をも一種の工作物と見たものが少くなかつた。例へばマルクストは、国家は支配階級が被支配階級を搾取する目的のために作つた一種の工作物であり、装置であると考へた。自由主義者(ナチ党員は自由主義者といふ語をその反対論者一般を呼ぶ呼称として使つてゐる。ちやうどマルクストが反対論者一般をブルヂョワ学者と呼ぶやうに)は国家は個々人が個々人の所有権及び人格権を擁護する目的のために作つたやはり一種の道具であり機械であると考へた。しかしいまわがドイツ国民社会主義はいかなる国家工作物説にも一般的に反対するのである』と。
ではドイツ国民社会主義者のいはゆる国家は、積極的にいふと、どんなものなのであらうか?ゲルバーは語を次いでいふ——『ドイツ国民社会主義は、国家をば民族の生活形式と見る。生活形式とは、「人が生活へ押付けた形式」といふ意味ではない。「生活そのものが産み出した型」といふ意味、再言すれば「生活そのものの内的本質から有機的に産み出された形態」といふ意味である。国家は作られたものでなくて生れたものであり、人為的なものでなくて自然的なものであり、機械的なものでなくて有機的なものである』と。
かやうにナチの学者たちは『国家工作物説』一般に反対して、『国家は民族の生活形式だ』といふ・かなり難解なもののいひ方をするのであるが、彼等がその際いひ現はさうとしてゐる真の意味は、『国家は個々人が作つたものでもなく、階級が作つたものでもなくて、全民族が全民族のために作つたものだ』といひたい点にあるらし\CHUT{い}{(一)}。一体に合理主義を去つて神秘主義・精神主義へ後ずさりしようとしてゐる彼等は、『精神・意志・生活表現・生活形式』などいふ神秘ががつた言葉を愛用する傾向が強いのである。
一 ナチ党及ナチ学者も往々国家は手段だとか方法だとかいふ語を使用する。しかしそれは全民族のための手段だといふ意味であつて、階級のための手段だとか、個々人のための手段だとかいふ意味ではない。
次に法理学界の耆宿ユリウス・ビンダーの新作『民族国家』をひらいて見ると、結論はやはり国民社会主義者一般の見解と同じだが、さすがにその思想の豊麗・表出の自在さにおいて、余人の追従を許さざるものを示してゐる。曰く——『一民族は、歴史的に一定の地域を占有し、利用し、他民族の侵奪から永くこれを守つて来た。同一運命の運載者として、生死を共にする単位体として、遠く歴史の上を流れて来た。彼等の血は累代の族内婚姻によつて共同化され、彼等の精神も言語・風俗・文化の共通によつて共同化されて来た。民族とはかかる血液・精神及び運命の共同体をいふに外ならない。人間は個々人であるよりも、より多く民族の一員である。彼は生れながらにして一定の民族に所属すること、恰も出生によつて一定の家族に所属するがごとくである。彼は民族から脱離することをえず、民族自身の活動を抑制することもできない。彼の思想の方向と行動の方向とは強く民族によつて規定されてゐるのである。大体において彼は民族が感じるやうに感じ、民族が考へるやうに考へ、民族が活動するやうに活動してゐるのである。信念も意志も大体において民族共同的であるのである。そしてこの最後の意志の共同といふことが、国家の成立に対しても法律の形成に対しても大関係をもつのである。法律の本質が意志であるやうに、国家の本質も意志である。国家は民族共同の意志の上に打ち建てられてゐる。民族の自我意識の上に、祖国愛の上に、打建てられてゐるのである』と。
つまりビンダーは個人を国家構成の基礎と見ずに、民族即ち『血液及び精神の共同体』を、国家構成の基礎と見るのである。彼は揚言してかうもいつてゐる——『従来の国家学説は個人の観念から出発してゐた。個人だけが実在であり、所与であり、疑ふべからざる前提である。団体などといふものは架空の想像か、仮設の概念に過ぎないと考へて来た。しかし団体は架空でもなければ仮設でもない。それは個人を現実に支配してゐる社会的実在である。少くとも最近の社会学は団体を一箇の社会的実在と見るのである。団体は実に最近の社会学的発見物の一であるといつていい。而して今われらはこの最近の発見物たる団体を基礎としてわれらの国家学説を立てるのである。国家の基礎は個々人ではなくて民族である』と。
かやうな国家学説、即ち民族を国家の基礎と見る学説は、何をその結論としてもたらすであらうか?第一にそれは異民族排斥主義を結果する。凡そ異民族は血液を異にし、精神を異にするので、これとは到底相共に国家を構成し、政治的運命を共同にしてゆくことができないと見るからである。ナチ独裁者があの通り、ユダヤ人を公職から追つたり、ユダヤ人とドイツ人との間の結婚を禁止したりしたのも、元はといへば、ユダヤ人は異民族であるから、彼等と相共に国家を構成することはできないといふ理由からであるであらう。第二にはこの国家学説は単一家主義を結果する。凡そ同民族は血液及び精神を共同にするので、合同して単一国家を作り、単一の中央的政治意志の指揮の下に立てば足ると考へるからである。ヒットラーがあの通り、ドイツの各州即ちプロイセンとかバイエルンとかいふ・今までは独立の国家であつたところの各州から独立国家的要素を剥奪して、これを単なる地方団体としての地位へ突き落してしまつたのも、元はといへば、一民族は一国家を有てば足るとの見地からであつたであらう。実に『ドイツ単一国の建設は』、ゲルバーのいつてゐる通り、『国民社会主義の国家政策の本質的目的であるのである』。
『一民族、一国家』(ein Volk, ein Reich)——これは新ドイツの一神教である。そしてこれは、一方においては異民族排斥主義となり、他方においては単一国家主義となつて現はれつつあるのである。
ビンダーの雄弁はなほつづく。彼は民族性と国家形態との関係を論じてかういつてゐる——『国家は民族を基礎として成立するから、国家の形態は民族別に相異してゐていいわけである。だのに従来の国家学説は、画一固定の規準を立て、これを以て国家の善悪・発達未発達を判別して来た。即ちデモクラシーを唯一絶対の基準に取り、デモクラシーの要請を満すこと多ければ善い国家であり、少ければ悪い国家であると決めて来た。即ち従来の国家学説は各民族が自己の歴史・自己の性情に適合せしめて各別にその国家型態を決定しうる権利をもつといふことを失念してゐたのであつた』と。
かういつてビンダーはドイツ現在の国家即ちアドルフ・ヒットラーの独裁的統率の下に立つ国家を——ビンダーはこれを『アドルフ・ヒットラー国』(Reich Adolf Hitlers)といつてゐる——ドイツ民族の性情に最も適合的なる国家形態なりとして、支持し是認し称美してゐるのである。ワイマール憲法の自由主義・民主主義などは、ビンダーにいはせると、ドイツ人の民族性に対する『不正』であり、『犯罪』でしかなかつたのであつた。
以上をもつて私はナチ学者の民族国家理論を紹介し了へたつもりだが、元来この理論は自由主義的国家理論への反対物として主張されてゐるのであるから、自由主義的国家理論に対する彼等の批判を参照することによつて、一層十分に彼等の民族国家理論そのものを明かにしうるかとおもふ。よつて私は自由主義的国家学説に対するランゲの批判を併せてここに紹介しておくとしよう。
ランゲはその著『自由主義・国民社会主義及び民法』の中でいふ——『自由主義者は抑も何から自由であらうと欲したか?それは時代によつてかなりの変化を示したのであつた。即ち宗教改革時代の自由主義者は、教会から自由にならうと欲した(信仰上の自由主義)。啓蒙時代の自由主義者は、因襲的諸観念・諸思想から自由にならうと欲した(思想上の自由主義)。しかしその後の自由主義者は、信仰上思想上といふやうな内的心的な自由よりも、もつと俗的外的な自由を望むに至つた。フランス革命の自由主義者は専制政治から自由にならうと欲し(政治上の自由主義)、経済学上の自由主義者は個人の営利活動に対する国家の一切の干渉・一切の取締から自由にならうと欲した(経済上の自由主義)。しかしここに至つて自由主義は遂に一箇の放縦主義に堕したのである。人民は欲するがままに考へ、信じ、言ひ、行動し、取引し、蓄積し、消費しうることとなつた。国家は人民の傍若無人なる営利活動を拱手傍観してゐる外はなくなつた。古来自由主義ほど国家の統制機能を後退させたものはなかつたであらう』と。
自由主義に対するランゲの怨みは綿々として尽くる所を知らない。語を次いでさらに彼はいふ——『自由主義の弊は遂に祖国を忘れさせるに至つた。資本家は祖国を忘れて国際的に投資し、取引し、労働者も亦祖国を忘れて外国労働者と国際的に団結し、学者も亦祖国を忘れて外国思想に動かされ、芸術家も亦祖国を忘れて外国芸術を謳歌するに至つた。自由主義の下においては労働者に祖国なきばかりではない。資本家も学者も芸術家もみな祖国を有たぬのである』と。
『しかし、』とランゲはこの辺で話題を一転する——『幸なるかな、いまドイツでは「自由」の代りに「共同」が登壇した。ドイツではもう「単なる個人」は見られない。人間はみな共同体の中へ織込まれ、その中で地位づけられ、その中で責任づけられてゐるのである。人間はみな有機体の一分枝である。彼は単に他人の利益を犯さず、全体の発達をも害せざるべき極めて限極せられた範囲内において、行動の自由を享有するに過ぎないのである』と。
一層彼は語気を強めて、『民族は共同体の完成であり、極致である。民族の利益の前には、個人の利益は粉砕されていいのである』ともいつてゐる。
なるほどナチ学者のいふ通り、自由主義の国家学説は、『全体の立場』といふものを知らずにゐた。もちろん個人の放邪を全然取締らうとしなかつたわけではなかつたが、自由主義の国家学説が個人の放邪を取締らうとしたその原理は、もし一個人が放邪であるならば、他の個人の利益や自由がこれによつて侵害されるに至るからといふにあつた。全体の立場からする統制ではなくて、個人利益の擁護といふ・やはり一種の個人主義的立場からする取締に過ぎなかつたのである。又自由主義の国家学説といへども国家の防衛を閑却せず、国家は外敵の襲来を防がざるべからずと主張はしてゐたが、これとても、もし外敵の侵入を受けるやうなことにでもなれば、これによつて個々人民の生命財産が害されるに至るだらうといふ・やはり一種の個人主義的動機に基いたのであつた。決してそれは国威そのものの発揚・国利そのものの伸張といふ思想から出たのではなかつたのである。結局国家は彼等にとつては、『個人利益擁護のための道具』であり、それ以上のものではなかつたのである。
しかしいまドイツ国民社会主義の国家観は『全体の立場』を主張する。彼等はまづ民族意思といふ超個人的精神の実在性を承認し、国家はかかる全体精神の実現を以てその任務となすと考へるのである。敢て彼等の忌避を冒して、『工作物』といふ語を使用するならば、『国家は全民族の自我実硯・意思達成のために全民族の作つた工作物』だと考へるのである。だから国民社会主義の国家が個人の行動を制肘するのは、その個人の行動の結果他の個人の利益が害される虞があると見るからではない。むしろ民族そのものの利益の伸張上、その個人の行動に制肘を加へる要ありと見るからである。又国民社会主義の国家が外敵と戦ふのは、外敵によつて個々国民の利益が犯されると見るからではない。外敵によつて国利そのもの、国威そのものが傷つけられると見るからである。ビンダーがいつてゐる——『民族国家は内に向つては、「共同」の精神・「義務」の思想を以て、個人の自由を抑へようとする。外に向つては、一民族としての権威を高め、他民族によつて犯された名誉を回復しようとする。民族自身の自我を実現し、民族自身の利益を伸張するのが民族国家の本然の任務である』と。
二 ナチ学者の法律観
以上ナチの『国家観』を紹介し了へた私は、進んで彼等の『法律観』を見ようとするのであるが、彼等の法律観は彼等の国家観の当然の延長でしかないがために、簡単な概線的説明のみを以てしても、ナチ法理学に対する読者の理解を十分にかちうるかとおもふ。
まづラレンツの新著『法律更新と法律哲学』を覗見すると、こんなことをいつてゐる——『法律は君主の命令でもなければ議会の製作品でもない。むしろそれは民族共同体の生きた意志である。けだし民族共同体は共同体内部の構造へ恒久の組織を与へ、成員相互の関係へも安定的秩序を与へようと欲してゐるのであるが、かかる民族共同体の意志の現はれこそ、即ち法律に外ならないのである。それは実在であり、経験的現実である。そしてそれは裁判官及び執行官によつて適用され、実現されてゐる。法律は裁判所と不可分に結びつき、権力と一体をなしてゐる。適用され執行されないやうなものは、たとへ民族共同体の意志であつても、法律ではない。せいぜいのところ道徳か風習かに止るであらう。法律の法律たるゆえんはその執行性にある』と。
かういつてラレンツは法を実在だとして、民族共同体の意志だとして、即ちどこまでも民族主義の見地よりして、法律を本質づけてゐるのである。
法律の妥当の問題に関しても、ラレンツは民族主義的立場より解答を与へようとする。曰く——『個人は独立の人格であり、独立の意志主体であるがゆゑに、個人の意志が常に必ずしも民族の意志と一致するとは限らない。個人意志と民族意志との間に分裂を見、矛盾を発見することも決して稀ではないのである。しかし個人は元来民族共同体を足場として立ち、根として生きてゐるものに過ぎぬのであるから、個人は結局、民族共同体の意志へは屈服せざるをえない。ここにおいて個人は民族共同体の意志へ屈服することを、自己自身の義務なり、当為なりと観想し、自己の方から自発的にこれに服従して行かうとする態度を示すのである。古来「法律は当為か存在か」といふ議論が、法理学上の問題として争はれ来つたが、答は何人の立場からこれを見るかによつて異るべきだ。法律を強行する共同体自身の立場からすれば、法律はどこまでも力であり、実在である。法律に服従する個人の立場からすれば法律は義務であり、当為である』と。かういつてラレンツは法は当為か存在かといふ古来の難問をも、民族法理学の立場から事もなげに片づけ去つてゐるのである。
法の価値の問題に対しても、ラレンツはやはり民族主義の立場から断案を下す。曰く——『法律は民族から制約される。法律の価値は、それが民族の特有の道義観を反映してゐればゐるほど、又、民族特有の風習と堅く結びついてゐればゐるほど、高くして且つ純である』と。
民族特有の性情を法律価値判定上の究極基準に取らうとする右のやうな考へ方は、ひとりラレンツの特有ではない。一般にナチの学者は、民族的法律価値観とでもいふべきものを抱いてゐるのである。その極遂に、『ドイツ法の中から非ドイツ的のものを芟除せよ』とか、『ローマ的・ユダヤ的のものを駆逐せよ』とかいふ主張を試みるやうにもなつてくるのである。ここにはその一つの例としてハイデブランドのドイツ法純化論を紹介しておくとしよう。
ハイデブランドはその著『法律更新』の中でいふ——『ドイツの法律界で奇怪至極なことは、健全なドイツ人の不名誉と考へ、下等と考へ、到底為すに忍びないと考へてゐる多くの事が、法律上「合法」とされ、「可能」とされ、裁判所の協力をえて実現されてゐる一事である。いまもし一個の素人がその率直な胸に道理と感じ、正義とおもふ所のものを法律家の前へ披瀝してみたとすると、彼はきつとその法律家から、「それは素人の考へサ」といつて一蹴されるのを免れえないであらう。実にドイツの法律家は廉恥心ある健全なドイツ人の正義感情を育て上げずに、むしろそれを殺してゐるのである。これは全くドイツの法律学がローマ的・ユダヤ的考へ方の過大な影響の下に育つて来た結果だつたといはねばならない。けだしローマ的・ユダヤ的考へ方の特色は、一定の効果を挙げんとして一途に無遠慮に冷酷に突進する点にある。それは一の事物を他との聯関において捉へ、全体との調和において見ようとするドイツ固有の考へ方とは、凡そ対蹠的な考へ方でしかないのである。実にドイツ人固有の調和的・平和的・全体主義的法律生活はローマ的・ユダヤ的考へ方のためにすつかり荒らされてしまひ、傷けられてしまつたのである』と。
このやうな民族的法律価値観に立脚してドイツ法を根本的に改正しようとする志向は、ナチ法学運動の基本方向の一つである。いはゆる『法律更新』の事業は民族的法律体系の樹立へ向けられてゐるのである。ラレンツも『法と民族との間に横はる間隙を填め、ドイツ法をしてドイツ民族の道義観念に適合するごとき内容と形式とを有せしめ、真の意味に於いてこれをドイツ法たらしめんとすることが、ドイツ国民社会主義の法律更新事業の目的である』と言明してゐるのである。
三 ナチ学者の法学観
しかしドイツ国民社会主義の主張は、法律そのものの更新だけに満足してゐるのでは決してない。進んでさらに法律学そのものの更新を叫び、法律学者をして従来のごとき形式的・抽象的論理遊戯の弊を脱せしめようとしてゐるのである。而してこの方面の運動をいとも花やかに指導しつつあるのは、ベルリンの教授カール・シュミットであるから、私は彼からその主張を聴くこととしよう。
カール・シュミットはその新著『法律学的思惟の三型』の中でいふ——『法律更新は同時に法的思惟の更新である。ドイツ法学の法的思惟は今まさに新しき形態へ移らんとしつつあり、又移らねばならぬこととなりつつあるのである。おもふに在来の法的思惟はあまりといへば形式的であり抽象的であつた。それは純粋に法学的であらうがために、一切の実質的考慮、即ち道徳的・政治的・社会的・経済的諸考慮を斥けて来た。それは法律と道徳・法律と政治・法律と社会・法律と経済を対角的に峻別して来た。しかし道徳を離れ、政治を離れ、社会を離れ、経済を離れて、果して何が法律として残るであらうか?そこには単に形式的な論理と空虚な概念とが残るのみではなからうか?今ドイツにおいては国家と民族とが一致し、法律と道徳とが合体しつつある。ゆゑに現下のドイツ法律学者は、法律と道徳・法律と政治を同じベットに寝かしつけなければならない。これらのものを全的具体的秩序として把捉しなければならない。ドイツの法律学はいま思惟転換の重大危機に直面してゐるのである』と。即ちシュミットは法律解釈の中へ、社会的政治的道徳的考量を思ひ切り大量に導入させようと企ててゐるのである。彼はかういふ解釈の新方法を、『全的秩序としての法の把捉』と呼んでゐる。
シュミットの旧法律学的方法に対する火のやうな攻撃はなほつづく。曰く——『在来の法律学は法的保護の予見といふことを主眼にしてゐた。どんな利益は法から保護されてゐるか、どんな利益は裁判所掩護の下に強制的に獲得しうるか、それを予め見透しておきたいといふ動機に支配されてゐた。だから在来の法律学はまづ法の内容を疑ひなきものに確定しておかうとして、法の文言に周到細心な註釈を加へたのである。又法を運用する裁判官の心理及び手法を洞見しておかうとして、判例を研究し、その変遷の跡をも尋ねたのである。彼等が法的考察の「純粋」を尊び、政治的・経済的・道徳的諸考慮の侵入を防止しようとしたのも、かかる実質的考慮の侵入によつて、法律の意味内容が不明瞭にされ、不確実にされ、その極遂に人民の法的期待を裏切るに至るであらう、と専らその点を恐れたからである。なるほど人民は法的期待の安全保障を希望してゐやう。彼等は予め、どんな利益は裁判所の協力をえて強制的に他人から捲上げらるるか、どんな損害は裁判所の承認の下にこれを他人へ転嫁させうるか、間違なく知つておきたいと考へてゐるのである。そして在来の法律学は、人民のかかる希望に答へ、又それだけに尽きたのである。だから旧法律解釈学は、民族共同体の意思が何を「正」と考へ、何を「不正」と考へてゐるかを認識しようとする学ではなかつた。単に法廷においてはいづれが勝ち、いづれが敗けるかを予め教へておかうとした学たるに過ぎなかつた』と。
このやうにカール・シュミットは在来の法律学の性格を鋭く突いた後、かかる学的方法の棄てられなければならぬ所以を説明する。曰く——『十九世紀の人民が法的安全の利益を享有しえたゆゑんのものは、法律学が純法学的考察の方法を採用してくれた結果ではない。十九世紀の国家自体が比較的安固な存立を保つてゐたからである。国家が安定してゐたればこそ、人民の法律上の地位も安定しえたのである。然るに現下のドイツは変革の過程にある。国家も法律も根本的に動きつつある。かかる変革期の法律に対して純粋法学的考察の方法を用ゐても、あまり意義がないではないか』と。
要するにシュミット等は法律家に対して、形式的抽象的考察方法の廃棄を命令するのである。そして社会的・道徳的・経済的・政治的考量の導入を要望するのである。殊にこの最後のもの即ち政治的考察の導入を切に勧告してゐるのである。然らば政治的考量の導入とは、具体的にいつてどんなものを導入せよといふのであらうか?
去る一九三四年五月カール・シュミットは司法大臣フランクの嘱を受けて『ドイツ法曹時報』の編輯に当ることとなつたが、翌六月の同報に『法律家の進むべき道』たる一文を発表してこんなことをいつてゐる——『裁判所は独立の地位を有し、法律に依るの外何人の意志にも動かされる必要のないこと、今さらいふまでもないが、このことは、何も裁判所は古い概念の塔の中にとぢ篭つてゐてもいいといふ意味にはならない。民族共同体の意志は不断の進展を示しつつあるのだから、裁判所は生きた現在の民族意志に立脚して法律を解釈適用する必要があるのである。而していまドイツでは、国民社会主義の勝利が生活の全面へ、殊に法的生活へ、新しい内容を与へてゐるのであるから、裁判所は、国民社会主義の運動によつて一新された民族意志に基いて法律を解釈適用しなければならない』と。即ちカール・シュミットの、『法律解釈の中へ政治的考慮を挿入せよ』といふ主張は、具体的にいひかへると、『国民社会主義運動の精神に則つて法律を運用せよ』といふことなのである。
ラレンツもかういつてゐる——『ドイツにおいてはヒットラー出現以前の法律にして明示的廃止を受けざるもの多々残つてゐるが、これらがなほ法的効力を保つや否やは、裁判所これを審査決定することをえない。裁判所はただ、大総統アドルフ・ヒットラーによつて法的効力を有すと認められたる条規のみを解釈適用してゐさへすればそれでいいのである。而してこれを解釈適用するに当つても、裁判所は、ヒットラー出現以前の旧民族意思を基準に取つてはならない。ドイツ民族の法律意思はヒットラーの登場によつて根本的に一新されてしまつたのであるから、裁判所たるものは、彼登場以後の新民族意思に則つて、旧き法律を解釈補充すべきである』と。
ニコライは最も果敢なナチ法律運動の闘士であるが、一九三四年一月三十日公布の『国改革法』を註釈したその著述中において、次のやうに力説してゐる——『ワイマール憲法の法律精神又は国家精神は、もはや規準的ではなくなつた。この憲法の旧精神は、国民社会主義の新精神によつて超克されてしまつたからである。一切の法律的領域において、国民社会主義の精神に則る新解釈が下されねばならぬことになつて来た』と。
果然、ナチ学者の主張の要旨は、『法律の解釈適用は、ナチ運動の精神に則つて進められねばならない』といふに在つた。
四 ナチ学者の私法観
以上をもつて私はナチの国家観及び法律観の要相を紹介しえたので、以下特に彼等の『私法観』だけを見ようとする。元来私法は、政治から遠隔の地域に存し、政治の影響を被ること最も薄稀なのであるが、この安全地帯さへも、今では相当に揺れつつあるといふことは、以てナチ運動の法律へ及ぼす影響の、いかに広大なるかを示すものだとおもふのである。しかし配当されたページは、いま数枚を余すのみとなつてゐる。よつて私は、目下その必要を叫ばれつつあるドイツ民法改正の問題に絡んで、ナチ学者がいかなる改正意見を持してゐるかを具体的に示すことによつて、彼等の私法観を仄見せしめるといふ簡単な紹介方法を使用することにしたい。しかもそれさへ民法全範囲に亘る改正意見を示すことは不可能なので、単に『民法総則』中の一二の規定に対する彼等の改正意見を見本的に示すだけに止めるとしよう。
第一は総則の第一節『人』に関する規定の改正問題であるが、これについて彼等はいふ——『現行民法は団体から遊離した個々人を権利義務の主体としてゐる。個々人が財産主体であり、意思主体であり、行為主体であり、責任主体であり、あらゆる法律現象の基本単位であると見てゐる。しかしこれは、あまりに技巧的なる個人主義的構想産物でしかない。現実の人間は決してそのやうな不羈独立の主体ではなくて、この周囲から強く拘束されてゐる主体である。即ち彼は家族であり、夫婦であり、労働者であり、兵士であり、若くは学生であり、店員であるのである。いづれかの団体に所属し、その団体内において一定の地位を有し、一定の権利をもち、一定の責任を果してゐるのである。ゆゑに当来の民法は、人間を「個人」として掴まず、「団員」として掴まなければならない。何等かの団体に所属するものとしてこれを掴み、その中において彼がいかなる権利を有し義務を負ふか定めるといふ全然新規な構成技術へ転向しなければならない』と。即ちナチ学者は、個人主義基礎の上に立つ現代民法の大組織を一旦微塵に分解して、団体主義的基礎の上にこれを再構成しようと欲してゐるのである。
第二は『物』に関する規定の改正に関してであるが、ナチの学者はかう考へてゐる——『現行民法は物界において独立の存在を有するものを一物として、その上に一所有権を成立せてゐるが、これはあまりにも極端なる単一物主義である。現実界を眺めると、物は或は他物に附随してその従物となり、或は他物と結合してその構成部分となり、或は他物と集合して集合物を形成し、或は人間の労働・無形の権利・事実上の利益等と相結んで経済的価値高き『組織』となり、『経営体』となつてゐる。在来の考へ方は、あまりに分割的であつたのである。それはちやうど人を他人との結合から切断して個人にしてしまつたやうに、物をも他物との結合から切断して個物にしてしまつたのである。団体主義の時代には人が団員となるやうに、物も集合物とならなければならない。集合のまま保護され、集合のま権利の対象となり、集合のまま取引さるといふことにならなければならない』と主張する。
しかしナチ的改正意見の焦点を民法総則の規定中に求めれば、もちろんそれは契約自由の規定に関する改正意見であらう。現行ドイツ民法は人の知るごとく、『善良の風俗に反する法律行為』を無効としてゐるのであるが、ナチはこのやうな微温的干渉には満足できない。もつと強力鋭利な干渉を個人間の契約へ加へようと欲してゐるのである。例へば闘将ニコライはいつてゐる——『法律行為は善良の風俗に違反する場合にばかりでなく、ドイツ人的名誉感・ドイツ人的礼譲感・ドイツ人の公益公安を害する場合にもまた無効とされなければならない』と。
では『ドイツ人の公益公安を害する契約』とはどんなものなのかといふと、ニコライは暗に、『ヒットラー総統の施す政策又は指導の趣旨に背馳する事項を約した契約』を意味させてゐるのである。なぜかなら、彼によると、ヒットラー総統の施す具体的各政策・具体的各指導は、常にドイツ人の公益公安を増進してをり、これに反する意見や行動は常にドイツ人の公益公安を害してゐるからである。彼は恐らくヒットラーの施す貿易政策・為替政策・農民保護政策等の趣旨に背馳する契約を片つ端から無効とさせたいのであらう。
しかしかう逐条的に、ナチの民法改正意見を紹介してゐては全く切りもないので、私は、ナチ国における個人の地位を説いたビンダーの一句を最後につけ加へてこの小論を終るとしよう。この句ほどナチの根本的私法観を簡潔に示したものはないとおもふから——
『民族国家においては、個人は共同体の分枝であり、国家は分枝の統一者である。分枝たる個人は統一者たる国家の精神を以て常にその精神としてゐる。彼のあらゆる行為・あらゆる活動・あらゆる創作のなかに、国家共同の精神が血となつて流れ込み、魂となつて貫かれてゐる。もし国家生活から全然脱出してゐる生活を「個人の自由地帯」といふならば、民族国家の成員たる個人はかかるものを有たぬこととなる。なぜかなら民族国家の個人は常住国家共同の精神の上に生きてゐるからである。民族国家においては公法と私法との有機的統一を見る』。