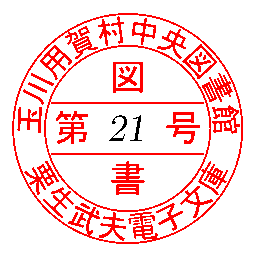
一 はしがき
宗教信者の生活は、法的規整の対象となるよりも、宗教的又は道徳的規範の統制を受ける場合の方が多いであらう。彼等の規範は、彼等の心霊の内奥を規律するのである。それは彼等に向つて『一定の外的態度を示せ』とか、『一定の外的効果を発生せしめよ』とかは命じない。一層深く彼等の内的心理過程に滲透して、『一定の内心的態度をとれ』と命じるのである。行為よりも心術を規定するのである。がしかし信徒の数が著しく増加し、信徒相互の関係や信徒対教会の交渉が著しく複雑化してくると、多少ともこれらを事務的・機械的・形式的に処理し去る必要を感じて来る。内に隠れた心術を見ず、外に顕はれた行為のみを材料として是非曲直の判断を下すやうになつてくる。この時はじめて教会法の誕生があるのである。Schulteのいつたやうに『もし外的効果(äussere Wirkungen)の発生に関する点が法規の特色であるならば、外的効果の発生に関する規範が教会内に発生した時点を以て、教会法の発生時点となさざるをえぬであらう』(一)(二)。
さてかやうに教会内において宗教規範と法的規範との分岐を生じてくると、第一に何人が教会生活に関し法的規範を定立しうるや、即ち何人に立法権ありやが問題となつてくる。国家に立法権ありや教会にありや、教会にありとすると、それは教会の固有に係るか、乃至また国家からの伝来取得によるかといふことが問題となつてくる。第二に教会に立法の権ありとすると、その立法権は教会のいかなる機関が行使するのか、信徒が法を作るのか、僧侶が作るのか、僧侶中の一部のものが作るのかといふ問題を生じてくる。法律意思の表示形式に関しても、慣習によるのか、成文によるのかといふやうな問題を生じてくる。
これをクリスト教会の歴史について見るに、(一)紀元一世紀から四世紀初までは、教会は国家から禁じられ迫害された『不法の団体』に過ぎなかつた。がそれは事実上立法の権を固有し、信徒のために種々の法を立てつつあつた。立法の機関は監督であつた。各地方教会の監督はその執務上の慣例を以て、それぞれの地方教会のために法を作りつつあつたのであつた。これを使徒教会法(apostolisches Kirchenrecht)の時代といふ。(二)四世紀から八世紀までは、教会はローマ皇帝の下に立つ一種の自治体であつた。ゆゑにこの時代には、教会自身が立法しえたけれども、皇帝もまた立法しえたのであつた。教会自身の方は、主として『僧正会議の決議』といふ形式の下に立法してゐた。一県の僧正は県宗教会議を催して一県のために、一州の僧正は州宗教会議を催して一州のために、全帝国の僧正は一般宗教会議を催して全帝国のために、教会法規を作つてゐたのである。これをローマ教会法(römisches Kirchenrecht)の時代といふ。(三)八世紀から十二世紀までは、教会は再び国別に分裂し、各国国王の支配の下に立つた。僧正会議も国王の命によつて国別に開かれ、その決議も国王の同意を経てはじめて法となつた。ローマ時代の教会法が帝国的・世界的であつたのに反して、この時代の教会法は地方的・封建的であつたのである。これをゲルマン教会法(germanisches Kirchenrecht)の時代といふ。(四)十二世紀から十五世紀までは教会の最盛期である。この期の教会は国家の下に立たず、むしろその上に立ち、少くともその外に立つた。教会の有する立法権は国家から伝来せず直接神に発すると考へられた。法王は教会最高の機関として訓令を発し、訓令の作用によつて地方諸教会の慣習や法律を廃止変更することができた。一般宗教会議も亦法王の召集にかかり、その決議も法王の是認の下にのみ法となりうるだけとなつた。これを法王教会法(päpstliches Kirchenrecht)の時代といふ。従前の立法が民衆的・会議的であつたのに反し、この期の立法は君主的・独裁的であつたのである(三)。
本稿において私は一世紀から十五世紀に至るまでの間の教会立法の大要を概示して見ようとおもふ。すなはちこの間に教会の立法形式はいかに変遷したか、各時代にいかなる法典が、若くはいかなる法源集が編纂されたかを見、傍ら教会法学の発生過程にも言及して見たいのである。
一 Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts I. 32.
二 教会法の意義に関しては二説ある。(一)は立法の主体に着眼するもので、『教会法とは教会によつて独立的に作られた法(das von der Kirche selbständig erzeugte Recht)なり』とする。この説に従ふと、教会法律関係を定めた国家の法律は、それが教会から承認され継受された場合は格別、然らざるかぎり、教会法たりえぬといふことになる。(二)は規定の内容に着目するもので、『教会法とは教会の法律関係を定めた法(das die Rechtsverhältnisse der Kirche regelnde Recht)なり』とする。これによると立法の主体は誰であれ、教会法律関係を定めたものなるかぎり、教会法となるのである。本論において余は第二の用語例に従つた。
三 余が本論において教会の法源史を使徒時代・ローマ時代・ゲルマン時代・法王時代等々に分つのは、主として斯学の泰斗Stutzの時代区分法に模したのである。Stutzは一世紀から十五世紀までを四期に分ち、(一)使徒教会法(Missionskirchenordnung)の時代として一乃至四世紀を、(二)ローマ教会法(römisches Kirchenrecht)の時代として四乃至八世紀を、(三)ゲルマン教会法(germanisches Kirchenrecht)の時代として八乃至十二世紀を、(四)カノン法(kanonisches Recht)の時代として十二世紀乃至十五世紀を含ませてゐる(Stutz in Holtzendorff-Kohlers Enzykl. V. 279 fg.)。この区分法が教会法の発達段階に対する深き理解の産物であることについては、Vgl. Sohm, Kirchenrecht II. 152 fg.
なほStutzの門下Koenigerは、(一)一世紀から四世紀までを教会法の自由発生期、(二)四世紀から七世紀までをローマ法の影響を受けし時代、(三)七世紀から十二世紀までをゲルマン法の影響を受けし時代、(四)十二世紀から十五世紀までを学説の影響を受けし時代、としてゐるがこの区分法もKoeniger自身の認めるごとく、Stutzに模したものであるのである(Koeniger, Grundriss einer Geschichte des katholischen Kirchenrechts 1919)。
二 使徒時代及ローマ時代
教会法最初の萌芽は、イエス自身の教のうちに見出されるともいはれてゐる。例へばKoenigerは、マルコ伝一一章一五節・マタイ伝二一章一二節・ルカ伝一九章四五節等を援用して、これらの箇所に見える・『イエス宮に入りその内にて売買する者を逐出し、両替する者の台を倒し云々』の事蹟のごとき、たしかに不信者に対してイエスの加へた処罰行為そのものであつた。イエスは教を説いたばかりでなくて、律法をも立て処罰をも敢てしたのである。信徒をして愛・信仰・克己・正義の新生活を送らせるためには、時々彼等に法と刑とを加ふるの必要あるべきことをイエスみづから示したのであると説いてゐる(一)。
又同氏は、マタイ伝二八章一九節・マルコ伝一六章一五節等を援用して、イエスは、彼がその十二の使徒に福音の伝道を遺嘱した際、彼等に対して教師(Lehrer)たると同時に裁判官(Richter)たれとも教へたといふのである。イエス自身が為せると同様、使徒等もまた信徒に対して時宜により威嚇を用ふべしと教へたといふのである(二)。
かかる伝説の解剖はしばらくおき、とにかく使徒を源頭として教会法の発達が始つたといふことは事実であつた。彼等十二の使徒たちはイエスの死後四方を歴遊して各地に小宗教団体を設立し、その基礎的組織を定めると同時に、信者の守るべき道徳的又は法律的範則をも定立したのである。彼等は教会の開基であつたと同時に、教会法の設定者でもあつた。教会及教会法はイエスからといふよりも、むしろ使徒から発生したのである(三)。
使徒等の後に出でて次代の教会生活を指導したのは、当時、監督(episcopus)・長者(presbyterus)・補佐(diaconus)などと呼ばれてゐた長老(四)の一列であつたが、彼等もまた初期教会法の進展に貢献するところ少くなかつた。なぜなら彼等は、『主の言葉』や『使徒の遺訓』を尊重すると称しながら、実は執務の実際に当つてこれを変改する場合があつたし、名を先例にかりて新法規を創始する場合も稀ではなかつたからである。初期教会法の若々しい新芽が伸びやかに成長することをえたのは、一に彼等の裁判慣例と執務先例とによる新法規造出の賜であつた。彼等は又、地方的小会議を催して裁判方針を一定し、一地方の判例に統一をもたらす作用をも営んだ。
一 Koenger, Grundriss 1.
二 Koeniger, a. a. O.
三 Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten 2. Aufl. 1906.
四 episcopus(監督)とpresbyterus(長者)との間に、初めどんな区別の存せしやは不明であり、一つの謎となつてゐるやうであるが(Vgl. Friedberg, Kirchenr. 20)、後にepiscopusの地位が向上して後世のBischof(僧正)の前身となるに至つたこと、presbyterusの地位が低下してepiscopusの単なる補助者となるに至つたことについては、異説を見ぬものの如くである。diaconus(補佐)に至つては、初めからepiscopusやpresbyterusの補佐役に過ぎず、主として病者・貧者の救済事務を取扱つてゐた。
二・三世紀以降に及んで種々の法源集の編成を見ることとなり、殊にシリア・パレスチナ等の東部地方において、多くの法源集の出現を見るに至つた。西部すなはちイタリイにおいてその頃未だ法源集の出現を見ることをえなかつた理由は、イタリイにおいては、新宗教に対する政府の弾圧が峻酷を極め、教会の発達も教会法の成長も東部に比し共に著しく遅れがちだつたためであつたといひうるでもあらうか。
さて東部で出来た法源集中の最古のものは、近く十九世紀に至つて発見されたところの——即ち一八八三年Bryenniosによつて発見されたところの——Didacheといふ説教集であつたであらう(一)(二)。これは使徒自身の説教集たる体裁を有してはゐるが、その果して然りしやは疑はしく、むしろ真実は、二世紀頃の教会規則を、使徒の訓言に仮託して宣示したものであつたらうといはれてゐる。用語はギリシャ、編纂年代は二世紀の初め、内容は例へば、洗礼は僧侶これを執行す・一般信者はこれを執行することをえずとか、信者はユダヤ教の説教師とクリスト教の説教師とを注意して鑑別し、前者を排して後者のみを歓待せよとか、いかにも発生期の教会法らしさを呈示してゐるのである。
一 Ausg : Harnack in Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur II. 2. 178--192. Friedberg, Die älteste Ordnung der christlichen Kirche (Didache mit Übersetzung), Zeitschr. f. Kirchenr. XIX. 408.
二 Didacheの内容を示すためにFriedbergの訳から一例を抜く---c. 11 : Wer nun zu euch kommt und euch alles dies lehrt, was oben gesagt ist, den nehmt auf. Wenn aber der Lehrende, verkehrt, eine andere Lehre predigt, die zur Auflösung führt, den hört nicht.……Jeder Apostel, der zu euch kommt, werde aufgenommen wie der Herr. Er wird aber nicht bleiben über einen Tag.……Geht der Apostel fort, so nehme er nichts mit ausser Brot bis zur nänchsten Herberge reichend. Fordert er aber Geld, so ist er ein falscher Prophet.……
Didacheよりやや遅れてDidascalia(一)が出現した。六篇より成り、やはり使徒自身の説教集としての形式をとつてはゐるが、これまた仮面に過ぎす、真実は二・三世紀頃における東部教会の法規慣例の成文化であつたのである。内容上の特色は、僧正の権限に関する規則、例へば僧正は献金を管理すとか、信徒間に生ぜる争を裁判すとか、いふ類の規則を多く含んでゐる点に存す。原文はギリシャであつたが、今はそのシリヤ訳ラテン訳等のみが伝はつてゐる。編纂地はシリア又はパレスチナ。編纂年代は三世紀の初半か後半。とにかくコンスタンチン大帝(306--337)以前の制作と見られてゐるのである(二)。
一 Funk, Didascalia et constitutiones apostolorum I. II. 1906.
二 Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche I. 736.
四世紀の初めになると、Didascaliaへさらに二篇を加へて八篇とした法源集が現はれた。これをConstitutiones Apostolorumといふ(一)(二)。加へられた二篇のうちの一つ、すなはちConstitutiones Apostolorumの第七篇を成してゐる部分は、前述Didacheそのものに外ならなかつた。言ひかへればDidacheが、相当の修正の下においてではあつたが採択されて、新編纂物の第七篇と化したのである。加へられた他の一篇、すなはちConstitutiones Apostolorumの第八篇を成してゐる部分は、種々の素材からの抜萃であつたが、ローマの学僧Hippolytusの著書を最も重要な材料として利用してゐるといふ。要するにConstitutiones Apostolorumは、古代主要法源の掻集めであつたのである。編纂地はやはりシリアであつた。
一 Ausg. Bunsen, Analecta ante-Nicaena II. 33 fg.---Funk, Die apostolische Konstitutionen 1891.
二 Constitutiones Apostolorumは、東方において一時は有効に行はれたが、六九二年のコンスタンチノープル宗教会議が、不真正のものとしてこれを棄てた結果、東方においてすら行はれざるものとなつた。
四世紀の末に至つてCanones Apostolorum(一)(二)(三)が出た。これは最初は五十箇条から成つてゐたが、後に追加されて八十五条となつた。その多くは東方教会において当時問題となつてゐたらしいところの信徒の処罰問題に関係してゐるのである。資料は、概して四世紀中東方で屡々開かれた諸会議の決議文や、前出Constitutiones Apostolorumなどから取つた。殊に三四一年のAntiochia会議の決議を基礎としてゐるのである。編纂地はやはりシリアであつた。
一 Ausg. : Bruns, Canones Apostolorum 1839.
二 東方教会では、六九二年、コンスタンチノープル宗教会議の決議を以て、Canones Apostolorum八十五箇条の効力を公認した。西方ではこれを、それとしては公認しなかつたが、五〇〇年頃Dionysiusが、Canones Apostolorum旧五十条をラテン語に訳して、之を彼の法源集の中へ収納したので(後出参照)、旧五十条の分だけは、Dionysiusを通して西方にも行はれることとなつた。
三 Canones Apostolorumは量において少かつたので、六世紀頃、Constitutiones Apostolorumの第八篇へ、最後の一章として附合されることとなつた。
四世紀においてクリスト教は、ローマの国教(Staatsreligion)となつた。それを信ずることが嘗ては一の犯罪であつたのに、今ではそれを信ずることが法律上の一つの義務となつた。クリスト教以外のものを信ずることが、今では逆に犯罪となつたのである(一)。
教会の合法性獲得は、教会法の性質の上へ重要な変化をよび起した。以前は教会法といふのは、『不法の法(二)』(``unlawful law'')であり、不法結社(教会)の内部で事実上発生したものといふ意味を出ぬのであつたが、今ではそれが『合法の法』となり、国家的承認を得た法律秩序の一部と成り変つたのである。教会の合法化は又、教会法規の発生淵源の上へも大変化をもたらした。以前は教会のみが法源であり、教会のみが教会法を作つてゐたのであつたが、今では国家も法源となり、いはゆる国家教会法(Staatskirchenrecht)を作るやうになつたのである。殊に教会の配置・管轄・職制に関して、幾多勅法の発布を見た。けだし国家からいへば、教会は今や一種の国務担当者である。教化及救貧といふ国家の重要な行政事務を担当する公共団体である。ゆゑに国家は、他の公共団体に対してのごとく、教会に対しても組織決定の権を有しなければならなかつたからであつた。
がしかし本論では国家の立法は見ず、教会自身の立法のみを見ると、教会内において立法の局に当つたのは、宗教会議に外ならなかつた。宗教会議は或は大僧正の召集によつて開かれた。この場合には大僧正管区に駐在する僧正のみが参集した。これを県宗教会議といふ。一県のみの意思で決定できかねる一般問題については、州又は帝国の宗教会議が開催された。州の宗教会議は、教主管区に駐在する僧正等の会議であり、教主によつて召集された。帝国の宗教会議は、帝国全僧正等の会議であり、皇帝によつて召集された(三)。帝国宗教会議はもちろんのこと、その他の宗教会議といへどもそれぞれ法律自定の権はもつてゐた。自己管内の純教会的事項に関して宗教会議がなした決議は、皇帝の裁可はもちろん、その同意をさへうることなしに、当然に法となりえたのであつた。
又宗教会議は、その決議を以て法律上の疑義を解決したり、判例の方針を協定したりしたが、かかる解答及協定の集積の中からも、多くの教会法規の産出を見たのである。
一 ローマでクリスト教の信奉が事実上黙許されたのは、二六一年Gallienus帝の時であつた。法律的にそれが認許されたのは、三一二年Constantin大帝の時であり、国教となつたのは、三八○年Gratian及Valentinian両帝の時代であつた。三九一年には、クリスト教以外の宗教の信奉が禁止されることとなつたのである(Koeniger, Grundriss 17)。
二 Maitlandは、原始時代の教会法を、適切にも『不法の法』(unlawful law)と呼んだ(Pollock and Maitland, History of English Law I 1923 2)。
三 ローマの教会組織は同国の行政組織に擬したもので、市区はそのまま僧正管区となり、県はそのまま大僧正管区となり、州はそのまま教主管区となつた。市に市知事がゐて市区を管轄してゐたやうに、市知事のゐる都市には僧正がゐて、市区とその範囲を同一にする教区を管轄してゐた。県に県知事がをり、州に州知事がゐて県や州を管轄してゐたやうに、県知事・州知事の駐在する主要都市には大僧正や教主がゐて、県又は州とその範囲を同一にする大僧正管区又は教主管区を管轄してゐた。州の上に皇帝がゐて全国の行政を総轄してゐたやうに、教主の上には皇帝がゐて全帝国の教務を司つてゐた(Sohm, Kirchengeschichte im Grundriss 39; ders., Kirchenr. I. 247 fg.)
さて四世紀の宗教会議は、多くは東方で開かれ、東方にのみ効力ある規則を制定してゐたのであつたが、五・六世紀には、西欧の教会が東方の教会法を承認し、その通用力を西欧へ伸長させたので、ここに至つて元来ギリシャ語で書かれてあつた東方の諸決議をラテン語に訳して、その西欧への通用を便利にする必要を感じ出した(一)。かくして生れ出たラテン訳法源集二あり、(一)はPrisca——これは五世紀中屡々増補され、同世紀の末、完成したもので、初めはNicäa会議のラテン訳のみを含んでゐたが、次いでAncyra, Antiochia等の決議のラテン訳を加へ、さらにChalcedon, Konstantinopel等の決議のラテン訳をも加へて完結するに至つた。編纂地はイタリイ。(二)はVersio Hispana——これも亦Nicäa, Sardica, Chalcedon, Antiochia, Laodicea, Konstantinopel等における諸宗教会議の決議をラテン文に訳載せるもので、やはり屡次の補足の結果、五世紀中に完成した。編纂地はやはりイタリイであつた。
翻訳ならざる法源集としては、Codex Canonum Ecclesiae Romanaeが出た。これは諸処の宗教会議の決議文や、僧正達の訓令や、ローマ皇帝の勅法やを含み、六世紀頃ガリアで作られたと見られるが、後述Dionysiusの法源集に押されて、大した勢力とはなりえなかつたらしい。なほこの法源集は、一六七五年に神学者Quesnel(1634--)が、初めてこれを刊行したので、刊行者の名に因み、Quesnelische Sammlungと呼ばれる例である。
一 Ausg. : Bruns, Canones apostolorum et conciliorum saec. IV-VII 2 Bde. 1839---Lauchert, Die Kanones der wichtigsten altchristlichen Konzilien nebst den apostolischen Kanones 1896.
ローマ法時代に現はれた法源集中、最も組織的だつたのはCollectio Dionysianaに外ならなかつた(一)。その編成者Dionysius(†vor 555)は、五世紀末から六世紀始めにかけてローマ市に住んでゐたSchythe人の学者であつたが、法王庁筋の命を受けて、既出Canones Apostolorumの五十条をラテン文に訳し、又Nicäa, Ancyra, Neocäsarea, Gangra, Laodicea, Antiochia, Konstantinopel等々の諸会議の決議中、ギリシャ文のものはこれをラテン文に訳し、ラテン文のものは原文のままにて、一巻のラテン文決議録を編成したのである。次いでDionysiusはやはり法王庁筋の命を受けてローマ法王の訓令集をも作つた。ローマ法王の訓令(decretales)が法源的価値を獲得し始めたのは、四世紀以後の事、殊に法王Siricius(二)(384--398)以後の事であつたので、DionysiusはSiriciusからAnastasius IIまでの間、年代でいへば三八四年から四九八年までの間の訓令を蒐集して、一巻の訓令集となしたのである。後にDionysiusはみづから彼の決議集と訓令集とを一巻に併合したが、これこそCollectio Dionysianaに外ならなかつたのであつた。
Collectio Dionysianaは、教会史上決定的役割を演じた。それは前代の殆どすべての法源集を通用から駆逐して、自分自身西欧の唯一の勢力となるに至つたがゆゑである。
七七四年法王Hadrian IはCollectio Dionysianaに爾後の法令を補追したものを、西欧における標準的教会法なりとして、カール大帝に伝授した。カールはこれを継受してフランク教会の教会法典(Codex Canonum)たらしめた。このHadrian Iによつて増補された集をCollectio Dionysio-Hadrianaといふ。
一 前出一八二頁註二参照。
二 Stutz in Holtzendorff-Kohlers Enzykl. Bd. 5 291 Anm. 3.
三 ゲルマン時代
ローマ帝国を滅ぼしてその旧趾に建国したゲルマン諸国はどんな教会政策をとつたかといふと、ローマと同様、国家教会主義(Staatskirchentum)をとり、教会を国家統制の下に服属させた。が同じ国家教会主義でもローマのそれとゲルマンのそれとは性質を異にしてゐたのであつて、ローマは教会を一種の国務担当者、すなはち教化及救貧の行政部門を担当する公共団体と見、この見地から、教会の配置・職能等へ容啄もしてゐたのであつたが、ゲルマンの王たちは、教会を自己の私有物なりと見、私益的見地から自在にこれを処分してゐたのであつた。自己の領内に自己が建てた以上、教会もまた自己の財産である・王はこれを自由に処分し分割し贈与し相続さすこともできる・僧侶も『王の僧侶』(Eigengeistlicher)である。その任免監督は王みづからが司る・法王は国王の僧侶任免権に干渉することができない・教会のもつ洗礼権(Taufrecht)・埋葬権(Begräbnisrecht)といへども、国王の附与に係る・決してローマ法王に由来するのではないと断定してゐたのであつた。すなはちゲルマン王の教会支配は、教会を王の私有物と見る見地から出てゐたのであつて、ローマの教会支配の、公法的なりしに反し、著しく私法的・物権的・経済的であつたのであつた。
がとにかくゲルマンの王等は強く自己領内の教会を統制してゐた。宗教会議もゲルマンでは、王の召集に基き、国内の僧正のみを以て開いてゐた。一県一州の僧正等が、大僧正や教主の召集を受けて集合するといふやうな現象は稀であつた。決議の効力も国内的たるに止つた。例へばフランク国の宗教会議はフランク国内においてのみ通用する教会法を作り、西ゴート国の宗教会議は西ゴート国においてのみ通用する教会法を作つたのである。ローマ時代の教会法の帝国的・世界的であつたに対し、ゲルマン期のそれは地方的・封建的・国民的であつたのである(一)。
一 Koeniger, Grundriss 25 fg.
が同時にそこには、国王の教会支配を排撃せんとする反対傾向も存在してゐた。それは法王の立場であつた。法王は国家教会主義(Staatskirchentum)でなくて、教会国家主義(Kirchenstaattum)であつたのである。彼によれば、『法王は日、国王は月である。後者はその光を前者から受取つてゐるのである』。教会の一機関として教会目的の達成に奉仕する所にこそ、国家の存在理由は存在する・国王のくせに僧侶を任免し、教会法を作るがごときは、事理の顛倒に外ならない。僧侶の任免・教会法の形成は、本来的に法王の独占に専属するといふのであつた。法王側の希望は、国民的教会法でなくして世界的教会法であつたのである。宗教会議の決議による法の制定でなくて、法王の命令による法の制定であつたのである。この意味において法王は『ローマ帝国皇帝の相続人』であつた。ローマの皇帝と同様に、彼は世界教会法の最高淵源たらんと志したのであつた。
要するにゲルマン期は『法王と皇帝との抗争期』であつた。文化史の全面において然りしがごとく、教会法の立法史においても、国王主義と法王主義、国民主義と世界主義との熱火的抗争が見られたのである。
今、眼を本期における法源集の編纂へ転じて、まづ西ゴートを見るに、六世期中にCapitula Martini Bracarensisが出てゐた(一)。これはBraga市の僧正Martinus(†580)の編にかかり、五七二年、同市に開かれた宗教会議の公認を受けて、西ゴートの標準的教会法典となつた。内容は東方諸会議の決議文の中から、西ゴートの教会事情に適しさうな規定を拾つて、これをラテン文に訳したものであつた。
一 Ausg. : Bruns, Canones apostolorum et conciliorum saec. IV--VII, 2. Bd. 43 fg.
その後西ゴートは、王Reccared(586--601)のときに、アリアン派(Arrianismus)からカトリック正教(Katholizisums)へ改宗した。そこで従来の教会法典たるMartinus僧正の法源集へ、改修を加へる必要を生じ、第三Toledo宗教会議(589)の直後、Martinus集を改修増補した新標準法典を編纂した。通常これをCollectio hispana(一)といふ。その後それは屡々補正を加へられて、七世紀には編制も組織的となり、八世紀には最後の完成形態へと到達した。最後の形態についてこれを見るに、第一部すなはち決議録の部は、古き東方諸会議の決議等をも含むが、主要部は、七世紀中西ゴート王国で開催された国民的宗教会議の決議の集りに外ならない。累年ToledoやMadridにおいて開かれてゐた国民的宗教会議の決議の成果がCollectio hispanaの中に盛上げられてゐるのを見るのである。第二部すなはち訓令集の部には、法王DamasusからGregor I(590--604)に至るまでの間に発しられた訓令一〇三箇が掲げられてゐる。
一 Collectio hispanaはLiber Canonumともいはれ、Collectio Isidorianaともいはれる。Isidorの名を冠せられる理由は、不正確にも本集が、有名なSevillaの僧正Isidor(† 636)の編纂にかかると誤認されたことがあつたからである。
フランクでは、カール大帝の時代までは、古くガリヤ・イタリイ等で生れた法源集すなはちいふところのQuesnell法源集(前出)や、Dionysius法源集(前出)やを使用してゐたのであつたが、カール大帝の時、八〇二年に、かねて法王Hadrian Iから伝受してゐた法源集——Collectio Dionysio-Hadriana——を公認し、これをフランクの標準的教会法典たらしめた。
その外にフランクでは、カール及その子孫が、発したいはゆる神事勅令(capitula ecclesiastica)があり、これまた教会法源の重要な一部を構成してゐた(一)。僧正の発した訓令(capitula episcoporum)も法源たることを失はなかつた。中んづく七九七年頃Orleans市の僧正Theodulphの発した訓令・八五〇年にBourges市の僧正Rudolphの発した訓令・八五二年頃Rheimsの僧正Hincmarの発した訓令のごときは、Collectio Dionysio-Hadrianaの補足と発展とに大いに役立つたところのものであつた。
一 拙著・西洋立法史九七頁参照。
九世紀には法王は、王権の衰微に乗じて着々勢力を伸ばしつつあつたが、その際彼に問題となつたのは、いかにすれば彼がその新得せる事実上の勢力を、法的に正当化しうるやの点にあつた。窮余の一策として案出されたのが、古文書の偽造変造であつた。偽書によつて権利を産み、以てその既得せる事実上の地位を、法的に正当化させようとする老獪な一案であつた。
偽書の一つは、Capitula Angilramiである。AngilramはMetzの僧正であつた。同僧正これを編して法王Hadrianへ捧げたとは、序文において、この書みづからのいふところ(一)(二)。がしかし学者はこれを信じない・多分これは、次にのべるIsidor偽書と同一の作者から出てゐるだらうといふのが定説である。内容はおもに訴訟法に関してをり、僧侶を被告とする訴は、教会裁判所に専属す・世俗裁判所はこれを取扱ふことをえずなどとうそ吹いてゐるのである。出現は九世紀の半であつたであらう。
一 逆に、本書は法王Hadrianこれを作り、七八五年九月十九日、同法王よりMetzの僧正Angilramへ贈られたと、その序文に書してゐる『異本Capitula Angilrami』もある。
二 Ausg. : Hinschius, Decretales Pseudo-Isidorianae 1863.
しかし偽書の最も有名なのはIsidor偽書(Pseudoisidorische Sammlung)である(一)。
この書の本文は三部に分れてをり、第一部には既述Collectio Dionysianaから取つたと見えるCanones Apostolorum五十条を含み、その上に、初代法王等の訓令をも収めてゐる。Clemens I(† 101)からMelchiades(† 314)に至る総計三十人の法王の訓令六十箇を、年代順に収めてゐるのである。しかし学者は、この六十箇の訓令を全部偽物だと見てゐる。第二部は決議録であり、Toledoその他のスペイン諸市で開かれた諸会議の決議や、古くAncyra, Gangra, Sardica, Antiochia, Laodicea等で開かれた諸会議の決議やを収めてゐるが、これらは大抵Collectio hispanaからの借物を出でぬ。しかも原形のままの借用ではなくて、短削したり加添したり、恣ままな変造を加へてゐるのである。第三部は法王の訓令集で、Sylvester(† 335)からGregor II(† 731)に至るまでの間に発しられた多数の法王訓令を載せてゐるが、そのうち三十五箇が偽造だといはれてゐる(二)。
本文の外に、この書は序文と附録とをもつてゐる。序文には有名なSevillaの聖者Isidor(†636)がこの書を編める旨、麗々と吹いてゐる(三)。附録としては、それ自身また偽作物であつたところのCapitula Angilrami(前出)を加へてゐる。
一 Ausg. : Hinschius, Decretales Pseudoisidorianae 1863---Lit. : Maassen, Pseudoisidorische Studien Wien. Sitz.-Ber. CVIII. CIX. 1884-5---Lurz, Über die Heimat Pseudoisidors 1898---Simon, Die Entstehung der pseudoisidorischen Fälschungen in Le Mans 1886.
二 Isidor偽書の偽物性は、十五世紀頃すでに、少数の学者から猜定されてゐたといふ。が無遠慮にその仮面を剥取つたのは、十七世紀における新教会の学者Blondelであつた(Blondel, Pseudo-Isidorus et Turrianus Vapulantes 1628)。
三 ,,Incipit praefatio S. Isidori libri huius.……``
偽作の目的はどこにあつたか?偽書の内容を見れば端的に明かである。偽書は僧侶の優越性を企図してゐる。『ペテロ僧侶等にいへり。汝等の義務は俗界の君主等を教ゆるに在り。俗界の君主は、彼等が神に従はざるべからざるごとく、汝等僧侶にも従はざるべからず』などと偽句つてゐるのである。又それは俗権の排斥につとめてゐる。教会の職員並に財産は、教会固有の裁判官によつて裁判せらる・俗界の判事によつて裁かるることなしなどといつてゐるのである。又それは法王の地位の至上化を策してゐる。僧正は大僧正の監督に服せず、直接法王の統督を受くなどといつてゐるのである。目的はたしかに、僧正及法王の利益のためであつた。僧正を俗権又は大僧正から解放して、直接法王へ下属させようためであつた。
作者は何人であつたか?或はかのBenedictus Levita(一)の作者と同一人であつたらうといひ、或はMainzの僧正Otgar(826--847)であつたらうといひ、或はRheimsの僧正Eboであつたらうといひ、その他数説あるも、みな臆断に過ぎない。制作地は、写本の形状・その発見地等より推して、フランスのRheims県と見らる。制作年代は、通説に従へば、八四七年から八五三年までの間。
一 拙著・西洋立法史一〇四頁参照。
九世紀以後の教会立法は、Isidor偽書的基礎の上に進行して行つた。古き教会組織は滅びて法王中心の新組織を生じつつあつた。法王が『僧正中の僧正』(Bischof der Bischöfe)となり、教会事項に関する司法立法行政の諸権を一手に集握せんとする形勢を示しつつあつた。彼はまづ十分に事実上の支配を獲得してから、その新事実を根拠づくべき法律を出して行つたのである。十世紀は法王の訓令の多産的発布となり、殊にGregor VII(1073--1085)によつて、豊富な訓令立法(Dekretalengesetzgebung)の発布を見た。
要するに宗教会議による立法の時代が過ぎて、法王の単独立法の時代となりつつあつたのである。民衆的・会議的の時代から、貴族的・独裁的の時代へうつりつつあつたのである。
訓令の多量生産に促されて、種々の新法源集の編纂となつたが、その中の主なるものを示すと、(一)はCollectio Anselmo dedicata——八八三年から八九七年の間にMailandの大僧正Anselmにより編せらる。(二)はLibri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis——九〇六年頃Prümの修道院長Reginoにより編せらる。(三)はCollectarium——一〇一二年から一〇二三年の間に、Wormsの僧正Burchardにより編せらる。(四)Polycarpus——一一一八年頃枢機官Gregorにより編せらる。(五)Liber de misericordia et justitia——一一二〇年頃学僧Algerusによつて編せらる。
以上の法源集は、昔のもののやうに地方教会の使用を目標とせず、むしろ広く全教会の共通的使用を目標として編まれたのであつた。編纂の方法も組織的で、昔のやうに決議録の部と訓令録の部とを分けたり、年代順に羅列したりせず、むしろ事項別に材料の類纂を行つたのであつた。(五)に掲げたAlgerusの書のごとき、次代の大家Gratianへ、方法上の標準を示した概さへあつたのである。
ゆゑにSchulteはいふ——Gratian以前には、教会法の学的考察なく、単なる『法規の蒐集』(Sammeln der Rechtssätze)しか見られなかつたが、しかし九世紀までの法規集とそれ以後のものとは異る。九世紀までのものは、純年代的蒐集(rein chronologische Sammlung)に過ぎなかつたが、九世紀以後のものは系統的蒐集(systematische Sammlung)となつたと(一)。
一 Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts I. 31.
四 十三世紀初頭の法王立法
十二—五世紀は教会法の完成期として、向外的には国家対教会の関係が、向内的には僧侶対信者の関係及び僧侶対法王の関係が、それぞれ整頓し、教会国(Kirchenstaat)の法源機構の全く完整を遂げた時代であつた。
すなはちこの期の教会は、僧侶に対してはもちろん一般信徒に対しても強大な命令強制の権を有した一箇の支配団体であつたのである。この権力を教会権(potestas ecclesiastica)といふ。教会権は分れて、教化権(potestas ordinis, Weihegewalt)と統治権(potestas jurisdictionis, Regierungsgewalt)との二つになつた。教化権は布教権であり、統治権は司法立法行政の権であつた。二権とも僧侶階級の独占であり、一般信徒はこれに与ることをえぬのであつた。信徒は教会権の単なる物体に過ぎぬのであつた。権力の担持者たるためには、僧侶(ordo)たることが必要的前提であつたのであつた。
僧侶自身も、上から下まで階段的に身分づけられてゐた。統治権は一部上級の僧侶——法王及僧正——の独占であり、他はこれに与らなかつた。いひかへれば一般の僧侶は教化権のみを有したのである。これを一般階級(hierarchia ordnis)といひ、統治権をも併せ有した者すなはち法王及僧正を、支配階級(hierarchia jurisdictionis)といつた。
法王は教会国の独裁君主として、『神事』に関するかぎり、無限の権力を有してゐたのであつた(一)。彼は訓令の力を以て、各地方教会の法律や慣習を廃止変更することさへできた。一般宗教会議(ökumenische Konzilien)も、今では法王の召集によつて開かれ、その決議も、法王の承認を受けねば法となりえぬありさまとなつた。世俗君主の神事立法も、法王の承認を受けた限度内において、教会生活の規制者たりえたに止つた。ローマ法に対しても、法王は、同法と趣旨相反する訓令を連発して行くことによつて、同法を徐々に教会外へ退却させようと企てたほどであつた。要するに法王は、彼の利益に合し、彼の意思に協つた世俗法のみを採用し、他はすべて顧みなかつたのである。これを教会の世俗法変更権といひ、『教会法は世俗法に先だつ』(Kirchengesetze gehen den weltlichen vor.)ともいふ(二)(三)。
一 法王の権力は、法王Gregor VII(1073--1085)の頃から盛んに上向線を昇り始め、Alexander III(1158--1181)及Innocenz III(1198--1216)に至つて頂点に達した。
二 法王は特定人に、法の一般に禁じてゐるところものを特許することもできた。すなはち彼は一般の原則(decreta generalia)を破つて特別の例外を立てることができたのである(specialia privilegia)。又、『法を立てうる者のみ法を解釈することをうべし』との見地から、解釈の権を壟断し、彼自身か若くは彼より特許を受けたものでなければ、教会法規の解釈を試みることができないとしてゐたのであつた。
三 Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts I. 92. fg.
右のごとく教会は、『神事』に関するかぎり、全く不羈独立の立法権をもつてゐたのであつたが、然らば『神事』(causae spirituales, geistliche Angelegenheit)とは何であつたか、いひかへれば何が教会の立法事項であつたのかといふに——(一)教会は、教会秩序に対する犯罪を処罰する法律を発することができた。教会盗・教会冒涜・魔法使・異端的信仰等は教会によつて罰しられ、教会裁判所によつて裁かれたのである。(二)教会収入に関してもみづから立法することができた。信徒に対する課税の方法・教会財産に対する管理の方法等、すべてみな自家製の法律のみで処弁してゐたのである。(三)『罪悪』(Sünde)の観念に入るべき非行の取締に関しても教会は立法の自由をもつた。利子の徴収・暴利的売買・奴隷虐待等は教会の立法対象をなしてゐたのである。
(四)教会儀式を件ふ行為、例へば婚姻・婚約等も教会立法の対象であつた。子の嫡出・嫁資等の問題も教会の立法及裁判に一任されてゐた。宣誓を伴へる契約の特別の効果についても教会は規定するところがあつた。(五)遺言は、当時のそれが大抵教会を受遺者とせるものであつた関係上、やはり教会法の範囲に引き入れられてゐた。(六)私闘の禁止についても教会は立法することができたのである。私闘禁止令には二種あり、一は一定の人又は物を保護することを目的とせるもので、例へば僧侶・抵抗力なき農民・商人・婦人・教会財産・家畜等を特別保護の対象となし、これらに対する侵害行為を処罰すべき法律を発してゐたのである。二は一定日における全社会の平穏を確保するためのものであつたのであつて、例へば日曜の夕から月曜の朝までの間、一切の私闘を禁ずるとか、水曜の夕から月曜の朝までの間、一切の私闘を禁ずるとかいふやうな禁止令を発してゐたのであつた。
要するに教会は僧侶に対してばかりではない、俗人に対しても『神事』については立法しえたのであつたが、『神事』の観念はもとより伸縮自在的のものであつたから、教会の実勢力の伸びると共に『神事』も伸び、従つて教会の立法権も伸び、遂に俗人生活の大部面へまで干渉するやうになつたのであつた。
法源集の編纂からいつても、当期はDecretum Gratianiの編纂あり、法源史上の最も輝ける収獲期であつた。
今まづDecretum Gratianiの著者その人から述べると、著者Gratianの生死の年は共に明かでないが、生れながらのイタリイ人であつたこと、僧正でなくて修道僧であつたこと、十二世紀の前半Bologna市のSt. Flex寺に在職し、傍ら同市の大学教師として教会法の講義をも行つてゐたこと等については、衆説の一致を見る。Decretum Gratianiなるものは、実はGratianが、Bologna大学における講義用として作つた一の講義案(Grundriss)そのものに外ならなかつたのであつた。
Decretum Gratianiを通じてGratianの講義ぶりを想見するに、その主力の注がれた点は法源の解釈といふよりも、むしろ法源の蒐集・吟味及整理そのものであつたらしい。即ち彼はまづその講義を三部に分ち、第一部(Pars Prima)においては法源論と『人の法』とを取扱つてゐるのを見る。法源論としては、教会法の法源は何か、法王の権力と一般宗教会議の決議との関係はどうか、慣習法の成立要件は何かといふやうなことを論じ、次いで人の法として僧侶の任免・階級・特権等を論じたのであるが、これらの論述を運ぶ際、彼は少しく説いて多く引用したのである(一)(二)。自説の主張に小胆にして典拠の挙示に周密であつたのである。例へば彼は講義案の第一部第十七節の冒頭(Princ. D. 17)において、一般宗教会議の決議といへども法王の是認なしには法となりえざる旨を、今日の印刷本(三)にして約三行半述べた後に、その立証法源として、約三頁にわたり、多数の法王の訓令類を引用してゐるのである。又講義案の第一部第八節の冒頭(Princ. D. 8)において、慣習法は理性及自然法に反しては成立しえざる旨を、今日の印刷本にして九行ほど述べたのち、その立証として約四頁にわたり、会議の決議や法王の訓令やを引用してゐるのである。自説は簡にして引用は豊溢。ゆゑに出来上つた体裁は主客殆ど顛倒し、引用文が主で、説明は附註に過ぎざるありさまとなつた。系統的な法源類集の上へ、編者が短簡な解題文を冠らせたかたちとなつた。ひとのこれを法源集視するに至つたのは、著者の目的よりも著書のかかる成立形態を見たからであつた。
一 引用条文の出所は明かでないが、大部分は前代の法源集からの抜抄であつたであらう。九世紀以後の成立にかかる組織的法源類集、その中でも殊にAlgerusの集を利用した形跡は確かだといはれてゐる。Isidor偽書をも利用してゐるが、これは当時、未だこの書がその偽書性を摘発されずにゐた関係からであつた。又集中には新しい法王の訓令も見えるが——一一三九年のものが最新——これらは他書からの伝写にあらず、原文からの直写であつたであらう。
二 Gratianは、人(personae)・物(res)・訴権(actiones)の区別を基礎原理として法源の分類を行つたらしいのである(Schulte, Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts I. 23)。
三 Decretum Gratianiは、後に至りCorpus Juris Canoniciの中へ収納せられ、その構成一部分となつた。ゆゑにDecretum Gratianiを見ようとおもへばCorpus Juris Canoniciの刊本を繙けばいいのである。
講義の第二部(Pars Secunda)においては、Gratianは、『物の法』及『訴権の法』を取扱つた。がこの部においては、第一部でのやうな系統的論述の方法をとらず、直ちに数十の例題(Rechtsfälle)を示してその解答を迫つてゐるのである。
この場合にも著者の態度は法源本位的である(一)。即ち彼は、その講義の第一部においてと同じやうに少しく説いて多く引用してゐるのである。彼は直接には例題の解決に答へない。ただ例題の解決に対して先決関係をもつべき論点を指摘し、傍らその先決問題の解決資料となるべき条文を多数蒐集しておいてくれただけである。例へば講義案の第十七例(C. 17)には次のやうな例題が挙つてゐる——『他人の建立にかかる会堂を守つてゐた僧、一旦病を獲て世をはかなみ、修道院に入らんと欲するに至つた。よつて会堂は建立者へ返還し、私有の財産は彼の新に入らんとする修道院長の有へ移したが、たまたま病の癒えたるために修道僧たらんとする意思をひるがへし、会堂の建立者へは会堂の返還を、修道院長へは原財産の返還を共に請求するに至つた。この際問題となるは次の四点である。(一)修道院入院の宣誓は取消すことをうるや?(二)会堂の建立者は一旦返還せられたる会堂を再び与へざるべからざるか?(三)修道院長は、一旦その有に帰せる財産を返還せざるべからざるか?(四)修道院長はほしいままに財産返還の承諾を与へうるか?これらが先決問題である』と。そして著者は、これらの先決論点の解決資料となるであらうところの条文を、即ち訓令や決議文の類を、例の周密さを以て豊富に引用しておいてくれてゐるのである。著者の期待では、一の論点はそれに関聯するものとして著者の引用しておいた諸条文を読めば自然にとかれ、次の論点も、それに関聯してゐるものとして著者の引用しておいた条文を読めば自然にとかれ、かくして必要な先決論点はみな解かれて、自然に例題自身の全面的な解決に到達する、とでもおもつてゐるらしいのである。その結果やはり講義第二部も講義案たる体裁を失つて、一の法源集となつてしまつた。例題及論点の指示が僅々数行又は数十行に過ぎぬのに、引用の条文が数頁又は数十頁に及んだからである。後にはひとは本来それが一の応用問題集であつたことにすら気づかず、初めから法源蒐集の目的で作られた書と考へるやうになつたとさへいふ。
講義の第三部(Pars Tertia)では、Gratianは祭儀典礼に関する純僧侶的規則のみを取扱つたが、ここでもやはり説明は簡にして引用は豊富。ために出来上つた体裁は、講義案でなくして法源集となつてしまつたのであつた。
一 なぜGratianは、自説の主張にはああまで臆病であり、法源の引用にはああまで熱心であつたのであらうか?実はそこにGratianの、いな中世の学者一般の、方法論的特性が色濃くあらはれてゐたのである。当時の学者は、法源の円満性と完全性とを厚く信じてゐたのであつた。法源には矛盾もなければ欠陥もない・神の秩序に遺漏なきがごとく、教会法の秩序にも欠陥はない・欠陥ありとおもふは法源の蒐集足らざるがためであり、矛盾ありとおもふは条文相互の関係を吟味せざるがためである・豊富に条文を集めれば欠陥なきことを知り、順序よく条文を排列すれば矛盾なきを知る・学者はみづから語らずに、条文をして語らしめねばならない・蒐集自体によつて欠陥を補填し、排列自体によつて矛盾を除去し、以て法源本来の円満具足性を発揚させねばならない・学問の要は、法源の蒐集とその排列とにあると考へてゐたためであつた。
Gratianはその著述に、Concordia Discordantiun Canonumと命名した。Decretum Gratianiと呼ばれるに至つたのは、十二世紀の末頃からである。編纂年代は一一四〇年頃であつたであらう。一説には一一四一年から五〇年の間といひ、他説には一一三九年から四二年の間といふ。
Gratian集は、その後著者の門下生Paucapaleaによつて多大の補正を加へられ、かなりその容姿を改めた。Paucapaleaは師が脱漏した新旧の法源を拾つて、師の遺著に挿入し、丁寧にその欠を補つて行つたのである。又彼は師の遺著の第一部を一〇一節に、第三部を五節に細分し、もと師が一まとめにしておいた法源類を、各節下に分置配当したのである。その結果Gratian集は、今日見らるるが如き形態をとるに至つた。
それはすなはち三部(Partes)に分れる。第一部(Pars Prima)は一〇一節(Distinctiones)に分れ、各節はそれぞれ多数の条(Canones)に分れる。各節の初端には、その節題に関してGratian自身の述べた簡短な意見を、二三行乃至七八行掲げてゐる。これをDicta Gratianiといふ。各条の初端にも、条意を数語にちぢめた見出《みだし》様の句が附せられてゐる。これを(Rubricae)といふ。今日の印刷本では、Dicta GratianiとRubricaeとは、イクリック態に印刷される例である。
第二部(Pars Secunda)は三十六箇の応用問題(Causae)に分れ、各問題は二三乃至七八の論点(Quaestiones)に分れる。各論点の下には、それが解決に資すべき決議・訓令の類を、やはり箇条的(Canones)に列載してゐるのである。
第三部(Pars Tertia)は五節(Distinctiones)に分れ、各節は多数の条(Canones)を含む(一)。
一 Decretum Gratianiの引用方法は次のごとし——第一部から引用するには、条(Canon)及節(Distinctio)のみをあげる。例へば第一部・第十七節・第十五条の引用は、c. 15 D. 17で足る。
第二部から引用するには、条(Canon)、例(Causa)論点(Quaestio)をあげる。例へば第二部・第二十例・第一論点・第五条の引用法は、c. 5 C. 20 qu. 1である。
第三部から引用するにも、条(Canon)・節(Distinctio)をあげるが、この場合にはde consecrationeなる但書を添へる。例へば第三部・第二節・第一条の引用法は、c. 1 D. 2 de cons.である。
Decretum Gratianiは、前代のどの法源集よりもはるかに多くの条文を含んでゐたし、条文排列の方法も系統的であつたから、前代の法源集の一切は急速に通用から駆逐されて行く結果になつた。古い条文を引くにも直接原典からせずにGratianの集から引くやうになり、新たに法源集を作るに際してもGratian集を基礎におき、その足らざるところを補つて行くといふ風になつた。
補追の方法は、最初はGratian集中の関係箇所へ、新令を挿入してゐた。これを挿入(paleal)といふ。後にはしかし挿入の場所に不足を感じ来つた結果、附録として巻末へ添加した。これを附録(appendix)といふ。がしかし十二・三世紀は、教会立法の多産期であつたために、附録の方法もたちまち不便になつて来たのであつた。一一七九年の第三次Lateran宗教会議・一二一五年の第四次Lateran宗教会議は、改革的な多くの決議を行つたし、法王Alexander III、Innocenz IIIに至つては影響的な訓令を最も多量に連発したし、どうしてもこれらを一まとめにした独立の一巻が必要であつたのである。これらGratian集の以後に出た法王令を新令(Decretales extravagantes)といふ。
新令蒐集事業の主もなものをあげると、第一はBreviarium Extravagantiumであつた。通常これを第一集(Compilatio prima)といふ。編者はPaviaの僧正Bernhard、編纂年代は一一九一年頃といはる。編纂の目的は、Decretum Gratiani以後の新令の蒐集にあつた。
『第一集』は五篇(Libri)に分る。第一篇はJudex(教会裁判官)の篇で、法源・教会職制等に関する規定を集め、三四章(Tituli)・一六九条(Capita)に分る。第二篇はJudicium(教会裁判権)の篇で、訴訟法規を集め、二一章・一六六条に分る。第三篇はClerus(僧侶)の篇で、僧侶及教会の私法関係を規定し、三七章・二五〇条に分る。第四篇はConubia(婚姻法)の篇で婚姻法を規定し、二二章・一一二条に分れ、第五篇はCrimen(刑法)の篇で、刑法及刑事訴訟法を規定し、三七章・二二六条に分る。すなはち総計一五一章・九二三条あるのであるが、そのうちの大部分実に五一七条までが、Alexander IIIの訓令であつた(一)。
一 Ausg. : Friedberg, Quinque Compilationes antiquae 1882.
一二一〇年に至つて、『第三集』(Compilatio tertia)なるものが出た。これは法王Innocenz IIIが、秘書Petrus Collivaciusに命じて編纂させ、Bologna大学に勅諭して同大学の有権的教材たらしめたもので、又、公撰法源集の開初でもあつた。篇別は前出『第一集』と同様、Judex, Judicium, Clerus, Conubia, Crimenの五篇より成り、第一篇には二六章・一二〇条、第二篇には二〇章・一〇七条、第三篇には三八章・一三四条、第四篇には一六章・三七条、第五篇には二三章・九三条を収む。全部Innocenz IIIの訓令であつた(一)(二)。
一 Ausg. : Friedberg, Quinque Compilationes antiquae 1882.
二 『第三集』の名は別に『第二集』(Compilatio secunda)があつたからである。後者はJohannes Galensisの編せるもので、出現は『第三集』より却つて後であつたが、含める法源が古く、ちやうど『第一集』と『第三集』との中間期のものを集めてゐたので、『第二集』の名を附せられたのである。
一二二六年に至つて『第五集』(Compilatio quinta)が出た。法王Honorius IIIが編纂させた公の第二次編纂物であつたのである。篇別はやはり、五篇式で、第一篇Judexの篇には二五章・五九条、第二篇Judiciumの篇には二〇章・五四条、第三篇即ちClerusの篇には二七章・六六条、第四篇Conubiaの篇には三章・五条、第五篇Crimenの篇には一九章・四一条をふくむ。その殆ど全部がHonorius IIIの訓令であつた(一)(二)。
一 Ausg. : Friedberg, Quinque Compilationes antiquae 1882.
二 『第五集』の名は、別に『第四集』(Compilatio quarta)があつたからである。これは一二一七年頃に出来、Innocenz III晩年の訓令を収めたものであつた。
五 十三—五世紀の法王立法
一二二七年に法王に就任したGregor IX(1227--1241)は、翌二八年に法典編纂の計画を立て、三〇年に至つて実行に着手し、僧Raymundを編纂委員に命じた。編纂の目的は、『Gratian集の以後に発布された歴代法王の訓令の中には、意味において重複したり、語において冗漫に失したり、稀には互に矛盾さへする規定もあるので、新たに編纂の業をおこして、Gratian集以後の新令に清算を与へる』といふにあつた。
一二三四年に至つて編纂は完了した。法王はこれを一般に公布すると同時に、Paris及Bolognaの二大学に教書を送り、爾今二大学における新令の講義は、この新法典を基礎として為されざるべからざる旨、厳達した。いはく『すべての裁判所及学校はこの新法典を使用せざるべからず。何人といへども法王の特許を受けずして恣ままに旧法規集の類を使用することをえず』と。
新法典はLiber Extraともよばれ、Gregorianaともいはれた。篇別は『第一集』乃至『第五集』の先例に倣つて五篇とし、第一篇には裁判官(Judex)、第二篇には管轄(Judicium)、第三篇には僧侶(Clerus)、第四篇には婚姻(Sponsalia)、第五篇には刑法(Crimen)を規定した。さうしてさらに第一篇は四三章・四三九条に、第二篇は三〇章・四一八条に、第三篇は五〇章・四九一条に、第四篇は二一章・一六六条に、第五篇は四一章・四五七条に、合計一八五章・一九七一条に細分されたのである。が学者の研究(一)によると、全条一九七一条のうち、実に一七五九条までが、『第一集』乃至『第五集』からの移植にして新創のものは少数に過ぎす、殆どLiber Extraとは、古資料の新装に過ぎざるかの観さへあるといふのである。もつとも古資料の転載にあたつては、相当に剪刀を用ゐ、重複を削つたり、冗漫をちぢめたり、相互の間に統一をつけたりはしたが、大体においてLiber Extraが、古法源の単純再生産に過ぎなかつたことは事実であつた。
一 Schulte, Geschichte II. 12.
しかしLiber Extraは、古法源の単純再生産たる以上に何の意味はもたなかつたのかといふとさうではない。それは実にある重大の意味をさへ包み持つてゐたのである——単なる法規集でなくて、一の法典(ein einheitliches Gesetzbuch)であつたといふことがすなはちそれ。
いふまでもなく法典と法規集との区別は、(一)法典は一の立法者の与へたものだが、法規集は多数の立法者の諸法令の集りであるといふ点。(二)法典はその資格において通用するが、法規集はそれとしては通用力を有せず、ただその中に含まれてゐる箇々の法令が、それぞれの発布者の名において通用するに過ぎないといふ点。(三)法典中の諸条規は同一日附を有し、相互の間に新法旧法の差別を欠くが、法規集中の条規は別々の日附を有し、同一集中にありながら新法旧法の差別をもつといふ点——要するに法典は一の統一体であるが、法規集は多数条規の、本来的の意味なき集合に過ぎぬのである。
Liber Extraについてこれを見るに、この書は法王Gregor IXがその名において公布し、その名において遵守を命じたところのものであつたのである。内容はなるほど前代の諸法令の集りではあつたが、しかもそれらは原態のままの転載にあらず、或は短縮され、或は加添され、意味の上にも変改を受けて、すなはちいはゆるInterpolation(一)(改竄)を受けて、再録されてゐるのである。Gregorから見れば、前代の諸法令はみな立法の資料に過ぎなかつた。彼はこの資料へ加工を施し、生命を吹込んで、彼自身の法律たらしめたのである。すなはちLiber Extraの中に盛られた諸条規は、素材的には前代の法王のものであつたが、法律的には全部Gregor自身のものであつたのである。それらは理論的には、全部同一の日附であり、相互の間に新旧の差別を有しなかつたのである——要するにLiber Extraは、Gregor IXといふ一立法者の与へた統一的法律であつた。一層ちぢめていへば一の法典であつたのである。
一 Interpolation(改竄)は、法規集の時代から法典の時代へ遷らうとする過渡期において屡々見られる現象である。かかる時代の法典編纂者は、立法の素材を過去の法源に仰がざるべからざる事情の中に在るが、法典の編纂者は法規集の編者と異り、典中の全規定に対して制定者としての責任を負担する関係上、全規定を真に自己の意思に合致せしめんとつとめるのである。過去の素材に改竄を加へることをあへてしてまで、素材と立法者意思との間の完全なる一致を所期するのである。これに反し過去の法律を過去の姿のままに輯集することを任とする法規集の編者は、かういふ必要を感じない。また十分に強大化した立法権を有する後世の立法者も、改竄の必要などは感じない。なぜかならこの種の立法者は、全然過去の資料を無視して自己の意思のままに立法することができるからである。改竄は立法者が多少未だ過去の法源に拘束されてゐた時代の現象である。
終りに問題となるのは、なぜGregorが法典などを作つたかである。なぜ前代の法源の効力を否定し、全教会法を自己の法律にしてしまつたかである。学者はGregorの意中を察して、それは彼が彼の立法権の不羈独立性を証拠立てるためであつたらうと見る(一)。なぜかなら、彼には実は新編纂の必要などはなかつた。前代の諸法王令は全部遺漏なく、『第一集』乃至『第五集』の中に収められてゐたし、法条の検索も、右の五法規集が、篇(Liber)・章(Titulus)・条(Caput)の排列方法によつてゐた関係上、比較的軽便であつたからである。だのにGregorは、彼の就任の翌年に、直ちに新法典の編纂を計画してゐる。どうしてもそれは、実質的な必要からではなくして、形式的な理由からであつたとしかおもへない。恐らく彼は一法王の立法権の、必ずしも前任者の法律に拘束せられざるゆゑんを中外に表明しようと欲したのであらう。『法王の立法は世俗の権力・宗教会議の決議から掣肘を受けないやうに、先行諸法王の訓令からも自由である。一の法王は彼の先代の訓令類を無視し、法律の連続性(Rechtskontinuität)を破りて、自由に立法することができるものだ』といふことを、力強く証示しようとしたのであらう。よつて任意的に一箇の新法典を編纂し、古法令の一切を一旦失効せしめ、古法令中の保存に値するものには、あらためてGregor自身の印を捺し、Gregor自身の命令なりとして新法典中へ転籍させたのであらう。Friedbergの言葉(二)でいひ直せば、Liber Extra法典は、『獲得された権力汪溢の自覚』から作られた法典であつたのであつた(三)(四)。
一 Schulte, Geschichte II. 3 fg.
二 Friedberg, Kirchenr. 144.
三 Liber Extraは、後にCorpus Juris Canoniciの中にその一部として収納されたので、正文はCorpus Juris Canoniciの刊本について見ることができる
四 Liber Extraからの引用方法は、例へば第二篇・第十二章、『占有と本権との係争について』と題する章の中から第二条を引かうとならば、c. 2 X de causa possessionis et proprietatis, II, 12とする。XはLiber Extraの略である。
Gregor IXはLiber Extra法典発布の後も、単行法令の発布はやめなかつたし、次代の諸法王も益々盛んに単行法を発しつづけてゐたから、勢ひそこに追加的編纂の必要をよび起して来た。然るに法典の編纂は、Gregor以来官の独占事業となり、私人のたづさはることは禁じられてゐたので、追篇編纂のためには、どうしても官の再度の立法活動を待望するの外はなかつたのである。
Bonifaz VIII(1294--1303)に至つて、追加法典の編纂を見ることができた。編纂年は一二九四年。編纂委員は僧Wilhelm, Berenger, Richard等。材料はLiber Extra以後における諸法王の訓令。殊にInnocenz IV, Alexander IV, Clemens IV, Gregor X並にBonifaz自身の訓令が、主要材料を為したのであつた。
名はLiber Sextusと呼ばれた。第六(Sextus)の名を附された理由は、本書は追加物にして、Liber Extraの第五巻末に続くものなりとの見解からであつた。篇別は、『第一集』以来伝統的となつてゐた五篇式で、第一篇(Judex)は二二章・一三四条に、第二篇(Judicium)は一五章・四七条に、第三篇(Clerus)は二四章・九四条に、第四篇(Sponsalia)は三章・五条に、第五篇(Crimen)は一二章・七九条に、合計七六章・三五九条に細分されたのである。
Liber Sextusの特色は、素材に対するInterpolation(改竄)の度合が、Liber Extraの場合よりも甚しかつたことであつた。Extraの編者は、臆病な慎重さを以て原文に改竄を施したに過ぎなかつたが、Sextusの編者は、原文が明かに或特定の場合を予想し、その場合にしか関してゐないのに、強ひてそれを一般原則に変化させたり、原文が臨時的性質を有してゐるのに、大胆にもそれを恒久の規則化させたり、要するに各条文をして法規的一般抽象性を帯有させるために、あらゆる作為を敢てしたのである。明かにSextusの編者は、任意に材料を駆使する独裁者の態度で立法したのであり、それだけSextusの法典的体裁は、Extra以上に端整的とはなつた(一)(二)。
一 Liber Sextusも、後にCorpus Juris Canoniciの一部となつた。ゆゑに正文はCorpus Juris Canoniciの刊本において見られる。
二 Liber Sextusからの引用方法は、例へばその第二篇・第九章『自白について』の章の中から第二条を引かうとならばc. 2 de confessis in VI° II 9とする。VI° はLiber Sextusを意味する。
Liber Sextusの発布から七年の後、一三一一年にVienne宗教会議が開かれ、種々の事項に関して改革案が立つた。よつて時の法王Clemens V(1305--1313)は、改革案を基礎とした新追加法典を作ることとなつたが、改革案の中には、穏当を欠くものも少くなかつたので、Clemensは独自の見識を揮つて多大の修正をこれに加へた。さうしてその結果を一箇の法典と化して、一般への公布の手続(Publikation)は済ませたが、大学への送付手続(Versendung)は、未だ終了せざる間に、突然Clemensの病歿となつた。すなはちClemensの法典は、彼の在世中には効力を発生せずにゐたのである。なぜかなら当時は新法典は、Paris及Bolognaの二大学へ送付し、これにつき新講義を開始させて後、効力を発せしめる例であつたがゆゑである。
しかしClemensの法典は、次代の法王Johann XXIIが一三一七年に二大学への送付手続をとつてくれたために、同年以後正式の効力を発生することになつた。これをClementinae法典といふ。
Clementinae法典もやはり五篇に分れ、第一篇(Judex)には一一章・二八条を、第二篇(Judicium)には一二章・二二条を、第三篇(Clerus)には一七章・三三条を、第四篇(Sponsalia)には一章・一条を、第五篇(Crimen)には一一章・二三条を含んでゐる(一)(二)。
一 Clementinaeも、後にCorpus Juris Canoniciの一部に収納された。ゆゑに正文はCorpus Juris Canoniciの刊本について見ることができる。
二 Clementinaeからの引用方法は、例へばその第二篇第十章『抗弁について』の章の中から第一条を引かうとおもへばc. I de exceptionibus II 10 in Clem.とする。Clem.はClementinaeの略。
上来長々と教会の立法過程をのべたが、要するに中世の教会法は、四つの記念的編纂物に結晶してしまつたのであつた。(一)は十二世紀現行法の集大成としてのDecretum Gratiani (二)はDecretum以後の歴代訓令集としてのLiber Extra (三)はLiber Extra以後の歴代訓令集としてのLiber Sextus (四)はVienne宗教会議の決議を基礎案として作られたClementinae。
Clementinae以後にも、単行の法律はないわけではなかつた。Johannes XXII(1316--1334)のごとき、非常に多くの単行法を出したのである。又ClementinaeはVienne宗教会議の決議を基礎としたものであつた関係上、同会議以前の発行にかかる単行法にして採用から漏されてゐたものも少くなかつた。Bonifaz VIII, Benedikt XI, Clemens Vの訓令のごとき然り——ゆゑに畢竟、十四世紀初頭の状態としては、法典としてDecretum, Extra, Sextus, Clementinaeの四者があり、新令として、Johannes XXIIその他の諸法王の単行訓令が、相当に多く存在してゐたわけであつた。
ところがその後一世紀を過ぎた十五世紀の初めになると、四法典と単行訓令とは法源としての価値を別にするものである、四法典の方は当然に各国のクリスト教徒を拘束するが、単行訓令の方は、各国民から特別の継受・特別の承認を受けざるかぎり、その国民を拘束することなしと論じられるやうになつた。これは法王権の国内侵入を最小限度に喰ひ止めんとした当時の国民運動の現はれであつたのであつて、とりも直さず、法王権の衰落を物語る以外の現象ではなかつたのである。一四一四年のConstanz宗教会議・一四三一年のBasel宗教会議のごときは、露骨に右の思想を表明し、『Decretum, Extra, Sextus, Clementinaeの四者は、教会の成文典(jus scriptum)として各国のクリスト教徒を当然に拘束するも、単行の訓令は当然には各国民を拘束することなし』と決議した。又この二会議は、右四箇の法典を一括して、それに『完結教会法々典』(Corpus Juris Canonici Clausum)なる名称を捧げもした。これは四法典を単行訓令以上に、一段高く価値づけると共に、四法典にだけ世界法的性質を認め、単行訓令にはこれを認めることを拒まうとする老獪な企てに外ならなかつたのであつた。
ここになほ一事の注意せらるべきは、Corpus Juris Canoniciそれ自身は、決して法典ではなかつたといふことである。なぜかといふに、Corpus Juris Canoniciはその名においては通用力を有せず、その組成部分たる四つの書物が各々別々の名で通用したに止つたからである。ひとがCorpus Juris Canoniciの第何条として引用せず、Extraの第何条とか、Clementinaeの第何条とかいつて引用するのも、各部だけが法典で、全体はさうでなかつたからであつた——Corpus Juris Canoniciとは、四法典をかりに一括した便宜的総称に過ぎなかつたのである。
終りにCorpus Juris Canonici Clausumからとり残された単行訓令の、その後の運命を一見すると、一五〇〇年にフランスの学者Johann Chappiusが、彼刊行のCorpus Juris Canoniciへ附属させる目的から、単行諸訓令を二つの篇に分類した。一はExtravagantes Joannis XXIIで、これにはJohann XXIIの訓令二十箇を含ましめ(一)、二はExtravagantes Communesで、これにはBonifaz VIII, Benedikt XI, Clemens V等々の訓令七四箇を含ましめた(二)。この二箇の単行令篇を附属せしめてゐるCorpus Juris Canoniciを、『広教会法々典』(Corpus Juris Canonici non Clausum)と呼ぶのである。通常の刊本(三)は、『広教会法典』であつて、四法典(Decretum, Extra, Sextus, Clementinae)の外に二単行令篇(Extravagantes Joannis XXII, Extravagantes Communes)を附属せしめてゐるのである。
一 Extravagantes Joannis XXIIは一四章に分る。引用法は、例へばその第一四章『語の法的意味について』の第一条を引かうとおもへば、c. 1 de verborum significatione in Extrav. Joh. XXII. XIV.とするのである。
二 Extravagantes Communesは伝統の篇別に従つて五篇に分る。但し第四篇(Sponsalia)は、篇名のみあつて内容なし。引用方法は、例へばその第一篇第三章『選挙について』の第一条を引かうとおもへば、c. 1 de electione in Extrav. Comm. 1 3とするのである。
三 Corpus Juris Canoniciの主な刊本は、Pithou, 1689; Böhmer, 1747; Richter, 1839; Friedberg, 1879--1881; 独語抄訳はSchilling-Sintenis, 1834--1837.
六 前期教会法学
以上を以てわたくしは、一世紀から十六世紀初に至る教会の立法史をのべたのであるが、ここで少しく視野を広げて、十二世紀以後の教会法学をも覗見しようとおもふ。けだし教会法学が一箇の学問として自立したのは、十二世紀半のことであつたが、その後における斯学多彩の発展は教会法の発達そのものをも左右し主導したかの観があり、学者によると、十二—五世紀を『学的影響の時代』と呼ぶほどであるのであるから(例へばKoeniger)、立法史に対する一例面史としても、学説の歴史を見ておく必要があるとおもふがゆゑである。
ところで学説史は、同期の立法史が十三世紀初頭を画線として前後の二期に分れたのと同様に、十二—三世紀に亘る前期と、十三—五世紀に亘る後期とに分れるのであつて、そこに学風の相違の見逃しがたいものもあつたのである。研究の対象からいつて前期の学問はDecretum Gratianiを主題にし、単行の訓令を顧みない風のあつたのに反し、後期の学問は単行訓令を主題目にとり、又、後期の産物であつたExtra, Sextus, Clementinae等の法典へも、大いに研究力を傾けたのであつた。学風からいふと前期の学問には、単に古典の意味内容をあるがままに把捉しようとする訓詁学的傾向の強かつたのに反し、後期は、ちやうど教会事務が大いに膨脹し、僧侶が実務に鞅掌しつつあつた時代のこととて、実学に重きをおき、実際的見地から現行法を整理し、解明しようとした形跡の歴然たるものを示したのである。が同時に前期の学問には、いかにも新興のそれらしい溌剌とした新鮮味があふれてゐたが、後期の学問には、細心精緻な作品の出現もあつたとはいへ、多少その考へ方に形式的な固定と無気力な停止とを生じてゐたことも争はれなかつた。
本節においては、まづ前期教会学者の講義及述作の様式を見、それから主もな学者の列伝を試みようとする。
前期教会学者の仕事も講義及述作の二方面に分れてゐた——講義の方から見て行くと、教師はDecretum Gratianiの解釈に入る前に、まづ条文の文言の検認を試みるのである。すなはち教師は条文を学生に読聴かせ、書取らせ、流俗本の誤脱などを訂正してやる。条文を本文(litera)、読聴かすことを朗読(legere)、訂正することを校正(emendare)といつた。次に教師はいよいよ解釈に入るのであるが、各条の説明をはじめるに先ち、一箇の制度の趣旨全体を概説しておく。これを序説(summa)といひ、各条の解釈を註釈(glossa)といつた。教師は条文を構成する語の概念を定めたたり、関係条文を参照したりしながら、各条の意味を定めて行くのである。又教師は条文相互の間の矛盾を指摘した上、これを解釈して見せ結局教会法源には矛盾なきものなることを明かにする。矛盾の指摘を対立(contrarietas)、条文相互間の関係を明かにすることを峻別(distinctiones)といふ。又教師は、実際上又は想像上の例をあげた上、これを解決して見せ、結局教会法源には欠陥なきものなることを明かにする。例を設例(casus)といひ、これを解くことを解決(solutiones)といふ。又教師は各条文を綜合して要約を作つたり、他人の学説を批判したりする。要約をbrocardica、学説批判を論議(argumentum)といふ。
著述の様式にもいろいろあつたが、第一類は註釈書(glossa)であつて、行間註釈書(glossae interlineares)と欄外註釈書(glossae marginales)との二種に分れた。前者はDecretum Gratianiの本文を書写したその行間へ、註を挿入せるもの。後者は本文を書写したその左右及上下の余白へ註を充填せるもの。前者は条文中の難句を断片的に註した単なる文理解釈に過ぎなかつたが、後者は各条文の包みもつ意義を論理的に組織的に解明しようとしたものであつた。第二類は論述(summa)であつたのであつて、これは各条の意味よりも全篇の解説に重きをおき、従つて説明の方法も、条文の排列順には従はず、篇及章の順序に従つたのみであつた。第三類は単行論文(Monographieen)にして、これには或実際上又は仮想上の設例を解決することを主眼とした応用的のものと、或制度をすべての視角から徹底的に究明することを主眼とした学理的のものと二種あつた。前者を問題論文(quastiones)、後者を学術論文(tractatus)といつた。第四類は要約(brocarda)であつて、これは条の順序にはもちろん、章篇の順序にさへ拘束されず、全く自由に法理を要約したものであつた。
その外にそれ自身解釈ではないが、解釈を補助させることを目的とした一列の仕事があつた。一は目次の調製である。すなはちDecretum Gratianiの諸条文を簡便に索出し得るやう、各条に簡短な見出しを附したり、事項索引を作つてアルハベット順に並べたりするのである。見出しを標題(rubricae)といひ、索引をindicesといつた。二は条文の摘録である。すなはち法典中の諸条文を、その意味を損ぜぬやうに簡短にちぢめ、人をして尨大にして高値なるDecretumの代りに、簡便な代品を使用させようとするのである。これを摘録(excerpta)といつた。
Gratian集へ最初の註釈を加へた人、すなはち最初の教会法学者と見らるべき人は、Paucapaleaであつた。Gratianの直門で、一一五〇年ごろBolognaで教鞭をとつてゐた(一)。この人の業績は前にも一言したとほり(二)、(一)Gratian集の第一部を一〇一節に、第三部を五節に、それぞれ細分したこと、(二)Gratianの洩らした古法令を拾つて集中へ挿入したことにあつたのであつて、挿入文をpaleaeといふのも、Paucapaleaの名に因んだからである。が、これだけに彼の業績は尽きたのでない。彼は(三)glossa(註釈)をも試みた。集中の難語を註したり、或は難句を敷衍したりしたのである。さらに(四)summa(序説)の方法、すなはち一節の内容をその節の初めにおいて略説するといふ方法もとつたし、(五)一説にはrubricae(標題)の方法、すなはち各条文へ簡単な見出文を附することも彼に始つたといふのである。
一 中世の教会法学者の閲歴及学業は、Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwartの第一巻及第二巻に詳述されてゐる。すなはちその第一巻には、前期教会法学者約二十五名を伝し、第二巻には、後期教会法学者約三百三十名を伝してゐる。余の以下の教会法学者伝は、Schulteの右の第一巻及第二巻を基礎材料に取り、傍らSavigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalterの第四巻及第五巻に散見する教会学者に関する記事を参看して、試みたものに係る。
二 前出四参照。
Paucapaleaとほぼ時代を同じくしてRolandus及Rufinusがゐた。(一)RolandusはBolognaの教師。後ち選ばれて法王となり、Alexander III(1159--1181)と号した人で、学績としてはGratian集への論述(summa)がある。よく簡潔の語法で法典の全網を闡明したといはれてゐる。(二)Rufinusの方は経歴やや不明であるが、若い頃Bolognaに学んでローマ法学の泰斗Bulgarusからローマ法を学んだらしく、後にはParis大学の教会法の教授となつた。そしてやはりGratian集への論述を書いてゐるが、その内容は該博な知識を存分に展示したもので、叙説精密、同一事項の説明量がRolandusに約三倍してゐるのである。
十二世紀後半の学者としては、(一)はAlbertus——Bolognaの教師であつたが、晩年には選ばれて法王となり、Gregor VIII(1187)と号した。教師時代の記念として、Gratian集の各部門へ亘る註釈書(Glosse)がある。(二)はGadulphus——経歴全く不明であるが、やはりGratian集の各部門に及ぶ註釈書をかいてをり、その間まま非常に新鮮の気にあふれた独創的解釈を見せた。(三)はStephan(1135--1203)——有名な僧侶で、一一七九年のLateran宗教会議へも出席してゐる。業績としてはGratian集の論述(summa)があるが、その価値は、Schulteにいはせると、『Paucapaleaの上、Rolandusのやや下、Rufinusよりはずつと下る』といふ(一)。(四)はJohannes Faventinus(†1190)——これまた有名な僧侶で、一一七九年にはLateran宗教会議へ出席。一一八九年にはドイツ皇帝Friedrich Iに従つて第三十字軍へ出征。一一九〇年に同帝と共に戦歿してゐる。その著には、論述(summa)と註釈書(glossa)とあるが、論述の方はRufinusその他先賢の書をあまりにも多く利用したもので、『それは全然剽窃物に過ぎなかつた』と、Schulteはいつてゐる(二)。註釈の方はしかし彼自身の仕事で、立派な特色も具へてゐる——古い語義註(wörtliche Glosse)の状形を十分に脱して、完全な逐条講義(Commentaren)となつてゐる点がそれであつた。(五)はSimon——この人の経歴も不明であるが、一一七四年から一一七九年の間に一の論述(summa)を著してゐる。その特色は、Gratian集のみを解釈せず、同集以後の発布にかかる新令をも解釈してゐる点にあるのである。著者はけだし従来の法律書が、Gratian集にばかり囚はれて現行法の説明を軽視し来つたのを憾みとし、現行法本位・実用本位の解釈を新建しようと試みたのであらう。果然この新方法が学界を風靡して行くこととなつた。(六)はHuguccio(†1210)——この人こそ前期教会学者中の最高峯ではあつたのである。彼は一一八七年頃有名な一の論述(summa)を著した。それはGratianの集を全尽的に解釈したもので、集中の条文は、小数の片々たるものを除き、全部、彼から解釈を受けたのである。Gratian集以後の新令をも相当に考案の範囲へ取込んだのである。解釈に当つては彼は注意を先行諸大家の学説へ向けた。Paucapalea, Rufinus, Rolandus, Albertus, Gandulphus, Stephan, Johannes Faventinus, Simon等の学説を批判し、整理し、組合せつつ、壮麗な学説の綾織物を織つたのである。又或事項がローマ法と関聯をもつ場合には、彼はきつとローマ法源をも使用したが、ローマ法源の駆使ぶりも極めて自由であつたと評されてゐる。要するに彼のsummaは、十二世紀教会法学の集大成であつたのであつた。
傾向からいふと、Huguccioは法王権の味方で、法王を絶対至高の地位へ上らしめたいとの念願に燃えてゐた——『世俗法においては形式的厳格性が、教会法においては公平の観念(canonica aequitas)が、支配的である』と彼はいつてゐる。『世俗法は、教会法と牴触せざる限度においてのみ行はる』ともいひ、『僧侶は絶対に俗人の上にある。俗人は僧侶に対しては訴を提起することえず』ともいつてゐる。注意に値することは、大法王Innocenz IIIがHuguccioの門弟であつたことで、Innocenzが法王の地位の絶対至上化に成功しえたのも、その師Huguccioの理論を実践に移した結果であつたかも知れぬのである。
十二世紀後半の学者としては、Bernhardをも見逃すわけにゆかない。彼は前にのべたとほり、『第一集』(Compilatio prima)の編者であつたが、一面また気の利いた著作者でもあつたらしく、新味ある様式の著述を幾種類も残してゐるのである。その一は『第一集』に対する註釈書(glossa)であつたが、これこそ実に新令の研究に最初の先鞭を着けたものであつた。爾後続出した諸ろの新令註釈書類は、要するにBernhardの後を迫つたものであつたのである。その二は『婚姻法論』『法王選挙論』といふやうな幾つかの単行論文であつたが、これによりBernhardは単行論文(Monographie)の祖といふ栄冠をもかちえたのである。その三は教会法の全般に亘る一の論述(summa)であつたが、これぞ教本的叙述方法(summa titulorum, Lehrbuch)の最初のものに外ならぬのであつた。在来の論述は条文に即し過ぎて、註釈書との区別を失ひがちであつたが、Bernhardのは、箇々の条文の内容よりも条文相互間の関聯を重視し、全体の構造を概論的に通叙したものであつたのである。いかにもそこには、教科書らしい短い定義や簡潔な断定の陳列が見られるのである。
一 Schulte, Geschichte I. 136.
二 Schulte, Geschichte I. 138.
十三世紀前半の学者としては、(一)Johannes Teutonicus(†1269)——やはりBolognaの教師で、Gratian集への有名な註釈書を作つた。その特色は、極めて豊富に他人の学説を引用した点にあつた。恐らく著者は、註釈書として許さるる限度内において——本文の周囲の余白にしか書込みえぬといふ窮屈な框内において——極力多量に他人の学説を集録しようとしたのであらう。引用された学説は、原文よりも短縮はされたが、原意は害されずにゐると見られてゐる。又引用された他人の学説と著者自身の見解とが、充分よく接合して、有機的な連続体に成り切つてゐるともいはれてゐる。いはばこの書は、自説の周囲に他人の重要な学説を全部結集させた一箇壮麗な学説総攬であつたのである。
(二)はDamasus——これまたBolognaの教師で、種々の著作を残したが、有名なのは、問題論文集(Quaestiones)と原則集(Brocarda)。前者は二七八箇の法律問題をかかげ、一々理由を附してそれに解決を与へたもの。後者は諸大家の著書を広く渉猟して教会法上の不動の原則一二五箇を拾ひ集めたもの。原則集の編纂は、実にDamasusに始るのである。
(三)は十三世紀の大教会法学者としてのTancred(†1235)——その著に婚姻法論(Summa de sponsalibus et matrimonio)及訴訟法論(Ordo judiciarius)があり、『第一・第二及第三集』に対する註釈書もある。婚姻法論は、婚姻に関する当時の実定法を細密に論述したもので、類書中の最高権威を以て目された。訴訟法論も、教会訴訟法に関する最も深い又最も精しい論述に外ならなかつた。『第一・第二及第三集』に対する註釈書も、三集に対する標準註釈書(glossa ordinaria)に外ならなかつた。
七 後期教会法学
後期教会法学者の仕事様式は、講義においても著述においても、大体、前期のそれを踏襲したものであつたが、多少の進化は示さぬでもなかつた。すなはち(一)講義においては、正教師(ordentlicher Lehrer)と助教師(ausserordentlicher Lehrer)との区別を生じた。これは講義の対象が、正科書(libri ordinarii)であつたか、科外書(libri extraordinarii)であつたかに基いた区別で、十三・四世紀頃のBologna大学々則によると、Decretum GratianiとLiber Extraとを講義しうる資格を有する者は正教師。Liber SextusとClementinaeとを講義しうるに止る者は助教師であつた。前二書が正科書となつてゐたのに後二書は科外書に過ぎなかつたからである。又本講義(lectura)の外に復習講義(repetitiones)及特殊講義(disputationes)等の新様式が発生した。復習講義とは、未だ教師資格を有してゐない研究者が、特に総長の許可をえて初学者のためになしたもので、既修科目の中から、学生にとり難解であらう箇所を撰び、一層丁寧に之を説明してやつたのであつた。特殊講義はすでに教師資格を有してゐる者の仕事で、実際上又は仮設上の法律問題を掲げてこれを解決しつつ、傍ら学生の反対意見も聴きその批評をも試みるといふやり方であつた。復習講義の題目(thema)や特殊講義の問題(quaestiones)やは、講義の数日前に学生に掲示しておき、準備の余裕を与へたのであつた(一)。
一 正教師の講義は午前になされ、助教師の講義は午後になされた。木曜日には本講義はなく、復習及特殊の講義のみが行はれた(Schulte, Geschichte II. 456; Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter II. 267)。
次に著述の様式について見るに、この期に入つて眼についたのは、(一)逐条講義(commentaria)の発達である。前期のglossaの中には、なほ発生当初の形状をとどめて語句の解に偏せるものが多かつたが、今期のそれは詳密にして法理的なる逐条講義への完全なる転換を示したのである。名称上もglossaとはいはず、逐条講義(apparatus, commentarius)といふやうになつてゐた。(二)は教本(summa titulorum)や提要(compendia)の発達である。教本の特色は、説明上、単に法典の章の順序(Titelfolge)に従ふだけで、条の順序には従はないといふ点に存し、提要の特色は、章の順序さへも追はないといふ点に存するのであるが、前期にあつてはこの種の述作は共に寥々。今期に入つてやうやく見られるやうになつたのである。(三)は学術論文(tractatus)の発達である。今期に入ると、教会法上の各種の問題につき、殆ど無数の学術論文が出たのである。(四)は鑑定録(responsa)の出現である。これは前期の問題論文(quaestiones)の進化したもので、問題論文が仮定的設例に対する解答であつたのに対し、鑑定は、現に判決に服せんとしつつある法律問題に対する意見の表示であつたのであつた。後期の著名な学者は、大抵鑑定録を著してゐるのである。(五)は判決録(decisiones)の出現である。これも前期には見られなかつたが、後期に入ると法王が最高裁判所として非常に屡々重要な判例を発したので、これを整集する仕事として、判決録の出現を見たのである。(六)は通俗講話類の発生である。これは、教会法の実地運用に携つてゐた下級僧侶を法的に啓蒙するために書かれたもので、やはり後期の産物であつた。
十三—五世紀は教会法学の最盛期で、殆ど無数の学者を出した。Schulteの教会法史第二巻に伝記された学者の数だけでも三百三十余名の多数に上つてゐるのである。余はここにその中の極めて著名な数人だけをあげることにしよう。
十三世紀の学者としては、(一)Innocenz IV(1243--1254)——若い頃Bolognaに学んでJohannes Teutonicusから教会法を、Azo, Accursius等からローマ法を学習し、後ち同地で教会法の教師となり、一二四三年、法王に選挙された。その著に『第五集』への逐条講義(commentaria)がある。学理的にして実際的なる名著で、著者の地位と相俟ち、『第五集』に対する標準的註釈書として尊ばれた。紛糾せる諸問題を、実際家的活眼から裁断してゐると評されてゐる。
(二)Johannes de Dco——Bolognaの教師。無比の多作家で、今日知られてゐる著書だけでも二十五種の多きに上つてゐる。がそのうちの多くは通俗実用の書で、学術価値あるものは少い由である。Savignyが皮肉つたやうに、『われわれは著書の多量なことから実価以上にJohannesを買ひかぶる危険があるのである(一)』。
一 Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter 2. Aufl. V. 459.
(三)Martinus de Fano(†um 1275)——BolognaでAzoからローマ法を学び、後Arezzo大学の教授となつた人。ローマ法・訴訟法・封建法・教会法等の各方面に亘つて相当多くの著述を残した。
(四)Wilhelmus Durantis(1237--1296)——この期における最大教会法学者の一人。Modena大学の教師だつたこともあつたが、後法王庁へ出仕して枢要の地位に上つた。その著に有名なSpeculum Judicialeがある。教会の訴訟法を取扱つたもので四篇から成り、第一篇において人すなはち裁判長・陪席判事・訴訟当事者・代理人・弁護人・傍聴人等を論じ、第二篇において訴訟関係すなはち訴の原因・反訴・抗弁・判決手続・証拠法等を論じ、第三篇において教会刑事訴訟の手続を簡要に述べ、第四篇においては実際家の便宜のために訴訟書類の書式を示してゐる。説明に当つては、教会法及ローマ法の法源をやや過剰に過ぎた感もするほど多量に引用してゐる。又他人の学説を文字通りに借用しておきながら出所を示さず、自説の如くに見せしめてゐる箇所もあるとかで非難もされてゐる。がしかしこの書は遂に一代の圧倒者であつたのであつた。なぜかならこの書は、驚くべき組織力を以て散乱的な材料を蒐集し整理し排列してゐるし、精密な論程の間に、さすがは最高司法の枢機に参与してゐた人だけの冴えた達見を光らせてもゐるからである。それにこの書の著者の文献的知識は全く汪溢的で、当時のローマ法及教会法に関する一切の文献を読破してゐたのかと想はるるばかりであつたから、正当にもこの書は、教会訴訟法論中の『王』となり、遠き後世にまで大且つ継続的なる影響を垂れたのであつた。
(五)Boatinus(†1300)——Padua大学の教師。Liber Extraの中から比較的少数の規定を抜いて註してゐるが、これは一般条文に対する註釈は他人に委せ、少数の条文に対する自家独創の見を示さうとしたためと察せられる。しかし彼の創見なるものは、知識の該博性と考察の鋭利性とを二つながら欠き、平凡な理論を仰々しくふりまはすに終つたといはれてゐる。彼の著の出たのは一二八○年頃であつたが、当時すでに教会法学の衰兆がきざしつつあつたのではないかと想はせるほどであつた。
十四世紀の学者としては(一)Guido de Baysio(†1313)——Bolognaの教師。著書としてはLiber Sextusに対する詳密な逐条講義がある。該博な知織の披瀝ではあつたが、新創の見と法理的鋭利性とにおいていささか欠けたものがあつたといふ定評である。
(二)Johannes Monachus(†1313)——Parisに学び、Meaux市の僧正となつた人。その著にLiber Sextusに対する逐条講義がある。後出Johannes Andreaeの同典註釈書には及びもつかなかつたが、前出Guidoの註釈書よりはすぐれてをり、特にフランスの教界からは広き使用を受けたのであつた。
(三)Johannes Andreae(†1348)——時の人から『法の泉』と称された教会法学最大の巨星。Bolognaにて前出Guido de Baysioから講義を聴き、成業の後Padua大学の教授となり、後Bolognaへ転じ、四十年の久しきに亘り教鞭をとつてゐた。政治的には熱心な法王権の弁護人であつた。
著書にはいろいろあつたが、その一はLiber Sextusへの逐条講義——当時この書はSextusに対する標準的な註釈書と見られてゐたのであつた。その二は婚姻法論(Summa de sponsalibus et matrimonio)——これこそ実に数多き教会婚姻法論中の最大の記念碑であつたのであつた。その三は教会法上の血族及姻族の親等計算法を論明した親等論(Lectura aboris consanguinitatis)。その四はClementinae法典をかなり詳密に解説した同典註釈書(Apparatus ad Clementinas)。
しかし一ばん彼を有名にしたのは、Durantisの名著Speculum Judicialeに対する彼の補追(Addictiones ad speculum Guil. Durantis)であつた。けだしJohannesは、古人の名著を増補訂正する傍ら彼自身の、長い学究生活の間に獲得せる溢れるばかりの文献的知識を、一気に放出しようと試みたもののごとく、多少の脱線ぶりを示して、中世の諸学者の閲歴とか、彼等相互の間の関係とか、彼等の著書の内容とかについて種々物語つてくれたのである。ためにこの書はDurantisを補訂する追加篇であつたと同時に、中世の学問に関する貴重な一箇の史料集ともなつた。価値はむしろこの書の脱線的方面に存した位であつたのである。
Johannesの為人に関してSchulteはいふ——『Johannesは天才的な法の把握者ではなく、個性の強い学者でもなかつたが、知識は実に該博を極めた。彼は中世の全法律文献を知つてゐただけではなくて、深くそれらを究めてゐたのである。彼は既製知識の飽くなき採集家であつた。彼の仕事は、彼の休みなき採集精励の産物であつたであらう』と。
(四)Johannes Colderinus(†1365)——Johannes Andreaeの門弟にしてその養子となつた人。一時大いにBolognaにて教師的名声を馳せた。多数の単行論文をものし、多角多彩の才筆を歌はれた。
(五)Johannes de Lignano(†1383)——初めBolognaの教師であつたが、のち法王庁に出仕。多忙な生活の間に多種多数の作品を残した。彼の長所は、他人の述作を基礎にして手速く書物を作つた点に存し、短所は思索に徹底力を欠いたところにあつたといはれてゐる。
(六)Antonius de Butrio(†1408)——やはりBolognaの著名な教師の一人。Liber Sextusの逐条講義と多数の単行論文とを残した。
十五世紀に入つてからも、Antonius de Rosellis(†1466), Andreas de Barbatia(†1479), Johannes a Turrecremata(†1468)等々、多数の有名な教会法学者を輩出した。しかし大体においてそこには、旧い知識の機械的な結合と陳腐な類型の反覆としか見られなかつた。