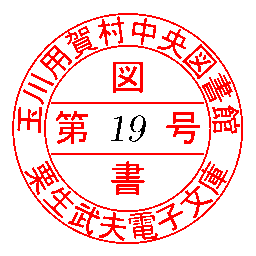
一 前 言
今ではいづれの立法も多数の離婚原因を列挙してをり、わが民法も八一三条一号から十号へかけて沢山これを列べてゐるが、かやうに離婚に寛大になつたのは、まづ十八世紀の末頃からで、それ以前には、離婚の原因といふものが比較的に少かつた。一層歴史を遡つて十五世紀頃の状態を見ると、もはやそこに離婚制度なく、従つて離婚原因に関する規定等も見出しえぬのである(一)。換言すれば宗教改革の頃までは離婚は全く禁じられ、その後も僅々四五の場合に許されてゐたに過ぎなかつたが、十七・八世紀の自然法運動を越えた頃から著しく自由になり、遂に現に見るやうな沢山の羅列とはなつたのである。
一 離婚が禁じられるに至つたまでの経過を略記しておくと——初めから教会は離婚を非とする思想を有し、屡々これを禁止せんと試みたこともあつたが(E. Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts Bd. II S. 600 fg.)、何分にも信徒たるゲルマン人が放縦な婚姻観を有し、協議上の離婚はもちろん、夫の恣意的離婚さへも是認してゐたので、俄に禁止を断行することを得ず、一時信徒の慣習に妥協せざるを得なかつた。すなはち協議離婚はこれを許し、法定の原因に基く離婚もこれを許し、ただ夫の恣意に基く離婚だけを禁ずることとしたのであつて、例へばフランク族に対しては、妻が姦通せる場合、夫を遺棄せる場合、夫を殺害せんと企図せる場合、夫が奴隷に墜つべき罪を犯せる場合、夫婦の一方が捕虜となりて帰来の見込なき場合には、一方離婚をなすことができると説き(Hinschius in der Zeitschrift für deutsches Recht Bd. XX S. 77 fg.)、アンゲル・ザクセン族に対してもほぼ同様に教へたのである(Hinschius, S. 67 fg.)。しかし九世紀において、教会は強硬主義へ一転した。協議離婚を禁じ、一方離婚権の発生原因をも縮少した。爾来益々この方針を進め、遂に十一世紀に、禁止の断行となつたのである(Hinschius, S. 83 fg.)。
本稿において私は、宗教改革以後に於ける離婚原因の拡大史を述べて見ようとするのであるが、それには離婚法の背後を流れる性的自由の思想の発達を看過するわけには行かないので、敢てこの不案内の土地へも立入ることをなすならば、かの宗教改革の頃は、ちやうど性の問題に対するヨーロッパ人の思想の転形期ではあつたのであつた。Engelsはこの時代における性的思想の変化に関していふ——宗教改革の運動に先つ二・三十年前、盛に行はれてゐるところの諸発見と諸発明とは、その頃の経済状態及び思想状態へ異常のセンセーションを捲き起した。人間の外的および内的の限界が俄かに広くなり、インドの富・メキシコの銀へ向つて活溌な野心を湧すやうになつたと同時に、性の問題に関しても、自由な恋愛婚を喜び肯定するやうになつた。その頃までは封建の風として、親が子のために家の利益を標準として配偶を選定し、子も従順にそれに従つてゐたのであつたが、もはやそのやうな家本位の婚姻形態は維持できぬことになつた。家本位の婚姻の代りに常事者本位の婚姻が現はれ出して来たのである。当事者間の相互愛を、唯一絶対の基礎とする個人主義的結婚が始まりかけて来たのである。正に宗教改革期は、近世ブルヂョアジーの創生期であつたと同時に、個人主義的婚姻形態の発芽期でもあつたと、かうEngelsは見てゐるのである(一)。
一 Engels, Der Ursprung der Familie(Internationale Bibliothek)S. 65 fg.
尤も宗教改革のチャンピオン等が拓いてくれた離婚可能の範囲は、さほど広汎なものではなかつた。これは彼等がその『聖書主義』(Schriftprinzip)に束縛されてゐたためであつて、彼等は元来ローマ教会の伝承から離れて『神の言葉』へ直参し、聖書そのものをあくまでも信条の源泉としようといふ所にその運動の眼目を置いてゐたのであるから自然、聖書の権威を絶対視する傾向を有し、離婚原因の認定に当つても、聖書の文句に囚はれ勝ちたるを免れなかつたのである。尤も聖書が明瞭に離婚の原因と見てゐるのは、僅々一二の場合に過ぎないので(例へばマタイ伝五章三十二節、十九章九節)、改革家等もさすがにその狭隘性を痛感したらしく、或は拡張解釈の方法により、或は類推の方法によつて聖書の離婚原因規定を可能的の広さにまで拡張せんと試みもしたのであつたが、何分にもその立論の根柢が聖書主義であつたがために、十分に自由には離婚原因を認めることができなかつた。結局、『神では救はれなかつたのである』。神学から離婚原因を引出すことは絶望であつたのである。新しき離婚法は新しき方向から導来せねばならなかつた!
自然法の運動は、聖書そのものを揚棄しようとした運動であつた。宗教改革のやうな単なるローマ教会からの解放運動でなくて、宗教一般からの解放運動であつた。この運動を乗り越えた頃から、諸ろの文化が初めてその神学的色彩を脱して近代的な性質を取るに至つたのである。故に私は、かのTroeltschが、十八世紀を以て近世史の発端とした・その鋭敏な史識に全く推服する。彼はいつた(一)——『近世史は十八世紀に始まる。十七世紀までは中世であつた。けだし近世文化の特色は、自然(Natur)と理性(Vernunft)を基礎とするところにあるのに、かやうな傾向の始まつたのは、実に十八世紀に入つてからであつたから』と。離婚法の歴史も十八世紀においてやうやく聖書の制約から離脱したのである。「自然」と「理性」とを基礎にして離婚の原因を自由に新定するやうになつたのである。十八世紀こそ離婚法史の転回点。自然法こそ現代離婚法の母乳であつた(二)。
一 E. Troeltsch, Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit (Kultur der Gegenwart I, 4. 1. 2. Aufl.), S. 600 fg.
二 穂積博士『離婚制度の研究』は、離婚法に関してのこの国最高の文献である。しかし同書は何故か旧教会の婚姻法の研究にあまりに多く傾き過ぎ、新教会の婚姻法の研究を殆ど全く閑却してゐる。新教会こそ離婚法の原産地なのであるから、離婚法の研究には絶対に新教会法を無視することができない。これを無視して離婚法の発達を研究しようとされたのは、穂積博士の大なる見当違ひであつたであらう。
二 総 説
で、私は私の課題に立帰つて、離婚法の内部の構造そのものの変遷史を描いて見ように——
新教会の離婚史の第一ページは、一五三七年Luther(1483--1546)の一派が、かの有名な『シュマルカーデン箇条書』(Schmalkadische Artikel)を条定して、改革運動における彼等の態度方針を闡明にした際、同箇条書の附録において、『離別後における無責配偶者の再婚を禁ずるは非なり』(,,Es ist unrecht, dass wo zwei geschieden werden, der unschuldige Teil nicht wiederum heiraten soll'')と宣言したことによつて、開始されたのであつた(一)。なぜならばこの宣言は、再婚を許さざる不完全の離別・すなはち別居制を排撃して、再婚を許す完全な離別・すなはち離婚制を是認したものであつたからである。別居制は無責配偶者に対してあまりにも酷である。この方法によるときは、無責配偶者は、なるほど過責配偶者と同居するの苦痛からは脱しうるが、過責配偶者の生存中、独身を守らざるべからざるに立ち至るからといふので、別居制を斥けて、代へるに離婚制を以てせんとしたものであつたからである。
しかし何が離婚の原因となるやについては改革家の間にも意見の完全なる一致はなく、所説甚だ区々たるを免れなかつたのであつて、まづLutherその人の所見を叩くと、一五二二年の作Die Predigt vom ehelichen Lebenの中では、姦通が離婚の原因となるといつてをり(二)、翌二三年の作Die Auslegung des 7. Kap. 1. Kor.の中では『一方が怒に乗じて家を去り、帰家を肯ぜざる場合には、他方は離婚をなしうべし』といひ、正に今でいふ準遺棄(Quasidesertion)を離婚原因としてをり(三)、一五三〇年の作Von Ehesachenの中では、『恣まに家を出でて音信を絶ち、扶養を廃するは姦通以上の悪なり』といひ、正に今でいふ固有の遺棄(eigentliche Desertion)を離婚の原因としてゐる(四)のを見るのであるが、これ以上の広さにおいては認めてゐない。後出Melanchton一派のやうに、虐待や殺害企図を離婚の原因と見た形跡はないのである。これLutherが、聖書に拘泥して彼の離婚論を建てたからで、彼のやうに聖書に拘泥することになると、明かに離婚原因となりうるのは、姦通と遺棄の二つ位のものである。即ち姦通は、マタイ伝五章三十二節及十九章九節に、妻姦通の場合にはこれを離別するも差支なき旨明言してゐるので、姦通が離婚原因となりうることについては疑がない。又遺棄も、コリント前書第七章五節の句を便宜に解釈するならばこれまた離婚原因となる。なぜならば同箇所には、『不信者自ら離れ去らばその離るるに任せよ』とあり、この『不信者』は狭く取ればクリスト教を信ぜざる者の謂ひとなるが、広く解すればクリスト教は信ずるもその信じ方の正しからざる者即ちいはゆる誤れる信者(falsche Christin)をも含むこととな(五)る(六)。又所謂『自ら離れ去らば』を、配偶者を棄てて家出せる者即ち遺棄者の意味に解するならば、遺棄者はこれを『離れ去るに任す』ことができることとなり、即ち離別しうることとなり、結局遺棄者に対しては残留配偶者が遺棄を理由として離婚の訴を起しうるといふことになるからである。しかしせいぜいこれ位のものである。姦通と遺棄以外には、聖書中遂に離婚原因なく、離婚のために援用しうる聖句も発見しえぬのである。
一 Scheurl, Das gemeine deutsche Eherecht und seine Umbildung(1882)S. 201.
二 Werke(Erlanger Ausgabe, 2. Aufl.)Bd. XVI, S. 523 fg.
三 Werke, Bd. LI, S. 38 fg.
四 Werke, Bd. XXIII, S. 143 fg.
五 Scheurl, S. 300.
六 コリント前書第七章は、Lutherが彼の離婚論の根拠として以来、これに倣ふ者多く、遂に新教会の離婚論の主たる淵源となるに至つた(Scheurl, S. 294)。
ではLuther以後における新教会の離婚論の発展はといふに、これに関してはRichterの名著(一)と、これに価値ある補充を加へたMejerの論文(二)とがあり、二者相補つて新教会の離婚論史に関する絶対の権威書となつてゐるので、余もこれに準拠して論歩を前進せしめるならば、Lutherの門弟Bugenhagen(1485--1558)は、準遺棄の観念を明瞭にした(三)——準遺棄とは遺棄者の居所分明の場合で、この場合には裁判所は離婚判決宣告の先行条件として、先づ帰還命令(Rückkehrbefehl)を発しなければならない・帰還命令に従はなかつた時から、準遺棄者は固有の遺棄者と同視されるに至ると、彼は主張したのである。この説は、当時の裁判実務へ決定的影響を与へ、裁判所は準遺棄者へ帰還命令を発するやうになつたさうだが、これは決して離婚の原因に新らしきものを加へたわけではなかつた。Bugenhagenは単にその師Lutherが不明瞭にしておいた準遺棄の観念を明瞭にしたに止まつたのである。彼においてもその師においても、離婚の原因は姦通と遺棄との二つに止まつたのである。
有力な神学者Chemnitz(†1522)の見解も、結果においては、同一であつた。なぜならばChemnitzは、姦通を唯一無二の離婚原因とは見たが、これは彼の『姦通』が、広く一切の婚姻破壊行為を意味し、遺棄をも姦通の観念中に併せ含ませてゐたせゐで、実質上はやはり姦通と遺棄とを離婚の原因としてゐたものであつたからである(四)。Calvin(1509--1564)の離婚原因論も甚だ聖書的であつたのであつて、姦通と遺棄との二を中心にし、これを一二の類似の場合に類推してゐたに過ぎなかつた(五)。彼の片腕であつたBeza(1516--1605)の見解も、ほぼ同一であつたといふ(六)。
一 Richter, Beiträge zur Geschichte des Ehescheidungsrechts in der evangelischen Kirche(1858).
二 Mejer, Zur Geschichte des ältesten protestantischen Eherechtes in Zeitschrift für Kirchenrecht Bd. XVI, S. 35 fg.
三 Richter, S. 24 fg.
四 Richter, S. 28.
Chemnitzが姦通の意味を非常に広く規定したのは、もとLutherに傚つたのである。Lutherも、一切の婚姻破壊行為を姦通とよび、遺棄をも包含せしめてゐた(Mejer, S. 80 u. S. 83)。
五 Richter, S. 25---Bonifas, Le Mariage des protestants p. 35.
六 Richter, S. 26.
右の諸見解と趣を異にし、非常に自由な傾向を示したのは、Lutherの同志Melanchton(1497--1560)の意見であつて、彼は姦通および遺棄ばかりでなく、虐待及び殺害企図も、同様に離婚の原因になると断じたのである。これ彼が彼の論拠を、ローマのクリスト教皇帝Theodosius II(408--480)の離婚法に求めたからで、彼にいはせると、『過責配偶者に対しては神の福音なくして皇帝の法の適用あり、故にこれにTheodosiusの法を適用して差支なし』とのことであつたが(一)、かやうに彼がTheodosius法を離婚のために援用した真の動機は、元来Theodosiusの離婚法といふのは、ローマ諸皇帝の諸離婚法中、婚姻原因を認めること最も広汎、最も自由なものだつたので(二)、これを淵源とすることより、離婚の原因を同時代人のために少しでも広くしてやらうと考へたために他ならなかつた。ところがここに一見不思議な現象は、右Melanchtonの離婚論が南ドイツの諸都市をその活動の舞台とした宗教改革家らに歓迎された一事であつた。例へばButzer(三)(1491--1551)、Sarcerius(四)(1501--1559)、Bulinger(1540--1575)等はMelanchton説に追従して虐待・殺害企図等も亦離婚の原因になると説いたのであつた。このことたる、当時の南ドイツの経済状態を少しく窺へば、おのづから首肯できる所であつて、元来当時の南独都市はクリスト教国中の最富区にして夙に早期資本主義的繁栄を示し、思想も開発的にして自由と平等とを求める風が強かつたから(五)、この傾向が自然に南ドイツの離婚法の内容を自由的に規定させたこととおもはれるのである。ローマ法との関係からいつても、南ドイツは北ドイツ以上に深刻にローマ法を継受してゐたから、Melanchtonらのローマ法を淵源とする離婚論を受容れる下地が、南ドイツでは十分に築上げられてゐたのであらう。何にせよ、北ドイツに活躍した改革家らが、Luther一派の厳正な聖書主義的離婚論を奉じたる間に、南ドイツに活動した改革家らがMelanchton一派の寛大なるローマ主義的離婚論を執つたといふのは、面白い現象ではなかつたらうか。
なほ当時の宗教法院(Konsistorium)の判例が、右寛厳いづれの学説に与みしたかを見ると、最古且つ最有力の宗教法院であつたWittemberg宗教法院の判例を詳細に研究したRichterらの研究報告によると、表面は厳格主義で、姦通および遺棄の外には離婚を許さなかつたが、しかし『生命に危険な虐待』を遺棄の一種とし、遺棄としてこの場合には離婚できると見てゐたさうであるから(六)、内実はかなり寛大主義へ接近してゐたかともおもへるのである。
一 Richter, S. 32 fg.; Mejer, S. 83 fg.
二 Theodosius, C. 5, 17, 8---拙著・ビザンチン期における親族法の発達一一七頁。
三 Richter, S. 34 fg.
四 Mejer, S. 75 fg. S. 87 fg.
五 M. Beer, Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe III, S. 42 fg.
六 Richter, S. 43 fg.
十七世紀に入つてからも、離婚の原因を遺棄および姦通に限る聖書的厳格主義と、それ以上に広く認めるローマ的寛大主義との対立が続けられてゐたが、事実上この世紀の厳格派は、かなり寛大派に譲歩してゐたのであつて、『遺棄』といふうちに、虐待や殺害の企図はもちろん、夫婦の一方が結婚後その過責によつて性交不能症に陥れるごとき場合をも包含せしめ、『遺棄』を名としてこれらの諸場合には、離婚の訴を起しうると説いてゐたのであつた。神学者としてはHollaz(一)(1648--1713)が、法学者としてはJohann Gerhard(1582--1637)及びかの有名なBenedikt Carpzow(1595--1666)が、この説をとつたのであつた。しかし、かやうに厳格主義が一方において寛大化しつつある間に、寛大主義の方は更に一層寛大化し自由化しつつあつたのであつて、実に姦通・遺棄・虐待・殺害企図・性交不能の諸場合はもちろん、夫婦の一方が終身又は永年の懲役に処せられた場合にも離婚ができる、と説くまでになつてゐたのである——当時諸所に刑法の改正あり、死刑やうやう減少して終身又は永年の懲役刑がこれに代置される傾向を示してゐたので、懲役刑を独立の離婚原因と認むべき新たなる必要が生じつつあつたものと見えるのである。
一 Richter, S. 58 fg.
十八世紀に入つてから寛厳二派の対立薄れ、漸く新教徒一般の離婚原因法の結成を見るに至つた。一体に十八世紀は、統一法典がその出現を準備しつつあつた時代であり、地方諸法の間に内容上の接近を来たしつつあつたが、離婚立法においても同じ傾向の現はれとはなつたのである。
では十八世紀における新教会一般の離婚法は、離婚原因として何々を認めてゐたかといふと、当時における新教会の代表的学者Just Henning Böhmer(1674--1740)が彼の時代の離婚原因として挙げた所のものを見ると、姦通・遺棄・性交拒否・性交不能・虐待・殺害企図・終身懲役等々が原因となつてゐるのである(一)。即ちそこにLuther的厳格主義と、Melanchton的寛大主義との統一を発見しうるではないか。
一 Realencyklopädie f. protestantische Theologie u. Kirche, Bd. XXI, S. 873.
十八世紀は又、離婚法の法源に変化を齎らし、王許離婚なる離婚法上の新視野を発展させた。
元来新教国の君主は十六世紀の初め、Lutherらの力をかりてローマ教会から婚姻主権を奪還してゐたのであるから(一)、婚姻につき、みづから司法し立法する権限があつたわけで、現に一時は、国法の一部としていはゆる教会婚姻法(Kirchen=Eheordnung)を作り、国家機関の一部としていはゆる宗教法院(Konsistorium)を建て、国務として婚姻事件を処理したこともあつたのであつたが、実はこれは名義上の事に過ぎなかつた。なぜならば教会婚姻令は、その内容を神学者が作つて君主が形式的に裁可したものに過ぎなかつたし、宗教法院の方も構成員はみな神学者で、彼らが実権を掌握してゐたからである——要するに十七世紀末までは、神学こそ離婚法の主源であつたが、次世紀に入つてから、国家は教会の離婚学説の石灰化を見て取つた。聖書的離婚原因論の全面的行詰り、これに対する一般の絶望ぶりを見てとつた。しかも自己の内部には、教会抑圧の実力のすでに十分に張切つて来たのを感得した。
よつて王は、離婚法の新法源として自らを現はしたのである。あへて教会の離婚法を否認はせぬが、同時に国王もまた離婚法の淵源なれば、国王の特許をえて離婚をなすことも可能だと定めたのである。教会が聖書を立論の基礎としてゐた間に、王は必要と衡平との見地に立つた。そして非常に自由に離婚を許した。——例へば『著しき不行跡』『重大な侮辱』等の諸場合には、離婚をなしうと定めたのである——畢竟、王許離婚は教会的離婚法の欠陥を補完した補助法源であり、聖書主義の厳酷を緩和した衡平法であつた。一体に一つの法律体系の発展が行詰つてくると、別箇の体系が併行的に発生し、衡平法として前者の厳酷性を緩和する役目を果たすものであるが、教会的離婚法の行詰りに際しても、このやうに衡平法の発生が見られた次第であつた。
一 婚姻主権をローマ教会から国家へ奉還させるために、Lutherはその著``Von Ehesachen''の中で有名な次の句を吐いた---,,Es kann ja niemand leugnen, dass die Ehe ein äusserlich weltliches Ding ist, wie Kleider und Speise, Haus und Hof, welcher Obrigkeit unterworfen.'' Werke(Erlanger Ausgabe)Bd. XXIII, S. 93 fg.
十八世紀の末端プロシヤ州法の発布を見たが、さすがにこれは『近世最初の統一法典』であり、『自然法運動の結実』であつただけに、大いに新味ある規定ぶりを示したのであつた。実に同法は、十六世紀以来新教会の学説判例が認め来つた全離婚原因を、そのまま是認し、さらにその上にも出たのである——(一)姦通(二)遺棄(三)性交拒否(四)性交不能(五)殺害企図(六)重大犯罪(七)不行跡(八)扶養拒否等々を離婚原因としただけに止まらず(一)、進んで(九)不具および(一〇)精神病をも離婚の原因としたのである(二)。最後の二者即不具と精神病とはいはゆる無責離婚原因である。なぜなら結婚後夫婦の一方が不具者となり精神病者となつてしまつたといふことは、必ずしも彼の過責に基いたものではない、むしろ多くは偶然の不幸に因つたのであるが、それにもかかはらず、彼に対して離婚の訴を提起しうることとなつたからである。これはプロシヤ州法が離婚制度の本質目的を従前とは異つた仕方において把捉した結果といふの外はない。従前のやうに離婚制度を以て加害配偶者制裁のためのものなりと見るならば、離婚権の発生につき加害者の過責を要件とする筈であるが、かかる見解をとらず、むしろ離婚は被害配偶者救済のためなりとの見地をとつたがために、苟もそこに配偶者の一方を婚姻継続の苦痛から救つてやる必要さへあるならば、その必要が果して相手方の過責によつて生じたか、無責の原因に基いたかの点は問題とせず、広く離婚の権を、婚姻の継続を苦痛とする配偶者に与へてやらうとしたものであつたのである。いひかへれば加害配偶者制裁の見地から離婚の原因を規定する主義をすてて、反対に被害配偶者救済の見地からこれを規定する主義へ一転した結果、広く加害者の重大過責によつて不幸に落ちた配偶者と、偶発事情に基いて不幸に落ちた配偶者とを一様に見て、これらの者に平等に離婚の権を与へてやることになつてしまつたのである。この事たる、まことに離婚法史の一大飛躍であつた。なぜならば従前の離婚原因はみな過責行為の範囲内に跼蹐してゐたのに、今やプロシヤ州法は勇敢にもこの埒外に飛出たからであ(三)る(四)。
一 Preuss, Ldr. II, 1, 670 fg.
二 Preuss, Ldr. II, 1, 697 fg.
三 新教徒が有責主義の埒内に止まつたのは、一はSchmalkadische Artikelの文句に煩されたからでもあつた。同書の附録文は、新教徒が敢然として離婚を肯定した最初の宣言書ではあつたが、それには『無責配偶者再婚の禁は非なり』といひ、暗に離婚を相手方過失の場合に限るべき旨を洩らしたので、これが永く後世の累となつたのであつた(前出参照)。
四 例外として無責離婚原因を認めた神学者もないではなかつた。Zwingli派の人々は精神病および不治の疾病も離婚原因となるといひ(Richter, S. 11)、十六世紀の学者Butzer(1491--1551)も精神病および不治の疾病が離婚原因となると論じたといふ(Richter, S. 34 fg.)。
その後多少の反動は来た。反動なしに聖書主義が歴史から消えるといふことは不可能事に属したのである。例へば一八二五年には、Friedrich Wilhelm IIIが『宗教および道徳の原則を顧慮して』(in Rücksicht des religiösen und sittlichen Prinzips)、他日州法の離婚原因を修正し、無責離婚原因を排斥するに至るであらう旨を宣示した。一八四四年には次王Friedrich Wilhelm IVが、かの歴史法学の巨頭にして当時プロシヤ司法大臣の要職にも就いてゐたSavignyをして、無責離婚原因を排除する趣旨においての離婚法修正案を起草させた(一)。五四年には、司法大臣Simonsをして、やはり無責離婚原因を排斥する趣旨においての修正案を起草させ、今度はこれをプロシヤ議会に提議させた。しかしSavigny案もSimons案も共に法律とはならなかつた。一八五九年にも離婚法改正の議があつたが、その際にはプロシヤ州法上の無責離婚原因の規定を廃止せず、むしろこれをそのまま存置するを可とする旨の決議案が、プロシヤ議会を通過した位であつた。
かやうにプロシヤ州法上の無責離婚原因の制定が論議の中心テーマとなつてゐた間に、皮肉にもプロシヤ州法に倣つて無責離婚原因を認める立法が続々と増加して行つた。一八〇三年十一月二十五日のニュルンベルグ離婚法・一八〇九年二月三日のバーデン州法・一八三四年八月十五日のゴータ婚姻法・一八六三年一月二日のザクセン民法等みなプロシヤに倣つて無責離婚原因を設けたのである。
以上われわれは十六世紀以後における離婚原因の拡大史を総説したので、これから分析叙述に入り、箇々の離婚原因規定を各別に取扱ふと共に、考察の中心を現代に移し、いかに現代の離婚原因法が変転しつつあるかの大要をも示すこととしよう。
一 Savigny, Darstellung der in den preussischen Gesetzen über die Ehescheidung unternommenen Reform, 1844(in den vermischten Schriften Bd. V.)S. 222 fg.
三 配偶者に対する直接侵害
* 立法例上、離婚原因は多々あるが、私はこれを(一)過責離婚原因と(二)無責離婚原因とに大別する。不具・精神病その他の疾病・失踪等は、無責離婚原因である。過責離婚原因はこれを(イ)配偶者に対する直接侵害と(ロ)やはり配偶者に対する間接侵害とに小別する。被告自身の不道徳な行状・子又は第三者に対する侮辱・虐待・犯行等々は配偶者に対する間接侵害である。その他は姦通でも遺棄でも、虐待・侮辱でも、みな配偶者に対する直接侵害の観念に入る——私はこの分類型式をBergmannがRechtsvergleichendes Handwörterbuchにおいて現代諸国の離婚原因を分類するために用ゐた分類形式から学び取つた(Art. Ehescheidung u. Ehetrennung, Rechtsvergl. Handwörterb. Bd. II, S. 716 fg.)。
先づ姦通を見ると姦通とは配偶者以外の者と通ずることをいふ。その相手方が、有夫の婦なるや否やは問はない。
この意義の姦通は、ローマ教会では永久別居の原因であり、Luther以後は離婚の原因となつた。離婚原因性の認定に関しては、学説かなり相岐れたが、姦通を離婚原因と見ぬ学者はなかつた。
もちろん教会は性的忠実の義務を重んじ、夫婦に平等にこれを命じたので、妻の姦通が離婚の原因となつたごとく、夫の姦通も離婚の原因となつた(一)。新教の中では殊にCalvin派が、夫の貞操義務を強調した(二)。しかしゲルマン固有の観念は、妻にのみ貞操を強ひ、夫にはこれを強ひなかつた(三)ので、近世に至つて反動的に固有法の復活あり、仏民のごとき妻の姦通は直ちに離婚の原因となるが、夫のそれは情状特に重き場合、即ち夫がその情婦を夫婦の共同住所に連込んだ場合にかぎり、離婚の原因となるに過ぎぬと見たが、今は仏法もこの不平等を除去した(四)。ベルギ−・スペイン等は今も改正以前の仏法的不平等を留めてゐる(五)。わが国も不平等主義をとつてゐる(八一三条二号・三号)。ドイツ法は、プロシヤ州法の当時から平等主義をとり(六)、民法も平等主義をとつた。
一 Innoc. I ad Exsup. c. 4---Scheurl, S. 261 fg.
二 Marianne Weber, Ehefrau u. Mutter in der Rechtsentwicklung, S. 287.
三 Bartsch, Rechtsstellung der Frau als Gattin u. Mutter, S. 90.
四 拙著・婚姻法の近代化一五九頁。
五 Belg, C. c. 230---Spanien, C. c. 150 Nr. 1.
六 Preuss. Ldr. II, 1, 670 fg.---nürnb. Ehescheidungsordn. Nr. 8---goth. Eheg. 75 fg.---altenb. Eheordn. 195 fg.---sächs GB. 1713 fg.
未遂姦も離婚の原因となりえたかといふに、一八五五年のツェレ裁判所(O.A.G.)の判決(一)・一八五三年のダルムスタット裁判所(O.A.G.)の判決(二)・一八七九年のベルリン裁判所(O.T.)の判決(三)は、未遂姦もまた離婚の原因となり得ると見たが、一八五六年のローストック裁判所(O.A.G.)の判決(四)・一八五九年のオルデンブルグ裁判所(O.A.G.)の判決(五)は、反対に未遂姦は離婚の原因にならないと見た。ザクセン民法も未遂姦は離婚の原因にならないと見た(六)。ドイツ帝国裁判所の判例も離婚原因としての姦通は既遂たることを要すとしてゐる(七)。
一 Seufferts Archiv, Bd. XII, Nr. 38.
二 Seufferts Archiv, Bd. XXV, Nr. 31.
三 Seufferts Archiv, Bd. XXXV, Nr. 132.
四 Seufferts Archiv, Bd. XIII, Nr. 147.
五 Seufferts Archiv, Bd. XVIII, Nr. 145.
六 Sächs GB. 1715.
七 RG. Bd. XXVIII, Nr. 47.
夫婦双方がそれぞれ姦通した場合はいかんといふに、一八四八年のドレスデン裁判所(O.A.G.)の判決(一)・一八六一年のローストック裁判所(O.A.G.)の判決(二)等々は、いはゆる相殺主義(Kompensationsprinzip)をとり、原告自身に姦通の事実あれば、被告の姦通に基いて取得した離婚権を喪失するに至るべきものとなし、プロシヤ・ザクセン等の民法もこれに倣つて相殺主義をとつた(三)。しかし今日は、一方の姦通によつて惹起された夫婦関係の破綻は、他方の姦通によつて増しこそすれ減じはせぬとの理由から、相殺主義を捨てた(四)。すなはち今では夫婦双方姦通の場合には、互に離婚権を取得し、互に他を離婚することができるのである。
一 Seufferts Archiv, Bd. II, Nr. 194.
二 Seufferts Archiv, Bd. XVII, Nr. 54.
三 Preuss. Ldr. II, 1, 670 fg.---sächs GB. 17 fg.---altenb. Eheordn. 200 C.
四 BGB. 1574.
重婚は夙に刑法上の犯罪となつてゐたから、重婚を理由とする離婚判決は、刑事訴訟に附帯して下された。すなはちそれは教会法上の離婚原因でなくして、国法上の離婚原因であつたのである。近代の法典の中でも、重婚を独立の離婚原因とするものはむしろ少い。多くは姦通の一種と見てゐる(一)。
一 十九世紀の立法中、重婚を独立の離婚原因と見たのは、sächs GB. 1728だけであつた。今ではBGB. 1565; Griechenl. Eheg. v. 24/6 1920 2; Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 58; Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 47---わが民法もまた重婚を独立の離婚原因と見る(八一三条一号)。
不自然性行は、一八八三年のブラウンシワイグ裁判所(O.L.G.)の判決(一)が、離婚の原因になると見た。国法としてはプロシヤ・ザクセン等の民法がこれを独立の離婚原因となし(二)、今ではドイツおよびスカンヂナビヤの立法がこれを独立の離婚原因と見てゐる(三)。
一 Seufferts Archiv, Bd. XLIII, Nr. 25.
二 Preuss. Ldr. II, 1, 672---nürnb. Ehescheidungsordn. 12---goth. Eheg. 76---altenb. Eheordn. 205.---sächs GB. 1728.
三 BGB. 1565---Schweden, 8---Norwegen, 48---Dänemark, 59.
次に遺棄を見ると遺棄とは正当の理由なき同居の廃棄、すなはち理由もないのに、若くは夫婦間の合意もないのに、自ら家出し若くは他方を追出すことをいつた。理由あつて家出した場合には、その家出の理由が消滅した時から遺棄となるとしてゐた。
この意味の遺棄はLutherがその晩年に、離婚原因として承認したところに係る。彼は初め姦通のみを離婚の原因としてゐたが、後に遺棄もまた離婚原因になると見るやうになつたのである。その際コリント前書第七章第十五節『不信者自ら離れ去らば、その離るるに任せよ』の句が、根拠として彼に役立つたといふことは既述した。
又Lutherの門弟Bugenhagenが、遺棄者の居所分明の場合には離婚判決に先ち、一応帰還命令(Rückkehrbefehl)を発することを要すと説き、これが当時の実務に影響したといふこともすでに述べたが、十九世紀に入つてからも、裁判所はこの古例を守つてゐたのであつて、一八四九年のドレスデン裁判所(O.A.G.)の判決(一)・一八五二年のウィスバーデン裁判所(O.A.G.)の判例(二)等、みな帰還命令を離婚判決の先行条件と見てゐる。国法においてはプロシヤ州法を初め、概ね同一主義をとつた(三)。今日においてもドイツ民法は、遺棄者の居所分明の場合には、先づ同居回復の命令を発すべきものとしてゐるのである(四)。レットランドのごとき新興国、日本・ギリシャのごとき無伝統国には、帰還命令の規定がない(五)。遺棄一定の期間に満つれば、遺棄者の居所分明の場合にも、直ちに離婚を請求しうる(六)。
一 Seufferts Archiv, Bd. III, Nr. 67.
二 Seufferts Archiv, Bd. XIII, Nr. 36.
三 Preuss. Ldr. II, 1, 679 fg.---altenb. Eheordn. 208 fg.---sächs GB. 1731---goth. Eheg. 101, 109.
四 BGB. 1567---ZGB. 140---Tschechoslowakei, G. v. 25/5 1919 13c.
五 Lettl. Eheg. v. 1/2 1921 44---Griechenl. Ehescheidungsg. v. 24/6 1920 4---Niederl. BWB. 266.
六 わが民法は遺棄期間を定めない。悪意の遺棄を直ちに離婚の原因とする(八一三条六号)。
頑固な性交拒否(hartnäckige Verweigerung der ehelichen Pflicht)は、Lutherはこれを遺棄の観念に入れ、Bugenhagen以後は準遺棄の一場合と見て来たが、十九世紀に入つてから、独立の離婚原因となつた。プロシヤ・ザクセン等の民法は性交拒否を独立の離婚原因と見たのである(一)。しかし今は昔に還り、これを遺棄又は侮辱の一場合と見る。
一 Preuss. Ldr. II, 1, 694---nürnb. Ehescheidungsordn. 28---altenb. Eheordn. 217---sächs GB. 1731.
扶養の拒否は新教会では遺棄又は準遺棄の一場合として来たが、プロシヤ州法はこれを独立の離婚原因と見た。今ではエストランド法がさう見てゐる(一)。
一 Preuss. Ldr. II, 1, 713---Estland, G. v. 27/10 1922 28 Nr. 5.
次に殺害の企図を見ると、殺害企図とは配偶者を殺害せんとする予備・陰謀・着手・未遂等をいふ。初めてこれを離婚の原因としたのはMelanchtonで、その際ローマの離婚原因法が、彼に、淵源して役立つたといふことはすでに述べた。十六世紀中には、Melanchtonの亜流だけがこの見解に賛してゐたが、十七世紀以後新教徒一般の承認を獲得した。
十九世紀に入つてからは、ドイツ内の諸立法は、みな殺害企図を独立の原因とした(一)。今ではドイツ・スヰスばかりでなく、スカンヂナビヤ諸国もこれを独立の離婚原因としてゐる(二)。わが国は仏法に倣ひ、これを重大侮辱(injure grave)の一種と見る。
一 Preuss. Ldr. II, 1, 699---nürnb. Ehescheidungsordn. 25---goth. Eheg. 97, 102---sächs GB. 1735.
二 BGB. 1566---ZGB. 13---Tschechoslowakei. G. v. 25/5 1919 13a---Griechenl. G. v. 24/6 1920 3---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 XI. Kap. 10---Norwegen, Eheg. 18/5 1918 50---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 61.
虐待を離婚の原因と見たのも、最初はMelanchton一派だけだつたが、十七世紀頃から全新教徒がこれを離婚の原因と見るやうになつた。十九世紀のドイツ諸立法もこれを独立の原因としたのである(一)。尤も当時の虐待は意味狭く、『相手方の生命又は健康を危険ならしめる身体侵害』のみをいつてゐたが、今は『相手方をして婚姻的生活共同の意思(Wille zur ehelichen Lebensgemeinschaft)を喪失せしむべき身体侵害』を広く虐待といふ。故に相手の地位や教養が高き場合には、すゐぶん些細な身体侵害でもなほかつ虐待となるのであつて、現にドイツの判例は、相手が伯爵夫人であつたといふ関係から、夫伯爵の為した一回の面打を虐待と見、これを離婚の原因にさせた。地位教養高き相手方は、些細な侵害をも強く感じ、これによつて婚姻的生活共同意思を喪失するに至るのが常であるからである(二)。
一 Preuss. Ldr. II, 1, 699---nürnb. Ehescheidungsordn. 25---goth. Eheg. 97 fg.---sächs GB. 1735 fg.
二 Rosenberg, Ehescheidung u. Eheanfechtung(1926)S. 3 u. 12---Vgl. auch C. c. 231; ZGB. 138---Niederl. BWB. 264 Nr. 4; Schweden, Eheg. II Kap. 10.
侮辱は、十八世紀の王許離婚法によつて初めて離婚の原因とされた。その起源はつまり教会法的でなくて、国法的であるのである。十九世紀に入ると、仏法もドイツ諸法も共にこれを独立の離婚原因とした(一)。今では凡そ相手方をして婚姻的生活共同の意思を喪失させるほどの軽蔑意思の表現ならば、みな侮辱となるのである(二)。
一 C. c. 231---ZGB. 138---preuss. Ldr. II, 1, 706 fg.---nürnb. Ehescheidungsordn. 25---goth. Eheg. 96.
二 Rosenberg, S. 3 u. 12.
誣告とは、配偶者の犯罪につき故意に虚偽の申告をなすことをいふ。初めは重大侮辱の一種であつたが、十九世紀中、これを独立の離婚原因と見る例も生じた(一)。今は昔に還り、これを侮辱の一種と見る。
一 Preuss. Ldr. II, 1, 705---nürnb. Ehescheidungsordn. 25---goth. Eheg. 123.
以上の外、種々の直接侵害行為が離婚の原因となる。エストランド法は、夫婦の一方が他方の自由を侵害したことを離婚の原因となし(一)、ブルガリア法は他方の精神的自由ことに信教の自由を制限したことを離婚の原因とする(二)。ポルトガルやスカンヂナビヤでは、他方へ性病を伝染させたことを離婚の原因とする(三)。
一 Estl. G. v. 27/10 1922 28 Nr. 5.
二 Burgarien, Exarchatordn. v. 1883 187.
三 Schweden, Eheg. II Kap. 9---Norwegen, Eheg. 49---Dänemark, Eheg. 60---Portugal, Dekret v. 3/11 10 Nr. 10.
独立の離婚原因を次々に増加せしめつつある間に、人はおのづから離婚原因の一般化の可能に気づく。たとへばHülsemannは十七世紀における新教会の代表的神学者であつたが、姦通および遺棄を離婚の原因と見ると同時に、これらと同等以上の過責も一般的に離婚の原因となると断じた(一)。Savignyも、プロシヤの司法大臣として州法の離婚規定の修正を策した際、姦通および遺棄ばかりでなく、これらと同等以上に婚姻関係を破壊すべき一切の過責行為も離婚の原因となると定めようと企図した(二)。立法においては、一八三七年五月十三日のAltenburg婚姻令が、その一九四条において、いはゆる一般条項(clausula generalis)を設け、列挙の離婚原因と同程度に婚姻の目的を妨害すべき諸事情が、裁判官の裁量によつて離婚原因となりうるものと規定した。すなはちAltenburg法における箇々原因の列挙は、離婚原因の例示であつて、その限定ではなかつたのである。列挙のどれに該当しなくても、婚姻目的を著しく妨害する行為ならば離婚原因となつたのである。
この規定型式は、非常に影響的であつた。ドイツ民法はこれに倣つて姦通以下数箇の離婚原因を例示すると同時に、凡そ相手方の過責のみによりて婚姻関係を甚しく破壊された場合には、それを原因として離婚請求をなすことができると定めたのである(三)。いはゆる婚姻関係の甚しき破壊とは、侵害の結果被害配偶者が加害配偶者と婚姻的生活共同をなすの意思を喪失するに至つた状態をいふ(四)。けだし婚姻的生活共同(eheliche Lebensgemeinschaft)は、夫婦関係の中枢であり、その基底である(五)。この基本関係を維持するの意思を喪失せしめられたとせば、被害者はこれを理由に加害者を離婚できねばならぬ筈と見るのである。ドイツの判例は、かなり軽微な侵害をも婚姻破壊的と見る——例へば、家計の不しだら・財産管理上の不注意・扶養の過怠。スヰス・ギリシャ・チェッコスロバキア・レットランド等もドイツ民法に倣つて、一般的に婚姻破壊的侵害行為を離婚原因と見る(六)。
一 Realencyklopädie f. protestantische Theologie u. Kirche, Bd. XXI, S. 872.
二 Savigny, in den vermischten Schriften Bd. V, S. 222 fg.---穂積・離婚制度の研究八六九頁以下。
三 BGB. 1568---夫婦の一方が他方の侵害行為を誘発した場合、例へば夫の虐待行為の前に妻の侮辱的態度あり、後者が前者の原因をなしたやうな場合には、妻は夫の虐待を理由として離婚をなすわけに行かない(Rosenberg, S. 12 fg.)。
四 Rosenberg, S. 12
五 拙著・婚姻立法における二主義の抗争二六三頁以下。
六 ZGB. 142---Griechenl. G. v. 24/6 1920 5---Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1919 13h---Lettl. G. v. 1/2 1921 45.
四 配偶者に対する間接侵害
夫婦の一方が婚姻的生活共同の意思を喪失するのは、他方から直接に侵害を受けた場合だけに限らない、間接に侵害を受けた場合にも、これを喪失するに至る。例へば夫婦の一方が他方の親族を侮辱し、他方の子を虐待し、共同の子の教育を怠り、娘に性業を勧めたりなどしたとすると、行為の直接対象は子又は親族であるが、配偶者の他方も間接に苦痛を感じ、婚姻的生活共同の意思を喪失するに至るであらう。又一方が下賎な職業を営み、酒に溺れ、賭博に耽つたりなどしたとすると、行為自体は本人自身の品位を傷けるだけだが、間接にはやはり配偶者をも苦しめ、彼をして生活共同の意思を喪失させるに至るであらう。故に間接侵害の行為をも離婚の原因たらしめる必要がある。以下まづ箇々の間接侵害についてのべ次に間接侵害一般についてのべることとすると——
相手方の受刑は、十七・八世紀の頃から離婚の原因となつたが、これは永年の受刑を以て一種の遺棄と見做した上のことであつた。その身獄舎に繋がるるは、故意に配偶者を遺棄したも同然だとの見地から受刑者を遺棄者と同様に取扱つたのである。その後受刑そのものを独立の離婚原因と見るやうになり、国法も、何年以上の懲役は離婚の原因になるとか、何罪による何年以上の懲役は離婚の原因になるとか定めた。十九世紀後の立法は概ねかやうな定め方をしてゐたのである(一)。
しかし近時の立法は、刑罰よりも犯罪を離婚の原因と見る。破廉恥の動機から夫婦の一方が犯罪を犯した場合には、刑の有無・刑期の長短に論なく、他方は離婚をなすことができると見る(二)。夫婦の一方が犯罪を犯した場合には、これに因る刑の有無を問はず、他方は苦痛を感じ、生活共同の意思を喪失するに至るが常であるからである。
一 Preuss. Ldr. II, 1, 704 fg.---sächs GB. 1740---C. c. 232---Belgien, C. c. 232---ZGB. 136---Schweden, Eheg. Kap. 11---Norwegen, Eheg. 51---Dänemark, Eheg. 62.
二 BGB. 1568; Vgl. Rosenberg, S. 10.
刑罰又は犯罪の外に、種々の間接侵害行為が離婚の原因となる。例へばプロシヤ州法は、夫婦の一方が下賎な職業をなすならば、他方は離婚できるとした(一)。同法は又、夫婦の一方が暴酒癖若くは浪費癖を有した場合にも、他方は離婚できるとした(二)。ポルトガル法は賭博癖を離婚原因とする(三)。娘に対する性業勧誘を離婚の原因とする国もある(四)。
一 Preuss. Ldr. II, 1, 707; nürnb. Ehescheidungsordn. 38.
二 Preuss. Ldr. II, 1, 708 fg.---nürnb. 36---goth. Eheg. 124---sächs GB. 1733.
三 Portugal, Dekret v. 31/1 1910 4 Nr. 9.
四 Rechtsvergleichendes Handwörterb. II. S. 718
ドイツ民法は婚姻破壊的な直接侵害行為一般を離婚の原因としたやうに、婚姻破壊的な間接侵害行為一般をも離婚の原因とした(一)。苟くも相手方をして婚姻的生活共同の意思を喪失させるやうな間接侵害ならば、行為の種名のいかんを問はず、それを以て離婚の原因となすことができるとしたのである。例を判例に求めると、常習的飲酒はこれによつて家計を乱されざる場合にも離婚の原因となる。下賎な職業例へば淫売宿の経営・密輸入業・常習犯罪等も離婚の原因となる。不謹慎なる異性との社交も離婚の原因となり、継子いぢめも離婚の原因となる(二)。
一 BGB. 1568.
二 Rosenberg, S. 9 fg.
五 偶発の事情
プロシヤの州法が無責の離婚原因を認め、精神病その他を離婚の原因としたといふこと、及びこれに対しては種々の反対的修正論も出たが結局この主義が維持されたといふことを前述したが、現代法も精神病その他の偶然の事情を、やはり離婚の原因と見つつあるのである。
ドイツ民法は全治の見込なき精神病を離婚の原因としてゐる(一)スヰス・スヱーデン・ノオルウェー・デンマーク等も全治の見込なき精神病を離婚原因と定めてゐる(二)。チェッコスロバキア・エストランド・レットランド等の新興国も同様の定めをなしてゐる(三)。
一 BGB. 1569.
二 ZGB. 141---Schweden, Eheg. 11 Kap. 13---Noeregen, Eheg. 53---Dänemark, Eheg. 63.
三 Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1915 13 fg.---Estl. G. v. 1/5 1923 26---Lettl. G. v. 1/2 1921 45.
プロシヤ州法は結婚後生じた不治の性交不能症と嫌忌せらるべき不具とを離婚の原因に数へてゐたが、ドイツ民法はこれらを離婚の原因とすることを罷めた。すなはち今のドイツでは、精神病だけが無責の離婚原因となつてゐるのである。しかし他の国にはプロシヤ主義復興の形勢が見える。例へばレットランドおよびギリシャは、結婚後生じた不治の性交不能性を離婚原因にした(一)。レットランドおよびエストランドは、著しく嫌忌せらるべき疾病を離婚の原因にした(二)。エストランドは又性病そのものを、離婚の原因とした(三)。
一 Lettl. G. v. 1/2 1921 47b---Griechenl. G. v. 24/6 1920 8.
二 Lettl. 45---Estl. G. v. 1/5 1923 26.
三 Estl. 26 Nr. 2.
プロシヤ州法は『和合の見込なきまでに強烈な相手方嫌厭の情』を離婚の一原因に数へた(一)。フランスでも大革命の際——一七九二年九月二十日の法律で——嫌厭が離婚請求の原因となる旨定めたことがあつたが、今ではどこの国でも嫌厭そのものは離婚の原因とならず、単に嫌厭を生ぜしめる相手方の過責行為が離婚の原因となるのみと見る。しかしオーストリーやチェックでは非クリスト教徒に対し嫌厭を理由にする離婚を許してゐる(二)。
一 Preuss, Ldr. II, 1, 718a---嫌厭を理由にする離婚と恣意離婚とを混同すべからざることについては、拙著・婚姻法の近代化一八三註1)。
二 ABGB. 115---Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1919 13i.
過責主義に執着した従来の立法は失踪を離婚の原因としてゐなかつたが、近時の立法はこれを独立の無責離婚原因とし、夫婦の一方が一定の期間生死不明となつた場合には、他方はこれを理由に、離婚請求を起すことができると見る。ノオルウェー・デンマーク・ポルトガル等のごとし(一)。わが民法また然り(八一三条九号)。
一 Norwegen, Eheg. 46---Dänemark, Eheg. 57---Portugal, Dekret v. 3/11 1910 4. Nr. 6.
六 結 言
十六世紀は近世資本主義の発芽期であり、各方面に中世的拘束を脱却しようとする気分の大いに動き出した時代であつたが、性の自由を欲求する思想もこの世紀において初めて芽を吹き、中世的鉄則の一たる離婚禁止の主義を遂に揚棄することになつた。Luther等宗教改革者の手によつて離婚の扉は始めて開かれるやうになつたのである。が、元来宗教改革は聖書を『神の言葉』と見、絶対の権威と仰がうとする趣旨のものであつたから、宗教改革者達の立論はとかく聖書に拘泥し、その外に出ることを妨げたのであつた。離婚の原因についても、Lutherらは聖書の規定に拘泥し、聖書が明かに離婚の原因と見てゐた二つのもの、即ち姦通と遺棄だけに限つたのであつた。Calvinの離婚論もほぼLutherに近かつた。しかしMelanchtonは、これに反して非常に自由な態度に出で、姦通と遺棄ばかりでなく、虐待および殺害の企図もまた離婚の原因になると説いたが、これはMelanchtonが、聖書と同時にローマ法をも淵源として使用し、殊にローマ法の中でも離婚にかなり寛大だつたTheodosius IIの離婚原因法を淵源として使用した結果であつた。
その後新教会の内部には、Lutherを祖述して聖書のみを淵源にとり、姦通と遺棄だけを離婚の原因と見ようとする厳格派と、Melanchtonの流を汲んでローマ法をも淵源にとり、虐待および殺害企図にも原因性を認めんとする寛大派と、両々対峠の姿勢を続けたが、概言すると、北ドイツに活動した神学者たちは厳格説に与みし、南ドイツの諸都市に活動した神学者たちは寛大説に加担したのであつて、これは南ドイツが北ドイツに比してより濃厚にローマ法の感化を受け来つた関係上、ローマ法的離婚論を受納し易かつたためと、もつと究極的には、当時の南独諸都市がクリスト教国中の最富区にして、早期資本主義的繁栄を呈し、思想も開発的にして性的自由を貴ぶ風の強かつたためとに他ならなかつた。
その後聖書的厳格主義とローマ的寛大主義とは漸次に対立を失ひ、遂に十八世紀において、統一的新教会法の完成となつたが、その間に離婚原因の範囲は逐年膨脹し、(一)姦通(二)遺棄(三)虐待(四)殺害企図等はもちろん、(五)性交拒否(六)性交不能(七)終身懲役(八)扶養拒否等々も離婚原因になると見られるまでになつてゐたのである。しかしこれは教会的立場から認められうる離婚原因の殆んど全部を挙げ尽した結果としてであり、従つてこれ以上の拡張を行ふためには、勢ひ教会的立場そのものを棄てて別の立場に立たねばならぬ必要があつた。見地の更新を行はざるかぎり、離婚原因の拡大はもはや不可能となりつつあつたのである。
自然法学は人類の文化を聖書の勢力から解放させようとした運動であつた。単にローマ教会へのプロテストでなくして、聖書そのものへのプロテストであつた。この運動を越えてから歴史は初めて『近代』へと入つたのである。『神学の勢力を脱して自然と理性とを基礎にする新時代』へと進んだのである。離婚法も自然法の運動を転機にして、初めて旧き神学的色彩から離脱した。
神学的離婚法から自然法的離婚法への橋梁が、かの王許離婚法ではなかつたらうか?王は一方において新教会の離婚法をそのまま是認すると同時に、他方において自分自身また離婚特許の法源として立現はれたのである。さうして専ら衡平の見地から、頗る寛容に離婚の特許を与へたのである。教会法上離婚の許し難き場合にも、王は特許の作用によつて離婚を許した。王許離婚こそは教会離婚法の欠陥を補ふ補助法源であり、教会離婚法の厳酷を緩和する衡平法ではあつたのであつた。
プロシヤの州法は近世統一法典の魁であり、自然法学の結晶であつただけに、その離婚原因規定は革命的に嶄新であつた。すなはち同法は十六世紀以来認められ来つた離婚原因の全部を法認し、思ひ切つて過責離婚原因の数を殖やすと同時に、新たに無責の離婚原因をも定めたのである。精神病のごとき無責偶発の不幸が離婚の原因となると定めたのである。
現代の法律はプロシヤの先例に倣つて無責離婚原因を認めつつある。過責離婚の原因をも極度に増加しつつある。今では姦通・遺棄・虐待等の重大な非行が離婚の原因となるだけでない。家計の不しだら・財産管理の不注意・扶養の過怠のごとき比較的軽微な非行も離婚の原因となるのである。配偶者に対する直接の侵害ばかりが離婚の原因となるのではない。間接の侵害、すなはち直接には行為者自身を害し、又は第三者を害するに過ざるごとき非行も亦離婚の原因となるのである。下賎な職業・暴飲・賭博・不謹慎な社交は、直接には行為者自身を害するに止まる。しかし離婚の原因となる。犯罪・継子いぢめ・娘に対する性業勧誘は直接には子又は第三者を害するに止まる。しかし離婚の原因となる。
離婚原因の無限の膨脹は、必然的に離婚原因の規定技術そのものにも変化を与へた。今の立法は箇々の直接侵害行為を離婚原因として列挙することをせぬのである。原則的に凡そ相手方をして婚姻的生活共同の意思を喪失させる直接侵害行為ならば、みな離婚原因になると定めるのである。さらに又箇々の間接侵害行為を列挙することをもしないのである。凡そ相手方をして婚姻的生活共同の意思を喪失させる間接侵害行為ならば、みな離婚原因になると定めるのである。
資本主義の発生が性に関するヨーロッパ人の思想を自由にさせ、婚姻観を一変させ、離婚を否定する主義からそれを肯定する主義へと一転させた。資本主義の発展が性的自由の思想を爛熟させ、離婚の原因をいよいよ拡大させた。離婚原因拡大史の背後には性的自由の思想史があり、性的自由の思想史の背後には資本主義の発展史があるのである。