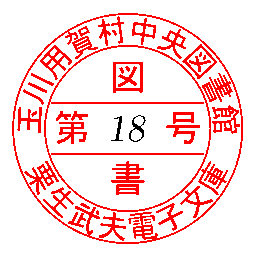
解釈法学とはどんな性質の学問かに関しては、他の学問の性質論においてもさうであらうやうに、すいぶん物々しい・厳めしい・そのくせ相互に一致はせぬ沢山の定義を見る。例へばケルゼンはいふ、『解釈法学とは、立法者によつて現実に定立された実定法の内容を純粋に、すなはち政治的考慮等から全くはなれて、把握し整序することを以て任とする規範科学である』1)と。ラスクはいふ、『解釈法学とは、現実に通用してゐる実定法の内容を組織的に把握せんとする組織化的文化科学(systematisierende Kulturwissenschaftである』2)と。マックス・ウェーバーはいふ、『解釈法学とは、その対象とする実定法において、正当な妥当な意味を研究しようとする理義的科学(dogmatische Wissenschaft)である』3)と。
1) Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und Rechtspositivismus. 1928
2) Lask, Rechtsphilosophie. In der Festschrift für, Kuno Fischer 2. Aufl. 269, 298.
3) Max Weber, Wirtschaft u. Gesellschaft, Grundriss der Sozialökonomik III. Abt. 2. Aufl. 2.
これらの諸説は、いづれ劣らぬ鋭利な頭脳が、深い省察の力をはたらかせて把握した・まことに洞見に満ちたものではあらうが、どうも私たちにはこの種の定義が、よくいつてあまりに論理的、わるくいふと殆ど空虚的にしか響かぬのである。このやうな定義は、定義せらるる対象の現実姿態を半分以上見落してをりはせぬかとおもはれるばかりであるのである。ちやうど蒸溜水でも飲まされたときのやうで、純粋ではあるが、生きた甘味を抜きとられてゐるといつた感じである。私たちはもつと生まな・荒つぽい解釈法学の姿に接したい。隠蔽されないその素顔を眺めたい。できることなら解釈法学の社会的性質を指摘し、その存在被拘束性を曝露してくれたやうな定義を望む——では『汝みづからそのやうな定義を作れ』、といはれたところで、今のわたくしにそれのできやう道理もないが、しかし解釈法学の性質についてこの頃切に感じてゐるところのものを正直に披瀝することだけは許される筈だ。それによると——
『解釈法学は神学である』
○
一体にある学問が、どんな性格を担つてゐるかは、その学問における仕事の運転方法そのものを客観的に見て決せらるべきである。学者が、その従事するところの学問の性質について宣言した言葉は、さすがにそのなかに貴重な体験素を含ませてゐる場合のあると同時に、すいぶん独りよがりの偏見も混入させてゐるものなので、あまり過大な標準力を与へるわけにゆかぬのである。人の性格は彼の日常行為を見て決せらるべく、学問の性格は、彼の作業の実際を見て決せらるべし。おれは健康だと自称する人を医学上健康人のなかへ入れる必要のないごとく、おれは文化科学だ・おれは規範学だと自称するところの学問をも、必ずしもその自称部類へ所属させる必要はないのである。だから解釈法学の性質を決めようとする場合にも、われわれは、斯学の作業歩程そのものを基準に取らなければならないが、わたくしがいま、わたくしの机上に立並ぶ民法・刑法・訴訟法等の註釈書なり教本なりを取出して任意のページを開き、そこに展開されてゐる知的作業の跡を点検するに、何とまァそれらが、無方針・無秩序・無貞操であることよ!!!
○
例へば手近かなある註釈書の註釈ぶりを検してみると、それは法典のある一ケ条を註していつてゐる——『条文にaとあるが故に、aたるべきこと炳として明らかなり』と。しかし次条の註を見るとそれはいつてゐる——『条文にはbとあれども、他条との関係上b'の意味ならざるべからず』と。その次の註ではいつてゐる——『条文にはcとあれども、立法の理由より見てc''の意ならざるべからず』と。前の場合には他条との聯関を重んじ、後の場合には立法の理由を貴んでゐるのである。その又次の註を見るといつてゐる——『条文にはdとあれども、沿革上本条はd'''の意なり』と。この場合には沿革の前へ条文を屈服させてゐるのである。その他、判例を楯にして条文を曲げてゐる場合もあり、学説を楯にしてさうしてゐる場合もある。外国における最近の立法傾向・新学説の趨向等を理由にしてゐる場合もあり、実際上の不都合の回避を主眼にしてゐる場合もある。『もしこれを文字通りに解せんか、適用の結果として斯く斯くの不都合を生ずべきが故に、法意は文字的意義の外に存すと解せざるべからず』といつた式だ。
○
かやうに解釈法学の駆使する解釈手段は、条文・判例・沿革・立法理由・立法傾向・多数説・新学説・論理・条理・比較法・実際界の需要等々、七つ道具も啻ならざるありさまであるが、なぜかう解釈法学は、大小幾個の道具を、殆ど順序もなく聯絡もなく、使用するのであらうかといへば、察するに解釈法学の内心のどこかに、国家の作り与へた実定法の内容を、できるだけ美しく完全にしたいとの一念の潜んでをればこそだ。
実際、解釈学者は実定法をその研究対象として取上げておきながら、一向これを科学的に解剖しようとはせぬのである。すなはち(一)解釈学は実定法成立の社会的原因を探らうとはせぬ。法律も一の社会的産出物である以上は、ある実定法の成立がいかなる社会的現実態によつて制約されてゐるかを問題となしうるわけであるが、解釈法学は、かかる法律成立の原因などは問はぬのである。(二)又解釈法学は法の社会的機能をも問題にせぬ。法律も一の力であり、社会生活を指導し牽引する作用をも具へてゐるものなる以上、ある実定法が、社会生活の展開へどんな効果を及ぼすかの点をも当然に問題となしうるわけでゐるが、解釈法学は、かかる法の社会的効果をも問はうともせぬのである。(三)いな解釈法学は、実定法の批判すら避けようとしてゐる。ある実定法が、真によく社会生活の成立と発展とに対して寄与的であるか否かを究竟的に考察することは、法理学の任務だとして、法理学の肩上へこれを転嫁してゐるのである。では解釈学は何をするか?いはく、これは支配者の作り与へた実定法の『説明弁士』たらうとする。
○
解釈学は支配者の作り与へた実定法の『説明弁士』だとわたくしはいつた。けだし解釈学者の為すところを見るに、彼はまづ自己を立法者の意思過程のなかへ移入させ、できるだけこれと共鳴共感しようと努めるのである【立法者意思説か法律意思説かは言葉の争に過ぎぬ】。立法者の意思状態を追感(nachfühlen)し、彼の心を以てわが心としようとするのである。彼と同じ立場に立ち、同じ考を押し進め、彼のいはんと欲していはざりしところを補ひいはんとするのである。1)これが弁士的態度以外の何ものであらうか?
だから、解釈家が法の制作者と同じ社会的階級に所属し、同じ社会的立場に立ち、同じ社会的意識を有してゐる場合には、解釈の仕事は、比較的に安易である。彼は制作者の作品において自分自身の法律感情の表現を見出す・これを「われらの法律」(our law)と感じる・その健やかなる成長を心からこひ願ふ。彼は実に積極的な歓喜を感じつつ解釈の仕事をすすめることができるのである。が反対に、彼が法の制作者と、その社会的立場を異にしてゐる場合は悲惨である。この際は、制作者との間に共通の仲間意識を欠き、共通の法律感情を欠き、従つて制作者の作品に対しても外々しい感じしかもちえぬが、しかもなほ解釈家たるかぎり、無理にも自己を実定法の前へ屈服せしめねばならぬからである。不本意ながら、自欺的ながら、喜劇的ながら法律制作者の制作品を、妥当なもの正当なものとして承認せざるをえぬからである。Kraftの言葉をかりていへば、解釈家は、立法者の立てた実証的条規組織(positives Satzungssystem)に対して客観的法性質(objektive Rechtsqualität)を認容することを余儀なくされてゐるのである。実定法を正当法と仮定し、この仮定の下にその解釈作業を進行さすことを余儀なくされてゐるのである。解釈家へは、実定法への反抗はおろか、それへの批判すらも許されてゐない。解釈家が解釈作業の進行中実定法の批評に渉ることをえないのは、映画の弁士が映画の説明中、映画の批評をなすことをえないのと好一対だ。
1) Diltheyいはく——『われわれは他人の身振や言葉や態度から、その他人の内的精神過程を追感(nachfühlen)することができる。かやうに、他人が感性界へ表出した諸記号から、その他人の内心を追感することを理解(Verstehen)といふ。解釈(Auslegung)は理解の一種である。文書を通じて作者の内心を理解することがすなはち解釈であるのである』と(Dilthey, Gesammelte Schriften 7, 205 fg. 216 fg.)。Max Weberもいふ——『理解とは他人の心理過程を追体験(nacherleben)することである。他人の心内に近づけば近づくほど、われらの理解は、明証の度を加へる』と(Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft 2. Aufl. 1, 1 fg.)。法律解釈等における解釈も亦、Dilthey等のいはゆる『理解』の一種なること疑を容れぬとおもふのである。
○
解釈法学者はしかしながら実定法の正当性を仮定するだけではなくて、その円満性・完全性をも独断しなければならぬのである。彼等の信ずるところ、若くは信ずるまねをしてゐるところに従へば、法律は正当であるばかりか完全でもある。その中には不当も不明もなく、遺漏も欠陥もなく、重複も矛盾もない。不備不当は法の表見的汚点に過ぎない・真によく法を解釈すれば法にはさやうな欠点のなきことを知りうるといふのでゐる。解釈学者の仕事は、かかる法の表見的諸欠点の清拭にある。例へばもし法に『不当』あらば、彼等はいはゆる『合理註』を施してこれを合理化さすであらう。法に『不明』あらば、いはゆる『説明註』を加へてこれを明瞭化さすであらう。条文相互の間に『重複』や『矛盾』あらば、一の条文に『縮小解釈』を加へて、その妥当領域を故意に狭め、以て他条との衝突をさけさせるであらう。法に『欠陥』あらば、一の条文に、『拡張解釈』か『類推解釈』かを加へて、その妥当領域を故意に広め、問題の場合をその条文の支配下に包摂させてしまふであらう。しかもこれらの場合に解釈学者は、断じて自分たちが法を変改したとか、創作したとかはいはぬのである。却つて、『学者は存在してゐた法を発見することはできるが、新たに法を創作することはできぬ』などと謙遜的なもののいひ方をするのである。1)解釈の結果、実定法の面目が一変されてしまふことは事実である。乱脈蕪雑な条規の堆積が、秩序あり統一ある雄大精緻の論理的体系に一変してしまふことさへあるのである。が解釈学者にいはせると、解釈は宣言的であつて創造的ではない。解釈の結果と同じ内容のものが、初めから成文条規の底に横つてゐたのを、解釈学者がこれを明るみへ引出したに過ぎぬといひ張るのである。彼等の言草だけきいてゐると、法律は、社会生活のあらゆる葛藤に対する適切な答を、初めから網羅的に用意でもしておいたかの如くである。法律は、どんな力でもその中から抽出す微妙な機械だ。その中から適切な解答を抽出しえぬのは、機械が悪いのでなくて技師が悪いのである・条文の操縦さへ宜しきをうれば、どんな難問だつてそれにより解決される筈だと見てゐるもののごとくである。解釈学者は決して外部から法の修正を試みようとはせぬ、ただ内面から法を完全化させようとするだけである。いはば彼は立法者の室内に入り、室の内側から室の壁穴をつくらふのである。巧妙な化粧術師は素顔が元来美しかつたかの如くに化粧する。解釈家も化粧の跡を留めずに法を化粧するのである。
1) Hellwigはいつた——『成文法や出来上つた慣習法に、欠陥の存することは疑なき事実である。がしかし成文法及慣習法以外に、未だ成文となつてもをらず、慣習ともなつてをらない規範の存することも、これまた疑なき事実である。われらは場合の必要に応じてこの種の法規範を発見しなければならない。しかし発見は初めから存せしものの発見で、存せざりしものの創造ではない。法の創造は許されぬが、法の発見は許される。而して法の発見の結果、欠陥多き成文法や慣習法が、欠陥なき法律秩序となるに至るのである』と(Hellwig, System des deutschen Zulprozessrechts II. 2)。実際、解釈の目的は、欠陥多き成文法や慣習法を変じて、欠陥なき法律秩序たらしめるに在るともいへるのである。
○
要するに解釈法学とは、実定法を内面から美化させ完全化させ円満化させ深遠化させ精密化させ荘厳化させることを以て任とする学問(?)である。ゆゑにこれは『科学』からは、凡そ縁遠いものであらう。科学ならば少くともその対象を、あるがままに記載する筈だ。又その対象がいかにして成立したか、いかなる結果を他の現象へ及ぼすかをも考察する筈だ。しかし解釈法学はそのいづれをもせぬのである。世にもし実定法の姿をありのままに、すなはちその不完全を不完全のままに、卒直に記述する学問あらば、そはともかく学としての資格を具有してゐるといへるであらう。田村博士が提唱された制定法学なる学問は『制定法のありのままなる記述』を課題としてゐるのである。1)又もし実定法成立の社会的原因を尋究する学問あらば、それももちろん科学の名に値ひするであらう。Kraftが考へてゐる法律社会学は、『実定法成立の社会的原因の説明』を課題としてゐるのである2)4)5)。又もし一旦有効に成立した実定法が爾後の社会生活の発展に対していかに作用するであらうかを考究する学問あらば、それももとより科学と称するに足るであらう。Mannheimが、最近考へてゐる法律社会学は、その課題の一として、『実定法の社会的効果の説明』を志ざしてゐるのである。3)しかし在来の解釈法学は、記述もせず、原因もさぐらず、結果をも説かぬのである。それは対象を正直に記述するどころか、むしろ対象を粉飾しようとする。対象(実定法)のもつ諸欠点を隠蔽しようとさへする。それがどうして『科学』でありえようか?
1) 田村・法律学の価値に関する懐疑・一八〇頁。
2) Kraftいふ——『法律社会学は、人類社会における法律制度の存在を説明することをその課題とする。法律社会学は、法律制度の存在を支配する法則の学である』と(Kraft, Rechtssoziologie, in dem Handwörterbuch der Soziologie herausgegeben von Vierkandt, 468)。
3) Mannheimはいふ——『法律社会学は二重の課題をもつ。一はいかにして社会学的現実態のなかから規範が成立するに至るかを論ずる成立論、二は一旦成立した規範が社会生活の爾後の発展に対していかなる逆作用を及ぼすかを論ずる逆作用論である』と(Mannheim, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie 1932, 16)。
4) Kraftは、法律社会学(Rechtssoziologie)はもちろん学として可能であるが、社会学的法律学(soziologische Jurisprudenz)は学として成立不可能であるとは見てゐる。いはく『社会学的法律学なるものは、一の社会に法として通用してゐる規範を、社会学的に説明すること・恰もそのことによつて、解釈法学たらんと欲するもので、まさに方法の誤用である。それは社会学を正当の領域を越えて濫用せるものである』と(Kraft, a. a. O. 468)。
5) 法の解釈に当つて特に社会の規範意識に注意し、なるべく社会規範を国家法のなかに取入れようと試みる学派を社会法学とよぶことがある。この意味の社会学は社会学ではない、単にこれは、社会規範を重要視するといふ点で特色をもつ一種の解釈学そのものに過ぎぬのである。
○
しかし世の中には、解釈法学に近似せる学問(?)もないではない。神学がそれだ。
神学は経典の解釈学である。それはまづ経典の内容の正当性・深遠性・完全性・円満性を独断的に前提し、信仰的に予断し、然るのち解釈作業に取かかる。それは経典の表面に浮在する『不明』を払ひ、『不当』を正し、『重複』や『矛盾』を去り、『浅薄』や『欠陥』を補ひ、簡素な経典の文章を深遠雄大な意味体系に一変させるが、かくのごとき意味体系は、決して神学者のお手製によるのではない・初めから経典自身の内裡に包想されてゐたところのものを明るみへ引出しただけだ、といふのが神学者側のいひ分である。経典を内面から美化させて行かうとするその態度・その方法は、全く解釈法学のそれと同一であるのである。
神学の対象は、教会が有権的に作り与へた経典であり、解釈法学の対象は国家が強制的に押しつけてゐる法典である。両者共にその研究対象を官権から受取り、これを是認し、弁護し、防衛し、糊塗し粉飾するのである。権力者の命令の美化・完全化・荘厳化のためには、両者共に、あらゆる種類の解釈手段を、かなり無秩序無貞操に使用するのである。両者共に『権力への忠貞な侍女』なのである。ゆゑにもし経典の解釈が神学ならば、法典の解釈も神学である。経典の解釈家が牧師ならば、法典の解釈家も牧師である。
附記 神学そのものの性質については、別の拙論『法律解釈学の神学性はいかにして始つたか』(法学志林・三四巻九号一〇号一一号)において論じておいた。同論文は、解釈法学がいつ頃・どんな事情から神学的性質を取るに至つたかの史的過程の叙述にも触れてゐる。わたくしは、この読者が右の別論文をも併読せられんことを御願する。