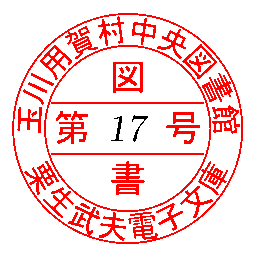
婚姻法は異性法である。異性獲得の方法を規定した法律である。確実に『なんぢの男性』を獲得し、『なんぢの女性』を獲得する・その方法を、規定した法律である。
法律は、ことに私法は、一定の行為を命ずるといふよりも、一定の方法を指示するといつた方が真に近い。途上の道標が、右に行けと命ずるのでなくて、右に行けばA地に達すると指示するのと一般、私法も私益獲得の方法を指示するのである。財貨獲得の方法・労役獲得の方法を指示するのである。
なるほど法の指示せぬ方法によつても、事実われわれは私益を獲得することをえよう。欺瞞や暴力で、他人の財を奪ひ、他人を労務に強ゐるがごとし。しかしこれらは安全な確実な方法ではない、裁判所これを保護せぬからである。真に確実に財貨を取得しようとおもへば、やはり法の指示する・売買とか賃貸借とか相続とか贈与とかいふ方法によらねばならず、真に安全に他人から労務の提供を受けようとおもへば、やはり法の指示する・雇傭とか請負とかいふ方法によらねばならない。
異性の問題また然り。手れん手くだは、異性獲得の方法として未だ確実なものでない。裁判所これを認めぬが故である。確実なのは法の指示する方法・すなはち婚姻である。婚姻は異性を法的に安全に獲得する・ただ一つの手段である。
獲得した異性をどう消費するか?それはなんぢ自身の任意問題である。法律は異性獲得の方法とその喪失の手続とを規定するだけで、夫婦関係の継続中・互に何を為すべきかについては、あまり詳規することをなさぬ。ちやうど財貨の取得と喪失とにつき規定するだけで、その消費の方法については、殆ど規定せぬのと一般である。故に婚姻法の中枢は結婚法と離婚法とに存する。夫婦関係法は、副次的部門に過ぎない——もしそれ、かの夫婦財産法に至つては、まさしく現代の尖端問題の一つではあるが、その本質は婚姻法といふよりも財産法である。
われわれは本書において結婚法と離婚法・夫婦関係法と夫婦財産法とが、今日どんな変化の中に動揺しつつあるかを見よう。
参考書
Leske-Löwenfeld, Das Eherecht der europäischen Staaten u. ihrer Kolonien, 1904.
Roguin, Traité de droit civil comparé. Le mariage, 1904.
Bergmann. Internationales Ehe- u. Kindschaftrecht, 4 Bde., 1926--29.
M. Boeth, Neues Eherecht, 1925.
Klink, Die Reformbestrebungen im Ehescheidungsrecht, 1928.
Hans Keller, Das Einspruchsrecht gegen die Eheschliessung im französischen, schweizerischen und deutschen Recht, 1927.
Richard-Prassinos, Le divorce et la séparation de corps en droit comparé et en droit international privé, 1928.
K. Th. Kipp, Rechtsvergleichende Studien zur Lehre von der Schlüsselgewalt in den romanischen Rechten, 1924.
Eversley, On domestic relations, 1926.
Freund, Zivilrecht in der Sowjetunion, 1927.
Knecht, Handbuch des katholischen Eherechts, 1928.
Mariane Weber, Frau und Mutter in der Rechtsentwicklung. 1907.
M. J. Ostrogorski, Rights of Womans: Comparative Study in History and Legislation, 1912.
Isidor Loeb, The Legal Property Relations of Married Parties. Study in Comparative Legislation, 1901.
Francesco Cosentini, Droit civil comparé européen et américain, Le droit de Famille, 1928.
Baligand, Der Ehevertrag, 1906. Neubecker, Der Ehe- und Erbvertrag, 1914.
序 説
第一節 婚姻立法の権
一 教会の婚姻立法権
イ 教会は信徒をして戒律を守らせるために、いろいろの手段を用ゐたが、中んづく邪淫の戒を重んじ、峻厳無比の婚姻法を造つて信徒に臨んだ。殆ど教会の発生と同時に、あの固苦しい・審判者風の婚姻法が、その発達を開始したのである。1)国家ははじめ教会の婚姻立法権を認めなかつたが、事実上教会が婚姻法を造り、信徒がそれに従つて行くのをどうすることもできず、暗黙の間に遂に教会の婚姻立法権を認めてしまつた。中にも婚姻の故障・結婚と離婚・夫婦間の人的関係等の規定は、教会の専属管轄に移された。第十世紀ごろから教会が殆ど完全な婚姻事務の主管者となり了つた。2)
東ヨォロッパの諸国民はギリシヤ教会の婚姻法を守り、西ヨォロッパの諸国民はロォマ教会のそれを守つた。各国家に婚姻法なく、ドイツ人もフランス人もスペイン人も、一様に教会婚姻法に服し、婚姻につき、一時、世界私法を実現したのである。
1) 拙著・ビザンチン期における親族法の発達・二七以下。
2) 拙著・婚姻立法における二主義の抗争・一五。
ロ 第十六世紀に新教運動成功し、一部の教徒ロォマ教会を脱出した。初め彼等は、婚姻は『衣食住の問題と同じ俗的性質のものなり』と見たので、新教の君主は、婚姻事件を僧侶の手から世俗裁判官の管轄へ移して見たが、何にしろ当時婚姻法といへば、教会のそれより外にはなかつたから、事毎に僧侶の意見を徴せざるをえず、裁判官は僧侶の鑑定に常に引きづられがちだつた。新教会自身も、後には婚姻の神的性質を主張し出した。一旦国家化せんとした婚姻事務は、かくして再び——ことに十八世紀初頭以来——教会の手へ戻るやうになつたのである。1)
1) 拙著・二主義の抗争・一六一註1)。
二 国家の婚姻立法権
イ 十六世紀の後半、まづオランダが、国家もまた婚姻事務を執るといふ一大新例を打開した(一五八〇年)。宗教改革以来、新旧二派各々婚姻法をもち、一派政権を握れば自派の婚姻法を他派の者にも強制し、徒に他派の者の反感を挑発し来つたのであつたが、いまオランダはこの式をすて、教会の代りに国家官庁の面前で、締結することも可能だとし、以て非国教派の人々をして、国教々会から婚姻祝福を受けるといふ不愉快を免れしめたのである。これを撰択民事婚(fakultative Zivilehe)といふ。今日でもスェデン、1)ノォルウェ、2)チエック・スロバキア3)等は撰択民事婚主義をとる。
1) Eheg. v. 11/6 1920 4 Kap. 1.
2) Eheg. v. 15/5 1918 20.
3) Eheg. v. 22/5 1919 12.
ロ フランスは一七八七年、すなはち大革命勃発の前々年、撰択民事婚の制を布いたが、革命と共に思想激化し、教会の婚姻主権を全く否定し(一七九二年)、凡そ国民は国家官庁の面前において締結行為をなさざるべからずと定めるに至つた。これを必要民事婚(obligatorische Zivilehe)といふ。
オランダ・ベルギイ・イタリイ1)・スイス・ドイツ2)は十九世紀中に、二十世紀に入つてからは一九一〇年にポルトガルが、一七年にソヴェート・ロシアが、二六年にトルコが、必要民事婚主義をとつた。わが国またもちろん然り。
1) イタリイは、一八〇六年に必要民事婚主義をとつたが、一旦中絶し、六五年の民法から、確定的にさうなつた。スペインは、一八七〇年に必要民事婚主義をとり、七五年からは旧教徒の結婚は旧教会にて、その他の者の締結は国家の官庁にて、取扱ふことになつた。今でも宗教的相違によつてその取扱を異にしてゐる(Spanien, C. c. 75 fg; 83 fg.)。
2) ドイツでは一八五〇年にFrankfurt a. M.が卒先して必要民事婚主義をとり、七四年三月九日のプロシヤ法・七五年二月六日の帝国法がこれに倣ひ、民事婚主義に統一された。
第二節 立法主義
婚姻法の立案にあたつて二つの態度が対立する。一は性慾否定の態度、二は性慾肯定の態度。
三 ロォマ法1)
1) 拙著・二主義の抗争・一以下。
イ 勇敢に性慾肯定の態度をとつたのは、クラシック期のロォマ法であつた。同期のロォマ法は、絶対的性的自由(absolute Sexualfreiheit)の思想の上に、その婚姻法を築き上げたのである。その結果同法においては、結婚の禁なども至つて少かつた。禁は配偶の撰択方針に対する国家の干渉である。自由を尚ぶと、結婚の禁、減少するのである。ロォマ法は若き男女をしてなるべく広汎な範囲から、その配偶者を撰択させようとしたから、ごく僅か結婚の禁をおいたに止まつた。
婚姻の締結方法そのものにも干渉しなかつた。官庁の面前へ出頭する必要もなく、締結後届出をなすの要すらもないとしてゐた。恰も取引契約のごとく、単純な意思と意思との合致で、婚姻の成立を見たのである。
ロ ロォマ法はまた、婚姻の外に内縁なるものをおいてゐた。これまた一夫一婦の結合で、法から承認され・効果をも附せられた合法関係であつたのである。いはばロォマ法には婚姻と内縁と、合法結合の典型が二つあつたわけであつて、婚姻のやうな厳粛な法律関係に立ち入ることを欲しない気軽な男女は、それよりも効果の軽微な内縁の方を撰ぶことができたのである。
ハ ロォマ法はまた、契約の無効および取消に関する一般規定を、そのまま婚姻に適用した。従つて婚姻の無効取消も取引契約におけると同じやうに、軽且つ易だつた。特に厳重にそれを制限するために、特別な無効取消規定を婚姻のために立てねばならぬなどとは考へてゐなかつたのである。
ニ 離婚も甚だ自由、当事者の合意だけで行ふことができ、裁判も届出も必要でなかつた。合意を以て合したものは合意を以て離る、婚姻は官庁の協力なしに成立するから、やはり官庁の協力なしに解かれると見てゐたのである。
ホ 効果も頗る軽かつた。妻は能力に制限を受けず、身分財産に変動を被らず、夫婦対等といふよりも夫婦分立に近かつた。平等よりも独立を悦んだのである。
四 教会法1)
1) 拙著・二主義の抗争・一三以下。
イ 極端に性慾否定の態度をとつたのは、教会法であつた。同法は、『なんぢ姦淫するなかれ』の思想の上に、その婚姻法をうち建てたのである。すなはちまづ配偶撰択の方針に干渉して、たくさんの婚姻故障をおき、大いに婚姻の自由を妨げた。締結の方法にも干渉して厳重な方式を守らせ、方式に従つて締結されないものを一切違法の私通と見た。性を罪とし、婚姻だけを合法としたから、婚姻か非婚かを明別するの必要を感じ、その標準として厳格な方式を立てたのである。ロォマ法の無式主義に対して要式主義をとつたのである。
ロ 教会は内縁を認めず、婚姻を以て両性結合の唯一無二の適法形式とした。婚姻と私通との間に、何らの中間形式なしとした。すなはちロォマ法の婚姻内縁二元主義に対して婚姻一元主義をとつたのである。
ハ 教会はまた婚姻の無効取消を特別に制限するために婚姻特有の無効取消規則を造つた。契約一般の無効取消規則を婚姻に適用しようとはしなかつた。普通の契約に対してなら無効原因となりえた事由も、婚姻に対しては無効の原因となりえなかつたのである。取消の方法に関しても、婚姻取消は裁判外の意思表示を以てなすことをえず、訴および判決の方法によらざるべからずと定めた。訴においては裁判所自ら証拠を蒐集し、実体的真実に照らして取消権の存否を判定しようとした。なるべく取消を避けようとしたから、取消原因を特に少くし、その方法手続をも特に慎重にしたのである。ロォマ法の一般無効主義に対して特別無効主義をとつたのである。
ニ 離婚もこれを禁じた。後に許すやうにはなつたが、なほも離婚権の発生原因を厳重に法定し、法定原因なければ離婚権なしとし、また離婚は訴および判決の方法によつてこれをなさざるべからずともした。すなはちロォマ法の離婚自由主義に対して禁止主義又は制限主義をとつたのである。
ホ 結婚の効果も重かつた。夫婦は一の血肉(ein Fleisch und Blut)にして、姓を一にし、住所を一にし、栄誉を一にし、子に対する権利義務を一にし、妻が夫に対して貞操の義務を負ふごとく夫もまた妻に対して同じ義務を負ふとした。財産関係についても、身分を一にする者は財産をも一にすとの見地から、夫婦共産主義の確立に尽力した。すなはちロォマ法の夫婦分立主義に対して夫婦一体主義をとつたのである。
ヘ 要するに性慾否定の態度をとると、配偶の撰択範囲を狭くするために、たくさんの結婚の禁をおくやうになり、適法の婚姻と違法の私通とを峻別するために、結婚の方式を厳重にするやうになり、結婚の効果を重くして夫婦を固い忠実義務に結びつけ、離婚を禁じて夫婦を終生分離させまいとするやうにもなる。
反対に性慾肯定の態度をとると、結婚の禁を減じて自由撰択の範囲を広め、結婚の方式を緩めて無方式の結合をも適法視するやうになる。結婚の効果を軽くして夫婦相互を独立させたり、離婚の禁を撤して男女を自由に離合させたりするやうにもなる。性を「罪」と見るか、「自然」と観ずるかによつて、婚姻立法の内容は根本的に異つてくるのである。知らず、近代の立法傾向はそのいづれに就かんとするか?
五 近代の立法傾向1)
1) 拙著・二主義の抗争・二二以下。
一言以てこれを蔽へば、ロォマの自由婚姻が近代婚姻法の理想である!近代の立法家は、近代法の中に今なほ古臭く残つてゐる教会的分子を洗ひ落とし、もつと自由な・もつと明るい・もつと生き生きした性的秩序を、再建せんと努力しつつあるのである。
すでに結婚の禁に関する規定のごときは、殆どロォマの昔に還つた。あの煩瑣な意地悪な教会風の干渉はすたれたのである。離婚のごときもますます容易になりつつある。愛なき二人を終生、法の鎖につないでおくやうな惨酷さは消えたのである。夫婦一帯の主義もすたれてロォマ風の分立主義へもどり、夫婦各々に身分および財産の独立を保証するやうにもなつてきた。ただ結婚の方式・離婚の手続・無効取消・夫婦関係の規定等には、今なほ教会の遺物、濃厚に残つてゐるのを見るが、漸次これらも洗ひ落されて行くであらう。
以下われわれは、ロォマ風の自由主義が婚姻法の諸方面においていかに教会風の干渉主義に打ち勝ちつつあるかを詳細に見て行かう。
本 論
第一章 結 婚
第一節 結婚の禁
結婚禁の規定は、教会法で発達した。けだしロォマ法は男女交通をなるべく自由ならしめんため、ごく僅かしか禁止規定をおかなかつたが、反対に教会は、男女の交通を監視すべく、厳密な禁止規定を立てたからである。これを婚姻故障(Ehebindernisse)といひ、殆ど教会学者の研究主目をなしてゐた。近代法の結婚禁止規定は、教会法の影響から、未だ本当に独立してゐるといへないのである。
六 不適齢婚【七六五条七八〇条】
イ 教会法1)は、女十二年・男十四年未満を婚姻不適齢としてゐたが、近代法は、性的成熟のみを見ず、経済上の能力をも参酌し、大いに適齢を高めた。仏法はこれに先駆し、女十五・男十八を適齢とし、ベルギイ・イタリイこれに倣つた。2)ドイツは女十六・男二十一とする3)も、女十六は低きに失すとの意見多い。スイスは女十八・男二十とする。ノォルウェこれに倣ふ。4)わが民法は仏に近く、女十五・男十七を適齢とする【七六五条】。
1) Friedberg, Kirchenr. 440.
2) C. c. 144---Belgien, C. c. 144---Italien, C. c. 55.
3) BGB. 1303.
4) ZGB. 96---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 1---立法の趨向は、女十八・男二十一を適齢と見つつある(Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 2. Kap. 1---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 6)。
ロ 違反の場合に関しては、教会法は、違反婚すなはち不適齢婚を、当然無効とせず、取消しうるに止まるとしたが、取消権者の数は多く、当事者にはもちろん、親族・検事(defensor matrimonii)等にも、これを与へてゐた。これ不適齢婚を公益違反と見たためである。1)
1) Friedberg, 441---仏・伊は今なほ教会法主義をとる(C. c. 184---Italien, C. c. 104)。
ハ 近代法は不適齢婚を私益違反に過ぎずと見る。その結果、親族・検事には取消権を与へず、不適齢婚当事者およびその保護者たる親・後見人にのみこれを与へる。1)ドイツ民法に至つては、不適齢婚禁止の規定はベシ規定(Sollvorschriften)にして要ス規定(Mussvorschriften)にあらず、故にこれに違反するも婚姻そのものは完全有効なりとする。スェデン・ノォルウェ・デンマァク等の婚姻法また然り。2)
1) Preuss. Ldr. II, I, 37. 990 fg.
2) Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10. Kap. 1 fg.---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 31 fg.---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 42 fg.
ニ わが民法は、不適齢婚に対しては各当事者・其戸主・親族又は検事より取消の訴を起しうとするが【七八〇条】、これ不適齢婚を公益違反と見た教会思想のなごりで、立法の趨勢に従ふならば、不適齢婚は違法婚なるも完全有効なりとすべきであらう。改正要綱はこの点にふれず。
七 重婚【七六六条・三二条・七八〇条】
イ もちろん教会法も重婚を禁じ、違反の場合には、各当事者・親族・検事等において取消しうとしてゐた。近代諸国法においてまたさうである。1)
わが民法も重婚取消権を各当事者・其戸主・親族および検事に与へる【七八〇条】。改正要綱はこれに満足せず、重婚を当然無効にしようとしてゐる2)3)【要綱第十三】。
1) C. c. 184---BGB. 1326---ZGB. 120 1---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10. Kap. 1.
2) 現行法の下においては重婚の成立は不可能に近い。なぜなれば婚姻の成立には届出を要し、而してその重婚となるべき場合には、市町村長これを受理せぬからである(七七六条)。これに反し改正要綱は慣習上の儀式を挙げることによつても婚姻成立すとするから(第十二)、重婚の成立可能となる。届出によつて甲女と婚姻してゐる男が、他地に旅行し、乙女と慣習上の儀式を挙げるがごとし。
3) 改正要綱が重婚を当然無効にしようとする理由は、『単に取消しうべきものとして一旦なりとも成立させることは一夫一婦の根本義及び人倫の上からも許すべからざることである』といふにある(穂積・民法改正要綱・法協・四六・五・八二)。がしかし、重婚は私通や内縁のやうな非婚(Nichtehe)にあらず、届出をなし若くは慣習上の儀式を挙げて成立した婚姻である。しかも相手方は大抵善意、第三者もまた届出なり儀式なりを見て、これを有効と信ずるであらう。故に当然に重婚を無効とするは不可。余はやはり取消を可とする。
ロ 重婚取消の訴を起す以前に、第一婚が、元来瑕疵附きのものであつたために取消されることがあるが、かかる場合にもなほ重婚取消権者は、第二婚を重婚なりとして取消すことをうるやといふに、少くとも近時の立法は、かかる場合にはもはや重婚取消を許さずとする。1)わが現行法の下においても同様に解しうるであらう。2)
1) Schweden, Eheg. 10. Kap. 1 Abs. 2---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 31 Abs. 2---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 42 Abs. 2---BGB. 1326.
2) 改正要綱のやうに重婚を当然無効とすると、第一婚が取消され又は解消した場合にも、第二婚当事者は第二婚を維持できず、もう一度締結行為をなさねばなるまい。
ハ 死亡宣告取消の場合、取消に先ち留守配偶者のなしたる第二婚が重婚となるやといふに、教会法は、宣告取消の場合には第一婚回復するが故に第二婚は重婚となり、取消されるに至ると見た1)が、ドイツ民法は、善意悪意を区別し、第二婚両当事者が悪意なりし場合、すなはち失踪者の生存を知りし場合には取消さるるも、善意なりし場合、すなはちこれを知らざりし場合には、失踪者の帰来にもかかはらず、第二婚を維持することができると見る。2)わが民法また然り【三二条】。プロシヤ州法のごときは当事者悪意なりし場合といへども第二婚完全に有効なりとした。3)
1) Friedberg, 437 fg.---仏・伊は今も教会法主義(C. c. 139---Italien, C. c. 113)。
2) BGB. 1348.
3) Preuss. Ldr. II, I, 666.
八 待婚【七六七条七八〇条】
イ 女は前婚の解消又は取消の日から一定期間婚姻をなすことをえない。これを待婚義務(Wartepflicht)、その期間を待婚期間(Wartezeit)といふ。旧教会は再婚を禁じたから、待婚の制をおかなかつたが、ロォマ法は再婚を許して待婚を命じてゐた。1)近代諸国の法律は、みなロォマ法主義に倣ふ。期間は大抵三百日、わが民法は六ヶ月2)【七六七条一項】。
1) D., 3, 2, 11, §1---C. 5, 9, 2.
2) オォストリアはわが民法に近く、百八十日の待婚を命じてゐる(ABGB. 120)。
ロ 待婚規定の趣旨は血統の混乱を避けるにあるから、この虞なければすぐに再婚をさせて差支なし。故にロォマ法は女が明かに前婚の子を懐胎せざりし場合・すでに前婚の子を分娩し了りたる場合には、待婚期間の適用なしとしてゐた。1)近代法も同一の規定をおく。わが民法また然り2)【七六七条二項】。
1) D., 3, 2, 11, §2.
2) 待婚規定の目的は子の父不明となることを避くるにあるから、『前婚解消後更ニ前夫ト再婚スル場合ニハ七六七条一項ノ期間ヲ遵守スル必要ナシ』(明四三・名・控・判・親族法総覧・上・四一三——大元・同一趣旨の回答あり・同書四一二)。
ハ ノォルウェ・デンマァク等の新立法は、女子の再婚を早からしめんために、待婚期間の進行は、離婚判決確定の日に始らず、事実上の同居の廃止日に始るとする。1)
1) Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 10---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 16.
ニ 違反の場合に関しては、大多数の立法は、待婚期間をベシ規定とし、これに反するも婚姻は完全有効なりとする。わが民法は各当事者・其戸主・親族・前配偶者又は検事に取消権を与ふ【七八〇条】。
九 相姦婚【七六八条七八〇条】
イ 教会法は厳に相姦者の結婚を禁じ、違反の場合には各当事者・前配偶者・親族・検事等において取消しうとしてゐた。1)
1) Friedberg, 451 fg.
ロ 近世法は相姦婚の禁を寛和せんと欲し、例へばプロシヤ州法は、姦通そのものが理由にて離婚判決を受けたる者のみが相姦者との婚姻を禁ぜらるるに止まるとした。フランスは一八八四年に相姦婚禁止の規定を民法に挿入したが、一九〇四年に削除してしまつた。一九〇六年にはルゥマニア、一〇年にはポルトガル、一五年にはスェデン、一八年にはノォルウェ、一九年にはチエックスロバキア、二二年にはデンマァクが、いづれもこれを廃止した。ドイツは今なほおくも、同時に免除の道を開き、官庁の許可をうれば相姦者とも結婚できるとする。日本は厳重に禁じてゐる1)【七六八条七八〇条】。
1) 日本の外今なほ厳に相姦者との結婚を禁じてゐるのは、Belgien, C. c. 298---Niederlande, BWB. 89---ABGB. 67---Polen, Eheg. v. 16/3 1836等々。
一〇 血族婚【七六九条七八〇条】
イ 教会は、四親等以内の傍系親族は互に結婚すべからずとしてゐた。一時ではあつたがこれより先き、七親等傍系血族間の結婚を一切禁じたことすらあつた。1)
1) Friedberg, 443.
ロ 親等の計算方法にロォマ式と教会式とある。ロォマ式は、二人より同始祖に至るまでの両側の世数(Zeugung)の和を以て親等の数とし、教会式は、二人より同始祖に至るまでの世数の多少を見、等しきときはその一側のみをとり、異るときはその多き側のみをとり、これを以て親等の数とする。例へば兄弟はロォマ式では1+1=2等親であるが、教会式では1等親。叔姪はロォマ式では1+2=3等親であるが、教会式では2等親。前述四親等の禁とは、教会式計算のそれであつた【わが民法はロォマ式計算方法をとる——七二六条】。
ハ 近代法は教会法の禁止範囲を広きに過ぐとし、簡単な叔姪婚の禁を以てこれに代へた。フランス・イタリイ・ポルトガル・スイス等のごとし。1)ドイツは一層禁を寛くし、単に兄妹婚を禁ずるに止まる。ノォルウェ・デンマァク・チエックスロバキア・ソヴェート・ロシア等ドイツに倣ふ。2)わが国はフランスに倣う3)4)【七六九条】。
1) C. c. 163---Italien, C. c. 59 3---Portugal, Eheg. v. 25/12 1910 8---ZGB. 100 1.
2) BGB. 1310---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 7---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 12---Tschechoslowakei, Eheg. v. 22/5 1919 25---Sowjetrussl. G. v. 27/9 1921 69.
3) 結婚の禁に関しても、継親子又は嫡母庶子は、親子同然に取扱はれるであらうか?民法七二八条には、『継父母ト継子ト又嫡母ト庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス』とあるが、これは親権・扶養・相続等の問題につき、これらの者を親子に準ずといふ意味で、結婚禁についてまで親子同然に取扱ふといふ意味ではない。もちろん継親子又は嫡母庶子は、一種の直系姻族であるため、結局結婚はできないが、それは直系姻族だからであつて、親子であるからではない。換言すれば七七〇条の規定の適用を受けるからで、七六九条の規定の適用を受けるからではない、七六九条の『血族』の中には、法定血族は含まぬのである(通説は反対)。
4) 『継母ノ妹ハ之ヲ妻ト為スコトヲ得』(親族法総覧四二七所載・明三二年回答)。
ニ 違反の場合については教会法は各当事者・親族・検事等において取消しうとしてゐた。近世諸国の法律は大抵教会法主義をとる。わが国また然り【七八〇条】。改正要綱は当然無効に改めんとしてゐる【要綱第十三】。
一一 姻族婚【七七〇条七八〇条】
イ 旧教会は四親等以内の傍系姻族との結婚を禁じてゐたが、新教会は、かなりこの禁を寛大にした1)(その限界を数字的に示すことはしなかつたが)。プロシヤ州法に至つて遂に傍系姻族間の禁を撤し、直系姻族間の禁のみを保留した。2)スェデン・デンマァク・チエックスロバキア等はプロシヤの例に倣ふ。3)わが国また然り【七七〇条】。故に例へば先妻の連子とは、直系だから結婚できぬが、先妻の姉妹・先夫の兄弟とは、傍系だから、結婚できるのである。4)
フランスは未だ教会主義を脱しきらず、亡妻の姉妹とは結婚しうるも、去りたる妻の姉妹とは結婚しえずとする。5)
1) Friedberg, 443 fg.
2) Preuss. Ldr. II, I, 6.
3) BGB. 1310 Abs. 1---ZGB. 100 Nr. 2---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 9---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 8---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 13---Tschechoslowakei, Eheg. v. 22/5 1919 25 Nr.3.
4) 子ある男が、子ある女と結婚した場合、子同志は姻族でないから結婚できる。司法省回答もいふ『妻カ婚姻前実家又ハ他家ニ於テ挙ケタル子女ハ夫ノ直系卑属(前妻ノ子)ト法律上何等ノ親族関係ナキモノトス故ニ婚姻ヲ為スコトヲ得』(親族法総覧・上・四二六)。
5) C. c. 162---Belgien, C. c. 162.
ロ ソヴェート・ロシアの婚姻法に至つては、直系姻族結婚の禁すらなし。姻族婚は血族婚と異り、生れる子に悪影響を及ぼさぬからといふ科学的見点からである。1)
1) Sowjetrussl. G. v. 27/9 1921 66 fg.---vgl. auch Kessler, Zf. ausl. u. intern. Privatr. I, 206 fg.
ハ 違反の場合については教会法は各当事者・親族・検事等において取消しうとしてゐた。近代法は大抵教会法主義をとる。わが民法また然り【七八〇条】。改正要綱は当然無効主義に改めんとしてゐる【要綱第十三】。
一二 縁族婚【七七一条七八〇条】
イ 教会法は縁組当事者間の結婚はもちろん、当事者の一方と他方の配偶者との結婚、養子と実子との結婚もまたこれを禁じてゐた。1)
1) Friedberg, 450.
ロ 近代法は縁組の効果を当事者に限り、第三者に及ぼさず、従つて当事者間の結婚を禁ずるだけで、1)当事者の一方と他方の配偶者との間の結婚、養子と実子との間の結婚はこれを禁じない。オォストリア・ソヴェート・ロシアのごときは、当事者間の結婚さへ許してゐる。2)
フランス・イタリイ等は、今なほ教会的に広汎な縁族婚の禁をおく。3)わが国ややこれに近し4)【七七一条】。
1) BGB. 1311---ZGB. 100 Nr. 3---Schweden Eheg. v. 11/6 1920 20.
2) ABGB. 47 fg.---Sowjetrussl. G. v. 27/9 1921 66 fg.
3) C. c. 354 (G. v. 19/6 1923)---Italien, C. c. 60---Spain, C. c. 84 Nr. 5.
4) ただわが国は、実子と養子との間の結婚を認める(七六九条但書)。理由書に曰く、『養子縁組ハ人為ナリ婚姻ニ関シテハ之ヲ実子ト区別シ養家ノ兄弟ト姉妹ト婚姻セシムルモ決シテ乱倫ノ行為ニ非ス』(同書・四五)。
ハ 違反の場合に関しては、教会法は各当事者・親族・検事において取消しうとしてゐた。近代法中には、フランスのごとく縁族婚の禁はベシ規定にしてこれに反するも婚姻は有効なりとするものもあり、ドイツ等のごとく『結婚は縁組を破る』、養親子結婚すればもはや養親子でなく、単なる夫婦となるとするものもある。後の立法の下では、縁族婚の禁は殆ど無同然である。
イタリイおよびわが国は、なほ教会主義をとり、当事者・親族および検事に取消権を与ふ【七八〇条】。改正要綱はこれに満足せず、当然無効たらしめんとしてゐる【要綱第十三】。
一三 悪疾婚
最近立法のあるものは、遺伝性若くは伝染性の悪疾者、ことに心神喪失者又は耗弱者の結婚を禁ずる。1)わが国にはこの禁なし。
1) ZGB. 97; ABGB. 48; Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 2 Kap. 5; Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 10; Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 5等は心神喪失者の結婚を禁じてゐる---ABGB. 48; Schweden 2 Kap. 5は心神耗弱者の結婚を禁じてゐる---Italien, C. c. 61; Portugal, Eheg. v. 25/12 1910 4 Nr. 4は心神喪失に基く禁治産者の結婚を禁じてゐる---Dänemark, 11; Norwegen, 6は性病患者の結婚を禁じてゐる。米国の数州例へばConnecticut, Michigan, New Jersey, New York等も然り。
一四 結論
結婚の禁は近代に入つてからその種類を減少した。相姦婚の禁とか縁族婚の禁とかがなくなり、若くはなくなりかけてきた。直系姻族結婚の禁すら消滅に瀕してきた。血族婚の禁は存続するが、その範囲は縮小し、兄妹婚を禁ずるだけで叔姪婚は是認しようとするやうになつてきた。待婚期間も短くなり、僅々数月の間隔にて再婚できるやうになつてきた。違反の効果も軽くなり、禁に違反して結婚しても無効とならず、取消されもせず、完全有効とされる。
かやうに結婚の禁が少くなり・軽くなつたのは、自由放任の大浪が今や婚姻法の領域へも押しよせてきたからである。一たい十九世紀の立法者には一の矛盾があつたのであつて、財産法の制定には自由放任主義をとり、婚姻法の制定には干渉取締の態度に出たのである。教会の伝統と警察国の思想とを背景にして、幾多無用の故障をおき、男女の自由交通を妨げたのである。現代の立法が結婚の禁を大いに少くしたのは、財産法進歩の跡を追ひ、市民のために結婚の自由——配偶撰択の自由——を確立したものといへよう。
しかし現代法は他面また新規の婚姻故障を作りつつある。悪疾者結婚の禁がこれである。この禁はしかし、昔日のそれのやうに宗教的・倫理的動機からではない、社会衛生の見地からである。個人善のためでなくて社会善のためである。今後の婚姻法は、ちやうど今後の財産法が、個人の取得活動に制限を加へるごとく、やはり社会的の見地から、個人の配偶撰択方針に強く干渉することにならう。
わが民法は今なほ相姦婚の禁・縁族婚の禁等、倫理主義の禁を羅列してゐる。社会衛生の見地からでなくて風俗警察の見地からである。改正要綱はもつと反動的で、違反婚の全部を当然無効たらしめんと企ててゐる。
第二節 結婚同意
結婚同意の規定は、ゲルマンで発達した。ロォマには家長制度あり、結婚同意も大抵家長が与へてゐたから、親の同意といふ肝心な規定部分の発達を見ず、教会に至つては婚姻独占の野心から明かに親の同意を排斥してゐた。親の同意は子の結婚に対する親の干渉であるから、国家の結婚干渉の排斥せざるべからざるごとく、親の同意もまた排斥しなければならぬと見たのである。が、ゲルマン人は、結婚の同意を、子に対する親の保護権の一大作用と見たから、これに関する立法の権を握つて放さず、国法の定むる同意権者の同意をえざる婚姻は、たとへ教会法上完全有効に成立するとも、国法上、一定の制裁を免るることをえずとし、間接に制裁を以て同意を強制し、教会法の足らざる所を補つたのである。教会の婚姻立法権滅びるや、同意制度は、国家立法の表面へあらはれ出した。が、中世の間に教会といふ一大統一者の手を離れてゐただけに、その規定ぶりは今なほ不統一を極める。
一五 家族の結婚に対する家長の同意【七五〇条七七〇条】
イ ロォマでは家族は単独にて婚姻を締結することをえず、父に家長権あれば父から同意をうることを要し、祖父なほ存命し、祖父に家長権あれば祖父からそれをうることを要し、養子の場合には養父からそれをうることを要した。1)家族の身分を脱してしまへば未成年でも単独に締結しえたが、脱しないかぎり、年齢に拘らず同意をうるの必要があつたのである。2)ロォマ以外かかる制度は見なかつた。
1) Inst. 1, 10, pr.---D., 23, 2, 2. 3.
2) D. h. t. 25. 20
ロ わが国には今なほ家長制度のなごり存し、家族が結婚するには戸主の同意をうることを要し、えずに結婚すれば、戸主はその家族を離籍することができる1)【七五〇条一項二項】。が、戸主の同意なき婚姻は、かかる制裁にかかはらず完全に有効である【七七六条但書】。
改正要綱は戸主の同意を廃止しようとしない。ただ戸主が、その同意なしに結婚した家族を制裁する際、家事審判所の許可を受けさせようといふだけである【要綱第八ノ三】。
1) 『法定ノ推定家督相続人カ戸主ノ同意ヲ得スシテ妻ヲ娶リタルトキハ推定家督相続人ハ一家ヲ創立スルコトヲ得サルモナルニ拘ラス戸主ハ之ヲ離籍スルコトヲ得』(明・三一・一〇・一五・回答・親族法総覧・上・二四三)。
一六 子の結婚に対する親の同意——同意権の主体【七七二条七七三条】
イ ゲルマンの諸法は多数の同意権者をおき、父なければ母、父母なければ後見人又は近親、これらの者なければ父母の友人において同意を与へうとしてゐたが、時代の下ると共に権利者減じ、近親・友人等は同意権なきことになつた。1)十九世紀の初頭には父にのみ同意権を与へる主義が流行し、例へばプロシヤ・オォストリアは、母は私生子に対してのみ同意権ありとし、フランスは母にも同意権あるが、意見衝突の場合は父に従ふとした。2)最近は父母双方に同意権を与へると同時に、父母といへども、もし親権を失へば、同意権をも失ふとするものが多い。3)これ同意は親権の効果にして親子関係そのものの効果にあらず、父母といへども不行跡等のため親権を失へば同意権をも失ふに至るべき筈なりとの見地からである。
1) 拙著・二主義の抗争・一〇八以下。
2) Preuss. Ldr. II, I, 29---ABGB. 49---C. c. 148.
3) ZGB. 98---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 2. Abs. 2---Norwegen, 15/5 1918 2. Abs. 2---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 7.
ロ わが民法は『家ニ在ル父母』に同意権を与へる【七七二条】。しかし家を同じうする者必ずしも子の保護に適当とはいへぬ。親権濫用のため親権を失つても親は子と家を一にしてゐるから。家を異にする者必ずしも子の保護に不適当ともいへぬ。父乱行のため離婚して父の家を去つた母は、家こそ異なれ、子の保護に父よりも適任といへようから。故に『家ニ在ル父母』に同意権を与へず、親権を行ふ父母に与へるを可としようが、改正要綱はかかる改正を企てず【要綱第十一ノ一、第四ノ三】。
ハ 嫡母や継父母に婚姻同意権を与へた例はない。ひとりわが民法は、嫡母および継父母にも同意権を与へる【七七三条】。
ニ 祖父母に同意権を与へる例は1)近似殆ど滅びた。改正要綱は時運に逆行し、父母なき場合には祖父母の同意をうべきことを定めんとしてゐる【要綱第十一ノ一、第四ノ三】。
1) Preuss. Ldr. II, I, 50---sächs. BGB. 1571---C. c. 150---Italien, C. c. 64.
ホ 養子は婚姻につき養実双方の父母の同意をうべしとする主義も滅びた。1)今は大抵の国養親の同意のみにて足るとする。2)わが国また然り。3)
1) Sächs. BGB. 1573.
2) BGB. 1306.
3) 『養子カ養家ニ於テ婚姻ヲ為ス場合ニ其家ニ養父母ト実父母トアルトキハ養父母ノミノ同意ヲ得レハ足ルモノトス』(明三二・二・一四・回答・親族法総覧・上・四三八)。
一七 同意年齢【七七二条】
イ 中世諸法は、女子は年齢にかかはらず、結婚につき同意権者の同意をうることを要し、男子は婚姻に関する特別成年期、すなはち独立して婚姻を締結しうと特に法の定めた年齢——に達せざる間、同意権者の同意を要すとしてゐたが、後には女子の場合も生涯的でなく、一定の年齢まで要するに過ぎないこととなつた。1)
1) 拙著・二主義の抗争・一〇八以下。
ロ 十九世紀の立法は、例へば男三十年・女二十五年までは同意を要すとか、男二十五年・女二十二年までは同意を要すとか、年限こそ区々であつたれ、とにかく特別の成年期は設けてゐたが、近時はこれを廃し、一般成年期の規定を結婚にも適用し、独立して財産行為をなしうる者は独立して婚姻をも締結しうるとする。1)智能完熟し保護の必要なきに至れる成年者は、財産上も身分上も、一般的に親の権力から解放するをよしとする見地からである。
1) ZGB. 98---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 2---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 2---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 7.
ハ わが民法は男三十年・女二十五年までは同意を要すとする【七七二条】。すなはち特別年齢の定め方は立法例中最も高し。改正要綱に至つてはこれに満足せず、生涯『家ニ在ル父母』の同意を要することに改めんとしてゐる【要綱第十一ノ一】。
一八 違反の場合【七八三条】
イ 中世諸法は同意規定に違反して結婚した者に一定の制裁を加へ、或は相続権を剥奪し、特有財産を没収し、或は嫁資請求権を喪失させてゐたが、近世に入り、制裁主義は殆ど滅びた。
ロ 違反婚そのものの効力に至つては、中世においては完全有効、何人も取消すことをえなかつた。けだし婚姻の効力は教会法によつて定まるのに、同意は世俗法の制度に過ぎぬ、これに反するも、世俗法上の制裁こそあれ、効力は影響を受けぬ理であつたからである。1)十九世紀に入つてから取消主義流行し出し、少くとも未成年者が同意なしに締結した場合には取消すことができるとされた。今日においてもスイスは同意権者に取消権を与へ、ドイツは無同意結婚者、すなはち未成年者自身に、取消権を与へる。2)しかし新しい立法は完全有効主義をとり、同意権者はもちろん未成年者自身といへども同意規定違反の婚姻を取消すことをえずとする。3)
1) Preuss. Ldr. II, I, 994, 997.
2) ZGB. 128---BGB. 1331.
3) Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10. Kap. 1 fg.---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 31 fg.---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 42 fg.
ハ わが民法は同意権者に取消権を与へる1)2)【七八三条】。未成年者が同意なしに結婚した場合ばかりでなく、成年者(三十年又は二十五年以下の)が同意なしに結婚した場合にも、同意権者は取消権を揮ひうるのである。改正要綱に至つては、取消主義に加ふるに制裁主義を以てし、無同意結婚者に相当の制裁を加へんといつてゐる【要綱第十一ノ二】。
1) 同意権者にのみ取消権を与へた理由につき、理由書はいふ——『婚姻ノ当事者カ婚姻ヲ為スニ父母後見人等ノ同意ヲ経ヘキニ之ヲ経スシテ随意ニ婚姻シ而シテ後ニ至リ自ラ其取消ヲ請求スルコトヲ得ストスルハ却テ婚姻ヲ軽視スルニ至ラシムルモノナルヲ以テ……婚姻ノ当事者ニ其婚姻ノ取消ヲ請求スル権ナキコトトシタリ』(民法修正案理由書六三以下)。
2) 通説は七八三条にいはゆる『同意ヲ為ス権利ヲ有セシ者』の中に親族会をも含ましめ、親族会員共同して取消すこともまた可能なりとする。
一九 同意拒絶の場合
イ 十九世紀の立法は、子は、同意権者から同意を拒まれた場合、同意に代る判決を求めることができると見た。少くとも成年の子にはこの権利ありと見たが、1)現代立法は子にかかる権利を認めぬ。その理由は、今日は同意年齢低下し、殆ど未成年の子のみ同意を要することとなつたのであるが、未成年の子が同意を拒まれた場合は、成年の子が拒まれた場合と異り、その非、つねに拒絶を受けた未成年者自身の側に存すと見て差支なきためである。
1) 拙著・二主義の抗争・一二一以下。
ロ わが国の判例も子には父母の同意に代る判決を求むるの権なしとする。1)しかしわが国の同意年齢は甚だ高く、成年を過ぎてもなほ同意を要するので、少くとも成年の子には同意に代る判決を求めるの権を認めていいであらう。
1) 『父母カ其子ノ婚姻ニ同意ヲ与フルト否トハ父母ノ自由ニ委セラレタルモノナルヲ以テ其同意ヲ強要スルコトヲ得サルモノトス』(大八・二・三・東京控、新聞・一五三一号二六)。
二〇 禁治産・準禁治産者の結婚に対する保護者の同意【七七四条】
禁治産者や準禁治産者は独立して結婚できるかといふに、多くの立法は、本心回復中といへどもこれらの者は、独立して締結することをえず、後見人なり保佐人なりの同意をえて締結せねばならないとして来たが、1)最近の立法は一歩進めて、心神の喪失者および耗弱者から結婚能力を奪つてしまつた。たとへ保護者の同意をえても、これらの者は結婚できないとしてしまつた。2)
わが民法は正反対の方向をとり、禁治産者や準禁治産者は、本心の回復中ならば、保護者の同意なしに結婚できるとする3)【七七四条】。
1) Preuss. Ldr. II, I, 29---BGB. 1304---C. c. 509---ABGB. 49---ZGB. 90.
2) 前出一三参照。
3) Sächs. GB. 1984も本心の回復中ならば同意なしに結婚できるとしてゐた。
第三節 婚 約
現代の婚約法はロォマ法を基礎にする。嘗て一度、ゲルマン法や教会法の元素が、婚約法の中へ入り込んだこともあつたが、今は殆ど駆除されてしまつた。けだしロォマの婚約は、締結が簡単、解消も容易、効果また薄弱で、婚約の拘束力の強過ぎることを恐れる現代人の思想に、最もよく投合するからである。
二一 締結
イ ロォマの婚約は、当事者間の単なる合意で成立した。1)使者や手紙で婚約することもでき、暗黙の間に婚約することもできた。指環の交換は、婚約成立の有力な証拠だつたが、唯一の方法ではなかつた。
教会法においても婚約は単なる合意を以て足りた。2)近代に入り一時要式主義の流行を見、証人を要すとか、裁判所又は公証人の面前で約することを要すとか定められたが、3)今は各国ロォマ風の無式主義に帰つた。4)使者による締結、暗黙の間の締結をも認める。
1) D., 23, 1, 4.
2) Dittenberger, Verlöbnisr. 7.
3) Preuss. Ldr. II, I, 82.
4) ZGB. 90.
ロ ロォマ法は婚姻不適齢者の婚約をも認めた。1)婚約は将来の婚姻に関するから、現に婚姻に不適齢の者でも判断能力さへあるなら、同意権者の同意をえて締結しうる筈だと見たためである。近代の法律も同一見解をとる。2)3)
1) D., 23, 1, 7.
2) ZGB. 90.
3) 『婚姻ノ予約ハ婚姻ノ成立スル前提事項タルニ止マリ、婚姻其モノトハ全ク別個ノ契約ナレハ民法七百六十五条ノ婚姻年齢ニ達セサル者ノ為シタル婚姻予約ト雖モ当時既ニ年齢十五年五ヶ月ノ未成年者ニシテ意思能力ヲ有スルモノナル以上ハ自己ノ行為ノ何タルカヲ弁識シテ為シタルモノナルヲ以テ其契約ハ無効ニ非ス』(大八・四・二三・大判・民録六九六)。
ハ 婚約の無効および取消は、ロォマ法ではもちろん教会法でも契約一般の法理によつて決した。婚姻の無効および取消に関する特別規定を婚約に準用することはしなかつた。その結果婚約の方は、虚偽表示等を理由に取消すこともできたのである。婚姻には特別規定あり、虚偽を理由に取消すことをえなかつたが、婚約の場合にはこれらを取消の理由とすることができたのである。また婚姻には条件期限を附することをえなかつたが、婚約にはこれを附して差支なかつた。近代法はまたこの例を襲ふ。
離婚を条件に配偶ある者が、さらに第三者と婚約しえたかといふに、うるとすると、本来完全に自由であるべき筈の離婚の決意が、第三者との婚約により不当に促進されるだらうといふ理由から、えずとしてきた。1)婚姻取消を条件とする第三者との婚約も無効であつた。2)
1) Reichsg. Entsch. 29, 98 fg.---Seuffert's Archiv 78, 315.
2) 『本件ニ付キ原裁判所ノ確定スル所ニ依レハ被上告人ニハ配偶者アリテ上告人モ其事実ヲ知レルニ拘ハラス将来該婚姻ノ解消シタル場合ニ於テ互ニ婚姻ヲ為スヘキ旨ヲ予約シタルモノトス斯クノ如キ婚姻ノ予約ハ我国民道徳ノ観念ニ照シ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ニシテ全然無効ナルモノト解スルヲ相当トス』(大九・五・二八・大判・民録七七五)。
二二 効果
イ 婚約者は、ロォマでは、婚姻締結の債務を負つただけだつたが、ゲルマン法は、婚約者を夫婦に準じ、新婦は妻と同じく貞操の義務を負ふ、違反は姦通の一種なりと見た。1)近代法はみなロォマ主義であるが、中にはゲルマンの思想を加味し、一定の点につき予約者を夫婦に準ずるものもある。例へば独法は、婚約者は親属(Angehöriger)の一種にして訴訟上証言義務を免除さるとする。2)
1) Dittenberger, Verlöbnisr. 5.
2) Wolff, Familienr. (1928) 19.
ロ 婚姻締結の義務は、ロォマ法では、訴求するわけにいかなかつた。1)教会法はこれに反し、訴を以て相手方に婚姻締結を請求することができるとし、2)ドイツ普通法も、教会法の影響を受けて締結の訴を認め来つたが、今はどこの国も純粋ロォマ法の主義にかへり、婚姻締結の訴を排斥する。3)違約金約款も、相手方の自由意思を妨げるので無効である。4)
1) D., 24, 2, 2, 2.
2) Dittenberger, 7.
3) Dittenberger, 9.
4) BGB. 1297---ZGB. 91---ABGB. 45---Spanien, C. c. 43---婚約につき明文を置かない国では、学説を以て違約金約款を否定してゐる。
ハ 婚約者が婚約中性交(copula carnalis)に入ることがある。教会法は一時——十二・三世紀のころ——性交と同時に婚約は、婚姻に一転するものなりと見たが、後にこの見解をすてた。1)現代法は婚約者の性交を一般の和姦と同視し、法的干渉の外に放任する。よつて何の法律効果も生じない。もしそれ当事者の一方が婚約を手段として相手方を性交に誘つた場合は貞操蹂躙となり、慰藉料等の問題を起すこともちろんである。2)
1) Friedberg, Kirchenr. 477 fg.
2) 拙著・人格権法の発達・五五以下。
ニ 婚約者が婚約中同棲を実行することがある。が、在来の法制は同棲なる事実に別だんの法律効果を附与しなかつたから、同棲的婚約者も婚約上の義務、すなはち正式結婚の義務を負ふに止まつた。今日の法制は同棲なる事実を重視し、同棲者を内縁法律関係に立たしめる結果、同棲的婚約者は二重の義務を負ふ。婚約上の義務と内縁者としての義務と、これである。すでに同棲を開始したからとて婚約本来の義務を免れるわけに行かない、正式結婚を拒否すればやはり予約違反となる。1)
1) 大正四年一月二十六日大審院民事聯合部のなしたいはゆる『婚姻予約有効の判決』は、同棲的婚約者が婚約に違反し婚姻届をなすことに協力しなかつた場合に関してであつた。単なる婚約者に関するにあらず、単なる内縁者に関するものでもなかつたのである。
二三 解除
ロォマ法も理由ある解除と理由なき解除とに分けてはゐたが、その理由なるものをかなり寛大に考へてゐた。近代法もあまりこれを限定せず、凡て婚約の継続又は履行を強ゐることが酷である場合には、正当に解除することができるものと見てゐる。1)離婚原因に該当する事実ある場合はもちろん、さまで重大ではないが、とにかく暴行・侮辱乃至品行上の嫌疑あるとか、相手方の不具なること・難病持ちなることを婚約後発見したとか、重大なる事情の変更が婚約後相手方の身上又は財産上に起きたとかいふ場合には正当に解除しうとしてゐる。2)
1) BGB. 1298 Abs. 3---ZGB. 92.
2) Vgl. Preuss. Ldr. II, I, 100--111.
二四 損害賠償
イ 理由なき解除、すなはち違約の場合には、違約者に対し損害賠償を請求しうるか?ロォマ法は消極説をとつたが、ドイツ普通法は、婚姻締結の訴の補充としての損害賠償請求を認めた。けだし婚姻締結を命じたところで、被告が頑強に履行を拒めば、事実何んともできぬので、被告に履行の誠意なきときは、原告は締結の訴の代りに賠償の訴を起しうるものとしたのである。後には締結の訴滅び、賠償の訴ばかりとなつた。1)オォストリア民法ザクセン民法等は賠償の訴のみを認めた。2)
1) 普通法の判例は賠償の訴を締結の訴の補充と見たが、事実は賠償の訴ばかりであつた---Seuffert's Archiv 27, 37--30.
2) ABGB. 46---sächs. GB. 1579, 1581.
ロ 賠償範囲に関しては、破約者は信頼利益の賠償をなせば足る。すなわち相手方又はその親が、婚約を信頼したるがためになすに至りし出費を賠償すれば足る。1)2)親が式服を注文したとか、料理を注文したとか、新郎が新婚生活のために借家したとか、新婦が妻となるだらう予想の下に、女教員の職を抛つたとかいふごとし——履行利益の賠償までする必要はない。例へば夫となりそこねたため、妻の財産に対する収益権を取得できなくなつたとか、妻となりそこねたため夫からの扶養を受けえなくなつたとかいつてきても、それに応ずる必要はないのである。親をも保護する理由は、将来の婚姻のため出費するのは、多くの場合、婚約者自身でなくして親であるからである。3)
1) Sächs. GB. 1581---BGB. 1298---ZGB. 92.
2) 『当事者ノ一方カ正当ノ理由ナクシテ其約ニ違反シ婚姻ヲ為スコトヲ拒絶シタリトセンカ之レカ為メニ相手方カ其約ヲ信シテ為シタル準備行為ハ徒労損失ニ帰シ其品位声誉ハ毀損セラルル等有形無形ノ損失ヲ相手方ニ被ラシムルニ至ルコトナシトセス是レ其契約ノ性質上当ニ生スヘキ当事者ノ婚姻成立予期ノ信念ニ反シ其信念ヲ生セシメタル当事者一方ノ違約ニ原因スルモノナレハ其違約者タル一方ハ被害者タル相手方ニ対シ如上有形無形ノ損害ヲ賠償スル責任アルコトハ正義公平ヲ旨トスル社会観念ニ於テ当然トスル所ニシテ法律ノ精神亦之ニ外ナラスト解スヘキヲ以テナリ』(大四・一・二六・大判・民録五三)——本件は単なる婚約違反にあらず同棲を伴ふ婚約の違反であつたから(二二ノ二註1)参照)、大審院は信頼利益の賠償の外、精神苦に対する慰藉料支払をも命じたのであらう。単なる婚約の違反だけなら、精神苦に対する慰藉の問題は起らぬ筈であつた(Vgl. BGB. 1300)。
3) Motive, IV, 4.
ハ 相手方に解除の理由を与へた者、すなはち自己の有責行為によつて相手方を解除へ誘つた者は、違約者と同一視され、損害賠償の責を負はされる。1)さうでもしないと、違約を欲する狡猾者が、自分の方から違約せずに、乱暴でもして相手の方から解除させ、以て賠償なしに目的を達する、といふ不都合を生じるかも知れぬので。
1) Preuss. Ldr. II, I, 120---sächs. GB. 1581---BGB. 1299---ZGB. 92.
二五 結納の返還
ロォマ法では婚約者は、婚約解除の後互に婚約証拠品(指環)および婚約贈与品を返還することを必要としたが、1)近代法またこの例を襲ふ。2)けだし贈与品は、贈与を原因とした給付に相違ないが、婚約解除と同時に贈与は取消され、贈与品は原因を失ひ、不当利得となるに至るからである。3)4)
然らば違約した者若くは解除の原因を作つた者へも、やはり証拠品や贈与品を返還せねばならぬか?ロォマ法は違約者等へは返還の要なしとしてゐたが、5)これは同法が違約者に損害賠償の義務を課さなかつたため、その代償として贈与品の没収を行ふ必要があつたからで、近代法のやうに賠償義務を認めると、実はもう贈与没収の理由もないのであるが、因襲の久しき、多くの立法は、今でも没収といふロォマ的罰を存置す。6)
1) C., 5, 3, 15.
2) Preuss. Ldr. II, I, 122---sächs. GB. 1584---BGB. 1301---ZGB. 94---ABGB. 1247.
3) 『結納ナルモノハ他日婚姻ノ成立スヘキコトヲ予想シ授受スル一種ノ贈与ニシテ婚約カ後ニ至リ当事者双方ノ合意上解除セラルル場合ニ於テハ当然其効力ヲ失ヒ給付ヲ受ケタル者ハ其目的物ヲ相手方ニ返還スヘキ義務ヲ帯有スルモノトス』(大六・二・二八・大判・民録二九三)。
4) 近時大審院は、結納授受の契約は常に必ずしも『後日法律上有効ナル婚姻成立セサルトキハ効力ヲ失フヘキ趣旨ノ解除条件附契約』なりといふことをえずとなし、同棲実行の場合は、未だ婚姻の成立を見るに至らざりしときといへども、契約の効力確定し、授者は、結納の返還請求権を失ふに至ると見た(昭和三年(オ)九〇四号)。
5) C., 5, 1, 5.
6) Preuss. Ldr. II, I, 122---sächs. GB. 1585---BGB. 1815.
第四節 結婚方式
結婚の方式に関する規定は、教会で発達した。けだし教会は、適法の結合と違法のそれとを峻別するために厳格な方式を立て、方式に従つて締結されたもののみを婚姻と見たのであつたが、近代法またこの主義に倣つてゐるからである。方式の内容も、僧侶の代りに世俗官吏が立会ふに至つたといふまでで、あまり大した相違を見ない。
二六 ロォマ法
ロォマ法では、婚姻は当事者間の単なる合意で成立した。官庁の面前での表示を要せず、届出さへ要しなかつた。手紙や使者で婚姻意思を表示することもでき、儀式の挙行・同棲の実行等によつて暗黙の間に婚姻意思を実現することもできた。とにかく婚姻意思の合致さへあれば、婚姻の成立となつたのである。1)
1) D., 35, 1, 15---D., 23, 1, 66---C., 5, 4, 22.
二七 教会法
イ 旧教会法では、婚姻は当事者間の要式の合意で成立した。方式の内容は、当事者がその一方の住所地を管轄する僧侶の面前において、二人若くは三人の証人立会の下に、婚姻意思を表示することであつた。この方式を践まざれば、たとへ当事者間に夫婦関係の創設に向けられた意思の合致があつても婚姻の成立を見なかつた。方式が法定の表示方法であり、方式を践まざれば表示なきに等しかつたからである。反対に方式さへ践めば真意のこれに伴ふと否とはしばらくおき、婚姻の成立を見た。方式による表示の有無が婚姻意思の存否を認定する唯一の標準であり、方式による表示ある以上、婚姻意思ありと認定せざるをえなかつたからである。尤も真意のこれに伴はざるものある場合には、表意者は、真意欠缺を立証して表示を取消すことをえたが、取消あるまでは婚姻存在した。
ロ 新教会も十八世紀ごろから、やはり要式主義をとり、二人以上の証人を帯同して管轄牧師の面前にあらはれ、互に婚姻意思を交換せざるべからずと定めた。1)
1) 拙著・二主義の抗争・一四九以下。
二八 近世法
近世諸国の法律も旧教会の主義を踏襲し、当事者自ら身分吏の面前において二人以上の証人立会の下に互に婚姻意思を表示することを要すとする。分説すると、自身出頭を必要とし、使者を許さない。同時出頭を必要とし、別々に出頭することを許さない。身分吏は新郎新婦のいづれか一方に対し、他方と婚姻に入らんことを欲するやを問ひ、『然り』の答をえてから同様の問を他方に発し、同じく『然り』の答をえた上、『なんぢらは民法の規定に従ひ婚姻に入りたり』と宣言する。最初の然りは、外見上身分吏に対してゐるが、その実は乙女に対する甲男の婚姻申込に外ならず、後の然りも外見上は身分吏に対してゐるが、その実は甲男に対する乙女の婚姻承諾に外ならず、身分吏は申込および承諾を誘発する作用を営むに止まると見られる。従つて身分吏の問を俟たず、直接に婚姻意思を交換し合つても、身分吏の面前でなしさへすれば、やはり婚姻の成立を来たすのである。また婚姻は申込および承諾の合致せる時に成立するから、『なんぢら云々』の語は宣言的にして創設的にあらず、従つて身分吏これをいふを失念しても、婚姻の成立を来たすに何ら差支ないのである。最後に身分吏は、当事者の氏名その他を詳細に婚姻簿に登録し、当事者証人等をしてこれに署名させるが、署名の際、女は夫の姓を使用する。登録前意思の合致ありたる時においてすでに婚姻成立し、妻となつてゐるからである。1)2)登録は証拠保全のために過ぎない。
1) BGB. 1317 fg.---ZGB. 116 fg.---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 4. Kap. 8---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 27---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 36---C. c. 165 fg.---Italien, C. c. 93 fg.---Niederlande, BWB. 126 fg.---Spanien, C. c. 86 fg.
2) 緊急のため、官庁の協力なしに結婚することがある。臨終の際、今まで内縁の妻だつた女を正妻に直したくおもふも、官庁へ出頭する力なしといふやうな場合である。旧教会法はこれを緊急婚(Notehe)といひ、この場合には僧侶の力を借らず、証人の立会のみえて結婚することができるとしてゐた。現代でも緊急婚を認めるものがある。ブラヂル・アルゼンチン等のごとし。
二九 わが民法【七七五条】
わが民法に対しては、教会法の影響著しく稀薄である。なぜなればわが国においては、当事者双方が二人以上の証人を帯同して身分吏の面前に自身出頭し、互に婚姻意思を交換するといふ・あの古典的な儀式を行ふことの必要なく、簡単に一片の届出書で足るからである。『当事者双方及ヒ成年ノ証人二人以上ヨリ署名シタル書面ヲ以テ』婚姻を届出れば足るからである【七七五条二項】。が、全然教会法的影響を留めないといふほどでもない。書面主義と共に教会風の要式口頭主義も併置されてゐるからである【七七五条二項】。『証人二人以上』といつてゐる点なども、教会法のなごりといへばいへるであらう。
三〇 ロシア法とわが改正要綱
イ 一九二七年一月一日施行ソヴェート・ロシア新婚姻法も、届出主義を採用し、書面届出を以て婚姻に入りうとした。1)また事実上の婚姻をも認め、夫婦的同棲(eheliche Zusamenleben)あれば、法律上当然に婚姻の効果を生ずともした。前者を登録婚(registrierte Ehe)後者を無登録婚(nichtregistrierte Ehe)といふ。同棲・家計共同・相互扶助・子の共同養育・第三者に対する夫婦関係の表示等あれば、届出の有無を問はず、当事者の意思いかんを見ず、法は二人を夫婦と認めるのである。2)
1) Sowjetrussl. G. v. 19/11 1926 2---登録婚をも併用した理由に曰く、『動もすると家計を共通にし、同一場所に同棲する機会がなく、従つて夫婦が一時離れ離れに生活しなければならないことがある。例へば赤軍の若い兵士は、誰でもをして自分の愛せる婦人を以て自分の妻なりと知らしめたいと欲してゐる。されば登記をして何等の説明をなす必要がないやうにして置くことがよろしい。文書は万事を立証する。その方が妻にとつても容易であり、幼児にとつても容易である。両者共に法律の前で保護を加へられる。之れ我々が登記をなさしめる所以である』(木沢・ソヴィエット聯邦婚姻法成定の行緯・法律春秋四ノ四)。
2) Sowjetrussl. G. v. 19/11 1926 12.
ロ わが改正要綱も登録婚の外、無登録婚をも認めようとしてゐる。しかしロシアのやうに一切の同棲者に婚姻効果を附与しようといふのではない、『慣習上認メラレタル儀式ヲ挙ケタル男女』だけに、婚姻効果を附与しようといふのである。それだけ不徹底といはねばならぬ。なぜなれば儀式なしに同棲に入る者少からず、儀式は挙げたが、その儀式たる、一向慣習的のものでなかつたといふ場合(富士山顛の結婚・飛行機上の結婚)とあるからである。無登録婚を認める趣旨は、すべて同棲者に夫婦関係を認めようといふにある。故に儀式の有無を問題とすべきでない。
がともかく、現行法が、書面による届出で足るとしてゐるだけでも、かなり教会法を離れてゐる。さらにいま無登録婚をも認めようとするのは勇敢な教会主義の抛擲である。教会主義の衰退ロォマ主義の復活は、婚姻法の全面に漲る一大潮流であるが、わが国はロシアと共に、この傾向の尖端を切つてゐるわけである。
第五節 内 縁
前節においてソヴェート・ロシアの新婚姻法は、同棲を婚姻と同視し、これに婚姻効果の全部を附与すといつたが、かくまで極端ならざるも、婚姻効果のあるものだけは同棲にも附与してゐる立法がある。それを内縁制度とする。
内縁制度はロォマで発達した。そうしてその後長い間殆ど全く姿を没してゐたが、近時再び出はじめた。
三一 ロォマの内縁
ロォマ法は、同棲を婚姻に準じ、これにある種の婚姻効果を附与してゐた。けだし婚姻の効果に二種ある。一は当事者間の性的結合を確保するための効果であり、二は当事者の一方を他方の親族と連絡させるための効果である。扶養の義務とか、貞操の義務とかは前者に属し、夫婦は互に他を相続すとか、生れる子が嫡出子となるとか、一方が他方の血族と姻族関係に立つとかいふの類は後者に属するが、ロォマ法は、当事者本位の婚姻効果だけを内縁に附与し、親族団本位の効果は婚姻に特有としてゐたのである。具体的にいふと、内縁の夫も扶養の義務を負ひ、内縁の妻も貞操の義務を負つた。しかし内縁夫婦間には相続権なく、一方が他方の血族と姻族関係に立つといふこともなく、生れた子が嫡出子になるといふこともなかつたのである。その理由は、これらは親族団本位の法律効果であるが、親族団本位の効果は、婚姻の正式的性質に由来する。故に正式に婚姻を締結しない内縁夫婦には、これを附与するわけに行かないといふにあつた。1)2)
1) 拙著・二主義の抗争・二四〇以下。
2) 内縁効果は当事者の意思いかんを問はず発生した。同棲といふ事実上の結果さへ実現されてあれば、当事者の意思に反しても、法は二人を内縁法律関係に結びつけたのである。意思を基礎とせず、事実上の結果を基礎として法律効果を附与したのである。約していへば内縁は契約でなく、事実行為(Tathandlung)であつたのである。
三二 教会法および近世法
イ 教会は内縁を否定した。適法結合の典型はただ一つ婚姻のみ、他は一様に野合なりと見た。近世法も同じ主義をとり同棲なる事実を法的に承認することをしない。十六・七世紀、警察国の時代には、同棲は一種の犯罪であり、風紀警察の問題でさへあつたのである。1)
1) 拙著・二主義の抗争・二四九以下。
ロ しかし前世紀の半過ぎから、少くともこれを犯罪とは見ぬやうになつた。例へばオォストリアの行政裁判所は、同棲は私事のみ、警察の取締るべき対象にあらずと判示した。一九二〇年同国の遺族扶助法に至つては、被害者死亡の以前、少くとも二ヶ年これと同棲せる婦女は妻に準ずとし、同棲女にも遺族扶助料を認めた。一九二一年の同国税法も、担税者と永続的に家計を共通にする婦女は妻に準ずとし、同棲女を独立の担税者とは見ぬことにした。1)自余の諸国も遺族扶助料請求権については大抵同棲女を正妻に準じてゐる。2)
わが鉱業法八十条も、鉱業権者は鉱夫が業務上死亡したる場合には、その死亡の当時鉱夫の収入に依りて生計を維持したる者を扶助すべしと規定し、工場法十五条また同一趣旨を規定し、同棲女にも遺族扶助料請求権を認めてゐる。
1) Ehrenzweig, Syst. d. allg. Privatr. II, 2. 4 fg.
2) Rechtsvergleichendes, Handwörterb. II, 687.
ハ しかし同棲者の問題は、単に同棲女に遺族扶助料請求権を認めるだけで足りるだらうか?扶養請求の権利義務・性的忠実の権利義務・同居の権利義務・日常家事の代理権等をも認める必要がないであらうか?いひかへれば婚姻効果の規定の少くとも一部分は、これを同棲者に準用する必要がないであらうか?余はおもふ、今日世界の各国は同棲の問題——いはゆる友愛結婚(Kameradschaft)の問題——に悩まされてゐるが、これを解決する法的手段はただ二つ、ロシアのやうに同棲を婚姻そのものと見、これに婚姻効果の全部を附与するか、ロォマのやうに同棲を準婚(Quasiehe)と見、これに婚姻効果のあるものを附与するかであると。前の手段をとると、同棲者は扶養義務・同居義務等を負ふはもちろん、互に他を相続もし、他方の血族と姻族にもなり、生れた子とも嫡出関係に立つに至るが、後の手段をとると、単に扶養・同居・貞操・家事代理権等、当事者本位の法律効果を発生するだけで、相続・姻族・嫡出等の関係は起さぬのである。二者いづれを可とするやは問題であるが、いづれにせよ、教会風の婚姻一元主義が老廃観念となりつつあるは事実である。1)
1) すでにわが国の判例は、夫婦扶養義務の規定(七九〇条)又は婚姻費用負担の規定(七九八条)を内縁に準用し、内縁夫婦もまた扶養の義務を負ふとしてゐる。曰く——『法律上夫妻関係発生セストスルモ、事実上婚姻関係ノ持続スル以上ハ、夫ハ一家ノ生活費用ヲ負担セサルヘカラス』(明・四二・一二・一五・東地判)——『未タ婚姻ノ届出ヲ為ナササルモ相当ノ儀式ヲ挙ケ夫婦ノ事実存スル場合ニ於テハ、其一方ハ自己ノ負担ニ於テ他ノ一方ヲ扶養スヘキ筋合ナリ』(大・一一・六・三・大判)。
第六節 結婚の無効および取消
婚姻の無効および取消に関する規定は、教会で発達した。教会は例の婚姻維持の大原則(Prinzip der möglichsten Aufrechthaltung der Ehe)から、婚姻の無効取消を最小限に制限しようとし、婚姻のために特別な無効取消規則を作つたのであるが、それが殆どそのまま現代に伝つてゐるからである。
第一項 意思欠缺婚
意思欠缺婚とは、婚姻届に相当する真意を欠く場合である。当事者の一方又は双方が、故意に非真意の婚姻届をなした場合もあり、不慮の間に非真意の婚姻届をなしてしまつたといふ場合もあらう。心裡留保婚・虚偽婚は前者に属し、表示錯誤婚は後者に入る。
三三 心裡留保婚【七七八条以下】
イ 心裡留保婚とは、当事者の一方が婚姻届に署名はしたが、夫婦となる真意はなかつたといふ場合である。この場合署名者は、真意の伴はざりしことを理由として、届出の無効又は取消を主張しえたかといふに、少くとも新教会の法律はこれを許さなかつた。1)けだし相手方および第三者は、表意者の真意を知らず、ただ彼が方式に従つて表示したのを見て、婚姻の成立を欲したものと認め易いからである。近代法も新教会の主義を襲ひ、表意者は心裡留保を理由として無効又は取消を主張することをえないとする。2)わが民法上またさうである。なぜなれば民法は七七八条において『婚姻ハ左ノ場合ニ限リ無効トス』とし、七七九条において『婚姻ハ後七条ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス』とし、無効および取消の場合を、特に限定しつつ、しかもその限定された場合の中へ、「心裡留保」を算へ込んでをらぬからである。
1) 拙著・二主義の抗争・一七八以下。
2) C. c. 180 fg.---BGB. 1323 fg.---ZGB. 120 fg.---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10. Kap.---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 31---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 42 fg.
ロ 相手方が、表意者の表示の真意に合せざることを知りし場合、すなはち相手方が悪意なりし場合はどうかといふに、多くの立法は、取引契約上の留保表示は、相手方悪意の場合無効となるとしたが、婚姻についてはこの例外さへも許さなかつた。1)方式に従つて婚姻意思を表示した上は、もはや非真意の抗弁提出の余地がない、たとへ相手方が悪意だつたとしても、表意者は表示に拘束されねばならぬと見たのである。わが民法も、取引契約上の留保表示は相手方悪意の場合無効となるものと定めてゐるが【九三条二項】、婚姻に関しては絶対に心裡留保の抗弁を許さず、故意に真意に反する婚姻届を提出した者は、心ならずもその相手方と夫婦とならざるをえぬとしてゐるのである【七七八条以下】。
1) C. c. 180 fg.---BGB. 1323 fg.---ZGB. 120 fg.---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10. Kap.---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 31---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 42 fg.
三四 虚偽婚【七七八条以下】
虚偽婚とは当事者双方が届出はしたが、同時にその無効を密約しておいたといふ場合である。かかる場合に当事者は婚姻の無効又は取消を主張しうるかといふに、少くとも近世の法律はこれを許さぬ、取引契約においては、虚偽無効の抗弁を許すが、婚姻においては、恰も心裡留保の抗弁を禁ずるごとく、虚偽無効の抗弁をも禁ずるのである。方式に従つて公に締結された行為が、私の密約によつてその効力を左右されてはならないからである。1)
わが民法も、婚姻の無効取消の許される場合の中へ、虚偽表示を算入してをらぬ【七七八条以下】。故にわが国においても虚偽婚は無効とならず、取消すこともできぬであらう。2)
1) 拙著・二主義の抗争・一七八以下---Wolff, Familienr. 1928 74.
2) わが民法の判例は不法目的に出た縁組を、虚偽縁組の名の下に、無効にしてゐる——『兵役義務ヲ免ルルノ目的ヲ以テ合意上表面仮装ノ縁組ヲ為シタル場合ニハ縦令其登録アルモ当事者間ニ縁組ヲ為スノ意思ナキヲ以テ其縁組ハ無効ナリトス』(明・三九・一一・二七・大刑判・録一二・一二八八)——『養子縁組カ養女ヲシテ芸妓稼業ヲ為サシムルノ便宜ニ出テタル仮装ノモノニシテ真ニ当事者ニ親子関係ヲ発生セシメントスル意思アリシニアラサルトキハ其縁組ハ無効トス』(大・四・二・八・東地判・評論四ノ一・民・四二)。
三五 表示錯誤婚【七七八条一号】
イ 表示錯誤婚とは、欲せざる婚姻届を不慮の間に出してしまつた場合である。或は相手方の同一性を誤つてゐることがある。届出には甲氏の長女春子と結婚すると書いたが、それは春子と秋子とを人違したためで、真意においては、次女秋子との結婚を欲してゐたといふごとし。或は届出の種類を誤ることがある。婚姻届を出してしまつたが、実は寄留届のつもりで署名してゐたといふごとし1)【七七八条一号】。
1) 拙著・二主義の抗争・一八七以下
ロ 教会法も近世法も、錯誤者だけはさすがに救つた。錯誤は、心裡留保や虚偽表示と異り、故意から出ずに不慮から出で、同情の余地多いからである。しかし錯誤婚の救済方法は、錯誤表示一般の救済方法と、やや趣を異にしてゐた。錯誤表示は無効となつたが、錯誤婚は取消しえたに止まつた。錯誤はあるにせよ、方式に従つて表示され、公簿上にも登録されてゐるので、当然には無効とならない、取消判決によつて失効するに過ぎないと見たためである。1)
尤も言葉の上では、今日もなほ無効婚(nichtige Ehe)といつてゐるが、それは教会法が、無効婚(matrimonium nullum)の語で取消婚を意味してゐた例に倣つたためで、語こそ無効だが、実は『無効となしう』(vernichtbar)の意味、すなはち『取消』の意味に外ならぬのである。『当然無効』の意味ではないのである。当然無効の意味をあらはすためには、教会法は、不存在婚(matrimonium non existens)といつてゐた。
1) C. c. 180---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 Kap. 10 3---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 35 2---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 44 2.
ハ わが民法も『人違其他ノ事由ニ由リ当事者間ニ婚姻ヲ為ス意思ナキトキ』は、『婚姻ハ無効トス』といつてゐる【七七八条一号】。『人違其他ノ事由ニ由リ当事者間ニ婚姻ヲ為ス意思ナキトキ』とは、『表示上ノ錯誤アリタルトキ』の意味であり、『無効トス』とは、『無効トナシウ』の意味である。通説がこの『無効』を、当然無効の意味に解してゐるのは正しくない。1)
1) 婚姻取消に公益取消と私益取消とある。前の取消権は、公益違反婚を取消すためであるから、当事者・双方親族・検事にまでも与へられるが、後の取消権は、被害当事者救済のためであるから、被害当事者自身に与へられるに過ぎぬ。前者の効果は既往に遡り、初めより婚姻なかりしものとするが、後者は婚姻を将来に向つて取消すに過ぎぬ。私益取消権は追認によつて消滅するが、公益取消には追認なし。無効の語の廃れない一つの理由は、私益取消を単に取消すといふに対し、公益取消を単に無効とよばんがためである(拙著・二主義の抗争・一九三)。
三六 表見婚【七七八条二項】
表見婚(Scheinehe)とは、婚姻がその成立要件を欠くにかかはらず、従つて真実には成立してをらぬにもかかはらず、婚姻簿上、婚姻成立せりとして登録されてゐる場合である。身分吏が勝手に登録したとか、子の知らぬ間に親が婚姻届を作つて登録したとかいふごとし。
教会法は表見婚を当然無効とせず、取消うるに止まるとした。1)近代法も同一主義をとる。公簿上に存在を有し第三者から信頼されてゐる関係上、当然無効とはなりえぬのである。2)
わが民法も、『当事者カ婚姻ノ届出ヲ為ササルトキハ』は『婚姻ハ無効トス』といつてゐる3)【七七八条二号】。『当事者カ婚姻ノ届出ヲ為ササルトキハ』とは、『他人カ婚姻ノ届出ヲ為シタルトキ』の意味であり、『無効トス』とは、『無効トナシウ』との意味である。通説がこの『無効』をも当然無効の意味と解してゐるのは、やはり正しくない。3)
1) Friedberg, Kirchenr. 464.
2) C. c. 191---Italien, C. c. 104---BGB. 1324, 1329.
3) 『原判決ノ認メタル事実ニ依レハ被上告人ハ一旦上告人ト結婚ノ式ヲ挙ケタルモ式後僅ニ二三日ニシテ実家高橋藤作方ニ立チ帰ヘリ上告人ト同棲スルコトヲ拒絶シ之レト婚姻ヲ為スノ意思ヲ有セサルニ拘ハラス上告人ハ婚姻届ヲ為スニ於テハ被上告人モ意思ヲ翻シテ同棲スルニ至ルヘシト思惟シ被上告人ノ父母ニ請ヒテ婚姻届ニ調印ヲ受ケ且被上告人ノ承諾ナキニ父藤作ニ於テ該届書中被上告人ノ名下ニ擅ニ調印ヲ為シ以テ戸籍吏ニ届出テタリト云フニ在リテ即チ其婚姻届ハ被上告人ノ承諾ナキニ拘ハラス父藤作ニ於テ擅ニ之カ届出ヲ為シタルモノニシテ其婚姻ハ民法第七百七十八条ニ依リ無効タルヤ明ナリ』(大・九・九・一八・大判・録・一三七八)。
『一時賜金及遺族扶助料ヲ受クル目的ヲ以テ親族等相謀リ出征軍人ノ意思ニ依ラスシテ他ヨリ幼者ヲ貰受ケ、養子縁組届ヲ為スモ其養子縁組ハ無効ナリ』(明・四〇・五・二七・大控判・新聞・四三四・八)。
『戸主カ闘病ノ為メ到底家政ヲ執ル事能ハサルニ付キ親戚等相図リ戸主ノ弟ヲシテ家政ヲ処理セシムル為メ戸主ノ養子トシテ縁組届出ヲ為シタルカ如キハ当事者ニ於テ養子縁組ヲ為ス意思アリシ者ト謂フ事ヲ得ス従テ其養子縁組ハ無効ナリトス』(秋田地判・新聞・九三四・二二)。
『無効ナル養子縁組ハ戸籍簿ニ登録セラルルモ之ニ因リテ何等の効力ヲモ生セサルモノトス養子縁組ノ無効ハ第三者ト雖モ之ヲ主張シ得ルモノトス』(大・四・一〇・一八・大判・録・一六五)。
第二項 意思瑕疵婚
意思瑕疵婚とは、結婚意思の発表過程に欠点なく、むしろその成立過程に欠点のあつた場合である。結婚意思は届書に正確に発表されたが、元来その結婚意思たる、不正常な判断の所産だつたといふ場合である。誤れる判断を前提としたため、その決意をなすに至つたとか、他人の不正干渉に影響されてその決意をなすに至つたとかいふがごとし。動機錯誤は前者に属し、詐欺強迫は後者に入る。
三七 動機錯誤婚
イ 結婚の決意に対して、動機として作用する判断は数多い。相手方が美人であるとか・品行方正であるとかいふ人的性質に関する判断も前提となり、相手方の門地が高いとか・財産があるとかいふ外部事情に関する判断も前提となる。故に動機として作用したところの判断に誤謬があつたからとて、一々取消を許さば、婚姻の安全、全く破壊されてしまふであらう。故に適度に錯誤取消を制限するの必要があるが、
ロ まづ旧教会は一切の錯誤取消を排斥した。外部事情に関する判断に誤謬ありしに過ぎなかつた場合はもちろん、人的性質に関する判断に誤謬があつた場合にも、なほ婚姻を取消すわけには行かないとしてゐた。新教会に至つて少しく錯誤者を救済したが、取消の許されたのは、せいぜい相手方に破廉恥罪の前科ありしことを知らなかつた場合とか、相手方の処女性を誤断してゐた場合とかに限られ、それ以外に出なかつた。1)
1) 拙著・二主義の抗争・二〇〇以下。
ハ 近代の法律も、外部事情の錯誤(Umstandsirrtum)は全くこれを救済しない。相手方の門地・家系を誤認したとか、学歴・財産状態を誤認したとかいふに過ぎぬ場合には、取消の道全くないのである。人的性質の錯誤(Eigenschaftsirrtum)も多くは取消の理由とならない。存外相手方が愚鈍だつたとか、病弱だつたとか、嫉妬深かつたとか、浪費好きだつたとかいふことを後から発見しても、婚姻を取消すわけにはゆかぬのである。が、元来その相手方が、錯誤者のやうな人の、配偶たるに適せぬ種類の人間だつたといふことを、あとで発見した場合には、取消すことができる。例へば嫌悪すべき皮膚病の人、重い結核の人、梅毒又は性交不能症の人は、凡そ身体の正常な人の配偶たるに適しない、故に結婚後この種の身体欠陥を相手方の身上に発見した身体正常の人は、相手方の種類を見誤つたとして婚姻を取消すことができるのである。同様に不治の精神病者・強度のヒステリイ者、低能者は、凡そ精神の正常な人の配偶たるに適せず、犯罪癖・強暴又は乱酒の癖ある者は、凡そ徳性の正常な人の配偶たるに適せぬので、結婚後この種の精神的又は道徳的欠陥を相手方の身上に発見した・精神又は徳性の正常な人は、やはり相手方の種類を見誤つたとして、婚姻を取消すことができるのである。1)
しかしわが民法は、全然錯誤取消を許さない【七七八条以下】。相手方の種類そのものを見誤つた場合にも、日本では、婚姻取消が許されぬのである。2)
1) BGB. 1333---ZGB. 124 Nr. 2---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10 Kap. 3 Nr. 3---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 35 Nr. 3 u. 4---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 44. Nr. 3.
2) 拙著・二主義の抗争・二一六。
三八 強迫婚【七八五条】
強迫婚とは、相手方又は第三者の強迫によつて結婚意思を決定した場合である。
教会法もこの場合は取消を許してゐた。親の強迫によつて子が婚姻を決意したといふ場合にさへ、被強迫者たる子に婚姻取消権を与へてゐた。近代法また然り。1)
1) BGB. 1335---ZGB. 125 Nr. 1---Schweden, Eheg. v. 8/6 1904 10 Kap. 3 Nr. 5---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 35 Nr. 6---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 44. Nr. 5.
三九 詐欺婚【七八五条】
詐欺婚とは、詐欺にかかつて相手方の欠点を看過した場合である。
旧教会は詐欺婚を錯誤婚の一種と見、特別の救済も講じなかつたが、新教会は二者を区別し、詐欺婚の取消を、特に一層容易にした。例へば相手方の門地・家系を単に錯誤したに過ぎぬ場合には、婚姻取消を許さなかつたが、詐欺によつて錯誤した場合には、取消を許したのである。けだし詐欺は自己の軽卒によらず、他人の欺罔によつて誤断したもので、同情救済の余地多いからである。
近代法においても詐欺婚の取消は特別容易であり、人の種類を詐欺された場合にはもちろん、その瑕疵を詐欺されたに過ぎぬ場合にも、なほ被害者は取消救済を受けるのである。例へば新郎がその再婚なることを秘したとすると、再婚者が初婚者の配偶たりえないといふわけではないのであるから、配偶資格上の種類を詐欺したものとはいへぬが、にもかかはらず彼は新婦から婚姻を取消されることを免れぬのである。なぜなれば再婚者であるといふことは、配偶資格上の一瑕疵には相違なく、従つて種類は詐欺せぬが、瑕疵は隠蔽したといふことになるからである。新婦がその家系賎しきことを秘した場合・精神病の血統あることを秘した場合にも瑕疵の隠蔽あり、従つて婚姻を取消されることを免れぬのである。1)2)
わが民法も、錯誤婚の取消は許さぬが、詐欺婚の取消はさすがにこれを許す3)【七八五条】。
1) BGB. 1334---ZGB. 125---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10 Kap. 3 Nr. 4---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 34 Nr. 5---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 44. Nr. 4.
2) Reichsg. Entsch. 34, 124.
3) 『抑モ旧穢多ハ往古ヨリ最モ卑賎ノ一種族トセラレ、一般人民ハ歯スルヲ得サリシモノニシテ之ト婚姻ヲ交フルヲ嫌忌スルハ今日ト雖モ旧穢多ニ非サル者ノ普通ノ情態ナレハ旧穢多ノ家ニ生レタル事実ヲ隠蔽スルノミナラス実家ハ血統正シキ旧家豪農ナリト称スルハ詐欺ニシテ婚姻取消ノ原因ト為ルモノナリ』(明・三五・一二・一七・広島控・新聞・一三〇・七)。
第三項 追認と善意保護
四〇 追認【七八五条二項】
イ 追認の規定は新教会で発達した。けだし追認は瑕疵婚の維持を欲する取消権者の意思の表現であるが、新教会は旧教会よりも、取消権者の意思の力をはるかに重く見たのである。取消権者自ら、その維持を欲するのなら、瑕疵婚といへども維持させてやらうと考へたのである。1)
近代の立法も新教会の主義をとり、被強迫者・被詐欺者および錯誤者に、瑕疵婚追認の権を認める。彼らは、明示又は黙示にこれを追認し、瑕疵婚を完全有効のものたらしめることができるとしてゐる。2)わが民法また然り【七八五条二号】。
1) Friedberg, Kirchenr. 465.
2) BGB. 1325---C. c. 183---Italien, C. c. 109---Niederlande, BWB. 146.
ロ 瑕疵婚の取消権は一定期間の経過により当然に消滅する。通例六ヶ月、1)わが民法上は三ヶ月【七八五条二項】。
1) C. c. 181---BGB. 1339---ZGB. 127---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10 Kap. 3 ---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 35---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 44---Spanien C. c. 102.
四一 善意保護【七八七条二項】
イ 善意保護の規定は教会法に出る。同法は取消権の附着を知らずに結婚した善意の当事者を救ふために、取消された婚姻もまた、善意者のためには、普通の婚姻効果を生ずとしてゐたのである。1)善意婚(Putativehe)といふのがそれである。
近代の法律も同じ主義をとり、善意者を取消の影響の上に超越させる。例へば夫が悪意者だつたとすると、彼は遡及的に夫たらざりしものとなり、従つて夫として取得したところの利益(例へば妻の財産を使用収益することによつてえた利益)を全部返還しなければならないことに立ち到るが、善意者たる妻の方は、将来に向つて妻たる地位を失ふだけで、既得の利益(例へば既に受けた扶養)は、そのまま保持し、返還の必要がない、と定めてゐるのである。
1) Friedberg, Kirchenr. 471---子は、父母の一方又は双方が悪意なりし場合といへども、嫡出子たるの地位を失はなかつた。
2) C. c. 201, 202---Italien, C. c. 116---Niederlande, BWB. 150, 151.
ロ わが民法は、善意者保護のために取消遡及効の原則を破らず、むしろ身分関係維持のためにこの原則を破つてゐる。すなはち身分関係は、わが民法上、いかなる場合にも遡及的に消滅せず、単に将来的に消滅するに過ぎない。善意者はもちろん悪意者といへども、初めから妻たらざりしもの・夫たらざりしものとはならず、単に将来に向つてさういふ地位を喪失するに過ぎぬのである【七八七条一項】。
財産関係の方はこれに反し遡及的に消滅するので、夫婦は『婚姻ニ因リテ得タル利益ノ全部』を互に返還せねばならぬこととなるが、さすがに善意の点も参酌され、1)善意者は『現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テ』返還すれば足る2)【七八七条二項】。
1) プロシヤの州法も返還義務の範囲につき、善意を参酌したに過ぎなかつた(Preuss. Ldr. II, I, 956, 959)。
2) ドイツ民法は婚姻取消を離婚に準じ、悪意の当事者に有責離婚者と同一の責任を負はせてゐる(BGB. 1345)。スイスおよびスカンヂナビアの立法も然り(ZGB. 134---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 10 Kap. 4---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 36)。
第二章 夫婦関係の内容
第一節 人的関係
人的関係の規定は教会法において、若くは教会の思想の影響のもとに、ゲルマン諸法において、発達した。けだし教会は、例の『夫婦は一体』(Mann und Weib ein Leib)の見解から、両性の忠実を高調し、二人を一個の共同体に結びつけようとしてゐたのであつたが現代法もこの主義をとり、一体主義の上に夫婦関係法を建設してゐるからである。しかし今はロォマ風の分立主義に対する憧憬も強い。ロォマ法は夫婦を独立対等の関係に立たせてゐたのであつたが、この主義を復活して、夫婦関係法を根本的に改正すべしとの意見、漸次多きを加へつつあるのである。
四二 姓共同【七八八条】
ロォマ法は妻をして結婚後も処女時代の姓を称せしめてゐたが、ゲルマン諸法は、教会の『二人のもの一体となるべし』の教に従ひ、妻をして夫の姓を名乗らせ、二人の姓を一致させた。近代法の大多数も、妻は夫の姓を称すべしとする。1)わが民法また然り【七八八条一項】。
が、姓の共同は、夫の背後に妻を隠くすものともいへる。女子が一個独立の人格として、社会的に活動し出すと、独立の人格標表——すなはち独立の氏名——を要求してくるのである。女優・女著作家・女音楽家・女芸人等は、結婚による姓変更のために、人気および収入の上に、損害を受ける虞さへある。故に学者は、姓共同の規則を攻撃し、ロォマ法におけるごとく、妻をして処女名を続用せしむべしと主張する。2)
1) Preuss. Ldr. II, I, 192, 193---sächs. GB. 1632---ABGB. 92---BGB. 1355---ZGB. 30---Cod. Jur. Can. c. 1112.
2) Mariane Weber, Ehefrau u. Mutter in der Rechtsentwicklung, 420.
四三 住所共同【七八九条】
ロォマ法は、妻に夫と同居するの義務を課せず、夫にもまた、妻と同居するの義務を課しなかつたが、1)ゲルマン諸法は夙にクリスト教の夫婦一体の教に従ひ、同居を夫婦相互の法律上の義務とした。2)近代の法律もこれを法律上の義務とする3)【七八九条】。ただ特別の事由あるとき、例へば夫が定住なしに放浪するとき、未開地を旅行するとき、妻を扶養せざるとき、妻が疾病を有するとき、夫がその両親と同居せんと欲するも、その事が妻にとり極度に苦痛なるときは、妻は夫に追随の要なしと見る。しかし学者はいふ、今日の経済生活において、夫婦に同居を命じるのは酷である、無産階級の夫婦にとつては、同居は婚姻生活の最初でなくて最後ではないか、夫婦各別に居住して各別に働き、相当の生活基礎を作つてからやうやく住所を共同にしうるのみではないか、初めから住所を共同にすべく命じるのは、不能を命じるものである4)と。すなはち住所共同の規定も、今は時勢後れとなつて来たのである。
1) 拙著・二主義の抗争・九。
2) Grimm, Weisth, I, 85: die sind einander gnosz und erb.
3) Preuss. Ldr. II, I, 175---sächs. GB. 1633---C. c. 214---ABGB. 44---Cod. Jur. Can. c. 93 1.
4) Mariane Weber, 417 fg.
四四 性共同【七八九条】
イ ロォマ法もゲルマン法も、妻には貞操の義務を課し、ことにゲルマン法のごとき、夫もし妻の姦通現場を発見せば、殺すも罪とならずとしたほどだつたが、夫の貞操といふ観念はもたなかつた。1)教会は夫の貞操義務——性慾上の忠実義務——を高調し、その違反を夫の姦通と呼んだ。有夫の婦と通ずることばかりでなく、妻以外の女子と通ずることが一般に、「姦通」であつたのである。2)
近代の法律ではプロシヤの州法が率先して貞操の義務を平等にした。3)仏法はそのはじめ、妻のみに貞操義務を課し、且つゲルマンの古法をそのまま、妻もしその姦通現場を発見されれば、殺されても止むをえないとまでしてゐた4)が、一八八四年以来この義務を夫婦平等とした。5)自余諸国も平等主義をとる。
1) Bartsch, Rechtsstellung d. Gatten u. Mutter, 90.
2) Bartsch, Rechtsstellung, 91.
3) Preuss. Ldr. II, I, 181.
4) Code penal. 324.
5) 拙著・二主義の抗争・三四以下。
ロ 貞操義務の観念を表出する立法技術そのものの変遷を見るに、プロシヤ州法のころは、「夫婦は互に貞操の義務を負ふ」と露骨にこれを言明したが、1)ドイツ一草以来は、貞操義務と他の一切の人的義務とを一括し、夫婦は婚姻的生活共同(eheliche Lebensgemeinschaft)の義務を負ふと規定するに止まる。2)換言すれば婚姻的生活共同の義務といふ抽象的言句の中に、貞操義務をも包含させることとなつたのである。わが七八九条の同居も、独瑞法の「婚姻的生活共同」と意味を同じくし、その中に夫貞操の義務をも含むといひうるであらう。3)
1) Preuss. Ldr. II, I, 181.
2) I. Entw. 1272---BGB. 1353 1---ZGB. 159 1.
3) 拙著・二主義の抗争・二六三以下。
四五 扶養義務【七九〇条】
イ ロォマ法もゲルマン法も、夫は妻を扶養せねばならぬとはしてゐたが、妻に対する扶養の義務が、普通の親族に対する扶養の義務と根本的に異るものだといふことは、比較的近代になつてハッキリした。十九世紀の立法および同紀に入つてからの普通法の判例は、妻扶養の義務が当然に夫の地位に随伴するものだといふことを明かに認めたのである。1)それは普通の扶養義務のやうに、『受ける者の困窮』を前提とせぬ。妻に財産があり取得の能力があつても、夫はなほ且つ妻を扶養せねばならない。またそれは普通の扶養義務のやうに、『与へる者の余裕』を前提ともせぬ。夫が妻扶養のために彼自身の生活を破壊せざるをえぬ場合にも、なほ且つ彼は妻を扶養せねばならない。『有するものを妻と分たねばならぬ』(Was er hat, muss er mit der Frau teilen)といふことになつたのである。
1) Preuss. Ldr. II, I, 185, 186---C. c. 214---sächs. GB. 1634---Seuffert's Arch. 42, 306.
ロ 次に妻もまた夫を扶養せねばならぬかといふに、ロォマ法は、妻には夫扶養の義務を課せず、ゲルマンでは、課したものと・さうでなかつたものとあり、十九世紀に入つてからも立法の態様区々であつたが、1)普通法の判例は、妻に補充的扶養義務を認めた。すなはち妻は、夫に財産あり取得能力ある間は、夫扶養の義務を負はぬ、しかし夫が全く無財産(völlig vermögenslos)・全く取得無能力(völlig erwerbsunfähig)となつた際には、夫を扶養せねばならぬと見たのである。2)現代法もこの主義をとる。3)
1) Vgl. Preuss. Ldr. II, I, 262---C. c. 1448---bayr. Ldr. I, 6, 12 Nr. 7.
2) Seuffert's Arch. 27, 267---拙著・人格権法の発達・一三。
3) 明文の定めなき国でも、夫婦の扶養義務が、相異るものだといふことは認める。ドイツの学者は、夫婦間の扶養義務も夫婦間の他の義務と一般、独民一三五三条一項いふところの『婚姻的生活共同(eheliche Lebensgemeinschaft)の義務』によつてその内容を決定されなければならぬのであるが、婚姻的生活共同の義務とは、妻は妻らしく、夫は夫らしく行動せよとの意に過ぎぬから、結局妻に対する夫の扶養義務は重く、夫に対する妻の扶養義務は軽くならざるをえぬ、と説く。すなわち『婚姻的生活共同』なる句を根拠にして、夫婦の扶養義務の程度相異るゆゑんを説明するのである(Motive, IV, 127)。わが七八九条の『同居』は『婚姻的生活共同』と同義であるから(拙著・二主義の抗争・二六三以下)、『同居』の文字を根拠にして、夫婦の扶養義務に程度の差異を附することがでるであらう。
四六 行為能力【一四条】
イ ロォマ法においては妻は行為能力に制限を受けず、独立して——すなはち夫の同意なしに——自己の債務を負ひ、自己の財産を処分することをえたが、ゲルマン諸法は妻を無能力者とし、夫を後見人(Vogt und Meister)とし、妻は自己の債務を負ひ、自己の財産を処分するにつき、夫の同意をえねばならぬとしてゐた。1)
1) Bartsch, Rechtsstellung, 90.
ロ 十九世紀に入つても、妻の行為能力は殆ど拡張を受けなかつた。フランス・プロシヤ・ザクセン等、十九世紀の代表立法は、いづれも妻を行為無能力者としたのである。1)尤も中には、妻の債務負担能力はこれを制限せず、ただその処分能力だけを制限したに過ぎぬものもあつた。Nürnburg市法のごとし。2)後の主義の根拠とするところは、妻の財産は、夫の使用収益に服してゐるので、妻はこれを処分するにつき夫の同意を受けねばならないといふにあつた。すなはち妻自身の人格に欠点あるわけではないが、処分の客体たる財産の上に、他人の権利——すなはち夫の使用収益権——存するので、処分にあたり、夫の同意をうることを要すといふにあつた。従つて夫の使用収益に服してゐる財産部分(いはゆる持参財)を処分するにあたつては、夫の同意を要したが、然らざる財産部分(いはゆる留保財)を処分するについては同意をうる必要がなかつた。ドイツ民法もこの主義をとり、3)持参財の処分にのみ夫の同意を必要とする。4)5)6)
わが民法は今なほ十九世紀初半の立法例に倣ひ、妻を無能力者とし、夫の同意なしには、十四条所掲の処分行為および債務行為をなすことをえないとしてゐる。
1) C. c. 217, 220 fg, 1124, 1125---bad. Ldr. 215 fg.---RG. Entsch. 6, 123---Preuss. Ldr II, I, 188, 189, 320---sächs. GB. 1638, 1641---Würtemb. Entw. 133 fg.
2) RG. Entsch, 1, 37 (Nürnburg)---RG. Entsch. 6, 123 (Nassau)---oldenb. G. v. 24/4 1873.
3) BGB. 1395.
4) 元来夫の使用収益権を安全にするために、妻の処分能力までを制限する必要があるであらうか?物権法は制限物権者を安全にすることに留意してゐるが、別だんそのために所有権者の処分を禁じてはゐない。ただ制限物権者自身を絶対権者となすことによりて、彼を安全にしてやつてゐるだけである。それと同じ方法に出ることができぬであらうか?夫の使用収益権を絶対権とするならば、夫はそれだけで救はれる。持参財の第三取得者に対しても、使用収益の権利を主張しうることとなるからである。自己を安全にするために他人を無能力者とするの必要はない、自己自身を絶対権者とするならば事すでに足るのである(Motive, IV. 225)。
5) 手形能力については意見区々だつたが、通説は、債務負担能力の有無を見て手形能力の有無を決した。独立して債務を負担しうる場合ならば、手形によつて債務を負ふについても夫の同意を要しないが、元来債務を負ふにつき、夫の同意を要すべき場合ならば、手形によつて債務を負ふについても、また固より夫の同意をえねばならぬと見たのである。すなはち妻を絶対的手形無能力者と見ず、相対的手形無能力者と見たのである。
6) 営業については、中世法はもちろん近世法の大多数も、夫の許可を必要としてゐるが(Stobbe-Lehmann, deutsch. Privatr. IV, 105, 192 fg.)、夫の許可なしに開業しうるとする立法もないでない。これは妻の営業上の債務に対する引当の範囲につき見解の分裂あるの結果で、もしドイツ民法のやうに(BGB. 1414, 1462)、妻の留保財のみが妻の営業債務の引当となるとするならば、留保財は妻の自由財であるから、夫において、妻の開業に容啄すべき理由がない、従つて夫の許可を不必要とするに至るであらう。しかし他の多くの立法のやうに(C. c. 220, C. de comm., 5; Alt O. R. 35, 2)、妻の持参財までが妻の営業債務の引当とならざるをえざるものとすると、持参財の上には夫の使用収益権が存立してゐるので、夫保護の必要上、夫に営業許可の権を認めざるをえぬこととなるのである。
四七 訴訟能力【一四条】
イ ロォマ法においては妻は訴訟能力を有し、自ら原告となり被告となることをえたが、ゲルマン諸法は妻に訴訟能力を与へず、夫をして妻を代理させた。妻が他人を侵害すれば夫が代つて訴へられ、妻が他人から侵害されれば夫が代つて訴へたのであつた。1)
1) Bartsch, Rechtsstellung, 90.
ロ 十九世紀に入つても妻の訴訟能力は拡張を見なかつた。フランス民法やWürtemberg州法は、妻を訴訟無能力者とし、夫をして訴訟上妻を代理させた。1)プロシヤ州法やザクセン民法は、妻を訴訟能力者としたが、妻が訴訟をなすには夫の同意をえねばならぬと制限してゐた。2)ことに財産に関する訴訟には必ず夫の同意を要すとしてゐたのである。
なぜ財産の訴に、夫の同意を要したかといふと、妻敗訴の場合には、夫もまた、彼が妻の財産上に有するところの使用収益権を失ふに至るからといふにあつたが、学説はこの憂を一掃した。妻敗訴の判決は妻に対し効力あるのみにて、夫に対し効力なし、妻の留保財が執行を受けるのみにて、その持参財は執行を免ると見るやうになつたからである。換言すれば妻が敗訴しても夫はその使用収益権を失はないので、妻の訴訟に干渉するわけに行かないといふことになつたのである。3)一八七七年一月三十日のドイツ民事訴訟法は、この見地から、『女子の訴訟能力は、妻たることによつて、制限を受けず』と規定した。4)妻を訴訟無能力者としたWürtemberg法・制限能力者としたプロシヤ法およびザクセン法は、一様に廃止となつたのである。5)
わが民法は、今なほ妻を制限能力者とし、訴訟行為につき夫の同意を要すとする【一四条・一二条四号】。6)
1) C. c. 215, 218---Würtemb. Ldr. I, 18, §2; Würtemb. G. v. 21/5 1828.
2) Preuss. Ldr. II, I, 188, 230, 239.---sächs. GB. 1638, 1682, 1693.
3) Gaup, Civilprozessordnung I, 172.
4) C.P.O. v. 30/1 51 Abs. 2: ,,Die Prozessfähigkeit einer Frau wird dadurch, dass sie Ehefrau ist, nicht beschrankt``
5) Gaup, a. a. O.
6) 大正一一年七月八日大審院判決は、被告となるについては、夫の同意をうることを要せずとし(民集・七・三七六)、新民訴もこの旨明記した(五〇条)。原告となるについても、人格権の侵害を理由とするやうな場合には、夫の同意を要せぬであらう。妻がこの訴を起したからとて、妻の財産に対する夫の権利は、いささかも害されはしないからである。
第二節 財産関係
第一項 夫所有の推定
四八 夫所有の推定【八〇七条二項】
ロォマ法は、妻が結婚後占有するに至つた物につき、夫所有の推定を下してゐた1)が(sog. Praesumptio Muciana)、ドイツ普通法は一層夫を有利にし、妻の占有物一切を夫の所有と推定した。すなはち夫は、係争物につき、その結婚後の占有なることを立証するの要すらなく、ただちに所有の推定をうけうるとしたのである。これたしかに、普通法の判例が固有法の思想に化せられた結果であつて、固有法は、夫の財産支配を強大のものとしてゐたから、勢、夫所有の推定をも強めざるをえなかつたのである。2)
1) D., 24, 1, 54---C., 5, 16, 6.
2) Tenge, Über die Bedeutung d. s. g. Praesumptio Muciana, Arch. f. civ. Prax. 45, 305 fg.
がしかし近時に入つて夫所有の推定は薄弱となつた。ザクセン民法のごとき、夫は夫居宅内の動産につき、所有の推定を受けうるに過ぎぬとした。1)すなはち不動産については所有の立証を必要とし、動産についても、それが妻の独立の居所又は営業所に在る際は、やはりその立証を必要としたのである。ドイツ民法に至つては、夫の債権者こそ、妻占有の動産を夫の所有と推定して差押をなしうるが、夫又はその相続人は、妻の占有物を夫の所有と推定することをえず、これにつき所有権を主張せんとならば証拠をあげて立証せざるべからずとした。2)すなはち夫の債権者だけを保護し、夫自身およびその相続人を保護せぬのである。元来夫所有の推定には、夫の債権者を保護するためと、夫自身およびその相続人を保護するためと、二つの意味があるのであるが、独法は、後の機能を否定し、前の意味のみと取つたのである。
わが民法上は、動産ばかりでなく不動産もまた夫の所有と推定される。夫の債権者のためにばかりでなく、夫自身およびその相続人のためにも夫の所有と推定される【八〇七条二項】。
1) Sächs. GB. 1656.
2) BGB. 1362.
四九 妻所有の推定
ザクセン民法1)は女子用具の性質を有する動産につき妻所有の推定を下した。女子用具にまで夫所有の推定を押し及ぼすのは、あまり経験に反するので、むしろこれを妻の有と見たのである。彼女は推定所有者として、夫占有の下にある女子用具につき、反証あるまでは所有権を主張できるとしたのである。
ドイツ民法も同じ主義をとる。2)わが民法には妻所有の推定なきも、判例は、女子用の衣類調度は、妻の『所有物ナリト認定スルヲ相当トス』といつてゐる。3)
1) Sächs. GB. 1671.
2) BGB. 1362. II.
3) 明・四〇・一〇・一〇・東控判は、『其財産カ婦人用ノ物件ナリト云フノミヲ以テ他ニ特有財産タル反証ナキニ拘ラス直ニ妻ノ財産ナリト認ムルコトヲ得ス』と判示したが、大・一〇・二・九・東控判は、婦人用具は、妻の所有と認定するを相当とする旨判示した。
五〇 夫婦間の契約【七九二条】
普通法の判例は、夫婦間の贈与を無効としてゐたが、1)プロシヤ州法やオォストリア民法は、夫婦贈与の禁を撤し、売買・賃貸借・組合等が、夫婦間に約されても有効であるやうに、贈与もまた有効だと見た。一八七三年および七九年のオルデンブルグ法なども、夫婦間の贈与を有効とした。2)けだし往時の法制は、夫婦一体の原則を貫き、夫婦は財産をも全部総有にせざるべからずと見てゐたから、夫婦間の贈与をば無意義として排斥せざるをえなかつたのであるが、今日は夫婦一体の主義廃れ、各自独立の利益主体となつたので、両者間の贈与も肯定せらるべきこととなつたのである。ドイツ・スイスの民法も、夫婦間の贈与を有効とした。
わが民法では、夫婦間一切の契約が、取消されうる【七九二条】。贈与ばかりでなく、売買でも賃貸借でも、それが夫婦間に約されたといふ理由だけで——意思表示の瑕疵等を理由とせずに——取消されうる。夫婦分立の趨向に背馳すといふべし。
1) Windscheid-Kipp, Pand. III. §509---auch sächs. GB. 1647, 1649; C. c. 1096.
2) Preuss. Ldr. II, I, 310, 313---ABGB. 1246---oldenb. G. v. 24/4 1873, 37, v. 10/1 1879 35.
第二項 妻の日常家事代理権
妻の日常家事代理権の規定は、源を十三世紀の都市法に発する。大体そのころまでは、各家それぞれ自給自足の家内経済を営み、あまり外部と経済上の交渉がなかつたから、妻に、夫を代理して第三者と取引しうる権能を認める必要もなかつたが、都市の勃興・交換経済の普及は、妻をして家族の生活必需品を外部から購入せざるをえざるに至らしめ、勢そこに、妻が夫の負担において第三者と取引する家事代理の制度を成生させたのである。十八・九世紀の各州立法も、みな妻の家事代理権を規定した。それらが現代の家事代理制度の史的基礎をなしてゐるのである。1)
1) 近藤・夫婦財産法の研究・二六九以下参照。
五一 日常家事代理権の取得
十八・九世紀の各州立法も、現代の各国法も、明文の上では、妻にのみ家事代理の権を与へ、内縁の妻には与へてをらぬ。1)が、内縁の妻にも代理権を与へておかないと、彼女を正妻と誤認して与信した第三者に、不測の損害を蒙らせるといふので、最近の学説判例は、内縁の妻にも日常家事の代理権を認めるに至つた。例へばフランスでは一九〇二年に、冬期、海辺の一ホテルに、情婦と投宿してゐた一紳士をして、そのいはゆる『妻』が、呉服屋から掛で買つた莫大の衣服代を支払はしめた。2)一九一二年には、ある小女の買ひ込んだシンガミシンの代価を、契約の際、小女が『夫』と呼んでゐた情夫をして支払はしめた。3)ドイツの学説も、同国民法一三四四条の規定を内縁の場合に準用し、善意の第三者は、内縁の妻のなした家事行為の効果を、直接に内縁の夫に帰せしめることができると見てゐる。4)5)
1) Preuss. Ldr. II, I, 321 fg.---Zürich. GB. v. 1887, 603---sächs. GB. 1645---oldenb. G. v. 24/4 1873 4.
2) Trib. Nice 27/10 1909 (Dalloz, Recueil périodique, 1912, 2, 216).
3) Trib. paix Paris 14/11 1912 (Recueil de la Gazette des Tribunaux, 1913, 2, 444).
4) 独民一三四四条は、婚姻に取消原因の附着することを知らずに、夫婦の一方と取引した善意第三者を保護する規定であるが、学説はこれを婚姻不成立の場合に準用し、不成立を知らずに妻と取引した第三者も、婚姻が有効ならば彼女の夫に対して取得しうるだらうところの権利を、彼女の情夫に対して取得するとしてゐる(Staudinger-Engelmann, Komm. Bem. 2a zu §1357 u. Bem. 4 zu §1344)。なほ詳細は、Vgl. K. T. Kipp, Rechtsvergleichende Studien z. Lehre v. d. Schlüsselgewalt, 27 fg.
5) 取消しうべき婚姻の場合には、もちろん妻は代理権を失はない。取消判決あるまでは、やはり妻であるからである。未成年の妻も代理権を失はない。無能力者でも、代理人とはなりうるからである(一〇二条)。
五二 代理権の範囲
イ 十三世紀ごろの都市法は、妻の代理しうる事項を内容的に示し、金いくら以内の売買は締結しうとか、或種の穀物・或種の服地は買入れうとか定めてゐたが、1)十八・九世紀以後の立法は、凡そ日常家事の性質を有する事項ならば、何でもこれを代理しうと見るに至つた。内容的に列挙するよりも、各家庭の生活程度、ことに夫の収入を標準として、何を妻に代理さすべきかを、各別に決する方が、妥当だと見るやうになつたのである。概言すると、家庭用の衣服・食物・燃料・照明の購入・家庭不用品の売却・医師の招聘・女中の雇入れ等は、普通は日常の家事と見られたが、貧しき家庭にとつては、それさへ必ずしもそうでなかつた。手形行為・借財・家庭教師の雇入・住宅の借入・高価な楽器の購入等は、普通は日常の家事にあらずと見られたが、富める家庭にとつては、これらも日常の部類に入つた。要するに夫の収入が標準であつたのである。2)
1) Hamb. R. v. 1270, 9, 13---Lüb. R. 1, 21; 2, 96.
2) 『妻カ其子女ニ着用セシムル為呉服類ヲ買入ルヽカ如キ行為ハ日常ノ家事ナリ』(大・一三・一・一八・大判・法評一三・民二八六)——『電話加入名義変更ハ日常ノ家事ニ属セス』(大・八・一二・一九・東地判・新聞・一六六九・一八)。
ロ しかし今日は、夫の真実の収入額を標準にすることが、妥当でないと見られるに至つた。なぜといふに夫の真実の収入額は、第三者には分らない。従つて夫の真実の収入額を標準にするときは、妻の代理範囲の以外に狭少であつたことを後になつて発見し、往々、善意の第三者を失望させるからである。故に最近の学説は、夫の表見的生活程度(,,train de vie``, ,,manière de vivere de la famille``, ,,fortune apparente``)に信頼した善意の第三者をも保護しようとしてゐる。1)夫の生活の派手やかさに信頼した第三者は、その信頼を保護され、夫の実収入の多少に関せず、夫に履行の責を負はせることができねばならぬと説くのである。この見地からフランスの判例は、実収入少き夫をして、その妻が二ヶ月間に買ひこんだ九五〇〇フランの衣服代を支払はしめ、2)オランダの判例も、自働車をもち宏壮な邸宅に住んだ夫をして、その妻が十六ヶ月間に買ひこんだ一一〇〇〇グルデンの衣服代を支払はしめた、3)夫の贅沢が妻を広く権限づけることになつて来たのである。
1) Planio-Ripert-Rouast (1926) Nr. 394.
2) Paris 5/11 1907 (Recueil de la Gazette des Tribunax, 1908, I, 2, 184).
3) K. T. Kipp, Schlüsselgewalt, 73 fg.
五三 代理権の越出
イ 妻が、性質上家事でない事項を第三者と約することがある。これを日常家事代理権の質的越出(qualitative Überschreitung)といふ。性質は家事だが、購入の量又は対価の額が、夫の生活程度に調和せぬこともある。これを日常家事代理権の量的越出(quantitative Überschreitung)といふ。1)2)
質的越出の行為は無権代理である。故に夫の追認を要する。夫の営業の部類に属する行為をなしたときのごとし。量的越出の行為も、もし購入の目的物が不可分ならば、行為全部が無権代理となり、全部につき夫の追認を要する。一〇〇円の敷物ならば夫の生活程度と調和するのに、五〇〇円のを註文したといふ場合には、五〇〇円につき夫の追認を要するのである。しかしもし購入の目的物が可分ならば、越出部分につき追認をうれば足る。一俵の米ならば夫の生活と調和するのに、十俵買つたといふ場合には、一俵については追認を要せず、九俵についてのみ追認を要するのである。
1) K. T. Kipp, Schlüsselgewalt, 81 fg.
2) 『漁業会社ノ日雇漁夫ノ妻カ四十五日間ニ金一百三十七円三十銭ノ反物並ニ既成子供洋服ノ買入ヲ為シタル行為は、当事者ノ身分ヲモ参酌シ買入レタル品目代金用途等ヨリ観察シ日常ノ家事ニ該当スルモノト認ムルヲ相当トス』(大・一三・一・一八・大判・青木民判集・一〇六四)。
ロ 妻が同種の物品を数人に註文した場合に、個々の註文は代理権内にあるが、総註文額は夫の収入に越えることがある。多数の米屋に一俵づづ註文したときのごとし。かかる場合に第一の註文が日常家事の代理であることはいふまでもないが、第二以下の註文も必ずしも無権代理とは限らない、第二の註文の相手方が、もし善意なりしならば、すなはち註文の競合を知らざりしならば、彼は善意の保護を受け、妻の行為を代理なりとして、夫に代金支払を求めうるであらう。ただ相手方が悪意であつた場合、すなはち諸方面への註文が相合して夫の収入に越ゆべきことを知つてゐた場合には、妻の行為は無権代理となり、従つて相手方は、夫が妻の行為を追認せざるかぎり、夫へは代金の支払を求めえぬこととなる。1)
1) K. T. Kipp, Schlüsselgewalt, 81 fg.
五四 代理権の消滅および否認【八〇四条二項】
イ 夫死亡の場合に妻の代理権の消滅すべきはもちろんだが、死亡の事実が急に分らぬこともある。支那の奥地を旅行中死亡したといふがごとし。この場合には妻や第三者は、依然夫の負担とするつもりで契約してゐやうから、彼ら保護のために、本人の死亡を越えて代理関係を存続さす必要がある。この点に関する学説の推移を見るに、ドイツ従来の学説は、重きを善意の妻の保護におき、妻善意の場合には代理権存続し、妻悪意の場合には代理権消滅すとしてゐたから、結局第三者が直接に夫の相続人を訴へうるのは、妻善意の場合に限り、妻悪意の場合には、第三者自身は善意なるにも拘らず、夫の相続人を訴へえず、無権代理人たる妻を訴へる外なかつたのであつたが、1)2)フランスの学説はこれに反して、むしろ重きを善意第三者の保護におき、第三者さへ善意なら、妻はたとへ悪意でも、代理関係存続し、第三者は妻はたとへ悪意でも、代理関係存続し、第三者は直接に夫の相続人を訴へうるとしてきた。3)後説の方が善意の第三者に有利である。彼自身善意ならば常に夫の相続人を訴へうるからである。故にドイツの学説も最近は後説に傾きつつある。4)
1) 夫死亡の事実を妻は知らず、相手方は知つてゐる場合があるが、かかる悪意の相手方は、夫の相続人を訴へえぬはもちろん、善意の妻をも訴へえぬ。なぜなれば善意の妻には無権代理の責任を負はせてはならないからである。法が妻善意の場合に代理関係を存続さすのも、善意の妻に無権代理の責任を負はせまいためである。故に善意の妻は、相手方の悪意等のために代理関係の存続を見ざる場合にも、なほ無権代理の責任を免れねばならぬのである(Tuhr, allg. Teil II, 2, 403 Anm. 168.)。
2) Staudinger-Engelmann, Bem. 3a β zu §1357.
3) Planiol, Traité élém. II, Nr. 2264.
4) K. T. Kipp, Schlüsselgewalt, 96 fg.
ロ 正当の理由ある場合は、夫が妻の日常家事代理権を否認しうることもちろんだが、1)否認の意思表示は妻に対してなさるべきか、第三者に対してなされてもいいかといふに、従来の学説は、妻に対する意思表示を以てなすことを要すとすると同時に、第三者の保護をも考へ、すでに妻に否認の意思表示のなされたことを知らずして取引した善意の第三者は、なほ妻に代理権ありと看做し、夫を訴求できるとしてきた。1)今日でも妻に対する・いはゆる内部否認が原則ではあるが、同時に第三者に対する・いはゆる外部否認も認められ、第三者に対する意思表示を以て妻の代理権を否認することも可能だとする2)——婦人の浪費癖高まり、妻の代理権が夫にとつて甚だ危険となつたため、否認の方法も簡単となつたのである——特定の第三者、例へば妻が愛顧せる商人に対して、否認を表示することもでき、夫婦居住地の新聞紙に広告して、一般人に対し否認を表示することもできる。
1) 善意第三者の保護に想到したのは、プロシヤ州法の頃からである。同法は公告なき否認を無効とした(Preuss. Ldr. II, I, 323)。ザクセン民法は無式で足るとすると同時に、善意の第三者にはこれを以て対抗しえないとした(Sächs. GB. 1645)。ドイツ民法、一三五七条やわが八〇四条二項は、ザクセン法に倣つたのである。
2) K. T. Kipp, Schlüsselgewalt, 99 fg.
五五 妻の直接責任
上述のごとく従来の立法は、妻の家事行為の効果を全部夫に帰し、夫にのみ責任を負はせてゐた。これを夫単独責任の原則(Grundsatz der Alleinhaftung des Mannes)といふ。
しかしスイス民法は、妻にも直接補充の責任を認め、夫に支払能力なき場合には、妻はその全財産を以て第三者に対し責任を負担しなければならぬとした。1)フランスの学説も、少くとも夫婦別産制の場合には、妻はその費用分担義務の範囲内において、直接補充の責任を負はなければならぬと見つつある。2)夫単独責任の原則はやうやく崩壊に瀕してきたのである。
オランダの婚姻法改正草案(一九二七年)に至つては、全く妻の日常代理制度をすててしまつた。そうして夫婦連帯して責任を負ふといふ全然新しい主義へ転じてしまつた。その理由は、各人はそのなした行為につき各々責任を取らねばならない。いかに日常の家事行為が、夫の利益のためだからといつて、夫にのみ責任を負はせ、妻には全然負はせないといふのはよくない。須らく夫妻連帯してその責に任ずべしといふにある。すなはち同案は、なるほど夫にも責任は負はせてゐるが、それは日常の家事行為が夫の利益のためだといふ理由に基く。夫妻の間に代理関係があるからといふわけではない。代理が原因でなくて、行為の性質が原因となつてゐるのである。代理は同案の認めぬところである。3)
おもふに妻の無責任は、そのむかし妻が無資力・無財産であつた頃の紀念物ではなからうか?無資力であつたために責任を負ひたくも負ふべき力なく、止むなく無責任の地位に立つたのではなからうか?しかし現代における相続法の改正は、妻をも有産者にした。行為能力法の改正は、妻をも営利行為者にした。夫婦財産法の改正は、妻の財産に対する夫の使用収益権を滅ぼし、妻の物を妻へ返へした。今や彼女は責任の手段をもつのである。故に自ら責任を負つてもいいのである。代理主義をすてて連帯主義をとり、彼女をして直接責任の衝に立たしむべき時となつたのである。
1) ZGB. 207 II, 220 II, 243 III.
2) Collin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, III. 253---後出六五参照。
3) K. T. Kipp, Schlüsselgewalt, 19 fg. 117 fg.
第三項 収益管理制
五六 序説
イ 夫婦間の財産関係は、中世の間、各領主の立法や各地方の慣習に一任されてゐたため、かの婚姻身分法が、教会の大きな手で、よく世界的に統一されてゐたのとは異り、夫婦財産法は、殆ど四分五裂の状態にあつた。今日でも夫婦財産法の典型は、国により著しく異るのである。中には一国にして数種の法定夫婦財産制をおき、当事者をしてその一を撰択させてゐるものさへあるのである。よつてわたくしは、わが現行法の採用してゐる収益管理制1)(Nutzniessung)と、改正法の採らうとしてゐる別産制(Gütertrennung)との二つだけについてのべよう。
1) 収益管理制は、管理共同制(Verwaltungsgemeinschaft)とも呼ばれる。
ロ まづ収益管理制の意義と由来とをのべておくと、収益管理制とは、夫が妻の財産および労働から生ずる収益(Ertrag der Arbeit u. des Vermögens der Ehefrau)を取得しうとする制度である。夫は妻の財産そのものは奪はない、結婚前妻のもつてゐた財産は結婚後も彼女の有であり、婚姻中彼女の取得する財産も彼女の有である。しかし果実は夫に移る。労働の成果も夫に移る。夫は妻との共同生活費を負担する代りに、妻の財産を収益し、その労働成果をも取得するといふわけである。
わが国現行の法定夫婦財産制が、収益管理制であることは明瞭である。なぜなれば民法は八〇七条一項において、『妻カ婚姻前ヨリ有セル財産及ヒ婚姻中自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス』と規定して、婚姻により所有変動(Eigentumsveränderung)の生ぜざる旨を明かにし、八〇一条一項において、『夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス』と規定して、管理権の夫にある旨を明かにし、七九九条において、『夫ハ用方ニ従ヒ妻ノ財産ノ使用及ヒ収益ヲ為ス権利ヲ有ス』と規定して、夫に使用収益の権ある旨を明かにしてゐるからである。
ハ 次に収益管理制の由来はといふに、この制度の発祥地は東部ザクセンであつた。十三世紀のころ東部ザクセンの夫たちは、妻の財産および労働の収益を取得してゐたのであつて、今日の語でいへば、収益管理制によつてゐたのである。が、一時この制度は非常に衰へた。それは、この制度とその思想的根底を反対にする一般共産制(allgemeine Gütergemeinschaft)が流行し、ザクセン地方にもおし寄せてきたからで、十六世紀の頃この制度の残塁を守つてゐたのは、ザクセンの極一小部分とスイス山間の町々位のものだつたが、個人主義的思想の勃興と共に勢を挽回した。この制度は、夫婦をしてその財産を別有させる点において、一般共産制よりも遥かに個人主義的色彩に富むからである。須臾にしてドイツ全土に蔓延し、民法制定のころは、人口にして約二千百万が、この制度の下にあつたといふ。よつてドイツ民法もこの制度を採用して法定夫婦財産制の一つとした。わが国は、ドイツ民法からこの制度を学んだのである。1)
ただドイツの収益管理制はザクセンの旧慣そのままの再興にあらず、多大の修正を加へた新型のものだが、わが国は、ドイツ民法が新に加へた修正箇所を恰も無視し、古い実体だけを輸入したため、非常に旧式のものとなつてゐる。十三世紀ごろの東部ザクセン慣習が、そのまま日本民法に採択された観がある。
1) 拙著・二主義の抗争・二八六以下。
五七 法定留保
イ 収益管理制は、妻の財産を夫の収益管理に移し、妻の労働収益を夫の所有に移す。いはば妻を『夫の搾取を受ける女奴隷』たらしめるのである。故に進歩した近代の収益管理制は、夫の収益管理権を大いに狭ばめ、ある種の労働収益は法律上当然に妻の有となるとし、ある種の財産部分は法律上当然に妻の自由管理に残るとする——
まづ労働収益を見ると、十九世紀前半までの法律は、妻は夫から扶養される代りに、その労働収益を夫に捧げねばならぬとしてゐたが、一八七〇年イギリスにおいて、妻財法(Married Woman's Property Acts)の制定あり、妻が労働者として、女教員・女芸術家として、取得した労賃は妻の有となるとした。ドイツでも一八六二年のリウベック法・一八七三年のオルデンブルグ法あたりまでは、妻の労賃をまだ夫の有としてゐたが、1)民法は妻の労賃を妻に帰せしめ、且つそれを彼女の自由財とした。2)フランスも一九〇七年七月十三日の法律を以て同一趣旨を規定した。
わが民法には、妻の労賃が妻の自由財となる旨の規定がない。故にそれは、妻の特有財産ではあるが【八〇七条一項】、七九九条以下の規定に従ひ、夫の収益管理権に服せざるをえないであらう。
1) Lüb. G. v. 15/2 1862 2---oldenb. G. v. 24/4 1873 2.
2) BGB. 1367---もちろん妻は地位相当に家事労働をなす義務を負ふ。故に夫の家又は店で働き、夫をして女中一人分又は小僧一人分の給料を節約せしめえたとしても、彼女は彼に、それだけの労賃を請求することはできない。が、義務以上に働いた場合は請求できよう。専門の技術家として夫の店舗で働いた場合のごとし。
ロ 十九世紀後半期の法律は、営業を営む妻に独立人と同一の能力を与へてゐたにもかかはらず、1)営業から入る収益は、これを妻に与へず、夫の有に帰せしめてゐたのであつたが、後期に入り、妻の営業収益は妻の有にして、且つ妻の自由財なりと認めるに至つた。前記、労賃の自由財的性質を認めた立法は、大抵同時に営業収益の自由財的性質をも認めたのである。
わが民法は営業収益についても特別の規定をおかない、故にそれは妻の特有財産ではあるが【八〇七条一項】、自由財ではないのである。やはり夫の収益管理権に服せざるをえぬのである【七九九条八〇一条】。
1) 前出四五参照
ハ 夫の収益管理権に服する妻の財産を、持参財(eingebrachtes Gut)といひ、妻の自由管理に残る財産を、留保財(Vorbehaltsgut)といふが、持参財の代表物はやはり持参財となり、留保財の代表物はやはり留保財となると見られて来た。1)
ただそのいはゆる代表物(Surrorgation)の意味は必しも明かでなかつたが、今は、留保財の破壊・毀損・奪取に対する賠償を留保財の代表物といふはもちろん、留保財たる権利に基いて取得した一切の利益をも留保財の代表物といふ。故に例へば債権が留保財であつた場合には、それに基いてえた給付は、正に債権の代表物であつて、従つてまた妻の留保財となるのである。
わが民法には法定留保の制度なく、ただ任意留保の余地を存するだけであるが、代表物の原則(Surrogationsprinzip)は任意留保財にも共通するので、わが国においても留保財の代表物はやはり留保財となるといひうるであらう。
1) Preuss. Ldr. II, I, 217, 218---sächs. GB. 1693.
五八 任意留保
イ 婚姻前又は婚姻中、妻がその財産の一定部分を自ら管理する旨を夫と契約することがある。何番地の山林は妻これを管理すと約すがごとし。これを任意留保といふ。
近代法は留保契約につき公示主義をとり、登記を要すとする。1)けだし留保は、妻の財産に対する夫の収益権を消滅さす行為で、それだけ夫の財産を減少さすから、不測の損害を夫への与信者に及ぼさないとも限らない。故にそれを公示して、夫の担保力の減少したことを、予め夫への与信者に知らしめておかうとするのである。
1) 留保契約は、法定夫婦財産制を変更する夫婦財産契約の一種であるから、夫婦財産契約と同様の方法で約させ、登記を必要とするのである(Preuss. Ldr. II, I, 209---BGB. 1368---ZGB. 190)。
ロ 然らば登記済の留保契約の効力はといふに、もしこれに、広く第三者に対抗しうる効力を認めんか、登記前からの債権者も、登記済留保契約の対抗を受け、後発の留保行為によつて害されるといふ不都合を生じよう。もちろん債権者には、詐害的留保行為を取消す権能はあるが、わざわざ取消さねばならぬといふのは、面倒である。むしろ初めから後発の留保契約は、前発の債権者に対して、当然に効力なしと定める方が、より十分に前発債権者を保護するゆゑんだといふので、スイス民法は、留保契約は、その登記前からの債権者に対しては、当然に無効なりと定めた。1)元来債務者が債務負担の後、妻と留保契約を締結し、好んでその収益権を喪失するのは、大抵債権者詐害のためであり、極言すれば、債務負担後の留保は常に詐害的だともいへるので、債務負担後の留保契約の効力を、前発債権者保護のために特別に制限しても、債務者に酷だとはいへぬのである。
1) ZGB. 190, 179 III. 後出七一のロ参照。
五九 収益関係【七九九条】
イ 留保財を除いた妻の財産、すなはち夫の収益管理に服する財産を持参財(eingebrachtes Gut)といふ。
中世の収益管理制は、妻の持参財を夫の占有に移した。妻がいかなる財産をどこに蔵するか、夫これを知らず、従つて何ら支配意思を有せざる場合にも、当然に夫は、妻の持参財の上に占有を取得した。
近代の管理制も妻の財産を夫の占有へ移す。ただし近代の管理制は、昔日のそれのやうに、夫ばかりを占有者として保護せず、妻をも間接の占有者として、占有の保護を加へる。
わが民法上も、妻の持参財は、婚姻締結と同時に法律上当然に夫の占有に移る【七九九条】。しかし妻は間接占有者たるを失はぬのである。
ロ 中世の管理制は妻の物を使用しうる権利を夫に与へ、権利として彼は妻の家に住み、妻の物を使用することができるとし、しかも何ら制限するところがなかつたが、1)今の管理制は、夫の使用権を可なり制限し、過度の使用や用途の変更を禁ずる。2)3)妻の持参せる山林を濫伐したり、工場を住宅に変じたり、庭園を田畑にしたりするわけには行かぬとするのである。
わが七九九条も、『用方ニ従ヒ』といひ、用途の変更・過度の使用を禁じてゐる【七九九条】。
1) Agricola, Gewere zur rechten Vormundschaft, 293 fg.
2) Sächs. GB. 1655---preuss. Ldr. II, I, 231---oldenb. G. 24/4 1873 5.
3) BGB. 1383---ZGB. 201.
ハ 中世の管理制も夫に収益権を与へ、持参財から生ずる天然および法定の果実は、夫の有となるとしてゐた。妻の土地から生ずる穀物・妻の貸金から上る利子、いづれもみな夫の単独所有となつたのである。故に例へば既分離の天然果実は、夫死亡の場合、妻へ戻らずに夫の相続人の有となり、妻死亡の場合にも、妻の相続人へ行かずに夫の有に残つた。1)
この点は今の管理制も同一だが、ただ今日は過度の収益を禁じ、過度の収益による元物毀損に対して損害賠償の義務を課す。2)3)わが国でも夫は、元物毀損の場合には、損害賠償の義務を負はねばならない【八〇〇条六〇〇条】。
1) Agricola, Gewere 256-259.
2) Preuss. Ldr. II, I, 561---sächs. GB. 1655---Lüb. G. v. 10/2 1862 6.
3) BGB. 1383 fg.---ZGB. 201.
六〇 処分関係【八〇二条】
持参不動産の処分については、中世の管理制も、妻の同意を要すとしてゐた。譲渡の場合はもちろん、質入の場合にも同意を要したのである。無同意処分は無効で、妻は一定の期間内に第三者から取戻すことができた。1)近代の管理制においても同然である。動産につき無同意処分を許した例はあつたが、不動産についてはみな同意を要すとしたのである。2)
持参動産については、中世法は妻の同意を必要とせず、夫は妻に無断にて有償又は無償に処分できるとしてゐた。3)近世の管理制も初めは無同意主義だつたが、4)ザクセン民法が動産についても妻の同意を要すとして以来、立法の趨向一変し、動産不動産を問はず常に処分には、妻の同意を要とするに至つた。5)6)
債権の処分につきまた同じ経過がある。中世法上は妻の同意は必要でなかつたが、今はそれを必要とする。結局今では、『妻の同意なき夫の処分』(Mannesverfügung ohne Frauenkonsens)が、一般的に禁じられることになつたのである。
わが民法も『夫カ妻ノ財産ヲ譲渡シ之ヲ担保ニ供スルニハ妻ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス』とし【八〇二条】、妻の同意なき夫の処分を排斥してゐる。
1) Agricola, Gewere 301 fg.
2) Preuss. Ldr. II, I, 332.
3) Agricola, Gewere 222 fg.
4) Preuss. Ldr. II, I, 247---oldenb. G. 24/4 1873 7---Lüb. G. v. 10/2 1862 5.
5) Sächs. GB. 1675---Roth, deutsches Privatr. II, 215.
6) BGB. 1375---ZGB. 202.
六一 管理関係【八〇一条】
中世の管理制も近代のそれも、共に夫に、持参財管理の権を与へたが、管理の意味の明瞭になつたのは比較的近時である。近時の学説は、管理とは他人の一定の財産を一定の目的へふりむけるために、それにつき法律上および事実上の行為をなすことをいふと定義し、保存・改良の行為はもちろん、目的の範囲内における処分行為をも含ましめる。1)例へば持参財は婚姻費用のために——すなはち夫婦の共同生活費のために——消費されることを目的とするので、この目的のためにならば、夫は妻に無断で保存・改良の行為をなしうるはもちろん、やはり妻に無断で、持参財の果実を処分することもできるが、個人的目的のためには、全然処分することをえないとするのである。持参財の目的明かとなり、目的内の処置広く肯定されるに至つた。2)
1) Siber, Verwaltungsr. an fremd. Vermögen in BGB. Jahrb. f. Dogm. 67, 81 fg. 拙著・二主義の抗争・三二二以下。
2) 持参財の元本の無断処分は、法が積極的にこれを禁止してゐるため(六〇参照)、婚姻費用の目的のためにも、無断処分をなすことをえない。
六二 注意義務【八〇五条】
中世の管理制は、夫に管理上の注意義務を課さなかつた。従つて夫は管理の結果につき賠償の責に任じなかつた。持参財たる物を不注意に賃貸して賃借料をえず、反つて賃借物を毀損されたとか、持参財たる債権を適当の時期に取立てず、回収不能に陥らせたとかいふ場合にも、なほ夫は妻に対し、損害賠償の義務を負はなかつた。1)
近代の管理制は夫に一定の注意義務を課し、不注意に管理して損害を生ぜしめたものに、賠償の責を負はせる。而してその注意義務の程度は、漸次加重の傾向を見せつつあるのである。プロシヤ州法・リウベック法等は、夫に故意又は重過失あつた場合に損害賠償の義務を負はせたに過ぎなかつたが、2)ザクセン法・オルデンブルグ法等は、夫は自己の物に対すると同一の注意義務を以て、妻の持参財を管理せねばならぬと定め、具体的過失に対する責任を負はせた。3)ドイツ民法また然り。4)わが民法も、『夫カ妻ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テハ自己ノ為メニスルト同一ノ注意ヲ為スコトヲ要ス』と規定する【八〇五条】。
1) Agricola, Gewere 292 fg.
2) Preuss. Ldr. II, I, 561---Lüb. G. v. 10/2 1862 4.
3) Sächs. GB. 1655---oldenb. G. 24/4 1873 13.
4) BGB. 1359
六三 担保の供与【八〇三条】
担保供与の規定は、十七・八世紀のころロォマ法の影響を受けて発達した。1)ロォマ法は、妻は夫の総財産の上に先取特権を有し、以てその嫁資返還請求権を担保するものとしてゐたが、これに倣つてドイツの地方法も、妻をして夫の財産上に先取特権を取得させたのである。しかし後には、当然には夫の財産上に先取特権を取得せず、ただ夫の管理の失当な場合に、夫に対し担保の供与を請求しうるに過ぎぬと見られるに至つた。法定質の代りに担保請求があらはれたのである。夫が妻の請求に応じて抵当権等を設定するに当つては、やはり登記の必要があつた。2)
しかしその後の発達は、漸次、担保供与の制度を否定しつつある。なぜなれば、夫の管理権に対する法律上の制限が非常に厳重になつた今日、夫の管理の失当を心配する必要は殆どなく、且つ担保制度には、夫が、担保に借口して財産を妻に供与し、以て彼の債権者を詐害するの弊を、必ず伴ひ易いからである。夫の管理の失当の場合には妻自ら持参財を管理しうとする立法3)において、担保制度の必要なきはもちろんである【七九六条一項】。
1) Stobbe-Lehmann, deutsch. Privatr. IV. 217.
2) Vgl. C. c. 2121, 2135, 2136---preuss. Ldr. II, I, 254---sächs. GB. 390---oldenb. G. v, 24/4 1873 14---BGB. 1391, 1392---ZGB. 205.
3) Sächs. GB. 1683---Seuffert's Arch. 46 Nr. 199.
六四 引当関係
イ 中世の管理制においては、妻の持参財は一切夫の債権者から差押へられることを免れなかつたが、1)十七・八世紀の都市法中には、妻の持参動産だけを夫の債務の引当と見たものが多数あつた。2)動産は妻の同意なしに夫これを処分しうるから、夫の所有物と同視され、夫の債権者から差押へられても止むをえなかつたのである。動産の処分にも妻の同意が必要となつてからは、消費物たる持参動産だけが差押の目的になつた。消費物にあつては使用即処分で、夫に使用させるのは、夫に処分させるものであるから、消費物だけは夫の所有と看做され、夫の債権者から差押へられても止むをえなかつたのである。しかし一八三八年四月七日のプロシヤ法は、妻の持参財は、消費物より成る場合といへども、夫の債務の引当となることなしとし、ザクセン民法も同一趣旨を規定した。3)現代の法律も夫の債務に対しては、夫の財産のみが引当となると見る。これを債務分離の原則(Prinzip der Schuldentrennung)といふ。
わが民法上も、夫の債務に対しては夫の財産のみが引当となるに止まると解しなければならない。
1) Vgl. Agricola, Gewere 384 fg.
2) Pommern, Holstein, Hessen等の一部では、古くから妻の持参財が夫の債務の引当となつてゐた。Lübeckは一八六三年十月十六日の法律で、Wismarは、一八七五年十二月九日の条例で、妻の持参財が夫の債務の引当となるといふ主義をとつた(Roth, deutsch. Privatr. II. 221 fg.)。
3) Sächs. GB. 1678.
ロ 次に持参財から分離した果実はと見るに、これについてはどの立法も、差押性を認めた。1)すでに元物から分離してしまつた果実は、もはや妻の有でなくて夫の有であり、従つて夫の債権者から差押へられることを免れえぬからである。しかし果実本来の使命は、夫婦および子の生活費のためだといふ点から、債権者に対して、夫婦および子の生活費に充てらるべき部分を残すことを命ずる立法も少くない。1)わが国においても夫の債権者は、持参財から生じた果実の中から、夫婦および子の生活に必要な部分を除き、残余を差押へうるに過ぎぬのである【旧民訴強制執行篇六一八条】。
1) Preuss. Ldr. II, I, 257, 262---sächs. GB. 1683---Entsch. d. Reichsg. bei Gruchot 24 1023; 25 891.
ハ 問題は夫の収益権自体が差押の目的物となるかにあるが、十九世紀立法の多数は、夫の収益権は夫の一身に専属する権利であるから、他人これを差押へることをえぬと見たが、1)中にはやはり、扶養に必要な額だけを残して他を差押へうると見たものもないではなかつた。収益権は一身専属の権利ではあるが、その行使はこれを他人に許して差支ないとの見地からであつた。2)3)
1) Sächs. GB. 1683---oldenb. G. v. 24/4 1873 10.
2) Preuss. Ldr. II, I, 257---deutsch. Konk. Ordn. 1, Abs. 2.
3) Vgl. auch Motive, IV, 213 fg.
第四項 別産制
別産制の故郷はロォマである。ロォマの夫婦は結婚後も未婚者のごとく、別々に所有し、別々に管理収益し、別々に債務を負うてゐたのであつた。1)ロォマ法の継受と共にこの主義はドイツへも流れて来たが、固有の制度たる収益管理制や一般共産制に比べると、その勢はるかに衰り、わづかにBayern, Braunschweig, WaldeckおよびHannover辺に行はれたに過ぎなかつた。2)それすら純粋な形態においてではなく、ややもすればドイツ固有の収益管理制と混血せんとする傾向さへあつた。暗黙の意思表示によつて妻の財産は夫の収益管理に移ると見たごときその一例である。
しかし夫婦別産の主義は近時における夫婦分立の思想と調和するので、やうやく流行を見んとしつつある。すでにオォストリア・チエックスロバキア・イタリイ・セルビア・トルコ等はこれに依り、イギリスもこれに依り、3)米国多数の州もこれに依り、4)ドイツ・フランス及びスイスも、模範的夫婦財産制の一としてこれを掲げてゐる。5)わが改正要綱も、『夫婦ノ一方カ婚姻前ヨリ有セル財産及ヒ婚姻中自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トスルヲ原則トシ夫又ハ女戸主カ其配偶者ノ財産ニ対シテ使用及ヒ収益ヲ為ス権利及夫ノ妻ノ財産ニ対スル管理権ヲ廃止スルコト』と言明し、将来別産制に転ずべき旨を予告してゐる。
1) 拙著・ビザンチン期における親族法の発達・一三六以下参照。
2) Roth, deutsch. Privatr. II. 40 fg.
3) ABGB. 1363 fg.---Tschechoslowakei, ABGB. 1363 fg.---Italien, C. c. 1425 fg.---Serbien, C. c. 759 fg.---Türkei C. c. 170---England, Married Woman's Property Acts.
4) Connecticut, Columbia, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Missouri, New-Jersey, New-York, Pennsylvania etc.
5) BGB. 1462 fg.---C. c. 1536 fg.---ZGB. 241 fg.
六五 別産主義
イ 別産制のもとでは、夫婦は他人のやうに財産上分立するが、例外がないでもない。その一は、扶養義務である。夫が妻を扶養し、妻が夫を扶養するのは、婚姻の本質そのものから来てゐるので、別産主義に依る場合といへども、これを免れるわけには行かないのである。その二は、所有の推定である。法が所有不明の財産を夫の所有と推定し、女子専用の動産を妻の所有と推定するのは、彼らの共同生活に伴ふ財産混同を両断せんがためで、この必要は、共同生活の存するところ常に随存するのであるから、別産制に依る場合といへども、夫婦は所有の推定を受けざるをえぬのである。
問題は別産制のもとにおいても、妻は日常家事代理権をもつか否かにあるが、従前の学説は積極説をとり、妻はこの場合にも代理権を有し、夫の単独責任において自由に第三者と契約しうるとしてゐた。1)最近は反対論多く、別産制の場合には妻は独自の財産を有するのであるから、夫にのみ家事上の債務を負はせてはならない、夫と連帯して直接第三者に対し家事上の債務を負ふか、若くは少くとも夫に支払能力なき場合に、第三者に対し直接補充の責任を負はねばならぬと見るやうになつて来た。2)
1) Wolff, Familienr. (1928) 231.
2) 前出五五参照。
ロ 別産制のもとにおいても、妻がその財産の全部又は一部を、夫の管理に委ねることがあるが、それは通常の委任契約に過ぎない。当然には夫は妻の財産を管理する権利もなく、その義務もないのである。
六六 出費義務(Beitragspflicht)
イ 別産制のもとにおいては、夫は妻の財産を使用収益することをえぬが、一定の出費は妻に請求することができる。
出費の方法はロォマでは財産の一部分を夫の所有に移させた。これを嫁資といふ。嫁資は婚姻中夫の所有であり、婚姻解消後妻へ復帰したのである。1)近代の別産制は、元本そのものを夫の所有へは移させない、元本から生ずる果実の一部分、又は妻の営業若くは労働から生ずる収益の一部分を、夫へ捧げさせるだけである。果実又は収益の三分の一以内を出費することを要すとする国もあり、2)地位相当の額を出費することを要すとする国もある。3)
1) 拙著・ビザンチン期における親族法の発達・一三六以下。
2) C. c. 1537---oldenb. G. v. 24/4 1873 33---hess. Entw. 539.
3) BGB. 1427---ZGB. 246.
ロ 妻から財産管理を委任された夫は、それから生じた収益の一部を天引して婚姻費用の一部にふり向けうるが、天引額は、妻の出費義務の範囲を越えてはならない。これを越えて天引した場合には、不当利得となり、妻から利益の返還を請求される。1)
1) Motive, IV, 325 fg.
第三章 夫婦関係の変更
第一節 身分関係の変更——別居制
別居制度は旧教会法で発生した。同法は離婚を絶対に禁じてゐたので、離婚制度の代用としての別居制度を、是認する必要があつたのである。しかし別居の作用は離婚の代用たることに尽きない、その他種々の機能があるので、離婚を認める近代の法制も、大抵同時に別居制をおく。
六七 別居の効果
イ 別居中の夫婦の関係は、旧教会法におけるよりも著しく簡単になつて来た。旧教会法は別居中の夫婦にも貞操の義務を課し、もし第三者と性交に入れば姦通となるとしてゐたが、今日では、夫婦は別居の断行と共に貞操の義務を免ると見てゐるのである。1)夫は別居中婚姻費用負担の義務を免れ、妻の財産に対する使用収益の権を失ひ、妻もまた日常家事の代理権を失ひ、処女時代の姓を回復し、独立人の能力を再得する、とも見てゐるのである。妻たり夫たるの地位そのものは失はないが、夫婦間の権利義務は殆ど消滅するのである。
が、依然妻たり夫たるの地位を失はないので、両者の間に夫婦の関係を再興させるためには、何も婚姻締結をやり直す必要はない、同棲を再開しさへすれば足りるのである。又別居中は再婚ができない、すれば重婚となる。
1) Wolff, Familienr. 135---オォストリアにおいても通説は夫婦は別居と共に貞操義務を免れるに至ると見る(Vgl. Ehrenzweig, System d. allg. Privatr. II. 2. 92 Anm. 88)。
ロ 別居は右様の重大な結果を生ずるので、これをなすには裁判を要する。裁判外の別居は、どこの国でも認めぬのである。1)
1) 健康上の理由などで、夫婦が一時居所を別にすることがあるが、これは別居契約ではない。居所を別にするだけで、夫婦関係の中枢たる忠実義務そのものを廃棄しようとするのではないからである。真正の別居契約、すなはち婚姻的忠実義務の廃棄そのものを約する契約は、無効である(C. c. 307; Belgien, C. c. 307)。
六八 別居原因と離婚原因
イ 旧教会法は、姦通・遺棄・虐待等々、普通離婚の原因となつてゐるやうな事実を、別居判決請求の原因としてゐた。1)けだし同法は離婚を許さず、その代りに別居をおいたため、通常の離婚原因を、そのまま別居原因としてゐたのである。イタリイ・スペイン・ポォランド等は今も離婚を許さない。従つて通常離婚の原因となつてゐるところの事実を、別居原因としてゐるに止まるのである2)。
1) Friedberg, Kirchenr. 507 fg.
2) Italien, C. c. 148 fg.---Spanien, C. c. 104 fg.---Polen, Eheg. v. 16/5 1836 62 fg.
ロ ドイツ・フランス・ポルトガル・ハンガリイ・トルコ等は、離婚と別居とを併せ認めてゐるにも拘らず原因は共通である。なぜといふにこれらの国は、単に国内旧教徒の便宜のために別居制をおいたに過ぎなかつた。統一民法は布いたものの、国内の旧教徒が依然離婚を嫌つてゐるので、別居制といふ離婚の代用物を、彼らのために特設したに過ぎなかつたからである。代用物なるが故に原因を共通に定めたのである。1)
1) BGB. 1575---C. c. 306---Portugal, Dekret v. 3/11 1910 43---Ungarn, Eheg. v. 1894 104---Türkei, BGB. v. 17/2 1926 135.
ハ しかし最近の立法は、共通原因の外、別居にのみ特有な原因を定める。例へばオランダでは、軽度の虐待は、離婚の原因とはならないが、別居の原因にはなる。1)スェデン・ノォルウェ・デンマァク等では、暴飲や扶養拒否は、離婚の原因とならないが、別居の原因にはなる。2)つまりここでは別居は、離婚の代用としてではなく、むしろその拡大としておかれてゐるのである。離婚の原因は何といつても甚だ狭い、それだけでは男女の分離を十分に自由にすることができない。よつて別に別居制をおき、事情やや軽微にして離婚を正当化し能はざる場合に夫婦を別居させ、以て彼らの分離目的を、十二分に満たしてやらうといふ趣旨なのである。3)
1) Niederl. BWB. 288 III.
2) Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 11. Kap. 1 fg.---Norwegen, G. v. 15/5 1918 42---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 52.
3) ソヴェート・ロシアおよびわが国は別居を認めない。けだし離婚が非常に自由で、この上さらに別居制をおく必要などがないからである。
第二節 財産関係の変更——夫婦財産契約
夫婦財産契約は、ゲルマンの都市法で発達した。けだしゲルマンには種々の内容の法定夫婦財産制があつたが、どれもみな夫の利益に偏し、妻の立場を無視してゐたので、都市の勃興・婦人の覚醒と共に不満の情起り、契約の力でその適用を排し、任意の新内容において夫婦財産関係を規律しようと試みるに至つたのである。すなはち夫婦財産契約は夫の専制を排し、法定制の不合理を除くために生れたもので、人のいふやうに婚姻法上の``Magna Carta``としてであつた。
六九 夫婦財産契約の自由【七九三条】
イ 十五・六世紀ごろの都市法は、一般的夫婦財産契約(generellar Ehevertrag)の締結を許してゐた。すなはち夫婦は法定の夫婦財産制を全体として排斥し、新たな内容の財産法を約定することができるとしてゐた。近代の法律も多くは一般的財産契約の締結を許してゐるが、この主義は夫婦の債権者を不安にさせる。債権者の立場からいふと、債務者夫婦が債務の負担後は、あまり彼らの財産関係を改変しないことを望むのである。よつてスェデンおよびデンマァクは、一般的財産契約の締結を禁じて部分的財産契約(spezieller Ehevertrag)の締結のみを許し、夫婦は法定財産制に随伴する法律関係に変更を加へ、又は法定財産制の適用を受ける財産の範囲に制限をおくことはできるが、法定財産制そのものを全体として排斥することはできないとする。1)ドイツやスイスは、数種の模型的夫婦財産制を法上に掲げ、夫婦はそのいづれかを撰択することはできるが、法律所掲のものと全く異る新内容の財産制を、約定することはできないとしてゐる。すなはち自由撰択主義(freie Güterstandwahl)を捨てて限定撰択主義(beschränkte Güterstandwahl)をとつてゐるのである。2)
1) Schweden, G. v. 1925 8. Kap. 1---Dänemark, G. v. 1925, 4. Kap. 28, 29.
2) ZGB. 179 II---BGB. 1432 fg.
ロ わが民法は、フランス・ベルギイ・ノォルウェ・オランダ・スペイン・ポルトガル・オォストリア・チエックスロバキア等の諸国1)と同じく一般的夫婦財産契約を認め、法定制と全く異る新内容の財産制を約定することも可能だとしてゐる【七九三条】。
1) C. c. 1387---Belgien, C. c. 1387---Norwegen, G. v. 1888 1. Kap. 1---Niederl. BWB. 194---Spanien, C. c. 1315---Portugal, C. c. 1096---ABGB. 1217---Tschechoslowakei, ABGB. 1217.
七〇 締結および改廃【七九三条七九六条】
イ 十五・六世紀の都市法は、夫婦財産契約は、婚姻締結前にも締結後にも、約することができるとしてゐたが、近代に入りこれが締結を婚姻前に限るに至つた。すなはちフランス民法は、財産契約は婚姻中に約しうるに止まる、夫婦となつて後は約しても無効なりとし、イタリイ・ポルトガル・スペイン・オランダ・ベルギイ・ルゥマニア等もこれに倣つた1)。しかし婚約中の新郎新婦にのみこの契約の締結を許すは、無意味も甚しい。なぜなれば婚約時代には財産的自覚なく、真に財産契約の必要を感じてくるのは、夫婦となつて後のことであるからである。故に近時に至つて夫婦にも財産契約の締結を許す主義が殖えてきた。ドイツ・スイス・チエックスロバキア・ユゥゴォスロバキア・スェデン・デンマァク等のごとし2)。しかしわが民法は仏法主義をとり、『婚姻ノ届出前ニ』これを締結することを要すとする。
1) C. c. 1387, 1394 fg.---Italien, C. c. 1382 fg.---Portugal, C. c. 1096, 1105---Spanien, C. c. 1315, 1319 fg.---Niederl. BWB. 194, 203, 204---Polen, G. v. 1825, 207, 209---Belgien, C. c. 1387, 1394 fg.---Rumänien, C. c. 1228 fg., 1270.
2) BGB. 1432---Tschechoslowakei, ABGB. 1217---Jugoslawien (Serb. BGB.) 759---Schweden, G. v. 1920, 8. Kap. 1---Dänemark, G. v. 1925, 4. Kap. 28.---墺においては、明文上多少の疑問あるに拘らず、学説を以て婚姻中の締結を是認する(拙著・二主義の抗争・三三三以下)。
ロ 十五・六世紀の都市法は、婚姻中に財産契約を締結することを許したごとく、婚姻中に財産契約を改廃することをも許してゐた。しかしフランスおよびこれに倣つた諸国の民法は、1)婚姻中の締結を禁じたと同時に、婚姻中の改廃をも禁じてしまつた。
しかしこの事もまた無意義であつたであらう。なぜなれば夫婦の財産状態は婚姻中に幾変転し、一旦締結したものを改廃する必要を感じてくることがあるからである。故にドイツおよびこれに倣つた諸立法は2)、婚姻中の締結を許すと同時に、婚姻中の改廃をも是認した。しかしわが民法は仏法主義をとり、夫婦財産契約は、『婚姻届出ノ後ハ之ヲ変更スルコトヲ得ス』としてゐる【七九六条一項】。
1) 前出イ註1)
2) 前出イ註2)
七一 方式および効力【七九四条】
イ 十五・六世紀の都市法においては、夫婦財産契約の締結に親族の立会を必要としてゐた。親族の立会をえずに締結されたものは、夫婦財産契約とは見られなかつた。1)今日では大抵の国は、公証人をしてこれを作成させるか又は登記を必要とする。2)スェデン・ノォルウェ・デンマァク3)のごとく、二人以上の証人の立会あらば、私署証書を以て約しうるとする国もないではないが、大抵は公証人又は登記官吏の協力を要すとするのである。わが民法上も夫婦財産契約は、『登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗』することをえない。【七九四条】
1) 拙著・二主義の抗争・三三五以下。
2) BGB. 1434---C. c. 1394---Italien, C. c. 1382---Österr. G. v. 25/6 1871 1a---Portugal, C. c. 1097---Rumänien, C. c. 1228---Spanien, C. c. 1321---ZGB. 181.
3) Dänemark, G. v. 1925, 4. Kap. 1, 2---Norwegen, G. v. 1888, 2---Schweden, G. v. 1920 8. Kap. 10.
ロ 十五・六世紀ごろの都市法も、夫婦財産契約のために、第三者の利益、ことに夫婦の相続人の利益の侵害されんことをおそれた。よつて財産契約の締結には相続人の同意をうることを要すと定め、或は財産契約の締結によつて遺留分権利者の権利を害することをえずと定めてゐたが、1)近代に入り、債権者の保護が問題となつて来た。仏民が、夫婦となつてから後財産契約を締結するのを禁じたのも、実は夫婦が債務負担後これを締結して、一方の財産を他方へ移し、以てその債権者を害することなきやを憂へたからであつた。よつてスイスの民法は、夫婦にも財産契約の締結を許すと同時に、かかる契約の効力を特に制限し、夫婦となつてからの財産契約は、その締結前からの債権者に対し効力なき旨を明記した。2)これによつて締結前からの債権者は、夫婦財産契約の締結によつて悪影響を蒙らずに済むやうになつたのである。スイス以外の国は夫婦の債権者を保護するためにかかる特別手段を講じてゐない。普通の詐害行為取消権を与へてゐるだけである。
1) 拙著・二主義の抗争・三三七以下。
2) ZGB. 179 II.---前出五八ノロ。
七二 契約内容【七九四条】
十五・六世紀ごろの都市法は、夫婦は財産契約を以て婚姻中の財産関係を規律しうるのみならず、婚姻解消後のそれをも約しうるとしてゐた。1)けだし妻にとつて切実なのは、婚姻中の財産関係でなくして婚姻解消後のそれである。婚姻中は夫から扶養されるが、婚姻解消後をいかにすべきか、夫先死し寡婦となつた後をいかにすべきか、それがより剴切な問題である。故に覚醒した婦人は、夫婦財産契約を以て法定財産制の不合理を除去しようとしたと同時に、相続契約を以て法定相続制の欠点をも直さうとしたのであつて、同一契約書中に婚姻財(Ehegut)と寡婦財(Witwengut)とを併せ記し、婚姻中および婚姻後の生活を、一石二鳥的に確実にすべく力めたのである。
十九世紀に入つてから、ドイツでは、夫婦財産契約と相続契約とは、内容を異にする二個の契約なるが故に、各別に約されざるべからず、財産契約書中に相続契約を併記することをえずとの見解が一時勝を制したが、民法制定の際、夫婦又は婚約者は、同一契約書中に、財産契約と相続契約とを併約することができるといふ昔の主義に復帰した。オォストリアも特別法を以て同一趣旨を宣明した。2)寡婦の相続権に触れないやうな契約は殆ど無意義であるからである。
フランス・スペイン・ポルトガル・オランダ・ルゥマニア等は、原則として相続契約を認めず、法定の相続制は契約の力では左右できないとしてゐるのであるが、しかし同時に夫婦財産契約の当事者のために例外を設け、特に彼らだけは、相続契約を締結することができ、しかもそれを夫婦財産契約書の中に併約することができるものとしてゐるのである。相続権に触れない財産契約は無意義であるので、財産契約の当事者だけに特別の便宜を与へてゐるわけである。3)
わが民法上、夫婦財産契約の当事者は相続契約をも併約しうべきか?{}七九四条は夫婦財産契約は『登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人』に対抗することをえずとし、財産契約の内容が夫婦の承継人(相続人)の権利に触るることあるべきを明かに予想してをるので、わが国においても夫婦だけは、夫婦財産契約の中で相続契約を約しうると解しえないわけでもあるまい。
1) 拙著・二主義の抗争・三三九以下。
2) BGB. 2276 II---ABGB. 1217, 1249; Hofdekret, v. 25/6 1817.
3) C. c. 1130 II---Belgien, C. c. 1130 II---Niederl. BWB. 1370 II---Spanien, C. c. 1271 II.---拙著・二主義の抗争・三四一以下。
第四章 離 婚
離婚法は新教会で発達した。旧教会では、婚姻を終生結合とし、結ばれた以上解くことをえないとしてゐたから、離婚法発達の余地も存しなかつたが、新教会では離婚を許し、一定の原因存する場合には離婚することができると見たのである。尤もその原因は、最初は極少く、姦通と悪意の遺棄の二つだけだつたが、後には姦通に準じて重婚・不自然性行をも離婚原因とし、悪意の遺棄に準じて虐待・殺害企図・性交拒否をも離婚原因とし、さらに後には、長期に亘る自由刑・重大な侮辱等も離婚の原因となると見るやうになつた。年と共に離婚の許される場合が殖え、分離が自由となつたのである。自然法学者の論述も離婚原因の拡大に貢献した。男女の結合と分離とを極端に自由化しようといふのが、彼らの根本主義であつたからである。立法においてはプロシヤの州法が離婚原因を認めること最も広かつた——(一)姦通・悪意の遺棄・性交拒否・殺害企図・重婚・不行跡・扶養の拒否等の重大な過失(schwere Verschulden)を離婚原因としたのはもちろん、(二)精神病・不能症のごとき偶然の事由(zufällige Umstände)をも離婚原因とし、(三)子なき場合には任意に(als Willkür)協議離婚をなすことさへ可能だとしたほどで、1)同法こそ近代の離婚自由主義の先駆者であつたのである。現代立法は概してプロシヤの先蹤を追つてゐる。
1) Preuss. Ldr. II, I, 699 fg.---その後プロシヤでは一八四四年・五四年・五九年の数回に、州法の離婚原因を縮小しようとする趣旨の改正草案が作られたが、どれも成法とはならなかつた。
第一節 裁判離婚
新教会は離婚は許したといふものの、みだりに行はれないやうに充分に警戒した。すなはちまづ離婚権の発生を制限し、離婚権は法定の原因に基いてのみ発生す、法定原因に該当する事実なきかぎり離婚を行ふことをえずと定めた。さらに離婚権の行使方法を制限し、離婚権は通常の形成権のやうに、単なる意思表示を以て行ふことをえず、必ず離婚の訴の提起によらねばならぬともした。而して離婚の訴においては、原因の有無・権利の存否を、実体的真実において突きとめようと試みたのであつて、その目的から、或は検事をして弁論に立合つて意見を述べしめ、或は裁判官をして職権斟酌をなさしめた。どこまでも婚姻の維持・離婚の防止が眼目であつたのである。充分に離婚原因の存在を確めた上でなければ離婚を許すまいとしたのである。1)
1) 本書においては、離婚権の発生原因に関する規定の変化を叙するに止める。行使方法に関する法律規定の変遷は、訴訟法の歴史となるので、ここに述べることを避けたい。なほ今日の人事訴訟法が、教会の訴訟法に淵源してゐるといふことについては、拙著・二主義の抗争・一九四参照。
第一項 性的不忠実
七三 姦通【八一三条二号三号】
イ 姦通は離婚を許す立法の全部が、離婚原因として認め来つたところのものであつた。Lutherのやうに離婚原因を認めること甚だ吝だつた人でさへ、姦通は離婚の原因になると見たほどであつた。その後新教会は夫妻の姦通を平等に取扱ひ、妻のそれも夫のそれも、共に離婚の原因になるとした。1)
近代の法律も夫婦の姦通を平等に取扱ひ、妻の姦通が離婚原因になるごとく、夫のそれも離婚原因になると見る。2)ただ一時仏法は、夫の姦通を妻のそれから区別し、妻の姦通は直ちに離婚の原因となるが、夫のそれは情状特に重き場合(夫が姦婦を夫婦の共同住所に連れこんだ場合)にかぎり、離婚の原因になるに過ぎないとしたが、一八八四年七月二十七日の法律でこの不平等を除去し、夫の姦通も直ちに離婚の原因となると見るに至つた。今ではベルギイ・スペインなどが、改正以前の仏法的不平等主義をとつてゐる。3)わが国に至つては極端で、妻姦通の場合には夫は直ちに離婚できるが、夫姦通の場合には、てうどそれが姦淫の罪に該り、よつて夫が処刑されたといふ特別な場合を除くの外、彼を離婚することができない【八一三条二号三号・刑法一七七条及一八三条】。改正要綱も、妻の姦通は直ちに離婚原因となるが【第十六ノ一ノ(一)】、夫の姦通は『著シキ不行跡』と認められる場合の外、離婚の原因とならぬとしてゐる【第十六ノ一ノ(二)】。
1) Friedberg, Kirchenr. 514.
2) 十九世紀中、平等主義をとつた立法は、preuss. Ldr. II, I, 670 fg.; nürnb. Ehescheidungsordn. altenb. Eheordn. 195 fg.; sächs. GB. 1713 fg.---ドイツ民法制定の際には、ドイツ聯合婦人会が、貞操の義務につき夫婦平等の主義を採用せられんことを建議した(Vgl. das Organ des Allg. deutschen Frauenvereins: ,,Neue Bahnen`` Bd. 12, Nr. 8)。
3) Belg. C. c. 230---Italien, C. c. 150 II---Spanien, C. c. 150 Nr. 1.
ロ 姦通の未遂はどうかといふに、新教会では、未遂も離婚原因となるといふ説と、ならないといふ説とがあつたが、1)ザクセン民法が明文を以て未遂姦に基く離婚を排斥2)して以来、大勢これに決し、未遂姦は離婚原因とならないと見られるに至つた。
挙証に関しては、間接挙証を許してきた。直接に立証しえずとも、第三者と不謹慎の交際あり、切実に姦通を推定しうる場合には、姦通そのものを理由に離婚しうるとされてきた。3)4)
1) Dafür: Seuffert's Arch. 12, 38; 25, 31; 31, 237; 35, 131---dagegen: Seuffert's Arch. 13, 147; 14, 142; 18, 145; Entsch. d. Reichsg. 9, 47.
2) Sächs. GB. 1715.
3) Preuss. Ldr. II, I, 673---nürnb. 10---goth. 75 fg.
4) 『妻カ夫ノ不在中年若キ独身ノ男子ト自宅ニ於テ飲酒シ又ハ是レト劇場ニ同行シ帰途夕食ヲ共ニシタル挙動アリタリトスルモ該男子ト夫トノ交際カ親密ノ間柄ニシテ且ツ該男子ニハ別ニ婚約ノ婦子アリテ該婦子モ右会合ニ同席又ハ同行シタル事実ノ立証アル時ハ必スシモ会合ノ全部ニ渉リ一々其ノ同席同行ヲ立証セラレサリシトスルモ此ノ一事実ヲ以テ妻ノ貞操ヲ疑フコトヲ得ス』(大正一二・一二・四・大判、青木民事判例集一〇七八)。
ハ 夫婦の一方が、他方の姦通を幇助したり教唆したりした場合はどうかといふに、教会法も国法も、1)かやうな場合には、初めから離婚権を取得することをえないとしてきた。幇助したり教唆したりするのは、配偶者の姦通を初めから苦痛とせぬ証拠であるからである。同じ理由で、姦通に同意した者も離婚権を取得せぬ2)【八一四条】。
1) Seuffert's Arch. 7, 192; 20, 41---preuss. Ldr. II, I, 719---altenb. 200 d.---sächs. GB. 1718.
2) 新教会では、夫婦の一方が他方の姦通に同意した場合にもなほ離婚権を失ふべきやにつき論議岐れた(Seuffert's Arch. 8, 268; 27, 139)。ドイツ民法は同意した場合には離婚権なしと明言し(BGB. 1565)、他の立法もこれを明言する(ZGB. 137; Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 11. Kap. 8; Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 48; Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 59)。わが民法また然り(八一四条一項)。
ニ 序に離婚権の消滅一般について述べんに、新教会法も国法も、離婚権は宥恕(Verzeihung)によつて消滅すと見たが、1)当時の「宥恕」は、離婚権の喪失を欲する意思の表示といふ意味であつた。2)従つて、離婚権者がかかる意思を表示せぬかぎりは、いくら相手方と和合しても、離婚権は失はないとされてゐたが、今の学説では宥恕は感情の表現である。事実上離婚権者の感情が和らいでしまへば、果して彼に離婚権の喪失の意思ありしやを問ふことなく、当然に彼の離婚権を消滅させてしまふのである【八一四条二項】。
1) Seuffert's Arch. 41, 113; 43, 25---preuss. Ldr. II, I, 720---nürnb. Nr. 48---sächs. GB. 1720---bad. Ldr. 272.
2) 宥恕は明示の意思表示に依らねばならぬと定めたものさへあつた(Preuss. Ldr. II, I, 720; nürnb. Nr. 48)。
ホ 離婚権は短期に消滅する。その期間は、プロシヤの州法では離婚原因を知つてから一年だつたが、1)今は一層短くなり、知つてから半年、発生から二・三年で消滅するものさへある。2)わが国では、知つてから一年、発生から十年で消滅する3)【八一七条】。
1) Preuss. Ldr. II, I, 721.
2) Schweden, Eheg. 8---Norwegen, 48---Dänemark, 59.
3) わが民法では、悪意の遺棄に基く離婚権も、知後一年の経過で消滅する。故に悪意の遺棄に気附いて後さらに数年、遺棄者の帰宅を待ちわびたといふ場合には、離婚権すでに失はれ、もう離婚できぬのである。多くの外国法は、悪意の遺棄に基く離婚権を特別に取扱ひ、これだけは時間の作用で消滅せぬとしてゐるから、右様の不都合を生じない(ZGB. 140; Schweden, 5; Norwegen, 45; Dänemark, 56)。
ヘ 終りに夫婦双方が、姦通した場合について見るに、新教会は他方の姦通に基いて離婚権を取得した者が、自身又姦通すれば、一旦取得した離婚権を失ふとし、1)国法も大体これに倣つたが2)(相殺主義Kompensationsprinzip)、今日は夫婦双方に離婚権を与へ、互に他を離婚しうるとする。その理由は、離婚権は離婚権者を婚姻継続の苦痛から救出すためで、有責者処罰のためではない。処罰のためなら、権利の附与につき権利者の身の潔白を前提ともしようが、さうでないのだから、自身姦通した者にも離婚権を与へて差支ないといふにある。被告もまた反訴を提起して原告を離婚しうるから、不公平ともならぬのである【わが民法八一五条は、犯罪に基く離婚権だけは、相殺的に消滅するとしてゐる】。
1) Seuffert's Arch. 2, 194; 17, 53; 20, 41.
2) Preuss. Ldr. II, I, 670 fg.---sächs. GB. 17 fg.---altenb. 200 c.---Seuffert's Arch. 2, 194; 17, 53; 20, 41; 21, 59; 23, 230; 31, 239.
3) BGB. 1574.
七四 重婚その他【八一三条一号】
イ 重婚を特殊の離婚原因とした国はむしろ少く、大抵は姦通の一種とした。事実それは大抵同時に姦通となるので(ならないのは、重婚はしたが重婚配偶者と性交しなかつたといふ稀有の場合)、特殊の離婚原因とするほどの価値もないのである。1)
1) 重婚を特殊の原因として規定したのは、sächs. GB. 1728---現在ではBGB. 1565; Griechenl. Eheg. v. 24/6 1920 3---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 58---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 47---わが民法もこれを特殊の離婚原因とするが、わが国では重婚は姦通と異り、妻がなしても夫がなしても離婚原因となる故、姦通から区別されねばならぬのである(八一三条一号)。
ロ 新教会ではある種の猥褻行為——ことに不自然性行——を離婚の原因とした。1)国法中にも、これに倣ふものが少くなかつた。2)
1) Seuffert's Arch. 43, 25.
2) Preuss. Ldr. II, I, 672; nürnb. Ehescheidungsordn. 12; sächs. GB. 1728---現在ではBGB. 1565; Schweden, 8; Norwegen, 48; Dänemark 59---わが民法は猥褻行為そのものを離婚原因とせず、これによる処刑を離婚原因とするのみ(八一三条四号)。
ハ 新教会はまた頑固な性交拒否(hartnäckige Verweigerung der ehelichen Pflicht)を離婚の一原因とし、1)国法中にもこれを特殊の原因としたものがないでになかつたが、2)裁判上これを理由にさせるのは面白くないといふので、今日の立法は、拒否を「悪意の遺棄」若くは「重大な侮辱」の一場合と見て、若くは「夫婦関係の著しき破壊」の一場合と見て、離婚させる。3)
1) Seuffert's Arch. 17, 56.
2) Preuss. Ldr. II, I, 694---nürnb. 28---altenb. 217---sächs. GB. 1731. 新立法の中には、夫婦の一方が他方の意思に反して避淫手段を講じたことを以て、離婚原因となすものがある(Lettl. Eheg. v. 1/2 1921 47; Estl. Ehestandg. v. 1/5 1723 25)。
3) 不能症を離婚原因とする国もある。例へばLettl. Eheg. v. 1/2 1921 47; Griechenl. Ehescheidungsg. v. 24/6 1920 8---多くの国では、不能症は、それが結婚の当初から存在してゐた場合に婚姻取消の原因となりうるのみで、結婚後さうなつた場合には、離婚の原因となりえぬと見てゐる。
第二項 同居の廃止
七五 悪意の遺棄【八一三条六号】
イ 悪意の遺棄(bösliche Verlassung)の観念は、新教会がこれを樹てた。同会で悪意の遺棄とは、理由なき同居の廃棄、すなはち正当の理由もないのに、若くは夫婦間の合意もないのに、自ら家出したり他方を追ひ出したりすることをいつたのである。理由があつて不在した場合には、その理由消滅の時から悪意の遺棄となつた。留守配偶者へ扶養を続けてゐても、不在に理由を欠けば、遺棄であつた。1)
1) 『民法第八百十三条ニ所謂悪意ノ遺棄ハ扶養義務ノ如何ニ関セス夫婦ノ一方カ悪意ヲ以テ他ノ一方ヲ遺棄スルヲ云フ』(明・三三・一一・六・大判・録・一〇・一六)。
ロ ところで新教会が悪意の遺棄に離婚原因性を認めた際には、なほ不徹底の点をあましてゐた。なぜといふに新教会は、遺棄を遺棄者の居所不明の場合と分明の場合との二に分ち、不明の場合には——これを固有の遺棄(eigentliche Desertion)といつた——被遺棄者は、遺棄者が同居を廃棄してから一定の期間経過したことを理由に、直ちに離婚判決を仰ぎうるが、居所分明の場合には——これを準遺棄(Quasidesertion)といつた——まづ裁判所に申請して遺棄者へ帰還命令(Rückkehrbefehl)を発せしめ、これに遺棄者が服従せざりしときにかぎり、離婚判決を仰ぎうるのみとしてゐたからである。1)つまりまだ婚姻維持の思想に囚はれてゐたのであつて、遺棄に因る離婚を最小限度に喰ひ止めようと努力してゐたのである。1)
1) Seuffert's Arch. 3, 67.
ハ 十九世紀の法律は新教会に倣つて、固有の遺棄と準遺棄とを区別した。1)今日においても多数の立法は二者を区別し、準遺棄の場合、すなはち遺棄者の居所分明の場合には、離婚判決申請の先行条件として帰還命令の発令を仰がなければならぬとしてゐる。2)少数の新立法は居所分明の場合を別段に軽視せず、この場合にも被遺棄者は、一定の遺棄期間を経過せることを理由に、直ちに離婚判決を仰ぎうるとしてゐる。3)遺棄期間は長いので五年、短いので六ヶ月。4)
1) Preuss. Ldr. II, I, 679 fg.---altenb. Eheordn. 208 fg.---sächs. GB. 1731---goth. Eheg. 101, 109.
2) BGB. 1567---ZGB. 140---Tschechoslowakei, G. v. 25/5 1919 13c.
3) Niederl. BWB. 266---Lettl. Eheg. v. 1/2 1921 44---Griechenl. Ehescheidungsg. 24/6 1920 4.
4) 他の国はみな一定期間継続した悪意の遺棄を離婚の原因としてゐるのに、わが国だけは悪意の遺棄そのものを離婚原因としてゐる(八一三条六号)——改正要綱は、悪意の遺棄を『甚シキ不当ノ待遇』といふ非常に広汎な離婚原因の中に、包括させようとしてゐる(改正要綱第十六ノ一ノ(三))
第三項 配偶者に対する直接の侵害
七六 殺害企図
殺害企図を初めて離婚の原因と見たのは、Melanchtonであつた。彼は彼の同志Lutherが、姦通と悪意の遺棄の二つを離婚の原因としたのに追加して、虐待や殺害の企図も同様に離婚の原因になると説いたのである。新教会はズツトこの説を守つた。企図といふ中には、配偶者を殺害せんとする予備・陰謀・着手・未遂等すべてを含めてゐた。1)
十九世紀の立法も新教会の例に倣つて殺害企図を離婚原因の中に数へた。2)現代の立法もさう定めてゐる。3)仏法系の法律だけはさう定めてをらないが、判例で殺害企図を重大侮辱(injure grave)の一種と見てをるため、事実上殺害企図は離婚原因をなしてゐるのである。わが国においても、殺害企図は重大侮辱の一種であらう【八一三条五号】。
1) Friedberg, Kirchenr. 515.
2) Preuss. Ldr. II, I, 699---nürnb. Ehescheidungsordn. 25---goth. Eheg. 97, 102---sächs. GB. 1735.
3) BGB. 1566---ZGB. 138---Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1919 13a---Griechenl. G. v. 24/6 1920 3---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 11. Kap. 10---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 50---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 61.
Rumänien, BGB. 215.は、他人に配偶者殺害の企図あるを知りつつ告げぬならば、それもまた離婚原因だと定めてゐる。すなはち殺害企図に関する警告の過怠を離婚原因の一と見るのである。
七七 虐待【八一三条五号】
虐待を離婚の原因と見た最初も、Melanchtonであつた。彼は配偶者の生命又は健康に危険な虐待は、殺害の企図と同様、離婚の原因になると説いたのである。新教会はズツトこの説を守つて来た。1)
十九世紀の立法中にも、『配偶者の生命又は健康に危険な虐待』のみを離婚原因としたものもないではなかつたが——ドイツの州法は概ねさうであつた2)——これはあまり狭すぎるといふので捨てられた。現時の立法は、凡そ配偶者をしてその婚姻の継続を堪え難く感ぜしめる程度の虐待ならば、生命・健康に危険はなくとも、離婚の原因になると見てゐるのである。各国法にいはゆる『甚しき虐待』(service grave, schwere Misshandlung)とは、3)婚姻の継続を堪え難からしめる程度の虐待といふ意味である。4)
1) Friedberg, Kirchenr. 515---Seuffert's Arch. 35, 36.
2) Preuss. Ldr. II, I, 699---nürnb. Ehescheidungordn. 25---goth. Eheg. 97 fg.---sächs. GB. 1735 fg.
3) C. c. 231---bad. Ldr. 231---Italien, C. c. 150---Niederl. BWB. 264 Nr. 4---ZGB. 138---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 11. Kap. 10---わが民法はこれらの立法よりも一層正確な語を用ゐ、『同居ニ堪ヘサル虐待』といつてゐる(八一三条五号)。
4) 『創傷ニ至ラサル暴行ト雖モ激シク繰返サルルニ当リテハ民法八百十三条ニ所謂同居ニ堪ヘサル虐待ト言フコトヲ得ルモノトス』(大・三・三・三〇・東控判・新聞・九六二・二九)。
七八 侮辱【八一三条五号】
イ 侮辱は十八世紀中、新教会の判例によつて初めて離婚の原因となつたものらしいが、十九世紀に入ると、多数の立法によつて、離婚の原因になると認められた。1)現代法も重大侮辱を離婚原因としてゐる2)【八一三条五号】。重大とは、やはり、配偶者をしてその婚姻の継続を堪え難からしめる程度の、といふ意味である。3)
1) Preuss. Ldr. II, I, 706 fg.---nürnb. Ehescheidungsordn. 25---goth. Eheg. 96.
2) C. c. 231---Italien, C. c. 150---ZGB. 138.---スェデン・ノォルウェ・デンマァク等は、侮辱を離婚原因としてゐない。
3) 判例は、畜妾を妻に対する重大な侮辱としてゐる——『正妻アルニ拘ハラス他ニ女ヲ畜ヘ妻トシテ偶シ之ト同棲スルカ如キハ民法八百十三条第五号ニ所謂妻ニ対スル重大ナル侮辱ヲ加ヘタルモノト認ムルニ足ル依ツテ離婚ノ原因タルモノトス』(大・二・七・一四・東地判・法新八九二号二一)——『夫カ其妻ヲ顧ミス他ノ女ト内縁ノ契ヲ結ヒ之ト同棲スルノ行為ハ民法八百十三条第五号ニ所謂重大ナル侮辱ニ該当ス』(大・七・一二・一九・大判・録・二三・六四)。
ロ 新教会はまた誣告を離婚の原因にした。1)国法中にもこれに倣つて夫婦の一方が他方の犯罪につき故意に虚偽の申告をなした場合には、他方はこれを離婚しうる旨をわざわざ明記したものもないではなかつたが、2)多数はこれを特殊の離婚原因と見ず、重大侮辱の一に居らしめたに過ぎなかつた。
1) Entscheid. d. RG. 4, 104.
2) Preuss. Ldr. II, I, 705---nürnb. 25---goth. 123.
七九 その他の直接侵害行為
上述のごとく従来の立法は、配偶者に対する直接侵害の行為の中から、特に二三のものを撰んで離婚の原因としたに過ぎなかつたが、一八三七年五月十三日のAltenburg婚姻令は、一方において虐待等を離婚原因として掲げると同時に、他方において一般条項(clausula generalis)なるものを設け、その他すべて婚姻の継続を堪え難く感じさせる程度の直接侵害行為は、みな離婚の原因となる旨規定した。1)すなはち従来の法律が、限定的意味において離婚原因を列挙したに反して、Altenburg法は、例示的意味においてこれらを掲げ、離婚原因の規定方法に一新機軸を出したのである。現代法の中にはAltenburg法の例に倣ふものが少くない。ドイツ・スイス・ギリシヤ・チエックスロバキア等のごとし。2)これらの国々においては、甚しき虐待と重大な侮辱ばかりでなく、自由の侵害でも、扶養の拒否でも、性病の伝播でも、家政執行上の不誠実でも、凡そ婚姻の継続を堪え難く感じさせる程度の直接侵害行為ならば、何でも離婚の原因となりうるのである。3)わが国においても、改正要綱は広く『配偶者よりの甚しき不当の待遇』を離婚原因たらしめようとしてゐる【改正要綱第十六ノ一ノ(三)】。
1) Altenb. Eheordn. 194.
2) BGB. 1568---ZGB. 142---Griechenl. G. v. 24/6 1920 5---Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1919 13h---Lettl. G. v. 1/2 1921 45.
3) 自由侵害を独立の離婚原因として明言した国もある。例へばEstl. G. v. 27/10 1922 28 Nr. 5は、身体的自由の侵害を離婚原因とし、Burgarien, Exarchatord. v. 1883 187は、信教の自由の制限を離婚原因とした。扶養拒否を離婚原因として明言した国もあつた。古くはpreuss. Ldr. II, I, 713今ではEstl. 28 Nr. 3。又、性病伝播を明言するものもあつた。Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 11. Kap. 9; Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 49; Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 60; Portugal, Dekret v. 3/11 1910 4 Nr. 10.等。
第四項 配偶者に対する間接の侵害
八〇 刑罰【八一三条四号】
刑罰は新教会の判例によつて離婚の原因となつたが、同教会がこれを離婚の原因としたのは、刑のために夫婦がその共同生活を長い間廃止せねばならぬことになるから、といふにあつた。すなはち長年月の受刑を一種の遺棄と見ての事であつたが、十九世紀の末に考を一転し、離婚の真の理由は、刑のために共同生活が廃止されるからでなくて、これにより配偶者が間接の侵害を受け、婚姻継続を堪え難く感ずるに至るからだと見るやうになつた。そこで離婚の判決を下す際にも、従来のやうに刑の軽重・罪の種類ばかりでなく、配偶者の受ける苦痛の程度をも考量し、もし配偶者が受刑者との婚姻を堪え難く感ずべきならば、刑期の長短・犯罪の種類に論なく、離婚を認めてやらうといふことになつた。1)
国家の法律も十九世紀中のそれは、単に何年以上の刑は離婚の原因となるとか、何罪に因る何年以上の刑は離婚原因になるとか定めたに過ぎなかつたが2)——そうして今でも多くの立法はさういふ定め方をしてゐるが3)4)——進歩的な少数の立法は、苦痛の程度を基準にし、配偶者が受刑者との婚姻の継続を堪え難く感ずべきならば、刑種および刑期に論なく、離婚しうるとしてゐる。5)
1) Entsch. d. RG. 1, 120; 9, 47; 13, 46.
2) Preuss. Ldr. II, I, 704 fg.---nürnb. Ehescheidungsordn. 37---goth. Eheg. 122---sächs. GB. 1740.
3) 現代法の中には重きを刑期におき、一定年限以上の自由刑に処せられれば、離婚原因となるとする国と、重きを刑種におき、凡そ懲役刑に処せられれば、刑期の長短に論なく離婚原因となるとする国もある。スカンヂナビアの立法は前者に属し(Schweden, Eheg. v. 2/11 1915 11. Kap. 11; Norwegen, Eheg. v. 31/5 1918 51; Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 62; Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1919 13)、フランスおよびスイスは後者に属する(C. c. 232; Belgien, C. c. 232; ZGB. 139)。
4) 民法八一三条四号は、『配偶者ノ偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物ニ関スル罪若クハ刑法第百七十五条二百六十条ニ掲ケタル罪ニ因リテ軽罪以上ノ刑ニ処セラレ又ハ其他ノ罪ニ因リテ重禁固二年以上ノ刑に処セラレタルトキ』とあるが、これは旧刑法に準拠したもので、もし現行刑法を基礎として書き改めるならば、『配偶者カ偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領又ハ贓物ニ関スル罪若クハ刑法第百八十六条第二項第二百六十二条ニ掲ケタル罪ニ因リテ罰金以上ノ刑ニ処セラレ又ハ其他ノ罪ニ因リテ懲役二年以上ノ刑に処セラレタルトキ』といふことになる(穂積・離婚制度の研究七三七)。
5) BGB. 1568.
八一 その他の間接侵害行為
犯罪以外にも間接侵害の行為がないではない。例へば夫婦の一方が、他方の親族を侮辱し、継子を虐待し、子の教育を怠り、これに売淫を勧めたりしたとすると、他方は間接の侵害を受け、婚姻の継続に堪えざるに至るであらう。又一方が下等な職業を営み、酒に溺れ、賭博に耽り、その他放埓な行状を示したとすると、これらの行為は直接には、本人自身を害するだけだが、間接にはやはり配偶者を害し、彼をして婚姻の継続に堪えざらしめるに至るであらう。故にこれらの行為を離婚原因の中へ数へ込む必要があるのであるが、従来の立法は、かかる規定をなすことを怠つて来た。せいぜい一二の間接侵害行為を離婚原因と見ただけで、1)2)間接侵害一般を離婚原因とはしなかつた。今日でも多数の立法はまだ旧套を脱してをらぬが、少数の立法は間接侵害一般を離婚の原因とする。3)ちやうど婚姻の継続に堪えざらしめるほどの直接侵害行為が一般的に離婚の原因となるやうに、同じ程度の間接侵害行為も一般的に離婚の原因となるとするのである。
1) 或ものは下賎な営業を離婚の原因とした(Preuss. Ldr. II, I, 707; nürnb. Ehescheidungsordn. 38)。或ものは暴酒癖や浪費癖を離婚の原因とし(Preuss. Ldr. II, I, 708 fg.; nürnb. 36; goth, Eheg. 124; sächs. GB. 1733)或ものは賭博癖を離婚の原因とした(Portugal, Dekret v. 3/11 1910 4 Nr. 9)。Cuba, Panama, Venezuela等では、娘に対する売淫勧誘を離婚の原因としてゐる(Rechtsvergleichendes Handwörterbuch. II, 718)。
2) わが国法は、配偶者が自己の直系尊属を侮辱・虐待したこと、配偶者が自己の直系尊属から侮辱・虐待を受けたことを以て離婚の原因とする(八一三条七号・八号、改正要綱第十六ノ一ノ(四))——西洋諸国に類例のない規定である。
3) BGB. 1568---ZGB. 139---Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1919 13 fg.---Estland, G. v. 1/5 1923 27---Lettland, G. v. 1/2 1921 46.
第五項 無責離婚原因
八二 疾病
イ 新教会は1)有責の侵害行為を離婚原因としただけで、偶発の事情を離婚原因とはしなかつたが、プロシヤの州法は偶発事情の一である精神病を原因の一に加へた。2)ところがこれに対しては、罪なき病人を見棄てるといふ非難があり、改正も幾度か企てられたが、州法は固く当初の主義を維持した。3)他のドイツ立法もプロシヤに倣つて続々精神病を離婚の原因とするやうになつた。4)ドイツ民法も、猛烈な反対論を押し切つて、不治の精神病を離婚原因として規定した。5)ドイツ以外にも、『一定の期間継続し且つ全治の見込なき精神病』を離婚の原因と定める国が、漸次多くなりつつある。6)夫婦は肉体の共同のみならず、精神の共同をも尚ぶのに、精神病者とは精神を共同にすることをえないといふのが、精神病離婚説の論拠である。
わが民法は、もちろん精神病を離婚原因にしてをらないが、改正要綱は、『婚姻関係ヲ継続シ難キ重大ナル事情』を広く離婚の原因としてゐるので、精神病も重大事情の名の下に、離婚原因となることになるであらう。
1) Seuffert's Arch. 2, 195; 5, 295; 7, 58.
2) Preuss. Ldr. II, I, 698.
3) 一八四四年のプロシヤ離婚法改正草案は、精神病を離婚原因の一と規定した。五四年の草案は、これを削除しようとしたが、五九年の草案に至つて旧に復し、これを離婚原因として留保すべく試みた。
4) Nürnb. Ehescheidungsord. 32---bad. Ldr. 232a---goth. Eheg. 113---sächs. GB. 1743.
5) 第二読会では一二五対一一六で否決され、第三読会では一六一対一三三で可決された。
6) ZGB. 141---Schweden, Eheg. v. 11/6 1920 11. Kap. 13---Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 63---Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1919 13g---Estland, G. v. 1/5 1923 26---Lettland, G. v. 1/2 1921 45.
ロ プロシヤの州法は、婚姻中に生じた難治の性交不能症1)と、嫌忌すべき疾病2)とを離婚原因の中に数へた。しかしプロシヤその後の諸草案は、これらを離婚原因の中から削除すべく提案し、遂に現行ドイツ民法に至つて削除の目的を達した。今のドイツでは精神病だけが離婚原因であるのである。その他の国においても精神病以外は、概ね離婚の原因とならないが、最近、反対の立法傾向も見え出した。レツトランドやエストランドでは、婚姻中に生じた難治の不能症3)・伝染的性病4)・著しく嫌悪すべき疾病5)等を離婚原因としてゐるのである。
1) Preuss. Ldr. II, I, 696---sächs. GB. 1742.
2) Preuss. Ldr. II, I, 697.
3) Lettl. G. v. 1/2 1921 47b---Griechenl. G. v. 24/6 1920 8.
4) Estl. G. v. 1/5 1923 26 Nr. 2.
5) Lettl. 45---Estl. 26.
八三 制し難き嫌厭(unüberwindliche Abneigung)1)
プロシヤの州法は、『和合の見込みなきまでに強烈な相手方嫌厭の情』を離婚の一原因に数へたが、2)同国その後の改正諸草案は、嫌厭そのものは離婚の原因とならない、嫌厭を催させる相手方の一定の有責行為が、離婚の原因となるのみと見、『嫌厭』を離婚原因の中から駆逐してしまつた。フランスでも大革命の際に、嫌厭を理由に離婚を請求しうる旨を定めたことがあつたが、民法編纂の際これを廃してしまつた。3)今ではどこの国でも嫌厭は離婚の原因として絶対に不適当だと見るやうになつたのである。ただオォストリアとチエックスロバキアの二国では、特に非旧教徒の間において、嫌厭が離婚の理由となるものとしてゐる。4)
1) 嫌厭を理由とする離婚においては、原告は、彼が被告との婚姻生活を嫌厭してゐるといふ事実を提示し立証することを要する。この点において、それは一方的任意離婚と異るのである。後者にあつては、離婚権者は一方的に離婚意思を表示すれば足る、何らの理由を示す必要がないのである。
2) Preuss. Ldr. II, I, 718a.
3) Frankr. G. v. 20/9 1792 8 fg.
4) ABGB. 115---Tschechoslowakei, G. v. 22/5 1919 13i.
八四 失踪【八一三条九号】
失踪も無責の原因である。過責に基かざる生死不明の状態であるからである。故に過責主義に執着した従来の立法は、これを離婚の原因としなかつたが、現代では失踪も離婚の原因となる。すなはち新立法のあるものは、夫婦の一方が一定の期間生死不明となつた場合には、他方はこれを離婚しうるものとしてゐたのである。1)わが民法も同様に定めてゐる2)【八一三条九号改正要綱第十六ノ一ノ(五)】。
1) Norwegen, Eheg. v. 15/5 1918 46---Dänemark, Eheg. v. 30/6 1922 57---Portugal, Dekret v. 3/11 1910 4 Nr. 6.
2) わが民法にはもう一つ特別な無責離婚原因がある。縁組の解消又は取消がそれである。婿養子縁組の場合に離縁あり、養子と家女との婚姻の場合に離縁又は縁組の取消があれば、夫婦の一方は過責なき他方を離婚しうるのである(八一三条十号)。かやうな無責離婚原因は他国に見ない。
第六項 不定離婚原因
八五 不定離婚原因
上来われわれは離婚権の発生原因が次第に広く認められるに至つた経過を叙したが、その要所を再言すると、当初は離婚の原因極少く、わづかに姦通と悪意の遺棄の二つだけだつたが、漸次新規のものが附加された。まづ姦通に準じられて不自然性行が離婚の原因となり、悪意の遺棄に準じられて虐待・侮辱・犯罪等々が離婚の原因となつた。十九世紀に入つてからは、虐待・侮辱等ばかりでなく、一般に婚姻の継続を堪え難く感じさせる直接侵害の行為が、すべて離婚の原因となり、又犯罪ばかりでなく、一般に婚姻の継続を堪え難く感じさせる間接侵害の行為が、すべて離婚の原因になると見られるに至つた。有責原因の外に無責原因も加はり、相手方の過責ばかりでなく、偶発の事由もまた離婚の原因となる、ことに精神病は主要な無責離婚原因だと認められるやうにもなつた——要するに、婚姻の継続を堪え難からしめるやうな事由ならば、有責か無責か、直接か間接かを問はず、すべて離婚の原因になると見られることになつたのである。
が、かやうに一切の事由を離婚の原因と見るやうになると、もはや列挙の必要はない。むしろ初から列挙を廃し、婚姻の継続を堪え難からしめる事由が、すべてみな離婚の原因となる旨の原則規定一条を、掲げておけば足るであらう。そうして裁判官をして、この原則に照らして各場合が、果して離婚に値するかどうかを判定させればいいであらう。かかる離婚原因の定め方を不定原因主義といふ。不定原因主義は離婚原因拡大史の極致である。
果然、ソヴェート・ロシアの離婚法は不定原因主義をとつた。同法は離婚の原因を列挙することをしない、ただ夫婦の一方は、何時にても離婚の訴を起すことができ、裁判所は、離婚の訴が起された場合には、原被双方を召喚して事情を聴取し、事情が離婚を相当とすれば、決定を以て離婚を言渡すとしてゐるだけである。1)事情が遺棄であるか、姦通であるかは一切問はない、程度が婚姻の連続を難からしめさへすれば、離婚できると見てゐるのである。結局、程度だけが標準であるから、離婚の許される場合が非常に多い。新教会以来の離婚原因拡大史は、ソヴェート・ロシア法において、極大化したといつて、あへて過言でないであらう。
1) Sowjetrussl. G. v. 27/9 1921 87 fg.
第二節 協議離婚【八〇八条以下】
協議離婚はフランス革命の産物である。同革命は裁判離婚の原因を拡大するだけに満足せず、協議離婚といふ新規の制度をも開いたのである。けだし裁判離婚は、私法上の自治を尊ぶ近代の傾向と一致しない。なぜなればそれは、離婚の当否を国家の手で検討し、正当な離婚原因存するときにかぎり離婚を許さうとするもので、多分に干渉的性質をもつからである。裁判を要すとする以上、いくら原因を拡大しても自由な離婚とはいへぬであらう。で、フランスの革命立法は、裁判離婚の外に協議上の離婚を認めた。当事者さへ離婚を欲するならば、国家からその理由の当否を審問されることなしに、離婚できるといふことにした。私法上の自治を離婚にまでも拡大した次第であつた。
しかし離婚の自治などは、伝統の観念からは到底是認さるべくもなかつたので、革命の一過・反動の襲来と共に、廃滅に帰した。ナポレオンの法典はまだ、厳重な制限裡に協議離婚制を存置したが、旧王政の再興後、一八一六年五月八日に、全廃されてしまつたのである。そしてその後復活を見ずにしまつたのである。フランス以外の国々も、協議離婚には強い反対を示しつつ今日に及んだ。がしかし最近に至つて台頭の気合も見える。1)例へばソヴェート・ロシアは協議離婚を認めた。レツトランド・エストランド等の新興国もこれを認めた。2)ポルトガルも一九一〇年十一月三日の命令でこれを認めた。今後いよいよ性の絶対自由が叫ばれてくると共に、協議離婚は、離婚のむしろ正常な方法となりはせぬであらうか?
1) ベルギイはナポレオン法典を継受し、同法典と同一内容の協議離婚制をおく(Belgien, C. c. 275 fg.)。オォストリアは国内のユダヤ人にだけ協議離婚を許す(ABGB. 133 fg.)。
2) Lettl. G. v. 1/2 1921 51---Estl. G. v. 1/5 1923 30.
八六 協議離婚の制限
イ フランス革命の際の協議離婚法は、夫婦はその年限および年齢にかかはらず、協議離婚をなしうるものとしてゐたが、1)ナポレオン法典は、結婚後二年間は協議できぬとし、夫二十五歳・妻二十一歳以下の場合にも協議できぬとした。2)近時の協議離婚法も大抵はこれに類似の制限をおくが、3)中にはソヴェート・ロシア法のごとく、フランス当初の主義に帰つて一切の制限を撤し、結婚後二年以内にも協議離婚ができ、二十五歳以下でも協議離婚ができるとしてゐるものもある。4)わが国法もさうである【八〇八条】。
1) Frankr. G. v. 20/9 1792.
2) C. c. 275, 276---Belgien, C. c. 275, 276---bad. Ldr. 275, 276.
3) Portugal, Dekret v. 3/11 1910 35.
4) Sowjetrussl. G. v. 27/9 1921 87---ABGB. 133, 134.
ロ ナポレオン法典は、夫婦が協議を以て離婚をなすには、その父母の同意をえねばならぬとしてゐたが1)、最近の立法はこの点についても、ナポレオン法典の主義を破つて革命当初の主義2)を回復し、離婚には父母の同意を要せずと定めつつある。3)
わが国法は右の傾向に逆行し、満二十五年に達せざる者が離婚をなすには、結婚同意権者の同意をえねばならぬとする【八〇九条】。その結果、父母がその同意権を悪用して、離婚を欲せざる夫婦に離婚を強ゐるといふ弊が起きてゐるのである。
1) C. c. 278---Belgien, C. c. 278---bad. Ldr. 278.
2) G. v. 22/9 1792.
3) Portugal, Dekret v. 3/11 1910.
八七 協議離婚の手続
イ 協議離婚の手続は、革命当時にさへ、さう簡単なものでなかつた——まづ夫婦が、双方の近親によつて組織された親族会に、自身出頭して離婚せんとする旨を申出る。親族会は和解を勧告する。勧告の効なきを見てから、市町村吏に申請し、親族会の勧解の奏効せざりし旨を証明させる。その証明書を携へて、夫婦は身分吏の面前に出頭、身分吏から離婚の宣告を受けるといふ順序であつた。1)親族会の招集と開会との間に一定の間隔をおき、証明書の日附と宣告申請との間にも一定の間隔をおき、夫婦の軽挙を防止しようともしてゐた。
1) Frankr. G. v. 20/9 1792 II, 1--7.
ロ ナポレオン法典は、濃厚な協議離婚反対の気勢裡に出来上がつただけに、手続の困難は革命法に倍加した。今度は夫婦は、親族会にではなく、裁判官に、離婚を申出さねばならなくなつた。裁判官はこれに対して和解を勧告する。勧告の効なきを見てから、夫婦より離婚の申出ありし旨の証明書を下附する。夫婦はその後一定の間隔をおきつつさらに三回、裁判官に離婚を申出で、その都度和解の勧告を受けねばならぬ。第四回の勧解が無効に終つてから、やうやく正式の離婚許可の申請をなすことができる。これに対しては、裁判官は実質的審査をなさずに離婚を許可するが、離婚は未だこれを以て完了しない、夫婦双方が右許可書を携へて身分吏の面前に出頭し、身分吏から離婚の宣告を受けることによつてはじめて完了するといふ仕組であつた。1)
1) C. c. 279--294; Belgien, C. c. 279--294; bad. Ldr. 279--294.
ハ 比較的手続の簡単だつたのは、墺法が、国内のユダヤ教徒のために設けた協議離婚法であつたが、それすら勧解の手続は置いてゐた。すなはち離婚の申出を受ける管轄牧師(Rabbi)が和解を勧告し、その効なきを見てから和解成らざりし旨の証明書を下附する、その証明書を見た裁判所も、すぐには離婚を許可せず、和解の望あるときは一定期間の延期を命じ、延期も効なきに及んで、やうやく夫が妻へ離婚状(Scheidebrief)を授けることを許可するといふ丁重な順序であつた。1)
1) ABGB. 133, 134.
ニ しかし新しき立法は、断然、勧解の制度を捨ててしまつた。離婚を欲する夫婦に和解を勧告するのは、夫婦の自治能力を信頼せざる干渉主義の遺風である。真に夫婦の意思を尊ぶためには、一切干渉を捨てねばならないと見るからである。ソヴェート・ロシア法のごときは、正にこの見地に立つもので、同法によると、離婚せんとする夫婦はこれを身分吏又は裁判所に申立てる。身分吏が申立を受けた場合には、その申立が真に当事者双方よりなされたりとの確信をえた上、離婚登録をする。裁判所が申立を受けた場合には、期日を指定して当事者双方又はその代理人を呼出し、真にその申立が当事者双方からなされたりとの確信をえた上、決定を以て離婚を言渡し、その決定謄本を身分吏に送付するといふ仕組である。1)全然和解は勧告しない、ただ当事者の出頭を促して、彼らの申立の真否を確かめるばかりである。
わが国では一片の離婚届を提出すれば足りる。和解の勧告はもちろん、申立の真否の審査さへも、試みようとはしないのである【八一〇条八一一条】。その手続の簡単さは、正にソヴェート・ロシア法以上である。
1) Sowjetrussl. G. v. 27/9 1921 87 fg.