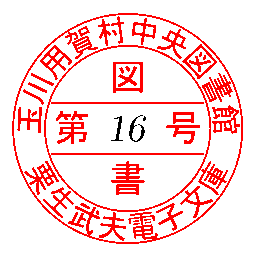
はしがき
狩猟権(Jagdrecht)及漁撈権(Fischereirecht)は、共にゲルマン法によつて育て上げられた制度である。ゲルマン法は古代においてすでに狩猟権及漁撈権の萌芽型態を有し、王朝期に入つてこれを成長させ、封建期に入つて益々成長させ、継受期に入ると、すでにそれは鬱然として形ちを成し、ローマ継受法の勢力を以てしても容易に動かすべからざるものとなつてゐた。もちろんローマ法一般と共に先占自由の原則も継受されたが、この新来の原則は固有法の勢力のために、その適用を阻止されなければならぬのであつた。ローマ継受法の規定にしてゲルマン固有法の規定のために、その適用を阻止されたものは多々あつたが、先占自由の原則もその一つだつたのである(一)(二)。即ちこれを現代に見るも、ローマ法に由来する先占自由の原則は、ゲルマン法に由来する狩猟権及漁撈権のために、その適用力の半以上を失墜せしめられてゐるありさまである。ゆゑに無主動産先占の法理を説くに当つては、この法理そのものの意味を明かにすると同時に、この法理の適用を阻止し牽制してゐる狩猟権及漁撈権についてもまた説くところがなければならぬのであつて、わたくしがここに狩猟権及漁撈権の小歴史を書くのも、かうした趣旨からである。
一 Windscheid曰く——先占自由の原則は、ドイツにおいては、狩猟権及漁撈権が国家・地主その他の者の専属に帰してゐたがために、局限された適用を見出しえたに止つた。即ちドイツにおいては、先占された動物は先占者の所有とならずに、狩猟権者又は漁撈権者の所有となつたのであると(Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts I. 9. Aufl. 1906 S. 942 f.)。
二 Wächterはローマ法もまた狩猟権を知つてゐたと主張した。曰く——ローマ法においても地主は狩猟の権をもつてゐた。彼は他人が自己の土地に立入ることを禁止することができたばかりでなく、他人が自己の土地において狩猟することをもまた禁止しえたのであると(C. G. v. Wächter, Das Jagdrecht und die Jagdvergehen. Sammlung von Abhandlungen der Mitglieder der Juristenfakultät zu Leipzig I. 1870 S. 333 ff.)。しかし通説の見るところはこれと異る。通説はローマ法では無主物先占の自由があつただけで、地主の狩猟権はなかつたと見てゐるのである(Windscheid, a. a. O. S. 942 Anm. 5)。
第一節 狩猟権
一 ゲルマン期(一—六世紀)
ゲルマン期においては自由人はみな狩猟及漁撈の自由をもつてゐた。村の共用地(Allmende)に立入つて狩猟及漁撈をなすことができたばかりでなく、他人使用の田畑へも、収穫完了の後でありさへすれば、自由に立入つて狩猟及漁撈をなすことをえたのであつた。田畑の使用者は、収穫完了の後には——即ち猟期が始つてからは——村人達の狩猟のためにする立入を禁止することができないのであつた(一)。だからいはばゲルマン期においては、個々の田畑の上に、収穫を目的とする利用権と、狩猟を目的とする利用権とが平行的に存立し、さうして前者は各家に、後者は村人一般に、帰属してゐた次第であつた(二)(三)。
奴隷及半自由人は、村の共用地や他人の田畑へ立入つて狩猟及漁撈をなしえぬ定めであつたが、程なく不自由人と自由人との身分別そのものが不明瞭となつてしまつたために、不自由人もまた狩猟仲間(Pürschgenossen)の一員と看做されるやうになつた(四)。ゆゑに慨言してゲルマン期は自由狩猟及自由漁労(freie Pürsch und freie Fischerei)の時代だつたといつてよかつたのである。
かやうにゲルマン期においては各人に狩猟及漁撈の自由があつたから、数人の占取行為(Aneignungshandlungen)の競合する場合も生じ、従つて法としては、かかる場合の紛争を処理する規定を立てておかねばならなかつた。ランゴバルド法のごときは、他人の飼育してゐる家畜はもちろん、他人の訓練した犬及鷹も先占の目的とはならぬ・他人によつて傷けられた動物・他人によつて現に追撃されつつある動物も先占の目的とはならぬ・他人によつて標識づけられた樹木に巣くつた鳥禽もまた先占の目的とはならぬ、と頗る詳密に規定してゐるのである(五)。ザリカ法及リブアリア法も、他人によつてすでに占取されをる動物や他人によつてすでに傷けられをる動物やを捕獲することを禁じ、これを犯せば盗罪の一種となるとしてゐるのである(六)(七)。
かやうな狩猟及漁撈の自由——これこそは部族社会における各人の自由平等性を基礎とした、いはば狩猟権の部族社会型であつたのであつた。
一 各村人は村の共用地においてばかりでなく、収穫完了後でありさへすれば、他人の田畑へも立入つて狩猟することができたといふこと、換言すれば田畑の使用者は、収穫の完了後は、狩猟のためにする村人達の立入を忍容しなければならなかつたといふことについては、Vgl. G. L. v. Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt 2. Aufl. 1896 S. 152; F. v. Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts 1894 S. 396; O. Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts II. 1. 3. Aufl. 1896 S. 568.
二 田畑の使用者は収穫後こそ他人の立入及狩猟を忍容せねばならなかつたが、収穫前には、他人の立入及狩猟を禁止することができ、排他的に自己の使用地に現在する鳥獣を捕獲することもできた。ザリカ法は、収穫前の他人の使用地に立入つて狩猟することをば一種の罪に数へ(Pactus Legis Salicae 33, 1)、リブアリア法も、やはりこれを罪の一種としてゐるのである(Lex Ribuaria 42, 1)。
かやうな自己の使用地において排他的に狩猟しうる権利——これこそは後世の地主狩猟権(Eigentümerjagdrecht)の萌芽型態であつたといはねばならない。
三 Gerberは、ゲルマンには『一般人の狩猟の自由』なるものなく、単に『地主の狩猟権』があつたに止つたといつてゐるが、これは氏が封建期以後の法律状態を見て立言したからである。遡つてゲルマン期の状態をも眼中におくならば、そこに『一般人の狩猟の自由』のあつたことを否定しえなかつたであらう(C. F. v. Gerber, System des deutschen Privatrechts 7. Aufl. 1895 S. 159)。
四 v. Thudichum, a. a. O. S. 396.
五 Edictum Rothari, 309--321.
六 Pactus Legis Salicae 33, 2. 3; Lex Ribuaria 42, 2. 3.
七 当時の狩猟は罠や陥穽の方法を用ゐたので、隣人達に危険が多かつた。よつて西ゴート法などは、陥穽設置の際は隣人達に通告することを要す。通告を怠つた場合に損害を生ずれば、賠償の義務を免れず、と厳重に規定してゐるのである(Lex Visigothorum VIII, 4, 23. Vgl. auch G. L. v. Maurer, a. a. O. S. 153)。
二 王朝期(七—一〇世紀)
王朝期に入ると、もと人民の有だつた狩猟及漁撈の自由が王の独占へと移り始めた。けだし当時の組織法は公法・私法の区別を明かにしてゐなかつたため、人民の権利は国家の有へ移り易く、さらにまた王の有へ移り易く、従つて人民は逐年自由を失つて行かねばならなかつたのであつて、このことは、いはば自然の、いな不可避の成行だつたのであつた(一)。がしかしこの間の関係をもう少し明かにするがためには、わたくしは王による私権の独占、即ちいはゆるRegalienなるものについて、一言を添えなければならない。
Regalien即ち王による私権の独占とは、私法上の能力若くは権利にして、法の特別規定により、王の独占に帰してゐるものをいふ(二)(三)——(一)或は私法上の能力が王の独占に帰してゐることがある。例へば塩の専売・酒の専売といふやうな一定の営利活動をなす能力が王の独占となつてゐる場合。(二)或は物の使用権が王の独占に帰してゐることがある。例へば河川使用の権・牧場使用の権・森林使用の権が王の独占となつてゐる場合。(三)或は物の占取権即ち物権取得権(Aneignungsrecht)が王の独占に帰してゐることがある。例へば採鉱の権・狩猟の権・漁撈の権が王の独占となつてゐる場合。
かかる独占の設定は一般人民の自由や権利に対して一大限界をおくこととなつた。けだしもし或営業が王の独占に入つたとすると、一般人民は同種の営利活動をなしえなくなり、或物の使用権が王の独占に入つたとすると、一般人民はその物を自由に使用できなくなり、或種の物権取得権が王の独占に入つたとすると、一般人民はその種の物権を取得できなくなるからである。だから『独占への編入』はちやうど『公物への編入』の逆だつたといふべく、後者が物を公共の直接使用に供するための行為だつたのに反して、前者は物を王の単独支配へ移すための行為なのであつた。公物から公物性を奪つて王自身の私有財産へ転化させてしまふことが、独占の趣旨とする所だつたのである。
独占は徐々にその範囲を擴め、逐次にその数を加へて行つた。いまその発展の過程を正確に物語ることはできないが、Heuslerに従ふと、漁撈権は早く王の独占に入り、殊に王室所有の林野に沿うて流れる河川においての漁撈の権は、最も早く王の独占に入つたといふ。採鉱の権もまた早くから王の独占に入つたこと明かであるが、狩猟の権は、これに反して、なかなか王の独占へ移らなかつた。といふのは、狩猟は森林利用の一種であり、森林の利用は、ゲルマン人の日常生活と堅く結付いた大切な権利だつたから、民衆は容易にこれから離れようとせず、王も強ひてこれを取上げようとしなかつたためであらう。Heuslerに従ふと、狩猟の権が王の独占に入つたのは、Otto諸帝が民衆から武器を取上げ、彼等を全く『牙なき豚』にしてしまつてから以後のことだつたといふ(四)。
さて或区域においての狩猟若くは漁撈が王の独占に入つたとすると、その区域を独占猟区(Forst, Wildbannbezirk)といふ。独占猟区においては、王若くは王から許可を受けた一部の人々のみが狩猟行為をなすことができ、一般人民はこれをなすことをえぬのであつた。けだし独占猟区は公物性を失つてしまつた土地であり、一般人民の利用しうべき限りではなかつたからである(五)。
尤も独占猟区が、王室林野(Königs-od. Herzogsgut)即ち王の所有地とその範囲を一致させてゐたとばかりは限らなかつた。独占猟区の大部分が王室林野であつたことは事実であるが、その外になほ村の共用地や個人の私有地をも取込んでゐたのであつた。いひかへれば王は自己の所有地の上ばかりでなく、村の共用地や、個人の私有地の上へも、彼の独占網をひろびろと張り廻はすことができたのであつた(六)(七)。けだし当時の観念に従へば、河川使用権・森林使用権・牧場使用権のやうな物の使用権は、土地所有権そのものの一内容ではない。それは土地所有権と相並んで同一土地上に併立する別個の権利である。いひかへれば土地の上には収穫を目的とする土地所有権と、舟行・通行・放牧等を目的とする使用権とが併立し、前者は地主に、後者は一般公衆に、帰属してゐるのであるから、後者が公衆を経由して王の独占へ移つて行つても何等異とするに足りない。採鉱権・狩猟権・漁撈権等の物権取得権もまた土地所有権と併立する別個の権利である。従つてそれもまた、地主以外の人即ち王へ、移つて行つても何等異とするに足りない、といふのであつた(八)。
つまり王の独占狩猟権は自己の土地においての狩猟権(Jagdrecht auf eignem Grund und Boden)とばかりは限らず、往々にして他人の土地においての狩猟権(Jagdrecht auf fremden Grund und Boden)でもありえたのである。
後世に至つて政治上の一大問題となつた『他人の土地においての狩猟権』は、すでにその萌芽を王朝期に発してゐたと見ねばならない。
一 Calisse曰く——ローマの公物(res publicae)は国有であり、而も公共の直接利用に供されてゐたが、ゲルマンの私権独占(Regalien)は王の私有であり、且つ公共の直接利用から遠ざけられてゐたと。又氏は、もと人民の有だつた公物が王の私有へ移つて行つた径路に関していふ——国家の成立と共に人民の権利は国家へ移り、国家を通じて王へ移つてしまつたのであると(C. Calisse, A History of Italian law 1928 p. 675)。
二 Regalienの意味は時代と共に変化した。即ち(一)最初は語義通り、王の有する公権・私権一切の権利を指称したが、(二)十一・二世紀の頃から、王の有する諸権利のうち、王に収入を齎らすもののみを指称するやうになつた。しかし(三)王に収入を齎らす諸権利といふときは、徴税権・造幣権・裁判権のごとき、王の支配権そのものと直接的に結付き、従つて私人へは譲渡することのできない権利をも包含することとなるので、十八世紀の法律家及財政家《カメラリスト》は、王の支配権と直接的に結付き、従つて私人へは譲渡しえざる底の王の収入権と、王の支配権と直接的には結付かず、従つて私人へも譲渡しうる底の王の収入権とを区別し、前者を呼ぶに本質独占(regalia essentialia s. maiora)、後者を呼ぶに偶然独占(regalia accidentalia s. minora)の名を以てした。(四)近代の用語法は、昔日の『本質独占』に対しては国家高権(Staatshoheitsrechte)の語を用ゐ、『偶然独占』に対してのみRegalienの語を用ゐる。即ち近代では、独占された私権のみがRegalienである。Vgl. A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts I. 1835 S. 369; O. Gierke, Deutsches Privatrecht II. 1905 S. 396 ff.; R. Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts 5. Aufl. 1930 S. 286 ff.; G. Seeliger, Art. ``Regalien'' im Hoops Reallexikon der germanischen Altertumskunde III. S. 480 ff.; v. Künnssberg, Art. ``Regalien'' im Handwörterbuch der Rechtswissenschaft III. S. 770 ff.
三 私権の独占即ち固有の意味のRegalienに対する定義として有名なのはHeusler及Gierkeのそれである。Heuslerはいふ——Regalienとは、物に対する収益及先占の権(Nutzungs-oder Occupationsrecht)が権力の作用によつて国家に専属してゐる場合であると(A. Heusler, a. a. O. S. 372)。Gierkeもまたいふ——Regalienとは、私法上の権能が公法の規定によつて国家に専属してゐる場合であると(O. Gierke, a. a. O. S. 399)。わたくしがこれを定義して、Regalienとは、法の特別規定により王の独占に帰してはゐるが、その本来の性質は私法上の権利又は能力であるといつたのも、Heusler及Gierkeの定義に型取つたのである。
四 Heusler, a. a. O. S. 371.
五 当時の人々が独占猟区を呼ぶに、Forstの語を以てしたのも、独占猟区が公共の直接使用の『外』にあつたからである。Forstの語は、『外』(ausserhalb)を意味するラテン語のforisから来たのである(O. Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts II. 1. 1896 S. 568, Anm. 7)。
六 v. Thudichumによると、独占猟区が、村の共用地や個人の私有地の上まで延び擴がつてゐたのは、稀な事実でもなかつたといふ(F. v. Thudichum, Die Gau-und Markverfassung in Deutschland 1860 S. 306 ff.; ders, Geschichte des deutschen Privatrechts 1894 S. 394)。
七 Seeligerは、王は個人の私有地を独占猟区へ取込むことはできなかつたと見た。曰く、王は王の所有地における一般人民の狩猟を禁ずることはできた・村の共用地における村人達の狩猟を禁ずることもできた・しかし個人の私有地における地主自身の狩猟を禁ずることはできなかつたと(S. Seeliger im Hoops Reallexikon III. S. 482)。しかしこの見解は事実にも反し、法理にも反する。事実上当時は個人の私有地の上にまで延び擴がつてゐた独占猟区が多かつたし(前出註六)、法理的にもそのことが不可能ではなかつたから(後出註八)。
八 私権の独占(Regalien)と土地所有権との間の関係を明瞭ならしめたのはGierkeである。曰く——独占私権は土地所有権の一内容ではなくして、土地所有権の外に立つ権利である。それは所有権の内部から出て所有権を制限してゐる制限物権ではなくして、所有権と相並んで同一物上に併立する独立の権利であると(O. Gierke, a. a. O. II. S. 403)。
三 封建期(一一—一五世紀)
封建期に入ると、王の独占私権が諸侯(Fürst)・守護(Graf)・地頭(Freiherr)・教会・修道院などへ移り始めた。けだし独占私権は王に専属してゐたとはいへ、本質は私権だつたのであるから、贈与・封与等の方法によつてそれが封建領主の手へ移つてゆくといふことは、ごく自然な成行だつたのである。従つてこの期においては王の独占猟区が減少して、封建領主の独占猟区の、広汎なる展布を見ることとなつた。
都市もまたこの期においては自己の独占猟区をもつこととなつたが、都市の独占猟区利用の方法は、封建領主のそれといささか趣を異にしてゐた。封建領主はみずからの娯楽のためにこれを利用し、若くは税収入の目的のために、これを貸附けてゐたのであつたが、都市はこれを自己の市民一般へ公開したのである。もちろん中には税収入の目的のために対価を取つて一部の人々だけに利用させた場合もないではなかつたが、概していふと、都市は封鎖主義の代りに公開主義をとつたのである。前段においてわたくしは公物は王朝期において公物性を失ひ、王の私有物となつてしまつたといつたが、都市法期に入ると、それが再び公物性を取戻したのであつた(一)。
封建領主や都市の独占猟区も、往々所有地の範囲を踰越してゐた。ちやうど王が、個人の私有地の上へまでその狩猟独占網を張り廻はすことができたやうに、封建領主や都市もまた、個人の私有地の上へまでその独占網を張り廻はすことができたのであつた。
ではゲルマン古来の自由狩猟及自由漁撈の原則はどんな変化を受けたかといふと、独占猟区以外の場所においては依然として自由の原則が行はれてゐた(二)。ここを自由猟区(Pürschbezirk)といふ。自由猟区は公物性を有し、村人達の直接利用に供せられてゐたから、村人達は自由猟区の区域を明認させるために、その隅角に標識を立てた。今日においてもTübingen附近の山々からは、F.P.の二字を刻した石片が屡々発見されるといふことであるが、F.P.はFreie Pürsch(自由狩猟)の略字である。即ちそれは自由猟区の区域を示した標識の遺物なのである(三)。
自由猟区もまた往々村の共用地の範囲を越えて擴がつてゐた。v. Thudichumのいふところによると、自由猟区が個人の所有地はおろか、王・諸侯の所有地の上へまで擴がつてゐた場合さへあつたといふ。凡そ狩猟権は、上来屡々見たやうに、土地所有権の一内容ではなくて、これと相並んで同じ土地の上に併立してゐた別個の権利だつたのであるから、恰も王や諸侯が村の共用地の上へまでその狩猟権を延ばしえたやうに、村もまた王や諸侯の土地の上へまでその狩猟権を延ばしえたのであつた(四)(五)。
しかしゲルマン古来の自由狩猟及自由漁撈の原則が封建期に入つて、適用の範囲を狭められたことも事実であつた。眼ぼしい山嶽や林野や河川は、王・領主・都市などの独占に移り、村人達の自由に利用しうるものとしては、残り少なになつてしまつてゐたからである(六)。
一 都市がその独占猟区を公開してゐたといふことについては、C. F. v. Gerber, System des deutschen Privatrechts 1895 S. 159 und dort zitierte.
二 ザクセン・シュピーゲル編成の当時、自由狩猟の原則がなほ行はれてゐたことは、同書が、『神は人類を創造した際、人類に魚と鳥と獣とに対する権力をも与へた』(Ssp. II. 61 §1)といひ、『流るる河の面においては何人も漁撈をなすことができる』(Ssp. II. 28 §4)といつてゐるのを見ても明かである(Vgl. A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts I. 1885 S. 369)。
三 v. Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts 1894 S. 395.
四 v. Thudichum, a. a. O. S. 395.
五 v. Maurerによると、Schwaben, Tirol, Schweizの三地方では狩猟の自由がかなり後々まで認められてゐたといふことであるが、この事は頗る興味ある現象でなければならない。なぜかといふと、この三地方は小地主の層の最も遅くまで残存してゐた地方であり、独立の気概も強く、武器携帯の風も後々まで廃れずにゐたのだからである。けだし小地主の層と狩猟の自由との間には密接な関係があり、小地主の層が漸次没落して行くのにつれて、狩猟の自由もまた平行的に失はれて行つたものと見えるのである(G. L. v. Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-und Stadtverfassung 2. Aufl. 1896 S. 154)。
六 一般人民は独占猟区において狩猟することはできなかつたが、そこを通行することは差支なかつた。尤もザクセン・シュピーゲルは、独占猟区通行の際には、弓は弛め、箙は覆ひ、犬は繋いであるべし、と教へてゐる(Ssp. II. 61 §3)。
四 継受期(一六—一八世紀)
継受期は一般人民の狩猟漁撈の自由の極度に弾圧された時代であつた。第一にこの期には自由猟区そのものが減少したし、第二に狩猟の手段たる猟具が制限されたし、第三に狩猟の目的物たるいはゆる狩猟鳥獣(jagdbares Tier)の種類も限定されたし、結局古来の自由主義は有名無実となり、新たにローマ法と共に継受された無主物先占の法理も、その適用を見出しかねる状態だつたからである。
まづ自由猟区の減少から説出すと、継受期は分国の勃興期であり、分国は領土高権の思想に駆られて国権の伸張に専念したから、自由猟区に対する分国の監視権(Aufsichtsrecht)は一転して利用禁止の権(Verbietungsrecht)となり、一般人民を自由猟区の利用から遠ざけてしまつたのであつた。いひかへれば、人民の層から狩猟の自由を奪つてこれを貴族の層へ独占させてしまつたのであつた(一)。いまこれを国別に見てゆくと、Bayernでは一四八七年(二)・一四九三年(三)及一五二〇年(四)に、農民及小市民の狩猟を一般的に禁止してしまつたが、これは恐らくフランスの先例に倣つたものであらう。フランスでは十五世紀以来、いはゆるRoture即ち小都市の市民及農民の狩猟を禁じて、領主に狩猟の権を帰せしめ、領地を有する者は狩猟の権をも有す(Qui a fief a droit de chasse)の原則を確立してゐたのであつたが(五)、Bayernもいまこの例に倣つて、農民及市民の狩猟を一般的に禁止し、凡そこの階層の者は、自己自身の所有地の上においてさへ狩猟をなすことができない、としてしまつたのであつた。
次にSchwabenを見ると、この地方の立法史は明瞭を欠くが、一五二五年、この地方を中心に勃発した農民戦争の指導者達が、有名な十二ヶ条の要求(sog. Artikel von 1525)の中で、農奴制の廃止・夫役労働の軽減・家畜十分ノ一税の撤廃などと共に、狩猟漁撈の自由をも絶叫してゐるところから推すと、やはりこの地方においても、農民の狩猟を禁止する旨の法律が出てゐたものと見えるのである。その後一五五二年になると、西部シュワーベンの領主達が地方会議(Kreistag)の決議を以て、市民及農民に対する狩猟の禁止を断行してしまつた(六)。本部シュワーベンの領主達も、一六八七年及一六九七年にやはり地方会議の決議を以て同趣旨の禁令を発したが、これに対してはUlm, Leutkirsch, Biberach等の諸市が猛烈に反対したため、遂にその実施を見るに至らず、ために本部シュワーベンにおいては、近く十九世紀に至るまで、自由猟区の残存を見ることができた(七)。
Brandenburg, Mecklenburg, Pommern, Preussen等における立法の経過も亦明かでないが、Preussenにおいては、一七〇一年まで自由猟区の残存を見たらしい(八)。
次に狩猟の方法を見ると、継受期に入つてから、庶民階級(市民及農民)に対する武器携帯の禁が厳重化して来たので、庶民階級は、自由猟区が認められてゐた場合においても、武器の使用はできなかつた。庶民にして武器を携帯する者は平和攪乱者(Friedbrecher)と看做し、死罪に問ふといふのが、当時の掟だつたのである(九)。庶民としては罠・陥穽等の原始的方法において狩猟をなすの外はなかつた。
次に狩猟の目的物を見ると、継受期には狩猟鳥獣を大小の二級に分ち、大鳥獣は貴族のみの狩猟目的となる・庶民階級は、自由猟区をもつ場合にも、小鳥獣しか狩猟できぬとしたのであつた。大小の分ち方はもとより区々であつたが、熊・鹿・猪・鶴は概して大鳥獣に数へられ、兎・狐・獺・栗鼠・雁・鴨は概して小鳥獣に数へられた。中には大中小の三段主義をとり、大鳥獣は上級貴族(hoher Adel)のみの狩猟目的となり、中鳥獣は下級貴族(niederer Adel)の狩猟目的となり、小鳥獣のみが庶民階級の狩猟目的となるとしたものもあつた(一〇)。
又この時期には先猟権(Vorjagdrecht)の制度を生じた。先猟権とは猟期が始つてから数日間は貴族のみが狩猟をなし、そのあとで庶民が狩猟をなすとするもので、庶民の狩猟を実質的に空無ならしめたものであつた(一一)。
上述のごとく継受期には庶民は狩猟から遠ざけられ、貴族のみがこれを独占するやうになつたが、かうなると、貴族の狩猟熱は益々高まるばかりであつた。彼等は彼等のなすべき公の任務を忘れて狩猟にのみ熱狂するやうになつたのである。それも猪狩とか鹿狩とかいふ荒々しい種類のものばかり好むやうになつたのである。彼等は猟期の娯楽を高めるために、平素から野猪の類を蕃殖させておく方針をとつたから、彼等の猟区に隣接する農民の田畑は、常住野猪の害に曝されてゐなければならなかつた。而もかうした野獣害(Jagdschaden)に対して、彼等は賠償の責任に任じなかつた。野獣の蕃殖は貴族の狩猟権そのものの中に含まれる当然の権能だと見られてゐたからである。農民は彼等の農作物を現に荒しつつある鳥獣をば殺すことはできたが、殺した鳥獣は狩猟権者たる貴族に納付しなければならなかつた。又農民は彼等の農作物を保護するために田畑の周囲に障囲をめぐらすことはできたが、障囲の費用は自分で負担しなければならなかつた。それのみか猟期になると、農民は貴族の狩猟行為を援助するために勢子(Treiberdienst)その他の雑役にも服さねばならなかつたが、これもまた無償であつた。勢子の役目は、彼等が貴族に対して負ふ夫役労働の一種だとされてゐたからである(一二)。
ゆゑに貴族の狩猟特権に対する庶民の反感は猛烈を極めた。それは封建制そのものに対する彼等の益々高まりゆく反感の、一原因とさへなつたのである(一三)。
かかる貴族の身分特権たる、他人の土地へまで侵入して狩猟しうるところの権利——それこそは狩猟権の封建社会型でなければならない。
一 Heuslerは、王朝期の私権独占(Regalien)に関して、王は人民の共用地利用の方法を監視することができたが、かかる監視権(Aufsichtsrecht)は人民の直接利用を禁止する禁止権(Verbietungsrecht)となり易く、遂には進んで共用地そのものに対する王の所有権ともなつてしまつたといつたが、この説は王の私権独占に対してばかりでなく、分国君主の私権独占に対しても妥当するのである(A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts I. 1885 S. 368)。なほ継受期に入つて私権独占の範囲が広まり、著しくその数を増したことについては、Vgl. R. Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts 5. Aufl. 1930 S. 268 ff.
二 Herz. Albrechts v. Baiern Verordn. v. 1487. Abgedruckt bei Kraut, Grundriss zur Vorlesungen über das deutsche Privatrecht 1886 S. 223 Nr. 16.
三 Herz. Albrechts v. Baiern Verordn. v. 1493. Abgedruckt bei Kraut, Grundriss S. 223 Nr. 17.
四 Baierisch. Landpot. Blatt 41. Abgedruckt bei Kraut, Grundriss S. 224 Nr. 18.
五 Ordonnance de 1396, 1451, 1533, 1581. Vgl. auch W. Schäffner, Geschichte der Rechtsverfassung Frankreichs II. S. 365 ff.
六 Polizeiordnung der Stand im Elsass. 1552. Abgedruckt bei Kraut, Grundriss S. 224 Nr. 28.
七 v. Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts 1894 S. 398.
八 v. Thudichum, a. a. O. S. 398.
九 十五世紀以後、分国の君主達はいはゆる平和同盟(Landfriedensbündnis)を結んで相互の平和を誓ひ合つたが、平和規約(Landfriedensgesetz)の中には警察法・刑法・刑事訴訟法等の規定を含み、庶民階級の武器携帯を禁ずる旨の規定をも含んだのである。
一〇 Cod. August. tom. II. p. 611, 612. Abgedruckt bei Kraut, Grundriss S. 224 Nr. 21. Vgl. auch Preuss. Lr. II. 16 §37.
一一 v. Thudichum, a. a. O. S. 396.
一二 一七八六年頃、Badenの或不明作家の書いた書物に、『バーデン国にもまた、他国におけると同じやうに、人類の安寧・幸福よりも、鹿類の保存の方がもつと大切な事だとおもつてゐる林務官がゐる。彼等は、百姓達がその田畑の周囲に繞らす垣の高さをなるべく低くさせ、鹿類をしてこれを飛び越えることにつき、あまり苦労をさせたくないと考へてゐる云々』と書いてゐるさうである(Abgedruckt bei Thudichum, a. a. O. S. 400 f.)。
一三 貴族の狩猟権に対する農民の不平がフランス革命の一原因となつたといふことについては、Vgl. H. Schreuer, Deutsches Privatrecht 1921 S. 154.
五 フランス革命と狩猟権
フランス革命は、封建制度の遺物として当時なほ残存してゐた貴族の諸特権を一撃的に払拭したが(一)、封建的狩猟権即ち貴族がその身分特権として他人の土地においても狩猟をなしうるといふ権利もまたこの嵐のなかに覆滅し去つたのであつた。即ち一七八九年八月四日、国民議会(Assemblée nationale)は徹夜の会議を以て封建的諸特権——領主裁判権・十分の一税・夫役労働制・買官制等々の廃止を決議したが、封建的狩猟権の廃止もまた、この決議の一項目として包含されたのであつた(二)。尤も同夜の決議は、貴族に対する民衆の反抗心を一時的に鎮静せしめんとする動機に出たので、決議条項の中には、あとから修正を受け内容を抜かれて、空文化したものもないではなかつたが、狩猟権に関するかぎりは、即時の実行を見たのであつた。けだし地方の農民は、八月四日夜の決議内容を伝聞するや、『封建特権は廃止された。狩猟特権もまた廃止された。狩猟は今や万人のものだ』と叫び、それぞれ自己の土地においての狩猟を開始し、貴族がその身分特権をふりかざして農民の土地へまで入猟して来るのを事実上阻止してしまつたからである。ゆゑに同夜の決議第一条の冒頭にいふ、国民議会は完全に封建制を破壊したり(L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal)の句は、狩猟権に関するかぎり、直ちに効力を発生したと見ねばならない(三)。
即ちここに貴族身分を基礎として他人の土地へまで立入つて狩猟をなすといふ、封建型の狩猟権が廃止されて、土地所有者がそれぞれ自己の土地において狩猟をなすといふ、あくまでも土地所有権者を本位にした、市民社会型の狩猟権が発生した次第であつた。
一 封建制は政治上の封建制と私法上の封建制とにわかれる。政治上の封建制とは、貴族の政治的支配権をいひ、私法上の封建制とは、貴族の私法上の特権をいふ。後者は前者を基礎として生れたものであつたが、前者よりもはるかに長く生き残つた。殊にフランスにおいては貴族の政治的支配権は、十六世紀以後の王権の華々しい発展のために、早くも萎縮してしまつたが、私法上の特権の方は、十八世紀末まで生き残つた。さうして後者に対して遂にフランス革命の嵐が起きたのである。いひかへればフランス革命は、政治上の封建制に対して起つたのではなくて、私法上の封建制に対して起つたのであつた。
二 一七八九年八月四日の決議は、進歩的な二人の貴族——vicomte de Noailles et duc d'Aiguillon——の発議の下になされたが、これらの貴族がみづから進んでこのやうな『崇高な棄権行為』をなしたのは、これによつて、当時始まりかけてゐた、貴族の邸宅に対する民衆の焼打行為を中止せしめんとの民心緩和策としてであつた。ゆゑに情勢に安定を生じ、危険やや去ると見ると、貴族達は豹変して、八月四日夜の決議を裏切るやうな態度をとり出した。殊に一七九〇年二月頃から反動の形勢が顕著になつた。尤も狩猟特権とか領主裁判権とか夫役請求権とかいふ類の、いはば名誉的な封建特権は、さすがにこれを抛棄することを惜まなかつたが、農民の土地に対する貢税・譲渡税・相続税といふ類の、いはば実質的な利益を伴ふ封建特権は、できるだけ保持しようとし、少くとも農民若くは国家から相当の賠償あるまでは、保持しようとしたのであつた(Ph. Sagnar, La législation civile de la révolution française (1789-1804); essai d'histoire sociale 1898 p. 120)。
一七九二年八月以来、革命の嵐がいよいよ激化し、封建制の維持に汲々としてゐた貴族達を片つ端からギロチンの下へ運んでしまつたのも、もちろん過度に興奮せる人民の罪ではあつたが、同時に貴族達が先きの約束を反古にし、一旦抛棄した封建特権を保持し続けようと、無用の小策を弄し過ぎた因果の報でもあつたであらう。
三 国民議会は一七八九年八月四日夜の決議(arrêté)については、王に裁可を求めずに公布のみを求めたが、これは、もし裁可を求めると、王が否認権(veto)を行使して失効させてしまふかも知れぬといふ危惧からであつた。果して王は公布についても躊躇し、同年十一月三日に至つてやうやく公布手続(promulgation)をとつた。ゆゑにフランスにおける封建的狩猟特権の廃止は形式的には一七八九年十一月三日からであつた。
さて以上のやうな革命立法の、ドイツに対する影響はといふと、ドイツは、フランスが一夜の間に覆へしたものを覆へすために、六十年の歳月を要したのであり、而もそれは、大征服者ナポレオンの刺ある鞭にさんざん打叩かれて、長夜の惰眠から起きあがつた上のことなのであつた。よつていまナポレオン時代におけるドイツの形勢を一瞥することにすると、この時代のドイツは三つの部分に分れた。一はライン左岸の地であつて、ここにはドイツ諸侯の領地が、人口にして三百万、地域にして千平方哩も擴がつてゐたが、これらは一八〇一年、全部ナポレオンの直接統治下へ収められてしまつた。ナポレオンは勝誇つた鷲印をここに打立てると同時に、従前の法律を廃して、新しいフランスの法律を施行することとしたから、同年以後、ライン左岸の地においては、貴族の狩猟権の廃止となり、地主狩猟主義の確立を見たのであつた。
二はドイツの中央部であり、Bayern, Baden, Würtemberg, Nassau等の、いはゆるライン同盟の諸国から組成されたが、これらの諸国は、ナポレオンからいはば間接の統治を受けてゐたので、この皇帝より、フランス革命の遺産たる新法律をも受容れ、それぞれ自由主義的なる国内改革を行ひつつあつた。尤も貴族の狩猟特権の廃止を断行するまでには至らなかつたが、狩猟の目的物となる、いはゆる狩猟鳥獣の、加へるところの害については、貴族といへども、損害賠償の責任を免れずとする旨の法律は、続々と発布されつつあつた。年代順にこれをならべてみると、一八一〇年八月六日のHessen法、一八一一年五月二十一日及一八一五年一月十日のNassau法、一八一七年六月十三日のWürtemberg法、一八三三年十月三十一日のBaden法等々。
三はPreussen及Österreichの二大国であるが、この二国は、フランス革命の影響から遠ざかつてゐただけに、その後も十八世紀的な法律状態をもちつづけた。殊に一八一四年、ナポレオンの支配力が顛覆されてからといふものは、封建的諸勢力が再興し、新しいすべての計画と思想とを反動の波の中に押流してしまつたので、狩猟法の改革も、停頓状態に陥つてしまつたのであつた。
しかし一八四八年パリに二月革命が爆発し、フランスが共和国として宣言されたといふ報が伝はると、さすがのドイツも俄然として立上つた。三月五日にはいはゆるハイデルベルヒ会議(Heiderberger Versammlung)が開かれ、三月三十一日にはいはゆるフランクフルト予備議会(Vorparlament)が召集された。これらの会議は自由主義者達の任意の集りに過ぎず、公の資格は欠いてゐたが、しかし次第によつては国民みづから自己の憲法を制定せんとする警戒すべき気勢を示さずにはおかなかつた。よつて公の機関たる同盟会議(Bundestag)も——これは各国政府の代表者の会議であり、自由主義運動鎮圧のための機関でもあつたが——大あはてにあはて出し、従来の反自由主義的諸決議を撤廃すると同時に、みづからその組織を改めて国民の代表者をも自己の中へ参加せしむべき旨を宣言した。三月三十日には同盟会議は国民代表者の選挙方法に関する決議をなし、五月十八日には、この選挙方法によつて選挙された議員達がFrankfurt a. M.に集合した。これがいはゆる憲法制定のための国民議会(deutsche konstituierende Nationalversammlung)であるが、同議会は、その仕事の手始めとしてドイツ国民の基本権(Grundrechte des deutschen Volks)に関する決議をなしたのである。さうしてその決議の中において、出版の自由・言論の自由・集会の自由等々と共に、封建的狩猟権の廃止をも宣言したのである。即ち同決議の七節三十七条はいふ——
『土地所有権の中には自己の土地における狩猟の権も含まる。他人の土地における狩猟権は、狩猟夫役その他の給付と共に、無賠償にて廃止せらる。将来といへども、他人の土地における狩猟権を物権として設定することを許さず』(一)。右の決議は一八四八年十二月二十七日公布されて効力を発生した。よつてドイツ内の諸国はこの新原則に則つてそれぞれ狩猟法の改正を行ふことになつたが、Preussenだけに関していふと、同国は一八四八年十月三十一日の法律を以て、『他人の土地における狩猟権は無賠償にて廃止せらる』(二)、『土地より分離して物権としての狩猟権を設定することは、将来といへども、これを許さず』(三)、『土地所有者は、その土地において、許されたる方法を以て、それぞれ自己の狩猟権を行使することを得』(四)と規定したのであつた。
その他の諸国も同じ方向へむかつて、狩猟法の改正を行つていつた。
かくしてドイツにおいてもまた、市民社会型の狩猟権、即ち土地所有者が自己の土地において狩猟を行ふとする制度が、フランスにおけると同様に、充分なる確立を示したのであつた(五)。
一 Grundrechte des deutschen Volks Art. 7, §37.
二 Preuss. Ges. v. 13. 10. 1848 bert. die Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden und die Ausübung der Jagd. §1, I.
三 Preuss. Ges. v. 31. 10. 1848 §2
四 Preuss. Ges. v. 31. 10. 1848 §3, I
五 狩猟及漁撈に関しては、各支邦はドイツ民法施行後も従来の法律をもちつづけることができた(EGBGB Art. 69)。いな各支邦は、その後も、新しい狩猟法や漁撈法を制定することができたのであつた(EGBGB Art. 218)。Preussenだけに関していふと、同国は民法施行前の旧い法律としては、一八五〇年三月七日の狩猟警察法(Jagdpolizeigesetz)・一八九一年七月十一日の鳥獣害法(Wildschadengesetz)・一八九五年七月三十一日の狩猟免状法(Jagdscheingesetz)をもち、民法施行後の新しい法律としては、一九〇四年七月十四日の鳥獣保護法(Wildschongesetz)・一九〇六年七月四日の共同猟区の管理方法に関する法律(Gesetz über die Verwaltung gemeinschaftlicher Jagdbezirke)をもつた。一九〇七年七月十五日の狩猟令(Jagdordnung)は、以上諸種の狩猟法を集大成した法典であり、(一)狩猟権の範囲(二)猟区(三)狩猟免状(四)鳥獣保護(五)鳥獣害(六)鳥獣害の予防(七)官庁(八)刑罰(九)経過規定の九節に亘つて、詳細の規定を含んでゐる。
六 現 代
以上をもつてわたくしは狩猟権変遷の跡を述べ終つたので、附論として現代諸国の狩猟制へも論及しておくと、わたくしはそこに三つの基本型を発見する。一は各人に狩猟の自由を認め、ただ狩猟行為の方法に関してのみ一定の規則を立ててゐる国々(スペイン・ポルトガル・北米合衆国の諸州)であり、二は国家又は地方団体に猟区設定権を認め、国家又は地方団体が設立した猟区へは一般人は入猟することができず、特に入猟の許可をえた者のみが入猟できるとする国々(スヰスの諸州)であり、三は土地所有者に猟区設定の権を認め、土地所有者が設定した猟区へは土地所有者と彼から入猟の許容を受けた者のみが、入猟できるとする国々(ドイツ・フランス・ベルギイ・オランダ等々)である。ちやうど歴史上、狩猟の自由と領主の狩猟権と地主の狩猟権との三型があつたやうに、現代法上も、ほぼこれに類する三型を見るのである(一)。
まづ狩猟自由(Jagdfreiheit)の主義をとつてゐる国々(スペイン・ポルトガル・北米合衆国の諸州)を見ると、これらの国々では、狩猟は、一定の人々が権利の行使として排他的にこれを行つてゐるのではなくて、すべての人々が自由の享受として平等に行つてゐるのであるが、法律は狩猟行為の方法に関しては一定の制限をおく。けだし現代のやうな利害関係の錯綜せる社会の中においては、狩猟行為の方法を各人の自由に一任しておくわけに行かないからであるが、よく見ると、その制限に二つの別がある。一は鳥獣の保護・公安の保持といふ見地より加へられた行政法上の制限であり、二は土地所有者の保護といふ見地から加へられた私法上の制限である。前者即ち行政法上の制限としては、或は狩猟の用具を制限し、或は狩猟の時期及場所を制限する。後者即ち私法上の制限としては、狩猟者に対する土地所有者の立入禁止権を認める。
而もさらによくこれを見ると、私法上の制限は細別されて二となる。一は狩猟者の側に重点をおくものであり、二は土地所有者の側に重点をおくものである。
前者即ち狩猟者の立場を重んずる国々では、狩猟者は原則として自由に他人の土地へ立入ることができ、土地所有者はこれを忍容しなければならない。ただ狩猟行為が土地所有者の利益を害する虞ある場合、即ち土地が耕耘されてゐるとか、土地に作物があるとか、障囲があるとかいふ場合にのみ、土地所有者は狩猟者の土地立入を禁止することができる、としてゐるのである。スペイン・ポルトガル・南米の国々はこの主義をとる。
後者即ち土地所有者の立場を重んずる国々では、狩猟者は原則としては他人の土地へ立入ることができない。耕耘されてゐる土地・作物のある土地・障囲のある土地へはもちろん、開かれたる土地・収穫完了後の土地へも当然には立入ることができない。立入を欲する場合には一々土地所有者の承諾をえなければならないとしてゐるのである。北米合衆国の諸州はこれに入る。
ゆゑに北米合衆国の諸州は表面こそ狩猟自由の主義をとつてゐるが、事実上は地主狩猟の主義へ傾いてゐると見ていい。なぜかなら北米の諸州においては土地所有者は、狩猟者の土地立入を禁止した上で、自分自身、狩猟を行ひうるのだからである。
わが国も狩猟自由の主義をとる。即ちわが国においては無主動産先占の自由に基いて何人も無主の鳥獣を捕獲することができるのである。もちろん狩猟行為の方法については行政法上の制限があるが、土地所有者保護のためには殆ど制限らしいものを見ない。ゆゑにわが国においては土地所有者は原則として狩猟者の立入を忍容すべき義務があり、ただ耕耘された土地・作物のある土地・障囲のある土地等について、狩猟者の立入を拒否することができるだけだと見ねばならない【参照、狩猟法第十七条】。即ちわが国は北米式の土地所有者尊重主義ではなくて、スペイン・ポルトガル式の狩猟者尊重主義をとつてゐるのだと見ねばならない(二)。
次に国家狩猟主義(Jagdrecht des Staates)をとつてゐる国々を見ると、この種の国々では国家又は地方団体が一定の猟区を設定し、一般人の入猟を禁止し、一定の賃料を納めた人々にのみ入猟を許容するのである。猟区は公有地の上ばかりでなく、私有地の上へも設定される。けだし狩猟権は所有権から独立してゐる権利であるから、猟区設定権者たる国家又は地方団体は、土地所有者の同意をえ又はえずして他人の土地の上へも猟区を設定できると見るからである。特定人へ入猟を許容するについては、狩猟賃貸(Jagdpacht)の方法によるが、狩猟賃貸は賃借人に狩猟権の行使を許すのみで、土地の使用権を与へるのではない。従つて狩猟借人は狩猟権を実質的に行使するのみで(Jagdausübungsrecht od. Jagdrecht im materiellen Sinne)、土地につき占有を有してはゐないのである。賃料は相当の高額に上る。けだしそれは公物の使用料ではなくして、独占権の賃借料なのだからである。国家又は地方団体にとつては、それは一つの財源とさへなつてゐる。
かやうに国家狩猟主義は、国家が一定の猟区を独占して私人に賃貸する主義であるから、その本質は、封建時代の私権独占(Regalien)と異る所がない。強ひて相異を求めれば、昔は封建領主が猟区を設定して私人に賃貸し、今は国家又は地方団体が猟区を設定して私人に賃貸するだけである。
わが国法も、『国、道府県、郡又ハ市町村』に猟区の設定の権を認めてゐる【狩猟法第十四条】。さうして猟区設定者は『一日ニ付五円ヲ越』えざる『承認料』を取つて猟区における狩猟を許容しうるものとしてゐる【狩猟法第十八条、狩猟法施行規則第二十二条二項】。ゆゑにわが国は一方においてはスペイン・ポルトガル式の狩猟自由主義をとつてゐるが、地方においてはスヰス式の国家狩猟主義をとつてゐるのだと見なければならない。
しかし国家狩猟主義は、昔日の私権独占のなごりであるだけに、多くの国々からはすでに見すてられてしまつてゐる主義である。今日この主義をとるものは、スヰスの諸州とわが国位のものではあるまいか?
終りに地主狩猟主義(Grundeigentümerjagdrecht)をとつてみると、この主義はフランス革命の遺産として仏独を初め、現代ヨーロッパの国々の殆ど全部が採用してゐるところであるが、細別すると二つになる。一は猟区の面積に何等の制限をおかず、いかなる小面積の土地所有者も、それぞれ自己の土地において狩猟をなすことができるとする、いはば純粋に個人主義的な行き方である。フランス・ベルギイ・オランダなどはこれに入る。二は猟区の面積に一定の制限をおき、制限以上の大面積を有する地主は自己の土地のみを以ていはゆる自己猟区(Eigenjagdbezirk)を設定することができるが、制限以下の小面積を有するに過ぎない地主達は、彼等の小所有地を寄集めて、いはゆる共同猟区(gemeinschaftliche Jagdbezirk)を設定すべしとする、いはば共同主義を加味した行き方であり、ドイツ・オーストリイ・チェッコ・ルーマニアなどはこれに入る。では土地なき者は狩猟ができないのかといふと、独法は、土地なき者も狩猟賃貸(Jagdpacht)の方法によつて他人の猟区に入猟することができると見る(三)。即ち物権としての狩猟権(Jagdrecht)を他人の土地上に設定することはできないが、債権としての狩猟行使権(Jagdausübungsrecht)を約させることは可能だと見る。仏法は、永小作権者及用益権者を所有権者に準じ、これらの者に当然に狩猟権を帰属させ、借地人もまた、当事者間の契約によつて狩猟権者となりうると見てゐる。ゆゑに土地なき者のためにも、狩猟の道は充分に開かれてゐるのだと見ねばならない。
一 現代諸国の狩猟法に関する一般的叙述としては、P. Gieseke, Art. Jagd-u. Fishereirecht im Rechtsvergleihenden Handwörterbuch fü das Zivil-u. Handelsrecht IV. S. 542 ff.; Stier-Somlo, Art. Jagdrecht im Handwöterbuch der Rechtswissenschaft III. S. 241 ff.; Endres, Art. Jagd im Handwöterbuch der Staatswissenschaften 4. Aufl. V. S. 371 ff.——邦文としては佐藤百喜『狩猟制度ニ就テ』(国家学会雑誌第三十二巻七号八号)。
二 イタリイは一方において狩猟自由の主義をとり、凡そ政府の免許をえた者は、自己及他人の土地において狩猟を行ふことができるとしてゐるが、他方においては土地所有者主義をも併用し、土地所有者若くはその組合は、政府の許可をえてその土地の上に猟区を設定し、排他的に狩猟を行ふことができるともしてゐる(P. Gieseke, Art. Jagd-u. Fishereirecht im Rechtsvergleihenden Handwörterbuch für das Zivil-u. Handelsrecht IV. S. 543)。
三 猟区利用の方法は、普通は狩猟賃貸(Jagdpacht)の方法により、他人をして狩猟権を行使させるのであるが、時とすると狩猟権者自身経営の主体となり、猟師(Jäger)を雇傭して狩猟の実際に当らしめる場合もある。西洋において猟師(Jäger)とは、普通、狩猟権者に雇傭されて現実の狩猟行為に従事する者をいふ。
七 二三の問題
上来の叙述は、狩猟権の主体即ち狩猟権が何人に帰属するやの点を中心とした考察であつたがために、自然、(一)狩猟が一般人の自由であつた時代、(二)領主の独占であつた時代、(三)地主の独占となつた時代の別を生じたが、狩猟権に関してはなほさまざまの問題がある。でわたくしは上来の叙述に対する補遺として、残されたる諸問題を簡単に取扱つて見るとしよう。
まづ狩猟権(Jagdrecht)の性質からいふと、狩猟は、自由狩猟主義の下においては権利でなくして自由である。なぜかならこの主義の下においては、何人も自己又は他人の土地において狩猟を行ひうるのだからである。もちろん行政法上の制限はあるが、行政法上の制限は、狩猟そのものに対する制限ではなくて、狩猟行為の方法、殊に狩猟の目的物・用具・時期・場所に対する制限であるから、かかる制限にもかかはらず、一般人は狩猟の自由即ち無主動産先占の自由をもつてゐるのである。
ところが国家狩猟主義及地主狩猟主義の下においては、狩猟は単なる自由でなくして私法上の一権利である。けだしこれらの主義の下においては、国家若くは地主が一定の猟区を設定し、一般人の入猟を排斥しつつ、独占的に狩猟を行ひうるのだからである。
然らばこの権利の性質はといふと、むろん物権ではない。なぜかならそれは特定物を支配しうる権利ではなくして、無主物を取得しうる可能(Erwerbsmöglichkeit)なのだからである。又それは期待権でもない。期待権の場合には、物は法の作用によつて当然に権利者に帰属するが、狩猟権の場合には、占取行為(Aneignungshandlung)といふ権利者自身の行為によることを必要とするからである。ゆゑに狩猟権はいはゆる物権取得権(Aneignungsrecht)に入ると見なければならない。物権取得権の特徴は、権利者自身の一方的占取行為によつて物を自己の所有に帰属せしめうる点にあるが、狩猟権もまた漁撈権や採鉱権と共にかうした特徴を具有してゐるのである(一)。
次に狩猟権の内容を見ると、この権利の主たる内容は、一定の猟区において無主の狩猟鳥獣を先占しうる点にあるが、これだけに尽きるのではない。その外に狩猟権者は、猟区において発見される狩猟鳥獣の死体【寒気の襲来・動物相互間の格闘によつて無数に生ずることがある】・狩猟鳥獣の落せる牙・角等を当然に収取することもできるし、垣を結んで動物の逸走を防ぎ、その蕃殖を図る、いはゆる囲込権(Hegerecht)をももつのである。
ゆゑに他人の猟区に侵入して狩猟した場合ばかりでなく、猟区の附近に餌をまいて動物を誘致且つ捕獲した場合にも、それによつて狩猟権者の権利行使を不可能ならしめたものとして、狩猟権の侵害となるであらう。
かやうに狩猟権者は自己の猟区における狩猟鳥獣を排他的に捕獲しうるのであるから、狩猟鳥獣が猟区を離出して隣地又は隣地の作物を害した場合、即ちいはゆる鳥獣害(Wildschaden)の場合には、狩猟権者において損害賠償の責に任ずべき筈であるが、このためには特別の規定を要する。なぜかなら猟区に存在する鳥獣は自由な鳥獣であつて、未だ狩猟権者の占有に移つてをらず、従つて狩猟権者に対して動物占有者としての責任を問ふわけにゆかぬからである。これ各国が鳥獣害について特別の規定を設けるゆゑんであるが【例、一八九一年七月十一日のプロシヤ鳥獣害法、一九〇七年七月十五日のプロシヤ狩猟令、ドイツ民法八三五条等】、わが国にはかかる特別の規定がない。従つてわが国法の解釈としては、狩猟鳥獣が猟区を離出して隣地又は隣地の作物を害したやうな場合にも、猟区の設定者は損害賠償の責に任ずる必要がないであらう。
なほ『狩猟鳥獣』の語について一言すると、独法は狩猟権の見地から鳥獣を三種に分つ。一は狩猟権者といへども捕獲することをえぬ鳥獣であつて、これを保護鳥獣(geschütztes Tier)といふ。二は狩猟権者のみがその猟区において捕獲しうる鳥獣であつて、これを権利狩猟鳥獣(befugt jagdbares Tier)といふ。三は狩猟権なき者も自由に捕獲しうる鳥獣であつて、これを自由狩猟鳥獣(frei jagdbares Tier)といふ。けだし独法は既述の通り、地主狩猟主義をとつてはゐるが、例外として自由狩猟(freier Tierfang)をも認め、あまり価値なき鳥獣虫魚の類は、何人といへども、自己又は他人の土地において自由にこれを捕獲することをうとしてゐるので、ここに自由狩猟鳥獣の概念を生じ来るわけなのである【Vgl. Hedemann, Sachenrecht. 1924 S. 157.】。
ところがわが国法を見ると、狩猟法の第一条第一項は、『狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ之ヲ捕獲スルコトヲ得ズ』と規定してゐるので、『保護鳥獣』に対立する概念として、『狩猟鳥獣』の語を使用してゐることがわかる。従つてわが国法の狩猟鳥獣は、独法のそれよりも広い意味をもつことになる。即ち独法のそれは、狩猟権者がその猟区において捕獲しうる『権利狩猟鳥獣』のみをいふのであるが、わが国法の狩猟鳥獣は、(一)狩猟権者【猟区設定者及之より承認を得たる者】が、この猟区において捕獲しうる『権利狩猟鳥獣』の外に、(二)狩猟免状を有するすべての人が、自己又は他人の土地において自由に捕獲しうる『自由狩猟鳥獣』をも包含するのである。
然らば狩猟鳥獣はいつ狩猟者の所有に入るかといふと、もちろん先占完了の時期でなければならないが、先占完了の時期については見解の相違がある。一はこれを厳格に解するものであつて、鳥獣を射落しただけでは足らず、現実にこれを狩猟者の実力下に齎らすことを要すると主張する。二はこれを寛大に解するものであつて、これを実力下に齎らすの必要はない。射落しただけで充分である。否、致命傷を負はしめただけで先占となると主張する。いづれかといふと、古くは前説が盛んだつたが、今は後説が有勢である(二)。
致命傷を負はしめられた鳥獣が遁走して他人の土地内へ潜入した場合はどうなるかといふと、狩猟者は、土地所有者の承諾をえて彼の土地に立入り、みづからその鳥獣を捕獲することもでき、土地所有者に請求して、その鳥獣の返還を受けることもできる。けだし致命傷を負はしめられた鳥獣は、すでに先占せられて狩猟者の所有に入つてゐるのであるから、狩猟者は、その所有権に基いてその鳥獣の返還を求めうるわけである。
では軽傷の場合はどうかといふと、それがすなはち追撃権(Verfolgungsrecht od. Jagdfolge)の問題である。而してこの問題への解答も時代によつて異るのであつて、昔は概して狩猟者に追撃権を認め、狩猟者は自己が追出し若くは傷けた鳥獣に関しては、他人の土地へまで侵入してそれを捕獲することができると見てゐた(三)。現代においても自由狩猟主義をとるスペイン・ポルトガル・北米合衆国の諸州などでは、やはり追撃権を認め、狩猟者はすでに開始せる先占を完了させるためには、土地所有者の反対にもかかはらず、他人の土地内へ侵入することができると見てゐるが、地主狩猟主義をとる独仏その他の国では追撃を許さず、狩猟者は鳥獣が他人の土地に到達するや否やその追撃を中止しなければならぬとしてゐる(四)。
終りに密猟者(Wilderer)と密猟物(Wilderegut)との関係を見ると、この問題の取扱ひ方も時代によつて異る。領主が狩猟権を独占してゐた時代には、領主は猟区に存在する一切の鳥獣の上に所有権を取得しうる権利を有すと考へられたから、領主は自分自身先占行為をなさず、密猟者がこれをなした場合にも、先占物即ち密猟物の上へ法律上当然に所有権を取得することができた。いはば彼の所有権取得は先占の効果といふよりも、彼の地位に伴ふ特権であつたのであるが、かやうな考へ方は、実は、多少の変容の下に現代へまで残存してゐるのである。例へばドイツ民法九五八条第二項は密猟者は密猟物の上に所有権を取得することなき旨を明規してゐるし、学説もまた、構成の仕方こそ区々であるが、ひとしく密猟物を狩猟権者の所有に帰せしめんとする傾向を示してゐるからである。
しかし密猟物の狩猟権者への帰属は、領主狩猟主義・国家狩猟主義・地主狩猟主義等の下においてこそ可能であるが、自由狩猟主義の下においては、維持さるべくもない。なぜかなら自由狩猟主義の下においては、侵害せらるべき狩猟権がない。従つて真の意味の密猟もない。そこにはただ行政法の規定に対する違反があるだけであるから、所有権の帰属に関する限りは、先占者が、行政法規に対する違反にもかかはらず、なほ先占物即ち密猟物の上に所有権を取得すと見ざるをえないからである。
然らばわが国法上はどうかといふと、既述のごとく、わが国法は自由狩猟主義と国家狩猟主義とを併用してゐるのであるから、密猟の問題についても、場合を二つに分けなければならない。一は狩猟者が権利なくして他人の猟区で狩猟した、真の意味の密猟の場合であり、二は狩猟者が行政法の規定に違反して狩猟した、単なる違反の場合である。さうして私見によると、真の意味の密猟の場合には、密猟物は狩猟権者即ち猟区設定者の所有となるが、単なる違反の場合には、捕獲物は、行為の違法性にもかかはらず、捕獲者の所有となる。なぜかなら前の場合には狩猟権者といふ独占的取得権者があるが、後の場合にはかかる独占的取得権者なく、従つて、捕獲物はこれを捕獲者に帰せしめるの外に道がないからである。さうでもしなければ、捕獲物は捕獲にもかかはらず、なほ無主物だといふことにならざるをえまい。
人或はいはん、違法行為によつて所有権を取得することが可能であるかと。しかし違法行為から適法状態の生ずる場合がないでもない。例へば悪意の加工者は不法行為者であるが、しかし加工物の上に所有権を取得するではないか【民法二四六条一項但書、BGB. §950; Motive zum Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deitsche Reich III. Sachenrecht S. 360】。密猟者の密猟物取得もまたこれと類似の関係にある。
かやうに密猟物はわが国法上二種に分れ、或は狩猟権者の有となり、或は捕獲者の有となるのであるから、贓物の罪を論ずるに当つても場合を二つに分けなければならない。即ち他人の猟区で狩猟した真の密猟の場合には、密猟物は他人の物であるから、情を知つてこれを買へば、これによつて他人の所有権の行使を妨げたこととなり、贓物故買の罪を犯したことにもなるが、単なる行政法違反の場合には、捕獲物は捕獲者の所有であるから、情を知つてこれを買つても他人の所有権の行使を妨げたことにならず、従つて贓物故買の罪にもならぬのである。
要するに狩猟権をめぐる各種の問題は、法が、歴史の産み出した三つの狩猟型のうち、いづれをとつてゐるか、即ち自由狩猟主義をとつてゐるか、国家狩猟主義をとつてゐるか、地主狩猟主義をとつているかによつて、その答へ方を根本的に別異にさせてゐるのである(五)。
一 わが国の通説は漁撈は権利であり、狩猟は自由であると見るやうであるが、一概にさうはいへない。わが国においても、狩猟法十四条の規定によつて設定された『猟区』における狩猟は、自由の享受でなくして、狩猟権といふ物権取得権(Aneignungsrecht)の行使である。
二 P. Gieseke, Art. Jagd-und Fischereirecht im Rechtsvergleichenden Handwörterbuch IV. S. 547.
三 Sachsenspiegel II. 61, §4は追撃権に関する有名な規定である。曰く——『或人が野獣を森(領主の独占猟区を指す——栗生)の外で狩り、そしてそれに随いて犬が森の内部に入れば、その者は……追躡して何等差支ない。そして若し彼が野獣を即時に捕へたときには、それに於て何等違法行為を犯したのではない云々』(金沢理康訳による)。
四 Preuss. Ges. v. 31, 10. 1848 §4: Das Recht der Jagdfolge ist aufgehoben; Hannov. Ges. v. 1850 §13: Jagdfolge findet nicht ferner statt; das Wild gehört demjenigen, in dessen Jagdbezirk es ergriffen wird.
五 密猟物は何人の所有に属するかといふと、通説は密猟者は密猟物を占有してゐるだけで所有はしてゐないと見る。その理由は、猟区の鳥獣を有効に、即ち所有権取得の効果を以て、先占しうるのは狩猟権者だけである。密猟者は先占はできても、その先占に所有権取得の効果を伴はしめることができない、といふにある。
では狩猟権者はいかにして密猟物の上に所有権を取得するかといふと、その理由には窮せざるをえない。なぜかなら無主物の上に所有権を取得するためには、先占を必要とするのに、狩猟権者は先占を行つてゐないのだからである。即ち密猟者は『効力なき先占』をなし、狩猟権者は『必要なる先占』を欠いてゐるといふことになる。
或は曰く、狩猟権の中には、初めから密猟物を取得しうる権能が含有されているのだと。しかし封建時代の領主ならば格別、現代の狩猟権者にこのやうな優越的地位、即ち他人の先占した物を当然に取得しうる地位を認めるわけにはゆかない。ゆゑにGerberのごときは、初めの間こそこの説をとつてゐたが、後には、『再考の結果その非を悟つた』といつて、この説を棄ててゐるのである(Gerber-Cosack, System des deutschen Privatrechts 17. Aufl. 1895 S. 161 Anm. 1)。
第二説はいふ——狩猟権者は占有の取得によつて、みづから所有権を取得しうる。なぜかなら密猟者が占有してゐる密猟物は、先占にもかかはらずなほ無主物なのであるから、狩猟権者はこれに対して有効なる、即ち所有権取得の効果を伴ふ占有を取得することができるからと(O. Gierke, Deutsches Privatrecht II. 1905 S. 530)。第三説はいふ——狩猟権者は代理によつて所有権を取得しうる。なぜかなら密猟者は狩猟権者の無権代理人として狩猟権者のために先占行為をなしたのだからと(Schültze, Jahrb. des gem. deutschen R., herausg. von Bekker und Muther VI. S. 103 ff.)。第四説はいふ——狩猟権者は直接には所有権を取得することをえないが、間接にはこれを取得しうる。なぜかなら密猟は狩猟権の侵害であり、不法行為であるから、狩猟権者は密猟者に対して損害賠償の請求権を有し、賠償の一方法として密猟物そのものの返還をも請求できるからと。Gerberがその著の一七版において採つたのはこの説である(Gerber-Cosack, a. a. O. S. 161 Anm. 1)。Stobbeもこの説に従つた(Stobbe-Lehmann, Handb. des deutschen Privatrechts II. 1. 1896 S. 583)。
右の諸説はいづれもみな密猟物の所有権を狩猟権者に帰せしめるものであるが、反対にこれを密猟者に帰せしめるものもないではない。Thonの説がこれである。曰く——密猟物が『無主物』だといふことになると、これを侵奪しても『盗』にならなくなり、実際上不都合である。だからわたくしは禁じられたる先占によつても所有権は取得できると見たい。即ち密猟物は密猟者の有となり、狩猟権者はこれに対して賠償の請求権をもつに過ぎないと見たいと(Thon, Rechtsnorm und subjektives Recht 1878 S. 337 Anm. 19)。
これを立法例に徴すると、恰も学説におけると同じやうに、狩猟権者に密猟物の所有権を認めるものと、密猟者にこれを認めるものとの二主義がある。ザクセン民法は前の例であり、ウルテンベルグ法は後の例である(Sächs. GB. §231. Würtemb. Jagdgesetz v. 27. 10. 1855)。
しかし概していふと、真の意味の密猟の場合即ち他人の独占猟区で密猟した場合に関しては、狩猟権者に密猟物の所有権を帰せしめる見解が優勢であり、単なる違反の場合、即ち狩猟者が行政法規に違反しつつ自由猟区で狩猟した場合に関しては、捕獲物の所有権を捕獲者に帰せしめる見解が優勢である。なぜかなら後の場合には侵害さるべき狩猟権が存在しないのであるから、捕獲物はこれを捕獲者に帰せしめるの外に、取るべき道がないからである。
要するに密猟問題の取扱方は、いはゆる密猟が独占猟区において行はれたか、自由猟区において行はれたかによつて、全く答を別異にする。前の場合には密猟物は狩猟権者に帰し、後の場合には捕獲物は捕獲者に帰するのである。
(本稿は第一節において狩猟権を論じ、第二節において漁撈権を論ずるつもりで執筆し始めたが、第一節を論じただけで、予定の紙数を越えてしまつた。一旦ここで擱筆する。)