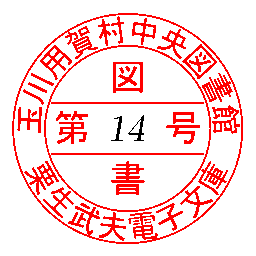
一 懐疑的態度と神学的態度
『法律家は、制定法の内容を知らねばならないが、彼の任務はそれのみに尽きはしない。彼はさらに法を、その正当性において検討し、法として立ち現はれてゐる不当の制規(die als Recht auftretende Satzungen)を除去し、改廃することに配慮すべきだ』とH. Marxはいつた(一)。実際、制定法の内容には、欠陥もあれば矛盾もあり、不明もあれば不当もある。規定すべくして規定しなかつた場合・規定の趣旨の相互抵触するもの・規定の精神の明瞭ならざるもの・規定の内容の正当ならざるもの等々、数へ来れば『制定法は、穴だらけの、切り張りの、矛盾且撞着の小作品に外ならぬ(二)』ともいへるのである。そのゆゑにこそ、解釈学者は、制定法におけるこれらの諸欠点を除去しようと、鏤心刻骨の苦を積みつつあるのであつて、その広く内外の学説を漁り、社会の通念を問ひ、最近の傾向を案じ、方法的にはまた、拡張解釈・縮少解釈・その他種々の論理的曲芸を演ずるのも、詮すればみな、制定法の不備を補ひ、矛盾を去り、不明を明瞭にさせるためで、制定法完全化の目的外には出てをらぬのである。解釈学は決して制定法の内容をあるがままの姿において把握し記載することを以て任としてゐるものではない。それは、実に、制定法に拠つて制定法の上に整然たり完然たる体系を構築せんことを目的としてゐるものなのである。
一 H. Marx, Der Wissenschaftscharakter der Jurisprudenz, 1918, 87 fg.
二 田村博士・法律学の価値に関する懐疑・一二〇頁。
右のごとく、すべての解釈学は、程度に多少の差こそあれ、いづれもみな制定法の完全化に悩苦しつつあるのではあるが、しかもなほ彼等の標榜するところは、分れて二となる。(一)は、制定法の諸欠点を卒直に承認し、従つて解釈に、制定法補完の作用、換言すれば新法規創造の作用を認むるもの。(二)は法律秩序の完全性を仮説し、従つて学説による法規の創造を認めず、事実上は学説を以てこれを創造しながらも、表面上は恰も法律自身の内部に初めから解釈の成果と同一のものが包有されてゐたかのごとくに云ひ、『学説は法律に新たなるものを加へず、初めから法律中に存在せしものを明るみへ引出すに過ぎず』と説くものである。後の解釈態度は、謙虚といへばいへるのであらう。みづから法を生産しておきながら、初めから法律裡にそれが内蔵されてゐたかのごとくに説くからである。しかし、見方を易へれば、自己の所信に反して法律の完全性を説く説教師的態度だともいへるであらう。充分に制定法の諸欠点を知悉してゐながら、知悉してゐればこそ、それを糊塗し彌縫せんとして種々の論理的曲芸をも弄してゐながら、人に向つては法律秩序の完全性・円満性をまことしやかに説くものであるからである。
第一の態度、すなはち制定法の完全性を疑問としつつ解釈作業にとりかかる態度を、解釈上の懐疑主義といひ、第二の態度、すなはち制定法又は法律秩序の円満性・完全性を信仰しつつ解釈作業にとりかかり、解釈の成果が初めから法律裡に内蔵されてゐたかのごとく説く態度を、解釈上の独断主義とよぶ。独断主義は又神学主義ともよぶ。なぜならば、かくのごとき研究態度は、他の学問において類例を見ず、わづかにかの神学と称するものにおいて比疇を見出しうるに止るだけであるからである。
二 神学の特性
本稿において、わたくしは、法律解釈学が、いつ、いかなる事情から、神学的態度をとるに至つたかを尋ねたいのであるが、それにはまず神学そのものの性質を究明しておかねばならない。なぜなれば、法律解釈学が神学的態度をとるに至つたのは、後に論証しようごとくに、中世の末にそれがカトリック教会の神学たるスコラ学の影響を受けたためであつたのであるから、スコラ学こそ法律解釈学の助産婦にして、その性質を把握するは、やがて法律解釈学そのものの神学性を明にするゆゑんともなるだらうからである。
よつて、わたくしは、有名なGrabmannの著述『スコラ的方法の歴史』第一巻序説のなかから、スコラ的方法の特性に関して近世の諸大家の下してゐる諸見解を学びとり、以てスコラ学の何たるかを見ると共に、斯学と法律解釈学との関係をつきとめる一助ともしたいのである(一)。
一 Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode I, 1-37
Grabmannのあげた学者の数は十数人の多きに上つてゐるが、その中の代表的な二三を選ぶと、Paulsenはいつてゐる——
『スコラ学の目的は、教会の信仰を合理的なものとして証拠立てようとするに在つた。教会の信仰は大体において学問的認識と相一致するものだといふことを証示するのが彼等の仕事であつた』と。つまりPaulsenに従へば、スコラ学は一方において信仰を支持し、他方において理性を尊び、信仰と知識とを平行さすことによつて、信仰の虚妄ならざるゆゑんを示さうとしたのである。根底において、それは、信仰主義であり、決して理性主義ではなかつたのであつた。せいぜいのところ半理性主義(Semirationalismus)で、純理性主義ではなかつたと、Paulsenは考へるのである。
Seebergも同じ考を次のやうな言葉でいひ表はしてゐる——
『スコラ学者に共通の要素は、権威と理性(auctoritas und ratio)とであつた。彼等はバイブル・教説・独断・伝承・法王等を、毀損すべからざる基本材料として受取り、盲目的にこれを尊重した。彼等はこれらの基本材料を整序し、組織し、信仰と学理とを連結せんと試みた点において、理性の働きをわづかに発揚しえたに過ぎなかつた』と。すなはちSeebergに従つても、スコラ学では信仰が主、理性は従に過ぎなかつたのであつた。
転じてGingensohnの説を見ると、彼いはく——
『中世の学問にとつての基礎前提は、権威及信仰(Autorität und Glauben)であつた。当時の考では、真理は新たに求めらるべきではなくて、すでに存在してをり、すでに啓示されてゐるのであつた。人々は、啓示されてをり、公認されてをる真理を疑ふことを許されなかつた。教会の威勢は、公認真理に対する力強き保証であつたのであつた。学問的活動はただ二つの方向において存立しえたに過ぎなかつた。(一)は、啓示されてゐる真理を系統的に組織立てる企て。(二)は、啓示されてゐる真理を、この世の日常の出来事へ適用して見る試み。後者は、それによつて、いかに「真理」が地上一切の出来事を裁いて綽々としてなほ余裕あるかを、換言すれば、いかに「真理」が深遠博厚のものであるかを、証示せんがためであつた』と。つまりGingensohnに従へば、スコラ学は、半理性主義どころか、全然独断主義・信仰主義であつたのである。理性は全く信仰と権威との背後にひそみかくれてその鋭鋒を示さずにゐたと見るのである。
その他Loofs, Seeberg, Eucken等の定義も、概して同様であり、いづれも、スコラ学を以て外的権威に服属した一の『拘束科学』(gebundene Wissenschaft)と見てゐるのである。
わが波多野博士も、
『組織神学は、一定の特殊宗教の具体的、個性的なる生内容を承認し、主張する。それ故にそれは最早単なる学ではないであらう……組織神学は一つの信仰であるか』といつてをられる【波多野精一博士・宗教哲学の本質及其根本問題・二九頁。】。
右の諸説を見るとき、われわれは『われらの学問、法律解釈学』の肖像を見せつけられるがごとき思ひをせぬであらうか?あまりといへばわれらの学問が神学に類似してゐるのに驚愕せぬであらうか?実に、二つは、相似形のごとくに相似てゐるのである。神学者が教会の教説を是認し、その完全性円満性を主張するやうに、法律学者は国家の法律を是認し、その完全性円満性を主張するのである。教説のなかにあらゆる人生問題への答が用意されてゐると神学者が考へるやうに、法律秩序のなかにはあらゆる法律問題への答が用意されてゐると法律学者は考へるのである。神学者にとつて、真とは教説と一致することをいひ、偽とは教説と一致せぬことをいふのであるが、法律学者にとつても、正とは条文と一致することであり、不正とは条文と一致せぬことである。他の学問が理性の要求に傾聴してゐる間に、神学及法律学は外的権威に拘束されてその外に出ずにゐるのである。他の学問が実験を重んじ、事実がいかにあるかを探らうとしてゐる間に、神学及法律学のみは『言葉』を重んじ、法典や経典に何が書かれてあるかを見ようとしてゐるのである。その他、抽象的観念を重んずる点において、条文を大前提として推論式に判断を進めて行く点において、あまりといへば法律学は神学に近似してゐるのである(*)。
が、しかし、法律学のかかる性格は果して先天的宿命的であるのであらうか?法律学たるかぎりかかる性格を担はざるをえずしてさうなつてゐるのであらうか?いないな、吾人の見るところを以てすれば、法律学の神学性は、中世の末、それがスコラ学の影響を受けてから以後のことで、中世の初頭までは、決してかかる坊主臭を帯びなかつた。すなはち、法律学の神学性は、吾人の見るところを以てすれば、全く歴史的・経過的・一時的のものたるに過ぎぬのである。先天的に法律学がさうなければならぬといふ宿縁もなささうに見えるのである。以下、われらは、法律学における神学性の端緒をさぐり出すために、ローマ以後の法律学を見るであらう。
(*) 神学と法律解釈学との相似性に初めて気づいたのは、十九世紀の輝ける神学者Schleiermacher (1768--1834)であつたであらう。彼はその『解釈の観念について』(Ueber den Begriff der Hermeneutik)と題する秀れたる小品論文のなかにおいて、法律解釈学の特質にもふれ、含蓄ある次の一句を残した——
『大体において法律解釈学は、制定法の範囲の確定(Bestimmung des Umfanges der Gesetze)を仕事にしてゐる。すなはち、それは、ある条規の中に明確には包想されてゐない場合に対して、その条規がどんな関係に立つであらうかを決定せんとつとめるものである』(Schleiermacher, Ueber den Begriff der Hermeneutik, Stämtliche Werke, 3. Abt. 3 Bd. S. 347 Anm.)
と。この句は、第一に、制定法のなかに不明その他の欠点あることを認め、第二に、解釈学は制定法中の諸欠点を除去し補正する任務をも担ふものなることを認め、第三に、解釈学は事実上みずからの力で制定法中の諸欠点を補完しておきながら、みずからの力でこれを補完したとはいはず、初めから法律中に解釈の成果と同一の内容が包有されてゐたかのごとくに説くと見てゐるのである。すなはち、解釈学は、神学と同様に、制定法の完全性を独断的に仮定し信仰的に予断してゐると見てゐるのである。なほ、神学と解釈学との類似性については、vgl. Radbruch, Grundzüge der Rechtsphilosophie (1914), S. 192 fg. ——但し本年に入りRadbruchは、新著ともいふべき姿において彼のGrundzügeを改訂し、表題も単にRechtsphilosophieと改めたが、新著においては、神学と解釈学との類似の問題を扱つてをらない。
三 ローマ時代の解釈態度
ローマの学者は、法律解釈の方針につき体系ある理論は立てなかつたが、断片的には諸所に彼等の解釈態度を示してゐる。Digestaの開巻第一に出てゐるCelsusの、『法は正義・衡平の術なり』(Ulp. D. 1, 1, 1)の語のごときも、制定法解釈の方針を示せるものとも見られうるであらう。Celsusは又、
『法の文言を知れるを以て法を知れりとなすべからず、法の意味精神を知れるを以て法を知るとなすべし』(D. 1, 3, 17)ともいつてゐる。彼にとつては、文言は枝葉的な価値しかもつてゐなかつたのであつた。
Modestinusもいふ——
『文言には然々とあれども、精神上然らざる場合多し』(Modestin. D. 27, 1, 13, §2)と。彼にとつても文言は標準ではなかつたのであつた。
Paulusに至つては明瞭にいふ——
『凡そ法においては衡平を考慮せざるべからず』(Paul. D. 50, 17, 90)と。彼は又、
『文法的にいかに正しくとも、衡平の要求に反する解釈は、法文の故意的曲解なり』(Paul. D. 10, 4, 19. Vgl.)とさへいひ放つてゐるのである。
Ciceroもいふ——
『衡平を説けば法の解釈となる』(Rep. 5, 2)と。これらの単句は、いかに衡平の観念がローマ人にとり解釈の原理(Auslegungsmaxime)であつたかを示してゐるとおもふのである。彼等のいはゆる解釈(Interpretatio)は今日の解釈(Auslegung)とは根本的に性質を異にしてゐたのであつた。それは、制定法裡に包有されてゐる意味内容を明にする宣言的なものではなくて、制定法中に存せざる規範を産む創設的のもの、若くは制定法中の不当を改変させる修正的のものであつたのである。従つて、ローマ法においては、制定法の意味の一義的に明かなりし場合においても、解釈の余地はなほあつたわけで、現にUlpianusのごとき、
『法務官の告示の意味が明瞭なる場合にも解釈の必要はなほ存す』(Ulp. D. 25, 4, 1, §11)といつてゐる位であるのである。修正が目的であつたから、意味明瞭な場合にも「解釈」の必要はあつたわけだ。
近代のローマ法研究者たちの通説も、制定法に対するローマ人の態度の懐疑的且つ自由的なりしことを認めつつあるのであつて、例へばSavignyはいふ——
『ローマ人の「解釈」は、往々、解釈の限界を越えて法の修正となつてゐた。今日のわれわれよりも彼等ははるかに大なる解釈の自由を有したのである』【Savigny, System I, 297 fg.】と。Puchtaもいふ——
『われらは、今日、制定法の意味を確定することを解釈といつてゐるが、ローマ人は、成文法へ不文法を加へ、此によつて彼を補正することを解釈といつてゐた。彼等は成文法の言語的内容や立法者の原動的意思やに拘束されず、むしろ生活の実際的必要を見、自由なる解釈の作用によつて制定法と生活とを握手させようとしてゐたのである』【Puchta, Institutionen I. 316 fg.】と。Kippもいはく——
『ローマ人の「解釈」は衡平の要求に従つて法を育成させるために行はれた。「解釈」は、法と衡平との仲介者に外ならなかつた』【Kipp, Geschichte d. Quellen d. röm. Rts. 4. Aufl., 8】と。Kissもいふ——
『ローマの学者は、論理上からだとか、立法者の意思がかうだとかいふだけでは満足しなかつた。この種の結論を、彼等は衡平の試金石で検したのである。法規の論理的意味への執着よりも、一般福利の観念の方が、彼等には重要であつたのであつた』【Kiss, Jherings Jahrb. 58, S. 431 fg.】と。最近ではBruckが次のやうにいふ——
『ローマ人は制定法に対して非常に自由な考をもつてゐた。彼等は制定法が何を規定してゐるかを見るよりも、実際上利益がいかに衝突してゐるかを認識し考量しようとしたのである。法律形式(Rechtsformen)よりも生活形象(Legensgebilde)を見ようとしたのである。解釈の名において彼等は新しい法規を発見して行つた。大なる自由を以て衡平の観念に合する法規を創造して行つた。彼等の活動は法の適用(Rechtsanwendung)に存せず、むしろ法の創造(Rechtsschöpfung)に存したのである。「ローマ法の精神」は、その方法の自由法学的だつた点にこそ存する』【Bruck, Römisches Recht und Rechtsschöpfung der Gegenwart 1930, 21 fg.】
『ローマ人は、判断の過程よりも判断の結果を重んじた。条文を解いたり、ほじつたりしながら、結論へ辿りついて行つたのでは、決してない。一種の政治家的達見を以て妥当な結論を直観し、端的に判断を下したのである。結論自身の立派さにも似ず、その判断過程は甚だ疎であつた。現時の英国の法律家たちがさうしてゐるやうに、彼等も屡々理由を示さずに直ちに``yes'' ``no''を答へたのであつた』【Bruck, a. a. O.】と(*)。
(*) 実際上も、学説は、ローマ法の発達に対して顕著な貢献をなしたのであつた。共和の末から帝政の初期へかけての同法の旺盛な発育ぶりは、主として、学説によつて制定法の固陋を訂正してゆくことができたことに原因したのであつた。Pomponiusいはく、『十二表法の制定後、漸次、学者による解釈の必要を生じたるが、学者によつて作られし法を不文法(Jus non scriptum)又は市民法(Jus civile)といふ』と(Pomp. D. 1, 2, 2, 5)。実に、学説法は、制定法と相共にローマの法律組織の一半を形成してゐたといつても過言ならざるありさまであつたのである(恒藤・羅馬法に於ける慣習法の歴史及理論・二〇頁以下)。
如上の所解に対しては、次のやうな疑ひも生じるであろう。——『帝政初期までのローマ人の解釈態度は、所説のやうな懐疑主義・自由主義のものであつたでもあらうが、ローマの法源史は、第三世紀の半以後、決定的な転換を示した。皇帝が専制絶対の君主となり、立法の権も解釈の権も皇帝の一手に帰属してしまつた。かかる大転換が生じてから後も、ローマ人はなほ自由法学的解釈態度を持続してゐたと主張しうるであらうか』と。いかにも三世紀の半以後、法律解釈の権が立法の権と同様に皇帝の独占するところとなつてしまつたことは事実であつた。だが、しかし、皇帝の解釈態度は実は曩日の学者の解釈態度と少しも異つてゐなかつたのであつて、やはり法と衡平との調和を図り、制定法の不備不当を補完修正することを以て眼目としてゐたのであつた。現に大帝Constantinusはいふ——
『衡平と法との間に生ずる疑義を決するは朕の権なり』(Constantin. C. 1, 14, 1)と。解釈の権こそ皇帝へ移りもしたれ、解釈の方針そのものは、昔のままの衡平主義であつたのであつた。実にConstantinusは、
『正義・衡平に対する尊敬は、制定法に対する尊敬の上にあらざるべからず』(Constantin. C. 3, 1, 8)とさへ、極言してゐるのである。
そこには制定法の完全性・円満性を信仰し仮想するやうな信仰的思想は、痕跡だも見られなかつた。反対に、そこには制定法の自足完了性を疑つてかかる懐疑的傾向と、解釈の作用を以て制定法の不備不当を払はうとする改革精神とが、盛んに燃え立つてゐたのであつた。
四 中世初期の解釈態度
すでにローマ人の解釈態度を見終つたわたくしは、眼を中世へうつして、中世初期——ここに中世初期とは、十一世紀末までをよぶ——の学者の解釈態度を検討しなければならないが、夕暗の空にも似たる当時の世界に、二つ三つ星のごとくに懸つてゐたのは、(一)イタリイはRavennaの法律学校。(二)やはりイタリイはPaviaの法律学校。(三)東方のConstantinopelの法律学校。——わづかにこの三つのみであつた。これらの三つの学的光星が、各々どんな解釈態度を示したかを左にのべて見ようとするのである。
Ravenna学者の解釈態度 Ravenna法律学校の教授たちの、制定法に対する態度を知るための基礎史料は、十一世紀の半頃同地で編纂された通称Exceptiones Petriといはれる法律書である。これは同地の学者Petrusが、さる地方領主のために、裁判上の参考書として作つたもので、その巻頭の序文には、次のごとき注意すべき一文が掲げられてゐるのを見るのである——
『法律の現状においては、不備不当の規定あまりにも多く、斯学の智識を修得せる者でさへも、事案に対して決定的判断を下し難い場合少くない。よつて、著者は、判決及弁論の成果のなかから、自然法及人定法の法理に合したもののみを拾つてここに一書を成す。著者は、法律中の、不使用に帰せる規定、廃止に遭ひたる規定、若くは衡平の観念に反する規定をば、躊躇するところなく踏みにじつて進んだ。著者は領主閣下にささぐるに、新たに発見されたる、若くは忠実に保存されたる真理のみを以てする。この書を閣下の裁判審理と法律起草とに使用さるることによつて、庶幾くは、閣下が、一切の不当と非難とから免れられ、正義のために、閣下の尊厳のために、上帝の称賛のために、何事も輝しくなるであらうことを』と(一)。
一 Abgedruckt in Savigny, Geschichte d. röm. Rts. im Mittelalter II. 321 u. Fitting, Juristische Schriften 151.
見よ、そこには現行法制の完璧性に対する信頼などは微塵もないではないか。反対に、そこには、現行法制の不備不当を単純に認める卒直さと、大いにそれを修正してやらうとする傲つた心とが、波打つてゐるのを見るではないか。われわれはRavennaの学者から、ローマ人からと同様の、いなそれ以上の改革精神を、熱いばかりに感じるのである。
されば、中世法律学の研究家Fittingはいふ——
『Ravennaの学者たちは、かの法規創造の権利を認められてゐたローマの法律家の後継者を以て、みづから大いに任じてゐた。全く自由な方法を以て既存の法規を改変することができ、新しき法規を創造することができ、内的なる正義の要求を直ちに法として通用させることができるものだと信じてゐる』【Fitting, Anfänge der Rechtsschule zur Bologna, 117】と。
実際又Exceptiones Petriの著者は、書中屡々著者自身の創造にかかるとしかおもへぬやうな規定をも掲げてゐるのであつて、例へば、
『原告が、被告の裁判所へ出頭せざるを怒つて、自力で、被告の動産、不動産を差押へ、家を焼払ひ、葡萄畑を荒し、木を切倒したとしても、罪とはならぬ』【Excep. Petri IV. 7】などといつてゐるが、かやうな規則はローマ法にはない。どうしても、それは、著者自身が、公権力の保護なかりし当時の社会状態に鑑み、又、自力救済を認め来つたゲルマン古来の慣行を案じて、みづから立てた、著者のいはゆる『新たに発見された真理』であつたとしかおもへぬのである。
結局Ravennaの学者は、ローマ的解釈態度の後継者であり、懐疑主義者であり、自由主義者であつたと見ることを至当とするのである。
Pavia学者の解釈態度 Paviaの法律学校は、前出Ravennaの法律学校がローマ法の学校であつたのに対してロンバルド法の学校であつたが、そこの学風は、十一世紀の半を画線として『古学』と『新学』との二派に分れるといはれてゐる。古学の方は未だ法律解釈学にはなつてゐなかつた。なぜなれば、古学は、ロンバルド古来の法源を蒐集し、分類し、便利な法源集を編成することを以て仕事の目的としてゐたに過ぎなかつたからである。Walcasus, Bonifilius等は、『古学者』(antiqui)に属する。彼等は単なる『法律上の博識家』にして、某年某月、王某・皇帝某が、某の法律を出したといふやうなことを暗んじてゐたに過ぎなかつた。
真正の解釈学は、十一世紀の後半に興つた『新学』に始るのであるが、新学の特色を知る基礎史料は、後に同地で『Pavia学者の学説彙纂』として結撰されたExpositio ad librum Papiensemなる書物である。そしてそのなかにわれわれは次の一句を見出すのである——
『法律のなかに答を見ざる新問題に逢着せる場合には、万人の普通法たるローマ法によりて決すべし』【Expos. ad Guido c. 5】と。この句はやはり、ロンバルド法自身の不完全性・不充分性を端的に自認してゐるのである。その制定法観において、Ravenna学者と何等異るところのないのを見るのである。
『新学者』(moderni)の錚々たるものをLanfrancusとする。かれは古学の破壊者であり、新学の創建者であり、彼を出発点として新学は発生したのであるから、彼を知るは新学を知るゆゑんともなるのである。よつて、わたくしはLanfrancusの解釈態度を知るために、Expositioのなかから一二の例を引いて見ると、(一)は、公正証書の真偽の決定方法に対する一法条への彼の解釈である。その法条にはかうある——『公証人及立会人共に死亡せる後において、公正証書の真偽が争はれたる場合には、当事者は、十二人の保証誓言者を立つることによりて、その証書の真実性を立証することを得』と。この条文を解釈してLanfrancusはいふ【Expos. ad Guido c. 5】——十二人の保証誓言者を立てさへすれば形式的に、証書の真実性を立証することができるといふごときは、『嫌ふべき慣習』(mos detestabilis)である。かかる反良俗的条規には、法としての効力をもたせてはならない。法としてそれは無効であると。勇敢にも彼は右条規の拘束力を否認してゐるのである。けだし、保証誓言の制度は、偽証の弊などの全くなかつた古代においては存在の意義もあつたれ、その弊のすでに生じつつあつたLanfrancusらの時代には、著しく不当のものとなりつつあつたので、彼はこの制度の絶滅を期しつつ、上のごとくに解釈したのであらう。そこにやはり制定法改革の精神の鋭いあらはれが見られるのである。
(二)は、重婚の問題に関してである。Lanfrancusは一の疑問を掲げていはく——『夫が第一の妻をして修道院に入ることを余儀なからしめた後、第二の妻を娶つたとすると、その場合に、夫の遺産に対して1/4の相続権をもつのは、第一の妻か、第二の妻か』と。而して、彼はみづから如上の疑問に答へていはく——『原則としては修道院入りは婚姻解消の原因なれども、夫から入院を余儀なくされたやうな場合には、入院には婚姻解消の効果なし。従つて問題の場合に1/4の相続権をもつは第一の妻にして第二の妻にあらず、第二の妻は法律上の妻にあらざるなり』【Expos. ad Guido c. 8】と。これもLanfrancusが、衡平の理念のために——婦人の地位の向上のために——成文規定を改変させようとしてゐた証示と見ることをうるでもあらう。
要するにPaviaの学者も、Ravennaの学者と同様、『解釈の要は、実際生活上の需要を考へて制定法を修正したり、新しい法規を創造したりするところにこそ在る』と見解してゐたのであつた。
Constantinopelの学者の解釈態度 ビザンチンの学風がどんなであつたかといふことにについては、わたくしは前に屡々詳述の機会をもつたので、それをここに再びしようとはおもはない(一)。ただ一言、本問の参考までにいひ添へておくならば、ビザンチンの特色を形成した研究方法は『抜萃書』の作成であつた。多種多様の古法源のなかから、学者が見て以て時代の要求に合すとするもののみを拾つて一書と成し、多少の説明をも加へて世上に提供するといふやり方であつた。Epitome legumとか、Synopis Basilicorumとか、Epanagoga anitaとかいふやうな有名な法書類は、いづれもBasilica大法典その他からの抜刷であつたのである。しかし、撰抜は選者主観の作用である。主観の優越性を認めないところに抜萃書などの現はれやう筈もないのである。ビザンチン学者の間に抜萃書の作成が風をなしてゐたといふ一事は、充分に彼等の対制定法的態度を物語つてゐるではないか。
一 拙著・西洋立法史・一一頁以下、ビザンチン期における親族法の発達・三三頁以下。
以上、わたくしは、初期中世の三つの星——Ravenna, Pavia, Constantinopel——について述べた。三者の対制定法的態度が、いかに懐疑的自由的であつたかをつきとめた。が、わたくしはなほ、見逃してはならないもう一つの星を残してゐる。それはサラセン人の法律学だ。サラセン人は中世の初めヨーロッパで勢力を張り奇しくも華やかな異国文化を咲誇つてゐたのであつたが、その法律学はどんな特色をもつたものであつたか、それを一応見渡しておく必要もあるかとおもふのである。
が、わたくしはサラセンの法律学についても嘗て論述の機会をもつた(一)。ゆゑに、ここにはその要所のみを摘んでおくと、サラセンの学界には、(一)Abu Hanifa (699--767)を始祖とするHanifa派、(二)Malik (†795)を始祖とするMalik派、(三)Shafiを始祖とするShafi派の三学派が流れてゐたのであつたが、いづれもローマ人やビザンチン人の解釈態度を模倣して制定法の完全性を疑ひ、解釈の作用でその足らざるところを補はうと努めつつあつたのであつた。すなはちHanifa派は、裁判官の主観的判断・個人的理性もまた法となると主張した。Malik派は、公益公安(istilah)の前には明文なしと叫んだ。Shafi派は、立法理由(illah)より見て解釈せざるべからずと主張した。——ここにもまた制定法又は法律秩序の完全性を独断するやうな思想は、痕跡的にも見られなかつたのであつた。
一 拙著・西洋立法史・三九頁以下。
ローマ人も制定法の完全性に対して懐疑的、Ravenna, Pavia, Constantinopelの学者も制定法の完全性に対してやはり懐疑的、サラセン人もまた懐疑的であつたとすると、制定法の完全性を仮説する神学的な学風は、いつ何人によつて始められたのであらうか?現代においてなほわれわれを支配しつつある法律解釈学の神学性はいかにして始つたのであらうか?次段において、わたくしはそれを述べよう。
五 中世後期の解釈態度
十二・三世紀はヨーロッパの法律学に新旧の一線を太く画した殊勲的な世紀であつた。ローマ法が大規模に研究され出したのもこの時代であり、教会法学が厳かな姿において建設されたのもこの時代であつた。解釈法学らしい解釈法学がその出生を完了したのも、十二・三世紀の頃であつたのである。
新法学の揺籃はイタリイのボログナの大学であり、そこを本拠に活動した註釈学者(Glossatoren)の一団こそ、新法学の父ではあつたのであつた。一時は『ボログナ以外に法律学を学ぶ地なし』と歌はれたほど、ボログナは、尖端的な存在であり、光輝ある指導者であつたのであつた。以下、われらは、ボログナ註釈学者の対制定法的態度が、ローマの学者や中世初期の学者の対制定法的態度といかに鮮明に対立してゐたかを示すであらう。
註釈学者の専門別 ボログナの註釈学者は二個の部類に分属してゐたのであつて、一は教会法学者(Canonisten)として教会法の講義に当り、他はローマ法学者(Legisten)としてローマ法の講義に当り、角逐の姿勢で対峙してゐたのであつた。教会法学の誕生は十二世紀の初半であり、ローマ法学の発生も十二世紀の初半であつた。前者はGratianとその弟子のPaucapaleaとによつて開始され、後者はIrneriusによつて創建された。同世紀の後半期に入ると、教会法の学者としてはRufinus, Huguccioのごとき巨匠が出、ローマ法の学者としてはMartinus, Bulgarius, Placentinusのごとき大家が出た。十三世紀の初めには、教会法の側にTancred, Durantisあり、その好敵手としてローマ法の側にAzoがあつた。十四世紀にはJohannes Andreaeが出て教会法学の発達に光輝ある結末をつけたやうに、十三世紀にはAccursiusが出てローマ法学の発達へ有終の美を添へたのであつた。しかし、勝利の星は概して教会法学者のために輝いてゐたのであつて、ローマ法学の発達は教会法学の進歩に遅れがちたるを免れなかつた。学者の数からいつても教会法学者の方がずつと多かつたらしいのである。Schulteの『教会法史』に伝されてゐるボログナ教会法学者の数は二百に垂んとしてゐるが(一)、Savignyの『中世ローマ法史』に出てゐるボログナのローマ法学者の数は二・三十を越えぬのである。著書の数なども教会法側の方が断然多数に上つたらしい。註釈の方法・著述の様式等も、教会法学の側において、より進歩的な行き方を示してゐたのである。——とにかくボログナの中心を形づくつてゐたのはむしろ教会法学であつたといふことを看過するわけにはゆかぬのである。
一 主もな教会法学者の略伝は、拙稿『教会法の法源』(法学論叢二七ノ五)において述べておいた。
註釈の対象 教会法学者の研究対象は、ローマ法王の法典たるCorpus Juris Canoniciであり、ローマ法学者のそれは、ローマ皇帝の法典たるCorpus Juris Civilisであつた。前者がC. J. Canoniciの外へは一歩も踏出さなかつたやうに、後者もC. J. Civilisの外へは出ずにしまつたのであつた。尤も、教会法学者はC. J. Canoniciの外に、単行の法王訓令(Dekretalen)をも研究はしたものの、単行の訓令は、逐次整理を受けつつC. J. Canoniciそのもののなかへ容収されてゆく例であつたため、単行訓令の研究がこれとして意義をもつまでにはなり兼ねたのであつた。ローマ法学者の方も、古へのローマ皇帝の勅令ばかり研究してゐたわけではなく、現存のローマ皇帝すなはち神聖ローマ皇帝の新勅法などをも研究はしたのであつたが、新勅法は数においてすでに稀少だつたので、その研究も重きをなすまでには至らなかつた。結局、教会法学者はC. J. Canoniciへ、ローマ法学者はC. J. Civilisへ、すなはち両者とも法典へ、その全心全力を傾瀉してゐたのであつた。
研究の対象が法典に限られてゐたといふことを別の側面からいひ直して見ると——
(一)註釈学者は、歴史を研究することをしなかつたのであつた。歴史へ溯ることを法典外へでも出るやうに思つて警戒さへしてゐたのであつた。もちろん、彼等の研究対象であつたC. J. CanoniciやC. J. Civilisやは、法王や皇帝の偶意的制作物ではなかつた。それは永き法的発展の結実であり、中には数世紀の沿革をもつ規定さへ含んでゐたのであるから、C. J. CanoniciやC. J. Civilisそのものを知るためにも、ローマ法史や教会法史を尋究する必要は大いにあつたのであつたが、註釈学者はこの方面の研究には一指だも染めようとはしなかつたのである。
(二)註釈学者はまた法律生活の実際を眺めようともしなかつた。生きて当時の社会に流れてゐた現実の法律は、断じてC. J. Civilisの規定ではなくて、封建領主の判例や地方的慣習や都市の条例などであつたのであるが、註釈学者は、生きたこの種の法律へは一視も投げず、紙の上の法律ばかり玩んでゐたのであつた。ちやうど古典学者が古典美のみを尚ぶやうに、註釈学者はローマ法の論理美のみを愛して、現実法の粗笨さを冷笑してゐたのである。
(三)同じローマ法でも、註釈学者の取扱つたものは古典的なローマ法で、中世の『訛れるローマ法』(römisches Vulgärrecht)ではなかつた。『訛れるローマ法』といふのは、中世化したローマ法、すなはちゲルマン分子を多くとり入れた不純なローマ法のことで、かのRavennaの学者の取扱つてゐたのはまさにこれであり、これこそ却つて中世の社会には適合してゐたでもあらうに、ボログナ学者は、この種のローマ法の不純さを嗤つて相手にもしなかつたのである。つまり、彼等はユスチニアンをして一切の問題を裁断させようとしたのである。帝の古典法を昔ながらの姿において再興させ、再現させ、そのまま再実施させようとしたのである。
(四)最も注意せらるべきは、註釈学者が陰に陽に地方教会法や地方法の勢力の駆除に努めたといふことであつた。例へばGratianはいふ——
『一般的宗教会議の決議も法王の是認なければ法となりえず』【Princ. D. 17】と。Hostiensisはいふ——
『地方教会の慣習法は、新しき一般法によつて廃せらる』【Vgl. Brie, Lehre vom Gewohnheitsrecht. 201】と。教会法学者にとつては、法王の訓令が絶対至高の法律であつたのである。宗教会議の決議や地方教会の法律やは、法王法の前に光を隠さざるをえなかつたのである。
ローマ法学者も地方慣習法——彼等が地方的慣習法の語下に表象してゐたのは、イタリイの都市法だつた【Brie, a. a. O. 125】——の排撃には力を惜しまぬのであつた。例へば、AzoはCodex 8, 53, 2に引かれてゐるコンスタンチン大帝の有名な勅法『永年の慣習といへども、法律に優越する力はなし』を註して、同条は、地方的慣習法が帝国の法律に抵触しては成立しえざる旨を規定したものだと解したのである【Brie, a. a. O. 124】。地方的慣習法の勢力をなるべく削つて全国の法律を皇帝法の下に統一させたいといふのが、Azo等の本音であつたこと疑を容れぬのである。
註釈上の根本態度 C. J. Canoniciなり、C. J. Civilisなりが、註釈の対象であつたとすると、これらに対して註釈学者はどんな態度をとつたか——
(一)第一に、彼等は法典に含まれてゐる諸条規が全部同一の価値をもつと前提したのであつた。法典は一の立法者から出た一の法律であるから、法典内の条規相互の間に効力の差のあらう筈がない。全部は同一の日附を有し、同一の地域を支配する。換言すれば、法典内の条規相互の間には新法旧法の差別もなく、普通法特別法の区別もない。全条規が同じ重量で、同じ平面に、林のやうに並立してゐるのだ、と考へたのであつた。
(二)第二に、註釈学者は、法典内の各条規は生活関係の一角づつを、その固有の支配領域として支配すると考へた。固有の支配領域をもたないやうな条規はない。もしあればそれは真の意味での条規ではないと見たのである。
(三)第三の彼等の前提は、各条規の支配領域は他を犯さないと同時に他からも犯されない関係に立つといふ断定であつた。換言すれば、同一の法律関係が多数の条規から重複的に又は矛盾的に支配されてゐるやうな場合はないと考へたのであつた。
(四)第四の予断は、法律関係の全部が法典中のどれかの条規によつて必ず規律されてゐるに相違ないといふ法典の完全性に対する大なる信仰であつた。彼等は考へたのである——条規は各々他を犯さず他からも犯されざる独自の支配領域をもつが、各条規の支配領域を聯ねて見ると法律生活の全面を掩蓋する。いづれかの条規の支配下に立たざる法律関係はない。どんな問題でもきつと法典から答を受けてゐるのであると。
要するに、法典には不明もなければ不当もない・重複もなければ疎略もない・矛盾もなければ欠陥もないといふのが、註釈学者の解釈上の根本前提であつたのであつた。
註釈の方法 法典には矛盾もなければ欠陥もないといふのが註釈学者の強い信仰であつたのであるから、彼等の註釈は、この信仰の基礎の上に展開されざるををえなかつた。彼等は、法典中に表見的に存するところの矛盾を去り、欠陥を填め、重複を去り、疎略を補ひ、不明を明にし、不当を合理化しようと企てたのである。そして、かくすることによつて法典の円満性・完全性・正当性を証拠立てようと企てたのである。——
(一)不明を明にする解釈手段は、語註(wörtliche Glosse)及説明註(paraphrasierende Glosse)であつた。語註とは、一語の代りに他の同意語を代置させることをいひ、説明註とは一語の意味を布衍的に説明することをいふ。註釈学者は、条文を、それを構成する個々の語に分解し、個々の語を逐一意味づけて行つたのである。
(二)不明を明にするもう一つの手段は要旨の摘記であつた。註釈学者は、一旦条文をバラバラな単語に解体したのち、再びこれを綜合し、其条の要旨を短い一句に一括しようと試みたのである。かかる要旨文をbrocardicaといふ。brocardicaは『原則』ではなかつた。原則とは法規の精神又は根抵的思想を道破したものの謂ひであらうが、brocardicaは語義註の総果を要約したものに過ぎなかつたから。
(三)条規相互の間の重複や矛盾を去る手段の一つはいはゆる峻別(distinctiones)であつた。峻別とは、一見恰も重複又は矛盾なるがごとくに見える数個の条文を拉し来つて、仔細にその支配領域を比較し、結局、各条はその支配領域を異にするものにして、相互の間には実は重複もなく矛盾もなしと論結するに至ることをいふ。峻別は註釈学者が、各条の領域が他から犯されざる独立のものなることを示すがために、すなはち条規相互の間に矛盾なきものなることを示すがために、力を傾けて従事した・彼等にとりまことに重要な仕事であつたのであつた。Stintzingいはく——
『中世の学者は、法規相互の間の矛盾を、より高き統一内に根本的に解決してしまはうとは試みなかつた。彼等は峻別の方法によつて各条各説にそれぞれの領域を限定し、妥協的に各自を並立させようとしたのである』【Stintzing, Geschichte der duetschen Rechtsw., I, 106】と。又いはく——
『中世の学者は、各条規を同じ重さにおいて取扱つた。偶然的な連結で積重ねて行つた。彼等の仕事は深さよりも広さに向つたのである。集中よりも散開に向つたのである』【Stintzing, a. a. O. 106】と。条規は各々固有の支配領域をもつといふ前提を立ててゐたればこそ、異常の辛苦をもして条規相互の間を『峻別』し、条規に各々固有の領域を配当しようとも企てたわけであつた。
(四)重複除去のもう一つの手段は、縮少註(einschränkende Glosse)であつた。これは峻別の方法を以て条規相互の間の矛盾重複を除去し能はざる場合に、窮余の手段として使用したもので、重複条文の一つを強ひて狭意に解し、他条との衝突を避けたのであつた。
(五)欠陥補填の有力な一手段は拡張註(ausdehnende Glosse)、すなはち或条文の支配領域を強ひて広めて、漏らされてゐる場合をもその条文の支配下に取入れるといふやり方であつた。法に欠陥なきことを仮定してゐた彼等は、往々にしてかかる彌縫をも試みざるをえぬ羽目に陥つたのであつた。
(六)実際、『法の欠陥』は『法の矛盾』と共に註釈学者の安眠を妨げてゐた悪夢であり、何とかしてこの疑念を去らうと彼等は努めつつあつたのであつた。『矛盾』の危惧を除くために用ゐた手段が前述の峻別であり、『欠陥』の不安を去るために用ゐた手段がここに述べんとする『例題』(causa)である。例題とは、一見法典にも規定なきがごとくに見える稀有の場合を拉し来り、苦心してそれに擬せらるべき条文を捜索し、結局適当の条文を発見して、その支配下に右の場合を包摂させることであつた。適当な条文を発見しえたときにそれを解決(solutiones)といつた。例題は、裁判の実際からとつたものもあり、想像を以て作為したものもあつた。わざわざ稀有の例まで作つてそれに擬せらるべき法律の発見に悩苦し、結局それを発見して『解決』を喜んだのは、それによつて法典の完全性に対する彼等の所信が確実にさせられたからであつた。すなはち、彼等の例題解決の目的は、具体的な例に即して妥当な規範を発見せんがためではなくて、それによつて法典の包容力の大を検するため、いかに法典が一切の難問を解去つて綽々としてなほ余裕あるかを証明せんがためであつた。
(七)『法の不当』——それはあまり註釈学者を悩まさぬ問題であつた。なぜなれば、註釈学者は法典の完全性を信ずる以上にその正当性を信じ、法典には不当の規定なしと独断してゐたからである。が、さすがに折々は、条規の不当性をおもはざるをえぬ場合もあつたのであつて、そんな場合には、彼等もやはり文言を犠牲にして正義の要求を貫かうと試みもしたのであつた。これを変更註(verändernde Glosse)といふ。一二、変更註の例を示してみると、例へばMartinusはCodex 5, 12, 30『嫁資に関するユスチニアン帝の勅法』を註して、
『嫁資は、婚姻中といへども妻の所有を離れず』【Gl. Naturali jure ad leg. 30 C. de jure dotium 5, 12】といつたのである。同条の文言解釈に従へば、嫁資が婚姻中夫の所有に移るべきこと明かなるに拘らず、Martinusはそれを不衡平と考へ、法文を曲げて、嫁資を妻の所有に留めたのである。
又、ローマ法では、『国庫が自己に属せざる物を処分せる場合には、例外として所有権移転の効果を生ず』とされてゐたのであつたが、Martinusはこの問題に関し、
『国庫により、他人の物が有効に処分せらるるは、国庫が善意にてその物を処分せし場合に限らる』【Hänel, Dissensiones dominorum, 57】と註したのである。これも衡平の原理のために法文を曲げた顕著な例であつた。
しかし、概していふと、註釈学者は、条文に対する忠実なる貞操家であつた。Martinusのごときはむしろ例外であつたのである。
Martinusの好敵手Bulgariusは明快にいつたではないか
『法と道徳と一致せざる場合には道徳を以て法律を変更せしめず、各者をしてその本領を発揮せしめよ』と【Landsberg, Die Glosse des Accursius, 16】。著述の様式 註釈学者は、概して健筆の著述家であり、一人にして二三十種の著書をものした人さへあつたが【例へばJohannes de Deo】、内容はみな現行法本位の解釈論たるに止つてゐた。歴史や法理学は彼等の研究圏外にあつたのである。
解釈学的著述の様式にはいろいろあつたが、その(一)は註釈書(glossa, commentaria)。これは条の順序を追ひつつ法典を解釈するを以てその特色とした。(二)は教本(summa, titulorum)。これは条の順序は追はず、単に章の順序のみを追ひつつ法典を解釈するを以てその特色とした。(三)は提要(compendia)。これは条はもちろん章の順序さへも追はず、単に篇の順序を追ひつつ法典を解釈するを以てその特色とした。その他のものとしては、(四)単行論文(Monographie)や、(五)問題論文(questiones)があつた。単行論文は或制度又は或規定の内容を詳細に論究することを以て目的となし、問題論文は或実際上の又は仮想上の設例を解決することを以て主眼とした——要するに著者も論文もみな条文本位であつたのである。而して、それは註釈学者の対法典的態度の真切なる反映そのものに外ならなかつた。法典といふ介殻内に堅く閉ぢ篭つてゐた彼等には、解釈書以外のものを書くことが全く不可能であつたのである。
以上を以て、わたくしは、ボログナ学者の対制定法的態度が、いかにローマの学者や中世初期の学者の対制定法的態度と異つてゐたかを明かにしたが、要約的にここの両者の態度を比較して見ると——
(一)ローマの学者や中世初期の学者が制定法を不完全な人為的作品と見、率直にその不備不当を承認してゐたのに反し、ボログナの学者は法典を以て人為の神品となし、その正当性・完全性・円満性を信仰的に独断してゐたのであつた。前者が制規に対する悲観的懐疑派ならば、後者は楽観的信仰派であつたのである。
(二)ローマの学者や中世初期の学者が解釈を以て制定法の不備不当を除去し補正しようとしたのに対し、ボログナの学者は解釈を以て法典内に包蔵されてゐる意味を確定しようとした。前者によれば、解釈の成果と制定法の内容とは相違する・解釈は制定法へ新しき何ものかを加へる作用であるからである。後者によれば、解釈の成果と制定法の内容とは一致する・解釈は初めから法典のなかに含まれてゐたものを外に引出すに過ぎぬからである。前者は解釈による法規の創造を認め、後者はこれを否認した。
(三)ローマ時代及中世の初期において、『善い法律家』とは『善い立法意見をもつ人』の謂であつた。社会のために善い法律を供給するのが当時の法律家の本務であつたからである。中世の後期に至つて『善い法律家』とは『巧みに条文を操る技師』の謂となつた。なぜなれば、後期の考では、法律家は法王や皇帝の作り与へた制定法典から拘束を受け、法律問題に対する彼の答の全部を法典のなかからひねり出さねばならぬ関係となつたからである。
輝ける註釈学者の一人Hugolinusは明瞭にいふ——
『凡そ裁判官の判決は成文法に根拠せざるべからず』と【Hänel, Dissensiones dominorum, 330Anm. h】。これ実に驚くべき解釈態度の変化ではないか。前期中世までは、判決が成文法に拘束されねばならぬといふやうな思想は毛頭なかつた。註釈学者に至つて遂にそれが出て来たのである。
近世の解釈法学・法の進化に参加することを忘れた解釈法学・消極的に皇帝の法典を守護するに過ぎない解釈法学——このやうなものはローマにもなく、中世の初期にもなかつたのである。それは全く十二・三世紀において註釈学者の手によつて作り上げられたものに過ぎなかつたのである。註釈学者こそ近世解釈法学の生母ではあつたのであつた。
Kissもすでにいつている——
『余は、今日なほ盛行してゐる論理解釈の方法が、註釈学者の解釈方法に由来するといふ主張に大いに重きをおくものである。通説は、論理解釈の方法並に法の欠陥を法自身の力で内部から補充させようとする方法をモンテスキューの三権分立説に由来するかのやうに説くが、焉んぞ知らん、かかる態度は註釈学者によつて遠き以前に完成されてゐたのであつた』【Kiss, Jhering Jahrb., 58. 436 Anm. 2】と。
要するに中世前期までの法律学は、条文から自由であつたといふ意味において『自由法学』、衡平の思想の実現を所期してゐたといふ意味において『衡平法学』であつたが、註釈学者の法律学は、条文に拘束されてゐたといふ意味において『拘束法学』(gebundene Rechtswissenschaft)、条文の操縦のみを事としてゐたといふ意味において『条文法学』(Paragraphenjurisprudenz)であつたのである。
然らば、かくの如き学問の大変革はいかにして起つたか、何が法律学をさうさせたか。——余は次にその原因を見届けねばならぬ。
六 スコラ学の影響
中世思想の影響 何故に十二・三世紀において法律学は俄然その方法を一変したか——その原因を知るために、われらは、まづ、当時における物の考へ方一般を見なければならない。なぜなれば、一個の学問が、その時代の思考方法の影響を受けずに孤島的に成育を遂げるといふやうなことは不可思的であり、註釈学なども必ずや中世的考へ方一般の影響を受けつつ成長したものであつたらうからである。では中世的な考へ方といふのは、そもそもどんな考へ方であつたか。——
(一)最初に顕著なのは、事実を尊重しようとする実験科学の精神が一向に芽生えてゐなかつたことであつた。今日のわれらがもつやうな精密な自然科学の当時なほ存せざりしことはいふまでもないが、実は、科学どころか、科学的考へ方すらもが存しなかつたのである。けだし、科学は多数の事例を蒐集する・精密にそれを観察する・系統的にそれを分類する・現象相互の間に必然的な関係を見出さうと努める・個々特殊の事例から普遍的な法則を帰納しようとも試みる。しかし、中世人には、蒐集も分類も観察も帰納も、余所事に過ぎなかつたのである。中世人は帰納せずに演繹してゐた。個々の事実を基礎として一般関係を発見せずに、先入的な独断から出発して個々の事実を説明してゐた。説明してゐたといふよりも、事実へ暴力を加へてゐたのである。先入の見・独断の定説を強制的に事実へ適用してゐたのである。
(二)非科学的な右の傾向と相結んで中世人を支配してゐたものは、形式的な三段論法であつた。中世人は一定の普遍的命題を、そのまま型通りに各事件へ適用してゐたのである。事件の特殊な色合や複雑な暗影やらを考慮に入れて事件毎にその取扱方を多少なりとも易へて行かうといふ細心性は、彼等において見ることをえなかつた。彼等はアリストテレスの形式論理を愛用した。それには『全体について真ならば部分についてもまた真なり』とあつた!何と部分の具体的特殊性を無視した表面的な論理であつたことよ。簡単便利、しかしあまりにも画一的な取扱方であつたことよ。
(三)形式論理の好きな中世人は、必然的に歴史嫌ひでもあつた。実に、中世には歴史的叙述も歴史的考へ方もなかつたのである。そこには、ただ、年代記(Chronik, Annalen)があつたに止つた。年代記は事件と人名と数字との無連絡な羅列であつた。偉大な世界的事件も、いふに足らない地方的小事件も、お伽話的異変事も、何もかも一所にした混沌たる集積であつた。今日の、選択あり・脈絡あり・発展もまたある史的叙述の方法とは、日を同じうして論ずべからざるしろ物であつたのである。ゆゑにLandsbergはいふ——
『中世には自然科学がなかつたやうに歴史もまたなかつた』【Landsberg, Die Glosse des Accursius, 23 fg.】と。われらもLandsbergと同様の感に打たれざるをえない。
(四)しかし、中世には自然科学と歴史学とがなかつただけではなかつた。哲学すらもなかつたのである。けだし、哲学は——殊に近代の批判哲学は——理性の立場から規範を立てる。それは外的なる一切の勢力・権威・伝統から自己を自由にしてゐる。外的者は、批判の客体とこそなれその基準とはならないと見てゐる。いはば近世の哲学は神よりも人を信じてゐるのである。人性そのものの内奥に、善悪判定の力あることを信じてゐるのである。それは善悪自律主義である。ところが、中世の哲学はその反対、すなはち善悪他律主義であつた。彼等は考へた。——絶対の価値は神のみである。人間は神に従ひ、神によつて導かれなければならない。善悪の区別は、人間が自己の良心に従つたか否かによらず、神の掟に従つたか否かに係ると。近世人は『衷なる声』に畏れ、中世人は『外なる権威』に屈してゐたのである。
かやうな見来れば、いかに中世の思想が註釈学の方法論的特徴の形成へ標準的影響を与へたかも明瞭となるであらう。われらはすでに見た、(一)いかに註釈学者が法の実証的研究、すなはち生きた現実法の研究に無関心であつたか、いかに法典の内容の解明と規定の機械的適用とに専心してゐたか、(二)いかに法の歴史的研究すなはちローマ法史や教会法史の研究を忽諸に附してゐたか、(三)いかに現行法への哲学的批判や自由なる法の発見やを擯斥してゐたかを。想へば、これらの註釈学的特徴は、すべてみな中世といふ時代の特徴であつたのである。時代の特徴がそのまま法律学へ反映して、法律学を『註釈学』たらしめてゐたのである。
スコラ学の影響 スコラ学すなはちカトリック教会の神学の性質については前出二に述べておいたので、再説することを避けたいが、要するに、スコラ学は、聖書や伝承やを、なるべく正当に円満に精密に深遠に、意味づけることを以て本旨としたものであつた。それは、聖書の句や教父の言葉や宗教会議の決議や法王の訓令やを、『有権的に与へられたる真理の泉なり』として有難く頂戴した。一切の教説・教則をこれらの官製淵源のなかから——それのみのなかから——汲取らうと欲した。しかも、彼等の独断は、経典のなかには、不当もなければ欠陥もなく、矛盾もなければ疎略もないと仮定させた。この種の欠点の存するがごとくに見えるは、鏡上一片の浮影に過ぎない。浮影を清拂して経典の真の姿——矛盾なく欠陥なき真の光——を発揚させるところにこそ、学者の任務は存在する。学者は経典へ新しきものを加へない。彼の仕事は宣言的であり、消極的である。彼は、初めから経典のなかに包蔵されてゐた思想を外界へ顕揚さすだけであると。要するに、スコラ学は信仰そのものであつた。経典の前へひれ伏してその正当性・完全性を謳歌する似而非学問であつた。
さらに、スコラ学者が経典における表見上の諸欠点を除去するために使用した諸手段を略見するに、矛盾除去の手段として用ゐたのが峻別(distinctiones)の方法であつた。峻別とは各教則の妥当する場合を厳格に差別することをいふ。スコラ学者によれば、教則には各々固有の支配領域がある。ゆゑに、各領域相互の間の境界を明画にして行きさへすれば、教則相互間の重複や矛盾はおのづから除かるべき筈だといふのであつた。峻別の方法を以てしても除去し能はざる矛盾の存するときは、スコラ学者は、縮少解釈の方法をとつて重複教則の一つを狭く意味づけ、強ひて二つを平行の関係にもたらした。
欠陥補充の手段は解体(Zergliederung)であつた。解体とは教会の教説内容を仔細に分析し、分析に分析を重ねて無数の教則を派生させ、教則の網を広々と散開させていくことであつた。かくすることによつて、大抵の問題をば、教説の支配下に包摂することをえたのである。どうしても教説の支配下に取りこみえぬやうな事案に逢着した場合には、近接の規則に拡張解釈を施し、その意味を広めて、無理にそのなかへ問題たる事案を包摂させたのであつた。
完全性試験の方法として愛用したのが例題(causa)であつた。スコラ学者は、一見経典もまた予想せざるかに見える例題を設けて、わざわざ解答を経典に求め、巧みに根拠を証引して、遂に解答の発見に成功し、今更らしく経典の含容に遺漏なきを確めえて、ひとりみづから悦に入つてゐたのであつた。解決(solutiones)とは、彼等にとり、問題を教説体系のなかへはめこむことの謂を出なかつたのである。
かう見てくると、スコラ学が註釈学の完成へいかに影響したかも明瞭となるであらう。われわれはすでに見た、(一)いかに註釈学者が法典の正当性・完全性・円満性を仮定してゐたか、(二)いかに矛盾除去の手段として峻別や縮少解釈の方法を、欠陥補填の手段として解体や拡張解釈の方法を、無欠陥証示の手段として例題の方法を、愛用してゐたかを。想へば、これらの註釈学的諸方法は註釈学者がスコラ学者から継受して、一層それを自覚的且つ組織的に発展させたところのものであつたのである。Stintzingはいふ——
『中世の学者は、信仰的に伝承を尊敬し、常習的に判断を権威の下に屈服させてゐた。真理なるものは、新たに発見せらるべきではなくて啓示されてある伝承のなかから学び取らるべきだと考へてゐた。従つて、中世人の仕事は与へられたる伝承を仔細に分析することと、与へられたる伝承を引証しつつ問題を解決することとの二つに局限せられざるをえなかつた。伝承の拘束を受けてゐる以上、それの分析といふことが学問の重心とならざるをえないわけだつたし、伝承の真理性を信じてゐる以上、それをそのまま機械的に適用して見たくなるのが、自然の勢であつたからである。解決とは、伝承との間の一致不一致を認識することの謂であつた。バイブルこそ真理の試金石・教会こそ真理の保管者であつたのである』【Stintzing, Geschichte der duetschen Rechtsw., I, 103fg.】と。又いはく——
『同一の現象は法律学の上でも繰返されてゐた。ここでも、分析が行はれ、峻別や例題の方法が盛んであつた。いな、法律学者にとつては、スコラ学者にとつてよりも、「真理は与へられてゐる、判断は拘束を受けてゐる」といふ感じが幾層倍も強かつた。彼等は、ただ、客観的に与へられてゐる法律を知らうとし、それより演繹して事案を解かうとしただけであつた。せいぜいのところ客観法を、その根拠と目的と内的関聯とにおいて認識しようとしただけであつた。生きた法規の現実態を観察したり、新しき法規を産出しようなどとは試みだもしなかつたのである』【Stintzing, a. a. O. 102 fg.】と。
なほ、スコラ学の歴史と註釈学の成立過程とを対照することによつて、われらは両者の関係の緊密さを一層切実に感じうるであらう。いふまでもなく、註釈学が活動したのは十二・三世紀のことであつたが、ちやうどこの時代はスコラ学の飛躍時代に相当した。前世紀すなはち十一世紀の末に『スコラ学の父』Anselm von Canterbury (1033--1109)が出て斯学の基礎を定置してから、スコラ学の発育は、沖天的であつた。アリストテレスの形式論理が教会へ継受されたのも——いはゆるアリストテレス継受(Aristotelesrezeption)も——十二世紀中のことであつたし、三位一体の学理(Trinitätslehre)の大成したのも十二世紀中のことであつた。フランスがスコラ学の中心地となり、思想の元締となり、学星悉くパリに集つたのも同じ時代のことであつた——『保守的神学者』Peter Abälard, 『哲人的神学者』Hugo von St. Viktor, さらにRobert von Melum (†1167), Petrus Lombardus (†1164), Gilbert de la Perrèe等々。実に十二・三世紀は、Grabmannがいつたやうに、
『全スコラ学の発達へ大なる影響を残した時代・来るべき高度スコラ学(Hochscholastik)の時代のために、基礎と準備とを作り上げた時代・変化と発展・努力と試みとの意義大なる時代であつたのである』【Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode II, 4】。おもふに、法律学が十二世紀に入つて俄然その面目を一新しえたのは、法律学が自己の力で自己改造の手段を発見しえたがためではなかつた。むしろ、それは、法律学が、他の学問すなはちスコラ学においてすでに使用されてをり、多大の効果をも挙げてゐたところの学的手段を借来つて、これを自己に応用したその結果に外ならなかつた。換言すれば、法律学は、神学の処方箋を用ゐて自己を改造したのである。切言してわたくしはいふ、註釈学は経典の代りに法典を対象としたスコラ学そのものであつたと。
七 政治の影響
学問の方法論上の特色は、その時代の哲学や思想の傾向からばかり決定されるのではなくて、その時代の政治的傾向からも相当な影響は受けるものとおもふのである。殊に法律は支配の武器・政治の道具であるので、これを対象とする法律学も、その時代の政治的勢力から少からず左右されることを何としても免れえぬとおもふのである。よつて、わたくしは、ここに簡単に、十二・三世紀の政治傾向を見ておかう。註釈学発生の原動力に触れるために。
中央集権の傾向 十二・三世紀は、教会内部においても、国家内部においても、中央集権の傾向の発生しつつあつた時代であつた、と概言しても誤りではないであらう。殊に、この形勢は教会内において顕著であつた。法王は真に『王』となり、独裁君主となりつつあつた。彼は、もはや、信仰の手段で信者を指導してゐたのではない。法律の力で信者を支配してゐたのである。彼と信者との関係は、宛然として国王と臣民との関係に変じつつあつた。信者は支配の単なる客体として法王の発した実定法を守り、これによつて裁判され、処罰されつつあつたのであつた。法王の周囲には法王を助けて専制政治を行ふ僧侶官吏の一群をも生じつつあつた。
当時の聖僧St. Bernardは教会世俗化の傾向を深慨して云つてゐる——
『法王は、毎日を、いや毎時間を、法的事務に捧げてゐる。全注意を法的事務に奪はれてゐる。「法」は今や全宮殿に響き渡つてゐるが、その法たる、主イエスの法ではなくて皇帝ユスチニアンの法である』【Dunning, Political Theories, Ancient and Mediaeval, 183】と。しかし、教会の世俗化・国家化・官僚化・法律化は十二世紀における大事実であつた。呪詛の言葉を超越した現実の大勢であつた。
転じて国家の側を見ると、国家における中央集権の形勢は教会におけるほど強盛ではなかつたが、それにしても王権伸張の傾向は著しかつた。殊にフランスにおいてさうであつた。そこでは、従来の間接統治主義、すなはち、国王が諸侯を通じて間接に人民に命令し課税するといふ主義は改められ、直接に国王が全国の人民へ命令課税するといふ直接統治主義へ転向しつつあつたのである。
元来、ゲルマンの王は『国民中の一人』としていはば内部から国民を指導して来たのであつたが、このやうなデモクラシーは今や滅び、王が外からの・上からの支配者となつたのである。王と人民との間に絶対的な間隔が生じつつあつた。王の周囲にはやはり彼を助けて専制政治を行ふ官僚の一群が発生しつつあつた。王の支配の武器も、もはや『道徳』や『慣習』ではなくて、『官僚的な成文法』となりつつあつた。
要するに、われわれは銘記せねばならない。註釈学の勃興期たる十二世紀は、教会にとつても、国家にとつても、権力の統一期・官僚政治の発生期・支配陣容の設備期であつたといふことを。
中央集権と註釈学 右のごとき中央集権の傾向と註釈学との間にどんな関係があつたかといふと、一口にいひ切つてしまへば、註釈学は中央集権運動の一翼であつたのである。法的側面から法王又は王を助けて、教会内における又は国家内における権力の統一を図らんとした一運動であつたのである。
そのことは註釈学者と法王又は王との間の内幕的情実をのぞいて見るとすぐにわかる。大体において、教会法学者は法王から、ローマ法学者は王から好餌を食はされてゐた御用学者であつたのである。著名な教会法学者にして法王庁へ出仕し、顕要の地位に上つた人が少くない。Stephanは僧正となり、Johannes Faventinusも僧正となり、Durantisは枢機員となつた。Rolandusは法王に選ばれてAlexander IIIとなり、Albertusも法王に選ばれてGregor VIIIとなつた。教会の要職に就かなかつた教会法学者はむしろ稀だつた位である。
ローマ法の学者の方は王や皇帝へ仕へた。IrneriusはHeinrich Vに仕へて政治の枢機にも参画した人。Bulgarius及Martinusは皇帝の御覚えの殊にめでたかつた人々であつた。Hugolinus, Azo, Placentinus等も皇帝の信任を忝くした。Odofredusに至つては帝の恩寵を鼻にさへかけてゐた。
学生の方はと見ると、これは大体が官吏志願であつたのである。教会法を修めた者は教会法のドクトルとなつて法王庁へ、ローマ法を修めた者はローマ法のドクトルとなつて王や皇帝へ仕へた。大規模に官僚化しつつあつた当時の教会及国家は、ボログナの卒業生を吸収して綽々たる余裕を示してゐた。Azoのもとに学んだ学生の数は一万に及んだといふ。生国別にして十八ヶ国の学生がボログナへ雲集してゐたともいふ。宛然としてボログナは官吏養成所たる観があつたのである。
情勢すでにかくの如くであつたから、ボログナの学問に御用的色彩の濃厚だつたのもけだしまた止むをえざるところであつた。実に註釈学の性質の或部分は、これを御用学と見ることによつて最もよく説明されうるのである。例へば、(一)註釈学者はとかく事件の具体的特殊性を無視して一律にこれを取扱はうとする傾向をもつてゐたといふことを前に述べたが、かやうな画一主義は、全く彼等の王法本位の思想から出てゐた。王の法律を本位にして統一を図らうとおもへば、事件の地方色や人的特殊性やを無視して一律にこれを王の法律に屈服させる必要があるといふことを彼等は百も承知してゐたのである。彼等の形式論理は彼等の目的たる法的統一のための単なる方便に過ぎなかつた。(二)又、註釈学者が地方法の研究に手を触れなかつたといふこと、民間の生きた慣習をも看過してゐたといふことを前に述べたが、これなど王法本位の統一主義からすれば、まことに当然の所為であつた。法的統一のためには地方法の無視が、得策といふよりも必要であつたからである。(三)註釈学者が教会法典やローマ法典を聖典視し、その正当性・完全無欠性を高調したといふことも彼等の権勢阿附心から説明のできないことではない。真に、彼等にとつては、法王や王の統治は悦しくも有難いものであつたのである。教会法典やローマ法典も、彼等にとつては真に輝しく美しく満ち足らへるものではあつたのである。彼等は王に対する彼等の崇拝を王の制作物へ移して、王の法典の謳歌者となつてゐたわけだ(一)。
一 教会法学者は法王へ、ローマ法学者は王又は皇帝へ仕へてゐた関係上、事一たび教会対国家の争となると、両者は意見を異にし、教会法学者は法王権の優越を、ローマ法学者は帝権の不可侵を力説せざるをえなかつた。すなはち、まず(一)教会法学者の方を見ると、最初の教会法学者Gratianはいつた、『皇帝の法律は教会の法律に優先せず、むしろこれに後続す』と(c. 1. D. 10)。十二世紀の代表的神学者Huguccioはいつた、『皇帝の法律は、これと趣旨相反する教会法のなき場合にのみ行はる』と(Schulte, Geschichte der Quellen u. Literatur des canonischen Rechts I. 168)。教会法最大の巨星Johannes Andreaeなども法王党で、法王権の優位のために論弁大いに努めたものであつた(拙稿・教会法の法源・法学論叢二七ノ六、五五頁)。Innozenz III (1198--1216)は学者としても秀抜な一人であつたが、傲慢にもかういつた、『国法上・教会法上の難問一切は法王のみより適当の答を与へらる』と(Dunning, Political Theories, Ancient and Mediaeval, 173)。その他大小の教会法学者、一人として法王権の優位を主張せぬ者はなかつたといつても過言ならざるありさまであつたのである。(二)ローマ法学者の方を見ると、彼等常套の論理は、『古代ローマの皇帝の権力は連綿として現代のドイツ皇帝に伝つてゐる。そこには中断なき帝権(imperium continuum)がある。ゆゑにドイツ皇帝は教会の上になければならない。なぜなれば古代ローマの皇帝がすべてのものの上に、従つて又教会の上にも、卓立してゐたことは疑を容れないから』と(Dunning, 180)。後期註釈学の大家Bartolusのごときは、極端にもかういつた、『ドイツ皇帝はローマ皇帝が然りしがごとくに、全クリスト教国の人民の元首である。ギリシャ人・トルコ人・ユダヤ人・インド人・サラセン人等を除くすべての他のヨーロッパ人はドイツ皇帝の下に立たねばならぬ』と(Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, III, 87 Anm. a)。各自その主のために歌つてゐたのであるから、主の利益相反すれば学説もまた相反したわけだ。
要するに、十二・三世紀はデモクラシーの死滅期・専制政治の発芽期であつたのである。支配階級と被支配階級との間に截然たる区別を生じつつあつた時代であつたのである。ゆゑに、支配階級は、彼のヘゲモニーを拡大強化するために、彼に迎合するイデオロギーはこれを保護助成し、然らざるものは鎮圧した。従つて、支配階級に仕へる思想体系のみが繁茂し、他は滅びて行つた。ボログナ大学は専制君主へ仕へた忠貞な侍女であつたのである。彼女は、専制君主が支配の新武器として組織的法律を需要しつつあつたので組織的法律を彼に献上した。又、専制君主が支配の機関として有能な官吏群を需要しつつあつたのでこれを供給した。ボログナこそは専制的官僚政治の水源地であつたのである。ボログナの学問の性格の一半は神学の影響から説くことをうるが、他の一半はその御用性から根本的に説明せられうるのである。
しかし、神学性は、ひとりボログナ註釈学のみの特性ではない。今日の解釈法学といへども、それが法律秩序の正当性・完全性などといふものを信仰し独断し仮定するものなるかぎり、やはり『神学』であつて『科学』ではないのである。