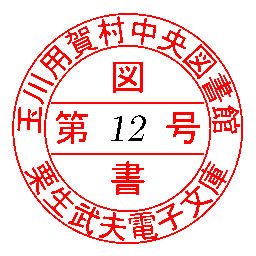
第一節 ロンバルド法源法上におけるローマ法の地位
一 ロンバルド国の政治方針
ポー河が支流を集めてゆるく流れてゐる北イタリイの低地に、ロンバルド族は落着いた。そこはイタリイ内でも、気候の柔らかな、地味の富饒な、最も生産的な区域であつた。ロンバルド族は、彼等よりも一足先きに侵入してゐた東ゴート族を追ひ払つて、新たに北イタリイの主人となつたわけであつた。しかし彼等の人口は少く、軍隊増加のためには、奴隷を解放して人為的に自由民の数を殖やさねばならぬ必要に会した位であつた。その後も人口は十分に豊多であることをえなかつた。ロンバルドの政治支配が全イタリイへ遂に伸びず、諸所に旧勢力の余燼を留めねばならなかつたのも、畢竟は、彼等がその族人を、イタリイ全土の上に氾濫さすことのできなかつた結果だつたらうとおもはれる1)。
人口のこのやうな不足性がロンバルドの政治方針へ影響した。少数の族人を基礎にして多数のローマ人を支配しなければならなかつた関係上、彼等はその民族精神をいやが上にも強調した。彼等はローマ・ロンバルド二民族の間の血液的並に文化的接近をできるだけ阻止しようとさへ企てたのである。一種頑固な執拗な排他心の非常に強いロンバルドの国民性は、右のやうな政治方針が進められてゐる間に、おのづから培成されたものとおもはれるのである。ローマ人に対する弾圧も物凄かつた。彼等はローマ人から自由なる土地所有権を剥奪してしまつた。ローマ人の大半はロンバルド領主の農奴にされてしまつた。ローマ人は、その軍功に応じて封じられて来るロンバルドの武士を領主と仰ぎ、これから居住移転の自由を制限され、これに対して労務調貢の義務を負担せねばならぬ関係となつた。被征服者としての彼等の地位は、喘ぐやうな重圧に苦しんでゐたのであつた2)。
1) ロンバルド侵入後も多数の地方がビザンチン帝国の領土として残つてゐた。南イタリイ一帯のごとき、Ravenna市のごとき、それである。Padua市のやうなロンバルド領に隣接した土地でさへ、かなり長い間ビザンチンの有であつた。
2) ロンバルド政府はしかし、ロンバルド人が、ローマ人をあまりに圧迫し、あまりにこれを収奪することを取締らうとも努めた。ローマ人の反感をいたづらに激発することは、少数の人口しかもたぬロンバルド国の、心して避けねばならぬ戒心事であつたからである。ロンバルド国の法制が、他のゲルマン部族国の法制に比して、はるかに完備整頓してゐた理由も、畢竟はこの国が法律組織の力に訴へて人民の貪欲な不節制を取締る必要を痛感してゐたからであつた。王権の強大は、ロンバルドにおいては、被征服者たるローマ人にとつても有利だつたのである。ローマ人はロンバルド王権の強力化を常に歓迎してゐたといはれてゐる(Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten II. 8.)。
二 ローマ法の事実的通用
何にしろ政府が右のやうな反《アンチ》ローマ政策をとつてゐたのであるから、ロンバルド期におけるローマ法の運命なども自然気づかはれるわけで、現にある学者などは、ローマ法はロンバルド族の侵入によつてその通用力を切断され、死せる法となつて古物館の中へ退席してしまつたのではないかと見てゐるのである1)。ローマ法のある部門、殊に刑法については、たしかにさうもいへるのである2)。ローマの刑法がロンバルド期に入つて全くその生命を絶たれてしまつたことは、疑ふべくもない事実なのである。なぜなればロンバルド人は公の関係についてはロンバルド法を適用する方針を貫徹し、ロンバルド刑法をロンバルド人とローマ人との双方へ押つけてしまつたからである。ロンバルド国内のローマ人は、ロンバルド法に従つて罰しられてゐたのであつて、決してローマ法に従つてその罪を問はれてゐたのではなかつたのである。
1) 後出第五節参照。
2) ローマ刑法は、ロンバルド期に入ると共に永遠的に死んでしまつた。十二世紀においてローマ民法の復活とはあつたが、ローマ刑法の再生は見られなかつた。
しかし民法の方はさう安々とは死ななかつたに相違ない。なぜかといふとロンバルド人が成文のロンバルド法を作定したのは、彼等のイタリイ侵入後七十五年目のことであり【後出第三節ノ一参照】、この七十五年間は、ロンバルド人は彼等伝統の旧慣だけを守つてゐたのであつたが、ロンバルドの旧慣を知るものはもちろんロンバルド人のみである。ローマ人はロンバルドの旧慣内容を知らず、従つてこれに従ふことも不可能であつたのである。だからこの七十五年間は(五六八年—六四三年)、ローマ人もまたその固有するところのローマ法を遵奉することを許されてゐた時期だと判断するの外はないのである。問題はそれ以後の形勢、すなはちロンバルド法典成立後のありさまであるが、法典の成立後も、やはりローマ人はローマ法を守つてゐたと信ずべき理由がある。それは二民族間の文化の相異である。当時のローマ人は、いかにも亡国の民らしい無気力無精神な廃頽生活を送つてゐたとはいふものの、さすが古典ローマ人の子孫だけあつて、澄んだ法律論理と冴えた法的判断力とは貯へてゐた。彼等の法律観念はゲルマン人のそれの粗野生硬なのとは比較にもならぬほど洗練を経たものであつたのである。彼等としてはその法的誇りを棄去るに忍びなかつたに相違ない。どうしてもゲルマン蛮法の前にその膝を折る気になれなかつたに相違ない。且つロンバルド政府の側からいつても、ローマ人間の内部法へまで干渉する必要はなかつたのである。政府は、ローマ人相互間の取引については、彼等の固有法を使用させておいて何らの不都合をも感じなかつたであらう。国内私法の統一といふ思想は近世のものに過ぎない。中世にはさやうな思想を見ず、むしろ私法を国内の各地方各民団の自治に一任しておく傾向を有してゐたのである。いかに国家主義の好きなロンバルド人といへども、私法の国家統一まで企てようとはしなかつたであらう。なるほど彼等はローマ人を農奴にはした。しかしこれはロンバルド人対ローマ人の関係においてローマ人を搾取しようとしたまでである。ローマ人相互間の内部関係へまで容喙しようと試みたのではなかつたのである1)。
或はいふかも知れない、『ロンバルド国においてはローマ法を適用する特別の裁判所がなかつた。特別裁判所なくして特別法があらうとは考へられない。ローマ法を適用する裁判所の実存を立証しえぬかぎり、ローマ法の死を想像しなければならぬのである』と2)。しかし中世は荘園制度の時代であつた。荘園は公権不入の特権をもつてゐた。国家の法及裁判所は、荘園の人民の私的生活にまで干渉することをえなかつた。荘民の私的生活は、その荘園の荘園法(Hofrecht)によつて規律され、その荘園の荘園裁判所(Hofgericht)によつて裁かれてゐたのである。では荘園法の内容はといふと、それは、その荘園を構成する荘民の民族確信や伝統慣習を基礎として出来上がつてゐただけに、荘園毎にかなりの相違は示してゐたが、概言すると、ゲルマン人を構成員とする荘園はゲルマン法的荘園法をもち、ローマ人を構成員とする荘園はローマ法を基礎繊維とする荘園法をもつてゐたのである。だから中世においてローマ法の特別裁判所がなかつたといふのは皮相の見だ。ローマ人を構成員としてゐた荘園の荘園法こそはローマ法であり、その荘園裁判所こそはローマ法の裁判所であつたのである3)。
当時ロンバルドの国内にはローマ人を構成員とする無数の荘園が散在してゐたが、それらはみなその内部にローマ法を貯蔵してゐたのである。荘園はいはばローマ法を鑵詰にせるものであつた。ローマ法は荘園といふ鑵の中へ鑵詰にされて、ともかくその余命を繋いでゐたのである4)。
1) Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten II. 59 fg.
2) Savignyはこの点を不安に感じた——『ローマ法保持のためにはローマ人の裁判官を要した筈だが、さやうな者の存在は立証できない。さればといつてロンバルド人の裁判官がローマ法に従つて裁判してゐたと主張するわけにも行かない。結局ローマ法は適用機関の欠缺のために通用困難に陥つてゐたのではなからうか』と(Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter I. 409.)
3) Hegelは考へた——『ローマ法は中世に入つてからは姿を農奴法若くは荘園法に窶して自己を保存してゐたのでなからうか』と。荘園法をローマ法の変装と見たのは、彼の一つの卓見であつた(Hegel, Geschichte der Städteverfassung von Italien I. 416)。
4) 荘園はローマ法を鑵詰にして保存してくれたばかりでなく、ゲルマンの古法をも鑵詰にして残しておいてくれたのである。ゲルマン古法の面影が永く保存されえたわけは、ゲルマン人を構成員とする各荘園が、荘園法の形ちで古法を保持してゐてくれたからであつた。
三 ローマ法の正式通用
ロンバルド王Liutprand (713--735)は、ロンバルド法の発達へ決定的な寄与をなした偉大なる立法王として聞えてゐるが1)、王はまたローマ人およびローマ法のためにも有利な転回をもたらしてくれたのであつた。王はローマ人へも公民資格を認め、参政権を認め、軍人にもこれを採用したのである。又ローマ私法中のある部分につき、正式にその通用力を承認したのである。ある部分とは相続2)・夫婦財産制3)・成年制度4)・子の法律上の地位などに関する部分をいふ。従来とてもローマ法は、ローマ人の間に通用し来つたのではあつたが、それは事実上の通用たるに過ぎなかつた。公にその通用力を認められた上のことではなかつた。ところがいまやLiutprandは、ロンバルドの裁判所に対して、ローマ人間の事件をも受理し、もしそれが親族相続に関するものであるならば、ローマ法に従つてそれを裁断してやれと命じたのである。又、公証人の職務に関しても一令を発し、公証人はロンバルド法に従つて証書を作成しうるばかりでなく、ローマ法に従つてもこれを作成しうるとしたのである5)。従来とてもイタリイの公証人は、ローマ法に依る証書の作成に当り来つたのではあつたが、それがいまLiutprandから正式の承認をかちえた次第であつた6)。
1) ロンバルド王Liutprandは、フランクのKarl大帝、西ゴートのRecessvind王と共に、ゲルマンの三大立法王と呼ばれてゐる。
2) Liutprand (Mon. Germ. Leg. IV.) 1--5, 102, 113.
3) Liutprand 7.
4) Liutprand 19.
5) Liutprand 91.
6) 一派の学者はローマ法の復活史における、Liutprand王の地位を重要視するのあまり、ローマ法はロンバルド国においてはLiutprand王の時から行はれ出した。それ以前のローマ法は死法に過ぎなかつたと説く。しかしこれは言ひ過ぎであらう。Liutprandは死んでゐた法を再生させたのではなくて、事実上行はれて来つたものへ正式承認を与へたに止つたのである(Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten II. 67 fg.)。
ロンバルド王国は七七四年、フランク族の攻撃に遭つて滅亡した。しかしフランクの征服者は、ロンバルドの遺法をそのまま受継ぎ、そのままこれを存続させたから、ロンバルド法はロンバルド国の滅亡を越へて残存しえたわけであつた。フランクの王たちはロンバルドの旧制を基礎に取り、これに必要な改訂を加へるだけに満足したのである1)。
然らばロンバルド法とローマ法との関係はどう改つたかといふと、フランク王は、二法を法源法上平等の地位に置き、恰も、ロンバルド人がその属人法としてロンバルド法の適用を受けうるやうに、ローマ人もまたその属人法としてローマ法の適用を受けうるとしたのである。すなはちここに二つの法系は属人主義の上に平行的に行はれうることになつたのである2)。
要するにロンバルドの侵入後ローマの遺民の間に事実上通用してゐたに過ぎなかつたローマ私法は、王Liutprandの時から部分的に公の通用力を獲得し、フランク時代に入つてから全部的に公の通用力を獲得し、法源法上のその地位を階段的に上昇させて行つた次第であつた。
1) 後出第四節参照。
2) Liutprandやフランク諸王の命令によつてロンバルドの裁判官は、ローマ人に対しローマ法を適用すべき任務を負ふこととはなつたが、当時のロンバルド裁判官にローマ法の適用を期待することは、事実上甚だ困難であつたであらう。なぜなれば紛糾したローマ時代の諸法源の中から相当する法条を発見することは彼等には殆ど不可能だつたし、といつて彼等の執務に便利なやうな簡単なローマ法抜萃書も、当時はあまり見当らなかつたからである(Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten II. 69)。
第二節 ローマ法のゲルマン化
一 ローマ法の質的堕落を証明するものとしての当時の法源及法書
ロンバルドにおけるローマ法は、Liutprand時代・フランク時代と、時代を進めるに従つて階段的にその法源法上の地位を上昇させ、遂にロンバルド法そのものと平等の取扱を受けるまでに進んだといふことを前節にのべたが、ローマ法の内容の方は逆にその間に、低落しつつあつたのであつた。あの端麗な古典法の姿は影を没し、昔のそれとは似もつかぬ粗悪な田舎ローマ法(römisches Vulgarrecht)となり下りつつあつたのであつた。その間の消息を鮮やかに示すものは中世イタリイのローマ法源である。われわれは中世のイタリイで編まれたローマ法の法源を時代順に見下ろして行くことによつて、ローマ法の質がいかにその間に低下して行つたかの過程を知ることができるであらう。
ロンバルド進入の直後、ロンバルド制下のローマ人間に通用力をもつてゐたローマ法源には三つあつた。一はCodex Theodosianus——これはいふまでもなくTheodosius II u. Valentinian IIIの両帝が四三八年に公布した大法典で、イタリイにおいては、ローマ滅亡の後まで確乎たる通用力を維持してゐたのであつた1)。後にのべるやうにロンバルドの王たちは、その立法中にローマ法的規定を取容れようとする際には、大抵資料をCodex Theodosianusに求めてゐるのであるが、このことからしても、いかにこの法典が、綿々として絶えざる余勢をイタリイに保有してゐたかがわかるのである。少くともロンバルド族侵入の直後においては、この法典はローマ人の間に標準的権威をもつてゐたのあらう。二はEdictum Theoderici——これはロンバルド族に先立つてイタリイへ侵入してゐた東ゴート族の統率者Theoderichが五一〇年頃に作つた法典であつたが、実質はローマ帝政末の法源からの抜萃を出でなかつた2)。すなはちこれも内容的には、古典ローマ法そのものでありえたのである。而してこの古典法も、後に九世紀に入つてイタリイで出来た、かのLex legumなどからローマ法の有力な材料視されてゐるところから推すと、かなり永くイタリイで勢力を維持したものとおもはれるのである。三はBreviarium Alaricianumであつた。これは西ゴート王Alaric IIがその領内のローマ人のために作つた法典であつたが、その内容はやはり古典ローマ法そのものの外ではなかつた3)。ただこの外国法典がイタリイにおいて果して法源的権威を認められてゐたかどうかについては議論があり、二三の学者はこれを否定するが4)、通説はBreviarium Alaricianumのイタリイにおける通用を肯定するのである5)。けだし八世紀の頃イタリイで出来たLex Romana Curiensisが、Breviarium Alaricianumを基礎に置き、これに多少の加工を加へるだけに止めてゐるところから推すと、Breviarium Alaricianumのイタリイ侵入を肯定せぬわけにいかぬからである。
要するにイタリイにおいては古典風のローマ法が七・八世紀の頃までローマ遺民の間に、主として(一)Codex Theodosianus (二)Edictum Theoderici (三)Breviarium Alaricianum等々に媒介されつつ、生残つてゐるのであつた。
1) 拙著・西洋立法史二八頁参照
2) 前掲拙著八六頁以下参照。
3) 前掲拙著六〇頁以下参照。
4) Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter II. 270. --Ficker, Forschungen zur Recht und Rechtsgeschichte Italiens III. 67.
5) Vgl. Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten II. 96.
転じて法律書の方を見ても、七・八世紀の頃現はれたものの中には、なほ古典法学の余香を留めた名作が少くない。例へば(一)ユ帝の法学提要(Institutiones)の註釈本としては、Turiner Institutionenglosseが出た1)。これは六世紀の末頃イタリイで作られたが、この書において人々は横溢的な法学知識の展示を見る。この書は決して法学提要だけを考察の対象にはしてゐない。広くユ帝法典の全般へ眼を配つてゐる。さうして密接に各法条を連絡させ、全体を一つの体系に纏め上げようと努めてゐる。所々、解釈において誤りを犯してゐる点もあるさうであるが、概して把握は的確、行文も充分に鋭利明晰だといはれてゐる2)。(二)勅法集(Codex)の註釈本としては、sog. Scholien zu Konstitutionen der Epitome Juliani3)があり、やはり六世紀の末イタリイで出来たが、これもまた著者における深大なユ帝法的知識の蔵畜を実証してゐるのである4)。(三)ユ帝法典の諸箇所を摘録的に註したものとしては、Dictatum de Consiliariis5)やCollectio de Tutoribus6)があるが、これらにおいても相当に高級な学術的手法の使用されてゐるのを見るのである7)。
1) Ausg.: Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter II. 420 fg.
2) Fitting, Über die sog. Turiner Institutionenglosse 5 fg.---Conrat, Geschichte des römischen Rechts im früheren Mittelalter 108 fg. ---Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter II. 199 fg. VII. 56 fg.
3) Ausg.: Hänel, Juliani Epitome Novellarum 178 fg.
4) Conrat, 123 fg.
5) Ausg.: Hänel, Juliani Epitome Novellarum 198 fg.
6) Ausg.: Hänel, Juliani Epitome Novellarum 201 fg.
7) Conrat, 137 fg.
しかし時代を下つて九・十世紀頃を見ると、もう到底古典時代の面影などはない。古典法の大殿堂は朽ち破れ倒れて、惨たる破材を地上へ投げ出してゐるありさまである。例へば十世紀の初頃南イタリイで出来たとおもはれる法律書にLex legum1)があり、同世紀の末北イタリイで編まれたとおもはれるものにQuestiones ac Monita2)があるが、両書とも、その載せてゐるところは、純粋なローマ法でなくてローマ・ゲルマン二法の混合である。すなはちLex legumの方はローマ・ロンバルドの諸法源からはもちろん、東ゴートの法典たるEdictum Theodericiからも採録し、西ゴートの法典たるBreviarium Alaricianumからも抜取つてゐるのである3)。Questiones ac Monitaの方もローマ・ロンバルド二法の諸法源からばかりでなく、ザリア・フランク族の法律Lex Salicaなどからも採択してゐるのである4)。そこには純粋なローマ法も見出されず、純粋なゲルマン法も見出されず、むしろ二元素の奇怪なる混合体を見るのである。例へばQuestiones ac Monitaの中から盗罪の規定5)をとつて見ると、これは盗賊に対してローマ式に身体刑を加へると同時に、ゲルマン式に又、贖罪金の支払をも命じてゐる。債務不履行の規定6)をとつて見ると、ローマ式に債務者を拘禁することにしてゐると同時に、ゲルマン式に又、債務者をして保証人を立てさせることにもしてゐる。万事がかういふ木に竹をつぐやり口でしかなかつたのである。
おもふに六・七世紀の頃まではローマ古典法の記憶なほ新鮮にして、かつかつその正統を危機の間に維持することもできえたのであらうが、時代と共に記憶は薄り、文化は低下し、ローマ人もゲルマン人もその間に差別を存せざる一様の野蛮人となり下がつてしまつたので、今はもう古典法の大組織を支へる力もなく、又そのやうなものをもつ社会的必要も消え失せてしまつてゐたのであらう。
要するにローマ法は九・十世紀に入つて全くその内容を荒廃させてしまつたのである。その頃のローマ法といふのは、決してかの論理的均整の美をもつた、古典ローマ法ではなくて、雑駁に中世化しゲルマン化し農民化した田舎ローマ法(römisches Vulgarrecht)でしかなかつたのである。吾人はその偽らざる姿態をLex legumやQuestiones ac Monita等において見る。
1) Abgedruckt bei Conrat 268.
2) Ausg.: Boretius in den Mon. Germ. Leg. IV.
3) Conrat, 268 fg.
4) Conrat, 274 fg.
5) Questiones ac Monita 7.
6) Questiones ac Monita 1.
二 ビザンチン区のローマ法
前段までの所説は主としてロンバルド区におけるローマ法の運命に関したのであるが、イタリイはロンバルド区からばかり成つてゐたのでなく、ビザンチン区ともいふべき地方も多く存してゐた。だからわたくしはイタリイ・ローマ法の全貌のために、ビザンチン区におけるローマ法の状況をも見渡しておく必要があるのである。
少しく古きに遡つてビザンチン帝国とイタリイとの関係を回顧して見るに、ビザンチンの皇帝ユスチニアンは失へるイタリイを回復して、ありし昔のローマ世界国を再建せんと欲し、屡々兵をイタリイへ出し、一時蛮人の手からイタリイを奪還したこともあつたのであつた。さうしてこの頃出来たての彼の法典をイタリイへ施行して見もしたのであつた。しかし帝の法典は、イタリイ人の歓迎するところとはならなかつた。東西に分れてすでに百余年、『西のローマ人』は『東のローマ人』を外国人視し、その法律を外国法視し、多少の反感さへ彼に対して抱く位になつてゐたのである。それにユ帝のイタリイ制覇も永続はしなかつた。僅々十五年の後、帝の覇業は新来の勢力ロンバルド人の攻撃に会つて覆滅せざるをえなかつたのである1)。しかし南イタリイ一帯の地はロンバルド族侵入の後もなほビザンチン帝国の領有として残つてゐた。後にノルマン人が来寇してノルマン王国を建設するに至るまで、南イタリイの地は、大なり小なりビザンチンの政治的勢力の下に立つてゐたのである。ゆゑにそこは法律的にもビザンチン法の勢力圏内に属してゐたと見るべきである。尤もこの点については異説も多いが、通説はやはりノルマン来寇前の南イタリイには、ビザンチン的ローマ法が行はれてゐたと見てゐるのである2)。Ravenna地方も永い間ビザンチンの領土であつた。そこはビザンチンのイタリイ経営の根拠地であり、本国から派遣された知事が在任してゐて、ビザンチン的勢力の挽回に努めてゐた。そこには一の法律学校も存在した。Ravenna法律学校なるものがそれである。この学校はかの有名なローマ市の法律学校の後身であつたらしい3)。ローマ市の法律学校は、ユ帝の時に、帝から、帝の法典を基礎として法学教育を施しうる特権を官許され、イタリイにおけるユ帝法典唯一の説明機関となつてゐたのであつたが、ロンバルド族の侵入に会い、難を避けてRavennaへ遷り、『Ravenna法律学校』とはなつたのである4)。ゆゑにRavennaの法律学校もユ帝法典を標準として初歩の法学知識をイタリイ在住のビザンチン人へ授けてゐたのである5)。よしやこの学校の学的活動は、一派の学者6)の考へるほど精力的ではなかつたにもせよ、ビザンチンの学芸をイタリイへ潅ぐ導管の役目は果してゐた。それは暗黒の世にローマ法学の伝統をかつかつ維持した・はかない一片の燈明であつたのである7)。
だから早期中世のビザンチン区は、優秀なローマ法書の産出地ともなつてゐた。前段においてわたくしは六世紀に編成されたローマ法書が、例へばTuriner Institutionenglosse, sog. Scholien zur Konstitutionen der Epitome Juliani, Dictatum de Consiliariis, Collectio de Tutoribus等が、いかに古典ローマ法学の余香を留めた高級品であつたかを説示したが、大抵これらの書はイタリイのビザンチン区で作られたものだつたのである。少くともTuriner Institutionenglosse8)やsog. Scholien zur Konstitutionen der Epitome Juliani9)が、イタリイ内のビザンチン区の産であつたことについてはほぼ疑を容れぬやうである。Turiner Institutionenglosseのごときは、その論述方法のあまりもビザンチン的であつたがために、ビザンチン本国の何人かの著書を種本にして作られたものではないかと疑はれてゐる位である10)。恰も好し、六世紀はビザンチン本国において法律学の花を開き、Theophilus, Julian以下いはゆる古学者(antiqui)の一群が躍り出でて一の法学隆盛期を現出してゐたので、その学風が直接的にイタリイに反響してTuriner Institutionenglosseのごとき高級学術書を産出させるに至つたものとおもはれるのである。
しかしイタリイにおけるビザンチンの勢力は日に日に縮つて行つた。殊にノルマン人の来寇が、ビザンチンのイタリイ経営を完全に倒壊させてしまつた。八・九世紀に入ると、ロンバルド法区のローマ法が堕落のどん底に落ちたやうに、ビザンチン区のローマ法も衰落の極に達してしまつたのであつた。
1) 拙著・西洋立法史二八頁以下参照。
2) ロンバルド族の侵入(六世紀)からノルマン王国の建設(十世紀)に至るまでの間、南イタリイはいかなる法律の下にあつたか、これは一つの熱火的論争問題となつてゐる(Vgl. Conrat, Geschichte des römischen Rechts in früheren Mittelalter 49 Anm. 1.)。
3) ローマ市の法律学校は、ConstantinopelおよびBerytusの法律学校と共に、帝政期における法律学研究の三大中心点を形成してゐた(拙論・ローマの法学教育・法学論叢第七巻第五号)。だからローマ市を占領した東ゴート族も、さすがにローマ法律学校は滅ぼさず、むしろこれをローマ法唯一の教授場として保護したのであつた。ユ帝は帝の法典をイタリイへ施行した後、この学校の教育特権を新認し、西欧においてはこの学校のみが法学教育をなす権利を有すと宣言したのである(Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter I. 133; Fitting, Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna 35)。
4) ローマ法律学校はロンバルド族侵入後、難を避けてRavennaへ移転したものらしいのである(Fitting, a. a. O. 37; Savigny, a. a. O. I. §137, IV. §§1, 2)。
5) 拙著・西洋立法史三〇頁参照。
6) Fitting氏は、Ravenna法律学校が、Bologna大学成立の以前において、かなり完全にローマ法学を教へてゐたかの如くに説いてゐるが(Fitting, Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna 38 fg.)、これは、氏の例の、法律発展の連続性(Kontinuität der Rechtsentwicklung)をあまりにも信じ過ぎる学癖の一つの現はれであつて、本当はRavennaの活動は、Bologna大学の先行者と称せらるべきほど、力強いものではなかつたらしいのである。
7) Ravenna法律学校は十一世紀の半頃なほ存続してゐた証跡がある(Fitting, Anfänge 38)。
8) Turiner Institutionenglosseの成立地については議論が多い。Savignyはイタリイにおけるビザンチン領内で成立したと見てゐる(Savigny, II. 95.)。Fittingはローマ法律学校の学者が作つたと考へた(Fitting, Über die sogenannte Turiner Institutionenglosse 29 fg.)。
9) Sog. Scholien zu Konstitutionen der Epitome Julianiの成立地についても多少の疑がないではない(Conrat, 12)。
10) Conrat, 108 fg.
第三節 ロンバルド法のローマ化
ローマ法が中世に入つてから著しく田舎化しゲルマン化したといふことを前節でのべたが、ゲルマン法の方もその間に実は大いにローマ化しつつあつたのであつた。ちやうどその頃ローマ人の血とゲルマン人の血とが混合しつつあつたやうに、又ラテン語とゲルマン語とが結び付きつつあつたやうに、ローマ法およびゲルマン法もその内容を漸次的に接近させつつあつたのであつた。でいまわたくしはローマ法のロンバルド化を説いたあとを受けて、ロンバルド法のローマ化を説明して見ようとおもふのである。
一 Rothari法
ロンバルド最初の成文法典をEdictum Rothariとする1)。六四三年、王Rotharによつて制定された。条数三百八十八、大体において三つの部分に分たれうる。一条から一五二条までは刑法規定、一五三条から二二七条までは身分法規定、二二八条から三六八条までは物権・債権・財産的犯罪に関する規定である。
内容は大体においてロンバルド族固有の慣習から成つてゐるが、注意してその内実を窺ふと、蔽ふべからざるローマ的感化の跡を発見しうるのである。例へば法典の前文はいつてゐる——『在来の制定法を更新是正し、その欠陥を補ひ剰を省くために云々』と(quae priores omnes renovet et emenda etc.)。この文字は、ユスチニアン皇帝が、教会財産の譲渡性に関して発した五三五年の新令中に用ゐてゐる文字であり(Nov. VII. v. J. 535)、それをいまロンバルド王が彼の法典の前文中へ無批判に借用したわけである。なぜ無批判にといふかといへば、ユスチニアン皇帝の場合には、『更新是正せらるべき在来の制定法』がたしかに存在してゐた。皇帝Leo, Constantin, Anastasius等が、教会財産に関して発した諸勅法がそれである。然るにロンバルド王の場合には、『在来の制定法』はない。王の法典そのものがロンバルド最初の制定法であつたのである。だのにこんな無自覚な言表をしてしまつたのは、いかに王がその法典の編纂に当つてローマ法源を利用したかを自白せるものに外ならぬのである2)。
さて法典の第一部類を点検すると、第二条は、ロンバルド王はその所為につき法的責任を負はざる旨を規定してゐるが、これはローマ法における『皇帝は法を超越す』(Princeps legibus solutus est.---D. I, 3, 31)の原則の移植であつたに相違ない。第七八条、七九条、八二条乃至八四条等には、不法に他人の身体を侵害せる場合の責任を規定してゐるが、その際、医師の治療費をも支払ふべしとしてゐるのはローマ法の影響であつたであらう(Dig. IX, 3, 7)。ロンバルドの旧慣に治療費の弁償などいふ思想があつたとはおもはれぬからである。一三八条は他人の物を不法に侵害せる場合の責任に関してゐるが、ここにもローマ法の影響を見る。なぜなれば同条は、ローマ法と同じやうに、加害者は加害行為前の一定期間内において被害物が有せし最高価格を被害者に支払ふべきものとしてゐるからである(Dig. IX, 2, 11, §4)。その他多くの類似点が探求に従つて発見しうるであらう3)。
第二部においては私生児の法的地位に関する一五六条及一五七条、相続財産の分割に関する一五八条及一六〇条、相続人の廃除に関する一六八条乃至一七〇条等々において、多かれ少かれローマ法との間の類似点を発見しうるし、第三部においても土地所有権の侵害、共同の不法行為、動物占有者の責任等々の規定においてやはり多くのローマ分子の侵入の跡を発見しうるのである。
1) Edictum Rothariの成立史については拙著・西洋立法史八五頁以下参照。
2) ロンバルド王は、直接ユスチニアンの新令集(Novellen)の中から、『在来の制定法云々』の句を取上げたのではない。ある媒介物を通じて——すなはちその頃ユ帝新令の標準的蒐集物と見られてゐたAuthenticumなる書を通じて——採択したのであつた(Conrat, Geschichte des römischen Rechts in früheren Mittelalter 3, 393)。
3) ロンバルド王は、直接にDigestaを利用したわけでもなかつた。当時はDigestaの存在が、イタリイにゐるローマ人それ自身からさへも知られずにゐた悲しい時代であつたのである。ロンバルド王はローマ滅亡の前後、西欧で出来た諸種の法源集、例へばCodex Theodosianus, Breviarium Alaricianum等からローマ的分子を摂取したのであらう。
二 追加法
Rothar王の法典は王の後継者すなはち王Grimoald, Liutprand, Ratchis, Aistulf等によつてたびたび追補を受けたが、追補の内容は、ローマ法の飛躍的輸入を意味するものに外ならなかつた1) 2)。なぜかといふとRotharの法律は、あくまでも固有の制度を基礎におき、ただその修正に当つて少しくローマを参照したり、それを法文に書現はす際ローマ法的用語を用ゐたりした位のものであつたが、GrimoaldやLiutprandとなると、固有法の知らざる新制度をローマ法から取入れたからである。それは単なる『法文の模倣』でなくて、『制度そのものの輸入』であつた。
例へばGrimoaldは取得時効の制度(c. 1)、承祖相続の制度(c. 5)をローマ法から輸入してゐるし、Liutprandは女子相続権の制度(c. 1--4)、消滅時効の制度(c. 54)、未成年者の法律行為取消権の制度(c. 58)等々をローマ法から取入れてゐる。RatchisやAistulfの追加法においても同じ行き方を発見しうるのである。
1) GrimoaldやLiutprandは、ユスチニアン皇帝の法典の中からローマ法を採用したのではなくて、西ゴートのローマ人法Breviarium Alaricianumを媒介してローマ分子を吸収したのであつた(Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten II. 123.)。
2) Liutprandの追加法は、ローマ法からばかりでなく、教会法からも顕著に影響されてゐた(拙著・西洋立法史八九頁参照)。
第四節 二法系の提携
一 立法作用の停止と法律学
ロンバルド王国滅亡の後これに取つて代つてイタリイを支配したフランクの諸王は、ロンバルド法を基礎におきつつ、これに必要な補充を加へて行つた。ロンバルド法補正のために発しられたフランク諸皇帝の勅法をイタリイ勅法(capitulare italicum)といふ。フランク諸帝は大抵イタリイ勅法を発したのであつて、例へばKarl大帝は七七九年から八一二年の間に、Ludwigは八一六年から八二〇年の間に、Lothar Iは八二三年から八三二年の間に、Ludwig IIは八五〇年から八七五年の間に多数のイタリイ勅法を発布してゐるのである。かくフランク皇帝の勅令で追補されたロンバルド法をFranco-Lombard法といふ。
フランク族のイタリイ支配が覆滅したあとを受けたのは、ドイツ皇帝であつたが、ドイツ皇帝もFranco-Lombard法に対して新法を附加し行く方針をとつた。例へばWido, Otto 一世二世三世, Heinrich 一世等は、イタリイ法の育成にかなり寄与するところがあつたのであつた1)。しかし概言すると、ドイツ皇帝のイタリイ立法は不親切でもあり不十分でもあつた。彼等は政治的にイタリイを攻略する野心には燃えてゐたが、北イタリイの法的需要へ備へる用意は欠いてゐたのである。で北イタリイの人民は、ドイツ皇帝の支配下に入つてからは、自己の工夫で自己の法的需要を満たして行かねばならぬ必要に会した。当時、北イタリイの地はいち早く商業に眼ざめ、取引も進み、都市も興り、人口も殖えつつあつたので、人民は、支配者がその責を果たさざる場合には、自己の工夫で新しい法律を作りもつ剴切の必要を感じたのである。而して人民のために新法産出の機関となつたのが学者であつた。学者は学説の力で新しい経済状勢に適合する新しい法律を産み出さうと努めた。十一世紀以後北イタリイは『学説による立法の時代』となつたのである。
1) Johannes Merkel, Die Geschichte des Langobardenrechts 19 fg.
二 古学と新学
学者の仕事は法源の整理蒐集に始つた。伝へるところによると、すでに早くOtto III (983--1002)の時代に、一の法源集が出た形跡があるといふ1)。それはロンバルド諸王の法律、フランク諸王のイタリイ勅令、並にドイツ王Wido, Otto 一世二世三世のイタリイ法を、その原始的形態において蒐集した上へ、ロンバルド学者の著書からの抄出文をも附加して一巻とせるものであつたらしいのである。次いでHeinrich I (1002--1024)の時代になると、Pavia法律学校の学者がいはゆる『Paviaの法律書』(Liber Papiensis)なるものを編成した2)。これはロンバルド王Rothar, Grimoald, Liutprand, Ratchis, Aistulf等の法律、フランク皇帝Karl, Pippin, Ludwig I u. II, Lothar I等のイタリイ勅令、ドイツ王Wido, Otto I. II. u. III, Heinrich II等のイタリイ法を蒐集せるもので、一〇二・三〇年頃出来たと見られてゐる。編輯方法は年代順であつたが、重複を省き、語句を正し、死法を捨て、一の現行法規集覧らしき体裁を具有せしめた。編成後間もなくこの書は、Pavia法律学校における法学講義の台本となつたのであつて、Paviaの学者は、この書が年代順に集めてゐる諸法源を、学理的統一的に把握すべく努力したものらしいのである。
でいまこの書に対するPavia学者3) 4)の研究態度を見ると、十一世紀前半の学者と後半の学者とは著しい方法論上の相違を示した。前半の学者は、概して固有法の尊重家であつた。彼等は好んでロンバルドの旧法制を研究した。新旧二法の比較対照によつて新法すなはち現行法の意義は初めて明かになるとでも考へてゐたらしいのである。又現行法の欠陥は、古法の隈なき探査の成果によつて十分に補填されうるとでも見てゐたらしいのである。彼等はすでに立法的に又は慣習的に、廃法となつてしまつてゐたところの古法令をも熱心に拾ひ集めた。そのために彼等の学問は解釈学といふよりも沿革史に近いものとなつてしまつた。当時民間に生れ出でつつあつた新しい法律意識に対しては彼等は盲目も同然だつた。
ローマ法との関係からいふと、十一世紀前半の学者は、ローマ法上の制度や規則をロンバルド法の組織内へ取り入れようとは企図しなかつた。彼等にとり唯一の法源はロンバルド法だけであつた。『ロンバルド法は一個の自足完了的法源体を成してゐる。これを意明するにはロンバルド的資料のみによるべきだ』と彼等は見た5)。彼等がロンバルド法の解釈に当つてローマ法的いひ表し方を用ひたり、ローマ法的に定義を下したり、組織を立てたりしたことは事実であるが、それはただローマ法学の手法を真似たに止る。純形式的な方法論上の模倣に止る。実質的にローマ法的規則や制度をロンバルド法の体内へ移植しようとは試みなかつたのである。
右のやうな方法論的特色をもつ学者は、後に古学者(antiqui)なる嘲笑的尊称を奉られた。Valacaus, Bonifilius, Lanfranc等がこれである。但、Lanfrancは見方によると新学の先駆者とも考へらるべき人であつた6)。
1) Johannes Merkel, Geschichte des Langobardenrechts, 19.
2) Ausg.: Boretius in den Mon. Germ. Leg. IV. 289.
3) Paviaの法律学校といふのは、中世の文学学校(Grammatikerschule)の進化したものか、又は公証人の実務教育所の発達したものであつたであらう——(一)文学学校といふのは教会附属の学校で、ラテン語の正しい読み方や綴り方を教へ、論理学修辞学等をも授けてゐたのであるが、法学知識の一端をも、修辞学と相結んで教授する例であつた。法学教育の要が叫出されると共に、文学学校のあるものは次第に法学教育を重んじ遂にはその組織を改めて、専門の法律学校と化してしまつた。Pavia法律学校はかうした経路をふんで成立したのかも知れぬのである(Vgl. Fitting, Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna 12 fg.)。又(二)公証人の実務教育所といふのは、中世においては、各職業の親方が、その職業上の知識を弟子ヘ直伝してゐるのであるから、公証人や判事も、その職業上の知識及経験を門弟たちへ教授してゐたに相違ないのであるが、法律組織の複雑化と共に優秀な専門家を雇つてこれに子弟の教育を託することとなつた。親方の家内教育が教師の講堂教育へと転化したのである。Paviaの法律学校もこんな経過を践んで成立するに至つたのかも知れない。中世の他の学校の成立史が大抵不明であるやうに、Pavia法律学校の沿革史も明かではないのである。
4) イタリイの法律学校としてはRavenna, Paviaの二法律学校が有名であつたが、イタリイ法律史におけるその地位の重要さからいふと、Paviaは遠くRavennaの上にある。なぜなればRavennaの意義は、高々、ビザンチン風のローマ法の保有に功献するところがあつたといふだけに尽きるが、Paviaの方は、ロンバルド法の徹底改造に功献し、ボローニヤ大学を中心として興つた・ローマ法学の華々しき再生のためにも、たしかに先駆者的役割を果してくれたからである。Halbanも両者の重要さは比較にならぬといつてゐる(Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten II. 82.)。
5) Pavia学者の学風についてはVinogradoff, Roman Law in medieval Europe 48---J. Merkel, Geschichte des Langobardenrechts 28 fg.参照。
6) Lanfrancがロンバルド法の解釈につきいかに自由な態度に出たかについては拙論『法律解釈学の神学性はいかにして始つたか』(法学志林第三四巻第九、一〇、一一号)参照。
十一世紀後半の学者となると、揃ひも揃つてローマ法の崇拝家であつた。彼等を新学者(moderni)とよぶ。Gaulcausus, Guilelmus, Ugo等がこれに属した1)。
新学者はローマ法から法の取扱技術だけを学んだのではない、法そのものを学び取つたのである。方法的形式的方面において影響を受けたに止らず、質料的実質的にも影響を受けたのである。彼等はローマ法を基準にして自国法制の価値を判定した。ローマ法に合する規定だけを是認し、然らざるものを擯斥した。法文の許す限りにおいて自国法規をローマ法へ接近させようと、彼等は努力したのである。自国法に欠陥ある場合にはローマ法を以てこれを補填した。ローマ法にはロンバルド法の欠を補ふ補充的効力があると、彼等は断言して憚らなかつた。ロンバルド慣習法のごときは、法源法上の地位においてローマ法に劣るとさへ見たのである2)。いはく——『ロンバルドにおいては慣習法は制定法に反して成立することをえない。制定法といふうちにはローマ法をも含む。ローマ法は制定法(lex)の一種である。ゆゑにローマ法に反する慣習法は法として成立することができない』と3)。すなはち新学者はローマ法を『ロンバルド慣習法の上、制定法の下』におき、これを補充法としてロンバルド制定法の欠陥をこれにより補充させようと欲したのであつた4)。
1) Vinogradoff, Roman Law in medieval Europe 50.
2) Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten II. 130 fg.
3) Conrat, Geschichte des römischen Rechts in früheren Mittelalter 508 Anm. 1.---Halban, II. 131.---Vinogradoff 51.
4) 十一世紀の末、すなはちPavia法律学校がやうやく衰落に傾いた頃、有名な一の註釈書が出た。Expositio ad librum Papiensem (Ausg.: Borerius in Mon. Germ. His. Leg. IV.)がこれである。これはLiber Papiensisに対するPavia学者の註釈の集大成とも見らるものであつた。なぜなればこの書の著者は、Liber Papiensisに収められる各法条を註釈するに当つて、判例や他人の学説を多数引用しておいてくれたからである。今日、吾人がPavia法律学校の学風をほぼ想見しうるのは、主としてこの書あるためである。
しかし考へて見ると、ローマ法がロンバルド法に対して補充的効力をもつに至つたといふことは驚くべき変化ではあつた。なぜなればローマ法がローマ人の属人法として行はれ来つた事実はすでに久しい。王Liutprandの時から二三のローマ法的制度がロンバルドに在住するローマ系統の人民の属人法として効力をもち出した。フランク時代に入つてからは全ローマ私法がローマ人の属人法として行はれ出した。しかしそれはローマ人の間に行はれえたに止る。ロンバルド人に対しては、何等の効力をも有たなかつたのである。ロンバルド法の内容が漸次ローマ化して行つたことは事実であつたが、しかしいくらローマ化したといつても、ロンバルド人の遵奉してゐたのはロンバルド法であつて、ローマ法ではなかつたのである。内実的にもロンバルド法は、そのローマ化の極点においてさへ、なほ顕著にロンバルド的であつたのである。つまりロンバルド法とローマ法とは、一はロンバルド人の属人法として、他はローマ人の属人法として、合することなき平行線の如くに流れ来つたのであつた。それが今どうなつたか、二つは遂に相合したのである。ロンバルド人はローマ法をロンバルドの法律そのものとしてしまつたのである。しかもローマ法の一部分をではなしに、その全体を、採用してしまつたのである。且つそれに『ロンバルド制定法の下、慣習法の上』といふ重要な法源法上の地位を認めてしまつたのである。久しく分立対峙の姿勢を保つて来た二法系は、今や提携補完の親和関係に入ることとなつた。
第五節 余 語
そもそも中世早期のイタリイにおいてローマ法がどんな運命にあつたかは、西洋法律史上の一大疑問である。十八世紀の末頃までの通説では、ローマ法及ローマ法学は、ロンバルド族のイタリイ侵入から十二世紀初半における註釈学派の勃興に至るまで数百年間、西欧の天地から失踪してゐたといふのであつた。いはく——『一一三八年、ドイツ皇帝Lothar IIは、南イタリイを征伐中、古都Amalfiにおいて戦利品中Digestaの完全なる古写本を発見し、これを帝の同盟市たるPisa市へ贈呈した。Pisaの学者は驚喜してこれが研究を開始したが、これぞローマ法学復活の開初ではあつた』と。この俗説に対しては十八世紀中すでに疑の眼を向けた学者もあつた。Muratoriのごとき法源探求家は、この伝説の不確実性を夙に看破してゐたのである(L. A. Muratori, Antiquitalis Italicae mediaevae 1738--1742. Vgl. Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter I. 2.)。しかし最後的にこの俗説を殺したのは、やはりSavignyの力であつた。彼は中世におけるローマ法の全運命を明瞭にさせるために、中世ローマ法史(Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter 1815--31, 6 Bde.; 2. Aufl. 1834--51, 7 Bde.)の七巻を著した。けだしSavignyの法理学に従へば——『法は国民の内部的必要性から産出される。一時の政策や政府の意思から作られるものではない。ローマ法が十二世紀において再生しえたのも、その背後に長い沈黙の発展史を有してゐたからであつたであらう。』と。かういふ信念に出発して彼は、広く古文献を漁り、古記録を尋ね、いかにローマ法が中世を通じて不撓の生存力を維持しつづけたかを明証したのである。彼に従ふと、十二世紀に入つてローマ法が新鮮な生命に輝き出したのは、当時北イタリイの都市が経済的に飛躍し、政治的に自由を獲得し、富と力とを充実するに至つた結果であつた。Digestaの発見といふやうな偶然の機会の結果ではなかつたのである。
しかしSavignyの業績は、その細部においてなほ多少の不十分さを残してゐた。註釈学勃興以前における法学研究の状況を十分に明瞭にしなかつたごときその一例である。けだし註釈学のごとき精密にして周匝なる大研究の生れ出づるためには、その前段階としてある程度の準備研究が積まれてゐなければならぬ筈であるのに、Savignyはこの前段階につき、あまり教へてくれなかつたのである。よつてSavignyの門弟Johannes Merkelは、先師の研究を補完するために註釈学勃興以前の法律学について研究した。而してPaviaの法律学校がいかに重要な先駆者的役割を果したか、いかに註釈学勃興のために必要な準備工作をなしたかを明かにした。その著ロンバルド法史(Die Geschichte des Langobardenrechts 1850)は僅か六十頁の小論文ではあつたが、中世法律学史の暗所を取除く上に頗る寄与的ではあつたのである。Stintzingもその名著『ローマ法及教会法に関する俗書史』(Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechtes in Deutschland 1867)の中において屡々ロンバルドの法律学に論及した。彼は註釈学以前の法律学史とそれ以後の学史とを連結させることによつて、それ以後の学史が初めて明徴になると信じてゐたのであつた。
Fitting1)に至つてはその学的全生涯を中世ローマ法の研究に捧げたかの観さへあつた。その論著の殆ど全部が、中世のローマ法及ローマ法学に関してゐたのである。Fickerもその雄深の大作『イタリイ法律史の研究』(Forschungen zur Reichs-u. Rechtsgeschichte Italiens 1868--74 4 Bde.)において、註釈学勃興以前の法律状態につき鋭い多くの洞察を投げた。Conratの力作『早期中世におけるローマ法法源史』(Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter 1891)や、Halbanの大著『ゲルマン部族国におけるローマ法』(Das römische Recht in den germanischen Volksstaaten 3 Bde.)に至つて、Savigny以来の長き研究史はやうやう収穫期に達し、一応の結末をつけられることとなつた2)。イギリスではVinogradoff3)が、フランスではFlach4)が、中世ローマ法の研究に寄与するところ少くなかつた。
ベルリン大学の故ゼッケル教授は、充分に検討せられたる史料の上に、堅実無比なる中世ローマ法史を建設せんとして、一生の間、蜜蜂的勤勉をつづけてをられたが、惜しいかな、その研究成果を手づから結収するに至らずして逝いた5)。
本論は、故教授の文庫の本学に所蔵せらるるを利用し、早期中世のイタリイにおけるローマ法状態につき、わづかに学びえしところのものを概線的に試描せるものに係る。
1) Fitting, Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna.---Über die Turiner Institutionenglosse und den sog. Brachylogus.---Über d. Heimat u. d. Alter d. sog. Brachylogus.---Glosse d. Exceptiones Legum Romanorum des Petrus.---Die Institutionenglossen des Gaulcausus.---Juristische Schriften d. früheren Mittelalters.---Summa Codicis des Irnerius.
2) 中世ローマ法史に関する諸家の研究をそれ自身歴史的に系統づけて簡単に紹介したものとしてはLandsberg, Die Glosse des Accursius und ihre Lehre von Eigentum 1--11を推す。
3) Vinogradoff, Roman Law in medieval Europe.
4) Flach, Études critiques sur l'histoire du droit romain au moyen âge.
5) Seckelの中世ローマ法史に関する研究の片鱗は、Seckel, Distinctiones Glossatorum --- Das römische Recht und seine Wissenschaft im Wandel der Jahrhunderte---Die Anfänge der europäischen Jurisprudenz im 11. und 12. Jahrhundert. Zeitschr. der Sav.-Stif. R. A. 1925等によつて窺へる。