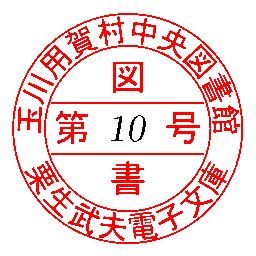
一
北イタリイの沃土を根拠として成長したロンバルド法は、同地方の政治的支配者がいくたび交替しても、変りなき愛撫を受けつつ、健やかに成長しつつあつたが、十世紀に入ると、その成長を停止してしまはねばならぬことになつた。それは、その頃イタリイの上へ政治的覇権を延ばし来つたドイツの皇帝たちが、ロンバルド法の増補改訂を怠慢に附し去つた結果であつた。彼等ドイツの皇帝たちは、イタリイを政治的に軍事的に制圧することのみを仕事とし、ロンバルド法を保育伸長さすことが彼等の立法者的責任であるといふことを失念してゐたのであつた。だから北イタリイでは、十世紀以降、『学説によるロンバルド法の修理時代』を現出しなければならぬ情勢となつた。なぜならば、たとへロンバルド法はその古物性・老朽性を露呈してしまつてゐたとはいへ、なほそれは北イタリイの実定法であり、北イタリイの生活関係は、この法的基準から裁かれ正される外はなかつたのであるから、北イタリイの人民としては、彼等の法律の反時代性・反社会性をなるべく緩和させ、なるべく弥縫するために、学者を動員して、この古物的法制の修理に当らしめねばならぬ必要を感じたからである。かくして北イタリイにおいては十世紀以降、学説に依る固有法の修理時代となつたが、学説に依る修理は、意外にも却つて固有法を破局に導く結果になつた。
それはロンバルドの学者たちが、固有法の修理工事を進めてゐる間に、漸次固有法を離れてローマ法の方へ接近して行つた経過の終局としてであつた。彼等といへども初めから固有法を蔑視してかかつたわけではない。初めの間はロンバルド法を一の『閉鎖的法源』と見、ロンバルド的法源のみを使用してロンバルド法を解釈せねばならぬとさへ考へてゐたのである。これをロンバルドにおける『古学時代』といふ。十一世紀前半がそれに当つた。この時代の学者はローマ法から影響らしいものを殆ど感受せずにゐたのである。しかしやがて『新学時代』が来た。十一世紀の後半がそれである。この時代の学者にとつては、ローマ法は光りに満ちた法律価値であつた。彼等はローマ法を標準として自国法制の価値を判定し、ローマ法に合するものだけを肯定し、ローマ法に合せざるものは軽蔑した。又ロンバルド法の明文に牴触せざるかぎり、最大限度において、ローマ法をロンバルド法の組織内へ移植しようとも試みた。しかしこの時代の学者は未だローマ法がロンバルド法そのものの一部を成すとまでは見解してゐなかつた。むしろローマ法は外国法であり、ロンバルド法解釈の一資料として役立つに過ぎないと見てゐたのである。しかし遂にローマ法が自国法そのものの一部と見られる時代が到来した。『継受時代』がそれであり、十二世紀以後がそれに当る。この時代の学者にとつては、ローマ法は外国法ではなくて内国法であつた。「ロンバルドの法律はロンバルド固有法とローマ法との二部分を以て構成され、前者の欠陥は後者を以て補はる換言すれば、ローマ法はロンバルド法に対して補充的効力を有す」と、彼等は見解してゐたのである。1)
ロンバルド法そのものの立場になつて見ると、ロンバルド法がローマ法に対して補充法的効力を認めるといふことは、いはば、軒を貸して母屋まで奪はれる危険を孕むものであつたが、果たせるかなこの危険は事実となつて現はれ、ロンバルド法の適用領域を漸次的に押し縮めて行つた。なぜならば、ローマ法の麗姿に眩惑されたロンバルドの法律家たちが、ロンバルド法の欠陥を補填するためと称して、多量のローマ法を必要以上に導入し、ロンバルド法の犠牲において、ローマ法の適用範囲を拡張して行つたから。
学者の立場になつて見ると、しかし、ローマ法がロンバルドの補充法となつたといふことは、華々しいローマ法研究の時代の開始を意味するものであつた。彼等はこれを機会として、ロンバルド法といふ陰鬱な中世的建造物の中から這ひ出し、ローマ法といふ無限の新視野の前に立つこととなつたのである。聖なる熱心を傾けて、彼等はこの古典法の分析を開始した。この歴史的大宝庫をさへ開くならば、新鮮な光りに輝く法律原則の多数を発見することもでき、永い間満たされずにゐた北イタリイの法的需要を全幅的に満たしてやることも可能だと考へた。彼等は断じて骨董趣味からローマ法の研究を始めたのではない。新社会のために新法律を供給せんとの実際的目的から始めたのである。いはば彼等は、立法者の怠慢を補つて一種の立法作用を営んだ変態の立法機関であつた。
なほその社会的経済的背景について一言を添へておくならば、十二・三世紀の北イタリイは、まさに新時代の最尖端であつた。そこにはあらゆる新鮮なもの・活溌なもの・若々しいものの新芽が動いてゐた。ヨーロッパの他の部分は、その頃未だ昏々として中世の眠りをつづけてゐたのに、ここイタリイの北部だけは、新鮮な生活感に眼ざめつつあつたのである。早くもここでは都市が興起し、貨幣経済が発展し、人口も増加し、商業も活況を呈しつつあつた。思想も開発的になり、ルネサンスの曙光さへ赫やいてゐた。凡そ人は「中世的」といふ形容詞のもとに、暗愚なもの・遅鈍なもの・無気力なもののいろいろを聯想し易いのであるが、かかるものとしての「中世的」は、まづイタリイの一角から消散し初めたのである。光りは北イタリイから発し、夜も北イタリイから明け初めた。想へばロンバルド法といふ中世の一大法律体系が地に倒れ伏してしまつたのも、ローマ法といふ古代法が再びその麗容を現はすに至つたのも、共に時代との関係からであつた。すなはち前者が新時代の法律たるに適する性格を欠き、後者がこれに適する性格を有したるがゆゑに、社会は前者をすてて後者をとり、『法の乗替』を敢行したまでのことであつた。2)
政治的にはその頃はちやうど、民族を基礎とする政治統一の思想が衰へて、地域を基礎とする統一の思想が興らうとする時代であつた。「苟も同一地域に居住し、同一都市内に生存する以上は、その血液のローマ系なりやロンバルド系なりやに論なく、共同して一個の政治団体を構成せざるべからず」との考へに移りつつあつたのである。かのロンバルド法がローマ法に対して遂に補充法的地位を認め、両者連繋の力によつて北イタリイの新生活関係を統制しようと策するに至つたのも、畢竟は、当時の北イタリイにおいて、民族的対立を超越した地域的法律協同体が新たに成立しつつあつた結果としてであつた。
しかし私はここでは十二世紀の北イタリイにおける法律変革の社会的政治的原因を探求しようとするのではない。単に右の変革運動へ花形選手として参加した四五の学者を簡単に伝して見ようとするだけである。
1) ロンバルドの法律学については、『東北帝大法文学部十周年記念法学論集』所載の拙稿『中世イタリイにおけるローマ法の運命』殊にその二二頁以下参照。
2) 中世末におけるローマ法復活の原因については、拙著『中世私法史』一八頁以下参照。
二
註釈学者がその学的活動の本舞台としたのは、北イタリイのボローニヤの法律学校だつたから、まづこの学校の起源を説いてみると、この学校の起源は、中世の他の学校の起源が大抵不明であるやうに不明である。伝説によると、古ローマの皇帝Theodosius IIが建てたのだといふことだが、Savignyがその雄作『中世ローマ法史』【Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter III. §62】の一節において、この伝説の虚妄性を指摘して以来、一人としてこれを信用する者はゐない。今日の通説は、多分この学校は、中世の文学学校(Schule der liberales artes)の進化してその型を転じたものであつたらうと見る。文学学校といふのは、教会附属の学校で、ラテンの文学や論理学や修辞学などを教へ、修辞学の一部分として初歩の法学的知識をも授けてゐた。それが十一世紀以後、漸次重きを法学教育におくやうになり、中にはその組織を改めて専門の法律学校化してしまつたものもあつたが、これは同世紀以後、法的知識の社会的重要性が承認され出した結果としてであつた。ボローニヤの学校も、かうした変化を辿つた末、専門の法律学校化してしまつたものだらうといふことである。十一世紀の末、そこにPepoといふ学者がゐた。その事蹟、頗る不明であるが、彼が修辞学の先生でなくて、法律学の先生であつたことだけは確からしい。恐らくボローニヤは彼あたりを端初の人として、専門の法律学校化したものかと考へられるのである。1)
1) なほボローニヤ大学の根源については石原謙博士・大学の歴史(岩波哲学講座)一三頁以下参照。
ではなぜひとりボローニヤだけが新興法律学の魁となり、学術復興の中心点となりえたのかといふと、先進の他の法律学校が、種々の原因から極度の不振状態に落ちてゐた際、ボローニヤだけが反対に、有利な多くの原因に恵ぐまれ、温められてゐたせいだつたと答へうるでもあらう。先進の法律学校とここにいふのは、Paviaの法律学校とRavennaの法律学校とである。まづRavenna法律学校の方を説くと、Ravenna市はビザンチン帝国の植民市であり、イタリイにおけるビザンチン文化の展覧会場でもあつた。元来イタリイが中世の荒廃裡において、ともかくも一種の文化をもち学問をも有しえたゆゑんのものは、イタリイ各地に残存してゐたビザンチン植民市からの刺戟に俟つ所多いとのことであるが、Ravenna市のごときは、ビザンチン本国の文化をイタリイへ注ぎ込む最も太い導管であつたのであつた。
しかしRavenna法律学校の活動は最初からさう華々しいものではなかつたらしい。高々それは、同市在住のビザンチン人へ、いはゆる田舎ローマ法(römisches Vulgarrecht)の簡単な知識を授ける位の機能しか営んでゐなかつたもののやうである。田舎ローマ法といふのは、ゲルマン的要素を雑駁に取入れたローマ法のことであつて、中世のローマ系人民は、かやうなゲルマン化し中世化し田舎化したローマ法を使用してゐたのであつたが、Ravenna市民も、その例から洩れてはゐなかつたから、同市の法律学校は、同市市民のために田舎ローマ法の解説を試みてゐたのであらう。しかし十一世紀に入ると、ビザンチンの勢力が全面的にイタリイから退潮してしまつた結果、Ravenna法律学校の運転も休止してしまつた。尤も一〇八〇年頃までは存続してゐた確証を留めてゐるといふことであるが、それは単に動きの止つた存在としてであつた。
次にPaviaの法律学校を見ると、Paviaといふ処はロンバルド古来の首府であり、ロンバルド裁判所の所在地でもあつたから、ここの学校としては、かのRavennaの学校がローマ法の教述を任としてゐたのに対抗して、ロンバルド固有法の教述を以てその目的となさざるをえなかつた。しかし十一世紀の後半になると、この学校もローマ法の研究へ手を延ばして颯爽たる新活動を開始したが、これはその頃北イタリイにおいて時代の急転があり、人間が息づまるやうな革新的興奮に駆られ出した結果であつたといふこと、前段で詳述したとほりである。実に十一世紀後半のPavia学者は、動き出したる新イタリイへ新法律を供給すべく、新知識・新素材を、ローマ古典法の裡にさがし求めつつあつたのであつた。だがしかし、その本来の目的がロンバルド固有法の教述にあつたといふことが、結局、Pavia法律学校を行詰らせてしまふ結果となつた。なぜならばその本来の目的がロンバルド法の説明に存したがために、万ざらこれを見棄てかねてゐる間に、時代はどしどしロンバルド法を離れてローマ法の方へ乗替へて行つたからである。十二世紀の初めボローニヤの法律学校が、新しい選手のやうな猪突性を以て登場し来つた頃には、Paviaは冷笑に送られて退場しつつあり、幾何もなくしてこの消息をさへ絶つてしまつたのであつた。
結局、新興の学問は、新興の学都によつて担当されなければならなかつた。ボローニヤは当時の新興都市であつたのである。新鮮と情熱とに満ちあふれた青年都市であつたのである。商工業は当時屈指を以て数へられたほど賑盛活溌であつた。場所がちやうどRomagna, Lombardy, Tuscany三地方を連結する十字路に当つてゐたので、旅人・商人の往来絶えず、市民は彼等からいつも思想上の好刺戟を受けつつあつた。とりわけTuscany地方は、商業的繁栄の中心であり、ルネサンス運動の本営でもあつたから、ここから吹いてくる新鮮な風がボローニヤ市民の思想を殊のほか生新にしてくれた。ボローニヤ市民は敏感的に新時代の刺戟に反応してゐたのである。Ravennaの古都はボローニヤより程近く、Paviaの町も遠くはなかつた。ボローニヤはこれらの先進学校の硬直せる伝承には囚はるることなしに、その遺した学的遺産だけは十分に継承し利用しえたのである。新学問興隆の地としての諸条件は、ボローニヤに備はつてゐた。ローマ法学といふ当時の新興科学が、ボローニヤ市をその快適なる住宅として撰んだのも、決して偶然ではなかつたのである。
三
でいまボローニヤを舞台として華やかに躍つた学星中の代表的四五を伝して見ると、ボローニヤ最初の学者だつたと伝へらるるところのPepoの事蹟は不明である。ただ十二世紀の註釈学者Odofredusがボローニヤ大学の起源を論じた文章中1)Pepoに論及し、彼こそボローニヤ最初の学者だつたといつてゐるところから推して、論者Odofredusの世代までは、なほPepoの事蹟が人の記憶に残つてをり、時々話題にも上つてゐたものと想像しえられるだけである。しかし彼はボローニヤ最初の学究であつたにしても、ボローニヤ学の特色たる註釈方法の形成へ、決定的な影響を与へた人だつたとは考へられない。年代的には最初でも、註釈学の父ではなかつたのであらう。真に父の名に値したのは、何といつてもIrneriusであつた。だからわれらも註釈学者の列伝をこの巨人から始めようとするのである。2)
1) Odofredus in Dig. vetus, L. Jus civile 6. de just. et jure : ……,,Quidam dominus Pepo coepit auctoritae sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua, nullius nominis fuit.'' Vgl. Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter III. §158. IV. §3.
2) 以下註釈学者の評伝は主としてLandsberg, Die Glosse des Accursius. 11 fg. 1. 2. 3.
Irneriusの生涯とても決して明白ではないが、彼が、ボローニヤ生れのボローニヤ市民であつたことだけは疑ないやうである。彼はボローニヤ法律学校の教師であつたと同時に判事でもあり、一一一三年に一度、一一一五年から二五年へかけて両三回、有名な訴訟事件を裁判してゐるのである。彼は政治家でもあり、侯Machildeに用ゐられてその顧問となり、侯の死後は、皇帝Heinrich Vの寵をえて政治の枢機にも参画したのである。晩年のIrneriusは、法律学を見棄てて政治に専心したと見る説さへあるが【Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter III. §7.】、それはあんまり穿ちすぎた想像説だといつて反対する人もないではない【Fitting, Die Anfänge der Rechtsschule zu Bologna 103】。
Irneriusの学的遠裔Odofredusの書いてゐるものによると、初めIrneriusは修辞学の教師だつたのを、転身して法律専門家となるに至つたものらしい【Savigny, Geschichte IV. §7】。この説にしてもし真ならば、Irneriusこそは、東洋の諺にいふ・文王なくして興つた豪傑の士だつたのである。独りで学び、独りで考へ、そしてよく新方法を案出し、新学問を樹立した稀有の一人だつたのである。彼の修業時代には、Pepoもすでにこの世になく、どこをさがしても師らしい者はえられなかつた。彼はPaviaの学者やRavennaの学者が書き遺した註釈書類を覚束ない便りとして、ただひとり、ローマ法学の原生林の奥へ奥へと踏み進んで行つたのである。さうしてとうとうあの浩瀚なユ帝法典の全篇の隅から隅までを学問的に征服し了へたのである。
その研究態度は破軌道的に嶄新だつた。彼とPaviaの学者とは、すでに、その研究対象を異にしてゐたのである。Paviaの学者は、ロンバルドの固有法を研究対象とし、僅かにロンバルド法の補充法としてローマ法を参見したに過ぎなかつたのに、Irneriusは、その研究対象をローマ法だけに限定したのである。ロンバルド法のごときは彼から一瞥をも受けえなかつた。又彼はRavennaの学者とも、その研究対象を異にしてゐた。Ravennaの学者はいはゆる田舎ローマ法、すなはちゲルマン法上の観念や規則やを不調和にとりこんだ不純なローマ法を研究してゐたが、Irneriusは、田舎ローマ法などへは全く見向きもしなかつた。彼は一途に純正ローマ法、すなはちユ帝法典の規定へ突進したのである。この聖なる経典を完全に知り、忠実に意明することを以てその全使命としたのである。これは全く伝統を打ち破つた・今まで夢想だもされえなかつた研究態度であつた。嶄新でもあり、警抜でもあり、大胆でもあつた。当時、ボローニヤ以外にローマ法を学ぶ地なしとして、無数の学生がヨーロッパの各地から、聖地へつどふ順礼のやうに集り来つたのも、Irneriusの、かかる研究対象上の特色がもたらした当然の好評といふべきものであつた。
ではIrneriusの研究方法上の特色はどこにあつたかといふと、彼がユ帝法典の意味の解明のために使用した手段に二つあつた。『語註』と『法理註』とがそれである。語註といふのは、法文中の難語難句の意味を辞書的に規定することをいふ。すなはち一語の代りに他の同意語を、一句の代りに他の同意句を代置することをいふ。この方法は何もIrneriusに始つたものではない。先進の法律学者、例へばPavia法律学校の学者なども、かうした方法はかなり使用してゐたのである。しかしもう一つの方法、すなはち『法理註』の方は、断然、Irneriusの独創であつた。それは法条の文字的意味に囚はれず、或はそれよりも広く、或はそれよりも狭く、時とすると全くそれを離れて法条を意味づけて行く方法であつた。この方法は法典の体系的統一性を仮定し前提する思想から出たのである。すなはちIrneriusは多分かういふ前提的思想をもつてゐたのであらう。いはく——「ユ帝法典に収載されてゐる無数の法条は、相連関し、相補完して一個の体系的統一体を成してゐる。各法条は孤立的に離在してゐるのではない、一全体の中の要素として、一秩序の中の節として、相対的に独立してゐるに過ぎない。ゆゑに註釈者は、各法条を無聯絡に意味づけて行つてはならない。他条との聯関において、全体との調和において、意味づけて行かなければならない。全体の立場から見て、その意味広きに過ぐと見らるる法条は縮小してこれを解釈し、その意味狭きに過ぐと見らるる法条は拡張してこれを解釈し、その意味正当を欠くと見らるる法条は合理化してこれを解釈しなければならない、解釈の要は調和的秩序の認識にある」と。かやうに法典の秩序性・統一性を信仰する思想と、この思想から当然に導き出された縮小解釈・拡張解釈・合理解釈等の方法とは、実にIrneriusの創案であつた。彼以前に、かかる思想を抱き、かかる方法を用ゐた者はなかつたのである。少くともIrneriusほど自覚的にこれを駆使した者はなかつたのである。この意味において彼は註釈学の父であり法律解釈学の創始者であつた。Savignyも『吾人は法理註の完全なる創作を、Irneriusへ帰するにつき、何等の躊躇をも感ぜず』といつてゐるのである【Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter IV. §11】。
四
十二世紀の後半に入つて、『四博士』(Vier Doktoren)又は『四つの百合の花』(Vier Lilien des Rechts)と美称される四人の大家を出した。Jacobus, Hugo, Martinus, Bulgarusがこれである。しかし四人のうち、その活動の特に目ざましかつたのはMartinusとBulgarusとであつたから、ここではこの二人だけを伝して見ると、二人はIrneriusの遺業を承受大成しただけでなくて、註釈学の後日の発展へも決定的影響を与へたのであつた。二人を対照してみると、二人ともユ帝法典の全範囲を、隅から隅まで知り抜いてゐて、自在にこれを引用したり使用したり解説したりすることができた。二人とも各法条の包有する意味をいとも鮮やかに把捉し、各条の適用せらるべき場合を極めて精確に限定して行くことができた。法条相互の間に意外に緊密なる相関関係を発見したり、相互の間に一見恰も存在するがごとくに見える重複や矛盾や欠陥やを、縮小解釈・拡張解釈・合理解釈等の方法を用ゐることによつて清潔に掃除して行つたりする手腕の冴え——この点においても二人は優劣の差をもたなかつた。たしかに二人は、最高の解釈学的頭脳の所有者であつたのである。しかし強ひて二人の相違を求めるならば、Martinusは、『合理解釈』(begründende Glosse)の方法を愛用し、『衡平』(Aequitas)の観念を特に重んじた。彼は衡平の観念に適合するやうに法律を意味づけ秩序づけようと欲したのである。衡平のためには、多少、条文の原意を損傷することさへ辞しなかつた。一二の例を示すと、ローマ法では、人は自己に属せざる物を有効に処分することをえないが、国庫が自己に属せざる物を処分した場合には、例外として所有権移転の効果を生ずべきものとなつてゐたのであるが(C. 7, 37, 2. 3.)、Martinusは、国庫といへども自己に属せざる物を有効に処分しうる謂れなしと考へた。それゆゑに彼は、国庫が他人の物を有効に処分しうるのは、国庫が善意なりし場合に限ぎると註したのである【Hänel, Dissensiones dominorum, 57】。すなはち彼は彼の衡平観念を満足させるために、わざわざ『善意』なる制約者をもちこみ、法文の原意を曲屈させてしまつたのであつた。又ローマ法では妻又はその親族が、婚姻に際し、一定の物を嫁資として指定した場合には、その物は婚姻の継続中、妻の所有を離れて夫の所有に移るといふことになつてゐたのであるが(C. 5, 12, 30)、Martinusは、たとへ婚姻の継続中だけにもせよ、嫁資が夫の所有に移るのは不合理だと考へた。「夫は嫁資に対し使用収益の権を獲得すれば足る。何もその所有権まで奪ふ必要はない」といふのが、彼一流の正義感情であつた。だから彼は法文を彼一流に合理化して、「嫁資は婚姻中といへども妻の所有に留る、夫は嫁資につき単に使用収益の権を有するのみ」と註した【Gl. naturali jure ad leg. 30 C. de jure dotium, 5, 12】。この類の小刀細工は彼においては珍らしくもなかつたのである。彼は一種の正法主義者であつた。
Bulgarusの方はこれに反して実定法主義者であり、忠実に厳格に実定法を意明しようと努めたのであつた。彼にとつては、実定法の内容が正法に合するや否やは問題でなかつた。「悪法といへども法として立てられたる以上は法である・解釈家としては、あるがままの内容において、法を認識し把捉しなければならぬ」といふのであつた。論敵Martinusのやうに、註釈家自身の主観的正義観を、解釈論のうちに織り込んでしまふのは、学問を純正にするゆゑんでないと見たのである。彼みずからかう言つたと伝へられる——『法と道徳とは相互に独立する。もし二つが一致しないならば、道徳の犠牲において法を遵守するより外はない』と【Landsberg, Die Glosse des Accursius 16】。彼はMartinusの自由主義的なるに対して厳格主義的であり、浪漫的主観的なるに対して現実的客観的であつた。
かやうにBulgarus, Martinusの二大家は、法に対する彼等の態度を両極的に対立させてゐたので、Martinusの衡平主義・正法主義に対して愛好をもつ学者および学生は、彼を頭目としてその周囲に集り、Bulgarusの厳格主義・実定法主義に対して同感をもつ者は、彼を中心としてその周囲に円陣を作つた。Martinusの名はGosiaであつたから、彼の支持者は``Gosiani''と呼ばれ、Bulgarusのフアンたちは``Bulgariani''と呼ばれた。ちやうどその昔ローマにおいて、学者Labeoを祖とするプロキユリアン学派と、Capitoから始まるサビニアン学派との二派があり、鋭い対立抗争を示してゐたやうに、註釈学者の陣営中にも、二学派の対立を生じたのである。Gosianiの側からは、Placentinus, Pyleus等の有力学者を出し、Bulgarianiの陣営中からは、Johannes Basianus, Nicolaus, Furiosus, Azo, Odofredus等の巨匠を輩出させた。十三世紀に入つてAccursiusが出て、二学派の学説を公平に取捨撰択し、大きくこれを統一したが、これはローマにおいて遂にJulianが出て、サビニアン・プロキユリアン二派の学問を集大成せると趣を一にせる現象であつた。
五
註釈学はPlacentinus, Basianus, Azo等を以て輝しい高潮期に入つた。
Placentinus (†1192)は、数多き註釈学者の中でも特徴的な存在であり、論理的構想の力に秀でた人であつた。彼は法律を一の論理的秩序と見、各条・各観念の間に論理的矛盾なきやうに留意しつつ、各条・各観念を意味づけて行つた。彼は債務関係の性質とか、権利と訴の関係とか、所有権の本質とかいふ理論的考察を愛好し、又これに得意でもあつた。他の註釈家たちが法典の文字の上を匍匐してゐる間に、Placentinusは、高く理論の世界に逍遥してゐたのである。
法学講義の方法についても彼は新味ある様式を創出した。他の諸家が、法典の篇・章・条の順序を追ひつつ法典の内容を解説してゐた間に、彼だけは法典の排列順に拘泥せず、法典の内容を論理的順序に分解再構して系統的にこれを説明して行くやり方をとつた。すなはち他の教師らの講義が逐条態(Kommentar)であつた間に、彼のは教本態(Lehrbuch)であつたのである。註釈学者中、最初に教本態の講義様式を思付いたのは実にPlacentinusであつた。
Johannes BasianusはPlacentinusと世代を一にし、Placentinusがゴシア学派、すなはち自由派の棟梁であつた間に、Basianusはブルガリ学派、すなはち厳格派の代表であつた。彼はPlacentinusのやうな大胆奔放な思想家ではなくて、刻苦細心の研究家であつた。厳密なる論程を辿つて、彼は、一歩一歩真理へ近づいて行かうとした。Placentinusは、敏鋭な直観力を以て一挙に真理をとらへようとする行き方であつたが、Basianusは、組織的研究の網を細心に張り拡げて行つて、極めて確実に真理をとりおさへてしまふ・やり口であつた。彼は非常に独断をおそれ、広く他人の学説を引用し、参考した。法律学において他人の学説を繁冗に引用する風は、Basianusあたりから始つたらしいのである。ローマ法源の解釈上、彼も屡々新説を出したが、それは彼の間然するところなき組織的研究の成果としてであつたらしい。十二世紀半以後ブルガリ学派は勢を増し、漸次、ゴシア学派を圧して行つたが、それは、ブルガリ学派の中にBasianusのごとき堅実無比な学究がゐて、厳格学派の地歩を着々踏み固めて行つた当然の結果であつたであらう。
Azo (†nach 1229)は全註釈学者中、Irnerius及Accursiusに次ぐ大なる名声を享受してゐる。彼は註釈学の最高潮を代表する華麗な存在であつた。所属学派からいふと、ブルガリ学派の人であつたが、この派の通弊たる渋滞窘束の苦を離れ、才気縦横、恰もその一身に、ブルガリ学派の長所たる堅実味と、ゴシア学派の長所たる奔放性とを兼ね有したる観があつた。彼は精緻な論考を流麗な文章に託し、自由な思想を緊い組織中に盛ることができたといはれてゐる。彼の学問は、該博と独創と華麗との綾織物であつたともいはれてゐる。単に文章道の上からだけいつても、彼の作物は、文芸復興期のイタリイ文学を代表する名品の一にして、流動自在、あらゆる変化を曲尽してゐると聞く。
六
註釈学発展の終結を成した者はAccursiusであつた【Savigny, Geschichte V. §92 fg.】。彼は一一八二年頃生れ、一二六〇年頃死んでゐる。彼は彼自身の註釈によつてよりも、むしろ他人の註釈を巧みに結集せるのゆゑを以て、その名を不朽ならしめることをえた学者であつた。彼の註釈書を『標準註釈書』(Glossa ordinaria)とよぶ。それにおいては、Irnerius, Bulgarus, Martinus以下、歴代諸大家の学説が多量に盛上げられてゐるのである。それはいはば著者の先及同時代の、諸学者の全給付・全業績を結撰した、註釈学発展の最後の記念碑であつたのである。
この書の後代に及ぼせる影響の広大さは、真に測るべからざるものがあつた。後代は、この書を通じてのみ間接に註釈諸大家の学説に面接することとなつた。この書は、実に註釈学者と後代との間を截然、中断してしまふ効果をもたらしたのである。いはばこの書は中世法律学の『学説彙纂』(Digesta)であつた。ローマの『学説彙纂』がローマ古典期の学説の綜覧であり、これに媒介されて古典期の学説が後代に伝はつたやうに、『標準註釈書』は中世法律学の綜覧であり、これに媒介されて、中世の法律学は、後世へ伝はることとなつたのである。
Accursiusと世代を一にしてOdofredus (†1265)が出た【Savigny, Geschichte V. §117 fg.】。この人は彼の学業の価値によつてよりも、彼の無用の駄弁によつて偶然にもその名を不朽ならしめることをえた稀なる幸運児であつた。「彼の遺した講義録を見ると、そこには輝けるものも、嶄新なものも、辛辣なものもない。ただ陳腐な凡説庸論が平板蕪雑な言辞のうちに力なく列べられてゐるだけだ」といふのがSavignyの批評である。かやうな無刺戟な講義を聴くことは、学生にとつては午睡を催ふす材料にしかならなかつたらうし、講者自身にとつてもかなりの苦痛であつたであらうとまでSavignyはいつてゐるのである。しかしOdofredusは、法律の大家ではなかつたが、漫談の大家ではあつた。彼はその独特の駄弁を以て、聴者の倦怠をまぎらす秘術を心得てゐたのである。彼はよく、彼の講義の間隙を利用して、ボローニヤ大学の成立史とか、初期のボローニヤ学者の学風とか、逸事とか、彼自身の学生時代の思出話とかを面白をかしく話して聞かしたが、幸にもそこには又、頭の悪い学生もゐて、師の凡庸な講義をそのまま筆記するばかりか、師の漫談までもそつくりそのままノートに取つて後世へ残してくれた。今日Odofredusの『註釈書』として残つてゐるところのものは、実はOdofredus自身の筆に成つたものではなくて、彼の劣等学生が取つた講義の筆記であつたのである。しかし低能教授と劣等学生とは、偶然にも大なる功名をなしてしまつた。なぜならば、彼等の余戯のおかげで、ボローニヤ大学の成立史や、学生生活の模様や、ボローニヤ学者の逸事やらが永く後代に伝はることができたからである。法律文化の発達に対するこの大学の寄与が、あまりにも重且つ大であつたがために、後の研究家は、この大学の成立および発達の過程を調べようとしたが、何分にも史料がない。八方これを求めた末、辛じて唯一の根本史料をOdofredusの講義録=漫談録において発見したのである。さうしてこの漫談録の価値を高々と見積つたのである。その結果Odofredusの名は、Irnerius, Azo, Accursius等と共に永遠に青史を照らすこととなつた。
七
以上をもつてわたくしはボローニヤを舞台として活躍した註釈学者の重なる四五を伝し了つたので、進んで彼等の学問の性質やその方法やを論明すべき順序なのであるが、これについては先年雑誌『法学志林』において私見を披瀝しておいたので、同誌の参照を乞ひつつ、ここにペンをおきたい【『法学志林』三四巻九,一〇,一一号】。ただ一言わたくしが十二・三世紀におけるイタリイの法律学を論じつつある間に強く感得した一事だけをいひ添へておくならば、凡そ社会は、その基礎的経済構造を根本的に変革させつつある転型期においては、旧来の法律体制を全般的に揚棄して、新法律体制を、最初の第一歩より建設し始めるものだといふ臆断である。社会転型の過渡期に際しては、旧社会の経済構造を反映するところの旧法律体制は、これを保存しこれを改良しこれを維持せんとするあらゆる努力・あらゆる企図にも拘らず、遂に崩壊し死滅して行くのを、何としても避けえぬのである。逆にいへば転型期においては、新社会の経済構造に相応する新法律体制が、これを弾圧し迫害し断種せんとするあらゆる企図にも構らず、結局生育を遂げてしまふのである。余のいま取扱つた史代に即してこれをいひ直せば、十二・三世紀は、自然経済から交換経済への転換期であり、村落生活から都市生活への飛躍期であり、仲間互助の倫理思想から個人独立の倫理思想への変化期であつたのである。だから法律上においても、『農民の法律』から『市民の法律』への転換が行はれなければならなかつた。かの中世のゲルマン法といふのは、村落生活をなし、自然経済を営み、相互扶助の倫理思想の中に生きていた中世の農民の法律であり、再生したローマ法といふのは、都市生活をなし、交換経済を営み、個人主義的倫理思想の中に生棲してゐた都市民の法律であつたのである。ゲルマン法をして時勢の進歩に遅れさせまいための改良と増補とは、決して試みられなかつたわけではなかつたが、何分にもその立法の基礎的原則・根本的主義が、古い仲間主義・相互扶助主義であつたがために、遂にそれは、旧社会の法律体制として棄てられねばならなかつた。ローマ法の再生を妨害し迫害せんとした企ても、決して行はれなかつたわけではなかつたが、その基調たる個人主義、独立主義が新社会の生活原理たるに適合したため、遂にそれは登場せざるをえなかつた。社会はその基礎的経済構造を更新する際には、その法律体制をも、根底的に更新してしまふのである。さうしてさういふ際には旧法律思想の打倒者・新法律思想の助産婦としての学者の活動が絢爛多彩に、展開されるのを見るのである。本稿で伝した註釈学者の一団も、当時生れ出でつつあつた新社会のために、旧法制の破壊・新法制の建設に従事した・時代の選手たちに外ならなかつた。