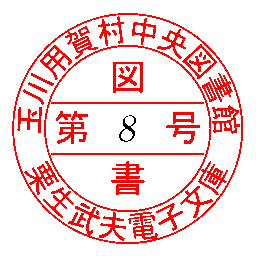
私塾時代
法学教育が独立の一科として専門的に授けられるに至つたのは、共和末の事である(一)。勿論其れ以前にも法律に関する教育が全然無かつた訳ではなかつた。十二表法の法文の如きは、ローマ最古の文章として、将た又国家の基礎的立法として、児童に之を暗誦させる風が、早くからあつたのである(二)。併し共和前期の法学教育は、修辞学や雄弁術やギリシヤ語と共に普通教育の一項目を為せしに過ぎず、未だ何人も之を専門的に学修するに至らなかつたが平民にして初めて神宮長(pontifex maximus)の職に就いたTiberius Coruncaniusが、紀元前二五四年頃、一般市民の需めに応じ、無報酬で法律事件の鑑定を為したのが動機となつて、法学教育に一転回が致された(三)。それはCoruncaniusが訴訟人の依頼に応じ法律上の意見を開陳する際、傍らに学生を立たして師の答ふる所を聴かしめ、更らに学生の質問にも答へ、或は之と議論を上下し、直ちに実際問題に当つて学生の知見を啓くといふ新教育を開始した結果である(四)。須臾にして此方法が全国に弘まつた。紀元前一世紀の初めには全国各地に、事件鑑定の傍ら教授にも従事するといふ私塾の開かれてあるのを見た。何人と雖も学力さへあれば学生を集めて法律を教へるに妨げなかつた。別に政府の許可等を要しなかつた(五)。教授の方法も次第に進歩し、初めは学生に傍聴と質問との機会を与へるだけであつたが、後には法律全般の綱領を説く法学通論(instituere)と、市民法及び大官法の詳細を論じる各論的講義(instruere)とが授けられた。併し共和時代の教授法は、いづれかと云へば傍聴(audire)に重きを置き、講義はほんのツケタリであつた。殊に各論的講義の如きは僅かに萌芽を示したに過ぎなかつた。それ故学生のことを、傍聴者といふ意味でauditoresと云つた(六)。
註一 Sherman, Roman law in the modern world vol I., p. 135.
註二 Cicero (106--43 v. Chr.)に従へば氏の幼少の頃は、十二表法の法文を児童に暗誦させる風があつたが、其成人の頃には此風もすつかり廃れてゐたといふ。de lege. 2, 23, 59 : discebamus enim pueri XII ut caemen necessarium, quae hodie nemo discit.
註三 Krüger, Geschichte d. Quellen u. Literatur d. römischen Rechts 2. Aufl. S. 55.
註四 Cic. or. 41, 142 : cur igitur jus civile docere semper pulchrum fuit hominumque clarissimorum discipulis floruerunt domus……42, 143 : alteros enim respondentes audire sat erat, ut ii qui docerent nullum sibi ad eam rem tempus ipsi seponerent, sed eodem tempore et discentibus satisfacerent et consulentibus. Top. 14, 56 : vestras in respondendo disputationes.
註五 Sherman, vol. I., p. 135.
註六 Krüger, S. 56.
私立学校時代
ローマの学校はギリシヤの哲学学校の模倣である(七)。ギリシヤの文化がローマを感化したことは非常なものであつたが、学校の設立もギリシヤ的影響の一つであつた。紀元前一世紀の末には家庭教育や私塾制度が廃たれて、児童は大抵、学校といふ組織的教育団体へ入れられた。法学教育の方面に於て初めて学校制度を採用したのはMasurius Sabinusであつたらしい(八)。彼は其師Capitoの法学研究所を公開して多くの学生を収容し、サビニアン派の最初の教頭(succedit)と仰がれた。Pomponiusの伝へる所に依れば、M. Sabinusは学生から授業料を徴して自らを支へたといふ(九)。サビニアン派の学敵たるプロキユリアン派も間もなく学校制度を採用して規則的な法学教育を施すに至つた。此二大学派は謂はば、ローマの二個の法科大学で、恰も現今のアメリカに於てエール・ハーバートの両大学が張り合つてゐるやうに、両々対峙して互に下らなかつたのである(一〇)。両派の外にも大小幾個の法律学校があつた。裁判所の建物の周囲にはきつと一つや二つの学校を見た。何人と雖も学校を立て学生を集めるの自由があつた。此状態は皇帝Diocletianus (284--305 n. Chr.)の時代まで続いた。
私立学校時代の教授法は傍聴よりも講義を主にした。其結果ローマ法の大要を説いた教科書の類が、Hadrianus (117--138)からAlexander Servus (222--235)に至るまでの間に、無数に出た。何時頃から斯る教科書主義が始まつたか明かに知ることを得ないが、多分Q. Mucius Scaevola (Kons. 95 v. Chr.)の頃からであらう。蓋しQ. Muciusはローマの法律学者中特に法理的概念構成の才に秀で、多くの法律上の概念、例へば遺言・後見・契約等の意義を明確に定め、其種類を分ち、ローマの法律学を初めて科学的に組立てた人である。模範時代(一一)(die klassische Zeit)の法律学者の論著は、大抵Q. Muciusの書を基礎にしたものであつた。
註七 Sherman, vol. I., p. 67.
註八 Sherman, vol. I., p. 136.
註九 Pomp. Dig. 1, 2, 2, 50 : ``huic nec amplae facultates fuerunt, sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est. ''
註一〇 Walton, Historical Introduction to Roman Law, p. 138.
註一一 模範時代若くは法学隆盛時代とは、Hadrianusの時代よりAlexander Servusの時代まで、即ち紀元九八年から二四四年までをいふ。Cuq, Institutiones juridiques des romains, II, p. 1.
官立学校時代
官立学校の起源は明かでないが、多分それは俄かに新設されたものではなくて、既存の私立学校に特別の保護を与へて漸次に成立を見たのであらう。Shermanに従へば、皇帝DiocletianusがRom及びBerytの法律学校を国家的に承認し、之に特別の保護を与へたのが動機となつて官立学校の成立を見るに至つたといふ(一二)。五世紀の初めには、Rom及びBerytの法律学校の外に、Athen, Cäsarea, Alexandria, Konstantinopelの法律学校も国家の管理に移されてゐた。此中Konstantinopelの法律学校が国家から財政上の援助を受けるに至つたのは四二五年であつた。斯く多数の官立学校が設立されるに伴れて私立学校は屏息の形となり、次第に其数を減じたが、当時は未だ私立学校の経営が禁じられてゐた訳ではなく、官立と私立と併存してゐたのである(一三)。
私立学校の経営が断然禁止されるに至つたのは四二五年である。其際の勅法に(一四)——
『皇帝テオドシアーヌス及びバレンチニアーヌスは、爾警視総監(praefecti urbi)に示す。 朕は、教授の称号を僣用して諸方より生徒を集め、之を公の学校若くは講堂内に収容し来りし者が、斯る所為を中止せんことを命ず。若し此法律の施行以後に於て、朕の禁じ且つ罰する所を企図する者あらんか、朕はこれを破廉恥の罪に問ひ、且つ違法の行為の行はれたる都市より其者を追放すべし。尤も生徒の私宅に到りて之を教授する者は刑罰の脅威の下に其業を禁ぜらるることなきも、彼等は私宅以外の場所に於て教授せざるやう慎むべし。又、カピトル殿内の講堂に於て教授すべく任命せられし者(官立学校教官)は、私宅教授を為すべからず。若し此禁に背き私宅教授を為すに於ては、カピトルの教官に任ぜられたるの故を以て賦与せられし総ての特権は、直ちに褫奪せられべきものとす。 朕は朕の学堂に、三名の雄弁術師と十名の文法家とを附置してラテンの語学及び文学を講ぜしめ、五名の詭弁家と十名の文法家とを附置してギリシヤの語学及び文学を講ぜしむべし。然れども朕は功名心ある青年に斯る技術のみを授くるの不可なるを思ひ、別に哲学の薀奥を究むる教官一名と法律及び正義の手続を論述する教官二名とを任命し(一五)、深遠なる学術の講究に当らしめんと欲す。爾警視総監は、各教授に其れ々々、各別の教室を給し、以て教授及び学生の声音をして外に洩れしむることなく、又外より響き来る他の教授及び学生の声音の為めに講義及び聴講の妨げらるることなく、静粛裡に教授し得るやう配慮すべし。此勅法に依り、国家の任命なき法学教師の、公の場所に於ける法学教授が禁止されるに至つたと同時に、官立学校教官(professores, antecessores)の私宅教授も厳禁されることになつたのである。
テオドシアーヌスの統治第十一年、バレンチニアーヌスの 統治第一年、二月二六日、コンスタンチノープルにおいて 賜ふ』
転じて官立学校に於ける法学教授の方法を見るに、最初は各教官が其適当と認むる方法に於て任意の教育を施してゐたが、後に教科目の確定を見、一定の年限内に一定の教科書を講義することを要するに至つた。今、ユスチーニアーヌス大帝がKonstantinopel及びBerytの教官達に宛てて発した、五三三年一二月一六日の勅法(Const. Omnem.)を基礎にして、帝以前の法学教育を想像するに、修業年限は四年にして、初学年生に対してはGaiusの法学提要四巻の講読と、嫁資(res uxoria)・後見・遺言・遺産に関する四巻の講読とが課せられ、第二学年生の為めにはPraetorの告示を講義し、特にUlpianusの告示註釈書の最初の部分(prima pars legum)を用ゐた。第三学年生に対してはUlpianusの告示註釈書の残余の部分とPapinianusの回答録とを課し、第四学年生にはPaulusの回答録を宛がつて各自に独学させたらしい。
更らに官立学校教官の任命方法を見るに、Konstantinopel及びBerytの法律学校教官は元老院に於て之を任命したが、Athen, Alexandria, Cäsareaの法律学校教官は地方庁に於て決定し、皇帝の裁可を仰いだ(一六)。二十年間在職の教官は元老院の議決を経て枢密顧問に任ぜられた(一七)。
註一二 Sherman, vol. I., p. 137. 註一三 Krüger, S. 392 f. 註一四 Cod. Theod. 14, 9, 3. 註一五 此勅法(Cod. Theod. 14, 9, 3)には、二名の教官が同時に新任されたやうに書いてあるが、実は其際任命されたのは単に一名で、他の一名——それは法学者Leontinusであつたが——は、此勅法の発布以前から既にコンスタンチノープル法律学校教官の職に在つたのである。Cod. Theod. 6, 21, 1; Cod. Justin. 12, 15, 1; Cod. Theod. 15, 1, 53; Cod. Theod. 14, 9, 1. 註一六 Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs I 100 f. 註一七 春木博士、ローマ法講義
ユ帝の改革
ユスチーニアーヌス大帝はローマの学制に頗る根本的な改革を加へた。即ち帝は、
(一)五二九年に先づAthenの法律学校を廃止し、次いで五五三年にCäsarea及びAlexandriaの両法律学校を廃止し(一八)、官立の法律学校をRom, Beryt, Konstantinopelの三校に限つて了つた——此中声名の最も高かりしはBerytの法律学校である。此学校は遠く三世紀の創立に係り、嘗てはUlpianusが教鞭を執つてゐたといふ尊い伝統さへあつて、代々学者を出し、ユスチーニアーヌスの時代には、Dorotheus, Anatolius, Cyrillus, Demosthenes, Domnuis, Eudoxius, Patricius, Stephanusの如き大家が教授の職に在つた。それ故時の人は此学校を法律の母(legum nutricem)と呼んでゐた(一九)。Konstantinopelの法律学校も帝都の官立学校として頗る完備し、ユ帝の時代にはTheophilus, Isidorus, Thalelaeusの如き代表的学者がゐた。之に反しRomの法律学校は西ローマ帝国全盛の砌こそ花々しかつたが、帝国滅亡の後はただ東ゴート諸王の厚き保護の下に辛じて存立を維持してゐたといふだけで、ユ帝が之を保護するやうになつてからも、格別学者を出さなかつた(二〇)。
(二)ユ帝は又官立法律学校の修業年限を五ヶ年に延長し(二一)、(イ)初学年生に対してはInstitutionに基いて先づ民法・刑法及び訴訟法の大綱を講義し、更らにDigestaの一巻乃至四巻に基いて法の概念・分類・歴史等の根本問題と、訴訟手続の一部分とを講義し、進んでDigestaの二十六巻・二十八巻及び三十巻に基いて後見・遺言・遺産等に関する制度の一班を説明した。(ロ)第二学年生に対してはDigestaの五巻乃至十一巻に拠つて所有権・役権・隣地権等の概念と、是等の権利の侵害に因つて発生する物の回復請求権及び損害賠償請求権を講義し、傍ら墓地及び埋葬に関する規定の説明をも加へた。(ハ)第三学年生に対してはDigestaの十二巻乃至十九巻に拠つて売買・交換・委任・寄託・賃貸借・消費貸借・非債弁済・質権及び海商法の大要を講義し、更らにDigestaの二十巻乃至二十二巻に準拠して保証・利子・遅滞・契約の解除等を説明したが、教授の裁量に依つてDigestaの十巻乃至十九巻の説明を第二学年に繰り下げ、五巻乃至十一巻の説明を第三学年に於て試みる場合もあつた。即ち物権篇と債権篇とを転換して講義することが能きたのである。又、(ニ)第四学年生に対しては婚姻・離婚・嫁資・扶養等を題にしたDigestaの二十三巻乃至二十五巻を宛がつて各自に独習させ、更らに後見人・保佐人・遺贈・信託等を題にしたDigestaの二十六巻乃至三十六巻を独習させたが、学生の独習を如何にして監督したかは不明である。但し全課程修業の後に試験があり、一定の成績を以て試験を通過した者でなければ司法官に採用されることを得なかつた。(ホ)第五学年生に対してはDigestaの三十七巻及び三十八巻とユ帝の新令第百十八号及び第百二十七号とを基礎にして無遺言相続の順位を研究させ、更らにDigestaの三十九巻乃至四十九巻を基礎にして刑法及び刑事訴訟法を研究させ、又Digestaの第五十巻に拠つて法律上の用語例と法律格言とを学ばしめたのみならず、進んでCodexを基礎にして刑法・民法・教会法等に関する雑多の勅法を独習させた——要するにユ帝の法学教育は、帝の大法典の内容を修得させることが眼目であつたから、其結果、従来使用され来つたGaiusの法学提要・Ulpianusの告示註釈書・Paulusの回答録の類は、教科目から斥けられた。ユ帝自身も、其法学志望の学生に与へた勅諭(二二)の中に、例の衒気に満ちた語調を以て、
『朕は汝等をして法学の初歩を古伝説的資料より収拾せず、直ちに帝者の光明中より領得し、汝等の耳と心とをして無用杜撰の印象を受けず、専ら実用適合の事物を暁覚せしめんことを期し、而して往時に在りては四年の苦学の後尚殆んど勅法をも読むこと能はざりしに反し、最初より其研究に着手し、殊に始めより終りに至るまで汝の皇帝の口より直ちに之を聞くの好運と名誉とに遭遇せしめんと欲す。』(末松博士訳、ユ帝欽定羅馬法学提要、三版四九頁)と云つてゐる。
(三)ユ帝は又校内の規律を厳重にし、教授及び同学の学生に対して不礼を為すものを罰した。即ちConst. Omnem. §9に於て
『朕は光栄ある朕の首都に於て勉学し、若くは麗はしきBerytの町に於て研究に従事する者が、奴隷にのみ相応し且つ往々人を害するに至るべき、かの野卑低劣なる悪戯を為すことを禁じ、更らに教授及び同学の友、殊に初めて法学の研究に入れる学生に対して不礼の行為あることを禁ず。蓋し悪結果を生む行為は、単なる戯言と見ることを得ざるが故に、朕は断じて此種の行為を許さず、朕の御代と将来とに亘つて厳重に之を処罰せんと欲す。夫れ人は先づ其精神を練り、次に其舌を練るべきなり。』と宣言した。——教授会は校内の風紀を取締る権能を与へられてあつた(二三)。
(四)ユ帝は又各学年に於ける学生の呼称を法律で一定した(二四)。従来一学年生は嘲弄的にDupondii (two-penniesの意(二五))と呼ばれてゐたのを改め、帝自身の名に因んでJustiniani novi (Justinian's freshmenの意)と呼ばしめた。二学年生は従来『告示講習生』の意義でEdictalesと呼ばれてゐたのを其侭襲用し、三年生も亦従前通りPapinianisteと名づけられた。『Papinianusの告示録を学ぶ者』の義である。又旧くから第三学年の学年開始の際Papinianusの霊を祀る風があつたが、ユ帝は此美風の保存を命じた(二六)。四年生は『聴講を免じられたる者』の意に於てλύτανと呼ばれ、五年生は『聴講を免じられたる上級生』の意に於てΠρολύτανと呼ばれた。蓋し四年五年は聴講よりも独習を主にしたからである。——学生の平均年齢は二十歳乃至二十五歳であつた。Romの法律学校に於ては、二十歳以上の外国人学生に対して入学を拒絶した(二七)。
註一八 Const. Omnem §7. 註一九 Libanius Espist. 566; Const. Omnem §7. 註二〇 西ローマ帝国を滅ぼしたオドワケルは、ローマ帝国の遺制を全部其侭存置した為め、ローマ法律学校も其存立に影響を受けなかつた。オドワケルを滅ぼした東ゴートの王テオドリツクも、ローマ法律学校の存続を認めた。テオドリツクの子アラリツクは、ローマ法律学校の教授達を厚く保護した形跡がある(Cassiodor, Vor. 9, 21; Amos, Roman Law, p. 103)。然るに擁護者たる東ゴート王国がユスチーニアーヌス大帝に攻められて遂に滅亡した為め、ローマ法律学校も一時危殆に瀕したのを、ユ帝が多大の費用を支出して之を再興し、道統の絶えんとするのを繋いだのである。拙稿、中世イタリヤの法源(同志社論叢七・五八頁以下)参看。
註二一 Const. Omnem §§2 et seq. 註二二 Inst. Prooemium §3. 註二三 Sherman, vol. I., p. 145. 註二四 Const. Omnem §§2 et seq. 註二五 Roby, Introduction to the Digest, p. xxvii, note 1. Vgl. H. Pernice, Miscellanet 1 107 f.; Rudolf in der Zeitschrift für Rechtsgeschite III 38. 註二六 Papinianusは、其秋霜烈日の性格と謹厳なる文章と精鋭なる論理とに於てローマの法学者中一頭地を出し、恰も法律的良心そのものの権化たるが観があつたから、ユ帝は氏を尊崇すること深く、第三学年の始めに於て学生をして氏の霊を祀らしめたのである。
註二七 Cod. Theod. 14, 9, 1; Cod. Justin. 10, 50, 1; Cassiodorus, Var i, 39; iv, 6; ii, 22.
其後の法律学校
Athen, Cäsarea, Alexandria(二八)の三法律学校がユ帝時代に廃校になつたことは既に述べたが、廃止を免れた他の三校、即ちRom, Beryt, Konstantinopelの法律学校は、其後どんな運命を辿つたかといふに、(一)Romの法律学校は五六八年にロンバルド人が大挙して伊太利に侵入し来つた為め、Ravennaに避難し、Ravenna法律学校と改称して十世紀まで存続した。但し研究は甚だ振はず、僅かにユ帝法典中の最易の部分たるInstitution及びNovellenを講義するのみで、Digestaの研究には触れなかつたが、それでも中世に於けるローマ法学の命脈は此学校に依つて繋がれ、Bologna大学の勃興もRavenna法律学校に負ふ所が甚だ多かつたのである(二九)。(二)次にKonstantinopelの法律学校はどう成つたかといふに、此学校はユ帝の死後凡そ百五十年間其隆盛を誇つてゐたが、七一七年、帝国がサラセン人の攻撃を受けて危急存亡の境に陥つた際に廃止された。併し其後更らに百五十年を経過した八六六年に、再興を見、東ローマ帝国に於ける法律学の淵叢として帝国滅亡の際まで続いたのである。(三)最後にBeryt法律学校はといふに、これは五五四年に同地方を襲つた強地震の際に祝融の災に罹り、一時Tyrusに移転したが、後Berytに復し、同地方がサラセン人の領有に帰してからも依然としてローマ法を講じつつ九世紀の中葉まで存続した。現今のBeryt法律学校は、一九一三年一一月一三日の創設に係り、主として仏国人の後援に成つたものであるが、古へのBeryt法律学校の道統を継いだものだと自称してゐる(三〇)。而して此学校も、今次の大戦乱の影響を受けて維持が困難に成つたと聞いたが、其後どう成つたか、わたしも知らない。
註二八 Alexandriaの法律学校は、ユ帝から廃止の命令を受けても、九世紀頃まで事実上存続したらしい。Sherman, vol. I., p. 139. 註二九 Savigny, Geschichte d. röm. Rechts im Mittelalter 1. §138; 拙稿、羅馬法分布史に於ける東羅馬帝国の地位(本誌六ノ二・三五頁以下)参看。
註三〇 37 Revue générale du droit, p. 575.
\enlargethispage{\baselineskip}