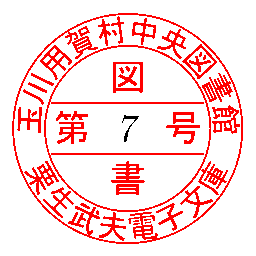
一 私塾時代
法学教育が独立の一科として専門的に授けられるに至つたのは、共和末のことである(一)。もちろんそれ以前にも法律に関する教育が全然無かつたわけではなく、十二表法の法文のごときはローマ最古の文章として、はた又国家の基礎的立法として、児童にこれを暗誦させるふうが、早くからあつたといふ(二)。しかし共和前期の法学教育は、修辞学や雄弁学やギリシヤ語と共に普通教育の一項目を為せしに過ぎず、未だ何人もこれを専門的に学修するには至らなかつたが、平民にして初めて神宮長(pontifex maximus)の職に就いたTiberius Coruncaniusが紀元前二五四年頃、一般市民の需めに応じて、無報酬で法律事件の鑑定を為したのが動機となつて、法学教育に一転回が致された(三)。それはCoruncaniusが訴訟人の依頼に応じて法律意見を開陳する際、傍らに学生を立たして師の答ふる所を聴かしめ、さらに学生の質問にも応じて学生の知見を啓くといふ新教育を開始した結果である。須臾にしてこの方法が全国に弘まつた。紀元前一世紀の初めには全国各地に、事件鑑定の傍ら教授にも従事するといふ私塾の開かれてあるのをみた。何人といへども学力さへあれば、学生をあつめて法律を教へるのに妨げなかつた。別に政府の許可などは要しなかつた。教授の方法も次第に進歩し、初めは学生に傍聴と質問との機会をあたへるだけであつたが、後には法律全般の綱領を説く法学通論(instituere)と、市民法及び名誉官法の詳細を論ずる各論的講義(instruere)とが授けられた。しかし共和時代の教授法はいづれかといへば傍聴(audire)に重きをおき、講義はほんの附けたりであつた。それゆゑ学生のことを傍聴者といふ意味でauditoresといつた(四)。
一 Sherman, Roman law in the modern world I. 1924 p. 135.
二 Cicero (106--43 v. Chr.)の幼少の頃は、未だ児童に十二表法の法文を暗誦させるふうが残つてゐたが、成人の頃には、もう廃れてゐたといふ。
三 P. Krüger, Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts 2. Aufl. S. 55; B. Kübler, Geschichte des römischen Rechts 1925 S. 130. 136 ff.
四 P. Krüger, a. a. O. S. 56.
二 私立学校時代
ローマの学校はギリシヤの哲学学校の模倣である。ギリシヤの文化がローマを感化したことは非常なものであつたが、学校の設立もギリシヤ的影響の一つなのであつた。紀元前一世紀の末には、家庭教育や私塾制が廃れて、児童は大抵、学校といふ組織的教育団体へ入れられた。法学教育の方面において初めて学校制を採用したのはMasurius Sabinusであつたらしい。彼はその師Capitoの法学研究所を公開して多くの学生を収容し、サビニアン派の最初の教頭と仰がれた。Pomponiusの伝へる所によれば、M. Sabinusは学生から授業料を徴して自らを支へたといふ(一)。サビニアン派の学敵たるプロキュリアン派も間もなく学校制を採用して規則的な法学教育を施すに至つた。この二大学校はローマの二個の法科大学で、恰も現今のアメリカにおいてエール・ハーバートの両大学が張り合つてゐるやうに、両々対峙して互に下らなかつたのである。両派の外にも大小幾個の法律学校があつた。裁判所の建物の周囲には、きつと一つや二つの学校を見た。何人といへども学校を建て学生を集めるの自由があつた。この状態は皇帝Diocletianus (284--305 n. Chr.)の時代まで続いた。
私立学校時代の教授法は傍聴よりも講義を主にしたので、その結果ローマ法の大要を説いた教科書の類が皇帝Hadrianus (117--138)から皇帝Alexander Severus (222--235)に至るまでの間に無数に出た。いつ頃からかかる教科書主義が始まつたかは明かでないが、多分Quintus Mucius Scaevola (Konsul in J. 95 v. Chr.)の頃からであつたであらう。けだし彼はローマの法律学者中特に法理的概念構成の才に秀で、多くの法律上の概念、例へば遺言・後見・契約等の意義を明確に定め、その種類を分ち、いはばローマの法律学に最初の組織を与へた人だつたからである。クラシック期(klassische Zeit)の法律学者の著述は(二)、Q. Muciusの書を出発点としてこれから発展して行つたものであつた。
一 Pomp. Dig. 1, 2, de origine juris et omnium etc. 2, 48.
二 クラシック期若くは法学隆盛時代とは、Celsusに始まつてModestinusに終るローマ法学の黄金時代即ち紀元九八年から二四四年までの間をいふ(Sherman, Roman law in the modern world I. p. 52)。
三 官立学校時代
官立学校の起原は明かでないが、多分それは俄かに新設されたものではなくて、既存の私立学校に特別の保護を加へて漸次にその官立化とはなつたのであらう。Shermanに従へば、皇帝DiocletianusがRom及びBerytosの法律学校を国家的に承認し、これに特別の保護を与へたのが動機となつて、官立学校の成立を見るに至つたといふことである。五世紀の初めには、Rom及びBerytosの法律学校の外に、Athen, Antiochia, Cäsarea in Palästina, Alexandria, Konstantinopelの法律学校も国家の管理に移されてゐた(一)。このうちKonstantinopelの法律学校が国家から財政上の援助を受けるに至つたのは四二五年のことであつた(二)。かく多数の官立学校が設立されるにつれて私立学校は屏息の形となり、次第にその数を減じたが、当時は未だ私立学校の経営が禁じられてゐたといふわけではなく、官立と私立と併存してゐたのであつた。
私立学校の経営が断然禁止されたのは四二五年のことである。その際の勅法に(三)——
『皇帝テオドシゥス及びバレンチニアーヌスは、爾・都長テオフィルスに示す。
朕は、教授の称号を僣用して諸方より生徒を集め、これを公の学校若くは講堂内に収容し来りし者が、かかる売名行為を中止せんことを命ず。もしこの勅法の施行以後において、朕の禁じ且つ罰する所を企図する者あらんか、朕はこれを破廉恥の罪に問ひ、且つ違法の行為の行はれたる都市よりその者を追放すべし。尤も私宅において指導を与ふるに過ぎざる者は、刑罰の脅威の下にその業を禁ぜらるることなしといへども、彼等は私宅以外の場所において教授せざるやう慎むべし。又、公の学堂において教授すべく任命せられし者は、私宅教授を為すべからず。若しこの禁に背き私宅教授を為すにおいては公の教官たるの故を以て賦与せられしすべての特権は、直に褫奪せられべきものとす。
朕は朕の学堂に、三名の修辞学教師と十名の文学教師とを附置してラテンの文学を講ぜしめ、又五名の修辞学教師と十名の文学教師とを附置してギリシヤの文学を講ぜしむべし。然れども朕は功名心ある青年にかかる芸術のみを授くるの不可なるを思ひ、別に哲学の蘊奥を究むる教官一名と正義及び法律の意味を解明する教官二名とを任命し、深遠なる学問の講究に当らしめんと欲す。爾・都長は、各教授にそれぞれ、各別の教室を与へ、以て教授及び学生の声音をして外に洩れしむることなく、又外より響き来る他の教授及び学生の声音の為めに講義及び聴講の妨げらるることなく、静粛裡に教授し得るやう配慮すべし。
テオドシゥスの統治第十一年、バレンチニアーヌスの統治第一年、四二五年二月二七日、コンスタンチノープルにおいて賜ふ』この勅法により、国家の任命なき法学教師の公の場所における法学教授が禁止されるに至つたと同時に、官立学校教官(professor, antecessor)の私的教授も亦厳禁されることになつた。
然らば官立学校の教課程はどうであつたかと見ると、最初は各教授がその適当と認める方法において任意の教育をなしうることになつてゐたが、後には教科目の確定を見、一定の年限内に一定の教科書を講義すべきこととなつた。尤もユ帝以前における教課程の詳細は実は明かではない。といふわけはユ帝以前の状態は、これを改革したユ帝の五三三年一二月一六日の勅法(Const. Omnem)から推測するの外ないのであるが、同勅法は、改革法の常として、改革の内容についてのみ明白であり、改革以前の状態については、間接的な報告しか洩らしてをらぬからである(四)。即ち同勅法によると、ユ帝の改革以前には、一年生のためにはGajusの『法学提要』と、『嫁資・後見・遺言・遺贈に関する四巻の単行書』(libri singulares)と、計六巻を講義したとあるが、Gajusの提要は四巻から成るので、これに四巻の単行書が加はると、計八巻となるわけであり、従つて計数においてすでに二巻の喰ひ違ひを示してゐるのである(五)。それに『嫁資・後見・遺言・遺贈に関する四巻の単行書』とは何人の著なのか?Gajusの著なのか?Ulpianusの著なのか?その点も明かでない(六)。又、第二年生のためにはprima pars legumと、de judiciis及びde rebusの一部分とを講義したとあるが、これも何人の書の一部分だつたのか?Ulpianusの『告示註釈書』の一部分だつたのか或は教授目的のために編纂された或読本(Chrestomathie)でもあつて、その本の一部分だつたのか?その辺のことも明かでない(七)。第三年生のためにはde judiciis, de rebusの残余の部分と、Papinianusの『回答録』の八巻とを講義したとあるが、これまたde judiciis, de rebusを含む本の何たるかが明かでない以上、不明である。第四年生に対してはPaulusの『回答録』を宛がつて温習且つ細目の研究を行はしめたとあり、これだけが明かである。
要するにユ帝以前の学修課程(Studiengang)としては、年限が四年だつたこと、うち三年が講義に宛てられ、あと一年が自修に宛てられたこと、講義にはGajusの『法学提要』とPapinianusの『回答録』が用ゐられたこと、自修にはPaulusの『回答録』が宛がはれたことが確実なだけで、爾余の点は不明なのである。
一 帝国の西部では、Rom市の外にKarthago市にも法律学校があり、ガリヤ地方にも法律学校があつたらしい(H. Fitting, Über die Heimat und das Alter des sogenannten Brachylogus 1880 S. 23; B. Kübler, Geschichte des römischen Rechts 1925 S. 427.)。
二 Konstantinopelの法律学校は四二五年Theodosius II.によつて建てられたらしい(C. Theod. 14, 9, 3=C. Just. 11, 19, 1 vom 27. Febr. 425.)。
三 C. Theod. 14, 9, 3=C. Just. 11, 19, 1.
四 Const. Omnemの日本訳は、春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂 ΠΡΩΤΑ《プロータ》』二二頁以下において見られる。
五 Gajus四巻・単行書四巻・計八巻を講義したとなると、勅法のいふ『六巻』よりも、二巻多くなるので、一派の学者はGajus四巻の中から、任意の巻を二巻だけ選講したのであらうと見る(A. F. Rudorff, Römische Rechtsgeschichte I. 1857 S. 311; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte I. 1885 S. 980; M. Voigt, Römische Rechtsgeschichte III. 1902 S. 136 n. 16. 19.)。
六 B. Kübler, a. a. O. S. 430.
七 B. Kübler, a. a. O. S. 430 f.
四 ユ帝の改革
ユ帝はローマの学制に根本的な改革を加へた(一)。即ち——
(一)帝はKonstantinopel及びBerytosの二学校だけを除いて、他の法律学校の全部を閉鎖してしまつた。よつてこの二校だけについて説明を加へると、Berytosの学校は遠く三世紀の創立にかかり、嘗てはUlpianusが教鞭をとつてゐたといふ尊い伝統などもあつて、代々学者を出し、ユ帝の時代にも、Dorotheus, Anatolius, Cyrillus, Demosthenes, Domnus, Eudoxius, Patricius, Stephanus等の大家が教職にあつたのであつた。時の人はこの学校のことを法律の母(legum nutricem)とよんでゐた(二)。
又Konstantinopelの法律学校も帝都の官立学校として完備し、ユ帝の時代にはTheophilus, Isidorus, Thalelaeus等の錚々たる学者がゐた。
ではRom法律学校はといふと、四七六年に西ローマ帝国を滅ぼしたゲルマン傭兵の将Odoakerが、ローマ帝国の遺制をそのまま存置したため、ローマ法律学校もそのまま存続することができたのであつた。四八九年にOdoakerを滅ぼしてその跡を継いだ東ゴート王Theoderichも、ローマ法律学校の存続を認めた。Theoderichの子Athalaricのごときは、ローマ法律学校の教授達を厚く保護した形跡があるといふことである。またユ帝も五五三年東ゴートからイタリーを奪還するや、東ゴート王が為したと同様に、ローマ法律学校を厚く保護し、さうして帝がこれより先き東方の法律学校のために作つた学修規則をそつくりそのままローマ法律学校にも適用したのであつた。ゆゑにユ帝治下の法律学校としては、東にKonstantinopel及びBerytosの二学校あり、西にRomの学校があつたわけであつたが、Rom法律学校からはあまり有名な学者を出すに至らなかつた。
(二)ユ帝はまた官立法律学校(Konstantinopel, Berytos u. Rom)の修業年限を五年に延長した。さうして(一)第一学年生のためにはユ帝のInstitutionに基いてまず法律全分野の概説を試み、さらにDigestaの一巻乃至四巻に基いて、法の概念・法の分類・法の起原・人・法人・物・契約・事務管理・詐欺強迫・未成年等の問題を説き、訴訟制度の大綱をも説いた(三)。(二)第二年生のためには、Digestaの五巻乃至十一巻(pars de judiciis)に基いて、所有権の訴・相続回復の訴・取得時効・人役権・地役権・用益権・物又は流出物による損害・経界の訴・分割の訴等、主として物権法を詳細に講述し、なほ学年の残部において、Digestaの二十三巻・二十六巻・二十八巻・三十巻に基いて、嫁資・後見・保佐・遺言・遺贈に関する法制の一端を講述した(四)。(三)第三年生のためには、Digestaの十二巻乃至十九巻に基いて、消費貸借・非債弁済・海商法・委任・寄託・組合・貸借・売買・交換等、主として債権法を講述したが、しかし教授の裁量を以て、二年の講義即ち物権法の講義と、三年の講義即ち債権法の講義とを転換させることもできた。しかしこの二部門(五巻乃至十一巻及び十二巻乃至十九巻)は、ユ帝の言葉に従ふと、『その結構未曾有の善美を尽くし、不用若くは廃用の規定は一もその中に存せざる』を以て、学生たる者は、全巻を悉く学修し、『何れの部といへどもこれを遺脱すべからざるもの』なのであつた。なほ第三年生は、学年の残部において、Digestaの二十巻乃至二十二巻を基礎とする質権・抵当権・利息・遅滞・契約解除・追奪担保等の諸問題に関する講義をも聴かねばならなかつた(五)。(四)第四年以後の者に対しては、講義を廃して自修を命じ、殊に四年生に対しては、講義から洩れたるDigestaの部分、即ち二十四巻・二十五巻・二十七巻・二十九巻及び三十一巻乃至三十六巻の十巻に基いて、婚姻・離婚・扶養・後見・保佐・遺言・遺贈及び相続等の諸関係を自修せしめた(Digestaの三十七巻から五十巻に至る十四巻は、学生の卒業後の研究に委ねられてゐた)。ユ帝にいはせると、以上三十六巻の聴講及び自修によりて、学生は初めて、『法律上の一切の事務に従事するの素養と現代の時勢に適応するの能力とを得べき』(六)ものなのであつた。(五)五年生に対しては、Codexを基礎にして刑法・公法・行政法・教会法等に関する雑多の勅法を自修することが命じられた(七)。
(三)ユ帝は各学年における学生の呼称を法律で一定した。従来は一年生に対しては嘲弄的な意味において``Dupondii'' (``Two-pennies''の意)といつてゐたのを、ユ帝は帝自身の名に因んでJustiniani Novi (``Justinians freshmen''の意)とよぶことにし、第二年生は従前通り``Edictales''とよび、第三年生も従前通り``Papinianiste''とよぶことにした。この二つの名は、その学年における主たる学科目即ち二年では告示(Edictum)を学び、三年ではPapinianusの回答録を学んだことから来たのであつた。四年は従来通り``Lytae'' (``freed from lectures''の意)とよばれ、五年は新たに``Prolytae'' (``advanced Lytae''の意)とよばれた。学生の平均年齢は二十歳乃至二十五歳であつた(八)。
(四)ユ帝は学内の秩序を厳重に維持させるために、学生が酒宴(Kommers)を催したり、教授や同学生殊に新入学生を嘲弄したりすることを禁じた。即ち前記の勅法の中において——
『朕は光栄ある朕の首都において若くは壮麗なるベーリッスの市において法学の研究に従事する者が自己の品位を損じ、人の名誉を害するに至るべき・野卑低劣なる悪戯を敢てし、以て教授・同学の友・殊に新入の学生を傷くるに至ることを禁ず。けだし悪結果を生ずる行為は単なる諧謔とはみることをえざるがゆゑに、朕は断じてこれを仮借せず、朕の御代と将来とに亘つて厳重にこれを処罰せんと欲す。それ人はまづその精神を練り、然る後その学問を磨くべきなり』(九)と。然し昔から第三年生が、Papinianusの『回答録』の講義の始まる日に、Papinianus祭といふのを催して、この秋霜烈日の慨ある大法律家を、追慕し来つた慣例だけは存続させた。
一 五三三年一二月一六日の発令の、通常Const. Omnemの名でよばれてゐる勅法。日本訳は春木・前掲書二二頁以下。
二 Const. Omnem §7.
三 Const. Omnem §2.
四 Const. Omnem §3.
五 Const. Omnem §4.
六 Const. Omnem §5.
七 Const. Omnem §5.
八 Sherman, Roman law in the modern world I. p. 142.
九 Const. Omnem §9.
五 その後の法律学校
Athen, Cäsarea, Alexandriaの三法律学校がユ帝時代に廃校になつたことはすでに述べたが(一)、廃止を免れた他の三校、即ちRom, Berytos, Konstantinopelの法律学校は、その後どんな運命を辿つたかといふに、(一)Romの法律学校は五六八年にランゴバルド人が大挙してイタリーに侵入し来つたために、Ravennaへ避難し、Ravenna法律学校と改称して十世紀まで存続した。但し研究は甚だ振はず、僅かにユ帝法典中の最易の部分たるInstitution及びNovellenを講義するのみで、Digestaの研究には触れなかつたが、それでも中世におけるローマ法学の命脈はこの学校によつて繋がれ、Bologna大学の勃興もRavenna法律学校に負ふ所が甚だ多かつたのである。(二)次にKonstantinopelの法律学校はどうなつたかといふに、この学校はユ帝の死後凡そ百五十年間その隆盛を誇つてゐたが、七一七年、帝国がサラセン人の攻撃を受けて危急存亡の境に陥つた際に廃止された。しかしその後さらに百五十年を経過した八六六年に再興を見、東ローマ帝国における法律学の淵叢として帝国滅亡の際まで続いたのである。(三)最後にBerytos法律学校はといふに、これは五五四年に同地方を襲つた強地震のために破壊され、一時Tyrusに移転したが、のちまたBerytosに復し、同地方がサラセン人の領有に帰してからも、依然としてローマ法を講じつつ、九世紀の中葉まで存続したといふ。
一 Alexandriaの法律学校は、ユ帝から廃止の命令を受けても、事実上九世紀頃までは存続してゐたらしい。Sherman, Roman law in the modern world I. p. 130.