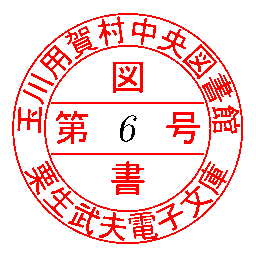
第一章 法史学とは何ぞや
第一節 法の本質
一 当為説
イ 法の本質に関しては当為説と実在説との対立が見られる。当為説は法は当為(Sollen)だといひ、実在説は法は社会意識だといふ。まづ当為説を批判してみることにすると、法は当為だといふ場合において、いはゆる法とは実定法のことでなければならない。即ち一定の時代・一定の社会に現実に行はれてをり又はゐた制定法及慣習法のことでなければならない。なぜかなら法の本質論が問題としてゐるところのものは実定法の本質であつて、自然法や理性法の本質ではないからである。で問題は転じてかう成る——実定法の本質は当為であるか、存在(Sein)であるかと。
ロ 当為とは価値実現のために人間が服従することを要すとされてゐる準則又は生活の仕方のことである。ゆゑに人間がもし当為に従つて生活したならば、必ずやそこに価値の実現が見らるべき筈であり、当為に従つて生活したにもかかはらずそこになほ価値の実現が見られなかつたといふならば、それは、初めからそれが当為でなかつたことを証拠立てるものだといはねばならない。では人々が制定法又は慣習法を遵奉し、その規定通りに生活した際、常にそこに法律価値の実現が見られるであらうか。
ハ もちろん法律価値の内容の点については見解の分裂がある。或人は法律は社会経済生活の安定を確保することを目的とするものにして、この目的に貢献する法律が善法、この目的に背馳する法律が悪法なりと説く。又或人は法律は社会文化の発展を促進することを目的とするものにして、この目的に合するや否やによつて法の善悪は分るとなす。さらに或人は法律は社会的生産力の維持及発展に役立つことを目的とするものにして、この目的が法の善悪を分つ標準点なりとなす。その他いろいろあり又ありうるが、いづれにせよ実定法即当為ならば、実定法の文字的遵奉と執行とによりて法律目的の達成・法律価値の実現が見られねばならぬ理窟となるが、事実果してさうであらうか。実定法の文字的頑守と文字的励行との結果、却つて社会生活の平和が破られ、社会文化の向上が妨げられ、社会的生産力の発達が阻害されるといふやうな事態もあるのではなからうか。
ニ ここにおいて何故に実定法の内容が法律価値と齟齬するに至るやの問題に逢着するが、制定法の場合について見ると、立法者が社会の発展のために真に貢献的なる法律を作らんと心を傾けつつあることは事実である。しかし一国立法の枢機には事実上いろいろの政治的勢力、例へば軍部・官僚・政党・資本家・ジヤーナリズム等々が参与する。而してこれらの立法参与者もまた社会に貢献的なる法律を作らんと努力しつつあることは事実ではあるが、いかんせん人間の判断はその人の社会的立場から拘束を受け、殊にその人の所属してゐる階級の利害から拘束を受けることを免れえない。いはゆる判断の存在拘束性(Seinsgebundenheit)なるものがこれである。ゆゑに主観的個人的には立法参与者の判断が真摯的であり、誠意的であるにもかかはらず、客観的社会的にこれを見るときは、それは彼等の階級の利益の反映であり表現でしかないといふ場合が往々にして生ずることを免れえぬのである。現に毎年議会期に入ると、法の制定によつて新たな利益にありつく望みのある人々の厚顔な立法運動・法の改廃によつてその現有利益を失ふ虞れある人々の利己的な反対運動・無智な輿論と横暴な勢力の跳梁、さういふものが群がり起きて前後左右から立法者の立法方向を牽制するのを見るではないか。
慣習法の場合はどうかといふと、慣習法は社会が無意識の間に分泌物でも分泌するやうにして形成してしまふのであるから、人為的歪曲を受ける虞はたしかに少いが、しかし永年の慣行をその成立の条件とする関係上、その内容は因襲と迷信との結晶に陥り易い。見方によると慣習法の中へは、制定法の中へ以上に、不合理な雑音が混入し易いのである。
かくして実定法は当為から離れ去ることとなる。当為と一致する場合、いひかへれば法律価値の実現に役立つ性質をもつ場合もあるにはあるが、然らざる場合も少くない。而してその然らざる場合においても実定法はなほ実定法たるを失はぬのである。いはゆる悪法も亦法なりとはこの謂である。ゆゑに法律は当為ではなくて存在である、価値界のものではなくて実在界のものだと断ぜざるをえぬのである。
二 社会意識説
イ 実在説は法律は社会意識の一種であるとする。しかし社会意識とは何であるか、わが国の学者中にはその概念を明晰に規定することなくして法は社会意識だとか、社会規範だとかいつてある人もないではない。われらはこの弊から逃れなければならない。
われらの見る所を以てすると、社会意識とは社会成員の全部又は多数が共通的に抱きもつてゐる意識内容のことである。けだし人はその人格の特異性に基いて特殊の感じ方・考へ方・欲し方をしてゐるが、他面、他人とほぼ共通の又は近似の思想・感情・趣味・意志・信念等も抱いてゐる。而して前者即ち個人的特殊的なる意識の内容を個人意識といふに対して、後者即ち社会的共通的なる意識の内容を社会意識とはいふのである。両者を対比して見ると、共に個人心内の現象である点においては変りがない。意識はすべて個人の頭脳をその生理的基礎として成立するものであつて、個人の頭脳を離れてはいかなる意識も成立しえぬのである。しかし社会意識はその内容において個人意識と異る。個人意識は個人の人格に固有的であるが、社会意識は他人のもつものと共通的であるからである。又二者はその存続において異る。個人意識は個人によつて担はるるの結果、個人の亡滅と共に亡滅せざるをえぬが、社会意識は社会の全員又は多数員によつて担はるるの結果、これを担ふ一部の人々が亡滅しても、残留の人々がこれを保持し、新来の人々がこれを継承して、久しきに亘り存続させてゆくことができるからである。又社会意識は個人意識を外部から制約し圧迫する機能をもつてゐる。けだし社会意識は個人心内の現象ではあるが、その内容が社会的共通的のものであるの結果、個人の主観的立場から見ると、それは外から来つてわれを制約するもの・一種の負担としてわれの上にのしかかるものとして映じ易いからである。
要するにわれらの心内には二つの精神が宿つてゐる。個人意識と社会意識とがそれである。そして後者は前者を拘束し、圧迫してゐるのである。
ロ 右のやうに社会意識とは社会成員の全部又は多数が共通的に抱きもつてゐる意識といふ意味であるから、法律は社会意識だといふ主張は、法律が含む命令・禁止・許容等々は社会の支配者からばかり発するのではなくして、社会の全成員からも出てゐるのだといふ主張となる。即ち社会の支配者ばかりが命令したり、禁止したり、許容したりしてゐるのではなくて、民衆自身もまた相互に命令したり、禁止したり、許容したりしつつあるのだといふ主張になる。さらに換言すれば社会の全成員又は多数成員がみな実定法の規定内容と全然同じ内容の命令意志・禁止意志・許容意志等を現実に抱きもつてゐるのだといふ主張になるわけだが、事実果してさうであらうか。事実果して一般民衆が法律と同じ内容の命令意志や禁止意志や許容意志を抱きもつてゐるであらうか。
ハ 慣習法の場合にはたしかに民衆は慣習法とその内容を一にする規範意識を抱きもつてゐる。なぜかなら慣習法とは元来民衆によつて担はれてゐる現実の規範意識そのものを指す語なのであるからである。しかし制定法の場合はどうであらうか。今日の制定法の内容は人生そのもののやうに複雑である。しかもそれは非常に学理的論理的な体系上に建てられてゐる。どう考へてもそれは「民衆的」ではない。それは民衆の心を遠く離れて聳立つ学理的な組織だといはねばならない。民衆が一種の法律感情をその胸に抱きもつてゐることは事実であるが、しかしそれは極めて単純な・粗朴な・無組織な・いはば正義感(sense of justice)といふやうなものに過ぎぬであらう。決してそれは実定法のやうな体系あり組織あるものではないのである。だから結局かう成る——民衆のもつてゐるものは法律にあらず、たかだか前法律的のものに過ぎないと。
かやうにして実定法殊に制定法の本質は当為でもなければ社会意識でもないといふことになつてしまつた。ではそれは何であるか、それに答へるために登場するのが擬制的社会意識説である。
三 擬制的社会意識説
イ 擬制的社会意識とは社会成員が共通的に抱きもつてゐると看做されてゐるに過ぎない意識をいふ。けだし社会成員はある程度までは斉一の思想・感情・意志・信念等をもつてゐる必要がある。かかるものをもつのは社会成員間の心的結合の度を強化するゆゑんであるからである。しかし発達した社会においては、その成員間に著しき個性の相異・意見の対立・利害の衝突・階級の分裂があるので、これを自然の成行のままに放置しておくならば、いつまでたつても社会成員の間に意識の斉一現象を招来させることができぬであらう。よつて発達した社会は純形式的技巧的に社会意識を作出しようとする。即ち前以て一定の手続を定めておき、その手続に従つて或意思が発表された場合には、その意思を以て社会意識と看做すべしと約束しておくのである。重ねていへば事実上の支配者にかかる権限を与へておき、支配者が一定の手続を踏み、一定の方式に従つてその意思を表示した場合には、その意思が一般民衆の意思と合致するや否やに頓着なく、その意識を以て社会全員の意思と看做すべしと予定しておくのである。擬制的社会意識とはかかる社会機構上若くは社会制度上、社会全員の意思と看做さるる所のものに過ぎない。ゆゑにそれは実は社会意識ではない。社会意識は社会全員によつて現実に共通に担はれてゐる意識でなければならないのに、擬制的社会意識は現実には全員によつて担はれてをらず、一部の支配者層によつて担はれてゐるに過ぎぬからである。実質上からいふとそれは支配者の意思でしかない。
ロ 法律殊に制定法が大体において右述のごとき擬制的社会意識に属することは明かであらう。なぜかなら制定法は権限ある国家機関が法定の手続に従ひ法定の方式を践んでその意思を表示し、そしてその意思が社会全員の意思として通用する場合の中の、最も顕著なものに属するのだから。
ハ 右のごとく制定法の本質は社会全員の意思ではなくて社会における支配者層の意思であるが、だからといつていつも法が支配者層の利益のためにばかり制定されるとは限らない。支配者層は彼等の利益のためにばかり法を制定するのではなくて、超階級的な利益即ち全体社会の利益のためにもまたこれを制定するのである。例へば生命身体の安全・社会文化の向上・国防の安全・民族の発展・衛生の完備・教育の普及等々の目的のために立てられた法律のごときは、何といつても超階級的な性質・全体社会的な性質をもつと見るべきであらう。又支配者層は被支配者層の利益のみのためにさへ法を制定する。かの社会立法・労働立法のごときは大体において支配者層が特に被支配者層の利益のために作れる所だと見るべきであらう。けだし支配者といひ被支配者といふも、もとこれ全体社会内の部分社会である。両者の間の関係は、我彼を倒さずんば彼我を倒すローマとカルタゴの関係ではないのである。もし支配者層が被支配者層を極度まで追ひつめてしまふならば、支配者層もまたその存立の基礎を失つて共倒れに倒れてしまふであらう。ゆゑに支配者層は自己の基礎的利益を失はざらんと努めると同時に、程度的に被支配者層に譲歩し、彼等の利益をも擁護してやるのである。
要するに制定法は擬制的社会意識である。その実質は支配者層の意思であるが、制度上社会全員の意思として通用するところのものである。
第二節 法の理解
四 法を対象とする学問
イ 制定法は支配者の意思であり、慣習法は人民の意思であつて、その内容は共に善なることもあり、善ならざることもあるといふことは、前節においてこれを明かにした。ゆゑにわれらは実定法に対しては次のごとき二種の学問的態度に出ることができるのである。
ロ その一は批判的態度である。批判とは与へられたる対象を一定の標準に照らして判別すること、即ちその中に推称すべきものと非難すべきものとを判別することをいふ。法律哲学は実定法に対してかかる態度をとり、殊に実定法批判の標準について論じるのである。その二は経験科学的態度である。経験科学的態度とはリアルなものをリアリスチツクに捉へんとする態度をいふ。けだし与へられた対象の中には善なるものあり悪なるものあり、美なるものあり醜なるものあり、完全なるものあり不完全なるものもまたあるわけであるが、経験科学的態度は対象をあるがままに、即ち悪なるものを悪なるままに、醜なるものを醜なるままに、不完全なるものを不完全なるままに把捉しようとするのである。本節において述べる法律理解の学と第四節において述べんとする法律説明の学とは法律に対してかかる経験科学的態度をとる。
五 法の理解
イ 理解(verstehen)とは他人が外界へ表出した諸記号、例へば言語・文章・身振等を通じて、若くは他人の実践的諸行動を通じて、彼が抱いてゐる思想・感情・信念等をリアリスチツクに認識することをいふ。ゆゑに(一)理解の対象は人に限られる。自然は理解の対象とはなりえない。言葉としては『自然の心を理解して……』といふやうな場合もあるが、それはその際自然を擬人化してゐるからである。又理解の対象は他人に限られる。自分自身は理解の対象とはなりえない。言葉としては『自分で自分を理解して……』といふやうな場合もあるが、それはその際自分自身を外化し他人化してゐるからである。(二)理解の材料は他人の表現又は行動である。われらは他人の表現又は行動を手がかりとし拠り所として他人心内の光景に迫り、彼がいかなる内容の思想・感情・信念等を抱いてゐるかを推断することができるのである。ゆゑに理解は表現とは恰も逆な方向へ進むといつていい。表現は表意者がわが内部にある所のものを外部へ表出する作用であるが、理解は理解者が外部に出てゐる所のものから表意者の内部へ再び還帰して行く作用だからである。又(三)理解の方法はいはゆる追体験(nacherleben)の方法による。追体験の方法とは、砕いていへば、相手の身に成つて見ることをいふ。われを彼の心内へ移入し、彼と合体し、彼の心を以てわが心とすることをいふ。われらは彼と合体するにあらざれば彼を知ることができない。彼我合一は我が彼を知るための唯一の道である。理解とは畢竟他人と実感を共同にすること・即ち他人と共鳴共感すること・そのことの謂ひに外ならぬのである。
ロ さて法律もまた理解作用の対象となりうるかといふに、それがさうなりうることは多言を要せずして明かであらう。なぜかなら(一)理解の対象は他人であることを要するが、その他人は単数であることを要しない。多数人の意思例へば一地方民の意思・一国民の意思・一時代の意思といふやうなものも、やはり理解の対象となりうるからである。法の実質は社会における多数人の意思であるが、この事は法が理解作用の対象となるための障害とはならぬのである。(二)或はいふ、理解の対象は他人の意思でなければならないが、法律は同時にわれの意思でもある。われは社会の一員であり、法律の担ひ手の一人である。ゆゑにわれは法律に対しては理解的態度をとりえないと。しかしわれはわれを他人化してこれを観察し、これを認識することができること既述の通りである。だからわれが法律の担ひ手だといふことは、法に対するわれの理解を妨げる何の障害ともなりえぬのである。又(三)他人の意思が理解作用の対象となるためには、その人の意思が何等かの記号、例へば言語とか文章とか行動とかの上に表出されてゐなければならないが、この要件も法律の場合には具備してゐる。制定法の場合には法文といふ厳密な表現が整然と備つてゐるし、慣習法の場合には慣行といふ行動による表白が存在してゐるからである。即ちわれらは制定法の場合には法文を通して社会が定立してゐる法的規範の内容を如実に知ることができ、慣習法の場合には慣行を蒐集し調査して社会が抱きもつてゐる規範意識の内容をさながらに捉へることができるわけである。そしてそれこそが即ち法律理解学である。ゆゑに法律理解学は法律に対して何らの歪曲も加へない、何らの加工も施さない。不明あらば不明あるままに、不完全あらば不完全あるままに、不当あらば不当あるままに、これを描写し、これを記述しようとするのである。それゆゑに法律理解の学は経験科学としての性格を立派に具備してゐるといはねばならない。リアルなるものをリアリスチツクに認識するものはすべて経験科学の名に値ひするのだからである。
六 二種の理解
イ 理解は他人と共鳴することであるが、共鳴には程度の差あることを免れない。よつてこの見地から理解を二種に分けることができる。一は理解者が他人の表現上又は行動上の目的を如実に把捉することはできるが、その目的が理解者自身の価値観から甚だしく離れてゐるために、感情的にはどうしてもそれに同感しえぬ場合である。この場合には理解者は他人の表現上又は行動上の目的をハツキリと見抜くことができ、この目的に従つてその他人の表現又は行動の全過程を跡づけ順序づけることもできるが、しかし自分みづからはさういふ表現なり行動なりをなしたいとはおもはない。これを理智的理解といふ。それは他人の心理を単に理智的に把捉するに止る場合であるからである。二は他人の表現上又は行動上の目的が理解者自身の価値観に近いため理解者自身全くその他人の心へ乗移り、自分自身が第二の他人となり切つてしまふ場合である。これを情緒的理解といふ。それは理解者が他人の心理を理智的に把捉するばかりでなく、情緒的にもこれに同感する場合だからである。
ロ 法の理解の場合はどうかといふと、われらが法に対して情緒的理解を寄せ、完全にこれと共鳴共感してしまふ例もないではない。それは立法者がわれらの法意識を取上げ、これを法上に表現してくれた場合であつて、この場合には法は『外から課せられた法』ではなくて、『内から発した法』であり、これに従ふのは内なる規範意識に従ふものである。ゆゑにかかる法に対してはわれらは心からなる愛を寄せ得るのであつて、例へば十九世紀の民衆のごときは、当時新たに作られた憲法や刑法や民法に対してこのやうな情緒的理解を寄せてゐた。けだし十九世紀の民衆は政治的には議会政治の確立を欲し、刑法的には専擅刑罰の絶滅を願ひ、民法的には所有権の保護・取引の安固を仰望してゐたのであるから、一たび当時の開明君主によつて議会主義の憲法・罪刑法定主義の刑法・個人主義の民法の制定せらるるを見るや、永年の理想の俄かなる実現に出遭へる思ひをなし、どこまでもこの法を支持し、どこまでもこの法を発展拡充させて行かうと考へたからである。十九世紀は史上稀に見る法律学の隆盛期であつたが、これは当時の法律学者が立法者自身とほぼ同質の法意識を抱き、立法者と心を協せて価値ある法律体系の具現に努力するといふ積極的・進撃的・創作的気分に充ち溢れてゐたせいに外ならなかつた。
ハ しかしその後における経済情勢の変化は社会を有産者と無産者との二層に分裂させてしまつた。そして両層の間の対立をも逐年鋭角的なものにしてしまつた。今では二層はいはば一つの全体社会内における二つの部分社会である。二層はその経済的利害を異にし、政治的基本要求を異にし、思想感情の形態をも異にし、価値観さへも異にしてゐるのである。一方の価値ありと見るもの他方は必ずしもさうとは見ず、一方の美と感じ正と見る所他方は必ずしもさうとは見ないといふ悲しむべき分裂を示してゐるのである。現代法制に対する限りにおいていへば、有産者層は現代法制のうちにわが正義感情の充分なる表現を見出すが、無産者層は必ずしもさうでない。現代法制のうちには改善すべき多くのものが潜んでゐると見てゐるのである。それゆゑに現代法制に対する両者の理解作用にもまた性質上の変化が生じて来る。即ち有産者層のそれに対する理解が熱と力とに充ち満ちた情緒的理解でありうるのに反して、無産者層のそれに対する理解はややもすれば冷やかな観察者としての理智的理解に止らうとする傾向を示すのである。今日一部の人々の間に法律学の発達が行詰つたとか、法律を学ぶ学生自身が法律に対して興味を感ぜぬやうになつたとかいはれてゐるが、このやうな現象を招来するに至つた原因の一つは、法律学の学修者が知らず識らず無産者層の立場に同情し、無産者的意識を以て現代法制を眺めてゐるためだと思ふがどうであらうか。
しかしここにしばらく科学を離れて諸君のためにあへて一つのモラルを説くならば、諸君はみだりに有産者の主張に雷同してはならないと同時に、容易に人民の中へ這入つて入つてもならない。けだし社会における、殊にこの国における、インテリゲンチヤの任務は重且つ大である。彼は有産無産二層の間を調節する第三の力である。彼は教養の媒介によつて有産者の立場を理解し又無産者の気分を察し、社会の両極を一層高次の次元に統一するのである。二層のいづれにも偏せず党せず、その中間にあつて、全体社会の理性を表現し、その利益を代表するのである。而してこの貴重なるインテリゲンチヤの任務は社会対立の先鋭化と共に益々加はるといふことを知らねばならない。
第三節 法の解釈
七 解釈の性質
イ 解釈(auslegen)とは他人の表現に対して何等か或別の意味を附与することをいふ。ゆゑにそれは理解と異る。理解は他人の表現がもつ意味(他人自身が思念してゐた意味)をそのままに受取らうとする作用であるが、解釈は他人の表現に対して解釈者の立場から、何等か或別な意味を附け加へようとする作用であるからである。前者はいはば対象の内部から外部へその意味を抽出しようとする仕事、後者はいはば対象の外部から内部へ新しい意味を持込まうとする操作。一は意味抽出、他は意味附与。又前者は対象が不完全であり不当である場合にもそのままこれを把捉するが、後者は対象が不完全である場合にはなるべくこれを完全化し、美化し、正当化しようとする。前者はリアルなものをリアリスチツクに把へんとする経験科学的な認識。後者はリアルなものをイデアルなものに改変しようとする実践的・創作的な行動。
ロ 従来の学説のうちには理解と解釈とを同一視するものがないでもなかつた。しかしわれらは前者をば『客観的なる意味の享受』、後者をば『主観的なる意味の附与』と定義し、二者の区別を截然と立てたい。さうすることが法理学上の難題たる法律解釈学の性質如何の問題を解決する大きな一つの鍵となるとおもふから。
八 神学と法律解釈学
イ まづ神学の性質を見ると、神学殊に聖書の解釈学は聖書からその原始的意味を抽出する作業といふよりも、むしろ外から聖書の中へ一層深遠な意味を持込む仕事だといつていい。けだし聖書はあらゆる煩悶の解決力である。宗教生活上における信者のあらゆる難問・あらゆる苦悶は、みな聖書の前へ持出されて、それからの解答を待つからである。そこで聖書は自己の前へ提出されて来るであらうところのあらゆる問題に適当に応答しうべく、予め自己を豊富化させ、完全化させ、深遠化させておかねばならぬのであつて、さういふ仕事が即ち聖書の解釈学に外ならない。ゆゑに聖書の解釈学は聖書の原始的意味を如実に把へる理解学ではなくて、聖書へ新たなる意味を附加する解釈学である。単純な粗朴な聖書の原始的内容が雄大深遠な意味体系に一変してしまふのは実にかうした解釈の作用に依るといはねばならない。
ロ 法律の解釈も神学と同じ性格を担つてゐる。けだし法律の世俗生活におけるはなほ聖書の宗教生活におけるがごとくである。信者の宗教生活上のあらゆる苦悶が聖書の前へ持出されてそれからの解決を俟つやうに、市民の社会生活上のあらゆる紛争もみな法律の前へ持出されてそれからの解決を俟つ。法律としては予ねてからそれへの答を用意してゐた場合もあるであらうし、さうでない場合もあるであらう。さうでない場合にも法律はなほ答へざるをえず、裁判所はなほ判決せざるをえぬのである。よつてここに法律の内容をその原始的意味を越えて精密化し明瞭化し体系化し豊富化し完全化する仕事が始まる。それが法律の解釈である。法律の解釈は法律の不備を補ひ、不明を去り、不当を除き、重複や矛盾を除く。ゆゑにそれは法律の現実態をあるままに把へんとする作業ではない。むしろそれは法律の現実態を陰蔽し糊塗し弥縫しようとする仕事である。ゆゑに又それは理解学ではなくて解釈学である。経験科学ではなくて神学である。いな学問ではなくて実践である。
九 法律解釈の方法
イ 法律解釈の目的は法の明瞭化・精密化・完全化にあるのであるから、法律解釈の手段はこの目的から規定を受ける。即ち法における不備不当が多ければ多いほど解釈の手段はその数を増し、且つこれらを益々多面的に使用せざるをえなくなる。これを現代の法律解釈学に見ると、解釈の手段は条文・判例・沿革・立法理由・立法傾向・多数説・新学説・比較法・社会通念・実際上の必要等々七つ道具も啻ならざるありさまであり、しかもこれらを使用する順序がまた甚だ無秩序であるのであつて、例へばいま私が私の机上に立並ぶ註釈書のうちから任意の一冊を抜き取り、その解釈操作の跡を調べて見ると、それは第一条を註釈する際には文理解釈の方法を用ひ、条文にaとあるがゆゑにaならざるべからずと論結してゐるが、第二条の註釈に当つては論理解釈の方法を採り、条文にはbとあれども論理上b′の意ならざるべからずと断じ、第三条の註釈に当つては沿革解釈の方法を探り、条文にはcとあれども沿革上c″の意ならざるべからずと断じ、その他立法の理由・立法者の意思を楯とする場合あり、社会の通念・判例の趨向を理由とする場合あり、外国における最新の立法傾向や新学説の主張を理由とする場合あり、甚だしきは露骨にも実際上の不都合の回避を理由とし、もしこれを文字通りに解せんか適用の結果として斯く々々の不都合を生ぜざるをえざるべきを以て、かかる不都合の発生を避くべく、強ゐてこれを別様に意味づけざるべからずと主張するのである。大小幾個の解釈手段を秩序もなく使用するありさまは教会の牧師が信者からの問ひに答ふべく、聖書をめくつて尤もらしい返答を抽出すのと些の相異もないのである。
ロ 殊に最近の独裁政権跋扈の時代となつてからは、法律解釈の神学性が愈々顕著となつて来た。なぜかなら独裁政権はその政治目的達成の便宜上どうしても専擅的な権力組織を所有しなければならないが、独裁政権成立の当初においては、自由主義時代の法制が未だ残存してゐてそれが権力行使上の桎梏となつてゐる。よつて独裁政権は一方、立法の方法によつて自由主義法制の残存を駆逐すると共に、他方、解釈の手段によつて旧法制を便宜に改釈しようとするのであつて、その際大いに用を為すのが、いはゆる法の精神解釈である。法の精神解釈とは一国法律組織の内奥には、その国の歴史の精華・その国の民族精神といふやうな深遠悠久のものが潜んでをり、全法制はかかる精神の表面化に外ならぬ・従つて法の表面に拠るべき直接の規定なきときは、裁判官はよろしく法の統一原理たる民族精神の中から適宜な判決規範を抽出すべく、又拠るべき直接の規定ある場合にも、その規定が民族精神の表現としてふさはしからぬ内容のものなるときは、その規定を越えて判決規範を見出すべしと説くものである。法の内奥に何等か或深遠の精神潜むと仮定する点において、精神解釈は最も神学的であるのである。ナチ法学者の学問の中には法律学といふよりも神学そのものと見て然るべきものさへないでない。
第四節 法の説明
一〇 説明の性質
イ 説明(erklären)とは対象たる現象を他の外在的現象と結びつけて把捉しようとすることである。当面の現象は一体どんな外在的原因に動かされて生起したか、どんな外在的結果を惹起させたかを問題にし、専ら注意を当面の現象を発生させた原因と、これから発生した結果とへ向けるのである。即ち説明とは因果関係の説明のことである。
ロ これを理解に対照させてみると、理解の方は他人の行為をその内在的目的に結びつけて把捉しようとするが、説明の方は対象たる現象を他の外在的現象へ結びつけて認識しようとする。即ち理解の方は他人の行為が何か或内在的目的に向つて為されたと見て、その行為とその目的との間の連絡を尋ねようとするのであるが、説明の方は現象が或外在的原因に押されて生起せしめられたと見て、その現象とその原因との間の連絡を把まうとするのである。一は志向聯絡を尋ね、他は因果聯絡を尋ねる。
ハ 対象との関係からいふと、理解は専ら精神現象や社会現象に対して用ゐられ、説明は主もに自然現象に対して用ゐられる。即ち自然現象に対しては理解といふことがあり能はぬが、社会現象に対しては理解と共に説明もあり能ふのである。なぜかなら社会現象といへども有原因の現象である。それは何等かの原因に押されて出現し、何等かの結果をそのあとに残すには相違ないからである。だからわれらは精神現象や社会現象については、現象の内部を覗見してその意味を把捉することができると共に、現象の外部を観察してその原因を尋ねることもできねばならない。
一一 法の説明
イ 法律は一つの社会現象であるから、われらはこれに対しては理解的態度に出ることもでき、説明的態度に出ることもできるわけである。が、一派の学者はこれに反対していふ——法律は立法者の自由意思によつて作られる。立法者は外的原因の支配の下に或内容の法律を作るのではない、彼は恣意を以て法律を作るのであると。この見解にしてもし真ならば、法律成立の外的原因を尋ねるといふことは無意味となり、法律については理解学だけ成立して説明学は成立しえぬこととなるであらうが、事実において立法者は自由自在な万能神ではない。われらの見る所を以てすると、凡そ一社会の成員たちは経済上互に密接に連絡し合ひ、影響し合ひ、作用し合つて生きてゐる。即ち彼等はお互を緊密なる物質的相互依存の関係に繋ぎ合はせつつ生きてゐるのであつて、仮りにこれを経済関係若くは経済生活と呼ぶならば、経済関係若くは経済生活こそは最も日常的な、最も土台的な生活面であり、他の一切の社会生活は、政治生活でも法律生活でも宗教道徳芸術の生活でも、みな経済生活を基礎構造としてその上にそそり立つてゐるに過ぎないと見ねばならない。よつていまここに一定の経済関係においてお互を繋ぎ合はせてゐる人々の集団即ち社会があつたとすると、その集団のために法律を設定するところのいはゆる立法者は、右の経済関係を基本的な前提としてそのまま受取り、これに調和させ順応させて法律を設定するの外はない。換言すれば右の経済関係を是認し肯定し、その存続を保証し、その発展を促進させるやうな意味と内容とにおいて法律を立てて行くの外はない。経済関係を無視して法律を立てて見たところで、さういふものは実際に行はれえず、結局その内容を変化させて経済関係に適合的なるものとなつてしまふの外はないからである。それゆゑに立法者の立法活動が完全に自由だとはいへない。彼の立法方向は経済関係から強く制約され規定されてゐるのである。
又立法者の立法活動は経済以外の関係例へば政治宗教道徳等からも或程度の制約を受けてゐる。なぜかなら政治や宗教や道徳はそれ自身また経済関係から制約されてゐる生活面ではあるが、或程度の逆影響を経済関係の上に及ぼすこともあるし、相互の間において或程度の影響を授受し合ふ場合もあるからである。時とすると政治や宗教は経済にも劣らぬ深甚の影響を立法者の立法方向の上に及ぼすことさへあるであらう。ゆゑにこの点から見ても立法者の立法活動は自由でない。彼の行動は経済的原因によつてはもちろん、政治的思想的の原因によつてもまた著しく拘束を受けてゐるのである。むろん立法者がその創意を働かしうる余地もないではないけれども、それはいはば経済的・政治的・思想的原因に取巻かれた僅少の空地内においての自由でしかない。ゆゑに結局われらは法律に関してもその経済的・政治的・思想的原因を尋及することができる。いひかへれば法律についても説明の学を立てうるのである。
例へば今ここに或内容の法律規定なり法律制度なり法律原則なり法律思想なり法律学説なりがあつたとすると、われらはそれに対して、それがいかなる原因から発生したか、いかなる原因に制約されてそのやうな内容をとり、そのやうな形態をとるに至つたかを問ひうるが、それが即ち法律説明の学に外ならない。
ロ しかし法律は経済関係その他から影響を受けるばかりではない。さらにそれらの関係へ逆影響を及ぼしもする。例へば法律が或社会行為の発生を禁圧することを目的として或禁令を発したとすると、もし自然のままに放任しておかれたならば発生したであらうところのその社会行為が、右禁令の作用によつてその発生を阻止されるといふことになるであらう。又法律が或社会行為の発生を誘発し促進することを目的として或命令を発したとすると、もし自然のままに放任しておかれたならば容易には発生しなかつたらうところのその行為が、右命令の作用によつてその発生を誘発され促進されるといふことになるであらう。法律は決して社会生活の自然の発展を静かに見送つてゐるのではない。それは積極的に社会経済生活の展開へ向つて働きかけ、法律の欲する方向へそれを索引して行かうとするのである。法律が社会を統制するとか行為を規律するとかいひうるのは、法律にかかる実生活索引の力があるからである。ゆゑにわれらは或法律規定なり或法律制度なりについてその成立原因を尋ねうるばかりではなく、進んでその制度なり規定なりが社会経済生活の展開の上へ及ぼした影響をも尋及しうるであらう。いひかへればその規定なり制度なりが、その成立後、社会経済生活の展開に対してどのやうな結果を及ぼしたかをも尋ねうるであらう。そしてそれもまた法律説明学の一任務ではある。
要するに法律を一個の社会現象と見て、それの成立原因とそれの成立後の結果とを見究めること、それが法律説明の学なのである。
一二 法律説明学としての法律社会学及法史学
イ 法律説明の学に二つある。一は法律社会学であり、他は法史学である。まづ法律社会学を見ると、この学科の任務又は課題は久しく薄明の間に低迷し来つたが、最近における斯学の発達は斯学の任務を明かならしめ、二つの課題を自分自身の上に課するに至つた。その一は法律規定なり法律制度なりがいかにして成立し変化し亡滅するに至るかを論ずる成立論、その二は一旦成立した法律規定・法律制度等が社会生活の爾後の展開に対していかなる逆作用を及ぼすかを論ずる逆作用論である。換言すれば法律社会学は一方においては法の社会的原因を説明し、他方においては法の社会的作用若くは社会的機能を説明しようとするものなのである。(一)
一 ゆゑにいはゆる社会法学(soziologische Jurisprudenz)は法律社会学(Rechtssoziologie)からは厳に区別されなければならない。いはゆる社会法学は法の解釈に当つて制定法の規定のみを見ず、生きた社会の規範意識をも見、二者を提携させ握手させることによつて制定法の不備不当を補完して行かうとするものであつて、その性質は説明学でもなく理解学でもなく、一個の法律解釈学そのものに外ならぬのだからである。わが国の学者中には認識方法の性質を充分に吟味せず、記述・理解・解釈・説明等々の諸方法を雑炊的に混用して、漫然これを法律社会学と呼んでゐる輩がないでもないが、われらはかかる無反省を排撃せずにはゐられない。
ロ 法史学もまた法の説明学の一つである。即ち法史学は法律社会学と共に法律規定・法律制度・法律原則・法律思想・法律学説等々の社会的根拠を問ひ、その社会的機能をも問題とするのであるが、法史学における説明は法律社会学におけるそれよりも一層具体的であり、一層特殊的である。例へば法律社会学においては凡そ経済は法律に対していかなる関係に立つかとか、凡そ政治は法律に対していかなる関係に立つかとか、凡そ宗教は法律に対していかなる関係に立つかとか、常に一般抽象的な設問の形式の下にそのシステムを展開するが、法史学においてはもつと具体的特殊的な設問の形式をとる。即ち一定の時代・一定の社会に現実に存在してをり又はゐた或法律規定なり法律制度なりをとらへて、それはその社会におけるどのやうな経済関係・どのやうな政治関係等々に影響されて成立したか、又それはその成立後その社会における経済関係・政治関係等々の発展の上にいかなる逆作用を及ぼしたかを問ふのである。要言すれば法律社会学は法の成立及作用に関する一般的因果法則の学。法史学は法の成立及作用に関する具体的因果関係の学。
ハ 右のごとく法史学は法律説明の学であるがゆゑに、それは法制史とは異る。法制史の或ものは、過去における法律状態をそのまま記述することを以てその仕事としたり、過去における法律変化の過程をそのまま記述することを以て仕事としたりしてゐるから、この種の法制史は、『史的叙述』(historische Darstellung)としての性質をもつといはねばならない。又法制史の或ものは、過去の法制に関係ある史料を蒐集・判読・分類・整理することを以てその仕事としてゐるから、この種の法制史は、『法律古事学』(Rechtsaltertümer)としての性質をもつといはねばならない。いづれにしても法制史は説明学としての法史学とは異つてゐる。
では法史学と法制史とはどのやうな関係に立つかといへば、法制史は法史学の基礎学又は補助学であると見ていい。けだし法史学は法の説明を以てその任務とするが、法の説明をなすためには当該の時代の法律状態そのものを正確に知らねばならず、この点において法史学は史的叙述としての法制史からはもちろん、法律古事学としての法制史からも多大の援助を受けるからである。
一三 西洋法史学の研究範囲
イ 西洋法史学は西ローマ帝国の滅亡以後、欧洲大陸においていかなる法律上の変遷ありしや、殊にいかなる私法上の変遷ありしやを記述し且つこれに社会経済上の説明を加へることを以てその任とする。ゆゑにこれは第一に西ローマ帝国滅亡以前の形勢即ちローマ法史には触れない。ローマ法史はその特別の重要性のゆゑを以て独立の一学科として取扱はれてゐるのである。第二にそれは大陸以外の法律史即ち英法史をも取扱はない。英法史はその発展のコースの独自的なるのゆゑを以てこれまた独立の一科となつてゐるのである。第三にそれは公法上刑法上の変遷にも触れない。公法上刑法上の変遷は公法史・刑法史としてやはり独立の学科を成してゐるのである。結局するところ西洋法史学の研究範囲は時代的には西ローマ滅亡以後、場所的には欧洲大陸、事項的には私法の変遷といふことになる。
ロ 本講義においては、われらは西ローマ帝国の滅亡から中世の末葉即ち十五・六世紀の頃までの間において欧洲大陸が閲みせる法律上の変遷殊に私法上の変遷を述べ、これにつき社会経済上の説明を加へる所あらんとするのである。
第二章 立法史
第一節 古代ゲルマン(紀元前一世紀—紀元五・六世紀)
一四 原始社会一般
イ ローマ帝国はライン河とドナウ河並に両河をその上流においてつなぐ一線を北辺の国境とし、以てゲルマン蛮族の侵入を喰止めてゐた。ラインの対岸にはいはゆる西ゲルマンの諸部族が、ドナウの対岸にはいはゆる東ゲルマンの諸部族が、鬱積的に集結し、帝国内へ侵入の機会もがなと待ち構へてゐたのであつたが、遂に国境の突破に成功し、帝国内へ乱入し、帝国を滅ぼしてその廃趾に多数のゲルマン新国家を建設したのであつた。ゲルマン人の歴史的登場から新国家の建設に至るまでの間、即ち紀元前一世紀頃から紀元後五・六世紀頃までを古代ゲルマンと呼ぶ。
ロ 古代ゲルマンの社会を知るためには、原始社会の性質一般をまづ知つておく必要があるが、この方面の研究家はわれらに教へる——人間の生産力が原始的に幼稚だつた時代には、人間は野生の鳥獣や魚介を捕へ、木の実や草の根を拾つてその日その日の生活を支へてゐたから、自然そこに野生の動植物の拾集に適合的なる組織をもつ人間の集団が生れた。これを群団(Horde)といふ。群団は二三十人乃至四五十人の小人数を以て組織され、鳥獣を追ひつつ山河を移動してゐたが、鳥獣の集合・植物の成長には季節的な規則があるので、一の場所を去つた群団は又その場所に戻り、一定の区間を去来しつつある間に、自然その区間を自己所有の狩猟区又は拾集区と考へるに至つた。
群団は一つの労働団体であり、共同して狩猟区を有し、共同して狩猟具を有し、共同して狩猟をなし、捕獲物をも共同に分配してゐた。だからそこには所有の差なく、主人召使の別なく、支配者と被支配者との対立もなく、奴隷制度なども未だ発生はしてゐなかつた。
群内の男女も一組づつの結婚はせず、入り乱れて交つてゐただけのことであつた。これを乱婚とか集団婚とかいふが、実は婚姻ではなくして、狭い範囲の人々の間における自由恋愛関係そのものに過ぎぬのであつた。当時は財産の独占といふことがなかつたやうに、異性の独占即ち婚姻といふ現象も見なかつたのである。出来た子は群団の子として全部の者から共同的に愛護されてゐた。
ハ しかし群団のなかにはそれの共産的性質と矛盾するやうな契機もあつた。個人が群民の助けを借らず全く単独にて捕獲した動植物はその個人の所有となるといふ規則がそれである。もとはこの種の捕獲物も群共同の所有となつてゐたのであつたが、後に至り個人の所有に帰せしめられた。例へば皆で獣狩りを行つてゐる際、偶然拾つた木の実は拾得者の有となるごときこれである。しかし一旦この特則が認められ出すと、個人的取得を目的として単独にて野山を駆け歩く者も生じ、群団を離れて愛人と独立の小屋に棲む者も生じ、群団移動の生活は崩れて、家族定住の生活へと移り出した。
しかし家族定住の生活が始つてからも男子は狩猟漁撈を業としてゐたが、女子は家に留つて子供の世話などしてゐる間に、種子を蒔けば収穫がえられるといふ自然法則をふとした機会に発見し、家の近所に園芸的な農業を始めた。ところがこれは男子の狩猟や漁撈よりも遥かに確実な所得の源泉であつたから、農業の方が一家経済の基礎となり、女子の方が一家勢力の中心となり、一時は母権社会といふ女子中心の社会をそこに現出させた。しかし男子も後にはその本業を農業の方へ移し、だんだん狩猟を離れて行つたので、狩猟漁撈の経済段階は過ぎて農業の段階へ移り、家庭生活も父権中心のものと変つて行つた。
ニ ところで農業の発生は広汎な変革を社会生活の全面に捲き起さずにはおかなかつた。その一は家族制度である。何にしろ一家全部の者が家長の指揮の下に農事にいそしんでゐた関係上、そこに家本位の思想を生じ、家長中心の制度を立てるやうにもなつたのである。その二は氏族制度である。農業時代になると人間が一ヶ所に永住し、人間相互間の血縁関係の有無も従つて明かとなり、祖先を同じうする者が相結び相助けるといふ制度即ち氏族制度も生じることとなつたのである。そしてこの制度は農業社会に階級の別を産む重大な契機ともなつた。なぜかなら一氏族が一党を組んで自ら衛り、他にも当つてゐた関係上、有力な祖先をもつ有力な氏族は益々党を殖やし勢を張り、他を抑圧して社会の支配者となることができたからである。第三に農業は奴隷制度を産んだ。群団移動の時代には奴隷をつれて山河を跋渉することが厄介であつたために、戦争の捕虜なども殺したり放したりしてゐたが、家族定住の時代になると奴隷労働の監視が容易となつたので、これを農業に使役するやうになつたのである。
しかし農業がもたらした最大の産物は何といつても国家であつた。けだし農民の軍事能力はあまり高くない。彼等はかなり分散的に居住する関係上、周囲の狩猟民の一旦隊伍を整へて侵入し来るに会へば、一たまりもなく潰えざるをえぬ運命にあつたのである。現に農業民にして狩猟民から征服を受けて永遠の隷属者と化し去つたものも少くなかつた。古代社会の宗教を見ると、貴族は牧畜の神を祭り、庶民は農耕の神を祭る例がよくあるが、これは狩猟民が農業民を征服して貴族の地位に上るに至つた大過去の事実を暗示してゐるのである。よつて農業民の或ものは自衛の必要上数ヶ村を合して郡(Hundertschaft)を作り、郡司を選んで軍事上の指揮権を委ねたが、みづから生産するよりも他人の生産したものを掠奪する方が有利だといふことを悟るに及んで、郡は自己を掠奪団体に一転し、屡々他地方を襲撃した。よつて他地方も対抗の必要上一層大なる軍事同盟を作り、遂には数郡又は十数郡を聯合した巨大なる軍事同盟も成立したが、これが即ち部族国に外ならない。
部族国の指揮者を王といふ。王は初めは臨時の軍事指揮官に過ぎなかつたが、後には戦争が終了してもその位を下らず、却つてその権限を一般政務の上に延ばして、遂に王とはなつたのである。
以上われらは原始社会一般の性質を論じたが、問題の場合即ち古代ゲルマンの場合にはどうであつたかといふと、それはすでに群団移動の時代を過ぎて家族定住の時代に入り、狩猟漁撈の段階を過ぎて農業の段階へ達し、郡・国等の政治組織まで具有してゐたといふものの、なほ原始共産時代の遺制をも濃厚に残存させてゐたのであつた。次に古代ゲルマン人の社会経済生活・法律生活等について簡単に述べる。
一五 古代ゲルマン人の生活
イ 古代ゲルマン人の生活状態はシーザーのガリヤ戦記(de bello gallico um 50 v. Chr.)とタキツスのゲルマニヤ誌(germania um 100 n. Chr.)とによつて、その大様を窺見することができる。当時のゲルマン人は文字を有せず、みずからの過去をみづから顧望するだけの智的年齢にも達してゐなかつたが、ローマ人にとつては彼等は恐るべき隣人であつた関係上、ローマ人は彼等の動静を仔細に観察し、これを筆にして後世へ残しておいてくれたのである。でいま右の二著を資料にしてゲルマン原初の生活状態を想見すると、シーザーが書いた紀元前五十年の頃、ゲルマン人は原野農法(Wilde Waldwechselwirtschaft)の方法によつて彼等の土地を耕作してゐた。原野農法とは臨時に原野の一部分を開いて耕作するが、収穫後は惜気もなく捨ててもとの原野に返してしまふといふ最も原始的なるやり方である。しかしそれから約百五十年を隔てたタキツスの頃になると、ゲルマンの耕作も進歩の跡を示していはゆる草地農法(Egartenwirtschaft)とはなつてゐた。草地農法とは開拓によつて予め原野地帯と可耕地帯とを区別しておき、可耕地帯の内部のみにて耕地の転換を行ふものをいふ。即ち収穫後の土地を原野には返へさず、次回の使用のために残しおくものをいふ。タキツスの記事によると、ゲルマンの村は一定の可耕地帯を有し、年々これを多数の地片に細分して各地片を抽籤の方法により各家に割当て、各家をしてその割当地片を利用させたが、収穫の後はこれを村に取上げ、翌年また新たな割当を行つてゐたといふ。
可耕地の外に宅地と共用地とがあつた。宅地とは家を取巻く或広がりの土地をいふ。そしてこれはその家の私的所有物ではあつた。各家はそれを他人に譲渡することもでき、子孫へ相続さすこともできたのである。又共用地(Allmende)とは森・牧場・水(Wald, Weide, Wasser)等をいふ。共用地は可耕地と同じく村民全体の有であつたが、可耕地のやうに各家の専属的利用には分与されず、村人共同の利用に委されてゐた。村人たる者はみな自由に共用地に立入つて放牧・狩猟・採木等の利用行為をなすことができたのであつた。
ロ 次にゲルマン人の家族生活を見ると、一夫一婦の原則を守つてゐたのは農民だけで、王・郡司・祭司・貴族その他生活に余裕あるものは多数の妻を持つたり、妾を畜へたりしてゐた。結婚年齢は以外に高く、男子は二十歳以上でなければ娶らなかつた。二十歳以下にて婦人を知れば男子筋骨の発達に害ありと考へてゐると、シーザーは書いてゐるのである。夫権は強く、妻に著しき不都合の所為あれば離婚することができ、妻の姦通を現場において発見すれば、殺しても差支ないとさへされてゐた。
家はいはゆる小家族であつて二世即ち親子と、未婚の弟妹とから成るを普通とした。三世即ち孫以下を含むといふことは例外的な現象でしかなかつたが、これはその頃土地に余裕があり、耕地を取得して独立の生計を立てるといふことが比較的に容易だつた当然の結果としてであつた。
女子は結婚によつて生家の人々と親族関係を断ち、婚家の人々と新たな親族関係をもつに至つた。女子が婚家で産んだ子も婚家の人々とだけ親族関係をもち、生家の人々とは親族関係をもたなかつた。従つてそこに女系を除外し男系のみを基礎とした親族関係が成立することとなつた。即ち自己と同一の母から出た者・祖母から出た者・母方の祖父から出た者はこれを除き、単に自己と同一の父から出た者・祖父や曾祖父から出た者のみを以て構成された親族団体が成立した。これを氏族といふ。氏族は相互に相続権を有し、共同して墓地を有し、そのうちの何人かが他から暴行を受ければ共同して復讐し、そのうちの何人かが他に暴行を加へれば共同して賠償の責任を負うた。
ハ 進んでゲルマンの階級関係を見ると、庶民の上に貴族があつた。貴族は軍事上の功蹟を過去にもつた家柄の人々で、多くの奴隷を所有し、土地や戦利品の分配についても庶民よりは多くの分前をもつてゐた。政治的には王・郡司・将軍・祭司等の顕官に選挙される特権をもつてをり、軍事的には平時から多くの青年を従士(Gefolgschaft)としてその邸内に養ひ、これに軍事的教練を施しおき、戦時にはこれにその身辺を護衛させつつ出陣しえたのであつた。
一六 政治及法律
イ ゲルマンの村は数個又は十数個集つて一つの郡を構成した。郡は独立の行政区であり、独立の裁判区であり、軍隊組織上の一単位でもあつた。郡は郡司・祭司・郡会(Hundertschaftsding)等の機関をもつてゐた。郡会は従軍能力ある自由人の全体の集合であつて、宣戦講和を決議し、民刑の裁判をなし、郡司の選挙をも行つた。郡司は通例貴族の家から選挙され、郡を代表して民会の決議を執行し、戦時は郡民を以て構成された軍団の指揮者ともなつた。
ロ 部族国は数個又は十数個の郡の聯合から成立した。タキツスの頃西ゲルマンには二十三個の部族国が並存し、各々独立の政治を行つてゐたのであつた。部族国には王・祭司・国会等の機関があつた。国会は従軍能力ある自由民全体の集合であつて、王や祭司を選挙し、宣戦講和をなし、民刑の裁判を行ひもしたが、郡会に比すると、やや形式的な存在となつてゐた。なぜかなら国会の場合には地理上の関係から全人民の集合が困難であつたために、事実それは一部の人民の集合に過ぎなかつたし、決議に際しても決議の内容は有力者が作り、国会はこれに形式上の賛成を与へるだけのことだつたからである。
ハ なほその外に一種の政治機関として祭司があつた。祭司は宗教上の儀礼を司るばかりでなく、民衆へ種々の宗教的禁忌を命じ、これに違反するものを民会(郡会又は国会)に訴へ、刑の執行にも携はつてゐたのである。いはば彼は古代社会の検事であり、公の秩序の維持者でもあつた。元来社会の秩序が輿論の力のみにて充分に維持できる間は宗教の必要さへもないが、輿論の力でそれが維持できなくなると、既存の社会秩序に宗教的解釈を加へ、神罰の脅威の下にこれを遵守させる必要を生じて来るのである。古代ゲルマンの社会において祭司が上述の通り強大な権威を振つてゐたのは、すでに社会の秩序が輿論の力のみでは守り切れなくなつてゐた証拠だつたと見られねばならないであらう。
ニ 最後に法律生活を見ると、当時の生活は堅い慣習の框の中を流れてゐた。何にしろ技術上の進歩といふものがなかつた結果として、社会の進歩が遅々、殆ど前後二時代の間に変化の跡を認めかねるありさまだつたから、社会意識の方も守旧的であり、ただ伝統的な行為の型を人々に押しつけてゐただけだつた。しかしそこにはすでに事実上繰返されてゐるに過ぎない行為の型即ちいはゆる事実上の慣習と国家がその遵守を要請してゐるいはゆる法たる慣習との区別を生じつつあつた。換言すれば国家は特に或種の慣行を取上げてこれに法たるの効力を附し、法としてこれを遵守すべきことを人民に命じてゐたのである。いはゆるゲルマン古法とはかかる慣習法のことに外ならない。制定法は当時はまだ生れ出てもゐなかつた。
ゲルマン古法の内容は第三章私法史において事項別に分析しつつ述べることとしよう。
第二節 中世初期の状態(五・六世紀—八・九世紀)
—ゲルマン人法・ローマ人法及勅令—
一七 ローマ帝国の崩壊
イ ゲルマン人は非常に繁殖力の旺盛な民族で、紀元一世紀の頃西ゲルマンだけでも五百万人を越えたらうと推算され、その後はなほなほ増加するばかりであつたが、ローマの国防の方は反対に弛緩してゆく一方であつた。よつて紀元三世紀頃からライン・ドナウの全線に亘つてゲルマン人の侵入戦が開始され、四七六年とうとう帝国を滅ぼし、その旧趾に沢山のゲルマン新国家を建設するに至つた。即ち今のイタリイには東ゴートやロンバルドが、今のフランスにはブルグンドやフランクが、今のドイツにはアラマンやザクセンが、今のスペインには西ゴートが、今のオランダにはフリイセンが、それぞれ建国に成功しえたのであつた。
ロ ではローマ帝国はなぜかう脆弱な終焉を遂げてしまつたかといふと、元来ローマ帝国は奴隷制度の上にその繁華を築き上げた国なのであつたが、奴隷制度のあまりにも極端なる発達は次のやうな意外な結果をローマ帝国の運命の上に及ぼして行つた——
その一は小地主・中小商工業者等の没落である。小地主・中小商工業者の層は、奴隷の大群を使役して大規模生産を行ふ大地主・大商工業者との競争に堪え得ず、徐々に没落の一踏を辿りつつあつた所へもつて来て、金融資本家の高利はこれに追撃の鞭を加へ、とうとう彼等を奈落の底に突落してしまつたのであつた。しかし奴隷使用社会の常として自由人は貧困化しても労働者とはならず、却つて一種の乞食となりルンペンとなり浮浪人となつてしまつたので、国家はかかるルンペン大衆の間に高つて来る革命気分を消散させるために、さまざまの方途を講じては見たが、ルンペン増加の大勢と彼等の間の革命気分とはどうしても医し去ることができなかつた。ローマがその政体を共和から帝政へ、さらに独裁専制へと移して行き、国家の権力を益々強化して行つたのも奴隷及ルンペン・プロレタリアートの間に漲る革命気分を鎮圧する必要から出たのであつた。第二は地方の荒廃であつた。元来ローマの戦争は敵国人を捕へてこれを奴隷とする目的から開始された場合が多かつたため、ローマの勝利は往々にして被征服民の奴隷化・被征服地の破壊を惹起したが、あとからそこへ派遣されて来る総督・収税吏・裁判官・兵士等々も亦人民に対する収奪の猛烈さにおいては戦争にも劣らぬ惨酷さを示したのであつた。人民から見るとローマ帝国とは人民の膏血を搾るための巨大な複雑な機関そのものなるかに見えたのである。ゲルマン侵入の当時ローマの人民がゲルマンの侵入者を救世主のごとくに欣び迎へたと伝へられるのも、かうした事情からであつたであらう。第三は大地主や大商人自身の行詰であつた。元来大地主や大商人が奴隷の大群を使役して大規模の生産を行ひ、よく莫大の利益を征しえたゆゑんのものは、人民大衆の生活になほ余裕があり、その購買力にまだ潤沢なものが残つてゐたためだつたが、田園の荒廃・都市の衰微・人口の減少・一般の貧窮化は商品の需要を減退させ、生産物の市場を亡滅させてしまつたのである。帝政の末葉には都市におけるマニファクチュアも、田園における農地経営もひとしく利益を挙げえざるやうになつてゐた。よつて大商人や大地主は彼等にとつて今や過剰物となり厄介者となり来つたところの奴隷を解放し、その企業を縮小して漸次小規模のものへと移して行つたが、それはただルンペン大衆の徒らなる増加と社会の一層の行詰とを招来するだけの事に終つた。要するにローマ帝政の末葉においては都市も田舎も貧者も富者も一様にみな出ることもできない袋小路の中へと押こめられてゐたのである。あらゆる階層がみな萎縮して相互争闘の意志を失ひ、社会発展の動力もそのゆゑに又休止してしまつてゐたのである。奴隷制度のおかげで勃興したローマ帝国は奴隷制度のたたりでまた亡滅したといはねばならない。
一八 ゲルマン新国家の政治
イ さてローマ帝国の廃趾に建てられた新しいゲルマンの諸国はどんな政治を行つたかといふと、まづ彼等は征服によつて獲得した新領土の1/3をそのままローマ人の所有に止めおき、残りの2/3を取上げて自分たちの間に分配してしまつたのであつた。分配の方法は森・牧場・水のごときは共用地として村又は村の聯合に与へ、耕地のごときは私有地として村内の各家に平等に分与した。即ちまづこれを平等の大さに細分し、抽籤の方法によつて各家へ分配したのであり、しかもそれは一時的な利用分としてではなくて、永久の所有地としてであつた。即ち古代からの耕地転換の風はここに棄てられ、各家はその耕地を子孫に伝へ、他人へも譲渡しうるやうになつたのである。
しかしゲルマンの人民が民族移動の結果その私有地の分量を幾倍かに増加しえた間に、王や王の臣下等はその財産を幾十倍幾百倍にも増加しえたのであつた。といふわけは新領土の面積は広大無辺であり、到底これを各家各村に分与し切れなかつたので、王は人民に分与したよりも遥かに多くの大面積を自己の臣下に与へ、自分自身もまたその私有地として広大な面積を取込んだからである。当時は公法私法の区別判然せず、王の取得したものは国有とはならずに王家の家産となつてしまつたのであつた。
ロ 政治の形態も民族移動を転機として大なる変化を見せて来た。以前の政治はあくまでも民衆的であり、王は民衆の意志を体してこれを指導してゐただけだつたが、民族移動の進行中、迅速な決定を要する事項を多く発生し、而して迅速な決定は遅鈍な民会の決議の能くしうる所ではなかつたから、勢ひ王権の強化を招来せざるをえぬこととなつたのであつた。新国家成立後も民会萎縮・王権伸長の形勢は止まなかつた。何にしろ新国家内にはローマの遺民が沢山雑居してをつたが、これらは民会出席の権能なき異民族のこととて、少くともこれらに対しては権力を以て臨まざるをえず、それに新国家内にはすでに貧富の懸隔・利害の衝突あり、これを越えて全体を統率するためにも権力強化の必要は剴切であつたからである。
もちろんそこには王権強化の運動の担ひ手となつた人々の一団もないではなかつた。従士がそれである。従士は王との間の特別関係に繋がれて王の相談役となり、王の命令の実行者ともなり、当時における破壊的急進分子として、民会の抑圧・王権の伸長のために邁進したのであつた。
ハ なほわれわれはゲルマン人がローマの皇帝主義を継承したことについて一言を添えねばならない。けだし王と皇帝とは観念上実際上大いに異る——王の権力は人民から発するが、皇帝の権力は神から発する。王の即位には宗教的儀式を要しないが、皇帝の即位にはそれを要する。王の権力は民会によつて制限されるが、皇帝の権力は民会を超越する。王は一民族を統率するが、皇帝は世界を統率する。王は同時に数人ありうるが、皇帝は一人しかありえぬ、とされてゐたのに、かかる絶対者としての皇帝が今やゲルマン人の上に現れ出て来たのである。カール大帝がそれである。大帝は分裂してゐたゲルマンの諸部族を統一し、一旦滅びた西ローマ国を再興し、ローマ教皇から帝冠を受けて皇帝の位には即いたのである。それこそゲルマン人の政治思想の最もラヂカルな変化を物語る現象には外ならなかつた。
一九 ゲルマン人法
イ 民族移動後における支配階級と被支配階級との分裂は社会統制の方法の上にも変化をもたらした。以前は主として宗教や慣習の力によつて社会の統制を行つてゐたのであつたが、今では権力的に制定された成文の法律の力に訴へて社会統制を強行せざるべからざる事態に立到つたのである。よつてゲルマンの諸国家はその成立後大抵五十年乃至七十年にして法典を作り、九世紀の初までには全部の新国家が法典をもち揃へることとなつた。実に四五〇年から八五〇年へかけての四ヶ世紀は西洋法律史上稀に見る賑盛なる法典編纂期であり、その後につづく四ヶ世紀即ち八五〇年から一二五〇年までの間の立法活動の、これまたあまりにも甚だしい寂寞さに比すると、雲泥の相違ではあつたのである。
ロ ゲルマン諸国家が民族移動後制定した成文の法典をゲルマン人法(leges barbarorum, Germanenrechte)といふ。
ゲルマン人法の制定手続は、王が有力な臣下の意見に基いて原案を作り、民会の賛成をえた上、ローマの学者をしてこれをラテン文に書綴らせるといふ順序であつた。当時のゲルマン語は未だ文言になつてゐなかつたので、文章にはみなラテン語を使用したのである。規定の内容はおもに刑法に関したが、親族・相続・物権等に関する規定もないではない。
ハ なほゲルマン人法制定の当時における各部族国の経済発達の段階はといふに、われらは各ゲルマン人法の内容を比較して見ることによつて、その制定の当時における各国の経済発達の段階を窺知することができる。例へばその中に規定されてゐる裁判所の構成の仕方・証拠の採り方・祭司の権限・刑罰の方法・犯罪の種類・土地移転の形式・結婚や離婚の仕方・親族相互間の権利等を見て、その当時その社会にはまだ農業共産制や氏族制度やが残つてゐたとか、すでにもう土地私有制度の発達や王権の発達やを見てゐたとかいふやうなことを窺知することができるのである。いまかやうな方法によつて法律制定当時におけるゲルマン各社会の発達程度を窺つて見ると、有名なLex Salicaの制定者であつたザリア・フランク族が最も幼稚な段階に位してゐたといふことがわかる。なぜかならLex Salicaはまだ農業共産制や氏族制度の多分の残存を物語つてゐるやうな規定を相当多く含んでゐるからである。(一)学者によると、世界のあらゆる立法中Lex Salicaほど原始的な社会状態を反映してゐる法律はないとさへいふのである。その制定年代は紀元後五一〇年頃であつたが、その規定の内容は紀元前四五〇年頃に出来た十二表法よりも、紀元前三七五年頃に出来たモーゼの律法よりも、否紀元前一九一四年頃に出来たハムラビーの法典よりも、遥かに幼稚な社会発達の段階を示してゐるといふのである。
ではゲルマン人法中最も進んだ社会段階を示したものは何であつたかといふと、ロンバルド族の法典Edictum Rothariに外ならなかつた。これは六四三年の制定に係つたが、王権の著しい伸長・私有財産制の立派な発達の跡を示してゐるし、商業の発生をも物語つてゐるし、ローマ法の感化・クリスト教の影響さへ仄聞させてゐるからである。
爾余のゲルマン人法例へばLex Alamannorum, Lex Saxonum, Lex Burgundionum等は上掲二つの法典の間に位する中間的な存在であつたと解せらるべきである。
一 Lex Salicaの日本訳は拙作・『蛮人法殊にLex Salicaに就て』(法学論叢・七ノ一)において見らる。なほゲルマン人法の詳細については拙著・西洋立法史四九頁以下参照。
二〇 ローマ人法
イ ゲルマン人法は法の効力に関しては属人主義をとり、自己の部民に対してのみこれを適用し、他の部民に対しては、その自国領内に住む者に対してすら、これを適用しなかつた。けだし当時の観念に従へば、法律は各部族固有の財宝であつたから、どうしてもこれを他の部民へは適用しえぬ筈であつたのである。ゆゑにその領内に他の部民、殊にローマの遺民を抱きもつ国においては、別にローマの遺民のために法律を制定し、これによつて彼等を規律して行く必要があつたのであつて、この結果、例へば今の南フランスに立国したブルグンド人や今のスペインに立国した西ゴート人やは、わが部民のためにブルグンド法典(Lex Burgundionum)や西ゴート法典(Lex Visigothorum)を作つたと同時に、わが領内に住むローマの遺民のためにも法典を作つたのである。かかるゲルマン征服者によつて作られたローマ遺民のための法典をローマ人法(leges Romanae)といふ。
ロ ローマ人法は王単独にてこれを作つた。当時はローマ人にしてゲルマン王に仕へてその廷臣となつてゐた者が少くなかつたから、王はかかる者共に命じて草案を作らせ、これを裁可して法律とはしたのである。しかし内容からいふと、ローマ人法は西ローマ帝国の末葉における皇帝たちの勅法の中から、実用性のある簡単な規定のみを拾つて少さく一纏めにしたものたるに過ぎなかつた。即ちそれは独創的な規定でもなければ大規模な法典でもなかつたのであるが、しかし都市も滅び、文化も亡び、商業も交通も寂びれ切つてゐた当時としては、却つてこの種の小法典の方が実際に適合的であつたのである。ゆゑにローマの遺民たちはゲルマン征服者の作つてくれたローマ人法典のみを使用し、ローマ皇帝たちの遺してくれた古典ローマ法の大体系は過去の帷帳の向ふへと捨て忘れて行つた。実にローマ人法こそは古代と中世との連絡を切断した立法史上の経界石ではあつたのである。
二一 カール大帝の勅令
イ カール大帝(768--814)は、すでに見たごとく、フランク族の王であると同時に、皇帝即ち諸部族の支配者でもあつた。だから彼は王としてフランク族のみに適用ある法律(lex)を作ることができたと同時に、皇帝として配下の部族の全部又は一部に通用する法をも作ることができた。カール及その子孫が皇帝たるの資格において発した法を勅令(capitularia)といふ。
ロ 勅令には独立勅令と附加勅令とあつた。独立勅令とは皇帝の大権事項例へば軍の統率・教会の統轄・宗教会議の召集・貨幣の鋳造・交通の設備・関税の徴収・公共の安寧秩序等につき皇帝の発した勅令をいひ、附加勅令とは皇帝が配下の部族の法律を改廃するために、その法律に附加して発した勅令をいふ。例へばロンバルド法改正のためのロンバルド附加勅令、ザクセン法改正のためのザクセン附加勅令等のごとし。
ハ カール立法の目的は帝権の伸長・帝国の統一・民会の圧迫等のためであつたと同時に、ゲルマン法のローマ化及クリスト化のためであつた。すでにゲルマン人がクリスト教に改宗した以上は法と道徳とも合体しなければならない。ゲルマン法はもつとクリストの教に聴き、もつとローマの思想を容れてみづからをより美しいものへ造替へなければならない、とカールは思立つたのである。そしてその結果は無数の独立勅令や附加勅令の落下となり、ゲルマン人法の文化化に寄与する所まことに大なるものがあつたのである。
第三節 中世中期の状態(八・九世紀—十一・二世紀)
第一項 庄園法及封建法
二二 人民戦線
イ 新国家の建設後ゲルマン人間における貧富の懸隔は益々甚だしくなつたが、さうなつて行つた原因の一つは開墾であつた。当時の規則によると、王の許可をえて荒蕪地を開墾すれば土地は開墾者の有となり、王の許可をえずして開墾すれば土地は一定の借地料の支払の下に開墾者これを使用しうるものとなつてゐたから、多くの奴隷や農奴を有した有力者たち、殊に王の重臣たちは、王の許可をえ又はえずして盛んに荒蕪地の開墾を行ひ、私有の土地の面積を益々殖やして行つたのであつた。王自身も開墾・租税・関税・罰金徴集・貨幣鋳造等の方法によつてその富を大にして行つた。王の左右には、王権政治の発達に伴つて多数の廷臣を生じ、これらを養ふためにも王はその富を掻き集める必要を感じてゐたからであつた。
ロ しかし人民にとり最も迷惑だつたのは国司(Graf)の制度であつた。国司は国司区(Grafschaft)内において王の重要な三つの権力即ち兵馬の権・徴税の権・裁判の権を代理しえたのであつたが、その地位は初めは世襲的でなかつたために、人民愛護の情に乏しく、冷酷に搾つて跡は野となれ式に引上げて行く傾向があつたのである。その収奪の猛烈さは古のローマの官吏にも劣らざるものがあつたのであつて、例へば当時の規則によると、人民の納めた罰金の2/3は王が取り、1/3は国司が取ることとなつてゐたので、国司は屡々過大の罰金を人民に課した。一六〇Solidiの罰金などといふ例は稀でなかつたが、当時は牛一頭の値一乃至三Solidi、一農家の全財産が一〇〇Solidi位であつたから、一六〇Solidiの罰金といへば、本人はもちろん本人と共同して支払の義務を負ふ一門一族の破滅をも意味する高額なる罰金ではあつたのである。又当時は距離上の理由その他から、人民の民会出席が不可能となつてゐたにもかかはらず、王や国司は屡々民会を召集し、不出席の廉を以て人民に高額の罰金を課した。又当時は兵役が一般の義務となつてをり、召集があれば人民は農事を抛擲し、武器を自弁して出征しなければならなかつたが、この事が人民を苦しめたこともまた非常なものであつた。
ハ かやうにして八世紀頃の農民の生活は疲労困憊、そのみじめさは四百年前のローマの人民にも劣らざるありさまとなつたが、それではローマの人民は官権の圧迫に押されて永遠に滅去つたのに、ゲルマンの人民はなぜ更正一番再び起上ることができたかといふと、われらの所見によれば、それはゲルマン人が官権の圧迫を押除けうる有力な或道具をもつてゐたからであつた。有力な或道具とは氏族制・農業共産制・民主制等々をいふ。これらの諸制度はすでに色褪せて力無きものとはなつてゐたが、それらを産み出した人民自治の根本精神だけはなほ脈々と波打つてゐたから、この根本精神に基いて新たな形ちの人民自治制度を建設することに成功しえたのである。それが庄園制度に外ならない。
二三 庄園制度
イ 王や国司の収奪に悩まされ抜いたゲルマンの農民が最後の切り札として投出したのは、土地の所有権を教会や地方の豪族の手へ譲渡して、その代りに生涯的の用益権を受取り、もとは自分の所有であつた土地を今は借地として使用するといふ方法であつた。この方法をとるときは、人民はただその保護主に対して一定の給付義務を負へば足り、国家に対しては保護主が代つて負担してくれるだけで、人民自身は何等直接の義務を負担しないのであつたから、これによつて人民は国家の飽くなき収奪から免れることができたのである。ゆゑに人民たちは起死回生の妙薬としてこの方法を盛んに使用したのであつて、例へばパリのサン・ジェルマン・デ・プレ修道院の古き土地台帳を見ると、カール大帝の頃、この修道院の広大な所有地の上には二千七百八十八戸の農家が存在してゐたが、その中の実に二千八十戸までは修道院に土地を与へてその代りに保護を受けた農民たちであり、他は奴隷、残りの僅か八戸だけが自由なる農民となつてゐるのである。いかに虐げられた百姓の群が、個々人としてではなくて一村又は一地方として、或は教会の下に、或は地方豪族の下に、その身を委ねて行つたかがわかるのである。
実に右のやうな、農民がその身を教会又は地方豪族の保護の下に委ねてしまふといふ方法は、国司からの無慈悲な圧迫を避ける最後の方法として、農民たちの巧妙にも案出したところのものではあつたのである。
ロ ところでこれを保護主の側から見ると、毎年農民が規則的に年貢を納めてくれるのはこの上もなく喜ばしい事だつたので、漸次彼等はこの関係を固定化し制度化して行くやうになつた。まづ彼等は農民が土地を売つたり、村を離れたりするのを禁じたのである。それから又農民が武器を執つたり党を組んだりすることをも禁じたのである。農民の土地売買と逃散離村とは保護主に対する消極的な反抗であり、農民の武装と徒党とは保護主に対する積極的な反抗であり、共に保護主の生活の破滅・支配の崩壊を意味したから、保護主としてはどうしてもこれらを禁ぜざるをえなかつたのである。斯くしてその初め完全なる自由人であつた農民は、数代の後には保護主から居住移転の自由を制限され、保護主の土地に束縛されて、その搾取に永遠に服従して行くべき運命のものとなり変つた。かやうな居住移転の自由を失へる農民を農奴といひ、農奴の保護者を領主といひ、領主の土地を庄園といふ。庄園は領主の私領であり、農奴は領主の私民であつた。従つて庄園の全国的拡布は取りも直さず国家の分裂・王権の没落を意味せるものではあつたのである。
カール大帝の没後庄園は欧洲の全般に広まつた。『領主なき土地なく、農奴ならざる人民なし』とまでいはれるやうな状態とはなつて行つた。
中には国司にして転身一回、王を離れて人民に味方し、任地にそのまま居据つて地方領主と化してしまつたものも少くなかつた。
二四 封建制度
イ 庄園制度の成立は兵農の分離・職業武人の発生を促した。なぜかなら庄園制度にあつては領主は自己に対する農民の反抗を不可能にするために農民の武装を禁止する必要があり、農民の側からいつても元来彼等が庄園の奥にその身を隠したのは領主一人に兵役の義務を負うて貰らひ、自分たちはこれを免れたいためであつたから、兵農の分離は農民の必然に希望する所でもあつたからである。
それにもう一つの有力な原因が協同した。それはアラビヤ人の侵入である。一体に掠奪的遊牧民の軍事能力が農民のそれに優るといふことはすでにのべたが、この一般則は、アラビヤ人の場合にも妥当したのであつて、かの優秀な軍馬に跨り隊を組んで遠征し来るアラビヤ人の侵入は、土に匍匐するヨーロツパの農民から見れば、魔軍の襲来のごとくに恐ろしいものだつたのである。よつてゲルマンの諸王はアラビヤ人の侵入を前にして急激なる兵制の改革を断行し、従前の歩兵中心主義を棄てて騎兵中心主義に進まねばならぬこととなつたが、その結果が兵農の分離となつたことはいふまでもなかつた。なぜかなら軍馬を蓄へ甲胄を持つことは貧農には可能でない、それは富有な領主たちのみの特権とならざるをえなかつたから。
遂にカール大帝に至つて人民を所有地の大小に従つて貧富の二層に分ち、富者にのみ兵役の義務を課し、貧者には兵役の義務に代る僅少の献金義務を課することとしたので、兵農の分離は制度的にもここに明立し、武士は戦争に出て政治にも参与する自由な人間、農民は政治的自由のない・ただの働くばかりの人間となつてしまつたのである。
ロ ところでこの領主の武門化といふ新しい事実はさらにまた一段の変化を波立てざるをえなかつた。武門相互の連絡といふ現象がそれである。
けだし領主の武門化は領主間の争闘を激化させた。武力を以て他の領主を倒し、その庄園を奪取するといふことが、殆ど武門の営業とはなつて来たからである。ここにおいて小なる武力を有するに過ぎない領主はその庄園の一部分のみを自己に留めて他の部分をより大なる武力を有する領主に献げ、これと保護服従の関係を結んだ。大なる武力を有する領主もまたこの庄園の一部分のみを自己に留めて他の部分を一層大なる武力を有する領主に献げ、これと保護服従の関係を結んだ。漸次このやうに階級的に上昇して遂に最大の武力を有する最大の領主にまで到上したのである。逆にいへば大領主はその庄園の一部分を自己に留めて他の部分を中領主に給与し、中領主もその庄園の一部分を自己に留めて他の部分を小領主に給与し、順次この関係を下降させて最小の領主にまで及んだのである。かくのごとく上下の関係に連絡づけられた庄園領主の網を封建制度といふ。
ゆゑに封建は領主と領主との間の関係であつて領主と農奴との間の関係ではない。農奴はその領主が他の領主と封建関係を結び、他の領主の臣下となつた場合にも、領主の主人たる大領主に対しては何等直接の義務を負はず、ただ自己の領主に対してのみ一定の義務を負担したに止つた。
二五 庄園法
イ 庄園法とは庄園領主と農奴との間の関係及農奴相互間の関係を規律した法律をいふ。もとよりそれは国家の作り与へたものではなくて、庄園領主の裁判例と地方の慣習との結合から成つたものであつたから、その内容は庄園毎にかなりの相異を示してゐたが、根本の性格は相類し、いづれもみな庄園の二重機構(,,double mechanism``)を反映してゐたのであつた。庄園の二重機構とは庄園が支配的な機構と共同的な機構とを併有することをいふ。けだし庄園は支配者に対する民衆の反抗として生れたものであつたから、当然にそれは権力支配的な性格と民衆共同的な性格との二面をもたねばならぬのであつた。従つて庄園の法律もまたこの二面を表現してゐたのであつて、概言すると、領主と農奴との間は支配服従の関係であり、農奴相互の間は仲間的共同的な関係であつた。
ロ まづ庄園法の支配法的方面を見ると、庄園内の農民は定期日に領主の直属地を無償にて耕作する義務を負つてゐたし、又農民自身の自作地から取つた生産物、例へば穀物・葡萄酒・亜麻・牛・豚・鶏・卵等の中から一定の分量を領主に納入する義務をも負つてゐた。庄園内には農民以外に鍛冶工・石工・車工・煉瓦工・織工・製革工・画師・金細工師・木彫師等も居住してゐたが、これらの人々も無償で領主のために或限度の労働をしたり、又は自己の手工業的労働の生産物の或部分を納入したりしなければならぬのであつた。何にしろ貨幣経済の未だ発達してゐなかつた時代のこととて、庄園の人民は自然的な方法にて、即ち労務又は生産物の形ちにて、領主に対し義務を負担してゐたのであつた。
領主が右のごとき年貢の規則的な流れに対する権利を確保するために、人民を土地に縛りつけ、その居住移転の自由を制限してゐたことについては既述二三のロを参看せよ。
ハ 次に庄園法の仲間法的方面を見ると、庄園内の農奴はみな庄園地の利用権者であつて、或者は1の割合にて、或者は1/2 1/3等の割合にて、庄園地の利用をなすことができた。従つて全農奴のもつ土地利用権の総数は数字的に一定してゐたわけでもあつた。ではこれらの農奴にそれぞれの利用地を割当てる方法はといふと、まづ領主が庄園内の数ヶ所において分散的にその年の耕区を選定し、各々の耕区を全農奴がもつ土地利用権の総数と同じ数に細分するのである。そして後抽籤の方法によつて各農奴をして各耕区において分散的にその利用権数に相当する利用地を取得させるのである。なぜ各農奴をして一耕区内においてその利用分の全部を取得せしめなかつたかといふと、一耕区内のみにてその全利用分を取得させるときは、各耕地の地味地勢の不同なるがために、不公平な結果を生ずる虞があつたからである。
各農奴は割当てられた自己の利用地のみを耕作し、そこからの収穫だけを自己のものとすることができた。しかし蒔種や収穫には一定の規則があつたのであつて、一例をいへば全農奴が同時に収穫を行はねばならなかつた。これは各家が別々にその利用地に立入ると、各家の利用地が接壌してゐた関係上、労働の際他家の土地を荒す心配があつたためである。
庄園には又附属の牧場・森・水等があつたが、これは各家の共同的利用に委ねられてゐた。各家はこれに自由に入会つて、定められる規則に従ひ、伐木・放牧・狩猟等の利用行為をなすことができたのである。
領主も一面また農奴の保護者として現れた。彼は農奴のために共用地たる森・牧場・水等の利用規則を作つたり、土地耕作上の便宜を図つたり、道路を修理したり、水路を穿堀したり、橋梁を架けたり、庄園内の安寧秩序を維持したり、警察の事はもちろん家畜の衛生、婦人労働者の保護にまで留意してゐたのであつた。
ニ 各庄園には庄園裁判所があり、農奴相互間の事件や農奴と領主との間の事件やを審理裁判してゐた。裁判の内容は庄園内の慣例を基礎にして領主これを作り、これを言渡した。
降つて十三世紀以後になると、庄園裁判所の判例や庄園内の慣習やらを蒐集整理した成文の庄園法が各地に出来上がつた。それらを村法集(Weistümer, Dorfordnung)といふ。
二六 封建法
イ 封建法とは封建主君と臣下との間の関係及同一主君の下に立つ臣下相互の間の関係を規律した法律をいふ。
封建関係は庄園関係のやうな非自由人に対する自由人の支配関係ではなくて、完全なる自由人相互の間における契約関係であつたから、その内容は当事者の意思によつて相異せざるをえなかつたが、ごく普通の封建契約について見ると、当事者の一方即ち主君は土地その他の継続的使用に堪えうる利権を他方即ち臣下に与へ、臣下はこれを占有し使用し収益する代り、主君に対して勇気と忠実とを以て武士的勤務に服することを要したのである。即ち臣下は主君の命令に柔順に従ひ、主君の身体財産名誉に不利益をもたらすべき一切の行為を避け、危急の場合に処しても忠実に主人を護衛すべきことを要したのである。かかる封建的忠誠に反することを反逆(Tolonie)といふ。主君に対して、その体面を汚すやうな種類の訴を提起したり、主君の犯罪を告発したり、民事刑事の訴において主君に不利益なる立証をなしたりすることも反逆の一種だと見られてゐた。戦争の場合には、その公戦たると私戦たるとに論なく、臣下は主君の召集に応じて従軍しなければならなかつた。平時においてもまた主君に対して金銭・馬匹・地方特産物等を捧げる必要があつた。
ロ 主君は臣下に対して保護の義務を負うた。臣下が封地たる土地を使用収益することを妨害せざるがごとき、臣下の生命・身体・財産の安全を保証するがごとき、臣下が他より侵害を受けた場合にこれを保護するがごときこれである。
ハ 臣下相互の間に争を生じた場合には主君はみずから裁判長となつてこれを審理裁判し、主君と臣下との間に争を生じた場合には、主君は自己の他の臣下を以て構成される封建裁判所をしてこれを審理裁判させた。
十二・三世紀になると、封建主君中その臣下との間の封建関係を成文化する者を生じたが、かかる成文封建法中最も有名なものをロンバルドの封建法典(liber feudorum)とする。これはロンバルド地方の封建関係に関する学説と慣例とを整理収載したものであつたが、ドイツ・フランス等の主君たちもこの書を継受し、法律としてこれを使用したから、同書は封建法に関するヨーロツパの普通法とはなつたのである。編纂年代は十二世紀頃。
第二項 教会法
二七 ローマの社会とクリスト教
イ クリスト教はその初めローマ帝国から国家秩序の破壊者として恐れられ禁じられ迫害されたにもかかはらず連戦連勝、止め難き勢を以て前進し、ローマの精神界を征服し、国権をも凌駕する一大勢力となつたが、そのここに至れる原因はといふと、すでに見たごとく、ローマ帝政の末葉においては奴隷・解放自由人・小農・中小商工業者の層はもちろん、大地主・大商人の層もまた救ふべからざる破滅状態に陥り、階級相互間の争闘意志も失はれ、社会発展の動力もまた休止してしまつてゐたのであつた。そこにはもう何の希望も何の努力も見られなかつた。自分たちの住む世界が日一日と暗い奈落へ落ちて行くのを感じたにもかかはらず、この趨勢を喰止めようともせぬほど、ローマ人の精神は、肉体は衰へ、自己自身の力に対する自信力も失ひ果ててゐたのであつた。だから彼等としては一縷の望みを奇蹟の作用にかけ、天来の力によつて世界が一気に明るくなるのを夢みるか、何もかも諦めはてて滅びるがままに滅びて行くかの外はなかつたのであつて、現に当時の精神界を見ると、諦めの哲学・不安の思想などが流行してゐる。ストア哲学や新プラトー説がそれであつて、これらによると、肉体は魂の煩累であり、精神の束縛である。真の幸福は肉体からの逃避によつてのみえられる。この世の感覚を完全に離脱して孤独な心の世界に深く沈潜して行つたときに、人間は初めて幸福となるといふのであつて、後日のクリスト教の教義と不思議なる一脈の暗合を示してゐたのであつた。又そこには奇蹟や予言をよろこび迎へる風も現れてゐた。実に当時のローマ人は何か或驚異的な出来事の出現を心に求めつつ、デマと蔭口とに、頼りなきその日その日を送つてゐたのであつて、例へば某地に某予言者が現れ、飢饉の襲来・疫病の発生・軍隊の暴動・外敵の侵入を予言したから、きつとそのやうな事実が現れるだらうとか、果してその通りに現れたとかいふことが、彼等の日常の話題であつたのであつた。彼等はもうありうべき事とありうべからざる事とを区別するだけの能力を失つてゐたのである。それは虚構と誇張の時代であり、狂信と熱狂との時代であり、来るべきクリスト教狂信時代のために燃え上がる燃料を用意しつつあつた時代であつた。クリスト教が燎原の火の勢を以てローマの精神界を席巻して行つたのは、ローマ人の間にかうした心的準備がすでに出来上つてゐたからに外ならなかつた。
すべて宗教は単なる精神の作用ではない。それは社会の現実的な諸関係から規定される必然的な気分である。われらはクリスト教の成立の基礎としてローマの社会的廃頽と精神的疲労とがあつたことを見逃してはならぬのである。
ロ しかしクリスト教は単なる精神運動ではなくて一種の経済運動でもあつた。初期の教会史を繙いて見ると、使徒たちはローマ帝国の恐るべき弾圧の下を潜りぬけつつ所々方々に出没して到る所に小さな沢山の教会を作つてゐる。そしてかかる小教会の基礎が固りかけると、それらを連絡づけ組織づけて一層大なる統一的勢力にまで高めてゐる。最初の信者は大抵落ちぶれた小農民や零落した商人などであつたが、これらの人々は各自少しづつ持寄つて教会財産なるものを作り、これを総有し、これを以て信徒中の病者や困窮者を救つてゐる。だから病者や困窮者にとつてはクリスト教会に入ることによつて精神上の慰安をうるばかりでなく、生活上の救済をも受けえたのであつた。それは決して私有財産を否定する団体ではなかつたが、同胞博愛の精神に基く組合ではあつたのである。従つてかかるものの急激なる普及は既存の経済秩序の破壊を招来することとなるべく、それこそは実に宗教の仮面を被つた一種の経済運動といふべきものであつた。時の勢力がクリスト教に対して極端な弾圧を加へたのもかうした事情からであつたであらう。
二八 中世の社会とクリスト教
イ 中世に入つてからのクリスト教は、しかし、上述のやうな破壊的性質を失つて、すつかり妥協的調和的なものと変つてしまつた。けだしローマにおいてはクリスト教は、それに向つて戦を宣せねばならぬ多くのものを発見したが、中世においては却つてそこに是認し支持すべき多くのものを見出したからである。中世こそはクリスト教にとり殆ど理想の天地であつた。
ロ 試みにいま中世のクリスト教の教則を見ると、それは例へば『他人の過失を寛恕せよ』とか、『人には人に誇るべき何ものもなし』とかいふやうな仁慈と愛憐・平和と平等の教へを説いてゐるが、これは当時の武士に対する教へとしてまことに適切なものであつたであらう。なぜかなら中世は武士が軍事的権力を以て農奴や手工業者をおのれに隷属させてゐた時代であつたから、社会の分裂を防ぎ、階級間の摩擦を少くするためには、仁慈の道を武士に説き、彼等の貪慾を或程度で抑へてしまふ必要があつたからである。又中世のクリスト教は、『この世の辛苦に堪へよ』とか、『地上の富を愛するな』とか、『神の御手におのれを委せよ』とか、服従と忍堪・克己と制慾との道を説いてゐるが、これも農民や手工業者に対する教としてはさうなければならぬ所であつたであらう。なぜかならこれらの人々は粗末な家に住み粗末な食物をたべながら、領主たちのために無償で労働し、無償で労働の生産物を献納しつつあつたのであるから、その不平の鎮静剤として彼等をして忍堪の美徳を携帯させておかなければならなかつたからである。又当時のクリスト教は、『各人その分を守れ』とか、『上を見るな下を見よ』とか教へてゐたが、これも、一種の身分社会であつた中世においては、各人をしてその分だけを守らせておく必要があつたために外ならなかつた。
クリスト教の教義ほど中世の政治経済秩序に適合したものはなかつたのである。
二九 教会法の管轄
イ 教会法とは教会生活に関する法をいふ。即ち教会の組織・教会と信者との関係並に信者相互の関係を律する法をいふ。けだし教会は初めは主として道徳的・宗教的規範を以て信者の生活を統制してゐたのであつたが、教会権力の急激なる伸長は信者統制の方法に変化を生ぜしめ、遂に権力と法とを以てこれを規律するやうになつたのである。
ところで信者の大多数はもちろん俗人であつたから、教会法はつまり、僧侶だけの法ではなくて俗人の法でもあつたのであつた。実に当時のヨーロツパ人は一定の事項については世俗の法律に服さずに教会の法律に服し、教会裁判の判決を受けてゐたのであつて、かやうにそれが俗人の生活にも渉つてゐたといふ点に西洋の教会法の特色があり、それがもつ法律史的重要性も潜むのである。(一)
一 教会法の発達史を見ると、教会は初めはもちろん不法の団体であつたが、事実上そこには彼等の間の特別法としての教会法が芽生えつつあつた。これを使徒教会法(apostolisches Kirchenrecht)の時代といふ。一—四世紀がこれに当る。(二)クリスト教がローマの国教となつてからは、国家も亦教会法の制定者として立現れた。教会は教化及救貧といふ国務の一部を担当する公の団体だといふことになつたため、国家もまた法を発して教会の管轄や組織を定めるやうになつたのである。これをローマ教会法(römisches Kirchenrecht)の時代といふ。四—八世紀がこれに当る。(三)ローマ滅亡の後は教会も国別に分裂し、各国王の統制を受けることとなつたから、この時代の教会法は各国王の命令や各国王の召集する宗教会議の決議によつて作られた。これをゲルマン教会法(germanisches Kirchenrecht)の時代といふ。八—十二世紀がこれに当る。(四)その後はローマ教皇の権勢がいよいよ絶頂に達し、僧侶の任免も宗教会議の召集もローマ教皇の命令によることとなり、教会法もローマ教皇の訓令(decretales)として作られた。これを教皇教会法(päpstliches Kirchenrecht)の時代といふ。十二—十五世紀がこれに当る。ここでは主として教皇時代の教会法を見る。
ロ 俗人生活のいかなる面が教会法の支配に服してゐたかといふと、約言すれば神事(geistliche Angelegenheiten)の観念に入る一切の行為がそれであつた。即ち(一)まづ教会生活の安寧秩序を乱すごとき行為は教会法上の罪となつた。例へば教会盗・教会冒涜・魔法使・異端的信仰。教会が定めた一定の平和日又は平和地において私闘を交へることも教会生活の安寧を乱す所為として教会法上の罪となつた。(二)教会の収入に関する事項も教会法によつて規定された。例へば教会への納税・教会への寄附。(三)クリスト教上の罪悪(Sünde)の観念に入るべき一切の行為もまた教会法によつて規定された。例へば悪意の行為・利子の徴収・暴利的売買・奴隷や外国人の虐待。(四)教会における儀式を伴ふすべての行為も教会法によつて規定された。例へば婚姻・婚約。子の嫡出に関する争も婚姻に附随する事項として教会の管轄に入つた。(五)クリスト教上の宣誓を伴つた契約の効力や遺言の効力なども教会法の規定に服してゐた。
三〇 教会法の重点
イ 私法の領域において教会が重点をおいたのは、財産法では利子の禁と暴利の禁、人事法では婚姻の禁と離婚の禁であつたから、これらについて説明を加へておくと——
教会は地主が地代を取つて土地を貸し、家主が家賃を取つて家を貸すことは許してゐたが、金主が利子を取つて金銭を貸すことは許さなかつた。これは土地の貸借・家屋の貸借は中世の経済生活にとつても欠くことをえぬ行為であつたが、金銭貸借の方は当時の経済状態が大資本を要求するほど進んだものでなかつた関係上、必要的ではなかつたし、たまたま行はれれば、それは貧民が借銭を以て一時の急を脱せんがために外ならなかつたから、当時の法律感情としては、たとへ金銭貸借は是認しても、利子を取ることだけは罪悪視せざるをえぬのであつた。教会は即ちこの思潮に棹さして厳重な利子の禁を立てたのであつて、それによると金銭貸借の場合には単に元金の返還を受くれば足る、元金以上のものはいかなる形ちにおいても受くることをえない、衣服食物の形ちにおいても、労働の形ちにおいても、とにかく元金以上の返還を受ければ利子の収受として罰せらる、他人の名義で貸金して利子を取つても、他人から借入れた金を更らに貸附けて利鞘を取つてもみな利子の禁に触れる、土地を質として取つた場合には、その土地からの生産物が元本額に達したと同時にその土地は返還せねばならぬ、それ以上生産物の収取をつづけてゐればこれまた利子の禁に触れる、信用取引の場合にも代金は現金取引の場合と同一でなければならぬ、この際もし現金取引以上に高く売るならば、それだけが利子となつて罰を受くと定めてゐたのであつた。それは実に利子による貨殖に対しての一大鉄槌であつたのである。
ロ 次に暴利の禁を見ると、教会といへども売買取引を否定はしなかつたが、しかしそれは一定の正当な条件の下に行はれねばならぬとしてゐた。例へば(一)売買の目的物に関しては、それは一般人の生活に必要なる物に限られねばならぬがゆゑに、一般人の生活に不必要又は有害なる物の売買・殊に奴隷の売買・官位の売買・僧官の売買・城の売買・都市の売買・領土の売買・酒毒物の売買等々は無効である、土地の売買は同じ領主を戴く人民相互の間においてならば有効であるが、領主を異にする人々の間ならば無効であるとしてゐた。(二)価格に関しては、致富の目的のために定めず、自家の生計費のために必要なる限内においてこれを定むべしとしてゐた。これを公正価格(pretium justum)といふ。公正価格は小売商の場合ならば、仕入原価と運送費と自家の生計費との和によつて決定された。これを越えた高さにおいて売れば暴利として一定の罰を受けたのである。(三)もちろん偽物を売り瑕疵ある物を売ることも禁じられ、(四)他人の物の売買も禁じられ、(五)豊年の際穀物を買占めおき飢饉の際高く売る行為のごときは殊に重い罪として罰しられてゐた。
つまり教会は公衆のための商業(negotiatio politica)と自己の衣食のための商業(negotiatio oeconomica)とは許したが、致富のための商業(negotiatio lucratica)は禁止してゐたのである。それは利己的経済活動への完全なる封鎖であつた。
ハ 婚姻に関してはどうだつたかと見ると、教会は婚姻もまた正当な一定の条件の下にこれを締結せねばならぬとしてゐた。即ち婚姻の故障については、重婚の禁・異教徒との婚姻の禁・血族婚の禁・姻族婚の禁・縁族婚の禁等々を多数羅列して配偶選択の範囲を厳重に制限し、婚姻締結の方法については、当事者は双方みづから僧侶の面前に出頭して婚姻締結の意思を方式に従つて交換しなければならないとし、離婚に関しては、神の結びたまへるものは人これを離すべからざるがゆゑに、一旦結婚の後はいかなる事態生ずるとも離婚をなすことをえずと定めてゐたのであつた。これこそは人間の性的交通の自由に対する峻厳無比の取締であつたのである。
ニ その他教会法は、刑法においては正当防衛を認めて犯罪成立の場合と不成立の場合とを判別し、応報主義をとつて罪と罰との均衡を図り、人格法においては奴隷の待遇を改め外国人の地位を高め、法人法においては社団や財団に人格を認め、時効法においては時効取得の重要なる要件として占有の適法性を要求し、相続法においては遺言の効力を認め、訴訟法においては書面審理主義をとつて審理を慎重にし、裁判所構成法においては三審制度を立てて上訴の道を開く等々、後世へも影響を与へたところのさまざまの規定を含んでゐたのであつた。
ホ 要するに教会法は中世生活の力強き保証者であつたのである。中世の生活は経済的には一家の生計費をうる程度に満足し、性的にはただ一人の異性を守るに堅かつた時代だつたから、かかる時代の秩序を破る所為即ち営利のための行為や享楽のための行動やは重大なる非行として排撃せざるをえなかつたのであつて、教会法こそは、その任務として、かかる非行の排撃に当つてゐたのである。中世の社会経済生活がよく安定をえ、よく秩序を保ちえたのは教会法の作用による所決して鮮少ではなかつたであらう。
法の効力からいふと教会法は世俗法に先つて行はれた(Kirchengesetze gehen den weltlichen vor.)。即ち当時のヨーロツパには無数の庄園法や封建法や地方法や都市法やが入り乱れて存在してゐたのであつたが、これらの法律は教会法と牴触せざる限りにおいて行はれたに過ぎず、牴触した部分は教会法から変更を受けることを免れなかつた。これを教会法の世俗法変更権といふ。教会法の世俗法変更権は世俗法相互の間の対立を除き、法源の分裂から来る不便を或程度まで喰止めることができた。実に教会法は庄園法・封建法・都市法・地方法等々のための共通の地盤となり、これらの法のもつ欠陥を補填し、これらの法相互間の対立を緩和させるといふ貴重な役割を果してゐたのであつた。
三一 教会法の法源
イ 教会立法の形式は時代によつて大いに異つたが、七世紀以後の形勢を見ると、各国の王は自己に自己領内の教会を支配する権ありと考へ、みづから僧侶を任免し、みづから領内の僧侶を集めて国内宗教会議を開かしめ、国内にのみ通用ある教会法を決議させてゐたのであつたが、九世紀以後における王権の衰微はローマ教皇をして教権独立のチヤンスを捉へしめた。教皇によれば教皇は日であり、国王は月である、後者はその光りを前者から受けてゐるといふのであつた。十二世紀以後に及ぶと教皇は宗教国家の独裁君主となり、無限の権力を一手に掌握するに至つた。宗教会議も今では教皇の召集によつて開かれ、その決議も教皇の承認を受けねば法となりえぬありさまとなつた。古来の教会法源も教皇から連発される命令の作用によつて多大の改正を受けてしまつた。教皇の命令を訓令(decretales)といふ。十二—五世紀は訓令の作用により教会法の形成された時代であつたのである。
ロ 最後に教会法の法源集を見ると、十二世紀の前半にボローニヤ大学の教師Gratianが、古来の宗教会議の決議や教皇の訓令の中からその頃なほ効力を保つてゐた法源のみを拾つて有名な一つの法源集を作つた。これをDecretum Gratianiといふ。
しかしDecretum Gratianiの出た以後において教皇の訓令の発布は却つていよいよ頻繁となり来つたので、一二三四年教皇Gregor IX (1227--1241)がGratian以後の訓令を集めた一つの法典を編纂した。これをLiber Extraといふ。Decretum Gratianiが私人の私著であつたのに反して、Liber Extraは官の編成にかかる統一ある一の法典ではあつた。
Liber Extra以後の諸教皇の訓令は一二九四年教皇Bonifaz VIII (1294--1303)によつて編纂されてLiber Sextusとなり、Liber Sextus以後の訓令は一三一七年教皇Clemens V (1305--1313)によつて編纂されてClementinaeとなつた。いはゆる教会法大全(Corpus juris canonici)とは、以上四個の編纂物即ち(一)Decretum Gratiani(二)Liber Extra (三)Liber Sextus(四)Clementinaeを主たる組部成分とし、これにClemens Vの次の教皇Johann XXIIの訓令をも附加せしめて出来た編纂物に対する便宜上の総称である。