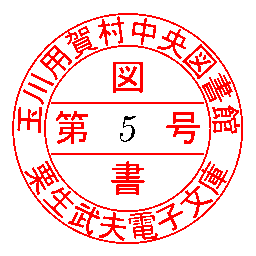
一 序 説
他人の動産に工作を加へて新物(nova species)へ転化させた場合に関して、ローマの法律学者の間に学派的な争ひがあり、プロクルス派(Proculiani)は新物の上に新所有権が成立し、加工者の所有となると見、サビーヌス派(Sabiniani)は新所有権の成立を否定し、従来の所有権がそのまま変形物の上に存続すると見たといふことは、ローマ法学の一頁を繙いた人の、誰れでも承知してゐるところであるが、かかる学派的論争に関して、Czyhlarzは注目すべき意見を吐いた。曰く——自然経済の社会においては、各家がそれぞれ自家の必要品を製作し、而も自家所有の材料を以てこれを製作してゐたのであるから、おのづからそこに材料本位の思想を生じ、加工変形物をも材料の所有者(dominus materiae)へ帰属させる。すなわち他人がわが材料を以て何物かを製作せる場合にも、われは加工者の行為を跡方もなく否定し、何の補償もなしに、その変形物をわがものとなすことができると見る。ところが一旦自然経済の時代を去つて貨幣経済の時代へ移り、又、奴隷労働の時代を過ぎて自由労働の時代へ進むと、自由人にして製作労働に従事するものを生じ、他人がわが材料を以て新物を製作せる場合には、われは加工者の創作活動に敬意を払ひ、新物上の新所有権を加工者へ委譲せざるべからずと考へるに至る、と(一)(二)(三)。
本稿においてわたくしは、ローマ法における加工の歴史ではなしに、ゲルマン法におけるその歴史を取扱はうとするのであるが、ここでもまた自然経済から貨幣経済への転換が、加工法の歴史を一変させたやうにおもはれてならない。なぜかならゲルマン法もローマ法と同様、もとは材料主義の見地に立ち、加工は材料を変形させるだけで新物を新生させるのではない、従つて加工変形物の上には材料の所有権が存続し、材料の所有者が加工変形物の所有者となると見てゐたが、ルネッサンス期に入つて人間の創作活動が華々しく発展するや、創作尊重の思想を生じ、加工は材料の単なる変形ではなくして新物の創造である、さうしてその上には新規の所有権が成立し、加工者その人に帰属するに至る、と見るやうになつたからである。概言すると、中世の旧統尊重の時代は材料主義。近世の創意尊重の時代は加工主義。それも初めの間は手工業者即ち労働する人を『加工者』と見、これに加工物を帰属させてゐたが、後には企業者即ち労働を命ずる人を『加工者』と見、これに加工物を帰属させるに至つたといふことが、以下の叙述から明かとなつて来るであらう。
一 Czyhlarz in Glücks Pandektencommentar, Serie der Bücher 41 und 42, 1. Th. S. 317 ff., 355 ff. Sulzerも、プロクルス派の加工説の経済的前提を検討して、結局、自然経済から貨幣経済・奴隷労働から自由労働への移行が、同派の創作本位の加工説を発生させた原因だつたと論結した(A. Sulzer, Der Eigentumserwerb durch Spezifikation 1884 S. 39 ff., 97 ff., 133 ff.)。
二 Czyhlarz一派の見解に反対したのは、Sokolowskiである。曰く——Czyhlarz一派の見解は、法源の解釈に無理があるばかりでなく、理論にも無理がある。なぜかならCzyhlarzは、自然経済の時代には材料本位の加工説を生じるといふが、この時代の加工者は自己の材料ばかりでなく、自己の労力をも使用してゐたのであるから、もし生産の様式が原因だつたとするならば、材料本位の加工説と共に、労力本位の加工説をも生ずべかりし筈だつたのではないかと(P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht I. 1902 S. 72, 102)。
しかし自然経済時代の加工は、専門の職人の所為ではなくて、素人の所為たるに過ぎなかつた。加工とはいつても、それは材料の表面に簡単な変化を与へるだけで、これを新物に転化させるほどのオリヂナリチイは欠いてゐたのであるから、自然経済時代の加工説が、労力よりも材料を重んじ、材料の所有者に加工変形物を帰属せしめんとしたのも、自然の経過だつたと見ていいであらう。
三 Sokolowski自身は、ローマにおける二つの加工説の対立をどう説明したかといふと、当時における二つの哲学思想の対立に帰因させたのであつた。曰く——ローマの思想界にはストア哲学を奉じる一派と、アリストテレス哲学を奉じる一派とがあり、前者が重きを質量(Materie)におき、質量こそは形式の変化を越えて存続する永遠の支盤なりと見たのに対して、後者は重きを形式(Form)におき、形式こそは内容の多様を統一する構成的な原理なりと考へた。ゆゑに前者の影響の下に立つ法律学者は、おのづから材料主義へ走り、材料は形相が変化しても死滅せず、従つて材料の上に成立せる所有権もまた死滅せずと考へざるをえなかつたのに反して、後者の影響の下に立つ法律学者は、おのづから加工主義へ走り、形相が変化すれば物自体も変化する。従つて在来の所有権は死滅し、新物の上には新所有権が成立するに至ると考へざるをえなかつた、といふのである。即ちSokolowskiによれば、ローマにおける加工説の対立は、資本とか労働とかいふ国民経済学上の概念から来たのではなくして、物の同一性又は新規性に関する自然哲学上の見解に由来したといふのである(Sokolowski, a. a. O. S. 71 ff., 92 ff.)。
Dernburgもまた同一の解釈を取つた(H. Dernburg, System des römischen Rechts I. 1911 S. 344 ff.)。
二 材料主義の時代(十二—五世紀)
さてゲルマン法上、加工に関する規定の散見するやうになつたのは、十三世紀以後のことであるから、端初をこの時代にとつて説起すと、十二—五世紀における加工製造業は、いはゆる手工業(Handwerk)の様式によつてゐたのであつたが、この様式の下においては、手工業者は、自己の家庭内で製作に従事してゐた。彼は材料の所有者であり、道具の所有者であり、且つ仕事場の所有者でもあつた。もし彼が紡績工だつたとするならば、彼はわが畑で亜麻を作り、妻や娘の手をかりてこれを晒らし、紡ぎ、これを糸にしてゐたであらう。もし又彼が織工だつたとするならば、彼はみづから近隣を歩き廻つて経糸・緯糸を買集め、やはり妻や娘の手をかりてこれを染め、これを織り、消費者なり地廻りの商人なりへ売却してゐたであら(一)う(二)。ゆゑに糸なり布なり、彼の製作品はみな彼の労力の結晶であり、熟練の成果でもあつたが、しかし当時の加工は何といつても幼稚であり、単純であり、材料の形相に些少の変化を与へる程度に止つてゐた。それは、『葡萄を以て葡萄酒を作り、木材を以て船・箱・椅子を作り、羊毛を以て衣服を作る』の域を越えなかつたのである【Gajus, 2, 79; Inst., 2, 1, 25】。ゆゑに当時の法律思想としては、どうしても材料主義をとり、加工物は独立の新物(neue, selbständige Sache)ではなくて、材料の変形物(umgestaltete Sache)であり、材料の所有権がそのまま存続すると考へざるをえず、従つてまた他人がわが材料を用ゐて何物かを製作せる場合にも、われは加工者に対してその物の返還を請求することができる、とも論結せざるをえぬのであつた(三)。
一 J. A. Hobson, The evolution of modern capitalism. A study of machine production 1916 p. 56.
二 中世都市の手工業者の性質に関しては見解の相異がある。Bücherは、手工業者は消費者の提供する材料に工作を加へる賃労働者(Lohnarbeiter)に過ぎなかつたと見た。彼等と近代の賃労働者との相違は、近代の賃労働者が特定の企業者に対して労働給付の義務を負ふに反し、中世の手工業者は一般の市民に対してこの義務を負うた点だけだつた、といふのである(K. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft I. 16. Aufl. 1922 S. 175 ff.)。
しかしBelowは反対の見解をとつた。彼によると、中世都市の手工業者は小資本家(kleiner Kapitalist)であり、自己所有の材料に工作を加へてゐた独立の手工業者(selbständiger Handwerker)であつた。靴工・鍛冶工・織工及パン屋において殊にさうであつた。裁縫師・屠殺師・壁工等は、消費者から提供される材料に工作を加へてゐたが、この方がむしろ例外だつたのであると(G. v. Below, Die historische Stellung des Lohnwerks. Territorium und Stadt 1923 S. 228 ff.)。
通説はBelowに従ふ(J.Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte I.1928 S.192 ff.)。
三 手工業時代には加工物は材料の所有者即ち手工業者自身の所有となつたから、商人が、加工物を取得するためには、売買の方法によらねばならなかつた。彼は手工業者をして労働そのもの(Arbeit als solche)を給付させずに、出来上つた労働生産物(fertiges Arbeitserzeugnis)を給付させたのである。後に問屋制や手工場制の発達を見るやうになると、請負や雇傭の方法によつて労働そのものを給付させることが出来るやうになつたが、手工業制の時代には、売買の方法によつて、出来上つた労働生産物即ち商品を給付させるの外はなかつたのである。
さてこれを法源に徴すると、Schwabenspiegelは、『他人の木材を以て船を作り、他人の羊毛を以て衣服を作れる場合には、船や衣服は、木材又は羊毛の所有者の所有となる』といひ(四)、又、『材料の所有者が加工変形物を必要とせず、これを引受くることを欲せざる場合には、彼はこれを加工者へ委譲し、その代りに材料の価格に相当する補償を求めることができる』ともいつてゐる(五)。又、alte Kulmも——これはKulm市の法書として十四世紀の末頃に作られたものであつたが——『加工物は常に材料所有者の所有となる』と述べ(六)、Brünner Schöffenbuchも——これはBrünn市の法書として十四世紀の半頃に作られたものであつたが——やはり『加工物は材料の所有者の所有となる』と述べ、且つ『盗める羊毛を以て作れる衣服はこれまた盗品なり』とも言明してゐるのである(七)。以て当時の法律がいかに材料主義の上に立つてゐたかを窺ふに足るであらう。
現代の学者も、ゲルマン法が材料主義の上に立つてゐたことについては、殆ど疑を挿まぬのであつて、例へば、O. Gierkeはいふ——『ドイツ古法は、材料所有者の利益において、加工の問題に答へてゐたらしく見える(八)』と。Hübnerもいふ——『ドイツ古法は、或人が他人の材料で新物を作つた場合に、新物の所有権を材料の所有者に帰属させてゐたやうに見える』と(九)。Rothenbücherのごときは語を強めて、『ドイツ法は加工の原則(Grundsatz der Spezifikation)を未だ知らなかつた』とまでいつてゐるのである(一〇)。又Schreuerは、ゲルマン法が一般に所有権の取得につき、労力尊重の立場を取つてゐたことを力説する人であるが、『加工の場合には、ゲルマン法といへども、材料を本位とし、材料の所有者に加工変形物を帰属させてゐた』と見るのである(一一)。
けだし当時の加工はオリヂナリチイを欠き、些少の変化を材料の上に加へる程度でしかなかつたから、法が重きを材料におき、材料の所有者をして加工変形物を取得させてゐたのも、尤もの次第だつたといはねばならない。
四 Schwabenspiegel (Lassberg) c. 373 u. 374.
五 Schwabenspiegel (Wackernagel) c. 390.
六 Alte Kulm V. 71--72.
七 Brünner Schöffenbuch 316. Brünner Schöffenbuch 316 : ,,Si ex lana furtiva vestimentum feceris, ……``の句がローマ法から出てゐること、即ちDig., 41, 3, 4, 20 : ,,Si ex lana furtiva vestimentum feceris, ……``の句から出てゐることは、疑ひがないとされてゐる(K. Rothenbücher, Geschichte des Werkvertrags nach deutschen Rechte. Untersuchungen zur deutschen Staats- u. Rechtsgeschichte von O. Gierke H. 87 1906 S. 74)。
八 O. Gierke, Deutsches Privatrecht II. Sachenrecht 1905 S. 584.
九 R. Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts 5. Aufl. 1930 S. 463.
一〇 K. Rothenbücher, a. a. O. S. 74.
一一 H. Schreuer, Deutsches Privatrecht 1921 S. 159.
三 材料主義と加工主義との対立時代(十六—八世紀)
進んで十六—八世紀の頃となつても、上述のやうな手工業的生産の方法はなほ根強く残つてゐたが、その外にもう一つの新しい生産様式が発生した。問屋制がそれである——
問屋制(Verlagssystem)の下においては、生産者たる手工業者は、みづから近隣を歩き廻つて材料の仕入れに奔走せねばならぬ煩はなかつた。みづから消費者を求めて加工製作品の販売にほねを折る必要もなかつた。材料の少くとも主要部分は——補助材料は往々手工業者から出たが——問屋即ち商人が供給してくれ、製作品も問屋が引受けてくれた。手工業者はただ技術をもち、道具をもち、仕事場をもち、孜々として家内労働(Heimarbeit)に従事してゐさへすればよかつたのである(一)。
すなはちこの新様式の下においては、手工業者は仕事場の所有者であり、問屋は材料の所有者であり、後者は前者のために材料を供給し、前者は後者のために技術を適用し、二者相助けて加工製造業を営んでゐたのであつたが、何といつても問屋は材料の所有者だつたから、材料主義の学説へ組みしやすく、手工業者は技術の人だつたから、労力主義若くは加工主義の学説へ傾きがちであつた。よつてここに問屋を支持者とする材料主義の学説と、手工業者を支持者とする加工主義の学説との並立的出現を見る次第ともなつたのである。
手工業者側は考へた——材料は加工によつて新物へ転化し、新物上には新所有権が成立してしまつたのであるから、その新所有権は、新物の創造者たる加工者へ帰属しなければならない。即ち新物は加工者において取得し、材料の所有者へは材料の価格を償還すれば足るのであると。
しかし問屋側は反対に考へた——よし加工によつて材料が新物へ転化したにもせよ、その新物は材料の所有者の所有とならなければならない。即ち新物は材料の所有者において取得し、加工者へは加工の賃金を支払へば足るのであると。
元来ルネッサンス期は、人間の創作労働(schöpferische Arbeit)の貴重性を知つた時代であつたと同時に、所有権の貴重性にも眼ざめた時代でもあつたのであり、近代がもつ自由所有権(freies Eigentum)の思想のごときも、その源頭は、ルネッサンス期に発してゐる位なのであるから(二)、この期において、一方、創作本位の学説を生じ、他方、材料本位の学説を産んだのは、自然の勢ひでなければならなかつた(三)。
一 J. A. Hobson, The evolution of modern capitalism. A study of machine production 1916 p. 56.
二 註釈学者(Glossatoren)は所有権を定義して、『使用・収益・処分の権能の全体なり』とか、『有体物上の完全なる支配権なり』とか、『物の法律上の運命をすべての部分につき、又すべての関係につき、決定しうる力なり』とかいつてゐた(Vgl. E. Landsberg, Die Glosse des Accursius und ihre Lehre vom Eigentum 1883 S. 92 ff.)。
これらの定義を一瞥しただけでも、いかにルネッサンス期が、所有権の絶対性に眼ざめた時代だつたかを想見するに足るであらう。
三 手工場制の下においては、加工製品は材料の所有者たる手工業者自身の手に帰した。従つて商人としては売買の方法によつて、手工業者から加工製品の給付を受ける外に道がなかつたが(前出二の註三参照)、問屋制の下においては、加工製品は直接に材料の所有者たる商人の手に帰したから、商人としては手工業者をして製品給付の義務を負はしめるの要なく、ただ労働給付の義務を負はしめれば足りた。換言すれば、請負の方法によつて、商人所有の材料の上へ、工作を加へさせるだけで足りたのである。
さてまづ材料主義の立法から見ることにすると、都市法の殆ど全部は材料主義を採用したのであつたが、事実上この主義を貫徹するためには、多くの困難を越えねばならなかつた。当時の歴史を繙くと、いかに都市がみづから立てた材料主義の法律を貫徹するために、みづから困苦したかがわかるのである。例へば都市は、手工業者が犯す『横領の罪』を絶間もなしに非難してゐる。僧侶をして各説教日に材料の所有権を尊重するやうに説かしめてゐる。罪を犯した手工業者へは、St. Peter寺院への懺悔の旅を命じてゐる。情状の特に重い者へは用捨もなしに破門の罰を加へてゐる(四)。中には例の、Hand wahre Handの原則に例外まで開いて、手工業者即ち占有者が、占有中の物を不法に他人へ処分せる場合には、所有者たる問屋は、物の所在に追及して所有権の主張をなすことができる、とまで定めてゐる(五)。
そこに材料主義とは根本的に異る思想、即ち材料よりも創作を重んじ、創作者へ加工物を帰せしめんとする思想が有力に横つてゐたればこそ、都市法はかうまで、自己の材料主義を貫徹するために、みづから手を焼かねばならなかつたのだと、解するの外はあるまい。
よつて都市法のあるものは、材料主義の加工法を立てると同時に、手工業者の立場を擁護する規定をも立てた。例へば、加工者は加工賃金の満足を受けるまでは加工物を留置することができる、とする規定などがそれである。けだし手工業者は、大抵は請負の形式で加工労働を給付してゐたのであるから(六)、彼等のために、加工賃金に関する留置権を認めてやることは、彼等の立場を擁護する最も有力な手段だつたのであつた。
一二の例を示すと、一二四九年のLübeck法、一二七〇年のHamburg法は、請負人即ち手工業者は、注文者即ち問屋から賃金請求権の満足を受けるまでの間、仕事の目的物を留置することができる・留置物を売却することはできないが、質入は差支ない、とまで規定してゐる(七)。Lüneberg, Augusburg, Regensburg等の都市法も、やはり手工業者のために留置権を認めてやつてゐるのである(八)。
四 都市が材料主義の加工法を施行するために、どんなに苦労せねばならなかつたかについては、Vgl. J. Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte I. 1928 S. 220.
五 Breslau, Kulm等の都市法は、Hand wahre Handの原則を堅守し、所有者は、加工者が不法処分をなした場合にも、第三取得者に対しては、物の返還を請求することができない、としてゐたが(Das Systematische Schöffenrecht V. c. 7; Alte Kulm V. 6)、Lübeck法のごときは明かに右の原則に対して例外を開き、加工者が不法処分をなした場合には、所有者は第三取得者に対して物の返還を請求することができるとした(Lübisches Recht. Codex II Art. 193)。なほこの問題については、Vgl. P. Laband, Die vermögensrechtlichen Klagen nach den sächsischen Rechtsquellen des Mittelalters 1869 S. 82 ff.
六 請負はルネッサンス期が盛んに使用した契約形式であり、材料の所有者が、手工業者をしてその材料の上に技術を揮はしめようと欲する場合には、大抵は、この契約形式によつたのであつた。ルネッサンス期を飾る千古不滅の芸術、絵画彫刻から建築まで、一切は請負契約の形式を以て仕上げられたのである(K. Rothenbücher, Geschichte des Werkvertrag nach deutschen Rechte. Untersuchungen zur deutschen Staats-u. Rechtsgeschichte von O. Gierke H. 87 1906 S. 8 f.; O. Gierke, Deutsches Privatrecht III. Schuldrecht 1917 S. 692; R. Hübner Grundzüge des deutschen Privatrechts 5. Aufl. 1930 S. 584 ff.)。
七 Lübeck法は、所有者は、加工者の質入せる物の返還を請求する場合、質権者に対して、加工賃金と同額のものを支払ふべしと命じてゐるが、これにつきRothenbücherは正当にもいふ——『賃金と同額のものを支払ふことによつて質権を消滅させることのできたのは、加工者が賃金請求権の満足のためにのみ加工物を質入できた好箇の証拠である』と(K. Rothenbücher, a. a. O. S. 103 f., 106 f.)。なほこの問題については、Vgl. O. Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts II. 1. 3. Aufl. S. 261 Anm. 29.
八 Rothenbücher, a. a. O. S. 103.
次に加工主義の立法をみると、十六世紀の初めに出たPurgoldts Rechtsbuchは、『善意の加工者は加工物を取得す』といひ(九)、同じく十六世紀の初めに出たRichterliche Klagspiegelも、『原形に還元しえざる場合には、加工物は加工者の所有となる』といつてゐる(一〇)。即ちこれらは古来の材料主義をすてて新興の加工主義へ就いた例であつたが、しかし加工主義の大宗は、何といつても継受されたローマ法であつた。継受されたローマ法は、原則として加工主義をとり、加工物は、それが原形に還元しえざる場合には、加工物の善意を条件として、加工者の所有となると定めてゐたからである(一一)。それに継受期の学説も、加工主義の味方だつたらうと想像すべき理由がある。といふのは、継受期の学説が註釈学者(Glossatoren)の影響の下に立つてゐたことはむろんの事であるが、註釈学者は、ローマにおける二つの加工説のうち、プロクルス派の説、即ち加工によつて材料の所有権は死し、加工物の上には新所有権が成立し、加工者に帰属するに至る、とみる見方に賛成してゐたといふ事実があるのだからである(一二)。
要するに十六—八世紀には、特別法としてはゲルマン古来の材料主義が行はれ、普通法としてローマ伝来の加工主義が行はれてゐたのであつたが、普通法は特別法によつて破られねばならなかつた関係上、加工主義の適用を見た場合は、事実において少かつたであらう。それにローマ法の加工主義そのものが、善意と原形回復の不能を条件とし、(一)加工者が、悪意即ち材料上に所有権を有せざることを知れる場合には、彼は加工物を取得することができず、(二)原形回復の可能な場合即ち加工物を材料へ還元さすことのできる場合にも、彼は加工物を取得することができない、としてゐたから、加工者が、加工を理由にして、加工物を取得できたのは、事実上絶無にも近かつたであらう。ゆゑに十六—八世紀はなほ材料主義の時代であり、加工主義は少しく芽をふき出した位のものだつたと見るべきであるが、一たび思ひを当時の経済状態の上へ移すならば、かかる事態も決して無理なものでなかつたことを知るのである。といふのは、当時の手工業者はみな独立の小資本家であり、仕事なども自分の仕事場で、みづからその順序・方法を定めつつ、自由に営んでゐたのであるから、彼こそが、語の正確な意味において、『加工者』であつたのであつた。従つてもし法がこの時代に、お先走つた加工主義でも採つてゐようものなら、手工業者が、『加工者』として、加工物の上に所有権を取得することとなるべく、その結果は材料の所有者たる問屋に、大なる危険と不安とを感じさせずにはおかなかつたであらう。ゆゑにこの時代の法律としては、未だ加工主義の加工法へ走つてはならぬのであつた。加工主義の加工法へ走つてもいいのは、手工業者がもはや『加工者』でなくなり、手工業者によつて加工物を奪取される心配も消え去つてからのことでなければならない。
九 Purgoldts Rechtsbuch III. 60 ff., 70.
一〇 Richterliche Klagspiegel 49 B1.
一一 Dig., 41, 1, 12, 1; Inst., 2, 1, 25; Vgl. auch Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts I. 9. Aufl. 1906 S. 967 ff.; Dernburg, System des römischen Rechts I. 8. Aufl. 1911 S. 344 ff.
一二 Glosse ,,Proculo placuit`` zu Dig. 41, 1, 7, §7.
四 企業主義の勃興
上述の問屋制(Verlagssystem)は、十六—八世紀における代表的な生産様式であつたが、より新しい様式としての手工場制(Manufaktur)もまた発達しつつあつた。よつてこの様式による加工製造の過程を見ることにすると、この様式の下においては、労働者は材料の所有者にあらず、道具の所有者にあらず、仕事場の所有者にあらず、単なる労働力の所有者に過ぎなかつた。従つて彼としては一介の労働者として毎朝その家を出でて企業者の手工場へ通勤するより外はなくなつたが、手工場における生産の過程はすでに相当に細分化されてをり、一労働者にして全生産行程を担当することはできなかつた。一労働者の担当しえたのは生産行程の中の一断節。而もそれさへ企業者の厳格なる指揮と監督との下に営まれねばならぬのであつた(一)。
よつてここに問屋制との比較において次のやうな相異を生じた——(一)問屋制においては、手工業者は家内労働(Heimarbeit)に従事したが、手工場制においては、出張労働(Störarbeit)に従事した。(二)問屋制においては、一手工業者が著手から仕上げまでの全行程を担当したが、手工場制においては、その中の一断節のみを担当した。(三)問屋制においては、仕事の順序・方法は手工業者自身が定め、注文者の容啄を許さなかつたが、手工場制においては、企業者が仕事の順序及方法を定めた。(四)問屋制においては、手工業者は創作者であり、創作の名誉と欣びとを享受することができたが、手工場制においては、労働者は企業者の命令下に機械的に立働くより外はなかつた。
だから手工場制下の労働者は、製作者でもなければ、『加工者』でもない。彼はなるほど実際の仕事には従事したが、仕事の目的・順序及方法は、企業者によつて決定された。彼は自己の意思に従つて働いたのではなくして、企業者の意思に従つて働いたのである。企業者の器具(Werkzeug)として、『延長された腕』(verlängerter Arm)として、労働力の一定量を給付しただけである。そこには『企業者の行為』はあつても、『労働者の行為』はなかつた。彼の行為は企業者の行為そのものの中に織込まれて、その独立性を失つてしまつてゐたのである。
企業者の方はこれに反して『加工者』であり、製作者であつた。なぜかなら彼は自己の創意を以て一の製作目的を定立し、この目的の実現のために自己の材料・道具・工場を動員し、他の人格即ち労働者の労働力までも駆使したのであつたから。もちろん彼は実際の仕事には携はらなかつたが、実際の仕事は、全部彼の意思から流出してゐたので、彼こそが、語の正しい意味において、『加工者』であつたのであつた。
ゆゑに手工場の経営者は、問屋と異り、『加工者』として、加工製品の上に所有権を取得する可能性をもつた。問屋は、語のいかなる意味においても、『加工者』ではなく、従つて加工製品の上に所有権を主張しようとおもへば、材料の所有権を根拠とする外に道がなかつたが、手工場の経営者は、語の正確なる意味において、『加工者』であつたから、かかる資格において、加工製品上に所有権を主張する可能性があつたのである。ここに手工場制と問屋制との最も根本的なる相異があつた。
だから手工場の経営者は加工主義に対して何の不便、何の不安をも感じなかつた。けだし加工主義は『加工者』へ加工物の所有権を与へてくれるが、企業者自身が今やその『加工者』なのであつたから。
反対に材料主義の方は手工場の経営者へ却つて不便と不安とをもたらすものと変つた。なぜなら手工場制が発達し、大量生産のために多くの材料を必要として来ると、手工場へ集中し来る沢山の材料の中に、他人の所有物が混入して来ないとは限らない。もちろん企業者は、大抵の場合は、即時取得の保護を受けて材料の所有者となりえようが、即時取得のためには複雑な諸要件を必要とするので、いつもいつも、さうなるとばかりは限らず、従つて企業者としては、彼の工場へ集中し来る沢山の材料について、一々その出所を検し、その所有関係を確めねばならぬこととなり、殆どその煩に堪えぬからである。すなはち彼としては、どうしても古来の材料主義に反対して、新しい加工主義若くは企業主義へ傾かざるをえぬ羽目になつたのであつた(二)。
経済史家の教へるところによると、十六—八世紀の頃は、繊維工業・皮革工業・金属工業・ガラス工業等は、主として手工場制により、高級品工業、例へばレース・リボン・絹織物・敷物・壁掛・武器・陶器・手袋・鏡・時計・タバコ・紙・石鹸等も概して手工場制によつてゐたといふことであるから、材料主義をすてて加工主義へ就かねばならぬ必要は、剴切に迫りつつあつたものと見ねばならな(三)い(四)。
一 J. A. Hobson, The evolution of modern capitalism. A study of machine production 1916 p. 58.
二 Sokolowski曰く——法がもし企業者をして彼の工場に到着した材料の出所につき一々責任を負はしめたとするならば、企業者の創作活動は重大な煩累を受けるであらう。ゆゑに近世の法律が、企業者にかかる煩累をかけさせまいとしたこと、いひかへれば材料主義をすてて加工主義をとつたことは、一応肯かれる措置であつたと(P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht I. 1902 S. 192 ff.)。
三 Kulischerに従ふと、十六—八世紀には、手工業制・問屋制・手工場制の三様式が並立してゐたが、繊維工業・金属工業等は主として問屋制又は手工場制により、全国向きの高級品即ちレース・リボン等々の製造も問屋制又は手工場制により、一地方向きの商品即ち衣服・肌着・帽子・靴・家具・道具等の製造は、これに反して、手工業の方法によつてゐたと(J. Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte II. 1929 S. 138)。
四 問屋制下の手工業者は、自由な家内労働(Heimarbeit)に従事し、手工場制下の労働者は不自由な出張労働(Störarbeit)に従事したので、労働義務負担の形式にも相異を生じた。前の場合は請負により、後の場合は雇傭によつたのである。
けだし請負は労働者を作品(Werk)にまで義務づけ、雇傭は労働者を働き(Wirken)にまで義務づける。前者は労働者に労働成果(Arbeitserfolg)の給付を命じ、後者は労働者に労働そのもの(Arbeit als solche)の給付を命じる。前者にあつては労働者は仕事上独立し、注文者の干渉を排斥するが、後者にあつては労働者は仕事上使用者の指揮監督に服する。従つて前者にあつては労働者が仕事の結果に対して責任を取るが、後者にあつては使用者自身が責任を取る。畢竟請負は道具又は仕事場をもつ人(請負人)と材料をもつ人(注文者)との間の対等の契約であるが、雇傭は労働力しか持たぬ人(労務者)と材料・道具・仕事場等を持つ人(使用者)との間の不対等の契約である。前者は純然たる債権関係、後者は命令服従の関係に近い。
手工場制の発達と共に請負は漸く廃れ、雇傭が益々多く用ゐられるやうになつたのであつた(O. Gierke, Deutsches Privatrecht III. Schuldrecht 1917 S. 590 ff., 688 ff.)。
しかしこれを立法に徴すると、法律が経済の変化に即応して直ちに自己を変化させるといふやうな突飛な行き方は示さぬのであつた。経済の進歩の急激なりしにも拘らず、法律の進歩は徐々的であり、秩序的であつたのであつた。例へば一八一二年のオーストリア民法を見ると、同法は、『他人の物に加工することによつて所有権を取得することなし』と言明して、アッサリと加工主義を片づけてゐる【Österr. G. B. §414】。尤も『原形への還元が不能なる場合には、加工物は関係者間の共有となる』とはしてゐるが、この場合にさへ、加工者がもし悪意ならば、材料の所有者は、加工者へ加工賃を支払つて加工物を取得するか、又は加工物を委譲して材料の価格を賠償させるか、二者その一を撰択することができるとし、どこまでも材料の所有権を擁護する方針を示してゐるのである(五)【Österr. G. B. §415】。
一七九五年のプロシヤ州法はこれに反して原則を加工主義にとり、『善意の加工者は新物上に所有権を取得す』とはしたが【Preuss. A. L. R. I, 9, §304】、それは、どこまでも善意を条件としての事に過ぎなかつた。悪意の場合に関しては、反対の主義即ち材料主義へ走り、材料の所有者は加工賃を支払つて加工物を取得するか、又は加工物を委譲して材料の価格を賠償させるか、二者その一を撰択することができる、としてゐるのである(六)【Preuss. A. L. R. I, 9, §§299--301】。
ところが一八〇四年のフランス民法になると、加工物の帰属を決するにつき、労働と材料との間の価値の差を標準にとり、労働が、価値において、材料に劣る場合には、材料の所有者が、加工賃金を支払つて、加工物を取得するが【Code civil Art. 570】、反対に労働が、価値において、著しく材料を越える場合には、加工者が、材料の価格を支払つて、加工物を取得するとした。ゆゑにフランス民法は、加工者の立場を大いに擁護したものだつたといつていい。労力が、価値において、材料を凌ぎさへするならば、加工者において、加工物を取得することができるとしたのであつたか(七)ら(八)。
仏法の影響の下に立てられたイタリイ民法・バーデン民法及わが民法も仏法と同じ行き方を示した(九)【Codice civile §470. Bad. L. R. §571. 民法二四六条】。
しかし概していふと、十八・九世紀交替期の加工立法は、材料主義と加工主義との間に低迷の姿だつたのであり、Sokolowskiの言葉をかりていへば、『そこには確たる基準なく、一体、立法者はそれによつてどんな状態を招来させたいとおもふのか、全く不明だつたのであ(一〇)(一一)る』。
五 オーストリア民法は材料主義をとつてゐるので(Österr. G. B. §414)、工場の経営者が工場製品の上に所有権を取得する場合にも『加工』を理由とせず、『材料の所有権』を理由としなければならない(J. Ofner, Das Sachenrecht 1893 S. 72; A. Ehrenzweig, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts I. 2. 1923 S. 203 ff.)。
六 プロシヤ州法は、『不法行為者は義務を負ふも権利を取得せず』の原則を立ててゐた関係上(Preuss. A. L. R. I, 3, §35)加工による所有権取得のためにも、善意を条件とせねばならぬのであつた。スヰス民法もこの流れを汲んでゐる(ZGB. Art. 726)。
七 加工物の帰属を決するにつき、労働と材料との間の価値の差(Wertunterschied zwischen Arbeit und Stoff)を標準にとるといふ式は、仏法(Code civil Art. 571)に始まり、独法・瑞法の踏襲するところとなつた(BGB. §950; ZGB. Art. 726)。
八 仏法は、労働が、価値において、著しく材料を越える場合には、加工物は加工者に帰すとしてゐるが(Code civil Art. 571)、仏法においてこの規定の適用を見る場合は、事実上稀であらう。といふのは、仏法はこの規定を任意法と見、当事者間に別段の定めある場合には、この規定は適用を失ふと見てゐるからである(A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français I. 7. édition 1931 p. 902)。
九 一八六五年のザクセン民法は加工主義をとり、『加工者は加工物の所有権を取得す。材料の所有者に対しては、善意の場合には利得の返還を、悪意の場合には損害の賠償をなせば足る』と規定した(Sächs. G. B. §246)。
一〇 P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht I. 1902 S. 192.
一一 十八・九世紀交替期の加工立法は、本文所述のやうに不統一であつたが、加工とは何ぞやの点になると、学者の間に定義の一致があつた。『加工とは新物の創造なり』といふのがこれであつて、Otto Fischerに従ふと、この点については殆ど反対を見なかつたといふ(Otto Fischer, Das Problem der Identität und der Neuheit mit besonderer Berücksichtigund der Spezification 1893 S. 61 f.)。
しかし普通法の学者中加工の本質を最も鋭く掴んだのは、Czyhlarzだつたとおもふので、少しく彼の定義を紹介しておくと、曰く——『物の観念は材料に従つて決せられず、材料の表現形態(Erscheinungsform)に従つて決せられる。材料は同一でも、その表現形態が変化すると、人はそこに旧物の消滅・新物の成立を認めるのである。ゆゑに加工とは、労働によつて物の表現形態を変へたこと、即ち一物を滅ぼして他物を成立させたことでなければならない。単に或物が分解され、改良され、美化されたといふだけなら、未だ加工ではない。人間労働の結果として一物が他物に変化したといふときに、その労働がはじめて加工となる。加工の本質は創造であり、生産である』と(Czyhlarz in Glücks Pandektencommentar, Serie der Bücher 41 u. 42, 1. Th. S. 249 ff.)。
Windscheidも、加工の観念を新物創造の場合に限つた。ドイツ民法九五〇条もWindscheidを通して、この考へを受継いだ(Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts I. 9. Aufl. 1906 S. 967 f.)。
五 企業主義の時代(十九—二〇世紀)
進んで機械工場制(Fabrik)の広汎な展布を見た現代を見ると、機械工場制において生産行程の主要契機を占めてゐるのは、機械であつて人間ではない。機械は人間よりもはるかに正確、はるかに精巧、はるかに多量に、生産しつつあるのである。否、機械は人間以上の道徳を実践してゐるのである。その優れたる正確性と規則性、無限につづく辛抱と服従——それはややともすれば怠惰になり、不注意になり、不忠実になる人間などの到底及びうる所ではない。それに、機械は進歩と共に漸次人間の手をば離れて行く。進歩せる機械は、女子供から簡単な補助行為を受けさへすれば、それだけで足りる。あとは自分で働き、自分で動く。正確に同一の間隔をおきつつ、無限に同一の作業を反覆し、完全に原形に合致した製品を産出する。それは自分で自分の誤りを訂正する力さへもつてゐる。見よ、その自動的なる自己調節の機能(一)を(二)。
従つて現代の法律としては、人間の労働をさまで高く評価するわけに行かない。それは人間の労働よりも、機械の作用を、より高く評価しなければならない立場におかれてゐるのである。
一 J. A. Hobson, The evolution of modern capitalism. A study of machine production 1916 p. 66--75.
二 工場制にあつては、企業者は仕事の目的・順序及方法を任意に決定できる立場にあるから、彼としては、労働者を義務づけるために、請負の方法による必要なく、むしろ雇傭の方法によれば足りるが、工場制の一層の発達と共に、雇傭よりも労働契約(Arbeitsvertrag)の方が望ましくなつた。けだし労働契約は労働者を労働規則の遵守一般にまで義務づける。即ちそれは、労働者を労働だけに義務づけずに、むしろ就業規則・給与規則・宿舎規則・服装規則等々へ包括的に義務づけるからである。
だからこれを一括して、手工業の時代には人々は手工業者を加工製品の給付にまで義務づけ(売買)、問屋制の時代には労働成果(Arbeitserfolg)の給付にまで義務づけ(請負)、手工場制の時代には労働者を労働そのもの(Arbeit als solche)の給付にまで義務づけ(雇傭)、工場制の時代には労働規則一般の遵守にまで義務づける(労働契約)、といつてよいであらう。加工法の変遷の背後には、かうした債権契約の変遷が、平行的に流れて来たのである(参照、前出二ノ註三・三ノ註三・四ノ註四)。
然らば法律はかかる機械工場制の急激なる発展に対応していかなる態度を示したかといふと、法律はこの場合にも、突飛な飛躍はしないのであつた。それは一方、経済に追進し、他方、伝統に固着し、二者の間に中を執らうとしたのであつて、かかる法律の漸進的態度は、ドイツ民法における加工法の制定史の中に最もよく表はれてゐるとおもふから、少しくこれを跡づけて見ように——
第一草案八九三条は、『既存の材料から新物を製造した者はその新物上に所有権を取得する』と規定し、敢然として加工主義即ち企業主義の採用を宣言したのであつた。而も、理由書のいふところによると、草案の加工規定は少くとも三つの点において嶄新性をもつた——(一)は加工を事実行為として性質づけたことである。理由書によると、加工行為は事実行為であつて法律行為ではない。行為者の意思は『新物の製出』といふ事実上の結果に向けられれば足り、『所有権の取得』といふ法律上の効果に向けられる必要はない。法律は新物の製出といふ事実上の結果さへ生じれば、これに対して所有権の取得といふ法律上の効果を附与する。その際、加工者自身が所有権の取得を欲してゐたかどうかは問題としない、といふのであつた(三)。(二)は物の新物か否かの最後の判定を裁判官の裁量に一任したことである。理由書によると、法律が物の同一・不同一を問題にするのは、これによつて所有権の帰属を決せんがためであるから、物の同一性《イデンチテート》に関する哲学上の理論は標準とならず、むしろ取引上の通念が標準となる。而も取引上の通念は往々明確を欠き、統一を欠くので、最後の判断は、裁判官に附託せねばならぬ、といふのであつた(四)。(三)は悪意の加工者をも保護したことである。理由書によると、法が加工者へ加工物の所有権を与へるのは、彼の新物製出の行為を尊重するからである。ゆゑに法は新物の製出といふ客観的な要素のみを標準とすればいい。善意悪意といふやうな主観的な要素まで参酌する必要はない。もちろん損害賠償の問題のためには、加工者の善意悪意をも参酌しなければならないが、所有権帰属の問題のためには、これを度外に措いても差支ないのである、と(五)。
かかるラヂカルな草案の出方に対しては非難の声が高かつた。いまそれらを論点別に分類してみると、第一点即ち加工行為の性質に関しては、O. Gierkeがいつた——理由書が加工行為は法律行為にあらずと宣言的に声明したのは僭越である。かうした問題はむしろ学理の決定に俟つべきではないかと(六)。しかしGierkeは、加工行為を有権的に性質づけようとした理由書の態度を非難しただけで、加工行為を事実行為(Tathandlung)と見ること・そのことに反対したのではない。換言すればGierke自身も、加工行為を事実行為だとは見てゐたのであり、このことは、彼の後日の著『物権法』の記述に照らしても明かだといふことを附記しておかう(七)。
第二点即ち新物か否かの判定を裁判官に一任したことについては、Otto Fischerの皮肉まじりの非難があつた。曰く——物の同一・不同一を判定する確たる標準は哲学上にも見当らない。取引の観念上も区々である。だからこれを近頃流行の裁判官の自由裁量とやらに附託するのも一案ではあらうが、さうすると、物が恣ままに新物とされたり、旧物とされたり、従つて甲の物にされたり、乙の物にされたり、する危険があるであらうと(八)。
しかし第二点に対する最も有力な修正意見は、Bärのそれであつた。彼はフランス民法が加工物の帰属を定めるにつき、労力の価値と材料の価値との差を標準にしてゐるのに示唆を受け、『加工者が勝つてもいいのは、加工の価値が材料の価値を越えた場合だけだ』と見たのであつたが(九)、第二草案委員会の委員の中にも、Bärと見解を一にした人があつたものと見え、第二草案は、『加工者は、加工の価値が材料の価値よりも少なからざる場合に限り、加工物を取得す』と定めたのであつた。さうしてこの第二草案八六五条の規定が、文句も殆どそのまま九五〇条として、ドイツ民法の中に採用されてゐることは言を俟つまい。
第三点即ち悪意加工者の保護に対しては非難の声が最も高かつた。Otto Fischerのごときはいふ、『善意を要件としないとなると、盗賊が盗品から新物を作つた場合——盗んだ布地で衣服を作つたやうな場合——にも、新物の所有権について無制限な保護を受けることになる。かうまで立法者は国民の道徳感情を無視してもいいのであらうか。事実行為だから主観的要件は問はないといふやうな言は、概念を弄ぶこと甚しいものである』(一〇)と。
第二草案委員会においても、この点は問題となり、数個の修正動議の提出となつた。動議の一はいふ、『加工者に悪意又は重過失ありし場合、即ち材料上に所有権を有せざることを知り又は当然知るべかりし場合には、加工者に加工物を帰属させてはならない』(一一)と。動議の二はいふ、『少くとも悪意の場合、即ち材料上に所有権を有せざることを知りし場合は除外せよ』(一二)と。動議の三はいふ、『少くとも犯罪の場合、即ち犯罪によつて他人の材料を占有するに至りし場合だけは除外せよ』(一三)と。しかし結局、委員会はこれらの動議全部を斥け、第一草案の主義即ち悪意の加工者をも保護するといふ主義を守り通したのであつたが、これもまた加工者の主観的条件は損害賠償の問題には影響するが、所有権帰属の問題には影響しない、といふ考へ方に発したのであつた(一四)。
かくしてドイツ民法九五〇条は出来上つた。それは『既存の材料から新物を製出した者は、加工による価値が材料の価値よりも少なからざる場合に限り、加工物の上に所有権を取得す』と定めてゐる。ゆゑにそれは、但書こそ附したれ、原則は加工主義である。従つてそれは、ゲルマン古来の材料主義を顛覆したものといつていい。ルネッサンス期以来芽を伸ばしつつあつた創作尊重の思想に、充分な表現を与へたものといつてもいい。而もそれが現代の工場生産の様式に最も適合した立法であることも間違ない。なぜかなら同条の『加工によつて新物を製出した者』とは、労働に従事する労働者をいふのでなくして、労働を命じる企業者を指すのであるから(一五)。
三 Motive zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich, III. 1888 S. 360.
四 Motive III. S. 361.
五 Motive III. S. 360 f.
六 O. Gierke, Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Recht 1889 S. 343 Anm. 2.
七 O. Gierke, Deutsches Privatrecht II. Sachenrecht 1905 S. 586.
八 Otto Fischer, Das Problem der Identität und der Neuheit mit besonderer Berücksichtigung der Spezification. Breslauer Festgabe für Rudolf von Jhering 1893 S. 63. なほここで、Fischerの右の書について一言を添へると、この書は物又は権利の同一性・新規性を決定する一般的標準を求めるために、継受取得・更改・訴の変更・加工等々の諸問題を徹底的に論究したものであつたが、それにも拘らず、得られた結論は懐疑的であり、消極的であつた。即ちFischerのいふには、同一性を判別する一般的標準なるものは存在しない。それは個々の場合につき一々具体的に判断されなければならない。即ち法の適用上、物の同一性が問題となつた場合には、裁判官は、法規の目的から出発し、当該の場合、物の同一性を認めて法律効果を発生せしめることが果して合宜的なりや否やを具体的に判断するよりの外はない、といふのであつた(O. Fischer, a. a. O. S. 72 f.)。
九 O. Bär, Gegenentwurf zum Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich III. 1890--1892 §886.
一〇 O. Fischer, a. a. O. S. 60 Anm. 1. Vgl. auch Cosack, Das Sachenrecht im Entwurf S. 33.
一一 Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs des bürgerlichen Gesetzbuchs. III. 1899 S. 239.
一二 Protokolle III. S. 240.
一三 Protokolle III. S. 239.
一四 Protokolle III. S. 241.
一五 第二委員会における注目すべき一つの動議は、『加工をなしたる者』ばかりでなく、『加工をなさしめたる者』にもまた所有権を取得せしめよとの意見であつた(Protokolle III. S. 239)。而も委員会はこの意見を斥けたが、それは、これに反対したがためではなくして、これを『自明の理』だと見たからであつた(Protokolle III. S. 243)。即ちドイツ民法の見解に従ふと、加工をなさしめたる者即ち企業者が、『加工者』として、加工物上に所有権を取得しうることは、全く自明の事理なのである。
終りにドイツ民法制定後における加工法の進歩の跡をのべておくと——
(一)は加工法の強行法性が確認されたことであつた。けだしドイツ民法は、法規の強行性又は任意性を明言することを往々回避したので(一六)、学説がこの点を究明せねばならぬ順序となつたが、加工法の強行性だけは一人として疑ふものがなかつた。例へばRegelsbergerは『凡そ共同生活の経済的基礎を護衛する法規は強行法だ』といつた(一七)。Ehrlichは『法が一定の事実に対して権利取得又は権利喪失の効果を附してゐる場合、即ち附合・混和・加工等の場合には、人は反対の意思表示を以て権利取得又は権利喪失の効果を予め拒絶することをえない』といつた(一八)。帝国裁判所も物権法の強行性を認めた(一九)。Hedemannもドイツ民法の九五〇条即ち加工の規定は強行法だと明言した(二〇)。Geilerも、第三十二回ドイツ法曹大会(32. Deutsche Juristentag in Bamberg 1921)において、動産抵当の問題を取扱つた際、九五〇条の強行法なることを前提となしつつ、立論した(二一)。
(二)かやうに加工法の強行性が明かになつたために、何人が『加工者』なりやが至大至重の問題となつて来た。『加工者』ならば加工物を取得することができ、『加工者』ならざれば加工物を取得することができず、それによつて取るか、取られるか、が決まるのだからである。
ゆゑにHedemannはいつた——加工法の中には『測るべからざる重大意義』が潜むと(二二)。Elsterもいつた——『もし企業者が加工者ならば、加工製品は企業者に帰し、労働者へは加工賃を支払へば足ることとなり、又もし労働者が加工者ならば、加工製品は労働者に帰し、企業者へは材料の価格だけを支払へば足ることとなる。加工者の意味の取り方一つで社会の組織が一変するだらう』(二三)と。もちろん正当な見解は企業者を加工者と見て、これに加工製品を帰属させることにあるのであるから、われらは、この見解を明白疑ひなき定理として確立させてしまはなければならない(二四)(二五)(二六)。
(三)は所有権留保契約(Eigentumsvorbehalt)の効力の限界が明かになつたことであつた。けだし動産の売主は附随の約款を以て、代金完済の時まで、売つた動産の所有権を留保しておくことができるのであるが【BGB. §455】かかる約款は、加工法の前に失効しなければならない。例へばわたくしがある加工製造会社へある材料を売り、所有権留保の契約をも締結したとすると、わたくしは、材料が運送の途上にある間所有権を失はない。材料が会社へ到着し、会社の倉庫へ収められても所有権を失はない。これみな所有権留保契約の作用によるのであるが、一たび材料が加工されて新物へ転化するや、わたくしは、所有権を失はねばならない。これ加工法の発動ある結果である。加工法は強行法であるため、所有権の留保を以てその適用を排除するわけには行かぬのである(二七)。
(四)所有権留保の効力に因んで述べておかねばならないのは、世界大戦の直後、ドイツ及オーストリアにおいて大問題となつた加工信用(Veredelungskredit)の事である。
ドイツ及オーストリアの加工製造工場の中に、材料の供給を外国に仰いでゐるもののあるのはいふまでもないが、大戦後の疲弊は、これらの加工製造工場をして材料の売主たる外国輸出商に対し即時に代金を支払ふことを不可能ならしめた。よつて外国輸出商は独墺の加工製造工場へ材料を掛売りすると同時に、その売掛代金を担保するために、売つた材料につき所有権留保契約を締結させた。しかし前述のごとく所有権留保契約は加工によつて消滅せねばならぬ関係上、この方法を以てしては、担保の目的を充分に到達することができなかつた。自然、外国輸出商は独墺の工場に対しては材料の売却を躊躇するやうになつたので、独墺の工場は、非常の材料入手難に陥らねばならなくなつた。よつてこれが打開策が問題となり、オーストリアでは、一九二〇年七月十六日の臨時措置法を以て、所有権留保契約の強化を図り、『外国にある売主が、内国にある買主に対し、加工の目的のために所有権留保附にて、材料を供給せる場合には、材料の所有権は、材料より作られたる加工物の上にも及ぶ』と定めたのであつた(二八)。ドイツにおいても所有権留保契約の強化が問題となつた。先きにわたくしは第三十二回ドイツ法曹大会において、加工法の性質が論じられたといつたがそれは、所有権留保契約の強化の目的のために、加工法を任意法に改むべきや否やの討議に外ならぬのであつた(二九)。しかしドイツ民法はあくまでも慎重の態度をとり、加工法の改正は行はなかつた。加工法はどこまでも強行法であり、所有権留保契約は加工によつて消滅するといふ建前を堅持して動かなかつた。
一六 理由書は、民法が個々の規定の強行性又は任意性を一々言明しなかつた点を弁解して、『一々これをいひ表はさうとすると、とても冗漫になりさうだつたから』といつた(Motive zu dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Reich I. 1888 S. 17)。しかしStammlerは、『数の少い強行法について一々その旨を表現すること位は、さしたる難事でもなかつたらうに』と皮肉つてゐる(R. Stammler, Das Recht der Schuldverhältnisse in seinen allgemeinen Lehren 1897 S. 73)。
一七 Windscheidは形式的に、『強行法とは当事者がその適用を欲せざる場合にもなほ適用のある規定であり、任意法とは当事者が別段の定めをなしたときはその適用を失ふ規定である』と定義したが(B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts I. 9. Aufl. 1906 S. 125)、Regelsbergerは実質に立入つて、『共同生活の道徳的・経済的基礎を護衛してゐる規定は強行法だ』といつたのである(F. Regelsberger, Pandekten I 1893 S. 130)。
一八 Ehrlichは加工法は任意法にもあらず、強行法にもあらず、法規の第三種なりと考へたが、これはEhrlichにおける強行法・任意法の区別が普通のそれと趣を異にしてゐた結果であつた。普通のそれは、法規を直ちに(一)強行法と(二)任意法とに分つが、Ehrlichのそれは、法規をまづ、(一)法律行為に関するものと(二)法律行為に関せざるものとの二種に大別し、(一)の内部においてのみ、(イ)任意法(ロ)強行法の区別が立つとするのである。従つてEhrlichとしては、事実行為・不法行為・不当利得等々に関する法規は任意法にあらず、強行法にもあらざる第三種類なりと断ぜざるをえぬのであつた。加工法もかくして法規の第三種類に入れられてしまつたのである(E. Ehrlich, Das zwingende und nichtzwingende Recht im bürgerlichen Gesetzbuch für das deutsche Reich 1899 S. 3; 7; 255 ff.)。
一九 帝国裁判所の判決はいふ——『物権法の規定には、強行法たる性質が内在する』と(Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 104 S. 73)。
二〇 J. W. Hedemann, Sachenrecht des bürgerlichen Gesetzbuches 1924 S. 169, 227.
二一 一九二一年九月Bamberg市に開かれたドイツ法曹大会の取扱つたテーマの一つは、『動産抵当制の採用を可とするや』といふのであり、Geilerが報告の任に当つたが、議論の核心たるドイツ民法九五〇条の改正問題即ちこれを任意法規に改むべきやの点に及ぶと、報告者自身否定的な論調を示したといふ(Deutsche Juristen-Zeitung 26. Jahrgang 1921 S. 573; 635)。
二二 Hedemann, a. a. O. S. 170.
二三 A. Elster, Spezifikation. Handwörterbuch der Rechtswissenschaft V. S. 569.
二四 加工法の性質に関するわが国の通説は、これを附合法と同一視し、附合の場合に、特約を以て従たる物の所有権を留保しうるやうに、加工の場合にも特約を以て加工物の所有権を留保しうると解するかのごとくである。しかしWindscheid, a. a. O. S. 980もいつてゐるやうに、加工と附合とは本質を異にする。(一)加工は新物の創造であるが、附合は二物の結合である。(二)加工の場合には材料の所有権は死し、新物の上に新所有権が生れるが、附合の場合には主たる物の所有権が従たる物の上へ拡大するに過ぎない。(三)加工の場合には収去権がないが、附合の場合にはこれがある。(四)加工法は、思想的にいふと、ローマのプロクルス派の流れを受け、創作本位の考へに立つてゐるが、附合法はサビーヌス派の流れに属し、材料本位の考へに立つ。極端にいへば、附合の場合には、従たる物の所有権は死んでをらず、一時休止してゐるに過ぎないともいへるのである。だからわが民法は、附合法の適用は所有権留保契約を以てこれを排除しうるが(民法二四二条但書)、加工法の適用は所有権留保契約を以てこれを排除しえずと見たのではあるまいか。いひかえれば附合法は任意法であるが、加工法は強行法だと見たのではあるまいか。
二五 雇傭の場合に、使用者が『加工者』として労務者の労働成果の上に直接に所有権を取得しうるといふ点は疑ひがないが、請負の場合に、注文者が『加工者』として、請負人の労働成果の上に直接に所有権を取得しうるかどうかは疑問である。請負人は材料こそ注文者から受けてゐるが、仕事は自分の仕事場で営んでをり、従つてそれは、自由な独立の行為だとも見られうるからである。もしも真にさうであるならば、加工製品は一旦請負人へ帰し、請負人からの供給によつて、注文者の所有に移るといふ段取りとなるであらう。しかし概していふと、今日の請負人は中世の請負人のやうな独立不羈の経営者ではない。彼は注文者の指揮下に立つこと、雇傭労働者と一般なのであるから、彼の行為もまた不独立の行為に過ぎないと見るべきであらう。換言すれば請負における注文者もまた、雇傭における使用者と同様、自分自身を『加工者』だとして、加工製品の上に所有権を取得できるのだと見るべきであらう(Hedemann, a. a. O. S. 173; ders. Schuldrecht des bürgerlichen Gesetzbuches 1931 S. 362; A. v. Tuhr, Der Allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts II. 2. 1918 S. 371)。
二六 O. Gierkeは、労務者の行為の効果は直接使用者につき発生するから、両者の間には代理関係がなければならぬと考へた(O. Gierke, Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Recht 1889 S. 343 Anm. 2)。しかし加工行為は法律行為ではないのであるから、真正の代理関係は成立することができない。Hedemannは代理類似の関係があるに過ぎぬとし、これを『加工における補助関係』(Gehilfenschaft beim Verarbeiten)と呼んでゐる(Hedemann, Sachenrecht S. 172)。
二七 Hedemann, Sachenrecht S. 169.
二八 Vollzugsanweisung v. 16. 7. 1920: ,,§1. Verträge, in denen jemand, der in Ausland seinen Wohnsitz (Sitz) hat, sich verpflichtet, einem Empfänger, der im Inlande seinen Wohnsitz (Sitz) hat, Rohstoffe zum Zweck der Verarbeitung unter dem Vorbehalte des Eigentums an den Rohstoffen und an den daraus hergestellten Erzeugnissen aus dem Auslande in das Inhand zu liefern,……``. Vgl. auch A. Ehrenzweig, System des österreichischen allgemeinen Privatrechts I. 2. 1923 S. 332 f.
二九 前出註二一。
結論としていふ——近代の加工学説は加工を新物の創作行為だと見る。加工によつて旧物は死し、新物は生れ、従つて旧物上の所有権は消滅し、新物上には新所有権が成立すると見る。
而してこれは、他人の動産に工作を加へた場合と、自己の動産に工作を加へた場合とによつて異るを見ない。わたくしがわたくしの肉片を以てビフテキを作り、ソーセージを作つた場合にも、肉片の所有権は死し、ビフテキの上・ソーセージの上に、新たなる所有権が成立するのである(三〇)。
しかし所有権の取得に関して問題となるのは、もちろんわたくしが他人の動産に工作を加へた場合だけであるが、近代法はこの場合につき、材料の所有権よりも加工者の創作労働(schöpferische Arbeit)を重んじる。即ち加工新生物を加工者に帰属させるのである。
しかし近代法にいはゆる『加工者』とは、現実に労働する人を指すのではなくて、労働を命じる人即ち企業者を指すのであるから、加工新生物は、『加工者』としての企業者に帰属することになるのである。
例へばここに会社あり、労働者を使用してパルプから紙を作り、綿から糸を作り、木材から家具を作つたとすると、会社こそが『加工者』である。従つて会社は『加工者』たるの資格において、これらの加工新生物の上に所有権を取得するのであつて、材料の所有者たる資格において所有権を取得するのではないのである。
もし法が材料主義をとり、材料の所有権を根拠として加工新生物を取得せねばならぬこととせんか、企業者は、他人のために加工するの愚を避けんがために、その工場へ集中し来る無限量の材料について、一々その所有関係を確めねばならぬこととなり、その煩累は、Sokolowskiがいつたやうに、『企業の創作活動を鈍らさずにはおかぬであらう(三一)。』
かくして企業者を『加工者』と見、彼をして加工者たる資格において加工新生物を取得させる企業主義が、現代の経済生活に最も適合せる加工法だといふことになるのである。
三〇 自己が自己の物の上に工作を加へた場合にも、新物の成立と共に新所有権が成立するといふことについては、Vgl. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts I. 9. Aufl. 1906 S. 968 Anm. 2. 三一 P. Sokolowski, Die Philosophie im Privatrecht I. 1902 S. 192 f.