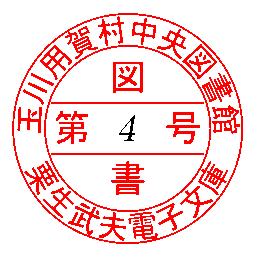
一 序 言
『森林と経済』と題するBücherの論文の書出しにかういふ句がある——『森林経済ほどその発展の途上において、国民経済に対するその地位を、多様に転変させて来た部門はあるまい』と(一)。さうして彼はこれを説明していふのである。森林の歴史は四たび変化した——(一)古代においては、森林は人類の敵であり、文化の障害であり、交通の自由と耕地の拡大とを阻害する位の作用しかもたなかつたが、(二)中世に入ると、森林に対する人間の永年の格闘が奏効して、耕地の拡大・村落の盛置となり、森林は農家にとり、家計を支へる欠くべからざる資源の一と変つた。しかし当時の人々が森林から享受してゐたのは、その使用価値であつて交換価値ではなかつたから、人々はただ森林へ入会つて互にこれを使用収益してさへゐさへすれば、これだけで足りた。入会は人々が森林の使用価値を享受するためには、最も適合した法律型態だつたのである。(三)しかし十六—八世紀の頃に及ぶと、森林の交換価値は高まり、森林生産物は、建築材として、加工材として、薪炭材として、舟筏の便に送られて、都市の市場へまで搬出される形勢と変つて来たので、人々はかやうな変化に即応した新しい法律型態を案出しなければならなくなつた。当時の歴史をひもとくと、国家は重商主義的経済政策をとり、資本主義又は自由主義の発展に対して桎梏となつてゐたところの中世的遺制をば片端から除去してゐる。さうして入会制もまた中世的遺制の一つだとして、これにむかつて用捨なき淘汰の斧を揮つてゐるが、かうした処置は、新しい法律型態への焦慮の一つの現れであつたであらう。事実また入会は、森林の交換価値を享受するための法律型態としては、不便極まるものだつたのであるから、人々がこれにむかつて淘汰の斧をふり上げたのも、無理からぬことであつたのである。かくして(四)十八世紀に入ると、入会は減少して稀有の現象となり、森林の大部分は個人又は法人の単独所有へと移つてしまつた。さうしてこれらの森林所有者は、一に営利の観点から合理的に森林の経営にあたることとなつたが、何といつても、現代は金属の時代(Metalzeitalter)であつて、木材の時代(Holzzeitalter)ではない。木材の用途は、金属の用途の益々拡大されてゆくのに反比例して、益々縮小しつつある事実を看過すべくもないのであると、かう、Bücherは結んでゐるのである(二)。
本稿においてわたくしは森林経済史の第二期及第三期、即ち中世と近世とを取扱つて見たい。といふのはこの前後二つの時期を取扱ふと、入会法の歴史の中心部がわかるのである。なぜかなら、中世は人々が森林からその使用価値を享受するために入会といふ法律型態を使用してゐた時代であり、近世は森林からその交換価値を享受するために単独所有といふ法律型態を使用してゐる時代であり、前者は入会法の開花期、後者はその凋落期に相当するからである。
しかし本論に先立つて法源を一瞥しておくと、中世の入会法は村の慣行と庄園裁判所の判決の中に埋れ、文字の上へは殆ど姿を示さずにゐた。入会法が文字上の表現をもつに至つたのは、十三世紀以降、『村法集』(Dorfweistümer)の編纂を見てからである。けだし十三世紀において農民の地位は高まり、自覚は進み、領主に対しても積極的な態度をとるやうになり、遂には進んで旧来の慣行を文字に明徴にし、領主をして文字以上の請求をなすことを不可能ならしめんと企図するまでになつたのであつた。ゆゑに村法集の中には、耕地に対して農民が有する権利の内容・領主に対して農民が負ふ義務の限界が、明細に規定されてゐるが、これと同時に入会地利用の関係も、詳細に記載されてゐるのを見るのである。
その後十六世紀に入ると、村法集の編纂は再び活溌になり、殊に農民戦争の鎮定後は、全国の村々、先を争つて村法集の編纂を企図する情勢とはなつた。これはもちろん農民戦争の鎮定者たる領主達が、農民に対する彼等の権利を文字に確定することによつて、優越する彼等の地位を永遠に不動ならしめようとしたからではあつたが、しかし、村法集の編纂は、農民にとつても不利な企てではなかつたであらう。なぜかなら、彼等は村法集の文字を援用することによつて、彼等に対する領主の飽くなき要求を確定不動の一線に喰止めることができたからである。その後も村法集の編纂は続いた。十八世紀に入つてからもなほ跡を絶たなかつた(三)(四)。
十六—八世紀にはまた藩(Land)の森林立法も活溌になつた。これを森林統制法(Forstordnung)といふ。一五一四年にはWürtembergが、一五二四年にはSalzburgが、一五五二年にはNassauが、一五六八年にはBayernが、一五八六年にはBadenが、それぞれ森林統制法を制定した。その趣旨とするところは、濫伐の禁止・販売の統制にあつた。それは、村民に対しては、森林の濫伐を禁じ、一定の需要を越えてなほ余りある部分を都市へ搬出すべきことを命じ、都市の木材加工業者に対しては、優先的な木材の購入権を保証してゐるのである。畢竟それは重商主義的経済政策の、森林部門における現れなのであつた。
要するに十三・四世紀までは、森林は一村落の需要に当てられてゐただけであり、従つてその法的規制も村落の自治立法に一任しておいて差支なかつたが、十六—八世紀となると、森林は一藩全体の需要に応ずることとなり、従つて藩がその統制に乗出さねばならぬこととなつたのである。前者の法的表現は『村法集』であり、後者の法的表現は『森林統制法』である。従つて村法集の中には発展期の入会法の姿が現れ、森林統制法の中には凋落期の入会法の姿が現れてゐるのである。
入会法の研究者としては、古くはG. L. v. Maurer,(五)v. Thudichum(六)の二大家があり、さらにO. Gierke(七)があり、近くはDopsch,(八)Lütge(九)がある。わたくしのこの稿は、これらの諸大家、殊にMaurer, Thudichum, Gierke, Dopschを学び受け、入会法の変化の跡のあらましを尋ねてみたものに過ぎない(一〇)。
一 K. Bücher, Wald und Wirtschaft. Die Entstehung des Volkswirtschaft II. 7. Aufl. 1922. S. 29.
二 K. Bücher, a. a. O. S. 29--60.
三 村法集の成立史については、Vgl. O. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen I, 1860. S. 585 ff.; II, 1864. S. 270 ff.
四 村法集の印刷本のおもなものは、J. Grimm=R. Schröder, Weistümer, 7 Bde., 1840-1878; Österreichische Weistümer, bisher 11 Bde., 1870 ff.; Sammlung schweizerischer Rechtsquellen bisher 4 Weistümerbände; v. Künssberg, Deutsche Bauernweistümer 1926; G. Franz, Der deutsche Bauernkrieg, Aktenband 1935; Deutsches Bauerntum, bearbeitet von G. Franz II. 1939.
五 G. L. v. Maurer, Geschichte der Markverfassung in Deutschland 1858; ders., Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland, 2 Bde., 1865. 1866; ders., Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt, 2. Aufl. 1896.
六 v. Thudichum, Gau-u. Markverfassung in Deutschland, 1860; ders., Rechtsgeschichte der Wetterau 1, 2. Heft 1 und 2, 1867. 1874. 1885; ders., Geschichte des deutschen Privatrechts, 1894. S. 403 ff. Maurerの特色が、その博覧多識《ベレーゼンハイト》にあることはいふまでもないが、Thudichumもこの点にかけては遜色がない。殊にWetterau, Maingau, Rheingau諸地方の状態にかけては、Thudichum自身、『自分はこの諸地方の状態にかけては、Maurerに数百倍する資料を所蔵してゐる』と自慢してゐる位なのである(Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts, 1894 S. 403 Anm. 1)。
七 O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, 2. Bd. 1873. S. 136 ff. 156 ff. 179 ff. 196 ff. Gierkeの右書中の右箇所は、入会法の歴史といふよりも、むしろその理論である。而もその理論は、彼の団体法論の角度から組立てられたものだつただけに、彼の主観的意見に彩どられてゐる形跡がないでもない。史料の読み方などについても、相当無理があつたらしく、この点は、Dopschがその新著Die freien Marken in Deutschland 1933のなかにおいて、一々、Gierkeの史料の読み方の無理と誤りとを指摘してゐるのを見ると、思半ばに過ぎるのである(A. Dopsch, a. a. O. S. 30, 33, 35, 38)。
八 A. Dopsch, Die freien Marken in Deutschland 1933. Dopschの右書は、後代の編纂にかかる村法集の記載から遡及して自由マルクの存在を立証しようとしたGierke一派の方法を攻撃するために書かれたものであつて、著者にいはせると、Gierkeが自由マルクの存在を証拠立てるものだとした規定を再検討して見ると、意外にもそこに領主が伏在してをり、これに対して農民達が何等かの夫役又は貢税を納入してゐた跡を発見する。だからGierkeが、自由マルク(freie Mark)だと信じてゐたものは、実は領主マルク(grundherrliche Mark)か混合マルク(gemischte Mark)だつたのであり、Gierkeは、彼の理論の好都合のために、これらを自由マルクと解釈したまでだといふのである。なほ自由マルク・領主マルク・混合マルクの観念については後述三参照。
九 F. Lütge, Die mitteldeutsche Grundherrschaft 1934; ders., Die Agrarverfassung des frühen Mittelalters in mitteldeutschen Raum 1937; M. Wellmer, Zur Entstehungsgeschichte der Markgenossenschaften 1938.
一〇 いはゆるマルク団体に関する無数の文献については、Vgl. R. Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts, 5. Aufl. 1930 S. 129 ff.
第一節 団体的総有
二 村と入会
入会を語るためにはまづ村から見てかからねばならないが、G. L. v. Maurerはいふ——今日、Bayern, Schweitz, Elsass, Sachsen, Westfahlen等の各地に散在する村のなかには、フランク時代から連綿として伝続せるものが相当あり、これらは屡々、フランク時代の古文書に出てゐる村名と同じ村名を担つてゐる。又北ドイツその他の各地には、中世以後の創設にかかる村が少くない。けだし十三・四世紀から十七・八世紀へかけて、貴族達は、自己所有の土地上に新村を建置し、他の地方から農民を誘致して植民させたが、かういふ村々が今日もドイツの各地に残存してゐるのである。中にはまた農民自身、自己の発意と努力とを以て新田を開拓し、荒野の中心に聚落を作つた場合もあつたが、かういふ村は、『新田』(Reut)の文字をその名に冠した。Eppenreut, Conradreut, Forenreut, Baireutなどいふ類がそれである、と(一)。
では、かやうにして作られた村々は、一体どういふ構造(Bauart)をもち、外貌をもつたかと見ると、そこに散居制(Einzelsiedlung)と群居制(Dorfsiedlung)との二様式があつたのであつた(二)——
散居制の村の特色は、可耕地(Feldgebiet)と住宅地(Dorfgebiet)との区別のない点にあつた。即ちこの種の村では各家は各自の耕地を、一の大なる可耕区の内部に密集させてゐたのではなくて、各家の建物の周囲に分散させてゐたのである。従つてこの式の村では、家と家との中間に黄菜青麦の茂るあり、離ればなれに家々は建ち、それらが連綴して一の村を形成してゐたのであつた。ゆゑにこれを系列村(Reihendorf)ともいふ(三)。
しかし系列村といへども、土地の全部を残りなく分配してゐたわけではなかつた。土地の或部分、殊に森林・放牧地・水流(Wald, Weide, Wasser)などは、共同の財産としてこれを残し、互に使用し収益してゐたのであつた。これを入会地(Allmende)といふ。従つて入会地は家々の連絡ともなり紐帯ともなつた。ややともすれば離ればなれに分裂せんとする散居制の村は、入会地を媒介として、共同体としての結束を堅くしてゐたのであつた。
群居制の村の特色は、一定の可耕区をもち、一定の住宅区をもつた点にあつた。即ちこの式の村では、各家の耕地は一大可耕区の内部に密集し、各家の建物も一大住宅区の内部に集積してゐた。ゆゑにこれを集積村(Hauendorf)ともいふ。可耕区の内部において家を建てることは許されず、住宅区の内部において耕地をもつことも許されなかつた。可耕区と住宅区とは生垣又は濠を以て区切られ、門を通つて交通した。夜間は門を閉ぢて野獣の襲来・盗賊の侵入に備へることにもなつてゐたのであつた(四)。
群居制の村もまた入会地をもつた。可耕区の周辺に横はる森林・放牧地・水流などは、入会地として各家の使用収益に公開されてゐたのであつた。
要するに中世の村は、散居制であれ、群居制であれ、みな入会地をもつてゐたのであつた。入会地をもたぬ村はなかつたらうとまでいはれてゐるのであるが、しかし、一村必ずしも一入会地をもつとは限らなかつた。数村が連合して一入会地をもつた場合もあつた。例へばここに巨嶽鬱林あり、その裾をめぐつて数村又は十数村が列置してゐたとすると、その数村又は十数村が、連合してその山嶽なり森林なりを利用してゐたのであつた。
一村入会の場合にせよ、数村入会の場合にせよ、凡そ入会地に対して利用権を有する者をマルク成員(Markgenosse)といひ、マルク成員の全体(Gesamtheit der Genossen)をマルク団体(Markgenossenschaft)といふ。一村入会の場合には、マルク団体は一村の人々の集りであり、村共同体(Dorfgemeinschaft)とその実体を一にしたが、数村入会の場合には、マルク団体は数村の人々の集りであり、村共同体を越えた一層高次の統一体として現れた(五)。
一 G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland I. 1865 S. 2 ff.
二 群居制と散居制との区別は古代からあつたのかも知れない。なぜかなら、シーザーは『ゲルマンでは一族全部が彼等に割当てられた土地の上に集り住んでゐる』といひ(Caesar, De bello Gallico VI, 22)、タキツスは反対に、『ゲルマン人は泉や野原や林に心惹かれるままに散りぢりに分れ住んでゐる』(Tacitus, Germania c. 16)と報告してゐるからである。
然らば二つの居住方法(Ansiedelungsweise)のうち、どちらが通則だつたのかといふと、十九世紀の通説は、散居制を通則と考へてゐたが、この見解は、有名なMeitzenの大研究によつて根底から覆された(A. Meitzen, Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven, 3 Bde. und Atlas zu Bd. III. 1895)。
Meitzenは旧い耕地地図を無数に蒐集し、村々の旧趾を精密に踏査し、結局、『ゲルマン人の家は、密集した集団として隣合せに建てられてゐた。村から遠く離れた場所に家の建てられてゐた形跡はない』と論結したのであつた(Meitzen, a. a. O. I. 1895 S. 46)。
但しMeitzenは思想上、G. L. v. Maurerの影響の下に立ち、史料の解釈においても、Maurerの自由マルク説を余りに多く標準にし過ぎた嫌もないではないと聞く(A. Dopsch, Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung I. 1923 S. 33, 253)。
三 散居制は、今日の通説では、耕地少き山間地帯、例へばThüringen, Tirol, Schweiz並びにWestfahlenにおいて見られた例外の現象だつた、とされてゐる(H. Cunow, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte II. 1927 S. 180 ff.)。このうちWestfahlenの散居制については特に議論が多いが、この点については、Vgl. Meitzen, a. a. O. I. S. 517 ff., II. S. 653.
四 中世ドイツの村落についてThudichumはいふ——歴史時代即ち七世紀以後は、一般に群居制が行はれ、村人達は濠又は生垣をめぐらされた一区画内に集り住んでゐた。これを垣(Zaun)といふ。垣は野獣の侵入・盗賊の襲来を防ぐためのものであつた。垣の内部では平和が保証され、貴族騎士といへども、ここでは復讐や決闘をなすことができなかつた。垣の外部には耕地があり、門をくぐつて耕地へ出た、と(Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts 1894 S. 80 f., Vgl. auch G. L. v. Maurer, a. a. O. I. S. 32)。
五 Stobbe曰く——同一のマルクを利用する者を、利用権の観点から呼んで、マルク成員といひ、マルク成員の全体をマルク団体といふ。マルク団体は、一村入会の場合には、村そのものと蓋合し、数村入会の場合には、村以上の統一体として現れた、と(O. Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts I. 1893 S. 502 f.)。なほマルクの語義については、参照、拙稿『土地所有権の成立』(『法律史の諸問題』三一六頁)。
三 毛上利用の権と地盤処分の権
入会地を構成してゐた森林・放牧地・水流の類は、何人の所有だつたのかといふと、この関係を知るためには、予め中世の村が(一)自由村(二)領主村(三)混合村の三種に分れてゐたといふことを承知しておかねばならない(一)。
自由村(freies Dorf)とは、自由農(Freibauer)達の住んでゐた村であつた。自由農は家(Haus und Hof)の所有者であり、宅地(Hofstatt)の所有者であり、又耕地(Bauerngut)の所有者でもあつた。彼は他人の土地を利用してゐたのではなくて、自己の土地を利用してゐたのである。従つて用益料としての意味においてならば、何人に対しても夫役貢租(Dienst und Abgabe)の義務を負はなかつた。ただ公課としての意味において、王又は王を代表する官吏に対して、夫役貢租の義務を負つただけであつた。尤も中世においては一般に公私の区別明かならず、公課と用益料との混同も行はれてゐたため、自由村か領主村か、判然を欠く場合もないではなかつたが、純粋な自由村においては、村民各自が土地所有者だつたのであつた。
然らば入会地はといふと、入会地の上には、『物から生じる一切の利益を自己に吸収しうる包括的な全能権』としての所有権は未だ成立してをらなかつた。入会地の上にはむしろ、その毛上(Frucht)を利用しうる利用権とその地盤(Substanz)を処分しうる処分権とが、別々に、存立してゐたのであつた。さうして前者即ち利用権の方は個々的人格としての各村民に帰属し、後者即ち処分権の方は団体としての全村民に帰属してゐた。自由村の入会地を自由マルク(freie Mark)といふ(二)。
領主村(grundherrliches Dorf)とは、いはゆる庄民(Hörige)達の住む村であつた。村民各自は宅地の所有者でもなく、耕地の所有者でもなかつた。家(Haus und Hof)だけは、通常、各村民の所有であつたが(三)、土地は宅地といはず、耕地といはず、みな領主の所有であり、各村民は用益料を支払つてそれを利用してゐたに過ぎなかつた。尤も用益の内容には複雑な差異があり、あるものは物権的、あるものは債権的、あるものは仮容的、又あるものは永代的、あるものは数代的、あるものは一代的、あるものは定期的であつたが、概していふと農民的用益権(bäuerliches Nutzungsrecht)はその効力からいつて物権的であり、その存続からいつて永代的又は数代的であつたから、それは『所有権』ではないまでも、殆どこれに近似する権利であつた。ゆゑに中世の学説は農民的用益権を性質づけて、下級所有権(Untereigentum)又は利用所有権(Nutzeigentum)なりといつてゐたのである。
では入会地はといふと、この種の村では領主が入会地の上にいはゆる上級所有権(Obereigentum)をもち、若くは所有権そのものをもつた。利用者たる個々の村民は下級所有権をもつか、若くは他物権としての利用権をもつに過ぎなかつた。領主村の入会地を領主マルク(grundherrliche Mark)といふ(四)。
混合村(gemischtes Dorf)には自由農と庄民とが混住し、若くは所属庄園を異にする庄民達が混住してゐた。さうして自由農は自己の所有地を宅地又は耕地として利用し、甲庄園の庄民は甲領主の土地を宅地又は耕地として利用し、乙庄園の庄民も乙領主の土地を同様に利用してゐた。
では入会地はといふと、毛上の利用に関しては、村民達が、自由農たると庄民たると、甲庄園の庄民たると乙庄園の庄民たるとに論なく、一様にこれを享受してゐたが、地盤処分の権は領主にあり、領主側の意思のみを以て処分してゐた。ゆゑに混合村の入会地もまた領主の上級所有権若くは所有権そのものに服してゐたのだと見ねばならない。混合村の入会地を混合マルク(gemischte Mark)といふ(五)。
以上わたくしは自由マルクの上には包括的全能権としての所有権の成立なく、むしろ毛上の利用権と地盤の処分権とが分立し、前者は村民の個々に、後者は村民の団体に帰属してゐたといつておいたが、ここは、かかる簡単な断定では済されぬ所である。よつてわたくしは一層これを詳説しようとするのであるが、それに先立ち、団体的総有(genossenschaftliches Gesamteigentum)の概念の解明に著勲のあつたO. Gierke及G. L. v. Maurerの所見を叩いておくとしよう。
Gierkeはいふのである——
『土地を所有権の対象と見ない遊牧時代の記憶は早くも消え失せてゐたが、入会地に関するかぎりは、中世の末葉まで、この観念が残つてゐた(六)。入会地を構成する森林・放牧地・水流は、何人も所有せず(Niemand eigen)、むしろすべての人が総有する(Allen gemeinen)と考へられた。Allmende (入会地)はEigen (所有地)の反対であり、ある土地がAllmendeだといふことは、それが何人の所有でもないといふ意味であつた(七)。では村民達は入会地につき全然排他的の行動・独占的の態度をとらなかつたのかといふとさうではない。村民以外の第三者(Ungenosse)が入会地に侵入し、これを占取又は利用したとすると、村民達は一団体となつてこれに対抗した。第三者との間に経界の訴が起きた場合にも、村民達は一団体となつて訴へ又は訴へられた。第三者に対して入会地の全部又は一部を処分する場合、即ちこれを分割・売買・贈与・質入する場合にも、村民達は一団体となつて行動した(八)。ゆゑに入会の法律関係は二の側面をもつたといはねばならない。入会地利用の権は村民の個々に帰属し、入会地処分の権は村民の団体に帰属したのである。前の場合には村民は『多数の個』(Vielheit)として現れ、後の場合には『一個の全』(Einheit)として現れた(九)』と。G. L. v. Maurerもまた同様の思想を異る言葉でいふ——
『村民の全体(Gesamtheit der Genossen)即ち団体(Genossenschaft)は、法的統一体(juristische Einheit)であり、又、法的主体(juristisches Subjekt)であつた。入会地処分の権のごときは、法的主体としての村民団体に帰属してゐたのである。しかし団体は決して法人ではなかつた。法人は成員から遊離して自立する第三人であり、成員達のもつ共同財産を全部自己に吸収し、成員達へは何ものも残さないが、団体は感覚的な人間の集りそのものであり、これを超越した第三人ではない。村民団体も地盤処分の権をその手にもつただけで、毛上利用の権は村民各自に残してゐた。換言すれば村民各自もまた団体と相並んで、入会地の上に各自の権利を行つてゐたのである(一〇)』と。おもふに、普通、『権利主体の多数』(Mehrheit von Subjekten)の語で呼ばれてゐる場合は、分つてこれを二となすことができよう。(一)は一の客体の上に多数の権利(mehrere Recht an einem Objekt)が存立すと構想せらるべき場合であり、(二)は多数の主体が一の権利(ein Recht mit mehreren Subjekten)をもつと構想せらるべき場合である(一一)。
第一の場合、即ち一の客体上に多数の権利存立する場合には、同一客体の上にAも権利をもち、Bも権利をもち、Cも権利をもつ。各主体の権利はそれぞれ独立する。ゆゑに本来ならば、各主体は傍ら人なきがごとくに行動しうべき筈であるが、各権利は同じ内容をもち、同じ順位に立つ関係上、互に他から制約を受けなければならない。いひかへればそこに『客体の共同』(Gemeinsamkeit des Objekts)あるがゆゑに、そこにまた『相互的制限』(gegenseitige Beschränkung)もあらねばならない。通常、人はこの場合を『持分共同』(Gemeinschaft nach Bruchteilen)といつてゐるが、実はこの場合には、一の物が分割されてゐるのでもなく、一の権利が分割されてゐるのでもない。ただ客体を共同にする多数の権利が互に他を制約しつつ並存してゐるだけである。
第二の場合、即ち多数の主体が、一の権利をもつといふ場合はAも権利をもち、Bも権利をもち、Cも権利をもつのではなくて、ABCが共同して一の権利をもち、共同してこれを行使するのである。而もこの際その多数主体は自己の存在を失つてゐない。そこにはただ多数人の集り即ちいはゆる団体(Genossenschaft)があるだけで、一個の法人があるのではないのである。法人は団体よりも一歩を進めた観念である。それは成員の外に立ち、上に立つ。従つて一法人が一権利をもつ場合は、一人格が一権利をもつといふ平凡の場合に過ぎないが、団体が一権利をもつ場合は、多数人が多数人のままにて一権利をもち、多数人のままにてこれを行使するといふ特殊の場合である。人はこれを総有共同(Gemeinschaft zur gesamten Hand)といつてゐる(一二)。
さてこれを中世ドイツの入会にあてはめて見るに、毛上の利用権は各村民に帰属してゐた。各村民はそれぞれ同一内容の、同一順位の、毛上利用権をもち、互に自己の利益のために——自家の家計のために——これを行使してゐた。ゆゑにそこには、『総有共同』はない。むしろ『持分共同』があつたのである。いひかへれば同一物上に多数の毛上利用権が相互に他を制約しつつ並立してゐたのである。
ところが地盤の処分権となるとさうではない。地盤の処分権は全村民が共同して享有し、共同して行使してゐた。ゆゑに地盤処分の権に関しては『総有共同』があつたと断じなければならない。一個の権利が団体としての全村民に帰属してゐたのだと断じなければならない。
かくのごとく入会地の上には包括的全能権としての所有権は成立してをらず、却つて毛上の利用権と地盤の処分権とが分立し分属してゐたのであつたが、二つは決して矛盾の関係には立なかつた。二つはむしろ相互補完の関係に立つたのである。O. Gierkeが美しくも表現したやうに、『村人の全体(Gesamtheit der Genossen)は、「一」(Einheit)としても現れ、「多」(Vielheit)としても現れた。「一」として即ち団体としては処分権をもち、「多」として即ち個人としては利用権をもつた。而も利用権と処分権とは有機的に相結び、調和的に相補つてゐた』ので(一三)(一四)ある。
一 中世の農民が宅地・耕地及入会地に対してどんな権利をもつてゐたかについては、Vgl. G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland I. 1865 S. 68 ff.; F. Lütge, Die Mitteldeutsche Grundherrschaft 1934 S. 65 ff.; v. Below, Geschichte der deutschen Landwirtschaft des Mittelalters 1937 S. 29 ff., 60 ff.
二 自由マルクの所有関係については、Vgl. Maurer, Dorfverfassung S. 68 ff. なほ参照、拙稿『中世の自由人』(『法律史の諸問題』一〇三頁以下)。
三 領主村においては家だけが各村民の所有であり、家の敷地は領主の所有であつたといふことについては、Vgl. G. L. v. Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt, 2. Aufl. 1896 S. 251 ff.
四 領主マルクの所有関係については、Maurer, Dorfverfassung, I. S. 72 ff.
五 混合マルクの所有関係については、Maurer, Dorfverfassung, I. S. 79 ff.
六 O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht II. 1873 S. 145.
七 Gierke, a. a. O. II. S. 145, 148. Amiraもまたいふ——Allmende (入会地)とEigen (所有地)とは相排斥する語であり、ある土地がAllmendeだといふことは、それが何人の所有でもないといふ意味であつたと(K. v. Amira, Grundriss des germanischen Rechts 1913 S. 193)。
八 Gierke, a. a. O. II. S. 151, 336. 入会地は閉された領域(geschlossenes Gebiet)であり、非村民(Ungenosse)の入込むべからざる土地であつた。非村民が入込めば村民はこれに対して対抗的態度をとることができた。Sachsenspiegelも、『入会地を犁き込み、堀込み、囲込んだ者』に対して罰金を課し、且つ侵奪地の返還を命じてゐるのである(Ssp. III. 86 §1)。ゆゑに経界の争(Grenzstreit)は入会地の所有権を眼ざめさせる刺戟剤であり,経界の平和(Grenzfriede)は入会地の所有権を眠込ませる催眠剤だつたといつていい。侵入や侵奪がなければ村民は権利主張の機会をもたなかつたのだからである。ところが村法集の規定の中には,経界の争に関するものは少いらしい。Gierkeもわづかに数例を挙げるに止まるのである。入会地の所有意識がなかなか発達しなかつたのも,かうした経界の平和が入会地所有の観念を眠込ませてゐたせいではあるまいか(Vgl. Gierke, a. a. O. II. S. 142 ff., 151)。
九 Gierke, a. a. O. II. S. 171 ff., 328 ff. und sonst durch das ganze Buch.
一〇 G. L. v. Maurer, Dorfverfassung, I. S. 83 ff. 団体と法人との区別については,拙著『中世私法史』九七頁以下が詳述してゐるので,ここでは再説を避ける。
一一 団体的総有(genossenschaftliches Gesamteigentum)の問題は,結局は,多数主体(Mehrheit von Subjekten)の問題である。なぜなればそれは,多数の主体が一の入会地を支配する場合の法理的構想に関するのだから。ゆゑにこの問題に参入するに際しては,人々は予め多数主体の法理を磨き持つてゐなければならないが,わたくしはv. Tuhrの多数主体論に拠ることにした。Tuhrの論は,従来の多数主体論の曖昧性を超克した鋭さをもつと考へたからである(Vgl. v. Tuhr, Der allgemeine Teil des duetschen bürgerlichen Rechts I. 1910 S. 78 ff.)。
一二 Binderは総有共同の観念に反対した。その理由は,多数人が一権利をもつためには持分的分数(Quotenteilung)がなければならない。持分的分数なくして多数人が一権利をもつことは論理上不能だといふにある(J. Binder, Die Rechtsstellung des Erben nach dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch III. 1905 S. 6 ff., 28.)。しかしどうしてこれが不能なのであらうか?数人が不分割のまま一の物権なり債権なりをもち,共同の意思を以てこれを行使することがどうして不能なのであらうか?持分共同が論理上可能であるやうに,総有共同も論理上可能でなければならない(v. Tuhr, a. a. O. I. S. 80 Anm. 11)。
一三 Einheit, Vielheitの語はGierkeの愛用し,頻用したところである。土地総有の関係を論じたGenossenschaftsrecht II. SS. 134--347だけをとつて見ても,何百回となくこの語が出て来るのであるが,この点につき鋭い皮肉を浴せたのがHeuslerである。曰く——Gierkeは『村民の全体は同時にEinheitであり,Vielheitである』とか,『団体的総有はEinheitsrechtとVielheitsrechtとの結合の上に立つ法律関係である』とか,凡そこの種のいひ廻はし方を,数百ページに亘り,著者も読者も,全く疲労困憊してしまふほど使用してゐるが,そこからは何等『明確な法的内容をもつた法理的構想』が浮んで来ない。これは恐らくGierke自身のもつ団体的総有の観念が,『明晰に形成化された観念』ではないためだらうと(A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts I. 1885 S. 272 f.)。
しかしわたくし自身は団体的総有の観念をさう不明晰なものだともおもはない。それは,(一)村民全体のもつ地盤処分権と(二)村民各個のもつ毛上利用権との結合の上に立つ法律関係だとして,充分明晰に把捉されうる概念なのであるまいか?
一四 Heusler自身の入会論については,後述参照。
第二節 外部からの崩壊
四 王の入会攻撃
入会地の上には、右に見たごとく、利用権と処分権の分立あり、これらを一に合せた統一的な所有権は未だ成立してゐなかつたのであるが、かかる素朴な状態がいつまでも続くわけには行かなかつた。晩かれ早かれ、それは何人かの単独所有権(Alleineigentum)へ移らねばならなかつた。
然らばそれは何人の所有へ移つたかといふと、これに根本的な二つの方向があつた。(一)は入会団体の外部に立つ勢力者即ち王や貴族が手を延ばして入会地を彼等の単独所有へ転化させて行くといふ傾向であつた。これを入会制の外部からの崩壊といふ。(二)は入会団体の内部機構が変化して団体が法人になり、入会地も法人そのものの単独所有に移るといふ傾向であつた。これを入会制の内部からの崩壊といふ。わたくしはまづ外部からの崩壊を述べようとするのであるが、それにつけても注意せらるべきは、王や貴族の入会地収奪が決して『単なる暴力』として発動せず、むしろ『正当な権利』として発動したといふ一事である。けだし中世はそれ相当に法的秩序の保たれてゐた時代だつたのであるから、王や貴族が入会地を収奪する際にも、何等かの法的名義(Rechtstitel)は必要としたのであらう。もちろん名義は僣用され、濫用されもしたが、とにもかくにも名義を必要としたといふ一事は注意に値するのである。ゆゑに入会崩壊の過程を辿るわたくしとしても、王や貴族によつて使用された入会攻撃の法的名義から見てゆかねばならない。
まづ王の使用せる法的名義から見ると、(一)王は入会攻撃のために『特別支配の権』を使用することができた。特別支配の権とは何かといふと、王は国土及国民の全範囲に対して一様無差別な保護又は支配を加へることができ、これを王の一般命令権(allgemeine Befehlsgewalt)といつてゐたが、王の権限はこれだけに尽きたのではない。王はさらに国民中の或部分、国土中の或部分に対して、特別の保護又は支配を加へることができたのであつて、これを王の特別支配(Bann, Banngewalt)といふのである(一)。
特別支配の権は適当の保護者を欠く人又は物に対して発動した。例へば寡婦孤児に対する特別保護・外国人ユダヤ人に対する特別保護。又、一般的な保護のみを以てしては充分ならずと見た場合にも発動した。例へば官吏に対する特別保護・教会に対する特別保護。
特別支配の内容は、罰則附の命令又は禁令であつた。即ち王は特別保護の客体に対して、一定の行為を為すべきこと若くは為すべからざることを命じ、違反者へは一定の罰金を課することができたのである。
これを入会地に当てはめてみると、入会地の上には、未だ統一的全能権としての所有権の成立を見てゐなかつたのであるから、それは、『適当な保護者を欠く物』に外ならなかつた。従つて王としては、それへむかつて特別支配の権を発動させることができた。例へば入会地の利用規則を定め、マルク団体の機関を任命し、入会地の一部を囲込んでこれを王の特別利用地とし、一般人のこれに立入るのを禁じ、違反者へは一定の罰金を課すごとき、これである。但し罰金は60 solidiを以て限度とした(二)。
(二)王はまた入会攻撃のために『独占』(Regalien)の法理を使用することもできた。よつてこれについても簡単な説明を加へておくと、中世の王は、公法上ばかりでなく、私法上も特別の地位にあり、私益の獲得についても、特別の便宜を享有してゐたのであつた。即ち王は他人を排斥し、若くは他人に優先して、ある種の私法上の利益を独占することができた。例へば一般に無主の不動産を独占することができたごとき、特定の山岳・森林・水流につき、採鉱権・狩猟権・漁撈権を独占することができたごとき、これである(三)。
独占は特別支配の権とは異つた。特別支配の権は公権であり、王がこれを行使するのは、これによつて人民保護の職責を全うせんがためであつたが、独占は私権であり、王がこれを行使するのは、これによつて王室の財産を増大せしめんがためであつた。
従つて特別支配の権の使用によつて入会地を収奪せんとする場合には、王はまづ入会地の利用方法に干渉し、村民達を入会地の利用から遠ざけてゆくことによつて、これを王有に移すといふ、いはば迂回的な順序に出でざるをえなかつたが、独占によつて収奪せんとする場合には、王は入会地又はその一部分を無主物なりと宣言して、これを王有に移すといふ、いはば直接的な順序に出ることができたのであつた。而してこれを当時の形勢に見ると、国土の全面は果てしも知らぬ森林の海に蔽はれ、その或ものは入会地。その或ものは無主地。その或ものは入会地か、無主地か、不明だつたのであるから、王は、その欲する箇所に対して、容易に独占権を発動させ、これを無主物なりと宣言することによつて、これを自己の所有に移すことが可能なのであつた。
一 ,,Bann``の語に『特別支配』の訳語を当てた理由について一言する——普通はBannは『罰令』と訳される。けだし王は一定の罰金附にて命令又は禁令を発することができたのであり、さうしてかかる罰金附の命令又は禁止を,,Bann``といつてゐたのであるから、,,Bann``に対して『罰令』の訳語を当てても不当ではないのである。
しかし罰令の根拠、即ち王は一体いかなる権限に基いてかかる罰令を発しえたかの点になると説は分れる。第一説はいふ——王の一般命令権(allgemeine Befehlsgewalt)はさまざまの形で表現した。罰令もその表現の一つである。即ち罰令は王の一般的職権(allgemeines Amtsrecht)そのものからの流出であつたと。称してこれを一般支配説といつてよからう。Zallingerによつて唱へられ、多くの人々から支持を受けてゐる(v. Zallinger, Über den Königsbann. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung Bd. III. 1882 S. 539 ff.; ders., Zur Geschichte der Bannleihe. Ebenda Bd. X. 1889 S. 224 ff.)。
第二説はいふ——罰令は特別の人又は物に対する保護又は支配である。普通以上の厚い保護・普通以上の厳な支配が、罰令の罰令たるゆゑんである。ゆゑにそれは王の一般的職権からの流出ではない。それはむしろ王の特別保護権、即ち必要があれば一定の人又は物に対して特別の保護者(Schutzherr)又は後見人(Muntherr)として現れうるといふ王の特別資格からの流出であつたと。称してこれを特別支配説といつていいであらう。Volteliniによつて唱へられ、Waasによつて最も力強く主張されてゐる(Voltelini, Königsbannleihe und Blutbannleihe. Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte 36 1915 germ. Abt. S. 247; A. Waas, Herrschaft und Staat im deutschen Frühmittelalter. Historische Studien. Heft 335 1938 S. 29 ff., 50 ff., 75 ff., 112 ff.)。
わたくしがいま,,Bann``に対して『特別支配』の訳語を当てたのは、Waas一派の特別支配説に動かされるところがあつたからである。
序に右のWaasの新著Herrschaft und Staat im deutschen Frühmittelalter 1938について一言すると、この書はOtto大帝の事業の中にドイツ肇国の精神を発見しようとする。曰く——Ottoこそはドイツに初めて政治的統一性を与へた人であり、ドイツ民族のために発展の礎石をおいた人である。ドイツはOtto以来ドイツとなり、ゲルマン族一般から異るものとなつた、と(Ebenda, S. 356 ff.)。けだし従前の中世解釈は、Karl大帝を中心に据え、フランク時代を以てドイツ史の第一期なりと見て来たのであるが、WaasはむしろOttoを中心に据え、彼のいはゆる『ドイツ的早期中世』(deutsches Frühmittelalter)、即ち従来の用語例に従へば、『早期皇帝期』(frühe Kaiserzeit)といひ来つたところのものを、ドイツ史の第一期なり、と見るのである。ここにWaasの特色があり、否、ナチス学者一般の中世解釈の特色がある。
二 王がその命令又は禁令の違反者に対して課しうる罰金の額には法律上の制限があつた。即ちそれは60 solideを越えてはならぬとされてゐたのである(Lex Ribuaria 35, 3. 58, 12. 60, 3. 65, 1, 3. 73, 1, 2, 4. 87. Vgl. auch H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II. 2. Aufl. S. 46 ff., Seeliger, Art. Bann, Banngewalt. Hoops Reallexikon.)。
三 独占(Regalien)については拙稿『狩猟権及漁撈権』が詳述してゐるので、再説を避ける(『法学』九巻三号及び四号殊に三号五頁以下)。
五 高級貴族の入会攻撃
高級貴族(hohe Adel)とは、諸候(Fürst)・僧正(Bischof)・守護(Graf)・地頭(Freiherr)等々、凡そ領地を有し、政治的支配権をもつ人々をいふが、彼等がかかる権利をもつに至つた原因に二つある。(一)は王の授権である。王は彼等に一定の領地を贈与又は封与すると共に、領地内において王の職権の全部又は一部を行使することをも可能ならしめたから、彼等はこれによつて政治的支配権の主体とならねばならなかつた。これについては説明の必要がない。(二)はいはゆる自由支配(Immunität)である。即ちまづ王から自由支配の権を与へられ、恣ままにこれを拡張して政治的支配者となるに至つたのであつた。これについては説明の必要がある。
おもふに自由支配の観念はローマ法に淵源する。ローマでは皇帝の所領は課税を免れ、皇帝から贈与された臣下の土地も課税を免れ、さうしてかかる課税の免除を,,immunitas``と呼んでゐたが、フランク王朝もこの制度を踏襲し、王の所領及び王から贈与又は封与された臣下の所領を特別地とし、これには租税を課せず、さうしてこれをも,,emunitas``と呼んでゐた。ゆゑにImmunitätの本来の内容は消極的であり、単に王の課税を拒否できるとか、国司(Graf)の干渉を阻止できるとかいふ程度に止まつてゐたのであつたが、幾何もなくして積極的内容へ転じ、自由支配者(Immunitätsherr)は、自由支配区(Immunitätsbezirk)の住民から自由に租税を取立てて自己の用に当てることができるとか、住民に対して自由に警察の権・刑罰の権・裁判の権を行使することができるとかいふ程度へまで進展したのであつた(一)。
しかし王の直接授権によつたにせよ、自由支配権の濫用によつたにせよ、とにかく高級貴族達は、政治上の支配権者となつてゐたのであるから、彼等はこの権力を背景として、領内の入会地に対して特別支配の権を揮ふこともでき、独占の権を用ゐることもできたのであつた(二)(三)。即ち彼等は、(一)王がさうしたと同じやうに、領内の入会地につき利用規則を作り、マルク団体の機関を任命し、入会地の一部を囲込み、一般人民のここに立入ることを禁じ、違反者ヘは一定の罰金を課することができたし、又(二)王がさうしたと同じやうに、領内の入会地の一部を無主の不動産なりと宣言して、これを彼等自身の所有地に編入することもできたのであつた。
但し命令の違反者に対する罰金の額は王のそれよりも低く、12, 6, 3 solidiの程度であつた。
一 自由支配権の歴史については、Vgl. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II. 1928 S. 382 ff.
二 中世の地主が借地人に対して半国家的権力(pseudo-od. halbstaatliche Gewalt)を揮つてゐたといふ事実そのものは何人も疑はぬ所であるが、かかる権力の由つて来つた根拠に関しては、見解が分れる。第一説はいふ——中世においては土地所有権そのものが住民支配の権を産んだ。凡そ地主は借地人から地代を徴取しえたばかりでなくて、借地人に対して政治的支配権即ち裁判の権・警察の権・刑罰の権をも揮ひえたのであると。これを領主説(grundherrliche Theorie)といふ。Lamprechtを以てその代表者とする。(K. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I. 1886 S. 991; Vgl. auch v. Below, Der deutsche Staat des Mittelalters 1914 S. 90 f.)。
第二説はいふ——中世の実際を見ると、地主必ずしも政治的支配者ではない。いはゆる自由農(freier Bauer)は、屡々その所有地を他人に賃貸してゐたが、彼等は借地人に対して地代を請求しえたに止まる。決して借地人に対して政治的支配権を揮つてはゐなかつた。ゆゑに政治的支配権を以て土地そのものの従物だと見ることは出来ない。それはむしろ貴族身分の従物だつたのである。貴族は王からの直接授与によつて半国家的権力の主体となり、若くは自由支配権の濫用によつて半国家的権力の主体となりえた。貴族身分は、かかる権力取得のための、必要欠くべからざる前提だつたのである、と。これを貴族説(Adelstheorie)といふ。Dopschがこの説の代表者である。彼の新著Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit 1939は、『貴族にあらざれば政治的支配権の主体となりえなかつた』と、口を極めて、力説してゐるのである(Ebenda, S. 1 ff., 219 ff.)。
三 高級貴族そのものについては、拙稿『中世の貴族』(『法律史の諸問題』七二頁以下)が述べてゐるので、ここでは述べない。
六 下級貴族の入会攻撃
下級貴族(niederer Adel)とは騎士(Ritter)をいふ。騎士はもと不自由人であつたが、十五世紀以後、高級貴族が邦主権(Landeshoheit)を獲得して藩(Land)の君主となるに至つた結果、これに奉仕してゐた騎士達も期せずしてその地位を高め、藩の貴族たる身分へ上ることとはなつたのである(一)。
下級貴族は藩の君主即ち高級貴族から領地を受けた。さうして領内の人民に対して任意に命令し、課税し、この命令を強制するために、裁判の権・警察の権・刑罰の権をも揮ふことができた。要するに下級貴族は、高級貴族が王国内において占めたと同様の地位を、藩内において占めたのである(二)。
だから彼等もまた、(一)高級貴族がさうしたと同じやうに、領内の入会地に干渉し、その利用規則を立て、マルク団体の機関を任命し、入会地の一部を囲込んで一般村民のこれに立入ることを禁じ、違反者へは一定の罰金を課することができたし、又(二)高級貴族がさうしたと同じやうに、入会地の一部分を無主物なりと宣言して、これを自己の所有に移すこともできたのであつた。
一 下級貴族がいはゆる下級裁判権(Niedergerichtsbarkeit)を獲得し、領内の人民を自由に支配しうるに至つたのは、十五世紀頃からであつたが、処によつてはもつと早く、十三・四世紀の頃からかかる形勢の樹立を見たといふ(A. Dopsch, Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit 1939 S. 15 ff.)。なほ下級貴族の発生史としては、拙稿『中世の貴族』(『法律史の諸問題』七一頁以下)。
二 下級貴族もまた貴族たる資格において領内の人民を支配してゐたのであり、地主たる資格においてこれを支配してゐたのではなかつた。いひかへればわれらは、貴族説(Adelstheorie)又は身分説(Standestheorie)を以て下級貴族の政治的支配権を説明すべきであり、領主説(grundherrliche Theorie)又は庄園説(hofrechtliche Theorie)を以てこれを説明すべきではないのである(A. Dopsch, a. a. O. S. 15 ff., 220 f.)。
七 学説の入会攻撃
学説もまた入会に対して攻撃的姿勢をとつた。分割所有権(geteiltes Eigentum)の理論がこれであるが、これを知るためには、一言、ローマ法における準訴権(actio utilis)の観念にふれなければならない——
ローマの大法官は、原告の主張が新規のものであつて、既存の訴権のいづれにも該当しないが、しかし衡平の観念上、その主張を貫徹させなければならないと見る場合には、擬制を以てその主張を既存の訴権のいづれかに該当すと看做して、これにその訴権を与へ、又は既存の訴権のいづれかを模型として、これに準ずる新訴権を作り、これを以て原告の主張の貫徹を援護したのであつた。かかる訴権を準訴権(actio utilis)といひ、準訴権に対して典型となつた旧訴権を本訴権(actio directa)といつた(一)。例へば大法官法上の相続人たる遺産占有者(bonorum possessor)に対して、準訴権として、市民法上の相続人(heres)が有すると同様の訴権を与へ(二)、地上権者(三)・永小作権者(四)に対して、準訴権として、所有者が有するのと同様の訴権を与へたごとき、これである。
かくのごとくローマ法においては、準訴権は本訴権の拡張又は模倣であつたが、もとより本準の間には差別あり、準訴権を以て保護されてゐる主張と本訴権を以て保護されてゐる主張とを混同することは許されなかつた。例へば地上権はあくまでも地上権であり、永小作権はあくまでも永小作権であり、いかにこれに対して所有権同然の訴権が与へられてゐればとて、これと所有権そのものとを混同することは許されないのであつたが、中世の末葉、註釈学者(Glossatoren)の時代に入ると、この点につき重大な誤謬が犯されることとなつた。
それは、準訴権(actio utilis)の『準』(utilis)の字を『利用』(brauchbar, nützbar)の意味に解し、地上権や永小作権は、利用所有権(Nutzungseigentum)だと考へるに至つたことであつた(五)。彼等によると、所有権は本所有権(dominium directum)若くは上級所有権と、利用所有権(dominium utile)若くは下級所有権との二つに分割される。地上権や永小作権は下級所有権であり、農民がその用益地に対してもつ農民的用益権(bäuerliches Nutzungsrecht)・市民がその用益地に対してもつ市民的用益権(bürgerliches Nutzungsrecht)・武士がその用益地に対してもつ武士的用益権(Vassalennutzungsrecht)も、下級所有権である。これらは他物権(jus in re aliena)のやうに他人の所有権を制限せず、むしろこれと平行して存在する。その機能も他物権以上に土地の利用の中に深く喰込んでゐる。ゆゑにそれは、一種の所有権でなければならない。即ち所有権は上級所有権と下級所有権との二権に分割され、同時に同一物上に並立してゐるのである、と(六)(七)。
だから分割所有権の理論は、市民及農民の地位に抑圧を加へようとの動機に発したものでは決してなかつた。動機はむしろ逆だつたのである。それは、市民及農民のために、『他物権』よりも一層強大な内容をもつ別の権利を尋ね、『下級所有権』においてこれを発見したのであつた。それは、下級者の犠牲において上級者を利したのではなくて、上級者の犠牲において下級者を利したのであつた。
しかし入会地に関する限りは結果は逆にならざるをえなかつた。なぜかなら入会地は宅地や耕地とは性質を異にする。宅地や耕地は貴族の所有地であり、市民及農民はこれを用益してゐたに止まつたから、学説がいま、上級下級二所有権の並立を認め、市民及農民に下級所有権を認めてくれたとすると、それは、市民及農民には思はぬ利益を、貴族には思はぬ損失を与へることとなつたであらうが、入会地は、元来貴族の所有地ではない。それは未だ何人の所有ともなつてをらず、ただ農民達の使用収益の対象となつてゐただけであるから、学説がいま、上級下級二所有権の並立を認め、貴族に上級所有権を認めてやつたとすると、それは、貴族へは思はぬ贈物を、農民へは思はぬ打撃を喰はしたことになる。なぜかなら貴族はこれによつて今まで権利をもたなかつた土地の上に、上級所有権といふ一種の所有権をもつこととなるのに反して、農民達は今まで何人の所有でもないと信じてゐた土地の上に、貴族の上級所有権を発見し、自分達は貴族の上級所有権を侵犯せざる範囲内において下級所有権を享有するに過ぎないといふことになつてしまふのだからである。
畢竟、分割所有権の理論は二重の作用をもたらした。宅地及耕地に関しては市民及農民を利し、入会地に関しては貴族を利したのである。
一 ローマ法における本訴権及準訴権の観念については、Vgl. L. Wenger, Institutionen des römischen Zivilprozessrechts 1925 S. 158 f.; C. Crome, Grundzüge der römischen Privatrechts 2. Aufl. S. 28 ff.
二 Inst., 3. 9; Gaj., 3, 32--8.
三 Dig., 43, 18, 1, §6.
四 Dig., 6, 3, 1, §1.
五 Glossa ad L. 1 et 2 Dig. de bonor. poss. 37, 1; ad L. 2 Dig. de superf. 43, 18; Noch weitere Belege bei Kraut, Grundriss zu Vorlesungen über des deutsche Privatrecht 1886 S. 171 ff.
六 註釈学者が,,utilis``の語を誤読して利用権(Nutzungsrecht)の意味にとり、この誤解の上に分割所有権の理論を組立てたといふことは有名な事実であるが、この事実を初めて発見したものは、A. F. J. Thibautであつた。彼はその著Versuche über einzelne Teile der Theorie des Rechts II Teile 1798--1801の中に含まれてゐる,,Über dominium directum, und utile``なる論文の中において、註釈学者が、その理論の粗笨さから又この理解の浅薄さから、『分割所有権』なるローマ法外の新法理を造出するに至つたといふことを明白に証拠立ててゐるのである(Thibaut, a. a. O. II. S. 70 ff., Vgl. auch E. Landsberg, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft III. 2. 1910 S. 83 f.)。
七 今日においても通説は、分割所有権の理論は註釈学者の犯した『誤謬』の中から生れたと見てゐる。例へばLandsbergはいふ——ローマ法では、所有者ならざる者に対して、衡平法上、所有者と同然の保護を加へた場合があつた。地上権者や永小作権者に、準所有物返還訴権(vindicatio utilis)を認めてゐたごときがそれであるが、註釈学者となると、訴訟法上、同一の取扱を受けてゐるものは、実体法上の性質をも一にすると速断してしまつた。かくして地上権及永小作権は所有権そのものの一種に数へられ、準訴権(actio utilis)は一転して利用所有権(dominium utile)そのものとなつてしまつた、と(E. Landsberg, Die Glosse des Accursius und ihre Lehre von Eigentum 1883 S. 98)。
尤も一派の学者は註釈学者が分割所有権の理論を立てたのは、法源の誤読からでなくして事実状態の考察からである。当時の事実として、そこには多くの用益権、即ち農民的用益権・市民的用益権・武士的用益権などが散在し、而してこれらは『他物権』の範疇に入れらるべくあまりに特異の存在だつたのであるから、註釈学者としては、これらを種類づけるために、分割所有権なる新範疇を作らざるをえなかつたのだ、といふのである(G. Phillips, Grundsätze eines Systems des deutschen Privatrechts. Mit Einschluss des Lehnrechts 3. Aufl. 1846 S. 19)。
傾聴に値する一説だとはおもうが、反対説もないではない(L. Duncker, Über dominium directum und utile. Zeitschrift für deutsches Recht II. S. 117 ff.)。
八 攻撃の敢行
以上わたくしは王や貴族が入会攻撃のために、特別支配権・独占権・上級所有権等の法理を使用したと述べたが、事実上これらを使用して入会地の収奪を行つた例は、中世においては、甚だ稀であつたであらう。なぜかなら中世の森林は一村一地方の需要に供せられてゐただけであり、全国的意味はもたなかつたのであるから、王や貴族が強権をふりかざして森林の全面的統制に乗出すといふ必要は殆ど感じなかつたであらうからである。もちろん王や貴族が土地の収奪を行つたといふ例は中世にも沢山あつたが、それは、無主地か所有者不明地かに対して行はれただけであり、入会地即ち村民が現に使用収益しつつある土地へ向かつて収奪の手を延ばしたといふ例は極めて稀でしかなかつたのであつた。
ところが十六世紀以後になると情勢は大いに変つて来た。けだし十六—八世紀は経済学者のいはゆる領域経済(Territorialwirtschaft)の時代であり、都市よりは大・国家よりは小なる無数の領域(Territorium)の散布を以て特色づけられた。ドイツだけでも三百から四百の藩(Land)があり、それぞれ領域全体の統一的発達のために果敢な政治を行ひつつあつた。内にあつては商業の発達・交通の開発・通貨の統一・ツンフトの抑圧・庄園及入会の破壊・外にたいしては輸入の禁止・輸出の統制・旅行の取締・関税の重課——それらが一連の国策として至上命令的に敢行されつつあつたのであつた(一)。
森林だけに限つていへば、当時はBücherのいはゆる木材時代(Holzzeitalter)であり、未だ金属時代(Metalzeitalter)にはなつてゐなかつた。建築にも木材が用ゐられ、造船にも木材が用ゐられた。什器も木器であり、燃料も木炭であつた。従つて藩としては森林の問題に無頓着であるわけにはゆかなかつた。彼は鉱山・冶金・製塩・牧畜の諸事業に対して統制を加へたやうに、森林の管理及経営に対しても統制を加へねばならなかつた。すでにわたくしは十六世紀以後各藩は先を競つて森林統制法(Forstordnung)を制定したといつたが、これは森林が当時の国家に対して、恰も石炭や石油が現代の国家に対してもつのと同じやうな意義をもつてゐたからであつた。
それに財政的原因が協働した。藩の面積は五千平方キロから二万平方キロ。人口は五十万から二百万。即ちその規模は決して大でなかつたにもかかはらず、その有する官僚の数はなかなかの多数に上つてゐたから、藩はこれらを維持するためにも、収入の増加を企てねばならなかつた。いはゆる財政家達(Kameralisten)は、この目的のために、智嚢を搾つて建策した人達であつたが、彼等の進言した方策の中には、入会地の収奪・入会地利用の制限・入会地利用者への課税が包含されてゐたのであつた。即ち藩は、入会攻撃のための諸武器、特別支配権・独占権・上級所有権及これらの新たなる統一物として現れた森林高権(二)(三)(Forsthoheit)を、現実に行使して、入会地の収奪を敢行せねばならぬ場合となつたのである。
が、何にしろ入会地は現に村民達が使用収益しつつある土地であつたから、これを高級又は下級の貴族の手へ移すといふについては、どうしてもそこに多少の無理を犯さざるをえぬ事情があつた。v. Thudichumは当時の模様を叙していふ(四)——
『十三世紀以来貴族の子弟はParis, Orleans, Montpellier等に学び、当時フランスにおいて通用してゐた上級所有権の理論を学んだ。さうしてこれをドイツに持込み、入会地の上に貴族の上級所有権を確立しようと企てた。しかしこれがためには村民達をして彼等が現に使用収益しつつある森林が、実は彼等の所有でなくして、却つて貴族達の所有だといふことを承認せしめる必要があつたから、貴族達は、村民をしてこれを承認せしめるために、種々の手を用ゐた。中には村民の代表者を館に招待して酒を振舞ひ、酔を利してこの事を承認せしめた例さへあつた。往々、村法集に『土地は君主に、利用は農民に』(dem Landesherrn gebührt Grund und Grat, den Bauern der Nutzen, der Gebrauch)とか、『地盤は君主に、毛上は農民に』(dem Herrn weist man den Boden, den Bauern den Wald, das Holz)とか、いつてゐるが、これらは大抵、貴族の誘惑又は強迫の下に、心ならずも村民の為したる自白であつたのである』と。又いふ——
『貴族は時として入会地につき所有権そのものを主張した。この場合には村民は曩の入会地即ち今の貴族地につき、単なる他物権者として、利用権をもつこととなり、若くは全然権利をもたず、ただ貴族の恩恵によつて、事実上の利用に浴するだけとなつた。現にMainzの大僧正は一五二五年に、Rheingauの村民達をして、大僧正を入会地の所有者と認める旨の証書に署名せしめてゐるのである。かうした例は他にもいくらも転がつてゐたことであらう』と。又いふ——
『古文書の偽造は教会が種々の目的のために屡々用ゐた狡猾な手段であつたが、入会地の収奪のためにもこの手を用ゐた。即ち教会は、ある森林を収奪したいとおもふ場合には、それが、その昔カール大帝より教会へ賜れる聖なる賜物であつた旨を証明するやうな古文書を巧みに偽造したのである』と。さらにいふ——
『一六三一年、フランス軍侵入の際、Winden及Weinährの二村は、裁判古記録の入つてゐる書函を、領主たるArnstein修道院に保管してもらつた。フランス軍が退却してしまつてから、右書函の返還方を修道院に請求したが、修道院は言を左右に托して返還してくれなかつた。恐らく右書函の中には村人の権利を証明する、従つて領主たる修道院にとつては不利なる書類が、一杯充満してゐたのであらう』と。何にしろ十六—八世紀は各藩が猛烈な発展欲に駆られて性急な政治を行つてゐた時代だつたのであるから、入会制の分解のためにも、多少の無理は敢へてこれを辞しなかつたものと見えるのである。Thudichumが挙げたやうな例は、彼自身がいふやうに『いくらも転がつてゐたことであらう』。
然らばその結果はどんな状態となつて現れたか?わたくしは次にこれを語らねばならない。
一 G. Schmoller, Das Merkantilsystem in seiner historischen Bedeutung. Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs-und Wirtschaftsgeschichte, 1898. 柚木重三『独逸経済史概説』(『経済史研究』三三—四九号連載、殊に三八号及三九号)。
二 森林統制法のあるものは藩主所有の森林の管理方法を規定するに止まつた。一五三二年のHessen法のごときこれであるが、その大部分は、入会山林の管理及経営にまで干渉した。一六一四年のWürtemberg法、一六二九年・一六五九年・一六八二年・一六八八年のHessen法、一六一六年・一六二〇年・一六五〇年・一六八三年・一六九〇年・一七二六年のBayern法のごときみなこれである。かやうに私人所有の山林の経営にまで干渉しうる国家の権力を森林高権(Forsthoheit)といふのである(G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland II. 1866 S. 202 ff.)。
三 森林統制法は、その主要規定として、村民に対しては、林務官(Förster)の許可なき伐木を禁じ、一定の需要を越えてなほ余りある部分を都市の市場へ移出すべきことを命じ、外国への輸出を禁じ、都市の木材加工業者に対しては、優先的に木材の配給を受けうる権利を保証してゐるのである(Maurer, a. a. O. II. S. 202 ff.; K. Bücher, Die Entstehung der Volkswirtschaft II. 7. Aufl. 1922 S. 41 ff.)。
四 v. Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts 1894 S. 423 ff.; ders., Die Gau-und Markverfassung in Deutschland 1860 S. 294 ff.
九 攻撃の結果
王・高級貴族・下級貴族の、永年に亘る入会攻撃の結果、殊に十六—八世紀におけるそれの尖鋭化の結果、どのやうな状態が現出されたかといふと、第一は自由マルク(freie Mark)の減少であつた——
中世の頃は自由農は沢山あり、自由村や自由マルクも随所に存在してゐた。自由農の地位も低くはなかつた。Maurerに従ふと、自由農はその富において騎士に劣らず、その名誉においてもこれと相引き、中には優に農民貴族(Bauernadel)を以て目すべきものさへあつたといふ。しかし十六世紀以後になると、彼等と騎士との間の身分的開きが大きくなつた。騎士は貴族となり、治者となり、政治に参画する身分となつたのに、自由農は貧農となり、庄民となり、純然たる被治者に堕してしまつたからである。農民貴族としての自由農は少くなり、自由村も自由マルクも少くなつた(一)。Dopschに従ふと、自由マルクの名を保つてゐた入会地さへ、その実は、領主を頂き、領主に対して保護料又は用益料を支払つてゐたといふ(二)。Gierkeなどはいづれかといふと、自由マルクの存在を大袈裟に見積つてゐた方であるが、それでさへ、後期中世における自由マルクの激減は認容せざるをえなかつたではないか(三)。
しかし自由マルクの全滅を速断してしまつても、これまた早計であらう。Thudichumが見たやうに、Westfahlen, Niedersachsen, Hessen, Wetterau, Nassau及びMain, Necker, Rhein三河の上流、並びにSchweizのUri州などでは、近く現代に至るまで、自由マルクの残像が見られたからである(四)。
一 Maurerはいふ——UngarnにはCortesと称する農民貴族がをり、多額納税者として議会へも出席してゐたが、彼等こそは昔日の自由農の後身であつた。ドイツにおいても、Oldenburg地方の農民は概して富裕であり、教養もあるが、これも彼等が自由農の後身だつたためである。大体昔日の自由農は、皆かうした地位にあり、騎士と同格を保つてゐたのであつたが、十字軍以来、騎士の地位は上り、自由農の地位は下り、次第に庄民(Hörige)の地位へ近づき、遂には全くこれと合流して、農民(Bauer)なる新階層を形作るに至つたと(G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland II. 1866 S. 191 ff. Vgl. auch v. Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts 1894 S. 129 ff.)。 二 Dopsch, Die freien Marken in Deutschland 1933は、自由村の名を冠した村々が実際は領主村又は混合村であつたことを立証せんとする目的そのもののために書かれてゐるのである(参照、前出一ノ註九)。
三 O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht II. 1873 S. 158 ff.
四 v. Thudichum, a. a. O. S. 404 ff.
第二は自由マルクが保護マルクに転化し、藩主の保護権(Schirmgewalt)に服するに至つたことであつた(五)——
元来自由村は自治村であり、村の事務(Gemeindeangelegenheiten)の全部を自治的に処理してゐた。殊に入会関係の事務は、規則の制定にせよ、機関の選挙にせよ、規則違反者に対する制裁にせよ、村の管轄に専属し、他人の容啄を許さなかつたのであるが、十六世紀以後になると、藩の勢力が強くなり、藩主が王の権限を引継ぎ、否、王のもつてゐなかつたやうな権限さへももつに至つた。けだし中世の王は治安の維持(Erhaltung des Landfriedens)を念とし、既成の秩序の存続に任ずるのみだけだつたから、その活動は消極的であり、村の自治ともよく平行することができたが(六)、近世の藩主は公共の福祉の増進(Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt)を念とし、藩の発展を人為的に促進しようとしたから、その活動は積極的となり、村の自治とは両立し難くなつたのであつた(七)。入会だけに限つて見ても、藩はみづから利用規則を制定し、機関を任命し、規則の違反者を処罰した。藩は今や自由マルクの後見者(Muntherr)となり、保護者(Schirmherr)となつたのである。従つてこれに対して課税することもできるやうになつた。もとより自由マルクは村民自身の総有に係つたから、用益料の意味においてならば、これに負担を課するわけに行かなかつたが、保護料の意味においてならば、負担を課するに差支なかつたのである。而も保護料の内容は夫役貢租(Dienst und Abgabe)の二種から成り、用益料との間に実質上の区別がなかつたから(八)、村民からすれば、保護料=用益料であり、藩主の支配=領主の支配(Landesherrschaft=Grundherrschaft)であつた。
さうしてこの種の入会地、即ち自由マルクでありながら保護料を支払つてゐる入会地が、非常に多くなつたのであつた(九)。
五 自由村の保護主となつたのは、多くは藩主(Landesherr)であつたが、普通の領主(Grundherr)が保護主となつた場合もないではなかつた。領主の大なるものは超庄園的勢力であり、わが庄園の人民ばかりでなしに、附近一帯の自由民をも支配してゐたから、彼等が自由村の保護主となつたのは、ごく自然の過程であつたのであつた。殊に教会や修道院が保護主となつた場合が多かつた。なほこの点については参照、戒能通孝『農地収益権に関する一考察』(『法学新報』四七巻六号四八頁註五)。
六 中世の王はキリスト教を保護し、国内の秩序を維持する最高の裁判所であつた。王が教会へ種々の特権を附与し、異端を取締り、寡婦孤児を保護したのは、キリスト教の保護者としてのその任務に由来したのである。又王が下級裁判所の判決につき控訴を受理し、下級裁判所の裁判を監督するために国内を巡回したのも、最高裁判所としてのその任務に由来したのである。しかし裁判(das Richten)とは、既成の秩序を保持し、その違反を正しきに還らす意味を出でなかつたから、王の活動も勢ひ消極的となり、治安警察の線内に自己を制限しなければならぬのであつた(K. F. Eichhorn, Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte II. 5. Aufl. 1843 S. 351 ff., H. Zoepfl, Deutsche Rechtsgeschichte II. 4. Aufl. 1872 S. 254 ff., F. Walter, Deutsche Rechtsgeschite I. 2. Aufl. 1857 S. 302 f.)。
七 近世の藩主の任務は安寧秩序の保持のみに存せず、公共の福利(allgemeine Wohlfahrt)の増進にも存した。国家の発展を人為的に助長し促進することが、彼の任務の重心でさへあつたのである。彼が市民の生活へ直接に干渉し、いはゆる警察政治を敢行したのも、彼が単なる司法官でなくして、行政官であつたからであつた。ゆゑにわたくしはいふ——中世の王の任務は消極的であり、司法的であり、治安警察的であつたが、近世の藩主の任務は積極的であり、行政的であり、助長警察的であると。一は『秩序の原理』で働き、他は『福祉の原理』で働いた。
八 保護料もまた夫役及貢租から成り、実質上用益料と区別がなかつたといふことについては、O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht II. 1873 S. 166 ff.
九 保護マルクは自由マルクの一種であり、その所有権は明かに村民の手にあつたが、村民は自由にこれを処分することができず、保護主の同意を得て処分しなければならぬのであつた(G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland I. 1865 S. 78)。
第三は自由マルクが領主マルク又は混合マルクに転化し、さうして領主の上級所有権に服するに至つたことであつた(一〇)——
元来入会地は、自由村においてはもちろん、領主村においても、混合村においても、もとは村民の総有だつたのであつ(一一)(一二)た。領主は宅地や耕地の上にこそ所有権はもつたれ、入会地の上には所有権をもたなかつたのであるが、永年に亘る領主の入会攻撃の結果は、彼等の上級所有権となつて示現した。領主は今や入会地の上級所有権者となり、村民は単なる下級所有権者となつてしまつたのである。
もとより下級所有権は他物権ではなくて、所有権そのものの一種ではあつたが、しかしそれが『自由な所有権』ではなくて、『負担附の所有権』だつたことも事実であつた。それには用益料といふ一種の負担が附着してゐたのである。即ち、村民は用益料として、年々一定の夫役貢租を領主に納付せねばならぬのであつた。処分の権も領主に移つてしまつた。領主は村民の同意を得て、入会地を売買・贈与・質入することができた(一三)。
Gierkeは、この種の入会地、即ち領主がその上に上級所有権をもつところの入会地が、数において、一ばん多かつたらうと見てゐる(一四)。
一〇 ここに庄園(Hofgemeinde)と村(Dorfgemeinde)との関係をのべておくと——庄園は『領主(Grundherr)への奉仕』を中心とした観念であり、村は『村内の居住(häusliche Niederlassung)』を中心とした観念であつた。ゆゑに(一)別の村に居住する人々も、頂く領主さへ同一であれば、同一の庄園に所属した。而もかうした例は稀ではなかつた。なぜかなら領主の大なるものは屡々数ヶ所に亘る大庄園をもつてゐたから。(二)同じ村に居住してゐる人々も、頂く領主が別々であれば、別々の庄園に所属した。而もかうした例もまた稀ではなかつた。なぜかならいはゆる混合村では、村民の或ものは甲領主を頂き、或ものは乙領主を頂き、或ものは全然領主を頂かなかつたからである。(三)一村全部が一領主を頂く場合にも、庄園と村とは観念を異にし、組織を別にした。村民は領主に従ふと同時に村総代にも従ひ、領主へ庄園的夫役貢税(Hofdienst und Abgabe)を納付すると同時に、村へも村的夫役貢税(Gemeindedienst und Abgabe)を納付したからである(G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland I. 1865 S. 115 ff.)。
一一 領主村における入会地の所有関係については、Maurer, a. a. O. I. S. 72 ff.
一二 混合村における入会地の所有関係については、Maurer, a. a. O. I. S. 79 ff.
一三 入会地処分の権は上級所有権者即ち領主にあつたが、現実に処分権を行使せんとするに当つては、領主は村民即ち下級所有権者の同意を得なければならなかつた(Maurer, a. a. O. I. S. 77)。
一四 O. Gierke, Genossenschaftsrecht II. S. 161.
第四は自由マルクが領主マルク又は混合マルクへ転化し、而も領主の単独所有権そのものに服するに至つたことであつた——
この場合には入会地は村民の総有でもなく、下級所有でもなく、むしろ領主の財産であつた。領主その人の、自由にして真正なる特別財産(freies und echtes Sondereigentum)であつた。名称上もこの場合には入会地(Allmende)といはれず、貴族地(Herrengut)といはれた。それに対する村民の関係は、全く、他人の財産に対する関係であつた(一五)。即ち村民は、(イ)貴族地たる森林や放牧地に対して他物権を設定し、他物権者としてこれを利用するか、(ロ)領主の恩恵にすがつて事実上の利用に浴させてもらふか、(ハ)そこはもう、村民の近づくべからざる禁制区(Forst)だとして遠方から眺めてゐるか、三つに一つを撰ぶより外はなくなつた。このうち法律的に問題とするのは、(イ)の場合、即ち村民が他物権者として貴族地を利用する場合であるが、これについてはさらに後述する(一六)(一七)であら(一八)う。
要するに王及貴族の永年に亘る入会攻撃の結果は、(一)自由マルクの減少となり、(二)保護マルクの増加となり、(三)領主マルク又は混合マルクの増加となり、(四)貴族地そのものとさへなつてしまつたのであるが(一九)、これらは要するにマルク団体の外部に立つ勢力者即ち王や貴族による入会攻撃の結果だつたのであるから、一括してこれを外部からの崩壊といつてよからう。わたくしが第二節を表題して『外部からの崩壊』といつたのはこの理に由る。
しかし入会地の利用権が他物権的性質をとるに至つたのは、外部勢力者の攻撃にのみ原因したのではない。村そのものが団体性を喪失して法人性を獲得し、もと村民の総有だつたものが、村そのものの単独所有に移つたといふこと、従つて村民としては、他物権者として入会地を利用する外に方法がなくなつてしまつたといふこと、にも原因したのであつた。さうしてこの過程は、これを内部からの崩壊といつても差支ないであらう。なぜかなら村の法人化は、村の内部構造そのものの変化であつたから。よつてわたくしは第三節を『内部からの崩壊』と題して、村が法人となり、入会地が村そのものの所有となるに至つた過程を跡づけることとしよう。
一五 O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht II. 1873 S. 159 f.
一六 Gierkeは入会に二つの根本型を考へた。(一)は自由マルクである。即ち村民が入会地の上に自由にして完全なる総有権をもつ場合。(二)は貴族地である。即ち貴族が自由にして完全なる単独所有権を有し、村民は貴族の恩恵により、仮容的(prekarisch)にそれを利用させて貰つてゐる場合。さうして氏はさらに右二つの根本型の中間に三つの中間型が介在すると考へた。(一)は村民が他物権者として貴族所有地を利用してゐる場合。(二)は貴族が上級所有権を有し、村民が下級所有権を有する場合。(三)は貴族が自由マルクの上に保護権をもつ場合。
わたくしが入会を分つて、(一)自由マルク(二)保護マルク(三)領主マルク(四)貴族地(五)恩恵地の五種としたのも、Gierkeに従つたのである(O. Gierke, a. a. O. II. S. 156 ff.)。
一七 他物権時代に入ると、利用分(Nutzungsquote)が、入会地の所有者即ち領主と、他物権者即ち村民との間の契約を以て、精確に一定されるやうになつた。或は(一)伐採の対象が一定された。例へば建築材(Bauholz)・燃料材(Brennholz)・垣根材(Zaunholz)・器具材(Geschirrholz)のうち何れか一を限つて伐採権を認めたごときこれである。或は(二)伐採の方法が一定された。入会権者自身は、伐採することをえず、領主の役人が伐採して引渡すべしとしたごときこれである。領主の役人はみづから斧を揮ひ、伐倒した木材を林道まで運出し、林道にて入会権者に引渡した。
一八 恩恵地の利用についても厳重な制限があつた——(一)果実を結ばぬ松・樅・白樺の類に限つて伐採しうるとか、(二)軟木即ち白楊・柳の類に限つて伐採しうるとか、(三)風に吹落された樹枝(Windbruch)に限つて伐採しうるとか、(四)領主が森林中に捨置いた木材(Ausholz, Überholz, Lagerholz)に限つて、伐採しうるとかいふごときこれである。
| 所在地\所有者 | 団体トシテノ村 | 法人トシテノ村 | 私人殊ニ貴族 | 国 家 |
| Bayern | −−− | 297, 218 | 1, 246, 776 | 829, 483 |
| Württemberg | 11, 720 | 174, 463 | 205, 695 | 193, 591 |
| Baden | 2, 233 | 249, 070 | 189, 868 | 98, 584 |
| Hessen | 2, 224 | 87, 047 | 81, 210 | 69, 512 |
| Nassau | 3, 845 | 162, 098 | 14, 195 | 50, 815 |
| Nannover | 90, 190 | 27, 110 | 250, 026 | 236, 691 |
一九 v. Thudichumは十九世紀末における森林及放牧地の所有状態を上表で示した(v. Thudichum, Geschichte des duetschen Privatrechts 1894 S. 411 f.)。
第三節 内部からの崩壊
一〇 村民権の拡張
村が法人化して行つた過程を跡づけるためには、まづ(一)村の成員の変化を見、(二)村の機関の変化を見、さらに(三)村の事務の変化を見なければならない。まづ村の成員の変化から見るとしよう——
自由村においても、領主村においても、混合村においても、村民は四つの身分別から成つた。(一)全権村民(二)半権村民(三)無権村民(四)名誉村民がこれである。
全権村民(vollberechtigte Genosse)とは村の政治に参与し、入会地利用の権利を有し、村の費用をも負担してゐる村民のことであるが(一)、いかなる人々がこの身分に入つたかといふと、家をもち、世帯をもち、耕地をもつてゐる人々であつた。即ち全権村民たるには、(一)家(Haus und Hof)をもつ必要があつたが(二)、宅地(Hofstatt)をもつことは必ずしも必要でなかつた。自由村においては、土地が村民の所有となりえた関係上、宅地の所有が村民権の要件をなしてゐたが、領主村や混合村においては、土地は領主の所有であり、村民はこれを領主から借りて用益してゐたに過ぎなかつた関係上、宅地の所有は村民権の要件とはなりえぬのであつた(三)。(二)世帯(Haushaltung)をもつ必要があつた(四)。家と世帯は、大体において一致してゐたが、例外として家持ちではあるが、世帯持ちではないとか、世帯持ちではあるが家持ちではないとかいふ人々もあつた。さうして、かういふ人々は全権村民とはなりえぬのであつた。(三)耕地(Bauerngut)をもつ必要があつた。自由村では耕地の所有権をもつことが要件であり、領主村又は混合村では、耕地の用益権をもつことが要件であつた(五)。
他所者(Fremde)を全権村民として採用するには、村又は領主の許可を必要とした。領主なき自由村では、村が許可を与へ、領主ある領主村又は混合村では、領主が許可を与へた。許可料(Aufnahmegeld)は、自由村では、村の収入となり、領主村及混合村では、村及領主の収入となつた(六)。
全権村民が家を失ひ、世帯を失ひ、耕地を失へば、全権村民たる資格を喪失した(七)。
一 全権村民の呼称はHuber, Hübner, Bauer等々、地方により区々であつた(G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland I. 1865 S. 132 ff.)。
なほ全権村民については、Vgl. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht I. 1868 S. 593 ff., II. 1873 S. 268 ff.
二 家の所有が全権村民たるための要件だつたといふことについては、Maurer, a. a. O. I. S. 61, 122.
三 領主村では村民は家(Haus und Hof)の所有者であつたが、宅地(Hofstatt)の所有者ではなかつたといふことについては、G. L. v. Maurer, Einleitung der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt 1896 S. 252.
四 世帯の独立を示すために、中世の人々はさまざまの表現を用ゐた。例へば『自己の竈』(eigener Herd)・『自己の煙』(eigener Rauch)・『自己のパン』(eigenes Muss und Brot)・『自己の料理』(gesonderte Speise)等々(Vgl. Maurer, Dorfverfassung I. S. 124 ff.)。
五 耕地の所有又は用益が必要だつたかどうかの点については、実は意見の対立がある。或はいふ——村民権取得のためには村の区画内で家をもち、世帯をもつてゐればそれだけで足りた。耕地をもつ必要はなかつた、と。これはThudichum及Schröderの説である(v. Thudichum, Geschichte des deutschen Privatrechts 1894 S. 407, 415; ders., Die Gau- und Markverfassung in Deutschland 1880 S. 221, 224; Vgl. auch R. Schröder, Lehrbuch der duetschen Rechtsgeschichte 7. Aufl. 1932 S. 458 Anm. 9.)。
或はいふ——十七・八世紀になると村民権の拡張が行はれ、村内の居住者全部が村民権をもつやうになつたが、中世の頃はさうでなかつた。中世の頃は耕地の所有権又は用益権が要件だつたのであると。これはMaurer及Gierkeの説である(G. L. v. Maurer, Dorfverfassung I. S. 120, 125 ff.; ders., Geschichte der Markverfassung in Deutschland 1858 S. 78 ff., 82 ff., 106 ff.; O. Gierke, Genossenschaftsrecht I. S. 163 f., 563 ff., II. S. 268 ff.)。
本稿はMaurer及Gierkeの説に従つた。
六 他所者の採用については、Maurer, Dorfverfassung I. S. 132 ff. 七 村民権の喪失については、Maurer, Dorfverfassung I. S. 185 ff.
半権村民(halbberechtigte Genosse)とは村の政治に参与できず、入会地の利用にも制限を受け、村費の負担も軽減されてゐる村民のことであるが(八)、いかなる人々がこの身分に入つたかといふと、耕地をもたない人々、即ち家をもち世帯ももつてゐるが、耕地に対しては所有権もなく用益権もないといふ人々であつた(九)。従つて借地農(Pächter)はこの身分に入つた。借地農は債権的に他人の土地を利用してゐただけで、物権的に利用してゐたのではなかつたから。それにその耕作面積も狭小。使用農具も簡単。犁(Pflug)をもたず、牛馬ももたないのが常であつた(一〇)。
しかし半権村民の主要部を占めてゐたのは、何といつても職人であつた。職人は元来都市の居住者であり、藩は村内には職人を居住せしめない方針をとつてゐたのであつたが(一一)、若干の職人は、村落生活の運営そのもののために欠くことができなかつた。よつてHessenでは、鍛冶工・裁縫師・亜麻織工に限つて村内の居住を許し、Brandenburgでは、鍛冶工・裁縫師・亜麻織工・パン工・大工・車工に限つて村内居住を許し、その他の諸藩でも、それぞれ種類を限つてこれを許した。さうしてこれらの村職人(Dorfhandwerker)が、村の半権者の主要部を構成してゐたのである(一二)。
半権村民の負担は全権村民よりも少く、全権村民の、或は1/4或は1/8であつた(一三)。居住の許可料も全権村民の場合に比して著しく少額であつた(一四)。
無権村民(nichtberechtigte Genosse)とは村の政治にはもちろん、入会地の利用にも与りえず、村費をも負担しない人々のことであるが、いかなる人々がこの身分に入つたかといふと、家すら有しない人々であつた(一五)。即ち、(一)僕婢はこれに入り、(二)未成年の子・未婚の子もこれに入つたが、何といつてもその主要部は(三)借家人(Hausling, Miethling)であり、殊に家を借りてゐる職人であつた。家をもつ職人が半権者だつた間に、家をもたぬ職人は無権者に過ぎなかつたのである(一六)。
最後に名誉村民(Ehrgenosse)とは全権村民としての要件には欠けてゐるが、全権村民と同一若くは近似の待遇を受けてゐる人々のことであり、牧師・教師などがこれに入つた(一七)。
以上は十五・六世紀頃の状態であるが、その後大きな変化が生じた。全権村民・半権村民・無権村民・名誉村民の区別が消え、村内の居住者全部が村民となり、全部が参政権をもち、入会地利用権をもち、村費をも負担するに至つたことがそれである。
その由来を考へてみるに、十五・六世紀以来交通は開かれ、商業は発達し、人事百般が流動性を帯びて来た。他所者(Fremde)が村内へ、職人として、商人として入来るやうになり、村民中にも農を捨てて手工業へ転じ、商業へ走るものが多くなつた。而もこれらの職人や商人は、その富と力とにおいて全権村民に譲らず、否、これをも凌がんとする勢だつたから、彼等は村民権の賦与を翹望してやまなかつた。加ふるに村の費用は逐年嵩み、従来の、全権村民のみを担税者となす租税体系を以てしては、到底、村費を賄ひ切れなくなつて来たので、いつその事、村民権を拡張して居住者全部を村民とし、居住者全部の上に課税しようといふ所にまで進んでしまつた(一八)。Maurerに従ふと、この改革を最初に断行したのは、SchweizのGlarus州であつたといふ(一九)。ここでは十六世紀において村民権の拡張を行つてゐるのである。ドイツの各藩も十七・八世紀において同様の改革を行つた。
さてかやうに村民権が拡張され、一列平等、全部の者が村民だといふことになると、村の組織法そのものをも変革せざるべからざる必要を感じ来る。即ち団体(Genossenschaft)としての組織を改めて、法人(Korporation)としての組織へ転ぜざるべからざる必要を感じ来る。何となれば、拙著『中世私法史』が詳論してゐるやうに、団体組織は、成員の数も少く、交替も少く、成員相互の間に利害の対立・意見の相異も少い場合に対してこそ適合的であるが、成員の数も殖え、交替も盛んに、利害の対立・意見の相異も甚しくなつて来ると、法人組織の方がはるかに適合的となるからである(二〇)。現に十七・八世紀に現れた町村制の大半は、村をば法人として性質づけてゐるが、これは、法人組織の方が、変化せる村の事情に適合したためであつたであらう。
八 半権村民の呼称も、Beisasse, Köter, Häusler, Huttner等々、地方的に区々であつた(G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland I. 1865 S. 136 ff.)。なほ半権村民についてはGierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht I. 1868 S. 603, II. 1873 S. 281, 381 ff.
九 半権村民は小屋(Häuschen)をもち、小菜園(Gärtchen)をももつた。稀には小耕地(Kleingut)をもつたものもないではなかつたが、概していふと、家持ち(Hausbesitzer)ではあるが、土地持ち(Grundbesitzer)ではない、といふのが半権村民の特徴であつた(Maurer, a. a. O. I. S. 138 ff.)。
一〇 借地農(Pächter)は大抵、完全村民から成下れる人々であり、耕地は失つてゐたが、小屋はもち、小菜園ももつてゐた(Maurer, a. a. O. I. S. 138 ff.)。
一一 農村が職人をもつと、都市の繁栄の妨害になつた。なぜかなら、農村が職人をもつと、農民が手工業品の購入のために都市へ出かけて来る場合が減じてしまふからである。藩が職人の農村居住を禁じたもの、かうした理由からであつた。参照、拙稿『中世都市の法』(『法律史の諸問題』一三〇頁以下)。
一二 各藩がいかなる職人の村内居住を許可したかについては、Maurer, a. a. O. I. S. 144 ff.
一三 半権村民の負担額については、Maurer, a. a. O. I. S. 140 f.
一四 半権村民に対する居住許可については、Maurer, a. a. O. I. S. 179 f.
一五 無権村民に対する呼称もUngeerbte, besitzlose Leute等々地方的に区々であつた(Maurer, a. a. O. I. S. 141 ff.)。なほ無権村民については、Vgl. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht I. 1868 S. 606 f., II. 1873 S. 280 f.
一六 自己の居宅(Wohnung)をもたぬ点が無権村民の特色だつたといふことについては、Maurer, a. a. O. I. S. 141 ff.
一七 牧師及教師が名誉村民の主たるものだつたことについては、Maurer, a. a. O. I. S. 155 ff.
一八 十五・六世紀以前における村組織の変化については、Maurer, a. a. O. I. S. 163 ff.
一九 Maurer, a. a. O. I. S. 164.
二〇 拙著『中世私法史』九七頁以下殊に一二七頁以下。
一一 機関の官僚化
村の機関としては、(一)村総代(二)村参事会(三)村民大会(四)村裁判所があつた。
村総代(Gemeindevorsteher)は村民大会これを選挙し、その数は一人又は数人。時とすると十数人。村民大会から委任された事務を執行したが、重大な問題については、大会を召集してその議決を経た(一)。
村参事会(Gemeinderat)は、小さな村は置かず、大きな村だけが置いた。やはり村民大会の選挙にかかり、その数は数人又は十数人。村総代の相談役たるに止まり、固有の権限はもたなかつた(二)。
村民大会(Gemeindeversammlung)は全権村民全部の集りであり、村の辻・橋の袂・教会堂の中などで開かれた。村総代は、鐘や角笛を鳴らして村民大会を召集するのを例とした。全権村民は全部これに出席すべき権利及義務があり、欠席すれば罰を受けた。議長は村総代がこれに当つた(三)。
裁判会(Dorfgericht)は裁判を目的とする村民大会そのものであつた。耕地に関する争・入会地利用規則の違反・平和侵害・殊に窃盗・傷害などがその管轄の主なるものであつた。審理は村総代がこれに当つたが、判決は陪席者たる村の長老がこれを発見した。村総代は法の問ひ手(Frager des Rechts)であり、長老は法の答へ手(Antworter des Rechts)であつたのである。村民は立会人(Umstand)として審理及判決を監視した(四)。
判決に対しては控訴がなかつた。耕地・入会地に関する事件といひ、村の平和(Dorffrieden)に関する事件といひ、みな村専属の事件であり、村のみがこれを裁判しうる、と考へられてゐたからである(五)。
以上は十五・六世紀頃までの状態であつたが、その後大なる変化が生じた。藩の官吏が村に出張して、村総代の執務を監視するやうになつたことがそれである。村総代は一々藩吏の指図を受けなければならなくなつた。殊に村民大会の召集には藩吏の許可が絶対の必要事となつた。中には村総代をも廃止し、単に村参事会のみを置き、これを相談相手として藩吏が村務を処理するといふ式の地方さへ生じた(六)。
藩はまた村裁判会の判決に対して控訴を受理した。中には村裁判所を廃し、従来の村裁判所の管轄を藩裁判所に移管したものさへ生じた(七)。
要するに十六世紀以来、村の自治は急速に失はれたのである(八)。従つて村の団体性も失はれなければならなかつた。なぜかなら団体は元来デモクラチックな組織である。成員の意思が重んじられ、総会の権威が認められてゐる間は団体組織でもよろしいが、それらが失はれて来ると、団体組織そのものもまた不適合となつて来るのである(九)。法人組織への移行は、早晩、時間の問題でなければならなかつた。
一 村総代の権限・数・呼称等については、G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung II. 1866 S. 22 ff.
二 村参事会の権限・数等については、Maurer, a. a. O. II. S. 65 ff.
三 村民大会の召集方法・集合場所・決議の方法等については、Maurer, a. a. O. II. S. 76 ff.
四 村裁判所の管轄・手続・執行等については、Maurer, a. a. O. S. 115 ff.
五 村裁判所の判決に対しては、もと控訴がなかつたといふことについては、Maurer, a. a. O. II. S. 141 f.
六 十六世紀以後における村組織の変化に関しては、Maurer, a. a. O. II. S. 265 ff.
七 十六世紀以後村裁判所の判決に対して控訴の道が開かれたといふことについては、Maurer, a. a. O. II. S. 142.
八 中世の自由村の自主独立性を最もよく証拠立てるものは、犯人庇護の権(Asylrecht)である。村内で犯罪が発生した場合又は犯人が村内へ逃込んだ場合、王吏は、自身村内へ立入つてこれを逮捕することができず、村総代が逮捕して王吏へ引渡してくれるのを俟たねばならなかつた。中には王吏へ引渡すことさへも拒み、村自身、犯人を処罰した地方さへもあつた(Sachsenspiegel II. 66 §I, II. 71 §5. Vgl. auch Maurer, a. a. O. II. S. 168 ff. 176)。
九 拙著『中世私法史』一二六頁以下。
一二 村の法人化
村の事務には、入会地・耕地及これと関連をもつ事項が多かつた。入会地についていへば、その利用規則を作るとか、違反を取締るとか、経界を見廻るとか(一)、他村民による越境を看守るとか、森林の増殖を図り、水流の浚渫を試みるとかいふの類。耕地についていへば、三圃式経営を指揮するとか、耕地侵害・水路妨害などを取締るとか、経界引縄に立会ふとか、土地売買に立会ふとか、牛馬・鶏豚の類が他人の耕地において生ぜしめた損害につき、その賠償を命ずるとかいふの類(二)。
もちろん村は平和団体(Friedensgenossenschaft)だつたから、村の平和(Dorffriede)の保持にも任じ、村内で発生した窃盗(三)・傷害(四)・不正の取引、殊に度量衡の不正(五)などをも裁判し、処罰したが、いづれかといふと、これらは副次的な任務に過ぎなかつた。主要なものはやはり土地関係の事務だつたのである。
以上は十五・六世紀頃の状態だつたが、その後大なる変化が生じた。いはゆる警察事項(Polizeisachen)、即ち内務行政事務の、著しき増加がこれである。入会の事・耕地の事はもはや村の重要事務ではなくなつた(六)。重要事務は、学校の事・教会堂の事・公会堂の事・消防の事・救貧の事・用水の事・度量衡の問題・建築の問題などであつた。国道の修理・橋梁の架設・土堤の構築・租税の取立・兵士の募集——これも村の重要事務となつた。村はパン屋・肉屋の取締・賭博飲酒の取締・ダンスの取締(七)から欠食児童の世話(八)まで焼かねばならなくなつた。即ち村は、村民自身の目的に奉仕するよりも、国家目的の達成に協力するものと化したのである。従つてその法人化——公法人化——も免るべからざる運命となつた。何となればそれはもはや村民が、彼等に共通する事務を処理するために設立した集団ではなくて、国家が、国家事務の一端を担当させるために設立し又は認可した集団となつてしまつたのであるから。それはすでにその自主性を失ひ、国家機構の中へ、その一部として巻込まれてしまつたのであつた。
かくして村は自己を法人として性質づけざるべからざる最後の段階へと到達した。十八・九世紀に現れた町村制は、大抵、村はこれを法人とする旨、明言してゐるのである。
例へば一八〇八年のBayern町村制第七条及第十条。一八一八年のBayern町村制第一条及第二十条。一八三一年のOldenburg町村制第十七条。一八四一年のPreussen町村制第一条。一八四五年のPreussen町村制第一条等々は、村は法人なる旨を明言してゐるのである(九)。
学説も、反対の規定なき限り、村は法人と認めらる、と説くに至つた(一〇)。
かくして村は法人化の階段にまで昇りつめたのである(一一)。従つて入会地所有の関係にも大変化を生ぜざるをえぬこととなつた——
一 経界廻りをGrenzbegehungといふ。Grenzbegehungは村の年中行事であり、村の祭礼でもあつた。村人達は村の神像(Götterbild)を神聖な車(heiliger Wagen)に乗せ、山車でも引くやうに、引巡したのである(G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland II. 1866 S. 6 ff.)。
二 Maurer, a. a. O. II. S. 3 ff.
三 村落における窃盗犯人の処罰については、Vgl. Sachsenspiegel II. 13 §1 u. 2; Schwabenspiegel (Wackernagel) c. 119; Schwabenspiegel (Lassberg) c. 174.
四 村落における傷害犯人の処罰については、Vgl. Sachsenspiegel I. 68 §2.
五 村落における不信売買者の処罰については、Vgl. Sachsenspiegel II. 13 §3.
六 営業警察(Gewerbepolizei)が、火警察(Feuerpolizei)森警察(Waldpolizei)等と共に、村の主要行政事務であつたといふことについては、Maurer, a. a. O. II. S. 10 ff.
七 十六世紀以来ダンスも取締の対象となり、時間的・場所的・服装的にこれを制限するやうになつた。殊に戦時中はダンスを一般的に禁止する例でもあつた。これらの諸点については、Vgl. Marianne Panzer, Tanz und Recht. Deutsche Forschungen herausgegeben von F. Panzer u. J. Petersen Bd. 32, 1938 S. 12 ff.
八 十八世紀以来、強制就学(Schulzwang)が始まり、貧困児童も学校へ入り来つたので、児童の保護が問題になり、殊に欠食児童の保護が問題になつた。Basel, Zürich, Wurzburgでは、欠食児童に対して或は食事を給し、或は金銭を与へなどした(Maurer, a. a. O. II. S. 240 f.)。
九 Maurer, a. a. O. II. S. 289 ff.
一〇 Savigny, System des heutigen römischen Rechts II. 1840 S. 242.
一一 法人の歴史については、拙著『中世私法史』九七頁以下。
一三 法人化の結果
村の法人化は全権村民の地位、殊に入会権者としての彼等の地位に、大影響を与へねばならなかつた。なぜかなら村の法人化の結果、無権村民もまた『村民』となり、今まで全権村民のみで独占し来つた入会地へ、無権村民もまた利用権者として参加し来らんとする形勢をば示したからである。よつて全権村民は入会地だけは彼等の独占に残しておかうと企てた。無権村民と合併して村を作り、すべての財産を共同にするやうにはなつたが、入会地だけは、旧村民即ち全権村民の間だけで、管理し利用したいといふのが、彼等の偽らざる希望だつたのである(一)。
この希望はSchweizにおいて実現を見た。例へばZürich湖畔の一村Stäfaでは、百五人の旧村民が入会地を独占し、新村民のこれに参加し来るのを拒んだのである。この百五人を伐木仲間(Holzgenossen)といひ、その他のものを仲間外(Ausgenossen)といふ。一六八八年になると、二個の集団は全く分離し、伐木仲間は入会地ばかりか、公会堂その他の財産までも独占してしまつた。一六九四年に至つて再び合併して一村を作り、公会堂その他は共同にもつやうになつたが、入会地だけは、依然、伐木仲間だけで独占してゐた。彼等は独立の一集団として、自己を含む大なる村の内部において、小なる一村を形成してゐたのである(二)(三)。
Bern州のBern村でも旧村民は村の中に村を作り、入会地の利用を独占してゐた。その他の村々でも同じ現象が見られた。概してSchweizでは、旧村民が特権団体(Privelegskörperschaft)を形成するといふ傾向が強かつたのである。
南ドイツの村々でも、かうした傾向は見られた。現にMannheimに近きOppauの村では、三十人の旧村民が特権団体として入会地を独占してゐた。Westfahlenの所々でも同じ現象が見られたといふ(四)。
いま右のごとき入会地を独占してゐる完全村民の一団を『部落』(Realgemeinde)と呼び、これを『村』(Ortsgemeinde)に対照させて見るに、(一)区域的には、村は自己の中に部落を含む広い区域をもち、部落は村の内部において狭い区域をもつてゐた。ゆゑに人々は村を大村(weitere Gemeinde)と呼び、部落を小村(engere Gemeinde)と呼ぶ。(二)成員からいふと、村は財産資格を要求せず、村内に住所をもつ者の全員に村民権を与へてゐたが、部落は財産資格を要求し、耕地の所有権者又は用益権者に対してのみ部落員(Realgemeindemitglieder)たる資格を認めた。ゆゑに人々は村を住民村又は身上村(Einwohnergemeinde od. Personalgemeinde)といひ、部落を物上村(Realgemeinde)といふ。(三)社会的に見ると、村の成員中には昔日の無権村民即ち職人や無産者が混入してゐたが、部落の成員は全部昔日の完全村民であり、家や土地の持主であつた。彼等は家柄も旧く、富もあり、勢力もあつた。村役場(Dorfregiment)を事実上動かしてゐたのは彼等だつたのである。HeuslerやGerberは、部落民は村の貴族(Dorfpatriziat)だつたとまでいつてゐる(五)(六)。
(四)法律上の性質はといふと、村が公法人であつたことはもちろんであるが、部落は一概にきめることができない。もちろん部落は公法上の人格はもたなかつたが、私法上の人格は、或はもち、或はもたず、地方によつて区々であり、学説もまた区々であつた。即ち一派の学者はいふ、ローマ法の継受以来、ドイツの団体はみな法人となつてしまつたのであるから、部落もまた、疑ある場合には(in dubio)、法人と推定せらるべきであると。他派の学者はいふ、部落は中世の村の直系の後裔であるから、中世の村と同様、団体(Genossenschaft)としての性質を保有しなければならないと。ローマニステンが多く法人説にくみし、ゲルマニステンが多く団体説に傾いた(七)。
いづれにせよ部落に政治的機能の欠けてゐたことは事実だつたから、人々は部落を私的村(Privatgemeinde)といひ、村を政治村(politische Gemeinde)と呼んだ。
一 スヰス及南ドイツにおける新旧二村民の間の対立抗争については、G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland I. 1865 S. 165 ff.; O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht I. 1868 S. 675.
二 Stäfa村における新旧二村民の抗争史については、Maurer, a. a. O. I. S. 165 f.; Gierke, a. a. O. I. S. 684 Anm. 99.
三 村の財産は二つの部分に分れた。一は村の公の目的に奉仕する財産である。これを『村の財産』(Gemeindevermögen, Geimeindeeigentum)といふ。村の公会堂・金銭のごときはこれに属した。二は個々の村民の経済的目的に奉仕する財産である。これを『村民の財産』(Genossengut, Gemeinheitsgut)といふ。入会地はこれに属した(Maurer, a. a. O. II. 1866 S. 252; Gierke, a. a. O. I. S. 663 Anm. 23, S. 683 f.; O. Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts I. 3. Aufl. 1893 S. 507)。
四 Bern村やOppau村における新旧村民の抗争史については、Maurer, a. a. O. I. S. 167.
五 村と部落との比較については、Gierke a. a. O. I. S. 673; A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts I. 1885 S. 291 f.
六 部落即ち物上村(Realgemeinde)の構成員達を一種の村貴族(dorfliche Adel)と見る説は、Heusler, a. a. O. I. S. 291; Gerber-Cosack, System des deutschen Privatrechts 17. Aufl. 1895 S. 80.
七 部落法人説・部落団体説の対立については、Maurer, a. a. O. II. S. 269 ff. 部落法人説の代表はRömerである。彼はローマ法継受以後の団体は原則として法人なりとの理由から、部落もまた法人ならざるべからずと論結した(Römer, Über die rechtliche Natur der Realgemeinden und Realgemeinderechte. Zeitschrift für deutsches Recht XIII. S. 103 ff.)。
部落団体説の巨擘はいふまでもなくGierkeである(Gierke, a. a. O. II. S. 325 ff., ders., Deutsches Privatrecht I. 1895 S. 602 ff.)。
さて問題は入会地の所有、即ち入会地は村の所有であつたか、部落の所有であつたか、部落員の所有であつたかにあるが、これに対しては、統一的な答へは与へられない。地方的相異の甚しいものがあつたからである——
(一)は団体としての部落に入会地を総有させてゐた地方であつた。換言すれば、全体としての部落民が処分及管理の権をもち、個人としての部落民が利用の権をもつと見た地方であつた。Schweizにこの例が多く(八)、ドイツにもないではなかつた(九)(一〇)。
八 G. L. v. Maurer, Geschichte der Dorfverfassung I. 1865 S. 165 f., II. 1866 S. 259; O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht I. 1868 S. 683 f.; ders., Deutsches Privatrecht I. 1895 S. 593. 九 Vgl. die Zitate bei G. Beseler, System des gemeinen deutschen Privatrechts I. 1885 S. 330 Anm. 10.
一〇 わが国の入会に関しても、部落を団体と見、入会地を部落民の総有に帰せしめんとする見解がある。例へば末弘厳太郎・農村法律問題一九頁以下。石田文次郎・土地総有権史論五七九頁以下。
(二)は法人としての部落に入会地を所有せしめた地方であつた(一一)。この場合には、部落員は部落所有の入会地の上に他物権(jura in re aliena)としての利用権をもつに過ぎない、と考へられた(一二)。
一一 Gierke, Genossenschaftsrecht I. S. 693; ders., Deutsches Privatrecht I. S. 593.
一二 Renaud, Die Gemeindenutzungen, insbesondere die Realgemeinderechte in ihrer geschichtlichen Entwicklung und rechtlichen Natur betrachtet, mit vorzüglicher Berücksichtigung der schwizer Verhältnisse. Zeitschrift für deutsches Recht IX S. 95 ff.; Römer, Über die rechtliche Natur der Realgemeinden und Realgemeinderechte. Ebenda. XIII S. 94 ff.
(三)は個々の部落員に入会地を共有させた地方である。この場合には、部落員は入会権者としてよりも、共有権者として、入会地を利用してゐた。
立法例としてはプロイセン州法がこの主義をと(一三)(一四)り、学説としてはDunckerがこの見解をとつた(一五)。
一三 Preuss. A. L. R. I, 17 §1 ff., u. 317 ff. Maurerによると、一七八五年六月四日のOsnabrück法も、入会地を村民の共有(Miteigentum)としたといふ(Maurer, Dorfverfassung II. S. 223. Vgl. auch die Zitate bei Gierke, Genossenschaftsrecht I. S. 664 Anm. 25)。
一四 中には入会共有を普通の共有から区別し、入会共有の場合には共有物の分割処分管理等につき特別の制限を受くと定めた立法もないではなかつた(O. Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts I. 3. Aufl. 1893 S. 509 Anm. 23)。
一五 Duncker, Gesammteigentum 1843 S. 169 ff.
(四)は法人としての村が入会地を所有し、個々の部落員が、慣習上又は契約上、村所有の入会地の上に他物権を有すと見た地方であつた。
学説としては、Maurer, Thudichum, Beseler等がこの見解に賛し、殆ど通説たる地位にあつた(一六)。
一六 Maurer, Dorfverfassung II. S. 224 f.; Thudichum, Die Gau-und Markverfassung in Deutschland 1860 S. 314 ff.; Beseler, System des deutschen Privatrechts I. 1885 S. 329; ferner die Zitate bei Gierke, Genossenschaftsrecht I. S. 664 Anm. 26--28.
(五)は法人としての村が入会地を所有し、個々の部落員が、村民たる資格に基いて、入会地の上に優先的利用権を有すと見た地方であつた。この際、部落員即ち優先的利用権者は株式会社における優先株主に比較されるのが例であつた。
Gerber-Cosackがこの説をとつ(一七)(一八)た。
一七 Gerber-Cosack, System des deutschen Privatrechts 17. Aufl. 1895 S. 81.
一八 本説と似て非なるものは、Heuslerの見解である。曰く——入会地の利用は、権利ではなくて事実である。村民は、財団法人の受益者が財団から利益を受けるやうに、又、一般公衆が公物から利益を受けるやうに、入会地から事実上の利益を受けるに過ぎないと。又曰く——凡そ制限物権は、所有権の反抗者である。それは所有権本来の流れに反抗し、本来の目的の実現を制約するものとして設定されるが、入会地の利用は、入会地の所有権に対してかかる逆行関係に立たない。それはよく入会地の所有権と平行して流れて行く。けだし入会地は、村民によつて利用されることを恰もその目的としてゐるから、村民がこれを利用するのは、入会地をしてその本来の使命を達成せしめる所以だと見なければならぬからと。さらにまたいふ——村は何時にても入会地利用規則を改廃することによつて、村民を入会地の利用から遠ざけることができた。この一事を以てしても村民の入会地利用が権利でなくして事実であつたことが明かであるであらうと(Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts I. 1885 S. 273 ff.)。
しかしわたくしはHeuslerの見解に従ふことができない。なぜかといふと、ゲルマン法には公共の利用に供せられる四個のWがあつた。Wald, Weide, Wasser, Weg (森林・放牧地・水流・道路)がこれである。而してこのうち、道路だけは他の三者から区別され、早くより公法の領域に取入れられたが、これは道路と他の三者即ち入会地との間に無視することのできない区別があつたためであつた。即ち(一)道路の利用は全村民に平等にこれを許したが、入会地の利用は全村中の一定資格者即ち土地持ち(Grundbesitzer)や家持ち(Hausbesitzer)にのみこれを許した。(二)道路の利用は一部の人に対してこれを禁止するわけに行かなかつたが、入会地の利用は一部に対してこれを禁止することができた。利用規則の違反者に対して、一定の期間、利用を禁じたごときこれである。(三)道路の利用には、確定した利用分(feste Nutzungsquote)といふものがなかつたが、入会地の利用には、確定した利用分があり、中にはこの利用分の譲渡を認めた地方さへあつた位であつた。ゆゑに入会地の利用は『権利』たる性質をもつたと見ねばならない。これを『事実』と見るときは、入会地の利用と道路の利用との間の区別が没了されてしまふであらう(入会地利用分の譲渡については、Vgl. Duncker, Gesammteigentum 1843 S. 187)。
(六)は法人としての村が入会地を所有し、全村民が村民権に基いて平等に村所有の入会地を利用すと見た地方であつた。ゆゑにこの場合は、(一)乃至(五)の場合と根本的に相異した。(一)乃至(五)の場合には、一般村民を入会地の利用から遠ざけ、部落員だけに入会地の所有権又は利用権を与へたのに、(六)の場合には反対に部落員からかかる特権を剥奪し、入会地の利用を村民一般に開放してしまつたのだからである。
この主義はフランス革命の影響を直接に受けた南ドイツの国々、例へば一八〇八年のBayern町村制、一八一六年のNassau町村制等によつて採用され(一八)(一九)た。けだしフランス革命が産んだデモクラチックな町村制は、全村民に平等の資格を与へ、全村民は村所有の入会地を平等に利用することができると見たからである。実質的にいへば、この種の町村制は、旧村民に対する新村民の勝利・旧村民からの入会地の収奪を敢行したわけであつた(二〇)。
一八 Vgl. die Zitate bei Gierke, Genossenschaftsrecht I. S. 690 ff. und ders., Deutsches Privatrecht I. S. 594 f.
一九 わが国の入会に関しても入会権を村民権そのものの流出と見、村民権の得喪は同時に入会権の得喪であり、従つて村民権の拡張が行はれた場合には、新村民は当然に旧部落民の入会地に対して入会権を取得せざるべからずと見る見解がある(織田萬・入会権と町村制の規定・京都法学会雑誌八巻十号)。
二〇 以上わたくしは近世の入会を分つて、(一)団体としての部落が入会地を総有した場合、(二)法人としての部落が入会地を所有し、個々の部落員が他物権者としてこれを利用した場合、(三)個々の部落員が入会地を共有した場合、(四)法人としての村が入会地を所有し、個々の部落員が他物権者としてこれを利用した場合、(五)法人としての村が入会地を所有し、個々の部落員が優先的利用権者としてこれを利用した場合、(六)法人としての村が入会地を所有し、全村民が村民権に基いて平等にこれを利用した場合の六つとなしたが、この分類は大体においてGerber-Cosackによつたのである(Gerber-Cosack, System des deutschen Privatrechts 17 Aufl. 1895 S. 81)。その他Beseler, Gierke, Stobbeの諸家がそれぞれ独自の見地から、入会典型の分類を行つてゐる(Beseler, System des gemeinen deutschen Privatrechts 1885 S. 329 ff.; Gierke, Genossenschaftsrecht I. S. 664 f.; Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts I. 1893 S. 509 Anm. 23)。
要するに総有としての入会地は、内外二方面から攻撃を受けた。外部からは、王・高級貴族・下級貴族による入会攻撃——さうしてその結果としては、入会地の少からざる部分が貴族の所有となり、村民は単なる他物権者としてこれを利用せざるべからざる立場となつたのである。内部からは、村及部落の法人化——さうしてその結果としては、入会地の少からざる部分が村そのもの又は部落そのものの所有となり、村民又は部落員は、やはり、単なる他物権者としてこれを利用せざるべからざる立場となつたのである。
総有としての入会権から他物権としての入会権へ——これが入会権の歴史の辿つて行つた運命の一線なのであつた(二一)。
二一 他物権としての入会権といふだけでは実はまだ充分でない。なぜかなら他物権なる物権は実際上存在せず、実際上存在するのは、『地役』とか『用益』とかいふ個々の他物権だけだからである。従つて入会権は他物権中の何に属するか、地役に属するか、用益に属するかが問題となるわけであるが、これを学説に徴すると、一派の学者は入会権は地役(servitut)に属すると見た。Maurerがこれである(Maurer, Dorfverfassung II. S. 224)。一派の学者は又、入会権は地役類似の他物権(servitutähnliche jura in re aliena)に属すると見た。Renaudがこれである(Renaud, Zeitschr. f. deutsch. R. IX S. 95 f.)。
しかしこの問題は、入会権が法定物権中のいづれに属するかの問題なのであるから、実定法の規定即ち実定法が他物権の種類をいかに法定してゐるかによつて、答を別異にしなければならないであらう(Vgl. auch die Zitate bei Gierke, Genossenschaftsrecht I. S. 664 Anm. 26--28)。