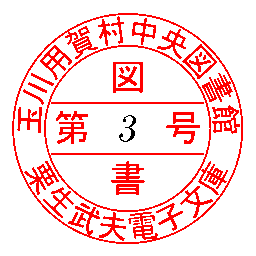
通 観
『ヨォロッパ法律史研究の間に、ますます強くわたくしの感じたことは、大陸の中部および西部の諸国は、今でこそ自身法律体系をもち、独立の国家をなしてゐるものの、過去十四ヶ世紀の久しき、私法の発展が主要的に類同だつたといふ一事である。全運動がヨォロッパ的であつたのである。だのにまだ、この見地から取扱はうと企てた著者はない。イタリイ法、フランス法、スペイン法、ドイツ法の歴史は多々あり、より少さいヨォロッパの国々の法律発展の歴史もあるが、ヨォロッパ法一般の歴史は、まだ現はれてゐないのである』(Munroe Smith, A general view of european legal history 1927, p. 3)
一
世界私法の理想は、一度ロォマで実現された。この卓越した支配者は、配下の諸族に固有法の遵守を許すと同時に、別に諸族共通の法を作り、諸族をしてこれによらしめ、自分自身もその固有法を去つて漸次これに就き、遂に法を統一に導いたのである。一の法律を以て世界に臨み、一の最高裁判所をして世界の判決を統一させてゐたのである。今でも吾人は、ユ帝法典の学説篇(Digesta)を繙くことによつて、当時の世界裁判所に奉職してゐた判事諸公の、名裁判ぶりを見ることができる。
二
法の統一は、ゲルマン人の侵入によつて破られた。彼らは無遠慮に、帝国の領内に入り来り、好みの場所を撰んで土着した。大帝国を滅ぼし、その跡に、脆弱な部族国家の多数を急造した。多数の部族、それぞれ別異の法律をもつてゐた。他方、ロォマ人の方でも、帝国の覆滅をよそ事に、ロォマ法を守つてゐたが、科学的練磨はすでに廃し、わづかに流俗の法源の中から、実用のありさうな規定を撰び、簡単な抜萃書を作るといつた程度だつた。堕落したロォマ法と、粗野なゲルマン慣習のいろいろと、不調和に紛然と並んでゐたのである。部族の数だけ法律があつたのである。『人、五人集まるも互に法を異にす』と、当時の人が書いたほど乱脈だつた。
三
封建制と共に、人的分裂は地的分裂に変つた。ロォマ人・ゲルマン人の区別消え、ゲルマン人相互間の小別も消え、藩籍(Landesangehörigkeit)のみ問題となつた。甲藩の人か・乙藩の者か、それのみ問題となつた。フランスだけでも大藩の数、四十を算し、各々法をもち、別々に裁判した。上訴の道がなかつたから、裁判に統一のあらう筈もなかつた。『駅馬を代へるごとに法をも代へる』ありさまだつた。しかし裏には、多少の統一も動いてゐた。緩いながら共同の結帯は巻いてゐた。第一、封建法そのものの内容が、各国ほぼ同じかつた。一般小作人の地位は、同一形態において、到る所低かつた。王領・教会領の小作人の地位は、一様的にやや高かつた。一代主義から世襲主義へ移つたこと、長子全産相続から諸子均分相続へ移つたこと、女子よりも男子の方が相続法上有利だつたこと、それらもほぼ共通だつた。ロンバルドの封建法典Libri Feudorumが、各国に継受され、一様に承認されてゐたことからも、封建法の世界性はうかがへる。第二に、教会法も世界普通法に外ならなかつた。それは、僧侶間の関係ばかりでなく、俗人間の、かなり重要な関係をも規定したのであつたが、国を越え、藩を越え、世界的に通用してゐたのである。法王へ上訴の道が開けてゐたから、充分裁判に統一もあつた。第三に、商法もまた世界普通法であつた。市場や海港には、内外人から構成された商事裁判所があり、国籍を越えて商人間の、取引上の紛議を裁判してゐたのである。便宜公平な商慣習法でありさへすれば、どこの国での発生であるかを問はず、採つて以て判決の規準としたから、進歩的な規則は、ずんずん古風な規則を駆逐し、平和のうちに、旧慣の淘汰・法の統一を成就して行つた。
四
自由諸都市の発した条例も,法の統一を馴致するに役立つた。新都市は古都市の条例をまね,小都市は大都市の条例をまね,附近の田舎も都市に倣ひ,だんだん都市の法律地図を大きくして行つたからである。いくつかの有力都市を中心に,いくつかの統一法圏が描き出されることになつた。イタリイのPisa, Mailand, Genuaのごとき,ドイツのMagdeburgのごとき,オランダのBrielleのごとき,影響多き都市法をもつた都市であつた。
五
中世のとばりやうやく上つて,明るい近世へ近づくや,各国いづれも,急激な経済の膨張と商業の発展とを見た。到底固有法の,悠長極まる成長を待つてゐられないほど,切迫した法的需要を感じ出した。そこで止むなく,民法の既成品《レデイ・メード》たるユ帝法典を仕入れ,かつかつ急場のしのぎをつけたのが,すなはち『ロォマ法の継受』である。
故にロォマ法の継受は,新法律の需要すでに興れるにかかはらず,その供給未だ足らざりし地方で見られた現象だつた——(一)取引なほ幼稚にして,新法律の必要を感じなかつた地方では,ロォマ法の継受もなかつたのである。スカンヂナビア諸国・スイス山間の諸州のごとし。(二)商業大いに興れるも立法機関の備はれるあり,新法を創定して敏速に社会の需要を満たしえた国でも,ロォマ法の継受はなかつたのである。イギリスや、スペインにそのころあつたアラゴン王国のごとし。(三)破毀裁判所の判決の偉力で,全国の判決を,どしどし開明へ導きえた国でも,ロォマ法の継受はなかつたのである。フランスの北部は南部と異り,王権強く,上訴の道も備はつてゐたから,ロォマ法を継受せずに終つたのである。しかしこれらは例外。他の全部は,食物を与へられない成長ざかりの少年のやうな状態にあつた。ロォマ法でも輸入して当座のしのぎをつける外に,何ともしやうのない状態にあつた。
六
で,大抵の国は,補充法といふことにしてロォマ法を継受した。が,ちゃんと固有法に規定のあるのに,ロォマ法の適用された場合も少なくなかつた。これ裁判官が,ロォマ法の秩序の整然たるに眩惑して,固有法を蔑視し,なるべく固有法の適用を阻止しやうとした結果である。彼らは,固有法を知ることが,自家本来の職責であることを忘れ,立証責任を当事者に一転し,当事者にして固有法の適用を受けんと欲せば,自ら固有法を立証し来れと命じた。しかし当時の固有法は,大半慣習の裡に潜在してゐたから,立証実に容易ならず,結局当事者は,固有法の適用を受けんと欲するも受けえざるありさまだつた。固有法主張の道は封じられ,到るところロォマ法の勝利となつたのである。
いはゆる『ロォマ法の継受』なかりし地方においても,ロォマ法の感化は深かつた。私法取引に関するロォマ法上の重要原則は,ロォマ法を全体として継受しなかつた地方においても,公理として承認された。ロォマ法的論理で固有法を説明し,ロォマ法の術語をかりて固有法上の諸観念を表出するやうになつた。
七
しかし当事者が,固有法の立証といふ無理な責任を負つたことが,固有法発達の動機でもあつた。成文にさへなつてゐれば立証し易く,立証さへできれば固有法の適用を受けえられるといふので,固有法を成文化する傾向へ向つたからである。初めまづ私人の編纂した『慣例集』が,証拠方法として用ゐられ,やうやく法典類似の力をもつた。これを法書(Rechtsbücher)といふ。法書はだんだん官の編纂物によつておきかへられた。編纂物の内容は整頓し,遂に厳然たる法典となつた。十三世紀から十八世紀までは,ロォマ法の感化の内深した時代であつたと同時に,固有ゲルマン法の整頓した時代でもあつたのである。二法並進の時代であつたのである。
八
十九世紀は,統一法典の時代である。統一国家の出現は,法律統一の欲求をよび起し,いたるところ法律編纂の事業の流行となつたのである。プロイセンまづ統一州法を作つて機運に先きがけし,仏墺これにつぎ,爾余の諸国さらにこれにつぎ,以て今日に及んでゐる。現代は正に,法の国民的統一の時代である。
しかしより大きいスケールの法律統一が,不可能であるであらうか?世界的なる私法統一が,絶望であるであらうか?そのむかしギリシヤの小都市国は,各別に法をもちつつ頻繁に来往してゐる間に,実質的意味のギリシヤ普通法を作つてしまつた。ロォマ配下の諸民族も,各自の市民法をすてて,いつの間にやら万民法を打成してしまつた。今日内外の情勢を見るに,各国国法の内容は,漸次類同へ向ひつつある。仏法は南欧・東欧の立法の基準となり,独法は中欧・北欧の立法の根幹となる。而して仏法と独法と,互に年々歩み寄り,漸く差異を失ひつつある。他国への影響なしに立法することはもちろん,裁判することさへも,今日はもう不可能であるのである。国際会議は頻繁に開かれ,比較法学は勃然と興り,解釈家は自国法の古きを,外国法の新しきへ近づけんと,日夜頭をいためてゐる。加速度的に世界私法へ向ひつつありといつても,あへて過言でないであらう。形式的にこそ,各国立法権の峻はしい対立を見るが,実際の立法内容は,大同小異であるのである。理論家が考へるよりも,世界ははるか早く,世界私法の時代に入つた。はるか多く,世界私法を作つた。実質的意味からいふと,今日はもう世界普通法の時代であるのである。各国国法は,世界私法の一部,普通法に対する特別法たるに過ぎぬといへやう。
第一章 東欧の形勢
第一節 ビザンチン1)
1) Zachariae, Geschichte des griechisch-röm. Rechts, 3. Aufl. 1892, S. 3 ff.---Mortreuil, Histoire du droit Byzantin, 3 Bde. 1843--1846---Krüger, Geschichte des Quellen und Literatur des röm. Rechts S. 407 ff.---Kübler, Geschichte des röm. Rechts 1925, S. 434 ——拙著・ビザンチン期における親族法の発達
一 ヨォロッパ立法史におけるビザンチンの地位
古ロォマの法律を近世の国民へ伝へるために,仲介の労をとつた二つの勢力があつた。一はイタリイである。イタリイは文芸復興発祥の地で,すべての古代文化は——商業でも,学問でも,芸術でも,——みな一旦イタリイで復活し,然るのち西欧の諸国へ分布されたのであるが,法律学上の文芸復興,すなはちロォマ法学の復活も,またイタリイの手を煩はさねばならなかつた。ドイツ・スペイン・フランス等西欧の諸国は,イタリイからロォマ法を継受したのである。二はビザンチン帝国であつた。この国は中世の欧洲を守護した・いはば一個巨大の障壁で,欧洲の入口たるバルカンに蟠居し,アジアから侵入してくる諸多の蛮族を撃退し続けたのである。さうして西欧の諸国が古代の文化を継受しうるだけの文化階段に達するのをまつて,これに自己が今まで入念に保全し来つたギリシヤ・ロォマの古文明を相続させ,自分自身はトルコ人のために滅されて行つたのである。文明の保全・欧洲の擁護が,その史的使命であつたのである。たとへていへば,古代と近世をつなぐ文化史上の橋梁のやうな役目を,彼は,果してくれたのである。故にロォマ滅後の立法活動を叙列することを任とする『ヨォロッパ立法史』は,この『古代と近世との橋梁』へ,その開巻第一章をささげるのである。
二 時代区分
ビザンチン帝国の立法史は,五期に分れる。一はユ帝法典が基礎的淵源となつてゐた時代,これをJustinian後期といふ。六世紀半から八世紀半までの二百年がこれにあたる。二はLeo IIIがクリスト教の倫理観念に基いてビザンチンの法律,ことにその親族法を根底から一新した時代,これをLeo III時代といふ。八世紀半から九世紀半までの百年がこれにあたる。三はBasil IおよびLeo VIが,Leo IIIのクリスト教的立法を覆へしてユ帝法を復活した復古時代,これをBasilica時代といふ。九世紀半から十一世紀半までの二百年がこれにあたる。四はビザンチン法律学の円熟期で,十一世紀半から十二世紀末までをいひ,五は滅亡期で,十三世紀から十五世紀までをいふ。
三 Justinian後期
イ ユ帝の死後(565)ビザンチン帝国においては,征服者がもたらしたロォマの文化に対し,被征服者が固有してゐた東方の文化,ことにギリシヤの文化が,恐ろしい勢で台頭しはじめた。ユ帝が恐らく,ラテン語を話した最後の皇帝であつたであらう。それ以後の皇帝は,みなギリシヤ語で話したのである。法廷の用語も,ユ帝から僅か五十年を過ぎたHeraclius(610--641)の時代に,ギリシヤ語に代つてしまつた。ラテン語を知るものは,教養ある階級の間にすら,稀になつた。従つてラテン語で書かれたユ帝法典をギリシヤ語に翻訳し,且つこれに,時勢の変化に対応する新解釈を加へる必要も切実になつた。法典に対する註釈は,ユ帝の厳禁したところであつたが,1)事実無数の註釈書の次から次と出てくるのを,どうすることもできなかつた。
1) Const. Deo auctore, 12. 13. Const. Tanta, 21.
ロ Institutionのギリシヤ訳は、Theophilusによつて書かれた。1)Digestaの訳および註は、Theophilus, Dorotheus, Stephanus, Kyrillus, Anonymus等によつて書かれた。Codexの訳および註は、Thaleläus, Isidorus, Anatolius, Theodorus等によつて書かれた。Novellenの訳および註は、Athanasius, Anonymus, Philoxenus, Symbatius, Theodorus等によつて書かれた。
その外、ユ帝と時を同じくした有名な法律学者に、Dorotheus, Cratinus, Julian, Basilides, Constantinus, Dioscorus, Eutolmius, Jacobus, Joannes, Leonides, Leontinus, Mena, Plato, Praesentinus, Prosdocius, Salaminius, Theodore, Thomas, Timotheus, Tribonian等があり、やや遅れて、Demosthenes, Dominus, Endoxius, Patricius, Phocas, Symbatius, Theodore等が出た。2)
1) 通常Paraphrasis Institutionumとよばれてゐる。Ausgabe von Reitz 1751; Ferrini 1883--1897. ドイツ訳はWüstemann 1823. 2) Anatolius, Dorotheus, Cratinus, Julian, Theophilus, Isidorus, Thaleläus, Kyrillus, Demosthenes, Dominus, Endoxius, Patricius, Stephanus, Anonymus等はConstantinopel又はBeirutにおける法律学校の教授であつた。Basilides, Contantinus, Dioscorus, Eutolmius, Jacobus, Joannes, Leontinus, Mena, Plato, Praesentinus, Prosdocius, Salaminius, Theodorus, Tribonian等は裁判官であつた。彼らのギリシヤ訳註の遺片は、Heimbach, Basilica, VI.に収められてゐる。
ハ 翻訳および註釈の盛行は、ユ帝の法典編纂(529--535)から、Heraclius帝の即位(610)の頃まで、凡そ八十年に亘つたと見てよからう。それ以後の法律史は寂莫だつた。有名なコンスタンチノォプルの法律学校も、七一七年に閉鎖されてしまひ、爾後百五十年間、八六六年まで開かれなかつた。ユ帝法典に対する研究は、その間、閑却されてゐたかに見えたのである。これ全く当時のビザンチンが、異常の国難に曝されてゐたためであつて、例の大ペルシヤ戦争が終るや否や、彼は直ちに当時の新興勢力であつたサラセン人と衝突したのである。六三四年にはシリヤを取られ、三七年にはイエルサレムを落され、四一年にはエジプトを奪はれ、遂に七一七年から翌年へかけてコンスタンチノォプルそれ自身を包囲された!ロォマ法の長歴史において七世紀だけが、空白ページに終つたのは、うち続くかかる国難が、その原因をなしたのである。
四 Leo III時代
Leo III (717--740)は、同世紀に西に出たカァル大帝(768--814)と、その偉大を併称されるほどの人傑であつたが、立法史の上においても、Ecloga legum1)の発布者として、特筆大書されなければならない。
それは七四〇年、Leo IIIと、その子にしてその相続人たるConstantin Vとの、連名で公にされた。起草者の中には、Nicetas, Marinusなどいふ当時著名の法律学者がゐた。わづかに一の前文と十八の章とから成る小法典に過ぎないが、中に、ロォマ法上の伝統的原則を大胆に破壊した改革・教会法の思想を思切つて採用した規定を含み、法律史の上からいふと、その価値、Basilica大法典の上にある。ことに離婚の禁・内縁の廃止・婚姻故障の拡張・夫婦間の財産共同・家長制度の撤廃・後見の公務化——凡そ近代式親族法の主面容は、この法典によつて形成されたといつていい位。2)
1) Ausg.: Zachariae in d. Collectio librorum juris Graeco-Romani ineditorum 1852. 2) 歴史家は、Leo IIIの事業を評していふ——『廃墟と悲惨とを受けついだ彼は、力と秩序と平和と、よみ返つたやうな繁栄とを残した。七四〇年六月十八日、彼死亡のとき、シィザァの国は、すでに堕落の深淵を脱し、もう一度、力と栄えとの大道へ上つてゐたのである』と(Foord, The Byzantine Empire, pp. 178, 179)。
五 Basilica時代
イ Leo IIIの死後凡そ百年間、ビザンチンは、外からはサラセン人やブルガリア人の攻撃を受け、内には教会との紛擾絶えず、加ふるに古ロォマのNeroにも比すべき暴戻なる皇帝の続出に苦められてゐたが、八六七年、Basil I即位し、マケドニア王朝の礎を開くに及んで、やうやく強大な政府から善良な統治を受けるに至つた。法律学復興の気運も萌し、過去百五十年の久しきに亘つて閉鎖されてゐたコンスタンチノォプルの官立法律学校も再興された。
ロ 八七〇—七九年の間のある年に、Basil Iは、Prochiron1)とよばれる一の小法典を編纂した。一の前文と四十の章とから成る。内容は、ユ帝のInstitution, Digesta, Codexからの抜萃を出ない。殆どそこに何の創意も見ないのであるが、創意なきところ、却つて重大の意義があつたのであつて、Basilはこの小法典により、古きユ帝の法律を復活させやうと欲したのである。Leo IIIのあまりにクリスト教的・あまりに反伝統的なりし改革を、根底から覆へし、ユ帝の昔へ返へさうと企てたのである。離婚の禁・夫婦財産の共同等、重要なLeoの改革は、危く覆されやうとした。
1) Augs.: Zachariae 1837.
ハ が、Leo以来百年、すでに改革法の遵守に慣れてゐた国民は、急にユ帝に帰れといはれて、却つて混惑を感じたことであらう。Basil自身も、Prochironの架空性に気づき、Prochiron発布の後間もなく——Zachariaeによれば八八四年から六年間の間だらうといひ、Krügerによれば七九年から八六年の間だらうといふ1)——Prochironの改正草案を編んだ。これをEpanagoga2)とする。やはり一の前文と四十の章とから成る。遂に法典にはならずにしまつたが、内容はかなりLeoの改革法に逆戻りしてゐた。例へば夫婦間の財産共同を認めたごとし。
1) Zachariae, Epanagoge, 55. Krüger, Geschichte d. Quellen u. Literatur d. röm. Rechts. S. 416. 2) Ausg.: Zachariae in d. Collectio librorum juris Graeco-Romani ineditorum, 1852.
ニ しかしながらProchironやEpanagogaは、Basil Iにとり立法事業の小手調に過ぎなかつた。彼がさらに大規模に、ユ帝法典の復活を図るの意思ありしことは、彼自身、Prochironの前文中に明言したところであつて、八八三年ごろ、四十巻の法典となつて、一旦この予告の実現を見た。しかしその成蹟は、未だBasilの意に満たざりしと見え、彼は法典の発布後、直ちにこれが改訂を子のLeo VIに命じ、Leoは、当時著名の法律家——その唯人たり幾人なりしかは不明——を会して拮据事に当つたが、父の在世中、遂に発布の運びに至らず、その死後八九二年ごろ、やうやく六十巻の大法典を仕上げた。これが現存のBasilica法典である。四十巻の旧Basilicaは湮滅して伝はらない。
ホ 材料は、(一)ユ帝法典、すなはちInstitution, Digesta, Codex, Novellenの中からも取つたが、1) (二)第六・七世紀の学者が、ユ帝法典に対して加へた訳註書の類をも、大いに利用した。2) (三)ユ帝以後の皇帝たちの発した勅法や、(四)Leo VI自身の発した勅法からも、かなり取つた。編纂の目的は、ユ帝法典の近代化にあつたのである。これを近代化して、当時の社会の法的需要を満たすことにあつたのである。用語はもちろんギリシヤを用ゐた。各巻(Buch)を章(Titel)に分ち、各章を条(Paragraph, θέματα)に分けた。章題のつけ方・ならべ方は、ユ帝法典の勅法篇(Codex)に倣つた。3) 4)
1) Institutionは極少ししか利用されなかつた。
2) ことにThaleläus, Kyrillus, Stephanusらの訳註を。
3) Basilicaとは、the Imperial lawsの意味で、皇帝Basilの名に因んだのではない。
4) Ausg.: Karl Wilhelm Ernst Heimbach, Basilicorum libri LX, 6 Bde. 1833--1870. Supple-mentbände von Zachariae 1846, von Ferrini u. Mercati 1897.
六 法学隆盛期
イ Basilica法典発布の結果、ビザンチンの裁判は、ユ帝法典と絶縁するやうになつた。ユ帝法典から判決の規範をとらず、Basilicaから直接これを汲みとるやうになつた。学問もBasilicaを対象とするに至つた。だんだんユ帝法典は忘れられて行つた。いま世紀を追うてBasilica以後の形勢をのべると、
ロ 十世紀中、三つの有名な法律書が出た。一はEpitome legum1)である。ユ帝法典およびEpanagogaからの抜萃で、五十章より成る。九二〇年に出た。二はSynopsis Basilicorum2)である。Basilicaの中の重要規定の抜萃であり、皇帝Constantinus (944--959)のころ世に出た。三はEpanagoga aucta3)——これはEpanagogaを基礎にとつた抜萃である。
この時代の法律家として有名なのは、SymeonおよびEustathius Romanusであつた。
1) Ausg.: Zachariae in d. Collectio librorum juris Graeco-Romani ineditorum II. u. VII. 2) Ausg.: Zachariae, Jus Graeco-Romanum VI. 3) Ausg.: Zachariae, Jus Graeco-Romanum IV.
ハ 十一世紀はビザンチン法学極盛の時期である。イタリイにおける註釈学派の勃興に比してもいいほど、花々しい状態を呈した。代表的学者としては、Garidas, 1) John Nomophylax, Patzus, Constantinus Nicaenus, Gregorius, Doxapater, Calocyrus Sextus等が出た。
後代に影響した法律書としては、まづΠειρα2)(Experientia Romani)——これは当時の国家および教会の判決例を、七十五の章下に類集したもので、円熟期のビザンチン法を窺ふための重貴の資料である。撰者はGaridasといふ説あるも確かでない。二はEcloga ad Prochiron mutata3)——これはLeo IIIのEcloga legum; Basil IのProchironおよび十世紀の法律書Epitome legumを材料にした抜萃書。三はOpusculum de jure4)——傑出した抜萃書で、一〇七二年Michael Attaliataの編したもの。四はSynopsis legum——当時の法律の要綱を韻文に綴つたもので、Psellusの作。彼はこれを時の皇帝Michael VII (1071--1078)に捧げたのである。
1) Constantinopel法律学校の教授。
2) Ausg.: Zachariae, Jus Graeco-Rom. I. 3) Ausg.: Zachariae, Jus Graeco-Rom. II u. IV. 4) Ausg.: Leunclavius, Jus Graeco-Rom. II. 1--79.
ニ 十二世紀に入つても、法律学は衰状を示さなかつた。Alexius Aristenus, Gregorius Doxapatri, Joannes Zonaras, Hagiotheodorites, Theodorus Balsamonなどいふ大家が出た。中んずくTheodorus Balsamonはギリシヤ教会の重要法源たるNomokanon in 14 Titeln1)に、註釈を加へた人として、有名である。
1) Pitra, Juris Ecclesiastici Graecorum historia et monumenta II 445 ff.
七 滅亡期
イ 十三世紀に入り、二個の代表的法書が出た。一はSynopsis minor1)——これは、十世紀に出たSynopsis Basilicorum major と十一世紀の学者Michael Attaliataの撰に成るOpusculum de jureとから抜萃したもの。二はProchiron auctum2)——これは、Prochironの増補で、一三〇〇年ごろ公にされた。
1) Ausg.: Zachariae in dem Jus Graeco-Romanum II. 2) Ausg.: Zachariae in dem Jus Graeco-Romanum VI.
ロ 一三四五年、当時Thessalonicaの裁判官であつたConstantine Harmenopulosが、通常Hexabiblosといはれる有名な抜萃書を作つた六巻八十七章。第一巻および第二巻に主として訴訟法を、第三巻に債権法および物権法を、第四巻に婚姻法を、第五巻に遺言法および後見法を、第六巻に不法行為法および刑法を収めた。材料は主にProchiron, Synopsis Basilicorum, Synopsis minor, Experientia Romani等から取り、Leo IIIのEcloga legumからも抜いた。これらの法源の中から生命ある規定を拾ひ、適当に排列し、実際家の便にそなへやうといふのが、編者の目的であつたのである。もとより私著ではあつたが、篇別の明快・内容の豊富・出所の確実のために、多大の信用を博し、事実上ビザンチンの法典となつてしまつた。
ハ これより先き一二〇四年、第四十字軍の将士は、ビザンチンの商敵ベニス市の賄を受けて、突如、コンスタンチノォプルに上陸し、これを襲ひ取つた。さやうに永く異教徒の攻撃を支へ来つた倨傲なるコンスタンチノォプルは、不意にクリスト教徒の襲ふところとなつて、滅びたのである。掠奪と殺戮とを肆ままにするために、十字軍の将士は、五十年間、そこに滞在した。世界の宝庫とよばれたコ市の富と栄えは、彼らのために尽磨された。一二六一年、皇帝Michael VIIIが、十字軍の将士を追うてコ市の自由を回復したが、昔の繁栄は取り戻すべくもなかつた。十四世紀に入ると、トルコ支配の日が急速に近づいて来た。ビザンチンの滅亡は、もう時間と機会との問題になつた。一千年の長歴史を有する・この神寂びた老大国の瓦解は、一四五三年五月二十八日の出来事であつた。
ニ 瓦解に先つ一世紀前から、ビザンチン帝国の人民は、来べき運命を予感したかのやうに、続々、故国を去つて西欧、ことにイタリイへ赴いた。ベニス・フロォレンスその他のイタリイ都市が、ビザンチンの避難民から東方の文化を相承し、文芸復興の巨花を開いたことは、人のよく知るところであるが、法律上の文芸復興——ロォマ法の復活——も、ビザンチンの影響にまつこと、決して少なくなかつたのである。また東方においては、征服者たるトルコ人が、帝国の遺民に対し、帝国の遺法を守ることを認めるの雅量を示してくれたため、ビザンチン法の余命はつづいた。ことに、ビザンチン法最後の忘れがたみなりしHexabiblos法書は、恋々として東方の国民の永く守つたところであつた。
第二節 ビザンチンの影響
一 イタリイへの影響1)
1) Savigny, Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter, 2. Aufl. I.
イ Justinian (527--565)は一時、蛮族の手からイタリイの支配を回復した。さうして、そのころ出来たての彼の法典を、そのまま半島の人民に施行した。1)しかしイタリイにおけるユ帝法典の施行は、遂に不徹底に終らざるをえなかつた。その故は、四三九年以来、イタリイにはCodex Theodosianusが行はれ、確乎たる地磐を築いてゐたので、今さらそれを押しのけて新法典を遵守させるためには、多大の時日を要したらうに、イタリイにおけるユ帝の制覇は永く続かず、僅々十五年にしてロンバルド人のために覆されてしまつたから、ユ帝法典の施行は、いはば、未だその根を下さざる間に、早くも抜きとられた姿であつたからである。イタリイの法律史家Calisseのいふところによると、その頃イタリイの人民は、ユ帝法典に従ふことを悦ばず、依然Codex Theodosianusを遵守し、学校のごときも旧法典の研究を先にし、裁判所さへも往々旧法典により裁判し、ことに教会は、新法の施行に強き反対気勢をさへ示したといふ。2)
1) ユ帝法典をイタリイに施行する旨のユ帝の勅令は前後二度発しられた——前回は五四一年に、次回は五五四年に。五四一年の勅令は無効に終つた。なぜなれば、同令発布後、東ゴォト王Totila叛をなし、一時イタリイをユ帝から奪還したからである。五五四年の勅令は、Totilaの乱、鎮定後の発布にかかる。
2) A general Survey (Continental legal history series I.) 22.
ロ かくの如くビザンチン帝国は、ユ帝法をイタリイに布くことにおいて明かに失敗したが、しかし南イタリイの海岸・若干の地は、十一世紀の末までビザンチンの所領に属し、自然そこに、ビザンチンの法律が行はれてゐた。Leo IIIのEcloga legumでも、Basil IのProchironでもEpanagogaでも、乃至またLeo VIのBasilicaでも、みなイタリイの一部を支配したのである。又ユ帝が、その法律の普及に資せんためにロォマ市に設立した法律学校は、ロンバルド人侵入の後、難をさけてRavennaに移転したが、十一世紀の初めまでそこにあつて、ビザンチンの法律を講じ、ことにユ帝法典中比較的平易の部門たるNovellenおよびInstitutionを教授してゐた。この学校が、註釈学派の勃興のために、必要なる基礎工事を築いたのである。
ハ 十二世紀に入つてからも南イタリイの海岸には、ビザンチンの法律が行はれてゐたに相違ない。なぜなれば、十二世紀ごろ、南イタリイの海岸にゐたビザンチンの遺民の、編纂した法律書に、Epitome ad Prochiron mutata, Ecloga privata aucta, 1)Ecloga ad Prochiron mutata2)等があるが、その内容は、いづれも純然たるビザンチン法を出てゐないからである。当時彼らは、政治的にはノオルマン人の支配の下にあつたが、法律的にはビザンチン法を守つてゐたらしいのである。
1) Ausg.: Zachariae, Jus Graeco-Rom. IV. 2) Ausg.: ebd.
ニ トルコ1)
1) Young, Corps de Droit Ottoman, 7 Bde. 1905 ff.---Jehay, De la situation légale des sujets ottmans nonmussulmans, 1906.
イ トルコ皇帝Muhammed IIは、ビザンチン帝国を滅ぼしたが(一四五三年)、ビザンチンの遺民に治外法権を認め、彼らはトルコ法に従ふの要なく、自身の法に従ふことができるとした。またギリシヤ教会の教主に、ビザンチンの遺民の間に発生する民刑一切の事件を裁判する権をも委ねた。1)教主はBasilica法典やHexabiblos法書により、裁判した。つまりビザンチン法は、ビザンチン帝国自身よりも長命し、帝国滅亡の後までその効力を持続したわけであつた。
1) Young, Corps de Droit Ottoman, II. 14.
ロ 十九世紀に入つてからトルコ政府は、各種の法典を編纂し、原則としてこれをクリスト教徒にも適用したが、婚姻・離婚・遺言・相続・後見等の関係については、なほもクリスト教徒の治外法権を認めた。依然として彼らは、この種の人的関係に、Hexabiblosの規定を適用してゐたのである。
三 ギリシヤ1)
1) Maurer G. L, Das griechische Volk in öffentl., kirchl. und privatrechtl. Beziehung vor und nach dem Freiheitskampf bis zum 31. Juli 1834, 3 Bde. 1835 f.
イ ギリシヤ地方は、早くからビザンチン帝国の支配を脱してゐたが、統一国を作らず、たくさんの小独立国に分裂してゐた。法律に関しても、ある地方はユ帝法典、ある地方はBasilica法典、その他ユダヤ法の行はれてゐた処もあり、ベニス都市法の行はれてゐた地方もあり、殆ど乱脈だつたが、一四六〇年、トルコ皇帝Muhammed IIの剣下に全部統一されてしまつた。その結果、はじめて法の統一を来たし、却つてビザンチン法の復活を見ることにもなつた。なぜなれば、クリスト教徒はトルコ皇帝の裁判に服せず、ギリシヤ教会の教主の裁判に服したのであつたが、教主の裁判は、かのビザンチンの遺法たるBasilicaやHexabiblosを規準としたものであつたからである。ビザンチンの法律が、久しぶりでギリシヤ一円に行はれ出した次第であつた。
ロ 一八二一年から二九年へかけて戦はれた独立戦争の結果、現代ギリシヤの出現となつたが、この戦争の未だ終了せざりし一八二二年に、ギリシヤ人は早くも一の宣言書を発し、ビザンチンの遺法Basilicaをギリシヤの法律となすべき旨宣言した。越えて一八三五年、すなはちトルコから独立の承認をえて後、改めて一の勅令を発し、Basilicaの代りにHexabiblosをギリシヤの法律とする旨宣言した——然かくBasilicaやHexabiblosは、ギリシヤ国民の花やかな思ひ出であつたのである。
四 ルウマニア1)
1) Alexandresco, Droit ancien et moderne de la Roumanie---Negulescu, Histoire du droit et des institutiones de la Roumanie 1898.
ルウマニアの前身は、Wallachia公国である。Wallachia公国は、そのむかし同地方に来てゐたロォマの移民の子孫たちの作つた国で、宛然、古ロォマの血と性情と言語とを伝へた国柄であつた。それだけビザンチンと密接不離の関係あり、法律のごときもビザンチン法を採用してゐた。BasilicaやHexabiblosが、そのままWallachia公国の法律になつてゐた。
一三九一年、Wallachia公国はトルコとの戦に破れて、その朝貢国となつたが、その際の条約に『トルコ皇帝は、Wallachia公国が、公国自身の法律によりて自らを統治することに同意す』とあつた通り、Wallachia公国は、その後もBasilicaやHexabiblosの適用を止めなかつた。
五 ブルガリア1)
1) Bozanoff, Übersicht über die Entwicklung der bulgarischen bürgerlichen Handels-und Prozessrechts. Ztschr. f. osteuropäisches Recht 1927, S. 92, 168
ブルガリアはビザンチンの宿敵で、その歴史は、ビザンチンとの戦で終始してゐた。その関係上、ブルガリアはあまりビザンチンの法律的影響に接せず、大体、スラブの慣習を守つてゐた。しかし一三六六年、トルコ人の滅ぼすところとなつた結果、ブルガリアのクリスト教徒も、やはりギリシヤ教会の裁判権に服するやうになつた。その後ギリシヤ教会からブルガリア教会が分離するに至つたが、独立したブルガリア教会の法律も、ギリシヤ教会のと大差なく、やはりビザンチン法を基礎としてゐた。かくしてだんだんビザンチン法と接触するに至つた。つまりブルガリアは、トルコに征服されて以来、ビザンチン法の影響を受けたのである。
六 セルビア1)
1) Georgéwitch (Djordjević), Syst. d. Privatrechts d. Königreichs Serbien, Allg. Teil 2 Bde., 1893 u. 1896.
イ もとセルビアは、ビザンチン帝国の県であつたが、一〇四三年、ビザンチンから独立した。真正の意味のセルビア国民史は、実にこの年にはじまるのである。独立後ビザンチンとの文化交渉は盛んとなり、一三三六年、位に上つたDušan大帝は、その宮廷をビザンチン風に華美にし、『皇帝』と称し、ギリシヤ旧教を国教とし、カトリック教を奉じる者を罰した。彼はまた一の法典を出した(一三四九年および一三五四年)。Dušan法典とよばれるものがそれで、主要な規定は、ビザンチンの法律たるBasilicaからとつた。セルビア国民法の形体は、この法典によつて定められた。
ロ 一三八九年以来、セルビアはトルコの治下に入つた。トルコは初めセルビア教会の独立を認めてゐたが、後にこれを否認し、ギリシヤ教会の法律をセルビアに施行した。そこでセルビアに対するビザンチンの感化が一層濃厚となつた。
七 モンテネグロ1)
1) Dickel, Das neue bürgerl. Gesetzb. von Montenegro 1889.
モンテネグロの法律は、スラブの慣習を基礎としたものであつた。一七九六年Danilo IIが、一の法典を制定したが、これも従前の慣習を成文に直したまでで、ビザンチン法の影響を見なかつた。またモンテネグロは、政教一致、君主自ら教主を兼ね、ロォマ教会にもギリシヤ教会にも属しなかつたから、教会を通じてビザンチン法を吸収する便も少なかつた。殆どビザンチンと没交渉に終つたのである。
八 ロシア1)
1) Goetz, Das russ. Recht, 3 Bde.---Kovalesky, Modern customs and ancient laws of Russia, 1891; Early Slavonic law, 19 Law Quart. Rev., 76.
イ ロシア皇帝Vladimirは九八八年、その人民と共にクリスト教に改宗した。Vladimirの子Yasolafは、キエフ市にビザンチン風の大伽藍を建てた。聖書の翻訳もでき、ロシア音をあらはすに適する・新しいアルハベットも工夫された。——みなビザンチンから来た僧侶たちの仕事である。されば法律もまた、大いにビザンチンの影響を受けたらうと想像されるが、事実はさうでなく、一〇一八年に出たIraslavの法律のごとき、スラブの旧慣を成文化したものに過ぎなかつた。
ロ それに黄色人侵入の結果、ロシアとビザンチンとの文化交通は絶たれてしまつた。三百年間黄色人は、ロシアを征服した。その間ロシアは、ヨォロッパから全然切り放されてゐたのである。人民の智的水平線は著しく低下した。西欧において商業の勃興・文芸の復興・新発見および新発明等、興奮的出来事の続出してゐる間、ロシアは昏々と中世の残夢をつづけてゐたのであつた。
ハ ビザンチン帝国の滅亡と先後して黄色汗国もまた滅び、汗国の廃墟の中から統一的新ロシアが出現した。その最初の皇帝Ivan IIIは、ビザンチン最後の皇帝Constantine Paleologusの姪を娶り、ビザンチンの旗章を受けつぎ、ビザンチンの相続人を以て自ら任じた。しかしそのためにロシア法の内容が、大いにビザンチン化したといふほどでもなかつた。婚姻法のやうな・教会の容啄を受けた区域は、さすがに大いに変化したが、他は旧態依然、スラブ古来の慣習によつてゐた。つまりロシアは、あまりビザンチンの感化を受けずにしまつたのである。
第三節 サラセン1)
1) Goldzieher, Principles of law in Islam (in 8 Historians' History of the World, ch. xii)---Sachau, Zur ältesten Geschichte des muhammedan Rechts, 1870; Muhammedan. Recht, 1897---Shermann, Roman law in the modern World, I. 178.
一 時代区分
アラビヤの立法史は、四期に分れる。第一期は七世紀初めまで、この時期においてアラビヤ人は、未だマホメット教を知らず、アラビヤの熱野に原始生活を営んでゐた。第二期は七世紀半から八世紀半まで、この間にアラビヤ人は、例の『Koranか剣戟か』をふりかざして四方を征服し、須臾にして地中海を南岸から半月形に囲む一大帝国を建ててしまつた。第三期は八世紀半から九世紀末まで、この間にサラセンは東西に分れ、バグダッドの宮廷とコルドバの宮廷と互に驕奢を競ひ、学問芸術満開し、いはゆるサラセンの黄金時代を現出した。第四期は十世紀以後、この期にサラセンは四分五裂し、勃興の時にふさはしい速度を以て急激に衰微して行つた。各時期の法律状態を略述すると、
二 第一期
改宗以前におけるアラビヤ唯一の法源はSunnaであつた。Sunnaとは、祖先の遺習をいふ。凡そ祖先の遺習を尊重するの風は、未開人に通有であるが、未だ嘗てアラビヤ人ほど、頑迷にこれを墨守したものはなかつた。予言者マホメットが、メッカの市民に容れられざりし理由も、彼はSunnaを尊敬しないといふにあつた。マホメットが『神が示せし法則に従へ』(Obey the laws which Allah sends you)といへば、『われらは祖先の遺風に従はんのみ』(We follow the customs of our fathers)と答へ、『神がその使者に授けし宗教をとれ』(Come and adopt the religion which Allah hath revealed to his ambassador)といへば、『われらは祖先以来の宗教に満足す』(We are satisfied with the religions of our fathers)と答へたといふ。凡そ祖先の足跡を践み、一歩も踰えじと、おそれ慎んでゐたのである。
三 第二期
改宗以後は、マホメットの説教集たるKoranが、主要の法源となつた。けだしマホメットは、教主であつたと同時に立法者でもあり・裁判官でもあつたから、その説教集は、経典たると同時に法典たり、以て判決の根拠とするに足りたのである。尤もKoran一巻の規定は、以て凡百の法律問題を解き去るに足りなかつたが、(一)Koranと共に、(二)マホメットの幕僚たりし人々の訓戒、(三)初期四代のKaliphの判決等にも法源たる価値を附し、さらに(四)古代のSunnaも、未だ全く法たるの権威を失つてゐなかつたから、合せて以てサラセンの法的需要をかつかつ満たすに足りたのである。初期四代のKaliphの判決にかぎり法源となりえたわけは、四代までのKaliphは、マホメット自身の近親又は僚友であつたからであつた。1)
1) 初代のカリフAbu-Bekr (631--634)はマホメットの養父にあたり、第四代のカリフAli (656--661)は、マホメットの養子にあたつた。第二代のOmar (634--644)および第三代のOthman (644--656)は、マホメットの忠実なる僚友だつた。教祖と、かく密接の関係ありし故、この四人の判決にかぎり、Koran同様の価値を有したのである。
四 第三期
進んで黄金期の法律状態を見るに、Kaliphの政府は、新附の人民にマホメット法を強制せず、固有法の遵守を許した。けだし新領土の大半はビザンチンの旧領で、人民の法的智識も進んでゐたから、アラビヤ法を適用することを遠慮した次第であつたが、とにかくビザンチンの大法系と、粗野なアラビヤ慣習と、一は被征服者のため他は征服者のため、並び行はれることとなると、後者の刺戟は、前者の発達を促がさずにおかなかつた。時恰も、サラセンの思想界に自由主義の大運動おこり、経典の語義を批評的合理的に解せんとする傾向を生じたので、神学の一部門たりし法律学も、一般の風潮に誘はれて自由法学をよろこび、解釈の力で盛んに新法規を創造し、旧法規を淘汰したが、創造された法規の内容をよく見ると、その大半がビザンチン法の剽窃であつたのである。1)乞ふ例を以て、ビザンチンの感化のいかに甚大なりしかを証拠立てんに、
(一) ロォマ法は、物を動産と不動産とに分ち、土地およびその定着物を一括して一物と見、これを不動産(res immobiles)と称し、その他の有体物を動産(res mobiles)とよんだが、マホメット法もこれと同一の分類を認めた。
(二) ロォマ法は用益権(usufructus)なる物権定型を有し、用益権者は、用益物の本質を変ぜざる範囲において、これを使用し、これより生ずる果実を収取することをう、用益権は一身に専属する権利にしてその譲渡を許さずとしてゐたが、マホメット法も、これと同じ態様において、用益権なる他物権を認めた。
(三) ユ帝の制定した法定相続の順位は、(一)死者の卑属親、(二)死者の尊属親、(三)死者の傍系親とし、卑属親中にあつては親等近き者が遠き者に優先し、同じき者は均分に相続し、先んじて死したる子の取得すべかりし分前は、孫これを受けたが、マホメット法上またさうであつた。
(四) ロォマ法は遺贈の自由に制限を加へ、遺産の一部分は相続人に遺留することを要すとしてゐたが、マホメット法もまた遺留分の制度を認めた。
(五) ユ帝の法律は、時効により所有権を取得するには動産は三年、不動産は十年又は二十年としてゐたが、マホメット法上の取得時効にも、三年・十年・二十年等の区別があつた。
(六) もしそれロォマ人の発見に係る契約の定型に至つては、売買でも、賃約でも、組合でも、消費貸借でも、使用貸借でも、寄託でも、委任でも、保証でも、和解でも、質でも、抵当でも、みなサラセン人の模倣採用するところとなつた。
この他後見人保佐人の制度において、遺言の方式において、幾多の類似点を発見しうべく、数へ来ればマホメット法とはアラビヤの衣を装ふロォマ法そのものにあらざるかを思はさせる。Amosいふ、『恰もマホメット教が、アラビヤの土壌に移植されたヘブライ教に外ならざりしごとく、マホメット法は、アラビヤの政治状態に適合せしめられたビザンチン帝国の法律に外ならなかつたのである』2)と。真に然り。
1) サラセンには、法の解釈権を独占する一種の閥族があつた。その長をFukaha (Fakih)といひ、法律上の質疑に答へてゐた。八・九世紀ごろのそれとしては、Abu Hanifa (699--767)を始祖とするHanifa派、Malik b. Anas (+795)を始祖とするMalik派、Muham Malik b. Shafiを始祖とするShafi派の三派あり、いづれも自由解釈の主義をとつてゐた。Hanifaは裁判官の主観的判断・個人的理性も法であると主張し、Malik派は公益(istilah)の前に明文なしといひ、Shafi派は、立法理由(illa)より見て解釈を下すべしと主張した。この種の自由解釈が、貧弱なKoranの内容を豊富にし、アラビヤ法をビザンチン法へ接近させたのである。
2) Amos, Roman law p. 415.
五 第四期
衰亡期に入ると、全く精神に活気を失ひ、自由解釈と比較法を忌み、ただただ先例を尚ぶに至つた。マホメットおよび初期四代Kaliphの遺訓をhadithといひ、hadithだけが法源である、何事もhadith通りに裁かねばならぬと、おもふやうになつたのである。
学者も、遺訓の系統をたづね、その出所を正すことを、主もな仕事となすに至つた。けだし当時の裁判所は、遺訓の認めない請求を一切棄却したから、当事者はその請求が、遺訓に合することをいかにもして立証せんとし、勢の趣くところ、遺訓の捏造となつたので、いはゆる遺訓なるものの真贋を鑑別する必要生じ、ここにhadithの学を産み出すこととなつたのである。その主題は何が合理的なりや(What is reasonable ?)でなくて、予言者は何をいひ何をなせしか(What did the Prophet say and how did he act ?)といふ事実の探求であつた。学問は考証に堕し、法律は沈滞固陋の体系と化したのである。
九世紀の末、学者は種々の遺訓集を編纂刊行するに至つた。そのあるものは、標準的真実性を認められ、事実上サラセンの法典となつた。すなはちサラセンにおいても、学者の私著たる法書(Rechtsbücher)が、法たる力をもつた時代——法書時代——が、あつたのである。BuchariやMuslinやの編した遺訓集は、中で最も権威があつた。
第二章 西欧の形勢
第一節 総 説1)
1) Brunner, Deutsch. Rechtsg. 2. Aufl. I 376 ff.---Schröder-Künssberg, Deutsch. Rechtsg. 246 ff.---Halban, Das röm. Recht i. d. germ. Volksstaaten III.---Conrat, Geschichte d. röm. Rechts im früheren Mittelalter---Vinogradoff, Roman law in medieval Europe.
一 ゲルマン人法の制定
イ 西ロォマ帝国瓦解のあとの荒野に、あちこち建つたゲルマン諸国は、粗野に力づよく、ずんずん発育しはじめた。新たな経済事情が、彼らの生活に変化を開き、クリスト教の感化が、彼らの倫理観念に一革新をもたらした。彼らはもう、父祖相伝の粗朴慣習を、そのまま守るに堪えなくなつた。口から口へ伝へられてきたものをすつかり整理し、正しさうなものだけを、文字に確定しておかうとおもふに至つた。
ロ 慣習の整理・部族固有法の成文化が、そこここに、はじまつた。あるものは自意的にその慣習を文書にし、あるものはカァル大帝の命をうけて記録した。フランクやロンバルドのやうな・早くからロォマ化した部族は、自発的に成文に直したが、遠き北方の野におちついた部族は、大帝の命令あるまでのばしてゐた。八〇二年に大帝が、Aix-la-Chapelleに帝国議会を開き、未だ法典を有せざるものは、いそぎこれを制定すべく、すでに法典を有するものも、この際修正するところあるべしと命じたので、これを機会に、諸部族の法典、一時に出そろふことになつた。すなはち西ロォマ帝国の滅亡からカァル大帝のころまでの間に——五世紀半から九世紀初めまでの間に——ゲルマン諸族は、大抵成文法典をもつやうになつたのである。これらを部族法(Volksrecht)又はゲルマン人法(leges barbarorum)といふ。
ハ 部族法又はゲルマン人法は、或は人民これを作り、或は人民参与の下に王これを作つた。年代の古きものは大抵人民の制定だつたが、新しきもの、乃至ロォマの感化を濃厚にうけた部族のは、人民参与の下に、王の制定したところに係つた。年と共に王権の伸張を見た結果である。起草者は、部族の古老で、ロォマ人ではなかつた。ロォマの専門家が参加した場合にも、その担当は、軽微な方面の仕事に限られてゐた。用語は訛れるラテンを用ゐ、所々にゲルマン語をそのまま挿み、又は語尾だけをラテン風に曲げて挿入してゐる。古きものほど、言表が粗荒である。内容は刑法および刑事訴訟法に関し、身ノ代金(Wergeld)贖罪金(Busse)の規定が、大半を領してゐる。けだし部族慣習法の全部を成文化せしにあらず、わづかにその一部——記録を要とした一部——を記録し、他を依然不文のままに放置しておいたからでもあらうか。どの部族も、制定後しばしば増補改訂を行つた。増補された新規定を修正法(leges emendata)といふ。
二 ロォマ人法の制定
イ ゲルマン征服者は、またロォマ法の法典をも作つた。けだし領内にロォマ人の住むもの甚だ少なかつた地方では、征服者は、その部族のために、ゲルマン法典だけを作つて、それをロォマ人に押しつけることもできたが、領内にロォマ人の住むもの相当に多かつた南欧の国では、彼らの法律慣習を尊重し、彼らのために特別法典を作つてやる必要があつたのである。西ゴォト・ブルグンド等のごとし。イタリイに在つた東ゴォト国などは、ロォマ法の法典のみを作り、これをゲルマン人にも強制したほどだつた。ゲルマン征服者が領内のロォマ人のために立てたロォマ法の法典をロォマ人法(leges Romanae)といふ。
ロ ロォマ人法は、或は人民参与の下に王これを作り、或は王単独にてこれを作つた。起草は、ゲルマン人法編纂の場合と異り、ロォマの専門家であつたらしい。主もな材料は、帝政末の三法典Codex Theodosianus, Hermogenianus, Gregorianusだつたが、GajusやPaulusの著書からも幾分抜いた。原文のまま摘録したに過ぎぬものと、原文に加工し、内容に統一をつけたものとあつた。あるものは先時代の法源を廃してこれに代る力をもつたが、あるものは先時代の法源を補充したに過ぎなかつた。しかし事実上どこの国でも、ロォマ人法発布の結果、古典的法源の死を来たしたのである。Codex Theodosianusその他が、現行法たる地位を失ひ、単なる歴史的紀念物となつてしまつたのである。古代と中世との間の法源上の連絡を切断したものは、実にロォマ人法であつた。
三 属人主義
ロォマ人はロォマ人法により、ゲルマン人はゲルマン人法によつた。同じゲルマンでも各部族互に法を異にし、同じFrankenでありながらRibuarierとSalierとChamavenと互に法を異にし、同じFriesenでありながらOstfriesenとWestfriesenとMittelfriesenと互に法を異にするありさまだつた。自己の部民にのみ部族法を適用し、他の部民に対しては、その自国領内にある者に対してすら、これを適用しなかつた。すなはち部族法の効力は、属人的であつたのである。ただし妻は、夫の部族法に従つた。身ノ代金・贖罪金は、被害者の部族法によつて、その成立および範囲を定められた。相続権は、被相続人の部族法によつて、その有無および程度を定められた。刑罰は、犯人の部族法によつた。僧Agobard von Lyonの『五人の犯人につき五つの法あり』といつた1)のが、偽りなき当時の実情であつた。
1) Ein Anszug in den Mon. Germ. Leg. III.
第二節 ゴォト系諸国の立法
一 東ゴォトのロォマ人法
イ 東ゴォト王Theoderich (454--526)は、四八九年の春、その部族全部を率ゐ、一大移民団を作つて、イタリイへ乗りこんだ。さうして三年が間、ロォマ人と戦つてこれに勝ち、遂に半島の主人となつた。新主人の布いた新政は、予期以上に善良だつた。後には彼の侵入の遅かりしことが恨まれたほど、彼は巧妙な政治を布いた。立法史を飾る彼の事業は、Edictum Theoderici1)の編纂である。
1) Ausg.: Bluhme in den Monumenta Germaniae histor., Leges V.---Vgl. Mommsen, Ostg. Studien, Neues Archiv 14.
ロ Edictum Theodericiは、百五十四ヶ条の本文と、前文および後文とから成り、『政務官の告示』(edicta magistratuum)として発布された。なぜ『法律』(lex)として出なかつたのかといふに、Theoderichは、皇帝を以て自らをらず、ロォマ帝国の一政務官を以て自らをり、従つて自分には法律制定の権なく、告示権(jus edicendi)あるに過ぎぬと考へたからであつた。起草者は判然しない。しかしそれがロォマ人であつたことだけは断言できやう。この法典に示されてゐるやうな広汎なロォマ法的知識を、ゲルマン人が、蓄へてゐたらうとはおもへぬからである。立法資料は悉くロォマ法に仰いだ。Pauli Sententiae, Codex Gregorianus, HermogenianusわけてもCodex Theodosianusが主要な材料であつた。ゲルマン法は、全然斟酌されなかつた。1)
1) Ausg.: Bluhme in den Mon. Germ. Leges V.---Vgl. Mommsen, Ostg. Studien, Neues Archiv 14, 223. 451 ff., 517 ff.
ハ 制定年代については議論あるが、五一二年乃至一五年の間と見るが通説である。その理由は、五一二年以前および一五年以後は、共にかの有名なるCassiodorが、Questorの要職に就いてゐた時代だが、彼はその著,,Variae``1)の中で、自己の起草にかかる法令についてはもちろん、その他一切の政治的出来事について記してゐるのに、Edictum発布の事にはふれてをらぬところを以て見ると、Edictum発布は、ちやうどCassiodorが官を退いてゐた一二年乃至一五年の間の事であつたらうと、推測して差支ないといふにある。2)
1) Ausg.: Mommsen in den Mon. Germ. Auctores antiquissimi. XII. 2) Gaudenzi, Entstehungszeit des Edictum Theoderici, Zeitschr. f. Rechtsg. 20, 29. 拙稿・中世イタリイの法源(同志社論叢七号)六〇頁以下参照。
ニ Edictum Theodericiは、ロォマ人にもゲルマン人にも、共通に適用された。しかしEdictumに収められた条規は僅々百五十四に過ぎず、しかもその殆どが、刑法又は刑事訴訟法であつたから、政府は、Edictumの規定に上らざる事項に関して、部族法の効力を留保し、ゲルマン人にはゲルマン慣習を、ロォマ人にはロォマ法を各別に適用し、さうすることによつてEdictumの足らざるところを補完せねばならなかつた。ところが当時のロォマ法たる、法源甚だ錯綜。検索にも不便だつたので、この際、領内のロォマ人のために、何か便利なロォマ法の抜萃書を作つてやらうといふことになつたが、恰もよし、先進国たる西ゴォトで、抜萃書Breviarium Alaricianumの発布あり、ブルグンド王国でもLiber Responsorumの発布あり、共に好評を博してゐたので、この二外国法典をそつくりそのまま継受して、東ゴォトの法律となし、これを以て領内のロォマ人の法的需要に備へやうといふことになつた。尤もさうした政府の命令が果してあつたか、単に人民が慣行で継受したに過ぎなかつたか、そこは明かでないが、とにかく西ゴォトおよびブルグンドの二外国法典が、東ゴォト領内のロォマ人に妥当し、裁判所もこれを法源と見てゐたことは疑ひない。ことに西ゴォトの法典Breviarium Alaricianumの方は、かなり広く行はれたものらしい。
ホ しかしTheoderichは、あへて古典法源の権威を無視しやうとはしなかつた。或は新法典を編纂し、或は外国法典を輸入したが、それは、生きた法規を時の社会に供給せんがためで、古典法源廃止の意思からではなかつたのである。後出ブルグンドや西ゴォトでは、新法典を以て古法源に代置させたが、東ゴォトでは、二者を平行させ、古法源の効力をあくまで保存したのである。尤も古法源中実用あるものは、大抵右のBreviariumやLiberの中に収容されてゐたらうから、古法源が、それとして使用された場合は事実甚だ少なかつたであらうが。
ヘ 終りにロォマ人とゲルマン人との間の取引につき、何法が適用ありしかを見るに、Theoderichはなるべく早くゲルマン人をロォマの文化に同化させやうとの彼の統治の根本方針から、二民族間の関係にも、ロォマ法を適用した。実地においても、ロォマ法の施行を確実にせんために、ゲルマン人たる裁判官の傍らに、ロォマの法律家を陪席させ、ロォマ法的知識の不足を補はせたほどだつた。そのため、東ゴォト王国におけるロォマ法の勢力は聳然高く、(一)刑事に関しては純ロォマ法たるEdictum Theoderici一般に行はれ、民事に関しても、(二)ロォマ人間の事件にはもちろん、(三)ロォマ人とゲルマン人との間の事件にもロォマ法行はれ、ゲルマン法は、わづかに少数の蛮民相互の間に、余喘を保つに過ぎざるありさまだつた。
やはりイタリイはロォマ法の舞台であつたのである。西ロォマは滅んでも、ロォマは圧倒的勢力を維持してゐたのである。
ト 五二六年にTheoderich死し、Athalarich (526--534)跡をついだ。彼も『告示』の形式で多くの法令を出したが、そのうち有名なのは、一の前文と十二の条とから成り、多分Cassiodorの起草に係つたであらうところのEdictum Athalarici regisである。1)内容は、土地の横領・その他当時流行した犯罪を禁圧することを目的としてゐる。
1) Ausg.: Mommsen in den Mon. Germ. Auct. ant. XII.
二 西ゴォトのロォマ人法
イ 西ゴォトが国したのは、今のスペインである。スペインは、西ゴォトの手に落ちるまで凡そ六百年、ロォマの県として存分ロォマ法を吸収してきた土地だつたから、ここに国した西ゴォトは、イタリイに国した・かの東ゴォトと同様に、ロォマ法を尊敬し、ロォマ人はロォマ法によつて生活することができるとした。
ロ 王Alaric II (485--507)に至り、ロォマ人のために一の特別法典を作つた。通常Breviarium Alaricianum1) 2)とよばれるのがそれである。
1) この法典は公の名をもたなかつたから、,,Liber legum Romanarum``, ,,Corpus legum``, ,,Lex Theodosii``, ,,Lex Romana``, ,,Liber Theodosianus leges Romanae``, ,,Lex Romana Visigothorum``等種々によばれた。十六世紀以来Breviarium Alaricianumの名が普通となつた。
2) Ausg.: Hänel, Lex romana Visigothorum 1849; Conrat, Breviarium Alaricianum 1903.
ハ 起草者はロォマ人だつたが、Graf Goiaricusといふやうな・ゴォトの学者もまじつてゐた。材料は主としてCodex Theodosianusであつたが、Codex Gregorianus, Hermogenianusの中からも取り、Theodosius以後の諸帝の発した新令(sog. posttheodosische Novellen)からも取り、Paulus, Papinianus, Gajus1)らの著書からも抜いた。すなはち帝政末の代表的法源を一とわたり渉猟し、その中から当時スペインにゐたロォマ人に、妥当しさうな条文を撰んだのである。撰んだ条文には、字句の変改を加へなかつた。原形のまま羅列したに止まつた。
1) GajusのInstitutionから直接抜いたのではなく、Institutionの抜萃書であり、そのころ学生および裁判官の必携書であつたLiber Gaiから取つたのである。
ニ 編纂の業終るや、王Alaricは、GasconyのAireに民会を召集してその賛成をえ、全国の侯伯に法典の謄本を送附し、爾後この法典のみによつて裁判をなすべきことを命じた。それが五〇六年二月二日だつた。この時以来西ゴォトでは、一切の古典的ロォマ法源その効力を失ひ、Breviariumのみ唯一のロォマ法源となるに至つたのである。
ホ その後百五十年間、Breviariumはスペインに行はれた。政府はその間に、Ulpianus, Papinianus, Modestinus等ロォマ古典期の学者の著書から抜撰し、屡々Breviariumの増補を行つた。六五四年、王Reccesvindの時にとうとう廃止されてしまつたが、外国ではなほ生命を維持してゐた。フランク配下のロォマ人は、つとにこのBreviariumを継受してゐたのであつたが、スペインで廃止されてからも、引きつづき八世紀ごろまで、遵奉してゐたのである。
三 西ゴォトのゲルマン人法
イ 西ゴォトは前示の通り、領内のロォマ人のためにロォマ人法を作つたが、実はそれよりも先きに、自分たちのためにゲルマン人法を作つてゐた。スペイン侵入後、慣習成文化の必要を感得し、これを編纂するに至つたのである。Codex Eurici1)といはれるのがそれで、Alaric IIの先代Eurich王(467--485)の時代に出来た。
1) Kritische Ausg.: Zeummer in den Mon. Germ. Leg. I, 1---Lit.: Zuemmer, Geschichte der westgot. Gesetzgebung, Neues Archiv XXIII (1898) ff.
ロ その大部分は堙滅に帰し、僅か伝つてゐる断片(c. 276, 312, 318--325, 327, 336)は、ゲルマン人とロォマ人との間の土地分配法・売買・贈与・消費貸借・親権および相続に関してゐる。制定年代は明かでないが、四六九年から八一年までの間、すなはち西ロォマ帝国滅亡のころだつたらうといふ。何しろそれは、ゲルマン最古の立法であつたのである。さうして後日の立法に少なからぬ影響を与へたのである。後出Lex Burgundionum, Salica, Alamannorum, Baiuwarionumのごとき、たしかにこれから影響された。
ハ その後百年間、Codex Euriciは、ほぼ原形のまま行はれてゐたらしいが、王Leovigild (572--586)の時、徹底的一大改正を受けた。改正の結果をCodex revisus Leovigildsといふ。Leovigildの子Reccared王(586--601)も、重要な幾多の新令を追発した。
ニ ちやうどこのころ、西ゴォトの国情に一大変化が起りつつあつたのであつて、第一に、ロォマ人とゲルマン人と混血し、ラテン語とゲルマン語と合体し、民族対立を失ひかけてきた。第二に、人民の代りに貴族が、立法に参与しはじめた。領土拡張による人民の増加の結果、全人民を立法に参加さすことができなくなり、殊勲ある者を貴族とし、人民の代表とし、彼らだけにはかつて立法するやうになつたのである。第三に、毎回Toledoに開かれる宗教会議が、法律に容啄しはじめた。第一および第二の会議は、さうでもなかつたが、五八九年の第三回会議、六三三年の第四回会議あたりから、純法律問題にも触れ出した。
ホ 第五回会議は、六三六年に開かれ、第六回会議は、六三八年に開かれた。時の王Chintilasは、これらの会議にはかつて幾多の新令を出したが、そのあるものはロォマ人にもゲルマン人にも適用された。二民族の対立薄すれ、その結果、共通法を出しうるに至つたのである。王Chindasvind (642--653)に至り、ロォマ人のための特別法典たるBreviarium Alaricianumを廃止する案を立てた。Breviariumの中から必要な規定を抜きとつて、これをゲルマン人法典の方へ移し、ゲルマン人法典の内容を豊富にすることによつて、Breviariumを廃止へ導かうと考へたのである。子のReccesvind王(653--672)に至つて、この案は断行された。王は、ゲルマン人法典たるCodex revisus Leovigildsに大修正を加へると同時に、ロォマ人法典たるBreviariumの廃止を宣し、はじめて西ゴォトに、統一的国民法典をもたらしたのである。修正されたCodex revisus LeovigildsをLex Visigothorum Reccesvindiana1)といふ。六五四年ごろの発布である。
1) Ausg.: Zeummer in den Mon. Germ. Leg. I, 1.
ヘ Lex Visigothorum Reccesvindianaは、公私両法を含む。全部で十二巻。巻を章に分け、章を条に分け、条の下に歴代の王令を組織的に配分してゐる。その状ほぼユ帝法典の勅法篇(Codex)に同じい。Leovigild以前から存した法条には、「古」(Antiqua)の字を附記し、爾後の諸王の新令には発布王の名を掲げてゐる。
ト その後六八一年に王Erwigが、Reccesvind法典に変質的大修正を加へた。これをLex Visigothorum renovataといふ。1)六八四年から七〇一年までの間に王Egikaが重要な幾多の新令を追加し、その子のVitica (701--710)も改正を行つた。2)改正毎にロォマ的・教会的要素が増して行つた。
1) Ausg.: Zeummer in den Mon. Germ. Leg. I, 1. 2) Ausg.: ebd.
四 ブルグンドのロォマ人法
イ ブルグンドの国したのは、今のフランスである。ここもロォマ法のかなり泌みこんだ区域だつたから、一方において侵入者は、自国民のためにゲルマン法典を作ると同時に、他方において先住ロォマ人のためにロォマ法の法典を立てざるをえなかつた——
ロ ブルグンドのロォマ人法を、Liber Responsorumといふ。1)制定年代不明。Gundobad王時代(474--516)の産物であるかも知れず、後継王Sigismund (516--)の作であるかも知れぬのである。けだしGundobadはブルグンド最大の立法王で、後出ゲルマン人法典をも編纂したが、その際、追つてロォマ人のためにもロォマ人法典を作るべきことを予告したので、もしこの予告が実行されたとすると、Liber Responsorumの発布は五一六年以前となる。しかしLiberの前文に、恰もSigismundの作なるがごとく書いてゐるので、これを信じると、五一六年以後となる。通説は五世紀の末Gundobadの発布したものと見る。
1) Liber ResponsorumはResponsum PapianiともいはれLex Romana Burgundionumともいはれる。Ausg.: Bluhme in den Mon. Germ. Leg. III---Lit.: Brunner, Deutsche Rechtsg. I. 2. Aufl. 508.
ハ 内容は民法・刑法・刑事訴訟法に亘る。材料は主もに、帝政末の三法典Codex Theodosianus, Hermogenianus, Gregorianusから取り、Gajus, Paulusらの著書からも抜いた。西ゴォトのロォマ人法Breviarium Alaricianumをも利用したらしい。しかしLiberは、Breviariumのやうな、単なる法源の羅列でなくして有機的統一をもつた真の意味の法典であつた。
古典的ロォマ法源は、この法典の発布により、全部効力を失つてしまつた。判決の淵源に一新を来たした。
五 ブルグンドのゲルマン人法
イ 立法王Gundobad (474--516)は、ゲルマン法典をも作つた。これをLex Burgundionum又はLex Gundobadaといふ。1)制定の年は、法典が王単独の作なること明瞭なるに、四九九年までは、王、単独支配者にあらず、その兄弟と共同政府を作つてゐたから、どうしても制定は、同年以後でなければならない、恐らく単独統治の第二年、五〇一年の事であつたであらう。
内容は、ブルグンドの慣習でなくて、Gundobad自身の命令および彼以前の諸王の命令の収集であつた。
1) Ausg.: Salis in den Mon. Germ. Leg. I. 1.---Lit.: Zeummer, Zur Textkritik u. Geschichte d. Lex Burgundionum im Neuen Archiv XXV.
ロ 王は、ゲルマン人に対してばかりでなく、ゲルマン人とロォマ人との間の取引にも、その法典を適用した。東ゴォトのTheoderichと反対に、ロォマ人をゲルマンの文化に同化させやうといふ根本の方針を取つたから、二法衝突の場合につき、ゲルマン法常に必ず優先すと定めたのである。
その後、新令追加の必要生じ、ことに後継王Sigismundが、たくさん新令を出した。しかしSigismundは、新令を単行法として別置せず、Lex Burgundionumの中へ、その有機的一部分として挿入したから、後世の人にとつては、Lexのどの部分が、Sigismundの挿入にかかるか、鑑別なかなか容易でない。が、今日伝はるLex Burgundionumの一章から四十一章までは、内容も簡単、行文も古風であるから、Gundobadにより保留された彼以前の王たちの命令なるべく、四十二章から八十八章までは、よりよき文体をもつから、Gundobad自身の命令なるべく、八十九章以下には古き規定の混入もあるが、大体Sigismundの追加法であらうといふ。
ハ ブルグンド王国は五三四年、フランク王国膨脹の犠牲となつて滅びたが、Lex Burgundionumはブルグンド人の属人法として、彼らの間に効力を維持した。Liber Responsorumの方はこれに反し、全く行はれぬことになつた。もとブルグンドの配下だつたロォマ人は、王国滅亡の後、蛮王の細工したロォマ人法Liber Responsorumに服するよりも、古典期の法源そのままの摘録なる・西ゴォトのロォマ人法Breviarium Alaricianumに服する方が、はるかに好ましいとなし、後者を継受して彼らの属人法としたのである。
第三節 フランク系諸国の立法
一 ザリア・フランク
イ ザリア・フランクの国したのは、今のベルギイであつたが、極めて早期に、慣習の整理および成文化を断行した。出来た法典が、有名なLex Salica1)である。
1) Ausg.: Behrend 2. Aufl. 1897---Lit.: Hilliger, Hist. Vierteljahrschr. VI, IX, X, XII, XIII; Krammer, Neues Archiv XXX, Ders. Festschr. f. H. Brunner 405 ff. 拙稿・蛮人法殊にLex Salicaに就て(法学論叢・七ノ一)。
ロ ハッキリしたその制定年代は分らない。が、五〇八乃至一一年の間と見るが、通説である。理由は、(一)フランク人のクリスト教改宗は、四九六年だつたが、法律の中に、まだ少しもクリスト教に染んでゐない原始的規則の、存するところから推すと、どうしても改宗後間もないころの制定としかおもへない。(二)王国の領土、Loire河以南へ延びたのは、五〇七・八年ごろだつたが、法律の中に、Loire以南の人民のために特別の便宜を図つた規定——訴提起の方法等につき——存するところから推すと、王国の領土が、Loire以南に延びて間もないころの制定と見らる、(三)有名なChildebert Iの治安維持法(Pactus pro tenore pacis)の出たのは五五七年よりも遥か以前、であつたに相違ないが、この法律の中にLex Salicaの引用されてゐるところから、当時すでにLex Salicaの存在せしことを知る。かやうに前後から追ひつめて、どうしても五世紀末か六世紀初頭——恐らく王Chlodwigが、その偉大なる征服的生涯の終りに、法典編纂の必要を感得し、これを編纂したのであつて、五〇八乃至一一年の間と見るがよからうといふのである。1)
とにかくそれは、前示西ゴォトのCodex Euriciに次ぐところのゲルマン最古の立法であつたのである。
1) So Brunner, Rechtsg. I. 433 ff.; Ders. Grundz. 38; Schröder-Künssberg, Rechtsg. 251---これに反し、Hilliger, a. a. O.は一部分は四八六乃至四九六年の間に、一部分は四九六乃至五〇七年の間に、さらにある部分は五二四乃至五五八年の間に出来たと見る。
ハ 制定の次第は、法典前文のいふところによると、四人の古老、委員となり、先例を蒐録し、王Chlodwigから補正を受けたのだといふ。ほぼ真に近いであらう。内容は西ゴォトの法典Codex Euriciを参照した形跡あるが、要部は大体、ザリア・フランク人の原始慣習だつた。
ニ その後、ザリア人が、フランク族中の中心勢力となるに至つた結果、Lex Salicaも適用範囲を広め、他の系統のフランク人、例へばMosel, Main両河の流域に住んでゐたフランク人、Hessenに住んでゐたフランク人にも、適用されることになつた。従つて内容に補正を加へる必要も生じ、歴代の諸王、種々の新令を追発したが、それらはいづれも単行法の形ちで出で、原典の修正によつたのではなかつた。原典の修正は、Chlodwig以後、遂に一度も試みられずにしまつたのである。今日伝はるLex Salicaの古写本に異本多きは、いかなる新令をどう原典に加ふべきや——挿入すべきや附録せしむべきや——が、全く編者の随意に出たためだらうといふ。官の手で修正が行はれてゐたのなら、古写本の間に、もつと統一があつた筈だ。1)
1) ある種の写本は、その欄外に、malb又はmallなる略字を冠したフランク語の傍註を附してゐる。malb又はmallとは、『裁判所』を意味するフランク語のmallobergoの略字で、その下に、法の運用に関する訓示の類が附記されてゐるのであらうといふが、その意味は、今日大部分不明である。
ホ 何にしろフランク人は、欧洲の支配者として欧洲各地に跋扈してゐたから、Lex Salicaもフランク人の属人法として、欧洲各地に行はれた。ことにイタリイにはフランク人多く、Lex Salicaの勢力も強かつた。また範をLex Salicaに取つて立法した部族も少なくなかつた。Lex Ribuariaのごとき、Lex Thuringorumのごとき、Lex Francorum Chamavorumのごとき、いづれもザリア人の立法から感化を受けた。
二 リブアリア・フランク
イ リブアリア・フランクの国したのは、ライン中流の両岸だつたが、六世紀後半、はじめて成文法典を作つた。今日伝はるLex Ribuaria1)の一乃至三十一章は、彼らの原始慣習をしのばせる古風な規則だが、多分それは、後日修正の際、新法典の中へとり入れられた当初の法典で、もと独立してゐたのであらうといふ。
1) Ausg.: Sohm in den Mon. Germ. Leg. V---Lit.: Sohm, Ztschr. f. Rechtsg. 5---Ernst Mayer, Zur Entstehung der Lex Ribuariorum 1886---Goldmann, Neue Beiträge zur Geschichte des fränkischen Rechts 1928.
ロ その後間もなく——やはり六世紀中に——同族ザリア人の法典Lex Salicaの中から、リブアリア人の旧慣と調和しさうな規定を抜き、少し加工して、これをリブアリア法典へ移した。明かにLex Ribuariaの三十二乃至六十四章は、Lex Salicaの移植である。
ハ つづく六十五乃至八十九章は、Dagobert I (+639)の勅令の収載である。当時すでに諸族の上に立つ統率者は、配下の部族の法律を、その部族民会の同意なしに補正しえたのであつたが、Dagobert Iも、全フランク族の統率者として、リブアリア法補正の勅令を発し、それがそのままリブアリア法典の一部となつたのである。
三 シヤマビイ・フランク
イ シヤマビイ・フランクの国したのは、ライン下流の両岸だつたが、南にザリア、北にフリイセン、東にザクセンの影響を受け、外国法の感化強きにすぎて、固有法の発達を見なかつた。他の部族のやうに、旧慣を成文にまとめておかうとも、しなかつたらしいのである。
ロ 八〇二・三年ごろ、カァル大帝の命を受けてシヤマビイ地方に出張し来つた巡察使が、シヤマビイ地方の裁判例につき、土地の古老と問答を交換し、えた答を、備忘録にとどめた。これがLex Francorum Chamavorum1)といはれ、Ewa Chamavorumともいはれるもので、四十八ヶ条あるが、実は法典でなくして、巡察使の単なる手控へ(memoratio)であつたのである。
1) Ausg.: Sohm in den Mon. Germ. Leg V---Lit.: Schröder, Untersuchungen zu den fränkischen Volksrechten 1879---Froidevaux, Études sur la Lex dicta Francorum Chamavorum 1891.
四 アンゲル
イ 今のドイツのThuringen地方に、Angeln, Warnerの二部族がゐた。南からリブアリア・フランクの感化を受け、東からザクセンの影響を受け、法律なども大抵二国からの継受で済ましてゐたが、八〇二年にカァル大帝の命令あり、にはかに法典編纂をやつた。出来たのが、Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum1)とよばれるところのものである。又の名をLex Thuringorumといふ——チユゥリング部族の法律といふ意に聞えるが、実はチユゥリングにゐたAngeln, Warner二族の法律であつた。
1) Ausg.: Richthofen in den Mon. Germ. Leg. V---Lit.: L. Schmidt, Hist. Vierteljahrschr. III---Schröder, Ztschr. f. Rechtsg. germ. Abt. XX.
ロ 条数は六十一。ゲルマン人の法典の中で最も短い。が、刑法ばかりでなく、相続にもふれてゐる。材料は主もにLex Ribuariaから取り、Lex Saxonumからも抜いた。
第四節 ザクセン系諸国の立法
一 ザクセン
イ ザクセンは今のドイツに国したが、気性荒く、屡々フランク人と猛烈な衝突をやつた。クリスト教へ改宗したのも、よほど後だつた。その立法の過程は、甚だ明かでないが、大帝カァルに征服されてしまふ以前から、成文法典は、あつたらしい。Lex Saxonum1)の一乃至二十章は、多分その断片で、貴族の特権を規定し、ザクセン初期の社会機構をほの見せてゐる。
1) Ausg.: Richthofen in den Mon. Germ. Leg. V---Lit.: Walter Schücking, Über die Entstehungszeit und die Einheitlichkeit der Lex Saxonum, Neues Archiv XXIV---Schwerin, Zu den Leges Saxonum, Ztschr. f. Rechtsg. germ. Abt. XLVI.
ロ 大帝の配下に入つてからも、屡々独立を企てたので、帝は圧迫主義をとり、酷烈な刑法を以て臨んだ。Lex Saxonumの二十一乃至三十八章は、些細の犯行にも死刑を課してゐるが、これなどはザクセン人の自意的立法にあらず、恐らくカァルが、あの有名なザクセンの乱(781--785)鎮定の直後、ザクセン人を懲らすために作つた勅令を、そのまま書き込んだものであらうといふ。
ハ 八〇二年、カァルは配下の諸族をAix-la-Chapelleに会し、未だ法典を有せざる部族はいそぎ制定すべしと厳達した。そこでザクセン人も、リブアリア・フランク人の法律Lex Ribuariaを手本にして、急にLex Saxonumを作り上げたが、その際、前示二個の法律、すなはちカァルに征服される以前からあつた旧法典と、カァル鉄血政策の紀念たる刑法とを新法典に合本し、通《とほ》し条文に列らべたのである。全部で、六十六条。三十九乃至六十六条だけが新制定で、他は旧法典又はカァルの勅令であつた。
二 フリイセン
イ フリイセンが国したのはオランダの海岸で、東部・中部および北部に分れてゐたが、七三四年、中部まづ、フランクの版図に入つた。この年彼らは、フランクの学者の手をかりて、中部フリイセンの旧慣を成文化したらしい。それがLex Frisionum1)の原形であつた。
1) Ausg.: Richthofen in den Mon. Germ. Leg. III---Lit.: Rietschel, Das Volksrecht der Friesen (Festschr. f. Gierke, 1911)---Hecke, Die Entstehung der Lex Frisionum, 1927.
ロ 七八五年に東部も西部も、全部フランクの手に帰した。よつてこの二部族も、彼らの慣習を文字に示さねばならぬこととなつたが、大体それは中部の慣習に似てゐたので、別に法典を作らず、中部人の法典Lex Frisionumをそのまま認め、これに各自の特則を書き込むだけに止めた。西部まづその特則を挿入し、東部もこの方法をとつた。
ハ 八〇二年にカァルより法典編纂の命あるや、フリイセン政府は、二人のフリイセン学者WlemarおよびSaxmundをして判例を蒐録せしめ、かなり準備を進めたが、何故か中絶し、遂に完成を見なかつた。今日伝はるLex Frisionumなるものは学者の私編で、中部フリイセンの法律と東西二部の特別法とを、二十二の章に収め、別に附録(Additio sapientum)としてWlemarおよびSaxmundの判例集を添へてゐる。
第五節 スワビヤ系諸国の立法
一 アラマン
イ アラマンの国したのは今の南独北瑞だつたが、とかくフランクの勢力に押され、その節度を受けてゐた。七世紀の前半——恐らくフランクでDagobert I (+639)の王たりしころだつたらう——Pactus Alamannorum1)なる一法典を編纂したが、その内容は、わづかに伝つてゐる五個の断章から推想すると、アラマン固有の旧慣でなくして、フランク法の模写に過ぎなんだ。
1) Ausg.: Lehmann in den Mon. Germ. Leg. V.
ロ その後アラマンは、フランクの一侯国となつたが、事実上の独立は保持してゐた。七三〇年とうとうフランクの滅ぼすところとなつたが、滅亡に先ち、かなり大部の一法典を作り上げた。Lex Alamannorum1)がこれである。作者は最後の侯Lantfrit (709--730)、制定年代は七一七年から一九年の間。フランクで、Chlotar IV (717--719)の王たりしときだつた。
1) Ausg.: Lehmann in den Mon. Germ. Leg. (Quartausgabe) V. 1---Brunner, Über das Alter Lex der Alamannorum in den Berliner Sitzungsb. 1885---Lehmann, Zur Textkritik und Entstehungsgeschichte des alamann. Volksrechts, im Neuen Archiv X.
ハ Lex Alamannorumは、三部九十八章から成る。第一部すなはち一乃至二十二章は教会の特権を規定し、第二部すなはち二十三乃至四十三章は公法を規定し、第三部すなはち四十四乃至九十八章は私法を規定してゐる。前二部の背後には、散逸した或フランク王の勅令あり、これを加工して出来たのであらうといふ説はBrunnerにはじまり、1)今は大方の承認をえてゐる。後一部は、Pactus Alamannorumを基礎にしたが、Lex Ribuariaや、Codex Euriciをも利用した。
1) Brunner, Über ein verschollenes merowingisches Königsgesetz des 7. Jahrhunderts, Berliner Sitzungsberichte 1901, S. 932.
二 バイエルン
イ バイエルンはアラマンの東北に国し、アラマンと同様、フランクの節度に服してゐたが、アラマンより少し遅れて法典を編纂した。それがLex Baiuwariorum1)である。正確にはわからぬが、七四三年から四八年の間に、侯Odiloが作つたのであらうといふ。
1) Ausg.: Merkel in den Mon. Germ. Leg. III---Riezler, Über die Entstehungszeit der Lex Baiuwariorum, in den Forsch. z. deutsch. Gesch. XIV---Schwind, Kritische Studien zur Lex Baiuw. Neues Archiv XXXI ff.
ロ 材料は多方面に亘り、或はLex Alamannorumから取り、或はCodex Euriciから取り、或はLex Salicaから取り、後出ロンバルドの立法からも抜いた。またかのLex Alamannorumが台本としたであらうところの或フランク勅令——それをも、たしかに利用したのであるが、精練甚だ足らず、複雑な材料を紛然と羅列しただけの観しかない。
ハ 七七二年および七四年(又は七五年)に、バイエルン最後の侯Tassilo IIIが、Lex Baiuwariorum補充の意味で、二個の法律を発布した。これをDecretum (Decreta) Tassilonisといふ。
第六節 ロンバルド
一 ロンバルドの史上地位
ロンバルドは、法律に稀有の才あつた民族で、整然たる法典を作り、ゲルマン人の法律思想に精確な表現を与へた。数あるゲルマン立法中彼らのが、一ばん組織的であつたのである。封建期に入つてからは模範的封建法を作つた。大抵の国はロンバルドの封建法を継受し、封土の取得喪失その他に関する疑問を、これによつて解決してゐたのである。
また彼らは法律学を再興した。その法律に学的加工を加へて組織的体系となし、ロォマ法に拮抗する大勢力たらしめた。ロンバルド国が滅びてもロンバルド法は残り、よほど後代まで——十三世紀まで——力ある余命をつづけたのである。
法律の文化史に永久の果実をもたらした点において、ロンバルドは、東西ゴォト・ブルグンドらと全く異る。
二 Edictum Rotari
イ さてその立法の経過をのべると、彼らがイタリイに侵入し、ポォ河の渓谷に建国したのは、五六八年のことだつたが、ゴォトやブルグンドのやうに、あはてて法典を作らず、判例ことに王の裁判所の判例に、法規創造の力を認め、1)判例の中から自然に法の成長してくるのを眺めてゐた。第十七代の王Rotariに至つて、はじめて法典を作つた。これをEdictum Rotari2)とする。
1) Bethmann-Hollweg, Der germanisch-romanische Civilprozess im Mittelalter, I. 322. 2) Ausg.: Bluhme in den Mon. Germ. Leg. IV---Lit.: Merkel Geschichte des Langobardenrechts 1848.
ロ 起草はロンバルドの古老だつた。古老先例を物語り、王の書記これを文章に直したのである。用語は、当時まだロンバルド語が文語になつてゐなかつたため、ラテン——イタリイでそのころ行はれてゐた・訛れるラテン——を用ゐた。条数三八八、民法・刑法・訴訟法に亘る。一乃至一五二条は刑法ことに国事犯の規定、一五三乃至一六七条は相続、一六八乃至二二二条は婚姻、二二三乃至二二六条は僕婢解放手続、二二七乃至三五八条は所有権とその侵害、三五九乃至三六八条は訴訟手続、三六九条以下は雑則である。
疑ひある語には定義を掲げ、重大な規則には理由を附し、類似の規定から、さらに普遍的な原則を抽出しやうとも努めてゐる。先例の無秩序な羅列でなくて、統一あり組織ある法典であつた。
材料はゲルマンの旧慣で、ロォマ法ではなかつた。遺言・時効・僕婢解放の手続等において、いささかロォマ法の影響を見る外、他はゲルマン的である。ゲルマン思想の濃烈な表出を、われらはここに見るのである。
ハ 発布にあたり王は民会を召集した。民会は官吏および軍人の全体から成り、その頃はもう時勢後れの廃退機関だつたが、古式に則つて召集し、その協賛をえて発布したのである。時に六四三年十一月二十二日、侵入後七十六年目だつた。
なぜ法律(lex)として発布せず、告示(edictum)として発布したかといふに、新侵入者には告示権(jus edicendi)あるのみにて法律制定権なしとの観念、まだイタリイに残存してゐたために外ならなかつた。ちやうどイタリイへ一足先きに侵入したかの東ゴォトが、『告示』の名で『法律』を布いたのと同じことを、やはりロンバルドもやつたのである。
ニ 効力に関しては疑義がある。ロォマ法の適用を排斥しえたかの点である。われらは消極説をとる。なぜなればEdictum Rotariには、『何人を問はず云々』(Si quis homo)といふ用語例もあり、『もしロンバルド人が云々』(Si quis Langobardus)『もしロォマ人が云々』(Si quis Romanus)といふ用法もあり、民族に従つて法の適用を二三にしてゐたこと明かであるし、王Liutprandの追加法九十一条にも、公証人はロンバルド法又はロォマ法の規定に従つて記録すべしとあり、二法の並び行はれてゐたことを実証してゐるからである。刑事に関しては知らず、少なくともロォマ人相互の間の民事に関しては、ロォマ法の適用があつたのである。
三 追加法
イ その後ロンバルドでは、非常に王権が強くなつたり、経済が発達したり、クリスト教の感化が内深したり、かなり生活に変動を生じたので、Edictum Rotari改正の必要を生じたが、その方法は、追加法の発布であつた。すなはちEdictumの規定を削らず、それをそのまま存置し、別に新令を発布するといふやり方をとつた。王Grimoaldが六六八年、九ヶ条を追加した。時効および相続に関する改正であつた。七一三年から三五年にかけて、王Liutprandが、一五三ヶ条の多数を追加した。訴訟制度の改革、教会特権の規定、婚姻故障の拡大が主題であつた。『人民の心霊の要求に基き』と王自身前文にいつてゐるやうに、法律内容をクリスト教の教へに近づけることが、改正の眼目であつたのである。
ロ 七四六年、王Rachiが十四ヶ条を加へ、七五〇年から五四年へかけて、王Astolfがさらに二十二ヶ条を加へた。
四 滅亡後
イ ロンバルド、は法王とカァル大帝との挟撃を受け、七七四年に滅びた。しかしロンバルド人そのものは滅びなかつた。彼らは半島の北地に固く根を下ろした実在の勢力であつたのである。ロンバルド法も滅びなかつた。それはロンバルドの遺民の属人法として根強い力を維持したのである。
ロ すなはちロンバルド王国の旧地に建てられたBenevet公国の公たちは、Edictum Rotariを承認し、そのままこれを公国の法律となし、必要な規定を追加するだけに満足した。公Aregisが七七四年から八七年の間に、十七ヶ条を加へ、公Adelchisが八六六年に八ヶ条を加へた——改正内容は、女子の地位の向上を図つたり、身ノ代金の計算を正確にしたり、公証人の制度を確立したり、とにかく人民の思想および需要の進歩を立証する種類のものであつた。
ハ カァル大帝もロンバルド法の発展に貢献した。なぜなれば彼は、配下の一国たるBenevet公国の法律を増補修正するために、たくさん勅令を発したが、それらは当然にBenevet法そのものの一部となり、直接にBenevet人——実質はロンバルド人——を拘束したからである。例へば帝は訴訟法を改正して裁判官の専断を塞いだり、不動産物権法を改正して貴族の横領を防いだり、教会の利益を伸長したり、教会主義の親族法を樹立したり、大いにBenevet法の内容を改めたが、それらはみな勅令の方法によつてであつた。
第七節 カァル大帝
一 カァル大帝の史上地位
イ いろいろの意味で、カァルは新時代を作つた——まづ立法に創設的機能を持たせたのは彼であつた。彼以前の立法は、出来上がつてゐる慣習を文字に直しただけで、新しいものを産まなかつたが、彼は立法の力で新規範を作出し、現行法の不備と不当とを、大いに改めやうとしたのである。確認的記述的な立法から創設的命令的な立法へ一歩を転じやうとしたのである。
なぜさやうな態度に出たかといへば、それはもちろん、カァルがゲルマン人の文化化に急だつたからである。彼は考へた、国家と教会と握手した以上、法と道徳とも一致しなければならないと。旧慣といへども陋なるものは棄てやう、諸部族の法律をして道徳的性質を採らせやうと彼は思ひ立つたのである。凡そ法律は事実的因襲的なものから、合理的批判的なものへ進むといふが、ゲルマン法もカァルあたりから、やや批判的になりかけた。
ロ またカァルは、属地主義の新原則を導入した。彼以前の立法は、殆どみな属人主義をとり、ある部族国の立てた法律は、その部民に適用あるのみにて他の部民には適用なし、領内に住む外国部民には、その固有部族法を適用す、内外二部民間の関係には、国際私法の撰ぶ一部族法を適用す、としてゐたのであるが、この原則に対しては、さすがに多少の制限を加へるものが古くからあつた。ゴォト・ブルグンドのごときは、一定の標準法典を作り、これを自分たちばかりでなく、自分たちと他の部民との間の関係にも一般的に強制し、さうすることによつて、他の部民法が、国際私法の助けをかりて国内に侵入してくるのを、やや喰ひとめやうと試みてゐたのである。換言すれば領内の法律を自国法で統一しやうと試みてゐたのである。が、真の意味の属地主義はカァルにはじまる。彼は法の効力を限るに、血液を以てせず、土地を以てしやうとした。種族主義の代りに地域主義を以てしやうとした。領内の者全部を一様に拘束するところの領土優越主義の法律を立てやうとした。1)
1) カァルはまた、立法と裁判とをかなりハッキリ分別した。彼以前は、いはゆる抽象裁判(Weistümer)の形ちで立法してゐたのであるが、カァルの頃から、個別的具体的事件の処理である裁判と、一般的抽象的規範の定立である立法と、やうやく分化するやうになつたのである。
二 勅 令
イ もちろんカァルその他のフランク王は、一部族の王として、その部族にのみ適用ある部族法を作ることもできた。これはlex (法律)の形ちをとり、民会の協賛をえて作られた。同時に皇帝として——諸部族の統率者として——配下の諸族全部に適用ある・若くはその数部に適用ある帝国法を立てることもできた。これをCapitula又はCapitularia (勅令)といふ。勅令は民会の協賛をえず、帝国議会の協賛をえて作られた。
ロ 法律が属人主義であつたのに反し、勅令は属地主義であつた。前者が旧慣の記述に過ぎざる是認的立法であつたのに反し、後者は新規範の作出を目的とする創設的立法であつた。実に勅令は、カァル大経綸の法的手段であつたのである。帝はこの手段によつて、従来分散してゐたゲルマン諸族を一の法律圏内にまとめ、彼らの間に一国民としての法的連絡を設定しやうと欲したのである。またこの手段によつて、ゲルマン古来の陋習を破り、彼らの法内容を合理的に改造しやうと欲したのである1) 2)。
1) Merowinger王朝のころは、edictum, decretum, decretio, praeceptum, praeceptio, auctoritasなどともいつてゐたが、Karolinger王朝になつてから、ことにカァルの世になつてから、capitula又はcapitulariaの名に統一されたのである。もとは法令の『各条』の意味だつたが、一転して勅令そのものを意味するに至つたのである。
2) Ausg.: Boretius-Krause in den Mon. Germ. Leg. (Quartausgabe) II, 1 u. 2---Komment. zu einzelnen Kapitularien; Gareis, Die Landgüterordnung Karls des Grossen, 1895---Lit.: Boretius, Beiträge zur Capitularienkritik, 1874---Beseler, Über die Gesetzeskraft der Kapitularien, 1871---Seelinger, Die Kapitularien der Karolinger, 1893.
三 勅令の制定公布
イ 勅令は通常、帝国議会の協賛をえて作られた。帝国議会は特に帝から招かれた俗的および宗教的の有力者から構成された。定時にも開かれ、臨時にも開かれた。議案は帝から出るを普通としたが、議会提議し、帝これに承認を与へるといふ場合もあつた。議案通過の際は、宰相これをラテン文に綴り、出席議員これに署名した。署名をえた原本は、宮中文書課(armarium capella)に保管された。
ロ 公布の方法には種々あつた。或は帝国議会に出席した有力者が謄本を故国にもち帰り、教会その他集会の場所において公衆に読み聴かせた。或は宰相から地方有力者に謄本を送附し、有力者をしてこれを公衆に読み聴かせた。巡察使(missi)が巡察の途上、適宜の方法で披露した場合もあつた。
四 勅令の種類
イ 勅令は神事勅令(capitula ecclesiastica)と俗事勅令(capitula mundana)とに分れた。神事勅令とは教会の組織・財産・僧侶の特権等を規定したものをいひ、1)俗事勅令とはその他一切の事項を規定したものをいつた。軍備・財政・教育・行政等の公事に関したのもあり、身分・財産等の私事に関したものもあり、刑事に関したものもあり、訴訟に関したものもあつた。公・私・聖いづれの事項をも、勅令は規定しえたのである。
1) 神事勅令は多くの場合、法王の命令又は宗教会議の決議の単なる反覆を出なかつた。恐らくこれらを承認するの意味において、カァルは、これらとその内容を一にする勅令を発したのであらう。
ロ 勅令はまた附加勅令(capitula legibus addenda)と独立勅令(capitula per se scribenda)とに分れた。
附加勅令とは特定の部族法を補足改正する目的で発しられた勅令をいふ。一個の部族法を改正する目的で発しられた場合、例へばLex SaxonumとかLex LonbardorumとかLex Ribuariaとかを改正する目的で発しられた場合と、数個の特定の部族法を一時に改正する目的で発しられた場合とあつた。いづれにせよ附加勅令は部族法そのものとなり、部族法と同一性質をとつたのである。従つて属人的に当該部民に適用あつたに過ぎなかつた。
附加勅令は部族法そのものとなつたのであるから、部民は部族法の制定に参与しうるごとく、附加勅令の制定にも参与しうべき筈であつた。換言すれば附加勅令の制定は、帝国議会の協賛をうるだけで足らず、当該部族の民会の協賛をもえねばならぬ筈だつたが、大抵の場合、これをえずに制定された。けだし帝国議会に出席した地方有力者を直ちに部族の代表者と見、すでに代表者の同意をえた以上、重ねて民会の同意を求むるの要なしと見たからであつたであらう。1)
1) 附加勅令は部族法補正のために出ただけで、当時同じく行はれてゐたロォマ法補正のためには出なかつた。ロォマ法は、改正の彼岸に絶対的優越を保つと見られてゐたのである。
ハ 独立勅令とは部族の立法事項に亘らず、皇帝固有の立法事項につき、皇帝の発した勅令である。具体的にいへば、官吏の地位・権限・貨幣・交通・税関・軍備・公共の安寧秩序等につき皇帝の発した勅令である。もとより皇帝の大権に基いたから、皇帝はこれを発するにつき部族民会の同意をうるの必要がなかつた。帝国議会の協賛は通常これを求めたが、これとても求める必要あつての事ではなかつた。一旦制定したものを廃止変更することも、皇帝の随意だつた。1)
独立勅令は属地的効力を有し、領内の者全部を一様に拘束した。
1) 当時の国法は、皇帝の立法事項をハッキリと限界づけてゐなかつた。どれだけの範囲で勅令権を揮ひうるやは、法によつて決せず、むしろ事実上の力によつて決定した観があつた(Schröder-Künssberg, deutsch. Rechtg. S. 283)。
ニ 皇帝はまた地方巡察の途の上らうとする巡察使(missi)に、勅令の形式で巡察心得を訓示したが、これを巡察勅令(capitula missorum)といふ。皇帝の独裁に出たこともあり、帝国議会の協賛をえて発しられたこともあつた。内容は多くは、視察の要点を指示したに止まつたが、元来巡察使は、視察官であると同時に伝達者であり、帝の命令を地方へ伝達する役目をも果したから、伝達事項として巡察勅令の中へ、直接に地方民を拘束するところの法規を含ませたことも稀でなかつた。
五 主もな勅令
イ カァルおよびその子孫の発した命令は総数百五六十個にも及んだらしいが、その中主もなものを示すと——
(一) 八〇二年五月、カァルは皇帝となつてからの最初の帝国議会を、Aix-la-Chapelleに召集し、集れる代表的有力者をして忠誠を誓はせ、四十の節に分れる一大勅令に同意させた。その内容は、帝命に服従の義務、宣誓違反の罪、私闘の禁、近親相姦の禁、外国人の帰化等々、頗る多岐だつた。ロ カァルの子Ludwig I (814--840)も多数の勅令を発布した。彼が八一七年Aix-la-Chapelleに召集した帝国議会は、カァルが八〇三年に召集した議会にも比すべきもので、各部族の法を一様に補正することを目的としたところのCapitula quae legibus adde da suntをはじめとなし、多くの勅令を可決したのである。八一九年にはLex Salicaを補正するCapitula Salicae legis a. 819を出した。
同会議はさらに、二個の巡察勅令の発布に協賛した。一をcapitula missorum per missaticum Parisiense et Rodomenseとし、二をcapitula missorum per missaticum Senonenseとする。
(二) 同年十月再びAix-la-Chapelleに会議を催し、例の法典編纂令を可決させた。諸部族の慣習が一斉に成文になつたのは、十月勅令の結果であつた。
(三) 八〇三年には、部族法の補正を目的とする多くの附加勅令が出た。例へばLex Salicaの補正を目的としたCapitula quae in lege Salica mittenda sunt---Lex Ribuariaの補正を目的としたCapitula quae in lege Ribuaria mittenda sunt---Lex Baiuwariorumの補正を目的としたCapitula addita ad legem Baioariam等のごとし。
同年また巡察使の質疑に答へた巡察勅令Capitula misso cuidam data a. 803が出た。
(四) その他カァルは八〇七年にCapitulare Aquense a. 807を、八一一年にCapitulare de exercitu promovendoを出した。共に軍備に関する。八一二年にはCapitulare AquisgranenseをおよびCapitulare de villis vel curtis imperialibusを出した。前者は裁判組織に関し、後者は行政組織に関した。
ハ Ludwig Iの子Lothar I (843--855), Karl II (843--877)もそれぞれ勅令を発布した。八六四年にKarl IIの出したEdictum Pistenseは、三十八節より成る長文のもので、西フランク王国の国法および刑法の根幹となつた。
六 勅令集
イ カァルもその子Ludwigも、公の勅令集は作らなかつた。で、『カァルおよびLudwigの勅令を、堙滅から救ふために』、Abt Ansegis von Fontanellaなる者、『彼の探しうるかぎりの勅令』を輯集し、八二七年に、Liber legiloquusと題する勅令集を公にした。もと彼はフランク名門の出で、帝室と近い関係にあつたから、宮中文書課に蔵されてゐる勅令原文を見る機会があつたのである。四巻と三つの附録とから成る。1)第一巻および附録一にカァルの神事勅令を、第二巻にLudwigの神事勅令を、第三巻および附録二にカァルの俗事勅令を、第四巻および附録三にLudwigの俗事勅令を、いづれも年代順にならべてゐる。勅令の総数二十九に過ぎなかつたが、原文の忠実な複写であつたため、忽ち官の信用を博し、Ludwigのごとき、早くも編纂の翌年——八二八年——に、父カァルの勅令および自分自身の既発の勅令を、Ansegisの集から引用した。
1) Ausg.: Boretius in den Mon. Germ. Leg. II. 1.
ロ 前示Ansegisの集に、Benedictus Levitaなる者の加へたといふ追録がある。1) Ansegisの四巻三附録へ、さらに三巻四附録を増したもので、序文には、編者Benedictus LevitaはMainz教会の執事で、大僧正OtgarからAnsegisの集に洩れた勅令を輯集すべく命じられ、同教会の書庫を漁つて、この三巻四附録に見るやうな勅令を発見するに至つた、とあるが、一人としてこの言を信ずる学者はない。なぜなればMainzで編まれたといふことその事自体すでにあやしい。九世紀のころ西フランクでこの書の大いに行はれたは事実であるが、Mainzではこの書の存在すら知つてゐなかつたらしいからである。勅令を集めたといふことも虚言である。この書の大部分——実にその四分の三まで——は、ロォマ・ゲルマンの雑法源、例へばBreviarium Alaricianum, Codex Theodosianus, posttheodotische Novellen, Lex Visigothorum, Lex Baiuwariorumなどの剽窃で、勅令ではない、たまたま勅令を引けば大抵、故意の変造を施してゐるからである。学者はこの書の内容があまりに教会に有利な点、一例を示すと、国家には僧侶を裁判するの権なしとか、国法と教会法と衝突の場合には教会法優先すとか定めてゐる点に疑ひをさし挟み、この書は教会が故意に企てた勅令の偽造(Pseudokapitularien)であると断じる。国家と教会との確執期には、両者各々その立場を有利にせんために、かかる陋事をも行つたのである。年代は八四八年から五〇年の間、西フランクにおいて作られたのであつたらうといふ。
1) Ausg.: Pertz in den Mon. Germ. Leg. II. 2---Lit.: Seckel, Studien zu Benedictus Levita I--VIII, Neues Archiv XXVI ff.---Conrat, Geschichte der Quellen u. Literatur des röm. Rechts im Mittelalter, I 299 ff.