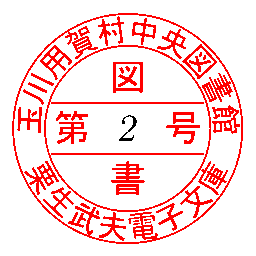
序 説
イ 十九世紀に入つてから、私法は、私益の番兵としてのその任務を、未だ十全に尽しきつてゐないことを発見した。私法の保護に洩れた私益あり、若くは私法の保護の十分ならざる私益あることを発見した。『人的利益』がそれである。
もちろん前代の法律秩序も、生命や身体・自由や名誉を、重大な法律貨物として厚く保護はしてゐたが、その方法は、私法的でなくして、刑法的乃至警察的であつた。ただ国家が、人的利益の侵害者を処罰しえただけで、被害者自信は加害者に対し、私訴を提起することをえず、不作為の請求権も損害賠償の請求権もなかつた。況んや精神苦に対する慰藉料などは認められてゐなかつた。
ロ 十九世紀は、私人が私益に眼ざめた時代である。自利の主張に鋭敏になり、銭勘定に正確になつた時代である。利益は洩らさず拾つて一々法の保護を求め、損害は隈なく数へてそれぞれ賠償を求めるに至つた。そこで初めて、私益にして未だ私法の保護なき人的利益なるものあることを発見し、有形財の侵害に対して損害賠償あるごとく、人的利益の侵害に対しても、また救済なかるべからずと叫ぶに至つた——
最初の叫びは、あの利益法学の創設者であり・新富者の巧妙な代弁人であつたRudolf v. Jheringから上げられた。いはく——『有形財のみが法律保護の対象であらうか?無形の精神的貨物が無視されていいであらうか?従来の裁判官は、財布の利益(Interesse des Geldsbeutels)のみを保護してきた。一歩財布を離れると、法律保護からも離れるごとく考へてきた』1)と。彼は利益の地平線を大いに広げて、無形利益をも含ましめ、一切の私益を、私法的保護の光りに浴せしめんことを期したのである。
1) Jhering, Ein Rechtsgutachten, in seinen Jahrb. 18, SS. 44, 49.
ハ 質実な法源探求者Brunsさへ、同時代の人々が、精神的利益の侵害を不法行為と見てゐないことに、不平をもつた。いはく——『有形財は手段に過ぎない、享楽のための手段に過ぎない。手段の破壊だけが不法行為で、目的の破壊、すなはち享楽自体に対する直接侵害が、どうして不法行為でないのであらうか』1)と。Gust. Lehmann, 2) Pfaff, Strohal, 3) Gierke, 4)らも、それぞれの立場から、人的利益の保護されざるべからざることを痛論した。
1) Bei Holtzendorff's Encyklopädie d. Rechtsw. 3. Aufl. (1877), S. 410.
2) Gust. Lehmann, Die Schutzlosigkeit d. immateriellen Lebensgüter.
3) Zit. bei G. Lehmann, S. 41 f.
4) Gierke, Deutsches Privatr. I. 702 ff.
ニ 立法においては、プロイセン州法・ザクセン民法・オォストリア民法等、多かれ少なかれ、この問題に留意した。ドイツ民法・スイス民法に至つて、ほぼ完全な保護方法の樹立となつた。ドイツ普通法の判例とフランスの判例とが、人的利益保護の拡大史に功献したことは非常であつた。
ホ 本書は、我慾の防禦を任務と考へた十九世紀の私法学が、いかなる人的利益をいかに保護しつつ以て今日に至れるを叙することを以て任とする。
第一節 生命の私法的保護
一 序 説
生命侵害の場合は、他の人的利益侵害の場合と異り、被害者自身の救済でなくして、遺族の救済が問題となる。いま他人に近親を殺されて扶養者を失つた遺族を救済するために、立法者の講じ来つた手段の変遷を見んに——
二 生命侵害
イ 私法上の生命侵害の意味は、刑法上の殺人の意味よりもずつと広くなければならない、さうしないと遺族の救済を受けうる場合、あまりに狭ばまるといふことは、中世の立法家もすでに充分に気づいたところであつた。十四・五世紀頃の法源は、(一)生命侵害の概念中に、殺害ばかりでなく傷害致死(Körperverletzung mit tötlichen Ausgang)をも含ませてゐた。傷害と死亡との間に時間の間隔あるも、二つが因果の関係に立つかぎり、損害賠償を求めるに差支なしとしてゐた。1)また(二)作為による殺害ばかりでなく、義務違反の不作為による致死をも含ませ、例へば道路の管理者が修繕を怠つたため車顛覆し、人負傷し、死を招いたといふ場合に、管理者を生命侵害者と見、これに賠償義務を負はせてゐた。2)
1) 中世法といへども、行為の結果にあらざる損害に対してまで賠償義務を命じやうとはしてゐなかつた(Hammer, Die Lehre von Schadenersatze nach dem Sachsenspiegel und verwandten Rechtsquellen, S. 57 ff.)。
2) ロォマ法は、加害者の作為による加害のみを見、不作為による場合を看過してゐたが(Windscheid, Pand. 6. Aufl. S. 973. 末川・不法行為の成立要件として観た権利侵害・法学論叢・一五ノ一・七四)、ドイツ固有法は、古くから不作為による加害を認めてゐたのである(Schwäbisches Weisthum v. 1307 bei Grimm, Weisth. I, S. 340)。
ロ 近世法においても私法上の生命侵害の意味は刑法上の殺人よりも広く、凡そ死を招く一切の不法行為をさうよぶのである。傷害致死や義務違反の不作為による殺害をも含むのである。1)
1) 一例をドイツの判例にとると——ある夜、原告の夫は、ある橋を渡つたが、橋の袂に立つ街燈の光すでに消えて暗く、且つ橋の欄干あまりに低くかつたため、踏みはづして川に落ちた。川からは救助されたが、墜落の際負ふた傷のため、二日目に死んだ。寡婦は橋の管理者たる村を相手取り、損害賠償の訴を起した。被告が管理義務に違反して欄干を適当の高さにしなかつたため、夫の死をひき起し、扶養請求権を失うに至つたといふのである。
これに対し被告はいつた——『橋は警察の許可をえた設計にかかる。且つ附近一帯の同種の橋に比し、特に欄干が低いともいへぬ。よく通常の高さを保つてゐる。街燈は毎夜十時に消すが、これは十時以後の通行者稀なるがためである。故に十時以後の通行者は、自ら照明を用意しなければならぬ。自ら用意を怠り落ちて死んでも、管理者に責任のあらう筈がない』と。
しかし帝国裁判所はいふ、『警察の許可があつた場合にも、橋の管理人は、善良なる管理者の注意を以て、交通の安全を図らねばならぬ。欄干の高さは附近一帯普通であるといふが、それはたまたま、すべての橋につき管理義務の違反ありしことを暴露しただけで、低い欄干を正当化するに足らない。十時以後は街路全部消燈するといふが、特に危険な橋の附近は、照明しておく必要がある。充分な欄干と、適当な照明と(zureichende Abschrank und gehörige Beleuchtung)を怠つたことは、何といつても管理義務違反の不作為であり、管理者はこれから生じた結果に対し賠償責任を負はねばならぬ』と(v. 18/5 1903, Entsch. d. Reichsg. 55, Nr. 7)。
三 遺族救済
イ さて右様の意味の生命侵害あつた場合、遺族は加害者に対し、何を理由に損害賠償を請求しえたかといふに、中世の法律は、近親被殺そのものを理由に、法律所定の身ノ代金(Wergeld)を、加害者に請求できるとしてゐた。すなはち当時の法律は、自由人の生命は金いくら、女子や小児はそれより幾何安いといふ風に、地位・性・年齢に従つて人の生命を金銭に評価し、ある人が殺されると、遺族は死者の法定生命価、すなはち身ノ代金を当然請求できる仕組にしてゐたのであつた。1)請求権者自身、損害を受けたかどうか問題でない。近親さへ殺されれば、遺族は自身少しも損害を受けてゐなくても、死者の身ノ代金額を加害者に請求できたのであつた。
1) Hammer, a. a. O. S. 104
ロ 近世法の個人主義は、近親被殺そのものを理由とする損害賠償請求権を認めず、遺族自身の被害を理由とする損害賠償請求権のみを認める。すなはち(一)近世法は、妻とか子とか各遺族が、賠償を請求しうるだけで、全遺族は、その名において請求することをえないとする。(二)各遺族も、その資格において当然に賠償を請求することはできず、扶養請求権を失つたとか、扶養期待権を失つたとか、労務請求権を失つたとかいふことを理由としてのみ、賠償を請求しうとする。換言すれば親族としてではなしに、扶養請求権者として、労務請求権者として、その他の権利の主体として賠償請求をなしうるに止まるとする。その結果、従来漠然たりし親族間の法律関係が、明細に分別されるに至つた。もと死者に対して有つてゐた・あらゆる権利を数へ尽し、あれも侵害された・これも失はれたとして、一々賠償を求めるに至つた。重もな権利についてのべると——
四 扶養請求権者の賠償請求
近世法は、親族関係の疎密に応じて扶養請求権の取得要件を定め、関係の密な者ほど扶養請求権を取得し易く、疎な者ほど取得し難い仕組にしてゐるので、そが当然の結果として、親族関係の密な者ほど、扶養請求権の侵害を理由に損害賠償を請求し易く、疎な者ほど、これを理由に損害賠償を請求し難い。妻が一番有利、未婚又は未成年の子これにつぎ、夫さらにこれにつぎ、その他の親族が一番不利といふことになつてゐる——
イ 妻は妻たる地位に基き、夫に対し当然扶養請求権を取得する、と見られてゐる。1)妻自身充分財産を有する場合にも、夫に対し扶養を求めうと見られてゐる。その結果、夫被殺の場合には、常に妻の扶養請求権の侵害あり、妻は必ず加害者にその賠償を求めうるのである。2)
1) 判例にいはく——『夫婦間の財産関係が一般共産制(allgemeine Gütergemeinschaft)によつて律しられてゐる場合には、妻の扶養料は、夫の特有財産からせず、夫婦共同の財産から支出される。而して共同財は、夫婦1/2づつの割合にて共有すと解すべきが故に、一般共産制の場合、妻は実は、扶養料の単に1/2を夫から受けをるに過ぎず、他の1/2は妻自身の支出にかかる。従つてこの場合、夫殺されたときは、妻は扶養料の1/2だけ侵害を受けたとして、加害者に賠償を求めうるのみにて、その全額に対する賠償を求めることをえない』(v. 6/7. 1908, Entsch. d. Reichsg. 69. Nr. 65)。
2) 妻の生活費は二種に分れる。一は妻がその婚姻法上の義務を履行するために必要とする費用——例へば彼女は夫と居住および地位を共同にせねばならぬが、そのために必要となる費用。二は単独にてもなほ要するであらうところの費用——例へば衣食費疾病治療費。共に夫の負担だが、法律は前者を婚姻費用の負担(日民七八九条)、後者を扶養(日民七九〇条)といふ。妻は夫を殺された場合、扶養請求権の喪失については賠償請求をなしうるが、婚姻費用負担者の喪失については、賠償請求をなすことができない。なぜならば夫の死と共に婚姻は解消し、婚姻費用を要せざるに至るから。
ロ 未婚又は未成年の子は、いはゆる元本維持の権(Recht, den Bestand der Adventitien unvermindert zu erhalten)を有し、果実と労賃とある場合は、これによつて自活せねばならぬが、それで足りぬ場合は、あへて元本に喰ひ込むの要なく、不足部分を親の支給に待つことができるとされてゐる。1)換言すれば、元本あるも果実なく労賃なき場合は、親に対し扶養請求権を取得すると見られてゐる。従つて親被殺の場合、未婚又は未成年の子にとつては、元本の有無は問題とならない。果実又は労賃さへなければ、扶養請求権の侵害を受けたとして、その賠償を加害者に求めることができるのである。
もちろん親の死と子の扶養喪失と、時間的に接着してゐる必要はない。二者の間に相当因果の関係ある以上、時間的間隔は大でも(むろん時効期間を越えてはならないが)、損害賠償を求めるに差支ないのである。親の死後数年にして、果実および労賃では食へぬことになり、親だに平均命数を保たば扶養を受けえたらうといふ場合には、やはり加害者に扶養請求権侵害の賠償を求めることができるのである。訴提起の際『親あらば扶養を受けえたらうに』の関係ありさへすれば足りるのである。2)
1) Preuss. Ldr. II, 2 §§65, 161 ff. 204, 287---Sächs. GB. §§1845, 1826---Österr. GB. §§139, 141, 220, 221---Code Civil Art. 203, 384, 385. 判例もいふ——『子がその財産の果実又は労賃を以て、その生活費と教育費とを支弁しうる間、父は何ら支出の要なし。しかし父は、子の特有財産の元本を滅ぜずに保持する義務(Pflicht, den Bestand der Adventitien unvermindert zu erhalten)があるから、子がその果実又は労賃で支弁しえぬ場合は、父は子の元本を処分せず、父自身の財産から支出せねばならぬ』(Erk. Cassel 18/6 1857 Seuffert's Archiv XII, Nr. 169)。
2) 判例にいはく——『扶養請求権は死者の生前すでに発生してゐたことを要せず、訴提起の際、「死者あらば扶養を受けえたらうに」の関係あれば足りる』(v. 21/6 1894, Entsch. d. Reichsg. 33, Nr. 65)。
ハ 夫は、果実や労賃を失つてしまつたといふだけでなく、元本さへも失つてしまふに及んで、初めて妻に対し、扶養請求をなすことができる1)。故にまだ財産を有し労働能力をもつ夫は、妻が殺されても、直ちには損害賠償請求をなすことができない。後日財産および労働能力を失ふに至るを待つて、これを請求する外ないのである。
1) Preuss. Ldr. II. l. 262---Bayr. Ldr. I. 6. 12---Sächs. GB. §1637---Oldenburg, G. v. 24/4 1873 Art. 33 §2---Erk. Darmstadt 2/11 1872 Seuffert's Archiv 27, Nr. 267---Buengner, Zur Theorie u. Praxis d. Alimentationspflicht, 176.
ニ 自余の扶養親族1) (alimentationsberechtigte Verwandten)が扶養請求権を取得するためには、受ける者の困窮と与へる者の余裕とを前提とせねばならない。受ける者に果実も元本も労働能力もなきこと。与へる者に、他人に対する義務を履行し、地位相当の生活を保ち、しかもなほ余裕あることを、前提とせねばならない。故に成年の子が、親を殺された場合には、親の生前すでに窮乏し、しかも親に救助の余裕あつたときにかぎり、直ちに損害賠償請求をなすことをうるのであつて、然らざれば後日窮乏におち入り、『親だにあらば、扶養を受けえたらうに』の関係生じるのを待つて賠償請求をなす外ないのである。2) 3)
1) 尊属卑属は、親等の数を問はず扶養親族であり、権利者の必要と義務者の給付能力とを前提にして扶養請求権を取得した。親子といふ中には養親子を含んでゐたが、配偶者の父母は含まず、継親子も含まなかつた。兄弟姉妹を扶養親族とした例は、極めて稀だつた(Roth, Deutsch. Privatr. II, S. 321 f.)。
2) 判例にいはく——『遺族が損害賠償の訴を起した場合には、生前すでに死者と遺族との間に扶養の必要と余裕と、ありしや否やを問題とすべきでない。むしろ訴提起の際遺族にその必要ありや?また死者の取得能力より考へ、彼もしあらば扶養を与へえしや?を見るべきである』(v. 21/6 1894, Entsch. d. Reichsg. 33, Nr. 65)。
3) 判例にいはく——『死者の扶養能力を判断するには、死亡の時のみを絶対の標準とせず、むしろ訴提起の時を標準にし、彼もしこの時にあらば幾何の余裕あつたらうかを判断することを要する。死亡の当時僅少の日給しかえてゐなかつたにせよ、後に増俸されてゐたらう場合には、後のものを標準とし、扶養能力の有無および程度を判断すべし』(v. 21/6 1891, Entsch. d. Reichsg. 65)。
ホ 加害者の行為により扶養者を失つたが、死者に代つて遺族を扶養すべき次順位の義務者なほ存すといふ場合にはどうなるか?遺族はなほ扶養請求権の侵害を受けたとして加害者に賠償を求めうるか?一派の学者は、次順位の扶養者ある場合には、遺族は何ら損害を被らず、従つて損害賠償請求権なし、加害者に賠償を求めうるは、遺族にあらずして次順位の扶養義務者その人ならざるべからずと説いたが1)、耳をこの説に傾けた者はなかつた。判例および通説は、次順位者ある場合には、遺族は加害者に賠償を求め、得たる賠償金によりまづ自活すべし、これにより自活しえざるに及んで初めて助けを次順位者に求むべしと見てきた。ドイツ民法も、次順位者の扶養負担に先ち、遺族をして加害者に賠償を求め、一まづこれにより自活せしむべしとの主義を採用した。2)
1) Eger, Reichshaftpflichtgesetz 1876, S. 280 ff.
2) Motive, II. S. 782——わが大審院は、次順位の扶養義務者ある場合には、遺族は損害賠償請求権を取得せずと見てゐる(大審・大正三・一〇・二九、民録八三四)。
五 扶養期待権者の賠償請求
イ 扶養親族が扶養請求権を取得するには、権利者の必要(Bedürftigkeit des Berechtigten)と義務者の給付能力(Leistungsfähigkeit des Verpflichteten)とを前提とすること、前述の通りだが、往々にして、一方はすでに窮乏に落ち、他方は未だ給付能力なき場合を見る。例へば貧困な親と未だ職業能力なき子との間のごとし。かかる場合もし親が、子の被殺により扶養期待権を侵害されたとして、賠償を加害者に求めることができるならば、老後の安逸を期してゐた親の期待を保護する上に、ほぼ遺憾ないであらう。一九〇二年、錠前屋の徒弟をしてゐた十五歳になる原告の子は、親方の過失で、鉄棒に頭を打たれて死んだ。母は洗濯女にして生活すでに困難、子が一人前の錠前職としてうべき一週二十一マァクの約2/3を、扶養料として給せらるべきの日を待ちかまへてゐたのであつたが、今この希望を失つたので、親方にその賠償を請求した。一審および控訴審は、子には未だ給付能力なかりしが故に母は未だ扶養請求権を取得せざりし、従つて賠償を求めることをえずと判決したが、上告裁判所は、子の死亡当時未だ扶養請求権を取得してゐなくても、後にこれを取得すべき可能存する以上、親は扶養期待権の侵害を理由とする損害賠償請求をなすことができるとし、原告の請求を認めた。1)この時以来扶養期待権の侵害が、損害賠償請求の理由となるに至つたのである。
1) Oberst. LG. f. Bayern v. 9/4 1902, Seuffert's Archiv 57, Nr. 218.
ロ しかしながら親の扶養期待権は、子が将来その扶養義務を履行するであらうといふ相当の可能存する場合にのみ成立すべきであるから、極めて幼少な子が殺されたやうな場合には、親は扶養期待権の侵害を云為することができないと見られてゐる。スイスの判例は、十三歳の子を失つた親に、扶養期待権の侵害を理由とする損害賠償請求を認めた。1)十歳の子を失つた親にもこれを認めた。2)しかし三歳半の子を失つた親にはこれを拒んだ。3)
1) Entsch. d. schweiz. Bundesg. 17. S. 641 f.
2) Entsch. d. schweiz. Bundesg. 33. 2. Abt. S. 88.
3) Bundesg. in Revue jud., 1896, S. 191 f.
六 契約上の扶養請求権者の賠償請求
多くの立法は、法律の規定に基き死者に対し扶養請求権をもつところの遺族にのみ、損害賠償請求権を与へ、契約上の扶養請求権にまでこれを認めることを躊躇してきたが、1)スイス法のごときは、夙に契約上の扶養請求権者にこれを認めた。契約上の扶養請求権者もやはり被害者であり、賠償請求を拒まるべき理由がないといふのである。2)
1) Österr. GB. §1327---Preuss. I. 6, §109---BGB. 844.
2) Schweizes Haftpflichtgesetz, Bundes G. 1/7 1875 (in Goldschmidt's Zeitschr. XXI, S. 206 ff.) Art. 5---Obl. R. Art. 45 (52)は、扶養者(Versorger)を失つた者は、加害者に賠償を求めやうとしてゐるが、そのいはゆる扶養者の中に、契約上の扶養者をも含めてゐるのである(Egger=Oser, Komm. zu Art. 45)。
七 労務請求権者の賠償請求
親は子に、夫は妻に、慣習上正当と見られる程度の労務を求めることができる。これを親族法上の労務請求権といふ。しかし普通法の判例は、労務請求権の喪失は賠償請求の理由とならずとし、例へば夫に労務を供し来つた妻が殺されても、夫は、労務請求権の喪失を理由としては損害賠償を求めるわけに行かぬと見てきた。1)ドイツ民法以来労務請求権の喪失を理由とする損害賠償請求権認められる。2)
1) これを普通法の判例に見るに——一八七一年、小車を引いて田舎道を行つた原告の妻は、被告の大車に轢かれて死んだ。原告は、彼の取得ににとり重要であつた死者の労務提供(die für seinen Erwerb wichtige Dienstleistungen der Getödteten)を失つたことを理由にして、その賠償を被告に求めたが、裁判所は、『新しき判例は、遺族が、法律上彼が死者に期待しえし扶養の代償を、加害者に求めることを可能にしてゐる。しかし労務の代償を求めうとはしてゐない。原告の請求は、立法史の未だ踏み越えてゐない限界の彼岸に立つ』といつて、原告の請求を棄却した(Erk. d. OG. zu Wolfenbütel v. 23/2 1875, Seuffert's Archiv 31, Nr. 36)。
2) BGB. 845.
八 相続分減少に基く相続人の賠償請求
さすがに被相続人の被殺によつて相続人の相続権が侵害さると見た立法はなかつた。けだし相続人は、加害者によつて相続権を奪はれるにあらず、遺産の実質を減少されるにもあらず、単に、より大きい遺産を取得しうる可能性を失はしめられるに過ぎないのであるが、この可能性たる、事実上のもので、不可侵を第三者に請求しうる底のものでないからである。1)
1) Vgl. Motive, II. S. 776 f.
九 相続に基く相続人の賠償請求
死者自身が、より大いなる遺産をのこす可能性を失つたといふことを理由にして、加害者に対し一旦損害賠償請求権を取得し、直ちにこれを相続人に相続さすと見ることが可能であらうか?換言すれば相続人は、加害者に対し原始的に損害賠償請求権を取得することはできないが、相続によつて伝来的にこれを取得すと見ることが可能であらうか?余の寡聞なる、いまだかかる法理によつた立法をも知らぬのである。中世においても、その後においても、より大いなる遺産をのこす可能性を失つたことを理由とする賠償請求権を、死者自身に与へた例はないやうにおもふのである。
ただ一つドイツ民法の第一草案は、被相続人の失つた利益を二つに分けた。1)一は被相続人が生存さへつづけるなら失はれずにすんだらうところの利益。二は被相続人が生存をつづけてもなほ失つたかも知れない利益。後者の喪失は生命侵害と必ずしも因果の関係に立たないから、その責を加害者に帰するわけに行かないが、前者の喪失は生命侵害と相当因果の関係に立つゆゑ、これを加害者の責に帰すべし。かの相続権・終身定期金債権のごときは、生存だに前提とすれば当然取得し若くは当然存続したらうところのもので、被相続人がこれらを失ふに至つたのは、一に全くその生命を侵害された結果といふべく、従つて加害者をしてこれを賠償せしめざるべからずと考へたのである。
第二草案の委員会では、被相続人の労働収益喪失に対しても加害者これを賠償せざるべからずと唱へる者を生じた。その理由は、生存さへつづけえたなら労働をもつづけえたらうし、従つて労働収益をもつづけえたらうに、生命侵害を受けた結果、被相続人は働くことも、貯めることもできなくなつたといふのである。侵害行為と労働収益の喪失との間に、相当因果の関係があるといふのである。
しかし第二草案委員会の決議は、以上諸提案を、『不明晰な感情に基くもの』(der auf dem unklaren Gefühle beruhende Antrag)として、すべて斥けた。その理由は、終身定期金の喪失や労働収益の喪失と生命侵害との間に因果の関係がないといふのでは、もちろんない。凡そ損害賠償請求権が発生するためには客観的に損害を生じたといふだけで足らず、さらに主観的にこれを損害と感ずる者——すなはちいはゆる損害関心者(Beschädigte)——を必要とするのに、生命侵害の場合には、侵害されてしまつた刹那に、これを損害と感じる関心者消え、遂に損害賠償請求権が、その発生要件を満たさずに終るからといふにある。2)
1) Protokolle II 616 ff.
2) 加害者に不法行為の成立要件すべて具備する以上、損害関心者の有無に関せず、賠償せしめざるべからずといふ説は、不法行為そのものを悪んだ昔の思想のなごりである。それは、被害を中心とする今日の個人主義的損害賠償法理に充分徹底した学説といふことをえない。歴史はかかる学説を、『不明瞭な法律感情に基くもの』として、すでに淘汰してしまつてゐるのである。
一〇 直接損害に基く賠償請求
死者が死亡までの間に要する治療費の賠償を加害者に求めうることはいふまでもなく、而してこの請求権が死亡と同時に相続人に移ることも明かなので、相続人が治療費を加害者に請求しうるといふことに、反対する論者はさすがになかつた。1)しかし埋葬費については、普通法の判例に、『埋葬費の負担は、相続人の早晩免れざりし所なるが故に、これを以て加害者の行為に出でたる損害なりとなすことをえず。従つて相続人は被相続人の埋葬費を加害者に請求することをうべからず』といふのがあるが、2)これは異例で、通常は、死体検査料・死体運送料・埋葬料等を、加害者の負担としてきたのである。3)現代法上また然り。4)
1) Preuss. Ldr. I, 6, §98---Sächs. GB. §1491---Reichschaftpflichtgesetz §3---Schweiz. Haftpflichtgesetz, Art. 5.
2) Seuffert's Archiv 15 Nr. 225.
3) Gruchot, IV, S. 171---Förster-Eccius, Preuss. Privatr. II. S. 479---Dernburg, Preuss. Privatr. II. S. 913.
4) BGB. §814---Schweiz. Obl. R. Art. 45.
一一 精神苦に対する慰藉料
精神苦も被害の一つである。で、遺族は近親被殺の場合、財産上の損害に対してばかりでなく、精神苦に対しても慰藉を求めうるかといふ問題を起すが、
イ 普通法は、身体侵害を受けた被害者にのみ慰藉料請求権を認め、1)近親を殺された遺族には、これを認めなかつた。ドイツ民法制定の際、精神苦に対する賠償を、もつと広く認めよとの議論が出たが、一般的にこれを認めると些細の感情苦に対してまで慰藉を請求する者が現はれるだらうといふので、特に法の認めた精神的利益の犯された場合につき、慰藉料請求を認めるだけに止めた。2)しかし特に法の認めた精神的利益といふのは、身体・健康・自由および貞操に対する精神的利益に過ぎず、3)近親の健在に対する吾人の満足の情のごときを、その一つに数へてをらぬため、つまりドイツでは、身体侵害・健康侵害・自由侵害および貞操侵害の場合には慰藉料を求めることができるが、近親被殺の場合には、財産的損害の賠償を求めうるだけで、精神苦に対する慰藉料を求めえぬのである。
1) Windscheid=Kipp, §257 Anm. 6. 地方法は普通法よりもより広く精神的利益を保護してゐた。ザクセン民法は、自由侵害を受けた者および貞操侵害を受けた者は、精神苦に対しても賠償を求めることができるとし(Sächs. GB. §1497, §1551)プロイセン州法は、貞操侵害によつて妊娠した婦女に、慰藉料請求権を認めてゐた(Preuss. Ldr. II. 1. §§1015, 1032)。
2) I. Entw. §221---II. Entw. §216---Mot. II. S. 21 ff.---BGB. 253.
3) BGB. §§847, 1300.
ロ フランスはこれに反し、同国民法一三八二条に、『いかなる行為にても凡そ他人の損害となる行為をなしたる者は、被害者に賠償せざるべからず』とあり、一三八三条に、『作為によりて生ぜしめたる損害に対してのみならず、不作為又は不注意によりて生ぜしめたる損害に対しても賠償せざるべからず』とある・その損害(dommage)の意義を広く解し、『無形損害(dommage moral)も損害なり、これに対しても賠償責任を免れず』としてきたのである。少なくとも通説はさう見てきたのである。1)判例も同一歩調をとり、或は貞操侵害者に、相手方の精神苦に対する慰藉料支払を命じ、2)或は名誉侵害者に同じ趣旨の支払を命じ、甚しきは婚姻予約にはあらざる単なる夫婦約束の・しかしあまりに勝手なる破約者に、相手方の精神苦慰藉の意味の支払を命じるといつた調子で、かなり広く精神上の利益を保護してきた。近親被殺による精神苦に対しても、もちろん慰藉料支払を命じてきたのであつて、被告に貞操を蹂躙されたために自殺した小女の親に、莫大な慰藉料を支払はしめた一八四七年十二月十日の判決のごとき、甚だ有名である。3)
1) Sourdat, traité général de la responsabilité (3 Ed) I. Nr. 2, 33 ff.---Seng, Vergütung nichtökonomischen chadens aus Delikten in Arch. f. bürg. R., 5, S. 341 ff.---Kohler, Die Ideale im Recht in Arch. f. bürg. R., 5, S. 259 ff.
2) 判例はSeng, a. a. O. S. 347 f.による。
3) ベルギイの学説判例も、仏と同じく精神苦に対する慰藉料を認める。一八八一年三月十七日の破毀院判決のごとき、鉄道事故によつて死んだ小女の父に、有形的損害の賠償として三千フラン、無形的損害の慰藉として一万フラン、二人の兄弟にやはり無形的損害の慰藉として千フランづつを認めた(Seng, a. a. O. S. 349)。
ハ スイスでは一八八三年一月一日旧債務法の効力発生するまでは、ドイツ系区域は独法主義をとつて遺族の慰藉料請求を認めず、フランス系地方は仏法主義をとつてこれを認めてゐたが、1)旧債務法以来、『裁判官は特別の事情、ことに被告の故意又は重過失を考慮し、有形損害の賠償の外、適当なる金額を慰藉料として原告に支払はしめることをうる』に至つた。換言すれば、仏法主義によつて統一を見ることになつた。2)
1) Seng, a. a. O. S. 350.
2) Schweiz Obl. 54 (47).
一二 要約
個人主義的思想の充溢と共に、損害賠償請求権も同じ主義の上に立つことになつたのである。他人が損害を被つても自分が賠償を求めるわけに行かない、自分の請求は自分の被害を理由としなければならない、といふことになつたのである。
近親もまた他人である。故に近親その人の被害を理由となすわけには行かない、被殺はなるほど近親その人にとつて絶大の損害であらうが、彼以外の者、すなはち遺族にとつて必ずしも損害でない、近親の死によつて遺族が扶養請求権を失つたとか、労務請求権を失つたとかいふときに、初めてそれが遺族自身の損害となる、他の損害賠償請求権者と同じやうに、遺族も彼自身の損害を理由として賠償請求をなさねばならぬ、といふことになつたのでる。
最も大きい遺族自身の損害は、もちろん扶養請求権の喪失であつたから、それを理由とする賠償請求が、遺族請求の第一であつた。十九世紀末までの遺族請求は、殆ど扶養請求権の侵害を理由とする請求に尽きてゐたといつていい。が、その後、『遺族損害』の分析精緻となり、扶養請求権の侵害を理由とする損害賠償請求権の外に、契約上の扶養請求権の侵害を理由とするもの、扶養期待権の侵害を理由とするもの、労務請求権の侵害を理由とするもの、直接損害を理由とするもの、精神苦を理由とするもの等々、各種の損害、各別の件名で救済を受けるに至つた。扶養請求権の侵害を理由とする賠償請求権それ自身も、妻が請求する場合、未成年又は未婚の子が請求する場合、夫が請求する場合、自余の扶養親族が請求する場合といふ風に、一々区別されてきた。
おもふに中世の身ノ代金制度は、扶養請求権の喪失を理由とする損害賠償請求権はもちろん、その他諸種の損害賠償請求権を漠然包蔵した観念であつたといつてよからう。爾後の史的発展が、この漠然たる観念を各種独立の損害賠償請求権に分解してしまつたのである。
第二節 身体の私法的保護
一 序 説
中世法は、身体侵害を受けた者は、贖罪金(Busse)として身ノ代金の幾割かを加害者に請求できることにしてゐた。1)ロォマ法は、身体侵害を受けた者は、治療費の支出・労賃の喪失・獲得能力の減退に対する賠償を、加害者に求めることができると、明瞭に規定してゐたので、2)同法の継受は、身体侵害に対する賠償の制度を、発達させるに与つて力があつた。ことに十九世紀における普通法の判例および学説が、この法制を明細に発展させた——
1) Schröder=v. Künssburg, Lehrb. d. deutsch. Rechtsg. S. 376.
2) D. 9, 1, 3; D. 9, 4, 7
二 身体侵害
イ 身体侵害の意味は古くから、ずいぶん広く、(一)疫痛を伴はざる身体組織の破壊、例へば頭髪切断(Zopfabschneiden)のごときを含み、(二)身体組織を破壊せざる横打(Schläge)のごときをも含んでゐた。1)(三)義務違反の不作為からも身体侵害を生ず、例へば道路の管理人が修繕を怠つたため、人ころび、負傷したとすると、管理人が、身体侵害者だとしてゐた。2)
1) Sachensp. II, 65: Schilt aber ein Mann ein Kind, oder räuffet er es bey den Haaren, oder schlägt es mit einer Gerten und seine Missethat, ......
2) Schwäbisches Weisthum v. 1397 bei Grimm, Weisth. I, S. 340
ロ 現代の判例中から、義務違反の不作為に基く身体侵害の場合を例示すると(一)鉄道踏切番が踏切を鎖ざすことを怠つたため、通行者汽車に触れて負傷したとか、(二)家の所有者が階段に燈火をともすことを怠つたため、上層の居住人へ郵便物を運ぶ配達夫が、落ちて脚を折つたとか、(三)電燈会社が、現代の技術上可能なるにかかはらず漏電防止の施設を怠り、ために発火して人を負傷させたとか、1) (四)医師が手術後適当の時に繃帯を除去することを怠つたため、傷口を化膿させた2)とかいふの類。
1) Entsch. d. schweiz. Bundesg. 27, 2. Abt., S. 494.
2) Entsch. d. schweiz. Bundesg. 18, S. 341; 30, 2. Abt., S. 308.
ハ 医師の手術が、患者又はその法定代理人の同意を以てした場合はもちろん、これを以てせずになした場合にも、なほ違法性を欠き、身体侵害とならないといふことは、何人も認めてきたが、なぜさうならないかの段になると、説明の方法区々であつた。現時の通説は、いはゆる目的説(Zwecktheorie)をとり、手術は、生命又はより重要なる体部の保全のために払はれる・より小なる犠牲にして、その目的正しきが故に、違法性を欠くと説く。従つて手術の方法、治療の目的に合せず、合するも過度なる場合は、医師の手術といへども身体侵害となり、損害賠償の原因となる。1)
1) Specker, Persönlichkeitsr. S. 277 ff.
三 賠償請求
被害者損害の額は、治療費の支出・労賃の喪失・獲得能力の減退等を見て量定される——
イ 治療費(Heilungskosten)とは、身体侵害を受けたために生じた一切の経費をいふ。医師・看護婦・義眼・義足・義歯の費用・温泉行の費用等が治療費であることはいふまでもない。足腰を折られて乳母車で行かねばならぬことになつたとすると、乳母車の代金および附添人の費用は、治療のための費用といひにくいが、身体侵害に原因する費用とはいひうるので、これを加害者に求めることができるとされてゐる。1)
1) Entsch. d. österr. oberst. Gerichtsh. in Ziv.-u.-Justizverw. 1. Nr. 14.
ロ しかし『折られた腕は、当り籤でない』(der gebrochene Arm darf nicht als Treffer erscheinen)——被害者は、治療の目的を越え、若くは生活慣習(Lebensgewohnheit)を越えたる治療方法の費用を、加害者に求めることはできぬのである。1)ゴムで足るのに金の入歯を入れ、2)安い温泉場で直しうるのに贅沢な場所へ行かうとはいへぬのである。3) 4)
1) Samml. Zivilr. Entsch. d. oberst. Gerichtsh. 10, Nr. 3817; 15, Nr. 6184; 16, Nr. 6304.
2) Beiträge zur Erläuterung d. deuschen Rechts 67, S. 570. 3) Samml. Zivilr. Entsch. d. oberst. Gerichtsh. 12, Nr. 4778. 4) 被害者は治療に要する費用を請求できる。すでに支払つてしまつたことを前提としない、支払以前治療費請求の訴を起して差支ないのである(Förster-Eccius, Preuss. Privatr. II. S. 481 Anm. 21)。
ハ 身体侵害の結果、一時業を休んだとすると、その間に取得しうべかりし労賃を、『失つた取得』(entgegangener Verdienst)として加害者に賠償させることができる。一週間休業したので一週間分の労賃を請求するといふがごとし。取得の可能を失はしめられたとすると、事物通常の進行に従へば期待しえし利益を、『将来失ふ取得』(künftig entgehende Verdienst)として加害者に賠償させることができる。廃人にされてしまつた場合に、然らざれば取得しえやうところの年収を、請求するごとし。1)また身体侵害のため職業変更を余儀なくされた場合には、新職業に対する準備費を加害者に求めることができる。足を折られた場合、坐業習得の費用を請求するごとし。取得能力を回復すれば、その範囲において、賠償請求権を失ふ。2)
1) 精確にいふと、訴訟終了までの間にすでに消えた部分が、『失つた取得』。以後失はるべき部分が、『将来失ふ取得』(Ehrenzweig, System. d. allg. österr. Privatr. II. 1, S. 628 Anm. 149)。
2) プロシヤ州法は、過失に比例して賠償程度を階段づけてゐた。——(一)軽い被害の場合には治療費を請求しうるのみで、喪失利益の賠償を求めることをえない、(二)重い被害の場合には、(イ)『失つた取得』に対しても賠償を請求することができ、(ロ)特に故意重過失に基くときは、『将来失ふ取得』に対しても賠償を求めることができると(Preuss. Ldr. I, 6 §§111 ff.)。
ニ 前示のごとく、労働者が労賃を失つた場合には、労賃全部を加害者に賠償させることができるが、営業主が営業利益を失つた場合はどうか?やはり失へる利益の全部を加害者に賠償させることができるか?だとすると、富豪安田某が身体侵害を受けて廃人となつた際、加害者は、安田自ら財産を運転せば収得しえやう年一千万円の利益喪失を安田に、賠償せねばならぬこととならうが、この大結果を避けるために、現時の学説判例は、財産収益と労働収益とを峻別し、後者の喪失に対してのみ賠償を命じてゐるのである。けだし富豪が財産を運転するのは、財産管理の労働をなすのである。身体侵害のため彼が失ふのは、この労働力であつて財産そのものではないのである——財産そのものは厳存する——故に、加害者は管理労働力の喪失に対してのみ賠償すれば足る。富豪自身と同様に財産を運転しうる財産管理人を傭入れる費用を、賠償すれば足る。安田某と同様に財産運転の能力ありと見られる結城某を傭入れる費用を賠償すれば足ると見てゐるのである。1)
1) 『従前同様の収益をあげるために堪能且つ有経験の財産管理人(tüchtiger u. erfahrener Wirtschaftsinspektor)を傭入れる費用』——それが廃人にされた営業主の真に被つた損害である(Vgl. Entsch. d. Reichsg. 69, S. 294)。
ホ 未婚の女子が身体侵害のため容姿を醜くされ、地位相当の婚姻をなす見込減少した場合に1)は、裁判官の適当と認める額を加害者から受けることができた。2)あまりに高齢の婦人は受けえなかつたが、若い婦人は、初めから醜くかつた場合にも、なほ婚姻見込の減少(Verminderung der Heiratsaussicht)を理由に、賠償を請求することができた。3) 4)
1) 容姿を醜くされたため財産損害を受けた場合、例へば俳優がために失職したといふやうな場合には、男女を問はず、一般原則に従ひ、損害賠償を求めることができた(Preuss. Ldr. I, 6 §128---Österr. GB. §1326---Zürich. GB. v. 1835, §1845---Sächs. GB. §1490)。
2) 一八二八年九月のStuttgart裁判所の判決は、婚姻見込の減少に対する賠償請求権なるものは、普通法上認むることをえずといつて排斥してゐるが、同四六年十一月のMünchen裁判所の判決は、これを普通法の法則と見てゐる(Seuffert's Archiv 1, Nr. 65)。地方法中結婚見込の減少に対する賠償請求を明記したのは、Österr. GB. §1326---Preuss. Ldr. I, 6, §§123 ff.---Sächs. GB. §1490.
3) Dernburg, Preuss. Privatr. II. S. 911, Anm. 16.
4) プロイセン州法は、結婚見込を減少された未婚の女子は、結婚すればその際父から受けえたらう利益——すなはち嫁入支度料——を、加害者をして賠償させることができる。加害者に故意又は重過失ありしときは、結婚すれば夫から受けえたらう利益——すなはち扶養料——を、加害者をして賠償させることができる、としてゐた(Preuss. Ldr. I, 6, §§123 ff.)。普通法は、過失に応じて賠償責任を階段づけることをしなかつた(Seuffert's Archiv 13, Nr. 28)。
四 慰藉料請求
イ 身体侵害を受けた者は、財産的損害に対する賠償の外に、苦痛に対する慰藉料——すなはちいはゆるSchmerzgeld——を加害者に請求することができた。1)故意侵害の場合はもちろん、過失侵害の場合にも、これを請求することができた。2)額は、苦痛の程度に従ひ、裁判官自由にこれを裁定した。大抵は賠償請求と併合して提起されたが、独立の慰藉料訴訟(Schmerzengeldklage)も可能であつた。
ロ 元来この制度はロォマ法源には見えないが、帝国法たるKarl Vの刑法典(CCC. dh. Constitutio Carolina Criminalis)二十条に、『違法に他人の身体に暴行を加へし者は、苦痛に対し賠償を与へざるべからず』とあつたので、これを根拠に、普通法として慰藉料請求の訴を認め来つたのである。3)地方法の中には、明文を以て否定したのもあり、4)明文を以て肯定したのもあつた。5)独一草は普通法の主義をとり、身体侵害を受けた者に慰藉料請求を認めた。6)フランスは前世紀半以来、判例を以てこれを認め来つた。7)
1) München (Seuffert's Archiv 31, Nr. 231 u. 232)---Jena (Seuffert 23, Nr. 31)---Oldenburg (Seuffert 1, Nr. 220; 31, 230)---Rostock (Seuffert 31, Nr. 232)---Celle (Seuffert 13, 31; 27, 30).
2) 判例にいはく——『慰藉料請求の条文的根拠たるKarl Vの刑法典第二十条は、慰藉料請求を、加害者の故意にかからしめず。故に過失による侵害の場合にもこれを求むるに妨なし』(Erk. d. Oberst. Gerichtsh. f. Bayern v. 12/11 1875 Seuffert's Archiv 31, Nr. 231)。
3) Karl Vの刑法典以前、すでに慰藉料請求を認めた痕跡あることについては、Vgl. Stobbe=Lehmann, Deutsch. Privatr. III. S. 526 Anm. 28
4) Bad. Ldr. §1382f: ,,Schmerzengeld kann nicht gefordert werden.``
5) Österr. GB. §1325---Sächs. GB. §1489---Schweiz 47 (54).
6) I. Entw. 728---II. Entw. 770---BGB. 847.
7) 二七頁参照。
第三節 健康の私法的保護
一 序 説
健康を独立の法益と見、その侵害を独立の不法行為と見るに至つたのは、独一草以来である。それまでは自身侵害(Körperverletzung)あるも健康侵害(Gesundheitverletzung)なし、せいぜい前の語中後の者を包含せしめたに過ぎなんだ——1) 2)
1) Preuss. Ldr. I, 6 §111; Österr. GB. §1325; Sächs. GB. §1483; Schweiz. Obl. R. Art. 53等みな身体侵害の語を用ゐるに止まる。
2) スイス新債務法も、健康侵害なる語は用ゐない。しかし学者は、四十六条の身体侵害中に、健康侵害を含ませてゐる(Egger=Oser, Komm. zu Art. 46)。オォストリアの学者も、同国民法一三二五条の身体侵害なる語をやはり広く解してゐる(Ehrenzweig, Syst. d. allg. österr. Privatr. II. 1, S. 627)。わが七百十条の『身体』中にも、健康を含ましむべきであらう。
二 健康侵害
イ 身体機能の侵害が健康侵害であることはいふまでもない。腐肉を売つて食した人を中毒させ、性交によつて病毒を相手に伝へるごとし。1)精神機能の侵害も健康侵害となる。汽車事故の際、乗客は身に寸傷を負はなかつたが、驚愕により恐怖性神経衰弱(traumatische Neurose)になつたといふ場合のごとし。2)
1) Samml. v. Zivilr. Entsch. d. k. k. Oberst. Gerichtsh. 11, Nr. 4079; 17, Nr. 6778.
2) Samml. 7, Nr. 2886.
ロ オォストリアの判例のごときは、健康を危険にする行為をも健康侵害に準じてゐる。例へば食した肉の腐敗に気づき医師に診断を乞ひしに、何ら異状なかつたとすると、健康侵害はない、しかし健康を危険にする行為はあつたのであるから、肉屋は、買主が医師に払ふ診察料を賠償せねばならぬといふごとし。1)
1) Samml. 10, Nr. 3983; 11, Nr. 4243.
ハ むろん不作為によつても健康侵害は成立する。医師が現代の医学が命じる当然の措置を怠つたため病気を重もらせたとか、薬剤師が劇薬瓶に「劇」字を附記することを忘れたため、滋養薬とまちがへて患者服用し、腹痛を起したとかいふがごとし。1)
1) Entsch. d. schweiz. Bundesg. 31, 2 Abt. S. 628.
三 賠償および慰藉料請求
被害者は治療費の支出・労賃の喪失・獲得能力の減退に対して損害賠償を求めることができ、苦痛に対して慰藉料を求めることができる。
第四節 自由の私法的保護
一 序 説
ロォマ法や普通法は、自由侵害は、他の要素と合体してなら格別、自身独立しては、不法行為とならないと見てゐた。仏法やスイス旧債務法は、自由侵害を不法行為と見てゐたが、そのために特別規定を立てず、不法行為一般の原則——仏の一三八二条・瑞の五〇条——を適用してゐたに過ぎなんだ。ドイツの立法はこれに反し、プロイセン州法でもザクセン民法でも、自由侵害につき特別規定を設けてゐた。1)オォストリアまた然り。2)現行ドイツ民法また然り。3)
1) Preuss. Ldr. I, 6, §§132 ff.---Sächs. GB. §1497---Bad. G. v. 6/3 1845 §6---Hess. Entw. Art. 666 ff.---Bayr. Entw. Art. 945.
2) Österr. GB. §1329.
3) Motive, II. S. 795 f.
二 自由侵害
イ 自由侵害とは、運動の自由(Lokomotionsfreiheit)を制限すること——居所転換の自由(Freiheit des Aufenthaltswechsels)を制限すること——をいふ。密室に監禁することばかりではない、出口を開放してゐても、被害者をしてそれが利用を不可能ならしめた場合は、やはり自由侵害となる。自動車に乗せて疾走するがごとし。被害者自身の抑制観念(Hemmungsvorstellung)——羞恥・恐怖の情等——を利用して彼の運動を妨げても自由侵害となる。入浴中の女の衣類を奪ひ、彼女をして外出を躊躇させるごとし。1)
1) Rosenfeld, Stier-Somlo=Elster, Handwörterb. d. Rechtsw. 2. S. 504 ff.
ロ その目的が合法な場合、若くは自由を制限されることにつき被制限者に同意ある場合は、自由侵害とならない。例へば医師が患者に運動を禁じ、演奏の主催者が音楽演奏中客の堂外に出づるを禁じ、1)また政党の袖領が議員を缶詰にするがごとし。
1) Rosenfeld, a. a. O.
三 賠償および慰藉料請求
イ 被害者は、(一)自由回復に要する費用を、加害者に請求することができる。1)例へば大阪の女が上海に監禁されたとすると、監禁地から旧居所までの復帰費、すなはち上海から大阪までの旅費は、加害者の負担となる。請負師の過失でトンネル崩壊し、中に働いてゐた工夫出口を失つたとすると、出口開放に要する費用は請負師の負担となる。(二)利益取得を妨げられた場合、すなはち労働収益を妨げられた場合には、その賠償を求めることもできる。紡績女工が監禁のため十日間働きえなかつたとすると、十日分の労賃を、工夫が三日間生埋めにされてゐたとすると、三日分の労賃を請求することができる。
1) Preuss. Ldr. I, 6, §§132 ff.---Österr. GB. §1329---Württemb. G. v. 5/9 1839, Art. 16---BGB. §823.
ロ 自由被害者に慰藉料請求権を与へた立法は、比較的少なかつた。これを身体被害者に与へた墺・普さへ、自由被害者に拒んでゐた。フランスの判例はこれに反し、自由被害者も他の人的利益の被害者と同じく慰藉料請求をなすことができると見てきた。1)ザクセン法に至つては、遠く十六世紀の昔から自由の被害者は、自由回復費および喪失利益に対する外、精神苦に対しても、賠償を求めることができるとしてきた。2)ドイツ民法も自由被害者の慰藉料請求を認める。3)
1) 二七頁参照。
2) Weiske, Abhandlungen aus dem Gebiete des deutschen Rechts, S. 108--111.
3) BGB. §847.
ハ ザクセン法上の慰藉料は、『監禁一日につきいくら』といふ風に、形式的に法定されてゐた。これをSachsenbusseといふ。1)現代の慰藉料は、被害者苦痛の程度・加害者過失の程度・両者の身分・財産状態等を参酌して、自由に裁判官これを量定する。
1) 古くは監禁一日40 Groschenの割だつたが(Stobbe=Lehmann, Deutsch. Privatr. III. S. 529)、一八六三年の民法以来、監禁一日、1 Thaler 10 Neugraschenの割となつた(Sächs. GB. §1497)。
第五節 精神生活の私法的保護
一 序 説
正しく社会事象を観念することは、取引活動を有利に営む必須の前提である。故に各人は、観念生活の完全性(Integrität des Vorstellungslebens)を保証されなければならない。みだりに他人から観念の正確さを攪乱されてはならない。詐欺された場合はもちろん、虚偽の報告や悪意のある推薦を受けた場合にも、よつて被つた損害を加害者に賠償さすことができねばならない——
二 詐 欺
イ ザクセン民法は詐欺を不法行為と見、被害者は詐欺に基く損害の賠償を加害者に求めうる旨、明かに規定した。1)自余の立法はこれを言明はしなかつたが、プロイセン州法の下においても、フランス民法の下においても、オォストリア民法の下においても、乃至また普通法の下においても、詐欺は不法行為だといふのが通説であつた。2)現行ドイツ民法上も詐欺は不法行為となる。3)
1) Sächs. GB. §1504; Dresd. Entw. Art. 1014.
2) Motive, II. S. 735 ff.
3) BGB. §§823 II, 826——わが国法上も詐欺が不法行為になることについては鳩山・債権各論・八四七。
ロ 被害者は、詐欺なきときの原状を回復すべく加害者に請求することができた。分説すると、(一)詐欺なかりせば全然契約を締結しなかつたらうやうな場合——成立詐欺(dolus causam dans)の場合——には、受けた給付を返還し、与へた給付を取戻すことができた。(二)詐欺なきも締結したるべく、ただ、さまで不利には締結しなかつたらうやうな場合——内容詐欺(dolus incidens)の場合——には、給付を取戻すことはできなかつたが、損害を排除することはでき、例へば詐欺のため二十円高く買つた場合には、その二十円を減額さすことができた。現代法上また然り。1)
1) 取消権だけで被害者は救はれぬ。別に損害賠償請求権の必要存す。なぜなれば、(一)詐欺にかかつて告知を中止し、告知期間を徒過したといふやうな場合には、取消の道なく、損害賠償を求める外に仕方がない。(二)内容詐欺の場合には、被害者は、取消さずに、損害の賠償だけを受けやうと欲する。(三)成立詐欺の場合には、被害者は取消権によつても、損害賠償請求権によつても、ひとしく給付を取戻しうるが、二者消滅時効を異にするの結果、やはり並有の実益あり(v. Tuhr, allg. Teil, II. 1, S. 627 ff.)。
三 助言・案内・紹介
イ 助言(Rat)案内(Auskunft)紹介(Empfehlung)等からは責任生ぜずといふのが、十九世紀立法の常則であつた。1)けだしこれらの場合には、与へる者に責任負担の意思なく、受ける者に、自己の危険において行動するの決心存す、且つもし助言等から賠償責任生ずとすると、人これを与へることを躊躇し、人間同志の交際と取引とが、あまりに重苦しくなるからである。現代立法も助言等からは責任生ぜずと見てゐる。2)
1) Seuffert's Archiv 32, Nr. 45---Preuss. Ldr. I, 13 §217---Österr. GB. §1300---Zürich. GB. §1131---Sächs. GB. §1301---Bayr. Entw. Art. 687---Bad. Ldr. §1381aa bis 1381ae.
2) BGB. §676.
ロ しかし故意に虚偽の報告をした者、すなはち、より善き知に反して(gegen besseres Wissen)報告した者は、その報告を判断の基礎としたために相手方の受けた損害を、賠償してやらねばならなかつた。1)ある男に支払能力なきことを知りつつ信用できると報告したり、2)ある種の方法で改築工事をはじめると、建物崩壊するかも知れないと知りつつ、その方法を教へたり、ある男に盗癖あることを知りつつ、安心できるとして出納掛に紹介したりした者は、3)その報告なり紹介なりに従つたために受けた相手方の損害を賠償してやらねばならなかつた。現代法上も、故意に出た虚偽の報告は不法行為となる。
1) Preuss. Ldr. I, 13 §218---Sächs. GB. §1301---Österr. GB. §1300. Vgl. Randa, Schadenersatzpflicht nach österr. R. S. 66.
2) Jurist. Wochenschr. 1917, S. 285.
3) Jurist. Wochenschr. 1913, S. 431. Vgl. auch Sammlung v. Zivilr. Entsch. d. k. k. Oberst. Gerichtsh. VI, Nr. 2490.
4) 判例にいはく——『直接原告に与へず、第三者に与へしときといへども、その助言、第三者より原告へ伝達さるべきことを知りし場合は、原告に対し損害賠償の責を免れず』(Jurist. Wochenschr. 1912, S. 293)。
ハ 報酬を取つて報告する者および業として報告する者の責任は、普通人のそれよりも重かつた。普通人は前にいつたやうに、故意に出た虚偽の報告に対してのみ責任を負つたが、報酬を取り若くは業とする者は、過失に出た軽率な助言(leichtsinnige Rat)に対しても責任を負つたからである1)——業とする者は多く報酬を取る。しかしさうでない場合もある。私立の無料法律相談所・無料衛生顧問・無料職業紹介所のごとし——また無免許医・無資格弁護士も、医又は弁護士を標榜する以上、医又は弁護士と同様に、過失に対し責任を負はねばならなかつた。2)
1) Preuss. Ldr. I, 13, §§219--221---Österr. GB. §1300 Satz I.
2) Ehrenzweig, System. d. allg. österr. Privatr. II, S. 665 ff.; Randa, a. a. O. 末川・民法に於ける特殊問題の研究二巻・五〇三頁以下。
第六節 貞操の私法的保護
一 序 説
イ 十九世紀の立法は、夫なき良家の婦女を孕ませた者は、その婦女と婚姻するか、支度料を与へて第三者との婚姻可能を高めてやるか、二者その一を撰ばねばならぬとしてゐた。1)これを嫁入りの訴(Deflorationsklage)といふ。2)
1) Preuss. Ldr. II, 1, §§1061, 1064 ff., 1025 ff.---Sächs. GB. §§151 ff.---Würtemb. G. v. 5/9 1839---Altenb. G. v. 25/5 1876 §§1 ff.
2) 嫁入りの訴は、教会法の影響である。教会法は夫なき良家の婦女と通じた者は、支度料当方持ちにてその婦女と婚姻せねばならぬとしてゐた。これを『婚姻且つ支度料』(duc et dota)の義務といふ。ややこの峻厳を寛和し、『婚姻又は支度料』(duc aut dota)、その一を撰べば足る、支度料当方持ちにて娶る要なしとしたのが、すなはち嫁入りの訴である(Vgl. Stobbe=Lehmann, Deutsch. Privatr. III. S. 530 ff.)。
ロ 嫁入りの訴に対しては、『嫁入請求は本来請求すべからざる事項を請求するものにして正しからず、支度料請求も父の責任の転嫁にしてこれまた不当。誘惑者に対しては別に正当の請求方法あるにあらずや?不法に貞操を侵害されし場合は不法行為上の責任を問ふべく、孕みたる場合は分娩および産褥の費用を要求すべし』といふ正当な反対意見が絶えなかつた。ドイツ民法以来、遂に嫁入りの訴を廃し、不法に貞操を侵害されし場合には不法行為上の請求、孕みたる場合には分娩および産褥費の請求といふことになつた1)——
1) Österr. GB. §1328は、つとに嫁入りの訴を廃し、妊娠せしめられた女は、婚姻又は支度料を求めることをえず、分娩および産褥の費用を求めうるに過ぎないとしてゐた。仏の判例も嫁入りの訴を認めず、ただ一三八二条を根拠に、貞操侵害者に損害賠償義務を負はせてゐたに過ぎなんだ(Zeitsch. f. franz. Civilr. 2, S. 336 ff.)。Bad. G. v. 6/3 1845 §§14 ff.; Würtemb. G. v. 5/9 1839 Art. 18また然り。
二 貞操侵害
イ 貞操侵害とは、暴力を用ゐたとか、心神喪失・抗拒不能を利用したとかいふ場合だけでなく、女子の許諾をうるにはえたが、しかし正常の許諾でなかつたといふ場合をも含む。1)例へば(一)女子がその性交を婚姻上のものと誤認してゐたのを利用した錯誤利用の性交、(二)欺罔行為を以て女子を錯誤に陥れ、その結果女子をして性交を許諾させた詐欺的性交、2) (三)強迫行為を以て女子に畏怖の念を生ぜしめ、その結果女子をして性交を許諾させた強迫的性交3)のごとき然り。
1) Preuss. G. v. 24/4 1854 §1---Österr. GB. §1328---BGB. §825---Zeitschr. f. franz. Civilr. 2. S. 336 ff.
2) 詐欺的性交として判例に現はれてくるのは、男が将来結婚するやうに吹聴したため、遂に許諾を与へるに至つたとか、妻あることを秘してゐたため許諾を与へてしまつたとかいふの類(Jurist. Wochenschr. 1906, S. 352; 1909, S. 415)。
3) 強迫的性交とは、許諾を与へざれば解雇すべしとか、犯罪を告発すべしとかいふの類。
ロ 従属関係の濫用によつて女子の許諾をかちえた場合も、貞操侵害と見られてゐる。1)雇主・債権者・後見人・警官・教師・医師等が、その地位を濫用した場合のごとし。間接従属関係の濫用、例へば、雇主が雇人の妻を弄ぶごときも、貞操侵害だとされてゐる。2)
1) Österr. GB. §1328---BGB. §825---Zeitschr. f. franz. Civilr. 2, S. 336 ff.
2) Ehrenzweig, Syst. d. allg. österr. Privatr. II. 1, S. 664.
ハ 不正手段と女子許諾との間には相当因果の関係あることを要する。故に手段極めて軽微にして、他の婦人に対してならば、恐らく効果なかつたらうといふ場合には、たまたまそれが当該の場合、その女子の許諾の原因をなしたとしても、貞操侵害ありといふことをえない。なぜなれば偶然の結果は、裁判官これを行為者に帰せしめることをえざるがため、男子の手段と女子の許諾との間に相当なる因果の関係なきときは、裁判官は畢竟、女子許諾の原因は別に存す、彼女は彼女自身の判断に基き許諾を与へしものにして、男の手段に動かされしにあらずと看做さざるをえざるが故である。1)例へば『婚姻の前ぶれ』と女子の許諾との間には、相当因果の関係あらう。従つてこれに動かされた女子は貞操侵害の訴を起しえやう。しかし『富の誇示』と女子の許諾との間には相当因果の関係なし。故にこれに動かされた女子は貞操侵害の訴を起すことをえないのである。
1) Rechts. d. Oberlandsg. 3, S. 210.
三 不貞の抗弁 (Einrede der Bescholtenheit)
イ 十九世紀の立法は、夫なき良家の女子のみ嫁入りの訴(Deflorationsklage)を起すことができる、夫ある者・数人の情夫をもつた者・賃金をとつて性交を許諾した者は、懐胎しても、男に対し『婚姻か支度料か』(duc aut dota)を請求することができないとしてゐた。1)またこの請求権を一旦取得しても、未だ男が結婚拒絶の意思を表示せざる間に、他へ嫁ぐか若くは不貞行為をなせば、請求権を失ふともしてゐた。2)けだし嫁入りの訴は、嫁入りさすことを主眼にしてゐたから、最初より妻たるに適せざる有夫の婦・性業婦・不貞の女にはこの請求権を与へず、後に妻たるに適せざるに至れば、一旦取得した請求権を失ふと定めざるをえなかつたのである。
1) Preuss. G. v. 24/25 1854, §9---Sächs. GB. §1552---Seuffert's Archiv 26, Nr. 133; 32, Nr. 291; 46, Nr. 49.
2) Preuss. Ldr. II, 1, §§1080 f.---Sächs. GB. §1552---Altenb. G. v. 29/5 1876 §2---Seuffert's Archiv (6), Nr. 45.
ロ しかし今日の貞操侵害訴訟は、誘惑者へ嫁がんがためでなくして、誘惑者の不法行為上の責任を問はんがためであるから、夫なき良家の女ばかりではなく、すべての女が原告となりうるのである。侵害を受けた後不貞の行為をはじめても、一旦取得した請求権を失ふには至らないのである。1)
1) 不貞の抗弁の弊害については、Vgl. A. Menger, Bürgerl. R. u. besitzlosen Volksklassen, S. 75 ff.
四 賠償および慰藉料請求
イ 貞操侵害によつて損害を発生させた場合には、その賠償をなさねばならない。例へば侵害によつて女子の身体若くは健康を害したとすると、治療費を出すことを要する。妊娠させ、分娩の費用を出させ、且つ休業させたとすると、すべてそれらを賠償することを要する——単なる和姦から妊娠させた場合の責任は、不法行為上の責任でなく、公平観念から特に法の命じた責任であるから、1)その範囲、分娩・産褥の費用を出ないが、貞操侵害から妊娠させた場合の責任は、不法行為上の責任であるから、すべての損害、すなはち休業のため失つた利益までも賠償せねばならぬのである。2)
1) Motive, IV. S. 912---Seuffert's Archiv 19, Nr. 212.
2) Ehrenzweig, a. a. O. S. 664.
ロ 精神上の苦痛に対する慰藉料を請求することもできる。仏の判例まづこれを認め、1)スイスは旧債務法以来仏に做ふこととなつた。2)ドイツのやうに原則として慰藉料請求を認めない国も、貞操侵害の場合にはこれを請求することができると、特に明記してゐるのである。3)墺法は今なほこれを認めないが、他方において婚姻見込の減少(verminderte Heiratsaussicht)を有形損害の一種と見、これに対し賠償を請求しうることにしてゐるので、事実、慰藉料請求を与へたも同然である。4)
1) Code Civil 1382. 一七頁参照。
2) Alt. O. R. Art. 55.
3) BGB. §253 §847 II.
4) Ehrenzweig, a. a. O. S. 664 f.
ハ 慰藉料請求は本人に限る。親は、娘の貞操を侵害されても慰藉料請求をなすわけに行かぬのである。1)
1) Motive, II. S. 753 f.
第七節 名誉の私法的保護
一 序 説
十九世紀の法律学は、未だ名誉と名誉感とをハツキリ分ち、各別にその侵害を論じるまでに至つてゐなかつた。截然たる両者の区別は、実に最近の事である。すなはち最近発達の成果を見んに——
二 名誉侵害
イ 名誉(Ehre)とは、地位相当の行動可能に対する社会の信頼である。あの人は、その年齢相当・性相当・職業相当・地位相当に行動しうる智力・体力乃至徳性を具備してゐるだらうと、社会から信頼されてゐるその状態が、すなはちその人の名誉である。故に名誉は共通性を有す。同一地位の人は同一程度の名誉を受けるのである。甲乙優劣の差は法律これを顧みない。地位に随伴する当然の名誉のみが法的保護の対象である。1)
1) スイスの判例は名誉を定義して、或は,,die äussere, soziale und berufliche Beziehungen``なりといひ(Entsch. d. schweig. Bundesg. 13, 87)、或は,,die Achtung der Stellung``なりといひ(31, 2 Abt. 246)、或は,,die Bewertung in der öffentlichen Meinung`` (33, 2 Abt. 591)なりといふ。
1) Specker, Persönlichkeitsr. S. 97.
2) Specker, a. a. O. S. 103.
3) Specker, a. a. O. S. 103.
4) Entsch. d. schweig. Bundesg. 20, 144.
5) Entsch. d. schweig. Bundesg. 21, 498 ff.
6) Entsch. d. schweig. Bundesg. 21, 1199.
7) Entsch. d. schweig. Bundesg. 31, 2 Abt. 274 ff. 33, 2 Abt. 591.
8) その他出生・教育程度・疾病・信仰・政見等に関する虚伝も名誉侵害となる(Ehrenzweig, Syst. d. österr. allg. Privatr. II. I. S. 658)。
9) Specker, a. a. O. S. 109 ff. S. 114 f.
ハ 伝播も侵害となる。他人の主張の事実に合せざることを知りつつそれを伝播し、若くは他人の主張を軽率に事実なりと信じてそれを伝播するごとし。誇張も侵害となる。一度泥酔したのを習慣的のごとく吹聴し、一度警察規則にふれただけだのに、その人を警察規則の常習違反者のやうにいひふらすごとし。不作為によつても侵害成立す。弁解してやるべき筈の人が沈黙せる場合、1)すなはち店員横領の嫌疑を受けたるが故に、番頭弁解してやるべき筈のところ、沈黙を守れる場合のごとし。
1) Lobe, Handwörterb. d. Rechtsw. 2. S. 159.
ニ 事実の報告は、憲法が吾人に保証する自由の一つで、もちろん名誉侵害とならない。たとへその結果、ある人の名誉に減少を来たさうとも、事実にそれが合してゐるかぎり、報告は名誉侵害とならない。ただある人の名誉に減少を来たさしめんとする目的のみのために、その人の名誉減少的事実をあばくならば、それは自由若くは権利の濫用の意味において、不法行為となるであらう。1)
1) これに反し正当利害関係人に事実を報告する場合は、不法行為とならない。婚姻せんとする人に相手方の素性卑しきを教へ、貸金せんとする人に相手方の不信用極まることを教ゆるごとし。
ホ 事実の批評も、市民的自由の一つで、名誉侵害とならない。たとへその結果、ある人の名誉に減少を来たさうとも、責を負ふ限りでない。ただ単にある人の名誉に減少を来たさしめんとの目的のみから、その人を悪罵するならば、それは自由若くは権利の濫用となり、その意味で不法行為とならう。
三 名誉感侵害
イ 名誉感(Ehrgefühl)とは地位相当の誇りである。一定地位の所属者が当然にもつ内的価値の自覚である。これまた共通性を有し、同一地位にある者は同一程度の名誉感をもつ。特別自尊心の強い人があつても、法はそれを顧みない。
ロ 名誉感すなはち価値自覚は、侮辱によつて侵害される。侮辱は価値否定の意思表現で、表示侮辱(Verbalinjurie)と態度侮辱(Realinjurie)とに分れるとされてきた。(一)表示侮辱とは、表示意思を以て価値否定の意思を表示する場合で、言語文章を以て人を侮辱し、劇に組み、1)絵にかいて人を侮辱する場合は大抵これに入る。身振りによる侮辱——舌を出し、唾をはきかくるの類2)——も大抵これに入る。(二)態度侮辱とは、周囲の事情から価値否定の意思を推知しうる場合をいふ。卑猥の目的から婦人の身体にふれ、嫌がる女に無理にキツスした男は、恐らく侮辱意思の表示を直接の目的としてはゐないであらうが、侮辱を前提とするにあらざればこの種の行為はなしえぬ筈だから、よつて以て彼の侮辱意思を推断しうるのである。他人の門標に不潔物をぬるがごとき行為からも侮辱意思を推断しうとされてゐる。3)
1) 嘗てハンブルグ市で、ある興行師の興行させた芝居に出てくる女魔術師(Zauberin)が、同市の某名流婦人を諷刺すること何人にも明かだつたので、その婦人が、名誉侵害を理由に、興行師に上演停止を請求し、勝訴したことがあつた。(Deutsch. Juristen-Zeit. 1904, S. 80)。
2) 面打のごときは、身体侵害であると同時に、侮辱意思の表示でもある。
3) Specker, a. a. O. S. 178 ff.——大官に辞職を勧告するために棺桶・自殺用器の類を送附したといふ話を、日本で屡々聞くが、この種の行為からも侮辱意思を推断しうるであらう。絶交同盟からまた然り。
ハ 表示侮辱の場合に真意と表示と齟齬し、侮辱の表示あるも真意これに伴はざることがある。この場合には侮辱の成立とならない。諧謔・皮肉のごとし。果して真意伴はざるやは、表示の際の顔色・声調等を見て決すべしとされてゐる。1)
1) 人の集合を侮辱することがある。『近時の学生は云々』『日本の貴族は云々』といふがごとし。集合そのものは法人でないから、名誉感の保護を受けないが、実は集合名詞が特定人を指してゐることあり、この場合にはその特定人の名誉侵害となるのである。——Specker, a. a. O. S. 174 f.
2) 甲に対する侮辱が乙に対しても侮辱となることがある。これを間接侮辱(mittelbare Injure)といふ。しかし人人独立の今日、雇人への侮辱が同時に雇主への侮辱となり、子・妻への侮辱が、親・夫への侮辱となるといつた場合は非常に少ない——Specker, a. a. O. S. 188 f.
ニ 侵害の対象は小別される。人類を動物のごとく罵詈するは、——,,die Zoologische Schelt-u. Schimpfworte`` ——人類的名誉感の侵害。1)女子の貞操を蹂躙するは、同時に女性名誉感の侵害。その他、地位職業等に従つて名誉感あり、そのそれぞれにつき侵害あるのである。
1) Specker, a. a. O. S. 97.
四 賠償および慰藉料請求
イ 十九世紀初頭の立法は、『名誉は売物でないから』(,,Weil einem ehrliebenden Bürger seine Ehre nicht um Geld feil sein soll``)といふ理由で、1)名誉侵害に対する金銭的慰藉を排斥した。ドイツ普通法は、もとは名誉被害者の慰藉請求を認めてゐたが、刑法典・刑事訴訟法典の施行と共に、人格侵害訴訟(Injurienklage)が廃止されてしまつたため、爾後慰藉請求をなしえざるに至つた。2)もちろん有形損害を被つた場合には、普通法上も地方法上も、3)その賠償を求めえたが、精神苦を被つたに過ぎなんだ場合には、その慰藉を求める道がなかつたのである。
1) Zeiler, Komm. üb. d. ABGB. zu §1330.
2) Einf. Ges. zur Str. P. O. §11, Abs. 1.
3) Einf. Ges. zur Str. P. O. §11, Abs. 1---Gruchot IV, 178---Österr. GB. §1330---Preuss. Ldr. I, 6 §§130, 131.
ロ ドイツやオォストリアは、今なほ名誉被害者の慰藉料請求を認めない。1)しかしフランスの判例は、つとに名誉被害者の慰藉料請求を認め、2)スイスも一八八一年の旧債務法以来これを認める。3)
1) BGB. §§253, 847---Österr. GB. §1330---Randa, Schadenersatzpflicht, S. 200: ,,Sicher und allgemein anerkannt, ist, dass für Ehrenverletzung (ohne Vermögensnachteil)keine Geldentschädigung verlangt werden kann.``
2) 二七頁参照
3) Alt. O. R. Art. 55——スイス民法二十八条と同新債務法四十九条との関係については、Vgl. v. Tuhr, schweiz. Obligationenr. I. S. 106 Anm. 2.
ハ 名誉減少的報告の取消を求める・いはゆる取消請求の訴(Klage auf Widerruf)、並びに陳謝請求の訴(Klage auf Abbitte)は、欧洲においては、近時殆ど姿を没した。1)
1) Einf. Ges. zur Str. P. O. §11, Abs. 1---Zeiller, Über den Wert der Ehrenerklärung, des Widerrufes u. der Abbitte, Zeitschr. f. österr. Rechtsgelehrsamkeit 1837 I. S. 237——墺・一三三〇条二項は今なほ取消請求の訴を認むるも殆ど行はれてゐないらしい(Vgl. Ehrenzweig, a. a. O. S. 657)。
第八節 信用および秘密の私法的保護
一 序 説
信用や秘密の保護は、二十世紀にはじまるといつていい。ことにドイツ民法1)およびスイス民法にはじまるといつていいが、もうその保護は、次の程度へ達してゐるのである——
1) Protokolle, 2. S. 637 ff.
二 信 用
イ 信用(Kredit)とは、支払能力および支払意思(Zahlungsfähigkeit u. Zahlungwilligkeit)に対する社会の信頼である。或は給付力および給付意思(Leistenkönnen u. Wollen)に対する社会の信頼だといつてもよいであらう。とにかく財産的義務の履行につき社会から受けてゐる好評(guter Ruf)が信用である——各人の生活、大いに商化しつつある今日、ただに商人ばかりでなく、一般市民も支払的好評を、法律によつて保護されねばならぬのである。1)
1) Specker, Persönlichkeitsr. S. 115.
ロ 信用は、事実の虚構によつて侵害されるばかりでなく、他人の主張の事実に合せざることを知るにかかはらず伝播し、若くは他人の主張を軽率に信じて伝播することによつても、また侵害されると見られてゐる。軽率に他人の言を信じて某銀行が取付けを受けたさうだ、某商店が行詰つたさうだと伝播するごとし。
ハ 肉体的および智能的労働者の、労働力および労働意思(Arbeitskraft u. Arbeitswilligkeit)に対する社会の信頼も信用に準じて保護されてゐる。その事実なきに、あの労働者は腕がないとか、怠け者だとかいへば、労働者の信用の侵害となる。1)
1) Vgl. Riezler, Arbeitskraft u. Arbeitsfreiheit in ihrer privatrechtlichen Bedeutung, Archiv f. bürgerl. Recht 27, S. 218 ff. insb. 236 f.
三 秘 密
イ 秘密(Geheimsphäre)とは、私生活上又は営業上、何人も他人に知得されることを欲せざるべき事実である。その私生活に関するものを私的秘密(Privatgeheimnis)といふ。封緘せる手紙その他の文書・日記・家計簿・写真・スケッチ・未発表の原稿・諸種の覚帳のごとし。その営業に関するものを営業秘密(Geschäftsgeheimnis)といふ。未だ特許をえざる発明・工夫・商業帳簿・諸種の設計図・流行や得意先の調査書等のごとし。1)
1) Giesker, Rechtsschutz des Briefes in der Schweiz, S. 3.
ロ 秘密は知得(Kenntnisnahme)によつて侵害される。秘密事項記載の文書を破毀したかどうかは問題でない。知得した知識を営利の目的に利用したかどうかも問題でない。知得さへすれば、すなはち秘密の侵害となるのである1)——秘密文書を写し取り、秘密写真を複写するごとき・いはゆる知の体化(Kenntnisverkörperung)も、またもちろん秘密の侵害である。2)
1) Giesker, Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre, S. 30 f.; Briefe, 15 f.
2) Giesker, Geheimsphäre 51; Briefe, 38 f.
ニ 秘密はまた漏洩によつて侵害される。漏洩とは知の媒介(Kenntnisvermittelung)、すなはち本人から相対的に秘密を解放された受信者が、第三者に伝播することをいふ。医師・弁護士・薬剤師・産婆等に、本人から解放された秘密を保持すべき義務あるはもちろんだが、その他の者も、明示又は黙示の契約上、秘密保持の義務(Geheimhaltungspflicht)を負ふ。工場労働者のごとき、工場秘密保持の義務を負はざるべからずとされつつある。1)
1) Wettbewerbsgesetz, §§9, 10---BGB. §826---なほ有馬・不正競業論一九三頁以下参照。
四 賠償および慰藉料請求
イ 信用侵害のため利得可能を減少させられた者は、その賠償を求めうるが、慰藉料請求はできない。なぜなれば信用は、人的利益でなくして財(Vermögensgut)であり、その侵害は、単なる財産侵害に過ぎぬからである。信用を人格と見、1)若くは人格と財との合体(Doppelgut)と見る説2)は、近時大いに廃れた。3)
1) Elzbacher, Handlungsfähigkeit, S. 318; Kohler, Lehrbuch 2 S. 517.
2) Huber, Kredit als selbstandiges Rechtsgut.
3) Entsch. d. schweiz. Bundesg. 31, 2. Abt. S. 245.
ロ 私的秘密侵害の場合には、損害賠償の外慰藉料をも求めることができる。なぜなればそれは人的利益の侵害であるから。営業秘密侵害の場合には、損害賠償のみを求めることができる。なぜなればそれは単なる財産侵害に過ぎぬから。
第九節 肖像権
一 序 説
イ 肖像(Bildwerk)とは、容姿の模写をいふ。絵画・彫刻・写真のごとし。請負契約に基いて製作される場合と、然らずに製作される場合とあらう。(一)請負契約に基いて製作された場合、肖像上の著作権は、注文者に移るか、それとも製作者に残るか?製作者に残るとせば、本人の利益保護上、相当に製作者の権利行使を制限する必要あらうが、通説は、肖像注文の場合には、著作権は当然注文者に移ると見る故、殆ど制限の必要を見ない。1)これに反し、(二)請負によらざる場合には、もとより著作権は製作者側に残るから、本人の利益保護上、大いにそれを制限する必要あるのである。肖像製作者の著作権を制限する本人の権利を、肖像権(Recht am eigenen Bilde)といふ。2)
1) G. v. 9/1 1876 §8 Abs. 1: ,,Wenn der Urheber eines Werkes der bildenden Künfte das Eigentum am Werk einem anderen überlässt, so ist darin die Übertragung des Nachbildungsrechtes fortan nicht enthalten; bei Porträts und Porträtbüsten geht dieses Recht jedoch auf den Besteller über.``---G. v. 10/1 1876 §7 Satz 3: ,,Bei photographischen Bildnissen (Porträts) geht das Recht [sc. der ausschliesslichen Nachbildung]auch ohne Vertrag von selbst auf den Besteller über``---Vgl. auch Kohler, Autorr. S. 202 f. Gierke, deutsch. Privart. 1. S. 779
2) 肖像権は、肖像の陳列や複製・頒布やを制限する権利で、撮影そのものを制限する権利ではない。もちろん吾人は、撮影そのものに対しても同意権をもつが、それは名誉権の作用で、肖像権の作用ではないのである。従つて同意なき早取写真は、侮辱とはなつても肖像権の侵害とはならぬのである。
ロ 肖像権といふ制限権なかりし当時は、裁判所は、名を侮辱にかりて、かつかつ肖像本人の利益を保護してゐた。——例へば(一)一八九八年、Ostsee海水浴で、若い婦人の裸体になつた一刹那を、早取写真にとり、絵はがきに製作し、売出した者のあつた際には、侮辱なりとして原版を没収した。1) (二)ビスマルク公死去のみぎり、公の死室へ忍び入り、公の死顔を撮影した者のあつた際には、家宅侵入によつて写したといふかどで、原版を没収した。2) (三)妻の写真を注文した夫が、離婚後その写真を自転車営業の広告に使用し、妻から禁止の要求あつた事件の際には、裁判所は、写真は夫の注文による、故に夫に複製・頒布の自由あり、妻はこれを禁止することをえずとまで判示せざるをえなかつた3)——一九〇七年一月九日、肖像上著作権の制限に関する法律(G. betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste u. der Photographie, §§22--24)の発布を見るに至つたのは、実にかかる不都合の続出に困りきつた結果であつた。
1) Entsch. d. 2. Strafsenats v. 29/11 1898, mitgeteilt von Gareis, Gutachten S. 6 f.
2) Entsch. d. Reichsg. in Zivils. 45, Nr. 43---Vgl. dazu Kohler, Der Fall der Bismarckphotographie (Autor-u. industrier. Abh. u. Guta. II. 53 ff.).
3) Entsch. d. Rechsg. in Strafs. 33, Nr. 90.
4) 仏の判例に関してはVgl. Kohler in seinem Archiv 10. S. 274; Das Eigenbild im Recht; Kunstwerkr. S. 157 f.; Olshausen bei Gruchot 46, S. 492.
二 肖像権の侵害—違法阻却の場合
イ 肖像権は肖像が、本人の同意なしに陳列・複製・頒布されることによつて侵害される。第三者がそれをやつた場合はもちろん、著作者がそれをやつてもやはり肖像権の侵害となる。他人が注文者であつた場合に、その他人が本人の同意なしに陳列・複製・頒布しても、またもとより肖像権の侵害となる。がしかし、
ロ 『公に生活する者は、世間がその肖像を見たがるのを忍容しなければならない』1)。『新聞的出来事の関係人物も、写真に撮られることを我慢しなければならない』。かかる人物を知りたがることは、世間正当の要求と見ていいからである——そもそも個人羞恥心の平穏のために、無同意複製の場合を、なるべく少なからしむべきか、公衆好奇心の満足のためにかかる場合を多からしむべきかは、肖像法制定の際、大いに争はれた二大立法見点であつたが、2)法律は後者をとり、無同意複製の場合を非常に多く認めたのである。すなはち——
1) Kohler, Autor-u. indust. Abhandl. u. Gutacht. S. 56: ,,Wer in der Oeffentlichkeit lebt, muss sich gefallen lassen, dass die Welt das Bedürfnis empfindet, sein Bild zu kennen, und dass sie diesem Verlangen entspricht.``
2) Keyssner, Recht am eigenen Bilde; Gareis, Verhandlungen d. 26. deutsch. Juristentages 1.は保守的態度に出で、なるべく本人の同意に懸らせやうとしたが、Kohler, a. a. O.は、肖像の公的性質を強調し、無同意複製の場合を多からしめやうとした。Vgl. dazu Rietschel, Das Recht am eigenen Bilde, Arch. f. Civ. Praxis. 94, 161 ff.
ハ 現代史上の人物には肖像権なし、同意なしにその肖像を陳列・複製・頒布されても、彼は異議をのべえぬことになつてゐるのである。1)しかも学説判例は、いはゆる現代史的人物の意義を最広義に解釈し、元首・政治家・外交官・議員・学者・発明家・著作家・芸術家等はもちろん、成功せる実業家・2)刑事被告人・異常の不運又は幸運に際会せる人々等も、現代史的人物にして、やはり肖像権なしと見てゐる。結果において、新聞的興味(journalistisches Interesse)の対象となりうる人は、すべて肖像権なしといふも過言でない。
1) Kunstschutzgesetz v. 9/1 1907 §231.
2) Juristisch. Wochenschr. 1925, S. 378.
3) 現代史的人物といへども、私生活上の肖像——政治家としてではなく、父とし夫としての肖像——については、肖像権をもつ(Specker, Persönlichkeitsr. S. 266)。
前期ビスマルク公の場合に関連して、Kohlerはいつた——『公衆は、病気中の公人の肖像を見たがるわけに行かない。病態は私生活であるからである。死態に至つては、私生活上の最厳粛のもので、それは何人からも破られないヴエェルに包まれなければならない』と(Kohler, Autor-u. indust. Abhandl. u. Guta. 56 f.)。
4) 本文所述のごとく、殆ど名士には肖像権がない。しかし商品の包装紙に、その写真を利用されたといふやうな場合には、名士といへども、肖像権を主張して、肖像使用を禁止させることができるのである。ある煙草製造場が、ツヱペリン伯の同意なしに伯の肖像および名を、商標に使用した際、伯は禁止の訴を起して勝訴した(Entsch. d. Rechsg. 74, Nr. 86)。
ニ 公衆の興味をそそる集会・行列・儀式等に参列してゐる人も、肖像権を主張するわけに行かない。1)もともと公的意味をもつてゐない所の人も、一旦行列に加はるや、公的意味を帯び来り、レンズの前で我侭をいへぬことになるからである。風景が主で人物が点景に過ぎない場合にも、その人物は、肖像権を失ふとされてゐる。
1) G. v. 9/1 1907, §23 I Z. 3.
ホ 絵画や美術写真のモデルも、肖像権を失ふ。1)画面に強く本人の特徴が出てゐる場合にも、本人は、著作者の陳列・複製・頒布を制限するわけに行かぬのである。法は、芸術に対する公衆の利益を本人の利益以上に保護し、著作者に完全な公表の自由を保証してゐるのである。
1) G. v. 9/1 1907, §23 I Z. 4.
ヘ 賃金をとつて肖像を写させた場合は、暗黙の間に本人が、陳列・複製・頒布の自由を著作者に与へた場合と見てゐる。陳列等が本人の広告になる場合にも、本人の同意ありと擬制してゐる。1)その結果モデル女に肖像権なく、芸妓等にも肖像権ないのである。
1) Elster, Handwörterb. d. Rechtsw. 1. S. 768.
ト 問題は漫画であるが、一派の学者は、現代史的意義ある人物は、肖像の陳列・複製・頒布を禁じえぬごとく、漫画のそれをも禁じえぬが、然らざる普通人は、肖像の陳列等を禁じうるごとく、漫画のそれをも禁じうると説く。1)が、進歩した学説は、漫画の絶対的自由(unbedingte Karikaturfreiheit)を主張する。曰く、『笑ひこそ人生の花、社交の色。漫画に笑ひ転げうることによつて、どれだけ社会は幸福を増すかも知れない。故にユウモアの目的(humoristische Zweck)に出づるかぎり、漫画の陳列・複製・頒布は、充分自由でなければならない。侮辱の意味ある場合はもとより格別だが、然らざるかぎり、本人は甘じて笑題にならなければならぬ』と。2)これ実にKohler, Allfeld, Fuld等の所説にして、当来の判例は、彼らの指し示した方向へ動いて行くかとおもふのである。
1) Elster, a. a. O.
2) Kohler, a. a. O. 56 f.
チ 肖像権は消極的な禁止権で、積極的な請求権ではない。肖像本人の方から、著作者へ、該肖像を陳列・複製・頒布するやうに請求するわけには行かぬのである。映画俳優がその傭主に対し、彼の写真をもつと盛んに広告用に使用すべきことを請求した事件に関し、ドイツの裁判所は、肖像主にかかる積極的請求権なしと判示した。1)
1) Entsch. d. Reichsg. 103, Nr. 95.
三 賠償および慰藉料請求
イ 肖像権侵害の場合、すなはち肖像権者の同意なしに肖像を陳列・複製・頒布した者あつた場合には、肖像権者は妨害除却を求めることができる。妨害除却は、侵害なかりしならば存すべかりし状態の回復——いはゆる自然的回復(Naturalrestitution)——を請求するものにして、損害賠償請求の一種である。陳列の中止・複製の回収のごとし。
ロ 慰藉料請求は、独法はこれを認めず、1)スイスはこれを認む。2)
1) BGB. §253.
2) Schweiz. Obl. R. Art. 59.
第十節 氏名権
一 序 説
イ 名は、個性ある個体を容易に思ひ浮べさせるための符徴である。1)個体の特徴を一々列挙するの煩をさけるために、人は、名といふ符徴を予め附し、これによつて個体を簡短にいひ表はすのである。地域にも名を附し、家畜にも名を附し、人類の創作にかかる有形無形の財にも名を附す。著作の表題・営業の商号・商品の商標、いづれも名である。ここでは氏名、すなはち人の名を取扱ふ。
1) Opet, Das Namenrecht d. bürgerl. Gesetzbuchs. Arch. f. Civil. Praxis 87, S. 319 ff.
ロ もと氏名には、事実的・社会的意味しかなかつた。各人任意にこれを使用し、少しも法の制縛を受けなかつた。十七世紀頃これに関する公法規定の発生を見るには至つたが、その内容は、氏名はみだりに変更することをえず、これを変更するには官の許可を要す、他人の名を僣用せる者は刑に処すといふの程度を出でなかつた。1)もちろん氏名権なる私権を認めるまでには至つてゐなかつたのである。十九世紀初頭の立法——例へばプロイセン法・オォストリア民法・ザクセン民法——も、氏名の取得方法に関し、嫡出子は父の姓を称すとか、私生児は母の姓を称すとか、棄児は官これに命名すとか定めただけで、私権としての氏名権は認めなかつた。2)これを認めるに至つたのは、実にドイツ民法以後である。
1) Hermann, Über das Recht d. Namensführung u. d. Namensänderung Arch. f. Civil. Praxis 45, S. 164 ff.
2) Preuss. Ldr. II, 1 §§192, 741, 742, 863, 864. II, 2 §§58, 559, 592, 640, 641, 682, 685, 688, 689, 713---Österr. GB. §§92, 146, 165, 182 ff.---Sächs. GB. §§1748, 1796, 1801.
ハ 尤もフランスでは共和暦十一年芽月二日、一定氏名の主体は同一氏名の使用を他人に禁止しうと明かに定めたこともあつた。1)民法の判例は、氏を家の一つの所有権と見、氏の僣用者を一種の所有権侵害者と見てきた。2)スイスは民法以来、ドイツに做つて氏名権を認めた。3)オォストリアも一九一六年三月十九日の勅令で私権としての氏名権を認めるに至つた。4)
1) Opet, a. a. O. S. 314 f.
2) Vgl. Planiol, droit civil 1 397.
3) Schweiz. ZGB. Art. 29.
4) Kais V. v. 19/3 1916, §1. (GB. §43).
二 氏名権侵害
イ 氏名を使用しうる権利を氏名権といふ——第一に氏名権は不使用(Nichtgebrauch)によつて侵害される。けだし氏名は、正当な指示手段(Bezeichnungsmittel)であるので、ある人を指すにはその人の氏名を以てせざるべからず、その人の氏名を以てせざるときは、その人は、氏名権の侵害を受けたとして、氏名の使用——すなはち正当指示手段の使用——を、その他人に請求しうることになるのである。強ゐて他人の名字を滑稽的に発音するごときは、不使用による他人氏名権の侵害でもあり、侮辱でもある。1)
1) この例は屡々日本の政界に出た。蔵原惟廓を『ぞうばら惟廓』とよみ、根本正を『根も正』とよんだごとし。
2) 芸術家は芸術活動につき芸名を用ゐうる。故にある興行師が、興行広告に、尾上菊五郎と書かずに彼の本名を書き、ある展覧会の主催者が、竹内栖鳳作と書かずに彼の本名を書くならば、やはり不使用による氏名権の侵害であらう。
3) 旧説は不使用による氏名権侵害の場合を看過してゐた(Jhering, in seinen Jharb. 23, S. 320; Regelsberger, Pand. I. S. 198; Thon, Rechtsnorm, S. 153)---Opet, Specker以後不使用による氏名権侵害を認められるに至つた(Opet, a. a. O. S. 377 ff; Specker, Persönlichkeitsr. S. 55 ff.)。
ロ 氏名権はまた使用(Gebrauch)によつても侵害される。けだし氏名は指示の手段(Bezeichnungsmittel)であると同時に区別の手段(Unterscheidungsmittel)でもあるから、人は、他人の名を自己指示の具に用ゐることをえず、自己指示の具に用ゐれば使用による氏名権の侵害となるのである。1)
1) 真実に反しある他人が云々の行為をなしたと主張する場合は、名誉侵害となるも氏名権侵害とならない。例へばその事実なきに某医学博士御推薦と書いて売薬広告をなし、某殿御賛助と書いて寄附金を募るごとし。けだしこの場合は、他人の名を自己指示の具に供せず、他人自身ある行為(推薦又は賛助)をなしたと、吹聴するに過ぎないからである。
ハ 使用による侵害は、他人の名をそのまま使用した場合にだけでなく、他人の名と外観上・呼称上又は観念上類似する名を使用した場合にも成立する。1)例へば綴りをかへてStresemannをStresemanと書き、字画をかへて豐島を豊島と書いても、外観上の類似あるため氏名侵害となる。多少字数を増減してもなほ侵害成立する。スイスの判例は、,,F. Roskopf & Cie``なる商号を,,F. E. Roskopf & Cie``なる商号の侵害と見てゐるのである。2)全然文字をかへても発音類似するときは、呼称上の類似としてやはり侵害成立する。河井を『かわい』又はKawaiと書くごとし。観念上の類似のために氏名権又は商号権の侵害となることもある。スイスの判例は、,,Schweizerische Milchgesellschaft``なる商号を,,Anglo-Swiss condensed milk Company``なる商号の侵害と見た。英独語を異にするも観念は同一だといふ理由からである。3) 4)
1) Specker, a. a. O. S. 157 ff.
2) Revue d. Gerichtspraxis 24, Nr. 13.
3) Entsch. d. schweiz. Bundesg. 27, 2. Abt. S. 520 ff.
4) ドイツ帝国裁判所は、夫の情婦が夫と旅行し、ホテルの名簿へ、「妻」と記入した場合には、妻は情婦のために、氏名権を侵害されたりといふべく、従つて情婦に対し、向後の不作為を請求するを妨げずと判示してゐるが(Entsch. d. Reichsg. 108, Nr. 66)、正確にいふとこれなどは、氏名そのものの詐称ではなくして、妻といふ私法的地位の詐称であらう。
ニ しかし外形上混同の危険あつても事実その虞れなきときは、氏名権の侵害とならない。むづかしくいふと、氏名権侵害成立するためには、抽象的なる混同の危険(Gefahr in abstracto)あるだけでなく、具体的なる混同の危険(Gefahr in concreto)あることを要するのである。1)故に、(一)異職同名の場合は、氏名権侵害にならない、事実混同の虞れなきが故である。靴屋が薬屋の商号に做つても薬屋の商号権を侵害したことにならぬのである。(二)同職同名でも、得意の方で同名者の実質的相異に着目すべき場合には、やはり氏名権侵害とならない。芝居の観客は重きを俳優の実質的相異におくから、東京の俳優が大阪の俳優に做つて同じ『中村福助』を名乗つても、後者の氏名権を侵したことにならぬのである。
1) Specker, Persönlichkeitsr. S. 157 ff.
ホ 数人各々合法に同一氏名を取得してゐる場合を氏名の平行(Paralleles Namensgebrauch)といふ。数人の山田太郎あるがごとし。この場合に各人『山田太郎』を使用するは、各人その権利を行使するものにして、もとより正当である。ただし具体的混同の危険存する場合には、各人その名に特別の肩書(unterscheidendes Zusatz)を附せざるべからず、これを附せざれば不作為による他人の氏名権の侵害となると見られてゐる。1)一番地の山田太郎、二番地の山田太郎と名乗らざるべからざるがごとし。また同名者を侵害する目的を以て自己の名を使用すれば、氏名権の濫用となるとも見られてゐる。すべての権利に濫用の禁あるがごとく、氏名権にもそれがあるといふのである。2)
1) Specker, a. a. O. S. 56 f.
2) Specker, a. a. O. S. 56.
ヘ 特殊の生活方面においては、人は変名使用の自由がある。著作に雅号を用ゐ、演劇に芸名を用ゐ、説教に僧名を用ゐるごとし。変名も氏名同然に保護されるかについては、ドイツ民法の解釈上異論あつたが、一九二一年一月二十一日、帝国裁判所は変名も氏名同然に保護さるとの新判例を開いた。1)
1) Entsch. d. Reichsg. 101, Nr. 61.
三 氏名の奪取 (Enteignung des Familiennamens)
イ 一九二五年次のやうな事件がドイツに出た——,,J. Malzmann``なる商号を以て煙草業を営んでゐたJ. Malzmann氏死し、その数子、同一商号の下に営業をつづけてゐたが、その中の一人Adolf Malzmann独立し、他の商人と共同して,,Lamata A. Malzmann & Co. G. m. b. H``なる商号をもつ有限責任会社を設立し、やはり煙草業をはじめたのでJ. Malzmannから、混同の虞れ(Verwechselungsmöglichkeit)ありとなし、有限責任会社に対し、その商号中よりMalzmannなる文字を削除すべく請求した。一審二審は共に原告を敗訴させたが、上告審は、『Malzmannといふ語は、略語的性質(Schlagwortcharakter)を有する商号中の重要語であるから、後で出来た有限責任会社は、たとへその社員にMalzmannなる姓の者あるにもせよ、この語を商号中に挿入することを避けねばならぬ』とし、原告を勝訴させた。1)
1) RG. in Jurist. Wochenschr. 1925, S.---Vgl. auch Entsch. d. RG. 75, Nr. 90; 111, Nr. 19.
ロ この判決に対しては、『判決のごとき見解をとると、たまたま氏名類似の商号を登記した者あつたために、氏名権者が、その当然の権利を行使しえぬことになる』と反対した者もあつたが、1) Rosenthal一派は、『氏名権の行使によつて取引を攪乱せしむべからず、判決が、混同の可能存する場合氏名を商号に用ゐるを許さずとせるは、洗練されたる法律良心(verfeinerte Rechtsgewissen)の発露なり』と激賞した。2) Kirchbergerはやや皮肉に、これを氏名の奪取(Enteignung des Familiennamens)とよんだ。3)
1) Vgl. Elster, Namenrecht, Handw. d. Rechtsw. 4, S. 179.
2) Rosenthal, Jurist. Wochenschr. 1925, S. 1289.
3) Kirchberger, Jurist. Wochenschr. 1925, S. 2106.
四 賠償および慰藉料請求
被害者が、氏名権侵害により財産的損害を受けたのならば——例へば得意を荒され、収益を減少されたのならば——その賠償を求めることができる。慰藉料に至つては独はこれを認めず、1)スイスはこれを認む。2)
1) BGB. §253.
2) Schweiz. Obl. R. Art. 45.
第十一節 私力的予防手段—自衛
一 序 説
人的利益の侵害あつた場合、被害者が加害者に対して、損害賠償若くは妨害除却又は慰藉料を請求しうるといふことは、各種・人的利益侵害の節下において各別にのべたが、真に充分に人的利益を侵害から擁護しやうためには、損害賠償・妨害除却乃至慰藉料といふやうな事後の救済手段ばかりでなく、事前の予防手段をも認めなければならない。すなはち私力による予防としての自衛(Selbstverteidigung)と、公力による予防としての不作為の訴とを発達させなければならない。まづ自衛方法の発達からのべる。
二 正当防衛 (Notwehr)
イ 正当防衛は、『歴史を有せず』1)といはれる普遍不動の法則で、ロォマ法も、ゲルマン法も、教会法も、みな認めた。けだし法益を不法の侵害から防衛することは、法律元来の任務であるから公力の救済を受けえざる急迫の場合に、私人自ら法益を不法の侵害から防衛するのは、法律に代つて法律の意思を実行するものにして、Titzeのいふごとく、2)法律のための事務管理であるからである。
1) Titze, Notstandsr. im deutch. BGB. u. ihre geschichtl. Entw. S. 23. 滝川・刑法講義一〇二。
2) Titze, S. 25.
ロ しかもなほそこに、多少の近代的変化を発見しえぬではない。(一)は、いはゆる受衛貨物(wehrhaftes Gut)、すなはち防衛行為を以て防衛しうる貨物の範囲の、大いに広まつたことである。生命・身体・所有権・占有権等のためにのみ正当防衛をなしうと見た限定主義1)が捨てられ、自由のためにも、名誉のためにも、2)氏名権のためにも、肖像権のためにも、3)すべての法益のために、正当防衛をなしうと見られるに至つたことである。
1) ロォマ法は、生命・身体・所有権・占有等のためにのみ正当防衛を許したに過ぎなかつた(Titze, S. 50 ff.)。ゲルマン法も、ほぼ同一限界を画してゐた(Titze, S. 37 ff.)。ドイツ普通法の学説はこれに反し、すべての法益のために正当防衛を行ひうとした。立法においては、Sächs. GB. §178 ff., Schweiz. Alt. O. R. 56が、はじめて一般主義をとつた。
2) ドイツ帝国裁判所は、演説者が聴衆の中のある人の名誉を毀損しはじめた刹那、その者立つて『黙れ、黙れ』と叫んだ事件に関し、かくのごときは、演説の妨害にあらずして名誉の防衛(Ehrennotwehr)なり。何人も法益侵害の終了するまで忍耐するの要なし。侵害のはじまらんとし、若くはなほ続かんとする際、未然にこれを防止することをうと判示した(Entsch. d. Reichsg. in Strafs. 21, Nr. 62)。
3) Keyssner, Das R. am eigenen Bilde, S. 28.
ハ (二)は、いはゆる可侵貨物(Verletzliches Gut)、すなはち防衛行為を以て反撃しうる貨物の範囲の大いに広まつたことである。従前は小なる法益を擁護するために大なる法益を反撃してはならない、それをすると防衛過剰(Notwehrexzess)になるといはれてゐたが、今は、過剰の有無を防衛者の意思によつて決す。防衛の目的に出づるかぎり、より大なる法益を反撃しても過剰にならない、防衛の目的に出なければ——復讐等の目的からなせば——より小なる法益を反撃しても過剰になると見る。客観的なる法益の大小によらず、主観的なる防衛者の意思によつて過剰かどうかをきめるのである。その結果、かなり安心して防衛権を揮ひうることになつた。
1) ドイツ帝国裁判所は、相手が侮辱の身振りを示したからとて、これを面打した事件に関し、面打は元来名誉防衛に適する行為にあらざるが故に、これを以て、防衛の目的に出でたる反撃と見ることをえず、むしろ新たなる追撃と見ざるべからずと判示した(Deutsch. Juristen-Zeit. 1909, S. 1091)。
三 対物防衛 (Sachwehr)
イ 対物防衛とは、他人の物から生じた急迫の危難を防衛するために、法益の主体が、危難の原因たる他人の物を毀損しうることである。1)
この法則もすこぶる古い——ことにゲルマン法に顕著に出てゐた2)——けだし他人の不正侵害を忍容する必要のないやうに、他人の物からの危難を忍容する必要もない筈。他人に対して正当防衛をなしうるならば、他人の物に対しても対物防衛をなしうべき理であるからである。
1) 対物防衛(Sachwehr)の語は、Kohlerに出る(Kohler, Lehrb. d. bürgerl. Rechts, I. S. 212 ff.)。
2) 田地を荒す他人の動物は、損害賠償責任を生ずることなしに、これを殺し又は傷けうといふ類の規定が多かつた(Titze, S. 44 ff.)。
ロ が、ここにもやはり、(一)受衛貨物の拡大と、(二)可侵貨物の拡大と眼につく——中世の頃は、生命や身体乃至不動産所有権の防衛のために対物防衛をなすことが許されてゐた位のものであつたが、1)今はすべての財産と人的利益とのために、対物防衛をなしうるのである。また中世の頃は、害をなす他人の動物を侵撃しえただけで、動物以外の物は、いかに危険でも侵撃するわけに行かなかつたが、2)今は、すべての種類の物に対し防衛行為をなしうるのである。3)
1) Titze, S. 44 ff.
2) Titze, S. 44 ff.
3) Preuss. Ldr. I, 9 §155は、生命および健康を防衛するために、害をなす他人の動物を反撃しうと規定してゐたが、同国の判例は、生命・健康以外の法益のためにも対物防衛をなしうることを認め、動物以外の他人の物に対しても対物防衛をなしうることを認めてゐた(Rechtsp. des O. T. 17, S. 261)。
四 緊急避難行為 (Notstandhandlung)
イ 緊急避難行為とは、急迫の危難を避けるために、危難の発生に関係なき他人の貨物、すなはちいはゆる中立貨物(neutrales Gut)を蹂躙しうることである。
かかる思想は、ロォマ法にない。1)ゲルマンには、明瞭にあつたが、2)『中立貨物の蹂躙』といふ言葉の響きの恐ろしさに、近世法典は、これを明文に言明することを避けてきた。3)箇別的には海商法における荷投げ(Seewurf)とか、物権法における隣地通行とか、必要排水とか、避難権の思想を前提とするにあらざれば認めえぬものを認めてゐたが、一般的に、『急迫の場合、他人の権利圏内に侵入しう』といひ切る勇気はなかつたのである。ドイツ民法に至つてとうとうこれを条文に掲載した(九〇四条)。スイスおよびオォストリアがこれに做つた。4)その他の国も、殆ど自然法的(beinahe naturrechtlich)だとして、これを認めるやうになつた。5)
1) Titze, S. 52 ff.
2) ゲルマンでは、諺にも、,,Not kennt kein Gebot,`` ,,ein besser Recht ist Leibesnot, als Herrngebot,`` ,,Not sucht Brot, wo sie es findet``などといつたほど(Vgl. Graf=Dietherr, Deutsch. Rechtssprichwörter S. 388 ff.)、広く緊急避難権を認めてゐた。彼らは、緊急の場合には、隣人の助力を乞ふこともでき、隣人のより小なる法益を犠牲にすることもできると見てゐたのである(Wilda, Straft. d. Germanen, S. 959)。
3) Titze, S. 65.
4) Schweiz. neu O. R. 52 II. Österr. GB. §1306 a (Nov. III, §156).
5) 独法が緊急避難の規定を設けたのは、確定法文からである。第一および第二の草案にはまだなかつた。故に一草の模倣たるわが民法にも緊急避難の規定はないのである。七二〇条二項は、対物防衛の規定で、通説のいふやうに、緊急避難の規定ではないのである。
ロ 緊急避難は、基礎を法益の比較におく。大なる法益を救出するために小なる法益を蹂躙するは、あへて不合理ならずとの基礎からである。1)故にそれは、可侵貨物の著しく(unverhaltnismässig)小さき場合にだけ、許される。対等又はより大なる他人の法益を犠牲にして自己の法益を救出するわけには行かぬのである。Rudolf Merkelはおもしろく例示した——溺れんとする人が他人のボォトにかぢりつき、凍えんとする旅人が他人の小屋にもぐりこみ、着てゐる衣服に火のついた人が他人のバケツの水をかぶるとき、彼は緊急避難行為をしてゐるのだと。2)飛行機に故障を生じて他人の田畑へ不時着陸するがごとき、村への溢水をふせぐために人住まぬ対岸の堤防を決潰するがごとき、またもとより緊急避難行為といへるであらう。むろんこれをなすに所有権者の同意を要しはしない。彼の意に反して彼の物を蹂躙しうるのである。3)所有権者は忍容せねばならぬのである。
1) v. Tuhr, allg. Teil, II. 2, S. 601.
2) Rudolf Merkel, Die Kollision rechtsmässiger Interessen u. d. Schadenersatzpflicht bei rechtsmässigen Handlungen, S. 37 f.
3) v. Tuhr, a. a. O. S. 602.
ハ 避難行為を以て第三者の中立貨物を侵害した者は、あとから補償せねばならないとされてゐる。けだし大法益救出のために小法益を犠牲にすること・そのことは止むをえないが、他人の出費において自己の法益を救出してはならない、避難行為を以て第三者に加へた損害は、避難者が自己の法益の救出のために要した費用であり、とりも直さず一種の保存費であるから、出費者に対して補償せねばならぬといふのである。避難行為そのものは合法だが、それによつて損害補償の責任を生ずと見るのである。1)
1) v. Tuhr, Notstand im Zivilr. S. 135
第十二節 公力的予防手段—不作為の訴
一 序 説
人的利益の事前的予防手段として正当防衛・対物防衛および緊急避難の発達を来たしたといふことを、前節にのべたが、事前的予防手段はこれに尽きない。外に不作為の訴がある。前三者の私力的なるに反して、これは公力的である。いまその発達経過を見ると——
二 適用範囲の拡大
イ ロォマ法においては不作為の訴は、所有権・地上権・永小作権・質権・占有等に対する侵害を、未然に防止するために起しえたに過ぎなんだが、1)十九世紀中普通法の判例は、大いに不作為の訴の適用範囲を広め、これによつて保護されうるものとして新たに種々の権利を加へた。2)人格権の中からは、氏名権がその撰に入つた。3)
1) Elzbacher, Unterlassungsklage, S. 6 ff.
2) Elzbacher, S. 18 ff.
3) 一八五一年五月七日、Celle Oberappellationsgerichtは、被告が、その私生児に、原告の姓を附してゐるのを、止めさせてもらひたいといふ原告の請求を理由ありとした(Seuffert's Archiv 19, Nr. 114.)。一八九二年四月十一日の帝国裁判所の判決も、氏名権侵害行為の停止を求める訴を是認した(Entsch. d. Reichsg. i. Zivilsachen. 129 Nr. 32)。
ロ 地方法も拡張の方針をとつて進んだ。プロイセン州法のごとき明示的には、占有の防衛のために不作為の訴を起しうる旨を規定してゐただけだつたが、1)判例は、他の物権のためにもこれを認め、物権以外の権利のためにも往々これを認めた。2)氏名権はここでも、不作為の訴を起しうる権利の一つとして数へられた。3) 4)
1) Preuss. Ldr. I, 7 §151.
2) Striethorst's Archiv 16, Nr. 17, 15 Nr. 70, 44 Nr. 34.
3) Entsch. d. Obertribunals 15, Nr. 35.
4) ザクセンでは、民法が不作為の訴を起しうる場合を、比較的詳細に列記してゐたため(Sächs. GB. §§321, 532, 325, 326, 327, 566, 205, 503, 762)、却つてこの訴の自由発達を妨げ、氏名権等のためにこれを認めるまでに至らなんだ(Elzbacher, S. 61 ff.)。
ハ フランスでは、不作為の訴に関する規定全くなかつたため、却つてこの訴の発達に便利した。所有権その他の物権のためにはもちろん、氏名権防衛のためにも、肖像権防衛のためにも、これを起しえたのであつた。1)小説家Alexander Dumasが、ある写真師に対し、彼がある婦人と写してゐる写真を市場に売りひろめることを中止すべく要求し、勝訴した事件2)のごとき有名である。
1) Elzbacher, S. 44 ff.
2) Sirey Recueil 1868 2, 41.
三 不作為の訴による人的利益の保護
イ 現代の学説判例に至つては、不作為の訴の適用範囲を極度に広め、凡そ絶対権の性質を有する権利が侵害を受けんとしてゐる場合には、権利者は、不作為の訴を起して侵害を未然に防ぐことができると見てゐる。人格権の限りにおいても、今はもう氏名権と肖像権とだけでない。すべての人的利益が、不作為の訴を以て鎧はれてゐるのである。すなはち(一)生命・身体のためにもこれを起すことができる。通行人に毎度犬をけしかける者ある場合に、その者に対してこれを起し、通行人に危険を感じさせる程度の大速力で毎度馬を駆る者ある場合に、その者に対してこれを起すがごとし。二階の窓際に植木鉢をつき出し、下を通る者に危険を感じさせる場合、森に仕掛猟銃を仕掛け、里人に危険を感じさせる場合また同じい。(二)健康のためにも起しうる。伝染病予防法によつて交通を遮断されてゐる区域内にみだりに出入する者ある場合に、その者の同居人が、その者に対し不作為請求をなすごとし。(三)自由のためにも起しうる。ストライキした労働者が、工場へ入らんとする労働者を腕力で阻止した場合のごとし。(四)名誉のためには、最もしばしば起されてゐる——引つづき無根の事実の流布されるのを防止する等のために。
ロ 宗教的・倫理的乃至美的感情を、一種の人的利益と見る論者は、この種感情利益の防衛のためにも不作為の訴を起しうと説く。例へば礼拝所等に対して公然不敬の行為をなす者、公然猥褻の行為をなす者、公然動物虐待をなす者、異常の騒音を発する者等々に対しては、あへて官憲の取締を待たず、私人自ら不作為の訴を起しうと説く。1)
1) Elzbacher, S. 138.
結 論
結論として少しく綜合的見地から、人格権法発展の全過程を回顧して見るに——
一 人格権法発達の動因としての個人主義
イ まづ気づくは、人的利益の個人的分解である。例へば昔は、家族の一員が侮辱を受けると、家長も侮辱されたとして訴を起しえたが、今では、侮辱の直接対象となつた家族だけ、原告となることができる。昔は、娘が他人に凌辱されると親もまた訴を起しえたが、今は、娘ひとり原告となることができる。雇人が侮辱されたといつて主人が怒り、団体員の一人が侮辱されたといつて全員怒るといふやうな現象は、遠い昔の語草となつてしまつた。有形財が各個人に分属するやうに、無形財も各個人に分属するのである。1)
1) 六三頁・七二頁参照。
ロ 損害賠償請求が、加害より被害を中心とするに至つたことも著しく眼につく。昔は、被害額の冷静な計算よりも、加害者その人を悪む心の方が先走り、被害の有無・程度をさしおいて、加害者を責めたが、今は、違法があつたといふだけでは賠償請求権なく、損害があつたといふだけでも請求権なく、損害を損害と感じる損害関心者(Beschädigte)あるとき、はじめてその者が賠償請求権を取得すると見る。その結果、生命侵害の場合に、相続人が、死者から損害賠償請求権を相続するといふやうなことが不可能になつた。死者は損害関心者にあらず、故に賠償請求権なし、故にこれを相続人に伝ふることをえずとの論理からである。遺族にして損害賠償請求をなさうとならば、各自その被害を理由とせねばならない、単に近親が殺されたからといはず、近親の被殺によつて自分自身扶養請求請求権を失ふに至つたとか、労務請求権を失ふに至つたとか、精神的安楽を害されたとか、いはねばならぬことになつた。
1) 三〇頁参照。
ハ 独立法益としての人的利益が、その数を増したことも顕著である。昔は人的利益は、刑法又は行政法の保護を受けたのみで、私法の保護は受けなかつた。強ゐて数へても、生命・身体・自由・名誉位が、私法的保護の対象となつてゐたに過ぎなんだ。信用・肖像・氏名・秘密・精神的自由等が、私法の保護を受けるに至つたのは、まことに最近の事である。
ニ 人的利益の侵害によつて生じた損害の額の計算方法が、正確になつたことも驚異である。昔は有形財のみを利益と考へ、その侵害のみを損害と見てゐたが、今は、精神上の安楽をも利益と見、その攪乱に対して慰藉料を求めうとする。有形損害の計算方法も厳密になり、受けたる損害の外、失へる利益を常に加算するやうになつた。失へる利益の計算それ自身、またいかに精確化しつつあるかは、身体侵害の賠償についてのべた所に見よ。1)
1) 三五頁以下参照。
ホ さらに近代に入つてから、人的利益の侵害に対する予防手段の発達を見た。緊急避難権と不作為の訴とがそれである。損害賠償・慰藉料請求といふやうな事後の救済で満足せず、事前の手段をも併用するに至つたのである。罹病を恐怖する者は、治療法(Terapie)よりも予防法(Prophylax)に重きをおく。自己の利益の侵害されることを極度に恐怖する現代人は、損害賠償・慰藉料請求では事遅し、事前の救済なかるべからずとして、ここに、予防手段の私力的なものとして緊急避難権を発達させ、その公力的なものとして不作為の訴を発達させるに至つたのである。
ヘ それ十九世紀は、すべての人間を商人化した。遺利の発見と損害の回避とに、人各々鋭敏な注意を輝かすに至つた。人的利益なる新利益を発見し、あらたにこれを私法の保護の下におくに至つたのも——これを個人的に分裂せしめ、各人恰も有形財を分有するやうに、無形財をも分有すと見るに至つたのも——被害を中心とし、被害者のみ損害賠償請求権を取得すと見るに至つたのも——賠償額の計算を厳密にし、有形損害ばかりでなく、無形損害や失へる利益やを常に加味するに至つたのも——さらにまた、不作為請求の訴といふやうな予防手段を案出するに至つたのも——詮ずればみな、各人自利の貴重に眼ざめ、自利に対する法的保護の、いやが上にも完全ならんことを所期した結果に外ならない。やはり利己心が、人格権法発展の根本動因であつたのである。
二 人格権の社会化
しかし風多き冬の日にも、木の間を洩れる日の光りの斑らに地上に輝くのを見るやうに、自我の主張のあまりにも執拗な人格権法の表面にも、革新の第二形相はすでにちらついてゐるのである。人格権社会化の傾向、これである。
イ すでにわれわれは、「肖像権」の節下において、ドイツ肖像権法制定の際、なるべく個人の羞恥心を擁護し、肖像本人の同意なければ、複製頒布しえぬことに定めねばならぬといふ個人本位の意見と、なるべく社会の好奇心を擁護し、少なくとも公的性質を有する人の肖像権は極力これを制限し、無断でこれらの人の肖像を複製頒布しうることにせねばならぬといふ社会本位の主張と、両々相対峙したが、法律は遂に後者に組みし、非常に多く、無同意複製の場合を認めたといふことをのべた。漫画についても、直ちにこれを本人に対する侮辱なりと見る説衰へ、漫画によつて社会は、『笑』を増す。故に本人は社会のために、無邪気な笑の材料となることを甘受せねばならぬと見る説、次第に勝利をえつつありとのべた。「氏名権」の節下においては、取引の安全のために、氏名権者の氏名権行使の停止される場合あることを注意した——これらが人格権の社会化以外の何ものであらうか?
いな、ひとり氏名権と肖像権とだけでない。身体でも自由でも名誉でも信用でも、すべて人的利益の主張が、公共善の前に大いに自制せねばならぬと見られることになつたのである。
ロ おもふに個人は、個々の個人でなしに社会の個人である。社会構成の微分子である。故に社会の維持および発展のためには、自我の主張を抑へねばならぬ。その抑へねばならぬ程度をわれわれは、『市民生活における忍容限界』とよぶ。忍容限界を越えた人格侵害のみが不法行為となるのである。忍容限界内の小侵害は、損害賠償の理由とも、慰藉料請求の理由ともならぬのである。1)電車の中で足を踏まれた。身体侵害なりとして損害賠償を求めうるや?いはく否。なぜなればそれは忍容限界内の小侵害に過ぎぬから。騒音のために安眠を妨げられた。精神的安慰を害されたとして慰藉料を請求しうるや?いはく否。これまた忍容限界内の小出来事に過ぎぬから。都会生活の密集化と共に、市民の忍容義務はますます重もるであらう。人格権主張の範囲がますます狭ばまるであらう。人格権なるものは、十九世紀利己主義の産んだ小市民的個人意識に過ぎぬ。所有権の社会化されねばならず、また現に社会化しつつあるやうに、人格権も社会化されねばならず、また現に社会化しつつあるのである。
1) スイス債務法四十九条は、慰藉料の請求を、過責又は侵害の特に重大な場合に限つた。軽過失又は軽侵害の場合には、損害賠償を求めうるのみにて、慰藉料請求をなしえずとした。軽微なる人格衝突は、人間交際に常時見るところにして、各人相互に寛容ならざるべからずと見たためである。人的利益の主我的主張を相当に抑制した規定といへるであらう。