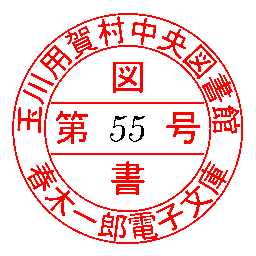
頃日接手したるRevue historique de droit français et étranger (1926, No. 4)は吾人羅馬法研究者に一大悲報を伝へたり即ち欧州羅馬法学界の一大権威Paul Frédéric Girard氏は長き疾患の後、遂に遠逝せられたること是れなり氏の風貌は門弟より氏に献呈したるÉtudes d'histoire juridique, T. 1 (1913)の巻頭に掲げられたる写真に依りて予の眼に触れたること屡々なりしが去る大正十一年【一千九百二十二年】六月欧米巡回の途次巴里法科大学楼上の一室に於て親しく氏のviva voxを聴くの光栄に浴したり是れを以て予は殆んど三十年の久きに亘りて氏のmanuelの門弟たるの故のみに因らず氏の遠逝を悲むの情、切なるものあり茲に聊か氏の功績の一端を述べて氏の英霊に敬意を表せんと欲す
氏は一千八百七十五年De la condition civile des aliénés (Thése pour le doctrat, Rennes)を書きたる以降羅馬法学に関する氏の絶筆les préliminaires de la renaisance du droit romain (Revue historique, 1922, pp. 5--46)の公表を見るに至りたる約半世紀の間に氏は茲に枚挙すること能はざる程多数の羅馬法関係の極めて有益なる著作物【広義】を公けにしたり其の中に左の数種あり
一 Droit public romain de Mommsen (traduction française, 1889--1895)Girard氏は数年に亘るの努力を以て不朽の羅馬法学者Theodor Mommsenのclassical workとして学会周知の羅馬国法を仏訳せり氏は右の大著の翻訳に従事完成せるに因りてMommsenの神髄を得たるものの如く随て氏の研究が厳に法源的なることMommsenのそれの如し
二 Manuel élémentaire de droit romain, 1896 (sept. éd. 1924)氏の名が世界の羅馬法学界に知らるる所以のものは実に此の大著あるが故なり此の書は簡単なる歴史的緒言を第一巻に置き第二巻以下に於て羅馬私法全体に亘りて比較的詳細なる組織的説明を為したり題してmanuel élémentaireと云ふと雖も各所に引用せらるる多数の文献に遡りて研究すれば其の含蓄する所頗る広く論旨又極めて深く一言半句だも苟にすること無く又各制度の歴史的変遷を明かにせんことに至大の努力を費やしたるものあるは予の実に敬服に堪へざる所なり此の書数版を重ね又独訳(Geschichte und System des römischen Rechtes übersetzt von R. Von Mayr, 1908 此の訳本中にはMayr自身の附加あり其の中には往々極めて有益のものあり)伊訳(Manuale elementare di diritto romano tradotto da C. Longo, 1909)及び其の第一巻即ち歴史的緒言の部分の英訳(A Short History of Roman Law by Girard, translated by Defroy and Camerou, 1906)ありWindscheid, Lehrbuch des Pandektenrechtsは独逸普通法教科書中にて第一位を占むることは蓋し何人と雖も之を認むるならんGirard氏のmanuel élémentaire de droit romainは純然たる羅馬私法を組織的に説きたる現代書中の白眉なりと称するも決して過言に非ずと信ず
三 Histoire de l'organisation judiciaire des romains I (les six premiers siècles de Rome), 1901羅馬民刑裁判所構成史を説きたるものにして完成に至らずRevue historique (1924, Octobre-Décembre, No. 4, p. 748)に拠ればGirard氏は本書の第二巻(les jurés de la république)中の一章Decemviri litibus judicandisをYale Law Journalに寄稿するの約を為したり然れども疾患に罹りし氏が果して其の約を履行したりしや否やを知らず【因みに記す先年予は翁に会見の際、翁は本書の続稿を起草中なりや否やを伺ひたるに然りと答へられたりと雖も翁は其の後幾許も無く筆を執るも堪へざる病に罹られたることを聞きたり故に翁の遺稿として公刊せられ得べき程度に続稿整頓しあるや否やを知らず】
四 Textes de droit romain (5ème éd. 1923)此の書はBruns, Fontes iuris Romani antique又はRiccobono-Baviera-Ferrini, Fontes iuris Romani Anteiustinianiの如き法源集にして各法源の原文の前に仏文を以て簡単に解題を附したり羅馬法研究者が一日も座右に欠くべからざる書なり
五 Mélanges de droit romain 2, 1912--1923Girard氏の羅馬法に関する論文中の重もなるもの若干は右に掲ぐる雑纂中に集録せらる其の中にて茲に左の二大論文に付て聊か述ぶる所あらんとす
(イ)l'histoire des XII Tables (Mélanges de droit romain 1, pp. 3--64. N.R.H. XXVI pp. 381--436)【此の論文とGirard氏が一千九百十三年ロンドン大学に於て為したる十二表法に関する講演(la Loi des XII Tables, London, University of London Press, 1914, voircomptes rendues par L. Debray, N. R. H. pp. 162--165, 1916)と区別することを要す】十二表法制定に関する古典の記事の詳細の点に付ては十九世紀末に至るまでに既に多数の学者問題と為し其の事実に非ざることを論じたりと雖も十二表法が紀元前四百五十年頃の立法行為に依りて成りたるの一事に付ては之を問題と為すの学者出でざりしが十九世紀末(1898)に於て伊太利の羅馬史家Ettore Paisは淵源の精細なる研究を遂げ現今十二表法(予は此の機会に於て我邦の学者又は教育者にして十二銅表なる名称を用ゐらるる君子に教を乞ふ一事あり即ち何故に十二銅表なる名称を用ゐらるるか是れなり)として知らるる法典には紀元前五世紀に成りたる部分も存し其の後数回の立法に依りて追加せられ遂に約一百五十年を経て最終の体形を具ふるに至りたることを提唱せり【以上Pais説の要旨はBruns-Lenel, Geschichte und Quellen des römischen Rechts in der Holtzendorff-Kohlers Encyclopädie der Rechtswissenschaft I. S. 325, 2te Aufl. 1915に拠るPais説を同様に紹介するはPetro de Francisci, Storia del diritto romano, V. I. p. 195, 1926 Theodor MommsenはEttore Paisの説を紹介して十二表法をCn. Flaviusの作にして羅馬の建国五世紀の半頃のものなりと論ぜりと為し(Mommsen, Gesammelte Schriften III, S. 373, 1907)KippはPaisの論旨は十二表法を以てius civile Flavianumなり随て紀元前三百年頃の私人の法律書に過ぎざるものなるか後世の羅馬人が之を官命に依りて成りたる法典と見たるものなりとす(Kipp, Geschichte der Quellen des römischen Rechts S. 35, Anmk. 4 4te Aufl. 1919)Mommsen, Kipp等のPais説の論旨の紹介は或は不十分なるものの如し(Beseler, Uebersicht über die italienische Rechts literatur 1915--1922, in der Z.-S.-Stif. 25ter Band, S. 551 rom. Abt. 1925】Paisに続きてリオンの法学先生Lambertは十二表法を以てSextus Ælius Petus Catus【一百九十八年執政官】の私著Ius Ælianumと同一視したり此の如くにしてLambertはPaisに比すれば十二表法の成立年代を約一百年引き下げ一層極端の説を為したりPais-Lambertの紀元前四百五十年頃の制定に係るものと認められたる十二表法抹消説は一時欧州学界に一大波紋を引き起したりしがGirard氏は前記の論文を起草し之をN. R. H.を以て公けにし新懐疑学者の所論を根本的に撃滅せんことを試たり氏の論旨の大綱は左の如し十二表法には農業時代の制定法と見るべき数多の規定あり又用語も紀元前四百五十年頃のものにして一世紀半も後のものに非ず且つ此の如き重要なる法律文献がLivius等が記す時代の産物に非ずして一世紀半も後のものなりせば後世の羅馬人が其の事実を伝へざるは奇怪なりと云ふに在り【Girard氏の論旨に関してはKipp, a. a. O.参照】Girard氏の伝来説擁護の論文の功績空しからず羅馬史の考証学者及び比較法学者に依りて引き起されたる波紋は幾許もなく鎮静に帰したり
(ロ)la date de la loi Æbutia (Mélanges de Girard I, pp. 68--174; Z.-S.-Stif. XIV, SS. 1--54, rom. Abt. 1893; N.R.H. XXI, pp. 249--294, 1897)lex Æbutiaの制定年代に付ては学者間に種々の想像説ありしがGirard氏は最も学問的の方法に依りて605(149 B. C.)--628(126)間の制定法なりと決定したり氏の説く所にては建国六百五年まではlegis actioの手続のみに依りて訴訟したるの証拠あり又六百二十八年以後に於てはlex Æbutiaを適用したる証拠ありGirard氏がlex Æbutiaの制定年代を上記の年代の間なりと決定したるの方法は必ずしも此の創見に出でたるものに非ず嘗つてPernice氏がLabeoの生年を略紀元前五十年【羅馬建国七百九十四年Pernice, Labeo I, SS. 9--11, 1873】に確定したるも又此の方法に拠りたり【Herzenがactio hypothecariaの制定年代を決するにも又此の方法を用ゐたりHerzen, Origine de l'hypotheque romaine Ch. I-Fixation de la date des actiones hypothecaires, p. 167 et seq. 1899】此の方法は問題たる事件が一定の時代には未だ存在せざることを確実なる証拠に拠りて決し又一方に於ては確実なる証拠に拠りて問題たる事件が既に存在したることを決し漸次に両極の間隙を減縮し問題たる事件発生年代を一定の年限間若は大約何年と決するものとす【Girard, Manuel, p. 1055, 7ème éd. 1924】由来羅馬法に於ける某lex又は某actioの制定年代を定むるには某の名が当該のlex又はactioに付せらるるを以て某が何年に執政官たり又は法務官たりしの記録を唯一の証拠と為すの方法に依りたる場合多かりしが此の方法は実は必ずしも常に確実なる結果を得べきものと云ふことを得ず
Girard氏が始めて羅馬法研究者として顕はれたる頃に於て一方には仏国の羅馬法家の一部分(Ortoland, Accariasの如き)は主として儒帝法学撮要ガーイウスの羅馬法解説其の他の法律的淵源に拠りて斯法を研究し羅馬法規定の一種の文理解釈者流あり又一方には啻に法律的淵源に拠るのみならず非法律的淵源をも合せて研究し且つ法制史の諸補助学(言語学金石学比較法学等)の力をも藉りて羅馬法制の歴史的進展の経路を明かにせんとするPaul Gide一派の羅馬法学者出でたりGirard氏は独逸羅馬法学者の影響を受けて新進の羅馬法研究学者中に加はり約半世紀に亘るの努力の結果、遂に仏国に於けるEcole de Girardなる羅馬法研究派の基礎を確立したるは仏国の法学者と共に吾人が永遠に記念すべき事なり。