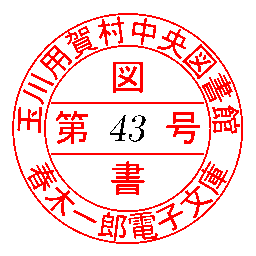
予千八百九十九年四月十七日ヨリ八月十五日ニ至ル伯林大学夏学期ニ於テVahlen先生ノErklärung der Bücher Cicero's de legibus mit besonderer Rücksicht auf das Sacral-und Staatsrecht der Römerノ講筵ニ侍シタリ本篇ヲ草スルニ当リ先生ニ負フ所大ナルコトヲ告白シ併セテ先生ノ定本M. Tullii Ciceronis de legibus libri (第二版千八百八十三年)ヲ使用シタルコトヲ附記ス一 「法律論」ノ著作ノ時代 「法律論」ハシセロ老年ノ作ノ一ナリ何時此ヲ書キタルカシセロ明言セス又羅馬時代ノ典籍中拠ルヘキノ確カナル淵源ヲ欠クト雖紀元前五十二年一月廿日ニ殺サレタルClodiusノ事ニ就テハ「法律論」第二巻第十七章第四十二節ニ説ク所アリ而シテ五十一年五月ニシセロハCicilia県知事トシテ同所ニ赴任シタル後四十三年十二月七日シセロカ殺サレタル時迄シセロハ潜心文筆ニ従事スルノ閑ナカリシヲ以テ考フルニ此書ハ多分シセロノ五十六歳ノ時即チ紀元前五十二年ヨリ五十一年ノ間頃ニ書カレタルモノナリ書中紀元前四十八年九月三十日前ニ没シタルaugurノAppius Claudiusヲ尚存命者トシテ記シ【第二巻第十三章第三十二節】又Pompeius【四十八年ニ殺サル】ニ就テモ屡存命者トシテ言ヘル等ノ事実ハ此書カ何時頃迄ニ書カレタルカヲ考証スルノ資料タリ
二 「法律論」ハ何人カ公ケニシタルカ シセロカ其生前自カラ「法律論」ヲ公ケニシタルカ否カモ何等拠ルヘキノ資料ヲ欠ク千八百四十二年Bakeカ「法律論」ノ定本ヲ出タシタル以来多分ハ他人カ公ケニ為シタルモノナリトノ説普通ニ行ナハレ又信ニ近カシ若モシセロ自カラ此書ヲ公ケニセシモノタリシナランニハ彼カ自カラ巻頭ニ緒言(prooemium)ヲ附シタリシナラン然ルニ此書ハ開巻第一ヨリ直チニ談論ニ入ル(Teuffel, Gesch. d. röm. Lit. Bd. I §184)
三 「法律論」ノ巻数 此書ノ全部伝ラス現存スルハ始ノ三巻【多少ノ欠文アリ】及ヒ僅少ノ欠文ナリ而シテ本来何巻タリシモノナルカ詳カナラス然レトモ少ナクトモ五巻ハ存シタリシコトハ確カナリ(Macrobius Saturn. 6, 4, 8. et Cicero in quinto de legibus)想像ヲ逞フセハ此書ハ本来シセロカ前ニ書キタル「国家論」ノ続稿ト見ルヘキモノナレハ「国家論」ノ如ク亦六巻ヨリ成リタリシモノナラン
四 「国家論」ト「法律論」トノ関係 シセロハ紀元前五十四年ニ於テ「国家論」ヲ著ハシ如何ナル国体カ最良ナルカヲ論シタリ「国家論」ト「法律論」トノ関係ハシセロノ親友Atticusノ言ニ徴シテ明カナリAtticusハ曰ク「汝ハ【シセロヲ指ス】既ニ最モ良キ国体ノ何タルカニ就テ論シタルカ故ニ汝ハ又法律論ヲ書クヘキハ当然ノ事トス」云々【「法律論」第一巻第五章第十五節】
五 シセロノ抱負 シセロハ其凌駕センコトヲ希望シタルデモステネスノ如ク確カニ羅馬第一流ノ弁論家ナリ彼ノ政治演説又民刑事ノ弁論ハ是ヲ証ス彼ハ精鋭ナル論法ニ依リテ聴者ヲシテ哀心道理ニ服セシムルコト能ハサリシト雖希臘羅馬ノ文学ニ精通シタルヲ以テ修辞絶妙ナルノミナラス幾多ノ師ニ就キ弁論術ヲ演習シ又有名ナル俳優ノ口吻働作ヲ学ヒタルヲ以テ彼ハ善ク聴者ノ感情ヲ動カスコトヲ得タリ又シセロハ大散文家ナリ羅馬ノ散文ヲ確立シ羅馬文学史上ニ一新時期ヲ画セリ吾人ハシセロヲ以テ大弁論家大散文家タリシコトヲ認ムト雖彼カ抱負シタルカ如ク政治家哲学者法学者トシテ彼ヲ見ル能ハスシセロハ一度羅馬ノ執政官ト為リ政治界ノ栄誉ヲ極メタリト雖政治家ニ必要ナル天下ノ大勢ヲ達観スルノ明ナク加フルニ節操ニ乏シク遂ニ其頭ヲ羅馬市演壇上ニ曝ラスノ末路ヲ来タシタリ彼ハ亦哲学者ニ非ス彼ハ明達ナル散文ヲ以テ多数ノ哲学関係書ヲ著ハシタリト雖皆希臘哲学者ノ思想ヲ羅列シタルニ過キスシテ何等ノ新想トシテ見ルヘキモノナシ哲学史ハシセロノ得意タリシ所ナリト雖哲学ハ其長シタル学科ニ非ス又シセロハ其経歴上法律ノ大体殊ニ国法ヲ知リタリト雖固ヨリServius Sulpiciusニ比スヘキ法学者ニ非ス然レトモ彼ハ其無限ノ知識慾及ヒ甚タシキ自負心ニ駆ラレde iure civili in artem redigendoヲ著ハシ組織的ニ羅馬私法ヲ解説スルノ方法ヲ示メシタリ此書今日ニ伝ハラスト雖後世羅馬ノ法学者カ是ヲ知ラサルモノノ如ク何等引用シタルコト無キヲ以テ見レハ法学専門家ノ手ニスルノ必要ナカリシモノト推測スヘキナリ(Krueger, Geschichte der Quellen. S. 77--S. 78)然レトモシセロカ同胞ニ尽サントセシ志ハ実ニ賞賛スヘク彼ハ希臘思想ヲ祖国ニ輸入スルコトヲ以テ素願ト為シタリde divinationeノ第二巻第一節ニ曰ク
一 予ハ如何ナル方法ニ依リテ最多数ノ人ニ利益ヲ与ヘ以テ国家ニ貢献シ得ヘキカヲ屡慎重ニ考慮シタリシカ高尚ナル学術ニ於テ同胞ヲ指導スルノ外他ノ良法ニ想到スルコト能ハス而シテ予ハ既ニ多数ノ著書ヲ為シ此方法ニ依リテ聊カ素志ノ一端ヲ得タルコトヲ満足スHortensiusト題シタル書ヲ以テ同胞ニ向ツテ哲学ノ研鑚ヲ熱心ニ勧告シタリ又四巻ノAcademicaeヲ以テ最モ穏健且統一ノ美アル哲学思想ヲ示メシタリ尚シセロハ其著書de consolatione, de senectute, Cato 三巻ノde oratore四巻ノBrutus五巻ノorator等ヲ算上ケ著書目録ヲ終ハレリ
二 又哲学ノ根本ハ善及ヒ悪ノ限界ヲ知ルニ在ルカ故ニ予ハ此問題ヲ五巻ノ書(de finibusヲ指ス)ニ於テ是ニ関スル種々ノ学説ヲ解説シタリ又五巻ノTusculanae disputationesニ於テ如何ニセハ幸福ナル生活ヲ為シ得ヘキカヲ明カニセリ【本節以下略ス】
三 此等ノ著述ヲ為シタル後予ハ三巻ノde natura deorumヲ完成シテ神ノ本質ニ関スル一切ノ問題ヲ包含セシメタリ而シテ予ハ現在此等ノ巻ニ於テde divinationeノ著述ニ着手シde natura deorumノ補遺タラシメントスde divinationeヲ完成シタル後ニハ進ムテde fato論セントス是ヲ以テ予ハ神ニ関スル一切ノ問題ヲ尽シタルモノト考フ而シテ予ハ以上ノ目録中ニ予カ国務ニ参与シタル項ニ書キタル六巻ノde republicaヲモ加ヘントス国家論ハ哲学ノ大問題ニシテPlato, Aristoteles, Theophrastus及ヒPeripatetici派ニ属スル学者カ特ニ深ク論シタルモノナリ
右ノ言ニ拠リテシセロノ抱負ヲ見ルヘク又シセロカ国家ニ関スル理論ハ哲学ノ一部ヲ成ストノ見解ヲ抱キタル事ヲ知ルヘキナリシセロハ本来法律学ヲ哲学ノ一部ト為シ法律学ハ哲学ノ根本観念ヨリ研究スヘキモノナリトノ意見ヲ有シタリ【後段参照】
六 「法律論」ノ材料体裁及ヒ主ナル内容 「法律論」ハシセロノ哲学書ノ如ク其材料ヲ希臘ノ哲学者ノ著書殊ニシセロ自カラ言ヘルカ如クプラトオンヲ模倣シ其περινὀμονニ求メタルトコロ少カラスト雖羅馬国法ノ規定中シセロノ理想ニ適合セルモノハ是ヲ材料ト為シタリ而シテシセロカ其材料ト為シタル羅馬国法上ノ規定ハ必スシモ凡テシセロ時代ノ規定ニ非ス寧ロ敬神ノ念慮旺盛ナリシ共和政時代ノ規定多キヲ占ム「法律論」ノ著作時代ト著者カ其理想ニ適合シタル国法上ノ規定カ有効タリシ時代トハ区別シテ「法律論」ヲ読ムコトヲ要ス
「法律論」ノ体裁ハ「国家論」ノ如ク談話体ニシテシセロ自カラ談話人物中ノ主位ヲ占メ其親友Titus Pomponius Atticus【紀元前百九年ニ生マルシセロヨリ三年ノ長年者ナリ】及ヒQuintus【百二年ニ生マレ四十三年ニ殺サルシセロノ弟】ヲ客位ニ置キ客ヨリノ発問又ハ希望ニ応シテシセロノ見解ヲ序シタリ
第一巻ノ重モナル内容ハ法ノ何タルノ解説ナリ第二巻ハ宗教法第三巻ハ官制トス第四巻ハ現存セスト雖刑事法(de iudicis)タリシコトハ疑ヲ容レス【「法律論」第三巻第二十章第四十八節】第五巻ニハ教育法及ヒ風紀法第六巻ニハ私法ヲ説キタリシモノノ如シ(Huschke in der Zeits. f. Rechtsg. XI S. 108)
七 「法律論」第一巻内容ノ梗概 第一巻ハ二十四章ヨリ成ル第一章ヨリ第五章ニ至ル迄ハ本巻ノ主意タル自然法ノ性質ヲ説クニ及ヒタル談話ノ径路ヲ序シ第六章以下ニ於テ自然法ヲ説ク
盛夏ノ某日シセロハ其弟Quintus及ヒ親友Atticusト故郷Arpinumニ於ケルLiris河畔ニ近キ森ノ中ニ鼎座シ懐旧談ヲ為ス話頭歴史ニ及ヒAtticusハシセロノ羅馬史ヲ編纂スルニ適任者タルコトヲ説ク【第二章】Quintusモ亦兄カ其適任ナルコトヲ説キシセロニ慫慂スルニ史ヲ編マンコトヲ以テシタリト雖シセロ時ナキヲ以テ之ヲ辞ス【第三章】是ニ於テAtticus更ラニシセロニ向ツテius civileニ関スル意見ヲ求ムシセロハ法ノ根本観念ニ就キ解説スヘキコトヲ諾スAtticusハシセロノ意ニ和シテ曰ク「然ラハ現代多数ノ学者ノ如ク裁判官ノ告示ニ拠ラス又古人ノ如ク十二表法ニ拠ラス哲理ノ根底ヨリシテ法理ヲ探求スルノ意ナラスヤ」ト【第五章第十七節】是ノ言蓋シシセロノ意ヲ得タルナリUlpianusカ法学ヲ以テ哲学ノ一部分ト為シタルハ(D. 1, 1, 10, 2)必スシモ氏一家ノ私見ニ非ス希臘思想ヲ継受シタル羅馬時代ノ学者ノ通念ナリ
第六章ニ於テシセロハ希臘哲学者ノ法ノ定義ヲ引用シ且自己ノ意見ヲ加ヘテ曰ク「希臘ノ学者ハ法ハ為スヘキコトヲ命シ又為スヘカラサルコトヲ禁スルトコロノ自然ニ存在スル最高条理ナリト定義ス而シテ其条理カ人類ノ霊中ニ確認セラレ且完全ニ了知サレタルトキニ於テ法ヲ為ス」云々【第六章第十八節】シセロハ客観的ニ絶対ノ条理ノ存在ヲ認メ而シテ各人ニ依リ弑サレタル条理即チ法ナリト考ヘタリ
シセロハ法ノ何タルヲ説キタル後νόμος及ヒlexノ語原ヲ説キ曰クνόμοςハνεμω【分配スルコト】ヨリ伝来シlexハlegere【選択スルコト】ヨリ伝来ス而シテlegereハ正及ヒ不正ヲ選択スルノ意ナリ云々ト【第六章第十九節】lexカlegereヨリ来タルト為スノ語原説ハ羅馬時代ノ言語学ノ大家Varroモ説キタリ(de lingua latina 5, 7)然レトモVarroハ読ムノ意義ヲlegereニ附シタリ蓋羅馬ニ於テハ古代ヨリ法案ノ朗読ヲ以テ法制定ノ形式ノ一部ト為シタルノ事実ト一致スシセロハ分配及ヒ選択ヲ以テ法ノ性質ト為シ希臘哲学者ノ思想ト自己ノ見解ノ調和ヲ勉メタリ
宇宙ハ神ノ支配スル所ナリ神ハ人類ニ理性ヲ附与ス理性ヲ有スルノ点ニ於テハ神人間ニ区別ナシ而シテ理性即チ法ナレハ神人ハ此法ニ因リテ連結ス【第八章】
理性ニ反スルノ行為ハ理性ニ反スルコト自体ヲ以テ制裁トス自然法ハ人定法以外ニ存ス人定法ノ制裁ハ不完全ナリ制裁ヲ恐ルルカ故ニ人定法違反ノ行為ヲナササル者ハ未タ理性ニ適合シタル者ト云フ能ハス【第十三章第十四章】
善及ヒ正義ハ理性ノ命スル所ナレハ善ナルカ故又正義ナルカ故ニ是ヲ為スコトヲ要ス【第十八章】
人類ノ行為ハ理性ニ従フヘキモノトス理性ノ認識即チ我ノ認識ハ哲学ノ範囲ニ属ス【第二十二章乃至第二十四章】
シセロカ「法律論」第一巻ニ説キタルコトヲ要約セハ法学ハ哲学ノ一部ナリ理性即チ法ナリ絶対法ナリ自然法ナリ其制裁ハ理性違反ナルコト自体ナリ神人共ニ理性ヲ通有ス理性ノ何タルヲ認識スルハ即チ哲学ノ研究ナリト云フニアリ自然法ノ観念ニ就テハシセロカ「国家論」中ニ既ニ説キタルコトハ一般ニ承認サル然レトモ其文章カ国家論ノ何レノ部分ニ存シタルカニ就テハ定説ナシ唯第三巻中ニ在リタルコトハシセロノ著作研究家多数ノ意見ナリ而シテシセロノ「国家論」中ノ文章ナリトシテ称セラルル自然法ニ関スルモノハLactantius, Inst., VI, ch. 8ニ見ユ此文章ハ実ニ「壮麗」ヲ極メタルモノニシテ本誌第二巻第五号掲載ノ畏友仁保博士ノ「自然法ヲ論ス」ナル論文中【二十六頁】ニ訳出サレタルカ故ニ予ハ今茲ニ訳ヲ省略ス
八 「法律論」第二巻内容ノ梗概 第二巻ハ二十七章ヨリ成ル第一章ニ於テ会談ノ場所ヲFibrenus河中ノ小島ニ変スルコトヲ記ス第四章ニ於テハ第一巻ノ話題タリシ自然法ノ何タルヲ要約シ最高ノ法ハ神意ニ淵源シ凡テノ成文法ニ優ル効力ヲ有シ其内容ハ正ヲ命シ不正ヲ禁スルモノナルコトヲ説ケリ第五章ニ於テ成文法ハ自然法ニ適合シタルモノナラサルヘカラス自然法ニ反スル成文法ハ法ト見ルヘキニ非サルコトヲ説ケリ第六章ニハ最モ賢明ナル哲学者ナルプラトオンハ先ツ「国家論」ヲ著ハシ之ニ続テ「法律論」ヲ著ハシタリシセロモ亦此例ニ傚フコトヲ宣言ス第七章ニ於テハ神カ万物ノ主宰者ナルコトヲ説キ次章以下ニ説カントスル宗教法ノ緒言トセリ
第八章第九章ハ本巻ノ骨子ニシテ主トシテ羅馬古代ノ宗教法ノ規定ヲ遵則トシ多少シセロノ意見ヲ加ヘ宗教規定ヲ提案ス左ニ此大体ヲ摘出セン
各人ハ公認サレタル神ヲ敬スルコトヲ要ス神ニ三種アリ天神天神ニ準セラレタル神(Hercules, Liber, Æsculapius, Castor, Pollux, Quirinus)及ヒ知(mens)勇(virtus)信(pietas)誠(fides)トス神ニ近カツクニ当リテハ各人潔白ナルコトヲ要ス
pontificesハ一般ニ神ニ奉任シ其祭典ヲ司トルヘクflaminesハ特種ノ神ヲ奉戴スヘク又virgines Vestalesハ市中ニ於ケル永久ノ神火ヲ不滅ノ状態ニ監視スヘキモノトス
神啓書ノ解釈ヲ職務ト為スquindecimviri sacris faciundis及ヒ天啓ノ解釈ヲ職務ト為スaugures及ヒ外交ノ職務ニ従事スヘキfetialesヲ設置スヘキモノトス
神ニ対スル重キ不敬罪ヲ三トス神社又ハ神社ノ保管物ヲ盗ミタル者ハparricidiumヲ為シタル者トス宣誓違反ノ行為ヲナシタル者ハ神法上ニ於テハ其人格ヲ剥奪シ人法上ニ於テハ令名減少ノ制裁ヲ加フvirgo Vestalisカ其潔白ヲ破フリタルトキハpontificesハ是ヲ死刑ニ処ス
私祭ハ永久不滅タルヘシ(sacra privata perpetua manento)
シセロノ提案シタルconstitutio religionumニ対シAtticusハ其大体ニ於テNumaノ制定シタル宗教法ニ同シキモノト考フル旨ヲ述フシセロ親友ノ言ヲ是認シ且羅馬ノ古制カ凡テ他ノ制度ニ優ルモノトシ国粋保存ノ意ヲ漏ラセリ【第十章第二十三節】
第十章以下第二十七章ニ至ル迄ハ大体ニ於テシセロノ提案ノ理由書ト見ルヘク今茲ニ是ヲ詳述セス
九 「法律論」第三巻内容ノ梗概 第三巻ハ二十章ヨリ成ル第一章ニハ官制ヲ説カントスルニ当リテプラトオンニ倣フテ緒言ヲ置キ第二章ニ於テ官制カ国家制度上必要ノモノナルコトヲ説ク第三章第四章ニ於テシセロハ官制ノ大体ヲ提案ス其要旨ヲ左ニ摘録ス
magistratusノ職権ハ正当ナルモノニシテ国民之ニ服従スルコトヲ要ス官吏カ服従ヲ強制スルカ為メニ三種ノ制裁ヲ附スルコトヲ得財産刑【罰金及ヒ財産差押】禁固及ヒ笞刑是ナリ官吏カ同等又ハ同等以上ノ職権ニ依リテ制裁ヲ附スルコトヲ禁セラレ若ハ国民ニ対シテ上訴アリタルトキハ官吏ハ制裁ヲ附スルコトヲ得ス出征中ノ将官ノ処分ニ対シテハ処分ヲ受ケタル者ハ国民ニ上訴スルコトヲ得ス将官ノ軍中ニ於ケル命令ハ法律ノ効力ヲ有ス
官職ヲ分チテmagistratus minoresトmagistratus maioresトス
magistratus minoresニ属スルモノ左ノ如シ
(イ)quaestores 国家ノ財産ヲ保管スルヲ以テ其重モナル職務トス
(ロ)triumviri capitales 三人ノ典獄ナリ死刑ノ執行ヲ為ス
(ハ)triumviri monetales 三人ノ通貨鋳造官ナリ
(ニ)decemviri stlitibus iudicandis 身分事件ヲ管轄スル裁判官ナリ
magistratus maioresニ属スルモノ左ノ如シ
(イ)aediles シセロハ此官職ヲ以テ高等官職ノ第一楷トセリ羅馬ノ実際ノ官制ニテハaedilesハ普通官職中ニ属スaedilesハ羅馬市ノ警察権ヲ有シ穀物ノ輸出入ヲ監督シ公ケノ娯楽ニ関スル行政権ヲ有ス
(ロ)censores 国民ノ年齢児童ノ数財産ノ調査寺院公路水道金庫ノ監視租税ノ徴収行政区割ノ分配等ヲ職務トナシ又未婚者ノ調査ヲ為シ是ニ制裁ヲ附シ又壮年者ヲ歩兵ニ編入スヘキカ又ハ騎兵ニ編入スヘキカヲ裁定ス
censoresハ二人トシ任期五年トス他ノ官吏ノ任期ハ一年トス
(ハ)praetores シセロハ裁判官ヲ称シテ国法ノ保護者(iuris civilis custos)ナリト云ヘリ裁判官ノ定員ナク元老院及ヒ国民ノ議決若ハ命令ニ依リテ幾名タリトモ同僚ヲ設置スヘキモノトス
(ニ)consules 定員二名トス執政官ハ最高ノ権力ヲ委任セラルヘク何人ニモ服従スルコト無カルヘシ又執政官ハ統帥権ヲ有スヘキモノトス十ヶ年ノ期間ヲ経過スルニ非サレハ同一人カ再ヒ執政官タルコトヲ得ス執政官タルコトヲ得ヘキ年齢上ノ資格ハ法律ニ依リテ定マル(紀元前百八十年ノlex Villia annalis参照)
(ホ)dictator 古代ハmagister populiノ称アリdictatorハ外国ト戦端ヲ開ラキタルカ又ハ内乱ノ如キ国家大事変ノ時ニ元老院カ機関体ヲ任命スル非常ノ官職ナリ一人ニシテ任期ハ六ヶ月ヲ越ユヘカラス職権ハ二人ノ執政官ノ権力ヲ包括スdictatorノ任命アルトキハ同時ニ其補助トシテmagister equitum任命セラルヘキモノトス
凡テ官吏ハ天啓祈願権(auspicium)ヲ有ス官吏ハ其職務執行ニ関シテ何等ノ財物ノ贈遺ヲ受クヘカラス官吏ハ退官ノ後其職務執行ノ状況ヲcensorニ報告スルコトヲ要ス
以上ハシセロカ第三章第四章中ニ説キタル官制ノ大要ナリQuintusハシセロノ提案セル官制カ大体ニ於テ羅馬国ノ実際ノ官制ニ同シト評シタリシセロモ亦是ヲ認ム【第五章】
第六章以下第二十章ニ至ル迄ハシセロカ提案シタル官制ノ理由書トシテ見ルヘキナリ其間シセロハストア哲学者ハ国法ニ就テ論シタルコト甚タ少ナク国法上ノ議論ハプラトオン及ヒアリストテレスノ書ニ就テ見ルヘキコトヲ説キ【第六章】又シセロト其弟トノ間ニ護民官ノ制ノ得失ニ就キ大議論アリ【第八章乃至第十章】
十 「法律論」カ羅馬法講究ノ資料中ニ於ケルノ地位 シセロノ著書カ概シテ非法律専門家ノ著書中ノ羅馬法講究ノ資料トシテ最モ重要ナル地位ヲ占ムルハ定論ナリ而シテ其「国家論」及ヒ「法律論」ハ其内容法律学ニ関スルモノナレハシセロノ著書中羅馬法ノ講究資料トシテ最モ価値アルモノト云ハサルヘカラス是ヲ以テHuschkeハ其IVRISPRVDENTIAE ANTEIVSTINIANAEノ第三版ニ於テ「法律論」ヲモ編入スルコトト為シタリ(ibid. P. 19)然レトモ「法律論」ハ羅馬私法ノ講究資料トシテハ多大ノ価値ヲ認ムル能ハス唯国法宗教法ノ資料トシテ参考トナルノミナリ而シテ此書ヲ援用スルニ当リテ注意スヘキハシセロカ往々自己ノ理想ニ因リテ羅馬国実際ノ法制ト異ナリタル規定ヲ提唱シタルコトナリ