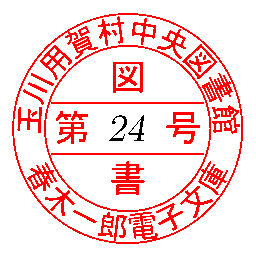
古典中最も詳細に平民の起原を説明したるはDionysiusの記事なり、其の大略は次の如し、Romulusは総ての民衆を三部に分ちたる上にて【Dionysius 2, 7】更らに出生、才能、財産に於て優越せる者と是等の点に於て比較的劣等なる者とを区別し、前者をπατέρεςと称し、後者をπλεβείοι【希臘人の謂はゆるδημοτικοί】と称したり、優越者をπατέρεςと称したる所以は是等の者は他の者に比するに年長者たるか又は是等の者は当時、子を有したるか又は其の出生に於て優れるか又は是等の総ての事実を具備せるかに由る、而して王は優越者と劣等者との間に於て公権上の差異を設け、優越者は国祭に関与し又政務官に就任することを得へく又裁判を為し又王を補助して国務を処理し得るものとせり、之に反し平民は専ら農事に従事し家畜を飼養し又営利の事業に従事するものとせり、【Dionysius 2, 8】Liviusの説く大体は次の如し。右に挙げたる古典の記事に拠れば羅馬時代の歴史家等は貴族と平民との起原を国祖が其の意思に因り貴族を国民中より区別したるに帰したり、羅馬王政時代に関する古典の記事が悉く信拠するに足らざるはPerizonius【1651--1715】以来幾多の学者に依りて考証論議せられたる所にして茲に亦多言を要せず、然れども平民の起原に関する古典の記事の大綱も又果して信拠するに足らざるものなるや否やWillemsの如きは後世の羅馬人は自国の制度にして起原の詳かならざるものは是れを国祖の制定に帰するを慣例と為したりとし、平民の起原に関する古典の記事を信拠せず、【Willems, le droit public romain, p. 31. 1888, 6emè. ed.】然れどもBotsfordの如きは却つて古典に見ふる平民の起原に関する記事は比較社会学の研究上、寧ろ事実と認むべきものとせり、【Botsford, the Roman Assemblies, pp. 38--45. 1909】予も亦貴族と平民との区別の起原に付ては古典殊に前掲のDionysiusの説く所を信ぜんとす、Dionysiusの説く所は理論上信じ得べきものなり、国家成立の後に於て半開以下の社会に優等なる実力を有する者が一団を為し社会上劣等の者の上に位するに至るは自然の趨勢なり、羅馬に於て貴族が国民中より分化したるに付ての古典殊にDionysiusの記事を見るに、門地、才能、財産を標準として王は貴族なる一団を国民中より選抜したりとす、是れに拠りて観るに貴族は国民中の比較的有力者なりしかば政権の行使に参加し国祭の事務を補助するの資格を有するものとせられたるは当然の事理なり。
Romulusは宗教制度を確定したる後に民衆(multitudo)の集会を催ふしたり、王は是等の民衆を一団と成し是れを支配するには法に如かずと思考し幾多の法律を設けたり、王は更らに保護所(asylum)を設け自由人たると奴隷たるとを問はず他市よりの逃亡者を此の所に収容したり、而して王は民衆中より一百人を選抜して是れを元老院議員(senatores)と為しpatresなる敬称を与へたり、【Livius 1, 7】Ciceroは簡単に貴族の起原を説き曰く「Romulusは国民中の主もなる者を以て元老院を構成し是等の者をpatresと称し其の子孫をpatriciiと称したり」【Cicero, de re publica Dionysius 2, 12参照】
近世の学者中に古典の記事に拠らずして平民の起原を説く者多数あり、Theodor Mommsenは其の一人なり、氏はplebsは本来cliens【隷属者】より出てたりとす、【Mommsen, röm. Forschungen, S. 388. 1864。Dionysius 2, 9に拠るにRomulusは平民をして任意に貴族を撰択して隷属関係を発生することを得しめたり、此の如き隷属関係に於ける保護者をpatronusと云ひ、隷属者をcliens (cluere, κλύειγ, hören)と云へり、両者間の関係に付てDionysiusは詳細なる序述を為せり、氏は曰く「貴族は隷属者の知らざる法と隷属者の知らざる法則を隷属者の為めに説明することを要したり、又貴族は隷属者が其の住所に不在の時たると否とに拘らず金銭の計算及び義務に関して親が其の子に対して為すを慣例と為すの一切の事務を執行して隷属者の事務を管理することを要したり、又若し或隷属者が契約関係に於て損害を受けたるときは其の隷属者の為めに貴族は不正行為に因るの侵害の救済を目的と為すの訴訟を提起し又隷属者の告発者に対して隷属者を防禦することを要したり。又予は簡約して説かんに貴族は公私の事務に付て総ての方面に於て隷属者に安定の状態を与ふる為めに至重の注意を払ふことを要したり。是れに対して隷属者自身は若し保護者が貧困なるときは其の保護者の娘に嫁資を供与し因りて保護者を保助することを要したり、(Dionysiusの説く諸種の関係中には後世の規則と認むべきものあり、隷属者が保護者の娘の為めに嫁資供与の義務の如きは其の一例なり、Muirhead, Historical Introduction to the Private Law of Rome, p. 9, 1899 2nd ed.)又隷属者は其の保護者又は子孫が敵の捕虜と為りたるときは是れを償贖することを要したり、又隷属者が個人より訴へられ敗訴の結果、勝訴者に支払ふべき金銭及び隷属者の支払ふべき公けの罰金を保護者は支出することを要したり、保護者は其の収出する金銭を隷属者に貸与するに非ず恩恵的に隷属者の為めに支出するに過きざるなり、又隷属者は其の保護者と血縁者なる如く保護者が政務官、宗教官としての身分より生する出費其の他の出費を分担することを要したり。保護者及び隷属者に共通なる法律関係は次の如し保護者及び隷属者が相互に刑事上の訴を為し又は反対の証言を為し又は反対の表決を為し、又は反対側に立つことは是れを不敬且つ宗教違反の行為とす。然れども若し或者が如上の不正行為の為め捕へられたるときは同人はロームルスの規定せる謀反法に依り責を負ふべきものとす。又如上の犯罪に付て有責とせられたる者は神の犠牲として何人たりとも之れを殺すことを得。」(Dionysius 1, 101)上記のDionysius文を見るに保護者と隷属者との間には封建制度に於ける君臣間関係に類似したるものあり、前に示したるが如くDionysiusに拠れば隷属者の起原は平民の起原の如く国祖の制定に基づく、然れども近世の学者中或は隷属者の制度は啻に羅馬の古に於けるのみならず希臘市及び伊太利の他市に於ても存在したるものなるが故に羅馬の立法者が制定したりと為すの古典の記事は信ずべきものに非ずとす。[例へばWillems, o. c. p. 27]惟ふに隷属者が羅馬建国の後幾何もなく貴族、平民の二階級の傍らに一階級を構成するに至りたるは古典の伝ふるが如く国祖の命に依るものなるべしと雖も始め隷属者と為りたる者は他市よりの逃亡者にして貴族に於て任意に其の保護の働を為したりしが他市の制度を模倣して国祖が隷属者なる一階級を認定するに至りたるならん。】然れども貴族に対して厳格なる宗教上の信義関係に在りたる隷属者が如何なる理由又如何なる方法に依りて其の関係より脱離し得たるものなるかを考ふること能はず。【Karlowa, röm. Rechtsg. I. S. 62. 1885】Fustel de Coulangesの平民起原説の大体は次の如し、平民は本来羅馬国民の一部分を構成せず、国民は貴族と隷属者とより成りたり、平民の起原に関しては古典中に確実なる説明を欠く吾人が正当に推察する所にては平民の大部分は被征服者なり、是等の者の家には祭祀なく家祭を司どる家長なく又自然の血族関係ありと雖も家祭を中心となす家族関係なく男女間に於ける自然の結合関係ありと雖も婚姻関係なし、是等の者は家神を有し家祭を為す貴族に比すれば劣等の階級を成せり、此の種の階級は啻に羅馬国の古代に於けるのみならず殆んど総ての国に於て存したり、希臘に於ても市民は国神の社殿の存在する高地πόλ ιςに住み劣等者は高地の麓に於ける家屋内に群居したり、市民は宗教上の一定の儀式の執行ありたる後に建設せられたる市内に住居し、劣等者は何等宗教上の儀式の執行なく建築せられたる家に住居したり、羅馬に於ては貴族及び其の隷属者は宗教上の儀式を執行してPalatinus岡の上に建設したる市内に住居し平民は国祖がCapitoliumに建設したる保護所内に住所を有したり、後に新来の平民はAventinus岡即ち市壁外の非宗教地に住居せしめられたり、蓋し平民は宗教の支配外の者たればなり云々。【Fustel de Coulanges, lacite antique, ch. II, pp. 277--282, 17éme ed. 1900】Fustel de Coulangesの説は要するに平民には宗教なかりしが為め宗教を有したる貴族に比して劣等なる一階級を構成したるものなりとす、然れども平民も亦貴族の如く自己のsacra privataを有し又其のsacra publica及び其の特有の神官を有したり、【Binder, die Plebs SS. 245--246, 1909】又平民が貴族との婚姻能力(connubium)を拒否するの辞に平民に貴族との婚姻能力を認むるに於ては祭祀の混乱を生ずと云へり。【Livius 4, 2】是れを以て観れば平民には其の宗教なしと云ふは事実に反す。貴族と平民とは本来其の宗教を異にしたるが故に羅馬時代に於て異なれる階級を為し長く争闘したりと論ずるは自から別論なりと雖もFustel de Coulangesの言ひたるが如く平民には宗教なかりしものなりと断じ平民の起原を説くは誤なり。
一派の学者は貴族と平民とが長年間争闘を継続し固く執りて相下だらざりし所以のものを種属の差異に求めんとす、【Zöllerの説にては貴族はSabiniにして平民はLatiniなりとす(Zöller, Latium und Röm. 5. S. 23 ff.1878) Ridgewayの説の梗概は次の如し、貴族はSabiniにして平民は固有の種属なるLiguriansなり、SabiniはLiguriansの征服者なり、貴族のSabiniなる事は後世の史実よりして之れを証明することを得大祭官(flamines maiores)は後世に至るまで貴族たることを要したり、是等の大祭官の奉仕する祭神は総てSabiniの神なり又結婚方法の一なるconfarreatioは貴族のみ執行し得べきものにして其の起原はSabiniに在り蓋し此の方法はSabiniより出でたるNuma王の設定したる所にしてSabiniの祖先が希臘にも輸入したるものなり。(Dionysiusは之れを希臘語のἱερὸς γάμοςと同一視す)又後世羅馬に行なはれたる人の死体処分の方法に土葬あり、火葬あり火葬は上流人間に土葬は下流人間に行なはれたり、而して火葬は蓋しSabini中に行なはれたる慣習にして土葬はLigurians中に行なはれたるものなり又他の証拠はServius Tulliusの設けたりと称せらるる軍隊の武器に付て之れを求むることを得、貴族より構成せらるるClassisは円形の楯を有せり、此の形の楯はSabiniに属するUmbriansの使用したる武器なりRidgewayは以上の四つの証拠に加へて尚ほ言語上の相違よりする証拠を説けり(Ridgeway, Ethnology in ``a Companion to Latin Studies'' pp. 32--33, 1913, 2nd ed.; ``Rome'' in Ency. Brit. 11th ed.)%又RidgewayはSabiniは其の始め欧州の中央部又は上部を原住地と為したる種属の一なりとす、(Ridgeway, o. c. p. 33)Binderの説にては羅馬国はMons Palatinusを定住地としたるSabiniとMons Quirinalisを定住地としたるLatiniとの合同より成りSabiniは貴族を成しLatiniは平民を成したるものとす。(Binder, a. a. O. S. 294 ff.)Greenidgeも亦二階級の区別の起原を種属別に帰し大要次の如く説きたり、平民が隷属者より出でたりと為すの一派の近世人の説(Mommsenが此の説を為したる事は前に言へり)は平民の起原を説明するに足らず、貴族は外来の征服者の種属にして平民は被征服者たる固有の種属なり羅馬法制中に数多の二様の制度の存在したるは其の結果なり、契約に付て云はばSponsioに対してnexumあり、婚姻法に付て云はば一方にはconfarreatioあり之れに対して一方にはcoemptio及びususあり遺言に付て云はばcomitia calataに於て作成せらるる遺言あり之れに対してper aes et libramの遺言あり、之れに加ふるに平民が政務官及び神官たるの資格を有せず、又平民は貴族との結婚能力を有せざるの事実は両階級間に種属的の根本的相違あることを示めす其の他考古学並びに人類学上の証拠は両階級の区別が種属別に基づくものなる事を確かむ云々(Greenidge in Poste's Gaius XIX, 1904, 4th ed.)然れどもGreenidgeは貴族及び平民が各如何なる種属より出でたるかを説かず、Clarkは最初の平民はRamnesにして貴族の核子はSabines即ちTitiesなりとし両階級の区別の起原を種属的なりとの仮定説を為せり、(Clark, History of Roman PrivateLaw, Part III Regal period p. 273, 1919)両階級の起原を種属別に帰するの一派の説中には貴族の起原をEtruscansなりとし平民は貴族なるEtruscansに依りて征服せられたる者なりと為すものありCunoの如きは此の如く論ずる学者なり、氏はLivius 1, 29に羅馬市は本来Etruria市なりと説きたる或歴史家ありと云へるとVarro 5, 5にVolniusなる文学者がRamnes, Tities, Luceresなる名称はEtruria語なりとするの故典に拠り貴族はEtruscansなる征服者なりとす、(Cuno, VorgeschichteRoms, I 1878, II 1888)Livius 12, 7に謂はゆる歴史家はEtruscansの文化が羅馬国に及ぼしたる影響の大なるに迷はされ羅馬市の起原をEtruria市に帰するの説を為したるに非ざるかとも思はる、又羅馬時代の或文学者がRamnes, Tities, Luceresなる語がEtruria語なりと為す(是れ固より疑問なり)と雖も未だ直に貴族の起原をEtruscansに帰し得べきに非ず、蓋しEtruscansの文化が羅馬国に或程度までの影響を及ぼしたるは事実なり又王制時代の後半には羅馬市がEtruscansの支配の下に在りたりとの説は信拠し得べきものの如しと雖も貴族の起原を直ちにEtruscansたる征服者に帰するの説は信じ難し】Waltonは是等一派の種属説を包括して批評して曰く此の説の真なる事を論証する事は不可能にして此の説を信ずるに足るべき基礎なきものと言へり、【Walton, Introduction to the Historical Roman Law, p. 64, 1918, 3rd ed.】然れども予は絶対に種属起原説を排斥せず両階級の起原を説くに当り全然古典を無視し是れを隔て起原を種属別に求めんとするの説には服し難しと雖も同時に種属別が両階級の争闘に絶対に影響したる事なしと断言する事能はず、如何となれば国祖が貴族を国民中より選抜するに当りて会或種属の者が比較的多数に貴族を構成したりとも想像し得べければなり。此の想像は必ずしも両階級の起原に関する古典の記事と矛盾せず。