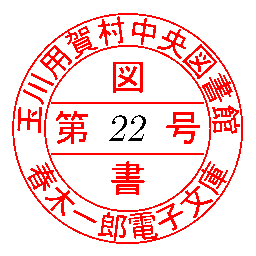
古今東西、法が道徳的価値を有すべきは自明の理なり悪法は法に非ず、然らば特に羅馬法の道徳的価値と題して云々するは無用なるものの如しと雖も、実は然らず。茲に云はんとするは他なし、即ち古代諸国の法制に比すれば寧ろ早く宗教律より分離したる羅馬法は政務官殊に法務官及び法学者に依りて道徳的規範と法律的規範とを及ぶ丈け一致せしむることに努力せられたるが故に、道徳的価値に於て他の古法制に超越し、極めて優秀なる地位を占むる事是れなり。法務官、法学者は「凡そ約束は之を遵守せざるべからず」との原則を尊重したり。又彼等は実社会の誠意律を法律化して、数多の規定を制定若は認定したり。法学隆盛時代の学識の重要なる唯一の結晶なる儒帝学説彙纂の読者は、法務官、法学者が告示若は所論の基礎を善及び中正に置きたる個所甚だ多きことを見出さん。他人の損失に因りて不当に自己を利すべからざるの道徳律は有名なる各種の不当利得返還請求訴権に依りて法律化せられたり。其の他、自己が救済し能ふに拘らず、拱手して他人の災害を看過すべからざるの道徳律は、法務官に依りて特に法律化せられたり。又二十五年未満の弱者を保護せんが為めに任侠的処分を定めたるは羅馬の「大岡越前守」なり。(羅馬法の進展に対する法務官の働に付ては法学士入江俊郎氏著「ius praetoriumの研究」【大正十四年巌松堂発行】参照)小ケルススは法(一説にては法律学)は善及び中正の術(一説にては組織)なりと云ひ、又ウルピアーヌスが法の根柢を正義に求めたるが如き又正義を解して各人に其の権利を配当するの恒常不断の意志なりとせるが如き又法の神髄を説きて各人が紳士的の処世を為し、他人を害せず、各人に其の権利を配当する事是れなりとせるが如きを以て考ふるに法学者が道徳と法との一致を以て其の理想と為したるを知るに足るNon omne quod licet honestum est (学説彙纂第五十巻第十七章、百四十四、パウルス)は「法の許容する所は必ずしも総て善行に非ず」との意義、随て法と道徳との区別を説きたるものに非ずして、成文法の禁ぜざる事実と雖もhonestas (紳士的行動)に反するものは法律上之を許すべきに非ずとの法意なり。(Ch. Appleton, Notre enseignemenet du droit romain dans Mélanges de droit romain dédiés àGeorges Cornil, I. P. 72, 1926)大法学者パーピニアーヌス(人格者なりしが故に大法学者と為り得たりしなり、氏の事蹟に関しては恩師大穂積先生著法窓夜話一参照)は曰く「如何なる行為たりとも吾人の敬虔、令名、道義心を傷つくるもの汎言すれば善良の風俗に反するものは吾人之を為すことを得ざるものと信ずべし」(学説彙纂第二十八巻第七章十五)と、此の炎々たる大言は、道徳律に違反するは即ち法に違反するものなることを喝破したるものに非ずして何ぞや、米国の法律学者シアーマン氏が羅馬法の価値として特にethical valueを挙げたるは(Sherman, Roman law in the Modern World, vol. I, P. 3--4, 1917)大いに我が意を得たるものなり。