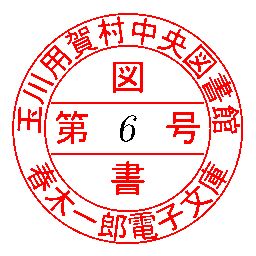
儒帝ノ学説彙纂開巻第一ニうるぴあーぬすノ法学提要中ヨリノ法文ヲ採録シテ曰ク『法ニ従事セントスル者ハ先ツ法ナル名称ノ由来ヲ知ルコトヲ要ス。法ナル名称ハ正義ヨリ来レリ【うるぴあーぬすカiusノ語原ヲ説キタルニ非ス。其ノ本質的基礎ヲ説キタルナリ[Glück, Pandekten, 1, S. 2 Anm. 2; Munroe Smith, Jurisprudence, p. 10, 1908]】。如何トナレハ、けーるすすカ巧妙ニ定義シタルカ如ク、法ハ善良及ヒ衡平ノ術ナレハナリ』ト。うるぴあーぬすハ客観的ノ意義ニ於ケルiusノ基礎ヲ正義ニ置キ、法ヲ研究セントスルノ士ハ、先ツ法ハ正義ヲ基礎トスルモノナルコトヲ提唱シ、けーるすすノ定義ヲ引用シテ、自己ノ立言ヲ確カメタリ。既ニ正義カ法ノ基礎ナリトセハ、正義ノ何タルヲ明カニスルノ要アリ。是ヲ以テ学説彙纂第一巻第十ノ首文ニ、同シクうるぴあーぬすノ法範中ヨリノ法文ヲ掲ケ、正義トハ各人ニ其ノ権利ヲ配当スルノ恒常不断ノ意志ナリトセリ。而シテ同章十ノ一ニ法ノ原想【,iuris praecepta'ヲ原想ト訳スハSavigny, System, I, S. 408ノ説明ニ拠ル】トシテ、正直ナル生活ヲ送ルコト、他人ヲ害セサルコト及ヒ各人ニ其ノ分ヲ配当スルコトヲ三綱領ト為シタリ。法ノ原想ニ次キテ法律学ノ定義ヲ掲ケ『法律学トハ神事及ヒ人事ノ知識ニシテ正及ヒ不正ノ暁覚ナリ』トセリ。儒帝法学提要第一巻第一章(正義及ヒ法ニ付テ)中ニ於テモ、右ニ示シタル学説彙纂第一巻第一章中ニ見ユル正義、法ノ原想【法学提要ニ謂ハユルsuum cuique tribuereハius suum cuique tribuereト解スヘクシテ学説彙纂ノ句ト其ノ意義ニ於テ異ナラス】及ヒ法律学ノ定義ヲ掲ケタリ。此ク法学隆盛時代ノ法学者又其ノ思想ヲ容レタル儒帝ノ法典ニ於テ、正義ヲ以テ法ノ立脚点トシ、法律学ヲ以テ何カ正義ナルカ不正ナルカノ暁覚ナリトセルハ明白ナリ。然レトモ、此ノ如キ法ノ立脚点ヲ採リタルノ裏面ニ於テハ、羅馬人ハ権利ノ思想ヲ閑却シタルモノニ非サルカノ問題ヲ生ス。羅馬人ハ客観的iusノ定義ヲ与ヘタリト雖モ、主観的iusノ定義ヲ与ヘス、儒帝法学提要並ニ学説彙纂中ニハ正義ノ何タルヲ説クト雖モ権利ノ何タルヲ説カス、又法律学ヲ以テ正及ヒ不正ノ暁覚ナリト為スト雖モ、権利ノ組織ヲ研究スルノ学ト為サス、是等ノ点ヨリ観レハ羅馬人カ権利ノ思想ニ乏シカリシニ非サルカノ疑問ハ理由アリ。嘗テMaineハ其ノ『古代ノ法ト慣習』第十一章中ニ【Maine, Early Law and Custom, p. 365--366, 1890】説キテ曰ク『羅馬人ハ吾人ニハ基本的ト考ヘラルル所ノ権利観念【Conception of a legal right】ニ到達、少クトモ充分ニ到達セサリキ。羅馬法律家ノ一般ノ用法ニ従ヘハjusハ「権利」ノ意義ニ非スシテ「法」ナリ。而モ、通常法ノ特別ノ分科ノ意義ナリ。jusノ一定ノ意味ニシテ「権利」ノ意義ニ接近シ若クハ密接シタルモノアルハ疑ヲ容レスト雖モ、達観スレハ羅馬人ハ記憶スヘキ其ノ法ノ組織ヲ構成スルニ権利ノ観念ヲ援用セサリシモノナリ』云云ト。【Mitteisモ亦羅馬人カ権利ヲ基本トシテ法ヲ説カサリシコトヲ論シテ曰ク『近世法ニ於テハ権利ナル抽象的観念ヲ基本トシテ法ノ系統ヲ定メ此ノ観念ノ各種ノ表現形式トシテ物権債権親族権相続権ニ関スル規定ヲ設ク。羅馬人ハ然ラス、其ノ謂ハユル,,Ius quod ad personas, ad res et ad actiones pertinet''ハ権利ノ区別ヲ云フニ非スシテ法ノ区別ナリ』ト[Mitteis, röm. Privatrechts, S. 73, 1908]】又牧野博士モ次キノ如ク言ハレタリ。『……権利といふ観念は果して法律の観念と始終すべきものであらうか。之を歴史的に考へても見ても、之を比較的に論じて見ても、法律といふものを理解する民族乃至国民にして権利の観念乃至思想を有せざるものが決して少くないのである。而して現に羅馬法に於ては、「アクチオ」actioといふ観念が存在して居たけれども、今日の権利といふ観念に相当する観念は無かつたのである。其の「ユス」jusといふ語に権利といふ意味を具有せしめたのは、中世の伊太利法学者の仕事で、遥に後世のことに属するとされて居る【牧野博士現代ノ文化ト法律、三五八乃至三五九頁、大正六年】。』
羅馬人ハ権利ノ定義ヲ与ヘタルコトナシ【Beckker, Pand. I §46 Anm. a. 1886】。少クトモ現存スル資料中ニハ之ヲ見出サス。羅馬人ハ権利ノ定義ヲ与ヘスト雖モactioノ定義ヲ与ヘタリ【D. 44, 7, 51 [Celsus]; I. 4, 6 pr. ニ類似ノ定義ヲ掲ク】。惟フニ、羅馬人ハ、実行ヲ離レテハ権利ナルモノニ何等ノ価値ナシ、実行力ノ伴ナフ所ノ権利ニシテ始メテ其ノ価値ヲ認メ得ヘク、因リテactioノ何タルヲ明カニスレハ権利ノ何タルヲ言ハサルモ足レリト為シタレハナリ。而シテ羅馬人カactioニ与ヘタル定義ハ、或者カ自己ニ負担セラルルモノトセラレ得ヘキモノヲ裁判所ニ於テ追求スルノ権利【,,Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi``】ナリトス。『自己ニ負担セラルルモノトセラレ得ヘキモノ』ト云フハ、啻ニ債務ノ物体ノミヲ指スニ非ス。随テ右ノ定義ハactio in personamノ観念ヲ表明セルニ非ス。汎ロク私権ノ保護権トシテノ訴権ノ観念ヲ表明シタルナリ。而シテ卑見ニ依レハ『自己ニ負担セラルルモノトセラレ得ヘキモノ』ト謂フハ、或者カ獲得スルヲ以テ正義ニ適合スルモノト裁判所ニ於テ決定セラレ得ヘキモノトノ意ナリ。けーるすすノactioノ定義中ノ,quod sibi debeatur`ノ解釈ニ付テ従来種種ノ説アリト雖モwhat is due to him即チ自分ノ分、更ニ換言スレハ、自己ノ権利ト解スルヲ以テ適当トス【Pollock, A first book of jurisprudence, p. 92, 3rd edition, 1911; Sherman, Roman Law in the Modern World, vol. II, §838, p. 393, 1917】。
iusノ語原論ハ姑ラク之ヲ措キiusナル語カ羅馬ノ法律書中ニ種種ノ意義ニ用ヒラルルハ周知ノ事ナリ。而シテ十二表法ノ原文ナリトシテ現今ニ伝ハルモノニ於テ、iusハ大凡二種ノ意義ニ用ヒラル。即チ、第一、裁判所、第二、法是ナリ。第一ノ意義ノiusノ見ユル法文ハ次ノ如シ。
Si in ius vocat, ito. (Tab. I, 1)第二ノ意義ノiusノ見ユル法文ハ次ノ如シ。
In ius ducito. (Tab. III, 2)
Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, etc. (Tab. III, 3)
Si qui in iure manum conserunt. (Tab. VI, 5)
Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunto. (Tab. III, 1)右ノ如ク十二表法中ニ於テハiusハ権利ノ意義ニ用ヒラルル所ヲ見スト雖モ、権利ノ意義ヲ示スニpotestasナル語ヲ用ヒタル所アリ。Voigtノ説ニテハ、iusナル語カ適法ニ取得セラレタル個人ノ権利ノ意義ニ用ヒラレタルハ後世ノ事ニシテ、十二表法時代ニハpotestasナル語ヲ以テ権利ヲ示シタリト【Voigt, XII Tabeln, Bd. I S. 116; S. 323】。十二表ノ正文中potestasナル語カ見ユルハ、第五表中ニ列セラルル,,Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto``ナリ【potestasノ語根ハpa[保護スル]ナリ。πόσις, πότνια, δεσπό, της, δέσποινα, δεσπόζωノ如キ語参考○尚ホpotestasナル語ハiusト連続シテ用ヒラルルコトアリ。Gaston May, Sur quelques exemples de gémination juridique [Mélanges Gérardin, p. 401]】。
Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto. (Tab. V, 3)
Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto. (Tab. VI, 1)
Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto. (Tab. VIII, 12)
【以上ノ法文ハBruns, Fontes, ed. sexta, 1893ニ拠ル】
十二表ノ正文中iusカ権利ノ意義ニ用ヒラレタル所ヲ見スト雖モ同正文中ニ用ヒラルル命令法形ノ働詞ニシテ『欲シ得ルコト』ノ意義ニ用ヒラルルコトアリ。例ヘハ、,Tertiis nundinis partiis secanto`【Tab. III, 6】ト云ヘルカ如シ。
権利ノ観念カ十二表法時代ニ存シタルハ上述ノ如ク十二表法其モノニ依リテモ立証シ得ヘシト信ス。次ニ述フル事ハ尚ホ此ノ事実ヲ確カムルニ付テ多少ノ意義アリ。此ノ時代ニ於ケルvindicatioノ手続ハlegis actio sacramentoナリ。神聖掛金額ニ付テ同法中ニ規定ノ存シタルコトハGaius 4, 14ノ証スル所ナリ。然レトモ此ノlegis actioノ手続ノ詳細カ同法中ニ規定セラレタリシモノナリヤ否ヤハ知ルニ由ナシト雖モGaius 4, 16ニ説明セルlegis actio sacramento in remノ手続ハ、其ノ大体ニ於テ十二表法時代ニモ行ナハレタルモノト見テ可ナラン。Gaiusノ伝フル所ニ拠レハ、原告ハ法廷ニ於テ、係争物例ヘハ奴隷ヲ握取シテ式語ニ依リテ目的物カ自己ノ所有物ナルコトヲ主張シ、次ニ実力ヲ表顕スルノ働作ヲ為シタリ。被告モ亦原告ト同様ニ式語及ヒ法定ノ働作ヲ以テ其ノ主張ヲ為シタリ。政務官カ双方ノ間ニ介入スルニ及ンテ、被告ハ原告ノ詰問ニ対シテius feci sicut vindictam imposuiナル式語ニ依ルノ答ヲ為シタリ。此ノ式語中ノius facereハ法ヲ実行シタリトモ解シ得ヘク、又自己ノ分(権利)ヲ実行シタリトモ解シ得ヘキナリ。仮リニ此ノ所ノiusヲ法ナリト解スルヲ正シト為スモ、法ノ認メタル自己ノ分タル思想ハ此ノ所ノius中ニ包含セラル。
予ハ羅馬時代ニ於ケル権利観念ノ発展史ヲ研究スルノ端緒トシテ、先ツ茲ニ十二表法ヲ吟味シタルナリ。予ハ他日尚ホ進ミテ十二表法時代以降ニ及ホサントス。惟フニ抽象的権利ノ観念ハ、十二表法時代ハ固ヨリ存シタリト雖モ、権利ノ各種ノ表現形式ノ発達ノ程度ハ極メテ低カリシナリ。dominium又ハproprietasヲ以テ所有権ヲ示スノ用語ト為シタルハ、後世ノ事ナルニ因リテモ、之ヲ推知スルコトヲ得ヘシ。蓋、抽象的権利ノ観念ハ古今各国ニ通シテ同一ナリ。抽象的権利ノ表現形式トシテ個個ノ権利例ヘハ所有権ノ観念カ時代場所ニ依リテ異ナルノミ。