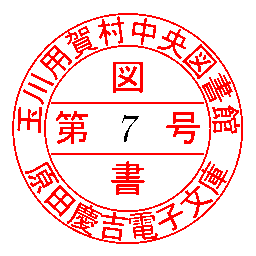
明治初年泰西法律文化が我が国に輸入せらるるや、羅馬法の意義も亦見逃される筈はなかつた(一)。明治七年五月東京開成学校と改称した東京帝国大学の前身に於ても、法学の学科科目中に「羅馬法」が設けられ、我が国羅馬法教育の第一歩が此処に歩み出された。講壇に於ける啓蒙的な羅馬法の講義が、先づ外人教師によつて開始せられたことも怪むに足らない所であつて、グリグスビー(Grigsby)、テリー(Terry)、ルドルフ(Rudorff)、ワイペルト(Weipert)等の名は、我が国羅馬法教育の恩人として忘るべからざるものである。邦人中にも羅馬法の研究を鼓吹し、其の紹介的研究を為す先覚者が現はれ始めた。堀口昇「羅馬元老議院記略」【明治八年、田中周友、論叢二八巻(昭和七年)一号参照】、小野梓「羅馬律要」【明治九年頃か】等は、恐らく其の第一線であつたであらう。小野梓が尚ほ「民法之骨」【明治一七年、西村真次編「小野梓全集」上巻(昭和一一年)に収録】に於て、賽非尼(Savigny)、保句多(Puchta)、渭為津沙為図(Windscheid)、亜安都(Arndt)等の学説に触れ、明治初年英仏法学独占時代に独逸のパンデクテン法学を紹介したのは異色の仕事であつた。彼は更に十二表法をも邦訳したとも伝へられる【註(一)参照】。彼に続いて馬場辰猪は「羅瑪律略」【共存雑誌二〇号—六二号(明治一二年・一三年)】に於て簡単な羅馬法外史を物し、尚ほ明治義塾法律学校の法律講義録【明治一七年—一八年、詳細な号数筆者に不明】に於て「メイン氏法律史」を連載してゐる。メーンの古代法は当事最も愛読愛講せられた書であつて、後述の鳩山和夫の翻訳の外、明治二十年代初期の英吉利法律学校東京法学院の講義録に見える増島六一郎の「法律沿革論」、菊池武夫の「古代法」は何れも其の翻訳的講義である。其の外高橋健三は専修大学に於ける羅馬法の物及び所有権取得方法に関する講義を発表し【明法志林二九号三一号(明治一五年)】、渋谷慥爾はSandarsを台本として「羅馬法沿革史之部」【明治一八年】「羅馬法講義」【明治二二年二三年頃】の如き英吉利法律学校講義録を印刷に附し、渡辺安積はMackeldey, Hunter, Poste, Sandars, Mackenzie(二)等を基礎とした帝国大学の数年の講義の結実たる「羅馬法」【明治一九年】を遺してゐる。羅馬法原典の翻訳を目的とした野心的な著述も現はれた。例へば作者年代不詳の「需斯知尼安法典」【註(一)参照】は儒帝の法学提要の全訳である。渡辺安積も亦儒帝の法学提要に対するガーイウスの法学提要の意義を知つて、これを翻訳せんとしたが、其の「グアイアス氏羅馬法律」【明法志林五六号五七号六二号(明治一六年)】は僅かに第一巻五十三を以つて中絶した如くである。翻訳書なることを明瞭に断つて、名著を紹介したものも現はれた。何礼之訳「法律類鑑」【明治一〇年】及び松野貞一郎・伊藤悌治「羅英仏蘇各国比較法理論」【明治二四年】は何れもMackenzie, Studies in Roman Law with Comparative Views of the Laws of France, England and Scotlandの翻訳、土方寧・有賀長雄訳述「羅馬法綱要第一」【明治一七年】はHadley, Introduction to Roman Lawの翻訳、鳩山和夫訳「緬氏古代法」【明治一七年】は謂ふ迄もなくMaine, Ancient Lawの翻訳、西川鉄次郎(三)「羅馬法入門」【明法志林一一〇号(明治一九年)以下、完成せしかは筆者には不明】はHunter, Introduction to the Study of Roman Lawの翻訳、磯部四郎重訳「法理原論」【明治二一年】はJhering, Geist des römischen Rechtsの仏訳よりの重訳である。尚ほ小林雄七郎訳「法律沿革事体」【明治九年】には羅馬法の外、カノン法、封建法、英吉利法、蘇格蘭法、仏蘭西法等の沿革史があるが、如何なる書の翻訳なるか筆者には不明である。此処に注目すべきは我が民法の三大人穂積陳重、富井政章、梅謙次郎は何れも他を凌駕し、当事の最高水準に位した羅馬法学者であつたことである。大正六年に儒帝の立法事業に付て御進講申し上げた穂積陳重は、過去の学歴に於ても明治十九年度より二十二年度迄帝国大学に於て羅馬法を担当し、其の比較法的進化論的論述中に散在する羅馬法に関する事項の外、其の早期の「万法帰一論」【法協一二号(明治一八年)】や「羅馬法を講ずるの必要」【日本之法律一四号(明治二二年)】等の全部又は大部分羅馬法に関する論文に於て、其の学力の片鱗を覗はせてゐる(四)。富井政章及び梅謙次郎のリヨン大学に於ける博士論文(五)は、それぞれ支払を受けざる売主及び和解に関する法制史的研究が半分を占めてゐる。明治十五年(富井)や二十二年(梅)に何人が日本内地に於て斯くの如き程度の羅馬法の論文を書き得たであらうか。明治二十年代の紹介的雑録的論文(六)と比較するならば、雲泥の差あるを発見するであらう(七)。其の他山本謙三、目賀田種太郎、東三条公恭、朝倉外茂鉄、田中遜、岡本芳次郎、津軽英麿、山川幸雄、杉田金之介等が明治二三十年代に私立大学の講壇に立つて羅馬法を講じ、多くは講義案を遺し、多かれ少かれ羅馬法学に対する啓蒙的役割を演じてゐた。然し乍ら是等の学者中には、一人として法制史学の専門家はゐない。帝国大学、東京帝国大学【明治三〇年六月以来】に於て羅馬法を講じた宮崎道三郎【担任明治二二年—二七年】は、法制史学者として羅馬法を講じた最初の学者であらうが、彼は羅馬法の専門家ではない。遺した羅馬法に関する研究も、「羅馬法の独逸に伝来したる始末を述」べた一篇【法協五九号六〇号六一号(明治二一年・二二年)】の外アイヒホルン伝【法協七三号七五号(明治二三年)】に於て註釈学派と後期註釈学派を語り、「古代売買ノ方法」【法協一二巻(明治二七年)九号】に於てマンキパチオ、人身売買に触れてゐる位に過ぎない。宮崎道三郎の後をうけた戸水寛人【担任明治二七年—四二年】は「すといつく哲学と羅馬法」【明治三一年】の如き特殊の研究の外、其の諸私立大学に於ける講義録を多数遺してゐるが、羅馬法に専心すべく余りにも才能は多方面にわたり、政治的性格にも強過ぎた。彼が所謂戸水事件後政界に入ることになり、其の後任として京都帝国大学より迎へられたのが即ち春木一郎教授【京都の担任明治三四年—四五年 東京の担任明治四三年—昭和四年】である。羅馬法研究の新機軸が同教授に起り、同教授によつて我が国羅馬法学の基礎が築かれたことは、此処に改めて述べる迄もない。蓋し同教授が初めて羅馬法を専門として海外に学び、同教授によつて羅馬法の原典に遡る本格的研究が為され始めたからである。固よりラテン語の素養と謂ふならば、春木教授の就任以前と退任後に京都帝国大学に羅馬法を講じた千賀鶴太郎【担任明治三二年—三四年、大正二年—一五年】が先ではあるが、彼も亦羅馬法の専門家ではない。従つて我が国羅馬法学の発達は、春木教授を新たな出発点とすると謂ふも差支へない。
春木教授の羅馬法一般に関する著書は、教授の学問的謙譲の故に、今日迄には未だ出版の運に至つてゐない。明治時代に羅馬法と銘打つた講義案的な書は多数存したが、今日に於ては学問的価値はない。昭和に至つて佐伯好郎「羅馬法綱要」【昭和二年】、船田享二「羅馬法」【昭和五年】、井上周三「ローマ法概論」【昭和八年】、戸倉広「羅馬法制史概論」【昭和一〇年】同「羅馬法概論」【昭和一五年】等を迎へ、筆者も「羅馬私法綱要第一分冊」【昭和八年】を出したが、是等の価値に付ては程度の差こそあれ、我が国羅馬法のスタンダード・ウォークたり得るものは未だ存せずと批評せざるを得まい。
春木教授の原典翻訳の事業は、遠く明治四十二年の昔に遡る。同年一月帝国学士院は羅馬法律書翻訳出版の議を決し、先づ同教授に儒帝の法学提要の翻訳を委嘱し、四十四年七月に其の草稿成つて、末松謙澄が其の校訂に当つたが、第三者には不明瞭な経過の裡に、宮崎道三郎の校訂を経た末松謙澄単独の翻訳書として、「ユスチーニアーヌス帝欽定羅馬法学提要」なる名のもとに、大正二年帝国学士院より第一版【四版大正一三年】が出版せられてゐる。帝国学士院は引続きガーイウスの法学提要とウルピアーヌスの法範の翻訳を末松謙澄に委嘱し、大正四年には「ガーイウス羅馬法解説」【三版大正一三年】、「ウルピアーヌス羅馬法範」【三版大正一三年】なる名のもとに、同じく帝国学士院より出版せられた。春木教授はこれに拮抗して、略々同時代にウルピアーヌスの翻訳【京都法学九巻(大正三年)九号—一二号】とガーイウスの翻訳【法協三二巻四号—三四巻一〇号(大正三年・五年)】を発表してゐる。是等の翻訳書が我が国羅馬法研究に一大便宜を供し、同法の研究を促進したことは言を要しない。教授は更に大正十五年以来儒帝法典に関係の諸勅法と学説彙纂最初の四巻の翻訳を法学新報法学志林に発表し、昭和五年には一応完結し、昭和十三年には「ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ」なる名称のもとに、一本として出版するに至つた。末松・春木両先達者による原典翻訳の事業は、其の同僚門弟によつて継続せられ、現に継続せられつつもある。千賀鶴太郎の学説彙纂第一巻第七巻【大正一〇年、一二年】、船田享二教授の第六巻第八巻第九巻【昭和七年—昭和一一年】、佐伯好郎講師の勅法彙纂【目下掲載中】、田中周友教授の新勅法【目下掲載中】、矢田一男講師の法学提要【昭和一四年】、筆者の法学提要希臘語義解【昭和八年—九年】の翻訳の如し【詳細に付ては矢田一男、法学新報四九巻(昭和一四年)一二号参照】。
春木教授は昭和七年に「儒帝法学撮要重要語纂訳」を世に送つた。名こそ法学提要中の重要法律語の出典を示して訳語を附したものではあるが、羅馬法関係の重要語は此の中に収録せられてゐるのであるから、辞書的作用をも営むものである。此のレキシコグラフィック方面の仕事は、近時町田実秀・吉永栄助「羅馬法関係羅甸語試訳抄」【東京商科大学法学研究4(昭和一四年)】によつて継続されんとしてゐる。
春木教授の幾多の論文【春木先生還暦祝賀論文集(昭和六年)冒頭の目録参照】中には、古代羅馬法に関するものが甚だ多い。其の初期の「十二表法」【京都法学一巻八号—二巻一号(明治三九年・四〇年)】に於て同法の一般的論述を試みた外、中期には同法のiniuria【法協三七巻(大正八年)四号】、ius【志林二一巻(大正八年)七号】、furtum【法協三七巻(大正八年)一〇号】、nexum【法協三九巻(大正一〇年)五号六号】等を論じ、十二表法は同教授の最も愛好した研究題目であつて、末松謙澄の十二表法の翻訳【ウルピアーヌス羅馬法範附録】と共に、我が国十二表法研究の礎石を据ゑたものである。其の他にも多かれ少かれ古代法に関係するものが多い。曰く「Legis actio sacramentoニ付テ」【京都法学六巻(明治四四年)一号】、曰く「Poena cullei」【京都法学七巻(明治四五年)三号】。其の他「Confarreatio及ヒCoemptioノ起源、方式ニ付テ」【穂積先生還暦祝賀論文集(大正四年)】、「Testamentum per aes et libramニ付テ」【法協三三巻(大正四年)九号】、「Lex Aquiliaニ付テ」【土方教授在職二十五年記念私法論集(大正六年)】、「羅馬法研究雑話」【国家三四巻(大正九年)一〇号】、「平民の起源に付て」【国家三五巻(大正一〇年)一〇号】、「売買ノ発展史ニ於ケルmancipatio」【新報三五巻(大正一四年)一号】、「質権ノ発達史ニ於ケルfiduciaニ付テ」【法協四三巻(大正一四年)一〇号—一二号】等々の如し。
羅馬法研究方法を一変せしめた近代的法文批判的研究に付いても、春木教授は固より無関心ではなかつた。初期にはインテルポラチオの意義と其の発見方法を論じた二篇【京都法学三巻(明治四一年)一一号一二号】があり、末期の翻訳中にも随時修正部分を指摘して居る【尚ほ「学説彙纂プロータ」一六二頁参照】。唯研究の前提条件として法文批判を為した後、立論過程に入ると謂つた方法を採つたものは、初期の古典法を中心とした論稿は固より、中期のものにも見当らない。一には研究の中心的対象が上記の如く古代法に存したが為でもあらう。
法文批判研究による視野の強化縦の研究と相前後して、視野を拡大して研究を横に伸ばしたのは、謂ふ迄もなくミッタイス(Mitteis)に始まる新研究方向である。其の羅馬帝国法と交渉を持つた法律として、最も重要性を有するに至つたのは希臘・ヘレニズム法であつて、其の実証的資料の大部分はこれを埃及発見のパピールスに仰いだことであつた。春木教授も此の方面に多分の関心を持つてゐたことと思はれるが、文書に遺したものはない。此の新方向を紹介し、其の重要性を指摘した功績は栗生武夫教授の「ビザンチン期における親族法の発達」【昭和三年】に帰すべく、それを法源に則して研究し、我が国法律パピールス学者、希臘・ヘレニズム法研究の第一人者の栄を贏ち得たのは、法源とがつちり組んだ物堅い論文(八)を連続して発表し来つた田中周友教授である。
法律パピールス学についで、楔形文字法が羅馬法の素養ある法学者によつて取り上げられ始めた。我が国に於ても(九)穂積八束がハンムラピ法典に関して明治四十一年に御進講申し上げてゐるが【註(四)の書に収録】、楔形文字法に対して常に注意を怠らなかつた第一人者は中田薫教授であり、「ハンムラビ法典とモーゼ法との比較研究」【史学雑誌二四編(大正二年)二号】、「西部亜細亜の古法律断簡三種」【論叢一五巻(大正一五年)三号四号】、「アッシリア法書及ヒッタイツ法典」【春木先生還暦祝賀論文集(昭和六年)】等其れ自体として纏まつた独立の研究を物した外、同教授の研究方法が常に比較法的であつたが為め、比較法制史的研究の一部として、楔形文字法を取扱つて来た。遊佐慶夫教授は後日の「古バビロニア法の研究」【昭和一〇年】に纏め上げたハンムラピ法典及び古バビロニア法の研究に一期を画し、最近は井上芳郎司書が法律よりはむしろフィロロギー社会史に重点を置いた幾多の研究を陸続発表し、筆者も末尾に附して斯学の現状を紹介する所があつた【註(九)参照】。
儒帝法の性格に関して、希臘・東部法の羅馬古典法に対する勝利を主張する新学説に対して反動が来た。儒帝法を古典羅馬法の単なる自然的発展(sviluppo naturale)と解するリッコボノ(Riccobono)学派である。これは古典法の意義と価値に再び醒めしめ、古典法を構成した各因子に其の史的役割を果さしめた点に重大な功績が存する。斯かる立場よりするも、入江俊郎「ユース・プレートリウムの研究」【大正一五年】は、法源取扱の第二次的なる已むを得ない不備はあれ、大局を把へた好著である。リッコボノ学派の主張は春木教授が論戦に立入るべく余りに新しい。尤も此の学説争に究極的には関聯を持つ儒帝法典の準備に関する所謂predigestoの問題やベリツス法学校問題に関しては、「学説彙纂編纂に関する一疑問」【新報三六巻(大正一五年)七号、「学説彙纂プロータ」に収録】に於て極めて明快に問題の現状を紹介してゐる。近時リッコボノ学派の我が国に於ける代表者を武藤智雄教授に見出す(一〇)。我が国のみならず、世界的にも最も忠実な同派の為めの闘将と評することを得よう。
民法が制定せらるるや、民法家にして著書論文に於て羅馬法に触れる者が輩出するに至つた。概して謂ふならば民法家の研究方法はパンデクテン法学を出てゐない。他面法制史家は純粋に歴史化した羅馬法研究の追求には上述の如く余念がないが、パンデクテン法学が有した羅馬法の現行法的意義を顧みようとはしない傾向があり、取扱はれた問題も現行法学と関聯を有するが如き問題は敬遠せられ勝ちの嫌なしとしない。春木教授も羅馬法に於ける代理【日本法政新誌一〇巻(明治三九年)一号】、果実【京都法学二巻(明治四〇年)一〇号】、埋蔵物の発見【日本法政新誌一二巻(明治四一年)一号】、負担【日本法政新誌一三巻(明治四二年)一号】、条件【京都法学四巻(明治四二年)二号】、他人の物の売買【京都法学五巻(明治四三年)一〇号一二号】に関する問題等現行法的問題を取扱つたのは、専ら其の初期のみである。船田教授は法理学的素養よりして、先づ衡平自然法法律学の如き問題に没頭し(一一)、次いで民事訴訟法の研究に転じ(一二)、更に進んで公法史の問題(一三)特に近来羅馬法学界に於て争はれたアウグスツスの政体に関する問題を取扱ひ、近年の名著「羅馬元首制の起源と本質」【昭和一一年】を以つて、我が国羅馬法学界の水準を高からしめた外、例へば内縁、不当利得、訴権論に関して現代法と関聯した問題や現代法への発展を論じたものも存し(一四)、近代的意義を一番考慮はしてゐるが、主たる研究を構成してゐる訳ではない。田中教授は前述の如くパピールスの法、希臘・ヘレニズムの法及び儒帝新勅法関係の法等原史料が希臘語を以つて記載せられてゐるものに其の研究の重心があり(一五)、武藤教授は羅馬法進化に関する概観的研究に麗筆を振ふに止まり、筆者も亦現行法学と関聯を持ち得る具体的問題を取扱つたものとしては、占有に関する一篇【筧教授還暦祝賀論文集(昭和九年)】に過ぎない。然し乍ら現行法学が歴史に遡ることも必要なるが如く、法制史家が現代法を振返ることも有意義でなければならない。特に羅馬法の如く現行法に対して圧倒的支配を振ふものと一般に漠然と考へられてゐる所では、其の継受の限界に関する研究は頗る重要である。羅馬法の中世及び近世に於ける地位は、我が国に於ても古くは穂積、宮崎、春木【明治法学六四号(明治三六年)】の諸先達により、近くは寺田四郎、宮本英雄、栗生武夫、小池隆一、西本穎、戸倉広、三戸寿等の法制史家非法制史家によつて概観的には取扱はれ来つたが(一六)、具体的に我が国の法、特に謂ふ迄もなく民法に於て、或ひは制度的に、或ひは個々的規定に、或ひは単に法律的考方思惟形式に採用せられてゐる状態、或ひは反対にゲルマン法独仏固有法又は我が国固有法に阻まれて、現行法に進入し得なかつた状態を指摘する仕事は為されてゐなかつた。筆者は其等の闡明に法制史家の一大使命あるものと信じ、曾つて平野義太郎「民法に於けるローマ思想とゲルマン思想」【大正一三年】の為した如き研究を、更に具体的細目的問題に則して展開せんとして、其の前提として民法典に於ける羅馬法的なものの篩分けの仕事を開始し【中田先生還暦祝賀法制史論集(昭和一二年)、法協五七巻(昭和一四年)四号—七号】、問題の所在を確めんと欲した。近時欧洲の地に於ても、其の余りにも歴史化した羅馬法学に対する反動として、羅馬法の現実化(Aktualisierung)の叫が聞かるるに至つた【拙稿法協五七巻(昭和一四年)一二号】。筆者は其の主張に自己の考と一脈相通ずるものあるを発見して、意を強うしてゐる。
以上主として羅馬法専門家を中心として、羅馬法希臘法東部法研究の動向を概観した。然し乍ら羅馬法研究の寄与者は固より専門家に限つたことはなく、法制史家よりしては中田教授の比較法的研究には大小羅馬法又は希臘法との比較は至る所に存し(一七)、栗生教授には婚姻制度其の他に関する太い線の研究があり、非法制史家よりしては恒藤恭教授の「羅馬法に於ける慣習法の歴史及理論」【大正一三年】の如き大作を初として、現行法学者がそれぞれの領域に於て、羅馬法のみを又は羅馬法を一部として取扱つて、多かれ少かれ啓蒙的な役割を演じて居り、又大正六年帝国学士院に設けられた藤田奨学費により研究報告にも見逃すべからざるものがある。
羅馬法の研究が泰西法律文化の輸入と同時と謂つてよいのに反し、西洋法制史学の研究は遥かに遅れて始まつた。大学に於ける講義も斯かる名称のものが設けられたのは、東京帝国大学に於ては大正五年、京都帝国大学に於ては大正十五年以来のことであつて、従前は比較法制史の名称を以つて呼ばれてゐて、東京に於ては宮崎道三郎【担任明治二六年九月—三五年一〇月】、美濃部達吉【担任明治三五年一〇月—四四年九月】、中田薫【担任明治四四年九月—大正五年九月】、京都に於ては比較法制史講座が独立した後【明治四〇年五月以来】は仁保亀松【担任明治四〇年五月—大正一二年三月】、中田薫【担任大正一二年四月—一五年三月】の諸教授の担任であつた。其の比較法制史の講義中には、現在西洋法制史の名称を以つて講ぜられてゐる独仏法制史が、一大部分を占めてゐたことと思はれる。否比較法制史にして比較的ではなかつたのが、東京帝国大学に於ける講座改名の主たる理由であつた(一八)。比較法制史講座以前に西洋法制史的な内容を含んでゐたかと想像されるものに、明治二十三年の法科大学の学科科目改正時に、政治学科に「日本法制沿革」に対して「法制沿革通論」なるものがあり、二十四年の改革時に法律学科に「独逸法律史」「仏国法律史」、政治学科に「本邦法制沿革」に対して「法制沿革」があつた。文献方面に於ても、慣例上も実質的理由よりしても西洋法制史の範囲から除外されてゐる英国の公法史関係のものを除けば寥々たるものであつて、到底羅馬法と比較することは出来ない。上記小林雄七郎訳「法律沿革史事体」【明治九年】、サン・ヂヨセフ著中江篤介訳「孛国財産相続史」、ボアソナード著ヂュブスケ訳秋月種樹斎藤利行校閲「遺物相続史」【明治一三年】等の如きものが其の代表的なものであらうか(一九)。西洋法制史学に於ても民法の三大人は先駆者であつた。穂積陳重には羅馬法と同じく纏つたものはないが、断片的なものは所々に散在し、其の点弟八束が「『タシトウス』ノ『ゲルマニヤ』ニ依ル古『ゲルマン』民族ノ建国」を明治四十三年に御進講申し上げた【註(四)の書に収録】のと好対照を為してゐる。富井、梅両人の前記博士論文には仏古法の記述もある。宮崎道三郎の如きは羅馬法に対するゲルマン法の意義を認識しつつ、独逸法制史を講述した最初の人であらうが、文書に遺されたものは何等ない(二〇)。従つて羅馬法の春木教授に比すべき西洋法制史学の建設は、正しく中田薫教授である。然し乍ら中田教授の学問的研究は、比較法的手段特に独仏法制史の示唆に基いて、我が国固有法を把握する点に其の主力が存した為め、比較法的研究の一部としては、「日耳曼法系不動産質」【「法制史論集」第二巻三二二頁以下】の如き独立論文に等しきものを初めとし、parage【同第一巻一〇二頁以下】、代位相続【同三三二頁以下】、収益後見【同三五一頁以下】、寺院法precarium及びbeneficium【第二巻一九九頁以下】、commendatio【同九二八頁以下】、Genossenschaft【同九八五頁以下一〇六八頁以下】、追奪担保【法協三八巻(大正九年)一〇号】、加害家畜法【国家三七巻(大正一二年)九号】、債務者凌辱【法協四三巻(大正一四年)一二号】、家族共産【国家四〇巻(大正一五年)七号】、為替【法協五七巻(昭和一四年)八号】、手附【「徳川時代の文学に見えたる私法」五一頁】の説明の如き比較的詳しきもの、更には一段簡単なVetterschaftssystem, Parentelordnung【第一巻二三頁以下】、Altenteil【同一三二頁、一九七頁以下】、有期所有権【第二巻一七頁以下】、Reallast【同九〇頁以下】、Gewere【同二三八頁以下】、分割所有権【同八一四頁以下】、私的差押、武士の徴象、本尊の権利能力【国家三四巻(大正九年)七号】等に関する説明並びに其の他到る所に存する極めて多数の単純な比較に於て、其の蘊畜の迸りを洩らしては居るが、西洋法制史専属のものとしては、「独仏中世ニ於ケル債務ト代当責任トノ区別」【法協二九巻(明治四四年)一〇号—一二号】の一篇を数ふるに止まり、春木教授同様学問的に謙譲な同教授は、其の退職【昭和一二年三月】に至る迄独逸及び仏蘭西法制史を毎年交互に講じてゐた講義の講義案も発表してはゐない。中田教授が第一線を退いた後、現在斯学を守る法制史家は栗生武夫、金沢理康、西本穎、久保正幡等であらう。総帥格の栗生教授には羅馬法に関する研究の外、西洋法制史に関する著書論文は頗る多い。是等は現在迄には「婚姻立法における二主義の抗争」【昭和三年】、「西洋立法史第一分冊」【昭和四年】、「人格権法の発達」【昭和四年】、「婚姻法の近代化」【昭和五年】、「中世私法史」【昭和七年】、「法の変動」【昭和一二年】、「法律史の諸問題」【昭和一五年】等の単行本及び論文集に収録せられてゐる。是等大部の諸研究の内容に立入つて、教授の斯学に対する学績を述べるは其の所ではない。唯一言其の学風に付いて触れるならば、教授の法制史研究は考証学的であるよりは解釈的である。其の史実の解釈、法律思潮の把得、制度規定の内面奥底に潜む思想意図合理精神の摘発の如き才能に至つては、鋭利透徹何人の追随をも許さず、其の麗筆と相俟つて読者をして限りなき興味に引付けないでは置かないが、其の反面法源による基礎付けに磐石の物堅さの欠ける感あるは否定し難い。法源の検討、原典に遡る基礎付けより出発せんとする新機軸は、最近に至つて金沢・久保の如き新ジェネレイションによつて開かれんとしてゐる。前者は「ザクセン・シュピーゲル」【早稲田法学別冊第八巻及第九巻(昭和一二年一四年)】、後者は「リブアリア法典」【昭和一五年】の翻訳者であり、其の論稿にも例へば前者のザクセン・シュピーゲルに見えた封建制度、独逸中世の損害賠償、後者の自由分の発展、贈与の有償性、属人法主義に関する研究(二一)には、法源の基礎に立つた物堅さが覗はれる。此のことは同時に「西洋法制史講義」【昭和一一年】を以つて斯学教科書のトップを切り、「利息法史論」【昭和一二年】を以つて筆者も多大の共鳴を寄する外国法制史学の実際的方向を実践し、個々の論稿も少からざる西本教授に対する望蜀的希望である。
上記の専門家の外羅馬法と同じく、又羅馬法と同一の意味に於ける非専門家の研究も少しとしない。特に商法史に於ては非専門家の活働は活溌であり、ゲルマニストを以つて任じてゐる民法家もある様である。更に一般史家、社会史家、経済史家、政治史家よりする研究にして法律と接触するものは羅馬法以上に多数存する。
(一) 明治時代の羅馬法研究史に付いては、矢田一男「民法学者としての小野梓」新報四一巻九号、「明治時代のローマ法教育」同誌四四巻三号四号、「需斯知尼安法典」同誌四八巻五号、「明治以来ローマ法源邦訳事歴」同誌四九巻六号—一二号に極めて詳細な研究がある。本稿はこれに負ふ所頗る多し。一々引用の煩瑣を避けて、詳細は同研究に譲る。
(二) Sandars, The Institutes of Justinian; Mackeldey, Roman Law (Lehrbuch des heutigen römischen Rechts の英訳); Poste, Gai Institutiones Iuris Civilis; Hunter, Mackenzieは本文参照。
(三) 本人の名は記載せられざるも,西川鉄次郎の作なることは渡辺安積の語る所である。矢田一男、新報四四巻四号一〇九頁参照。
(四) 進講録及び両論文は「穂積陳重八束進講録」(昭和四年)及び「穂積陳重遺文集」第一冊第二冊(昭和七年)に収録。
(五) Tomii, Droit romain: Des droits du vendeur non payé; Droit français: Du droit de résolution du vendeur non payé 1882; Oumé, De la transaction en droit romain, dans l'ancien droit français, en droit français actuel comparé avec le code civil italien et le project de code civil japonais 1889. (六) 例へば小松謙次郎「羅馬社会ノ変遷ニ対シテ羅馬法ノ沿革ヲ論ス」法協三三号三四号(明治一九年)、ワイペルト(植村俊平通訳)「羅馬法及法典編纂論」同誌四一号(明治二〇年)、磯部四郎「羅馬国民の性質」明法雑誌五一号五二号五三号(明治二一年)、太田資時「羅馬ノ森林所有権」法協九巻七号(明治二四年)、某「羅馬私法の夙に其の完備を来たした所以」同誌九巻一二号(明治二四年)、グリユーベル(鎮目真一郎訳)「英国ニ於ケル羅馬法ノ影響」同誌一二巻九号(明治二七年)、岡松参太郎「保証論一班」同誌一二巻九号一〇号(明治二七年)、「連帯債務ト全部債務ノ区別」同誌一二巻一一号一三巻二号(明治二七年・二八年)、萩原守一「イルネリユス」同誌一三巻四号(明治二八年)、某「英国法と羅馬法及宗教法」同誌一四巻七号(明治二九年)、某「羅馬法に於ける殺人罪」同誌一四巻九号(明治二九年)、某「希臘及羅馬の弁護士制度」同誌一四巻一〇号一一号(明治二九年)。
(七) 梅謙次郎の「和解論」に対するÖrtmannの批評「著者の説く所は人を啓発する思想頗る多く説明の方法亦功妙なり」(春木一郎「学説彙纂プロータ」二七二頁参照)参照。Index Interpolationum Tomus I 1929にも本書は引用せられてゐる。
(八) 論叢二三巻四号二四巻二号、二六巻一号、二七巻四号、二八巻一号、三二巻二号、同四号、春木先生還暦祝賀論文集。
(九) 我が国に於ける研究史に付いては、拙稿「楔形文字法序説」国家五四巻(昭和一五年)二号三号参照。
(一〇) 志林三六巻一二号、九州帝国大学法政研究六巻二号、九州帝国大学法文学部十周年記念法学論文集、法協五四巻七号—一一号、法律時報一〇巻三号。
(一一) 拙稿岩波法律辞典「羅馬法」二八一二頁上段二八一四頁中段参照。
(一二) 法律学研究二五巻五号—八号、一〇号—一二号、二六巻五号六号、二八巻七号八号、二八巻一一号、新報三九巻五号—八号、四六巻五号—一〇号、京城帝国大学法文学会第一部論集第一冊、第三冊、司法協会雑誌一一巻一号。
(一三) 京城帝国大学法文学会第一部論集第四冊、第七冊、新報四四巻四号、公法雑誌一巻八号、二巻八号九号、国家四八巻二号三号、五一巻五号六号。
(一四) 日本法政新誌二四巻二号—四号、法律学研究二四巻七号—二五巻三号、京城帝国大学法文学会第一部論集第三冊、法律学研究二八巻一一号。
(一五) 註(八)の外論叢三〇巻五号、四三巻五号。
(一六) 岩波法律辞典「羅馬法」二八一八頁上段二八一九頁中段の外、西本穎,論叢三五巻四号、三戸寿、法学五巻九号—六巻四号、戸倉広「羅馬法制史概論」(昭和一〇年)、同「羅馬法の世界的使命」(昭和一二年)。
(一七) 例へば代位相続(「法制史論集」第一巻三二六頁)、dike paranoias(同一三一頁)、プレカリウム(第二巻一九七頁以下)、売買と貸借の混同、本尊の権利能力(国家三四巻七号)、追奪担保(法協三八巻一〇号)、家族共産(国家四〇巻七号)、paramone(国家四九巻一一号)、手附(「徳川時代の文学に見えたる私法」四九頁以下)の如し。
(一八) 宮崎・中田両教授の講義は実質的には西洋法制史であり、美濃部教授は主として公法史を講じて居たが、——当事の作品として「欧洲古代の国民総会」新報一三巻一号(明治三六年)、「第十九世紀ニ於ケル英国国会ノ発達」内外論叢二巻二号四号(明治三六年)、「欧洲ニ於ケル成文憲法ノ発達」国家一七巻一九三号一九五号二〇二号(明治三六年)、「欧洲封建制度ノ起原ヲ論ス」法協二一巻六号二二巻七号(明治三六年・三七年)、「英国代議制度ノ発達」国家一八巻二〇三号二二巻七号(明治三七年・四一年)、「仏国憲法ノ百年ノ変遷」新報一五巻五号—一二号(明治三八年)、「英国国法淵源概論」国家二〇巻六号一〇号二一巻一号(明治三九年・四〇年)、「独逸ニ於ケル土地制度ノ発達ノ梗概」国民経済雑誌二巻一号三号三巻一号(明治四〇年・四一年)等の法制史的論文あり——必ずしも比較法的ではなかつた。但し京都に於ける仁保・中田両教授の講義は講座名に適当したものであつた。尚ほ京都に於ける講座内容の変更を主張したものに、栗生武夫「西洋法制史研究の必要に就て」論叢六巻六号(大正一〇年)がある。
(一九) 前者はBoissonade, Histoire de la réserve héréditaire 1873の抄訳、後者は筆者未見にして年代も不詳なるも、中江兆民はサン・ジヨセフ著「孛国財産相続法」なるものを明治一〇年に翻訳してゐるので、略々同時代のものかと推測せられる。其の他では斎藤修一郎稿「保伊頓氏国際法沿革史」明法志林三号(明治一四年)以下、某「欧洲決闘の沿革」法協五九巻六〇号(明治二一年・二二年)、花井卓蔵「国際法ノ沿革ヲ論ス」新報四四号(明治二七年)、ウイグモーア(添田敬一郎抄訳)「質ニ関スル観念ノ淵源及ヒ其発達」法協一五巻一一号一二号一六巻二号(明治三〇年・三一年)(極めて広汎にわたる比較法の一部として)の如き特殊のものが挙げ得べきか。
(二〇) アイヒホルン伝(本文二九六頁参照)に於ては、明かにゲルマニストとしてのアイヒホルンを描いて、ゲルマン法研究の勃興を記述せんと意図してゐたに違ひないが、肝心な所で中絶して了つてゐる。尚ほエルンスト・フロユンド著前川九万人訳鳩山和夫閲「日耳曼沿革法理」(Historical Jurisprudence in Germany)(東京専門学校法律学科参考科明治二六年頃か)は主としてサヴイニーの歴史学派に関するが、ゲルマン法研究の勃興も記され、コンリングやアイヒホルンなどが紹介せられてゐる。
(二一) 金沢理康、社会経済史学九巻八号、早稲田法学一九巻、久保正幡、法協五四巻一号—三号、中田先生還暦祝賀法制史論集、国家五四巻一〇号一一号。
* 本稿を草するに当り京都帝国大学の比較法制史の沿革に関し西本穎教授の御教示を辱ふした。附記して感謝の意を表する。