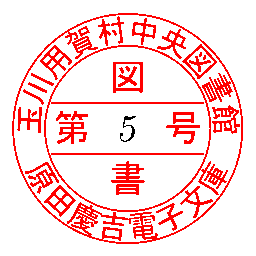
——法学提要の第三巻神と共に開始——
第一章 無遺言相続に付て
個別的取得の説明を終へたる後、包括的取得の叙述を開始して、先づ相続より始め、其の相続は或は遺言により、或は無遺言にて吾人に附与せらるることを述べたり。遺言による取得を、綱要に適する様出来得る限り完全に述べ、又順序として遺贈及び信託遺贈を説きたれば、今や無遺言相続に付て述ぶ可し。此の相続は、遺言を為さざる者が、死亡したるときに発生す。而て人の無遺言にて死亡するは、或は事実により、或は法律による。事実によるとは、全然遺言を作成せざるときなり。法律によるとは、遺言を作成するも、法律がこれを許さざる場合なり。即ち或は遺言の厳正なる形式に関する規定を無視したるが為、市民法によりて成立せざるか、或は有効に作成せられたるも破壊せらるるか(如何なる方法によりて、破壊が発生するかは、汝の知る所なり。即ち看過せられたる後生児の出生により、又は新なる自権相続人の発生により、或は自権相続人の附加による)、或は遺言者がcapitis deminutioを受け、其の侭にて死亡したるが為失効するか、或は又かくの如きものは何等発生せざるも、相続人に書き記されたる者が、相続を承継せざるときなり。
一 さて某が上述の方法に基き、無遺言にて死亡するときは、相続財産は第一位には、十二表法によりて、自権相続人に移転す。
二 而て吾人が前の法学提要に於て述べたるが如く、死亡者の権力に服する者、例へば息娘〔己が子よりは〕先に死亡せる息より生まれたる男孫女孫、予の息が産みたる男孫よりして、予の死亡前に生まれたる男曾孫女曾孫の如き者が、自権相続人と解せらる。子が実子なるか養子なるかにより、区別を設くることなし。而て合法婚姻より生まれたる者に非ざるも、勅法の規定する所に従ひ市会に与へられたる者も亦、此の自権相続人に算入することを要す。蓋し市会議員となれる者は、自権相続人の権利を保有するによる。尚某が某の女を、妻として有するに障碍あるに非ざれど、其の女と婚姻の意思なくして交はり、然る後それよりして子が生まれ、其の結果愛情増進して、彼の女と嫁資契約を為したるときは、嫁資契約書の作成後に生まれたる男子又は女子が、嫡出にして父の権力に服するのみならず、嫁資契約書作成前に生まれたる者も亦然ることを命ずる、吾人の至誠の皇帝の勅法が案出したる者も亦、彼等に附加すべし。蓋し嫁資契約の以前に生まれたる者なるも、其の後に生まれたる者に対しても、嫡出子なる最も尊敬す可き名称を取得するの機縁を与へたる者は、尊敬せらる可ければなり。而て吾人の至聖の皇帝は、仮令嫁資契約の後何人も生まるることなきか、或は生まるるも死亡したる場合にも、此の原則は嫁資契約の以前に生まれたる者に対し、適用ある可きを命じ給へり。男孫又は女孫、及び男曾孫又は女曾孫は、彼等に先立つ者が偶々死亡或は其の他の方法、例へば家長権免除によりて、己が親の権力に服することを已めたる場合に、自権相続人に算入せらる。何故となれば、若し何人か死亡したるときに、息を権力服従者として保有するときは、同人より生まれたる男孫は、自権相続人たることを許さるることなければなり。其の他の子に付ても同一なり。蓋し予が予の息、或は同人が死亡せるときは、同人より生まれたる男孫を、権力服従者として保有するときは、男曾孫は自権相続人たることを得ざればなり。後生児にも自権相続人たる可き資格を発見することを得。但し父の存命中に生まれしならんには、権力に服したる可かりし者に限る。
三 自権相続人は自ら知らざるときと雖も、相続人となる(或は相続人と観ぜらると謂ふも可なり)。否精神錯乱者となるも、尚均しく相続人たるなり。蓋し「吾人が知らざる中に、或る原因によりて、何物かが取得せらるるときは、それと同一の原因によりて、精神錯乱者も亦これを取得す」とは、一般的原則なることを知る可し。蓋し彼等は知らざる者に類似するが為なり。而て父の死亡と同時に、所有権は継続するものとせらる。即ち吾人は、父が死亡するときは、財産は死亡者の支配のもとに立つことを已め、暫く或る時間を経たる後、子の権力に服すと謂ふ者に非ずして、無中断且つ何等の中介物も従ふことなく、継続して所有権は子の権力下に発見せられ、其の間には何等の時間的間隙なしと謂ふ者なり。故に父が死亡するときは、子は未成熟たりとも、父の遺産取得の為には、後見人の助成を必要とすることなし。自ら知らざる者にすら、自権相続人として、相続財産は同人に移転せらるればなり。又成熟はすれど未成年者なる者、或は精神錯乱者も亦、これが為には保佐人の同意を必要とせず。尤も家外人に帰属する相続財産の承継は、一は後見人の意思に反し、他は保佐人の同意を欠きては、為し能はざる所なり。
四 〔父の〕死亡のときには、其の権力に服せざるも、後日均しく同人の自権相続人となるが如き場合を発見することを得。例へば予の息が敵によりて捕へられ、予の死亡後帰還したり。予の死亡のときには、予の権力服従者には非ずと雖も ポストリミニウムの権利は、同人を自権相続人となす。
五 尚又反対に予の死亡のときには、偶々予の家に在りと雖も、後日自権相続人たることを已むる場合あり。例へば甲が権力服従者たる息を有して死亡し、同人の死亡後、謀叛罪による訴追が死亡者に対し提起せられ(蓋し〔他の〕訴追は死亡によりて消滅するも、此の謀叛罪の訴追は、死亡者に対しても提起せらる)、甲は謀叛の認定を受け、此の旨を宣言する判決が下されたり。国庫は何人の財産を没収し、同人の権力服従者は相続人たらざることとなる。然れども人若し精確を穿鑿せんか、厳正の上、法律の上にては相続人たるも、同人の父の追憶が有責とせらるるによりて、相続人たることを已むるなり。見よ茲処に、或る者に附属せし相続財産の無形的名称【相続財産なる無形的財産】が、同人より剥奪せらるる場合あり。
六 息又は娘と、先に死亡せる息より生まれたる男孫更には女孫を、権力服従者として保有する某チチウスが、無遺言にて死亡したり。同人の遺言へは、息又は娘と、先に死亡せる息より生まれたる男孫又は女孫が、同時に召喚せられ、親等に於てより近き者、即ち息が、遠き者を排斥することなし。蓋し男孫及び女孫が、其の父の地位を襲ふは、正当なるによる。同一の理由に基き、人若し先に死亡せし息甲より生まれたる男孫又は女孫と、男孫も亦死亡し、唯同人より生まれたる男曾孫又は女曾孫を遺して死亡したるときも、甲より生まれたる男孫及び男孫より生まれたる曾孫は、同時に相続人となる。蓋し男孫は息の地位を襲ふが如く、男曾孫も男孫の地位を襲ふによる。故に死亡者の資産は、頭分に分割せらるるに非ずして、株分に分割せらる可く、其の結果息は遺産の半額を取得し、先に死亡したる息より生まれたる男孫は、二人にせよ、更に其れ以上にせよ、他の半額を取得すと謂ふは、当然の帰結なり。蓋し彼等の父が生存せしならんには、半額を取得したる可きが故に、彼等其の地位を襲ふ者も、固より半額を取得す可く、父が生存せしならんには、六ウンキアが与へらる可かりしが如く、彼等にもその六ウンキアが与へらるるなり。又人若し息は遺さず、唯二人の先に死亡したる息等より生まれたる孫を遺し、中一人又は二人の孫は、一人の息より生まれ、三人又は四人の孫は、他の息より生まれたるときは、一人又は二人は半額を取得し、三人又は四人は他の半額を取得す。
七 吾人が某は死亡者に対し、自権相続人と観ぜらるるか否か詮議するときは、死亡者が無遺言なることが、明かにせられたる日に於て、同人に自権相続人たる資格が備はることを要求す。此のことは、遺言が全然作成せられざるときのみならず、作成はせられたるも、何人もそれよりして、相続人とならざる場合にも発生す。故に若し息と、同人より生まれたる孫を権力服従者として保有する者が、息を相続より廃除して、家外人を相続人に書き記し、遺言者の死亡後、家外人が考慮中、息が死亡し、其の後家外人が、或は拒絶し、或は相続人たることを得ざるに至れるときは(蓋し偶々条件付にて相続人に書き記され、而て条件が不成就となりたるが為)孫が祖父に対し、自権相続人となる可し。遺言者が無遺言にて死亡したることが明かとなれるときには、中間時に息の死亡したるが為、孫のみが同人の家に発見せらるればなり。
八 同じことは、若し祖父の存命中に、孫が懐胎せられ、祖父の死亡後に出生し、家外人が、或は其の意思により、或は偶然にて、相続人となることなきときに於て、他に優先する者なくして、孫のみが死亡者の家にあることが発見せらるるときにも発生す。若し息より生まれたる孫が、祖父の死亡後懐胎せられ且出生し、次に中間者が死亡し、家外人は、〔祖父の〕相続人とならざるときは、孫は自権相続人たることなかる可し。蓋しかかる孫は、如何なる種類の親族関係をも、遺言者に対して有することなければなり。同じく予の息が家長権被免除者たるときに、養子に収養したる者も亦、卑属の中に算入せらるることなし。蓋し予若し無遺言にて死亡するが如きことあらば、家長権被免除者たる予の子が先に死亡するも、該家長権被免除者が生存中に、養子に収養したる者は、如何なる種類の親族関係をも、予に対して掌握することを得ざれば、予の権利を承継することなし。かくの如き者は、市民法に基きて、予の相続人となることを得ざるのみならず、血族として〔遺産〕占有を請求することも不可能なり。然れども是等は自権相続人に関してのことなり。
九 家長権免除を受けたる子は、〔法学提要の〕第二巻に於ても、吾人が述べたるが如く、市民法に基く限り、其の親に対し、何等の権利を有することなかる可し。何故となれば、彼等は親の権力に服することを已むるが故に、自権相続人たることを得ず、又発生したるcapitis deminutioの故に、血族として、十二表法によりて、召喚せらるることもなきが為なり。法務官は自然上の権利に着目して、彼等にunde liberiの〔遺産〕占有を与へ、何人か死亡したる時に於て、あたかも彼等を権力服従者として保有したるかの如く、死亡者の遺産に召喚したり。彼等のみが存すると、死亡者が他に権力に服従する子を有すると問はず。蓋し彼等【他の子】と共に相続人となればなり。故に人若し二人の子を遺して、無遺言にて死亡し、中一人は家長権被免除者にして、他は権力に服するときは、市民立法に関する限り、一人の権力服従者のみが、自己のもとに自権相続人たることより生ずる権利を保持して、相続人となる可し。然れども家長権被免除者は、法務官の恩恵によりて支持せられ、半額に召喚せらるるが故に、自権相続人は全額を相続するに非ずして、一部を相続することとなる可し。
一〇 予甲乙二人の子を、権力服従者として保有し、乙を権力内に保有し、甲はこれを家長権被免除者となしたり。甲家長権被免除者となり、自権養子縁組によりて、自らチチウスの養子となれり。若し予が無遺言にて死亡するが如きことあらば、乙のみが予を承継し、チチウスの養家にある甲も亦、承継することはなし。蓋しかくの如き子は、予の財産を承継することなければなり。予は予の死亡のときに於て、〔甲が〕養家にあるときに限りて、是等の言をなす。蓋し若し予の生存中、チチウスが同人〔甲〕を家長権被免除者となしたるときは、彼は均しく実父たる予の財産を承継すること、あたかも予が同人を家長権被免除者となすも、養家のもとには決して在らざるときと同然なればなり。故に同人の養父となりたる者に関する限りに於ては、同人は他人と称するは当然なり。然れども予の死亡後、チチウスが同人を家長権被免除者となしたるときは、彼【予の誤ならん】に対しても他人と解せらる可し。而てかかる見解が行はるるに至りたるは、実親の財産が何人に帰属せしめらる可きか、息なるか、宗族なるか〔の決定〕が、養父の権限内に存することが、不当と考へられたるが為なり。蓋し息を有する予が、同人を家長権被免除者となし、次で同人はチチウスの自権者養子となり、予は宗族を遺して死亡するときは、チチウスは子を養子縁組内に止めて、宗族に相続財産の承継権を与ふることも得可く、亦宗族を排斥して、養子をして予の資産を相続せしめんが為、予の死亡のときに、同人を家長権被免除者となさんと欲せば、故障なくこれを実行することも得可ければなり。吾人は、予が何人によりて相続せらる可きか、予の息によりてか、或は宗族によりてか〔の決定〕が、養父の権限に服するは、極めて不条理なりと謂ふ者なり。
一一 故に養子に属する権利は、実子のそれよりも僅少なり(直前に述べたる所を想起することを要す。其処に於ては、養父によりて家長権被免除者とせられたる者は、養父に対し、他人と考へらると謂ひたり)。蓋し予の実子が家長権被免除者となるときは、市民法に関する限り、承継の権利を喪失すと雖も、法務官によりて、子に算入せらるればなり。然るに養子が家長権被免除者となさるるときは、市民法に従ふも、子の地位を喪失し、法務官も彼等には救済を与ふることなし。而てこれ正当なり。何故となれば、自然的権利は、市民法これを除去することを得ず、又自権相続人たることを已めたるの故を以て、自然上息たり、或は娘たり、或は男孫たり、或は女孫たることをも已むる訳には非ざるも、家長権を免除せられたる養子は、他人たることを開始するが為なり。蓋し養子縁組によりて保持せし息又は娘の名称は、他の市民的の理、即ち家長権免除によりて、消滅すればなり。
一二 是等のことは、啻に無遺言相続に付て該当するのみならず、相続人にも書き記されず、合法的即ち個別的廃除者ともならざりし子に対し、法務官が父の遺言に反して許与したる、遺言書に反する〔遺産〕占有にも該当す。蓋し死亡者の権力内に発見せらるる者、及び家長権被免除者となりたる実子にして、看過せられたる者には、遺言書に反する〔遺産占有〕を以て武装し、而て実父の死亡のときに養家に止まる者には、遺言書に反する〔遺産占有〕を施すことなきも、若し予が予の養子を家長権被免除者となすときは、予が無遺言にて死亡するも、予を相続することなきのみならず、予の遺言の中にて看過せらるるも、其の遺言に反して、遺言書に反する〔遺産占有〕を受くることなかる可ければなり。何故となれば、予の子の中に算入せらるることを已むるが為なり。
一三 次のことを記憶することを要す。即ち予の実子が自ら養子となりて、養家に在るとき、又は予の死亡後、養父によりて家長権免除を受くるときは、仮令unde liberiの〔遺産〕占有に基くものとして、実父たる予の財産を承継することを得ずと雖も、他の順位、即ち死亡者の血族が遺産を承継す可き順位に基きては、召喚せらる可し。但しこれは、予が自権相続人も、家長権被免除者も遺すこともなく、又予に何人か宗族も存せざるとき、初めてよく然り。蓋し彼等は彼に優先せしめらるればなり。即ち法務官は、自権相続人たると、家長権被免除者たるとを問はず、先づ子を召喚し、是等の者が存せざるときに、宗族を召喚し、而て若し宗族なきときは、血族が召喚せられ、予の子にして養家に在る者は、其の血族の中にて、初めて現はるるなり。
一四 次のことを予備知識として保持す可し。予若し権力服従者たる三人の子を有し、一人を汝に養子に与へたるときは、かかる養子縁組は、ex tribus maribusと称せられ、〔それに付ては〕アフィニアーヌム元老院議決ありて、汝は三人の男子の中より養子に与へられたるかかる子には、常に汝の財産の四分の一を遺すことを要す可く、若し同人に遺さざるときは、元老院議決は、其の四分の一の請求に付き、汝の相続人に対して提起す可き訴権を、同人に附与す。汝に予め是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。前述したる所は、総て古く行はれたる所なり。今や吾人の皇帝は、実父によりて養子に与へられたる者に付て論議せし其の勅法によりて、これに特別の改革を加へ給へり。蓋し帝は、子が養子縁組中に在るが為、実父の相続権を喪失し、家長権免除によりて養子縁組が容易に解消して、何れの父に対する相続にも召喚せられざる或る場合——これ吾人も亦述べたる所なり——を発見し給ひ、帝の常例に従ひて、これをも良き方に導き、上に述べたるが如く、勅法を制定し、それによりて、仮令実父が其の子を他人の養子に与ふるも、実父のもとに於ける総ての権利は原状に止まり、あたかも全く養子となることなきと同様、実父の家を出づることなき旨を命じ給へり。唯一の場合に於てのみ、養子縁組は或る種の効果を発生すと観ぜらる。子が養父とも称す可き者の無遺言相続財産を承継し得ることこれなり。若し遺言が同人【養父】によりて作成せらるるときは、市民法によるも、法務官によるも、同人の相続財産よりして何物をも引き抜くことを得ず。又養父には、何等自然上の結帯によりて結ばるるに非ざるが如き者を、相続人に書き記すか、或は廃除人と為す必要は存することなきを以て、遺言書に反する〔遺産占有〕を要求することなく、不倫遺言の訴を提起することもなし。予は尚謂ふ、若しアフィニアーヌム元老院議決に従ひ、三人の男子より同人を養子に収養したるが如き場合にも、然ることなしと。即ちかかる養子縁組に於ても、四分の一が元老院議決に基き、同人のもとに保存せらるることもなく、四分の一の請求に対する何等かの訴権も備はることなし。唯吾人の至聖の皇帝の上記の勅法に基き、実父が当該の子の祖父に、養子に与へたるが如き養子は例外とす。蓋しかかる場合には、双方の権(一は親族関係による自然的権利、他は養子縁組に基く法律的権利)が競合するを以て、何人かが自主権者なるときに自ら養子となれるときと同じく、かかる養子縁組には、古の権利を保存するなり。是等のことは、前に述べたる勅法の文言よりして、特別的にも個別的にも、知ることを得。
一五 同じく次のことも、然る可き留意に浴したり。即ち古人は、男性よりの卑属をより以上に尊重し、男性よりの卑属たる男孫又は女孫のみに、自権相続人の権利を附与し、彼等を宗族に優先せしめたるも、娘よりの孫、及び女孫よりの曾孫は、これを血族の中に算入し、宗族に次いで召喚せらる可きものとせり。蓋し母方の祖父の財産に召喚せらるるにせよ、父方母方何れの祖母曾祖母の相権財産に召喚せらるるにせよ、宗族が存せざるときに限ればなり。然れども数年前君臨し給ひし諸帝は、かくの如き失当を匡正せざる侭に、放置し給ふことなし。蓋し孫及び曾孫の名称は、男性及び女性の卑属に共通なるを似て、これが為、彼等に同一の地位と同一の相続順位を恵与し給ひたればなり。但し男性側の者は、自然の知遇も得、古人によりても尊重せられたる者として、少しく余分に取得、即ち三分の一丈多額を取得す可きものとし給へり。蓋し人若し息及び死亡せる娘より生まれたる男孫又は女孫、男曾孫又は女曾孫を遺して死亡するときは、息は八ウンキアを取得す可く、先に死亡したる娘より生まれたる男孫又は女孫、男曾孫又は女曾孫は四ウンキア、即ち彼等の母又は祖母が生存せしならんには、取得したる可かりし額よりは、三分の一丈少額を取得す可し。蓋し彼等の母又は祖母が生存せしならんには、彼の女は六ウンキアを取得したる可きも、彼の女は死亡せるを以て、彼の女より生まれたる孫又は曾孫は、祖父又は曾祖父の遺産〔より取得する額〕の三分の一、即ち二ウンキア(相続財産の六ウンキアの三分の一は、二ウンキアなればなり)丈少額に取得す可し。而て又若し婦女が息又は娘と、先に死亡したる息又は娘より生まれたる孫又は曾孫を遺して死亡するが如きことあらば、息又は娘は八ウンキアを取得す可く、先に死亡せる息又は娘より生まれたる孫又は曾孫は、四ウンキアを取得す可し。即ち彼等も亦彼等の父又は母、祖父又は祖母——父方たると母方たるとを問はず——が取得す可かりし額よりは、三分の一丈少額を取得す可し。祖父又は祖母は、父方たると母方たるとを問はざるは、相続財産に付て問題となれる死亡者は女性なれば、孫又は曾孫が、男性よりの卑属たると、女性よりの卑属たるとによりて、何等の差異を生ぜしめらるることなければなり。若し男が先に死亡せる娘より生まれたる孫を遺して死亡し、或は又婦女が死亡し、先に死亡せる息又は娘より生まれたる孫を遺すが如きことありて、而も死亡者に宗族が残存するときは、古くは既に述べたるが如く、十二表法が、宗族をかかる孫に優先せしめたるも、今日に於ては、単に孫が残存するに過ぎざる場合にも、孫又は曾孫は自己を生みたる者の地位を襲ふを以て、宗族には十二表法に基きて、死亡したる男子又は女子の資産に対しては、何等の承継権が附与せらるることなし。然れども既に述べたるが如く、死亡せる男子又は女子に息又は娘あるときは、死亡せる男子に付ては、女性の側の孫、又死亡せる女子に付ては、男性又は女性の側の孫は、其の尊属よりは三分の一丈少額を取得す。然れども彼等の対抗が、唯宗族に対する場合には、尊属の全遺産を収得す可し。然れども古くかかる孫に対して九ウンキア、宗族に対して三ウンキアを附与したる勅法存したり。
一六 更に後に発布せられし勅法にして、これに反対のものあるも、其の趣旨は曖昧なり。吾人の皇帝は、曖昧より生ぜるかかる疑義を除去し、上記の他の勅法を其の勅法彙纂の中に記入することも、テオドシアーヌス法典より移したるものを、其の勅法彙纂内に採録することも許可し給ふことなく、自ら一般的且極めて明確なる勅法を発布して、九ウンキアと三ウンキアの分割を廃止し、上記の孫及び曾孫を、全く宗族に優先せしめ給へり。蓋し傍系親が卑属親よりも優位にありとは、背理なればなり。今又簡単に該勅法が、其の中に規定せらるる所と、其の中に指示せらるる期日に従ひて、効力を保持す可き旨を命じ給へり。而て前に吾人の説きたるが如く、人若し息と先に死亡せる息より生まれたる男孫及び女孫を遺して死亡するときは、先に死亡せる息より生まれたる孫は、株分にて召喚せられ、頭分にて召喚せらるることなきが如く、同じく若し男子が息と先に死亡せる娘より生まれたる孫を遺して死亡するときは、総ての孫は株分にて召喚せらる。但し三分の一丈少額を取得す。若し女子が、息と先に死亡せる息又は娘より生まれたる孫を遺して死亡するときは、孫は幾人ありとも、同じく四ウンキアを取得す可し。而て男子が息は遺さず、唯先に死亡せる息等より生まれたる孫を遺し、一人の息よりは一人又は二人、他の息よりは三人又は四人と数を異にするときは、分割は頭分にて為さるることなく、株分にて為さる。而て一人又は二人は六ウンキアを取得す可く、三人又は四人は他の六ウンキアを取得す可し。同じく又男子が、先に死亡せる娘等より生まれたる孫を遺して死亡し、或は又女子が先に死亡せる息又は娘を遺して死亡し、一方の側よりは例へば一人又は二人、他方の側よりは三人又は四人と数を異にするときは、相続財産は株分にて分割せられ、一人又は二人は六ウンキアを取得し、三人又は四人は他の六ウンキアを取得す可し。蓋し死亡者が女性にして、孫が孫に対して争ひ、伯叔父又は伯叔母に対して争ふには非ざるときは、先に死亡せる者の取得す可かりし全額を取得す可く、三分の一の減額は為さるることなければなり。
第二章 宗族の法定相続に付て
次のことを予備知識として保持す可し。親族とは一般的の名称にして、三に別たる。尊属親、卑属親、傍系親これなり。而て尊属親とは吾人を産みたる者なり。例へば父母、祖父祖母、曾祖父曾祖母、及び尚彼等に遡る者なり。卑属親とは吾人より生まれたる者、例へば息娘、男孫女孫、男曾孫女曾孫、及び尚彼等より下る者なり。傍系親とは吾人を産みたる者にも非ず、吾人より生まれたる者にも非ず。唯吾人と同一の血統と根源を共にする者、例へば兄弟姉妹、伯叔父伯叔母、甥姪、及び尚彼等より下る者なり。而て傍系の親族は二に別たる。宗族及び血族これなり。而て宗族とは男性によりて吾人に結合せらるる者にして、血族とは女性によりて然る者なり。而て親族の各順位は諸種の異る親等を有す。尊属及び卑属に付ては、親等の了解は比較的簡単にして容易なり。蓋し是等の者の各は一親等を為し、簡単に謂はば、代の数丈親等も亦存すればなり。然れども傍系親の親等を発見するは、極めて困難にして、且了解にも易からず。蓋し吾人は、傍系の者へは容易には至ることを得ず、先づ傍系親の原因者に達する迄、尊属に向つて行進を為し、これを探し当てたる後、問題となれる傍系の人物に向つて、下ることを要すればなり。かくの如くにして、一は上道に向ひ、他は下道に向つて、連結せる全部の代を計算することを要す。即ち各代を各一個の親等に置き、以て計算を為す可し。卑属に対しては此のことは容易なり。例へば予の息は何等親に属するか。予は〔彼を〕産みたり。見よ一代が一親等を作れり。故に予に対して一等親の関係にあり。孫は何等親に属するか。予は息を産み息は孫を産みたり。見よ二代が二親等を作れり。故に孫は二等親に属す。曾孫及び玄孫に付ては、順次これに同じ。尊属に付ても同様なり。父は何等親に属するか。父は予を産みたり。見よ一代が一親等を作れり。故に予に対し一等親の関係にあり。祖父は何等親に属すか。父は予を産み、祖父は父を産みたり。見よ二代は二親等を作れり。故に祖父は二等親に属す。母祖母及び其の他、男性又は女性の全尊属に付てもこれに同じ。傍系親に付ては、既に述べたるが如く、親族の原因を為したる者に向ひ、上に趣きて代を計算し、更に転じて問題となれる者に至る迄、下に下つて代を勘定することを要す。故に人若し汝に向ひて「汝の兄弟は汝に対し、何等親の関係にありや」と問はんには二等親と謂ふ可し。何故なるか。父に向つて上り、父より汝に至る一代が一親等を作るを見よ。然る後、汝は代の原因者を発見するが故に、兄弟に向つて下り、其の間に他の一代を加ふ可し。見よ二代は二親等を作れり。故に兄弟は二等親に属すと称して、正しく可なり。又人若し汝に向ひて「伯叔母は汝に対し、何等親の関係にあるか」と問はんには、三等親と謂ふ可し。蓋し汝は、汝の父に向つて上り、父は予を産み、祖父は父を産みたりと謂ふことを要す。見よ此処に二代あり。同じ祖父は予の伯叔父を産みたり。見よ三代は三親等を作れり。故に伯叔父は予に対して三等親の関係にあり。かくの如くにして、これに続く者に付ても、同一の法則を守りて、親等を解することを得可し。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。人若し何等自権相続人も、自権相続人の地位に召喚せらるる者——法務官によりて召喚せらるる家長権被免除者の如き、或は勅法によりて召喚せらるる前に述べたる孫の如き——も遺さずして死亡し、或はかかる者が存在するも、何等かの事情にて、死亡者の遺産を承継せざるときは、十二表法は第二順位に於て 最近の宗族を相続に召喚す。
一 宗族とは法学提要第一巻に於ても説明したるが如く、父よりして血族たる者として、男性によりて吾人に結合する親族なり。故に同一の父より生まれたる兄弟は、相互の間に宗族にして、羅馬の語によればconsanguinei、希臘の語によれば、ὅμαιμοιと称せらる。同一の母の出なるか、異る母の出なるかは、何等区別することなし。又予の父方伯叔父は、予の宗族にして、予も亦彼の宗族なり。又二人の男兄弟より生まれたる者も、相互の間に宗族的権利を保持し、彼等はfratres patruelesと称せらる。consobriniと称するは濫用なり。蓋しconsobriniとはconsororiniとして、本来二人の姉妹より生まれたる者を称すればなり。此の原則を用ひて、幾多の親等に到達し、以て予の父方伯叔父の息及び同人より生まれし孫は、宗族なりと謂ふことを得。要言せば、汝が女性の人間が親族関係を切断せざることを見る間は、生まれたる者を宗族と呼ぶ可し。而て父の生存中に生まれたる者のみならず、同人の死後生まれたる者も亦、同血者の権利を予に対して保持す。而て十二表法によりて、全宗族が同時に死亡者の遺産に召喚せらるるに非ずして、某が無遺言にて死亡したることが明かとなりたるとき、比較的近き親等を保持する者が、召喚せらるるなり。これを如何に解するかは、先に至りて学ぶ可し。故に若し兄弟と、其の外に伯叔父が存するときは、兄弟は二等親、伯叔父は三等親に属するを以て、兄弟が優先せしめらる。
二 出生のみならず、養子縁組も亦、宗族関係を結成す。例へば予実子を有し、更に某を養子に収養したり。是等の者は、相互を宗族と呼ぶのみならず、同血者と呼ぶ可し。更に他の宗族、例へば予の兄弟、或は父方伯叔父、或は更に父方伯叔父の息又は孫が、某を養子に収養するときは、吾人の間に宗族関係が結成せらる。
三 相続財産は、男子の間に宗族的権利によりて移転せらるるときは、仮令死亡者と同人を承継する者が、相互の間に、比較的遠き親等の関係にあるとも可なり。蓋し〔各代〕全部男性を通じての父方伯叔父の男玄孫なるときは、同人は七等親に属するを以てなり。蓋し伯叔父は三等親に属し、同人の息は四等親、男孫は五等親、それより生まれたる男曾孫は六等親、男玄孫は固より七等親に属すればなり。然れどもこれは男子間のことなり。若し相続人が女子なるときは、宗族的権利によりて、死亡者の遺産を取得することを得るは、唯同血者たる場合、即ち姉妹なる場合のみ。故に父方の伯叔母、又は兄弟の娘なるときは、宗族としては、相続することを得ざりき。蓋し一般に、同血関係の親等を越えたる女性は、宗族的権利によりて相続することなきは、汝の知ることを要する所なればなり。然れども若し死亡者が女性にして、同女の相続財産に召喚せられたる者が男性なるときは、三等親に属すると、四等親たると、五等親たるとを問はず、宗族的権利によりて相続したり。〔即ち〕予の兄弟又は父方伯叔父の娘、或は父方伯叔母が若し死亡するときは、予は宗族として相続したり。然れども若し予が死亡するときは、彼女等は宗族的権利によりて、予の相続財産を承継することなかりき。此のことは次の如くに解せられたり。即ち男子は戦争に従事し、賦役を負担し、政務官となる等、国家に有用なるを以て、此の男性が女性よりも、より屡々相続財産に召喚せらるるは、国家にとり必要と観ぜられたるによる。然れども彼女等が、家外人類似の者として、死亡者の承継より全然除外せらるるは、極めて非道なることと観ぜられたるを以て、法務官は自然の権利に着目して、血族に対して無遺言相続への承継権を恵与したる部門に基きて、換言せば、宗族もなく、より近き血族も発見せられざる場合に、彼女等にunde cognatiの〔遺産〕占有を約したり。
三イ 吾人は、女性は宗族的権利によりて相続するも、同血関係の親等を越えたる者は、相続することなしと謂ひたるも、これは十二表法の発見には非ず。蓋し十二表法は、法律に通例なる簡単を愛して、自権相続人に倣ひ、如何なる親等に属するかを問はず、男性又は女性の全宗族を、均しく死亡者の遺産に召喚すればなり。然れども十二表法の後、同法よりは後なるも、皇帝の勅法よりは以前の法学者が、厳正を好みて上記の区別を設け、彼女等を全然親族の承継より排除し、遂に(上述の如く)法務官が学者によりて国内に移入せられたる苛酷を、博愛心を以て匡正し、彼女等を血族として召喚し、或は又欠けたる所を補ひて(此のことは彼等法務官の慣習なり)、第三順位血族的順位を発案し、unde cognatiの〔遺産〕占有を彼女等に約して、彼女等を血族として召喚したり。
三ロ 吾人の至聖の皇帝は、十二表法によりて発案せられたる、承継に関する男性と女性の平等を遵守し、一方には法務官が女性を全然承継の外に置くことを許さざりし博愛心を嘉し給ひしも、尚他方彼等法務官は、婦女に対する不正の救済手段を、完全に発見したる訳には非ずと宣へり。蓋し一の同一親等に属して男子と競合し、自然の親族関係を有するのみならず、宗族関係を保存する婦女が、男子と同一の方法によりて承継することなく、唯単に姉妹のみが、宗族的権利によりて、死亡者の遺産を承継するは、極めて非道なればなり。吾人の至聖の皇帝は、かかる理由に動かされ給ひ、古代の権利——十二表法によるものを指す——を呼び返し、且其の勅法を以て、男性によりて死亡者に関係する者は、男子たると女子たるとを問はず、同一の方法によりて、無遺言法定相続に召喚せらる可き旨を命じ、親等の優先を常に保存し給へり。蓋しより近き男子又は女子を、遠き者に優先せしめんと欲し、以て婦女が同血関係の親等を越ゆるの故を以て、より僅少の権利を保有することは、希望し給はざればなり。従つて人若し同一親等に属する二人の親族を遺して死亡し、其の中一人は男子他は女子なるときは、同時に承継す可し。例へば先に死亡せる父方伯叔父の息と、伯叔父の娘とが存するときには、彼女は、仮令四等親に属し、同血身分を越ゆと雖も、己が兄弟と共に、均しく死亡者を承継す可し。
四 吾人の至聖の皇帝は、上記の勅法に於て、此のことを規定し給ふに当り、次のことをも附加し給へり。即ち一の親等——或は人間と謂ふも可なり——を血族的地位より宗族的地位に移し給ひしことこれなり。蓋し予の兄弟の息及び娘が宗族として、既に行はるる所に従ひ、予の相続財産を承継するのみならず、姉妹——父を同じうすると、単に母のみを同じうするとを問はず——の子も亦、然る可き旨を命じ給ひたればなり。故に人若し先に死亡せる兄弟の息或は娘と、先に死亡せる同父又は同母姉妹の息或は娘を遺して死亡するときは、同一割合を以て承継し、一は父方の伯叔父として、他は母方の伯叔父として、これ【死亡者】を承継すること、あたかも全部が男性より出たるが如し。唯此のことは、既に例を設けたるが如く、兄弟及び姉妹——彼等は是等の卑属なり——が存せざる場合のことと、解することを要す。蓋し是等の者が生存して、死亡者の遺産を嘉納するときは、これに続く親等出の者は、静止す可けばなり。勅法によりて発案せられたる上記の者は、遺産を頭分に分割して承継し、株分に分つことなし。前に述べたる所及び今説く所は、設例を以て明かにすることを要す。某同母姉妹と、先に死亡したる兄弟より生まれたる息を遺して死亡したり。古くは死亡せる兄弟の息は、宗族として相続せり。親等に於ては多けれど、——蓋し同人は三等親に属するに、姉妹は二等親に属せばなり——より強力なる地位に基けばなり。然れども今日に於ては、吾人の皇帝の勅法によりて発案せられたる所に基き、同女は兄弟の息よりは優先せしめらる可し。頭分とは次の如し。例へば予偶々先に死亡せる兄弟の子と、先に死亡せる姉妹の子とを遺して、無遺言にて死亡し、兄弟には三人又は四人の子あり、姉妹には一人又は二人の子ありたり。姉妹の子が半額、兄弟の子が半額を取得すと謂ふことを要せず。然らずして分割は頭分に行はる。故に兄弟の子は四人なれば四分を取り、姉妹の子は二人なれば二分を取る可し。
五 無遺言にて死亡し、異る親等に属する多数の宗族あり。十二表法は比較的近き者を召喚す。故に例へば死亡者の兄弟と、先に死亡せる兄弟の息、又は父方の伯叔父も存するときは、兄弟が好地位にある可し。蓋し一は二等親に属するに、他は三等親に属せばなり。仮令十二表法は「最近の者共」とは謂はず、「最近の者」を優先せしむと謂ひて、単数を用ひたりと雖も、比較的近き者が一人なる場合に、彼が死亡者の遺産に召喚せらるるのみならず、近き親等にある者が多数なる場合にも、全部が同時に承継す。故に死亡者に三人の兄弟と、先に死亡せる者の子一人が存するときは、三人の兄弟は、先に死亡せる兄弟の子に打勝ちて、相続す可し。同じく又十二表法に最近の者と称せられ、これは本来多数親等の比較を示すものなり。然れども言葉の意義は其の意なるも、存する親等は一個なる場合にも、十二表法に基く召喚が発生す。例へば某父方の伯叔父のみを遺して死亡し、他に親族を有せざるときは、自己が比較せらる可き他の親等に属する者なしと雖も、伯叔父は最近の者として承継す。
六 而して何人か無遺言にて死亡するときは、死亡の時に於て、被相続人に最も近き者が、最近の者として承継す。然れども人若し遺言を為して死亡するときは、何人も遺言に基きて、死亡者の為相続を承継する者無きこと明かとなりたる時に於て、何人が最も近かりしかを詮議す。蓋し其の時初めて、本来某は無遺言にて死亡したるものと謂ふ可ければなり。而て此のことは、時としては長時間を経過して、明かとなることもあり。其の中間時に於て、死亡時には比較的遠き親等にありし者が、比較的近き者となりて相続するが如きことは、往々発生す。例へば某が、兄弟及び父方の伯叔父の存するとき、家外人を相続人に書き記して、死亡したり。指定相続人は、承継す可きか否か考慮せり。其の間に遺言者の兄弟は死亡し、其の後家外人は遺産を拒絶したり。伯叔父は比較的近き者として承継す可し。蓋し今や死亡者が、無遺言なることが明かにせられたればなり。死亡の時には、当時死亡者に兄弟が存するを以て、先行せらると雖も、指定に基きて、遺産を承継する者何人もなきを以て、伯叔父は此較的近き者たることが判明すればなり。
七 宗族的承継に付ては、十二表法は転属を知らず。即ち吾人は比較的近き者が、或は承継前に死亡し、或は相続財産を拒絶する場合に、それに次ぐ親等に属する法定者が、相続すとは謂ふことなし。例へば某、兄弟及び父方の伯叔父の存するときに、無遺言にて死亡したるときは、兄弟が比較的近き者として、召喚せられたるは明かなり。若し兄弟が或は承継前に死亡し、或は相続財産を拒絶するが如きことあるも、十二表法は転属を知らざるが為、伯叔父は宗族として、承継することなかる可し。然れども法務官は、市民法の誤を匡正し、完全には非ざるも、或る救済手段を発案したり。蓋し転属が存在せざるが為、宗族的権利を欠くを以て、血族的地位よりして伯叔父を召喚したればなり。吾人の至聖の皇帝は、総てに通じて立法が完全なる可きことに努力し給ひ、勅法を制定し、其の中にて、保護者の権に関して述べ、博愛心を以て此のことを凝視し、宗族的相続に付ても、転属の存す可き旨を命じ給へり。蓋し法務官が血族に対して恵与したるもの(彼等の間の転属なり)が、宗族に対しては存せずとは、理由なきことと解せられたるによる。特に後見の負担のもとに、転属の存するをや。蓋し人若し未成熟者にして、且〔同人には〕二人の宗族、例へば兄弟及び父方伯叔父が存するときは、兄弟が比較的近き者として、後見に召喚せらる可く、彼若し死亡し、かくして二等親が消滅するときは、転属を発生し、伯叔父も、亦法定後見人となる可ければなり。故に後見の負担に付て適用あるものが、相続の利得に付ては適用なしとは背理なり。
八 特別に信託契約を結んで、息又は娘、男孫又は女孫、及び彼等より後の者を、家長権被免除者となしたる父は、法定者の順位よりして、死亡せる卑属の遺産に召喚せられたり。今日に於ては、吾人の皇帝の勅法に基き、特別に信託契約を結んで、家長権被免除者となすことは無用なり。蓋し推定により且暗黙的に、此のことが家長権免除の中に内在す可きことを、上記の勅法は希望すればなり。
第三章 テルツルリアーヌム元老院議決に付て
前の所に於て述べたる所よりして、吾人は相続に対する、十二表法の厳正及び偏狭を知りたり。蓋し一方家長権被免除者は、これをcapitis deminutioの故に認めずして、父の承継より排除し、他方男性の出を尊重し、女性の出を無視すること、無遺言にて死亡せる息又は娘を、母が相続することなく、母が是等の者によりて相続せらるることなかりし程なればなり。然れども法務官は常に自然〔の情〕を醸成して、血族の順位にて、是等の者の相続に相互を召喚し、彼等にunde cognatiの〔遺産〕占有を附与したり。
一 此の法律の偏狭は、其の後救済を受くることとなれり。先づ神聖クラウヂウスは、死亡したる子の慰籍の為に、母に法定相続を附与したり。
二 暫くしてハドリアーヌス帝の代、テルツルリアーヌム元老院議決制定せられ、これに付き更に完全なる立法を為し、子を失ひて悲嘆せる母に、法定相続を恵与したり。祖母に対しては、此の恩典を与ふることなし。蓋し若し子が母を遺して死亡し、而て彼女が生来自由人にして三子の権、被解放者にして四子の権を有するときは、宗族の如く、無遺言にて死亡せる男及び女の子の遺産を、承継す可き旨を宣言すればなり。而て単に母が自主権者なる場合のみならず、自己の父の権力に服する場合たりとも然り。但し彼女は、父の命令に従ひて承継す。
三 死亡者の相続財産に於ては、卑属が母に優先せしめらる。蓋し人若し卑属及び母を遺して死亡するときは、死亡者の卑属が承継すればなり。卑属が自権相続人たると、自権相続人の地位に在る者、例へば家長権被免除者たると、一等親に属すると二等親に属すると、更には其れ以上たるとを問はず。更に又死亡者が女性なる場合にも、死亡者の子は、自己の祖母が相続することを許さず。男子又は女子が死亡したり。父は生存するも、其の権力服従者には非ず。尚母もあり。父が優先せしめらる可し。若し祖父又は曾祖父が生存するも、其の権力服従者に非ざるときは、相続に関して争ふ者が、唯彼等【祖父又は曾祖父】のみなる限り、母が優先せしめらる。而て死亡せる男子又は女子の同血兄弟は、彼等の母に優先せしめらる。若し同血姉妹が存するときは競合す。即ち同一の割合を以て相続す。若し兄弟と姉妹と母とが存するときは、兄弟が母に優先せしめらる。母が子の権を有するとも尚然り。而て遺産は兄弟と姉妹との間に、共有となれり。故に単に死亡者に兄弟が存するときも、兄弟と姉妹と母が存するときも、母は排除せられたり。若し兄弟は存せず、姉妹と母のみなるときは、母も六ウンキア、姉妹も亦六ウンキアを取得す可し。
四 然れども是等は古のことなり。吾人の皇帝の勅法が制定せられ、同帝の勅法彙纂にも編入せられたるが、此の中にて自然に眼を注ぎ、且時には死亡迄惹起する分娩による危険を見、意思によらず、偶然の事故に基いて発生するものが、母に損害を加ふるは、非仁も甚だしきものと思惟し給ひて、母を救済す可き旨を規定し給へり。蓋し母が生来自由女にして三人の子、或は被解放女にして四人の子を生まざるときは、不当にも、死亡者の承継より排除せられたればなり。死亡せる男又は女のみを、法定的権利によりて相続することを得しむ可き、三人又は四人の子を生まずとて、如何にして母の過失を考ふることを得んや。
五 暫く以前に君臨し給ひし諸帝の諸勅法にして、法定相続に付て規定するものは、一部は母に救済を与へ、一部は彼の女を圧迫し、全部に亘れる子に対する承継を彼の女に恵与せず。唯或る場合、例へば子の権利を有する場合に、彼の女より三分の一を削減して、これを或る者に譲り、反対に彼の女が法定的権利を備へざる場合にも、相続財産の或る部分を以て、彼の女を慰藉したり。(上述せし所を更に明瞭にせんが為)設例に徴して、述ぶることを要す。若し子の権を備ふる母を有する某が、死亡するが如きことあり、而て法定者たる伯叔父、又は伯叔父の息が存するときは、母は八ウンキアを取得し、伯叔父又は伯叔父の息は、四ウンキアを取得したり。若し反対に母が子の権を有せざるときは、伯叔父又は伯叔父の息は、八ウンキアを取得し、母は四ウンキアを取得したり。吾人の至聖の皇帝は、真直簡明の道よりして、母を総ての法定者に優先せしめ、死亡せる子の承継は、何等減殺することなくして、これを彼の女に譲与し給へり。但し兄弟姉妹は例外とす。死亡者と同血者たると、或は死亡者に対し、血族的権利を有するとを問はず。蓋し皇帝は、彼の女を他の総ての法定者に優先せしめたるが如く、総ての兄弟総ての姉妹は、仮令法定者に非ずとも、彼の女と共に遺産に召喚し給ひしなり。而て其の方法は、若し宗族的又は血族的権利を有する姉妹のみと、男女死亡者の母が存するときは、半額は母これを取得す可く、他の半額は全姉妹がこれを取得するが如くにす。例へば某が、母が存し、女性たる姉妹も二人又は三人存するときに死亡したり。六ウンキアは母が取得し、六ウンキアは全姉妹が取得す可し。然れども若し死亡者に兄弟又は更に姉妹も存し、或は又血族的又は宗族的権利を保持する、諸兄弟又は諸姉妹をも交ふるときは、遺産は頭分に分割せらる可し。故に若し兄弟が存せざるときは、母が常に半額を取得し、姉妹は幾人存するとも、一人と解せらる可く、若し兄弟が存するときは、多数の姉妹は一人の地位を占むることなし。
六 吾人の至誠の皇帝は、母に軫念を用ひさせ給ひしが如く、母が其の子に意を注ぐ可きことを命じ給ふ。蓋し当初より後見人が存せず、或は任命せらるるも就任免除を援用し、或は嫌疑者として免黜せられたるときには、未成熟者にして看護者を欠く者の為に、後見人を請求し、彼等を等閑に附したるが侭に放置せざる可き旨を、彼の女に告ぐればなり。而て子の為に後見人を請求する権能を有す可き期間、即ち一ヶ年を彼の女に附与し給へり。若し母が一年以内に、後見人を未成熟者の為に請求することを怠りたるときは、母は子を相続することなし。蓋し子を無援の侭に放置せる者が、子の承継を享有するは失当なればなり。
七 母は仮令内縁関係より生まれて死亡したる子を有する場合にも、テルツルリアーヌム元老院議決に基きて、子の遺産に召喚せらる。
第四章 オルフイチアーヌム元老院議決に付て
前に説きたる所に於て、吾人は、十二表法は母を子の遺産に召喚することもなく、子を母の遺産に召喚することもなかりしも、法務官は彼等に対して、血族的〔遺産〕占有を発案したる旨を説きたり。而て尚吾人は、時が進み、子の承継に対し、母に法定的権利を譲与せしテルツルリアーヌム元老院議決が制定せられたるも、該議決も前章にて説きたるが如く、吾人の皇帝の勅法によりて、完全なる匡正を受けたる旨を述べたり。而てテルツルリアーヌム元老院議決を模倣して、マールクス皇帝の代、オルフイツース及びルーフスの執政年、オルフイチアーヌムと称せらるる元老院議決制定せられ、これによりて、息又は娘に、仮令権力服従者たりとも、母の承継に対し、法定的権利が附与せられたり。彼等は母の同血兄弟姉妹、及び他の宗族に優先せしめらる。
一 此の元老院議決は、孫に救済を与ふることなし。蓋し祖母がテルツルリアーヌム〔の利益〕を有せざるが如く、孫もオルフイチアーヌム〔の利益〕を有せざるなり。然れども、オルフイチアーヌムは、皇帝の勅法よりして匡正を受け、該勅法は息と娘に倣ひて、男孫及び女係を祖母の遺産に召喚したり。
二 catitis deminutioは、新規に発案せられたる法定相続を奪ふことなく、唯十二表法を発見者に書き留むるもののみを破壊すと謂ふ原則により、catitis deminutioは、オルフイチアーヌム又はテルツルリアーヌムに基きて、附与せられたる法定権を、廃止することなきを知ることを要す。
三 内縁関係より生まれたる子も亦、オルフイチアーヌム〔の利益〕を保有す可し。
四 人若し多数の同一親等に属する法定者が存する場合に死亡し、他の者は承継するも一人のみは拒絶し、又は死亡其の他の原因によりて、相続を妨げらるるときは——蓋し勅法によりて、相続を阻止せらるる者は、其の数多し——同人の相続分は、承継者に添加す。例へば四人存するときに、三人は承継し、一人は拒絶し、又は死亡し、又は法律によりて受領を阻止せられて、欠けたるが如し。同人の相続分は、三人に同一の割合を以て添加す。承継者が生存すると、彼等も亦死亡するが如きことあるとを問はず。
第五章 血族の相続に付て
無遺言にて死亡したる者の相続財産へは、自権相続人及び法務官によりてこれに算入せられたる者、例へば家長権被免除者、及び勅法によりてこれに結合せられたる者、例へば市会に与へられたる者、及び〔夫が〕夫婦の情を懐くことなかりし婦女より生まれ、後嫁資証書の作成によりて、自権相続人の権利を取得したる者が、召喚せらる可き旨を吾人は述べたり。彼等の次には、無遺言召喚は、宗族及びテルツルリアーヌム及びオルフイチアーヌム元老院議決が、宗族的権利を譲与したる者——予は謂ふ、母と其の子なり——に関す。而て吾人の極めて敬虔なる皇帝の勅法は、女性たる姉妹より生まれたる者にも、法定的権利を附与し給へり。
一 上記総ての者の次には、法務官は一の順位を発案し、其の順位によりて、自然には知られたるも、十二表法の極めて偏狭なる立法の認めざりし血族を召喚したり。capitis deminutioを受けたる者、及び同人より生まれたる子が彼等に当る。彼等capitis deminutio故に、十二表法に嫌はれたる者を、法務官は第三順位よりして召喚したり。但し予は唯男性たると女性たるとを問はず、兄弟姉妹にして家長権免除を受けたる者を除外して、是等の言を為す。是等の者より生まれたる者に付ては、然ることなし。蓋し故アナスターシウスの勅法制定せられ、人若し現状の権利を有する兄弟、即ちcapitis deminutioを受けざる兄弟と、他のcapitis deminutioを受けたる兄弟とを遺して死亡するときは、両人は死亡せる兄弟又は姉妹の相続財産に召喚せらるるも、同一の割合には非ずして、法定者は少しく多額に収得する様、即ちcapitis deminutioを受けたる者は四ウンキア、現状の権利に属する者は倍額、即ち八ウンキアを取得する様にす可き旨を宣言すればなり。これに関する総ての立法は、汝上記の勅法を読むとき、これを学ぶことを得。capitis deminutioを受けたる兄弟は、法定的権利を汚すことなく保持する者と共に召喚せらるるも、上述の如く、少額を取得す。然れども他の親族には、全額に付きて優先せしめらる。仮令其の親族が、capitis deminutioを受けずとも尚然り。血族に優先するは尚更なり。故に予若しcapitis deminutioを受けたる兄弟と、父方の伯叔父を遺して死亡するときは、兄弟は優先せしめらる可し。然れども何人もcapitis deminutioを受けたる者は、唯兄弟又は姉妹に非ざる限り、宗族的順位よりして、召喚せらるることなし。兄弟の子は然らず。是等の者はcapitis deminutioを受けて、血族的地位へ下ればなり。
二 capitis deminutioを受けたる者と同じく、十二表法によりて認められざりし女性の出たる卑属も亦、法務官は第三順位によりて召喚したり。
三 第三順位は尚、養子に与へられたる子が、実父の相続財産を承継せんと欲するときに、これを包含す。
四 某の婦女、内縁関係を結びて子を儲けたり。かかる子は某に対し、法定権を有することなかる可し。蓋し宗族関係は父よりして認定せらるるに、是等の者は父を有するものとは解せられざればなり。故に又相互の間に於て、同血者にも非ず。蓋し同血関係は、宗族関係の一種なればなり。然れども血族的権利は、内縁関係よりの兄弟が、相互に対しこれを取得すること、母を通して彼等に知られたる全親族に対するが如し。故に法務官によりて発案せられたる第三順位は、兄弟を除き、capitis deminutioを受けたる宗族及び是等の者より生まれたる者、尚女性によりて吾人に知らるる者を包含す。尚養家にありて、実父を相続せんと努むる者、及び内縁関係より生まれたる者も然り。是等総ての者に対しては、最近関係の名目を以て、unde cognatiの〔遺産〕占有が約せらる。即ち全部を同時に召喚するに非ずして、親等に於て近き者を召喚す。
五 宗族と血族の間に存する多数の差異の中には、尚此の外次の如きものもあり。蓋し人若し無遺言にて死亡するときは、同人の宗族は、仮令十等親に属すとも、尚且同人の相続に召喚せられ、十二表法に基くものとして承継し、法務官に基くものとして、unde legitimi〔の遺産占有〕を請求することを得。若し死亡者に宗族は存せざるも、血族は存するときは、六等親迄の者なる場合に、彼等血族に、unde cognatiの〔遺産〕占有が附与せらる可し。蓋し七等親より以下は、唯下の如き者、即ち再従兄弟姉妹の息又は娘のみが、召喚せらるればなり。何人がかくの如き者なるかは、先の章に於て学ぶ可し。
第六章 血族の親等に付て
今前に親等に付き前置として述べたる所をして、一層の信を得しめんが為、これを本文自体を以て示すことを要す。親族の親等は、次の如くにして計算せらる可し。先づ第一に親族は、或は尊属親なるか、又は卑属親なるか、或は傍系と称せらるる横より来る者、即ち男性及び女性の兄弟姉妹、及び彼等より生まれたる者、尚これに続いて、父方又は母方の伯叔父母に属するものなることを知ることを要す。而て尊属及び卑属の親族関係は、一等親より開始するに反し、傍系の親族は二等親より開始す。蓋し傍系の者に付ては、一等親を発見することを得ざればなり。
一 一等親は尊属に於ては父母を包含し、卑属に於ては息娘を包含す。
二 二等親は尊属に於ては祖父祖母、卑属に於ては男孫女孫、傍系に於ては兄弟姉妹を包含す。
三 三等親は尊属に於ては曾祖父曾祖母、卑属に於ては男曾孫女曾孫、傍系に於ては兄弟姉妹の息及び娘、これに続いて父方の伯叔父、母方の伯叔父、父方の伯叔母、母方の伯叔母を包含す。父方の伯叔父は、羅馬の語にてはpatruus、即ち父の兄弟と称せられ、これは希臘語にてはπατρῷοςと称せらる。母方の伯叔父はavunculus、即ち母の兄弟と称せられ、これは希臘人のもとに於ては、適当にμητρῷοςと称せらる。共同しては、総てθεῖοςと称せらる。父方の伯叔母はamita、即ち父の姉妹と称せられ、母方の伯叔母はmatertera、即ち母の姉妹と称せらる。両者は共にθεία、或る者の間にては、τηθιςと呼ばる。
四 四等親は尊属よりは高祖父高祖母、卑属よりは男玄孫女玄孫、傍系よりは兄弟及び姉妹の男孫女孫、父方の大伯叔父、父方の大伯叔母、同じく母方の大伯叔父、母方の大伯叔母、即ち予の祖父予の祖母の兄弟姉妹を包含す。尚consobrinus及びconsobrina即ち男性又は女性の兄弟姉妹より生まれたる者あり。古人の或る者は、consobrinusとは元来consororinusとして、二人の女性姉妹より生まれたる者を称すとし、二人の男性兄弟より出でたる者は、本来fratres patruelesと呼ばる可しと謂ふ。これ正当なり。若し二人の男性の兄弟より、娘が生まれたるときは、相互をsorores patruelesと呼び、兄(弟)又は(姉)妹より生まれたる者は、本来amitiniと呼ばる。予の父方の伯叔母の子は、予をconsobrinusと呼び、予は彼等をamitiniと呼ぶ。故に要約せば、二人の男性又は女性の兄弟姉妹より生まれたる者が、consobriniと呼ばるるは濫用なり、本来は男性の兄弟より生まれたる男子はfratres patrueles、女性の姉妹より生まれたる男子又は女子はconsobrini又はconsobrinae、兄(弟)と(姉)妹より生まれたる者はamitiniなりと謂ふことを要す。然れども女の生みたる息は、男の生みたる息をconsobrinusと呼び、男の生みたる息は女の生みたる息をamitinusとも呼ぶ。
五 五等親は尊属よりは高々祖父高々祖母、卑属よりは男玄々孫女玄々孫、傍系よりは兄弟又は姉妹の男曾孫女曾孫を自己のもとに包含す。而て尚これに続いて、父方の大々伯叔父、父方の大々伯叔母、即ち曾祖父の兄弟及び姉妹、母方の大々伯叔父、母方の大々伯叔母、即ち曾祖母の兄弟又は姉妹も然り。兄弟姉妹より生まれたる者(彼等は既に述べたるが如く、或る場合はfratres patrueles、或る場合はsorores patrueles、尚或る場合にはconsobrini及びconsobrinae、或る場合にはamitini及びamitinaeと称せらる)の息又は娘にして、proprius sobrinus、propria sobrina、即ち父方及び母方の大伯叔父母の息及び娘と称せらるる者も亦同じ。
六 六等親に属するは、尊属よりは高々々祖父、高々々祖母、卑属よりは男玄々々孫女玄々々孫、傍系よりは兄弟又は姉妹の男玄孫女玄孫、及びこれに続いて父方の大々々伯叔父、父方の大々々伯叔母、即ち高祖父の兄弟及び姉妹、母方の大々々伯叔父、母方の大々々伯叔母、即ち高祖母の兄弟又は姉妹なり。consobrinus及びconsobrina即ちfratres patrueles又はconsobrini 又はamitiniより生まれたる者も亦同じ。
七 如何にして、親族の親等が計算せらるるかを明かにするには、これ迄にて足る。蓋し汝は生まれたる人間は、常に親等を増加することを知るを要せばなり。而て各人が何等親に属するかを述ぶるは、親族のそれぞれの名称を示すよりは容易なり。
八 同一の方法によりて、宗族の親等も、血族の親等も、計算せらる。
九 然れども真実は、耳によるよりは、むしろ眼による方が、一層効果的なる確信を得ることなれば、親等の説明の後に、親等自体を今の巻に書き収め、以て耳と眼を以てこれを理解せんとする若き学徒に、親等に関する完全なる認識を取得せしむることは、必要と考へられたり。
一〇 次のことは、何よりも先に知ることを要す。即ち血族的順位を発案したる法務官も、奴隷の中に成立する親族関係を、血族内に算入せざりしことこれなり。蓋し比較的古き法律、例へば十二表法も、或は又親族関係に付て規定する他の法律も、これを認めざればなり。然れども吾人の至聖の皇帝は、保護者の承継に付て規定せる勅法の中に於て、其の間に存する不明瞭と、立法の混乱を廃止し、博愛の眼を以て、次の如く宣言し給へり。即ち人若し奴隷たるとき、自由女又は女奴より子を儲け、又は反対に婦女が女奴たるとき、男の自由人又は奴隷より子を産み(子が何れの性たるかは問はず)、更に父たる奴隷又は女奴たる母が、偶々解放せられ、而して奴隷の腹より出でたる子も解放せらるるときは、己が親を承継す可き権能を有し、保護者の権は静止す可しと。而て該勅法が特に希望するが如く、奴隷状態に在る間に生まれて、其の後解放せられたる者のみが存すると、親が解放せられたる後、他の者が生まるるが如きことあるとを問はず。かくして生まれたる者等は、己が親を承継するのみならず、相互に相互の相続財産を取得す。蓋し彼等【親の解放前生まれたる子】は、彼等【親の解放後生まれたる子】と共に、父又は母の遺産を承継す可く、親の解放後生まれたる者が、同一の母又は同一の父よりして明みに出でたると、又は異るものよりして然るとを問はざればなり。而て一言にして謂はば、彼等に付ては、総て合法婚姻より生まれたる者に倣ひ、効力を有す可し。
一一 上に述べたる所よりして、簡単に反復概括するときは、親族の順位に、自権相続人、法定者、血族の三順位存すと謂ふことを要す。故に親等に於てより近き者が、相続に於て優先せしめらるとは謂ふことを得ず。何故となれば、順位が順位に優先し、前の順位に属するときは、仮令親等に於て遠かるとも、より強大なる順位に基くものなれば、相続に付ては優先すればなり。蓋し多数の人間が、同一順位よりして承継するときに、初めて親等の比較が行はるるなり。故に親族の同一親等を保持する者が、常に同時に相続する訳にも非ず、より近き者が常に優先者にも非ざるなり。蓋し第一順位は、自権相続人、及び自権相続人に算入せらるる者、即ち家長権被免除者及び女性より生まれたる孫、及び前に於て、順次数へたる者の有する順位なるが、今死亡者に曾孫又は玄孫が存し、又兄弟又は父或は又母が存すと仮定せよ。曾孫又は玄孫は、より強大なる順位より来れる者として、仮令親等に於ては多数を占むるも、優先せしめらる可し。蓋し父又は母は、前述したる所に従ひ、一等親に属し、兄弟は二等親、曾孫は三等親、玄孫は四等親に属すればなり。玄孫は四等親の出なりと雖も、優先せる順位に属するの故を以て、一等親又は二等親より出でたる者よりも、優先せしめらる。曾孫又は玄孫が、死亡者の権力服従者なるか、家長権被免除者となれるが為、権力服従者には非ざるか、或は家長権被免除者より生まれたるか、或は女性の者より出でたるかによりて、何等の区別存することなし。
一二 自権相続人、又は自権相続人に準ずる者が存せず、宗族即ち法定的権利を欠くることなく有する者が存するときは、仮令より遠き親等に属するも、多くの場合、より近き血族よりは、其の地位良し。蓋し父方の伯叔父の曾孫又は玄孫——中一は五等親、他は六等親に属す——は、母方の伯叔父及び伯叔母が三等親を保有するとも、これに優先せしめらるればなり。故に吾人が、より近き血族が地位良し、或は同一親等を保持する者と共に、召喚せらると謂ふは、自権相続人又は自権相続人の地位を保持する者も存せず、宗族も存せざる場合のことなり。蓋し是等の者は、相続に付ては、優先せしめらるればなり。唯かく称するも、兄弟及び姉妹にして、家長権免除を受けたる者は、これを除外す。蓋しかかる人間は、capitis deminutioによりて、宗族的承継を害せらるることなく、三等親或は又それ以上の親等に属する全宗族に優先せしめらるること、アナスターシウスの勅法の希望せらるるが如きを以てなり。即ち直前に「多くの場合」と称したるは、家長権免除を受けたる兄弟姉妹を、考慮して謂ひたるなり。蓋し是等の者は、古くは血族的権利を有する者なりしも、上記の勅法に基きて、優先せしめられたればなり。
第七章 被解放者の相続に付て
次のことを予備知識として保持す可し。親族とは一般的名称にして、尊属親、卑属親、及び傍系親の三に分たる。然れども此の三種の親族は、生来自由人に付て観察したる所にして、被解放者に付ては、古人は尊属【独訳八六頁の卑属は誤訳】を知らざりき。蓋し奴隷状態に於て生まれたるときに、如何にして可能ならんや。傍系親も亦知ることなし。蓋し尊属を有せざる者は、傍系親も得ざればなり。是等の者は、尊属よりして下れる者なればなり。彼等は唯卑属、即ち解放の後懐胎せられて、彼等に生まれたる者を親族に有す。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。生来自由人の承継に付て言を尽したる吾人は、当然被解放者に付ても述ぶることを要す。若し被解放者が無遺言にて死亡するときは、何人が同人の相続を承継す可きか。若し解放後懐胎せられたる子が、同人に存するときは、自権相続人の順位に基きて、同人が相続す可し。若しかかる者なきときは、何人が召喚せらるるかを吾人は研究す可し。先づ宗族とは謂ふことを得ず。何故となれば、被解放者は奴隷状態の中にて生まれたる者なれば、尊属親を有せず、従つて亦傍系親にも与ることなければなり。蓋し是等の者の起源は、彼等尊属に発すればなり。宗族なきを以て、法律は宗族に代へて、保護者を発案したり。宗族を死亡者の承継より排除したる者は、亦保護者を被解放者の相続より駆逐す。故に被解放者に子が存するときは、保護者に相続の余地なし。又遺言の作成は、宗族に相続を許さざるを以て、又当然保護者にも許すこともなし。然れども古く、十二表法に基く限り、保護者を看過の侭に遺すことは、被解放者に許されたり。蓋し唯自権相続人も存せず、遺言も存せざるときに初めて、十二表法は保護者に、被解放者の遺産に対する承継権を附与したればなり。而て若し子が存したるときに、保護者が駆逐せらるるも、此のことは堪え得可きことなりき。蓋し同人が自然に従ふは、非道に非ざればなり。然れども、自ら自権相続人の権利を有する養子も亦、保護者に優先せしめられたるときは、同人【保護者】が養子に敗れて、被解放者の承継を剥奪せらるるの極めて不当なる結果を、それより発生したり。
一 此処に於て時を経て、法務官は自己の立法によりて、此の種の不正を匡正し、被解放者が遺言を為す場合には、常に其の財産の半を、保護者に遺す可き旨を宣したり。而て若し全然、又は半額より少額を遺したるときは、被解放者の遺言に反対して、保護者に遺言書に反する〔遺産占有〕が附与せられ、これによりて常に六ウンキアを取得せり。若し被解放者が養子を遺して、無遺言にて死亡したるときは、法務官は保護者に対し、遺言書に反する〔遺産〕占有を附与し【此処固より何等かの誤なり。無遺言相続にbonorum possessio contra tabulasの存在する余地なし。独訳八九頁】、これによりて六ウンキアを取得せしむ。被解放者に実子が存するときは、権力服従者たる場合のみならず、家長権被免除者たる場合、更には養子に与へられたる息子たる場合にも、保護者を排斥したり。唯養子に与へられたる者は、極めて少額の割合にても、相続人に書き記されたる場合に限る。例へば予被解放者にして、保護者を有し、更に実子をも有し、此の者を養子に与へたり。若し遺言に当りて、同人を一部に付き相続人に書き記すときは、保護者は排除せらる可し。若し同人を看過の侭にて遺すときは、保護者は当然予の遺言に対して、遺言書に反する〔遺産占有〕を請求す可し。予の息にして、権力服従者又は家長権被免除者たる者が、予を相続するときは、意思又は法律によりて、保護者に対し勝利を得。意思によるとは、予が彼等を相続人に書き記す場合なり。法律によるとは、予が無遺言にて死亡するか、或は又彼等を看過の侭に遺して、遺言を為す場合なり。蓋し一方〔権力服従者は〕法律上当然に〔遺言を〕破壊し、他方家長権被免除者は、遺言書に反する〔遺産占有〕によりて、予の財産を取得し、保護者には余地を与へざればなり。何故となれば、遺言書に反する〔遺産占有〕は、法務官これを実子に対抗して、附与することなければなり【何故となれば以下は、保護者に余地を与へずと謂ふ点のみの説明ならん】。然れどもかくの如く、保護者に援助を与へし法務官の立法の後と雖も、被解放者に或る方法存し、これによりては、何等の危険なく保護者に何物をも遺さざることを得たり。蓋し若し実子を有するときは、十二表法も法務官も、自然に恥ぢて、保護者を援護することなければなり。
二 然れども時を経て、パピア法は保護者の権を増大したり。蓋し同法は曰く、若し被解放者が富裕にして(十万セーステルチウスを有する者は、富裕者と定義せらる)且三人よりも少き子を遺したるときは、遺言を為して死亡すると、又は無遺言にて死亡するとを問はず、保護者に一定の割合が保存せられたればなり。故に一人の息又は一人の娘を有する富裕なる被解放者が、遺言を為して死亡するが如きことあらば、パピア法はあたかも一人の子が存せざると同様、死亡者の遺産の半額を保護者に与へて、保護者をして、息又は娘に仲間入りせしむ。若し二人の息又は二人の娘を、相続人に指定したるときは、保護者は三分の一に付て仲間入りし、三人存するときは、子が十分存するの故に、排除せられたり。
三 是等は古のことなり。吾人の皇帝の勅法制定せられ、総ての者に明かならしめんが為、希臘語を以てこれを発表し給ひ、多大の簡潔を策し給へり。帝は同法の中にて、男性又は女性の被解放者がcentenariusより少き者なるとき、即ち百金より少き資産を有するときには(蓋しパピア法によりて規定せられたる十万セーステルチウスの額を、かくの如く解釈し、従つて千セーステルチウスを百金に相当すとなし給ひしなり)、遺言が存する場合には、相続に付ては、保護者に何等の余地は与へられざる可しと規定し給へり。蓋し子を遺さずして、無遺言にて死亡するときは、保護者は十二表法に基きて、全額に付て承継を取得すればなり。若しcentenariusより多額なるときは、市民法により、或は家長権被免除者なるが故に、法務官法によりて召喚せらるる相続人たる子を遺して死亡したる場合には、子が一人たると数人たると、性の如何親等の如何を問はず、是等の者が全部にわたりて召喚せられ、保護者又は保護者の子は、此の種の相続より排除せらる。若し被解放者がcentenariusより多額にして、子なくして死亡したるときは、無遺言の場合には、男性又は女性の保護者は全遺産を取得す可く、若し遺言を為して、男性又は女性の保護者の看過を許したるときは、子なきか、或は子を有するもこれを廃除者となしたるか、或は死亡者が〔息を有する〕被解放女なるか、又は先に死亡したる娘より生まれたる孫を有する男性の被解放者にして、是等の者——前者は息、後者は先に死亡したる娘より生まれたる孫——を看過し(蓋し是等の者に付ては、第二巻に於て吾人が教授したるが如く、看過は相続廃除と解せらるればなり)、且是等の子が不倫遺言の訴によりて、遺言を破壊することを得ざる場合には、吾人の至聖の皇帝の勅法に基き、男性又は女性の保護者に、遺言書に反する〔遺産占有〕が附与せられ、古の如く、半額には非ずして、三分の一が取り去られ、或は三分の一に欠けたる額が補充せらる可し。例へば偶々一ウンキア又は二、更には三ウンキアに付て指定せられたる為の如し。遺言書に反する〔遺産占有〕によりて、三分の一を取得するは、彼等が第三者のみならず、男性又は女性の被解放者の子にも、遺贈又は信託遺贈を、其の中より履行する必要なき様にしてこれを行ひ、彼等によりて〔履行せらる可きものとして〕遺されたる物は、共同相続人が認めて負担す可し。【遺贈又は信託遺贈云々と謂ひたるは、恐らく廃除人又は被看過者——看過は廃除に類似するものなれば——に対するならん。蓋し若し相続人に書き記されたるときは、保護者に対して何物をも負担せず、保護者が相続人に書き記さるるが如きことあらば、遺贈は子に負はるればなり】【括弧内がglossemaなるは定説。意義も明かならず。】尚上記の勅法は、今の法律問題の整理に必要なる多数の場合を蒐集せり。蓋し男性又は女性の保護者、及び同人の卑属、尚これに止まらず五等親迄の傍系親が、被解放者の遺産を承継す可き旨を命じたればなり。故に若し同一の男性の保護者、又は同一の女性の保護者、或は二人の男性の保護者、又は二人の女性の保護者、更にはそれ以上の数の保護者の子が存するときは、親等に於てより近き者が、男性又は女性の被解放者の遺産に召喚せらる可し。例へば男性又は女性の被解放者が、子なく且、無遺言にて死亡し、男性及び女性の保護者は存せず、唯卑属、恐らくは孫及び曾孫が存するときは、孫が承継す可し。而て相続財産は、頭分に分割せらる可く、株分に分割せらるることなし。例へば一人の保護者に二人の子あり。他の保護者には三人の子あるときは、相続財産は五分せらる可し。同一のことは、男性又は女性の保護者の傍系の親族に付ても該当す可く、従つてより近き者が優先し、且相続財産は頭分に分割せらる。蓋し上記の勅法は、承継に於ては、生来自由身分と解放自由身分の法律は、殆んど同一と命ずればなり。「殆んど」と謂ひたるは、生来自由人に付ては、男性又は女性の保護者の五等親以上の親族にも、相続の権利は及ぶに反し、被解放者に付ては、五等親迄なればなり。
四 以上のことは、羅馬市民たる被解放者に付て、吾人今日これを取扱ふ。何故となれば、他には被解放者存せざればなり。蓋し汝は、前巻に学びて、降伏者の権利も、ラテン人の権利も廃止せられたるを知ればなり。然れどもラテン人が国に存したるときは、彼等に付ては、何等合法的承継は問題とせらるることなかりき。蓋し仮令自由人として生活するも、奴隷の如く死亡し、生命と共に自由をも喪失し、同人の遺産は其の解放者によりて、相続せられたればなり。即ち相続は、奴隷に付ては問題とす可きに非ざれば、ユーニア法に基き、特有財産の権利に基きて、解放者がこれを取得したるなり。然れども以上はユーニア法に基きてのことなり。其の後ラルギアーヌム元老院議決が制定せられ、同法は、ラテン人の権利を有する被解放者の承継に関する限り、解放者の子にして、個別的に廃除せられざりし者は、家外相続人に優先せしめらると命じたり。例へば予、予の奴隷を解放して、ラテン人と為したり。予、予の子と、尚家外人を相続人に書き記して、死亡せり。ユーニア法によれば、ラテン人が死亡するが如きことあらば、予の子が予の家外相続人と共に、ラテン人の遺産を承継したるも、ラルギアーヌム元老院議決によれば、子は個別的廃除者とならざるを以て、同人のみがラテン人を承継す。ラルギアーヌム元老院議決の後、トラヤーヌス帝の告示が制定せられ、該告示は、保護者の意に反し、又は不知の間に、羅馬市民権を自己の為に請求して、これを得たるラテン人は、羅馬人として生活し、全羅馬人の権を実行するも、死亡するときは、ラテン人として死亡す可き旨を命じたり。然れども吾人の皇帝の勅法は、かかる羅馬人として生活し、ラテン人として死亡するが如き、状態の変化を以て慊らずとなし、ラテン人の権も、ユーニア法も、ラルギアーヌム〔元老院議決〕も国家より放逐したるのみならず、トラヤーヌスの告示をも廃止し、以て総ての被解放者は 羅馬人たる可きこととして、それより起る他の困難を除去し給へり。尚或る創意或は附加を以て、曾ては或る方法によりて解放せられて、ラテン人となりたると同一の方法によりて、奴隷を羅馬市民権に赴かしむ。
第八章 被解放者の指属に付て
被解放者に関して述べたる吾人は、最後として、彼等に付て為されたる指属に付ても述ぶ可し。汝は保護者の子は、同一の親等を保持するときは、同時に且同一の割合を以て、父に属せし被解放者の遺産を、承継することを知れり。其の後元老院議決が制定せられ、多数の子を有する保護者をして、子の中の一人に被解放者を指属することを許す可き旨を宣言したり。而て其のときは、被解放者の死亡の後は、指属せられたる者のみ、保護者の権を有し、指属なかりしならんには、同時に相続す可かりし他の保護者の子は、同人の相続に対する何等の承継権なし。若し被解放者の指属せられたる子が、子なくして死亡するが如きことあらば、初めて他の保護者の子が、古の権利を恢復し、同人等は彼を承継す可し。
一 男性の被解放者のみならず、女性の被解放者をも、これを指属することを得。又息又は男孫に対して、指属することを得るのみならず、娘又は女孫に対しても然り。
二 二人又はそれ以上の子を、権力内に保持する保護者に、指属が許さる。蓋し家長権被免除者に対しては、指属することを得ざればなり。人若し其の被解放者を権力に服する息に指属し、其の後も生き延びて、同人を家長権被免除者となしたるときは如何。吾人は指属が無効なるかを問題とす可し。而てユーリアーヌスにも、法学者の多数にも、それは無効とするに傾きたり。
三 遺言に於て、指属することを得るのみならず、無遺言の場合も可能なり。又これには、発案せられたる定型的文言もなし。指属に付て規定する元老院議決は、クラウヂウスの御代、スイルルス、ルーフス及びホストーリウス、スカプラが執政官たるとき、制定せられたり。
第九章 遺産占有に付て
十二表法が遺言又は無遺言相続を発案し、或は召喚せられたる者が〔当然に〕〔相続人として〕現はれ——例へば必然相続人の如し、——或は承継する——例へば彼等以外の者の如し——こととなしたるが如く、法務官も亦、〔遺産〕占有を発案し、これによりて、或は市民法を匡正し、或は反対したり。〔法務官は〕既に述べたるが如く、無遺言相続に関するのみならず(蓋し市民法は、capitis deminutioを受けたる者、及びそれより生まれたる者、更には又女性よりの出の者を認めざりしも、法務官は第三順位を発案して、彼等にunde cognatiの〔遺産〕占有を附与したればなり)、遺言に於ても亦、十二表法の過失を匡正したり。蓋し人若し死亡に当りて、他人の後生児を相続人に書き記したるときは(汝は他人の後生児とは如何なる者なるかを知れり。即ち予に自権相続人として生まれざる者なり)、かかる後生児が出生するも、市民法に基く限り、市民法はかかる指定を排斥するを以て、承継することを得ざりしも、法務官は遺言書に従ふ〔遺産〕占有を同人に許容し、同人を遺産占有者となしたればなり。然れども吾人の極めて敬虔なる皇帝の勅法は、かかる後生児は市民法によりて認められたるも同然、適当に相続人に書き記さる可き旨を希望し給へり。又法務官は時としては匡正はせず、更に進んで市民法に反対したり。例へば既に吾人の説きたるが如く、被解放者が若し保護者を看過の侭に遺したるときの如し。十二表法は、遺言の作成によりて敗北せる保護者には、被解放者の遺産承継権は附与せざりしも、法務官は、遺言書に反する〔遺産占有〕を発案したり。見よ此の場合には、真正面に反対して戦へるなり。
一 法務官は統御し易からざる者、戦を好む者には非ず。蓋し市民法を以て、発揚す可きものと見たる場合には、匡正もせず、反対もせず、却てむしろ確認に向つて其の立法を置けばなり。蓋し人若し適法に遺言が作成せられて、相続人に書き記されたるときは、市民法に基きて承継することを得るのみならず、法務官も亦同人に遺言書に従ふ〔遺産〕占有を附与し、一【市民法】は彼を相続人となし、他【法務官】は遺産占有者となせばなり。無遺言相続も一致す。蓋し自権相続人と宗族とを市民法は召喚し、一はこれを〔当然に〕〔相続人として〕現はれしめ、他は承継せしむ。法務官は市民法を確認して、一にはunde liberiの〔遺産〕占有を附与し、他にはunde legitimiの〔遺産〕占有を与ふ。而て仮令〔遺産〕占有を請求せずと雖も、尚均しく市民法に基く相続人なり。故に法務官は、或は匡正し、或は反対し、或は確認す。匡正すとは、家外の後生児に関する場合の如し。反対すとは、看過せられたる保護者に関する場合の如し。確認すとは、指定相続人及び、第一順位又は第二順位に基く無遺言相続人に関する場合の如し。
二 法務官のみが〔遺産〕占有に召喚し、市民法は然らざる者は、法律上当然に相続人となることなきも(蓋し相続人なる名称は、法務官は何人にも頒つことなければなり)、法律又は法律の地位を占むるもの、例へば元老院議決又は皇帝の勅法は、相続人たらしむ。元老院議決とは、テルツルリアーヌム及びオルフイチアーヌムに於けるが如し。勅法とは、姉妹の子を法定者に算入する吾人の皇帝の勅法の如し。然るに法務官は、相続人を作らず、唯〔遺産〕占有を与へて、相続人の地位に同人を置き、遺産占有者となし、以て同人が擬制的に訴へ訴へられしむ。法務官は、上記の〔遺産〕占有unde liberi, unde legitimi及びunde cognatiを発案したるのみならず、何人も承継者なくして死亡することなからしむとの唯一の目的を持ちて、他の多くのものも発案したり。蓋し十二表法に基きて、極めて狭隘なる境界内に閉ぢ込められたる承継の権を、善及び正義より眺めて、拡大したればなり。
三 〔遺産〕占有中、或るものは遺言に基き、或るものは無遺言に基く。遺言に基くものに、次の二あり。第一は遺言書に反するものにして、これをば看過せられたる子に約し、第二は遺言書に従ふものにして、これをば法律に従ひて、相続人に書き記されたる者に許容す。而て先づ遺言に基くものを考案したる後、無遺言のものに転じ、第一位に自権相続人、及び同人【法務官】によりて自権相続人に算入せられたる者——家長権被免除者のことを謂ふ——に、unde liberiと称せらるる〔遺産〕占有を附与したり。第二順位の〔無遺言遺産占有〕として、法律によりて、死亡者の相続に召喚せらるる者に、unde legitimi〔の遺産占有〕を附与したり。例へば宗族及び男性又は女性の被解放者の権利を承継する保護者、及びテルツルリアーヌム又はオルフイチアーヌム、又は勅法に基きて、無遺言相続権を有する者の如し。第三順位として、unde decem personae〔の遺産占有〕を〔認む〕。これによりて、尊属親、卑属親、及び二等親迄の傍系親に属する十人の者を、自由身分を有する者を解放したる家外人に、優先せしめたり。これ何の謂なるか、仮令現時は国内には存せずと雖も、述ぶる必要あり。若し予が予の息を家長権被免除者となさんとして、汝に第一回と第二回と第三回の準奴隷に与ふるが如きことあり、汝は同人を解放し、自主権者となし、自由の附与によりて、同人に対し保護者に類似の法定的権利を得たりとせよ。而て若し此解放せられたる者が、無遺言にて死亡するが如きことあらば、汝は、既に述べたるが如く、解放によりて法定的権利を有する者として、同人の総ての親族にして、受けたるcapitis deminutioの故に、同人に対しては唯血族の関係にある他の者に、優先す可し。然れども単なる解放のみにて、汝が同人の総ての親族に優先せしめらるるは、非道なるが故に、これが為法務官は、無遺言承継に付き、汝に優先せしむ可き十人の人間、息娘、男孫女孫——息の出たると、娘の出なるとを問はず——父母、祖父祖母——父方たると、母方たるとを問はず——兄弟姉妹を召喚したり。是等の者をば家外人たる解放者に優先せしめ、これにunde decem personaeの〔遺産〕占有を附与したり。蓋し請求者の数よりして、〔遺産〕占有は其の名称を得たるなり。第四としては、unde cognati〔の遺産占有〕あり。第五として、tum quam ex familia〔の遺産占有〕を約したり。これは次の如き場合に発生す。被解放者が子なく、且無遺言にて死亡し、保護者はなし。保護者の宗族は、tum quam ex familiaと称せらるる〔遺産〕占有に基き、被解放者の財産を承継す。第六のものを発案して、これをば男性の保護者にも、女性の保護者にも附与し、更に其の尊属にも卑属にも与へたり。これをunde liberi patroni patronaeque et parentes earumと呼びたり。蓋し被解放者が死亡し、男性及び女性の保護者、又は其の子がunde legitimi〔の遺産占有〕に基きて赴くことを欲せず、占有の期間が経過し(蓋し各〔遺産〕占有は、先にても学ぶが如く、一定期間に囲まるればなり)、又tum quam ex familia〔の遺産占有〕も請求せざるときも、尚今の〔遺産〕占有に基きては、保護者自身、保護者存せざるときは、其の子、又は男性又は女性の保護者の親が、承継することを得ればなり。第七位にunde vir et uxor〔の遺産占有〕を発見したり。蓋し人若し無遺言にて死亡し、何人も親族を遺さず、或は又婦女が、前に述べたる〔遺産〕占有に基きて、召喚せらるることを得可き者は何人をも有せずして、無遺言にて死亡したるときは、今の〔遺産〕占有が発生し、夫は妻の財産、妻は夫の財産を承継す可し。無遺言〔遺産占有〕に於て、第八位はunde cognati manumissorisがこれを占む。即ち若し無遺言にて死亡し、何人も全然存せず、保護者も保護者の子も、宗族もなきときは、保護者の血族が今の〔遺産〕占有を請求す可し。
四 是等の〔遺産〕占有を法務官は発案したるなり。二個は遺言による場合、八個は無遺言の場合なり。吾人の至聖の皇帝は、何物をも手に触れざる侭に放置することなく、匡正を要するものは、これを一層良き方に導き給へり。遺言書に反する〔遺産占有〕及び遺言書に従ふ〔遺産占有〕は、必要なるを以て、原状に止め、無遺言のものは、unde liberiとunde legitimiと〔の遺産占有〕を止め給ふ。無遺言遺産占有中の第三、遺言遺産相続をも加ふるときは第五、即ちunde decem personaeは、簡単なる言葉を以て、其の無用を明かにして、遺産占有の数より駆逐し給へり。蓋し上記の遺産占有は、既に速べたるが如く、十人の人間を家外人たる解放者に優先せしめたるも、家長権免除に付て解答せられたる吾人の皇帝の勅法は、総ての父及び解放者に、推定上信託契約を結びて解放することを認め、此のことは暗黙に家長権免除を其の中に包含することとなれるを以て、何人も家外の解放者となることなければ、当然上記の〔遺産〕占有は、無用と観ぜられたるなり。第五たりしunde decem personae〔の遺産占有〕が廃止せられたるを以て、古く第六たりし〔遺産〕占有、即ちunde cognatiは、これを第五となしたり。
五 第六にしてtum quam ex familiaと称せられたる〔遺産占有〕、第八のunde liberi patroni patronaeque et parentes earum〔遺産占有〕は、共に保護者の権に付て規定せる帝の神聖なる勅法の中にて、意味なきものなることを明かにし給へり。蓋し生来自由人の承継を模倣して、被解放者の相続を設け、生来自由人と被解放者との間に或る差等を生ぜしめんが為、これを五等親迄に縮小せしとき、帝は保護者の親族が被解放者の無遺言相続財産を自己に引寄することを得んが為には、遺言書に反する〔遺産〕占有、unde legitimi〔遺産〕占有、unde cognati〔遺産〕占有を以て足ると命令し、是等の〔遺産〕占有を、あらゆる困難と果しなき誤謬より、解放し給ひたればなり【少しく意訳】。
六 unde vir et uxorと称せらるる第九の〔遺産〕占有は、第六位に置き、第十——unde cognati manumissorisのことを謂ふ——は、保護者の権利に付て設けられたる勅法の中にて、詳述したる原因に基きて、無用なることを明かにし給へり。故に全通常〔遺産〕占有の残るは、単に六個のみとなれり。二個は遺言〔遺産占有〕、遺言書に反するものと、遺言書に従ふもの、四個は無遺言〔遺産占有〕、unde liberi, unde legitimi, unde cognati, unde vir et uzorなり。
七 是等に尚第七〔遺産占有〕が追加せらる可し。これ法務官が最善の理由に其きて発案し、元老院議決又は勅法が、其の附与を命令せし者に、其の告示の最終位に於て約せしものなり。これを遺言〔遺産占有〕に算入することも、無遺言〔遺産占有〕に算入することも、確定せるに非ずして、最終の且発案せる順位外の救済手段として、必要の要求あるときにこれを形成して、或は有遺言、或は無遺言の場合に、これを附与したるなり。此の名称はquibus ut detur lege vel senatusconsulto vel constitutione comprehensum estなり。これは別の名を附して、tum quibus ex legibusと呼ぶことも可能なり。
八 法務官によりて発案せられ、順位に従ひて集積せる〔遺産〕占有は多数なれば、各個の〔遺産〕占有には、時には親等を異にする多数の者が存することあるを以て、債権者の訴訟が延滞に陥らず、債権者をして対手と為され得可き者を得しめんが為、〔又〕容易に死亡者の遺産の占有を得、占有によりて自己に安全を保持することなからしめんが為、法務官は各個の〔遺産〕占有を限るに、一定期間を以てし、これを経過せば、これに続く者に地位が与へらるることとなれり。尊属及び卑属には、実親子関係のそれと養親子関係のそれとを問はず、法務官は有遺言又は無遺言にて、彼等に属する総ての〔遺産〕占有の請求に、一ヶ年を附与し、此の期間を経過するときは、彼等に属する〔遺産〕占有を喪失することとせり。其の他総ての親族及び家外人には、これに対し、百日の期間を附与したり。
九 而て人若し此の日数内に、〔自己に〕属する〔遺産〕占有を認むることを怠るときは、何人か同一親等に属する者存する場合には、請求せざる者の相続分は其の者に添加す可く、同一親等に属する者、何人も出でざる場合には、次順位出の者が、転属に基くものとして、承継す可きこと、あたかも先行し乍ら、請求せざりし者が存せざると同じ。予に〔遺産〕占有が属し、予は偶々尊属又は卑属たりし時とて、一年内に、或は或る其の他の者たりし時とて、百日内にこれを請求す可きことを知れり。予これを拒絶したり。吾人は一年又は百日に残存の期間の経過する迄待つことを要し、其の時初めて次位者に地位が施さると謂ふ者には非ず。直ちに次の親等に属する者、又は次の順位に属する者が、〔遺産〕占有に召喚せらる可し。
一〇 〔遺産〕占有の請求期間は、実用期間にして、継続期問には非ず。即ち〔遺産〕占有の日数は、自己に〔遺産〕占有が属することを知り、且これを利用することを得る者に対して、進行す。蓋し若し自己が死亡者の〔遺産〕占有に召喚せられたることを知らず、或は又時には同人の親族の何人かが死亡したることも知らず、或は又知るも大なる必要に強制せらるるが為、〔遺産〕占有を利用することを得ざるときには、〔遺産〕占有の期間は、進行することなければなり。然れども古くは〔遺産〕占有は、請求せらる可きものにして、法務官に対し請求し、特に「予に某の遺産占有を附与せられよ」と謂ふことが必要なりき。今日に於ては、皇帝の勅法は、如何なる方法によるにせよ、〔遺産〕占有の帰属せし者が、規定の期間中に、如何なる種類のものにせよ、〔遺産〕占有を自ら請求することを明かにするときは、これ【遺産占有】の完全なる恩恵を享有す可き旨を宣言す。
第十章 自権者養子縁組による取得に付て
吾人は二個の包括収得、相続——これは有遺言又は無遺言にて、吾人に取得せらる——、並びに〔遺産〕占有——これ亦同じく、有遺言又は無遺言にて取得せらる——に付て述べたり。尚第三の包括取得を述ぶ可し。これは十二表法によりて、発案せられたるにも非ず、法務官によりて発案せられたるにも非ずして、学者の不文の合意によりて、国内に移入せられたるものなり。蓋し法律と市民法とは、別個のものにして、法律とは例へば十二表法、アイリア、センチア法、フーフイア、カニーニア法、ファルキヂア法の如く、特別の名称を有するものなるに、市民法とは、何物か起源明かならざる中より発見せられ、次で利用故に拡張せられ、最後に法学者がこれを認めて、其の合意によりて、有用なることを確認するときの、学者の不文の合意なればなり。
一 蓋し見よ、人若し自主権者にして、自己を自権者養子に与へたるときは、同人の有体無体全財産、並びに同人に負はれたるものは、capitis deminutioによりて消滅するもの、例へば労務の債権(これが如何なるものなるかは、先に至りて学ぶ可し)及び宗族関係の権利(蓋しcapitis deminutioによりて、従前宗族たりし者を、宗族的権利によりて召喚することは、なかりしを以てなり)の如きものを除き、古くは収養者の取得に帰し、同人を其の財産の所有者たらしめたり。使用権及び用益権は古くは消滅したりしが、吾人の皇帝の勅法は、最小のcapitis deminutioによりて解消せらるることを禁止し給ひたり。
二 此の神聖なる吾人の皇帝は、自権者養子縁組によりて発生せる取得を縮少し、これを実親の取得と同一にし給へり。蓋し父の財産によらずして、外より子が取得したる財産に付ては、実父にも養父にも、用益権以上の何物かが、取得せらるることなければなり。若し自権者養子縁組に収養せられたる者が、収養者のもとに於て死亡するが如きあらば、吾人の皇帝の勅法によりて、取得せられざる財産の承継に付て、父に優先せしめらるる者存するが如きことなき限り、財産の所有権も亦収養者に移転す。
三 自己を自権者養子に与へたる者が、何人かに債務を負ふときは、法律上当然、旦厳正によりて、収養者が拘束せらるることはなし(蓋し如何にして一人が契約せるときに、他人が訴えらるることを得んや)と雖も、子の名義を以て訴えらる可し。而て若し彼を防衛することを欲せざるときは、関係官庁の命令を以て、若し自己を自権者養子に与へざりしならんには、用益権と共に、養子に与へられたる者の所有たる可かりし財産は、債権者の占有のもとに置かれ、合法的方法によりて、これを処分す可き権限が債権者に附与せらる可し。
第十一章 自由故に遺産の裁定附与を受くる者に付て
尚包括的取得の第四の種類あり。最新にして古人には未知のもの、至聖のマールクスの勅法によりて発案せられたるものなり。蓋し遺言の中にて自由を得たる者が、何人も他に承継せざるを以て、自由を確保せんが為、遺産の裁定附与を受けたき旨を要求するときは、ポピリウス、ルーフスに対し、下の如き場合に於て、解答せられたる上記マールクスの勅法の希望せらるるが如く、これに与る可ければなり。
一 某ウヰルギニウス、ワレーンス遺言を為し、且チチウスを相続人に書き記し、債権者を持ち乍ら、其の奴隷に自由を遺したるに、相続人に書き記されたる者は、相続を承継することを欲せざりき。債権者は遺産の占有を得て、これを欲するが侭の方法に従ひて、処分せんとしたり。遺言の中にて自由を取得せる者の一人にして、ポピリウス、ルーフスと称せらるる者、自己に遺産を裁定附与し、以て自由も保存せられ、債権者も損害を受くることなからしめ度き旨を要求したり。マールクス皇帝は、これに赴き、これに付て解答し給へり。「若しウヰルキニウス、ワレーンスが、其の遺言に於て奴隷を解放し、指定相続人は承継を欲せず、従つてこれが為、遺産が債権者に売却せらるるの危険を醸したるときは、遺言の中にて自由を得、且自己に遺産が裁定附与せられ、以て自由を保持せんと欲する者より来訪を受けたる関係政務官は、来訪者の趣旨を聴き、以て同人に遺産を裁定附与す可し。但しこれは、先づ保証人の設定、又は其の他の方法によりて、各人に負はるる負債は全部返済せらる可き旨の保障が、適当に債権者に為されたる後、直接的又は信託的自由を附与せんが為なりとす」と。而て直接的自由を有する者が、解放せらるる方法は、相続人が承継すると態様を同じうす。即ち幽界的被解放者となる。然るに信託的自由が遺されたる者には、遺産の附与せられたる者が、解放行為を施し、以て被解放者は固より、同人に属す可し。遺産を裁定附与せられたる者は、直接的自由を有する者も亦、予の被解放者となる可しとの条件を以てするに非ざれば、予は予に遺産が裁定附与せらるることを欲せずと謂ふことを得可し。蓋しこれを附言するときは聴許せらるるも、同人の要求は、唯直接的自由を得たる者が同意する場合にのみ、皇帝これを確認すればなり。尚勅法は其の博愛心を確認せしめんが為め、次のことをも附言せり。即ち曰く、何人も承継せざるを以て、国庫が相続人曠缺として、遺産を取得せんと欲するときは、承継が行はれたらんには、遺言の中にて解放せられたる者が恩恵に与る可かりし死亡者の希望が、彼等に確保せらるるが如くするに非ざれば、取得することなかる可しと。
二 今の指令は自由に対し、保護を与へたるのみならず、死亡者に対しても、同人の財産が債権者の占有のもとに置かれ、以て売却せらるることなからしめんが為、これに保護を与へたり。蓋し自由の名目を以て、自由を取得したる者の一人に、遺産が裁定附与せらるるときは、遺産の売却は停止すればなり。蓋し全部に付てする債務の保証を債権者に提供する、適当なる債務者の防衛者存すればなり。
三 先づ第一に、自由が遺言の中にて附与せられたるときに、此の勅法の適用あることを述べざる可からず。然らば人無遺言死亡に際して、小書付の中にて自由を遺し、何人も無遺言〔相続〕に基きて、承継を忍ぶ者なきときは如何。勅法の趣意は、此の場合にも引き入れらる可し。又人若し遺言を為すも、遺言の中にては何人をも解放せず、小書付の中にて自由を遺したるときは、勅法が取扱はるるは疑なし。
四 勅法の文言は、何人も無遺言〔相続〕に基きて、死亡者に相続人として現はるることなきとき、其の適用あることを示す。故に某が相続するか、或はせざるかが不分明なる間は、勅法は停止す。若し何人も承継せざること明かとなるときは、勅法は其の効力を発生す。
五 某自由を遺言の中にて遺して、死亡したり。未成年者が同人の相続に召喚せられ、相続を拒絶したり。勅法の適用ある可きか。或は原状恢復によりて、再び相続を承継し得るを以て、勅法は停止す可きか。吾人は仮令相続拒絶者は、意を翻して、原状恢復によりてこれを回収することを得とも、勅法に基きて、請求者に遺産の裁定附与が適当に行はると謂ふ者なり。然らば自由の恩恵と遺産の裁定附与の後、弱年者が原状恢復を為して、遺産を回収したるときは如何。一度帰属せし自由は、撤回せらる可きか。決して然らず。
六 今の勅法は、自由の保全の為に発案せられたるものなり。故に自由が遺され居らざるときは、これ【勅法】を取扱ふことを得ず。債権者を有するチチウスが、生前に某の奴隷を解放し、解放に当りて「予は今の病気を逸るること能はざるときは、汝等が自由人たる可きことを欲す」と謂ひて、某に死因自由を与へたり。チチウス死亡したり。債権者は其の詐害に於て、自由が附与せられたりと謂ひて、解放を取消さんと欲したり。解放せられたる者は、債権者に損害なからしむ可きことを約して、自己に遺産が裁定附与せらる可きことを要求したり。勅法の文言は今の場合には関せずと雖も、かく称する者は聴許せらる可し。
七 吾人の至聖の皇帝は、今の立法に多数の区別が缺くるを見て、勅法を発布し、これによりて、かかる承継の権利を完全なるものになし給へり。此の区別に付ては、此の勅法の文言が教ふる所ある可し。
第十二章 資産売却によりて行はるる相続と、クラウヂアーヌム元老院議決に基く相続との廃止に付て
前章に於て、吾人が叙述したる包括的取得の前に、尚他の包括的取得あり。例へば資産売却の如し。これは多数の迂回と多数の廻道を以て、売却せらる可き、債務者の財産に付て行はれ、通常裁判が行はるる時、即ちconventus(conventusは吾人法学提要第一巻に於て説きたり)の時期に入りたるときにのみ、発生したり。今日に於ては、裁判は非常裁判にして、且何時にても開かるるを以て、資産売却は不使用となれるは当然なり。而て某なる多数人に債務を負ふ者が発見せらるるときは、裁判官の職権を以て、債権者に、共同債務者の財産を占有し、彼等に有用と観ぜられたる方法に従ひて、これを処分する権限が附与せらる。これは学説彙纂の更に広汎なる説明よりして、更に完全に知ることを得可し。古くは次の如くにして行はれたり。若し某が多数の者に債務を負担して、行方を晦まし、何人をも防衛者に得ざるが如きことあらば、債権者は訴を為して法務官に至り、此のことを同人のもとにて詰り、法務官は彼等に、債務者の財産を占有せしむることを許可し、彼等一定日数の間これが占有を為したり。此の日数が経過するや、彼等の中より、財産を売却す可き者一人を選ぶ権限を、彼等に備へしめられたき旨を請求する彼等よりして、第二回の陳情が行はれたり。蓋し総ての者が、毎日同様の訴を為すことは、困難なることなれば、彼等の中よりmagisterと呼ばれたる一人を選び、同人は次に購買希望者と合意を為したるなり。かくして市の目貫きの場所に、次の如き掲示が為されたり。「某我等の債務者、売却の境遇に陥る。我等債権者同人の財産を売却す。購買希望者は来談あれ」と。次に少数の日数が経過したるときは、第三回の陳情が行はれ、其のときに資産売却約款を作成することが許されたり。蓋し其のとき、上述の掲示に、次のことも附加したればなり。「購買者は債権者に対しては(例へば)債務の二分の一に付て責任を負ふ可きこと、故に百金の債権者は五十金、二百金の債権者は百金を取得す」と。而て其の間に一定の期間が経過したるときは、購買者に資産が裁定附与せられ、購買者は資産購買者と称せられ、資産売却を受けたる者に帰属せし訴権、及び彼に対して存せし訴権は、全部資産購買者に移転せられ、同人は遺産占有者の如く、準訴権によりて訴え又は訴えられたり。蓋し両者共法務官的承継者なればなり。然れども既に述べたるが如く、是等総ての迂回は、今日に於ては、裁判が総て非常的なるが故に、停止す。
一 此の外尚クラウヂアーヌム元老院議決に基きて、発案せられたる他の包括的取得ありたり。蓋し若し自由女が、予の奴隷に思慕の情を寄せ、其の結果労務に障碍を来したるときは、予は七人の証人の面前にて、同女に通告を為し、同女に予の奴隷より離る可き旨を通知することを得たり。若し離れざるときは、第二回の通告を用ひ、尚同女が依然として同一状態に止まるときは、更に三度同女に通告す。それにても彼女予の奴隷より離れざるときは、政務官の面前に通告を明かにし、その上にて宣告が行はれ、同女を予の奴隷に引き下げ、予は同女の主人となるのみならず、同女の全財産の所有者となりたり。吾人の極めて敬虔なる皇帝は、これを以て、帝の時代に相応しからざるものと決定して廃止し、帝の国より放逐し給ひ、其の学説彙纂の中にも、書き記すことを許し給はず。故に包括的取得は下の如し。相続、〔遺産〕占有、自権者養子縁組によるもの、自由保全の為の遺産の裁定附与これなり。これは国内に存す。資産売却及びクラウヂアーヌム元老院議決に基き奴隷に下ることは、廃止せられたり。
第十三章 債務関係に付て
物に関して述ぶる所ありたる吾人は、今や債務関係に移る可し。然れども人ありて、かかる順序を攻撃し、かくては前触れしたる所に違反して、債務関係に付て論述することとならんと謂ふ者あらん。蓋し法学提要第一巻に於て、羅馬の立法は幾何のものに関するかを吾人が論述したる場合に、人、物、訴権の中に存する旨を述ぶればなり。然らば人に付て論述し、更に物を取扱ひたれば、勢訴権に付ても述ぶる必要あらん。然るに何故に訴権を後にして、債務関係に赴くか。然れどもかくの如き順序は、理なきに非ず。蓋し債務関係に付て論述する者は、徐々且暗黙の中に、訴権に付て論述すればなり。債務関係は訴権の母なるによる。順序に付て弁解したれば、債務関係とは何たるかを述ぶ可し。債務関係とは法鎖にして、それによりて、人は負はれたるものを、吾人の国の法律に従ひて、弁済することを強制せらる。蓋し汝は債務の弁済の総ては、法律に従ふに非ざる限り、其の中に効力を有するに非ざることを知ればなり。予は此の言を、未成熟者に対する弁済、又は未成熟者よりする弁済は、後見人が同意することを要す可く、又時には或る別個の事項の遵守が存することを要す可きことを指して、これを為したり。
一 総ての債務関係の最高分類は次の如し。即ち或は市民的債務関係なるか、又は法務官的債務関係なるか、これなり。市民的債務関係とは、法律によりて発見せられたるか、或は少くとも市民法によりて、確認せられたるものなり。法務官的債務関係とは、法務官が其の裁判権を発動せしめて、定めたるものにして、亦名誉的とも称せらる。これ第一の分類なり。
二 第二の分類は下の如し。これは四に分たる。即ち或は契約によるもの、或は契約によるものに準ずるもの、或は不法行為によるもの、或は不法行為によるものに準ずるものこれなり。而て第一には、契約に基くものに付て詳言することを要す。契約とは、債務を成立せしめ、以て一方が他方に対して、責任者となることに関し、二人又は多数人が同一点へ合致又は合意することなり。四個の債務関係が、契約より発生す。物、言語、文書、合意によるものこれなり。而て各個に付て詳言することを要す。
第十四章 如何にして物による債務関係は結ばるるか
物による債務関係は、事実或は勘定と、手より手への移転とよりして成立し、其のもとには消費貸借あり。消費貸借とは、受領者が所有者となることにして、吾人に対し物自体に付て債務者となるには非ずして、同種同量の他の物に付て、債務者となることなり。「受領者が所有者となる」と謂ひたるは、使用権及び寄託を避けんが為なり。是等に付ては、受領者は所有者となることなし。「吾人に対して債務者となる」と謂ひたるは、贈与を避けんが為なり。蓋し〔贈与に於ては〕受領者は一方所有者となるも、他方債務者には非ざればなり。「物自体に付てに非ずして、同種同量の他の物に付て」と謂ひたるは、消費貸借の効用を除外せざらんが為なり。蓋し各人はこれを自己の利用に消費し、それに代へて他の物を返還せんが為、消費貸借を為す可ければなり。総ての物が、消費貸借の目的となるには非ずして、重、数、量の物のみが然り。重の物とは、例へば金、銀、鉛、蝋、瀝青、錫の如し。量の物とは、例へば葡萄酒、油、穀物の如し。数の物とは、小貨幣の如し。簡単に謂はば、数を数へ、或は量を測り、或は重を測るに際して、受領者の有たらしむる目的、物自体には非ずして、同性質同量の他の物が、吾人によりて返還せらる可き目的を以て、吾人が与ふる物〔が、消費貸借の目的物〕なり。消費貸借がmutuumと称せられたるも、「予の物(meum)よりして、汝の物(tuum)とならんが為、予より汝に与へられたるが為なり。」此の契約よりして訴権が発生し、condictioと称せらる。
一 非債弁済も物による債務関係なり。蓋し予若し汝に百金の債務を負ふと誤信して、これを錯誤によりて汝に弁済するときは、予は汝を所有者となす。後に真実を知るときは、予はcondictioによりて、これを取戻すことを得。蓋し訴ふるに当りては「若し某が与ふることを要すること明かなるときは」と謂ふも、消費貸借を請求する場合にも、既に述べたるが如く、同一の文言を用ひて、condictioを提起すればなり。而て一は消費貸借上のcondictio、他は非債弁済のcondictioと称せられ、消費貸借上のcondictioと、非債弁済のcondictioは、両者共に勘定の事実が先行する点に於て、共通点が存するのみならず、更に未成熟者が、法学提要第二巻に於て吾人が述べたるが如く、後見人の助成なくして、消費貸借を受くるも効力なく、又負担せざる債務を、後見人の存在なくして、同人に弁済するも、同人を非債弁済のcondictioによる債務者として、拘束し得ざる点にも存在す。而て是等の点には共通が存するも、消費貸借上のcondictioは、契約よりして発生するに——蓋し予は汝を債務者として拘束せんが為に、消費貸借を為せばなり——、非債弁済のcondictioは、其の中に契約を包含することなき——蓋し誤信せられたる債務を認めて、これを解消せんと欲する者の意思を以て、予が弁済を為し、成立せしめんが為には非ざるときに、如何にして契約と呼ぶことを得んや——点に差異あり。
二 物による債務関係のもとには、尚使用貸借も入る。蓋し人若し、予の書を自己に貸され度き旨を要求し、予が貸すときは、此処に事実が実行せられ、物による債務関係を産み、使用貸借訴権が出生すればなり。使用貸借は著しく、消費貸借とは懸隔る。蓋し消費貸借は所有権を移転するも、使用貸借は移転することなく、これが為、借主は物の返還に拘束せらる。而て尚他の差異あり。蓋し消費貸借の借主は、如何なる偶然の事情例へば火災、崩壊、難船、盗賊又は敵人の襲撃によりて、貸借の目的物を滅失するも、均しく責任者たり。然るに使用貸借の借主は、注意して使用貸借の目的物を管理することを要求せられ、同人が貸されたる物に付て、自己の物に付て用ふるが如き注意を示すを似ては足らず、他の一層注意深き者が持ち得るが如き注意を、示すことを要すと雖も、不可抗力によりて、使用貸借の目的物が滅失するが如きことあるときは、自己の原因によりて、此の滅失を惹起したるに非ざる限り、拘束せらるることなかる可ければなり。故に予若し汝に書を貸し、汝外出に当りて、自己と共にこれを携帯し、敵人又は海賊の襲撃によりてこれを失ふときは、疑もなくこれが返還に付て拘束せらる可し。蓋し汝は予の意思に反して、外出に携ふることを得ざればなり。使用貸借はgratuitumなることを要す。即ち予は報酬が与へらるることも、これが定めらるることもなくして、汝に無償にて貸与することを要す。報酬が介在するときは、書の使用権が、汝に賃貸せられたるものと観ぜられ、かくの如きものは、使用貸借と呼ばるることなし。蓋し既に述べたるが如く、使用貸借は無償たることを要すればなり。
三 寄託も亦これを、物による債務関係のもとに収む。蓋し予が汝に予の物を寄託するときは、汝は物による債務関係、其の寄託物の請求に当りて、汝に対して予が保有す可き寄託訴権に拘束せらる可ければなり。寄託物に付ては、汝は唯悪意のみの責任を負ふ。故に若し汝の過失又は不注意によりて、寄託物が悪化するも、汝に過失ありて、何人かに物が盗まれたるときと同じく、汝は責任を負ふことなかる可し。蓋し過失ある友人に、保管の為物を託する者は、自己の不明を責む可ければなり。
四 予汝より百金を借りて、質として、汝に予の奴隷を与へたり。汝は予に対し物による債務関係、質訴権の拘束を受け、此の訴権によりて、債務の弁済後は、其の物を予に返還することを、汝は強制せらる可し。而て此の質は、借主たる予、貸主たる汝二人の利益の為に、案出せられたるものとす。予の為とは、汝が質物を取りて、容易に汝の百金を予に貸与するが為なり。汝の為とは、質物の占有によりて、汝は債権に対して安全を得るが為なり。固より債権に対して安全を得るが故に、利得を為す者として、汝は多大の注意を、其の保管に付て示すことを要す。然れども若し偶然の事情によりて、質物が滅失するが如きことあらば、債権者は無責任にして、均しく債務を請求す可し。
第十五章 言語による債務関係に付て
物による債務関係を説きたる吾人は、言語による債務関係を述ぶ可し。これは何物かが、為され、与へらる可きことを、吾人が要約するとき、問とこれに対応する答よりして成立す。与へらる可きこととは、例へば「汝は予に百金を与ふることを約するか」の如し。為さる可きこととは、例へば「汝は予の為家屋を建築することを約するか」の如し。言語による債務関係よりして、二個の訴権が発生す。condictioとactio ex stipulatuこれなり。而て若し「汝は予に某の土地又は某の書を与ふることを約するか」と謂ひたるが為、問答口約の内容に来るものが、確定的なるときは、condictioが帰属す。若し「汝は予に箱の中又は倉の中に存する物を与ふることを約するか」と謂へるが為、不確定なるときは、actio ex stipulatuが生まる。stipulatioと呼ばれしは、古人のもとに於ては、「確定」がstipesより出でたるstipulumと称せられたるが為に由来す。
一 言語による債務関係には、次の))spondes ? spondeo(( ))promittis ? promitto(())fideipromittis ? fideipromitto(( ))fide iubes ? fide iubeo(())dabis ? dabo(( ))facies ? faciam((の如き多数の文言が伝へられ、これによりて問答口約が発生したり。然れども))spondes ? spondeo((は希臘語に翻訳せられずと雖も、他のものは翻訳せらる。))promittis ? promitto((は即ち))ὁμολογεῖς; ὁμολογῶ(())fideipromittis ? fideipromitto((は即ち))πίστει κελεύεις; πίστει κελεύω(())dabis ? dabo((は即ち))δώσεις; δώσω(())facies ? faciam((は即ち))ποιήσεις; ποιήσω((の如し。而して問答口約は、唯契約者の双方が謂ひたることを解する限り、希臘語羅馬語によりて行はるると、其の他如何なる国語、例へばシリア語エヂプト語によりて行はるるとによりて、何等の差異なし。双方が同一の国語を用ふることも、必要には非ず。唯問に対して相適応する答が、返答せらるるを以て足れり。例へば汝が予に))promittis ?((と要約するときに、予は))ὁμολογῶ((と謂ひ、又は反対に、若し汝が))ὁμολογεῖς;((と謂ふときに、予は))promitto((と謂ふことを得。更に二人の希臘人が、例へば))promittis ? promitto((の如く、羅馬語を以て、言語による債務関係を結ぶことすら可能なり。是等の典型的文言は、古くは行はれたるも、其の後レオの勅法は、問答口約の典型的文言を廃止し、双方の側よりの合致と合意の存することを要求するも、文言の遵守は問題とすることなし。
二 問答口約は、或は単純に、或は期限附、或は条件付に成立す。単純にとは、例へば「汝は予に二百金を与ふることを約するか」の如し。かかる問答口約は、直ちに請求権を発生す。期限附とは、物が履行せらる可き日が、問答口約に附加せられたるときなり。例へば「汝は予に十金を来る三月一日に与ふることを約するか」の如し。期限附に要約せられたる物は、直ちに負担せらるるも、期日の到来以前、更には朔日自身にも、請求せらるることを得ず。何故となれば、弁済す可きや否やに付ては、其の全日が被要約者の自由の中に存する所なればなり。蓋し同人が弁済せずして、同日の七時又は八時が経過するも、決して不当なる者とは決定せらるることなければなり。蓋し同人が十二時に於て履行することも可能なればなり。唯同人が何物も履行せずして、四月朔日全日が経過せるときには、初めて不当なる者となることを得。
三 予某に次の如く要約したり。「汝は予の生存する間、予に年金十金を与ふることを約するか」と。かかる問答口約は単純なり。蓋しかかる場合には、直ちに最初の一年の請求が為さるることを得、且永久的にして、何等期間によりて消滅することなければなり。蓋し問答口約は、例へば「汝は十年迄、予に十金を与ふることを約するか」と謂はんが為、即ち十年内に汝に請求するときは、予これを得可く、十年が経過し、予汝に請求することなきときは、訴権が消滅せんが為、或る期間迄のものと為すことは、不可能なればなり。故に「汝は予の生存する間、予に年金十金を与ふるか」と謂ふ問答口約に付ては、訴権は永久的なり。然れども若し要約者が死亡し、其の相続人が要約者の死亡後の年の額を請求して、actio ex stipulatuを提起するときは、「予の生存する間」なる条件のもとに要約したる者として、約束の抗弁によりて、排除せらる可し。蓋し此のことは約束の抗弁に発生を与ふればなり。
四 条件附問答口約は、債務が偶然の事柄に懸けられ、其の結果、何物かが為され、又は為されざるときは、問答口約が成立するときに発生す。例へば「汝は若しチチウスが執政官となれるときは、予に五金を与ふることを約するか」或は「汝は若しチチウスが執政官とならざるときは、予に五金を与ふることを約するか」の如し。人若し「若し予がカピトリウムに赴かざるときは、汝は予に五金を与ふるか」と要約するときは、かかる問答口約は、あたかも予が汝に「汝は予が将に死亡せんとするときに、五金を与ふることを約するか」と要約したるときと同じ。蓋し予がカピトリウムに赴かざることが明かにせらるるは、予が将に死亡せんとするときなればなり。何故となれば、予の生存中に、幾何の期間が経過し、且〔其の間に〕予がカピトリウムに赴かずとも、予がカピトリウムに赴かざる可き確信を与ふるには、充分ならざればなり。蓋し六十歳又は七十歳迄は、カピトリウムに赴かざりし者が、其の後になりて赴くことも可能なるも、最後の呼吸にある者が赴くことは、最早不可能なればなり。条件附に要約したる者は、自己に債務が負担せらる可き希望を有す。故に死亡するときは、此の希望を自己の相続人に移転す。蓋し仮令、吾人が法学提要第二巻に於て述べたるが如く、条件附遺贈は、条件の成就以前に受遺者が死亡するときは、同人の相続人へは移転せずと雖も、条件附問答口約は、要約者が条件の成否未定中に死亡するときも、相続人へ移転すればなり。
五 吾人は問答口約中に、場所をも附加するを習とす。例へば「汝はカルターゴーに於て、或は某々の土地に於て、予に十金を与ふるか」の如し。かかる問答口約は、一見したる所にては、単純なるかの如くに観ぜらると雖も、尚被要約者が、カルターゴーに到着し、以て履行を為すことがある迄、経過す可き暗黙の期間と延期を、其の中に包蔵す。故に羅馬に在る者が予に対し、「汝は今日カルターゴーに於て、予に与ふることを約するか」と要約するときは、問答口約は、其の中に不可能事を包含するものとして、効力なし。蓋し一日にて、羅馬よりカルターゴーに至るは、不可能なればなり。不能の条件のもとに為されたる問答口約は無効なり。
六 懸ることを過去又は現在に持つ条件は、或は直ちに債務関係を成立せしめざるか、或は延期を其れに恵与することなし。過去にとは例へば「若しチチウスが執政官たりしときは、汝は予に十金を与ふるか」の如し。現在にとは、例へば「若しマエビウスが生存するならば、汝は予に十金を与ふるか」の如し。蓋し若し是等がかくあらざるときは、即ちチチウスも執政官たらず、マエビウスも生存せざるときは、問答口約は無効たる可く、若し是等がかくあらば、問答口約は直ちに効力を有し、請求権が帰属すればなり。蓋し吾人が是等がかくあることを偶々知らざるが故に、請求権に対する猶予と延期が発生するに非ざればなり。事物の性質上明かとなれる物は、仮令契約者のもとには明かならずと雖も、債務を延期することはなし。
七 物例へば土地、奴隷、書が問答口約の内容に入れらるるのみならず、行為も亦然り。例へば予が「汝は予の為に家を建つるか」或は「汝は某の為に家を建てざるか」と要約するが如し。かかる作為又は不作為が、内容となれる問答口約に付ては、違約罰を附加するを以て最上の策とす。例へば、若し為すときは、或は又若し為さざるときは、汝は予に十金を与ふるか」の如し。蓋し違約罰を附加せざるときは、約したる所と何等か反対のことを為す者は、何を負ふかは明かならざればなり。蓋し利害関係に付て判決せられんとするときには(これは明かならず)、原告が其の利害に関する所幾何なるかを、証明すること必要なればなり。故にかかる困難を避けんが為、違約罰を附加することを要し、若し予が汝に「汝は某のことを為すか」と要約するときは、予は違約罰に付て「若しこれが為されざるときは、違約罰として予に十金を与ふるか」の如くに要約する必要あり。若し問答口約に、作為を内容とする或る事実、不作為を内容とする或る事実を含ましめたるときは、違約罰に関する約款は、次の如くに附加せらるることを要す。即ち「若しこれに反することが行はれたるときは」或は又、是等の中の何物かが為されざるときは、違約罰として予に十金を与ふるか」と。若し汝が作為又は不作為を蹂躙するが如きことあらば、かかる違約罰の約款は、多額の罰金の履行に付て、汝を拘束す可し。
第十六章 二名の連帯要約者及び諾約者に付て
問答口約に付て詳言せる者は、連帯要約者及び連帯諾約者に付ても教授することを要す。是等の者は、二人又はそれ以上たることを得。而て連帯要約者は、甲及び乙が某に百金を貸与し、彼等の各々が同人を全部に付ての拘束者として有せんと欲し、彼等の各々が別々に要約し、全部の者の要約後、被要約者が「予は約す」を謂ひたるときに発生す。例へば甲予に対し「汝は百金を与ふることを約するか」と要約し、同様に乙も亦要約したり。次に予二人に対し「予は汝等の中の一人に与ふることを約す」と謂ひて、返答したり。蓋し先づ甲に向ひて「予は与ふることを約す」と謂ひて返答し、其の後乙に向ひて又返答するときは、別々の債務関係発生し、二人の連帯要約者が発生すとは、称せらるることなければなり。二人又はそれ以上の連帯諾約者は、次の如くにしてなさる。例へば若し予が五金を貸したるマエビウス及びセイウスに対し、「マエビウスよ、汝は予に五金を与ふることを約するか」「セイウスよ、汝は同一の五金を予に与ふることを約するか」と要約し、各自は別々に「予は約す」を返答するときの如し。
一 かかる問答口約よりして、要約者の各自に対し、全額が負担せられ、被要約者の各自は、全額に付て債務者となる可し。蓋し各債務関係に於ては、或る一個の物が実行せらるればなり。蓋し連帯要約者の一人が債務を受領せば、共同要約者より請求の権能を剥奪もすれば、連帯諾約者の一人が債務を弁済するときは、他の共同被要約者をも亦解放もすればなり。
二 二人の連帯諾約者の中、一人は単純に、他は期限附又は条件附にて、債務者となることを得。即ち一人の単純に要約せられたる者が、直ちに請求せらるることには、障碍となることなし。他の者が期限附又は条件附に諸約することは、単純に要約せられたる者が、それによりて直ちに訴えらるるに、障碍となることなきなり。
第十七章 奴隷の問答口約に付て
奴隷は無人格者なれば、自己の主人の人格よりして資格付けられ、要約することを得るか、或は得ざるかに付て彼等が決定せらるるのも、これよりしてなり。然れどもこれは、要約する奴隷の主人の存する場合なり。何故となれば死亡し、何人も未だ承継者とならざるときは、相続財産が奴隷を支配すればなり。蓋し多くの場合、死亡者の地位を占むる者として、支配すればなり。故に若し相続財産に属する奴隷が、承継以前に要約したるときは、無形の相続財産の為に取得し、其の後承継せる相続人は、他の物並びに訴権と共に、かかる問答口約を相続財産中に発見す可し。
一 奴隷が如何に要約するかによりては、何等の差異なし。蓋し「汝は予又は予の主人に与ふることを約するか」と謂ふと、「汝は予又は予の同僚奴隷に与ふることを約するか」と謂ふと、或は又「汝は与ふることを約するか」と謂ひて、人を示さずして要約するとを問はざればなり。蓋し総てかかる方法による問答口約よりしては、主人に取得す可ければなり。吾人は尚権力服従者に付ても、同一と謂ふ者なり。但し吾人に取得し得可き原因による場合、即ち吾人の財産による場合に限る。
二 行為が吾人の奴隷の為す問答口約の内容に来れるときは、同人の人格が観察せられ、主人の人格が観察せらるることなし。例へば某に「汝は汝の土地を横ぎりて、ire(即ち単に通行のみする)こと、或は又agereする(即ち駄獣と共に通行する)ことを、予に許容することを約するか」と要約するときの如し。蓋し主人が土地を横ぎりて通行することを、妨碍せられたるときは、同人の問答口約に基きては、何等の訴の方法が附与せらるることなきも、奴隷が妨碍せらるるときは、問答口約内に存する行為は、奴隷の人格に関するの故を以て、問答口約は違約せらるればなり。
三 共有奴隷が要約するときは、主人の各々に、主人権の割合に応じて、問答口約より発生する債権を取得す。主人が同一の割合を以て支配すると、異る割合を以て支配するとを問はず。異る割合を以て支配するとは、例へば某死亡に当りて、甲と乙とを相続人に指定し、一を八ウンキア、他を四ウンキアに付て指定したるときに発生す。蓋しかかる割合に従って、相続財産中に発見せらるる奴隷を支配すればなり。即ち一は三分の二、他は三分の一に付て支配す。若し共有奴隷が要約するに当り「汝は予の主人甲に与ふることを約するか」と謂ひて、主人の一人を指名するときは、同人のみに取得す。又特に問答口約中には甲を指名せず、人を示さずして問答口約を為すも、甲の命令によりて要約するときは、又同じ。蓋しかかる場合にも、主人の命令は、名の指名と同一の効力あるの故を以て、甲のみに取得すればなり。若し奴隷が要約するときに当り、問答口約の内容をなす物が、主人の一人に取得せらるることを得ざるときは(蓋し予と甲とが共有の奴隷を有し、チチウスが吾人の奴隷によりて「チチウスよ、汝は某の土地を与ふることを約するか」と要約せられ、而て其の土地が予の所有に属すと仮定せよ)、予に関する限り、問答口約は効力なし。予は予自身によりて、予に所有せらるる物を、予に与へらる可きことをば、今更有効に要約することを得ざればなり(蓋しdareとは、所有者と為すことにして、予の物の更に完全なる所有者に、予が為さるることは得ざればなり)。然らば予の人格に関する限りに於ては、問答口約が無効なりとするも、予に取得せらるることを要することに関する限りに於ては、効力なき問答口約が〔依然〕無効なるか、或は予には取得せられざるも、共有者には全部が与へらる可きかが争はれ、所有者の一人に取得せられざる物は、取得に適合せる他の者に取得せらると謂ふ原則に基きて、肯定に傾きたり。
第十八章 問答口約の分類に付て
吾人が問答口約の分類を知ることも、脱線には非ざる可し。問答口約の中、或るものは司法的(iudicialis)、或るものは法務官的(praetoria)、或るものは合意的(conventionalis)、或るものは共通的(communis)即ち法務官的たると同時に司法的なり。
一 司法的問答口約とは、単に裁判官の職務より来れる、単純なる形態のものなり。悪意の問答口約の如きはこれなり。これは例へば予が、何人か問答口約に基きて奴隷を負ふ者に、actio ex stipulatuを提起するときに発生す。被告は如何にするも、敗訴判決を受く可きことを知りて、奴隷の引渡後暫くにして、同人を殺すに至る可き毒薬を、同人に供したり。かかる陰謀の為に、引渡さる可き奴隷の損害に於ては、何等の悪意を為さざりし旨を要約せらるることを、被告に強制するは裁判官の職務なり。逃亡中の奴隷に関する問答口約も、司法的問答口約なり。蓋し人若し某より、善意且無瑕疵にて、予の奴隷を買ふときは、何等の障碍なく時効取得は進行す。若し時効取得を完成す可き期間の終了前恐らく二三ヶ月に、予が占有者に物的訴権を提起し訴訟継続中、時効取得が完成し、其の後被告の悪意なくして、奴隷が逃亡し、其の後原告たる予は、奴隷が予の所有権に服したることを証明するときは、奴隷の逃亡に付て過失なき被告が、敗訴するは失当なるも、同人が免訴せられ、其の結果、かかる訴訟に於ける勝訴も、予には何等甲斐なきこととなることも亦、失当なるを以て、被告に、此の奴隷を発見したるときは、今やさきの時効取得によりて、所有者となれるを以て、所持者に対して、物的訴権を提起し、以てこれ【奴隷】を予に返還するか、或は其の代価を返還す可き旨の保証の提供を強制することは、裁判官の職務なり。蓋し若し時効取得せざるときは、予はかかる保証を要せざればなり。原告は他の総ての所持者に物的訴権を提起し得るに何等の障碍なきが為なり。
二 法務官的問答口約とは、単に法務官の裁判権より発生するものなり。damni infectiの如きはこれなり。これは隣人の家が、それに存する腐朽故に、倒壊の惧あるときに発生す。蓋し隣人がこれに付て注意を為すことを欲せず、又「若し此の倒壊によりて、予が損害を受くるが如きことあらばそれよりして発生せる損害を、予に賠償す可き」旨を諾約することをも欲せざるときは、予は危険なる建物を占有せしめらる可ければなり。故に隣人が、予の同人の建物を占有することを欲せざるときは、損害予防に付き、かかる問答口約を要約せらるることを強制せらる。蓋し倒壊よりの損害が未だ発生せざるの故を以て、damni fecfiと称せらるるなり。又legatorum問答口約も亦、此の種の問答口約なり。蓋し人若し死亡に際して、汝を相続人に指定し、更に予に、例へば「若し船がアヂアより来れるときは」なる条件のもとに、遺贈を為すときは、条件の成否未定中は、予は如何なる訴権をも、相続人たる汝に提起することを得ざるも、然かも中間時に汝相続人が、遺産を消費し、為に無資産となりて、遺言者の恩恵を予に無為と為す惧は、小ならざるを以て、法務官は、汝相続人が条件の成就前に要約せられ、且条件が成就するときは、遺贈を履行す可き旨の保証人を設定す可き旨を命ず。若し相続人がこれを行ふことをせざるときは、予は遺贈の目的物か、或は全資産を占有せしめらる可し。法務官的問答口約には、按察官的問答口約も亦算入せらる。蓋しこれも按察官の裁判権よりして、其の起源を有するものなればなり。これは売却せらるる奴隷の瑕疵故に為さるる問答口約に付て発生す。蓋し売主は買主に対して、売却せられたる奴隷に隠れたる瑕疵が発見せらるるときは、例へば二倍額を履行す可き旨を、要約せらるることを要すればなり。
三 合意的問答口約は、各当事者の共同の合意よりして行はる。即ち裁判官の命令にもよらず、法務官の命令にもよらず、契約者の意思よりして行はる。合意的問答口約の種類は、殆んど契約の数丈け存す。
四 共通的問答口約とは、例へばrem salvam pupilli fore問答口約の如し。蓋し法務官は、法学提要第一巻に於て述べたるが如く、後見人となれる者に、未成熟者の財産が安全且無損害に保管せらる可き旨の、保証人の設定を命令すればなり。若し偶々保証前に、後見人が未成熟者の〔相手方たる〕債務者を訴えたるに、同人は返答することを欲せず、又保証が未だ後見人によりて設定せられざるの故を以て、訴訟に応ずることも欲せざるときは、訴訟は他に進行の途なきを以て、後見人と未成熟者の〔相手方たる〕債務者に裁判を行ふ裁判官は、rem salvam pupilli fore保証の設定を命じ、これが為法務官の裁判権と、裁判官の職務の共通のものと観ぜらるるなり。ratam rem問答口約に付ても同一なり。蓋し法務官は、他人の名目を以て、訴を為す者に対し、本人の意思に従ひて、訴訟を為せるか曖昧なるを以て、保証の設定を命令するものなるが、若し偶々某が不在者の委任に従ひて、予に対して訴訟を提起し、予が委任に付て疑問視するを以て、訴訟が進行することを得ざるときは、裁判官は訴訟人に対し、ratam rem dominum habiturum保証を提供することを強制す。かくの如くにして、今の問答口約の成立に付ては、一般的に此のことを立法する法務官と、訴訟が進行せんが為、此のことの行はる可きことを準備する裁判官とは共同す。
第十九章 無効の問答口約に付て
問答口約の中、或るものは有効、或るものは無効なり。然れども有効のものは多数なるも、無効のものは少し。故に少きものに付て述ぶることを要す。蓋しそれよりして、有効なる方の多数を知ればなり。先づ総て吾人の所有権に服し得る物は、動産たると不動産たるとを問はず、適当に問答口約の内容とせらるることを知ることを要す。
一 人若し事物の自然の中に存せず、又存し得ざる物が、同人に与へらる可きことを要約するときは、問答口約は無効なり。而て自然の中に存せざる物とは、次の如し。例へば「汝は予に奴隷スチクスを与ふることを約するか」の場合に、同人は死亡せるに、同人が生存せるものと誤信するが如し。存在し得ざる物とは、例へば「汝は予に半人半馬《ヒツポケンタウルス》を与ふることを約するか」の如し。これは存在することを得ず。既に述べたるが如く問答口約は無効なり。
二 又人若し人法に服するものと信じて、神聖物又は宗教物を、或は永久に国民の利用に指定又は献納せられたる公物、例へば広場、劇場、円形劇場、其の他類似の物を、或は奴隷と誤信して自由人を、或は取引権(取引権とは、売買することを得可き権限なり。取引権を有せざるが如き物あり。例へば正統派教会に属する土地は、異端者これを取得し得ざるが如し)を有せざる物を要約し、或は又予の物を予が「汝は予に某なる物を与ふることを約するか」と謂ひて、汝に要約するときも亦同じ。蓋しdareとは、所有者と為すことにして、予は予の物の更に完全なる所有者となることは、不可能なればなり。而て中間時に於て公物が、恐らく皇帝が許可したるが為、私人の所有に帰し得ること、又恐らく被解放者たる者が忘恩者として、保護者の奴隷に引下げられたるが為、自由人が奴隷となることを得ること、又取得権を取得することを妨げられたる物に付て、取引権を屡々皇帝より取得することを得ること、又予の物が予の所有に属することを已むることを得ることは、有り得可きが故に、問答口約の力と成立が、停止中にありて、其の結果問答口約は有効なりと謂ふに、何等の故障なきに至らしむとは、吾人謂ふことなし。然らずして当初より直ちに、かかる問答口約は無効なりと吾人は謂ふ者なり。同じく反対に、仮令当初より問答口約は有効なりと雖も、其の後前言したる状態の一に、被要約者の意思と希望に従はずして陥るときは、問答口約は消滅す。例へば予汝に対し「汝は予に奴隷スチクスを与ふることを約するか」と要約したり。同人は甲の奴隷たり。問答口約は固より有効なるも、次に汝の意思によらずして、偶々同人が主人より解放せられたるが如し。或は予汝に「汝は予に某なる場所を与ふることを約するか」と要約し、其の土地は私有なりき。後請求前、神聖物又は宗教物となりたり。問答口約は、既に述べたるが如く、疑もなく無効となる可し。蓋し事情が起源を起すことを得ざるが如き場合となるときは、消滅すればなり。当初には自由人も、神聖物又は宗教物も、これを要約することを得ざりしなり。然らば人若し自由人に付て、「汝はチチウスが奴隷となれるとき、これを予に与ふることを約するか」或は又公物に付て「汝は若し劇場又は円形劇場の存する某なる場所が、私人の権利に服するときは、これを予に与ふることを約するか」の如き要約を為したるときは如何。其の性質上吾人の所有に服せざる物は、有効に問答口約の内容に入るることを得ざるが故に、問答口約は当初より無効なり。
三 人若し他人が或る物を与へ、又は為すことを約するときは、債務者となることなし。例へば予が「予はチチウスが汝に十金を与ふることを約す」或は「汝に家屋を建つることを約す」と謂へるが如し。若し予が、チチウスが汝に十金を交付する様、慫慂す可しと謂へるときは、問答口約は有効なり。蓋し予自身の行為を約したればなり。
四 人若し他人の為に——其の者に対しては、自己は権力服従者に非ず——要約するも、無効なる要約なり。然れども履行は、他人に対しても為さるることを得。例へば予若し「汝は予又はセイウスに、十金を与ふることを約するか」の如き要約を為すときの如し。蓋し債権は要約者たる予のみに取得せらるるも、履行は仮令予の意思に反するも、汝は有効にセイウスに対してこれを為し、以て汝は履行によりて、法律上当然解放せらるることを得可ければなり。尚予はセイウスに対し、同人に与へられたる金の請求に付き、委任訴権を有す可し。予若し「汝は予及びチチウス(予は其の権力服従者に非ず)に十金を与ふるか」の如き要約を為すときは、問答口約は有効なるも、チチウスは取得に適せざるが故に、あたかもチチウスは問答口約内に加はらざりしが如くに観ぜられて、問答口約内に含まれたる全部が負はるるか、或は「及び」なる語は加重的接続語なるが故に、半額が負はるるか曖昧となれり。而てチチウスの名を、問答口約内にあげたるは無効なるが故に、半額以上のものが、要約者たる予に取得せらるることなしとすること、通説となれり。予若し「汝はチチウスに与ふるか」と要約し、其のチチウスは予の権力服従者たりしときは、予は予の為に取得す。蓋し予の声は予の権力服従者のものと観ぜらるること、あたかも予の息の声は予のものと解せらるるが如きを以てなり。但し〔後者に於ては〕吾人に取得せられ得る物に限る。今日に於ては、これは父の財産によるものと解す可し。
五 上記問答口約の外、次のもの、即ち人若し要約に対応せずして、返答したるときも無効なり。例へば「汝は予に十金を与ふることを約するか」に対し、汝は「予は五金を与ふ」と謂ひ、或は予が五金を要約し、汝は条件付にて約し、或は反対に条件付に予が要約し、汝は単純に返答するが如し。予は汝が明かにこれを表現したるとき、即ち予が条件付又は期限付にて要約したるに、汝は自ら直ちに与ふ可しと返答したるときに、此の言を為す。蓋し若し「予は約す」のみを返答したるときは、汝は簡単を旨として、同一の期限又は条件付に、返答したるものと観ぜらるればなり。蓋し要約に対する返答に於ては、要約者が発言したると同一の文言全部を繰返すは、必要に非ざればなり。蓋し「予は約す」〔の語〕は、要約に合まれたる総てのものに関係すればなり。
六 同じく予が予の権力服従者に要約し、或は彼等に要約せられたるときも、問答口約は無効なり。蓋し吾人の間には、訴権は行使せらるることを得ざればなり。然れども奴隷は主人がこれに要約するも、債務者とならざるのみならず、他の或る者が要約するも亦然るに、権力に服従する息は、他人に要約せらるるときは、拘束せらる。蓋し権力服従者は、契約に於ては、自主権者に類似すればなり。
七 唖者が要約することも、要約せらるることも得ざるは、学説の一致する所に属す。此のことは、聾者に付ても認められたり。要約者となるも、被要約者の文言を、被要約者となるも、要約者の文言を聞くことを得ざればなり。而て此の理は、徐々ならば聞ゆる聾者には関せずして、全然聞えざる聾者に関す。
八 精神錯乱者は、契約を為すことを得ず。蓋し行はるるものに対する理解を有せざればなり。意思を奪はれたるに基く。然るに意思は契約の母なり。
九 未成熟者はあらゆる契約を有効に締結す。但し後見人の助成の必要あるとき、例へば自ら債務者とならんとするとき、後見人が招致せられたる上のことなり。他人を自己の債務者と為すことは、未成熟者は後見人なくして、これを為すことを得。
一〇 然れども、吾人が未成熟者に付て述べたる所は、行はるる所に関して、既に或る理解を有する者に付て、固より真なり。蓋し幼児、又は幼児期に近き者は精神錯乱者より懸隔ること、余り大ならざればなり。蓋しかかる年齢にある者は、何等の理解を有する者とは観ぜられざればなり。未成熟者と謂ひたれは、一般に未成熟者の年齢は、三に分たることを学ぶ可し。蓋し未成熟者の中或る者は幼児、例へば未だ乳を吸ふ者、及びそれより少し進みたる者、或る者は幼児期に近き者、例へば良く話し始めたる者、或る者は成熟期に近き者と称せらるればなり。而て幼児は話すことを得ざるを以て、要約することを得ず。幼児期に近き者、例へば七歳又は八歳にある者も亦、然ることなし。蓋しかかる者は、言語を発達することを得と雖も、謂ひたるものが何を意味するかを、理解することを得ざればなり。成熟期に近き者は、有効に要約す。蓋し発言もなし、謂ひたることを了解することも、可能なればなり。然れども〔法律の〕厳正に従はず、博愛の理に従ひて、幼児期に近き者も亦、成熟期に近き者と同じく、有効に要約すること通説となれり。未成熱の権力服従者は、父の助成あるも、債務者となることなし【Ferrini p. 339の羅甸訳は誤】。
一一 問答口約に附加せられたる不能条件も、問答口約を無効となすことを得。不能条件とは、自然が其の成就を妨ぐるものなり。例へば若し「若し予が予の指を以て空に触るるときは、汝は予に十金を与ふるか」或は「若し予が海を呑みたるときは」と謂ふときの如し。又人若し「若し予が予の指を以て空に触れざるときは、汝は予に与ふるか」の如き要約を為すときは、債務は単純に発生するものと解せらる。故に直ちに請求することを得。
一二 同じく不在者間に行はれたる、言語による債務関係は、効力を奪はる。然れども、かかることは、恐らく多大の時日を経て、かかる訴訟抗弁を対抗して、同人又は要約者は其の都市には存在せずと争ひて、徒に事を好む徒輩に、訴訟の口実を与へたるを以て、これが為、吾人の皇帝の勅法制定せられ、かかる濫争を簡単に廃止したり。此の勅法はカイザレイアの弁護士に対して、解答せられたるものにして、其の中にて、各当事者の名の示されたる証書は、かかる防訴抗弁を対抗する者が、完全明瞭に、適当なる証書又は証人によりて、証書が作成せられたる当日は終日、同人又は其の相手方は、他の場所にて暮したる旨を証明するに非ざる限り、常に信用す可き旨を規定し給へり。
一三 人其の死後自己に与へらる可き旨を要約するも無効なること、あたかも彼の要約をうけたる者の死後に、与へらる可きことを要約するに同じ。又他人の権力服従者たる者、例へば奴隷又は息も亦、其の父又は主人の死後に、〔与へらる可きことを〕要約するも有効には非ず。更に人若し「予又は汝が死亡せんとする一日前に、与ふることを汝は約するか」の如き要約を為すも、「前日」は「死後」に関係するを以て、問答口約は無効なり。蓋し死亡の前日は、死亡によりて知り得るものなればなり。然れども、屡々述ぶるが如く、契約者の合意よりして、問答口約は効力を有するものなれば、吾人の皇帝は、法律の此の部をも、匡正に値す可きものと解せられ、為に要約者又は被要約者の死後にせよ、死亡の前日にせよ、問答口約がかかる内容のものなるときは、疑なく有効となりたり。
一四 前後顛倒の問答口約も亦無効なり。例へば人若し「若し明日船がアヂアより来るときは、汝は今日予に与ふることを約するか」と要約するときの如し。蓋し履行は条件の成就より前たることを得ず、後たることを要するを以て、此の問答口約は無効なるなり。然れども前後顛倒の問答口約を許したる、嫁資に関するレオの勅法存するを以て、これが為吾人の皇帝は、総ての問答口約に付て、附加せられし前後顛倒の瑕疵は、債務関係を排除せざるを以て正当なりと思惟し給へり。蓋し予が「若し明日チチウスが執政官となるときは、予は今日汝に十金を与ふることを約す」と謂ふも、或は又嫁資に関して、若し夫が妻に「若し汝が無子にて死亡するときは、予は死亡せんとする汝に、嫁資を与ふることを約す」と謂ふときも、問答口約は前後顛倒なればなり。蓋し履行は生存の時に関係し、条件の成就即ち無子の成就(蓋し「若し汝が無子にて死亡するときは」と謂へばなり)は、死後の時に推し遣らるるを以てなり。故に嫁資に関するのみならず、総て如何なる問答口約に関しても、発生したる前後顛倒〔の条件の附加〕は、問答口約を無効となすことなきこと通説となりたり。
一五 要約者又は被要約者が死亡するときに、との問答口約は有効なり。これは若しチチウスが要約せられて、「予は予が死亡せんとするときに、汝に与ふ」と謂ふときに発生す。蓋し此の問答口約は、古人のもとに於ても有用、今も効力を有すればなり。
一六 他人の死後にとして、為さるる問答口約も亦、古人のもとに於ても有効なりき。例へば人若し「予はチチウスの死亡後、汝に十金を与ふることを約す」と謂ふときの如し。契約者の生存中に、チチウスが死亡することは、ありたればなり。
一七 若し問答口約の証書の中に、チチウスが約したる旨が記載せらるるときは、問答口約が行はれて、返答したるが如くに解せらる。蓋し証書内に記載せられたる返答は、推定によりて、要約の先行を表現すればなり。
一八 多数の事物が、一個の要約内に収めらるる場合に——例へば「汝は予に某なる奴隷と、某なる土地と、某なる書と、某なる衣服を与ふることを約するか」の如し——、要約せられたる者が、若し単純に「予は約す」と返答するときは、総ての物に付て拘束せらる。若し要約中に含まるるものの、恐らくは一又は他に付て、返答するときは、返答せられたるものに付てのみ、債務者となる。即ち多数の要約が為さるるも(要約内に包含せらるる物の数丈、要約の数も存すればなり)、返答せられたる一又は他のみが、完成せるものと観ぜらる。蓋し要約内に包含せらるるものの各に対して、返答も亦為さるることを要すればなり。蓋しかくの如くにして全部に対し、要約が完成するなり。
一九 他人の為に要約することは、前にも述べたるが如く、何人も有効にこれを為すことを得ず。蓋し今の問答口約は、各自が利害関係を自己に取得せんが為、発案せられたればなり。故に人若し、利害関係者に非ざる者として、他人の為に要約するときは、行はれたるものは無効なるを以て、人若しこれを有効となさんと欲せば、違約罰を要約し、以て此のことが行はれざるときは、違約罰の請求権が帰属する様にすることを要す。例へば「汝はチチウスに十金を与ふることを約するか、若し与へざるときは、違約罰として五金、恐らくは更にそれ以上を、予に与ふるか」と。蓋し仮令予が利害関係如何を明かにすることを得ずとも、違約罰の請求権は、予に帰属すればなり。蓋し人違約罰を要約する場合には、吾人は、要約者に何等か利害関係が存するかを穿鑿することなく、問答口約の条件中に含まるる違約罰の額は、幾何なるかを調査すればなり。然らば問答口約の条件とは何ぞや。其の中に「若し為さざるときは、違約罰として、予に十金を与ふるか」が挿入せらるることなり。故に人若しチチウスに与へらるることを要約するときは、何物をも為し遂ぐることなし。若し問答口約に違約罰恐らくは十金が挿入せらるるときは、求むる所を為し遂ぐ。
二〇 然れども若し違約罰を問答口約に挿入せざりしも、利害関係が存するときは、問答口約を有効とするを通説とす。蓋し甲と乙とが後見人たるとき、甲が共同後見人乙に管理を託し、同人が未成熟者の財産を安全且無損害に保管す可き旨を要約するときは、此のこと【完全なる保管】が実行せらるることは、要約者に利害関係あるを以て(蓋し乙が管理に付て、極めて不良に行動するときは、〔甲も〕後見訴権の責任者となればなり)、問答口約は有効となり、其の結果乙に対する有効なる訴権を、甲に発生す。同じく人自己の執事に与へんことを、予に要約するときは、問答口約は有効なり。蓋し他の土地に住居する汝の執事が、租税の履行、家屋の修繕、或は土地の改善の為、金銭を必要とし、汝は其の土地へ旅行せんとする予に「汝は予の執事に、百金を与ふることを約するか」と要約したり。蓋し見よ、此の場合には予の執事に金銭が与へられざるときには、無資力によりて、予が損害を被るの利害関係が存すればなり。若し汝が債権者を有し、同人に対し恐らく汝の物を担保に供し、汝の不履行あるときは、同人にこれを売却することを許し、或は又若し約束の日に金銭を返済せざるときの違約罰を要約せられ、次で汝予に対し「汝は予の債権者に、某の金を与ふることを約するか」と要約する場合に、予がこれを充さざるときは、汝は利害関係の額に付て、〔即ち〕或は質物が売却せられ、或は違約罰を請求せられて、汝が受けたる損害額に付て、予を責任者に有す可し。而てこれはdareを内容とする問答口約に関す。
二一 人若し他人が、何物かを為すことを約するとき、例へば「某が汝に家屋を建つ可きこと」を約するときは、違約罰が問答口約に挿入せられざる限り、全然無効なり。其の結果、dareの問答口約と、facereの問答口約の間には、与ふることに付て違約罰が存せずとも、利害関係の存するときは、問答口約は無効なるに、facereの問答口約に付ては、違約罰なくして、他人へ関係せしむるときには、問答口約は有効となることなき差異あり。
二二 吾人は前に説きたる所に於て、自己の物を要約することは、更に完全に自己の物の所有者となることを得ざるにより、不可能なることを述べたり。これよりして次のことが問題となれり。某死亡に当り、甲を相続人に指定し、其の奴隷スチクスをば「若し船がアヂアより来れるときは」なる条件附にて、予に遺贈したり。予に十金の債務を負ふ某チチウス、十金に代ふるに、彼の奴隷スチクスを同一条件の下に、予に与へんことを要約せられたり。遺言者が死亡し、承継が行はれ、暫くして後、遺贈の条件——此の条件は問答口約にも関係す——が成就したり。遺言に基きて、予がスチクスの所有者となれることは明かなり。予は今や遺言に基きて、予の所有権に服せるスチクスを要求して、チチウスに対し、問答口約に基くものとして、訴ふることを得ず。蓋し既に述べたるが如く、当初に予の物なりしならんには、これを問答口約の中に収むることなきと同じく、予の所有権に服せんとする場合も、これを問答口約内に入るるは、不可能なればなり。
二三 返答は要約に対応することを要すと謂ひたれば、次のことも問題とせられたり。即ち時に要約者が、或る物に付て考へ、被要約者は他の物に付て考へたるときは、同じく債務関係を発生せざること、あたかも要約せられたる物に対し、被要約者が返答せざりしときと同じ。例へば若し「汝は予にスチクスを与ふるか」と要約したるに、汝はパンフィルスが、スチクスと称せらるるものと考へて、要約はパンフィルスに関して謂はれたるものと、誤信したるときの如し。
二四 醜悪なる原因に基きてなされたる問答口約は無効なり。例へば人若し自ら殺人、神の冒涜、姦通を為すことを約するときの如し。
二五 問答口約が条件付に行はれたるに、其の成就前に要約者が死亡し、其の後条件が成就するときは、要約者の相続人は、問答口約に基く訴権を有す可し。被要約者が死亡し、後条件が成就するときも亦同じ。蓋し同人の相続人は、均しく請求せらる可ければなり。
二六 今年又は今月に与ふることを約する者は、年又は月の全日数が経過するに非ざれば、訴えらるることなし。
二七 若し汝が土地又は奴隷を与ふることを約するときは、引渡が為され得可き期間が、経過するに非ざれば、直ちには訴えらるることなし。
第二十章 保証人に付て
被要約者に代つて、他の者が債務者となるを通常とす。これはfideiussoresと称せらる。契約が安全なる地位にある可きことを留意する者は、此の保証人を徴する習なり。
一 総ての債務関係に於て、保証人が徴せらるるを通常とす。即ち成立が物によると、言語によると、文書によると、合意によるとを問ふことなし。更に保証人の附加せられたる債務が、市民的なるか自然的なるかも、吾人には何等の差異なし。これ何のことなるか、述ぶる必要あり。次のことを予備知識として保持す可し。問答口約の中、或るものは市民的、或るものは自然的なり。市民的問答口約とは、それよりして訴権を生じ、其の訴権は債務者となれる者に提起せられて、同人を判決する準備を為すもの、それに基きて為されたる弁済は、取戻を許さざるものなり。蓋し責任者となれる者が、意に反して請求せらるるも、履行せば取戻すことを得ざればなり。自然的問答口約とは、訴権を発生せず、判決にも至らしめざるものなり。此の中には、二個の注意事項を発見することを得。即ち為されたる弁済は、取戻を許さざること、附与せられたる保証人は、自然上も法律上も、拘束せらるることこれなり。蓋し或る者の主たる債務者が、自然上拘束せらるるときは、其の保証人は、自然上も法律上も、拘束せらると称する法則あればなり。後見人の助成なくして、消費貸借を受けたる未成熟者の如きはこれなり。蓋し同人は自然上拘束せらるるも、同人を保証する者は、自然上も法律上も、拘束せらるればなり。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。吾人は市民法上の債務に対するのみならず、自然的債務に対しても亦、有効に保証人が徴せらるる旨を述べたり。自然債務と呼ぶは、例へば主人に非ざる者、又は主人に対して、債務者となれる奴隷(固より自然的に然るなり。蓋し法律上は請求することを得ざればなり)が、或は他人、或は其の主人に対し、彼に負ふ所の物の為に、保証人を与ふるときの如し。保証人は、主たる債務者、即ち奴隷が、自然上拘束せらるるの故を以て、自然上も法律上も拘束せらる。
二 保証人は、自身自らが債務者となるのみならず、死亡するときは、其の相続人をも債務者として遺す。
三 保証人は、其の保証する者の債務に先在することも可能なり。例へば、汝某より借入を為さんとして、契約の成立の為、保証人を与へたるときの如し。或は又契約の成立後に、汝が予を保証人となすも可能なり。
四 若し多数人が保証人となれるときは、幾何の数ありとも、一部に付て拘束せらるるに非ずして、彼等の各人が、全部に付て拘束せられ、其の結果、債権者には、其の欲する者に対し、全部に付て訴ふる自由あり。然れども、ハドリアーヌス皇帝の勅書によりて、債権者は争点決定の時に於て、資力ある各保証人に対し、一部を請求することを強制せられ、為に保証人の或る者が、其の時に於て、無資力者なることが発見せられたるときは、同人の無資力は、共同保証人に負担を与ふ。例へば百金の債務あるとき、保証人五人ありたり。総ての者が資力あるときは、各二十金宛にて訴えられたり。彼等の中一人が無資力者なるときは、無資力は残余の者に損害を齎す。蓋し四人は二十金を請求せらるるに非ずして、二十五金を請求せらるればなり。而て人若し共同保証人の一人を訴えて、全額を得たるときは、其の請求せられたる者のみの損害なり。蓋し共同保証人に対して、訴権を有することも許されず、無資力なる主たる債務者に対しても、有効に提起せらるることなければなり。かかる保証人は宜しく自己を責む可し。蓋し訴えられたるときは、ハドリアーヌスの勅書に基きて救助せられ、同一の割合にて、共同保証人と共に請求せらるる様、図ることを得たる可ければなり。
五 保証人は、或る者の為に債務者となりたるときは、其の者が債務を負担するより以上に、自らが負担するが如くにして、債務者となることを得ず。蓋し保証人の債務は附随物なればなり。主たる訴に於けるよりは、より以上のものが、附随物に存することを得ざればなり。反対により少額に債務を負担する様、債務者となることは可能なり。これが為主たる者、即ち債務者が、十金を与ふることを約するときは、彼等【保証人】は有効に五金の要約を受く可し。主たる者が五金を要約せらるるときは、保証人は良く十金に付き保証人に徴せらるることなし。同じく主たる債務者が、若し単純に要約せられたるときは、保証人は条件附に要約せらるることを得。反対に主たる債務者が、条件附に要約せらるるときは、保証人は条件附にては、適法に要約せらるるも、単純にては、適当には要約せらるることなし。蓋し多きか少きかは、額のみならず、期間に於ても亦、考ふることを要すればなり。蓋し如何なる物にせよ、直ちにこれを与ふることは、より多くのこと、後日与ふることは、より少きことなればなり。
六 主たる債務者に代りて、弁済したる保証人は、与へたる物の回収に付き、同人に対し、委任訴権を有す可し。
七 保証人は多くの場合、希臘語を以て、次の如くに約す。τῇ ἑμῇ πίστει κελεύω θέλω λέγω(予の信を以て予は命じ欲し謂ふ)と。若しφημὶと謂ひたるときはλέγωと謂ふも同一なり。
八 保証人の問答口約に付ては、如何なる物が為されたる旨記載せらるるも、それは為されたるものと、推定によりて観ぜらるることを知らざる可からず。故に人若し保証人となれる旨を記載するときは、通常習とする総てのもの、例へば同人が保証人として要約せられ、又同人がこれに続きて約したるが如きことは、実行せられたるものと観ぜらるるは、学説の一致する所なり。
第二十一章 文書の債務関係に付て
物による債務関係、及び言語による債務関係の後、文書による債務関係に付て述ぶ可し。文書による債務関係は古くは次の如き定義を容れたり。文書による債務関係とは、古き債務が、定型的文言と文書によりて、新しき貸借に変形せられたるものなり。蓋し人若し十金を、或は売買、或は賃貸借、或は消費貸借、或は問答口約に基きて(債務の発生原因は多数なり)予に負ひ、予は同人を文書による債務関係の責任者と為さんと欲するときは、予が文書による債務関係の債務者と為さんと欲する者に対し、次の文言を語り、且記載することを要したり。語り且記されたる文言は下の如し。「賃貸借を原因として、汝が予に負ふ百金を、予は汝に支出したり」と。次に既に賃貸借に基きて、債務者となれる者によるものとして、次の文言が記入せられたり。「汝は予に支出したり」と。かくして前に存せし債務は消滅し、後の債務、即ち文書による債務が発生したり。これは文書の中に存することよりして、其の名称を受けたり。今日に於ては、これは使用せらるることなし。然れども、人若し精密に穿鑿するときは、別の形態なるも、今日に於ても、文書による債務の行はるるを発見することを得可し。蓋し人若し予より消費貸借を受けんと欲して、予に此のことを語り、予は同人に文書の作成を命じたるに、彼は予の不在の裡に、単独にて文書を作成し、其の中にて「予は今日某より借入を為し、これを債務として負担す」と謂ひ、而て問答口約も挿入せられず、或はかかる証書が、貸主の存せざる間に作成せられたるが為、挿入にも術なきとき、後多数の時日を経過するときは、上記の文書を作成せる者が、訴えられ得可きか疑問とせらるればなり。而て吾人は今の人間は物による債務に基きて訴えらるることを得ずと謂ふ者なり。勘定が為されざればなり。又言語による債務に基きても、然ることなし。両当事者立合の上にて、問答口約が為されたるにも非ず、或は又問答口約は全然為されざればなり。残るは唯、文書のみに基きて、同人が債務者となることのみ。見よ、今日に於ても、時に人の文書による債務者となるを。多数の時日とは、古くは五ヶ年迄転回せり。其の期間の後は、不受領の抗弁、即ちnon numeratae pecuniae抗弁を対抗し、貸主に対し「汝が勘定したることをば証明せよ」と謂ふことを得ざりき。蓋しこれ皇帝の多数勅法に述べらるる所なればなり。此のことは債権者にとり、困難なることなりしを以て、吾人の皇帝は、多数の時日即ち三年又四年が経過して、債権者がこれが真なる可き旨を説明せんことを要求せられたるとき、経過せし期間の長きが為、証明の困難に陥り、それが為、其の債権を喪失するが如きことなからしめんが為、勅法を制定し、該勅法は五ヶ年を二ヶ年に変更したり。其の結果、此の期間内には、かかる抗弁は有効に対抗せらるるも、二ヶ年の後は全然不可能なり。
第二十二章 合意による債務関係に付て
物による債務関係、言語による債務関係、及び文書による債務関係を述べたる吾人は、今や合意による債務関係に付て述ぶ可し。此の種の債務関係の成立は、売買、貸借、組合、委任の如き契約に於て存在す。
一 合意による債務関係が、かかる方法によりて成立するは、文書による債務関係に於けるが如き記載も、言語による債務関係に於けるが如き立会も、全然不必要なるによる。又合意による債務関係が成立を受くるが為には、物による債務関係に於けるが如く、何物かが与へらるることも必要に非ざるなり。蓋し合意による契約を結ぶ者が、合意するを以て足ればなり。
二 故に此の種の契約は、不在者の間に於ても、有効に成立す。例へば手紙又は使者によるが如し。
三 而て此の点に於て、合意による債務関係は、他の債務関係と異るのみならず、他の債務関係に於ては、一人が責任者となり、一人は他人を責任者として拘束する点に於ても差異あり。例へば物による債務関係に付て見るに、与ふる者は債務者を拘束し、受取る者は責任者となる。言語による債務関係に付て見るに、要約者は債務者を拘束し、諾約者は責任者なり。文書による債務関係に付て見るに、記載者は債務者、記載を得たる人は、同人を債務者として拘束す。然るに合意による債務関係に付ては、善良及び正義に基きて、一方が他方に履行することを要するものに付て、各人が各人に対し責任者となる。然るに言語による債務関係に付ては、一は要約して債務者を拘束し、他は約して債務者となるなり。
第二十三章 売買に付て
吾人は先づ第一位に、売買に付て述ぶ可し。売買は各当事者が代価に付て合意するとき、直ちに成立す。蓋し予若し「予は汝にこれを百金にて売却す」と謂ひ、汝は其の代価に満足するときは、仮令未だ代価を勘定せず、手附も何等交付せられずとも、売買は直ちに成立すればなり。而て売主には売却訴権、買主には購買訴権を発生す。手附の為交付せられたる物は、売買成立の証拠証明にして、自身が成立〔要件〕なるには非ず。これは文書の作成なくして行はれたる売買に付てのことと吾人は考ふ。蓋し此の種のものに付ては、吾人の皇帝は何等新にし給ひし所なければなり。文書を用ひて行はれたるものに付ては、吾人は売買証書を、或は売主の自筆を以て作成するか、或は他人が代書し、売主が下書するに非ざれば、完成せずと謂ふ者なり。若し公証人によりて作成せらるるときには、下書が行はれて、完成が伴ひ、証書が部分より解放せらる【全部分が完成するの意】るに非ざれば、〔売買は完成せず〕。蓋し是等の中の何物かが欠くる間は、後悔が許され、買主又は売主は、何等の損害を受くることなく、契約を解約することを得ればなり。尤も手附として、何等かの物が与へられざる場合のこととす。蓋し売買が証書を用ひて行はるるにせよ、用ひずして行はるるにせよ、手附が為さるるとき、契約解約者が買主なるときは、手附を喪失し、売主なるときは、二倍額、即ち与へられたるもの、及び他の同一物を交付することを要す可く、而て仮令手附の交付に当りて、此のことを合意せざるときたりとも、尚然ればなり。代価は常に、売買に付て定めらるることを要す。蓋し代価なきときは、一般に売買は存在せざればなり。
一 然も代価は確定せることを要す。故に若し某の間に於て、チチウスが某の土地を評価したる価額にて、売却せらる可き旨の合意成りたるときは、古人の間に於ては、かかる売買が成立するか、或は無効なるかに付て、多大の争を惹起したり。然れども吾人の皇帝の決定行はれ、其の決定は「此の土地は、某が評価したる価額にて、汝に売らる可し」の如く合意せられたるときは、其の条件にて契約は成立し、其の結果、指名せられたる者自身例へばチチウスが、代価を定めたるときは、全然同人の評価に従ひて、代価も履行せらる可く、物も引渡さる可く、為に買主は購買訴権、売王は売却訴権を有して、売買は終了に赴く可き旨を規定したり。若し指定せられたるチチウスが、或は代価を定むることを欲せず、或は不可能なるときは(蓋し恐らく代金額の知識は、同人の手に負へざるものなりしならん)売買契約は無効たる可く、定められたる代価が存せざるが為、彼等【売主買主】はあたかも、両者の間に、売買に関して合意なかりしと同然たる可し。此のことを皇帝の勅法は、売買に付て定め給ひしも、貸借に付てこれを引用するも、失当には非ず。
二 又既に述べたるが如く、代価は定めらるること、及び確定的たることを要するのみならず、金銭に於ても存在せざる可からず。蓋し金銭外の其の他の物に於て、代価が存在することを得可きやは、争はるればなり。例へば〔金銭外の〕他の物に属する、奴隷又は土地又は衣服が、代価たり得るかに付ては、激論せられたればなり。而てサビーヌス及びカスシウスは、他の物に於ても、代価は成立することを得と考へ、而てこれ坊間にて「物の交換によりて、売買も亦成立し、而て此の種の売買は、より古きものなり」と伝へらるるものなり。而て彼等は詩人ホメーロスを援用す。彼は其の詩篇中の或る部分に於て、自己に葡萄酒を購ふ希臘軍隊を仮想し、次の如き詩句を以て、或る物の交換によりて、売買の行はるることを述ぶ。——「茲に於て乎長髪のアカイア人は、或る者は銅もて、或る者は光目映き鉄もて、或る者は牛皮もて、或る者は牛そのものもて、更に或る者は奴隷もて、酒を買ひたり(οἰνίζοντο)」——と。「οἰνίζοντο」とは「酒を購ひたり」の謂なり。即ち彼等が葡萄酒を購ふを仮想して、代価として、或は銅、或は鉄、或は牛皮、或は牛、或は奴隷が与へらるる旨を述ぶるなり。プロクリアーニーは、物の交換と売買とは別物なりと謂ひて、反対説を唱へたり。而て謂ふ、物が交換せられたるときに、何が売却せられ、何が代価として与へられたるか、事情はよく決定せられざる可し、蓋し双方は売りもし、代価の名目を以て与へもしたりとは、理がこれを許さざればなりと。而て交換は売買とは別個独特の種類の契約なりと謂へるプロクルスの学説は、プロクルス自身も亦、他のホメーロスの句を自己の弁護に供し、以てこれに関し妥当なる理由を援用するを以て、当然勢を占めたり。句は下の如し。——「其の時クロニデース、ゼウスは、チデイデース、ヂオメーデースと、金の武器を銅の武器と、百頭の値ある武器を九頭の価ある武器と交換して、グラウコスを魂消げさせぬ」——。蓋し見よ、此処には、為されたるものは明かに「ἄμείψις(交換)」と呼ばれ、「πρᾶσις(売買)」とは呼ばれざるなり。これ古の皇帝も亦承認し、学説彙纂の中にも、広く採用せらる。
三 吾人は上述したる所に於て、各当事者の意に合するときは、無証書の売買は、代価に関する定めと額よりして、成立す可き旨を述べたり。而て上述の成立の後は、仮令未だ目的物が、買主に引渡されざるときと雖も、売買の目的物の危険は、直ちに買主に帰す。故に売却せられたる物が奴隷にして、それが死亡し、或は身体の一部、足又は手又は眼が傷けられ、或は家屋にして、全部又は一部が火災にて焼失し、或は土地が河勢によりて、全部又は一部を喪失し、或は洪水により、或は樹が暴風の為倒れて、土地が従前よりは遥かに、減少又は悪化したるときは、是等総てに関する損害は、買主に帰す。仮令目的物の占有を把まずとも、固より代価の弁済を強制せらる可し。蓋し若し一般に、売主の悪意又は過失なくして、何事かが目的物に発生するときは、売主は損害を受くることなきを知る可し。偶然の事情に基く売買の目的物の減少又は滅失が、買主にかかるが如く、売買の目的物に、何等かの利得が附加せらるるときも、買主に利す可し。故に若し寄洲作用によりて、土地が拡大せるときは(蓋し恐らく長さ百なりしに、売買の成立後、寄洲作用によりて、他の長さ百がそれに附加せられしならん)、買主は利得を享有する可し。蓋し悪化による危険をも負担する者が、利得を得ることを要すればなり。
三イ 若し引渡前に、売却せられたる奴隷が逃亡し、或は何者かによりて盗まれ、売主のこれに対する悪意又は過失が、証明せられざるときは、売主はこれに基く損害を賠償することを要するやを吟味す可し。而てこれは区別することを要す。若し売主が売却せられたる奴隷の保管を、引渡迄自己に引受けたるときは、custodia【法文には此の文字があり】〔の責任〕を負ふ可く(custodiaとは極めて厳重且異常の監視なり)、同人はそれより生じたる損害を認む可し。若し何等自己に引受けざりしときは、損害を受くることなかる可し。他の生物、例へば馬、驢馬、駱駝、其の他これに類似のもの、及び他の物に付ても、吾人は同一と解す。而て売主は、未だ目的物の引渡なきを以て、売主自身が未だ所有者なるの故に、売却せられたる目的物の恢復に対する物的訴権及び弁済訴権を、買主に譲渡す可き義務を負ふのみならず、盗人に対する窃盗訴権、売却せられたる物を毀損したる者に対するアクヰーリア訴権をも譲渡す可し。
四 売買は単純にも、又は条件附にても、契約せらるることを得。条件附にとは、例へば「奴隷スチクスは、若し一ヶ月の中に汝の意に合したるときは、汝に十金を以て売却せらる可し」の如し。
五 神聖物、又は宗教物、又は公物例へば広場又はバシリカは、知りて購ふときは無効なり。即ち契約を理由として、何等の訴権を有することなかる可し。若し売主に、あたかも私権に属するかの如くに欺かれて、これを買ひたるときは、売却せられたる物を、自己に有することを得ざるを以て、唯利害関係の請求に付て、購買訴権を有す可し。奴隷の代りに、其自由人を購ひたるときも、同一たる可し。
第二十四章 貸借に付て
貸借は売買に類似し、且同一の法則によりて発生す。蓋し売買は、代価が各当事者の意に合するときに、成立するが如く、貸借も亦、報酬が当事者の意に合するときに、成立するものと解せらるればなり。而て同所に於て、代価が確定的にして、且金銭に於て存することを要する旨を述べたるが如く、報酬も亦確定的にして、且金銭に於て存在することを要す。而て貸主には貸主訴権、借主には借主訴権が帰属し、これは前者には報酬を請求せんが為、後者には貸されたる物を、自己に取得せんが為に備はる。
一 而て代金の額が第三者の決定に任ぜらるるとき、例へば「チチウスが定めたる額にて、汝に売却せらる可し」の如き場合に、吾人が売買に付て説きたる所——其処に於ては、吾人は契約の成立に区別を設けたる吾人の至聖の皇帝の勅法を、参照したり——と同一のものが、報酬の額が第三者の判断に任ぜらるるときにも、前に吾人が教へたる所に従ひて、貸借に付ても説かる可し。人若し直ちに報酬を定むることを何等せず、唯後日両当事者の間にて合意したるものを、与ふることのみを許して、衣服を洗濯の為洗濯屋に、或は修繕の為裁縫師に与へたるときは、かかるものは貸借に非ずして、貸借外の他の契約なり。それに対しては、actio praescriptis verbisが附与せらる。而て何人も、これが皇帝の決定によりて裁断せられたるものとは、考ふること勿れ。蓋し勅法の考ふる場合は、別なればなり。蓋し勅法は「チチウスが定めたる額にて売却せらる可し」なるも、此処は「各当事者の意に合したる額にて汝に貸さる可し」なればなり。
二 而て物の交換が売買なりやが疑問となれるが如く、同じく貸借に付ても、予が使用又は収益の為、汝に物を交付したるに、交互的に他の何物かが使用又は収益の為、汝より予に与へられたるときは、果して貸借なりやが争はれて、同一事が売買と貸借を廻りて争はれたり。而て通説は貸借には非ず、一種独特の契約なりとなすに至れり。例へば次の設例に於けるが如し。某二人は隣人にして、其の各は一頭宛牛を有し、双方共一頭の牛を有するに過ぎざるが為、其の土地を耕すことを得ざりき。若し彼等の間に、〔互に〕一方は他方に十日間、其の牛を貸与して、借主の土地を耕さしむ可き旨の合意成り、借主のもとにて其の牛が失はれたるときは、此の場合、金銭に於て存する確定的報酬が存せざるの故を以て、かかるものは貸借にも非ず、又使用貸借にも非ず。蓋し使用貸借は無償たることを要するに、此の場合には見よ、貸主は反対に自己が受取ることによる利得を有し、或は其の希望あればなり。否吾人は此の場合には、喪失者に対抗するactio praescriptis verbisを定むる者なり。
三 売買と貸借の間には、或る場合には、為されたるものが売買なりや、貸借なりや曖昧なるが如き程の或る共通点あり。これは極めて類似せる場合に発生す。例へば永久的に或る者に、収益の為土地が引渡され、土地に対する報酬又は収入が交付せらるる限り、何人も借主又は其の相続人、或は借主又は其の相続人より、該土地の売却贈与を受け、又は嫁資の名目を以て与へられ、或は其の他の方法を以てする処分を受けたる者より、取り去ることなき様にせられたるときの如し。然れどもかかる契約は、古人の間に於て曖昧となり、或る者によりては貸借、或る者によりては売買と解せられたるを以て(相続人に移転し、種々の方法によりて譲渡せらるるを以て売買、毎年〔報酬が〕支払はるるを以て貸借なり)、至聖のゼーノンの勅法制定せられ、該勅法は、全然貸借に傾けるにも、売買に傾けるにも非ざる、独自の限界を以て成立せる、独特の性質をこれに考案して、これを「エンフィテウシス」と呼びたり。而て若し契約者の間に於て、何物かが合意せられたるときは、かかる性質が契約に存せしが如く、合意は効力を有す可し。蓋し合意は契約に対する性質たる可ければなり【合意より契約の性質定まるの意】若し物の消滅に付き、何等の合意なきときは、永借物全部の消滅が起れる場合には、所有者即ち永貸人に損害は帰属し、若し部分的なるときは、永借人が損害を認む可し。これ実際に行はれ、且国内の制度なり。
四 同じく次のことも、曖昧の事項に属したり。予某金工に例へば十金を与へ、該金工が自己の材料を用ひて、一定量と一定形態の金の指輪を、予に作る可きことを合意したり。かかるものが売買なるか、貸借なるかが争はる。而てカスシウスは、かかるものは同時に売買にして、且貸借なりと謂ふ。其の結果予が金の材料を、使用に堪えざるものとして苦情を為すときは、購買訴権を提起す可く、若し不出来のものとして、労作に苦情を為すときは、貸主訴権を有することとなる。然れどもむしろこれは売買なりとするを以て通説とす。蓋し労作は附属事項に属すればなり。然れども若し労作に対し、労銀を定めて、予が予の金を金工に与へたるときは、かかるものが貸借なることは疑なし。
五 借主は貸借の定めに従ひて、即ち契約者間の意思に従ひて、総てのものを行ふことを要す。若し何物かが合意の中に脱洩せられたるときは、善良及び正義に従ひて、これを形成することを要す。予若し某に衣服、又は土地、又は生物を貸与し、更にこれが使用の対価として、報酬として定額の金が予に与へられ、或は又与へらる可きことが約せらるるときは、受取人【借主】はこれが管理に付ては、極めて注意深き者が、自己の物に施すが如き程度の注意を負ふ。蓋し〔かかる注意〕を履行し、而て偶然の事情によりて、借用物が滅失するときは、物の滅失を理由としては、拘束せらるることなければなり。
六 予若し某に五年間、予の土地を賃貸し、第二年恐らくは第三年にして、借主が死亡するときは、同人の相続人は、五年の終了迄、貸借を代りて承継す。
第二十五章 組合に付て
売買及び貸借の後には、組合に付ても詳言することを要す。これは或る者の間に於て、或は全財産の組合として——これを希臘人は、適当にκοινοπραξίαと呼ぶ——或は種類を問はず、一個の商の組合、例へば奴隷の売買、油又は葡萄酒又は穀物の売買に対して成立す。
一 而て組合員の各自が、利得又は損害の幾何の割合を認むるかに付き、何等合意せざるときは、同一の割合にて、利得も損失も認む可し。若し割合が定められたるときは、合意したる所は遵守せらるることを要す。蓋し若し二人が相互の間に於て、一は三分の二の利得及び損失を認む可く、他は三分の一と合意したるときは、其の約束が有効なることは疑なければなり。
二 次の如き約束に付て争はれたり。即ち若しチチウス及びセイウスが、相互の間に於て、チチウスが三分の二の利得を取得し、三分の一に付て損失を受け、セイウスは三分の二に付て損失を受け、利得は三分の一を負担す可き旨を約束するときは、合意は有効なるか。クヰーンツス、ムーキウスは、かかる合意は組合の性質に反し、然るが故に約束は効力なしと謂ふに反し、セルヰウス、スルピキウス——氏の学説はむしろ通説となれり——は、或る組合員の組合に対する労務は、彼等が多額に利得し、彼等がより大なる利得を以て、組合に加入することを以て妥当とする程、貴重なることは屡々なるの故を以て、反対説を唱ふ。蓋し一が金銭を負担し、他が負担せずして、儲けたる利得は相互に共有たることとしても、組合が成立することを得るは疑なければなり。何故となれば、組合員の一人の労務は、金銭の負担と同一たり得ること屡々なればなり。而てクヰーンツス、ムーキウスに反対のセルウヰウスの学説が、勢力を得たるは、組合員の或る者が、利得の割前を受くるも、損失には服せざることを、組合員が約束することを得ることが、学説の一致する所に属することとなりたる程なり。此のことは、或る部分に於ては利得、或る部分に於ては損失が発生したるときに、compensatio(又は相殺)が行はれて、残余のみが利得と解せらるる様に、考ふることを要す。例へば奴隷と衣服の商を為したり。衣服の商に於ては、百金の損失発生し、奴隷の取引に於ては、三百金の利得が取得せられたり。先づ損失の百金が控除せられ、為に三百金の利得より、其の損失が填補せられ、二百金が為されたる約束に従ひて、組合員の間に分割せらる可し。故にこれよりして、同じ割合にて利得と損失とが組合に発生するか、或は利得のみが発生するときは、利得には与るも、損失には服せざる可きことを述ぶる約束に基きては、組合員は何等利得することなきも、若し単に損失のみが発生するときは、合意に基く利益が現はるることが、明かにせらる。蓋し彼等が各千金を負担し、上記の約束を行ひ、取引に於て二百金の損失のみが発生し、利得は全然なく、其の後組合が解消せられたるときは、一は負担したる千金、他は八百を受く可ければなり。
三 若し発生す可きもの【利得損失】の何れか一のみに、割合が明言せられたるときは、明示せられたるものは、又黙せられたるものに関する規則となる。これ亦学説の一致する所に属す。例へば一は発生したる利得の三分の二を、他は三分の一を取得す可き旨の約束が為され、損失に付ては何等述ぶる所なかりしか、或は又其の反対のときは、述べられざりし分は、述べられたる分と、同一にせらる可し。
四 組合は当事者が同一の意思を有する間存続す。若し組合員の一人が脱退するときは、其の後に発生す可きものに関しては、組合は解消せらる。人若し或る儲の利得を、自己のみが独占せんが為、悪意を以て組合より脱退したるときは、此の利得は共有となる可し。人若し利得を予見せずして、脱退したるときは、同人のみが利得す可し。例へば甲と乙は総財産の組合員なりき。偶々チチウスが甲を相続人に遺して死亡し、且セイウスの財産も亦同一の甲に齎されたり。或る者甲に赴きて、チチウスの相続財産に関して通知したるも、セイウスの相続財産は自己に帰属するやは、甲の知る所には非ざりき。甲は組合の解消後は、取得者のみの有なることを知り、チチウスの相続財産を独占せんと欲して、相続財産を独占せんが為、故意に組合より脱退したり。法律はチチウスの相続財産よりする儲けの利得を、共有にすることを強制して、同人の悪意を処罰す。セイウスの相続財産は、後日これを知りて受けたるときは、単独にて保有す可し。蓋しこれを取得す可き希望を以て、組合を解消したるには非ざればなり。蓋しそれが自己に齎されたることを知らざるときに、如何にして可能ならんや。然るに乙に対して為された組合の脱退後、乙に何物かが取得せらるるときは、今の利得の原因が仮令脱退より以前なりとも、彼の悪意は何等証明せられざるを以て、彼のみが取得す可し。
五 組合は此の外、組合員の死亡によりて解消せらる。蓋し組合を締結する者は、知りたる人を自己に選択し、予の組合員の相続人は、常に必ずしも組合に付き予に適当なる者なる訳には非ざればなり。更に若し多数の組合員が結合する場合たりとも、一人の死亡によりて、全員間の組合は解消せらる。残存者が死亡者よりも多数なるときも尚然り。蓋し五人或は又六人が組合を締結するとき、二人が難船にて、同時に死亡したるときは如何。蓋し死亡者によりて、組合が有用且推挙す可き組合たることは、時には存すればなり。但し組合締結に当り、一人が死亡するも、残存者によりて組合が保存せらる可き、別段の合意なき場合のこととす。
六 組合は締結の目的たるものが、完成せしときも解消せらる。蓋し恐らく奴隷の商に関して成立せるとき、かかる商が結了するに至りたるときは、組合も亦同時に廃止せらるればなり。
七 組合員の一人の官没も亦、組合を解消す。但し組合員の総財産が、官没を受けたるときに限る。蓋し官没を受けたる者の財産へ、他の者即ち国庫が代つて入るときは、死亡に類似したるものが移入せられ、為に組合が解消せらるるが為なり。若し為されたる官没が部分的なるときは、組合は依然として存続す。
八 若し組合員が、多教の公的又は私的債務の負担を負ひ、其の資産を離れ、其の財産が、売却せらるるときは、組合は解消せらる。然れども若し財産を奪はれたる後、同一の意思を保持するときは、組合は新に開始するものと観ぜらる。
九 組合員が組合員に対し、若し悪意を以て、組合に損害を加へたる場合には、それのみの為、組合訴権——組合員は相互に対し此の訴権を有す——の拘束を受くること、あたかも吾人が、自己のもとに他人の物が寄託せらるることを許したる者が、悪意によりて寄託訴権の拘束を受くる旨を説きたると同じきか、或はculpaの名目を以て、即ち過失及び不注意の名目を以て、拘束を受くるかは争点に属す。然れどもculpaの為にも、同人が拘束せらるることは、一様に認められたり。然れどもculpaは、極めて厳格なる注意に関することなし。蓋し組合員は、自己の事務に施すを通常とするものと同等の注意を、組合事務に示すを以て足ればなり。蓋し余り不注意なる者を、自己に選択したる者は、自ら自己に対する損害の原因者となれる者として、自己の愚を責む可ければなり。
第二十六章 委任について
合意による契約のもとに収めらるるものの中、尚委任が吾人に取残さる。これは五個の方法によりて成立す。蓋し予のみの為、或は予と汝の為、或は第三者のみの為、或は予と第三者の為、或は汝と第三者の為に、予は汝に委任すればなり。蓋し若し汝の為のみに、委任が行はるるときは、実行せられたるものは無用にして、合意による債務関係も、委任訴権も生まるることなければなり。
一 委任者のみの為、委任が行はるるは、例へば予の財産を管理し、或は某なる土地を予の為に購入し、或は予の保証を為す様、予が汝に委任したるときの如し。
二 予と汝の為の委任は、利息附にて、チチウスに金を貸す可きことを、汝に委任したるに、其のチチウスは、其の金を吾人の利用の為に、消費せんとする者なる場合の如し。蓋し為されたるものは、利息の受領によりて汝をも利し、予をも亦、予の利用の為に金銭が消費せらるるを以て、利するが為なり。或は又偶々甲が汝より貸金を受け、予が保証するとき、予を訴えんとする汝に対し、予の危険に於て、主たる債務者甲に対し、訴を為す可き旨を委任するが如し。蓋し見よ、此の場合には、予も今の訴訟を避けて利益を得、汝も主たる債務者を訴えて後、債務が充たされざるときは、予に立戻ることを得て、利益を得ればなり。【蓋し保証は担保権なくして行はれ、委任は担保権附にて行はれ、其の結果委任が何等かの利益を齎す場合を想像す可し】【括弧内は改竄と考へらる】或は又予汝に百金の債務あり、汝は予を訴訟に召喚せんと欲し、更に予は予の債務者を汝に指図し、次に予は汝に対し、予の危険を以て、彼【予の債務者】に要約す可き旨を委任したるときの如し。〔予の危険を以てと謂ひたるは〕蓋し恐らく汝は、予の債務者に要約して、同人の無資力故に、同人よりは何物も取得することを得ず、予に立帰ることも、更改によりて予に発生せる解放に基き、不可能にして、債権を喪失することなきやを危惧したればなり。蓋し見よ、此の場合には委任が各人を利するを。予を利すとは、差当り現在負担を負ふことなきが為なり。汝を利すとは、予の債務者をも問答口約に基きて責任者として保持し、且予に対しても、委任に基きて訴ふ可ければなり。而て以前には、汝は一人を責任者として拘束せしも、今や問答口約に基く彼と、委任に基く予との二人を有す。
三 第三者の為のみの委任は、チチウスの事務を管理し、或はチチウスの為に土地を購ひ、或はチチウスの保証を為す様、予が汝に委任するときに発生す。
四 予と第三者の為の委任は、予とチチウスの共同事務を管理し、或は予とチチウスの為に土地を購ひ、或は予とチチウスの保証を為す様、若し予が汝に委任するときに発生す。
五 汝と第三者の為に、予が委任するは、チチウスが金銭を必要とするとき、同人【チチウス】に利息附消費貸借を為す可き様、予が汝に委任するときなり。蓋し此の場合には、汝も利息故に利益を得、彼も亦自己の利用圏内にて為されたるが故に、利益を得ればなり。若し彼の為無利息にて、消費貸借を為す様、予が汝に委任したるときは、汝は何等利益を得ざれば、汝の為に委任が為さるるには非ず。
六 汝の為のみの委任は、汝の金を消費貸借に充つるよりは、土地の購入に充つるか、或は反対に、土地を購入するよりは、消費貸借を為す様、予が汝に委任するときに発生す。かかる委任は、委任よりはむしろ助言なり。これが為には、何等の債務を発生せず。蓋し何人も助言に基きては、委任訴権の拘束を受くることなければなり。仮令助言を受けたる者に、何等の利益なくとも尚然り。何人かによりて、助言の中にて己が為に開陳せられたるものが、果して有用なるか、自己の判断に従ひて吟味す可き自由なる権限が、各人に備はるが為なり。故に遊金を有せる汝に為し、何物かを購ひ、或はこれを消費貸借に充つ可き旨を、予が慫慂するも、仮令実行せられたるもの、例へば購入が、汝に利する所なしと雖も——恐らくは奴隷にして、其の奴隷が死亡又は逃亡し、或は無資力者に消費貸借を為したるが為ならん——予は汝の委任訴権に拘束せらるることなかる可し。而て其の然るは、チチウスに対し、利息附にて金を貸す様、汝に委任せし予は、果して委任訴権に拘束せらるるやに付き、古人の間に疑問起り、或る者はこれを以て助言とし、前に述べたる所に従ひ、債務を発生せずと謂ひたる程なり。然れども予が委任訴権に拘束せらると謂へるサビーヌスの学説が、むしろ勢力を得たり。何故となれば、予はチチウスなる、一定の人間を指示したるが故に、これが為、或る程度保証人に類似の者として、拘束せらるればなり。蓋し若し何等の指定なく、「汝の金を貸与せよ」と謂ふときは、既に述べたるが如く、委任は債務を発生するものに非ざればなり。予若し一定の人間を指示したるときは、現に行はるる慣習に従ひて、予は委任訴権の責任者となる可し。
七 助言に於て為されたる委任が、委任訴権を発生せざるが如く、善良なる風俗違反の委任も亦、然ることなし。例へば甲の財産を盗み、或は同人に損害を加へ、又は侮辱する様、予が汝に委任したるが如し。蓋し仮令予の委任によりて説伏せられし汝が、不法行為に基く刑罰を受くとも、尚均しく汝は予に対し、委任訴権を有せざればなり。
八 委任を引受けたる者は、委任の定めを越ゆる可からず。例へば百金迄にて、予の為に某なる土地を購ひ、或は百金迄にて、チチウスの保証を為す様、予汝に委任したり。汝はそれ以上の額にて、土地を購はざること、其れ以上に保証せざることを要す。蓋し吾人の述べたる程度を越ゆるときは、汝は予に対し、委任訴権を有せざること、サビーヌス及びカスシウスが、仮令超過額を蔑視して、百金迄、即ち予が汝に委任したる額迄、予に対して委任訴権を提起せんと欲するも、訴訟の結果は有用ならざる可きことを述ぶる程なればなり。然れどもプロクリアーニーは、汝が百金額迄は、適当に訴え得可しと説く。此の学説はむしろ良し。若し少額にて、例へば八十金にて購ひたるときは、固より汝は予に対し、委任訴権を有す可し。百金を以て、自己の為、土地を購ふ可き委任を為したる者は、固より若し可能ならば、少額にて購ふ可きことを、委任したるものと観ぜらるればなり。蓋し小は大に包含せらるればなり。
九 委任は適当に行はれたるも、若し事物の状態原状にある間に(re integra)、其の撤回が為されたるときは、解消せらる。例へば予某に、予の為奴隷を購ふ可きことを委任し、購入開始前に、委任を撤回したり。これ「事物の状態原状にある間は」なり。
一〇 同じく事物の状態原状にある間は、委任者又は受任者に発生せる死亡は、委任を解消す。然れども自然上の権利に基き、時には委任訴権が附与せらるること通説となれり。蓋し某の土地に赴かんとする汝に対し、馬の購入を委任したるときは如何。汝は委任を受けて、出発したり。購入を開始する以前に、予偶々死亡したり。汝は未だ生存すと信じ、委任に満足を与へて、馬を購入したり。帰還して予が死亡したることを知れり。事物の状態原状にある間に、汝に委任したる予の死亡が発生したるが故に、汝は予の相続人に対して、委任訴権を提起することを得ず。然れども事情を知らざる汝が、損害を受くるは失当なれば、理由ある不知が、汝に損害を齎すことなからしめんが為、人道に基き、汝が予の相続人に対し、委任訴権を保有す可きこと通説となれり。而てこれは次の如き場合を模倣して行はる。会計人とは主人の金を貸すことを通常とする奴隷なり。同人消費貸借を為すも、債権を取得することを得ず。蓋し奴隷なるに、如何にして可能ならんや。消費貸借に基く訴権は、これを其の主人の為に取得し、消費貸借を受けたる者は、或は主人に弁済するも、債権より解放せられ(蓋し彼は自己に対し訴権を有する者に、弁済したればなり)、或は奴隷に弁済するも亦、拘束より放免せらる。蓋しこれをば主人の意思によりて、与へたればなり。蓋し奴隷に消費貸借を為すことを許したる者は、自身消費貸借を受けたる者に、同一の会計人に弁済を為す可き権限を与へたるものと観ぜらるればなり。然れどもこれは、主人が奴隷に対して、同一の意思を持続する間限りのことなり。蓋しかかる意思を失ひたるときは、消費貸借を受けたる者は、適当に同人に対して弁済することを得ざればなり。然らば会計人を主人が解放し、次で消費貸借を受けたる者が、同人に対して金を弁済したるときは如何。債務より解放せらる可きか。〔法律の〕厳正に従へば、金の持主が欲する者と異る者に、弁済したるを以て、汝は解放せらるることを得ず。蓋し同人を解放したるを以て、同人に対するかかる意思【弁済を許す意思】なきは、明かなればなり。然れども理由ある不知が、弁済者に損害を齎すは失当なれば、同人が自然上の権利によりて、債務より放免せらる可きこと、通説となりたり。即ち会計人に関しては、理由ある不知が〔法律の〕厳正に反抗して、保護を与へたるが如く、同じく事物の状態原状にある間に、委任者が死亡するによりて、委任が解消するときも、同一の理由に基き、即ち理由ある不知に基き、委任訴権は提起せらる可し。
一一 予に対して為されたる委任は、これを受けざる可き権限予に備はる。然れども引受けたるものは、或はこれを完成することを要するか、或は出来得る限り迅速に辞任し、以て予に委任したる者が、或は自己自身、或は第三者によりて、同一物を完成する〔ことを得る〕様にすることを要す。蓋し事物は原状に保存せられ、以て同人【委任者】が従前とは異る所なく、損害を受くることなくして完成することを得るが如くにして、辞任するに非ざれば、予は委任訴権に拘束せらるればなり。蓋し次の如き場合は如何。予若し某の場所に出立せんとし、同じく汝の友人たるチチウスも出立せんと欲したり。汝は予に、奴隷又は其の他の或る物を購入す可き旨を委任したり。予若し委任を引受けたるときは、チチウスが未だ出発せず、従つて同人に購買を委任することを得る間に限り、予は何等損害を被ることなくして、辞任す可し。若し同人が出発せしときに、予が辞任するときは、委任訴権の責任者たる可し。蓋し委任者は、チチウスが出発したるを以て、未だ第三者によりて、委任を完成することを得るには非ざればなり。然れども若し、予に辞任を許さず、又は辞任を許すも遅延せしむる、理由ある原因が存するときは、予は寛恕に値す可し。蓋し公用又は其の他の或る必要なる理由が、委任を完成することを許さざるときは如何と謂ふ可ければなり。
一二 委任は期限附にても、為さるることを得。例へば「予は汝に二ヶ年後に、これを実行す可きことを委任す」の如し。又条件附にても可能なり。例へば「予は汝に、若し船がアヂアより来れるときは、これを実行す可きことを委任す」の如し。
一三 最後として、委任は無償たることを要することを、知らざる可からず。蓋し然らざるときは、他の契約に陥ればなり。蓋し報酬が定めらるるときは、貸借たることを開始すればなり。蓋し汝が報酬なくして、何物かを為すことを引受くる場合には、委任又は寄託訴権が発生し、報酬が介入する場合には、貸借が契約せらるることを、汝は一般に知ることを要すればなり。故に洗濯屋に洗濯の為、漂白人に漂白の為、或は裁縫師に裁縫の為、衣服を交付するときは、何等報酬が定められず、或は約せらるることなくして、洗濯屋又は裁縫師がこれを無料にて行ふことを約する場合には、これが回復には今や委任訴権が帰属す。
第二十七章 契約より発生するものに準ずる債務関係に付て
契約に起源を有する債務関係に付て述べたる吾人は、尚本来契約よりは発生せずして、然も不法行為より成立を受くるに非ざれば、あたかも契約より生まれたるものと観ぜらるる債務闘係に付て述ぶ可し。
一 若し予の不在中に某が予の事務を管理するときは、吾人の間に、互に訴権を発生し、事務の主たる予には、事務管理直接訴権、管理者には反対訴権が発生す。これが本来或る契約より生まれたるに非ざることは明かなり。蓋し委任なくして、他人の事務の管理に、自己を引入れたる場合に、これが発生すること明かなればなり。此の原因に基きて、管理せられたる事務の主は、知らずとも拘束せらる。然るに契約に基きては、何人も不知なる者は、拘束せらるることなし。これは突然且至急の出発を余儀なくされて、何人かに己が事務の管理を委任することを得ずして、出発したる不在者の利益の為に、発案せられたるものなり。利益は事務が何等注意を加へられざるが侭に、放置せられざることよりして発生す。蓋し若し他人の事務の管理に付き、支出したるものに付て、何等の訴権を有せざるときは、何人もこれ【他人の事務】に留意する者なかる可ければなり。而て他人の事務を有用に管理したる者は、支出したるものに付て、事務の主を債務者に保持するが如く、反対に管理者自身も亦、事務に対して、極めて厳格旦異常の注意をも施すことを要求せられて、管理の計算を施す可き拘束を受く。蓋し事務管理訴権の拘束を受けざらんが為には、自己の事務に付て為すことを通常とするが如き注意を、他人の財産に付て示すを以ては足らざればなり。尤も他のより注意深き者が、より有為に事務を管理せんとする場合に限る。蓋し其の場合には、管理者自身の注意によらず、他人の注意によりて、管理は決定せらるればなり。
二 後見訴権の拘束を受くる後見人も亦、契約に基きて、本来債務者となるものとは考へらるることなし。蓋し如何なる契約が、後見人と未成熟者の間に契約せられんや。未成熟者が幼児なるときは特に然り。然れども此の場合に、後見人は不法行為に基きて、拘束せらるるに非ざれば(蓋し未成熟者を慮りて発案せられたる後見は、如何なる不法行為たる可けんや)、あたかも契約に基きて拘束せらるるが如く観ぜらる。而て此の場合にも、各の側より訴権が発生す。蓋し未成熟者が後見人を、後見訴権への責任者として保持するのみならず、反対に、後見人が未成熟者の財産に関し、何物かを支出し、或は同人に代りて債務者となり、或は自己の財産を、未成熟者の貸主に担保に供したるときは、此の者【未成熟者】も後見人に対し、後見反対訴権の責任者となればなり。
三 若し組合なくして、或る者の間に、共有物が存する場合にも、同じく準契約のもとに収めらる。例へば同時に二人の某に、同一物が遺贈せられ、或は贈与せられたるが為なる場合の如し。此の場合に於ても亦、一人のみがそれよりして果実を取得し、或は又或る者が必要費を共有物に施したるの故を以て、訴ふるときは、一方は他方に対し、共有物分割の訴訟に拘束せらる。蓋し此の訴権は、本来契約より発生するものとは観ぜられざればなり。蓋し如何なる契約が、相互の間に締結せられ得んや。否一人は不法行為に基き、拘束せらるるに非ざるを以て、これは準契約と観ぜらる。
四 又某共同相続人にして、其の後共有物分割の訴訟に付て述べたる原因に基きて、遺産分割の訴訟を提起する場合も亦同じ。
五 又人若し死亡に当りて、予を相続人に指定し、又予より履行せらる可きものとして、他の物を遺贈したるときは、予は受遺者に対し、遺されたる物故に、遺言訴権に拘束せらる可し。此の遺言訴権は、契約より生まるることなし。蓋し受遺者が何人と契約を為したるものと観ぜられんや。受遺者の知らざる間に、彼遺言者がこれを遺したるものなれば、遺言者とも契約したるに非ず。又相続人の意に反して、受遺者に遺されたるものなれば、相続人と契約したるにも非ず。否実行せられたるものは、不法行為に非ざれば、準契約に基きて、所有者は債務者となるものと観ぜらる。
六 同じく人若し錯誤によりて、予に負はれざるものを、予に弁済するときは、契約に基くが如くに、拘束せらるるものと観ぜらる。蓋し本来契約に基きて、債務者となるに非ざるは、人若し厳格なる論理に接近するときは、前に於て吾人が述べたるが如く、むしろ負はれたるものと考へられたるものを、解消せしむるによりて債務者たり、成立せしむるによりて債務者たるに非ざる程なればなり。蓋し債務を弁済する意思を以て与ふる者は、存在すと考へられたる債務を、成立せしめんが為よりは、弁済によりて解消する目的を以て、与ふるものなればなり。然れども受領者は、消費貸借の借主と同じく、condictioの被拘束者となる。
七 与へたる総ての場合に付て、錯誤による弁済者に、取戻の権限が与へらるるには非ず。蓋し古人のもとに於ては、否認に基きて、実際に負はるるものが倍額にせらるるが如き場合と同一場合には、債務なくして弁済せられたるものは、取戻を許さるることなければなり。例へばアクヰーリア法に基くが如し。蓋し人若し希望して予に損害を加ふるときは、予は彼に対して、アクヰーリア訴権を有す。若し予に損害を賠償す可き旨要求せられて、債務を否認し、次に有責を認定せらるるときは倍額を弁済す。然れども若し損害を加へざるに、同人は予に損害を加へたりと誤信して、債務なきに拘はらず、弁済するときは、与へたるものを取戻すことなし。確定的に、人の如何を問はず或る者に、宣告式によりて、遺されたる遺贈に付ても、古人は同一と謂へり。確定的遺贈とは、「相続人よ、予は汝に、某に百金を与ふ可き義務を負はしむ」と謂ふときなり。蓋し「箱の中に存する物を、与ふる義務を汝に負はしむ」と謂ふときは、額が明かならざるを以て、遺贈は不確定なればなり。故に宣告式にて遺贈せられたる確定的のものに付て、相続人が債務を否認し、次で有責を認定せられたるときは、二倍額を弁済し、又債務を負はざるも、あたかも債務ありと誤信して、与へたるときは、取戻すことを得ざりき。吾人の皇帝の勅法は、遺贈及び信託遺贈に、一個の性質を定め給ひしを以て、否認に基く倍大も、遺贈のみならず、信託遺贈にも拡張せらる可きことを希望し、総ての受遺者には関せず、唯宗教的又は敬虔的観念を以て、吾人が尊敬する極めて神聖なる教会、又は殊勝なる場所に遺されたる遺贈及び信託遺贈に関することを希望し給へり。若し殊勝なる場所に、何等遺贈又は信託遺贈が遺されざるに、予遺されたるものと考へて弁済するも、相続人がかかるものを債務に負ひ、次に否認するときは、二倍額の弁済に陥るが故を以て、取戻は静止す。
第二十八章 如何なる者によりて債権は吾人に取得せらるるか
吾人は契約より発生する債務関係、又は準契約より発生する債務関係に付て述べたり。今や債権自体は、吾人自身によりて、吾人に取得せらるるのみならず、吾人の権力内にある者、例へば吾人の奴隷又は権力に服する息によりても亦、取得せらるることを述ぶることを要す。然れども奴隷によりて、吾人に取得せられたるものは、総て吾人のものとなるも、権力に服従する息によりて、債権の結果取得せられたるものは、訴訟によりて利得として取得せられたるものの使用権【むしろ用益権】は父のもとに、所有権は子のもとに保存せらる可しと、吾人の皇帝が決定せる、物の所有権と使用権【むしろ用益権】〔の分配〕を模倣して分配せらる。これ固より父が帝の新規且神聖なる勅法の規定に従ひて、訴訟を提起したる場合なり。
一 吾人が善意に占有する自由人及び他人の奴隷は、吾人の為に債権を取得す。但し二個の原因のみに基く場合、即ち彼の労務によりて何物かを得るか、或は又吾人の物によりて吾人に取得するかの場合に限る。
二 又吾人が用益権又は使用権を有する奴隷によりても亦、同じく二個の同一原因に基きて、吾人に取得が行はる。然れども吾人が使用権を有する奴隷の労務に基くものは、奴隷自身が自己自身を貸与するが如き場合に非ざれば、吾人に収得せらるることなきを汝は尚知ることを要す。
三 共有奴隷は主人権の割合に従ひて、即ち所有者の各人によりて、所有せらるる割合に従ひて、所有者の為に所得す。固より、所有者の一人のみを指名して、彼の為要約するとき、例へば「汝は予の所有者チチウスに与ふるか」の如き場合には、該チチウスのみの名を示して、何物かを引渡によりて取得したる場合と同じく、同人のみに取得するは、明白なることなり。若し所有者の一人の命令に基きて、奴隷が要約し、要約内には名を示さずして行ひたるときは、これに付て古人のもとに、多大の疑問が発生したり。然れども吾人の至聖の皇帝の決定行はれ、命令者のみに取得せらる可き旨を宣言したり。命令は名の指示と同一の効力を有す可きことに付て、上にも述べたるが如し。
第二十九章 債務関係は如何にして廃止せらるるか
債務関係の成立を述べたる吾人は、其の解消に付ても述ぶ可し。蓋し或る方法によりて成立せるものは、又或る方法によりて解消せらるればなり。第一に総ての債務関係は、負はれたるもの自体が弁済せらるるとき、弁済によりて廃止せらる。例へば金銭が負はるるときに、金銭が弁済せらるるときの如し。若し金銭の代りに、穀物又は其の他の或る物が弁済せられ、或は又其の反対のとき、債権者の同意を以て、これが行はるときは、債務者は債務より放免せらる。弁済者が何人なるか、債務者自身なるか、或は彼に代る第三者なるかによりて差異なし。蓋し債務者は、第三者の弁済によりても、解放せらるればなり。知ると知らざると、又意思に反しても、弁済がなされたるかを問はず。債務者が弁済するときは、彼に代りて債務者となれる者、即ち保証人及び委任者も亦解放せらる。若し保証人が弁済するときは、主たる債務者を解放し、自己自身をも債務より放免す。
一 acceptilatioも亦債務関係を解消す。acceptilatioとは、定義にして謂はば、典型的文言を用ひて行はるる仮装的弁済なり。蓋し言語による債務によりて、予に負はるるものを、若し予が汝に免除せんと欲せば、予が債務者たる汝に「予が汝に約したるものを、汝は受領したるか」なる文言を謂ふことを認容し、予も「予は受領したり」と返答するときに、免除は為さるることを得ればなり。然れどもはacceptilatioは、羅馬語を以て為さるるを通常とする所と同様に、ἔχεις λαβὼν δηνάρια τόσα; ἔχω λαβώνの如くにせば、希臘語を以てしても為さるることを得。acceptilatioは既に述べたるが如く、唯単に言語による債務関係のみを解消し、其の他のもの、例へば物又は文書又は合意による債務関係は、これを解消せず。蓋し言語によりて成立せし債務関係は、他の言語によりて解消せらるることを得るは、相対応したることと考へられたるによる。若し其の他の方法によりて、或る者が予の債務者なるとき、例へば物、文書又は合意による債務関係、又は事務管理、又は遺言による債務関係に基くとき、汝に此の債務を免除せんと欲するときは、予は汝に向ひて「汝は汝が某々の訴権に基きて負へるものを、予に与ふることを約するか」と要約することを得、汝が「予は約す」と謂ふときは、さきの訴権は廃止せられて、別に言語による債務関係発生し、尚言語による債務関係成立せるを以て、acceptilatioは適当に実行せらる。而て弁済は総ての債務関係を解消するに反し、acceptilatioは言語による債務関係を解消する点に於て、弁済とacceptilatioに差異あるも、一部の債務の弁済は、一部に於て債務関係を解消すると同じく、acceptilatioも亦、一部に付て為され得る点に於ては、共通あり。
二 吾人は他の方法によりて債務を負ふ者は、要約せられ且言語による債務関係の債務者となれるときは、acceptilatioによりて解放せらると謂ひたるを以て、アクヰーリアーナ問答口約を述ぶる必要あり。此の問答口約は、総ての債務関係を自己のもとに引込み、且acceptilatioによりて廃止することを得。即ちアクヰーリアーナ問答口約は、総ての債務関係を更改し、法学者ガルルス、アクヰーリウスによりて、次の如く構成せられたり。「如何なる原因によるにせよ、或は単純に、或は期限附にて、汝が或るものを与へ、又は為すことを要し、若しくは要す可きとき、且此の物の為に、汝に対する物的又は人的訴権が予に存し、又は存す可きとき、又凡そ汝が予の物を持ち、所持し、占有し(所持と占有の間の差異は、所持は自然的に掌握することなるに、占有は支配者の意思を以て、掌握する点にあり)若しくは以前に占有したるとき、或は占有せざらんが為に悪意を為したるときは(蓋し恐らく予に齎されたる相続財産を、汝が自己の所持のもとに置き、次で財産の或るものを占有したるならん。蓋し汝は悪意にて占有することをせざりし物に付ても亦、拘束せらるればなり)是等の物の各々が価する丈の金銭を与ふることを、アウルス、アゲリウスは要約し、ヌメリウス、ネギヂウスは約したり」と。かかる問答口約が行はれて、総てが言語による債務関係に置かれたる後、ヌメリウス、ネギヂウスは、アクヰーリアーナ問答口約に基きて、反対にアウルス、アゲリウスに対して「若し今日ヌメリウス、ネギヂウスが、アクヰーリアーナ問答口約によりて、汝に何物かを約したるときは、其の物全部を汝は受領したるか」と要約し、アウルス、アゲリウスは「予は受領し、且受領したるものを記入したり」と答ふ。而て見よ、初の文言によりて、言語による債務関係が成立し、これはアクヰーリアーナ問答口約によりて、以前に存せし全原因を更改し、第二の文言によりて、アクヰーリアーナ問答口約を解消する、acceptilatioが行はれたるを。而てこれ坊間にて、アクヰーリアーナ解消と称せらるるものなり。
三 又更改も訴権を廃止するを通常とす。蓋し汝によりて負はるるものを、予がチチウスに要約するときは、新人物が介入して、新なる債務を発生し、初のものは次のものに転換して、廃止せらるればなり。其の然るは、仮令問答口約が無効なるが如きことありとも、初のものは廃止せらるるも、次のものは、被要約者を法律上の責任者となすことを得ざる程なり。例へばチチウスが予に負ひたるものを、予が後見人の助成なくして、未成熟者に要約するが如し。此の場合には、債権は予に失はれ、チチウスも更改によりて解放せられ、未成熟者も後見人なくして、要約せられたるを以て、予の債務者となることなし。人若し他人の債務を、奴隷に要約したるときは、同一には非ず。蓋しかかる場合には、初の債務関係は、其の後何等問答口約が行はれざると同じく、動揺せざるが侭原状に残ればなり。而て何人も、要約を受けたる奴隷は、自然上債務者となり、同人によりて与へられたる保証人は、自然上も法律上も拘束せられ、而て自然債務は更改を為すことを得〔るに非ずや〕とは謂ふこと勿れ。否これに付ては汝は、自然債務が生まるることのみならず、人格者が存することが、更改を為すものなりと謂はざる可からず。然るに法律に於ては、奴隷は無人格なるなり。而てこれは一人に代へて、一人に要約する場合なり。若し予に債務を負ふ者を、予が要約するときには、更改が行はるるかを研究す可し。而て尚より完全に汝に説かんが為、若し物又は文書又は合意による債務関係に基き、或は準契約より発生する訴権に基きて、汝が予に債務者たりとせば、疑もなく更改は発生す。然れども若し以前は、言語による債務関係の債務者たるに、今又新に要約せらるるときには、初の問答口約の外に、何等か新しきものが、次の問答口約に齎さるる場合には、更改を発生す。蓋し恐らく条件又は期限又は保証が附加若しくは削除せられ、或は又量が増加せられしならん。蓋し初の問答口約は十金、次の問答口約は五金なるが故に、〔額が〕削除せられたるときは、更改は行はるることなかる可ければなり。十金の中には、五金が包含せられ、次のものは何等新しきものを有することなければなり。条件の附加に付て、更改を為すと謂ひたるは、条件が成就したるときに於て、更改が為さるるものと、解することを要す。何故となれば、若し不成就に逐りたるときは、初の債務関係は、持続すればなり。蓋しより強力なる債務関係——単純なる債務関係を謂ふ——が、弱き債務関係——弱き債務関係とは、条件が成否未定中なる間の、条件附債務関係を呼ぶ——によりて廃止せらるるは、失当なればなり。
三イ 然れども古人のもとに於て、更改の意思を以て、次の問答口約に転じたる場合に、初めて更改が為さるることは、均しく認められたる所なるも、何時契約者は更改の意思を以てこれに臨みしかが疑問とせられ、異る推測が、異る学者によりて、此の場合に移入せられたり。これが為、総ての曖昧を廃止せし吾人の皇帝の勅法制定せられ、該勅法は、契約者の間に、初の債務の更改の為、今の問答口約に移る旨が明言せられたる場合に於てのみ、更改が為さる可き旨を明かに定めたり。これが行はれざるときは、初の債務も原状に止まり、次の債務も附加せられ、債務者は此の神聖なる勅法によりて規定せられた所に従ひ、各の原因に基きて、予の債務者となる。上記の勅法を読む者は、更に完全に此のことを学ぶことを得。
四 上に述べたる外、合意より生まれたる契約は、反対の意思によりて解消せらる。蓋し予チチウスと物の売買に付て、同人が予より、某なる土地を百金にて購ふ可き旨を商議し、次で未だ実行せられざる間、即ち代価も弁済せられず、土地も引渡されざる間に、両者の間に於て、売買を解約す可き旨、意思の合致を見たるときは、相互に解放せられ、其の結果売主も買主に対して、売却訴権を有せず、買主も売主に対して、購買訴権を有せず。これ即ち未だ実行せられざる間の解約なり。貸借及び合意による債権関係のもとに包摂せらるる総ての契約に付ても、吾人は同一と謂ふ者なり。
法学提要第三巻は神と共に幸福に完了せられたり。