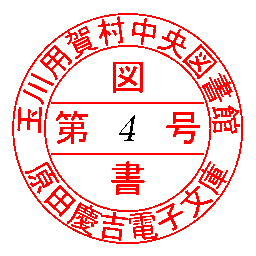
——神と共にする法学提要第二巻の開始——
第一章 物の区別に付て
前巻に於て、吾人は立法者を精細に説明し、法律の分類より開始し、羅馬の立法が次の三種、即ち人、物及び訴権に関して行はるることを述べたり。而て同巻に於て、人に関する教授を完了し、其の中にて、或る者は自由人たり、他の者は奴隷たり、而て自由人の中にても、或る者は生来自由人たり、他の者は被解放者たることを説きたり。人の中或る者は権力服従者たり、他の者は自主権者たり、而て権力は何人に対して成立するか、又如何なる方法によりて消滅するか、又自主権者中或る者は後見に服し、他の者は保佐に服すとする他の分類を述べ、後見人及び保佐人の成立及び消滅、就任免除、嫌疑者の訴追を知りたれば、今や順序の上にて第二巻に当る巻に及んで、物の分類に関して述ぶ可し。而て分類は無限の材料に対する簡潔なる把握なり。物の最高の分類は下の如し。即ち物の中、或る物は吾人の権力と財産の下にあり、他の物は吾人の財産と権力の外にありとなすことこれなり。蓋し或る物は、自然の権利又は万民法によりて、後にも述ぶるが如く、万人に共通、或る物は公有、或る物は法人に属し、或る物は無主、而て多くの物は、各人の支配する所に属す——是等は以下にて明かにせらるるが如く、諸種の原因に基きて、各人に取得せらる——ればなり。
一 さて自然法によりて、万人に共通なるものとは下の如し。空気、四時流るる水、海洋、及びこれによりて、海浜これなり。されば何人も、例へば散歩し、或は船の碇を下しなどして、海浜に趣くことを妨げらるることなし。但し別荘或は家宅、及び同所に建設せられたる記念碑、又は建物より遠かりて、是等を害はざる様にすることを要す。蓋し是等の物は、海洋の如くに万人に共通にも非ず、又万民法上のものにも非ざればなり。
二 河川及び港湾も総て公的、即ち羅馬国民に属す。故に港湾及び河川に於て魚獲を為す権も、総ての者に共通なり。
三 海岸が海洋自体と同じく、万民法上のものと謂ひたれば、海岸とは何ぞやを定義する必要あり。海岸とは冬の最大の波が及ぶ迄の場所なり。故に夏期に於ても、吾人は其の場所迄を海岸と定義す。
四 河岸の使用も、万民法の欲するが如く、公的なり。あたかも河川自体の使用が、公的なると同じ。故に固より船を此の河岸に碇泊せしめ、纜を同所に生えたる樹木に繋ぎ、船荷を同所に陸揚するが如き自由は、何人にも利す。あたかもこれによりて航行することが、禁ぜられざるに同じ。蓋し(人の謂ふが如く)河岸の使用は、公的即ち万民法上のものなればなり。然れども是等の河岸の所有権は、河岸が接続又は連結せる土地の所有者に属す。故に其の河岸に生ぜる樹木も、河岸の所有者の所有に属す。蓋し上にあるものは、下にあるものに従へばなり。
五 海岸の使用も亦、海洋自体の使用と同じく、公的又は万民法上のものなり。故に自己を休息せしむることを得可き小屋を、同所に建つる自由は、網を乾し、海より引きあぐると同じく、何人にても欲する者に附与せらる。海岸の所有権は、特定の所有者を記さず。蓋し海洋及び海の下にある海底又は土砂が服すると、同一の法に服すればなり。
六 団体又は法人に属して、個人各自に属せざる物とは、例へば都市にある劇場、競技場、公の浴場、柱廓及び其の他の物にして、都市に共有なる物の如し。
七 神聖物、宗教物及び聖護物は所有者なし。蓋し神法に属するものは、何人の所有にも服せざればなり。
八 神聖物とは適当に方式を践み、神官によりて神に奉納せられたる物を謂ふ。例へば教会、礼拝堂、殉教者の祠、及び適当なる儀式を経て、神の奉仕に充てたる献納物、例へば高価なる宝の如し。吾人の極めて敬虔なる皇帝の勅法は、捕虜の受戻しを原因とする場合を除き、是等の物が譲渡又は担保の目的とせらるることを禁じ給へり。即ち人蛮人に捕へらるるが如きことありて、而も其の都市の極めて神聖なる教会が、金銭に事を欠くときは、よりて以て捕虜を受戻す可き金銭を取得せんが為、高価なる器を売却又は担保品となす自由が、僧上又は会計掛に附与せらるるなり。人若し己が権威に従ひて、己が為、神聖なる場所なるかの如くに定むるも、人これを神聖とは呼ばざる可し。蓋し如何にして、通常神聖物とせらるるか其の方法如何は、既に一度説きたる所なればなり。否吾人はかくの如き場所は、世俗的又は私有的と称するものなり。若し神殿が地震起りて倒れ、又は古きが故に倒るることあるも、神殿を建てたる場所が、以前と均しく神聖にして、且無主なるは、尚パーピニアーヌスの説くが如し。蓋し神聖となるや、如何なる方法によるも、神聖たることを已むことなければなり。
九 宗教物も人の説くが如く、無主物に属す。各人は己が意思を以て、己が土地に死体を埋葬して、宗教物を作製す。若し場所は共有なるも、清浄にして未だ宗教的ならざるときは、共有者の意思に反して、遺骸を同所に埋葬することは、彼に許されず。若し墓地が共有ならば、他の共有者が欲せずとも、彼は遺骸を埋葬することを得。若し或る場所の用益権を他人が有し(用益権とは或る方法にて成立し、悟性によりて把握せらるる或る権利にして、予をして他人の所有権の使用収益を有すに至らしむるものなり)従つて同一場所に付て、一人は用益権を有し、他は所有権を有するときは、上述の当該の場所に遺骸を埋葬する所有者は、用益権者の意思に反して、其の場所を宗教的と為すことなし。蓋し若し宗教的となるときは、これは所有せらるることを得ざる可し。然るに用益権の定義は、用益権が他人の所有権に対して成立するものなることを吾人に教ふ。故に当然用益権者の同意が必要となるなり。蓋し所有者によりて、用益権者の損害に於て、行はるるものは何物たりとも、効力なければなり。又何人の場所たりとも、所有者の許可あるときは、これに遺骸を葬ることを得、其の場所は宗教的とせらる。又若し意思に反して葬らるるも、所有者が〔このことを〕知りたるときに、其の行為を追認せしときは、其の場所は尚宗教的となる。
一〇 聖護物例へば城壁城門の如きは、或る程度神法に属し、これが為、何人によりても所有せらるることなし。城壁を神聖と謂ひたるは、城壁に対し、何等かの不法行為を加へたる者、例へば石をもぎりとり、或は如何なる方法にせよ、域門に損害を加へたる者に対して、頭格刑が規定せられたればなり。此の故に、法律中の部分にして、法律違反者に対して、刑罰の書き記されたる所も亦、sanctioと称す。而てsanctaと呼ばれしは、sancireとは確固たるものとなすの謂なるよりして来る。蓋し城壁が吾人の安全を確保するが故に、これが為sanctaと称せらるるなり。呼称の理由にして、昔噺に類する或るものを与ふることも可能なり。蓋し人曰く、古き時代には、神は人と共にましまし、人をあらゆる方面より、損害を受くることなからしめて保護し給ひしも、時が進み、人間に飽きて、人間のもとを去り給へり、茲に於てか、其の助を失ひたる人間は、神よりの保護を模倣して、城壁を案出せり、而て尊敬す可きものは神聖なるが故に、最も尊敬す可きものの代りとして、案出せられたるものとして、城壁及び域門をsanctaと称したるなりと。
一一 吾人は此の外尚、人間各人の所有のもとに置かるる物に付て述ぶ可し。是等は種々の方法によりて、吾人の財産となる。或る財産に付ては、自然法(これは既に述べたるが如く万民法と称せらる)によりて、其の所有者となり、或る財産に付ては、厳正且市民的なる理、即ち羅馬人に特有なるものによりて、所有者となる。而て古き法より、研究を開始するを便宜とす。自然の権利がより古きは、諸家の言の一致する所なり。これ人類と共に、自然が光明に齎らせるものなり。蓋し市民的権利は、国家が建設せられ、官吏が選挙せられ、法律が書き記され始めしときに、既に発見せられたればなり。
一二 野生の獣、鳥及び魚(即ち地上海中又は空中に生まれたる総ての生物)は、人に捕へらるると共に、万民法に従ひて、直ちに其の者の所有に属し始む。蓋し以前に何人の所有にも服せざる物は、自然の理によりて、先占者の有となればなり。而て野生の獣又は鳥を、己が土地の中にて捕獲するか、或は狩をなし、又は黏にて捕へんが為に、他人の土地に侵入するかは、何等関する所に非ず。然れども、土地の所有者が予知せるときは、彼によりて適法に禁止せらる。蓋し彼が己が土地へ侵入するを禁止することは、可能なればなり。人若し上記の生物の或るものを捕ふるときは、彼の保管を持続する限り、其の所有の下に保持す。若し捕獲者の保管を脱して、自然の自由に復帰せしときは、さきの捕獲者の所有に属することを已めて、再び先占者の有となる。而て自然の自由は、吾人の眼界を脱し、或は吾人の眼界のもとに置かるるも、これが捕獲が困難なるときに、生物これを恢復するものと考へらる。蓋し極めて高き場所、又は歩行の困難なる場所にあるときは、何をかなさんや。
一三 次のこと争点となれり。鹿又は野猪が、予によりて、其の捕獲が容易【δισχεῆはεὐχερῆに改む】となれる程度に、傷けられたり。或る者は曰く、かかる生物は直ちに予の所有となると。或る者は、予によりて傷けられたるものは、致命的なる負傷と共に、予の有となるも、其の生物を追跡する間に限るとする説に傾けり。故に若し予これが追跡を已めたるときは、予の所有に属することを已め、先占者の有となることとなる。更に予が野獣を手にするに非ざれば、傷けたる予は、これが所有者となることなしと唱ふる或る者の主張にかかる第三説が現はれ、吾人の皇帝も次の如き理由を附加して、むしろ此の第三説を確認し給へり。蓋し曰く、其の間には、予が当該生物を捕獲することを許さざる多くの事変が発生することは、有り得可きことなり。偶々野生の動物が現はれて、それ以上進むことを妨ぐるが如きこともあれば、或は追跡中困難なる所に陥りて、野獣を追跡することが不可能となるが如きこともあらんと。
一四 蜜蜂の性質も野生的なり。故に汝の木にとまりたる蜜蜂は、吾人がキユフエラと称する蜂の巣箱の中に、汝がこれを閉ぢ込むる以前には、汝の所有となることなし。あたかも、汝の木に巣を営みたる鳥は、鳥黐にて捕へられざる以前には、汝の所有となることなきが如し。故に若し或る人が先に来りて、当該蜜蜂を己が蜂の巣箱の中に移したるときは、其の者の所有となる可し。又蜂巣も、若し蜜蜂によりて作らるるが如きことあらば、何人にても欲する者は、これを取り去ることを得。仮令予の土地に、これが生ずるとも尚然り。然れども他人が蜂巣を捕ふる以前に、予が予知して、彼が予の土地の中に侵入することを禁止せしときは(蓋し予は法律に従つて、このことを行ふことを得るなり)予は何人にも妨碍せらるることなく、蜂巣を取ることを得可し。蜂群が若し汝の巣箱を去りて飛び去りたるときは、汝の眼界の下にありて、これが捕獲が困難ならざる間は、汝の所有に属すと考へらる。蓋し若し捕獲が困難なるか、或は汝の眼界を脱したるときは、先占者の有となればなり。
一五 孔雀及び鳩の性質は野生的なり。立ち去り、後又再びたち帰るは、彼等の慣習なりとは、何人も謂ふ勿れ。蓋し蜜蜂もこれと同じことを行ふも、彼等の性質が野生的なるは、争なければなり。人、所有者を離れて森に去り、後再び帰り来るが如くに馴らされたる鹿を有するも、其の性質は同じく野生的なり。慣習上去りて後又帰るを通常とする生物、例へば蜜蜂、鳩、孔雀、鹿の如きものに付ては、次の如き吾人にとり極めて有効なる法則が伝へらる。即ち吾人は、是等の動物が吾人のもとに帰還する意思を有する間は、是等の動物は吾人の所有に属すと謂ふなり。蓋しかかる意思を有することを已むるときは、吾人の所有に属することを已めて、先占者の有となればなり。然れども、生物に対して此の意思を把握することは不可能なれば、帰還に関する慣習よりして、吾人は此の意思を看取するなり。予の鹿が予のもとを去りて森に至り、而て其の当日或は翌日或は三日目に帰還する通常とするも、三日以上予の家を離れたることはなしと仮定せよ。若し帰還することを通常とする期間三日以内に、何人かに捕へられたるときは、予は所有権を害せられたる者として、彼に対し物的訴権を有す可し。若し四日目に或る者がこれを捕へたるときは、予は彼に対して何等の訴権を提起せざる可し。蓋し帰還の慣習を守らざることよりして、予の所有を軽んぜしこと明かなればなり。
一六 家鶏及び鵞鳥の性質は野生的に非ず。此のことは、吾人が野生的と呼ぶ他の鶏即ち野鶏、及び吾人が野生的と呼ぶ他の鵞鳥にして野鵞と称せらるるものが存することよりしても、考ふることを得。故に汝の鵞鳥又は汝の鶏が、何等かのはづみに撹乱せられて逃げ去り、汝の眼界を逃れ去るときは、如何なる場所に発見せらるるにせよ、依然同じく汝の所有に属し、利得の目的、即ち領得の意思を以て、かかる生物を抑留したる者は、盗むものと観ぜられ、窃盗訴権の責を負ふ。
一七 敵よりの取得も亦、自然的取得とす。蓋し吾人が敵より捕獲せし物が、吾人の財産となるは、自然法の欲する所なればなり。故に捕虜となれる自由人も、直ちに吾人の奴隷となる。而て若し是等の物、例へば奴隷が吾人の権力を脱して、己が同胞のもとに帰還するが如きことあらば、従前の地佗を恢復す。
一八 高価なる石、宝石、其の他海岸に於て通常発見せらるる物は、自然の理に基き、発見者の財産となる。
一九 予の所有に属する生物より生まれしものも亦、これを生みたるものと同じく、予の所有に属す。
二〇 寄洲作用の取得も亦、自然的取得なり。寄洲作用とは、水の押流し又は水の齎せる堆積なり。蓋し寄洲作用によりて、川が吾人の土地に附加せしものは、自然法によりて、吾人の所有となればなり。寄洲作用はこれを定義せば、眼に見えざる増加なり。幾何の量が何時附加せられて、吾人の所有となれるかを考慮し得ざる程、少量づつ附加せられし物が、寄洲作用によりて、附加せらるものと解せらる。今予の土地と汝の土地の二個の土地あり、中間には河が流ると仮定せよ。若し河が少量づつ、又それと認識し得ざる中に、予の土地に何物かを附加せしときは、これは寄洲作用の権利によりて、予のものとなる。
二○イ 若し又河の勢及び襲撃が、汝の土地の或る部分を奪ひ去りて、予の土地に推し流したるときは、附加せられし物が、依然汝の所有たるは明かなり。蓋しこれは、認識し得ざる中に行はれたるには非ざればなり。
二一 若し汝の土地より取り去られし部分には樹あり、而て其の部分が予の土地に接着して、久しくこれに固着し、附随して推し流されたる樹が、其の根を伸して予の土地に密着するときは、是等の物は、予の土地の中に根を生して、予の土地より養はれ始めしときより、予の所有となる可し。
二二 島が海の真中に発生するが如きことあり(尤もこのことは、稀に起る事柄なり)。島は先占者の有となる。蓋し以前何人にも属せざりしものが、今や所有せらるることを開始すればなり。若し河中に発生せしときは(これは屡々起る所なり)河の中央なるときは、両岸に存する岸に接する土地の長さの割合に従つて、河の両側に岸に接して土地を有する者の共有となる可し。例へば此の島が百尺の拡がりあり、而て一方島の右側に河岸に接して土地を有する者は、百尺の長さにわたる土地を有し、左側の他方の者は、七十尺の長さにわたる土地を有せり。然らば一方は七十尺、他方は百尺の長さを、所有することとなる可し。若し一方の岸に接近し、他方の岸より遠かるときは、近き側に岸に接して土地を有する者の、単独の所有となる可し。若し予の土地のもとを流るる河が、或る部分にて分流し、二つに切られて予の土地の周囲を巡り、又は取巻き、而て最後に自ら合して一となり、中間の場所が島の形をとれるときは、取巻かれたる土地は、以前に予が所有したるの故を以て、依然予の所有に属す。
二三 若し自然の河床が全然遺棄せられ、河は他の場所を流れ始めたるときは、従前の河床は、両側に在る河岸に接続せる各土地の長さの割合を以て、河岸に接して土地を有する者の有となるに反し、新河床は、河も服する権利、即ち公権に服し始む。若し又或る時間を置いて、従前の河床に復帰せしときは、今や河に遺棄せられたる河床は、再び河岸に接して土地を有する者の有となり初む。
二四 若し河が氾濫して、予の土地を全部を浸したるときは、事情は異る。蓋しかかるときには、未だ吾人は、土地が公有となるとも、又土地の所有権が変更せらるとも謂はざればなり。何故となれば、依然予のものなればなり。故に若し氾濫して覆ひたる場所より退水するときは、予は予の土地を恢復し、公有となりたる新河床が、河の退水によりて近接の土地所有者の有となるが如くには、所有権が近接の土地所有者に属することはなし。
二五 人ありて、他人の材料より、物(εἴδος)を作れり。何人が自然の理に従ひて、物の所有者なるか、材料を物に変形したる者なるか、又は材料の所有者が又物の所有者となるかが問題とせらる。例へば他人の葡萄又はオリーブ又は穀芒より、例へば葡萄酒又はオリーブ油又は穀物を作り、或は他人の金塊又は銀塊又は銅塊より、何等かの器を作り、或は他人の葡萄酒及び蜂蜜より蜂蜜酒を作り、或は他人の薬剤を以て、膏薬又は眼薬を調合し、或は他人の羊毛より衣服を作り、或は他人の板より、船又は箪笥又は椅子を調製したるときの如し。而てこれに関しては、サビーニアーニー及びプロクリアーニーの幾多の論争行はれたり。プロクリアーニーは物を調製したる者が、調製物の所有者となると謂ひたるに反し、サビーニアーニーは材料の所有者が物の主となることを欲したり。次に或る中間の学説とも称す可き第三の学説出で、これによれば、一方に於てサビーニアーニー、他方に於てプロクリアーニーに一致し、吾人の最も敬虔なる主も、これを採用し給へり。蓋し第三説は曰く、若し調製物が、これを作れる以前の材料に分解し得る場合には、材料の所有者が又物の所有者となり、若し物が以前の材料に還元し得ざる場合には、物の調製者が作られたる物の所有者となると。例へば例をとらんに、銅塊又は銀塊又は金塊より調製せられし器は、以前の銅塊又は銀塊又は金塊に復旧せらるることを得るも、葡萄酒又はオリーブ油又は穀物は、葡萄又はオリーブ又は穀芒に還元することを得ず、又蜂蜜酒も葡萄酒と蜂蜜とに分解せらるることを得ざるなり。然れども、是等は全部の材料が他人のものなる場合のことなり。若し予と汝との材料より、予が或る物を作りたるとき、例へば予の葡萄酒と汝の蜂蜜より蜂蜜酒を、或は予と汝の薬剤より膏薬又は眼薬を、或は予と汝の羊毛より衣服を作りたるときは、かくの如き設例に於ては、調製者が所有者たることには何等の疑なし。蓋し物に対し己が労力を費したるのみならず、材料の一部を提供したればなり。
二六 人若し他人の紫糸を、己が衣服に織り込みたるときは、仮令附加せられたる紫糸が、織込をうけたる衣服よりも高価なるときと雖も、同じく附合の一場合に包含せられ、紫糸の所有者は、窃取したる者、及びかかる行為を行へる者に対し、窃盗訴権及び窃盗弁済訴権を有す可し。盗人自身が衣服を調製せると、一人が窃取し、一人が窃取せし糸を衣服に織り込みたるとを問はず。蓋し物的訴権は、紫糸の所有者これを提起することを得ざればなり。紫糸は自己自身の為に存在するに非ざるが故に、或る程度消滅したるものと観ぜらるるが為なり。然れども窃盗弁済訴権は常に提起せらる可し。蓋し変形せられたる物、又は姿を隠されたる物は、物的訴権によりて回収することを得ざるも、窃盗弁済訴権は、盗人及び総ての占有者——仮令盗人に非ずとも可なり——に対しては、提起することを得可し。然れども、若し紫糸の附着せる衣服を占有する者が盗人なるときは、窃盗訴権によりても、窃盗弁済訴権によりても、訴へらる可し。若し盗人以外の者ならば、窃盗弁済訴権に服せしめらるるも、窃盗訴権に服せしめらるることはなし。
二七 某二人に属する材料が、所有者の意思に従ひて混合せられたり。混合によりて作成せられたる物体は、双方の共有に属す可し。例へば某二人が、其の葡萄酒を混合し、或は銀塊又は金塊を溶し合せたるが如し。混合によりて一種独特の物が作成せられたる場合の原料たる材料が異るときは、例へば葡萄酒と蜂蜜よりして蜂蜜酒が、又は金と銀よりして、金銀の合金が作成せられたるが如き場合には、此の場合にも、吾人は作成せられたる物は、両人の共有に属すと謂ふ者なり。是等は所有者の意思に従ひて、行はれたる場合のことなり。然れども若し偶然に、又は所有者の選択によらずして、材料——それは異種的たると、同種的たるとを問はず——が混合せられたるときも、同一となる可し。
二八 若しチチウスの穀物が汝の穀物に混合して、一の聚積となりたるときは、汝の意思に基きたる場合には、其の聚積は共有たる可し。何故となれば、各一個の物体(即ち各粒)が、汝の同意によりて、共同の所有の下に置かれたればなり。若し或は偶然に混合が行はれ、或はチチウスが汝の意思に従はずして、穀物を混同したるときは、聚積は共有に非ざる可し。何故となれば、各粒は其の状態に止まり、混合が是等の粒を変形することなければなり。此の種の設例に於て、聚積が共有とならざるが如く、若しチチウスの家畜が汝の家畜に混淆せしめらるるとも、畜群は共有とせらるることなかる可し。若し穀物の聚積が、或は汝により、或はチチウスによりて留置せらるるが如きことあらば、他方の者は占有者に対して、物的訴権を提起す可し。各人の穀物は幾何なりしかを見積り、而て品質と分量に従ひて、原告に対し占有者を判決するは、裁判官の職務たる可し。
二九 人若し己が土地に、他人の材料を用ひて家屋を建築したるときは、建築物の所有者となる。蓋し建設せられし物は、土地に従へばなり。然れども材料の所有者は、該材料の所有権を永久に喪失するには非ずして、建物が存する間は、十二表法によりて、物的訴権も提示訴権も提起することを得ざること丈が明かなるのみ。同法によりて、何人も己が建物に結合せられたる他人の建築用木材の取外しを強制せらるることなく、唯de tigno iunctoと称せらるる人的訴権提起せらるるときは、其の二倍価額を弁償す可き旨が規定せられたり。此の訴権は、予の所有に属する材木を、或る者が其の建物に結合したる場合のみならず、石及び煉瓦更には円柱の場合にも発生す。蓋tignusなる名称によりて、建築の材料たり得可き一切の材料が、指示せらるればなり。かくの如く十二表法によりて立法せられ、木材が予の建物に組込まれたるを理由として、物的訴権又は提示訴権が提起せらるることなからしめたるは、裁判官が此の事件に付て予を判決するに当り、判決に満足を与ふることを理由として、予が家屋の解体を強制せらるることなからしめんが為なりしなり。蓋し十二表法は屡々、家屋を以て、其の考慮に値するものと解したればなり。若し何等かの原因よりして、当該建物が崩壊するが如きことあらば、材料の所有者は偶々de tigno iuncto訴権によりて、二倍額を取得せざる限り、物的訴権も提示訴権も、何等故障を件ふことなく、提起することを得。
三〇 前述せし所に於ては、己が土地の中に、他人の材料を用ひて、或る建物を建てたる場合を述べたり。今や反対の場合を例にとる可し。予が汝の土地に、予の材料を以て、家屋を建てたり。土地の主は、上にあるものは、下にあるものに従ふとの原則により、又建物の所有者となり、其の結果、予は材料の所有権を永久に失ふ。蓋し予は知りて、他人の土地の中に建築したるが為なり。而も仮令家屋が崩壊するが如きことありとも、予は材料に付き、対物訴権を有することなかる可し。唯若し建築したる予が、家屋の占有中なるが如きことあらば、土地の所有者が、上にあるものは下にあるものに従ふとの原則を援用して、予に対して対物訴権を提起するも、予が若し善意占有者たりしときは(蓋し土地を以て予のものと考へたるが為)、予は材料の価額のみならず、職人の給料をも受領す可く、彼若しこれを為すことを欲せざるときは、悪意の抗弁によりて排斥し得可きは、争なき所に属す。若し悪意にて其の場所を占有したるときは(蓋しそれが他人のものたることを知りたるが為)、予は何等の抗弁をも有することなく、場所を建物と共に返還することを強制せらる。蓋し何人も、如何なる理由により、知りて他人の場所に建築したるかと、予を責むることを得ればなり。
三一 チチウスが己が土地の中に、他人の樹木を植ゑたり。樹はチチウスの有たる可し。若しチチウスが、己が樹をマエビウスの土地の中に植ゑたるときも、樹はマエビウスのものとなる可し。但し両場合共に、植付けられたる樹が、其の根を下したるときに限る。蓋し其の根を下して、下の土地を把持する以前には、樹は従前の所有者に属するも、当該の植物が根を下したる後は、其の所有権は、樹の置かれたる土地の所有者に転ずればなり。茲に於てか、次の如きことが問題とせられたり。予の隣人が其の土地の境に、予の土地に接して、樹を有したり。其の樹の根が、漸次地下を逼ひて予の土地に達し、予の土地を把持し、同所より養分を採るに至れり。論争が行はれたる後、樹は予のものとなること通説となれり。蓋し自然の理は、〔己が〕土地の中に根を有する者以外の者に、樹が属することを許さざればなり。故に二個の土地の境界に樹が生じ、其の伸びたる根が双方の土地を把持したるときは、樹は共有となる可し。
三二 土地の中に養分を採りて成長する植物が、下の土地を所有する者の有となると同一の理由によりて、蒔かれたるもの、例へば穀物大麦其の他これに類するものも亦、土地に従ふ。然れども、善意にて他人の場所に建築したる者が、対物訴権にて訴へられたるときは、悪意の抗弁を以て、自己に損害を来すことなからしむるが如く、己が支出に於て、他人の土地に蒔きたる者も亦、善意にてこれを為したるときには、悪意の抗弁によりて安全を得可し。
三三 人ありて、予の紙又は羊皮紙をとりて、其の中に何物か書き込みたり。此のときも亦、土地に倣つて、上にあるものは下にあるものに従ふ。仮令上の文字が金なるときと雖も尚然り。かくて予は書物の所有者となる。書きたるものが韻律の詩なるか、又は歴史なるか、将又演説なるかによりて、何等異る所なし。唯予が書物を作りたる者に対して、対物訴権を提起し、書写の費用を直ちに給付せざるときは、これを為したる者が、善意にて占有する者なる場合には、悪意の抗弁によりて排斥せらる可し。
三四 人ありて、他人の平面板をとりて絵を描き、肖像画を作れり。肖像画は何人の物なるかが問題とせられたり。而て或る者は曰く、画家が平面板の所有者となり、平面板は絵画に従ふと。他の者は惟へらく、平面板の所有者が、絵画の主となる、絵画の如何なるものたるかを問はずと。而て吾人の皇帝は、むしろ前説を採用して、画家が平面板の所有者たらんことを欲し給へり。蓋しアペルレース又はパセラシオスの絵画が、極めて安価なる平面板に従ふとは、笑止千万と考へ給ひしなり。唯若し平面板の所有者が、肖像画を占有せるとき、画家が平面板の価格を提供せずして、彼に対して対物訴権を提起せるときは、悪意の抗弁によりて排斥せらる可し。若し画家が肖像画を占有せるときは、平面坂の所有者は直接対物訴権を有することを得ざるも——蓋し彼は絵画が描かれて、所有権を喪失したればなり——彼には準対物訴権が附与せられ、訴ふるに当りては「予はあたかも尚所有者の如くに」と称す。此の準対物訴権を行使する者が、若し画描に付て下されたる費用を、善意にて描きたる者に支払はざるときは、悪意の抗弁によりて排斥せらる可し。而て是等は、肖像画の所有権に関する限りに於て、取扱はれしなり。画家が平面板を盗みたると、其の他の者が盗みたるとを問はず、所有者には、盗人に対する窃盗訴権が附与せらるるは、諸家の学説一致する所に属す。
三五 予が汝を所有者と信じて、他人の土地を汝より買ひ求め、或は贈与其の他の正当原因、例へば交換によりて、善意にて取得せしときは、自然の理は収取せる果実に対して加へたる注意と介意の故に、予がその果実の所有者たらんことを欲す。故に後日、土地の所有者が訴を為して、土地を対物訴権によりて回収せんとするも、其れより収取して消費したる果実に付ては、何等の訴権を有せざる可し。若し知りて他人の土地を占有するときは、予は其の果実には与ることなかる可し。固より予は汝に対し、其の間に収取せし果実と共に、土地の返還を強制せらる。仮令其の果実はこれを消費するが如きことありとも尚然り。
三六 同一の土地に付て、予は所有権を有し、汝は用益権を有せり。用益権者たる汝は、果実を土地より収取するに非ざれば、其の所有者となることなかる可し。故に若し果実が成熟して土地に附着せるときに、汝が死亡するが如きことあらば、汝の相続人がこれを取得するに非ずして、是等は所有者に従属す可し。小作人に付ても、殆んど同一の規則なり。蓋し若し予が汝に貸与するときは、汝は土地より取り去るに非ざれば、其れより取得する果実の所有者となることなかる可し【fere即ち殆んどの語は、抹消せらる可し】【括弧内は後人の附加なること疑なし】。
三七 土地の用益権に付ては言葉を尽したれば、家畜の子は、乳、皮、毛と同じく、家畜の用益権者の有なることを知らざる可からず。故に子羊、山羊、犢、及び小駒は、出生と同時に、自然の理により。用益権者の所有となる。然れども女奴の産みたる子は、果実の中には入らず。故に若し予が、予の女奴の用益権を汝に譲るも、汝は女奴の労務と、手の仕事を果実中にに有す可きも、子は所有者の所有となる可し。蓋し果実は事物の自然が、人間の為にこれを案出したるに、人間が果実の中に算入せらるるは、背理と考へられたればなり。
三八 然れども、人若し畜群の用益権を有するときは、用益権者は、死亡したるものの代りを、出生せしものより捕足して、其の頭数を充たすことを要す。蓋しこれユーリアーヌスの説なればなり。例へば予が汝に対し、百頭の羊の畜群の用益権を譲れり。三十頭の羊が死亡し、五十頭の羊が出生せり。汝は汝に与へられたる頭数を保存せんが為、三十頭を原物に附加し、かくして残余の二十頭の羊を所有す可し。
三八イ 若し予が葡萄畑又は土地の用益権を汝に譲りたるときは、枯死せるもの又は古樹となれる葡萄の代りと、疲弊し又は倒れたる樹木の代りに、別のものを置き換ふることを要す。蓋し汝は、適当に且用方に従つて、汝に用益権の譲られたる土地に意を注ぎ、以て最も善良なる家長が行動するが如くに、行動することを要すればなり。
三九 人ありて、己が土地の中に埋蔵物を発見せり。至聖ハドリア−ヌスは、自然上の権利を護りて、発見者に埋蔵物を譲り、神聖地又は宗教地に於て、偶然に発見したる場合にも、同一の規定を命じ給へり。人若し他人の土地に於て、殊更になしたるに非ずして、偶然に埋蔵物を発見したるときには、ハドリア−ヌスは、半は土地の所有者に分譲し給へり。故に人若し禁止を受けずして、帝室所領地に於て、埋蔵物を発見したるときは、埋蔵物の半はこれを皇帝に提供し、半は発見者これを保留す可し。若し又人ありて、都市の所有地又は国庫所属地に於て発見したるときは、同様にして半は発見者これを享有し、半は国庫或は都市これを取得す可し。
四〇 引渡の方法も亦、取得の自然的方法なり。然らば引渡とは何ぞや。容易に行はれて、何等無用の煩雑を生ぜず、而て自然的行為を備ふる、手より手への移転なり。蓋し自己の物を他人に移転する所有者の意思を是認すること程、自然に合することは他になきを以てなり。予が引渡によりて、所有権を移転せんが為には、次の事項、即ち引渡を行ふ者が所有者なること、所有権の移転を欲する意思を以て、引渡を為すこと、及び引渡さるる物が有体物なることの三点が、競合することを要す。有体物と称したるは、接触不可能の無体物は、引渡を許さざるが為なり。引渡を行ふ者が、所有者なることと謂ひたるは、所有者たらざる者は、己が有せざる所有権を、移転することを得ざるが為なり。譲受人を所有者となすことを欲する意思を以てと附加せしは、使用及び寄託を除外せんが為に基く。蓋し是等の場合には、物は有体物たり、引渡人も所有者なれど、暫くして後、これを取り戻すことを期待して、交付すればなり。所有者より交付せらるる物が、如何なる物たるかは、区別することなし。イタリアの土地たると、上納的不動産たると、貢献的不動産たるとを問はず。県にある不動産は、上納的不動産及び貢献的不動産と称せらる。其の名称の理由は、下の如きものより来る。古く全土を支配し、其の勇気の故に、羅馬人の驚嘆の的となり給ひし羅馬皇帝は、県を分割し、一部は自己自らの支配とし、他は国民の分とし給へり。而て国民の県が上納的と称せられしは、下の理由より来る。スチペスとは上納にして、銀其の他の物の少量づつの徴集なり。県人は己がもとに生じたる物より、或る少量を集め併せて、国民をして、其の必要と喜に、これを消費せしめんが為、国民に送付せり。これが為に上納的の〔県〕と称せられ、其の外尚何等の故障なく、上納的家屋、上納的土地なる名称も出でたり。皇帝の県は貢献的と称せられたり。蓋しトリプートンとは重税にして、軍隊の給養に対し、多額の費用を出すが故に、皇帝がこれをば、己が県に課し給ひしなり。而て古く上納的不動産及び貢献的不動産を、国民又は皇帝の同意によりて有する者は、所有者には非ざりき。蓋し是等の物の所有権は、或は国民或は皇帝にありて、自己は唯是等に対して、他人に譲渡し、又相続人に遺すことを得るが如き使用収益権、及び最も完全なる占有を有するに過ぎざりき。然るに、イタリアの土地及び家屋の所有者は、所有権を有したり。然れども是等は古のことなり。今日に於ては、極めて敬虔なる吾人の皇帝の勅法は、イタリアの不動産と上納的不動産及び貢献的不動産の間に、何等の差別の存するを欲せず。若し所有者が自己の物を贈与、嫁資、其の他如何なる種類にせよ、合法的原因、例へば交換に基きて予に引渡すときは、予に所有権の移転することは疑なし。
四一 然れども、若し売りて引渡すときは、買主が売主に対し物の代価を支払ひ、又は彼に担保を設定するに非ざれば、所有権は買主に移転せず。蓋し彼に代つて代価を与ふ可しと約する某チチウスを立てたるとき、又は代価に代る質物を交付せるときは、何をか為さんや。これ十二表法によりても亦規定せらるる所にして、且此の制定法が又均しく万民法たることを、吾人は発見す。何故となれば、自然的正義が此の原則に横はり、為に万民の間に維持せらるればなり。故に他の原因よりして引渡を行ふ所有者が、〔直ちに〕所有権を移転するに反し、売買に付ては、代価を受取るか、代価に対する担保が彼に為さるるに非ざれば、其のことはなし。然れども売主代価を受けず、買主の為に諾約する者をも取らず、質物も取らずして、尚代価は取得し得可しと確信して、買主の信にて満足するときは、吾人は、所有権は直ちに買主に移転すと謂ふ者なり。
四二 引渡を行ふ場合には、所有者自身が引渡人なると、或は他の者が所有者の意思に従ひてなすとによりて、何等の区別なし。
四三 此の故に、若し予が、予の財産を希望通りに管理す可き自由を、何人かに附与し、彼此の財産の中より売却して引渡を行ふときは、譲受人に所有権を移転す。蓋し所有者の意思に従ひて、此のことが為さると観ぜらるればなり。
四四 又所有権の移転に、引渡なくして、単なる意思のみにて足る或る場合を発見することを得。例へば予が予の書物を汝に貸与し、或は汝に予の土地を貸借し、或は汝に予の食卓【仏訳二一五頁参照】を寄託し、若し其の後汝にこれを売り、或は贈与するときは、贈与又は売買と同時に、引渡が行はるることなくして、直ちに予は汝を是等の物の所有者となす。蓋し当該物の自然的占有は、汝のもとにあるが故に、予の物が汝の物たらんことを、予が欲すること自体によりて、贈与の為に特別の引渡が行はれたるかの如く、所有権は直に汝に移ればなり。
四五 予諸種の貨物を倉庫に貯蔵せり。是等の貨物を汝に売却す可きことを、汝予と協議せり。合意なりて、汝は代価を与へたり。倉庫に近寄りて、倉庫の鍵を汝に交付するときは、汝は直ちに貨物の所有者となる。
四六 予の知らざる者の中の何人かに、予自ら欲して所有権を移転し、而て其の者に付て問はるるも、贈与の前にも後にも、其の人間が何人なるか、全く語ることを得ざる場合も屡々あり。此のことは、行列又は観覧中、公衆に向つて、何物かを投ずるを通例とする法務官及び執政官に付て発生す。拾得せし者は直ちに所有者となる。而もこれを投ずる者は、何人が各個の投ぜらるる物を受けんとするかは、知らざるなり。
四七 此の故に若し予が予の物を軽んじて、これを予の占有より投棄するときは、古人が遺棄物と称する物は、直ちに拾得者の有となること明かなり。遺棄物とは、所有者が已が財産中に収むることを欲せざるが如き意思を持ちて投じ、為に直ちに所有者に属することを已むる物なり。
四八 海上にて発生せし嵐の為、船員が船に積入れられたる貨物を軽減せんと欲して投ずる物に付ては、事情は異る。是等の投下せられし物は、依然として投下者の所有に止まればなり。蓋し是等の物の投下は、投下者が自己自身の所有に属することを欲せざるが為に為さるるに非ずして、むしろ当該の船と共に、海の危険を免れんことを欲したるが為に為さるるものなることは、衆知の一致する所なればなり。故に若し人ありて、波に浚はれ、或は水に漂ふ物を手にし、利得者又は領得者の理を以て、これを取得したるときは、盗を犯すものとす。次の如き事例も、これに類似す。例へば予某地点に趣かんと欲したり。汝予がよりて以て旅行を終ふることを得可き車を有せり。予汝に対し、予が求むる地点に到着せんが為、予が其の車に座し、予の物を載することを依頼したり。汝料金を対価とし、或は料金をとらずして、これを為すことを、予と合意せり。予車の中に予の物を載せたり。偶々道程の中間にて、予の知らざる中に、物品の或るもの其の車より落ちたり。是等の物は、発見者のものとはならずして、予の所有に止めらる可し。蓋し彼等に対しては、対物訴権、提示訴権、窃盗訴権、窃盗弁済訴権が予に附与せらるればなり。
第二章 無体物に付て
前述せし所に於て、吾人は或る物は自然的或は万民法的、或る物は公的、或る物は団体に属し、或る物は無主、其の他の物は各個人の有たることを述べたり。而て又諸種の方法によりて、物が吾人の所有となることを述べ、自然的方法として、次の如きものを説きたり。狩猟、捕獲、海浜にて発見せらるる石又は宝石、吾人の生物より生まれたるもの、寄洲作用、海中(これは稀なり)又は河中(これは屡々なり)に発生する島、取り残されたる河床への近接、製作物を以前の材料に還元し得ざるが如き、他人の材料を用ふる物の製作、自己と他人の材料による製作、他人の紫糸の己が衣服への織込、某二人の同種又は異種材料の所有者の意思又は偶然のはづみによる混合、幾多の所有者の穀粒の所有者の意思による混合(一人の希望、又は偶然のはづみにて発生せし場合は然らず)。尚幾多の設例に於て見たるが如く、上にあるものは下にあるものに従ふと謂ふ原則あり。例へば予が他人の材料を用ひて、予の土地に建築し、或は予の材料を用ひて、他人の場所に家を建て、或は何人かが他人の樹木を己が土地に、或は己が樹木を他人の土地に根を下すが如くに植えたるときの如し。尚此の原則は、蒔かれたる穀物、及び予の紙又は羊皮紙に記されたる文字に付ても適用あり。肖像に付ては反対なり。蓋し他人の画板は絵画に従へばなり。所有者に非ざる者より、土地を善意にて取得することも亦、自然的取得の中に入る。蓋し此の善意の占有は、彼【善意の占有者】を消費せられし果実の所有者となすに足ればなり。埋蔵物の発見も亦、区別に従つて、全部又は一部を発見者に帰属せしむ。引渡による取得も亦、自然的取得なり。然れども是等は、総て有体物に付て説かる可し。
一 物の中、或るものは有体物、他のものは無体物(有体物とは、名称によりても認識せられ、接触看視を受くる物にして、例へば土地、家屋、衣服、奴隷の如し。無体物とは、悟性によりてのみ認識せられ、接触も看視も受けざる物なり)たるが故に、有体物に付て述ぶる所ありたる吾人は、更に無体物に付ても述ぶ可し。無体物とは権利に於て成立するもの、例へば相続権の如し。然らば相続権とは何ぞや。或る方法によりて成立し、悟性を以て把握せらるる或る種の権利にして、予をして一時に、他人の所有権【一本の「財産」の方優らん】の所有者たらしむるものなり。用益権も亦然り。用益権とは、或る方法によりて成立し、悟性によりて把握せらるる或る種の権利にして、予をして他人の所有権に対し、使用及び収益を有せしむるものなり。尚債権も亦然り。如何にして成立せしめられたるものなるかを問はず。蓋し債権成立の方法は、下にも学ぶが如く、多岐に岐ればなり。然らば債権とは何ぞや。債権とは法鎖にして、これによりて、為すことを要するそれぞれのものを為すことを、人が強制せらるるものなり。
二 何人も、相続権中には有体物が発見せらるとは謂ふ勿れ。相続権は、奴隷土地家屋更には書籍を含み、用益権は其の中に土地より採取する果実——これは有体物なり——を有し、債権よりして吾人に負はるる物は、多くは有体物なり。例へば土地奴隷金銭の如し。多くの場合と謂ひたるは、さきの所にて学ぶが如く、債権によりて、何等かの無体物を要求することも亦、屡々存するが為なり。即ち何人も相続権、用益権及び債権を以て、其れに包摂せらるるものが有体的なるの故に、有体的なりとは謂ふ勿れ。一体として他人の財産を取得し、他人の土地を収益し、債務を請求する権能を予に附与する権利が、無体的なること——仮令其の中に有体的なるもの包含せらるるにせよ——を、観察するを要せばなり。
三 無体物中には、所謂役権——一は建物役権他は地役権——も亦存す。然らば建物役権とは何ぞや。建物役権とは、或る方法によりて成立し、悟性によりて把握せらるる或る権利にして、これによりて、隣人〔の一方〕は〔他方の〕隣人の負担を甘受す。又地役権とは、或る方法によりて成立し、悟性によりて把握せらるる或る権利にして、これによりて隣地者〔の一方〕は〔他方の〕隣地者の負担を甘受す。尚此の外〔無体物には〕使用権もあり。然らば使用権とは何ぞや。ususとは使用なり。或る方法によりて成立し、悟性によりて把握せらるる或る権利にして、これによりては、予は唯他人の所有権の使用のみを有す。尚住居権もあり。住居権とは、或る方法によりて成立し、悟性によりて把握せらるる或る権利にして、これによりて、他人の家屋に住居する権能が予に附与せらる。使用権及び用益権とは別個のものなり。
第三章 役権に付て
吾人は先づ第一に、地役権に付て諭ず可し。地役権とは如何なるものなるか、其の定義は汝の知る所なるが故に、勢〔地〕役権の種類を述ぶる必要あり。地役権とは、例へばiter, actus, via, aquaeductusの如し。然らばiterとは何ぞ。例へば予土地を有し、汝も亦近接地を有せり。予予の土地に趣かんと欲するときは、多大の迂回を為さざる可からず。予汝に向ひて、予にiterを許容せられたき旨、即ち予が汝の土地を通行することを許されたき旨を乞ひたり。蓋しこれ予の土地に至る捷径なるが為なり。汝予に駄獣及び荷車を伴ひては通行せざることとして、予にiterを許容したり。然らばactusとは何ぞ。actusは、予汝に向ひて、駄獣及び荷車を伴ひて、汝の土地を通行することを予に許されたき旨を乞ひたる場合に存す。故にiterを有する者は、actusを有することなきも、——駄獣及び荷車を件ひて、通行することを得ざればなり——actusを有する者は、iterをも有す。単独にて通行すると、駄獣を伴ひて通行するとを問はず、共に可能なればなり。viaとは、予が通行し、駄獣をも通行せしむる或る権利なり。故にviaは、actusも亦有すると同一〔権能〕を包含す。然れども、他〔の部分〕には差異あり。それに付ては学説彙纂に於て学ぶ可し。aquaeductusとは、予が他人の土地を横ぎりて、水を引く権なり。例へば汝水の十分なる土地を有し、予も亦近接の土地を有するも、水を必要とす。予汝に向ひて、汝のもとに湧き出づる泉より、予の土地へ水を引くことを、予に許されたき旨を乞ひたり。汝予にこれを許容したり。此の役権をばaquaeductusと謂ふ。
一 吾人は建物役権を述ぶ可し。建物役権とは、建物に附着するものなり。それ故に羅馬の語にては、urbanorum praediorumと称せらる。総て家屋はurbana praediaと称せられ、仮令村に存するとも尚然るが故なり。然らば建物役権とは如何なるものなるか。予が隣人の負担を忍ぶことなり。下の如し。予家屋を有し、汝も亦隣接家屋を有せり。予汝に向ひて、予の梁木を汝の壁に貫通せしむることを、予に許されたき旨、或は予の屋根よりの雨水又は流水を、汝の家屋又は空地へ放流することを、予に許されたき旨を乞ひたり。或は又汝がかかる権利を、予の建物に対して有するとき、予汝に向ひて、汝が予の家屋又は予の空地に、汝の屋根よりの雨水又は流水を流さざる様にせられたき旨を乞ひたり。或は又予汝に向ひて、家屋を高くし、以て予の家屋の光線を妨碍することを得ざらしむ可き権利を、予に許されたき旨を乞ひたり。
二 地役権中には(此の問題に立戻ることを要す)予をして汝の土地に趣き、以て汝のもとに存する泉より、水を吸み取ることを得せしむ可きaquaehaustus、或は予が汝の土地に於て、予の家畜に水を飲ましめ、或は偶々多量の〔牧〕草存するが為に、同所に其の家畜を放牧せしめ、或は石灰を焼製し、土砂を採掘するが如きものも算入せらると、或る者は称す。これ適切なり。
三 上述したるものが、地役権又は建物役権と称せらるる所以は、土地又は建物なくしては、成立し得ざるが為なり。何故となれば、何人も建物又は土地を有せざる限り、建物役権又は地役権を取得すること能はざればなり。
四 隣人に役権を許容せんと欲する者は、約束及び問答口約によりて、これを設定することを得。役権の設定に関し、約束が為されたる後、取得せんとする者は、設定に付て要約して「汝は設定せられたる役権を守ることを約すか。若し守らざるときは、違約罰として、予に百金を与ふることを約するか」と称す。遺言に於ても亦、「相続人よ、予は汝が隣家の光線を妨碍することなからしめんが為、汝が建物を高くせざる可き義務を汝に負はしむ」或は「相続人よ、予は隣人が希望なるときは、其の梁木を汝の壁に貫通せしめ、或は隣人が雨水を汝の家屋に放流することを許容し、或は隣接地の者が汝の土地に対し、iter又はactusの役権を有し、或は其の土地より己が土地へ、水を引くことを許容す可き義務を汝に負はしむ」と謂ひて、其の相続人に義務を負はしむることを得。故に役権は、或は約束及び問答口約によりて成立し、或は遺言の中にて成立す。
第四章 用益権に付て
今や地役権及び建物役権の後をうけて、用益権に入る可し。上に於て用益権とは何ぞやに付き、如何に吾人が定義したるかは、汝これを了知す。而して他の定義を述ぶるは、脱線には非ず。用益権とは或る権利なり、それは予をして、他人の物に対し、其の元物が保存せらるる限り、使用及び収益権を有せしむ。用益権は無体物なれども、有体物を前提とす。故に有体物と共に、用益権も亦消滅するは必然なり。例へば予汝に、予の奴隷の用益権を設定したり。汝は用益権者にして、予は所有権者なり。奴隷が生存する間は、用益権は存続し、奴隷が死亡せば、用益権も消滅す。
一 用益権は所有権より分離せられ、幾多の方法によりて発生す。例をとれば例へば下の如し。予汝に予の土地の用益権を遺贈したり。相続人は予の土地の所有権を有するに反し、受遺者は用益権を有す。又反対に予汝に、deducto usufructu、即ち用益権を留保して、土地を遺贈したり。然るときは、受遺者は所有権を有するに反し、相続人は用益権を有す。或は又予汝に用益権を遺贈し、他の者に所有権を遺贈したり。是等は遺言に於ける場合なり。遺言無くして、人若し他人に用益権を設定せんと欲せば、約束及び問答口約によりて、これを設定することを要す。然れども用益権が永久に分離するが為、所有権が全く利用の余地なきに至るが如きことなからしめんが為、用益権が種々の方法によりて消滅し、以て所有権に復帰するは、普通一般に容認せらるる所なり。
二 土地又は建物の用益権のみならず、奴隷、駄獣其の他の物の用益権も亦設定せらる。但し使用自体によりて消費せらるる物は、これを除く。何故となれば、是等の物に対しては、自然の理によるも、厳正の理によるも、用益権は成立すること能はざればなり。然らばかかる物とは、如何なる物なるか。例へば葡萄酒オリーブ油穀物衣服の如し。金銭も亦是等の物に類す。蓋し使用自体、或は一人より他人へ移転することよりなる継続的交換によりて、或る意味にて消滅すればなり。而て是等の物には、用益権は発生すと謂ひ得ざるを以て、元老院議決が制定せられ、是等の物に付ても、或る方法によりて、用益権成立すと謂へり。何故となれば、若し何人か死亡に際して、予を相続人に指定し、汝に千金、或は千セツクスタリウスの葡萄酒、又はオリーブ油、千モヂウスの穀物の用益権を遺贈したるときは、汝受遺者は、金或は葡萄酒或はオリーブ油或は穀物を受取り、用益権の性質に反して、是等の物の所有者となる可し。何故となれば、用益権は他人の所有権に対して存するが為なり。然れども是等の物に対しては、法律上用益権は成立せざるが故に、是等の物に付ては、用益権の原則の破らるるは当然なり。【何故となれば、用益権は既に述べたるが如く、他人の所有権に対して存すればなり。】然れども汝は予に対し、若し汝が死亡又はcapitis deminutioを受くるが如きことあらば、汝が受取ると同量を、予に返還す可き旨の保証を提供す可し。是等は〔上に〕述べたる物に関するのみならず、他の物、例へば衣服或は果実、或は一言にして謂はば、使用が目的物を消費する場合にも適用あり。蓋し是等の物は、受遺者が死亡し、又はcapitis deminutioを受けたるときは、是等の物の評価額を返還す可き旨の保証を為すときは、受遺者の所有権に帰属し、其の評価額が返還せらるればなり(金銭に付ては、予は此の言を為す者には非ず。金銭は自体が他の物の評価なるが故に、評価せらるること無ければなり)。故にこれが立法を為したる元老院は、是等の物に対して、用益権を成立せしめたるに非ず。又かかることは不可能なり。唯保証の方法によりて、用益権の模倣物を案出したるのみ。
三 用益権は用益権者の死亡、最大及び中間の両capitis deminutio、一定の方法と規定の期間による不使用により消滅す。是等総ては、吾人の皇帝の勅法中に包含せらる。同じく用益権は、若し用益権者が所有権者に用益権を譲渡したるときにも消滅す。他人に譲渡するも、何等の効果を発生することなく、譲渡は無効なり。更に反対に、用益権者が所有権を取得したるときも亦、同じく廃止せらる。これを称してconsolidatioと謂ふ。用益権が所有権に結合せしめられて、同一人に帰するが為なり。若し又何人か家屋の用益権を有したるとき、家屋が火災に罹り、或は地震によりて倒壊し、或は老朽なるが為崩壊したるときは、用益権は消滅し、建物なき地所の用益権も、用益権者に保存せらるることなし。地所の用益権が同人に譲られたるに非ずして、家屋の用益権が譲られたるものなればなり。
四 上述の方法の一によりて消滅せし用益権は、所有権に復帰し、此の時より物の所有者は、物に対し最も完全なる自由を有す。即ち果実をも取得することを得。それ迄は果実を取得することを得ざるが故に、物に対して完全なる権利を有するものとは、観ぜらるることなし。
第五章 使用権及び住居権に付て
役権及び用益権の後に、使用権及び住居権を論ずるは順序なり。使用権は用益権と同一の方法によりて成立し、用益権と同一の方法によりて消滅す。
一 使用権より生ずる取得は、用益権のそれよりは少し。蓋し土地に対し使用権を有する者は、同所に生ずる野菜、果実、花、枯草、葉、材木にして、日用に十分なるものを使用するより以上のものを、有すること能はざればなり。使用権者は、土地の所有者に迷惑と観ぜらるることなく、又小作人にも妨碍にならざる程度に於て、土地に止まることを得。使用権を他人に売却し、又は賃貸し、或は贈与として譲ることは、同人には許されず。用益権者にも、是等総てのことを行ふことは、許されざればなり。
二 家屋の使用権を有する者は、下の程度の権能を有するものと解せらる。即ち同人自身のみが住居するも、他人には決して住居権を譲渡することはなし。友人を引入るることが、同人に許さる可きや疑問を生じ、多数学説は可能とせり。尚住居内に、己が妻子及び被解放者のみならず、奴隷同様に使用する他の自由人、例へば被雇傭者の如き者をも入るることは、同人に許さる。若し婦女に家屋の使用権が遺されたるときは、同所に夫と同居するは、何等支障なく同人に許さる。
三 若し奴隷の使用権が予に許されたるときは、予は同人の労働及び労務を利用することを得るも、他人に此の権利を移転することは禁ぜらる。駄獣の使用権が、予に譲られたる場合も同じ。
四 家畜例へば羊の使用権が、予に遺贈せられたるときは、乳も子羊も又それよりとる羊毛も、使用することは許さるることなし。是等のものは果実の中に含まれ、即ち用益権に属して、使用権には属せざればなり。羊の使用権を有することは、予に対しては、唯これを予の土地に駆りて、土地に肥料を与ふることにのみ寄与す。羊の肥料は土地を肥沃にして、生産的のものとなせばなり。
五 若し何人かに住居権が遺贈せられ、或は其の他の方法によりて成立したるときは、これ使用権とも用益権とも観ぜられず、一種独特の権利の如く解せらる。住居権を有する者が、これを他人に賃貸することを得可きや疑義を生じ、多数の法学者は反対なりしも、マールケルルスのみ賃貸を許したりしが、吾人の極めて敬虔なる皇帝の勅法制定せられ、疑を裁断し、マールケルルスの見解は、事情を綜合するに有用なるを以て、これを採用して、本人のみが住居するのみならず、若し希望なるときは、他人に賃貸することをも許容し給へり。
六 役権、用益権、使用権及び住居権の論述はこれにて足る。相続及び債権に付ては、然る所に於て取扱はる可し。吾人が如何なる方法によりて、自然的に財産を取得するか簡単に述べたれば、今や如何なる方法によりて、法律的市民法的権利によりて、他人の物が取得せらるることを得るかを論ずる必要あり。
第六章 時効取得及び長期占有に付て
自然的取得に論を進めたる吾人は、市民法的取得に付ても取扱ふ所ある可し。人若し自己の物を予に引渡したるときは、同人のもとにありたる所有権を移転するは、学説の一致する所なり。人若し他人の物にして、自己は所有者に非ざる物を、予に引渡したるときは如何。此の場合所有権を移転す可きか。吾人は決して然らずと謂ふ者なり。所有せざる物を、如何にして移転し得んや。然らば如何なることとなるか。彼が有したる占有【或は所持】は、これを予に移転す。而てこれ些細事には非ず。蓋し予若し善意にて物を受けたるときは(善意にてとは、売主、贈与者、其の他合法原因に基きて、例へ交換によりて、引渡を為したる者が、所有者なりと予の信ずることなり)古くは其の物が動産なるときは、予がイタリアに住すると、県地に住するとを問はず、一年を経過せば、予は所有者となり、若し不動産なるときは、二年を経過せば、土地又は家屋がイタリアに存在する場合に、予に時効取得せられ、予の所有権に帰属したればなり。これ十二表法の命ずる所なり。而て何人も、一方は取得時効によりて所有者となり、他方は己が所有物を奪はるるが故に、此の法律を不当なりと考ふ可からず。何故となれば、物の毀滅を無からしめんが為、此の制度は案出せられたるものなればなり。蓋し各人皆其の占有する物が、自己に属するや否やを知らず、他日真の所有者が出現して、其の物を持去ることを恐れて、其の物に注意を用ひず、かくの如き考慮よりして、人間は怠惰となり、人間が怠惰となれば、物は等閑に附せられたる侭となり、物が等閑に附せられたる侭となれば、該物に起るものは、恐らくは消失と損壊なりしなる可し、故に十二表法はかかる人間の心裡を目標として、動産に付ては一年の期間を定め、不動産に付ては二年を定め、該期間内に所有者が現はれざるときは、該物は占有者のもとに止まりて奪ふ可からず。所有者には怒る資格なし。同人には一年又は二年の期間は、自己の物の捜索に足ればなり。然れどもこれ十二表法の規定なり。吾人の皇帝は、更に一層善良博愛的なる思慮を用ひ、短期間の中に所有者が自己の物を奪はるることなき旨を規定し、且其の恩恵を定所に局限することなく、これに関する一般的なる勅法を発布し、其の勅法の中にて、動産は何処に於ても、三年経過せば時効取得せらる可く、不動産は長期の所持によりて、即ち所有者が現在するとき十年、不在なるときは二十年経過せば、時効取得せらるる旨を命じ給へり。例へば汝、チチウスに属する土地又は家屋を予に引渡し、予は汝が所有者なりと信じ、故に善意にて物を受けたり。若しチチウスが現在するときは、予の時効取得には十年を以て足る。若し不在ならば二十年なり。これイタリアに存する不動産に止まらず、往時上納的及び貢献的と称せられたる県地に付ても、其の他帝の主権に服するあらゆる土地に適用ある可き旨を立法し給へり。尤も常に善意の占有の先行するときのことなり。
一 吾人は善意占有者は時効取得をなすことを得可き旨を説きたるも、時効取得の吾人の役立たざる場合を発見することも得可し。例へば若し自由人、或は神聖物或は宗教物を占有するときの如し。時効取得は所有権を取得せしむるものなるに、是等の物は所有の上に在るものなれば、従つて当然に時効取得に服せず。若し他人の逃亡奴隷を占有する場合も、同様と考ふることを要す。蓋し時効取得の下に在らざればなり。
二 盗品及び暴力による占有物も、仮令十年又は二十年経過し、予又善意にて占有するとも、時効取得を許さず。然れども盗品は動産に関し、暴力による占有物は不動産に関すと解す可し。盗品の時効取得は、十二表法及びアチーニア法これを禁止し、暴力による占有物は、ユーリア法及びプラウチア法これを禁止したり。
三 人若し物を占有する某は、時効取得することを得可きや否やを、汝に質すときは、汝は先づ善意又は悪意にて、占有するか否かを詮議することを要す。而て若し善意なることを知りたるときは、直に第二の詮議を急ぎ、物が神聖物にも、宗教物にも、自由人にも、盗品にも、又は暴力による占有物にも非ざるかを詮議す可し。而て若し是等の一を発見せしときは、事物に存する瑕疵故に、時効取得は発生せずと謂ふ可し。さて盗人又は強奪者は、時効取得を為すことを得可きか。汝は或は早まりて、均しく盗品又は暴力による占有物なるが故に、事物に存する瑕疵の故を以て、然らずと謂はん。然れども汝はかくの如き言を為す可からず。そは順序を忘れたるものなればなり。然らずして、汝はそれよりも先の理由、即ち悪意にて占有するが故に、時効取得は発生せずと謂ふことを要す。自ら盗品又は暴力による占有物なることを知ればなり。若し強奪者又は盗人が、他人にこれを引渡し、同人が善意にて受取りたるときは、最初の解決点に基く限り、物を所持する者は善意にて占有するものなれば、時効取得は阻碍せらるることなし。唯事物に存する瑕疵故に、成立を妨げらる。蓋し盗品又は暴力による占有物なればなり。然らば盗品とは何ぞ。盗品とは夜中又は日中、密かに取去られたる物のみならず、総ての他人の動産にして、所有者の意思に反して、領得せられたる物なり。而て領得とは、物に関して所有者の如く立ち廻り、其の物に対して、所有者に相応の行為を為すことを謂ふ。今述べたる所が若し真ならば、他人の物は決して時効取得せらるることを得ず。何故となれば、他人の物を占有する者は、所有者の意思に反して領得し、所有者の意思に反して領得するときは、物を盗品と化し、盗品なるときは、時効取得は阻碍せらるればなり。〔故に上の〕定義には欠けたる所あり。それに尚悪意にての語を附加し、盗品とは夜中又は日中、密かに取去られたる物のみならず、総ての他人の動産にして、所有者の意思に反して、悪意にて領得せられたる物なりと謂はざる可からず。かくの如く定義して完全なり。
四 然れども此の語を附加するも、尚時効取得の発生せざるを吾人は発見す。蓋し〔かくては〕何等か他人の物を、其の所有者の意思に反して占有する者は、悪意にてこれを領得し、該物を盗品に化することとならん。然れどもこれ真実には非ざるなり。或る者他人の物を、其の所有者の意思に反して領得し乍ら、同人が悪意を欠く為、盗とならざる場合も是認せらるればなり。例へば例を採れば次の如し。予チチウスに予の書を貸与し、或は同人に予の奴隷を賃貸し、或は同人に予の円盤を寄託したり。同人汝を相続人として死亡したり。汝是等の物を遺産中に発見し、これを相続財産なりと信じて、或る善意取得者に売却し、又は贈与し、或は嫁資に与へたり。此の場合、他人の物を、且其の所有者の意思に反して、汝は領得するも、尚其の物は盗品となることなし。悪意なければなり。故に取得者は疑も無く、其の物を時効取得す可し。善意にて占有し、且其の物には瑕疵無ければなり。善意にて売りたる相続人が、盗を犯すとは謂ひ得ざればなり。
五 尚他の例に付ても、此のことを発見することを得。予汝に予の女奴の用益権を許容したり。女奴の用益権〔の内容〕は、同人の手による取得及び同人の労務なり。同女汝のもとにて子を生みたり。該児が、上に於て吾人が述べたる所に従ひ、所有者たる予に帰属すること明かなり。女奴の生みたる子は、用益権者たる汝に帰属するものと考へて、汝これを売却又は贈与したり。見よ此の場合に於ても、所有者の意思に反して、汝は行動したるも、汝には悪意なきが故に、其の行為によりては盗が犯さるることなし。蓋し一般に、盗は悪意なくしては犯さるることなきことを汝は知ることを要す。如何となれば、盗は盗の意思なくしては、犯さるること無ければなり。
六 予は汝に極めて稀なる例を述べたるも、事物の状態は、他人の物を其の所有者の意思に反して譲渡しながら、而も該物は盗品とならざることの判明する場合の多数を、指摘することを得。
七 上に述べたる所は盗品に関す。暴力による占有物は、何人か予に迫り、暴力を以て、予を予の土地又は予の家屋より追払ひたる時の、実際の腕力よりして判断せらる。これに反して盗品は、法律の規則よりして了解せらる。故に予若し腕力を以て、汝を不動産より追払ひたるときは、予は此の物を時効取得することを得ず。悪意を以て占有すればなり。然れども、予より善意にて他の物を受取りたる者も、物に存する瑕疵故に亦同じ。蓋し暴力による占有物なればなり。予に若し実際の腕力の汚無きときは、予より善意にてこれを受取りたる者は、時効取得を為すことを得。然らば〔かくの如きことが〕如何にして発生するかを述ぶる必要あり。某土地を有したり。外に出でて、これを等閑に附したる侭か、或は現在するも、土地に注意を払ふことなし。或は又某無遺言にて死亡し、何人も皆同人の財産を取得する者なし。予土地が何人にも所持せられざるを見て、其れを所持したり。如何なる理由によるも、予はこれを時効取得することを得ざる可し。其れが他人の物なることを知りて、悪意にて占有すればなり。然れども予若しこれを、善意にて受取りたる他人に引渡したるときは、時効取得は発生し、長期の期間は、既に述べたるが如く、同人に所有権を取得せしむ。何故となれば、最初の解決点は、時効取得に障碍となることなし。善意にて占有すればなり。他の解決点も亦然り。物には瑕疵なければなり。然れども人ありて、該物は盗品となると謂ふ者あらん。蓋し予は物が他人の物なることを知りて、これを譲渡したるものなれば、予は此の土地を盗品に化するを以てなりと。然れども此の理由は愚劣なり。盗は不動産に付ては、犯さるること無ければなり。蓋し不動産に付て、盗の犯さるることを認むる法学者の見解は廃止せられ、市民法よりも駆逐せられたればなり。又此の物は暴力による占有物にも非ず。腕力の実行伴はざればなり。故に残るは唯善意取得者が、長期且疑を受くることなかりし占有は、何人よりも奪はるることなき旨を宣言する勅法の保護を受けて、十年又は二十年を以て、土地の所有者となることのみ。
八 吾人は盗品及び暴力による占有物は、時効取得せらるることを得ざる旨を述べたり。然れども是等の物も、時効取得に服する場合もあり。例へば所有者の所持に復帰したるときの如し。蓋し其の場合には、取り纏はれゐたる瑕疵より解放せられて、時効取得に服すればなり。例へば汝チチウスの奴隷を盗み、或は腕力を以て同人の土地を奪取し、予に売却せり。時効取得の権利は阻止せらる。偶々其の中占有が、予より所有者チチウスに移転したり。該物は直ちに、盗品又は暴力による占有物たることを已む。故に其の後予の所持に服するときは、何等支障なく時効取得せらる可し。
九 次のことを予備知識として保持す可し。人若し遺言を作成して死亡するときは、被指定者は相続人として、同人を相続す。若し無遺言なるときは、同人の相続財産は、若し生存するときは同人の子、若し存せざるときは宗族が趣きて、相続人となる。宗族存せざるときは血族が又遺産占有者となる。上に述べたる者存せざるとき、或は相続を欲せざるときは、遺産は相続人曠欠となり、国庫に取得せらる。而て死亡者に対して物的、人的の訴権、或は抵当訴権を有する者は、如何なる訴権にせよ、これを四年の中に、国庫に対し提起す可し。汝に予め是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。吾人は上に於て、盗品及び暴力による占有物は、時効取得せらるることを得ざる旨を述べたり。此の外尚時効取得を許さざる他の物を発見することを得。例へば国庫に属する物は、時効取得せらるることを得ず。然れどもパーピニアーヌスは、人若し相続人なくして死亡し、同人の財産が相続人曠欠となるも、其の財産が国庫に通知せらるる以前に、何人か該財産中の或る物を、善意の買主たる予に売却して引渡したるときは、時効取得は発生すと謂へり。国庫は財産を受けざるが故に、未だ該物は国庫に属する物とはならざればなり。これピウス皇帝のみならず、至聖のセウェールス及びアントーニーヌスの解答し給ひし所なり。
一〇 最後として、下のことを知ることを要す。正に時効取得せられんとする物は、下の如くならざる可からず。即ち総ての瑕疵なく、該物が善意にて買求められ、或は贈与によりて受領せられ、或は其の他の原因に基きて取得せられたることこれなり。
一一 更に占有の原因は、真実なることを要す。真実に非ざる原因の錯誤は、時効取得に発生の余地を与ふることなし。例へば予物を占有し、これを買求めたるものと思雅したるも、実は買求めたるには非ず、或は又贈与物に非ざるときに、該物は予に贈与せられたるものと思惟したるが如し。占有に対する考が誤れるが故に、時効取得は阻止せらる。
一二 某善意にて他人の土地を占有し、所有者となるには、長期の期間を必要とせり。八年或は九年の後、市民法上の相続人、或は法務官法上の承継人を遺して死亡したり。かくの如き相続人又は遺産占有者は、残余期間占有せば、仮令其の土地が他人の土地なることを知るも、其の財産を有して奪はるることなかる可し。蓋し善意にて開始せられたる占有を、承継人の悪意が破壊すること無ければなり。若し反対に、何人か悪意にて他人の土地を占有したるときは、同人の相続人又は遺産占有者は、仮令土地が他人の物なることを知らずとも、占有が死亡者によりて悪意に開始せられたるの故を以て、援護せらるることなし。此の長期の期間に関する原則をば、吾人の最も神聖なる主の勅法は、時効取得にも拡張し、死亡者によりて善意に開始せられたる動産の占有は、時効取得の完成及び其の期間の継続に対し、仮令自身は他人の物なることを知るとも、承継人に利することとせり。又反対に、死亡者が悪意に占有を開始したるときは、善意の占有も相続人を援護することなし。
一三 又人若し善意にて他人の物を買ひ、或る期間占有し、然る後売却し、売主より買求めたる者も亦占有したるときは、各両人の占有期間を通算したるものが、第二の買主に物の所有権を取得せしむ。これセウェールス及びアントーニーヌスの解答し給ひし所なり。
一四 マールクス皇帝の勅法が、告示の形に於て制定せられ、国庫より他人の物を買求めたる者は、五年を経過するときは、物の所有者となると宣言し給へり。此の告示は、買求めたる物を、五年よりも短期間にて所有すること能はざる者にとり必要なりき(例へば偶々盗品なるが故に)。而て五年の期間の後は、買主が訴へらるるも、抗弁を以て訴人を排斥したり。然れどもこれ至聖のマールクス帝に付てのことなり。至聖のゼーノン帝の勅法発布せられて、国庫より買受けたる者、或は贈与又は交換によりて受取りたる者は、直ちに何等の懸念を有せず、訴へらるるにも訴ふるにも、同人は好地位を取得し、唯物の所有者は、四年迄は国庫に対して訴権を有する旨を宣言せり。該勅法は是等の規定を単に所有権のみならず、抵当権に付ても亦立法し、其の結果四年の後は、国庫によりて譲渡せられたる物に対しては、所有者も物的訴権、債権者もセルビアーナ訴権を保存することなし【此処Frégier p.238の仏訳は誤訳ならん】。更に最近制定せられたる吾人の皇帝の勅法発せられて、帝の稜威、或は吾人の最も敬虔なる皇后より賜はりたる物に付ても、ゼーノン帝の勅注が国庫の物の譲渡に付て規定し給ひし所と同一の規則の適用を欲し給へり。
第七章 贈与に付て
他の取得方法としては、尚贈与のそれあり。これに付て論述する必要あり。吾人は上に於ても、既に論述を進むる間に、此のことに触れたるも、今やこれに関する完全なる説明を行ふ可し。贈与に二種類あり。一は死因と呼ばれ、他は生前と称せらる。
一 死因贈与とは、死亡を予想して為さるるものなり。例へば人若し危険なる航海を為し、或は野獣追剥又は敵人の跳梁する道を採らんとして、何人かに贈与するが如し。若し贈与者に、何等か人間に常なる事変発生したるときは、受贈者をして奪ふ可からざる贈与を受けしめんが為なり。若し受贈者が贈与者に先ちて死亡したるときは、贈与者は贈与物を取戻すことを得。若し贈与者が意思を変更するときは、受贈者が先に死亡したるときと同じく、贈与を取戻す可し。是等死因贈与は、総てを通じて遺贈に類似す。往時法学者の間に、贈与に類似するか、又は遺贈に類似するかの或る疑義存したり。而て双方の学説——贈与とするものと、遺贈とするもの——ありて、或る者はこれは贈与に類似すと謂ひ、他の者は遺贈に類似のものなりと謂へり。此の論争を解決する吾人の皇帝の勅法発布せられて、殆んど総てに付て、これを遺贈と同一となす可き旨を宣言し給へり。「殆んど」と予は謂へり。これ生存者より生存者に対して為さるるが故なり。これより神聖なる勅法の述ぶる所に従ひて、後を追ふ可し。先づ第一として、贈与の相手方よりは、自己自身が所有することを欲し、且又己が相続人よりは、むしろ贈与を受けたる者によりて、目的物が取得せらるることを欲するとき、死因贈与なり。聖なるホメーロスはオヂセーイアに於て、かかる贈与をペイライオスに対して行ふテレマツコスを、下の如き句を以て描写せり。曰く「ペイライオスよ、事態は果して何処に趣くか、吾等は何等知る所なし。武勇を気取れる求婚者が、殿中にて密かに予を殺し、祖先伝来の全財宝を其の間に分配せんには、予は彼等の何人よりも汝をして、これを所有せしめ、其の楽を享けしめんと欲す。然れども予若し彼等に殺害と悪運を起さしめなば、喜びて家に持来り、喜溢るる予に引渡す可し」と。
二 死因贈与に付て学ぶ所ありたる吾人は、他の贈与——これ生前の贈与なり——に付て述ぶ可し。これは何等死亡者の意思存せずして行はれ、遺贈に類似することなし。これが完成すれば、濫りに取消すことを得ず。而てこれは贈与者が文書を以て、或は又文書によらずにして、自己の意思を明かにしたる場合に完成せらる。而て売主が売りたる物の引渡を強制せらるるが如く、吾人の皇帝の勅法は、贈与に対し完全〔なる効力〕を附与して、仮令引渡を伴はざる場合にも、贈与を希望する者に対しては、常に贈与の目的物の引渡を強制す。而て吾人の極めて敬虔なる皇帝は、贈与を受くる者の為に、此の規定を発案し給ひたるのみならず、或る他の規定を附加し給へり。蓋し以前の諸皇帝は、若し贈与が二百金を越ゆる場合には、登録の実行を以て贈与を明かにす可き旨を命じ給ひしが、同帝は五百金迄は、其の贈与が未登録なる場合も、有効とし給ひたればなり。但し帝は登録実行の必要なしと宣へる或る種の贈与を認め、かかる贈与は五百金の額を越ゆる場合たりとも、効力を有す可き旨を命じ給へり。此の外尚帝は広く贈与の成立を認めて、効力を有せしめんが為、幾多の規定を発案し給へり。是等の総ては、同帝の神聖なる勅法に触るる者、これを発見することを得。次のことはこれを知ることを要す。即ち上記の方法に従ひて為されたる贈与は、其の効力を有す可しと雖も、贈与を受けたる者が、若し恩恵者に対して忘恩者たることが示されたるときは、吾人の皇帝の勅法は、忘恩行為と目す可き諸種の原因によりて、これを取消す権能を附与し、何人たりとも、自己の物を恩恵の為他人に移転したる者が、受贈者よりして、何等かの侮辱又は損害を被ること無からしめ給へり。忘恩行為の方法並びに贈与を取消す可き訴権は、上記の勅法を読む者、これを学ぶことを得。
三 尚他の種類の生前贈与あり。これ法学者には未知のものにして、法学者より後の皇帝の勅法が、新に移入したるものなり。これ婚姻前の贈与と称せらる。而てこれ許嫁の男子が、女子に対して為す所にして、其の中には、婚姻がこれに伴ひし場合に、初めて効力を有すとの暗黙の条件を包含す。婚姻前の贈与と称せられたるは、それが同棲の成立前に行はれ、婚姻後には決して行はるることなかりしによる。蓋し婚姻成立中に、夫婦の間に為されたる総ての贈与は、一般に禁止せられたればなり。然れども神聖なる故ユスチーヌスの勅法制定せられ、古の法学者によりて、婚姻成立中に嫁資を増加することが許され、従つて若し偶々百金の嫁資を与へたる場合には、婚姻成立の時より後たりとも、妻が其の欲する額の金銭を与へて、嫁資を増額することを得、何人もかかるものは、これを贈与と呼ぶことなかりしが如く、婚姻前の贈与も亦、夫がこれを増額することを許し、以て一方が増額する場合には、他方にも亦同一事を実行することを得しむることとせり。然れども勅法がこのことを欲し、婚姻前なる名称は其の制度に不適当となりたるが為——婚姻後に為されしものが、婚姻前と称せられたればなり——吾人の極めて敬虔なる皇帝は、立法の完全無欠なる可きことを欲し、名称が実体に適合したるものたることに努力し給ひて、かくの如き贈与は、婚姻成立して後これを増加するのみならず、初めてこれを設定す〔ることを得〕可く、これを婚姻前のとは称せずして、婚姻故のと呼ばる可き旨を宣言して、例へば予が若し貧困なるが為、或は其の他の原因によりて、妻に対して婚姻前の贈与を為すことなくして結婚し、今これを設定せんと欲するときには、事情は予にとりて何等支障なき旨を規定し給へり。これによりて今や婚姻前の贈与は、嫁資と均調を保たる可し。而て嫁資を婚姻成立後に増加するのみならず、〔初めて〕これを与ふることも可能なるが如く、婚姻故に為されたる贈与も亦、婚姻に先ちて行はるるのみならず、其の成立後に於ても、部分的に行はることを得可く、其の時に初めて為さるることも得可し。
四 吾人は、取得時効によるものと、長期占有によるものとは、法律的取得なることを述べたり。人若し探求するときは、他の古き法律的取得方法を発見す可し。これ即ち添加によるものなり。これは次の如くにして行はる。甲とチチウスは共有の奴隷を有したり。甲はチチウスの意思に反して、共有奴隷を棍棒により、或は又遺言の中にて解放したり。市民的立法は、かかる設例に於ては、甲は何物をも為すことなく、奴隷を奴隷状態より解放することなきのみならず、彼に対して有せし共有部分をも失ひ、此の失はれたるものは、添加権に基きて、チチウスに帰属し、終局にはチチウスのみが同人の所有者となる可き旨を命じたり。然れども、奴隷も自由の当はづれ、自己の奴隷に対し或る恩恵を欲する主人も損害を受くるに反し、彼に対し憐憫の情を垂れて、奴隷状態より解放することを欲せざる者は、自己に奴隷の持分添加するが為、利得を為すは、最も悪き例なりしが為、吾人の極めて敬虔なる皇帝は、かくの如きは憎悪に充つるものと決定し、軫念を用ひて神聖なる救済の道を発見し給ひ、これによりて、解放したる甲も、同意せざるチチウスも、自由を得たる奴隷も、同帝の勅法に感謝の意を表することとなれり。蓋し帝は、古立法者も通則に反して、幾多自由に与する解決を発案したることなれば、奴隷は全く自由人となり、甲は同人より与へられたる自由が、効力を保持することに対して満足し、共有者は、同人が奴隷に対して有する共有部分に応ずる代価が、同立法に規定せられたる所に従ひて、解放者より同人に返還せらるるを以て、損失より保護せらるる旨を命じ給ひたればなり。
第八章 何人は譲渡し得又は得ざるか
これより所有者が自己の物を譲渡することを得ず、又所有者に非ざる者が、自己の有に非ざる物を、適法に譲渡することを得る稀なる場合を蒐集する必要あり。而て吾人は先づ第一に、何時所有者は譲渡することを得ざるかを述ぶ可し。例へば或る婦女が男子と結婚し、嫁資の名目を以て種々の物を与へ、且引渡によりて、同人を全嫁資の所有者と為したり。かかる男子は、嫁資の中にて同人に与へられたる物全部を、所有者として譲渡し、受取人に所有権を移転するも、嫁資なる土地丈は、仮令夫が所有者なりと雖も、ユーリア法其の譲渡を禁止す。然れどもユーリア法は、唯イタリアに存する不動産のみが、妻の意思に反して、夫より譲渡せらるることを禁止し、これを担保の目的に供するは、妻の同意あるも夫は不可能なりき。然れども物の移転ある譲渡は、妻の同意あるときは有効に為し得るに、所有権は依然として夫のもとに存する抵当権の設定は、意思に従ふも尚これを為すことを許さずとは理に合せざるものと観ぜられたり。然れども吾人は、同法は次の如き念慮に動かされて、かかる結果に到着したるものなることを述ぶるものなり。即ち法律は、夫が妻に対して嫁資財産の譲渡を口にするや、同女これを聴きて驚愕し、同意に堪えざることとなる可きを知る。然るに若し夫が抵当権に関して何等か謂ふ所あらば、妻は容易に説伏せらる可し。恐らくは抵当権の危惧は、其の立法によりて担保せられたるも、譲渡の危惧は、妻の苦悩に任ぜられたるならん。ユーリア法は妻の意思に反する譲渡を規定するも、抵当権は妻の意思に従ひて為されたる場合たりとも、これを禁止し、而てこれはイタリアに存する不動産に関してのみ適用ありたり。吾人の皇帝は、極めて有要なる念慮によりて、二個の点を変更し給へり。蓋し帝は、女子の性格の不健全が、其の財産に消滅を来すこと無からしめんが為、イタリアに存する土地のみならず、県に存する不動産に付ても亦、嫁資財産の譲渡及び抵当は、仮令妻が同意するも、夫に禁止せらる可き旨を命じ給ひたればなり。
一 今や何時所有者に非ざる者が、譲渡し得るかを述ぶることを要す。これは次の如き設例に於て発生す。予汝より百金の貸与を受けたり。予汝に対し、一年を経過するも、予債務を履行せざるときは、質物を売却することを得可き旨を約して、予の土地を担保に供したり。見よ此の場合には、債権者は所有者ならざるも、適法に譲渡す。然れども人若し精密に観察せば、何等理に反するもの存することなし。蓋し約束によりて、債権者に対し、債務の履行に関する懈怠ありたるときには、売却を許すことによりて、所有者たる債務者が売却するものと観ぜらるればなり。然れども古くは、債権者は或る種の方法を有し、これによりて抵当物又は質物の売却は、彼等に許されたり。然るに吾人の皇帝の勅法制定せられ、これは貸主が債務の請求を妨げらるることを欲せず、借主も亦早急且何等の審査なくして、自己の物を失ふことも欲せざりき。即ち或る譲渡の方法を発案し、此の方法によりて、質物の売却が行はるることを得ることとなれり。此の勅法は、借主及び貸主双方に、恩恵を与へたり。これが実行せられ得可き方法は、該神聖なる立法を読む者、これを知ることを得。
二 尚其の他の所有者にして、物を譲渡することを得ざる者を発見することを得。例へば未成熟の男子又は女子は、後見人の助成なくしては、自己の物を譲渡することを得ず、従つて又金銭を貸与することもなし。これ何の意なるか、述ぶる必要あり。次のことを予備知識として保持す可し。消費貸借の定義をあぐれば、受領者が所有者となり、物自体に付て、吾人に拘束を与ふものに非ずして、同種同量に付て、拘束を与ふるものなることこれなり。受領者が所有者となると謂ひたるは、使用権及び寄託を避けんが為なり。是等に付ては、受領者は所有者となることなければなり。吾人に拘束を与ふると称したるは、贈与を避けんが為なり。贈与に付ては、受領者は拘束せらるることなし。物自体に付てに非ずして、同種同量の他の物に付てと謂ひたるは、消費貸借の効用を除外せざらんが為なり。蓋し若し借主が、受けたる所と同一の物の返還を強制せられたらんには、消費貸借は無駄なる可し。消費貸借は総ての物に為さるる訳に非ずして、重、数、量の物に為さる。重の物とは、例へば金、銀、鉛、錫、臘、銅、瀝青、其の他類似の物の如し。数の物とは、数の中に存する物、例へば小貨幣の如し。量の物とは、例へば小麦、大麦、其の他類似の物の如し。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余の物を見よ。吾人は未成熟者は後見人の助成なくしては、自己の物を譲渡し得ざる旨を述べたり。彼後見人の意思に反して、消費貸借を為したるときは如何。消費貸借は有効なる可きか。吾人は決して然らずと謂ふ者なり。蓋し仮令〔一般的には〕消費貸借に付ては、受領者は所有者となると雖も、此の場合には然ることなし。未成熟者は後見人なくしては、譲渡することを得ざればなり。故に消費貸借も成立することなく、受領者も拘束せらるることなし。然らば如何なることとなるか。未成熟者は自ら貸与したる金銭の恢復に、物的訴権を有す可し。然れども、これ貨幣の明かに識別し得るときのことなり。若し悪意にて受領する者、即ち貸主が未成熟者なることを知れる者が、これを消費したるときは、提示訴権の拘束を受く可し。即ち明白なる物には、物的訴権が提起せられ、隠匿されたる物、又は悪意にて消費せられたる物には、提示訴権発生す。若し善意にて、即ち借主が貸主を成熟者と考へたるときに消費せられたるときは、物的訴権は提起せらるることを得ず。蓋し貨幣は明かならざればなり。提示訴権も提起すること得ず。蓋し貨幣は隠匿されたるにも非ず、悪意にて消費せられたるにも非ざればなり。然らば未成熟者には、何等法学者の〔建てたる〕原則に基く訴権無きが為、折角未成熟者の為に移入せられたる法律が、同人に損害を与ふるものとなるが如きことなからしめんとせば、如何にす可きか。残るは唯同人に、condictioが与へらるるのみ。而て金銭の支払が発生せしめざりしもの、——即ち消費貸借の成立、及び借主のcondictioの責任負担——は、善意の消費がこれを発生せしむ。蓋しこれよりして、condictio生まるればなり。若し、反対に、何人か未成熟者に、後見人の助成なくして、物を与へたるときは如何。未成熟者は所有者となる。蓋し法律は、同人が後見人の助成なくしても、其の財産を増加するに対しては、何等妬むことなければなり。然らば未成熟者の債務者が、同未成熟者に金銭を履行したるときは如何。未成熟者が履行せられたる物の所有者となるは、学説の一致する所なり。然らば債務者は債務より解放せらる可きや否や。吾人は決して然らずと謂ふ者なり。蓋し吾人若し債務者は解放せらると謂ふときは、未成熟者は後見人の助成なくして、債務を受けたることによりて、債権を譲渡する者と解せらるるも、かかることは禁ぜらるる所なるが故なり。故に債務の履行にも、後見人の同意は必要なり。蓋し若し同人の意思に反して、履行せられたるときは、債務者は解放せらるることなければなり。而てこれをば、吾人の至虔の皇帝は抜群の司法大臣ツリボーニアーヌスの暗示のもとに、カイザレイアの弁護士に対して解答し給ひし、極めて聡明なる勅法の中にて規定し、同勅法に於て、未成熟者の〔相手方たる〕債務者は、先づ履行を許可する裁判官の判断を無料にて下附せしめて、同人の後見人又は保佐人(蓋し汝は未成熟者も亦、保佐に服することを知ればなり)に、弁済することを要することを命じ給へり。かかる手続を践みて、裁判官が宣言し、債務者が履行するときは、履行者は債務より解放せらるるを以て、損害を受くることなし。若し上記の規定に反して、債務の履行が行はれ、而て履行せられたる金銭が、未成熟者のもとに保存せらるるか、或は受領者これを消費し、同人又は同人の財産が利得を為したるときは(蓋し時に家屋を建築し、或は自己の土地を肥し、或は教師に謝礼を交付し、或は債権者に履行したるが如きことあらん)、依然として均しく未成熟者は債務者に対し、有効なる訴権を有す。然れどもこれを提起して、債務を請求せんと試みるときは、悪意の抗弁によりて排除せらる可し。若し金銭を受領して濫りに浪費し、何等の増加なかりしとき、或は該金銭に付き盗難に遭ひたるときは、債務者に対し新に債務を請求す可し。何等の抗弁対抗せらるることなし。蓋し債務者は、早急に後見人の助成なく、且吾人の皇帝の勅法の規定に従はずして、弁済を行ひたるものなれば、敗訴判決を受くるは、疑を容れざる所に属すればなり。未成熟者は後見人の助成なくしては、履行することを得ず。蓋し彼等は後見人の助成なくして、其の財産を譲渡す可き自由を有せざるが故に、受領者に所有権を移転することなければなり。然らば履行し、受領者を貨幣の所有者となすことなきが故に、債務より解放せられざるときは、如何に為さる可きか。吾人は其れが明かなるときは、物的訴権を有す可く、隠匿されたるとき、又は悪意にて消費せられたるときは、提示訴権を有す可き旨を述べたり。若し善意にて消費せられたるときは(蓋し債権者彼等を成熟者と考へてこれを消費したればなり)該物は明かならざるが故に、物的訴権は存せず、悪意の消費が行はれたるにも、其の物が隠匿されたる訳にも非ざれば、提示訴権もなきを以て、唯結果の上よりして、未成熟者は債務より解放せられ、後見人の助成なくして為されたる弁済が実行せざりしものをば、善意の消費がこれを完成する訳となる。
第九章 何人によりて吾人に取得せらるるか
物にせよ、訴権にせよ、其処に於て述べたるものは総て、吾人によりて吾人に取得せらるるのみならず、吾人が権力中に収むる者、吾人が用益権を有する他人の奴隷、及び自己の奴隷と考へて、吾人が善意に占有する自由人、及び他人の奴隷によりても亦、取得せらる。吾人は其の各々に付て慎重に観察す可し。
一 第一に権力に服する吾人の子は、男子たると女子たるとを問はず、吾人の為に取得す。然れども古くは、軍営特有財産を除き、総て彼等に到達したる物は何物たりとも、彼等を権力服従者として保有する吾人の為に取得し、而て子によりて取得せられたるものが、尊属に属する有様は、一人の息又は一人の娘によりて取得せられたる物を、他の子又は他人に、贈与売却其の他の方法によりて移転する等、あらゆる権限が同人【尊属】に備はる程なりき。吾人の極めて敬虔なる皇帝に、非人道的と観ぜられたる此の制度は、一般的勅法によりて然る可き保護を受け、これによりて子にも惜み、父にも亦負はる可き物を保護し給へり。蓋し同帝は、若し父の財産によりて、何物かが権力服従者の得る所となりたるとき、例へば父が贈与を為し、或は其の他の方法によりて、同人に譲渡したるときは、当初よりの原則適用あるものとして、全部父に取得せらる可く(蓋し父の原因に基きて、同人(子)に到達したる物が、再び父に復帰するは、妬む可きことに非ざればなり)、若し他の原因よりして、権力服従者が取得したるときは、これが用益権は父に取得せらるるも、所有権は子のもとに止まる可き旨を命じ給ひたればなり。蓋し若し多大の労働又は幸運の働きによりて、何人かに到達せし物を他人に与へて、初めて取得したる者に対し、嘆の原因を起すは、不当なればなり。蓋し取得せられざる物は、取得後奪はれたる物程には、人を悲しますことなければなり。
二 吾人の極めて敬虔なる皇帝の勅法以前と難も、父に取得せられざる或る物、例へば母方財産及び配偶者よりの利得の如きものも存し、又子に家長権免除を行ふ父に、取得せられざる財産の三分の一を、所有権の名義を以て、家長権免除の代償して留保することを許す可きことを宣言する勅法あり。為に権力服従者をば、自主権者となす範囲に於ては、権力服従者に対する尊重の意味にて為されたる家長権免除が、自己の財産を奪はれ、其の財産が減少するが為に、同人に害あるものに転ずるの、非人道的結果が発生せり。これが為吾人の極めて敬虔なる皇帝は、子に属して〔父には〕取得せられざる財産の所有権の三分の一を、父が留保するに非ずして、半分の用益権を留保す可き旨を規定し給へり。かくの如き方法によりて、子の財産は、何等減少することなくして、子のもとに止まり、父も亦半分の用益権を得、割合の増加を以て尊敬せられて歓喜す。三分の一に代ふるに、二分の一を取得すればなり。
三 権力服従者たる子が、吾人に取得するのみならず、吾人の奴隷も亦然り。引渡によりて何物かを取得すると、或は要約すると、或は其の他如何なる原因によりて、利得するとを問はず。これは主人が知らざるとき、更に進んでは欲せざるときにも亦、取得せらる。蓋し奴隷は権力に服従するものなれば、何等自己の物を有することなければなり。相続財産は除外せよ。蓋し予の奴隷が、何人かに相続人に指定せられたるときは、隠れたる負担が、明かなる利得よりは大なることもあるを以て、吾人の命令に従ひて承継するに非ざれば、それは取得せらるることを得ざればなり。吾人が知らざるに、或は又欲せざるに、損害を齎す相続財産を取得するは失当なればなり。これが為、其の取得には、主人の命令が先在することが必要なり。若し予の奴隷が予の意思に従ひて、承継したるときは、予はあたかも予自身が相続人に書き記されたると同じく、相続人となる可し。上に記したる所に従ひて、奴隷に遺されたる遺贈も亦、吾人に取得せらる。所有権が権力に服する者によりて、吾人に取得せらるるのみならず、占有も亦然り。蓋し人若し自己の物に非ざる物を、予の権力服従者に交付したるときは、動産を善意にて受くると、不動産を受くるとを問はず、其の所持に基きて、時効取得又は長期の占有によりて、予は其の物の所有者となる可ければなり。
四 これ吾人の奴隷に付てのことなり。他人の奴隷にして、吾人がこれに用益権を有する者も亦、上に述べたると同じく、吾人の為に取得す。されど総ての原因よりして然るに非ずして、唯予の財産によるか、或は彼の労務によるかの二個の場合に限る。予の財産によりてとは、例へば予が予の財産の注意を同人に託し、或は同人に予の財産を貸与することを許可し、以て同人を所謂会計人となしたるときの如し。かくの如き者は、自己の頭脳の働により、或は土地又は貸したる金よりして、吾人に負ふ所の物を減少せずして、其の外に何物かを利得するを得たる可し。これ予の物によりてと称せられ、予に取得せらる可し。彼の労務によりてとは、例へば彼が裁縫師か、又は大工か画家なるときなり。予同人を、他人の為に働かしめ、其の技術に対して定額の賃金を取得せんが為に、雇傭に就かしめたり。同人は定められたる賃金の外、或る物を取得することを得たり。これより得たる物は予の為に取得す。これ彼の労務によりてなり。若し此の二個の原因の外に、何物かを取得したるときは、そは所有者に帰属す。故に彼が相続人に書き記され、受遺者に書き記されて遺贈を取得し、或は何人かより贈与を受けたるときには、是等は用益権者の為に取得せずして、所有者の為に取得す。予が用益権を有する奴隷に付て述べたる所と同一の原則は、予が善意にて占有する者にも適用あり。同人が自由人たると、他人の奴隷たるとを問はず。蓋し彼等も亦二個の原因よりして、即ち吾人の物によるか或は彼の労務によりて、吾人の為に取得すればなり。若し此の二個の原因の外に、何物かを取得するときは、予が善意にて占有する自由人が取得したる場合には、法律は、同人が自己の身分を知りたる時迄、保存の義務を課して、同人の為に保留す。若し予に善意にて占有せられたる者が、奴隷なる場合には、二個の原因外にて、其の奴隷にて取得せられたる物は、真の所有者に取得せらる。而て善意にて他人の奴隷を占有する者は、三ヶ年を経過せざる間に限り、二個の原因のみにて取得せられし物を享有す。三ヶ年を経過せば、尚奴隷を時効取得し、あらゆる原因にて奴隷に来りし物は、同人に取得せらる可し。蓋し人の謂ふが如く、自由人を善意にて占有する者は、時効取得を為すことはなし。用益権を有する者も亦、決して時効取得することを得ず。第一に占有せざるが為なり。占有存せざるが故に、時効取得も進行せざるによる。占有とは支配する人の意思を以て、占有することなり。然るに同人【用益権者】は単に使用収益の権を有するのみ。人若し法律観念に従はず、外観に盲従して、用益権者は占有すと称すとも、尚用益権者は悪意にて占有するが為、他の更に大なる理由によりて、時効取得は阻止せらる可し。蓋し他人の物なることを知ればなり。所有権が、吾人が用益権を有し、又は吾人が善意にて占有する奴隷、或は予が予の奴隷なりと信じて占有する自由人によりて、吾人に取得せらるるのみならず、占有も亦然り。固より直前に述べたる所に従ひて、即ち予の財産によるか、又は彼の労務によるかの二原因によること勿論なり。蓋し若し二個の原因によりて、他人の物を支配者ならざる者より受くるときは、彼等が保持する期間によりて、時効取得は予に進行すればなり【Frégier p.254の仏訳意味を為さず】。
五 既に説きたる所によりて、吾人の権力服従者にも非ず、善意にて吾人の奴隷となれる者にも非ざる自由人、同じく又吾人が用益権を有することもなく、善意の占有を有することもなき他人の奴隷によりては、如何なる原因に基くにせよ、吾人に何物かが取得せらるることなきこと明かとなれり。これ、これより述べんとする場合を除き、「吾人は他人によりては、何物も取得することを得ず」と総ての人によりて称せらるるものなり。蓋し人若し予に他の場所に存する物を売り、而て予は当該の場所に赴くことを得ずして、予の執事を派遣し、同人が占有を受取りたるときは、其の物の占有は、同人によりて予に取得せらる可ければなり。而て吾人が知れるときに、此のことが発生したる場合のみならず、仮令知らざる間に、吾人の名義を以て、何物かが同人に与へられるときにも亦、占有は吾人に取得せらるること、セウェールス皇帝の勅法の希望するが如し。其の外、占有が吾人に取得せらるるとき、交付者が所有者なる場合には、所有権も亦暗黙的に従ふ。若し所有者ならざるときは、時効取得によるか、或は長期間の経過によりて、予は引渡されたる物の所有権を取得す。
六 個々の物が如何なる方法にて、吾人に取得せらるるかに付て論を進むるは、これ丈にて足る。此の外に尚取得方法あり。遺贈のそれ(これにより、個々の物は吾人に到達す)及び信託遺贈のそれ(これによりても亦、個々の物が吾人に遺さるることを得)なり。是等は先の所に於て説くを可とす。故に取得は或は自然的たり。或は法律的たり。自然的取得には十四あり。即ち(一)狩猟(二)捕獲(三)海岸に於て発見せられたる石又は宝石(四)吾人の生物の子(五)寄洲作用(六)海中又は河中に発生せし島或は(七)河の取残したる河床に接近して、〔土地を〕有すること(八)他人の材料を原材料に還元し得ざる物に変形すること(九)自己及び他人の材料を用ひて物を作ること(十)同一又は異る材料を所有者の意思に従ひ、又は偶然に混合すること(十一)上にある物は下にあるものに従ふと称する原則。種々の例に於て看取せられしが如し。他人の材料を用ひて予が予の土地の中に家屋を造り、或は予の材料を用ひて他人の土地の中に家屋を造りたるとき、或は他人の木を自己の土地に植ゑ、反対に自己の木を他人の土地に植ゑて、根を生じたるとき、或は文字を予の羊皮紙又は紙に書きたるときの如し。肖像に付ては、原則は排除せられたり。画板は絵に征服せられたればなり。(十二)善意にて他人の土地を占有し、これに播種すること(十三)埋蔵物を自己の地所、或は神聖物或は宗教物の中にて偶然に発見すること。若し他人の地所なるときには、半分の所有者となる。其の地所が私人の有たると、皇帝の有たると、国庫の有たると、都市の有たるとを問はず。(十四)此の外尚引渡、これなり。法律的取得は古くは五、今は四個なり。即ち(一)時効取得(二)長期の占有(三)共有奴隷を躁急に解放するによりて、古く発生したる添加(四)遺贈及び(五)信託遺贈これなり。而て是等は、為さるる行為が一個にして、且一個の物が吾人の所有に帰属することとなれるを以て、特殊的取得と称せらる。然れども此の外包括的と称せらるる取得あり。これに於ては、為さるる行為は一個なれども、多数の物が一個の行為によりて、吾人の所有権に服することとなる。包括的取得は下の如し。相続、遺産占有、自権者養子縁組、及び自由を保存せんが為他人の財産が吾人のもとに来ることこれなり。而て先づ相続に付て論を進むることを要す。然れども相続財産の取得には二種存するを以て(蓋し遺言によるか、或は無遺言にて、吾人に到達すればなり)、先づ遺言によりて到達するものに付て述べざる可からず。而て暫く入門として、如何にして遺言が行はるるかを研究することを要す。
第十章 遺言の調製に付て
他のことはこれを措き、先づ遺言の定義又は語源を述ぶる必要あり。遺言は羅馬人のもとに於てはquod testatio mentis est即ち死亡者の意思の証明を有するが故にとの語源よりして、testamentumと称せらる。
一 昔行はれたるものを知らずとも、何等の危険を齎す訳には非ざれども、これに付て何等吾人が知る所なきが如きことを避けんが為に、歴史の為、如何にして漸次時の経過するに従ひて、変化したるかを学ぶが為、述ぶる所あるは脱線には非ず。古くは遺言に二種存したり。一はcalatis comitiisと称せられ、他はprocintuと称せられたり。calatis comitiis遺言は、平和の時、一年に二回下の如くにして行はれたり。即ち伝令者は召集しながら、全市をかけ巡り、全国民が集合し、希望者は国民の証人のもとにて遺言したり。calatis comitiisと称せらるるは、次の事情より来る。calareとは召集なり。comitiaとは民会なり。召集せられたる者が集合したるが故に、calatis comitiisと称せられたるなり。procinctu遺言は、将に戦争に赴かんとする時に行はれたり。其の名称は、遺言者の着せし服装よりこれを受く。武装して出征の準備成れる者は、procinctusと称せらるればなり。蓋し帰還し得るかは不明なるを以て、先づ遺言を為し、以て戦争に赴きたればなり。此の二種類が存せしとき、突然の死亡に襲はれたる者が、無遺言にて死亡する場合起れり。何故となれば、未だ其の時期到達せざるが為、calata comitiaに於て遺言を為すことなく、戦争もなければ、procintusにて行ふこともなければなり。健康者が其の他の方法にて遺言せば、身に子なしと考へたり【他の方法にて遺言せば、不吉の象徴が現はれると考へたりとの意】。これが為per aes et libramと称せられたる第三種のもの発案せられたり。蓋しemancipatioによりて行はれたればなり。emancipatioとは仮装の売買なり。下の如くにして行はれたり。成熟の羅馬市民たる五人の証人と、持衡器者の立会あり。彼等立会の上にて、死亡者の承継人たらんとする者は、或る定まりたる文言を唱して(これを述ぶることは今では無駄なり)、将に死亡せんとする者の財産を買ひ、仮装の代価として、財産の所有者に一片を交付したり。買主はfamiliae emptorと称せられ、将に死亡せんとする者は、同人の死亡後、何が与へらるることを要するかを定めたり。蓋し遺産購買者に対し、「予は汝が某には土地を、某には百金を与へんことを欲す」と謂へばなり。此の種類が発案せられて、先の二種類calatis comitiisとprocinctuは、既に長く不使用に帰し、per aes et libram自身も亦漸次軽んぜらるるに至れり。蓋し遺産購買者は自身亦相続人にして、それよりして尚自己が承継人なることを知り、財産所有者に対して陰謀を企てたればなり。これが為従前の形式に従ひて、遺産購買者が招かれ、同人は仮装的に将に死亡せんとする者の遺産を購買するも、遺言者は自筆にて、板或は紙に、自己の欲する者が其の相続人たる可き旨を記したり。
二 然れども今述べたる種類の遺言は、市民立法のみが知りたる所なり。其の後法務官の告示は、遺言の作成に関し、他の方法を発見したり。蓋し法務官法に従へば、何等emancipatioは行はるることなく、七人の証人の捺印を以て、法務官的遺言の作成に足ればなり。蓋し人若し遺言を為し、該遺言が七人の証人の捺印を以て、捺印せらる可きことを手はずしたるときは、市民法は証人の捺印の必要を知らずと雖も、法務官的遺言は完成せられたればなり。
三 然れども間もなく、一には人間の種々なる利用、一には勅法の匡正したる所によりて、市民法と法務官法とが一の融合物に結成し始めたるを以て、同一時に(これ市民法の欲せし所なり)七人の証人立会ひて下書し(これ勅法の発案したる所なり)且捺印して(これ法務官の欲したる所なり)遺言が明かにせらるることが、行はるるに至りたり。故に今日に於ては、遺言は次の三法律より成立す。市民法、勅法及び法務官法これなり。蓋し市民法よりしては、証人の立会のもとに、続け様一息にて、完成せらるべきこと、遺言者と証人との下書は勅法より、捺印及び七人の証人数は、法務官の告示より来ればなり。
四 是等一切の遵守事項に尚、遺言の作成が総ての奸計より解放せられ、遺言が総ての悪意より純ならんが為、吾人の極めて敬虔なる皇帝の勅法によりて、遺言者は自筆にて、予は某を相続人に指定したりと書き記して、相続人の名を明かにす可きことが附加せられたり。同人これを行はざるときは、証人に対し相続人の名を読む必要あり。一般に其の他一切は、皆彼の神聖なる勅法の述ぶる所に従ひて、行はるることを要す。
五 吾人は証人は捺印することを要すと謂ひたるを以て、汝一個の指輪を以て、遺言に捺印することを得ることを知るを要すること(蓋し七人の証人が指輪を有するも、其の七個の指輪が一の刻付けなるとき、即ち同じ一個の意匠を有したるときは如何と謂はざるを得ざればなり)、ポーンポーニウスの解するが如し。且他人の指輪を以てしても捺印することを得。
六 或る者に対し吾人が遺言作成権を有するときに其の者、即ち吾人によりて相続人に記さるることを得る者、及び吾人を相続人に記すことを得る者は、証人に徴せらるることを得。而して全く遺言に於ける証人たることを得ざる者もあり。例へば婦女、未成熟者、奴隷、唖者、聾者、精神錯乱者、浪費者、其の外尚improbus intestabilisqueの如し。これは如何なる者なるか。例へば或る者遺言為すとき、チチウスが証人に呼ばれたり。証人行為を為し、即ち遺言の中に下書し、捺印したり。遺言者死亡したるとき、彼は赴きて下書及び捺印は、己がものなることを証言することを欲せざりき。法律はかくの如き者を憎みて、同人が他人の遺言によりて、何物をも取得することを許すこともなく、同人に遺言の権能を与ふることもなく、他人が遺言を為すときに、証人たることを許容することもなし。かくの如き者がimprobus intestabilisqueと称せらる。
七 遺言に証人となりし者の一人、遺言の時には自由人と考へられしも、其の後奴隷なることが明かとなりたるときは如何。かくの如き場合に、果して遺言が有効なるかを研究す可し。蓋し奴隷は、既に述べたるが如く、証人となることを禁止せらるればなり。これ疑問となりて、先づハドリアーヌス皇帝のカトーニウス、ウェールスに対する勅法制定せられ、再び同一事件発生したるとき、セウェールス、アントーニーヌスは、遺言の作成時には、当該証人は総ての者の考によりて、自由人なりと解せられ、身分に関して同人に疑を掛けたる者存せざるの故を以て、其の博愛心によりて、遺言を有効となすに合流し、かかる遺言は、全部自由人が証人に立会ひて、当初より攻撃を受くることなき様作成せられしならんには、在りたる可き地位に存す可き旨を解答し給へり。
八 予遺言を為す可きときには、甲は其の権力服従者乙と共に、予の遺言に証人として立会ふことを得。若し又二人が同一権力に服従する兄弟なるときも亦、均しく証人行為は禁止せらるることなし。蓋し一の家又は一のfamiliaの多数の者が、他人の遺言に証人として立会ふは、何等障碍には非ざればなり。
九 何人も遺言を為すとき、遺言が攻撃を受くることなきものたることを欲するときは、証人に立会はんとする者を詮議し、証人中の何人も、遺言者の権力服従者ならざる様、厳重に検査し、発見したるときは、同人を証人の立会より除外す可し。然れども吾人は、証人の或る者が、遺言者を権力服従者に持ち、又は遺言者と共同の権力に服する者ならざるかを詮議することはなし。理由は下の如し。汝は遺言者が自主権者なるを欲するか、又は権力服従者なるを欲するか。若し自主権者なるときは、何人かが同人と共同の権力服従者たり、或は同人を権力内に保持することなき様と云々することは起ることなし。若し汝同人が権力服従者なる場合を考ふるときは、汝は更に大なる理由によりて、遺言の成立を阻止す。蓋し権力服従者は、遺言を為すことを得ざればなり。遺言は財産に関する処分なるに、権力服従者は、自己の欲する処分を、物に付て実行す可き最も完全なる権力中に、何物をも収むるものとは解せられざればなり。若し吾人が権力服従者たる遺言者を見出すことを得ば、其の時初めて吾人は尚これに次ぐ事項が起ることを得可きやを観察す。而て詮索するときは、吾人は権力服従者たる満期除隊兵(満期除隊兵とは兵士にして、兵役より退きたる者なり)は、軍営特有財産即ち戦争に従事して得たる物に付て、遺言の可能者なることを発見す。これ勅法が同人を尊重したるが為なり。其の場合には、遺言者は権力服従者なるが故に、吾人はこれに次ぐ事項を取扱ふ可し。満期除隊兵たる権力服従者が、軍営特有財産に付て、遺言を行ふときには、同人を権力服従者として保有する父、或は共同の権力に服する兄弟は、証人たることを得可きか。吾人は決して然らずと謂ふ者なり。蓋し法学者がdomesticum testimoniumと呼ぶ家内証言は、遺言に於ては有効に為さるることなければなり。家内証言は親族によらず、権力服従の共同よりして、吾人これを了解す。勅法は権力に服従する者に遺言を許したるも、同人が遺言に当りては、〔法律の〕厳正を蔑にすることなかる可きことを要求す。
一〇 某遺言に当りて、予を相続人に指定したり。予は其の遺言の作成には、証人たることを得ず。予の権力服従者も、予を権力内に保有する父も、予と共同の権力に服する兄弟も亦然り。遺言処分に関し、今日行はるるものは、皆相続人と遺言者の間にて行はるればなり。蓋し仮令これに関する法律は、古く遺産購買者の制が其の効力を有したるときには混乱し、幾多の乱雑に充満せられ(蓋し一見したる所によれば、同人が相続人なりと考へられたるを以て、遺産購買者に権力関係に結ばるる者は、遺言に証人たることを得ざりしが、上述の如く、自筆を以て相続人に書き記されたる者に権力関係に結ばるる者、及び相続人自身が証人たるに、何等の障碍なく、全利得は遺産購買者に帰属し、自筆を以て相続人に書き記されたる者は、表面に現はれざるを以て、〔法律の〕厳正も、証人となることには反対には非ざりしを以てなり)古人も均しく、これを許し、相続人に書き記されたる者、及び同人と権力関係に結ばるる者が、遺言に証人となることを禁止せざりしとは曰へ、遺言者はかくの如き与へられたる権限は、これを濫用す可からざる旨は勧告したりしが、吾人の皇帝はかくの如き正道にあらざる点(権限を附与し乍ら、これを利用せざる様勧告するは、正道にあらざることと観ぜらる)を匡正して、古人の勧告を法律的必要に変更し給へり。而て往時の遺産購買者に付ては、遺産購買者と権力関係に結ばるる者の証人たることは、総て禁止せられたるが如く、同様にして、古の遺産購買者の残影を保存する相続人に付ても、同人自身及び、同人と権力関係に結ばるる者にも許さず。蓋し自己の利益に証人となるものと親ぜらるればなり。而て以前の皇帝の勅法にして、相続人に証人たることを許すもの存したりしかば、吾人の至聖の皇帝は、かかる勅法を勅法彙纂内に書き記すことを禁止し給へり。
一一 受遺者及び信託受遺者は無体物【相続財産】の承継人となることなく、同人等と権力関係に結ばるる者の何人によりても、証人の立会行はれて、障碍あることなし。然れども極めて温厚なる吾人の皇帝の勅法にして、彼等に関するものありて、特に遺言に証人たらんとする者——同人等と権力関係結ばるる者は更なり——に対して、遺贈を遺すことを許し給へり。
一二 遺言が如何なる材料の中にて行はれたるか、板なるか、紙なるか、羊皮紙なるか、其の他の材料例へば毛皮又は象牙板なるかは、区別する所なし。
一三 人遺言を為すときには、同種の多数の遺言を記すことを得。但し其の各通が、遺言に於ける遵守規定に従ひて、作成せらるるときに限る。数通の同じ遺言の存在は必要なり。蓋し時には、何人か航海せんとして、自己と共に〔一の〕遺言を携へ、他は家に残し置き、死亡したるときに、其の意思を明かにする資に充てんと欲するが如きことあればなり。其の他人間的状態より発生する多数の原因の為、これは極めて必要なり。蓋し時には同じものの一が盗難に遭ひ、或は受取りて預りたる者旅行に出で、時を過す可き場所が何処なるか不明なるが如きこと起ればなり。
一四 是等総ては文書による遺言に関すと考ふることを要す。人若し文書によらずして、遺言を作成せんと欲し(固より市民法的のものなり。法務官は常に捺印を要求するを以て、文書によらざる遺言は知る所なし)、七人の証人の立会のもとに、其の面前にて自己の意思を明かにしたるときは、かかる遺言は市民法に従ひ、完全有効たる可し。
第十一章 兵士の遺言に付て
前述せし所に於て、遺言が如何なる方法によりて作成せらるることを要するかを説きたり。然れどもかかる幾多〔法律上の〕厳正を遵守せしむるは、普通一般の遺言に於て行はるることにして、兵士の遺言に関しては、かくの如き規定は総て適用なし。何故となれば、彼等には其の法律に通暁せざるの故に、〔法律の〕厳正に従ふことなくして、遺言するを許さるればなり。故に若し一人が証人となりて遺言し、或は自筆にて相続人の名を記さずとも、其の者の意思は確認せらる。何故となれば、軍役に従事するが故に、総て厳正の遵守を知らざるは、当然なるが故なり。然れども古くは、如何なる所にて暮すとも、兵士式に遺言することを得たりしが、吾人の皇帝の勅法は、唯軍営或は従軍中にあるときに初めて、かかる方法によることを彼等に許可し給へり。かかる場合には、彼等の意思は、書面を用ひて表示せられたると、書面によらずして表示せられたるとを問はず、其の効力を有す可し。其の他の場所、又は自己の所謂sedesにて暮せるときには、遺言に当りて、兵士の特権を享有することはなかる可し。而て権力服従者たりとも、陣営外に在るときには、総て厳正を遵守せば、遺言をなすに何等の障碍なし。
一 トラーヤーヌス帝が下の如き場合に、兵士の遺言に関して宣示し給へる所を、中間に挿むは其の所を得ざるに非ず。某兵士、某々の立会を求め、其の面前にて某が己が相続人たり、己が奴隷が解放せられんことを欲すと謂ひたり。これは書面を用ふることなくして行はれたり。彼の死後、無遺言相続人と指定相続人との間に、論争が惹起したり。而て無遺言相続人の側にては、死亡者の言は、遺言の意思にて語られしものに非ずと謂ひ、指定相続人の例にては、兵士の特権を持ち出し、唯其の特権を理由として、遺言の有効を確言せり。スタチリウス、セウェールスかかる争を聴断するに当り、至聖のトラーヤーヌスに伺を発せり。帝は下の如く解答し給へり。「兵士の作成したる遺言は、如何なる方法にて作成せられたるにせよ、有効なりと謂ふ兵士の特権は、先づ第一に文書によるにせよ、よらざるにせよ、遺言が作成せられたること明かなる場合のことと解することを要す。今遺産に関して争の発生せる死亡兵士が、若し自己の意思を証人の面前にて明かにせんが為、某々を同人に召喚して、何人が自己の相続人たる可きことを欲するか、奴隷中の何人が自由に値す可きかを明瞭に明にしたるときは、かかる文書によらざる遺言は、有効たりと吾人は呼ぶものなり。然れども若し、多くの場合会話に於て通常発生するが如く、或る者が存する場合に某に向ひて「予は汝を相続人に指定す」或は「予は予の財産を汝に遺す」と謂ふも、これは遺言の効力を有することを得ず。何故となれば、欲するが侭の方法にて、遺言を為すの特権を附与せられたる兵士に付ても、会話にて話したるものが、遺言の形に受取らるることを、決して問題とす可きに非ざること、〔他の〕何人とも同然なればなり。然らざれば、総て兵士の死亡したる後は、某死亡者は某に対し「予は汝に対し、予の財産を遺す」と謂へるを聞きたりと主張する証人、何等の困難を伴はずして容易に現れ出で、これによりて、兵士の真の希望は覆さるることとなればなり」と。
二 兵士は或は唖者たり、或は聾者たりとも、有効に遺言を行ふ。但し同人は事故除隊によりて、未だ兵役より除隊せられたる者に非ざる者と考ふ可し。かくの如き者が兵役に在るは、道には非ず。一は大将の命令を聴くことなく、他は或る必要、例へば武器の必要ある場合あるも、これを謂ふことを得ざればなり。
三 皇帝の勅法によりて、兵士に〔法律の〕厳正に従はずして、遺言を為すことを許さるるは、兵役に服し、且軍営中に生活する間に限るものとす。除隊後、即ち或は満期除隊兵となり、或は軍営の外にあるときは、尚軍役に服すとも、普通一般人の〔践む可き〕厳正を遵守することを要す。吾人は軍営中にて遺言を為す者は、厳正を無視するも危険なしと雖も、満期除隊兵は厳正を遵守するを要すと謂ひたれば、これより生ずる兵士と満期除隊兵に関係ある疑問を見る可し。兵士軍営に生活中、自己の欲するが侭の方法によりて遺言を為し、後兵役より除隊せられて、死亡したり。吾人は同人の意思は、有効となす可きや否やを検討す可し。人若し〔遺言の〕為されたる時を問題とせんには、厳正に従はざるも有効なる可し。死亡したる時を問題とせんには、厳正に従ひて行はれざりしものは、効力を有することを得ず。然らば如何にす可きか。時が議論を解決す。即ち若し尚兵士的遺言を取消さずして、除隊後一年内、例へば十ヶ月又は十一ヶ月にして死亡したるときは、それに効力を与ふ。若し一ヶ年を経過して其の後ならば、最早有効たらざる可し。蓋し同人が自己の遺言を変更して、遺言を行はんには、中間時【即死亡より一年の間】は、彼が遺言に関して遵守することを要する厳正を、教ふるに十分なればなり。又若し兵士的遺言を為し、条件付にて相続人を指定し、除隊後一年以内に死亡し、相続の指定に付ての条件が、一年後に成就したるときは如何。吾人はこれが遺言が害するかを研究す可し。而て吾人は決して然らずと謂ふ者なり。吾人が除隊後一年内に発生を要求するは死亡にして、相続の承継には非ざればなり。
四 某普通人として、〔法律の〕厳正に従はずして遺言し、其の後兵士となれり。軍営に生活中、遺言を開封して、或るものを附加又は削除し、或は単に遺言を朗読し、或は他の行為を行ひ、以てこれ【遺言】が効力の発生を希望する兵士の意思を明かにしたり。其の後同人死亡したり。遺言は〔法律の〕厳正に従はずとも、軍営中に生活せしときに、遺言に対して懐きたる同人の新なる意思によるものとして有効なり。
五 軍営に生活中の兵士、〔法律の〕厳正に従はずして遺言したり。其の後capitis deminutioを受けたり。蓋し自主権者たりし者が、自ら自権者養子縁組を為し、或は権力服従者たりし者が、家長権被免除者となりたればなり。遺言は、効力に付て家長権免除後、兵士の新なる意思に触れたるものとして、均しく有効たる可し。何故となれば、該遺言を変更せざるときには、其の効力の保持を希望したるものにして、遺言者は兵士なれば、capitis deminutioも遺言を失効せしむることなければなり。さきにて又学ぶが如く、遺言者のcapitis deminutioは、遺言を失効せしむるも、此の場合にはかかる原則遵守せらるることなし。
六 或る種の権力服従者は、軍営特有財産は有せざるも、或は古き法律により、或は其の後の勅法によりて、準軍営特有財産を有することあり。顧問官、弁護士、政務官たることよりして得たるもの、即ち国民より彼等に下附せらるる俸給の如し。而て是等の者にも、権力に服し乍ら遺言を為すことを許さる。然れども彼等に付ては、或る小疑問存したれば、吾人の皇帝の一般的勅法制定せられ、総て準軍営特有財産を有する権力服従者は、かの普通一般の法律に従ひ、遺言することを得可き旨宣言したり。上記の勅法を読む者は、これに関係の規定に付ては、何等知らざることなし。
第十二章 何人に遺言の作成が許されざるか
人間の中、或る者は遺言を為し、或る者は為すことなし。吾人は遺言を為すことを得る者に付て述ぶ可し。然れどもこれ数に於ては多きを以て、〔数に於ては〕少き遺言を為し得ざる者に付て述べ、これよりして、数多き者を学ぶこととす可し。先づ第一に権力服従者は遺言を為すことを得ず。遺言は現存財産の処分なればなり。然るに権力服従者は、己が欲するが侭に、自己の物を処分することを得ざるなり。而て此の原則〔の峻厳〕は、仮令予が父にして、世上屡々行はるるが如く、子を愛して、これに予の財産の幾何にても其の欲する限り、遺言処分を為すことを許すとも、尚〔同人の〕遺言は禁止せらるる程なり。私人の意思は、法律よりも効力強大なることを得ざればなり。権力に服し乍ら、遺言を行ふ或る者あり。例へば軍営特有財産を有する者の如し。これ当初に於ては、アウグスツス、次にネルヴア、尚又最善の皇帝トラーヤーヌスの権威に基きて、唯兵士にのみ許容せられたり。其の後これを嫉む除隊兵に対するハドリアーヌスの勅法は、除隊兵にも、権力に服し乍ら遺言を為すことを許可したり。而て若し上記の総ての者が、軍営特有財産に付て遺言を為すときは、彼等が書き記したる相続人これを受くるも、若し後に遣れる子も兄弟もなくして死亡するときは、普通一般の法律によりて、他の一般的特有財産と同じく、尊属に帰属す。蓋し同人に対する尊敬の意を以て行はれたる改正を利用せざる場合には、古き法律に効力を認むるなり。古くは死亡したる子の特有財産は、父これを取得したり。普通一般の特有財産と軍営特有財産との間には、多くの差異あり。第一は軍営特有財産に付ては、権力服従者は遺言を行ふも、普通一般の特有財産に付ては、行ふことなきことこれなり。第二の差異は、父若し権力服従者に対して、怒を覚ゆるときは、〔普通一般の〕特有財産は、これを取上ぐることを得るも、軍営〔特有財産〕は然らざることこれなり。第三の差異は、若し多数人に債務を負ふ者、其の債権者によりて、〔財産〕売却の破目に陥るときは、普通一般の特有財産は共に売却せらるるも、軍営〔特有財産〕は決して然ることなきことこれなり。尚第四の差異あり。若し子が多数に存在するとき、父が死亡し、子の一人は偶々普通一般の特有財産と、軍営特有財産とを有するが如きことあらば、普通一般の特有財産は、其の時に生存せる総ての子に共有なるも、軍営特有財産は、取得者のみの有なり。権力に服従する子の、特有財産は総て、父の財産の一部と観ぜらるること、奴隷の特有財産が主人の財産に算入せらるると異ることなし。軍営特有財産に関して、述べたる所は、勅法に基きて、種々の原因よりして、〔父に〕取得せらるることなき物に付ても、〔同一と〕考ふ可し。軍営又は準軍営特有財産を有する者を除き、人若し権力に服従し乍ら遺言を為すも、同人の遺言は無効なり。仮令自主権者となりて死亡するとも然り。何故となれば、吾人は死亡の時は常にこれを観察するも、遺言作成の時も亦これを観察して、両時に於て遺言権能を有するや否やを質せばなり。
一 第二に未成熟者は遺言を為すことを得ず。遺言とは意思の証明を謂ふとは、汝の知る所なるが、未成熟者には、〔かかる〕意思を欠けばなり。精神錯乱者も、遺言を為すことなし。理性を欠けばなり。故に未成熟者も精神錯乱者も、遺言を為すことなし。思考力は一方には未だ発生せず、他方はこれに見離されたればなり。仮令一方は成熟者となり、他方は正気に恢復するも、彼等の遺言は無効なり。若し精神錯乱者が、精神錯乱を止めたる時に於て、即ち中間時に於て、遺言を為すとせば、有効なりや疑あり。然れども吾人は、遺言は合法的なりと謂ふ者なり。然らば又遺言を行ひて、精神錯乱者となりたるときは如何。後発の精神錯乱なる瑕疵は、適当に処理せられたる遺言を破壊することはなし。他の契約が精神錯乱の後発によりて、効力を失ふことなきと同然なり。
二 自己の財産管理を禁止せらるる浪費者にも亦、法は遺言を許さず。然れども浪費者となる以前、即ち財産の管理が同人に禁止せられし以前に、作成せられたる遺言は効力を保持す。
三 唖者又は聾者は常に遺言を行ふことなし。吾人は〔此処にて〕述ぶるは、全く聴くことを得ざる聾者に関し、徐々ならば聴くことを得る者に付て述ぶるには非ず。かかる者は遺言を行ふ〔ことを得〕。又吾人が唖者と謂ふ者も、徐々ならば話すことを得る者を謂ふに非ずして、全く話すことを得ざる者を謂ふなり。「常に〔行ふこと〕なし」と附加せしは、次の如き原因に基く。即ち文字を知り教育ある者も、不幸に見舞はれて(かかる不幸を惹起せしむる原因は甚だ多し)聴力又は発声能力を奪はるること屡々存すればなり。而て古人のもとに於ては、かかる者も亦遺言を為すこと能はざりしを以て、吾人の皇帝の勅法発布せられ、疾病の為かかる状態に陥りし者に対し、或る事項を遵守するときは、遺言を為すことを得可き旨を命じ給へり。上記新勅法を読む者は、其の方法並びに遵守事項を、欠くる所なく知悉することを得。若し遺言を為したる者、疾病に罹り、或は官吏の加ふる刑罰により、其の他事情の如何を問はず、唖者又は聾者となるも、以前に作成せられし遺言は、其の効力を保存す。
四 盲者は故神聖ユスチーヌスの勅法の述ぶる所を遵守して、遺言を為すことを得。
五 敵中に在る者は、敵中にて有効に遺言を為すことを得ず。仮令彼が吾人の祖国に帰るが如きことありとも然り。然れども吾人は、吾人のもとにて作成せられたる遺言は、其の後捕虜となれるときも、有効なりと謂ふ者なり。何故となれば、若し帰国するも、ポストリミニウムの権が其の遺言に効力を附与し、若し敵のもとにて死亡するも、コルネリア法が其の遺言に有効の恩恵を与ふればなり。
第十三章 子の廃除に付て
上述したる所に於て、吾人は如何なる方法にて、遺言が為さるることを要するか、例へば遺言者は自筆にて相続人の名を記し、或はこれを証人の面前にて読み、又証人は七人たることを要し、又是等の者は何人も中途にて他のことを行ふことなくして、遺言に下書し、これに捺印するが如きことを述べたり。若し是等の〔要件中〕或る一個が履行せられずとも、遺言は無効なり。有効に遺言を為さんが為には、吾人は啻に上記の遵守事項を必要とするのみならず、尚他の或るものをも求むるものなり。蓋し遺言者は権力に服する子を有するや否やを、探索するを要すればなり。即ち同人(子)をば相続人に書き記すか、或は一々指名して廃除者となすことを要す。若し黙して同人を看過したるときは、遺言は記載自体にて無効なり。仮令若し子が自己の父に先ちて死亡するが如きことあるも、当初遺言に於て無効なるものが、其の後に発生せる事実よりして、効力を取得することは不可能なりとの法則によりて、遺言は均しく無効なること勿論なり。而て指定相続人は、仮令看過によりて害せられたる子が生存せずとも、死亡者の遺産を受くることを得ざる可し。而てこれ息が権力服従者たる場合なり。人若し権力に服する娘、又は男孫、女孫、男曾孫、女曾孫を有し、是等の者を相続人に書き記すこともなく、廃除者となすこともなく、看過を以て彼等を蔑むるときは、遺言は無効には非ずと雖も、看過せられし者は、指定相続人に追加せらる。追加は割合の制限なり。若し指定せられたる者が家外の者なるときは、二分の一に付て追加が行はれ、若し自権相続人なるときは、同じ割合に付て行はる。例へば某は娘又は男孫を看過しながち、三人を相続人に指定したり。若し指定相続人が家外の者なるときは、娘又は男孫は六ウンキア、三人の家外相続人も六ウンキアを受く可し。若し自権相続人なるときは、同一の割合、即ち三ウンキア——これ父が無遺言にて死亡せば、取得したる可き額、即ち同人の財産の四分の一なり——を取得す可し。是等の者に対しては、一々指名して相続の廃除を行ふことを得るのみならず、「其の他の者は廃除者たる可し」と謂ひて、inter ceterosの相続廃除を為すことも許されたり。指名的相続廃除は下の如くにして行はる。「予の息チチウスは廃除者たる可し」〔の如し〕。職業によりて行ふことも可能なり。「文法学者は廃除者たる可し」〔の如し〕。又手工業者の如き技術、年長者年少者の如き年齢、白色又は黒色の如き皮膚の色よりして、行ふことも亦可能なり。一言にして謂はば、残存者を判然と明瞭にする言辞ならば、総て、指名的相続廃除を完了す。
一 遺言者は現在存する者のみならず、後生児に対しても留意し、是等の者も相続人に書き記すか、或は廃除者と為すことを要す。看過せられし者は、出生と同時に遺言を破壊すればなり。而て息たると娘たると、又男孫たると女孫たるとによりては、何等の差異を認むることを得ず。是等の者が看過せらるるときは、遺言は作成と共に有効なりと雖も、此の後後生男児又は女児が出生するによりて、遺言は破壊せられ、其れが為総ては無効となる。固より彼等を看過したるが為なり。然れども遺言の作成自体によりて、無効となるに非ずして、出生によりて然るなり。故に若し後生児の出生が予測せらるる婦女が、流産するが如きことあらば、指定相続人が相続財産を承継すること疑なし。而て女性の後生児は、或は指名的に、或は一括的に、相続より廃除せらる。蓋し若し遺言者が、「某は予に相続人たる可し。他の者は廃除者たる可し」と謂ふときは、此の文言によりて、後生女児も亦廃除せらると観ぜらるればなり。然れども出生後、濫りに「遺言者は妾を知らざれば、妾に付き何等言及せざりしなり」と称して、指定相続人に対し、訴を提起するが如きことなからしめんが為、遺言者は次の如く謂ひて遺贈を同女に遺すことを要す。「某は予の相続人たる可し。爾余の者は廃除者たる可し。生まる可き後生女には、百金を遺贈す」と。かくなすときは、吾人は同女に対し、汝に対し一括的相続廃除を為し、其れ故国より汝に遺贈を為すなりと謂ふこととなる。若し男性の後生児、即ち息、男孫、男曾孫なるときは、指名的に非ざれば廃除せらるることなしとするを通説とす。然らば未だ生まれざる者に対して、如何なる名を述ぶることを得可きか。吾人は次の如く謂ひて、これが明かにせらるるを見る。即ち「予に生まれたる男は何人たりとも、廃除者たる可し」と。或は「予の妻某よりして予に生まれんとする男は、廃除者たる可し」と。
二 尚他に後生児に類似せる者あり。そは親等上前にある自権相続人が死亡したるが為、〔新に〕自権相続人となれる者なり。例へば下の例に於けるが如し。予権力服従者たる息と、同人より生まれたる男孫又は女孫を有したり。而て息は他に先立たるることなき為、自権相続人たり、男孫又は女孫は権力服従者にして、己が父に先立たるるによりて、其の身には自権相続人たる資格を有せざりき。予遺言を為んとするときは、何人に対して考慮を払ふことを要するか。此の息に対し考慮を払ひ、同人を相続人に書き記すか、或は相続より廃除すること、固より自明のことなり。然らば男孫又は女孫に対しては如何。決して必要なし。蓋し是等の者は自権相続人に非ざれば、仮令看過せらるるとも、法律上当然に遺言を無効となすこともなく、相続人に追加せらるることもなし。何故となれば、是等のことは、自権相続人に特有のことなればなり。然れども唯死亡のとき迄、同一の状態が保存せられたる場合にして初めて、予よく此の言をなし得可し。若し予の生存中中間者が、或は死亡により、或はパツリキウスの栄爵を得たるにより、権力よ離脱することは有り得可きことにして、其の結果男孫又は女孫は、あたかも新宗族として出生したると同じく、従つて又後生児に倣ひて、自権相続人となるを以て(蓋し以前には自権相続人には非ざるも、今や自権相続人となり、是等の者は、後生児が出生によりて遺言を破壊するが如く、代襲によりて遺言を破壊すればなり)、新なる自権相続人たる代襲せる孫が、遺言を破壊することなからしめんが為には、息同様男孫又は女孫をも、相続人に書き記すか、或は指名的に相続より廃除することを要す。若し看過せらるるときは、代襲によりて、適法に作成せられざるものとして、遺言を失効せしむ。これユーリア、ウェルレーア法も述ぶる所にして、同法は後生児に倣ひて、彼等が廃除人と為さる可きこと、即ち男孫は指名的に、女孫は指名的にか、或は遺贈の授与と共に、一括的に為さる可しと謂へり。
三 某息又は娘を家長権被免除者となせり。彼は遺言を為すには、市民立法に関する限り、是等の者を相続人に書き記すか、廃除人となす必要はなし。蓋し受けたるcapitis deminutioの故に、十二表法には未知の者なればなり。法務官は自然的親族関係に着眼し、是等の者も子と認めて、家長権被免除者も、相続人に書き記さる可き旨を命ず。若し遺言者が欲せざるときは、男性は指名的に、女性は指名的にか、又は一括的にかにて、廃除せらる可し。若し相続人にも書き記されず、又上記の如くにして廃除もせられざるときは、法務官は彼等に遺言書に従はざる〔遺産占有〕を附与し、これによりて、息又は男孫は死亡者の全遺産を取得す可く、娘又は女孫は、相続人として追加せらるるによりて、権力服従者なりしならんには、受く可かりし額を取得す可し。
四 次のことを予備知識として保持す可し。予若し某を養子に収養するときは、同人は法律上も自然上も、予の子なり。法律上とは養子縁組により、自然上とは法律による。蓋し法律は自己のもとに、自然を包擁すればなり。養子縁組の実体が効力を保持する間は、予は自然上子の父と考へらる。若し予が同人を家長権被免除者となすときは、これは法律的行為なれば、養子縁組によりて成立したる法律〔上の効果〕を解消す。法律〔上の効果〕が最早保存せられざるときは、自然も自己を包擁するものを有せざれば、共に去る。汝に予め是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。予婚姻の為、予の娘を汝に与へたり。子が生まれたり。汝の権力服従者なることは明かなり。予に懇請せられて、汝は同人を予に養子に与えたり。吾人の中の何人が、遺言に当りて、同人に対する考慮を払ふことを要するかを、吾人は研究す可し。吾人は曰ふ、養父たる予なりと。蓋し養子縁組によりて、同人は合法婚姻よりして予に生まれたる者に類似すればなり。故に予は予の権力服従者たる嫡出子を相続人に書き記すか、或は先に述べたる所に従ひて、相続より廃除することを要するが如く、養子も亦かくの如く為すことを要す。実父たる汝は、同人を相続人に書き記す必要はなし。蓋し同人を権力服従者として保持するにも非ざれば、汝の法律上の子にも非ず、又法律によりて、養父たる予が自然上同人の父と観ぜられ、而て何人も二人の自然上の父を有すること能はざるを以て、汝の自然上の子にも非ざればなり。然れども若し同人を家長権被免除者となすときは、市民法によるも、法務官によるも、子の中に算入せらるることなし。故に予も同人を相続人に書き記すことを強制せらるることなく、実父も亦そのことを行ふことを強制せらることなかる可し。蓋し此の子は、あたかも実父たる汝によりて、家長権被免除者になされたる者と同様なればなり。
五 然れども是等は古のことなり。今や吾人の皇帝の勅法制定せられ、遺言に於ては男性たると女性たるとの間に、何等の差別も存することを欲せず。蓋し両者は共に、自然が均しく子の繁殖に適合せしめたる者にして、従つて彼等の間に何等の区別が存することなきは明白にして、これが為十二表法も無遺言の場合には、男性も女性も均しくこれを召喚したり。法務官も亦、十二表法に従ふ者と観ぜらる。故に息、娘、其の他総ての男性よりの卑属に付き、既に生まれたる者のみならず、未だ懐胎中の者も、又権力服従者に止まらず、家長権被免除者に対しても、法律を簡単一様にし給へり。而て子が自権相続人たると、家長権被免除者たるとを問はず、彼等が若し相続人に書き記されざるときは、指名的に廃除者となさる可き旨を命じ給へり。蓋し看過せられたる者は、自権相続人たると、家長権被免除者たると、既に生まれたる者たると、後生児にして後に生まれたるとを問はず、作成自体によりて、遺言を無効となせばなり。養子に付ては、吾人の至聖の皇帝は、養子となれる者に関して制定し給ひし他の同帝の勅法に於て、独特の規定を発案し給へり。
六 出征中の兵士が遺言を為し、既に出生せる己が子、又は懐胎中の己が子を、相続人に書き記すこともなく、指名的に相続より廃除することもなく、看過を以て軽蔑したり。吾人は同人の遺言が、果して有効なるかを研究す可し。而て吾人は、若し彼が彼等が後に残るものなることを知り、然も彼等を指示することをせざるときには、皇帝の勅法も欲するが如く、沈黙は指名的廃除と解せられ、同人の遺言は有効なりと謂ふ者なり。然れども若し知らざるときは、同人の遺言は法律上当然に無効となる。
七 母又は母方の祖父が遺言を為すときには、己が子を相続人に書き記すか、或は相続より廃除する必要はなく、是等の者を黙過することを得。蓋し母又は祖父の沈獣は、父の廃除と同等の効力あればなり。即ち母は其の息又は娘を、祖父は娘より生まれたる男孫又は女孫を、相続人に書き記し、或は相続より廃除する必要はなし。故に看過せらるるも、市民立法によりて救済せらるることなく、法務官が遺言書に従はざる〔遺産〕占有を同人に約することもなし。蓋し是等のことは、自権相続人又は自権相続人たることを已めたる者に付て、論ぜらるる所なればなり。然れどもこれに関しては、他の救済〔手段〕あり。これは少し後にて述ぶ可し。
第十四章 相続人の指定に付て
子の指定及び廃除に付て為したる研究の後には、他の者は如何にして吾人これを相続人に書き記すことを得可きかを、述ぶる必要あり。而て吾人は一方自由人、他方奴隷を指定することを得、奴隷は吾人の奴隷たると、他人の奴隷たるとを問はず。而て吾人の奴隷は、古くは多数法学者の意見によれば、自由を附与して〔相続人に〕書き記すに非ざれば、可能ならざりき。今日に於ては、吾人の皇帝の勅法に基き、自由の附与なくしても、指定は有効なり。該勅法は、彼等が自由の附与なくして、〔相続人に〕書き記さるるときも、何等支障なく、これを相続財産に召喚す。これ同帝の勅法が、何等かの新案に基きて、移入したるには非ずして、法学者の意見に従ひたるものなり。蓋し法学君アチーリキーヌスは、自由の附与なくしても、奴隷の指定は良く成立することを承認すればなり。極めて聡明なるパウルスは、其のマスリウス、サビーヌスに対する註釈書と、プラウチウスに対する註釈書に於て、同氏【アチーリキーヌス】〔の説〕に言及す。吾人が奴隷の用益権を他人に譲渡し、奴隷に対しては、唯虚有の所有権を有するに過ぎざるが如き者も、吾人の奴隷と解せらる。而て人己が奴隷に自由を附与して、相続人に書き記すも、有効ならずと謂ふ背理的一場合を発見することを得。これ至聖のセウェールス、アントーニーヌスの勅法に包含せらるる所にして、其の勅法は、次の如き場合に発生せり。某がチチアに対し、同女は同女の奴隷スチクスと姦通せりと述べて、訴追を為せり。訴訟が未だ終了せざる中、該チチアは死亡に際して、該スチクスに自由を附与して、相続人に指定したり。同女の死亡後、果して指定の実体は有効なりや否やの疑問を生じ、上記至聖の皇帝は、姦通の責ある奴隷は、訴訟の終了以前には、該女即ち奴隷の女主にして、同一犯罪に陥れる者として、訴追せられたる者によりて、遺言中に有効に解放せらるることなしと解答し給へり。故にかくの如き奴隷に為されたる指定は、全く効力を欠く。吾人は他人の奴隷をも、良く相続人に書き記す旨を述べたるが、遺言者が或る者に対し用益権を有するときは、其の者は他人の奴隷なることを知ることを要す。
一 予が予の奴隷に自由を附与し、或は附与せずして(蓋し既に述べたるが如く、何等の差異なければなり)、相続人に書き記すときは、予の権力下に服し止まる場合には、自由人となり、且予の必然相続人となる。然れども遺言後尚生き延びて、同人を解放するときは、承継するとせざるとの自由を有して、任意相続人となる可し。蓋し主人の遺言に基きて、二物即ち相続財産と自由の両者を、〔同時に〕取得することを得ざれば、必然相続人たること能はざるによる。若し予同人を解放せずして、譲渡するときは、新主人の命令によりて承継せば、同人【新主人】の為に遺産を取得す。何故となれば、同人は譲渡せられて、予の権力に止まることなければ、仮令指定が自由の附与付なりとも、自由人たり相続人たることを得ざればなり。蓋し主人は同人を譲渡したるにより、自由の附与を断念したるものと、解せらるるによる。然れども是等は吾人の奴隷に関してのことなり。若し予が他人の奴隷を、相続人に指定するときは、若し同一の主人のもとに止まるときは、同人の命令によりて、相続財産を承継して、相続財産を同人【主人】の為に取得す。若し遺言者の生存中か、或は死亡後主人の命令による承継前、譲渡せらるるときは、新主人の命令によりて、承継することを得可し。若し遺言者の生存中か、或は又死亡後承継前に、奴隷が其の主人によりて解放せらるるときは、自由人となれる者として、自己の権限に基きて承継す可し。
二 次のことを予備知識として保持す可し。主人を相続人に書き記すことを得る場合には、其の奴隷をも亦、相続人に書き記すことを得。蓋し奴隷は無人格者なれば、主人よりして資格付けらるるが為なり。これに続く爾余のものを見よ。チチウスがスチクスと称する奴隷を有したり。予「スチクスは、其の主人チチウスの死亡後は、予の為相続人たる可し」と謂ひて、該スチクスを相続人に指定したり。奴隷がよりて以て資格付けられんとするも、チチウスは死亡して既に現存せざるが故に、或は遺言が無効ならずやと疑問を懐く可し。然れども指定は有効なること通説となれり。蓋し仮令同人の主人たりしチチウスが存せずとも、奴隷は無体の相続財産の下に含まれて、相続財産に属すればなり。吾人は相続財産に属する奴隷に対しては遺言作成権を有す。蓋し未だ承継せられざる相続財産は、死亡者の人格を支持し、将来相続人たる可き者の人格を支持するに非ずと観ぜらるるが為なり。蓋しこのことが真理なるは、次のことよりして明白なればなり。即ち人若し懐胎中の子を遺して死亡するときは、未だ後生児が出生せざる中たりとも、予は良く死亡者の奴隷を、相続人に書き記すことを得と雖も、他人の後生児は(他人の後生児とは、出生するも予に対して、自権相続人たることなき者を謂ふ)、古人これを相続人に書き記すことは許すことなかりき。若し無体の相続財産が、将来相続人たる可き者の人格を支持するものとせば、相続財産に属する奴隷は、さきの設例に於ては、適当に相続人に書き記さるることなかる可きなり。
三 某多数の者が、一人の奴隷を所有したり。予は同人を相続人に書き記すことを得。而て予が全部の〔所有〕者に対し、遺言作成権を有するときは、予の相続財産は、主人権の割合に応じて、各一人に取得せらる可し。
四 予は一人を相続人に書き記すことも得可く、無限に多数人を書き記すことも得可し。
五 相続財産は、通常十二unciaに分たる。而て相続財産自身は、asと称せらる。而てそれは【アース】unciaよりas自体に至る迄、特別の名称を有する部分を、それ自体の中に包蔵す。それは下の如し。財産の十二分の一なるuncia、六分の一たるsextans即ち二uncia、三unciaたるquadrans(四分の一)、四unciaを形成するtriens(三分の一)、五unciaを形成するquincunx(三分の一と十二分の一)、六unciaを形成するsemis(半分)、七unciaを形成するseptunx(半分と十二分の一)、八unciaを形成するbes(三分の二)、九unciaを形成するdodrans(三分の二と十二分の一)、十unciaを形成するdextans(三分の二と六分の一)、十一unciaを形成するdeunx(三分の二と四分の一)、十二unciaたるas即ちこれなり。遺言者が遺言を為すには、常に必ずしも、それに十二unciaの存在を必要とせず。遺言者が欲する丈の数のunciaが、asを形成す。故に人若し一人を相続人に指定するに当りて、例へば六unciaを以てしたるときは、全asが其の六unciaの中に存するなり。何故となれば、指定相続人が六unciaを取得し、無遺言相続人が六unciaを取得すとは、吾人謂ふことなければなり。蓋し一般普通人は、同時に遺言相続と、無遺言相続を以て、相続せらるることを得ざればなり。然れども兵士は常に可能なり。彼等にとりては、遺言に於ける意思は、其の欲するが侭、法律たればなり。故に兵士が遺言に当りて、「某は三unciaに付て予の相続人たる可し」を謂へるときは、無遺言相続人は九unciaを取得す可し。人遺言に当りて、過小のuncia内に、asを縮小せしむることを得るが如く、過大のunciaに、これを拡大することも可能なり。例へば「某は十unciaに付て、又某は六unciaに付て、予の相続人たる可し」と謂ふことを得るが如し。
六 若し予が多数人を相続人に書き記し、彼等が平等に、予の相続財産を取得す可きことを欲するときは、「某と某及び某は予の相続人たる可し」と謂ひて、割合を定めずして彼等を相続人に書き記すを以て足る。蓋し予がunciaを指定せざるときは、平等額が彼等に取得せらるればなり。若し予が不平等の割合にて、彼等を相続人と為さんとせば、一定の割合を以て、彼等を相続人に書き記し、「某は四、某は六、某及び某は一ウンキアに付き、予の相続人たる可し」と謂ふことを要す。若し多数人を相続人に書き記すに際して、一人に付てはunciaを表明し、一人には割合を定めずして、指定したるときは如何。果して割合を定められざりし者は、幾何を取得す可きか。吾人は、若し偶々甲を五uncia、乙を三uncia、丙を二unciaに付て、相続人に書き記し、「丁は予の相続人たる可し」、或は更に「丁戌及び己は相続人たる可し」と謂ひたるが為、asに幾何かの残余が存するときは、割合を定められざりし一人又は三人は、二unciaを取得す可し。若し一人には六uncia、一人には四uncia、一人には二unciaの割合にて、相続人に書き記して、既に三人へasを費し、更に割合を定めずして、一人又はそれ以上の者を附記したるときは、割合を定めずして書き記されたる者が、取得す可きasの残余は、何等存せざるを以て、其の場合には、遺言者が二十四unciaにて遺言するものと観ぜらるるものとして、割合を定められざりし一人又は数人に、半額が与へらる。故に割合を定められざりし者は、或はasの残額か或はasの半額を取得することとなる。而て割合を定められざりし者が、冒頭に書き記されたると、総ての者の終なると、或は全部の者の中間たるとを問ふことなし。結果は常に同一たる可し。
七 予多数人を、一定の割合を定めて、相続人に指定したり。而て彼等にas〔全部〕を消費せす、尚幾分の残余あり。此の残余は何人に取得せらる可きか。吾人は、残余は書き記されたる者に、暗黙に添加すと謂ふ者なり。例へば予三人を、三unciaの割にて、相続人に指定し、其の結果他の三unciaが、残余として残されたり。これは相続分に応じて、相続人に書き記されたる者の各々に、暗黙に添加せられ、あたかも各人はasの三分の一に付き、指定せられたると同然、結果に於て各四unciaに付て相続人に書き記されたる者が、現はるることとなる。反対に予若し割合を定めて、多数人を相続人に書き記し、割合を定めたる指定に於て、十二unciaを超過するときは、超過額は各人より減額せらる。例へば予四unciaの割にて、四人を相続人に指定したり。法律は各人より、各一unciaを控除し、結果に於て各三uncia宛を有する者が、現はるることとなる。
八 予割合を定めて、多数人を相続人に書き記し、而て十二unciaを超過し、尚他の者を割合を定めずして、附加したり。割合を定められざりし者は、果して幾何を取得す可きか。吾人は、二asを充たさんが為に、残されたる額と謂ふ者なり。例へば、予若し「甲は予の為、五unciaに付て、乙は六unciaに付て、丙は八unciaに付て、相続人たる可し。尚丁も相続人たる可し」と謂ふときは、吾人は丁は残余の五unciaを取得すと謂ふ者なり。蓋し十九unciaが、割合を定められて相続人に書き記されたる者に、残さるるが為なり。三人に二asを費消し、其の後にて、或る者を割合を定めずして、附記したるときも同一なり。彼は一asを取得す可く、其の結果全額は三十六unciaとなり、二十四又は三十六unciaを一asの力に引き下ぐることとなる。
九 相続人を書き記すは、単純にても、条件附にても可能なり。単純にとは、「某は相続人たる可し」の如し。条件附とは「某は若し船がアヂアより来れるときは、云々」の如し。或る時期より、又は或る時期迄、或る者が有効に相続人に書き記さるることはなし。例へば「某は予の死亡後五年にして、或は四月一日より、予の相続人たる可し」、或は若し「某は一月一日迄、予の相続人たる可し」と謂ひたるときの如し。蓋し一日より、又は一日迄なる期限が抹消せられて、指定は単純に書き記されたると、同様となればなり。
一〇 予「某は若し海を呑みたるときは、予の相続人たる可し」と謂ひて、不能の条件の下に、何人かを相続人に指定し、或はかかる条件の下に、何人かに遺贈又は信託遺贈を遺し、或は奴隷に自由を遺したり。不能条件は抹消せられて(蓋し何等書き記されざるものと、看倣さるればなり)、遺されたるものは、単純なるものとせらる。
一一 予某を多数の条件の下に、相続人に指定したり。全部が成就する迄、待つことを要するかを問題とす可し。而て吾人は、若し結合的に(coniunctim)書き記されたるとき(蓋し某は若しカピトリウムに到り、又船がアヂアより到着し、更に某が執政官となれるときはと謂へるが為)は、全部の成就を待つことを要すと謂ふ者なり。予若し「某は若しカピトリウムに到るか、或は若しチチウスに百金を与へたるときは」と謂ひて、分離的に(separatim)書き記したるときは、それ等の中欲する一をを成就せしめて、相続人となる可し。
一二 未だ見たることなき者と雖も、有効に相続人に書き記す〔ことを得〕。例へば或る者外国に赴く兄弟を有し、此の者子を儲けたり。彼は未だ見たることなき兄弟の子を、有効に相続人に書き記すことを得。何故となれば、相続人に関する遺言者の不知は、指定を無効となすことなければなり。
第十五章 通常補充指定に付て
遺言者には、指定並びに補充指定を行ふこと、簡単に謂はば、相続人の多数の段階を設くることは、故障あることなし。段階とは、十二unciaを有するものを謂ふ。蓋し吾人には下の如くにして、遺言を為すこと可能なればなり。即ち「甲は相続人たる可し。若し甲が相続人たらざるときは、乙が相続人たる可し。乙が相続人たらざるときは、丙が相続人たる可し。丙が相続人たらざるときは、丁が相続人たる可し」と。而て吾人は無限に指定を為し、最後の場所、或は段階に於て、窮極の救済手段として、吾人の奴隷を指定することを得。若し総ての者が拒絶するが如きことあらば、奴隷をして必ず相続せしめんが為なり。
一 吾人は一人を一人の下に指定することも、一人のもとに多数の者を指定することも、多数の者の下に一人を指定することも、更に多数の者の下に多数の者を指定することも可能なり。一人の下に一人をとは、例へば「甲は相続人たる可し。甲若し相続人とならざるときは、乙が相続人となる可し」の如し。一人の下に多数の者をとは、下の如し。「甲は相続人たる可し。若しならざるときは、乙及び丙が予の為、相続人たる可し」と。多数の者の下に一人を指定するには、次の如くにす。即ち「甲及び乙は予の為、相続人たる可し。若しならざるときは、丙が予の為、相続人たる可し」と。而て多数の者の下に多数の者をとは「甲及び乙は予の為、相続人たる可し。若しならざるときは、丙及び丁が予の為、相続人たる可し」の如くにす。更に吾人は互に相続人を、他の相続人の下に指定することも得。例へば「甲は六unciaに付て、又乙も六unciaに付て、予の為相続人たる可し。若し甲がならざるときは、乙が同人の割前に対して、補充被指定者たる可し。若し乙が承継せざるときは、甲が乙の割前に対して、補充被指定者たる可し」の如し。
二 若し不平等の割合にて、或る者を相続人に書き記し(例へば一人は七uncia、他は五unciaの如く)、補充指定には、何等割合に付て示す所なくして、互に彼等を補充指定したるときは、補充被指定者は、自己が補充被指定者とせられたる者【指定相続人】が承継せしならんには、受く可かりし額を取得す可し。蓋し若し五unciaに付て、相続人に書き記されたる者は承継し、七unciaに付て相続人に書き記されたる者は、拒絶するが如きことあらば、甲は補充指定よりして、五unciaを取得す可しと謂ふを要せず、七unciaと謂ふことを要す。其の額を乙は取得す可かりしが故なり。
三 某なる者甲を六uncia、乙を六unciaに付て相続人に指定し、次で次の如く謂ひたり。「若し乙が相続人とならざるときは、甲が相続人たる可し。若し甲が相続人とならざるときは、丙が相続人たる可し」と。セウェールス及びアントーニーヌスは、甲のみが相続せざるときたると、甲及び乙が相続せざるときたるとを問はず、丙は何等の区別なく、相続することを得るものと解答し給へり。
四 予汝の奴隷を自主権者なりと信じて、相続人に指定したり。而て次の如く附言せり。「若し予の為相続人とならざるときは、マエヴィウスが相続人たる可し」と。予の死亡後、汝は予が相続人に指定したる汝の奴隷に、承継を命じたり。補充指定が発生するかを問題とす可し。而て吾人は、補充被指定者は半額を取得すと謂ふ者なり。然れども人ありて、補充被指定者が全部を取得することを要すと謂ふ者あらん。蓋し遺言者は「某は予の相続人たる可し。若しならざるときは、マエヴィウスがなる可し」と謂ひたればなり。此の場合には、指定せられたる者は奴隷にして、相続人たることを得ざれば、補充被指定者が、全遺産へ召喚せらるることを要するに非ずや。然れどもこれに付ては、「若し相続人とならざるときは」なる言は、若し指定せられたる者が、権力服従者にして、このことを遺言者も知る場合には、若し指定せられたる者自身も相続人となることなく、他人を相続人となす、即ち〔他人の為に〕取得することもなく、其の結果補充指定が発生するときは、の意に解することを要すと謂はざる可からず。然るに遺言者が自主権者なりと信じたる今の被指定者に付ては、「若し相続人とならざるときは」とは、若し相続財産を自己又は後日自己が権力服従者たることを開始す可き他人の為に取得せず、其の結果補充指定は全遺産に付て発生するときは、の意を表現するなり。かくの如き場合には、自主権者と考へられたる者は、既に権力服従者なるが故に、これが為半額は補充被指定者が取得す。これ、至聖アントーニーヌスも亦、己が奴隷パルテニオスに付て、解答し給ひし所なり。蓋し或る者皇帝の奴隷パルテニオスを自由人と信じ、「若しパルテニオスが予の相続人とならざるときは、マエヴィウスが相続人たる可し」と謂ひ、補充指定をなして相続人に指定したるに、其のとき相続財産の半額が、パルテニオスによりて皇帝に取得せられ、補充被指定者たるマエヴィウスは、半額へ召喚せらる可き旨の勅法が制定せられたればなり。
第十六章 未成熟補充指定に付て
吾人は相続人に書き記されたる他人に対し、補充指定を為すことを得るのみならず、吾人の子に対しても、「予の息某は相続人たる可し。若しならざるときは、某が予の為相続人たる可し」と謂ひて、為すことを得。而てこれは通常補充指定と称せらる。他人に対しても、子に対しても、総ての者に適合すればなり。然れども他人に対しては、例へば被指定者が遺言者に先ちて死亡し、或は相続を拒絶し、或は同人が条件附に相続人に書き記されたる場合に、条件が不成就となる等の如き多くの場合に、補充指定が発生し得るに、息に付ては唯一の場合、即ち権力服従者が遺言着たる己が父に先ちて死亡せる場合にのみ、補充指定を発生す。蓋し父が子に先ちて死亡せるときは、補充指定を発生することなければなり。彼は直ちに父に対して、相続人として現はれ、仮令自ら辞退するも、無形の名称が抛擲せらるる訳には非ざればなり。蓋し相続財産なる無形的名称は、一度或る者に附着するや、他人に移転せらるることは、困難なるによる。然れども尚他の補充指定あり。これは吾人の卑属に付て発生す。卑属に止まらず、権力服従者に付て発生す。更に権力服従者に止まらず、自権相続人たる未成熟者に付て〔初めて〕発生す。而てこれが取扱はるるときの年齢よりして、未成熟補充指定と称せらる。而て吾人は未成熟補充指定をば、次の如くにして行ふことを得。即ち「息は予の相続人たる可し。若しなりて、未成熟の中に死亡するときは、某が同人の相続人たる可し」と。而て若し子が相続人となりて、未成熟中に死亡するときは、補充指定の発生を見る。更に未成熟補充指定に、通常補充指定を交へて、所謂通常・未成熟補充指定を、次の如くにして為すことを得。「息は予の相続人たる可し。若しならざるとき(これ通常補充指定に特有なり)、或はなるも未成熟の中に死亡するときは(これ未成熟補充指定に特有なり)、某が予の相続人たる可し」と。而て子が父に先ちて死亡したるときは、汝は何をか謂ふ可きか。前の文言によりて、補充被指定者が父の相続人となる。然れども若し父が先に死亡し、子が相続人として現はれて、未成熟中に死亡したるときは、次の文言によりて、未成熟補充指定を発生し、補充被指定者は相続人となるも、父の相続人に非ずして、子の相続人なり。此の未成熟補充指定の実体は、特別の法律に基きて発案せられたるに非ずして、不文の慣習よりして、移入せられたるものなり。蓋し未成熟者なれば、遺言を為すこと能はざるを以て、彼等に代つて、父が遺言を作成したるなり。
一 次の如き事情に動かされ給ひて、吾人の至聖の皇帝は勅法を発布し給ひ、これを其の勅法彙纂中に、書き記す可き旨を命じ給へり。其の勅法の中には、次の如き場合に対して、軫念を用ひさせ給ひたり。蓋し人若し精神錯乱者、或は心神耗弱者となれる息、孫、又は曾孫を有するときは、性の如何、親等の如何を問はず、仮令成熟者たりとも、未成熟補充指定に倣ひ、かくの如き子が精神耗弱又は精神錯乱の中に死亡するが如き場合に備へて、父は某なる者を補充指定することを得可しと宣し給ひたればなり。若し精神状態恢復せば、補充指定は失効す可き旨を命じ給へり。これ未成熟補充指定の類似に従ひて、発案し給ひし祈なり。未成熟補充指定は、未成熟者が成熟者となると同時に無効となる。
二 上述の形式に従ひて、未成熟補充指定が調成せらるるときは、或る意味にて二個の遺言が存在す。一は父より子に対して行はれたるもの、他はあたかも子自身が、自己自身に相続人を指定したると同じく、子より補充被指定者に対して行はれたるものなり。或はむしろ(若し真実を謂ふを要するならば)遺言は一個にして、相続財産は二個ならん。一は父より子へ齎らされたるもの、他は子より補充被指定者へ到達せしものなり。蓋し未成熟者が父より受けたる総てのもの、或は同人が父の死亡後儲けたるものは、補充被指定者へ移転すればなり。遺言が一個なることは、唯七人の証人が徴せらるるに過ぎざることよりして明かなり。若し遺言が二個ならば、十四人の証人が立会ふことを要す可し。
三 未成熟補充被指定者が、〔未成熟者の〕父の死亡と同時に、自己が未成熟者の補充被指定者たることを知りて、未成熟者に対して、陰謀をたくらまずやとの、極めて深き危惧の念に、子に対し未成熟補充指定を行はんとする者が陥ることは、往々発生する所なり。年齢の弱小の故に、未成熟者が陰謀に陥るは容易なり。故に若し惧を懐く父ありて、それより生する惧を除去せんと欲せば、未成熟者を相続人に書き記し、通常補充被指定者を未成熟者の相続指定の直後に、惧を懐くことなくして書き記す可し。蓋し同人は未成熟者に対して、陰謀者たることを得ざればなり。父の存命中も然り。遺言の中に記されたることは、知るに由なければなり。遺言者の死亡後も然り。子が父に対して相続人として現はれ、通常補充被指定者に発生の余地を与えざればなり。何人も何等の利益なきに、未成熟者に対して陰謀をたくらむことなし。是等は通常補充指定に関してなり。人若し未成熟補充指定を調製せんと欲せば、次の如く謂ふ可し。「息は予の相続人たる可し。若しならざるときは、某が予の相続人たる可し」と。而て後見人、遺贈、信託遺贈、自由を遺したる後、遺言の最終の部分に於て、次の如く文言を記す可し。「若し予の息が相続人となりて、未成熟中に死亡するときは、某が同人の相続人たる可し」と。而て此の部分は、特別の糸を以て結び、特別の蝋を以て封緘せよ。而て遺言の前部には、次の文言を記す可し。「予は遺言書の後部は、予の息が生存中にして、未だ未成熟たる間は、開封ことを欲せず」と。蓋しかくの如くにして、未成熟補充指定が行はるるときは、子は陰謀をたくらまるることなかる可し。蓋し父自身の存命中は、全遺言が密封せらるるを以て、又父の死亡後は、未成熟補充指定中に記さるる所は、知るに由なきを以て、陰謀をたくらむ余地なければなり。人若し遺言を為し、未成熟の子を相続人に書き記し、直ちに未成熟補充指定を移入せば、補充指定は均しく有効なり。唯かくの如くなすことを欲し、未成熟補充指定を、子を自己の為の相続人に指定したる場所に記すときは、子に関する限り、危険なる遺言を為すものと観ぜらる。
四 相続人に書き記されたる未成熟の子に対し、親が未成熟補充指定を為すことを得るのみならず、廃除者となれる同人に対しても、行ふことを得。即ち子が未成熟補充被指定者を受くるは、権力を原因とし、相続人に書き記さるるが為には非ず。従つて吾人は、廃除者たる子に対しても、良く補充指定を行ふなり。然れども人ありて、廃除せられたる未成熟の補充被指定者は、何をか受く可きかと謂ふ者あらん。吾人は、若し親族又は父の友人の相続、遺贈又は贈与よりして、未成熟者に何物かが到達するが如きことあらば、それは総て補充被指定者に赴くと称するものなり。相続人に書き記され、又は廃除者となりたる未成熟の子の補充指定に付て述べたる所と同一のことは、後生児に付ても吾人これを引用す。蓋し吾人は後生児に対しても、次の如くにして、通常の補充指定を為すことを得ればなり。即ち「後生児は予の為相続人たる可し。若しならざるときは、某が予の相続人たる可し」と。而て〔相続人〕になることなきは、若し生まれず、或は生まるるも、父に先て死亡するときなり。未成熟補充指定は、次の如くにして行ふことを得。即ち「後生児は予の為相続人たる可し。若しなるも、未成熟の中に死亡するときは、某が同人の相続人たる可し」と。而て同人に対し通常・未成熟補充指定を行ふこと〔を得る〕は、上述せし所よりの当然の結論なり。
五 次のことを予備知識として保持す可し。父が自己の為に相続人を書き記す遺言中の部分は、主要部と称せられ、未成熟の子に補充指定を行ふ部分は、未成熟部と称せらる。未成熟部は主要部に依拠し、主要部より効力を取得す。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。吾人は吾人の未成熟の子に対し、補充指定を為すことを得と謂ひたるも、自己に相続人を書き記したるとき、即ち主要部を作成したるときのことと考ふ可し。此の部が作成せられざるときは、未成熟部は、よりて以て自己の為に効力を取得す可きものを有せざるを以て無効なり。蓋し未成熟部は、主要部の一部、従物も同然なればなり。而て主物存在せざるときは、従物又これを発見することを得ず。而て未成熟部がそれ【主要部】よりして効力を受くる程度は、主要部が効力を発生せざるときは、未成熟部も有効たることなき程なり。蓋し自ら主要部に於て、自筆を以て相続人の名を記さざるも、未成熟部に於ては、これを実行したるものと仮定せよ。主要部が無効なるを以て、未成熟部には何等の効用なし。
六 多数の未成熟の子を有する者は、各一人に未成熟補充指定を為すことを得、或は未成熟にて死亡する最終の者に、為すことも得。然れども未成熟の子の何人もが、無遺言にて死亡することを欲せざる場合には、各一人に対し、別々に補充指定を行ふ可し。若し無遺言相続を子のもとに保存せんと欲せば、未成熟にて死亡する最終の者に補充指定を行ふ可し。而て若し他の者が死亡するときは、残存の兄弟が遺産を取得す可く、若し彼等の中の一人が最後の未成熟者として死亡するときは、補充被指定者が現はる可し。
七 予は未成熟者に対して、指名的に補充指定を為し、「若し息が予の相続人となり、未成熟中に死亡するときは、チチウスが同人の相続人たる可し」と謂ふこと得。又一般的に同人に対して、補充指定を為すことも得。例へば予多数の者を、予の息と共に相続人に指定し、或は多数の者を、相続人に書き記して、子は廃除者と為せり。予は「若し何人か予、即ち父の為相続人となるときは、予の子が未成熟にて死亡する場合には、其の補充被指定者たる可し」と謂ひて、一般的に補充指定を為すことを得。此の言によりて、補充指定に基き、相続人に書き記され、且つ相続人にもなりたる者が、未成熟者の財産を承継す可し。蓋し若し相続人に書き記されたる者が、主要部を拒絶するときは、未成熟補充指定に基くものを、取得することなかる可ければなり。未成熟者の資産は、相続分に応じて、即ち父を相続したる丈の額に応じて、分割せらる。
八 然れども男の子に対しては、十四歳に至る迄は、補充指定を為すことを得。娘に対しては、十二歳迄なり。彼等が此の年齢を経過するときは、補充指定は効力を失ふ。
九 何人も家外の子、又は成熟の子に対しては、これを相続人に書き記すも、未成熟の子に倣ひ「某は予の為相続人たる可し。若し相続人となりて、(例へば)三十歳以前に死亡するときは、某が同人の相続人たる可し」と謂ひて、補充指定を為すことを得ず。唯次の如きことのみを為すことが、吾人に許さる。即ち某を相続人に書き記し、信託遺贈によりて、他人に遺産の全部又は一部を返還する様、同人を拘束することは可能なり。信託遺贈の実体が如何なる効果を有するかは、然る可き場所にて説かる可し。
第十七章 如何にして遺言は失効せしめらるるか
吾人は遺言が如何にして、合法的に成立するかを知りたり。然れども若し〔法律の〕厳正に関する事項の何物かが無視せらるるときは、遺言はは市民法に従ひて為されざるもの、或は簡単に謂はば、非合法(iniusta)と称せられる。偶々証人の法定数が遵守せられざるとき、或は七人の立会あるも、全部が下書せざるとき、或は全部が下書するも、捺印せざるとき、或は是等のことは実行するも、遺言者は自筆を以て相続人の名を書き記し、或は証人の面前にて、将来同人の相続人たる可き人を指名することをせざるとき、或は自権相続人たる子を有する者が、これを相続人にも指定せず、廃除者ともなさざるが為の如し。是等総てに付て、遺言は市民法に従ひて為されざりしものと称せらる。若し是等の事項中の何物も無視せられずとも、常に必ずしも死亡の時迄、遺言に効力が存する訳に非ず。蓋しruptaとなりinritaとなることあればなり。
一 次の如くにしてruptaとなる。某何等の瑕疵なく、遺言を為したり。遺言者が同一状態に止まるも、遺言の効力は減殺せらる〔ることを得〕。蓋し某遺言の作成後、或は自主権者を皇帝のもとに、或は吾人の至虔の皇帝の勅法の言に従ひ(即ち収養者が祖父なるときなり。其の時には養子縁組は自己の効力を発揮す)、権力服従者を政務官のもとに収養するときは、後生児の出生したるときと同じく、遺言は新自権相続人の附加によりて、破壊せらるればなり。
二 又合法的に完成したる後の遺言は、前の遺言を破壊することを得。後の遺言によりて、何人かが相続人となると、ならざるとを問はず。但し常に相続し得可かりしことを必要とす。蓋し吾人は、或る場合に相続し得可かりしや否やの一事のみを観察すればなり。然らば如何にして相続し得る者が、相続せざるか。例へば後の遺言に於て、相続人に書き記されたる者が拒絶し、或は遺言者の存命中、又は遺言者の死亡後承継前に死亡し、或は条件下に書き記されて、条件が不成就となりたるものと仮定せよ。是等の場合には、遺言者は二個の遺言を作成して、無遺言にて死亡する結果となる。前の遺言は後の遺言の作成によりて破壊せられ、後に作成せられたるものは、それによりて相続人となる者なき為、効力を発生することなし。
三 某若し遺言を為して、甲を相続人に書き記し、其の後暫くして、次の遺言の作成に進みたり。其の遺言も「乙は某々の財産に付て、予の相続人たる可し」と謂ひて、乙を相続人に指定して、合法的に作成したり。かくの如くにしても、初の遺言は均しく破壊せらる。蓋し乙が次の遺言に於て、或る部分に付て相続人に書き記さるることは、相続人の指定を無効となすことなければなり。これ神聖セウェールス及びアントーニーヌスも指令し給ひし所なり。此の勅法の文言は下の如し。(蓋し此の文言を掲ぐることは、他に此の文言よりして啓示し得可き、或る必要なる事項も存するを以て、軌を逸したることには非ざる可し)某遺言に当りて、多数の者を相続人に書き記し、次の遺言に於て、他の者を特定財産に付て相続人に指定し、前の遺言は依然として有効たる可きことを欲する旨を附言せり。彼死亡せり。事件はセウェールス及びアントーニーヌスに達し、帝はコクケーウス・カンパーヌスに解答し給へり。曰く「第二次に作成せられたる遺言は、仮令同遺言に於て、某が或る特定財産に付て、相続人に書き記されたるとも、均しく前の遺言を破壊す。あたかも後の遺言に於ける指定が、財産を示すことなくして行はれたると同じ」と。〔然れども〕後の遺言に於て、〔相続人に〕書き記されたる者が相続す可きも、同人は相続人として書き記されたる額の財産に甘んじて、前の遺言に於て指定せられたる相続人に対し、財産の返還に付き拘束せらる。唯同人に遺された物が、ファルキヂアに満たず、其の結果四分の一に満たざる額が補足せらる可きときは、此の限りに在ずと命じたり。其の理由は、前の遺言は有効なりと謂へる後の遺言に書き記されたる文言にあり。故に破壊の瑕疵は、幾多の方法によりて発生す。即ち看過せられたる後生児の出生、代襲せる新自権相続人、附加せられたる新自権相続人、後の遺言の作成は、遺言を破壊す。然れども、これは破壊の瑕疵に関することなり。
四 失効(τὸ inriton)も亦、作成せられたる遺言を解消す。例へば遺言者がcapitis deminutioを受けたるときの如し。如何なる方法にて発生するかは、吾人は前の法学提要にて詳述せり。蓋し若し遺言者が最大のものを受けて奴隷となり、或は中間のものを受けて市民権を喪失し、或は最小のものを受けて、自己をadrogatioの養子に与へて、権力服従者となるときは、遺言は失効す。
五 故に既に述べたるが如く、三の瑕疵が遺言に対して障碍となる。non iure civili factum, ruptum, inritumこれなり。吾人はinritumをruptumと称し、ruptumをinritumと称し、当初より合法的に作成せられざりし遺言をinritumと称し、何等区別を施すことなく名称を使用することを得。唯特に各瑕疵に特有なる名称を発案したる所以のものは、特別の名称よりして、発生せる瑕疵を知りて、これを区別することを得んが為なり。
六 然れども上記の三瑕疵は、〔単に〕市民添上の遺言を破壊す。法務官法上の遺言には触るることなし。何故となれば、法務官法上の遺言に付ても、non iure civili factumなる瑕疵を云々するは、笑止干万なればなり。ruptumの瑕疵も遺言を解消することなく、inritumの瑕疵も、遺言者が其の受けたるcapitis deminutioを逸るるが如きことあらば、解消することなし。何故となれば法務官は遺言作成の時と、死亡の時の両時を詮議し、若し両時に於て同人が遺言作成権を有することが判明するときは、中間時は、市民権又は自由身分を喪失したるか否かは、彼此詮索することなく、同人の遺言は有効と看做したればなり。蓋し七人の証人の捺印が施され、且何れの時に於ても、死亡者が遺言作成権を有するとき(即ち羅馬人にして自主権者たるとき)は、書き記されたる相続人に、遺言書に従ふ遺産の占有を附与すればなり。然れども自己をadrogatioの養子に与へ、〔再び〕自主権者となる以前に死亡したるが為、capitis deminutioを受けたる侭にて死亡するときは、法務官自身も遺言をinritumと認めて、指定相続人に遺言書に従ふ遺産の占有を約することなし。
七 某遺言を為し、遺言の作成後も生き延びて、「予は此の遺言が有効ならざることを欲す」と謂へり。かかる文言のみよりしては、遺言は無効とせらるることなし。蓋し合法的に成立せしものは、合法的に破壊せらるることを要すればなり。予は更に謂ふ、某遺言の作成後、他の遺言の作成に進み、中途にして死亡し、或は決意を変更して、其の第二の遺言を完成せざりしときは、至聖ペルチナークスの勅法制定せられて、前の遺言は有効なりと命じ給へり。蓋し曰く、合法的に作成せられたる前の遺言は、次の遺言が合法的に遂行せらるるに非ざれば、後の遺言によりて無効とせらるることなし、蓋し完成せざる遺言が無効なるは、争の余地なければなりと。
八 該勅法には、或る者が或る者に対して、訴訟を有するが故に、皇帝を相続人に指定したるが如き指定は、有効たらざる可きことも亦包含せられ、かかる遺言を有効と呼び給ふこともなく、皇帝に対して文書によらずして為されたる指定を受け給ふこともなく、法律の完全なる権威存するに非ざれば、〔如何なる〕書面によるも、自らは何物をも受納を忍び給ふこともなしと宣し給へり。至聖のセウェールス及びアントーニーヌスは、屡々此の勅法に従ひて、法律の拘束は受けずと雖も、仍法律に従ひて生活すと勅答し給へり。licet enim legibus soluti sumus attamen legibus vivimus!吾人はかくも有難き御言葉を畏み奉りて、これを口にすることを要す。
第十八章 不倫遺言に付て
吾人は前述せし所に於て、尊属が遺言を為すに当りては、卑属を相続人に書き記すことなく、廃除を為し、或は看過が廃除と解せらるる者に対しては、看過を以て卑むことを得可き旨を述べたり。然れども尊属がかかる権限を行使するときは、己が卑属を貧困に陥れて、これを害したり。何故となれば、男性による【父方】尊属の何人かが、卑属を廃除者となすときは、遺言は法律上当然に無効となることなく、卑属は無遺言承継を為すことも不可能なりしを以てなり。蓋し遺言の存在せるときに、如何にしてかくの如きことを為し得んや。法務官より遺言書に反する遺産占有を有することもなし。それ【遺言書に反する遺産占有】は、看過せられたる者には附与せらるるも、廃除せられたる者には、附与せられざればなり。若し遺言者が母なるときは、母方の卑属は、遺言書に反する遺産占有に心を寄することを得ず。女性の遺言に対抗しては、遺言書に反する遺産占有は、卑属に附与せらるることなければなり。茲に於て最後の救済手段として、自己は不当に廃除者とせられ、或は看過せられたること争ひて陳述を為し、死亡者は遺言を作成せしときには、精神錯乱者たりとの色を盾にとる卑属の為に、不倫の訴が発案せられたり。而て卑属がこれを主張するは、真実に死亡者が精神錯乱せるものとしてには非ずして、遺言は有効に作成せられたるも、慈愛の道の要求するが如くには為されざるものとしてなり。蓋し若し真実に精神錯乱せしならんには、遺言を為すことを得ざりしならん。むしろ自然を理由なく嫌悪したるが為、其の点に於て精神錯乱を起したる〔ものと観ぜらるる〕なり。
一 尊属の遺言に付き、正当に作成せられざるものとして、訴を提起することが、卑属に許さるるのみならず、尊属にも、卑属の遺言を覆す権能あり。姉妹及び兄弟が、死亡者の遺言を覆して、指定相続人に優先せしめらるるは、相続人に書き記されし者が、卑しき人格の持主なるときなり。例へば馭者、俳優、闘獣士、及び恥づ可き姦通に付き有責とせられたる者の如し。これ神聖なる諸勅法中に包含せらるる所なり。故に尊属及び卑属は、死亡者に対して忘恩者とならざる限り、総ての指定相続人に対し、不倫の訴を提起することを得可く、兄弟及び姉妹は、卑しき者に対してのみ然り。兄弟及び姉妹以上の親族は、不倫の訴に至る途なく、訴を起せば敗訴す可し。
二 子は実子たると養子たるとを問はず、吾人の皇帝の勅法の述ぶる所に従ひ、不倫の訴を提起す。不倫の訴を提起する者は、他の総ての救済手段を奪はれたる場合にして、初めて良く此の訴を用ふ。蓋し不倫の訴に基く救済手段は、最終的なればなり。蓋し尚外に他の権利を有し、それによりて死亡者の全部又は一部の財産を取得し得可き者は、不倫の訴に至る可き術なきによる。此のことは、既に生まれたる子に付て考ふることを要するに止まらず、後生児に付ても亦然り。
三 是等は、死亡者によりて彼等に全然何物も遺されざるときに初めて、吾人これを容認す。これ自然に適する尊敬の情を保存し給ひし吾人の至聖の皇帝の勅法によりて、発案せられたる所なり。蓋し古くは、負はれたるものの全額が遺されざるときに、不倫の訴発生したればなり。例へば某四百金の資産を有したり。彼は不倫の訴が提起せられざらんが為には、全部にて百金、即ち資産の四分の一を遺すことを要したり。然れども今日に於ては、廃除者に一金、又は相続財産の幾分、或は又何等かの財産が遺されたるときは、不倫の訴による争は停止し、仮令遺言者は自筆を以て、「若し何物かが欠くる所が発見せられたるときは、予はそれが善き人間の判断によりて、追完せらる可きことを欲す」とは謂はずとも、勅法は無遺言相続分の四分の一に欠くるものを補充す。蓋しこのことは附記せられずとも、該勅法は自然に従ふものと解したるなり。
四 人若し父の意思を是認したるときは、不倫の訴によりて、これを覆すことを得ず。これよりして、次の如きことが問題とせられたるを見よ。予の権力服従者、某未成熟者の後見を行ひたり。予死亡に当りて、他人を相続人に書き記し、予の権力服従者を相続より廃除し、尚権力服従者が後見人たる未成熟者に、遺贈を遺したり。予の子は未成熟者に遺されたる遺贈を要求したり。彼其の後、父の財産よりして、何物をも取得せざる者として、不倫の訴を提起せんと欲したり。可能なるか、或は又遺贈を請求したることによりて、死亡者の意思を認めたるものとして、何等かの不利を来さざるか。吾人は、或る後見上の義務を遂行して、遺贈を取得したるものなれば、彼は何等の不利益を受くることなく、其の結果、自己の名に於て、不倫の訴を提起するに、何等の障碍なしと謂ふ者なり。
五 又反対に次のことも問題とせらる。予未成熟の権力服従者たる子を有したり。他人を相続人に書き記し、子には何物をも遺さずして、廃除者と為したり。而て予が未成熟者に対し、遺言後見人として遺し、或は政務官が〔後見人として〕附与し、或は法律により適当に〔後見人に〕召喚せられたる某チチウスに、百金を遺贈したり。チチウスは未成熟者の名を以て、不倫の訴を提起し、未成熟者の廃除に理由あることが判明したるが為敗訴せり。其の後チチウスは指定相続人に迫り、自己に遺されたる遺贈を同人に要求せり。これが受理せらるることは、争の余地なし。
六 相続財産の中に存するにせよ、或は遺贈の中に存するにせよ、或は信託遺贈又は死因贈与の中に存するにせよ、無遺言相続分の四分の一が遺留せらるるときは、不倫の訴を排除す。生前贈与は算入せらるることなし。但し吾人の至聖の皇帝の勅法が記す場合に、該当するが如き場合に、贈与せられたるときはこれを除く。尚其の他古き法律、及び神聖なる勅法に包含〔規定〕せらるる方法に於て、四分の一が子に取得せらるるときは、不倫の訴は停止す。而て若し子が一人なるときは、自己の資産の四分の一を同人に遺すことを要し、二人又はそれ以上なるときは、一様に且【むしろ「又は」と謂ふ可きならん】割合に応じて、全部の者に遺されたる四分の一が、不倫の訴を停止せしむ。例へば二人あるときは、同人に各一uncia半を、三人なるときは、各一unciaを遺すことを要するが如し。
第十九章 相続人の性質及び区別に付て
相続人とは一般的名称なり。而て三に分たる。蓋し相続人の中、或る者は必然相続人、或る者は自権必然相続人、或る者は家外相続人なればなり。
一 然らば必然相続人とは如何なる者なるか。相続人に書き記されたる奴隷なり。かく呼ばるるは、欲すると欲せざるとを問はず、常に主人の死亡後は、直ちに自由人となりて、必然相続人となるが為なり。故に自己の財産状態に懸念を懐き、遺産の貧弱の故に、何人も其の遺産を引き受くることを敢てせざる可しとの疑を懐く者は、己が奴隷を第一位又は第二位又は第三位、更には其れ以下の順位に於て、相続人に書き記す習なり。例へば「予の奴隷スチクスは相続人たる可し」の如きは、第一順位に於てなり。第二順位に於てとは、次の如くにす。「甲は相続人たる可し。若しならざるときは、予の奴隷スチクスが相続人たる可し」と。其れ以上も同じ。而て若し何人も遺産の承継を敢てせざるときは、スチクスは当然に自由人となり、且相続人となる可し。而して仮令死亡者の債権者に対し、債務を返済することもなく、債務に対する保証も、彼等に為されずとも、死亡者は不名誉者ならざる者として止まる。唯相続財産は売却せらるるも、債権者は某死亡者の財産が、売却せらる可き旨を述ぶるに非ずして、相続人スチクスの財産が、売却せらる可き旨を述ぶるなり。而して債権者は遺産の占有を得て、或はこれを売却に附し、或は相互の間に分配す。かかる不名誉の代価としては、第一に何よりも貴き自由を取得す可く、次には次の如きものも、同人に帰属す。即ち仮令死亡者の資産は、債務を充たすには足らずとも、己が保護者の死亡後、スチクスが他の原因によりて、換言せば相続の理由に基かずして取得したる物は、同人に保存せられ、債権者によりてかき乱さるることはなし。これ必然相続人なり。
二 自権必然相続人とは、如何なる者なるかを吾人は研究す可し。自権必然相続人とは、例へば息娘、息よりの男孫女孫、及び以下これに続く総ての卑属にして、死亡の時に権力に服する者なり。然れども息及び娘は、常に自己のもとに自権相続人たる資格を有するも、男孫及び女孫は、自権相続人たる資格を取得せんが為には、死亡祖父の権力服従者たるときに、自権相続人の権利を有するのみならず、彼等の生みの親たる彼等の父が、其の父の権力服従者たることを、已めたることを要す。同人が権力より解免せらるるは、死亡によると、家長権免除によると、或は其の他如何なる方法によるも可なり。其の時初めて、男孫又は女孫は、己が父の地位を襲へばなり。而して自権相続人と称せらるるは、家内相続人なるが為、即ち父の生存中に、或る程度所有者と観ぜらるるが為なり。これが為十二表法も、無遺言相続の順位を定むるに当りて、第一召喚順位を彼等に附与したり。自権相続人と呼ばれしは、上述の理由に基く。必然相続人とは、欲すると欲せざるとを問はず、常に遺言並びに無遺言相続人となるが為なり。然れども市民法に従へば、必然相続人と自権必然相続人には、何等の差別なきも、法務官は自然上の権利に着眼して、彼等【自権必然相続人】が父の遺産は疑はしと考へたる場合には、自ら父の相続財産を拒絶する権能を、彼等に附与したり。何故となれば、両人【相続人と被相続人】が生来自由人なるときは、均しくそれよりして、不名誉を感ずる生存者よりも、むしろ死亡者が卑めらる可ければなり。故に同人が拒絶するときは、死亡者の財産は、債権者が取得す可きも、子の名のもとに取得するには非ず。
三 家外相続人とは、これ以外の総ての者にして、死亡者の権力に服せざりし者なり。故に吾人の子にして、家長権被免除者たる者も、家外相続人と称せらる。子も母に対しては、家外相続人と称せられ、且家外相続人となる可し。蓋し婦女は、子を権力内に保有することを得ざればなり。某遺言に当りて、其の奴隷を相続人に指定したり。後遺言の作成後も生き延びて、同人を棍棒を以て解放したり。彼遺言を変更せずして、死亡したり。吾人は指定相続人は、必然相続人なるか、或は家外相続人なるかを問題とす可し。而して吾人は、同人は家外相続人なりと謂ふ者なり。死亡者の遺言よりして、二個のもの、即ち自由と相続財産が、同人に帰属する訳に非ざればなり。
四 家外相続人に対しては、次のこと、即ち自身が相続人に書き記さるると、其の権力服従者が書き記さるるとを問はず、吾人が彼等【家外相続人】に対して、遺言作成権を有することを、守らざる可からず。吾人は、彼等の備ふ可き此の遺言作成権は、彼等が両時即ち吾人が遺言を作成する時(それより後、指定が有効ならんが為なり)と、吾人が死亡する時(有効に作成せられたる指定が、有用なる結果を得んが為なり)とに於て、有す可きことを要求す。然れども人若し精確に検討するときは、同人が遺言作成権を有することを要す可き第三の時をも、要求するに至らん。即ち遺産を承継する時これなり。此の点は単純に相続人に書き記されたると、或は条件の下にせられたるとによりて、何等の区別なし。蓋し相続人の権利、即ち相続人たることを得可きかは、相続を承継する時に於て、最も吟味せらるればなり。遺言の作成と遺言者の死亡、又若し条件附に相続人に書き記されたるときには、条件の成就に至る中間時に於ける、相続人の権利の変更は、承継に付き同人に何等の害を齎すことなし。故に若し予によりて、相続人に書き記されたる者が、羅馬人なるときは、遺言の作成後市民権を喪失するも、予の死亡前、又は条件附に相続人に書き記されたる場合には、条件の成就前に、これを恢復するときは、相続するに故障となることなし。故に約言せば、吾人は相続人が遺言作成権を有することを要する三個の時を問題とす。遺言作成の時、遺言者死亡の時、承継の時、即ちこれなり。就中問題とするは、遺言の作成と承継なり。遺言作成権は、遺言を為すことを得る者のみならず、仮令自身は遺言を作成することを得ずとも、他人の遺言よりして、〔自己に〕取得し、又は他人に取得することを得る者も亦、これを有すと考へらる。これが為、精神錯乱者も、唖者も、後生児も、幼児も、権力服従者たる息も、他人の奴隷も、遺言作成権を有すと称せらる。蓋し仮令遺言を為すことを得ずとも、他人の遺言によりて、自己又は他人に、取得することを得ればなり。精神錯乱者に付ては、同人が父によりて相続人に書き記されたる場合のことと想像することを要す。蓋し他人によりて、相続人に書き記されたる者は、恢復する迄は、自己の為にも、他人の為にも、相続財産を取得することを得可からざればなり。
五 家外相続人は、相続を為すか否かは、其の自由選択にあれば、任意相続人とも称せらる。其の他の者は、自ら当然に召喚せらるるが故に、必然相続人と称せらる。而て此の点に於て差異が存するのみならず、相続財産の承継は、家外相続人に付てはaditio、必然相続人に付てはimmixtioと称せらるる点に於ても差異あり。又相続財産を拒絶することは、家外相続人に付てはrepudiatioと称せらるるに、必然相続人に付てはabstinatioと称せらる。然れども拒絶する家外相続人は、何等相続財産に召喚せられざりし者と同然なるに、拒絶する自権必然相続人は、父の死亡後は、直ちに〔相続人として〕現はるるを以て、拒絶を考案したる法務官が、同人に対し、債権者より悩まさるることなからしめざる限り、均しく自己のもとに、無体物【相続財産】を保存することは、相続財産なる無形的名称は、一度何人かに附着するときは、他人に移転することは困難なりと屡々説かるるが如し。此の点に於ては差異は存するも、必然相続人が混合するも、家外相続人が承継するも、其の後は、二十五歳未満者ならざる限り、相続財産より離るることを得ざる点には共通あり。蓋しかかる年齢にある者に対しては、他の総ての事件に於て欺かれたるときと同じく、此の場合に於ても、損害を齎す相続財産を軽率に取得するが如き場合には、法務官は彼等に原状恢復を附与して援助し、以て相続財産を離れしむればなり。
六 然らば二十五歳以上の者が、死亡者の遺産を良好なるものと考へて承継したるに、後に至りて予想せざる債務が現はれ出で、それが遥かに相続財産を凌駕したるときは如何。ハドリアーヌス皇帝の勅法制定せられ、一見したるときには、相続財産は良好に見えたるも、承継の時に隠れゐたる予想外の債務が現はれ出でたる場合には、これに対して保護を与へたり。然れどもは、ハドリアーヌスは、特別の恩恵に基きて、特定の者に、此の種の恩恵を附与し給ひ〔しのみ〕、至聖のゴルヂアーヌスも、其の後兵士に対してのみ、此の種の恩恵を拡張し給へり。吾人の皇帝の仁慈は、均しき保護を、帝の版図の下に服する〔総ての〕者に与へたり。蓋し承継前に財産目録を作成す可き旨の、有名且極めて正当なる勅法を制定し、これには或る遵守事項の規定ありて、若しそれを遵守するときは、仮令貧弱なる相続財産を承継するも、相続財産の〔積極〕財産の額が集まりたる程度に於て、拘束せらる〔るのみ〕。従つて何等熟慮〔期間の制〕は必要に非ず。蓋し熟慮〔期間の制〕は、果して相続財産が受領し得可きやを知り、以て何人も不慮に損害を齎す相続財産を引受くることなき様にして、承継せんが為に、発案せられたるものなればなり。故に人若し吾人の皇帝の神聖なる勅法に包含〔規定〕せらるる所を無視して、熟慮〔期間〕を請求し、後相続財産を承継するも、勅法の保護を享有することを得ずして、全債務を請求せらる可し。
七 家外の指定相続人又は無遺言にて相続する者は、proheredegerereし、又は単なる意思のみにて、相続財産を引受くることを得。相続財産中の財産を持主として利用する者は、土地の売却又は耕作に於て、其の他一般に如何なる方法によるにせよ、若し相続財産を引受く可き旨の自己の意思を、行動又は言語によりて明かにするときは、唯遺言によりてか、又は無遺言に基きてか、相続することを知る限り、proheredegerereするものと観ぜらる。蓋し相続人に書き記されたるに、無遺言にて召喚せられたる者として、承継したるとき、或は又其の反対なるときは、相続人となることなければなり。proheredegerereとはpro domino gerereなり。蓋し古人はdominusに代ふるに、heresなる名称を用ひたればなり。「予は相続を引受く」と謂ふことによりて、単なる意思を以て、家外人が相続人となるが如く、「予は相続を承継せず」との反対の返答によりて、直ちに相続より転落す。唖者又は聾者は、生まれつきなると、後日疾病によりてなりたるとを問はず、proheredegerereし、以て自己に相続財産を取得するは疑なし。唯固より相続財産〔取得〕の目的を以て、これを行ふことを知りたるときに限る。
第二十章 遺贈に付て
遺言に関する教示の後には、遺贈に付て述ぶる必要あり。然れども人ありて、かく為すときは、教示の関聯を切断することとならんと謂ふ者あらん。蓋し包括的取得に付て、順序を追ひて述ぶることを予定し、従つて遺言に基きて齎されたる相続を述べたる者は、直ちに無遺言相続にも転じ、かくして取残されたるものを終へたる後、単独取得たる遺贈に赴くことを要したる筈なればなり。然れども弁解は手近にあり。蓋し吾人は遺言相続に付て詳言し、而て遺言の中にて遺贈も亦遺さるるを以て、これに続いて遺贈に付て述ぶるは、一理なきに非ざればなり。
一 而て先づ遺贈とは何ぞやを定義する必要あり。遺贈とは死亡者より遺されたる贈与なり。
二 然れども其の遺贈なる名称は、或る本源的のものにして、種にも均しきものなり。それよりして四の類が発生す。per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per praeceptionemこれなり。而て各種の遺贈に充てがはれたる或る典型的文言ありて、これによりて〔各〕種類が特徴付けらる。per vindicationemの文言は次の如し。「予は某に百金を与ふ」と。而てper vindicationemの遺贈は、相続人の承継と同時に、受遺者を所有者となし、以て同人をして、何人に対しても、物的訴権を提起することを得せしむ。これが為又これは、上に吾人が前触れしたるが如く、吾人に所有権を齎すそれぞれの行為の中に入れられたり。vindicatioとはvindicareよりしてかく称せられたり。これは物的訴権によりて、物に対して訴訟を提起することなり。per damnationemの文言は、「相続人よ、予は某に百金を与ふる責を汝に負はしむ」なり。これよりして、相続人に対するactio ex testamentoと称せらるる人的訴権が、受遺者に発生せり。sinendi modoは「相続人よ、予は某に対し某なる財産を取得することを許容す可き責を、汝に負はしむ」の如く謂ふ。而てこれよりしても、均しくactio ex testamentoが帰属したり。per praeceptionemの文言は「一部的相続人たる某は、某なる財産を先取す可し」なり。故に一部的相続人に非ざる者には、per praeceptionemによりては、吾人良く遺すことなし。蓋し羅馬の語にて、praecipito即ち「先取せよ」と謂ふは、相続財産中の先在部分〔ある〕を意味し、即ち同人に遺したる部分の外、尚同人が或る財産を予め取得す可きことを、予が欲すればなり。per praeceptionemはactio familiae erciscundaeによりて請求せられたり。然れども是等は古のことなり。最近の諸皇帝の勅法は、〔遺贈の〕種類がよりて以て示さる可き典型的文言を廃止したり。更に吾人の至聖の皇帝の勅法制定せられ、これをば重大なる関心を以て作成し、死亡者の希望が更に強大有効たる可きことに努力し、其の中にて、死亡者の言語に執着せずして意思に従ふ可く、其の結果総ての種類の遺贈に一個の性質が存す可く、如何なる言葉にて何物かが遺さるるも、受遺者はこれを取得することを得、人的訴権を提起せんと欲すると、或は物的訴権又は抵当訴権を提起せんと欲するとを問はずと命令し給へり。上記の勅法は尚幾多有用なることを教示す。該勅法の文言に接する者は、勅法の極めて完全なる力を完全に学ぶことを得。
三 然れども該勅法は、此の点迄にて停止することなく、更に大なる或るものを附加したり。蓋し遺贈が幾多の厳正に密着せるに、信託遺贈に付ては、むしろ遺言者の意思に篤く、従つて一層広汎なる性質を有するを見て、総ての遺贈が信託遺贈と同一にせらる可く、其の結果両者の間には何等の差異なかる可く、遺贈に欠くる所のものは、信託遺贈の性質よりして補充せられ、又何等かの点に於て遺贈に多きものあらば、これは信託遺贈と共にせらる可しと考へ給へり。然れども、遺贈と信託遺贈に付て、順序もなく混合して解説し、法律の初歩にありて未だ牢固たらざる青年の聴力を、難解なる学説の入門に於て撹乱するが如きことなからしめんが為、先づ別に遺贈に付て詳述し、然る後信託遺贈に付て詳述し、以て両者の性質を別々に知り、修業を積み、能力を備へたる後、何等の不安なく更に繊細且困難なる学説を受くるを以て、極めて適切と吾人は思惟す。
四 遺言者又は相続人の物のみならず、他人の物も亦、遺贈せらるることを得。尤も所有者が自己の物を奪はれんが為には非ず。蓋し相続人は所有者のもとに至り、売買に付て商議す可きことを強制せらるればなり。而て若し所有者が売却を希望するならば、相続人は購ひてこれを受遺者に与ふ可く、若し所有者が欲せざるが為能はざるときは、物の評価額を受遺者に交付す可し。人若し死亡に当りて、予が取引権を有せざるが如き物を、予に遺贈するときは、その遺されたる物を予に負はざるのみならず、予は其の評価額をも請求することを得ざる可し。蓋し人若し予にマルチウスの野(これ羅馬に近き公の場所なり)又は、バシリカ、又は寺院、又は公供の使用に捧げられたるもの、例へば劇場、円形劇場、競馬場を遺贈したるときは如何。蓋し此の種の遺贈は無効なればなり。吾人が少し前にて、予は他人の物を有効に遺贈することを得と謂ひたる言は、予が遺言に当りて他人の物なることを知りたるときのことと考ふることを要す。蓋し若し知らざるときは、遺贈は無効なればなり。何故となれば、物が予のものならざることを知りたらんには、予はこれを遺さざりしなる可しなる事情も、時にはあればなり。これ亦至聖ピウスの勅法に包含せらるる所なり。人若し予に他人の物を遺贈し、相続人はこれを購ひて与へ、又は評価額を交付することを欲せずして、遺言者はこれが他人の物なることを知らざるが故に、遺贈は無効なりと謂ひ、受遺者たる予は反対して、死亡者は物が他人の物なることを知るが故に、これが有効なることを主張するときは、何人が果して証明の負担を負ふ可きか。遺言者は知らずと謂ふ相続人なるか、或は同人は知ると謂ふ受遺者なるか。吾人は受遺者が証明の負担を負ひ、相続人は証明を強制せらるることなしと謂ふ者なり。蓋し受遺者は原告なれば、当然証明の負担を負へばなり。
五 チチウスが甲より金を借り、債務の為同人は自己の土地を質又は抵当に入れたり。債務返済前、チチウスが死亡に際して、其の土地を予に遺贈したり。相続人は、甲に債務を弁済し、且これ【土地】を抵当権より自由にして、予に与ふることを要す可し。而て此の場合に於ても、他人の物が遺贈せられたるときの前の設例にも適用ある同一の勅法が、適用ある可し。蓋し死亡者が物の拘束を受くることを知れる場合には、相続人は債務を弁済して、遺贈を抵当より解放することを強制せらるればなり。而てこれ至聖のセウェールス、アントーニーヌスの解答し給ふ所なり。然れども若し死亡者が受遺者が自ら抵当の拘束を解除す可きことを欲し、且其のことを特に明言するときは、相続人はこれを請戻すことを要せず。
六 予汝に他人の物を遺贈したり。予遺言の作成後も生き延ぶる中、汝受遺者は其の物の所有者となれり。相続人に対して、物自体を請求することを得ざるは(蓋し汝の所有権の下に服する物を、如何にせんや)、学説の一致する所に属す。然らば、其の評価額をも請求することを得ざるか。次の如く区別することを要す。若し汝が売買に基きてこれを得たるときは、相続人に対し遺言訴権を提起して、物の評価額を取得す可し。若し汝が贈与、或は又遺贈に基きて、其の所有者となれるときは、二個の利得原因よりして、同一物は度々取得せらるることを得ずと謂ふ原則に基きて、汝は価格を請求することなかる可し。同一の理由に基き、甲と乙とが同一物を予に遺贈し、然る後死亡するときは、予が両人の相続人に対し、遺贈を請求し得可きや否やを問題とす可し。而て吾人は次の如く謂ふ者なり。若し偶々一人の遺言よりして、物を取得するときは、他の遺言よりしては、予は物自体も(蓋し予の所有権の下に服するに、如何にして可能ならんや)、評価額をも取得することなかる可し。蓋し偶々利得原因よりして得たればなり。然れども一の遺言よりして、先づ評価額を取得したるときは、予が他の遺言よりして物を請求するは、何等の妨なかる可し。
七 吾人は自然中に存するもの【既に実在する物】のみならず、未だ存在せざるも発生の希望あるものも亦、良く遺贈す。例へば将に某なる土地より生ぜんとする果実、又は某なる女奴より生まれんとしつつある者の如し。
八 若し予が某々二人の者に同一物を、或は結合的に、或は分離的に遺贈し、両人が遺贈の請求を為すときは、遺贈は彼等の間に二個に分割せらる可し。若し一方が或は意思により、或は偶然に欠けたるときは(意思によりとは、遺贈を拒絶したるが為なり、偶然にとは、遺言者の生存中に死亡し、或は其の他如何なる方法にても——例へば市民権を喪失したる為の如し——効力を失ひたるが為なり)、全遺贈が共同受遺者に移転す。而て結合的にとは、下の如くにして遺したる場合なり。「チチウス及びセイウスに、奴隷スチクスを与へ且遺贈す」と。分離的にとは次の如し。「チチウスに奴隷スチクスを与へ且遺贈す、セイウスに奴隷スチクスを与へ且遺贈す」と。若し「セイウスに同一の奴隷を」と附言せらるるときも、均しく遺贈は、分離的に行はる。蓋し予は「チチウスに奴隷スチクスを遺贈し、セイウスに同一の奴隷を遺贈す」と謂ひたればなり。従つて「及び」なる接続詞が存するときは、結合的に遺贈を為し、若し記されざるときは、分離的にこれを行ふなり。
九 チチウスの土地を、汝死亡に際して予に遺贈したり。汝の未だ生存中、予はチチウスより同一の土地を、用益権を控除して購ひたり。即ち単なる裸の所有権を取得したり。故に用益権はチチウスのもとに止まれり。暫く経過して後チチウスは死亡し、同人の死亡によりて、同人が把持しゐたる用益権は消滅して、所有権に服帰したり。汝死亡するや、予は汝の相続人に対し、遺言訴権を提起せんと欲す。ユーリアーヌスは謂ふ、予は良く人的訴権によりて、土地所有権の評価額を請求すと。蓋し用益権は此の場合役権の地位にありて、用益権を控除したる後、相続人は予に評価額を交付す可しと命ずるは、裁判官の義務なればなり。例へば土地は用益権附にて百五十金の価あり、用益権なきときは百金なり。予百五十金を請求して訴ふるも、裁判官の義務は、予が唯所有権のみの評価額、即ち百金を取得せしむ。蓋し予が用益権の価格を取得するは、用益権は利得原因よりして予に到達したるものなるが故に、極めて失当なればなり。
一〇 某なる者予に予の土地を遺贈したり。遺贈は無効なり。蓋し予の物が一層安全に予の物となることは、不可能なればなり。仮令予が土地を譲渡するも、土地自体も、或は又其の評価額も、予に負はるることなかる可し。
一一 チチウスが奴隷を所有したり。彼これを甲のものと思ひて予に遺贈したり。遺贈は有効なり。蓋し真実が想像よりもより力あるが為なり。其の奴隷を以て受遺者たる予のものとの疑惑を有したる場合にも、尚依然として有効なり。蓋し遺贈は有用なる結果を有すればなり。何故となれば、死亡者も所有者たり、予も所有者に非ず、且所有権は何等の障碍なく予に移転することを得ればなり。
一二 汝予に汝の物を遺贈したり。汝生き延びてこれを譲渡したり。ケルススは謂ふ、若し撤回するものとして、且予に対する好意を棄つるものとして、汝がこれを譲渡したるときは、遺贈は予に負はるることなかる可し。若しかかる意図を有せずして、それを譲渡したるときは(蓋し恐らく公私の債務の必要が汝に迫り、汝は金に窮してこれを売却したるが為ならん)、予は汝の相続人に遺贈を請求す可しと。これセウェールス及びアントーニーヌスも亦解答し給ひし所なり。某なる者予に其の財物を遺贈したり。彼生き延びてこれを担保に供したり。同一の皇帝によりて、担保に供したる者は、遺贈を撤回する意思を以て、そのことを為したるものとは観ぜられずと解答せられたり。故に受遺者は、債務を債権者に弁済し、財物を抵当より自由にして提供す可きことを相続人に強制す可し。又人若し予に土地を遺贈し、生き延びて其の一部を譲渡したるときは、譲渡せられざる部分は、常に予に負はるるも、譲渡せられたる部分は、予に対する好意を棄ててこれを譲渡したるに非ざる場合に、初めて負はる。
一三 汝予に百金を負ひたり。予汝に債務の免除【即ち請求よりの解放と放免】を遺贈したり。遺贈は有効にして、予の相続人は、汝にも汝の相続人にも、将又相続人の地位を占むる其の他の者、例へば包括的信託受遺者又は遺産占有者にも請求することなかる可し。然れども反対に、汝はacceptilatioを以て汝を自由にす可きことを、予の相続人に強制して、遺言訴権を予の相続人に提起することを得可し。予は永久に債務の請求を、予の債務者に抛棄することを得るのみならず、期間を限りてこれを行ひ、「相続人よ、予は汝が十年迄は、予の債務者に債務を請求せざる可き責を汝に負はしむ」と謂ふことも得。
一四 若し反対に債務者が、其の負ひたる債務を債権者に遺贈したるときは如何。果して有効なるか、吾人は問題とす可し。吾人は、若し遺贈の中に何等増加なきときは、無効なりと謂ふ者なり。蓋し若し百金の債務ある者が、百金を遺贈したるときは、有効たることなければなり。若し百十金なるときは、附加故に有効なり。百金のみが遺贈の中に存する場合には、遺贈が何等の利得を齎すことなきによりて効力なし。利得を齎すことなき遺贈は無効なり。若し予期限附にて(蓋し恐らく汝は、予が汝に五年後百金を与ふ可きことを要約したるが為ならん)汝に債務を負ひ、或は条件附にて、例へば「若し船がアヂアより来れるときは」の如くにして、汝に債務を負ひ、次に同一債務を単純に汝に遺贈したるときは、遺贈が有効なるかを問題とす可し。而てこれは到来故に、即ち此の場合には直ちに履行せらるるが為、有効なりと謂ふことを要す。蓋し債権者は此の場合、十年後又は条件の成就後に同人に給付せらるるもの、或は又時には条件が不成就に逐りて、与へらるることなかる可きものを、即時に受領して利得すればなり。若し債務を負へる遺言者の生存中に期限が到来し、或は条件が成就するが如きことあらば、此の種の遺贈に付ては如何にす可きか。パーピニアーヌスは、当初より効力を有し、其の中には利得を蔵するが故に、遺贈は均しく有用なりと謂ふ。これ真なり。蓋し或る状態に到達し、其の状態よりしては遺贈は開始することを得ざるを以て、遺贈は失効すと主張する者の学説は、容れらるることなかりしを以てなり。蓋し見よ、期限が到来し、或は条件が成就するときは、債務は遺言者の死亡のときに於て、単純なるものと観ぜらるるを。即ち人若し当初より単純に負はれたるものを遺贈するときは、吾人は遺贈は有効なることなしと謂ひたるも、此の場合には、遺贈は当初は成立するが故に有効なり。
一五 予予の妻より嫁資を受けたり。未だ婚姻の成立中予死亡せんとして、同女に嫁資を遺贈したり。遺贈は有効なり。蓋し後に学ぶが如く、婚姻の解消と同時に常に嫁資が返還せらるとは限らざるも、遺贈は直ちに履行せらるるを以て、婦女が財産を遺贈として請求するは、嫁資によるものとして請求するよりも、利得あればなり。然らば予嫁資を受けずして、嫁資を予の妻に遺贈したるときは如何。セウェールス及びアントーニーヌスは、若し予が単純に遺贈するときは(蓋し予は、予の妻が予に持参したる嫁資を同女に遺贈すと謂ひたるが為)、遺贈は無効なりと解答し給へり。蓋し何物も予に持参せしことなく、額も不明なればなり。然れども若し明かなる額を記したるときは(蓋し予は、嫁資の理由を以て予に持参したる百金を、予は同女に遺贈す。或は又恐らく、予に持参したる某なる土地を、予は同女に遺贈すと謂ひたるが為)、遺贈は有効なり。或は又「嫁資証書に包含せらるるものを、予は同女に遺贈す」と謂ふときは、かくするも遺贈は有効なり。
一六 予汝に奴隷を遺贈したり。予の相続人の行為又は悪意なくして、其の奴隷が死亡したり。受遺者がこれよりして損害を受く可し。又若し遺贈られたる奴隷が他人のものにして、其の者が相続人の意思によらずして、所有者によりて解放せられたるときも、相続人は無責任なり。若し予が相続人の奴隷を汝に遺贈し、其の相続人が彼を解放したるときには、其の奴隷が予によりて遺贈せられたることを、相続人が知ると知らざるとによりて、何等の差異を設くることなく、相続人は評価額に付き拘束せらる可しとユーリアーヌスは謂ふ。又同人が奴隷を解放せざるも、同人を他人に善意にて、即ち遺贈回避の為に非ずして贈与し、贈与によりて受領せし者が、同人を解放したる場合も亦同じ。蓋し此の場合に於ても、相続人は、仮令同人が遺贈せられたることを知らずとも、其の評価額を請求せらる可ければなり。
一七 某なる者「予はチチウスに、女奴を其の生児と共に遺贈す」と謂ひて、女奴を其の生児と共に遺贈したり。遺言者生き延ぶる裡、女奴は死亡したり。同女に対しては遺贈は消滅するも、子に対しては遺贈は有効にして、子に対する遺贈が同女と共に廃止せらるることはなし。予の奴隷はordinariusと称せられ、予の奴隷の奴隷はvicariusと称せらる。vicariiを有するスチクスと呼ばるる奴隷を有する某なる者、vicariiと共にordinariusを予に遺贈したり。偶々ordinarius死亡するが如きことあり。此の場合に於ても、ordinariusに対する遺贈は失効するも、vicariiに対するものは有効なり。次のことを予備知識として保持す可し。〔此処に〕或る主物と其の従物とあり。而て主物が効力を有する間に限りて、それより出づる物も存在し、前者が廃止せらるるときは、後者も共に消滅す。例へば奴隷が主物にして、同人の特有財産が従物たり。奴隷が存在する間に限りて、特有財産も亦成立す。奴隷が或は死亡し、或は解放せられ、或は譲渡せらるるときは、特有財産も亦消滅す。蓋し主物が存在せざるに、如何にして特有財産が予のもとに存し得んや。又土地が主物にして、其の道具が従物たり。土地の道具とは、果実の生産、蒐集、運搬、保管と関係する総ての物を謂ふ。生産に関係する物とは、例へば農役の奴隷、牛、鋤、鶴嘴及びこれに類する物なり。蒐集に関係する物とは、例へば鎌及びこれに類似の物なり。運搬に関係する物とは、例へば車、籠及びこれに類似の物なり。保管に関係する物とは、桶、壷、扁豆形の器及び此の種の物なり。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。予汝に予の奴隷を同人の特有財産と共に遺贈したり。遺言の作成後も生き延びて、予奴隷を解放し、或は同人を譲渡し、或は偶々同人死亡したり。同人に対するのみならず、特有財産に対しても亦、遺贈は失効す。蓋し主物が保存せられざるを以て、従物も亦存在することを得ざればなり。予が予のinstruction土地即ち道具と共に土地を遺贈するときも亦同じ。蓋し此の場合に於ても、土地の道具は従物なるを以て、遺贈は道具に付ても消滅すればなり。
一八 予汝に予の畜群を遺贈したり。偶々其の後全畜群が、一頭の家畜となるの結果を生じたり。受遺者は残れる家畜を請求することを得。百頭の家畜ある予の畜群を、予汝に遺贈したり。予生き延ぶる中、他のものが生まれ、畜群は百五十頭なるの結果を生じたり。遺言の作成後に生まれたるものも亦、畜群中に算入せられ、受遺者は、ユーリアヌスの謂ふが如く、全部のものを受く可し。蓋し畜群は、幾多の頭〔数〕より成る或る一個の物体にして、家が牽連せる石又は材料より成る一個の集合物たると同然なればなり。
一九 故に若し予が汝に家屋を遺贈し、遺言の後柱又は大理石をそれに附属せしむるときは、汝は附属せしめられたる物をも取得す可し。
二〇 予汝に予の奴隷の特有財産を遺贈し、それは十金に価する物を蔵したり。後予の生存中にそれは十五金となり、或は五金となれり。利得にせよ、損失にせよ、それは受遺者たる汝に関す。次のことを予備知識として保持す可し。前進(προχώρησις)【=cessio即ち受遺者が遺贈の目的物を取得す可き期待権を有するに至る期日の到来。此の期待権は相続が可能なり。】とは、未だ受領せられざる遺贈の相続人【受遺者の相続人】への移転を謂ふ。相続人が自主権者に対する関係は、主人が奴隷に対する関係の如し。蓋し自主権者たる予が、受領前に予の相続人に移転することを得るものは、奴隷はこれを主人に取得し、前進することも得ず相続人へ移転さるることも得ざるものは、主人に取得せらるることなし。而て遺贈は吾人に提供せられたる場合に前進す。提供とは訴権の帰属なり。帰属は単純なる遺贈に付ては、遺言者の死亡により、条件附のものに付ては、条件の成就後に発生す。然れども古く遺贈は、相続の承継より前進したり。然れども此のことは、受遺者にとり損害を及ぼすことなりしを以て(蓋し相続人は、受遺者の或る者が瀕死の病気にあるを見て、同人に遺贈を帰属せしめず、又同人の相続人にも移転せしめざらんが為に、承継を延引したればなり)、これが為遺言者の死亡よりして、前進又は提供が為さるること通説となれり。蓋し此の時は相続人の意思の外に置かるればなり。然れども今日に於ても、或る遺贈が、法則の適用によりて、古き態様に従ひ、相続の承継より前進を行ふものあるを発見することを得。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。予予の奴隷スチクスの特有財産を遺贈したり。予の死亡後承継前に於て、上記のスチクスは何物かを取得したり。これは何人の利得となる可きか、相続人のもとに止まるか、或は受遺者に与へらるるか。ユーリアーヌスは謂ふ、若し遺言の中にて解放せられたるスチクス自身に、其の特有財産が遺贈せられたる場合には、相続人の承継前に取得せられたる総てのものは、解放せられたる奴隷自身に与へらる可しと。如何なる理由によるかを吾人は述ぶ可し。蓋しかかる遺贈の期限は、相続人の承継後に前進するを以てなり。若し遺贈が遺言者の死亡より前進するときは、相続人に帰属せしなる可し。然らば差異の原因は如何。前進とは、未だ取得せられざる遺贈の相続人への移転なることは汝の知る所なり。此のスチクスは、自己に遺贈せられたる特有財産をば、承継前には何人に移転せんとするか。相続人へは不可能なり。蓋し奴隷は相続人を有すること能はず、主人に取得すればなり。然らば承継前は彼の主人は何人なるか。即ち当然遺贈は不前進の侭にて止まる。承継後は自由人となりて、相続人を有することを得るを以て、固より当然遺贈は前進を保持す。即ち見よ、古法律に従ひて、今日に於ても、相続の承継より前進を有する例あるを。故に前進前に遺贈が増加したるものなるが故に、取得せられたる物は総て、固より当然受遺者たるスチクスに移転す。若し何人か第三者に、奴隷スチクスの特有財産が遺贈せられたるときは、予の死亡後、承継前に取得せられたる物は、相続人のもとに止まる。蓋しかかる遺贈は遺言者の死亡より前進すればなり。予の死亡後に取得せられたる物は、受遺者に与へらるることなしと予は謂ふも、そは特有財産中に存する主物よりして発生せし物が加はる場合——例へば特有財産中に女奴ありて、子を生み、又士地がそれより果実を発生したるが如し。——に非ざることとす。尚遺言の中にて解放せられたる奴隷には、特有財産が従ふことなきことを、汝は知ることを要す。若し生前に予が同人を解放するときは、予が特に特有財産を取消さざる限り、被解放者はこれを取得す可し。これ至聖セウェールス及びアントーニーヌスの解答し給ひし所なり。予の奴隷は、彼が如何なる原因にせよ、其の原因に基きて儲くる物を特有財産中に蔵するのみならず、主人たる予の為に何物かを支出せる場合にも、それは特有財産を増大す可し。例へば某なる者千金の特有財産を有し、予は彼に百金を借り、彼これを予の為に支出したり。同人の特有財産は千百金となる可し。而て予若しかかる奴隷を遺言の中にて解放し、更に同人に特有財産を遺贈するときは、彼が千金を取得するは学説の一致する所なり。然らば彼が予の為支出したる百金も亦然るか。同一の皇帝は、彼がかかるものに付ては請求権を有せざる旨を解答し給へり。蓋し掌中に存するもののみを遺贈するものと観ぜられ、彼が予の計算に於て支出したる物を遺贈すとは、観ぜられざればなり。若し予が予の財産の会計人を遺言の中にて、「自己の計算を終へたるときは」なる条件のもとに解放するときは、予は同人に特有財産を遺贈し、以て(同一皇帝の容れ給ひしが如く)同人に遺贈せられたるものと観ぜらるる特有財産より、同人は〔計算〕不足額を弁済す可しと謂ふものと観ぜらる。蓋し、奴隷たる者は、特有財産よりするに非ざれば、何処より債務を弁済せんとするや。仮令主人が生存中同人に債務を請求するも、其の特有財産よりして返済せんとするに非ずや。
二一 有体物のみならず、無体物も亦これを遺贈することを得。故に或る者予に百金の債務あるときは、予は同人に対する訴権を第三者に遺贈することを得。相続人はこれを受遺者に譲渡することを強制せらる。若し遺言後生き延びて、予が債務を請求するときは、遺贈は失効す。即ち見よ、此の場合には遺されたるものは無体物なるを。蓋し訴権が遺贈せられたればなり。次の如くにして遺されたる遺贈も有効なり。「相続人よ、予は某に属する家屋を改築する責を汝に負はしむ」或は「チチウスが拘束せらるる債務を免除する責を汝に負はしむ」と。
二二 某なる者「予は某に奴隷を与へ遺贈す」或は「予は某に馬を与へ遺贈す」と謂ひて、奴隷又は其の他の何物にても、これを不特定的に遺贈したり。吾人は何人に選択が与へらるるか、相続人に与へられて、其の結果彼は自己の欲するものを弁済す可きか、或は受遺者に与へられて、其の結果彼は自己の意に合するものを取得す可きかを問題とす可し。吾人は遺言者が特に反対のことを表示せざる限り、受遺者が選択を有すと謂ふ者なり。
二三 選択の遺贈、即ち死亡者が、受遺者は己が諸奴隷、己が衣服、又は諸本の中より選択す可しと命令したる場合は、其の中に条件を包蔵す。故に受遺者自身が生存中に選択せずして、選択前に死亡するときは「条件附遺贈は、条件の成就前受遺者が死亡するときは、相続人へは移転することなし」と謂ふ原則により、其の相続人へ移ることなし。選択は遺言者が「チチウスは予の家より一人の奴隷を選択す可し」と謂ひたるときに存す。然れども是等は古のことなり。吾人の至聖の皇帝の勅法は、これをも良き方に導き給へり。蓋し受遺者の相続人にも、受遺者が生存中に選択せざりし奴隷を選択する権能を附与し給ひたればなり。鋭意これが取扱に当り給へるとき、次のことをも其の勅法に附加し給へり。蓋し古く或る二人又はそれ以上の者に選択が遺されたるときは、選択に付て彼等に意見の一致を見ざるが如きことありて、或る者はスチクスを選択し、或る者はパンフィルスを選択したるときには、法学者の或る者に従へば、遺贈の請求は意見の一致を見る迄停止することとなり、又或る者に従へば、意見の分裂によりて消滅したりしが、帝は同一の勅法の中にて、一人の受遺者に多数の相続人が存して、選択に付て意見の一致を見ざると、多数の受遺者ありて、同一の奴隷を選択せずして、意見の一致を見ざる場合たるとを問はず、遺贈は解消せらるることなく(尤も良きことに反対の法学者の多数には、此のことは是認せられざりし所なりしも)、かかる選択或は選出をば運命に任せ、運命よりして決定を俟つ可き旨を命じ給ひたればなり。蓋し抽籤が行はれて、其の抽籤によりて選択権を附与せられたる者が、選択又は選出〔権〕を有し、他の共同受遺者又は共同相続人はそれに従ひ、以て抽籤によりて尊敬せられたる者が選択したる物をば、取得す可き旨を命じ給ひたればなり。
二四 或る者に対して吾人が遺言作成権を有する場合に、かかる者に対してのみ、吾人は遺贈を為すことを得。
二五 不特定の人間に対しては、遺贈も信託遺贈も遺すことを得ず。此のことは普通一般人に適用あるのみならず、兵士にも許容せられざること、至聖ハドリアーヌスの解答し給ひたるが如し。不特定の人間とは、遺言者が不明の決定を以て自己に描ける者にして、其の者に付て問はるるも、明瞭に述ぶることを得ざる者なり。例へば人若し「何人たりとも予の息に其の娘を嫁せしめたる者は、予の相続人より某なる土地を取得す可し」或は又「予の死亡後最初に執政官に選ばれたる者に対し、予の相続人は百金を与ふ可し」と謂ふが如し。此の場合に於ては人は不特定なり。蓋し何人が自己の娘を遺言者の子に嫁せしめんとするか、或は何人が遺言の後執政官に選任せらるるかは、不明なればなり。蓋し遺言者が其の者に付て問はるるも、恐らく何等か明確なることを謂ふことなかる可ければなり。其の他多数の場合を考ふることを得可し。又不特定の人間に遺されたる自由も無用なり。蓋し名を指示せられて奴隷が遺言の中にて解放せらるること通説なればなり。一定の説明(demonstratio)のもとに於ては、不特定の人間に対して、吾人は有効に遺贈を行ふ。例へば予若し「現に予の親戚たる者の中何人か若し予の娘を娶りたるときは、予の相続人より某なる物を取得す可し」と謂へるが如し。蓋し此の場合には、人間は明かならざれど、説明即ち全体【娘を娶る可き者の全体】は明かなればなり。蓋し予は「現に予の親戚たる者」と謂へばなり。此の数は明瞭なり。予不特定の人間に遺贈を遺したり。遺されたるものが無効なるは明かなり。然れども相続人が錯誤によりて弁済せしときは、取戻すことを得ざる可し。蓋しこれ神聖なる諸勅法に包含せらるる所なればなり。
二六 家外の後生児は不特定の人間と類似す。故に同人に遺贈するも無効なり。家外の後生児とは、生まるるも自権相続人となることなき者なり。故に家長権被免除者たる予の子よりして懐胎せられて生まれたる孫は、予の家外の後生児なり。
二七 然れども是等総ては古の制なり。吾人の皇帝の勅法が同帝の勅法彙纂内に収録せられて、相続財産のみならず、遺贈及び信託遺贈に於ても、不特定人に関する総ての法制を殊の外改善し給へり。上記の勅法を読むときは、極めて判然たり。不特定の後見人は、上記の勅法によるも附与せらるることを得ず。蓋し明碓たることを要すればなり。蓋し遺言者は明瞭に自己の子に対し、後見人を遺すことを要すればなり。故に若し遺言者が「予の葬儀に最初に参じたる者は、予の子の後見人たる可し」と謂ふときは、後見人の附与は無効なり。
二八 家外の後生児は、昔とても相続人に書き記さるることを得、今日に於ても、合法的に妻に娶ることを得ざるが如き婦女の胎内にあるに非ざる限り、何等の障碍なく書き記さる可し。
二九 現存の人間を明かにせんが為、古人は幾多の呼称を発案したり。蓋しnomen即ち本来の名、例へばチチウスあり。cognomen綽名あり。これは或は欠点より、或は美点よりして取らる。欠点よりとは例へばスーペルブス(Superbus)の如く、美点よりとは例へばピウス(Pius)の如し。尚praenomen即ちクレーマチスモス(χρηματισμός)なるものあり。これは或は祖先より、或は恩人より取らる。祖先よりとは、例へば人アエアキデース(Aeachides)をアキルレス(Achilles)と呼ぶが如し。恩人よりとは、県知事が自己の呼称の前に、自己を県知事になしたる者の名を置くを見るが如き類なり。例へばストラテギウス(Strategius)コンスタンチーヌス(Constantinus)の如し。さて某遺贈に当りて、受遺者の名に付て錯誤し、チチウスと謂ふことを要する所をセイウスと謂ひて、nomenに付て錯誤し、或はスーペルブスと謂ふことを要する所をピウスと謂ひたるが為、cognomenに付て錯誤し、或はストラテギウスと謂ふことを要する所をプリムスと謂ひたるが為、クレーマチスモスに付て錯誤したるときは、遺贈が果して有効なりやを問題とす可し。而て吾人は何人に付て指示せらるるかに関し、意見の一致を見たるときは、遺贈は依然として有効なりと謂ふ者なり。同一のことは相続人に付ても遵守せらる。蓋し某なる者を相続人に書き記すに際して、上述の中の或る一に付て錯誤するも、指定はそれよりして効力を失ふことなく、又それは当然のことなればなり。蓋し名は人を明かにせんが為に、発案せられたるものなればなり。故に方法の如何を問はず、他の何等かの方法によりて、現在の人間が把握せらるるときは、名に関する錯誤よりしては、何等の差異、何等の損害が発生することなし。
三〇 誤れる説明は遺贈を廃止することなしと謂ふ原則も、此の理に類似す。蓋し汝は、遺贈には或る場合には説明(demonstratio)、或る場合には動機(causa)が従ふを知ることを要すればなり。説明とは遺贈せられたる物の明示なり。例へば某なる者「予は家に生まれつきの予の奴隷スチクスをチチウスに遺贈す」と謂ひて遺贈したり。遺贈は、仮令スチクスが家に生まれつきのものに非ずして、売買によりてこれを得たる場合たりとも有効なり。或は又「予は予がセイウスより買ひたる奴隷スチクスをチチウスに遺贈す」と謂ひたるも、〔実は〕甲よりこれを買ひたる場合にも、誤れる説明は遺贈を廃止することなしと謂ふ上記の原則によりて、遺贈は有効なり。
三一 遺贈に発生せる誤れる動機も亦、遺贈を無効となすこととなし。causaとは遺贈が因りて以て為されたる原因の明示なり。例へば某なる者「チチウスは予の不在中に予の財産を管理したるが故に、予は予の奴隷スチクスをチチウスに与へ且遺贈す」或は「予はチチウスの援助によりて頭格的訴追を免れたれば、チチウスに奴隷を遺贈す」の如くにして遺贈したるが如し。蓋し仮令チチウスが予の財産を管理せす、又同人の援助によりて頭格的危険を免れたるにも非ずとも、誤れる動機は遺贈を廃止することなしと謂ふ原則によりて、遺贈は有効なり。然れども若し条件的に動機を表示したるに、動機の誤れることが発見せられたるときは、受遺者は何者をも受くることなかる可し。蓋し「予は若しチチウスが〔既に〕予の財産を管理せるときは、某なる土地をチチウスに遺贈す」と謂へるが為の如し。蓋し若し管理し居れるときは、条件は成就せるものとして受領す可きも、若し管理し居らざるときは、条件は不成就に遂りたるものとして、受遺者には何等の訴権も附与せられざる可ければなり。
三二 次のことを予備知識として保持す可し。原告と被告の権利が同一人へ集まるときは、かかる方法にて発生せる混同は訴訟を廃止す。蓋し自己自身に訴訟を提起することは、不可能なればなり。尚又少しく以前にて述べたること、即ち遺贈に関する提供は単純なるものに付ては遺言者の死亡、条件附のものに付ては条件の成就なることを知ることを要す。汝に是等のことを前置したれば、これに続く爾余のものを見よ。某なる者死亡に際して予を相続人に指定し、次に予の奴隷スチクスに予より履行す可き遺贈を遺したり。原告と被告の権利が同一人に競合するが故に、果して遺贈が良く遺さるるかを吾人は問題とす可し。蓋し予は相続人なるが故に被告、受遺者の主人なるが故に原告なればなり。即ち被告と原告の権利が予に競合するが故に、訴訟は混同す。然れども法学者の或る者は謂ふ、〔遺贈の〕提供、即ち遺贈の訴権の帰属のときに眼を注ぐ可し。而て其の時に於て、相続人と受遺者が互に人間を異にするきは(蓋し予に対して遺言を為す者が生き延ぶる中、予が予の奴隷スチクスを解放又は譲渡するは、有り得可きことなればなり)人間が分離せらるるを以て、遺贈は有効となる。若し予が遺言者の死亡の時に於て、奴隷にして且受遺者たる者を、権力服従者として保持することが発見せらるるときは、上記の理由によりて遺贈は廃止せらる可し。上記は単純に遺されたる場合なり。若し条件附なるときは、吾人は遺言者の死亡を観察することなく、条件の成就を観察す。而て条件が成就して、スチクスが或は自由人たり、或は他人の奴隷たるを発見せば、遺贈は有効なり。若し条件が成就して、予の権力服従者として発見せらるるときは、遺贈は効力を失ふと。以上は或る者の学説なり。通説は下の如し。使件附のものに付ては、条件の成就を観察することを要すと謂ひたる所は真なり。単純なるものに付ては「若し遺言の作成後直ちに遺言者が死亡せしならんには無効たらんとする遺贈は総て、遺言者が遺言の作成後も長期間生き延ぶるが如きことありて、其の結果相続人に己が奴隷スチクスを解放又は譲渡する機が発生すとも、其の故を以て確認せらるることなし」と称する原則によりて、遺贈は無効なり。蓋し遺言を完成すると同時に、遺言者が死亡せしならんには、奴隷は相続人の権力服従者として発見せられし筈なればなり。
三三 反対に某なる者、予の奴隷を相続人に指定し、予に対しては彼【奴隷】より履行せらる可き遺贈を遺したるときは如何。此の場合には、何等の疑問なく遺されたるものは有効なり。蓋し仮令遺言の作成後遺言者が死亡したるとも、相続人のもとに、遺贈の期限が前進せんとしたるには非ざればなり。蓋し主人が相続人にして、受遺者は奴隷なる上の場合には、奴隷に対して遺されたる遺贈は、直ちに主人に取得せられたらんも、此の場合には、主人に対して遺されたる遺贈は、相続人に書き記されたる奴隷に取得せられたりしならんとは謂ふことを得ざればなり。蓋し此の場合には、相続は遺贈とは分離し、他の者が此のスチクスによりて、相続人となることが可能なればなり。蓋し予が同人に承継して予の為に相続財産を取得す可き旨を命ずる以前に、彼が他人の権力へ移転せられたるときは、新なる主人に相続財産を取得す可く、若し又解放せられたるときは、自ら承継して自己に相続財産を取得す可ければなり。かかる場合には、遺贈は有用なり。相続人と受遺者とは、人間が別々となればなり。蓋し予は解放せられて承継する者、又は新なる主人に対して訴を為し、遺贈を請求することを得可ければなり。然れども未だ予の権に止まる中、予の命令によりて承継するときは、遺贈は失効す。蓋し予は指定に基きて受遺者、取得によりて相続人たることが発見せらるればなり。
三四 相続人の指定前に遺贈を為すも無効にして、又遺言は相続人の指定よりして、其の効力を取得するものなれば、当然のことなり。故に相続人の指定は全遺言の主脳且基礎と考えられ、其の結果相続人の指定前にて遺されたるものは、遺言の外にありと観ぜらる。同一の理由により、自由も亦指定前に附与せらるることを得ず。然れども吾人の至聖の皇帝は、吾人が遺言に於ける記載の順序を遵守して——此のことは古人によりても亦、非難せられたる所なり——以て死亡者の意思を無視するは不当と思惟し給ひ、勅法を発布し、これによりて現存の不備を匡正し給ひ、其の結果相続人指定の前に於ても、相続人指定の中間に於ても、遺贈——自由は更なり——を遺すことを得ることとなれり。此の自由は完全なる恩恵に価するものなり。相続人指定の前に於てとは、例へば予遺言を開始するに当り「予は某に百金を与ふ」或は「某は自由たる可し」と謂ひ、而て後「某は予の相続人たる可し」と書き記すが如し。相続人指定の中間に於てとは、予「甲は六ウンキアに付て予の相続人たる可し。予は某に百金を遺贈す(或は)奴隷スチクスは自由たる可し」と謂ひ、其の後他の相続人を附加して「乙は六ウンキアに何て相続人たる可し」と謂ふが如し。
三五 相続人の死亡後又は受遺者の死亡後〔に効力を発生す可き〕遺贈は遺さるるも無効なり。例へば人若し「予は予の相続人の死亡後、某に百金を遺贈す」と謂ふが如し。蓋し相続人が存する間は遺贈は請求せらるることなく、同人の死亡後は同人の相続人亦「吾人に対抗して開始せざる訴権は、吾人の相続人に対抗して移転することなし」と称する原則によりて請求せらるることなければなり。受遺者に付ても亦同じ。蓋し予若し「予は甲が死亡せるときに、甲に百金を遺贈す」と謂ふときは、遺贈は無効なればなり。蓋し本人自らも遺言者の文言によりて請求することを得ず、同人の相続人亦「吾人より開始せざる訴権は、吾人の相続人へ移転することなし」と称する原則に基きて、然ることなければなり。相続人又は受遺者の死亡する前日〔に効力を発生す可き〕遺贈も亦無効なり。例へば予若し「予の相続人が死亡せんとする一日前(又は)チチウスが死亡せんとする一日前に、予はチチウスに百金を遺贈す」と謂ふが如し。蓋し死亡の一日前なる日は明かならざればなり。蓋し死亡の後初めて、過ぎし方を顧みて、昨日が死亡の一日前に当ると謂ひ、これは死亡〔の時〕よりして理解せらるるものなれば、又死後の遺贈の類に入ればなり。然れどもこれをも亦吾人の至聖の皇帝は匡正に値せしめ、かくの如くにして遺されたるものに対しても、信託遺贈に倣ひて効力を附与し給へり。蓋しかくの如くにして遺されたる信託遺贈は、古人これを容認したりしも遺贈はこれを排斥したればなり。故に此の点に於ては遺贈と信託遺贈には何等の差異なし。蓋し双方共に有効なればなり。
三六 罰の名目を以て遺されたる遺贈は、取消的たると、移転的たることを問はず無効なり。むしろ何事かを為し、又は為さざらしめんが為、相続人処罰の目的を以て遺されたるものは、罰の名目を以て遺贈せられたるものと観ぜらる。蓋し多くの者は死亡に際して、相続人に何事かを為す可き旨を命令し、相続人に或る生活方法を指定して、それに従ひて生活することを要せしめたるも、相続人は何等の損害を受くることなくして、かかる意思を無視したりしが、人これを見て金銭罰を発案し、これを恐るるが為相続人は或ることを為し、又は為さざることを意に反して強制せられたればなり。罰の名目を以てする遺贈を例に徴して述ぶれば、例へば次の如し。「某は予の相続人たる可し。而て其の娘をチチウスに嫁せしむ可し」或は反対に「嫁せしむる勿れ。若し予の意思に反対なるときは、セイウスに百金を与ふ可し」と。或は又「予の相続人は、若し予の奴隷スチクスを譲渡するときは」或は又反対に「譲渡せざるときは、チチウスに十金を与ふ可し」の如し。かかる遺贈は二個の理由によりて、効力を有することなし。第一に法律は、相続人の意思の中に存して、遺贈債務を負ふも負はざるも、自己〔の一存〕にあるが如き(蓋し死亡者の言を充たすときは、何物をも弁済することなく、若し反対なれば、受遺者に対して債務者となる可ければなり)遺贈を嫌ふが為なり。次に遺贈は受遺者に対する好意と親愛によりて遺すことを要す可く、相続人に対する嫌悪の情を以てしては、遺す可からざればなり。罰の名目を以て遺されたる遺贈は無効なりと謂ふ原則の行はるるは、多数の勅法ありて、其の中には、皇帝も亦罰の名目を以て遺されたる遺贈を受くることを忍び給ふことなしと記され、又兵士の遺言とても、他の場合には遺言に於ける兵士の意思は法律として効力あれども、罰の名目を以て遺されたる遺贈の確認せらるるは見ることなき程なり。又罰の名目を以て遺されたる自由も効力を有することなく、罰の名目を以て相続人を書き記すも無効なるは、サビーヌスの述ぶるが如し。例へば人若し、「チチウスは予の相続人たる可し。若しチチウスが其の娘をセイウスに嫁せしめざるときは、セイウスは彼と共に共同相続人たる可し」と謂ふときは、セイウスの指定は無効なり。何故となれば、遺贈の授与が相続人を弱むるが如く、共同相続人を得ることは、同人に損害を与ふればなり。蓋し相続財産の半分が奪はるるを以てなり。然れども吾人の至聖の皇帝は、かかる帝の意に合せざる厳正をば、一般的勅法を以て廃止して「仮令罰の名目を以て或る遺贈が遺され、又は取消され、又は他人へ移転せらるるも、罰なくして授与又は取消又は移転が中に存する他の遺贈より隔ることなかる可し。唯固より不能なるもの、又は法律の禁ずるもの、其の他侮辱的又は非難す可きものはこれを除く」と宣へり。蓋し遺言者のかかる処分が効力を有するは、帝の帝国の祝福せられたる時代の知る所に非ずと思惟し給ひたればなり。不能とは例へば予若し「予はチチウスに、彼が空に至りたるときは、百金を与へ且遺贈す。若し空に至らざるときは、予これを甲に与ふ」と謂へるが如し。蓋し此の場合には、チチウスは取得す可ければなり。或は又「予はチチウスに、彼が某男の妻と姦通するときは、百金を遺贈す。若し姦通せざるときは、これを甲に与ふ」と謂ふが如し。蓋し此の場合にも、チチウスは取得す可ければなり。或は又「予はチチウスに、彼が其の母を擲りたるときは、百金を遺贈す。若しチチウスが其の母を擲らざるときは、その百金を甲に与ふ」と謂ふが如し。或は又「若し空に至らざるときは」又は「某男の妻と姦通せざるときは、」或は「其の母を擲らざるときは、同人に其の百金を遺贈せず」として、取消すが如し。蓋し前の例に付て移転が無効なるが如く、取消は無効なればなり。若し受遺者に依頼せられたるものが、不能にも非ず、法律違反にも非ず、probrosaと呼ばるる所の非難す可きものにも非ざるときは、罰の名目を以て為されたる授与、取消、及び移転は有効なり。
第二十一章 遺贈の取消に付て
遺贈の取消は同じ遺言の中にても、或は小書付の中にても、吾人は有効にこれを為すことを得、而て反対の文言を以て取消が為さるるも、其の他の文言を以て為さるるも、何等の差異なし。例へば予若し「チチウスに対し予は百金を遺贈す」と謂ひ、後暫くして、同じ遺言又は小書付の中にて「non」の語を附加して「チチウスに対しては予は与へ且遺贈せず」と謂ふが如し。これを称して反対のと謂ふは、「non」の語を附加して、与へたるときと同一の文言を以て撤回すればなり。何故となれば、doはnon doに対して反対なればなり。若し又他の文言を以て為すも、均しく撤回は効力を有す。例へば「チチウスに対して予は百金を遺贈す」と謂ひ、然る後「予はチチウスに対し百金の与へらるることを欲せず」と謂ふが如し。吾人は更に一人より他人へ転与することを得。例へば予チチウスに対し、予の奴隷スチクスを遺したり。予は「予がチチウスに対して遺贈したるスチクスは、これをセイウスに遺贈す」と謂ふことを得。而て吾人は同じ遺言の中に於ても、或は小書付の中に於ても、これを行ふことを得。而て転与は其の中に黙示の取消を包含す。蓋しチチウスよりセイウスへ遺贈を移転するものなるが故に、暗黙的にチチウスよりこれを取去る訳なればなり。
第二十二章 ファルキヂア法に付て
これよりファルキヂア法に付て述ぶる必要あり。同法によりて最終的に遺贈に対して制限が設けられたり。蓋し往時は全部又は殆んど全部の資産を遺贈に消費することを得たればなり。これ十二表法の許す所なり。同法に曰く、uti legassit suae rei quis ita ius esto.即ち何人か己が資産に付て、遺贈及び処分を為したるが侭法律たる可しと。然れども此の後、遺贈の自由は制限を受く可きものとの見解行はれたり。これ遺言者の為に案出せられたるなり。何故となれば、指定相続人はこれによりて、何等の利得を得ざるか、或は又利得あるも極めて少額なるの故を以て、承継を辞するが故に、遺言者は多くの場合無遺言にて死亡したるが為なり。而て此の後フーリア法が制定せられ、同法は何人にも千金を超過して遺贈することを得ざる旨を宣言す。人若し遺されたるものにして超過したる額を受けたるときは、超過額の四倍額を返還したり。例へば千二百金を取得したるときは、二百金の四倍即ち八百金を返還したるが如し。然れども此の種の法律は容易に回避せられたり。何故となれば、若し五千金の資産を有する者、五人の受遺者に各千金宛遺贈するときは、法律に触るることなく、再び相続人は何等利得なきの故を以て、相続を拒絶し、かくして再び遺言は失効に帰したればなり。茲に於て第二次にウォコニア法制定せられ、同法は受遺者は相続人よりも多額を取得せざる可きを宣言せり。これ亦回避は容易なり。何故となれば、若し百金を有する者予を相続人に指定し、九十九人の受遺者に各一金宛遺贈したるときは、法律を踏み越ゆることもなく、茲に又相続の拒絶を発生せしめたればなり。一金にては相続人は全遺産の負担を支ふ可くも非ざればなり。茲に於てか最後として、ファルキヂア法が制定せられ、同法は死亡者の財産を十二ウンキアに分ち、指定相続人が一人なる場合たると、其れ以上なる場合たるとを問はず、何人にも全財産の四ウンキア以上を遺贈することは許されず、財産の四分の一は、一人又は数人の相続人のもとに留まる可き旨を宣言したり。
一 四百金の資産を有する者、チチウスとセイウスの二人を同じ割合にて相続人に指定したり。而て特にチチウスと指名して、同人より履行す可き遺贈を下の如く謂ひて為したり。「チチウスよ、予は汝が某々に対し二百金又は百八十金に達する財産を与ふる責を汝に負はしむ」と。セイウスより履行す可き遺贈は、何等これを為さざりしか、或は同人の指定分の半を尽す額を遺贈し、其の結果同人には百金が完全に遺されたり。受遺者現はれてチチウスに迫り、且同人に全遺贈を請求したり。遺贈を差引きたる後は何等残余財産なきか、或は少額を有するに止まる彼は、己が指定分の四分の一、即ち五十金を保留せんと欲したり。受遺者これに反対して、遺言者は九ウンキア以上に資産を遺贈に費したる訳に非ざるを以て、遺言者はファルキヂア法に満足を与へたる旨を述べたり。チチウスは既に述べたるが如く、己が指定分の四分の一を保留する権利ありと思惟せり。かかる疑義発生して、各人は己が相続分の四分の一を保留す可きこと通説となれり。故にセイウスのもとに、六ウンキア或は三ウンキアが完全に存するの故を以て、チチウスが己が指定分の四分の一を保留することを妨げらるることはなかる可し。相続人の各々が、己が指定分の四分の一を有することを要すればなり。
二 吾人は死亡者の資産の四分の一が完全に相続人に保存せらるることを要する旨を述べたるが故に、如何なる時の死亡者の資産額が幾何なるかを詮議することを要するか。死亡の時なるか、或は又承継の時なるか。遺言者の死亡の時が詮議せらる可きことむしろ通説なり。故に承継迄に何等か損害及び財産の減少が発生するも、或は又資産が増加するも、ファルキヂアに関する限り、これは受遺者に損害を与ふることもなく、利することもなく、両者——予は謂ふ、減少と増加なり——の効果は、相続人がこれを認む可し。例へば例を取れば下の如し。某百金の資産を有したり。百金を遺贈せり。ファルキヂアによるものとして、二十五金即ち四分の一を保留するは、相続人に認められたるものなること明かなり。相続の承継遅延して、偶々相続財産に属する奴隷によりて、相続財産に何物かが附加せられ、或は女奴が子を産み、或は家畜の子が生まるるが如きことあり。かくの如き増加が相続財産に加はり、為に相続人は四分の一を有することを得るに至り、ファルキヂアの必要なきに至れり。然れども、通説によれば、死亡の時が詮議せられ、此の時にはファルキヂアが帰属したるが故に、中間に於て財産に発生したる附加は相続人に利す。蓋し同人は尚均しく百金の四分の一を保留し、其の外附加物を利得として保有す可ければなり。これは反対の場合にも取扱はる可し。百金の資産を有する者、七十五金を遺贈したり。遺言者の意思に基きて〔四分の一はこれを〕有する相続人が、ファルキヂアによる保留を要せざること明なり。同人の死後相続承継前偶々火災起りて、相続財産に属する家屋が焼失し、又は難破起りて、相続財産に属する物が壊滅し、相続財産に属する奴隷が死亡するが如きことありて、其の結果相続財産は二十五金方減少して、七十五金に変じ、或はそれ以下即ち七十金となれり。相続人が承継するときは、全遺贈の履行を強制せらる。遺言者の死亡の時に於ては、同人の意思に基きて四分の一を有する者として、ファルキヂアの助を要せざればなり。故にかくの如き設例に於ては、彼は何物をも利得せざるか、或は時には損害迄も加へらる。而て恐ること勿れ。相続を承継せざる者は、かかる損害を避くることを得ればなり、而て此のことが又、同人が相続を拒絶するときは、受遺者は遺贈に基きて何等得る所なきを知り、相続人と合意して、遺贈頻の幾分かを取得す可き旨を約する様しむくることとなる。かくしてファルキヂアの与へざりしものをば、承継拒絶を威嚇することによる方便が、これを相続人に附与したり。
三 資産の額は下の如くにして調査せらる。即ち死亡者の債務、埋葬に関する費用、及び解放せられたる奴隷の評価頻は控除せらるることを要し、然る後残額は幾何なるかを調査して(蓋しこれが純財産と解せらるればなり)、其の四分の一を保留することを要す。例へば例を取れば下の如し。八百金の資産を有する者、四百金を遺贈して死亡したり。彼債権者に二百金の債務あり。解放せられたる奴隷は百五十金の価あり。五十金は同人の埋葬費に費消せられ其の結果四百金残存せり。上に述べたるが如く控除が為さるるにより、四百金として、其の中より百金を保留することを要す。八百金として、其の中より二百金を保留するに非ず。故に四分の三が割合に従つて諸受遺者に与へらる可く、四分の一即ち百金が相続人のもとに残存す。四百金の純資産を有する者、四百金を遺贈したり。四分の一が保留せらるることを要す。若し三百五十金を遺贈したるときは如何。其の場合は八分の一が保留せらる可し。四百金の八分の一は五十金なり。相続人は遺言者の意思によりて五十金を、法律によりて他の五十金を有す。これが四分の一の額を構成す。若し四百金を資産中に有する者、五百金を遺贈したるときは(彼は五百金を、甲に百金、乙に百金、丙丁戌に各百金の如くにして、遺贈したるなり)、先づ超過額を控除し、即ち各受遺者の五分の一を削減し、各受遺者に八十金を残存する様にすることを要す。次にファルキヂアに基くものとして、相続人は各受遺者より各二十金宛保留し、同人は自己に百金即ち資産の四分の一を取得す可く、各百金の遺贈を受けたる五人の受遺者は、各六十金を有す可し。
第二十三章 信託遺贈に付て
遺贈に付て述べたる吾人は、今や信託遺贈に入る可し。信託遺贈の中、或るものは特殊的、或るものは包括的なり。先づ包括的のものに付て述べたる後、特殊的のものに移る可し。
一 吾人は先づ其の起源に付て観察す可し。往時は総て信託遺贈は確なる基礎を有せざりき。蓋し何人も交付の依頼を受けたる者に対し、自己の意に反して履行することなかりしを以てなり。信託遺贈は次の如き事情より発案せられたり。羅馬人が外人の親族を有し乍ら死亡する場合、屡々発生せり。然るに彼等に対しては、国籍の相違故に、相続財産も遺贈も遺すことを得ざりき。茲にに於てかかる者は、己に好意を寄せ、且信頼するに足る或る羅馬人にして、其の遺言相続人と呼ぶことを得る者を召喚し、これを相続人に書き記し、遺言の外にて、全相続財産か、或は其の一部か、或は又特定の物を、某々外人に返還せられ度き旨を同人に懇願せり。而てこれを与ふるか与へざるかは、指定相続人の権限に存したり。蓋し同人がこれを実行することを強制するものは、法の拘束に非ず、これは単に被懇願者の信義と羞恥心に懸るものなりしが故なり。これ又実にfideicomissa即ち信に信託されたる物と呼ばれし所以なり。然れどもこれは古き時代のことなり。此の後アウグスツス皇帝は初めて、信託遺贈受遺者にして、固より外人たる者に恩恵を示さんが為(蓋し時にはかかる人間は同帝の知悉し給ひしこともある可く、或は彼等に存する学識、其の他何等かの卓越の故に、尊敬に価する者なることもあらん)、又、同帝の幸福によりて、宣誓したる相続人が、屡々宣誓に背くが如きことありし為、更には大なる信義違反の故に(富裕なる者、貧困にして且極めて弱年の児童又は老齢の尊属に返還す可き旨の死亡者の懇願を受けて、信義を蹂躙するが如きことも時には存す可し)一度ならず二度迄心動かされ給ひて、執政官に命じ、帝の権威を加へて、懇願を受けたる者は、返還の実行を強制せらる可きものとし給へり。これは全国民にとり、正常且意を得たるものと考へられ、暫くにして裁判管轄事件、法律関係となり、信託遺贈に対する熱意の果しは、遂に時の経過する裡、信託遺贈法務官と称せらるる信託遺贈の請求に特有の法務官すらの選任を見るに至れり。
二 信託遺贈の起源を終へたる後は、包括的信託遺贈に付て述ぶ可し。包括的信託遺贈が効力を有せんが為には、先づ第一に、或る直接に遺言中に指定せられたる相続人にして、且他人に相続財産を返還す可き旨の懇願を受けたる者が存在することを要す。何人も相続人に指定せられざる遺言は無効なればなり。故に予若し「ルーキウス、チチウスは予の相続人たる可し」と謂ひて某を相続人に書き記すときは、予は更に附言して「ルーキウス、チチウスよ、予は汝に、汝が初めて予の相続を承継するをことを得るに至りたるときは、これをカーイウス、セイウスに還付返還せられんことを懇願す」と謂ふことを得。又予は相続人に懇願して、相続財産全部のみならず、相続財産の一部に付ても亦、返還せられたき旨を乞ふことを得。又単純にも、条件附にても、更には確定期限附にて、例へば予の死亡後二年の後としても、遺さる。
三 若し相続人に書き記され、且相続財産返還の懇願を受けて、これを返還したるときと雖も、均しく相続人たり。無体物【相続人たる身分】は同人に附着すればなり。これを受けたる者は、往時に於ては、買主の地位を占めたりしが、其の後は一時は相続人、一時は受遺者の地位を占めたり。吾人は第一には【Reizによる】買主の権利を説く可し。信託受遺者が利得を享有するに、相続人が相続財産の負担を負ふは、失当と考へられたるが故に、仮装の売買が発生することが行はれたり。即ち相続人は一片の金にて全遺産を売却し、相続人と信託受遺者との間に、或る問答口約が交はされ、此の問答口約は遺産売買の問答口約と称せられたり。蓋し相続人は信託受遺者に対し「信託受遺者よ、若し予が相続債権者より何物かを請求せられたるときは、汝はこれを予に与ふるか、或は予を弁護して、予に損害なからしむることを約するか」と要約し、信託受遺者は「予は約す」と謂ひ、信託受遺者も亦相続人に対し「相続人よ、若し汝が相続債務者に請求したるときは、汝はこれを予に与へ、或は予に訴権を譲渡し、以て予をして訴訟代理人(訴訟代理人とは如何なる者なるかは、後の所に於て学ぶ可し)の名義を以て、これを提起することを得しむることを約するか」と要約し、而て相続人は「予は約す」と謂ひたればなり。
四 然れどもかくするときは、相続人が紛争を避くるに熱心ならんとせば、二個の訴訟に服することとなる。蓋し相続債権者に対しては訴に応じ、履行したる物に付て償還を受けんが為には、問答口約に基くものとして、更に翻つて信託受遺者に対して訴を提起することを余儀なくせしめらるればなり。これが為ネロの代、カーイウス、ツレベルリウス、マーキシムス及びアンナイウスの執政官たるとき、一元老院議決制定せられ、該議決は、若し何人かに相続財産が、信託遺贈によりて遺されて、返還せられたるときは、市民法及び法の厳正に従ひて、相続人に属したる総ての訴権、及び相続人に対する総ての訴権は、信託受遺者の為又は信託受遺者に対して移転す可き旨を宣言せり。而て尚法務官は此の議決に奉仕して、utiles即ち模倣訴権をあたかも信託受遺者が相続人たるが如くにして、信託受遺者の為又は信託受遺者に対して附与し、其の結果同人が訴訟を提起するときには、「若し某が与ふることを要すること明白なるときは、あたかも予が相続人たるが如くに」と謂はしむ。見よ此の場合彼は相続人の地位を保持せるを。
五 事情かくの如くなりたるとき、指定相続人は多くの場合、殆んど全相続財産の返還を懇願せられ、何等の利得なきか、或は存するも極めて少額のみなるが為、相続承継を躊躇し、此の拒絶の為、信託遺贈も亦失効したるが故に、其の後ウェスパシアーヌスの代、ペーガスス及びプーシオーの執政年、ペーガシアーヌム元老院議決定められ、他人に対する相続財産の返還を懇願せられたる相続人には、ファルキヂア法に基き、遺贈より四分の一を保留することを許さるるが如く、四分の一を保留することを得せしむ可きを命じたり。而て単に包括的なる多額の信託遺贈のみならず、特別信託遺贈に付ても、同一の留保が許容せられたり。ファルキヂア法が遺贈の多額なる場合に於ける関係は、ペーガシアーヌムが信託遺贈の多額なる場合の関係と同じ。此の議決後は、相続人のみが負担を負ひ、信託受遺者は然ることなし。後信託受遺者は、幾分率の受遺者の地位を保持するものとなすこと通説となれり。蓋し往時第五種の遺贈存在し、これ「幾分率の」(partiaria)と称せられ、それは次の如くにして遺されたり。「チチウスは相続人たる可し。而て予の相続財産を、セイウスと半分の割合を以て分割す可し」と。尚両人の間に下の如き問答口約が交はされたり。相続人は受遺者に対し次の如く要約せり。「受遺者よ、若し予が訴へられて、二十金を履行したるときは、これが半分を予に与ふることを汝は約するか」と。答へて曰く「予は約す」と。受遺者も亦相続人に要約して曰く「若し汝が相続債務者より二十金を取得したるときは、半分即ち十金を予に与ふることを約するか」と。答へて曰く「予は約す」と。かくの如き問答口約は「partis et pro parte」と呼ばれたり。而て幾分率の遺贈を模倣して、問答口約が相続人と信託受遺者の間に交はされ、信託受遺者は下の如く要約せられたり。「信託受遺者よ、若し予が相続債権者より四十金の請求を受けたるときは、三十金を与ふることを汝は約するか」と。相続人も亦信託受遺者より要約せられたり。「相続人よ、若し汝が相続債務者より四十金を取得したるときは、三十金を予に与ふることを汝は約するか」と。而て答へて曰く「予は約す」と。かくの如くにして、包括的信託受遺者は受遺者の地位を保持し、利得と損失は割合に従ひて、信託受遺者と相続人の間に、共同たることを要したり。かくの如き問答口約も、「partis et pro parte」と称せられたり。
六 故に簡単に謂はば、若し相続人が、九ウンキア或はそれより以下の額を、信託受遺者に返還す可き旨の懇願を受け、自己のもとには遺言者の意思によりて、四分の一或は四分の一以上を有するときは、ツレベルリアーヌム議決に基く返還が行はる。而て四分の三に付ては、信託受遺者が準訴権を以て訴へ且訴へられ、四分の一に付ては、相続人が直接訴権を以て訴へ且訴へらる。若し相続人が、九ウンキア以上、例へば十又は十一ウンキア、或は総財産を返還す可き旨の懇願を受け、遺言者の意思に基きて、四分の一を有することなく、ペーガシアーヌム議決に発生を与へたるときは、相続人は自己の意思を以て(何故に「自己の意思を以て」と謂ひたるかは、先に於て吾人これを学ぶ可し)、一度相続を承継するや、四分の一を留保したると、留保するを欲せざるとを問はず、該相続人は相続の負担全部を負担す可し。然れども若し四分の一を留保したるときは、同人と信託受遺者の間に、相続人と幾分率の受遺者に倣ひて、partis et pro parte問答口約が行はれたり。若し全相続財産を返還したるときは、ツレベルリアーヌムは発動することなし。遺言者の意思によりて資産の四分の一が相続人のもとに存するを見ざればなり。ペーガシアーヌムも亦発動することなし。蓋し留保するを欲せず、且これが為partis et pro parte問答口約の行はるることもなかりしを以てなり。総ての保護手段欠くるを以て、相続財産売買の問答口約が行はれたり。然れども是等は、其の意思を以て相続を承継したるときのことなり。若し相続財産は、損害発生の惧あるが故に疑はしと称して、相続を拒絶したるときは、ペーガシアーヌム議決によりて、信託受遺者は法務官のもとに赴き、法務官は相続人に対し、承継して全相続財産を信託受遺者に返還す可き旨を命ず可き旨規定せらる。而て訴権は全体として、相続人より信託受遺者の為及び信託受遺者に対して移転せらるること、あたかもツレベルリアーヌムに基きて返還が為されたるときの如し。而てかくの如き場合に於ては両議決の競合あり。即ちペーガシアーヌムは被指定者の承継を強制し、ツレベルリアーヌムは訴権を移転す。然れども外に何等の必要的問答口約は、此の場合に為さるることなし。相続財産を返還したる者は、訴へらるることなくして、心配の無用を担保せられ、信託受遺者は全訴権を有して、安全を与へらるればなり。
七 然れどもペーガシアーヌムよりして発案せられたる問答口約は古人にとりても気受悪しく、或る場合には、法学者中の逸才パーピニアーヌスはこれをば害多しと称し、吾人の至聖の皇帝にも、法律が困難に充つるよりは単純なる可きは其の意を用ひ給ひし所なるを以て、同帝に両議決の類似及び相違の全部を挙げたるに、後の時代に発案せられたるペーガシアーヌムはこれを廃止し、ツレベルリアーヌム議決に全権威を置くことに一致し、其の結果相続人が遺言者の意思によりて四分の一を有すると、其れ以上たると以下たると、将又全然有するものなき場合たるとを問はず、信託遺贈的相続財産は全部、同法に基きて返還せらるることとなれり。蓋し指定相続人が或は全部、或は四分の三以上の相続財産を返還す可き旨懇願せらるるときは、同人は四分の一全部或は四分の一に不足の額を、吾人の皇帝の勅法に基きて留保し、或は弁済したるものを取戻すことを得可く、訴権はツレベルリアーヌムにより、割合を以て、相続人と信託受遺者の間に分割せらる可ければなり。故に若し相続人が其の意思に基きて、全相続財産を返還したるときは、全訴権は信託受遺者の為に及び信託受遺者に対して附与せらる可し。ペーガシアーヌム議決に規定せられたるものも亦、吾人の極めて敬虔なる皇帝は其の勅法によりて、ツレベルリアーヌムへ移し給へり。蓋し相続人が疑はしき相続財産の承継として拒絶したるときは、ペーガシアーヌム議決によりて承継を強制せられ、全訴権が信託受遺者へ移転せらるることは、少し前に見たる所なればなり。今よりはこれは単にツレベルリアーヌムのみによりて行はれ、相続人は意思に反するも承継して、相続財産をばこれを希望する信託受遺者に返還す可し。何等の損害、何等の利得、相続人のもとに残ることなし。
八 汝に対し全部に付き相続人に書き記されたる者に付て述べたる所と同一事は、部分に付て例へば六ウンキアに付て書き記されたる者が、全部分又は部分中の部分の返還を懇請せられたる場合にも、常に汝に述べらる可し。蓋し至誠の皇帝は此の場合に於ても、全相続財産に付て吾人が述べたる所と同一の原則が、遵守せらる可き旨を命じ給ひたればなり。
九 某なる者死亡に際して、予を相続人に指定し、然る後次の如く謂へり。「予は汝に懇請す、某々の土地又は其の他の財産を控除し、或は先取して(土地は全資産の四分の一を其の中に包含するものと仮想せよ)、相続財産を某に返還せられんことを」と。かかる設例に於ても「予は汝に懇請す、相続財産の四分の一を留保して、残余を返還せられんことを」と謂ひたる場合と同じく、ツレベルリアーヌム議決の適用あり。唯四分の一が〔特定の〕事物に於て相続人のもとに存するときは、全体としてツレベルリアーヌムに基き、訴権は信託受遺者の為に及び信託受遺者に対して移転し、物は相続人に遺贈せられたるものの如く、全く何等の負担を負はずして、相続人のもとに止まるに、権利に於て四分の一を有するときは(蓋し遺言者が「四分の一を留保して相続財産を返還せらる可し」と謂ひたるが為)、訴権は分割せられ、四分の三に付ては、信託受遺者が準訴権にて訴へ且訴へられ、四分の一に付ては、相続人が直接的に請求し、且訴へらるる点に於て差異あり。仮令指定相続人にして、一個の物を留保し(或は先取し)て、相続財産を返還す可き旨の懇請を受けたる者が、留保物中に相続財産の極めて大部分を有するとき(蓋し恐らくは全相続財産は四百金なるとき、相続人が留保を命ぜられたる土地が、二百五十金の価値あるが為)と雖も、尚金体として訴権は信託受遺者の為に且信託受遺者に対して移転せられ、かくの如き場合に信託受遺者は、信託遺贈を受くることが果して同人にとり利益なるかを考慮するの必要を生ず。相続人が二個又は其れ以上の物、或は定額を留保し、然る後相続財産を返還す可き旨を命ぜられたる場合も、吾人は同一と謂ふ者なり。蓋し此の場合に於ても、四分の一或は四分の一以上が、特定物又は特定額中に存するときは、ツレベルリアーヌムに基き、訴権は全体として信託受遺者に移転すればなり。全部に付て相続人に書き記され、且特定の一物又は数物を留保し、而て後相続財産を他人に返還す可き旨の懇請を受けたる者に付て述べたる所は、部分に付て相続人に書き記されたる者が、特定の一物又は数物を留保して、自己の指定分の返還を懇請せられたる場合に付ても、吾人これを考ふ。かかる場合に於ても、其の部分の訴権は全体として、信託受遺者に移転すればなり。
一〇 吾人は指定相続人に包括的信託遺贈の負担を負はしむることを得るのみならず、法定的権利によるにせよ、法務官〔法〕によるにせよ(蓋し恐らくは血族なりしが為)、吾人の資産を受くる無遺言相続人に対しても「予は汝に懇請す、法定相続人(又は法務官的遺産占有者)よ、相続財産の全部又は一部、或は某なる土地、或は奴隷、或は某額の金銭を某に返還せられんことを」と謂ひて、負担せしむることを得。然るに遺贈は遺言によりて遺さるることを得るも、無遺言にては然らず。即ち遺贈と信託遺贈には、遺贈は遺言に於てのみ遺さるるも、信託遺贈は更に無遺言の場合にも尚遺さるるの差異あり。
一一 予は又甲を相続人に書き記して、相続財産を乙に返還せられたき旨を同人に懇請し、更に又乙に対し同人に与へられたる全相続財産又は其の一部を丙に返還せられたき旨、或は某なる財産を丙に譲られたき旨を懇請することを得。
一二 本章の冒頭に於て述べたるが如く、信託遺贈の揺籃は相続人の信義に依存し、名称及び実質をそれより受け、更に至誠のアウグスツスが、古く自由意思に存せしものを、法律上必然的に履行するを要するものとなし給ひしが、吾人の皇帝は、未ださして多数日月を経過せざる以前に、上記至聖のアウグスツスに打勝たんと努力し給ひ、名声赫々たる司法大臣ツリボーニアーヌスが、帝の聖聴に達し奉りし事件が発生したるとき、勅法を発布し給ひ、同法の中に於て、若し何人か、包括的にせよ特殊的にせよ、書面を作成せずして其の相続人より履行す可き信託遺贈を遺し、而て文書によりてこれを証明することも、五人の証人——信託遺贈の成立には五人の立会を以て足る——の証言よりしてこれを証明することも能はざるときは(蓋し時には五人以下の証人が立会ひ、或は全然何人も立会はざることもあらん)、父が相続を為す子より履行す可き信託遺贈を遺したると、其の他如何なる者が遺したるとを問はず、若し相続人が事実を否認し、かくの如きものは何等伴はずと主張し、信義に違反して同人の信義に信託せられたるものの履行を拒絶し、信託受遺者はこれに対して反対するときは、信託受遺者は(先づ自ら詐害心を以て宣誓を挑むものに非ざる旨の濫争に関する宣誓を為して)、信託遺贈は遺されしことなき旨の宣誓を、相続人に強制することを得可き旨を規定し給へり。若し相続人が宣誓を拒絶するときは、遺言者即ち全部を相続人に信託したる者の最終の意思が蹂躙せらるることなからしめんが為、包括的又は特殊的〔信託遺贈〕の履行を強制せらる可し。若し上記の方法によりて、受遺者又は信託受遺者より履行す可き信託遺贈が遺されたるときも、同一の規定が適用ある可し。何物かの遺されたることを否認する受遺者又は信託受遺者は、何等遺されしことなき旨を宣誓す可く、然らずして拒絶せば、信託遺贈が請求せらる可し。若し信託遺贈を負担せしめられたる者が、自己の履行す可き信託遺贈の遺されたることは認むるも、信託遺贈の遺されたるときには、五人の証人は立会しことなしと謂ひて、法律の厳正に逃避するときは、かかる抗弁は無効なるものとして、疑もなく信託遺贈の履行を強制せらる可し。
第二十四章 債託遺贈によりて遺されたる個々の物に付て
既に吾人が述べたるが如く、吾人は包括的信託遺贈に止まらず、特別的信託遺贈、例へば土地、奴隷、衣服、銀、金銭も亦これを遺し、或は相続人自身、或は受遺者——仮令受遺者の履行す可き遺贈は遺すことは得ざれども——に対し、これを他人に返還せられたき旨を懇請することを得。
一 吾人は信託遺贈によりて、吾人の物のみならず、相続人の物、受遺者の物、及び信託受遺者の物をもこれを遺す。而て偶々同人【信託受遺者】に遺されたる物を他人に返還せられたき旨を要求し得るのみならず、其の他の物も、同人に属すると、他人に属するとを問はず亦然り。蓋し予若し汝に土地を遺すときは、予は汝に対し、其の土地か、或は其の土地の代りに家屋を、他人に与へられたき旨を懇請することを得ればなり。其の家屋が汝の物たるか、又は他人の物たるかは、何等関する所に非ず。固より何人も自己が利得するより以上のものを、他人に譲ることを懇請せらるることなきことは、遵守せらるることを要す。蓋し信託遺贈に存する超過分は、無効なればなり。例へば予汝に百金を遺し、而て汝に百十金の信託遺贈を負担せしめたり。超過額に限り、信託遺贈は無効なり。他人の物が信託遺贈によりて遺されたるときは、これを返還するは、懇請を受けたる者にとり強制的なり。蓋し彼は購ひ求めて信託受遺者に与ふるか、若し不可能なるときは評価額を交付すればなり。
二 吾人は金銭評価の可能なる物の信託遺贈を遺すことを得るのみならず、自由を信託遺贈によりて附与することも許さる。蓋し予は予の相続人又は受遺者、及び信託受遺者に対し、予の奴隷某を解放せられたき旨を懇請することを得ればなり。是等の者に対し、予の奴隷に付て請求をなすか、或は相続人、或は受遺者、或は又其の他の或る者に属する奴隷に付て為すかによりて、何等の差異なし。蓋し予は「相続人(或は受遺者)よ、予は汝に懇請す、汝の奴隷(又はマエウィウスの奴隷)を解放せられんことを」と謂ふことを得ればなり。彼はこれを買ひ求め、解放を報ゆることを強制せらる。若し所有者が同人を売らざるときは(彼は強制せらるることなければなり)、信託的解放は消滅すと称すること勿れ。唯或る時期迄停止して延期せられ、可能となりたるときは、解放が実行せらるるなり。蓋し懇請を受けたる者が、かかる奴隷の所有者となれるときは、所有者となれる方法の如何を問はず、同人の解放を強制せらるればなり。然れどもこれ奴隷の所有者が、遺言者の意思によりて、何物をも有することなき場合のことなり。蓋し若し遺言者の意思によりて、何物かを利得したるときは、常に奴隷の譲渡を強制せられたればなり。若し予が予の奴隷に信託的自由を遺すときは、解放せられし者は予の被解放者とならずして、解放者即ち解放なる行為を実行したる者の被解放者となる。然るに予若し直接的自由を予の奴隷に遺したるときは——蓋し「予はスチクスが自由人たることを命ず」と謂ひたるが為——スチクスは予の被解放者となり、同人は法学者のもとに於て、orcinus libertus即ち幽界的被解放者と称せらる可し。而て予は遺言作成の時と、予の死亡の時との両時期に於て、予の所有権に服する予の奴隷に対してのみ、直接的自由を遺すことを得。而て遺言者が他人に自由の附与を懇請せず、同人自ら自己の遺言に基くものとして、自由が同人【奴隷】に齎らさる可きことを欲したる場合に初めて、直接的に自由が遺されたるものと観ぜらる。
三 信託遺贈附与の為に定められたる文言もあり。それは甚だ多し。下の如きもの最も普通にして利用せらる。peto, rogo, volo, mando, fidei tuae committoの如し。是等は其れ丈にて用ひらるるも、併せて同時に用ひらるるも、同一の効力を保持す。
第二十五章 小書付に付て
吾人は尚小書付に付て述ぶ可し。小書付とは遺言に於ては不完全なる遺言者の意思の補充なり。而て小書付の起源に関して論ずるは脱線には非ず。アウグスツスの時代以前に於ては、小書付の作成は利用せられざりき。初めてルーキウス、レンツルスこれを発案して、これを普及せしめたり。蓋しレンツルスは、羅馬に於て遺言を作成し、其の娘とアウグスツス皇帝、及び其の他の者を相続人に書き記したり。彼は遺言の中にて下の如く謂へり。「若し予が此の後或る小書付を作成したるときは、有効たる可し」と。即ち将来の小書付を確認したるなり。彼アフリカに赴きたる後、同所に於て将に死亡せんとするや、小書付を作成し、其の小書付の中に於て、同人の部分的相続人たるアウグスツスに対し、何物かを為すこと、例へば某なる者に家屋を建築し、或は其の他類似の何等かの物を行はれたき旨を懇請し、更に己が娘より履行す可き信託遺贈及び遺贈を、〔娘の名を〕名ざして、某に遺したり。レンツルスの死亡後、遺言が朗読せられ、小書付が持参せられ、アウグスツス皇帝は自らレンツルスの希望を充し給ひ、其の他の共同相続人もアウグスツスに倣ひて、信託遺贈を履行したり。而てレンツルスの娘も亦、同女より履行す可く名ざして遺されたる遺贈を、取得不可能なる者に弁済したり。事情かくの如く相襲ぎたるとき、伝ふる所によれば、至誠アウグスツスは、当時の法学者を召集し——其の中には、当時に於て法律教育にかけては、権威最も大なりしツレバーチウスも存したり——法学者の面前にて、此の小書付の制度は採用することを要するか、又法理に背馳することなきかを質問せられたりと謂ふ。アウグスツスが此のことを質し給ひしとき、ツレバーチウスはアウグスツスに対し、小書付の制度は、戦争抬頭せしが為、古人のもとに於ては間断なく起りし大旅行長旅行の故に、羅馬人にとり極めて有用且必要なるものなることを進言したりと謂ふ。若し遺言作成に必要なる者不足にして、遺言を作成すること能はざる場合に、小書付を作成せんが為なり。其の後法学者ラベオーが小書付を作成して死亡したるときには、小書付が合法的実在を有することに、何人にも疑の余地なきものとなれり。
一 遺言の作成ある場合に小書付を書くことを得るのみならず、無遺言にて死亡する場合にも、同じ小書付中に信託遺贈を遺すことを得。若し何人か小書付を作成し、これが作成後も生き延びて、其の後遺言したるときは、同時に特に遺言の中にて「予は予の遺言の前に作成せられたる小書付が、効力を有す可きことを欲す」と謂ひて、これを確認せざる限り、パーピニアーヌスは先に作成したる小書付の効力保持を欲せざりき。然れどもこれパーピニアーヌスのことなり。至聖のセウェールス及びアントーニーヌスは、遺言の以前に書かれたる小書付の中にて遺されたる信託遺贈は、仮令確認なくとも、遺言者が同時に、小書付の中に記されたる信託遺贈の無効を明示せざり限り、これを請求するに妨げなき旨を解答し給へり。
二 尚「小書付によりては、相続財産は与へらるることもなく、奪はるることも能はず」と称する一般的原則あり。即ち小書付を作成する者は「某は予の相続人たる可し」と称し、又は「予の息は廃除者たる可し」と記すことを得ず。遺言と小書付の間に或る種の混同起り、無差別となることを避けんが為なり。是等【指定廃除】は遺言中にて為さるればなり。既に述べたるが如く、小書付の中にては、相続廃除を為すことも、相続人に書き記すことも不可能なれど、信託遺贈的相続財産はこれを遺すことは可能なり。而て上記の原則の適用せらるるは若し予甲を単純に相続人に書き記すときに、小書付に於てこれに条件を附加して「若し船がアヂアより来れるときは、予の相続人たる可し」と謂ふことを得ざる程なり。蓋し若し吾人が条件を許し、而てこれが成就せざるときは、遺言者は小書付の中にて与へし条件によりて、甲より相続財産を奪ふものと見らるればなり。更に又遺言の中にて相続人に書き記されたる者に対し、小書付の中にて直接に補充指定を行ひ、「若し遺言の中にて予が指定したる甲が予の相続人とならざるときは、乙が予の相続人たる可し」と謂ふことも不可能なり。
三 尚吾人は一個又は数個の小書付を作成することを許さる。小書付を作成する場合には、其の記載に関しては、遺言に付て、相続の指定を冒頭になす可しと謂ひたるが如き順序は、何等これを問題とすることなし。唯五人の証人のみを以て足る。
テオフィルス教授の法学提要第二巻は神と共に完了せられたり。