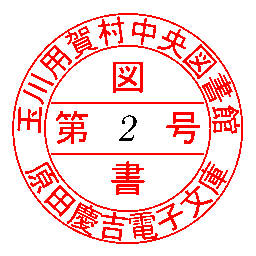
一 緒 言
カズイスチックな研究方法を生命とする羅馬法学には、凡そ通則めいた抽象的原則、統一的概念下の総論がない(1)。私法の原則的通則的規定の集合、私法総論を目的とする総則編(2)は勿論、一般的法律行為論(3)、一般的時効論(4)、一般的契約論、一般的不当利得論等凡そ総論めいたものは、羅馬法学には求めることは出来ない。契約の例を採つても、諾成契約(contractus consensu)、要物契約(contractus re)、言語契約(contractus verbis)、文書契約(contractus litteris)の理論はあつても、契約総論はなく(5)、不当利得の例を採つても、或る原因故に与へられたるに其の原因実現せざる場合のcondictio(condictio causa data causa non secuta, condictio ob causam datorum)、汚辱的原因故のcondictio(condictio ob turpem causam)、違法原因故のcondictio(condictio ob iniustam causam)、非債弁済のcondictio(condictio indebiti)等各種condictioの説明はあつても、一般的condictio観念はこれを見出すことは出来ない。儒帝法源には此の外に尚ほ原因を欠くcondictio(condictio sine causa)なるものが見えてゐるが、其の適用範囲には確然たるものがなく、決して普通法の如く、一般的不当利得訴権としての機能を有してゐたとは考へられない(6)。加ふるにcondictioは元来訴の方法であつて、不当利得の問題と無関係な大なる適用範囲がある外、他面condictioの訴によらざる不当利得の救済方法も頗る多く、不当利得観念がcondictioに於て統一完備せられて行つたとは謂ひ得ない(7)。同様のことは不法行為に付いても該当する。市民法の不法行為として窃盗(furtum)、強盗(rapina)、違法損害(damnum iniuria datum)、人格侵害(iniuria)、法務官法上の不法行為として悪意(dolus)、強迫(metus)、債権者詐害(fraus)其の他種々な不法行為の説明があるが、delictum総論と謂ふものはない。民法七〇九条に見えるが如き「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」の如き一般的原則は、此の点より謂ふも羅馬法とは遠きものがある。七〇九条の非羅馬性は啻に其の一般的抽象性に止まらない。羅馬法の不法行為の訴権の目的とする所は、罰金(poena)の追求にあつて、賠償の請求にあるのではない。仮令被害者に支払はる可き罰金が、経済的に見て、多分に損害賠償の作用を果たすことがあつても、これは単なる第二次的な結果であつて、被害者の要求するものは、加害者処罰の意味を主とする罰金の取得である(8)。更に「故意又ハ過失ニ因リ」の一句の高揚する所謂過失主義が、独逸法系の原因主義に対立する羅馬法の根本的基礎主義たることは、一般法律人の常識ではあるが、斯かる所謂過失主義が羅馬法内部の発展の如何なる段階の産物なるかは、現在羅馬法学者の論争の問題である。然らば如何なる過程を経て、七〇九条の如き規範が成立したのであらうか。其のドグマ形成の発展を一応跡付けんとするのが本稿の目的である。
問題の出発点は羅馬法のdamnum iniuria datumを律するactio legis Aquiliaeに存する。中世以来一方各種法益侵害に対する本訴権の適用範囲を拡張し、他方本訴権の罰的性格を抹消しつつ、ドグマは進展して行つたのである。従つて儒帝法に於けるdamnum iniuria datumを一応観察した後、其の後の発展を研究するのが順序でなくてはならぬ。然らば其の儒帝法は、lex Aquilia制定以来、古典法を経て、如何なる結果に到達してゐるのであらうか。観点を上記の三点、即ち法益侵害に対するactio legis Aquiliaeの適用、其の罰的性格、過失観念に限定して羅馬法内部の発展の跡を顧みて見よう。
(1) Schwartz, Pandektenwissenschaft und heutiges romanistisches Studium, 1928, S. 14-5.
(2) 総則編の源は自然法学派に発する。拙稿「日本民法総則編の史的素描」法協五七巻四号五九五頁。
(3) 一般的法律行為論も自然法学者に負ふ所が多い。拙稿前掲六号一〇二六—七頁。
(4) 羅馬法の各種時効制度を一のpraescriptioなる観念のもとに統卒したのは、注釈学派寺院法である。拙稿前掲七号一二七三頁。
(5) Buckland and McNair, Roman Law and Common Law 1936 p. 115 ,,Hence We get, not a theory of contract, but a theory of contracts, a number of contracts, each with its own theory.``
(6) Sohm-Mitteis-Wenger, Institutionen S. 443.
(7) 一般的不当利得観念は、普通法時代には一面condictio sine causaを発展せしめることにより、他面actio de in rem verso utilisの利用によつて、其の形成を基礎付けられたが、其処には自然法学者の影響を見逃す訳には行かない。Gierke, Deutsches Privatrecht III S. 994. 蓋し各種不当利得制度の基礎原理たる自然法的衡平観念を自然法学派が強調したのは当然であり(片山金章「不当利得制度の基礎原理の史的発展——殊に自然法との関連を基点として——」中央大学五十周年記念論文集三三一頁以下)、其の共通基礎原理の強調が一般統一的制度の出現を促したことは容易に理解し得る。
(8) Jörs-Kunkel, Römisches Privatrecht S. 170.
二 儒帝法に於けるactio legis Aquiliae(1)
通説によれば紀元前二八七年の制定にかかると称せらるる平民会議決たるlex Aquiliaは、「同法以前に違法の損害に付いて規定を設けたる総ての法律の一部廃止を為した。是等の法律は十二表法たると又は他の法律たるとを問はず(2)」。「是等の法律は茲に説く必要なし(3)」と記さるる結果、廃止せられた法律の具体的内容を知ることは出来ないが、同法の第一章が奴隷及び家畜中に算入せらるる四足動物を殺した場合、同第三章が上記同一物を傷けた場合、及び上記以外の物に対して加へられた一切の損害を規定する所より見るも(4)、同法が物の損害に関する不法行為に対して、最初の統一整理を施したことは疑を容れない(5)。actio legis Aquiliaeによる責任発生要件として、「身体的活動の直接の効果として(corpore)物の実質に(corpori)加へられた損害」(damnum corpore corpori datum)が存することを要した(6)。身体的活動の直接的結果に非ざる損害、例へば「他人の奴隷又は家畜を檻禁して餓死せしめ、輓駄用の四足動物を虐使して傷損せしめ、他人の奴隷を誘惑して樹上に登らしめ若くは井中に下らしめ而して其際墜落して死し若くは身体の一部を傷害したる場合(7)」、助産婦が薬——毒薬——を産婦(固より女奴なり)に与へ、産婦自身が該薬を飲んで死亡した場合(8)の如きは、法務官の救済によつて保護が与へられ、actio utilis 又はactio in factum が認められた(9)。純然たる不作為による損害亦、actio legis Aquiliaeの直接の適用範囲に属せざること言を俟たず。用益権者が土地を耘耕せず、葡萄を補植せず、水道を修繕せざるが如き場合は(10)、法務官によつて救済が与へられてゐるが、それがactio legis Aquiliaeの思想圏内の保護であつたかどうかは明らかでない。かく身体的活動の直接的結果に非ざる損害に関しては、上述の如く古典時代に、法務官の救済手段によつて其の保護が拡張せられてゐたが、物の実質自体には損害なきも、尚ほ且つ損害を発生するが如き場合にも、古典時代に既にactio legis Aquiliaeの思想圏内に入る法務官法上の救済が存在してゐたかは、Rotondi以来主としてイタリアの法学者によつて疑問視されてゐる(11)。ビザンチン法学者が憐憫の情に動かされて縛られた奴隷を逃走せしめた場合(12)、家畜を驚かせて逸走せしめた場合(13)、水中深く物を沈めた場合(14)、生殖の為め他人の動物を利用した場合(15)等を、actio legis Aquiliaeの範疇内のactio in factumの圏内に収めてゐることは疑がないが、彼等イタリア学派は、古典時代に於ては奴隷家畜を逸走せしめ、物を水中深く沈めた場合は、actio doli の思想圏に入るactio in factum、生殖の為めに利用した場合は、actio furtiの範疇内のactio in factumなることを主張するのである。私にはactio furtiの範疇内のactio in factumは尤もらしく思はれるが、他に救済手段なき場合に発生する究極的な補充的訴権たるactio doliより、更にactio in factumを派生せしめる様なことは、例へばactio doliのinfamiaの制裁を避けんが為めの必要などが考へ得ない訳ではないが(16)、此の場合何故にinfamiaの制裁を廻避しなければならないかの理由には余り積極性がある様には思はれないし、具体的な法源検討も、必ずしも充分な説得力がある様には思はれない(17)。唯古典法学者の考へてゐるactio in factumと、法典編纂人が脳裡に描いてゐるactio in factumとは、全然考を異にするものなることは、彼等イタリア学派の主張の通りである(18)。古典法学者の考へてゐるactio in factumは、個々の場合に応じて、或るタートベスタンドを限定して附与せられる普通一般のactio in factumであるが、法典編纂人のそれは極めて広汎な一般的性質を有するものである。儒帝法学提要四・三・一六に、damnum corpore corpori datumの場合にはactio legis Aquiliae自体、damnum corpore datum ではないが、尚ほcorpori datumの場合にはactio utilis、其の他の場合にはactio in factumの救済ありとして、訴権の三分類にそれぞれの適用範囲を分属せしめてゐるが、其処に見える包括的なactio in factumこそは、法典編纂人の眼中にあつたactio in factumなのであつて、後のビザンチン法学者はこれをば「損害を無からしめんが為めの一般的actio in factum」(imphaktoum genikē agōgē eis to azēmion=in factum generalis actio ob indemnitatem)と称してゐる。此の総括的actio in factumは、ビザンチン法学者にとつてはactio legis Aquiliae及びutilisの外に立つ補充的訴権と謂ふよりは、少くともactio utilis 恐らくはactio legis Aquiliae、其の他一切の物の損害に関する訴権をも自己の中に包含し、其の内部にあつて、actio legis Aquiliae及びutilis其の他の訴権の適用範囲に関する限り、是等の訴権が優先的に適用ある意味に於て補充的訴権の地位に立つものと解せられる。即ち物に関する損害は、一応此の総括的actio in factumによつて蔽ひ包まれて了ふのである。蓋しactio in factumを以て、各種契約に於ける共通因子たる合意と比較せらる可きものと考へてゐる外(19)、actio in factumはactio utilisを包含するも、逆は然らずとの趣旨の注釈は(20)、謂ふ迄もなくactio in factumがactio utilisを包摂することを物語るものであり、actio legis Aquiliaeもactio in factumも二倍額請求の訴権となつてゐる(21)——古典時代には唯in iureの手続に於て、被告が自己の行為を否認した場合にのみ、actio legis Aquiliaeの判決額が二倍となるのであるが、儒帝時代には訴訟手続の変更の結果、「否認」(infitiatio)の観念も変つて、出訴前に自発的支払を為さざることを意味し、従つて訴訟となつた以上常に二倍額の請求となるので、actio legis Aquiliaeの二倍額請求訴権と謂ふ考方を生じたものと思はれる(22)——のは、前者の性格が後者に浸潤した結果であるが、斯かる浸潤現象は恐らくはactio legis Aquiliaeがactio in factumに包摂せられてゐた結果ではないかと思はれるからである。其の他の訴権に関しては、法源は別に特定のものを掲げてゐる訳ではないが、他に訴権なきときは本actio in factumが発動することは、屡々明言せられてゐる(23)。ビザンチン法学者の斯かる不法行為の領域に於ける包括的一般的actio in factumは、契約の領域に於てactio in factum civilis(=actio praescriptis verbis)が一般的訴権(genikē agōgē)の働を営んでゐる(24)のと相対応するものである。
(1) 本稿の作成に当り特に参照した文献、春木一郎「Lex Aquiliaニ付テ」土方教授在職二十五年記念私法論文集。Rotondi, Teorie postclassiche sull' ``actio legis Aquiliae'', Scritti II p. 411--464; lo stesso, Dalla ``Lex Aquilia'' all'art. 1151 Cod. Civ., ricerche storico-dogmatiche, Scritti p. 465--578 (本稿は特にRotondiの此の二編の研究に基礎を置きつつ進められたものである); Kunkel, Exegetische Studien zur aquilischen Haftung, Sav. Z. 1929, S. 158 ff.; Arangio-Ruiz, Responsabilità Contrattuale in Diritto Romano, 2 ed. 1933 p. 220 ss.; Carrelli, La legittimazione attiva dell' ,,actio legis Aquiliae`` Rivista italiana per le scienze giuridiche IX, 2 1934 p. 356 ss. 尚ほ船田教授の手になるlex Aquiliaの「材料の在場所」(sedes materiae)D. 9, 2の翻訳(法学新報四五巻六号一〇三五頁以下、本稿に於て原文を訳文で引用する場合には此の翻訳によつた)及びThayerの翻訳(Lex Aquilia 1929)にも、其の附加的注釈故に便宜を得たこと多大である。
(2)(3) D. 9, 2, 1, pr. Ulpianus.
(4) Gaius 3, 210 et 217. 第三章の原形は唯奴隷家畜以外の物の滅失のみに関し、奴隷家畜に対する殺害以外の損傷は含まずとのJolowiczの学説The original scope of the lex Aquilia and the question of the damages, Law Quarterly Review 38 (1922) p. 220 ss.に対しては、Lenel, Sav. Z. 1922 S. 575 ff.参照。
(5) Girard, Manuel 8 p. 441; Rotondi p. 458; Carrelli p. 357.
(6) Gaius 3, 219; Inst. 4, 3, 16.
(7) Gaius 3, 219.
(8) D. 9, 2, 9, pr. Ulpianus.
(9) 法源では用法は一致してゐない。Rotondi p. 451 n. 1によれば、学派の対立によつて用法が異つたのであらうと謂ふ。
(10) D. 7, 1, 13, 2 Ulpianus.
(11) Rotondi p. 448 ss., 472 ss. これに賛してBonfante, Istituzioni 9 p. 505; Perozzi, Istituzioni 2 II p. 336; Costa, Storia 2 p. 327; Arangio-Ruiz, Istituzioni 3 p. 361; Marzo, Istituzioni p. 395. イタリアに於て殆んど全面的に支持せられてゐる此のロトンヂの学説は、他国では不思議にも顧みられて居らず、黙殺せられてゐる。
(12) Inst. 4, 3, 16.
(13) D. 47, 2, 50 Ulpianus(後続法文D. 47, 2, 51 Gaiusとの聯関を注意せよ)
(14) D. 9, 2, 27, 21 Ulpianus. これに対する某法学者の註(Heimbach(Basilica)V p. 294 sch. 65)「アクヰリア法又はactio in factumが発動す」参照。
(15) D. 47, 2, 52, 20 Ulpianus. これに対するHagiotheodoritaの註(Heimbach V p. 501 sch. 48)「単価についてactio in factumが予に提起せらる可し」参照。
(16) Rotondi p. 449. それは例へば卑属や被解放者が尊敬の義務を負ひ、其の結果尊属や保護者にactio famosa自体を提起し得ざるが故に、actio in factumが与へられることは(D. 4, 3, 11, 1 Ulpianus)理解が出来るが、今の場合にはactio in factumの存在理由が判らない。右のactio in factum に付いてはGlück V(1843)S. 528 ff. 参照。
(17) 憐憫の情に動かされて縛られた奴隷を逃走せしめた場合のInst. 4, 3, 16の出所は、D. 4, 3, 7, 7 Ulpianus「ラベオーは又左の場合を以て疑問とす即ち汝が予の奴隷を逃亡せしめんが為め其の鎖を解きたるときは予は汝に対して悪意の訴権を附与せらるべきものなるか如何。クウヰーンツスはラベオーの著書に対する注解に於て曰く、汝の行為が憐情の然らしめたるに非ざるときは汝は盗訴権に対する責を負ふ、若し憐情の然らしめたるものなるときは汝は事実訴権に対する責を負ものとすと」(春木一郎「プロータ」の翻訳による)である。成る程四巻三章は「悪意に付いて」の章であり、ラベオーの提出した悪意の訴権の適用ありや否やの問題に対する解答に於て、事実訴権の責ありと謂つてゐるのであるから、actio doliの範疇内のactio in factumの如く見える(Rotondi p. 449, 472)。然し乍ら家畜を驚かせて逸走せしめたり、罠にかかつた獣を放つて自然状態に復帰せしめた様な類似の場合は、actio doli関係のactio in factumの様には思はれない。D. 47, 2, 50, 4 Ulpianus「赤き布を見せて家畜をして逸走せしめ、盗人の手に帰せしめたる者に対しては、若し悪意を以つて為したる場合には、盗の訴権あり。然れども仮令盗を為さんが為めに斯かることを為したるに非ずとも、かくの如き危険なる悪戯は無罰に過ごさる可きに非ず。故にラベオーは事実訴権が附与せらる可きなりと記す」中のactio in factumは、直続の法文lex 51 Gaius「蓋し家畜が突き落されたるときすら、尚ほアクヰリア法に基くものとして準違法損害訴権が与へらるべければなり」により、actio legis Aquiliae関係のactio in factumとなるが、Rotondiはウルピアーヌス法文をガーイウス法文に連結することによつてのみ、actio legis Aquiliae関係のactio in factumとなつてゐるに過ぎないと主張する(p. 452, 473)。然し乍ら悪戯の為め赤い布を以て畜群を驚かせて、これを散乱せしめた場合は、ガーイウスによつて明らかにactio legis Aquiliaeに関聯せしめられてゐる(Gaius 3, 202--- Kniep, Gaius III 2 S. 62 ff.は「何となれば損害に関して制定せるアクヰリア法によりてculpaも亦罰せらるればなり」の一句を古典時代以後のglossemaとするも、根拠に乏しい。(Arangio-Ruiz p. 228 n. 1; Kunkel S. 163参照)。罠にかかつた獣を放つた場合のactio in factum(D. 41, 1, 55 Proculus)は、何等lex Aquiliaの問題とは関係がないとRotondiは謂つてゐるが(p. 455)、其の理由を解するに苦しむ(Jörs-Kunkel S. 257 Anm. 8参照)。Rotondi p. 455は同説としてKarlowa, Römische Rechtsgeschichte II S. 1337 を引用してゐるが、彼の理由は此のactio in factumに付いて、特に法源上actio legis Aquiliaeに関係すると断つてないからと謂ふにある。然るにRotondi(p. 452 n. 5)はquasi ex lege Aquiliaの如き句の不純を疑つてゐるのである。プロクルスは此の場合に「他人の杯を海中に投じたる場合に解答せられたると同じく、事実訴権が予に附与せらるることを要す」と記してゐるのであるが、器を水中深く投じた場合のactio in factumは後述の如く、actio legis Aquiliaeに思想的関聯を有するものとしか思はれない。器を水中深く沈めた場合に関して、D. 19, 5, 14, 2 Ulpianusは「然れども他人の銀杯を何人かが損害を与ふる目的を以て、水中深くこれを投じたるときと雖も、ポンポニーウスはサビーヌスに対する注解第十七条に於て記して曰く、盗の訴権も違法損害訴権(actio damni iniuriae=actio legis Aquiliae)も存せず、但し事実訴権は存す」と記してゐる。何等こだわることなくして一読すれば、明白にactio legis Aquiliae関係のactio in factumである。Rotondiは、此の法文の直前には奴隷を奪つて凍死せしめた場合には、衣服に付いてはactio furti、奴隷に付いてはactio in factumありと謂つてゐるのであるから、今の場合もポンポーニウスは、actio furtiもactio legis Aquiliae関係の法務官法の訴権も存せずと謂ふ意味を記したのであつて、ポンポーニウスの説く最後のactio in factumはactio doli関係のactio in factumと解するが(Rotondi p. 455, 473)、actio damni iniuriaeはactio legis Aquiliae自体であつて、これを法務官法上の訴権と解するのは無理である。D. 9, 2, 27, 21 Ulpianus「或者が手を以て予より貨幣を打落したるときは、サビーヌスは、例へば河又は海又は溝の中に陥りたる場合の如くに、喪失して他の者に取得せられざるに至りたる場合には、違法損害訴訟の成立有りとの意見を有す。之に反して、他の者が取得したるときは、故意に窃盗を為したるものとして訴訟を実行すべし、と。而して是れ古法学者も賛する所なり。同氏は、更に、事実訴権も賦与せらるることを得と述ぶ」に至つては一層明白である。サビーヌスが同時にactio damni iniuriaeとactio in factumを与へたとは到底信ぜられないことであつて、「同氏」とはサビーヌス以外の他の学者であつて、其の意見も記してあつたのを、法典編纂人は抹消した為め、結果に於て「同氏」がサビーヌスになつて了つたものと思はれるが(Rotondi p. 454)、既にサビーヌスが承認したactio legis Aquiliae自体が前に述べられてゐる以上、サビーヌス以外の某法学者の認めてゐるactio in factumも、actio legis Aquiliaeの思想圏内にありと見る可きであつて、Rotondiの如く「lex Aquiliaの野より退く」ものとするのは甚だ無理と思はれる。
(18) Rotondi p. 450 ss., 477.
(19) Heimbach, V p. 295 sch. 65に於けるHagiotheodoritaの註Rotondi p. 440.
(20) Heimbach, V p. 324 sch. 3; V p. 295 sch. 65 Hagiotheodoritaの註Rotondi p. 447--8.
(21) Rotondi p. 426 ss., 434 ss.
(22) Rotondi p. 432.
(23) Rotondi p. 441--2.
(24) Francisci, Synallagma II p. 34 ss.
我々は上に於て儒帝法のdamnum iniuria datum観念が、一面総括的actio in factumの働により、furtumの領域迄をも侵して、物の損害ある場合を広く自己の領域内に帰属せしめつつ、他面自己の内部に於て学問的にも組織化せられて、統一的観念に到達しつつあつた現象を見たのであるが、更に重大な異質的変化は、物の損害のみならず、自由人の損傷をも自己の領域に収めることによつて為された。近時の批判的研究は、自由人が損傷せられた場合のactio legis Aquiliae又はutilisを以て、法典編纂人の作とするを通常とする(1)。法源には家児が傷害せられた場合には家長はactio legis Aquiliaeを以て加害者を訴へて、治療費及び為し得べかりし労務額を請求し、家長自らが傷害せられた場合には、actio directaは提起し得ざるも、actio utilisは提起し得べき旨を記してゐるが、何れもinterpolatioの疑は頗る濃厚である(2)。物の損害に関する訴権を人の傷害に迄及ぼして来たのである。大なる思想的飛躍でなくして何であらうか。かくしてdamnum iniuria datumは著しく其の領域を拡大し、iniuriaと合すれば、人及び物に対する損傷と謂ふ現在日常の不法行為として頻発する多くの場合は、両者(damnum iniuria datum, iniuria)によつて蔽ひ得る程になつた。唯自由人を殺した場合は、羅馬法上私法的な保護はなく、damnum iniuria datumにも、iniuria にも属せずして終つた。その場合をも包含するには、後の発展に俟たなければならなかつたのである。
(1) De Medio, Rotondi, Schulz, Haymann, Taubenschlag, Perozzi, Arangio-Ruiz, Lenel等。Carrelli p. 391 n. 1及び以下の法源に対するindex interpolationum参照。家長自ら傷害せられた場合のactio utilisは儒帝のinterpolatioなるも、家児が傷害せられし場合の訴権は古典法に属すとする者Rabel, Grundzüge S. 457--8; Siber S. 232. 家長自ら傷害せられた場合のactio utilisは、本来は善意で奴隷状態にある自由人(homo liber bona fide serviens)に関するとする者Jörs-Kunkel S. 257 Anm. 9. 総ての場合の古典性を承認する者Bonfante, Carrelli其の他旧説。Carrelli前掲参照。
(2) D. 9, 2, 5, 3 Ulpianus「教師が奴隷を教育中に之を傷害し又は殺害せるときは、違法に損害を加へたるものとしてアクヰリア法に依つて義務を負ふべきか。而して、ユリアヌスは曰く、教育中に門下生の一眼を傷けたる者はアクヰリア法に依つて義務を負ふ、と。随つて、之を殺害したる場合にも亦軌を一にするは言を須ゐず。然るに、同法律学者は次の如き問題の提出を受けたり。曰く、靴製造人が生来の自由人且家子たる徒弟にして同人の指示したる所を能く為さざりし者の頭部を靴型を以て殴打し、為に徒弟は一眼を抉られたり。之に対してユリアヌスは曰く、同人は違法を為さむとして之を殴打したるものには非ず之に警告して之を訓育せむとして殴打したるものなるを以て、人格権侵害訴訟の成立無し、と。氏は賃貸訴訟が成立するに非ざるやを疑問とせり。是れ、訓育者には軽微なる懲戒の権のみが譲与せらるるものなればなり。然れども、予はアクヰリア法に依つて訴訟を実行し得べきことを疑はず」。D. 9, 2, 7 pr. Ulpianus「ユリアヌスは曰く、本訴訟に依り、家長は其家子が一眼を喪失せるに因つて失ふべき其労務及び其治療の為に支出したる費用を請求すべし、と」。此の二法文によつて儒帝法が家児の傷害による家長のactio legis Aquiliaeを認めてゐることは確である。然し乍らこれではユリアーヌスは自己が何等問題としてゐない訴権(D. 9, 2, 5, 3にはユリーアヌスは何等actio legis Aquiliaeには触れてゐない)を以て、労務及び治療の費用が請求出来ると謂つてゐることとなる(「本訴訟に依り」の本訴訟はactio legis Aquiliaeとならざるを得ない)。「予はアクヰリア法に依つて訴訟を実行し得べきことを疑はず」は実は法典編纂人の追加なのであつて、労務と治療費の請求が出来るとユリアーヌスが謂つてゐるのは、actio legis Aquiliaeを以てしてではなくて、actio locatiで出来ると謂つてゐるのである。実際古典法に於ては、奴隷の傷害後の恢復に要した費用は、actio legis Aquiliaeでは請求が出来ないとウルピアーヌスは謂つてゐるのであつて(Collatio 2, 4, 1——儒帝法典の此の法文に対応するD. 9, 2, 27, 17は反対に書き改められてゐる)、自由人の場合は出来るとユリアーヌスが謂つたとは尤もらしくない。事情かくの如くであるから、D. 19, 2, 13, 4 Ulpianusに見える全然同一設例に於けるactio legis Aquiliaeの指示もinterpolatioであり、D. 17, 2, 52, 16 Ulpianusに於て、総財産の組合の組合員自身にせよ其の息にせよ、傷害を受けてactio iniuriarum又はactio legis Aquiliaeを以て追求して得たものは、総財産中に繰入れることを要すると謂つてゐる法文中、actio legis Aquiliaeに関する限りinterpolatioである。D. 9, 2, 13, pr. Ulpianus「自由人は自己の名義を以て準アクヰリア法訴権を有す。何故となれば、何人も自己の肢体の所有者とは認められざるを以て、自由人は正訴権を有せざればなり」の原形は、恐らく「自由人は自己の名義を以てアクヰリア法訴権を有せず。何故となれば、何人も自己の肢体の所有者とは認められざればなり」の趣旨であつたであらう。奴隷に対する傷害と家児に対する傷害とは、其の法律的形態が頗る類似してゐるが、此の家児に対する傷害の場合にすら、actio legis Aquiliaeを否認してゐるならば、此の場合よりも思想的形態遥に遠ざかる家長自身に対する傷害に対して、自己名義のactio legis Aquiliaeが認められたとは解し難い。
儒帝法に於ても古典法と同じく、actio legis Aquiliaeは罰金訴権(actio poenalis)中に算入せられ(1)、数人共同の加害行為に於ける各人の責任は重畳的に競合し、一人が支払を為すも他は責を免れず(2)、noxae datioが認められ(3)、加害者の相続人に対しては訴権は移転せず(4)、capitis deminutioによつても訴権は消滅せざる(5)が如き罰金訴権の諸属性(6)も、表面的には其の侭残存してゐる。然し乍ら罰金訴権とは謂へ請求額は単価であり、而かも利害関係(interesse)が基礎となつてゐるのであるから(7)、其の罰的性格は他の不法行為、例へば盗の如きものと比較すれば稀薄たらざるを得ず、従つて既に古典法学者の口よりして、actio legis Aquiliaeが物の追求(rei persecutio)を行ふもの、即ち賠償的意義を有するものとして説かれてゐることであつて(8)、儒帝法に於ては此の傾向に一層拍車をかけ、罰金訴権の属性の実行に当つても新な制限を受け、罰金訴権の基礎付けにも、古典法には見られない罰的思想より遠ざかる理論が現はれてゐる。古典法に於てnoxae datioが許されないのは、唯家長主人が不法行為を知悉してゐた場合に限られてゐたが(9)、儒帝法に於ては「加害の惧れ有る奴隷を有したときは、斯かる奴隷を有したることを理由として、同人は違法損害の訴訟に依つて義務を負ふ」との選任に於ける過失(culpa in eligendo)の理論の出現(10)によつて、noxae datioの行使は更に一層制限せらるるに至つた(11)。罰金訴権の基礎付けも変つた。法典編纂人は謂ふ、lex Aquilia第一章に於ける加害者の責任は、其の物の「前一ヶ年以内の最高価額」であるから、若し奴隷が「被害の時に跛者なるか、又は一目の失明者なるか、又は四肢に不具の部分ありとも、其前一ヶ年以内に於て健全にして高価なりし時あるに於ては、加害者は加害当時の価格に非ず、其前一ヶ年以内の最高価格を負担すべき」であると謂ふこととなり、「損害の実額のみならず時として遠く其額以上に負担することあ」るが故に、罰金訴権と信ぜらる(12)と。かくては斯かる特殊事情なき場合には、罰金訴権ではないと謂ふ結果になる。事実彼等は続けて謂ふ、「然るが故に此の訴権が相続人に対して移転せざるは明らかなり。若し損害額を越へて訴訟が評価せらるるが如きこと決してなからんか、本訴権は移転すべかりしなるべし(13)」と。古典法学者は斯かる偶然の事情を理由として、actio legis Aquiliaeの罰金性を基礎付けたのではない。仮令本訴権を以て追求するものは利害関係額の単価であつても、それは依然として罰金と考へたのであり、罰なるが故に相続人に移転せざること、あたかも今日刑事被告人の相続人に被告人に対する罰が移転せざると同然なのであり、且つ請求額には実質的には罰的意義がなくても、他の部分特に共同加害行為者の重畳的責任に於て、罰金訴権の属性を顕現してゐたのである。儒帝法に於ける斯かる基礎付けの為めの理論の変更は、actio legis Aquiliaeの罰的性格の一層の稀薄化を物語るものであるが、斯かる稀薄化の現象は、夫婦間にactio poenalis, actio famosaの提起を禁止した儒帝法——斯かる禁止規定が古典法に属せざることは、Pampaloni, Zanzucchiの考証した所である(14)——に於て、actio legis Aquiliaeは依然として自由な提起が認められてゐる(15)ことよりしても窺はれる。かくてはactio legis Aquiliaeは不法行為より発生する訴権ではないとの論理的結論が生じて来る。後のビザンチン法学者は明白に此のことを物語つてゐる。曰く「注意すべし、私的不法行為は悪意、人格権侵害、強盗及び窃盗なることを(16)」と。damnum iniuria datumの代りに、dolusが置き換へられてゐるのである。斯かる傾向下の儒帝法に於て、罰金訴権の罰的性格の最も著しい顕現の一たる共同不法行為者の重畳的責任が、他の不法行為に付いては多分に法典編纂人の手によつて抹消せられて、連帯責任と化してゐるに拘はらず(17)、依然actio legis Aquiliaeに付いては維持せられたのは、むしろ当時の事情に忠実ならざるものであつて、唯歴史的伝統の遺物と見るの外はない(18)。
(1) Inst. 4, 3, 9; 4, 12, 1=Gaius 4, 112.
(2) D. 9, 2, 11, 2 Ulpianus.
(3) Inst. 4, 8, 4; D. 9, 2, 27, 1 et 2 et 11; D. 9, 4. のsedes materiae の幾多法源。
(4) Inst. 4, 3, 9; 4, 12, 1=Gaius 4, 112.
(5) D. 4, 5, 2, 3 Ulpianus. 尤も一般に不法行為に関する法文であるが、本訴権を除外はしてゐない。
(6) Girard p. 422 ss.
(7) Gaius 3, 212; D. 9, 2, 21, 2 Ulpianus.
(8) D. 17, 2, 50 Paulus; D. 44, 7, 34, 2 Paulus. Rotondi p. 498参照。
(9) D. 9, 4, 2, pr. Ulpianus; D. 9, 4, 5, pr. Ulpianus.
(10) D. 9, 2, 27, 11 Ulpianusと該当のCollatio 12, 7, 9との対比によつて、此のculpa in eligendoが儒帝の作なること疑なし。index interpolationum本条文参照。
(11) Rotondi p. 494.
(12)(13) Inst. 4, 3, 9.
(14) 特にC. 5, 21, 2 Diocletianus a. 290 vel 293 itp. 要旨に付いてはBonfante, Corso I p. 208 ss.
(15) D. 9, 2, 27, 30 Ulpianus; 56 Paulus. Rotondi p. 500.
(16) Heimbach V p. 447, B. 60, 11, 1へのsch. 1 Hagiotheodoritaの註、Rotondi p. 500参照。
(17) Bonfante, Scritti III p. 216 ss.; Istit. 9 p. 378.
(18) Rotondi p. 493.
近代の法文批判的研究が捲き起した問題の一に、ビザンチン期の主観主義、意思主義なるものがある。問題は種々雑多ではあるが、意思を基礎としたドグマの構成と謂ふ点に於て一脈相通ずるものがある(1)。不法行為法に於ける過失の問題も其の一に属する。culpaはactio legis Aquiliaeに於ても其の発生要件を為し、法源上極めて軽微なculpa(culpa levissima)と謂ふことが問題となつてゐるのであるが(2)、新な恐らくは急進的な学説は謂ふ、其の発生要件を為すculpaは、古典法に於ては因果関係(nesso causale)乃至は帰責可能性(imputabilità)の意義しか有せず、予見し得べきものを予見せざる不注意の意義は、始めてビザンチン法学に至つて発生したものであると。問題の提出者は恐らくFerriniである。彼はculpa概念の裏概念たる善良な家長の注意(diligentia)なる観念を、古典法のdamnum iniuria datumに付いて認めるのではあるが、「culpaなる語には広義の意味があつて、略々帰責可能性(imputabilità)に当る」と謂つた(3)。ついで民法学者Venezianは法源に見えるactio legis Aquiliaeの適用例を詳さに検討した挙句、羅馬法学者は問題の観点を一に因果関係に注ぎ、不注意不知なる基礎原理の上に問題を論じてゐるのではないことを考証して、テクニカルな意義に於けるculpa観念は未だ求め得ないとの結論に到達した(4)。此の方向をば近代的法文批判研究を加へて発展せしめ、近代的culpa論を一応纏つた形に形成して、これを学会に問ふたのはRotondiである(5)。彼は予見し得べきものを予見せざる不注意なる意義のculpaを以て、古典時代以後の法学者の観念とし、斯かる観念を表現する多数法文の純粋ならざることを指摘し、古典時代のactio legis Aquiliaeの要件としては、唯加害者の所為と看做さるる行為あるを以て足るとした。此の学説の基礎付けを為す法文批判に至つては異る見解を持してゐる所もあるが、学説の根本的基調に付いては全く軌を一にする者にArangio-Ruizがある。唯彼はculpa の語に関して帰責可能性と謂ふ言葉よりは、因果関係と謂ふ言葉を用ゐてゐる(6)。尚ほKunkel亦本質に於てRootndiと同一の結果に到達したのは偶然であつて、模倣ではないと断つてゐるが(7) culpaなる語を含む多数法文に対する批判的態度、diligentia観念の古典性の否認等に於て方向を同じうするものであつて、本文の最も重大な問題たるculpaなる語の古典的意義に付いては、不注意(Fahrlässigkeit)ではないが、尚ほ過失(Verschulden)であると謂つてゐる(8)点では、相当見解の開きがある様に思はれる。是等新学説の主たる根拠は凡そ下の六点に帰することが出来よう。(一)古典時代に於ても、精神錯乱者、未成熟者の損害行為に対しても、actio legis Aquiliaeの適用ありや否やが論議せられ、精神錯乱者に対する適用を否認するPegasus, Ulpianusの意見(9)、未成熟者に対する適用を単純に肯定するLabeoと恐らくはIulianusの意見(10)、dolus能力ある者に限定するUlpianusの意見(11)等が存在した。若しもculpaが予見し得べきものを予見せざる精神的活動の懈怠の意味であるならば、是等の者に付いてactio legis Aquiliaeの適用ありや否やの問題が、古典時代而かも法学隆盛の最絶頂期に迄持ち越したとは到底考へ得ない。特に未成熟者に対しては、Iulianusに至つても尚ほ故意の能力ありや否やを問題とせず、単純に責任者と考へてゐることは、重大な意義を有する(12)。(二)若しもactio legis Aquiliaeの責任が不注意に基くものならば、不注意は作為に於ても不作為に於ても存在し得るが故に、不作為に基く損害に対しても作為に基く損害の場合と同様に、actio legis Aquiliaeの責任は発生し得べき筈であるが、上述の【四四頁】如く法源上不作為の場合は明らかに適用はない(13)。(三)純粋の法文に関する限り、actio legis Aquiliaeに於けるculpaには不注意の意義はない(14)。(四)契約責任に於けるculpaとても、ビザンチン法学の産物である(15)。ガーイウスの法学提要に於ては、契約責任の場合は、dolusとcustodiaの責任があるのみで、culpaの責任なるものは何等記されてゐない。其のcustodiaの責任なるものは、古典時代には一種の客観的責任であつて、実際最も問題が発生する盗や奴隷の逃亡等に対しては、如何なる場合に於ても責任を持たされる。此の場合もculpa観念に服せしめ、目的物が盗まれ又は目的物の奴隷が逃亡しても、責任は一にかかつてculpaの有無にかかるculpa in custodiendoなる理論が出現したのは儒帝法に於てである(16)。不注意の意義のculpaが、契約責任の領域に於てもビザンチン法学の産物なることは、不法行為の領域に於けるculpaの語の意味変へに相対応するものである。(五)其の他の領域に於てもculpaの語は往々使用せられてゐるが、純粋法文なる限り、自己が原因を与へて自己の性に帰すべき行為、又は咎犯罪等の意義を有するに止まる(17)。用法は非法律的法源に於ても同一である(18)。(六)法源に見える諸具体的設例も、加害者の行為に帰せしめ得べきか否かの観点に立つて責任が論議せられて居り、不注意の基礎の上には立つてゐない(19)。第一の論点は相当有力である。特に未成熟者の中、dolusの能力ある者と然らざる者とを区別することが、一切古典時代の法学者の為した所ではなく、従つてウルピアーヌス亦単純に未成熟者の責任を肯定したとのTumedei, Albertarioの学説(20)にして正当ならんか、更に一層有力な理由とならう。(二)も亦理由がないではない。蓋しculpaが不注意ではなくて、因果関係的意義を有したとすれば、不作為の場合にactio legis Aquiliaeの適用を除外したことは、説明に無理がないからである。不作為の因果関係なるものは比較法制的に見ても、相当進歩した法制でなくては承認せられてゐないのであつて、羅馬法も同一であつたと解し得るのである(21)。最も問題となるのは(三)であらう。此処では法文批判のメスは縦横無尽に振はれ、ガーイウスの法学提要(三・二一一)の純粋も否認せられ(22)、某法学者の著書の抜萃として学説彙纂に引用せられる全lexを不純とせんが為めに(23)、某法学者の著書に古典時代以後の法学者が書き込んだ部分を、法典編纂人が某古典法学者の言として抜萃したと謂ふ仮説を絶対に必要とする。仮説としては一応成立するにしても、これのみを以てしては議論の当否は定め難い。(四)のculpa in custodiendoの理論の非古典性は、多分の可能性を以て考証せられた所であるが、仮令ガーイウスにdolusとcustodiaに関する記載しかないと謂つても、「ガーイウスは其の法学提要に於ては、契約関係より発生する権利義務を論じてゐない、彼は唯関係の形成と消滅に付いて叙述にたづさはつてゐるに過ぎない(尤も此の事実は一般には余り注意せられてゐないが)」とのBucklandの論駁(24)にもあるが如く、ガーイウスの法学提要に記載なきことのみよりして、古典時代に於ける存在を否認することは、単純には為し得ない。(五)は(三)の問題の一部である。(六)は極めて重要な問題であるが、Venezianの書を参照する機を得ないので、判断は不可能である。
惟ふに加害者の責任の基礎が、社会的判断に於て行為者の行動を是とせざること、行為者に落度あることが重要な因子と為してゐることは、culpaの語が咎犯罪の意に用ゐられる用法よりするも、配偶者一方のculpaにより離婚が為された場合に云々と謂ふが如き用法よりするも、否認し得ざる所と思はれる。此のことは精神錯乱者や未成熟者に宛てはめるときは必ずしも妥当な解決を得ない。然し乍ら是等の者にもactio legis Aquiliaeの責任を負はしむべきや否やが問題となつてゐるのは、昔の結果責任主義の名残と解し得ないこともない。羅馬の昔に於ても他の古代諸民族に於けるが如く、結果主義の法制が行はれてゐた。十二表法(VIII, 24a)は「若し槍を投じたりと謂はんよりは、手より滑り落したりと謂ふべきときには、牝羊が献ぜらる」(Si telum manu fugit magis quam iecit, aries subiicitur)と規定して、故意の場合と然らざる場合を区別し、故意ならざる場合には牝羊の犠牲を以て足るとしてゐるが、其処には過失観念は全然認め得ない(25)。然るに軈て加害者の加害行為に対する態度の是非に関する社会的判断を経た後に、責任の有無を決定する考の出現を見、斯かる新しき主義を以てするときは、精神錯乱者未成熟者は常に責任を免れると謂ふ結果を齎らすが故に、割り切れない気持を以て是等の者を取扱つてゐたことが、是等の者に長く問題を残してゐた原因ではなからうか。culpaに批難せらるるが如き落度なる道義的意味を存して居れば、それは過失と称して差支えない。そのことはculpaが予見すべかりしものを予見せずと謂ふ言葉の形になつて、既に古典時代に現はれてゐたかの問題とは自ら別である。斯かる方式化が古典時代に属するか否かは、私には未だ未解決の侭に残されてゐる。然し乍ら此の問題を解決せずとも、古典時代の法制を過失主義と呼ぶに何等の差支えとなるものではない。damnum iniuria datum中の「違法」(iniuria)の語に代へて、culpaなる語が置き換へられてよりは、羅馬法には最早原因主義客観主義結果責任と謂ふことは、damnum iniuria datumの領域に於ては、一般には主張し得ないのである。Kunkelが不注意ではないが過失であると謂つてゐるのは、恐らく同一の思想であらう。而してRotondiが、「古典法に於ては全然過失を問題とせず、責任者と為さんが為めには、損害行為に対する純粋単純なる客観的帰責可能性あるを以て足る。然らば古典法の状態は、凡そ法の基礎付けとしては「客観的責任」論者に資する所があらう。儒帝法に於ては責任は過失に従属せしめられ云々(26)」と主張する所には、未だ俄かに賛成を表し兼ねるのである。
(1) 問題に付いては、拙稿筧教授還暦祝賀論文集五一七頁以下。
(2) D. 9, 2, 44, pr. Ulpianus. 意義に付いて、春木一郎、前掲一五二頁。ビザンチン法学はculpa levissimaを以て、従前解してゐた如く、culpaの一等級と解したるに非ざるやの疑Arangio-Ruiz p. 232 ss.; Kunkel S. 164 Anm. 1参照。
(3) Ferrini, Diritto penale romano p. 250.
(4) Venezian, Danno e risarcimento fuori dei contratti, in Opere giuridiche I p. 83 ss. 本論文は参照の機を得ない。要旨はRotondi p. 481及びArangio-Ruiz p. 235参照。
(5) Rotondi p. 479 ss.
(6) Arangio-Ruiz p. 226 ss.
(7) Kunkel S. 159.
(8) Kunkel S. 164. 尚ほJörs-Kunkel S. 178, 179参照。
(9) D. 9, 2, 5, 2 Ulpianus.
(10)(11) D. 9, 2, 5, 2 Ulpianus; D. 47, 2, 23 Ulpianus.
(12) Rotondi p. 483--4.
(13) Rotondi p. 484-5.
(14) Rotondi p. 436 ss.; Arangio-Ruiz p. 220 ss..
(15) Arangio-Ruiz p. 62 ss. 尚ほlo stesso, Istituzioni 3 p. 370参照。
(16) Jörs-Kunkel S. 175.
(17) Arangio-Ruiz p. 221 ss.
(18) Pernice, Labeo II 1 1900 S. 6 ff.
(19) 上述Venezianの主張。
(20) Tumedei, Distinzioni postclassiche riguardo all'età 1922 p. 54; Albertario, Studi I p. 79 ss. 特にp. 90 n. 1.
(21) Jörs-Kunkel S. 172, 173.
(22) Arangio-Ruiz p. 228; Kunkel S. 182 ff.
(23) 例へばD. 9, 2, 6 Paulus; 10 Paulusの如し。
(24) Buckland, Diligens paterfamilias, Studi Bonfante II p. 89.
(25) Jörs-Kunkel S. 173.
(26) Rotondi p. 564 ,,In diritto classico dalla colpa si prescinde affatto, bastando a costituire responsabili la pura e semplice imputabilità oggettiva del fatto dannoso: sicchè lo stato del diritto classico gioverebbe se mai, de iure condendo, ai sostenitori dello ⋘responsabilità obbiettiva⋙. In diritto giustinianeo si subordina responsabilità alla colpa etc.''
三 註釈学派後期註釈学派に於ける発展
ボロニアの註釈学派以外の欧洲中世初期の法源は、Brachylogus Iuris Civilisにせよ(1)、Petri Exceptiones Legum Romanarumにせよ(2)、Lo Codiにせよ(3)、儒帝法を忠実に伝へてゐる。唯Petri Exceptiones(III, 15)のみが、「若し二人又は数人が同時に他人の家屋を焼き、又は他の損害を加へたるときは、全部が共同して責任者となる。但し一人が損害の評価額を弁済するときは、他は免責せらる(4)」として、重畳的責任が連帯責任と化してゐるのが、唯一の大なる変化である。註釈学派は比較的儒帝法源に拘束せらるること強かりし為め、actio legis Aquiliaeの自由奔放な発展を遂げるには至らなかつた。現存Irnerius(1055--1130)の作とせられる——尤も争あり——Summa(Codicis)には、儒帝法が其の侭伝つてゐる(5)。然し乍らそれでもactio legis Aquiliaeの適用範囲に関しては、一方Bulgarus(†1166)の如く、「死せる自由人の評価は為さるることを得ず」(non fieri hominis liberi mortui aestimationem)の考(D. 9, 3, 1, 5 参照)を基礎とし、自由人の殺害に対する適用を否認して、羅馬法に忠実な解釈を採つた者に対し、Rogerius(Bulgarusの弟子)、Azo(†1230)等によつて代表せられる新動向は、死亡者自身の評価は為し得ざるも、殺害より生じた諸損害はこれを賠償せしむることを得可く、但しそれはactio legis Aquiliae自体ではなく、utilis を以てす可き旨を主張してゐる(6)。彼等の主張するactio directaとutilisの区別は、儒帝法源とは無関係のものであるが、彼等にとつては斯かる区別は「法の厳正に関する限度」(quantum ad subtilitatem iuris)に於て重要性がある丈けで(7)、実生活ではどうでも都合よくあしらつてよい区別なのである。actio legis Auiliaeの罰金性は、註釈学派の何人も表からはこれを否認するに由なかつたが、出来得る限り其の罰的性格を狭義に解しようと努力はしてゐる。当時の煩瑣的法学の代表者たるOdofredus(1226--1265)は、罰金訴権(actio poenalis)と罰可能訴権(actio poenabilis)なる区別を設け、actio furtiは「其の中に唯罰のみが存するが故に」(quia in ea tantum est poena)actio poenalis、actio legis Aquiliaeは唯特殊事情が附加した場合にのみ罰的性格を採るが故に、actio poenabilisであるとした(8)。此のことは否認による倍額支払、過去一定期間中の最高価格評価等の特殊事情が存する場合に、其の限度に於てのみactio poenalisとなり、爾余の場合及び爾余の部分に付いてはactio reipersecutoriaとなるとの結論を齎らす。此のことは更にactio legis Aquiliaeに於ける責任の重畳的競合と、訴権の受動的相続性に関して重要な意義を持つ。蓋し損害行為当時の価格と、それ以前の三十日又は一ヶ年間の最高価格との差額のみが罰金であり、其の限度に於てのみ責任の重畳的競合を生ずるが、損害当時の価格の限度に於ては罰的性格がないから、一人の弁済によつて他は責を免れると謂ふ結果となり、亦損害当時の価格の限度では、相続も可能と謂ふ結果を生ぜざるを得ないからである。故に謂ふ「若し数人が損害を与へ、其の中の一人に対して訴訟が為され、同人が弁済するときは、他を解放せず。蓋し罰なればなり。……然れども訴権が賠償的なる限度に於ては、一人は弁済によりて他を解放す(9)」と。又訴権が加害者の相続人に移転せざる原則を示した後に謂ふ、「諸君、此の理は或る限度迄は正しきも、或限度迄は正しからず。本訴権が罰的なる限度に於ては(正し)。然れども物の真実価格に関しては正しからず、蓋し罰的に非ざればなり(10)」と。それにも拘はらず、彼が単純にactio legis Aquiliaeの受動的非相続性を承認してゐるのは、明確な法源を前にしては如何ともし難かつた為めであつて、彼は唯理論的批判としては、罰的要素の限度に於てのみ、actio legis Aquiliaeの受動的非相続性を基礎付けし得るに過ぎざる所以を指摘したに止まつたのである。
(1) Brachylogus(ed. Böcking 1829)III, 28 ,,de damno iniuria dato.''唯IV, 23, 3では責任は単純に単価(simplum)と記され、否認による倍額支払のことは記されてゐない。
(2) Petri Exceptiones(ed. Savigny, Geschichte II Anhang I A)III, 18(幼児精神錯乱者の無責任); III, 42(過去一年間及び三十日間の最高価格評価); III, 43(否認による倍額支払)。
(3) Lo Codi(Ricardus Pisanusによる羅甸語翻訳ed. Fitting und Suchier 1906)III, 31 ,,de dampno quod facit unus alii sine racione.'' III, 32 et IV, 26(加害者と争点の決定あるに非ざれば、加害者の相続人は利得額のみの責任)Lo Codiのculpa観念に関係して、Litten, Über ,,Lo Codi'' und seine Stellung in der Entwicklungs-Geschichte des Culpa-Problems, Mélanges Fitting II p. 601 ss.; Vinogradoff-Zulueta, Roman Law in Medieval Europe p. 74 ss. (戸倉広訳「欧羅巴中世の法律思潮」(昭和十八年)九七頁以下)但し多くは契約法に於ける過失に関する。
(4) Petri Exceptiones III, 15 si duo vel plures simul alterius domum incenderint vel aliud damnum fecerint, omnes communiter obligati sunt, sed uno solvente damni aestimationem ceteri liberantur.
(5) Summa Codicis(ed. Fitting 1894)III, 33 ,,de lege Aquilia.'' IV, 17, 2(相続人の利得額の責任)。
(6) gl. ad D. 9, 2, 7, 4 item si in publico certamine aliquo libero occiso, cessat Aquilia, ut hic dicit; an si alibi occidatur, vel vulneretur, habet locum pro libero homine: Bul. quod non et pro eo inf. e. l. huic. §si et inf. de. aedil, edict. l. qua vulgo. quibus dicitur non fieri hominis liberi mortui aestimationem. sed R. et Azo contra: et dicunt quod habet locum etiam libero homine mortuo et vulnerato utilis Aquil. quod in legibus a Bul. indictis dicitur, intellegas pro aestimatione ipsius corporis liberi hominis, pro qua non agitur l. Aquil. sed ad cetera damna sic. (然れども公の格闘に於て何人か自由人が殺されたるときは、此処に謂ふが如く、Aquiliaは停止す。若し其の他の場所にて殺されたるか、又は傷けられたるときは、自由人の為めに適用ありや。Bulgarusは否定す。彼の論拠は死亡自由人の評価は為されざる旨を言明する本レックス、パラグラフsi(=D. 9, 2, 7, 4)及びde aedilicio edictoのqua vulgoレックス(=D. 21, 1, 42)なり。然れどもRogerius及びAzoは反対にして、自由人が死亡し、傷けらるるとも、utilis Aquiliaが発生すと謂ふ。Bulgarusによりて援用せらるるレックス中に説かるる所のものは、自由人の身体自体の評価に関すと解す可し。斯かる評価に対しては、lex Aquiliaは問題とせらるることなし。然れども其の他の損害に関しては云々)。Azoの所説に付いては尚ほ*Summa Codicis(ed. Torino 1587)ad. h. t. n. 9(p. 57)参照。RogeriusとBulgarusとの本問題に関する学説上の対立は、尚ほMs. Paris 4458a(=Savigny, Geschichte IV Anhang III, 6)にも見えてゐる。尤もGaudentius, Bibliotheca iuridica medii aevi I, 49(1913)中に収録せられるRogeriusのSumma Codicis III, 24には、否認による倍額支払、過去一定期間中の最高価格評価、受動的非相続性が何等の躊躇もなく採用せられてゐる。
(7) gl. ad D. 9, 2, 7, 6.
(8) *Interpretatio in XI primos Pandectarum libros(ed. Lyon 1550)v. ult. f. 273. Inst. 4, 3, 9の注釈に「注意せよ、蓋し或る者は本訴権は其の本来の性質よりしては、poenalisに非ずして、唯poenabilisなりと謂はんと欲すればなり」(et cave: quia quidam volunt dicere, quod haec actio de sui primitiva natura non est poenalis, sed poenabilis solum)と記すは、彼等の学説を指すものである。
(9) l. c. f. 273 Si plures damnum dederunt et agitur cum uno et solvit, non liberat alium quia poena est,……sed quantum est persecutoria, solvendo unus liberat alios. D. 9, 2, 11, 2に対する注釈にも、「斯かる罰(損害当時の価格よりもより高価による)に於ては、一人が他人を解放せずと解す可し。然れども単価に関しては、condictio furtiva の場合と同一なり」(et in tali poena intellige hic, quod unus alium non liberat. de simplo autem sicut condictione furtiva)と。condictio furtivaはactio reipersecutoriaであるから、重畳的競合はしない。
(10) l. c. f. 273 rectro Or Signori, ista ratio quoad quid est bona, quoad quid non est bona.……quantum est poenalis ista actio: quantum ad verum pretium rei non est bona, quia non est poenalis.
actio legis Aquiliaeの損害賠償への接近は、actio legis Aquiliaeの目的に別個の内容を盛るに至つた。actio legis Aquiliaeを以て、原状恢復を請求することを認める学説である。C. 3, 35, 2 Gordianus a. 239には、actio legis Aquiliaeによる損害の追求を記した後、「然れども若し水が不法に他人にそらされたるときは、原状に恢復せらるる様、同一の審判人の注意を以て汝は請求す可し」とあるが、此の後の部分がactio legis Aquiliaeの領域に属せざることは疑なく、従つてAccursius(1182--1260)も、此の原状恢復はactio legis Aquiliaeを以て請求す可きではなく、interdictum quod vi aut clamを以てす可き旨を註してゐるのであるが(1)、彼以前にPillius(少くとも一二〇七年迄は生く)は、水車の新設によつて、他の水車の廻転に支障を来さしめたときは、actio legis Aquiliae utilisによる原状恢復を認めたのである(2)。今の場合と謂ひ、自由人を殺した場合と謂ひ、actio legis Aquiliae utilisは、中世法学に於ても法発展の有力な武器であつたのである。
(1) 本法に対する註にs. actione quod vi aut clam(即actio q. v. a. c.を以て)とあり。
(2) *Pillius, Quaestiones(ed. Roma 1560)p. 20.
法源に比較的拘束せられなかつた後期註釈学派も、actio legis Aquiliaeに対しては案外進歩を示してゐない。Bartolus(1314--1357)は被使用者の行為に対する使用者の責任を認めるが(1)、これは後述の如く【本号七〇頁】、寺院法学者Durandusの夙に提唱する所であつて、彼の創意ではなく、actio legis Aquiliaeの罰的性格も、通常の基礎付けを以て承認してゐるし(2)。唯典型的場合の外に、広範囲に亘つて少くともactio in factumの適用を認め、actio in factumを契約より発生するものと不法行為より発生するものとに別ち、契約不法行為の各領域に於て、actio in factumの補充的地位を認めてゐるが(3)、それとてもBarnardus Dorna(Azo の弟子)に近似の考があり(4)、ビザンチン法学も既に一歩先きに其の途を開いてゐた学説である【五七巻四号四六頁】。Bartolusの弟子Baldus(1327--1406)も、余り其の師以上には出てゐない。使用者責任の断乎たる否認(5)の如きは、却つて其の師に対する反動的退歩である。actio legis Aquiliaeの罰金性も、其れより生ずる諸属性、特に受動的非相続性と共にこれを承認し(6)、訴訟否認による倍額責任も、二倍額の請求が訴状に明記せらるる場合には許す可しとしてゐる(7)。然し乍ら彼とても時代の児である。彼はactio legis Aquiliaeを以てactio civilisとなし、此のactio civilisは一方公法上のactio criminalisに対立する意味を有する外、他方「単純に賠償的」なる点に於て、「復讐を目的とし、刑事事件の類似を嗜む」(agitur ad vindictam, et sapit instar causae criminalis)actio iniuriarumの如きものと対立する意味を有するものとなし(8)、本訴権の賠償性を高揚した外、水の侵害設備ある場合には、interdictum quod vi aut clamによるの外、actio legis Aquiliae utilisを以てしても、原状恢復を求め得可きものとした(9)。原状恢復に関しては、Cinus(1270--1336)も同一見解に到達してゐたことであつて、彼は原状恢復が不可能な場合には、損害賠償を求める外なしとしてゐる(10)。
(1) Bartolus, ad D. 47, 9, 7(Opera III ed. Basilea 1538 p. 379)「例へば小作人及び其の土地又は別荘管理の為めに据え置きたる者の労務を利用せる際に、其等の者が(漂流物を)取得せるときは、場所の所有者は如何なる責任を負ふか。註釈は同一方法(即四倍額の責任)と謂ふ。予はこれに賛せず。蓋し主人は自己の手下の者の不法行為よりしては、主人が其の労務を利用せる仕事の中にて、是等の者が何等かの不法行為を為すに非ざれば、責任を負はざればなり。例へば徴税請負人が、手下の者を徴税の為めに据え置きたるときの如し。徴税に関して不法行為が犯されたるときは、主人は責任を負ふなり。他の場合は然らず」; ad D. 39, 4, 1(Opera III p. 142)「師匠が其の徒弟の行為よりして、又主人が手下の者の不法行為に対して責任を負ふや。ヂヌスは普通は然らずと謂ふ。然れども真理は下の如し。即ち何人か手下の者を事務の為めに据え置き、己に任されたる事務に関して同人が不法行為を犯せるときは責任を負ふも、彼を据え置きたる事務の外にて不法行為を犯すも、責任を負はずとすることこれなり」松坂佐一「履行補助者の研究」(昭和十四年)七六頁参照。
(2) Ad D. 44, 7. 34(Opera III p. 525).
(3) Ad D. 19, 5, 10(Opera I p. 419). 「本レックス及び次のレックスは、契約より発生するactio praescriptis verbis又はactio in factumに関して述ぶるに非ずして、準契約又は不法行為より発生するものを記せるなり」; Ad D. 19, 5, 11(Opera I p. 419)「lex Aquiliaが欠くる場合には、actio in factumによりて補充せらる」。
(4) Bernardus Dorna, Summa libellorum(ed. Wahrmund, Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter I, 1 1905)§175 ,,de actione in factum generali''には、「本actio praescriptis verbisは総ての訴権の補充を為すものなり。蓋し訴権が欠け而も訴権の与へらるることが公平なる場合には、actio in factumが与へらるればなり」と記されてゐる。尤も彼は§56 ,,de actione in factum Aquiliae subsidiaria''に於て、儒帝法学提要に見えるactio in factumを思はすものを説いてゐる。Bartolusでは此のactio in factum generalisとactio in factum Aquiliae subsidiariaが合一し、一個のものとなつてゐると見て差支えなからう。
(5) Baldus, ad C. 6, 2, 21 dominus pro facto sui servitoris liberi hominis non tenetur (主人は自己の手下の自由人の行為の為めには拘束せらるることなし)松坂佐一、前掲七五頁参照。
(6) *Baldus, Opera 6, 33(ed. Lyon 1556).
(7) Opera 5, 216 ad C. 3, 35, 4 n° 4. 此の問題は争があり、倍額責任は訴権の性質に当然内在するものなれば、訴状に明記を要せずとする者も存し、Guido de Suzaria(†1238--1292)も「第一の学説(明記を要せずとするもの)はより確実にして、実際上もより良し」と称してゐる。Rotondi p. 511 n. 4.
(8) Opera 9, 299.
(9) Opera 5, 216 ad C. 3, 35, 2 Vide in lege ista duplicam formam libelli: unam in qua concluditur ad restitutionem damni, ibi dum dicit ut id damnum sarciat etc. alia in qua concluditur ad restitutionem in pristinum statum, ibi dum dicit ut in priorem statum etc. (本法に於ける訴状の二重形式を注目せよ。一の形式は損害の復旧に繋る、これ損害を賠償す可きことを謂へる場合なり。他は原状恢復に繋る、これ原状に恢復す可きことを述ぶるときなり)
(10) 此の際彼は救済方法として、寺院法学者が代物給付による賠償制度を認めてゐるが、市民法には斯かる途なきことを指摘してゐる。「若し汝が牛を殺したるときは均しく善良なる牛を汝が予に与ふる様予は訴を為す可し。斯かる方法は吾人の法に於ては、吾人これを有することなし」Rotondi p. 512 n. 4.
四 usus modernus Pandectarumに於ける変質
後期註釈学派の後には、法源に対しては比較的自由な立場に立つて、所謂ordo legalisより解放せられた有象無象の一般通俗啓蒙的な書が出た。我々はこれを「パンデクテンの現代的慣用」(usus modernus Pandectarum)に関する文献と呼ぶことが出来よう。是等の文献は気品ある学問的教養の高い書ではないが、実際生活に於ける法律制度の発展に対しては極めて重要な文献であつて、此の点復古学派とは全然対蹠的地位に立つてゐる。法律制度の発展を概観せんとする現下の課題にとつては、復古学派の学説の検討は必要ではない。従つて直ちにusus modernus Pandectarumに一瞥を与へて見よう。
先づ主観的要素としては、culpaは絶対的要件であつた。其のculpaは羅馬法源上の「極めて軽微なる過失」(culpa levissima)であつて、culpa levisに対立し、culpa levisよりは一等上級に立つものと解せられ、従つて極めて重い責任が加害者に課せられてゐる(1)。此の点では、刑法の領域ではculpaの行為が漸次罰せられなくなつたのと(2)、良心の世界に於てもdolusとculpa lataのみが問題となるに過ぎず、倫理神学上のculpa(culpa theologica)と法律上のculpa(culpa juridica)の相違が強調せられてゐる(3)のと、対立を為してゐる。固より学説の中には、斯かるculpa levissimaを以て過重とする者があつたが、それも此の原則は論議の余地なきものとし、従つてこれを否認することはせず、唯其の適用範囲を制限する挙に出た。例へばRobertus Maranta(†1530)は、culpa levissimaの適用を唯作為による損害に限り、不作為の場合には適用なきものとした(4)。これ法王庁裁判所の判決にも採用せられた理論である(5)。羅馬法上actio legis Aquiliaeは、作為の場合にしか適用がないから【五七巻四号四三頁】、culpaの要件も自ら其の場合にしか問題となり得ないのであるが、普通法に於ては不作為の場合にも及んだこと疑なきに拘はらず、主観的要件の余りにも厳格苛酷の故に、客観的適用範囲の拡大せられた部分——不作為の場合——に対しては、其の主観的要件の適用を否認すると謂ふ一種の妥協的考方に到達したのである。又Struvius(1619--1692)やMolinaeus(=Dumoulin)(1500--1566)の如きは、材料の性質がculpa levissimaを容れるか、又は契約の性質が要求する場合にのみ、culpa levissimaの適用を認めたが(6)、actio legis Aquiliaeの主観的要件は無差別に適用せらる可く、契約関係の如何によつて左右せらる可きものではないとのStryckius(1640--1710)の反駁に遭つてゐる(7)。
(1) 出典Rotondi p. 513.
(2) イタリアの刑事諸条例が、犯罪行為の罰則に何等主観的要件を規定せず、而して条例は厳格法にして、解釈も拡張も禁止してゐるので、裁判官の多数は故意の行為と過失の行為との間に区別を設けず、同一に罰してゐたのに対し、後期註釈学派の空気に育つた学者及び弁護士は、規定は唯故意の場合に限り、過失の場合は含まれずと主張し、漸次刑法の領域に於ては、過失は問題とせられなくなつて来た。Engelmann, Die Schuldlehre der postglossatoren und ihre Entwicklung 1895 S. 236 ff. 刑法の領域に於ける後期註釈学派のclupa論は、本書に詳し。尚ほRotondi p. 513 n. 1参照。
(3) actio legis Aquiliaeは「精神の領域に於ては、dolus又はculpa lataに因りて加へられたる損害の中に非ざれば」(in foro animae nisi in damnis illatis ex dolo vel lata culpa)問題となり得ない。*Valero, Differentiae inter ultrumque forum(ed. Maiorca 1616)p. 56.
(4) *Robertus Maranta, De ordine iudiciorum sive speculum aureum et lumen advocatorum in pratica civile(ed. Venezia 1586)p. 68 「蓋し極めて軽微なる過失に基く損害は、唯作為に於ける場合にのみ訴訟となればなり。懈怠の場合はこれと異る。汝は此のことに関する制限を、lex Aquiliaの四四レックス(=D. 9, 2, 44)の中に持つ。同所に曰く、lex Aquiliaに於ては、極めて軽微なる過失が考慮せらると。蓋し極めて軽微なる過失たるや、唯作為に於てのみ存在し、然らざる場合には存在せずと解せらるることを要すればなり」
(5) *Sacrae Rotae Romanae Decisiones p. 26 dec. 237 n. 7には、culpa levissimaは「特に過失が積極行動に於て(in committendo)存在するときに」発生すると謂つてゐる。
(6) Struvius, Syntagma iuris civilis(ed. Frankfurt 1692)Exerc. 14 thes. 20(p. 866)(「但し目的物の性質に従ひて、極めて軽微なる過失より免脱せられざる限り」作為不作為の場合共に責任を負ふ); *Molinaeus, Tractatus de eo quod interest n. 180. 是等の学説を要約して、Stryckius, Opera I, 330(ed. Firenze 1837)は、「素材となれる材料が極めて軽微なる過失を容れる場合の材料の理由によるか、又は先存の契約の性質が極めて厳重なる注意を要求する場合」(pro ratione materiae substratae, si haec quoque culpam levissimam recipiat, sive si natura contractus praeexistentis requirat exactissimam diligentiam)と謂つてゐる。
(7) *Stryckius, ibid. p. 331 「然れども損害の理のみが考慮せらる。lex Aquiliaによりては、何等の区別なく原状に恢復せらる可ければなり」。
客観的適用範囲の拡張は、羅馬法源の設例を援用して説明する学者の著書には、余り飛躍は認められないが、判例に於ては時勢の赴く所如何ともし難く、十七世紀の判決には、或ひは子の殺害より生じた無形損害に関し、或ひは夫が妻に与へた頚飾の返還に関して、actio legis Aquiliaeの適用を認めたものがある。第一の判決は車夫が子を轢殺したのに対し、親が慰藉金(solatium)を請求した一六五三年の事件である。判決自身も謂ふが如く、ザクセン法には斯かる請求は認められてゐるが、普通法には其の制度がない為めに争が起つたのであるが、裁判所はD. 9, 2, 5 et 13等を基礎として親の主張を認め、「人間の死亡に対しては、法律によりて評価せられたる確定金額は何等発見せられずと謂ふことは、本訴排斥に充分なるものに非ず。それよりして発生せる損害の故に、其の損害を評価し、愛情故に傷心する所のものを其の中に算入し、以て金銭の訴を提起することを禁止せらるることなければ、それを以て足る。親心に重大なる傷心を加へたる者より、何等かのものを慰藉の為めに返さしむるは公平なればなり(1)」と判決した。上掲法文は前述の如く【五七巻四号五一頁註2】、自由人の傷害には関するが、無形損害とは全然無関係である。第二の判決は法王庁裁判所の判決であるが、判決の基礎となつてゐるD. 9, 2, 27, 30は、夫の同意なくして妻が宝石に孔をあけて、これに損害を加へた場合であつて、普通のactio legis Aquiliaeの適用例であるが、判決はactio rerum amotarumが効果の峻厳な訴権なるが故に、これに代ふるにactio legis Aquiliaeを以てし、これに目的物返還の作用を営ましめたのであつた(2)。斯くの如く孰れの場合も、羅馬法の解釈としては不当であるが、時勢の要求には抗し難く、actio legis Aquiliaeに羅馬法に存しない適用範囲を附与した所に、興味ある法律の進化を見ることが出来るのである。
(1) Mevius, Decisiones(6 ed. Frankfurt 1726)dec. 211 nec sufficit ad istam excluendam, quod certae nihil pecuniae pro caede hominis legibus taxatum reperitur, satis est, non esse prohibitum agere ad pecuniam ob damnum ex ista oritum, in cuius aestimatione venit, quod ob affectionem inde dolet. Aequum est in solatium aliquid reddi ab eo, qui cordi paterno grave vulnus inflixit. Stryckiusは慰藉金の請求に関して、「此の正当性に関しては、疑問視せられたるは当然なり。正しく傷心(dolor)の評価其れ自体は何等存し得ざることは、何人も承認する所なる可し。蓋し傷(vulnus)自体が自由人に於ては評価を受け容れざれば、傷より生ずる傷心も評価せらるることを得ざる可ければなり」と謂つて否認してゐる。Strickius, Continuatio prima usus moderni Pandectarum(ed. 8 Halle 1749)(ad D. 9, 2)§10 p. 153. 十九世紀のパンデクテン法学に於ける此の理論の承認に付いては、Windscheid-Kipp, Pandekten II §455 n° 7(S. 980)参照。
(2) *Sacrae Rotae Romanae Decisiones pars 4 v. 2 p. 13 decisio 10.
actio legis Aquiliaeの罰的性格は、最早如何にも堪へ難きものとなつて、急進的学者はpoena privataなる観念の否認の挙に出た。此の問題は十七世紀十八世紀独逸に於て、自然法学派の影響のもとに活発に論議せられたが、多数学者は現行法秩序と相容れない限度に於ては、poena privataは継受せられずと主張した。Thomasius(1)(1655--1728), Westenberg(2)(1667--1737), Böhmer(3)(1674--1749), Samuel von Coceji(4)(1679--1755), Hellfeld(5)(1717--1732), Höpfner(6)(1743--1797), Glück(7)(1755--1831)の如し。実質的にactio legis Aquiliaeの諸々の罰的性格を検討しても、法源上actio legis Aquiliaeのactio poenalisたる所似とせられてゐた否認による倍額支払(8)、及び過去一定期間中の最高価格評価(9)は、最早問題とせられなくなつてゐる。罰的性格より生ずる諸原則の中、noxae datioは既に滅んで存しないので、残るは共同加害行為の責任の重畳的競合と受動的非相続性であるが、前者は一人の弁済によつて他は解放せられる連帯責任と化し(10)、Carpzov(11)(1595--1666)やBrunnemann(12)(1608--1672)の如きは、分割の利益迄与へんとしたが、流石にそれにはStryckius(13)やLeyser(14)(1683--1752)の如き有力な反駁があつた(15)。後者は後述の如く【本号六八頁】、寺院法がこれを打破して、加害者の相続人にも賠償責任を負はしめてゐたが、これをそつくり其の侭市民法に移す訳には行かない。学者例へばLeyserの如きは、寺院法と市民法との差異を指摘するに止まつたが(16)、多くはそれでは満足出来ず、相続人をして利得の限度(in id quod pervenerit)に於て、責任を負はしめる儒帝法に忠実な学説(Gomez, Farinaccius, Fachineus)に対して(17)、Stryckius, Voet(1647--1714), Antoninus Fabrus(1557--1624)等多数学説は、羅馬法源の解釈より寺院法に接近せんとした。或る者は法学提要四・三・九に「若し損害額を越へて訴訟が評価せらるるが如きこと決してなからんか、本訴権は(相続人に)移転す可かりしなる可し」【五七巻四号五四頁】を典拠とした。過去一定期間中の最高価格評価の制は既に滅んでゐて、損害額以上に評価せられることは最早ないので、相続人に移転するとの論理的帰結が導出せられるのである(18)。多数の学者はactio legis Aquiliaeがactio poenalisの性質を失つてゐることを根拠とする(19)。「今日に於てはactio legis Aquiliaeはactio poenalisに非ず」と高言せられてゐたのである(20)。更にはcondictio furtivaの原則を類推せんとする者もあつた。actio legis Aquiliaeを以て、不法行為より発生するactio reipersecutoriaなりとし、condictio furtivaに関する法則は、一般にこれに適用ありとするものである(21)。実社会の慣行に於ても同一である。Meviusは一六五七年の一判決に関して、「損害に関する訴権は、契約に基くと、不法行為に基くとを問はず、相続人に移転す」と註して、「契約に基く訴権が、能動的にも受動的にも相続人に移転するは、確定の法を以て伝へらる。然れども不法行為より発する訴権に関しては、二個の場合即ち死亡者と争点の決定が為されたる場合と、不法行為よりして何等かの物が彼に到来したる場合に於て、(相続人が)拘束を受くる外は、別個の普通法の規定あり。これよりして訴権が如何なるものか、不法行為に基くか或ひは契約に基くか等、訴権に関して研究を行ふ機会が発生す。然るに他人に加へられたる損害に関して争を生じたるときに、此の種の問題が発生したるが、其の論争は理由なきものと思惟せられたり。蓋し死亡者が契約を遵守せざることよりして生じたる損害は何等区別することなく、又不法行為の場合は実際損害が加へられたる限り、死亡者と争点の決定が為されざりしか、或ひは何物も同人より相続人へ到来せざりしかを注意することを要せずして、資力の許す限度に於て、相続人に於て損害を賠償するは公平なればなり」との判決要旨を伝へてゐる(22)。相続人の責任は一点の疑なき程迄に、当然と考へられてゐるのである。独逸の普通法のみならず、仏、白、伊の慣行が、加害者の相続人の全部責任を承認してゐたことは、諸書に徴して明らかである(23)。
(1) *Thomasius, De usu actionum poenalium in foro Germaniae(ed. Halle 1693)20(本書が此の問題の基本的研究なることは、諸家の引用に徴して明らかである)
(2) *Westenberg, De causis obligationum.
(3) Böhmer, Doctrina de actionibus(ed. Halle 1730)sec. I c. 3 §11 「殆んど総ての罰金訴権、特に二倍額等々に及ぶものは……知られざるものなり」
(4) *Samuel von Cocceji, Ius civile controversum(1713--1718)44, 7, 10.
(5) Hellfeld, Iurisprudentia forensis secundum Pandectarum ordinem(ed. 6 Jena 1783)§705 p. 244 (「吾人のもとに於ては、通常私罰は行はれざればなり」として、過去一定期間中の最高価格評価、否認による倍額支払、共同的加害行為責任の重畳的競合、受動的非相続性何れも現代に行はれずとする)
(6) Höpfner, Theoretisch-praktischer Commentar über die Heineccischen Institutionen(8 Auf. von Weber, Frankfurt 1818)§1127 S. 785.
(7) Glück, Pandekten Bd. 10(1808)§705 S. 382 ff. (罰的性格を殆んど取除いたものが、現代の慣行なりとする)
(8) *Samuel von Cocceji 1, 2, 91; Schilter, Praxis juris Romani in foro Germanico(ed. Jena 1698)Ex. 19 th. 65 p. 173 「吾人の裁判所の慣行はこれを遵守せざりき」; Stryckius Continuatio §20 p. 164 「裁判所の慣行によりて、此の二倍額は已まりしものと多数人は考ふ」等其の他甚だ多し。
(9) Böhmer sec. 2 c. 11 §22 p. 703 「然れども今日に於ては、総ての章に付いて同一のことが謂ひ得可し。否むしろlex Aquiliaの評価は継受せられずと謂ふを適当とせん」; Struvius §25 p. 374 「慣行は此の評価より転退し、損害行為当日の価格を以て物を評価す可きことをMathaeusは伝ふ」; Stryckius §2 p. 147 「然れども裁判所の慣行に関しては、今日に於ては損害は最早(損害行為)以前に在りたる良き状態に従ひて評価せらるることなく、加へられたる損害の時に於て在りし現状に従ひて評価せらる可しとする判断諸家の容るる所となれり」; Vinnius, Commentarius in Inst.(ed. Amsterdam 1765)4, 3 §9, p. 737 「今日に於てはactio legis Aquiliaeは罰金訴権に非ず、蓋し現在にては吾人は、違法に与へられたる損害を追求し、其の損害を越へて物が最近一ヶ年又は三十日の間に価したる最高額をも追求することはせざる限度に於て、本訴権を用ふればなり」等其の他甚だ多し。
(10) Böhmer §21, p. 703 「然れども今日に於ては単に損害の修復に関して訴が為さるるが故に、各人は全部に付いて拘束を受くと雖も、一人が弁済するときは、他は解放せらる」; Stryckius §21 p. 164 「今日に於てはactio legis Aquiliaeは罰金訴権に非ずして物追求(賠償)訴権なるが故に、多数して損害を与へたる者は、全部に付いて拘束を受け、仮令一人と訴を為すも、他は解放せられずと為すウルピアーヌスの意見は、果して今尚ほ裁判所に於て真実なりや。蓋しウルピアーヌスによりて置かるる理由、即ち「Lex Aquiliaよりしては、一人が履行するも他には影響せず、罰なればなり」との理由は、今日に於ては誤なればなり。此の故に、今日に於ても尚ほ多数して損害を加へたる者は、全部に付いて拘束を受くと常に謂ふ可きなり。契約に基かずして、不法行為に基きて拘束せらるるが為めなり。然れども訴権は唯損害の修復に対して向けらるるが故に、彼等の一人によりて此の損害が賠償せらるるときは、他は解放せらる」等其の他甚だ多し。
(11) *Carpzov, Practica criminalis P. II decis. 90(Rotondi, Brunnemannusには90とあるも、Leyser, Stryckiusには190とあり)。
(12) Brunnemannus, Commentarius in L libros Pandectarum(ed. 5 Wittenberg 1701)ad IX, 2, 11 p. 409 「然れども治療の費用に関しては、各人は頭分に付いて(pro virili)有責判決を下されたるを予見たり。例へば三人が一人を傷け同負傷者は外科医に十ターラーを、四ターラーを薬屋に支払ふ必要あり。中断労務の故には十四ターラーが裁定せらる。合して二十八ターラーなり。各人は三分の一を負担す。然れども其の中一人が何等資力を有せずと仮定せよ。同人の負担す可き欠けたる部分は他の負担となるや。常に然り。蓋し慣習は決して成文法より離れざる様解す可きものなればなり。更にCarpzovは不法行為者が総て現在し且つ弁済力あるときには、各人は割合に付いてに非ざれば拘束せらるることなしとさへ考ふ(quemlibet non nisi de rata teneri)」。Brunnemannの口調では、Carpzovの考と著しく異る様に見えるが、両者の意見の差は根本的ではない様に思はれる。Leyserは、BrunnemannはCarpzovに賛成すと記してゐる。両者の意見の差異は、前者が支払能力なき者の部分を他の共同不法行為者の負担とした点に存するのであらうか。
(13) Stryckius §21 p. 165 「然れども若し各不法行為者が弁済能力を有し、予が彼等の中の一人をば、罰の為めに訴ふるに非ずして、損害の恢復に関して訴ふるときに、同人は裁判所に於て分割の利益を援用し得可きかは問題なり。Carpzovはこれを肯定す。彼は自説の理由をば、連帯債務者の通常法則より主張すれども、此の原則が果して不法行為者に適当するかは、吾人これを疑問とするも正し」
(14) Leyser, Meditationes ad Pandectas(ed. Frankenthalii 1774)spec. 112 ad D. 9, 2 tom. II p. 484 (反対の理由Stryckiusと同じ)
(15) Schilter §70 p. 175は「過失は修復の適当原因に非ずして、損害を加へたることが其の原因なり。過失は唯それに附加するのみ。故に事物の理によれば、損害は多数人によりて分割的に且割合に従ひて修復せられ、過失は各人によりて全部に付いて洗はれ(責任を果す)得可し」(potest itaque per rei naturam et damnum restitui a pluribus divisim et pro rata, et culpa a singulis in solidum lui)と称して、罰に繋る過失と、賠償修復に繋る損害行為とを分析して考へてゐるが、具体的結果が如何になるのか、私には判らない。
(16) Leyser Meditationes spec. 112, corollaria 3 「相続人に損害を賠償する義務を負はしむる寺院法は正しく市民法に優る」
(17) *Fachineus(†1597), Controver. iuris(ed. Venezia 1619)9, 5: quatenus actiones ex delictis descendentes in heredes dentur (不法行為より発生する訴権は如何なる限度に於て相続人に対抗して附与せらるるか)参照。
(18) Stryckius §4 p. 149. 彼は此の外尚ほ公平の理由をも附加してゐる。
(19) Voet, Commentarius ad Pandectas tom. I(ed. Coloniae Allobrogum 1778)ad D, 9, 2 n° 12(p. 430)「然れどもこれよりして、吾人及び他の民族の慣習にて、不法行為より招来し、損害に具備せられたる他の訴権に倣ひて、本actio legis Aquiliaeは、仮令否認の後と雖も最早罰金訴権に非ずして、賠償訴権なりとせらるるに至り、其の結果加へられたる損害及び其の利害関係の評価のみを、原告が追求することとなれり。……従つて今日に於ては、相続人も亦全損害の賠償に対して責任あるも当然なり」。
(20) 五七頁註(9)Vinnius, 註(10)Stryckius参照。
(21) *Antoninus Fabrus, Coniectura iuris civilis(ed. 1609)4, 1; De erroribus pragmaticorum et interpretum iuris, dec. 76 err. 8.
(22) Mevius, Decisiones V dec. 39 quod aequum esset haeredem damnum a defuncto ex non observato contractu illatum sine discrimine, delicto nec ne damnum datum fuerit, quatenus vires patrimonii patiuntur resarciri, non attento……
(23) 仏白に付いて*Christianeus, Practicarum quaestionum rerumque in supremis belgarum curiis actarum et observatarum decisiones(ed. Anverse 1626)vol. 2 p. 376(ad l. IV Cod. tit. 17, dec. 22 n. 3). 彼は市民法に於ても、相続人が利得額以外に責任を負ふことを認める*Covarriuvias(1512--1577), Variae ex pontifico, regio et caesareo iure resolusiones 3, 3, 7を援用して、自説の権威付けを行つてゐる。伊に付いては*Richeri(1733--1797), Universa civilis et criminalis iurisprudentia 4, 40, 7, 3 de lege Aquilia V 12 p. 331(ed. Lodi 1829). 尚ほ倍額責任の否定(p. 333 §1381)、受動的相続性(p. 334 §1388)、連帯責任(p. 333 §1383 )、刑罰思想の否認「現行慣習によりては斯くの如き金銭罰は妥当視せられざるが故に」(p. 333 §1383)。
actio legis Aquiliaeの適用範囲の拡張は、今や遂にactio legis Aquiliaeを中心として、これに総ての不法行為の訴権を統合せんとする思想の発芽を見るに至つた。即ちactio legis Aquiliaに、他に適当なる訴権なき場合の補充的地位が認めらるるは勿論、他の訴権にも代位し得べき不法行為訴権の王座の地位が認められたのである。Böhmerは諸種の罰金訴権を数へ上げた後、actio legis Aquiliaeに及び、「この訴権は其の範囲(他に比して)より広し。而して今迄に述べ来りしものとは、選択的に競合す、但し異る理由に基く」と説き(1)、此の広汎性の故に、世上往々此の訴権を濫用し、他に該当訴権ある場合にも、直ちに此の訴権によつて賠償を申請する濫用を指摘してゐる(2)。広汎な一般的地位は尚ほ、「加へられたる損害の故に、救済の備はることが公平なる場合には、常にactio in factum legis Aquiliae」が附与せらると謂ふWestenberg(3)にも、特定の不法行為(iniuria)の訴権なき場合には、「一般的訴権」としては、故意に関してはactio doliとactio quod metus causa、過失に関してはactio legis Aquiliaeの救済ありとするMühlenbruch(4)(1785--1843)にも、明確に表現せられて居り、其の広汎性一般性に基く利用の頻繁さは、Molinaeusが仏蘭西に付いて、「総ての訴権中彼の訴権程頻繁に行使せらるる訴権は他になし」と記し(5)、Stryckiusがusus modernus Pandectarumに関して、「本章(=D. 9, 2: lex Aquiliaに付いて)の利用は極めて広汎なり。蓋し他人の何等かの過失が認定し得る限り、総ての損害の復旧はこれに基きて請求せらる可ければなり(6)」と称する所に看取することが出来る。斯くの如くactio legis Aquiliaeが、広汎な適用範囲を有する一般的不法行為の訴権として発展する過程中に於ては、actio legis Aquiliae, actio utilis, actio in factumの区別は最早其の意義を失ひ、多数学者(Meister, Stryckius, Brunnemann, Schilter, Böhmer)は、此の区別を全然抹消し(7)、区別を保存する学者と雖も、古羅馬法に於ける史的意義を復活せんとするのではなく、actio legis Aquiliae及びactio utilisをして、法源上典型的な場合を担当せしめ、actio in factumはこれを実際社会の要求に応ぜしむる為めに利用してゐる。例へばWestenbergが、actio in factumを以て公平を基礎とする訴権とするが如し(8)。
(1) Böhmer sec. 2 c. 11 §19 p. 700actio legis Aquiliae, quae latius se extendit et cum hactenus adductis elective quidem sed diversa ratione concurrit.
(2) Op. cit. 2, 4 §50 p. 359 n.(g)彼は此処で「損害が暴力又は陰密にて為されたる場合に、interdictum quod vi aut clamの代りに、直ちにactio legis Aquiliaeに拠りかかる弁護士」のことに触れてゐる。
(3) *Westenberg, Principia iuris secundum ordinem digestorum 9, 2 §40actio in factum legis Auiliae quotiens aequum est ut propter damnum datum remedium competat.
(4) Mühlenbruch, Doctrina pandectarum, deutsch bearbeitet, Lehrbuch des Pandecten-Rechts II Theil, 4. Auf. 1844, S. 308.
(5) *Molinaeus, Opera 3, 625 n. 1(ed. Paris 1681)cum in omnibus iudiciis nulla actio sit frequentior illa.
(6) Stryckius §1 p. 146 tituli praesentis(=D. 9, 2)usus amplissimus est, cum omnium damnorum reparatio ex hoc petatur, si modo ulla alterius culpa doceri possit.
(7) *Meister, Dissertatio de in factum actionibus 3 §40 ss.; Stryckius §4 p. 150「然れども此の種の事項の慣用は裁判所に於て何等存することなし。一には訴権の名称に関しては吾人は未だ板につかず、他にはactio directaによりて訴ふるかactio utilisによりて訴ふるかは、法律上は何等利害関係なければなり」; Brunnemannus, ad D. 9, 2, 7 n° 11 p. 408 「実際慣行に於ては此の区別は遵守せらるることなし」, 9 n° 1 408「然れども此の差異は裁判所に於ては遵守せらるることなし。蓋し過失に因りて死亡の原因を与へたる者は、訴訟に於ては何等区別なくlex Aquiliaによりて拘束せらる可ければなり」, 11 n° 14 「然れどもactio legis Aquiliae, actio utilis及びactio in factumの区別立てに於て、労力を費消し、板にもつかざる区別を設くることは、無用のことと思惟すればなり」; Schilter §60 p. 172(Brunnemannusと殆んど同文); Böhmer §23 p. 704「actio in factumと謂ふもactio legis Aquiliaeと謂ふも、今日に於ては自己の過失によりて損害を与へたる者に対し、修復の訴を為すものにして、あたかも同数の言ひ廻しを以てせると同然なり」
(8) *Westenberg, De causis obligationum diss. 5, 4 §14.
五 自然法学派に於ける統一的不法行為観念の成立
我々は上述した所によつて、学理も実際もがactio legis Aquiliaeを中心として、損害賠償債務を発生する統一的不法行為観念の形成に向つて、発展しつつあることを知つた。然し乍ら実定法源の障害は、結局乗り越へることは不可能であつた。羅馬法上比較的適用範囲の広い訴権としては、actio legis Aquiliaeの外に、尚ほactio doliとactio iniuriarumがあるが(1)、前者は詐欺ある行為の取消訴権と謂ふ方向に向つて変質して行つた為め、適用範囲は比較的狭小となつたけれども(2)、後者は継受後は独逸法固有の名誉感侵害行為をも其の対象中に包含して行つた為め、其の適用範囲はむしろ拡大し(3)、而してactio legis Aquiliaeと融合するが如きことはなく、両者は対立の侭に置かれてゐたからである(4)。然るに何等の伝統に拘はれず、専ら理性に基く法体系法原則の樹立に向つて力を致すことの出来た自然法学派は、法源の拘束、永年の伝統を振り切つて、真向ふより何等臆する所なく、不法行為はそれ自体として損害賠償債務を発生すると謂ふ基本原則を確立するに至つた。実に従来実際慣行の中に潜在し、学説が謂はんとして謂ふことの出来なかつた法思想に、思ひ切つた外的表現を与へたものは、自然法学派であつたのである。一六二五年の「和戦法論」(De iure belli ac pacis)第二巻第十七章を「不法に与へられたる損害及びそれより発生する債務に付いて」(de damno per iniuriam dato et obligatione quae inde oritur)なる問題に宛てたGrotius(1583--1645)は、債務発生原因を別つて、合意(pactio)不法行為(maleficium)法の規定(lex)の三としてゐるが(§1)、此のmaleficiumたるや、最早羅馬法に於けるそれぞれ各自の特別構成要件を有し、自己の中にのみ立て篭つて自足する個々的不法行為・準不法行為の共通的名称たるに過ぎざるものではなく、共通の因子たる過失によつて統一せられた総括的共通概念なのである。曰く「吾人は今や不法行為よりして自然的に負はるるものに付いて論ぜんとす。吾人は此処にては、人間が一般に又は何等かの資格の理由に基きて為すことを要する所のものと相容れざる総ての過失をば、不法行為(maleficium)と称す。作為に於て存すると、不作為に於て存するとを問はず。斯くの如き過失よりしては、若し損害が与へられたる場合には、債務が自然的に発生し、其の結果正しく其の損害が賠償せらるることとなる(5)」(§1)と。而して其の損害は通常の財産侵害行為は勿論のこと、殺人行為により(§13)、身体傷害により(§14)、姦通暴行により(§15)、窃盗強盗により(§16)、詐欺強迫により(§17)、名誉侵害によつても(§22)為され得るのであつて、生命、身体、名誉、貞操、財産に対する一切の不法行為は、何れもmaleficiumであつて、金銭賠償其の他の救済手段を発生せしめるのである。Heinrich Cocceji(1644--1719)も、本章に対する註に於て、「不法行為とは自然より許容せられたる能力の限界を踏み越ゆるあらゆる違法行為なり。これよりして行為より生じたる損害を修復す可き債務が発生す(6)」と定義し、Samuel Pufendorf(1632--1694)の「自然法及万民法論」(De iure naturae et gentium)(一六七二年)も、第三巻第一章を「何人も害せられざる可く、若し何等か損害が加へられたるときは修復せらる可きこと」(ut nemo laedatur, et si quod damnum fuerit datum, reparetur)なる表題に宛て、「何人も害せられざる可きこと、而して何等か損害を他人に与へたるときはこれを修復す可きこと」なる義務を以て、「総ての人間的制度の形成以前に、全人類を拘束す可き絶対的義務中、宜しく第一位を与へざる可からざる」ものとなし(7)(§1)、其の損害は「人間の身体、名誉、貞操に関する」(quae ad corpus, famam, pudicitiam hominis spectat)損害のみならず、「吾人に属する物のあらゆる損傷、悪化、減少若しくは奪取、又は自然より与へられたると人間の行為介在して与へられたると、法律によりて附与せられたるとを問はず、吾人が完全なる法律よりして有す可き所のものの掠取、更には他人が完全なる債務よりして、吾人に提供する責任ある何等かの給付の懈怠若しくは変質(8)」を含むとなし(§3)、Heineccius(1681--1741)も「自然法万民法綱要」(Elementa iuris naturae et gentium)(一七三七年)に於て、「他人に対する絶対且完全なる義務、特に他人を害せざる可きことに付いて」(de officiis erga alios absolutis et perfectis, speciatim de nemine laedendo)なる問題を取扱ひ、「損害を与へたる者は其の損害を賠償し、これに満足を与ふる義務あるものとす(9)」なる命題を以て、自然法の一般原理としてゐるのである。
(1) 末川博「権利侵害論」(昭和五年)四七頁。
(2) 拙稿「日本民法総則編の史的素描」法協五七巻六号三四頁。
(3) Landsberg, Iniuria und Beleidigung 1886 die gemeinrechtliche iniuria. 小野清一郎「刑法に於ける名誉の保護」(昭和九年)四九頁以下。近世普通法学に於て広汎な観念を持たしめられてゐるiniuria学説に付いては、石井茂樹「Iniuriaノ史的考察」法協四二巻七号一三〇頁以下。
(4) 尤も近世普通法の法学者や裁判所の判決の中には、actio legis Aquiliaeを以て、iniuriaによつて加へられた損害の賠償を請求することを認めるものがあつたが(Motive II S. 750)、十九世紀以前には斯かる学説は私の知る限り未だ発見することが出来ない。
(5) Grotius, (ed. 1646 photographic reproduction 1925)II, 17, 1 Veniamus ad id quod ex maleficio naturaliter debetur. Maleficium hic appellamus culpam omnem, sive in faciendo sive in non faciendo, pugnantem cum eo quod aut homines communiter aut pro ratione certae qualitatis facere debent. Ex tali culpa obligatio naturaliter oritur si damnum datum est, nempe ut id resarciatur.
(6) *Vol. III p. 180(ed. Lausanne 1679)delictum est omne factum illicitum quo quis excedit fines facultatis a natura concessas;……ex eo nascitur obligatio ad reparandum damnum ex facto datum.
(7) Samuel Pufendorf(ed. Amsterdam 1688 photographic reproduction 1934)III, 1, 1 In classe absolutorum, quae citra omne antegressum humanum institutuum omnes homines obligant, merito principalem locum huic deferimus: Ut ne quis alterum laedat, utque, si quod damnum alteri dederit, id reparet.
(8) ibid. III, 1, 3 omnem laesionem, corruptionem, diminutionem aut sublationem eius quod nostrum est, aut interceptionem eius quod ex iure perfecto debeamus habere, sive id datum sit a natura sive accidente facto humano aut lege attributum, sive denique omissionem aut degenerationem alicuius praestationis quam nobis alter ex obligatione perfecta exhibere teneatur.
(9) Heineccius I, 7, 210 ut qui damnum dedit ad illud resarciendum satisfaciendumque sit obligatus.
彼等自然法学者は、羅馬法のactio legis Aquiliaeを如何なるものと解してゐるか、又斯くの如くに発達し来つた不法行為訴権は、羅馬法のactio legis Aquiliaeと如何なる関係に立つものと見てゐるか。これに付いては自然法学派の中に二個の対立する思潮がある。一は羅馬法讃美論者の主張であつて、自然法の顕現を羅馬法のdamnum iniuria datumに於ても見、羅馬法のratio scriptaとしての意義を、此の領域に於ても主張せんとするものである。Grotiusは其の一書簡の中に於て、「多くの部門、特に契約又は違法侵害に関する部門に於ける此の法【羅馬法】の公平は斯くも顕著にして云々(1)」として、羅馬法のdamnum iniuria datumにも、絶対の讃辞を惜しんでゐない。Heinrich Cocceji(1644--1719)とSamuel Cocceji(1679--1755)父子は、過失を基本原理とするlex Aquiliaに自然法の要請を見た。Samuelによれば、実定法の諸不法行為が故意を要件とするは、「人間的脆弱さに基くもの」(propter imbecillitatem humanam)であり、過失を基本原理とする「lex Aquiliaの中に自然的組織の痕跡が残存する」(vestigia……regiminis naturalis supersunt in lege Aquilia)のであつて(2)、斯かる主張が父Heinrichの主張を承け継ぐものなることは、「然れどもlex Aquiliaに於て、何故に極めて軽微なる過失の責任が負はさる可きかの理由は、斯かく明瞭ならず。然れども父が初めて『過失論』三・一八に於て、諸国民の法の内部よりして、此の理を明らかにせり。蓋し彼は、人間は其の智性によりて予め備へ得可かりし一切のものよりして(ものに関して)、自然の厳格に基く責任を負はしめられ、従つて人間は自然上極めて精確なる注意を用う可き拘束を受く可く、而して此の自然の厳格こそ正しくlex Aquiliaの周囲に残存したる所以をば証したればなり(3)」と謂ふによつて明らかである。然し乍ら自然法学者とても、羅馬法礼賛者のみではない。不法行為の領域に於て、最も徹底した羅馬法排撃論を唱へたのは、「独逸人の法廷に採用せられたる加へられた損害に関する訴権よりlex Aquiliaの幽霊を撮み出す。」(Larva legis Aquiliae detracta actioni de damno dato receptae in foro Germanico)(一七〇三年)なる表題の単行書を現はしたThomasius(1655--1728)であつた。其の意恐らくlex Aquiliaの規定とせらるるも、実は然らざるもの(=幽霊)を明らかにするの意であらう。彼によれば、独逸の裁判所に行はれてゐる不法行為訴権と、actio legis Aquiliaeとの間には、「鳥と四足獣以上の相違」(magis……quam avis a quadrupe)があり(§1)、前者は不法行為に基く(ex delicto)訴権ではなくて、公平に基く(ex aequitate)訴権であり、羅馬法的なactio ex delictoの有する諸属性とは、凡そ縁遠いものであって、加害者の相続人にも移転し(§11)、否認によつて倍額責任を発生することもなく(§63)、損害は実害に付いて評価せられ(§34)、其の故にこそ又actio legis Aquiliaeではないと主張する。蓋し「過去に遡つて価したる額を請求せざるactio legis Aquiliaeは、実はactio legis Aquiliaeではない、其の点に該訴権の該訴権たる形式的所以(formalis ratio)が存するからである」(§47)。Heinecciusも「当代の損害訴権が自然法と祖国の法規に由来し、lex Aquiliaに由来せざる(4)」ことを主張してゐる。更にGrotiusやCoccejiの羅馬法讃美論者が、加害者の過失の中に、不法行為上の債務の自然法的基礎付けを求めたのに反し、Thomasiusは被害者の立場よりして、侵害の排除損害の賠償の権限を当然に自己の中に包蔵する権利を有することに、自然法的根拠を求めた結果、その責任論は客観的結果責任論となり、従つて幼児精神錯乱者の責任も承認せられた(§62)。此の理論はZeillerによつて踏襲せられ、軈て普州法墺民法にも影響し【本号七八頁】、ひいては独民法(八二九条)にも客観的結果責任の一場合として登場する途を開いた。
(1) *Grotius, Epistula ad Gallos(ed. Leipzig 1674)p. 338 tam evidens denique est eius iuris in plerisque partibus, iis maxime quae ad contractus aut damnum iniuria datum pertinent, aequitas……
(2) *S. Cocceji, Ius civile controversum(1713--1718), 2, 2, 144(ad D. 47, 1 qu. 1).
(3) ibid. 1, 2, 86(ad D. 9, 2 qu. 3)at ratio cur in lege Aquilia levissima culpa praestatur adeo evidens non est, sed primus e visceribus iuris gentium eam eruit parens in trac. de culpa, disp. 3, th. 18……. Probavit enim ille ex rigore naturali hominem obligari ex omni eo quod intellectu suo providere potuit ideoque teneri eum naturaliter ad exactissimam diligentiam: hunc vero rigorem naturalem remanisse circa legem Aquiliam.
(4) *Heineccius, Recitationes in elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum(ed. Amsterdam 1725)Inst. IV, 3に対する説明。
六 寺院法と独逸固有法の関与
上記の如き儒帝法より註釈学派、後期註釈学派、usus modernus Pandectarum、自然法学派と連る不法行為法の発展に対して、影響を及ぼした法体系ありとすれば、想像し得可きものは寺院法とゲルマン・独逸固有法とであらう。寺院法の影響疑なきものは、不法行為債務の相続である。c. 5 X v, 17 Alexanderは、某Hなる者が「幾多の犯罪に補はるる所となり、悪魔に唆かされて教会放火の罪を犯し、遂に病魔の見舞ふ所となり、罪を犯せる者なることを告白し、犯せし罪に関する懺悔容れられて、其のcapellanusの手によりて呪逐の判決より解除せられたが、死亡に際しては教会の埋葬を得ることが出来なかつた」と謂ふ事案に対する法皇AlexanderのClairmontの師教に対する一一八〇年頃の指令を収録してゐる。指令に曰く「此の故に、事情若し斯くの如くんば、卿が同人の死体を寺院境内に埋葬せしむ可く——これに対しては控訴なし——、同人の相続人には訓戒強制して、同人が放火其の他の方法によりて正義に反して損害を加へたる者に対し、其の資産に則して適当に満足を与へ、以て同人をして罪より解放せらるることを得せしむる様予は委嘱す(1)」と。斯かる確立した原則の基礎付けとして、学者は或ひは死者の委任を仮構し、或ひは「死者の良心の負担を取除かんが為め」(ad exonerandam conscientiam defuncti)と称してゐる(2)。不法行為上の債務の相続は、不法行為債務が賠償を目的とし、最早罰の追求を目的とせざることを予定する。此の不法行為に於ける単純な賠償性に関しては、基督教的倫理神学の影響が考察されねばならない。既に古くGregorius Magnus(ca. 540--604)は、教会所属の物件が窃まれた場合の返還に関して、「教会が地上の物件に関して喪失するものと観ぜらるる物をば割増付きにて取戻し、損害よりして利益を取得するが如きことなからしむ可し(3)」と称してゐるが、Thomas(1225--1274)も不法行為上の債務の内容をなすものは、侵奪(ablatio)の場合は返還(restitutio)、其の他の侵害の場合は賠償(recompensatio)であつて、倫理の立場よりすれば、「牛あるひは羊を窃みてこれを殺し又は売る時は五の牛をもて一の牛を賠ひ四の羊をもて一の羊を賠ふ」【出埃及記二二、一】俗法的規範は採り得ない、「蓋し返還は不法に侵奪せられたるものを公平に導くものなるが、各人は受けたる単価を返還するによつて、公平に導くからである。従つて受けたると同額を返還す可き拘束を受くるのみ(4)」と述べてゐる。恐らくは正当な対価に非ざる儲、相応する活動の結果に非ざる利得を排斥する思想の産物であつて、儒帝法では取戻人に悪意の占有者に対する費用の償還を、又善意の占有者に権利者に対する現存果実の返還を命じ(5)、中世法に於ては利息の禁止を齎らした思想と同一思想の表現であらう(6)。固より不法行為に於ける賠償性を、彼等神学者にのみ帰することは出来ないが、中世の思想界精神界を牛耳つてゐた彼等の主張が、既存の思潮に一の推進力を附与したであらうことは、否認することを得まい。是等の問題を除けば、教会を中心とする纏つた一の思潮と謂ふが如きものは、恐らくは存しないであらう。固より個々の寺院法学者の学説及び法王庁裁判所の判決中には、不法行為法の趨勢に関して注目す可きものは少くない。例へば註釈学派時代の寺院法学者Durandus(ca. 1230--1296)は、其の著Speculum Iuris中のde iniuriis et damno dato(7)に於て、自由人の殺害に関して、「仮令自由人の身体は評価を許さずと雖も、医師の料金其の他治療に費されたる費用に関しては訴ある可し。殺されたる者の父が失ひ及び失はんとしつつある労務額も亦これに入る可く(8)」、若し即死した場合には、「其の際は相続人は彼【殺された父】の生存中に、例へば靴屋、剥製人、商人又は弁護士たりしが故に失ひたるも持ち得可かりし労務額を評価す可く(9)」、其の労務の評価は「其の殺されたる者が生存し得たることが尤もらしき期間迄(10)」計算せらるとして、生命侵害に対する私法的救済に一歩を進めた外、被使用者の行為に対する使用者の責任を承認して、使用者責任理論にも一期を画して居り(11)、十七世紀の法王庁裁判所の判決にも、羅馬法には見ることを得ないactio legis Aquiliaeの拡張の存したことも上述の如くであるが【本号五三頁】、是等を以て教会側が指導力を握つてゐた法理と為すことは不可能であらう。実際damnum iniuria datumの領域に於ては、市民法と寺院法との間には、問題提出の仕方にせよ、解決の仕方にせよ、根本的な基調にさしたる相違の存しなかつたことは、市民法と寺院法の対立比較を取扱つた諸論稿、例へばC. Rittershus, Differentiarum iuris civilis et canonici sive pontificii libri septem(市民法と寺院法の相違七巻), I. Emericus a Rossbach, De comparatione iuris civilis et canonici tractatus (市民法と寺院法の比較論稿), Bartolus, Tractatus de differentia inter ius canonicum et civile (寺院法と市民法の相違論稿)等の単行書には、damnum iniuria datumに関して何等の相違が指摘せられてゐないことよりしても、想像せられる所である(12)。
(1) c. 5 X v, 17 Quapropter, si ita res se habet, mandamus, ut corpus eiusdem, appellatione cessante, facias in coemeterio sepeliri, et heredes eius moneas et compellas, ut his, quibus ille per incendium, vel alio modo damna contra iustitiam irrogaverat, iuxta facultates suas condigne satisfaciant, ut sic a peccato valeat liberari.
(2) Rotondi p. 521 n. 1. 本号五九頁註(17)のFachineusの書参照。
(3) *Gregorius Magnus, Epis. II, 56 a, 3 sed absit ut ecclesia cum augumento recipiat quod de terrenis rebus videtur amittere, et lucra de damnis quaerat.
(4) Summa Theologica II, 2, 62 §3(Opera omnia 1907 tom IX)quia restitutio reducit ad aequalitatem quod inaequaliter ablatum est. Sed aliquis reddendo quod accipit simplum, reducit ad aequalitatem. Ergo solum tenetur tantum restituere quantum accepit.
(5) Albertario, Introduzione storica allo studio del diritto giustinianeo parte I 1935 p. 89.
(6) Rotondi p. 519.
(7) Durandus, Speculum iuris(ed. Basilea 1574)Pars IV p. 507.
(8) ibid. §3 licet liberum corpus non recipiat aestimationem……agetur ad mercedes medicorum et alias expensas in curatione factas: venit etiam aestimatio operarum, quibus pater occisi caruit et cariturus est.
(9) ibid. §4 aestimabit haeres operas illas, quas amisit et habere potuit tempore vitae suae, puta quia erat cerdo, vel pelliparius, vel mercator, vel advocatus.
(10) ibid. §6 usque ad tempus quo verisimile est illum occisum vivere potuisse.
(11) §31「若し予の奴隷又は予の為めに労務を提供する者が、汝に損害を与へ、而して予が其の損害に付いて訴へられ、予これに満足を与ふるときは、彼予に其の労務を貸したる者なるが故に、予同人より借主訴権によりて、同人より其の賠償額を取戻し、同額を其の報酬より保留することを得可し」§32「而して予の手下の者(famulus)の不法行為よりして、又は同人によりて加られたる損害よりして予が拘束せらるるは、de his qui effuderuntの章si vero pluresレックス(=D. 9, 3, 5)よりの論結なり」。
(12) Rotondi p. 503-4.
ゲルマン・独逸固有法との接渉に関しては、自然法学者の一部に見える原因主義の責任論が、独逸固有法に繋ることは頗る明白である。今此処に通常の常識となつてゐる様な独逸固有法に於ける原因主義の問題に深入りする必要はない。「若し何人かが自由人をはづみにて不本意に殺したるときは、額の定まる所に従ひて、同人に贖金を支払ふ可し。敵対関係(faida)は求められず、欲せずして為したればなり」と規定して、刑事責任と民事責任の分化の後に残る民事客観責任を表現するEdictum Rothari 三八七条(1)、「小供は青年に達しないうちは、彼がそれを理由に罰として彼の生命を奪はれるやうには〔何事も〕為し得ない【即ち、十二歳未満の小児は、如何なることを為しても死刑を以て罰せらるることはないの意】。彼が或人を殴打し又は不具にしたならば、若し彼(後見人)に対し、それが証拠立てられるならば、彼の後見人は彼(被害者)の身代金〔の額〕を以て賠償すべきである。小供が加へたる如何なる損害も、彼はその価値に従ひ小供の財産を以て支払ふべきである(2)」と規定して、責任能力なき者に賠償責任を課するザクセン・シュピーゲル二巻六五条の一などを一瞥すれば足る。之に反して統一的な不法行為観念の源泉を、独逸固有法に求めんとする学説は、曾つては提唱せられた所であるが(3)、今日に於ては恐らく姿を消して了つてゐる。さうした主張を為すには、資料は余りに乏しく、着実な法制史家は触れることが出来ない為めであらう(4)。
(1) Edictum Rothari 387 Si quis hominem liberum, casum facientem, nolendo occiderit, componat eum sicut adpretiatus fuerit, et faida non requiratur, eo quod nolendo fecit. 尚ほLex Saxonum 59; Lex Angliorum et Werinorum 51; Lex Frisionum add. III, 69等参照。
(2) 金沢理康「ザクセン・シュピーゲル」(ラントレヒト)早稲田法学別刷八巻(昭和十二年)一二三頁の翻訳による。
(3) Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts 3, 3 Auf. 1898 S. 506; Heilfron, Deutsches Recht 1921 S. 330. 末川博, 前掲九七頁参照。
(4) Gierke, Deutsches Privatrecht III S. 7は、独逸債権法の現代法に対する関与の問題に関して、次の様に謂つてゐる。曰く「特に斯くの如き関与は、恐らくは或る程度に於ては起つたであらうが、個々の場合には屡々認識は困難であり、何れにしても今日迄には確実性を以て認識せられてゐない」と。
七 不法行為法発展の歴史的意義
統一的不法行為の観念は形成せられた。民事責任よりしては、刑罰思想は影を潜めた。過失責任は独逸のみならず、近世諸国を蓆巻した。暫く其の歴史的意義を簡単に省察して見たい。
統一的不法行為観念の形成は、学問的要求と実際的必要に基く。自己の中に立篭り、自己の中に於てのみ自足する個々的定型的不法行為を、ばらばらの統一なき状態に置いて置くことは、学問的要請に副ふものではない。自然法学説は斯かる状態に対して、統一性を求め、体系的整頓を試みたのであり、又事実斯かる仕事の最適任者でもあつた。彼等は個々的な不当利得型態に満足せず、統一的不当利得観念の形成に努力した。各法律行為に通ずる原則的通則的なものを探求して、現代法律行為論の先駆を為した(1)。不法行為の領域に於ても、同一の業績を遺したのである。実際的必要とは、個々独立の定型的なものしか存しない所では、救済の完全を期し得ないからである。如何に公平を説き、擬制を操り、解釈の名のもとに牽強附会を敢てしても、定型物にひつかかりを求める以外に途がない限りは、何時かは窮屈さに堪へ兼ね、破綻を招くに至る様な状態に立ち入るであらう。独逸民法草案は、斯かる意味に於て、統一的立場の必要を強調してゐるのである(2)。
(1) 拙稿、法協五七巻四号四一頁。
(2) Motive III S. 725--6.
不法行為の民事責任に於ける罰的性格の消滅、賠償性の支配は、刑事責任と民事責任の分化過程である。羅馬法は刑事責任を追求するiudicium publicumを発生するdelictum publicumと、民事責任を追求するiudicium privatumを発生するdelictum privatumの別を設けたが、何れの場合も追求するものは罰(poena)であつて、唯追求の主体が国家か又は個人かの相違があるに過ぎなかつた結果、同一行為が同時にdelictum publicumとdelictum privatumたり得る場合、例へば窃盗、iniuriaの如き場合にも、国家に対する責任と被害者個人に対する責任は、選択的に競合するに過ぎず、一方の責任が果されたときは、他の責任は発生しないのが通常で、強盗又は他人の奴隷の殺害の場合の如く、重畳的責任を発生するのは原則ではなかつた(1)。蓋し何れにするも罰であるから、二重に罰する必要はなく、唯極めて悪性のものに対してのみ、其の責任を加重せんとする考である。然し乍ら国家の立場のみを見て、個人の立場を無視することは、人間の法的感情に合しなくなつて、此処に羅馬法上単にdelictum publicumに止まつた行為、例へば自由人の殺害にも私法的保護が認められるに至ると共に、反対に羅馬法上単にdelictum privatumに止まつた行為に対しても、国家は自己の立場よりする干渉を要求し、此処に一個の同一行為よりして、同時に刑事責任と民事責任とが発生する場合は極めて多くなつて来たが、国家の独自の立場の干渉は、最早責任の選択的競合と謂ふ観念の存立を許さず、重畳的競合のみが残され、而して責任の罰的なものは専ら公的刑事責任に於ける国家刑罰に吸収せられ、私的民事責任は唯損害賠償に限定せられる進化過程が展開して行つたのである。故意ある行為の進化過程は上の如し。単なる過失行為は犯罪を構成しないのが原則であつて、此の場合には民事責任のみが存在するが、単なる過失行為は自ら罰の観念とは結びつき難い。羅馬法に於てさへ、過失が責任を発生するdamnum iniuria datumは、他の窃盗、強盗、iniuria等よりも、罰的性格が稀薄であつたのである。従つて過失の民事責任が、故意の民事責任以上に出ることが出来ず、損害賠償責任に止まつたのは当然である。
(1) Mommsen, Römisches Strafrecht S. 891 ff.
羅馬法の過失主義が、独逸法の原因主義を征服したのは、問題を拡大すれば、羅馬法の一般的継受の問題とも連る。過失主義は個人の自由な活動を促進する。中世封建社会を脱した後には、個人の自由な活動に俟つてこそ、新社会の新たな展開があり得たのである。これに対して、愛国的自然法学者によつて、原因主義結果責任の自然法性が主張せらるるに至つたが、独逸固有法が多分に自然法学者の温い同情を以て迎へられてゐたことは、周知の事実であつて(1)、敢て此の不法行為の領域の問題に限つたことではない。
(1) Gierke, Deutsches Privatrecht I S. 21.
八 近世初期の諸法典と民法七〇九条の成立
近世諸法典の編纂は、啓蒙運動自然法思想に連る。伝統に拘泥せざる理性法規を確立し、自然法思想の要請を方式化することこそ、法典の一大使命であつた。誠にプロイセン州法の先駆Corpus Iuris Friedericiani ——尤も債権法刑法に関する第三部は未発表の為め、同法典に於て今の問題が如何様に取扱はれてゐたかは、窺ひ知ることが出来ない——はSamuel von Coccejiの作にかかり、墺民法の編纂は、Kantの弟子Zeillerに俟つ所頗る多く(1)、仏民法にはDomatの強い影響が及んでゐる。何れ劣らぬ自然法学者の錚々たる者である。普州法(2)第一部第六章は、「不法行為より発生する義務と権利について」(Von den Pflichten und Rechten, die aus unerlaubten Handlungen entstehen)、一三七条の条文を配し、不法行為の各種態様を詳しく規定するが、要の所では一の不法行為(unerlaubte Handlung)観念に統卒せられてゐる。一般原則としては過失主義が基本となつてゐるが、故意重過失の場合と軽過失の場合とを区別して、取扱を異にしてゐる所に特色がある(3)。客観的責任の最も著しい例は、精神錯乱者、心神耗弱者、七歳未満の幼児の加害行為である(四一以下)。罰的思想は影を潜めて了つた。不法行為より発生する民事責任は、「損害賠償義務」(二八参照)である。共同不法行為の責任も、最早重畳的競合ではなくて、連帯責任を発生し(三〇、三二)、「損害賠償義務は加害者の相続人に移転する」(二八)。
(1) Zeillerを仲介とする墺民法とカントとの関係に付いては、Swobada, Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch im Lichte der Lehren Kants 1926; Derselbe, Die philosophischen Grundlagen des österreichischen bürgerlichen Rechts und ihre Bedeutung für die Gegenwart, Zeitschrift für Ausländisches und Internationales Privatrecht II 1928 S. 333 ff.参照。
(2) 普州法の規定の概観、末川博、前掲一三七頁以下。
(3) 故意重過失の場合には「完全なる満足」を履行する(一〇)、即ちdamnum emergensとlucrum cessansとを賠償する義務あるに反し(七)、軽過失の場合には、damnum emergensと被害物の通常の使用に於て挙げ得可かりしlucrum cessansの賠償を以て足り(一二以下)、共同不法行為の場合には、故意重過失の場合には連帯責任であり(三〇)、軽過失の場合には、何人が如何なる損害を加へたか不明の場合にのみ連帯責任であつて(三二)、然らざる場合には、自己の過失に付いてのみ責任を負ふに過ぎず(三一)、又故意重過失の場合には、損害発生時と訴提起との間の最高価格を支払う義務あるに反し(八五)、軽過失の場合には、損害発生時の通常価格の賠償が規定せらるるが如し(八八)。
墺民法(1)編纂の歴史は、マリア・テレサのCodex Theresianus (一七五三年開始一七六七年公布但し実施に至らず)に迄遡る。女皇の意思が旧法を維持しつつ、自然法の要請をして補正せしめるに存したので、全然新規の法典は成立しなかつたが、不法行為の領域に於ける自然法的基礎は疑の余地はなく、一七九七年の所謂「原案」(Urentwurf)を経て、一八一一年の本案に伝はつた。統一的不法行為の思想は、草案の「過失に付いて」(Von den Verschulden)の章(マリア・テレサ法典三、一三=原案三、一三)、本案の「損害賠償及び満足の権利に付いて」(Von dem Rechte des Schadensersatzes und der Genugthuung)の章(二、一三)の表題、及び特に「何人も加害者が過失に因りて加へたる損害の賠償を請求することを得」(本案一二九五)の規定に現はれてゐる。過失主義を採り、故意重過失と軽過失とによつて賠償範囲を異にする(本案一三〇二、一三二四、一三三一—一三三二)こと、普州法に類似する。客観的責任は此処に於ても、幼児及び精神錯乱者の行為に侵入してゐる(マリア・テレサ法典四六、原案四五六、本案一三一〇)。Zeillerは此の客観的責任を以て、自然法に合することを屡々主張してゐたのである(2)。理由は斯かる責任追求権は「正当防衛権と同じく、自己の所有権及び権利を保存し、主張す可き権利より導出せらるるが故」と謂ふに在る。罰的性格の否認は、マリア・テレサ法典に於て特に明瞭に主張せられてゐる。同法典は一般市民社会に対する義務が侵されるか、又は特に個人に対する義務が侵されるかによつて、公の過失(öffentliches Verschulden)と私の過失(Privatverschulden)とを分つてゐるが(四)、「公の過失に因りては常にその上に科せられたる刑罰が実現せらる。然れども私の過失を犯したる者は、主として加へられたる不正を排除する義務、即ち発生せしめられたる損失を填補する義務を自己に負ふ」(五)と規定してゐる。羅馬法のdelictum publicumとdelictum privatumの区別を想起せしめる区別であるが、同法と異り、Privatverschuldenは最早罰を生ぜず、損害賠償義務を発生する。従つて共同不法行為の場合も、連帯責任となり得ても(本案一三〇二)、重畳的競合ではなく、罰は加害者のみに止まるも、損害賠償義務は相続人にも移転する(マリア・テレサ法典五一、原案四六一、本案一三三七)。
(1) 墺民法の規定の概観、末川博、前掲一四五頁以下。
(2) Zeiller, Das natürliche Privatrecht 1802 §179 S. 186 ff.; Derselbe, Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch III Bd. 1812 S. 729.
仏民法(1)も「他人に対し損害を生ぜしめたる人の行為は如何なるものたりとも、自己の過失(faute)に因りて損害を生ぜしめたる者をして、損害を賠償す可き義務を負はしむ」(一三八二)と、「各人は自己の行為(fait)に因りて生ぜしめたる損害のみならず、自己の懈怠(négligence)又は自己の疎忽(imprudence)に因りて生ぜしめたる損害に付いても其の責に任ず」(一三八三)なる二ヶ条の一般的概括的規定を,,des délits et quasi-délits''の章に規定した。délitは故意を要し、quasi-délitは過失を要する。此の種の規定は仏民法の二大恩人Domat(1625--1696)にもPothier(1699--1772)にも見ることを得る。自然法学者たる前者は、Les lois civiles dans leur ordre naturel 2, 8, 4に於て「人間の行為に因りて到来し得可き総ての損失(pertes)及び総ての損害(dommages)は、其の行為が疎忽(imprudence)たると、軽率(légèreté)たると、知る可からざることを知らざることたると、其の他類似の過失(fautes)たるとを問はず、又其の過失が如何に軽微たりとも、自己の疎忽又は其の他の過失が損失及び損害を発生せしめたる者によりて、賠償せらるることを要す。蓋し仮令害する意思なきときと雖も、彼が為したる不正なればなり」との広命題を掲げてゐるし(2)、羅馬法学者たる後者も、Traité des obligations 1, 1, 2, 2 ,,Des délits et quasi-délits''の表題の下に、délitを以て「人が故意(dol)又は悪意(malignité)に因りて、損害又は何等かの不正(dommage ou quelque tort)を加ふる行為」と定義し、quasi-délitを以て「人が悪意はなきも、恕し得ざる疎忽に因りて、他人に何等かの不正を加ふる行為」と定義して(3)、羅馬法の言葉は用ゐてゐるが、内容は最早同法のそれとは異り、一般的に故意過失の違法行為が債務発生原因行為(causes des obligations)となることを前提としてゐる。是等両人の学説と仏民法本案との間には、諸種の草案、委員の説明等材料は乏しくはないが(4)、根本の傾向は一貫して何等の変更もない。
(1) 仏民法の規定の概観、末川博、前掲一六〇頁以下。
(2) Oeuvres de J. Domat(éd. Carré)1822 III p. 317.
(3) Oeuvres de Pothier(éd. Bugnet 2 éd)II p. 57.
(4) Rotondi p. 150-2.
我々は上に於て、我が民法七〇九条の規定するが如き過失主義を基礎とし、専ら損害賠償の追求を目的とする一般的概括的規定が、前世紀初頭の立法中に確立せられてゐるのを見た。斯かる限定せられた問題の範囲では、其の後のザクセン民法、独逸民法、瑞西民法其の他とても、其の基礎に於ては同一であつて(1)、十九世紀の歴史法学派パンデクテン法学の清掃作用も、此の大勢を動かすことは出来なかつたので、これ以上十九世紀の普通法に立入り、近世立法を辿ることは、現下の自分の問題の範囲では必要ではない。唯過失主義が修正を受けて、原因主義結果責任の独逸法主義の擡頭が益々強からんとすること(2)、学説的には無形損害の基礎付けに於て、peine privéeの思想の復活を見んとしつつあること(3)を指摘すれば足る。上記の如き立法的雰囲気の中にあつて、旧民法は仏民法に倣つて、財産編第二部第一章第三節「不正ノ損害即チ犯罪及ヒ準犯罪」の冒頭に「過失又ハ懈怠ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタル者ハ其賠償ヲ為ス責ニ任ス」(三七〇条)と規定した。新民法は周知の如く七〇九条に於て「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」と改めてゐる。両者比較して容易に目につく差異は、権利侵害の要件である。恐らくは来栖助教授が指摘せらるるが如く、「単なる加害者の主観的要件以上のものを意味してゐる」仏法の過失を、今や「独民法の様に純然たる主観的要件を意味するために用ゐられるに至つた結果、保護に価する利益を限定するために権利侵害の数字を加へたのではないかと推測される(4)」。此の外民法七〇九条には、条文の表面の上には浮び出てはゐないが、頗る重要な違法性の問題が存するが、自分の現在の直接の問題ではないので、一と先づ此の稿を終らねばならない。
(1) 立法の動きに付いては、末川博、前掲一七二頁以下。
(2) 岡松参太郎「無過失損害賠償責任論」大正五年。ナチス独逸に於て過失主義が依然として根底より崩壊せざる事情に付いて、川島武宜「ナチの不法行為法改正論」法協五九巻四号、浅井清信「ギールケ『損害賠償改革の基本問題』」法と経済一五巻四号。
(3) 戒能通孝「不法行為法に於ける無形損害の賠償請求権」法協五〇巻二号三号。
(4) 来栖三郎「民法における財産法と身分法」法協六一巻三号三七一頁。
(追記) 本号の叙述は、註釈学派以後の法源刊本の不足の為め、多分にRotondiの研究の透写し的紹介に終つた。法源は出来得る限り一々検討したが、Rotondiの引用を其の侭引用する外仕方のなかつた場合も多かつた。*の記号は斯かる直接参照することの出来ない原本を指す。同時に早期普通法文献を所蔵するギールケ文庫閲覧の便宜を賜つた東京商科大学図書館に対し此処に感謝の意を表する。